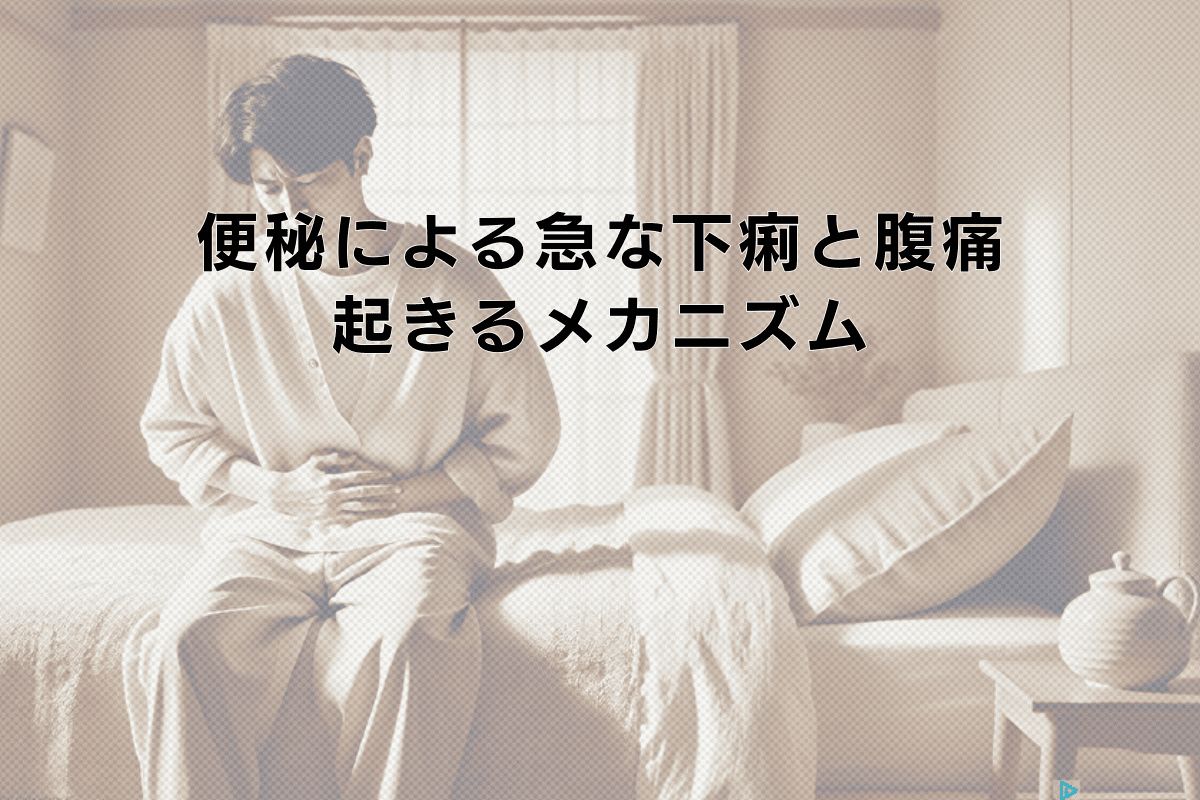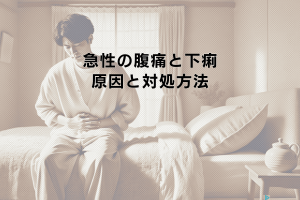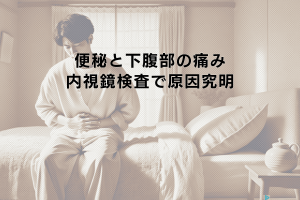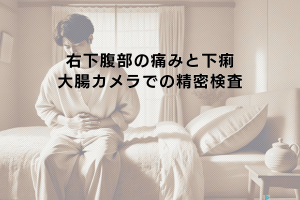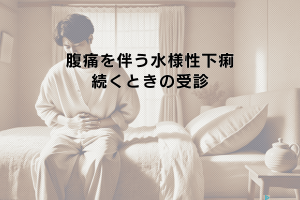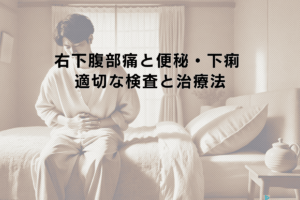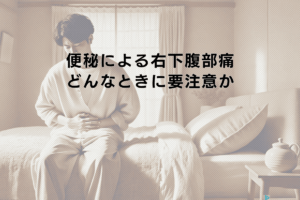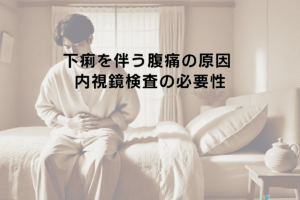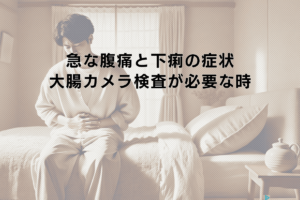多くの方が経験する便秘ですが、時には急な下痢や激しい腹痛を伴うことがあります。たかが便秘、と軽く考えていると、思わぬ症状に悩まされることも少なくありません。
この記事では、なぜ便秘が急な下痢や腹痛を起こすのか、その背景にある身体の仕組みを詳しく解説します。
また、同様の症状が現れる可能性のある他の状態や、ご自身でできる対策、医療機関を受診する目安についても触れていきます。
便秘とは?定義と主な原因
便秘は多くの人が抱える一般的な悩みの一つですが、その定義や原因は多岐にわたり、快適な日常生活を送るためには、まず便秘について正しく理解することが大切です。
便秘の医学的な定義
医学的には、本来体外へ排出すべき糞便を十分量かつ快適に排出できない状態を便秘と定義し、排便回数が週に3回未満であったり、排便時に強くいきむ必要があったり、残便感があったりする場合などが該当します。
ただし、排便の頻度には個人差があるため、回数だけでなく、排便の状態やそれに伴う苦痛の有無も考慮して総合的に判断します。
便秘の種類とそれぞれの特徴
便秘はその原因や状態によっていくつかの種類に分けられ、代表的なものが、機能性便秘と器質性便秘です。
機能性便秘は、大腸の機能低下や生活習慣の乱れなどが原因で起こるもので、さらに弛緩性便秘、痙攣性便秘、直腸性便秘に分類されます。
器質性便秘は、大腸がんや炎症性腸疾患など、腸そのものに病変があって便の通過が妨げられることで起こります。
機能性便秘の分類
| 種類 | 主な特徴 | 考えられる原因 |
|---|---|---|
| 弛緩性便秘 | 腸の蠕動運動が弱く、便を押し出す力が低下する。便意を感じにくい。 | 運動不足、加齢、食物繊維不足、長期の臥床など |
| 痙攣性便秘 | ストレスなどで腸が過緊張し、便の通りが悪くなる。ウサギの糞のようなコロコロした便が出やすい。腹痛を伴うことも。 | 精神的ストレス、環境の変化、過敏性腸症候群など |
| 直腸性便秘 | 便が直腸まで来ているのに、排便反射が弱まり便意を感じにくい。または我慢してしまう。 | 排便の我慢、加齢による反射低下、浣腸の常用など |
便秘を起こす生活習慣
日々の生活習慣が便秘の大きな原因となることがあり、特に、食物繊維の摂取不足、水分不足、運動不足は腸の働きを鈍らせる代表的な要因です。
また、不規則な食事時間や睡眠不足、過度なダイエット、精神的なストレスも自律神経のバランスを乱し、腸の蠕動運動に影響を与えます。
朝食を抜いたり、トイレに行く時間を十分に確保できなかったりすることも、排便のリズムを崩す原因です。
便秘と関連する可能性のある疾患
便秘の背後には、何らかの疾患が隠れている可能性もあり、大腸がんやポリープ、炎症性腸疾患(クローン病や潰瘍性大腸炎など)は、腸管を狭窄させたり炎症を起こしたりして便の通過を妨げます。
また、甲状腺機能低下症や糖尿病などの内分泌疾患、パーキンソン病などの神経疾患、うつ病などの精神疾患も便秘を起こすことがあります。服用している薬剤の副作用として便秘が現れることもありますので、注意が必要です。
便秘が引き起こす様々な症状
便秘は単に便が出にくいというだけでなく、身体に様々な不快な症状を起こし、症状を理解することで、便秘のサインを見逃さず、早期に対処することの重要性がわかります。
お腹の張りや不快感
便秘になると、腸内に便やガスが溜まりやすくなり、お腹が張って苦しい感じ(腹部膨満感)や、重苦しい不快感を覚え、時には、お腹がゴロゴロ鳴ったり、ガスが頻繁に出ることもあります。
食欲不振や吐き気
腸内に便が滞留すると、消化管全体の動きが悪くなり、食欲不振につながることがあり、ひどい場合には、胃の内容物が逆流しやすくなり、吐き気や実際に嘔吐してしまうこともあります。このような症状は、栄養摂取の妨げにもなりかねません。
肌荒れや体調不良
便秘によって腸内環境が悪化すると、悪玉菌が増殖しやすくなり、悪玉菌が産生する有害物質が腸から吸収され、血液を介して全身に運ばれると、肌荒れやニキビ、吹き出物などの皮膚トラブルを起こすことがあります。
また、頭痛や肩こり、倦怠感といった全身的な体調不良を感じる人もいます。
便秘と肌トラブルの関連
| 腸内環境の状態 | 主な影響 | 現れやすい肌トラブル |
|---|---|---|
| 善玉菌優位(良好) | 有害物質の産生抑制、栄養吸収促進 | 肌の調子が整いやすい |
| 悪玉菌優位(悪化) | 有害物質の産生増加、バリア機能低下 | ニキビ、吹き出物、乾燥、くすみなど |
痔やその他の合併症
便秘で硬くなった便を無理に排出しようといきむと、肛門周辺に大きな負担がかかり、いぼ痔(痔核)や切れ痔(裂肛)といった肛門疾患を起こしやすいです。
また、長期間便秘が続くと、稀にではありますが、腸閉塞(イレウス)や便が腸壁を傷つけて炎症を起こす虚血性大腸炎などを発症するリスクが高まります。
なぜ便秘から急な下痢と腹痛が起こるのか
長引く便秘の後に、突然激しい腹痛とともに下痢が起こることがあり、一見矛盾しているように感じるかもしれませんが、身体の防御反応や腸内環境の変化が複雑に関係しています。
腸内環境の悪化と悪玉菌の増加
便秘によって便が腸内に長時間滞留すると、腸内細菌のバランスが崩れ、悪玉菌が増殖しやすくなり、悪玉菌は、アンモニアや硫化水素といった有害物質やガスを産生し、腸内環境をさらに悪化させます。
悪化した環境は、腸管への刺激となり、下痢を起こす一因です。
腸管の刺激と蠕動運動の異常
硬くなった便や、悪玉菌が産生した有害物質が腸管の粘膜を刺激すると、腸はそれを異物と認識し、排出しようとします。
その結果、腸の蠕動運動が過剰に活発になり、便が水分を十分に吸収する前に急速に腸内を通過するため、下痢として排出され、急激な蠕動運動が、けいれん性の腹痛を起こすのです。
浸透圧性下痢の発生
便秘が長く続くと、腸内に滞留した便の濃度が高くなることがあり、腸管内の浸透圧が上昇し、体内の水分が腸管内に引き込まれ、便が軟らかくなり、下痢(浸透圧性下痢)が生じることがあります。
これは、便秘薬の一部(塩類下剤など)が作用する仕組みと似ています。
下痢の種類と特徴
| 下痢の種類 | 主な原因 | 便の状態 |
|---|---|---|
| 滲出性下痢 | 腸の炎症(潰瘍性大腸炎など) | 血液や粘液が混じることも |
| 蠕動運動亢進による下痢 | ストレス、刺激物、甲状腺機能亢進症など | 水様便、泥状便 |
| 浸透圧性下痢 | 消化吸収不良、一部の下剤 | 水様便 |
| 分泌性下痢 | 細菌毒素(O-157など)、一部の薬剤 | 大量の水様便 |
腸閉塞(イレウス)のリスク
非常に稀ですが、重度の便秘が続くと、硬くなった便が腸管を完全に塞いでしまう糞便性イレウス(腸閉塞)を起こすことがあり、この状態になると、腸の内容物が先に進めなくなり、激しい腹痛、嘔吐、腹部膨満などが現れます。
腸閉塞の初期症状として、閉塞部位より口側の腸管が過剰に動き、一時的に下痢のような症状が出ることがありますが、その後は排便も排ガスも完全に止まってしまうことが多く、緊急を要する状態であり、速やかな医療機関の受診が必要です。
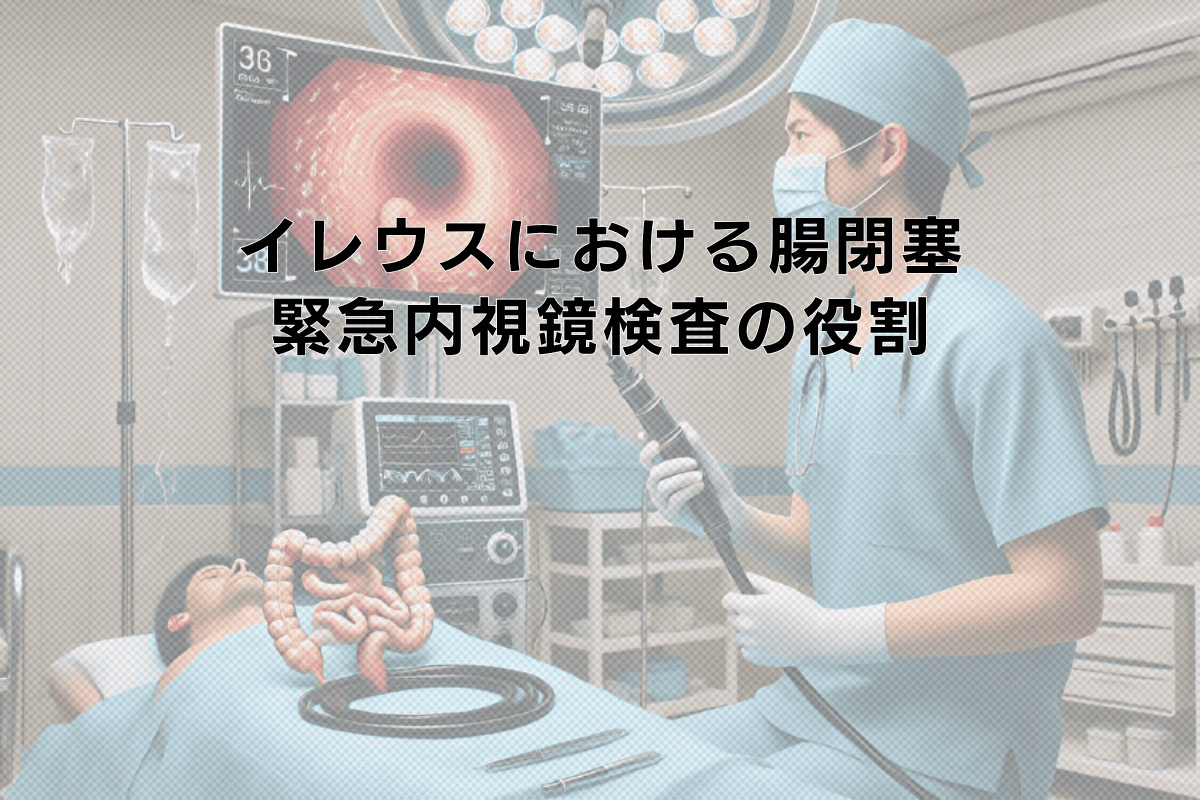
便秘と下痢を繰り返す過敏性腸症候群(IBS)との関連
便秘と下痢を交互に繰り返したり、腹痛を伴ったりする症状は、過敏性腸症候群(IBS: Irritable Bowel Syndrome)の可能性も考えられます。IBSは、腸に明らかな炎症や潰瘍などがないにもかかわらず、お腹の不調が続く病気です。
過敏性腸症候群(IBS)とは
過敏性腸症候群は、ストレスや生活習慣の乱れ、腸内細菌叢の変化などが複雑に関与して発症し、主に、腹痛や腹部の不快感があり、便秘や下痢などの便通異常が数ヶ月以上続く場合に診断されます。
命に関わる病気ではありませんが、症状によって日常生活に支障をきたすことも少なくありません。
IBSの主な症状とタイプ
IBSの主な症状は、腹痛、腹部膨満感、便秘、下痢です。症状の現れ方によって、いくつかのタイプに分類されます。
- 腹痛または腹部不快感
- 排便による症状の改善
- 排便頻度の変化を伴う
- 便の形状の変化を伴う
便秘型IBSと下痢型IBS、混合型IBS
IBSは、症状のパターンによって主に3つのタイプに分けられます。
IBSの主なタイプ
| タイプ | 主な症状 | 特徴的な便の状態 |
|---|---|---|
| 便秘型(IBS-C) | 慢性的な便秘、排便困難、残便感 | 硬い便、兎糞状の便 |
| 下痢型(IBS-D) | 突然の下痢、頻回の便意、腹痛 | 軟便、水様便 |
| 混合型(IBS-M) | 便秘と下痢を繰り返す | 便の状態が不安定 |
この他に、いずれにも分類されない分類不能型(IBS-U)もあります。便秘から急に下痢と腹痛という症状は、特に混合型IBS(IBS-M)で見られます。
IBSの診断と一般的な対処法
IBSの診断は、症状の詳細な問診に加え、血液検査や便検査、大腸内視鏡検査などを行い、他の疾患(大腸がん、炎症性腸疾患など)を除外した上で行われます。
対処法としては、まず生活習慣の改善(食事療法、適度な運動、十分な睡眠、ストレス管理など)が基本です。
症状に応じて、薬物療法(整腸剤、消化管運動調整薬、抗不安薬、抗うつ薬など)も行われます。IBSは症状が良くなったり悪くなったりを繰り返すことが多いため、根気強く治療に取り組むことが大切です。
自分でできる便秘対策と生活習慣の改善
便秘の多くは生活習慣の見直しによって改善が期待できます。ここでは、今日から始められる具体的な対策を紹介します。
食物繊維の積極的な摂取
食物繊維は、便の量を増やして腸の蠕動運動を促し、便通をスムーズにする働きがあり、食物繊維には水溶性食物繊維と不溶性食物繊維の2種類があり、バランス良く摂取することが大事です。
水溶性食物繊維は便を軟らかくし、不溶性食物繊維は便のカサを増して腸を刺激します。
食物繊維を多く含む食品
| 食物繊維の種類 | 特徴 | 多く含む食品 |
|---|---|---|
| 水溶性食物繊維 | 水に溶けてゲル状になる。善玉菌のエサになる。 | 海藻類(わかめ、昆布)、果物(りんご、バナナ)、こんにゃく、大麦など |
| 不溶性食物繊維 | 水に溶けにくく、水分を吸収して膨らむ。 | 穀類(玄米、全粒粉パン)、豆類(大豆、小豆)、野菜(ごぼう、きのこ類)、いも類など |

水分補給の重要性
便が硬くなるのを防ぎ、スムーズな排便を促すためには、十分な水分摂取が必要です。
朝起きた時にコップ一杯の水を飲むと、腸が刺激されて動き出しやすくなり、また、1日に1.5~2リットルを目安に、こまめに水分を摂るように心がけましょう。
ただし、コーヒーや緑茶などカフェインを多く含む飲み物は利尿作用があるため、摂りすぎには注意が必要です。
適度な運動と腸のマッサージ
運動不足は腸の働きを鈍らせる原因の一つです。ウォーキングやジョギング、ストレッチなどの適度な運動は、血行を促進し、腸の蠕動運動を活発にし、また、腹筋を鍛えることも排便時のいきむ力をサポートします。
お腹を「の」の字にマッサージすることも、腸の動きを助けるのに役立ちます。
- ウォーキング(1日20~30分程度)
- 腹筋運動
- ヨガやストレッチ
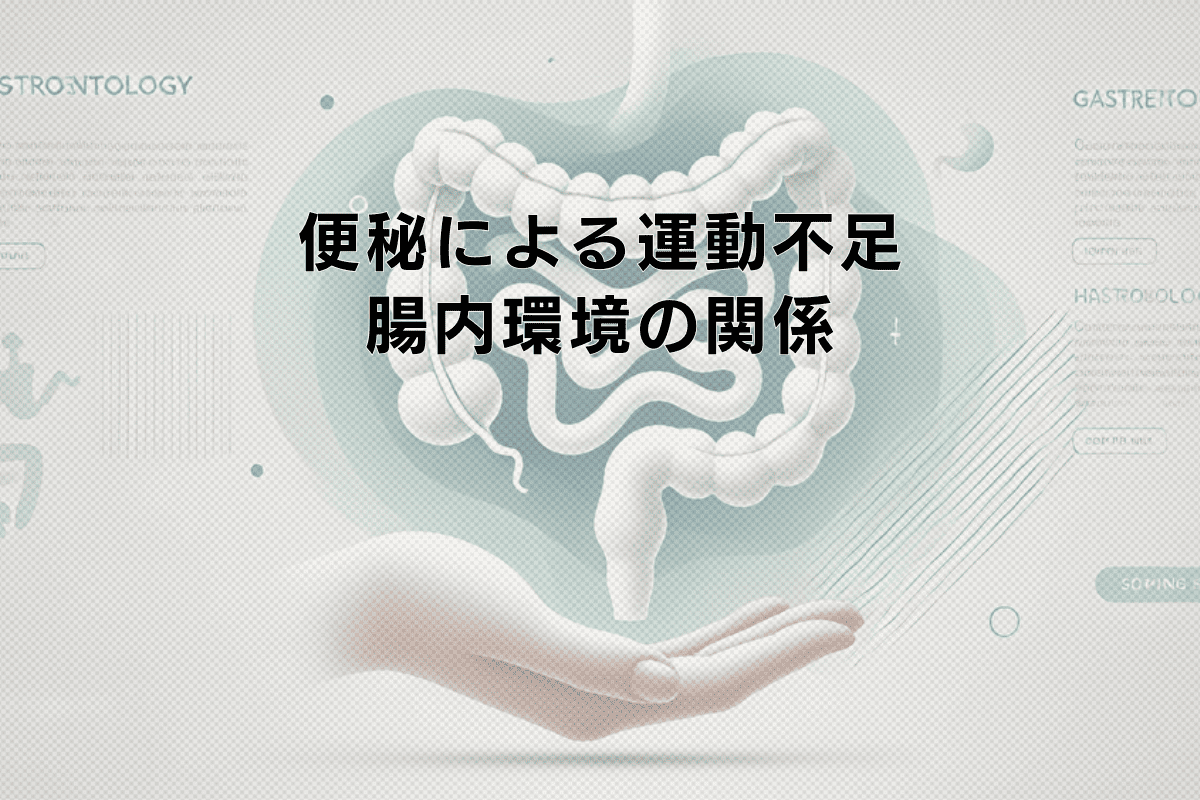
規則正しい排便習慣の確立
毎日決まった時間にトイレに行く習慣をつけることも大切で、特に朝食後は、胃に食べ物が入ることで大腸の動きが活発になる「胃・結腸反射」が起こりやすく、便意を感じやすい時間帯です。
便意を感じたら我慢せず、時間に余裕を持ってトイレに行くようにしましょう。リラックスできるトイレ環境を整えることも重要になります。
医療機関を受診する目安
便秘や下痢、腹痛はよくある症状ですが、中には注意が必要なケースもあり、自己判断せずに医療機関を受診した方が良い目安について説明します。
市販薬で改善しない場合
便秘薬や整腸剤を数日間使用しても症状が改善しない、あるいは悪化する場合は、医療機関を受診しましょう。市販薬が合っていない可能性や、他の原因が隠れている可能性があります。
特に、薬の使用を中止するとすぐに症状が再発する場合は相談が必要です。
激しい腹痛や嘔吐を伴う場合
我慢できないほどの激しい腹痛、繰り返す嘔吐、発熱などを伴う場合は、腸閉塞や虫垂炎、感染性腸炎など、緊急性の高い疾患の可能性があるので、速やかに医療機関を受診してください。夜間や休日であっても、救急外来の受診を検討しましょう。
注意すべき症状
| 症状 | 考えられる状態・疾患の例 | 対応 |
|---|---|---|
| 突然の激しい腹痛、嘔吐、排便・排ガスの停止 | 腸閉塞(イレウス) | 緊急受診 |
| 右下腹部の持続的な痛み、発熱、吐き気 | 虫垂炎(盲腸) | 速やかに受診 |
| 血便、粘血便、高熱、激しい下痢 | 感染性腸炎、炎症性腸疾患 | 速やかに受診 |
血便や体重減少が見られる場合
便に血が混じる(血便)、黒っぽい便が出る、原因不明の体重減少がある、貧血を指摘されたなどの症状がある場合は、大腸がんや炎症性腸疾患などの消化器系の病気が隠れている可能性があります。
症状に気づいたら、放置せずに消化器内科など専門医の診察を受けることが大切です。
便秘と下痢に関するよくある質問
便秘や下痢に関して、患者さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
- 便秘薬を長期間使用しても大丈夫ですか?
-
刺激性下剤のように、長期間連用すると効果が弱まったり、腸の機能が低下したりする可能性があるものもある一方、非刺激性の下剤や漢方薬など、比較的長期間使用しやすいものもあります。
自己判断で長期間使用するのではなく、医師や薬剤師に相談し、適切な用法・用量を守ることが大切です。
- 子供や高齢者の便秘で気をつけることは?
-
子供の便秘は、偏食やトイレトレーニングの失敗、学校のトイレを我慢することなどが原因となることがあります。食事内容の見直しや、規則正しい排便習慣を促すことが大切です。
水分をしっかり摂らせ、遊びや運動も奨励しましょう。高齢者の場合は、食事量の減少、活動量の低下、腸の機能低下、服用薬の影響など、様々な要因が絡み合って便秘になりやすいです。
脱水にも注意し、無理のない範囲での運動や、食物繊維を意識した軟らかい食事を心がけましょう。
- 食事以外で便秘解消に役立つものはありますか?
-
食事以外では、適度な運動、十分な睡眠、ストレスを溜めない生活が重要です。ウォーキングなどの有酸素運動は腸の動きを活発にし、また、質の高い睡眠は自律神経のバランスを整え、腸の働きにも良い影響を与えます。
お腹のマッサージやツボ押しなども試してみる価値があります。
- ストレスは便秘や下痢に関係しますか?
-
ストレスは便秘と下痢に大きく関係します。腸の働きは自律神経によってコントロールされており、ストレスは自律神経のバランスを乱す大きな要因です。
強いストレスや持続的なストレスは、腸の動きを悪くして便秘を起こしたり、逆に腸を過敏にして下痢を起こし、過敏性腸症候群(IBS)の発症や悪化にもストレスが深く関わっていると考えられています。
次に読むことをお勧めする記事
【腹痛や下痢が頻繁に起こる原因 検査と治療について】
便秘から急に下痢と腹痛が起こる仕組みを学んで、『過敏性腸症候群かもしれない』と思った方もいらっしゃるのでは?そんな疑問にお答えする詳しい診断基準と治療選択肢をご紹介しています。
【腸にいい食べ物を知る 腸内環境を整える方法】
便秘と下痢のメカニズムを理解したところで、根本的な腸内環境の改善についても知っておくと、より包括的な対策ができます。食事から始める腸の健康管理をご紹介します。
参考文献
Rangan V, Singh P, Ballou S, Hassan R, Yu V, Katon J, Nee J, Iturrino J, Lembo A. Improvement in constipation and diarrhea is associated with improved abdominal pain in patients with functional bowel disorders. Neurogastroenterology & Motility. 2022 Apr;34(4):e14253.
Bharucha AE, Wouters MM, Tack J. Existing and emerging therapies for managing constipation and diarrhea. Current opinion in pharmacology. 2017 Dec 1;37:158-66.
Cai J, Yuan Z, Zhang S. Abdominal pain, diarrhea, constipation-which symptom is more indispensable to have a colonoscopy?. International Journal of Clinical and Experimental Pathology. 2015 Jan 1;8(1):938.
Toney RC, Wallace D, Sekhon S, Agrawal RM. Medication induced constipation and diarrhea. Practical Gastroenterology. 2008 May;32(5):12.
Wong MY, Hebbard G, Gibson PR, Burgell RE. Chronic constipation and abdominal pain: Independent or closely interrelated symptoms?. Journal of Gastroenterology and Hepatology. 2020 Aug;35(8):1294-301.
Talley NJ, Dennis EH, Schettler-Duncan AV, Lacy BE, Olden KW, Crowell MD. Overlapping upper and lower gastrointestinal symptoms in irritable bowel syndrome patients with constipation or diarrhea. Official journal of the American College of Gastroenterology| ACG. 2003 Nov 1;98(11):2454-9.
Wright PS, Thomas SL. Constipation and diarrhea: the neglected symptoms. InSeminars in oncology nursing 1995 Nov 1 (Vol. 11, No. 4, pp. 289-297). WB Saunders.
Chey WY, Jin HO, Lee MH, Sun SW, Lee KY. Colonic motility abnormality in patients with irritable bowel syndrome exhibiting abdominal pain and diarrhea. Official journal of the American College of Gastroenterology| ACG. 2001 May 1;96(5):1499-506.
Bharucha AE, Chakraborty S, Sletten CD. Common functional gastroenterological disorders associated with abdominal pain. InMayo Clinic Proceedings 2016 Aug 1 (Vol. 91, No. 8, pp. 1118-1132). Elsevier.
Ikarashi N, Kon R, Sugiyama K. Aquaporins in the colon as a new therapeutic target in diarrhea and constipation. International Journal of Molecular Sciences. 2016 Jul 20;17(7):1172.