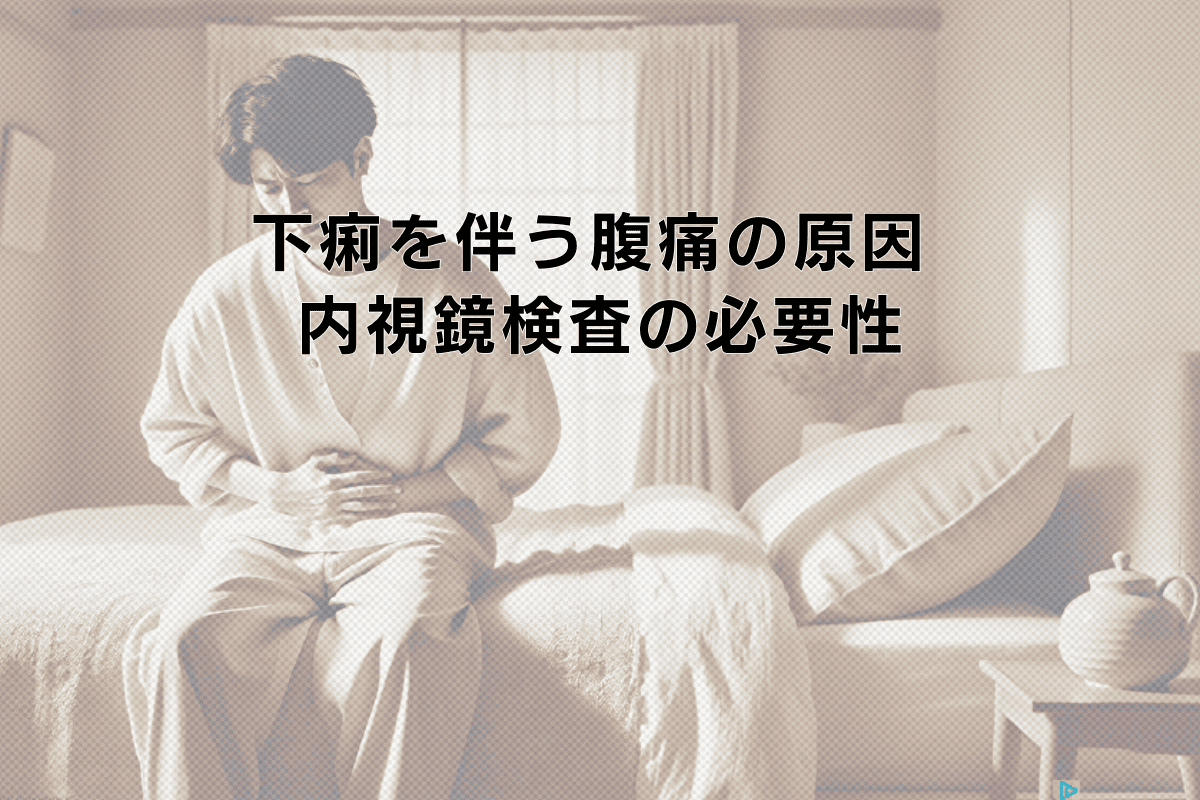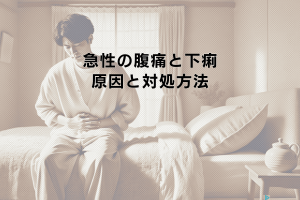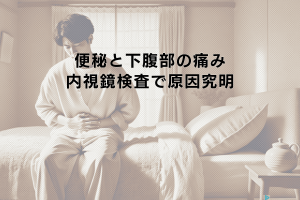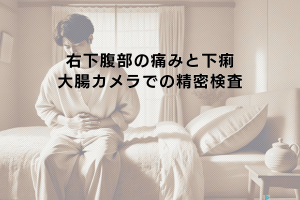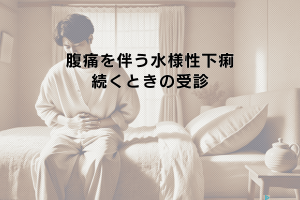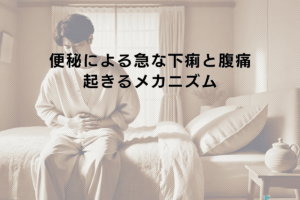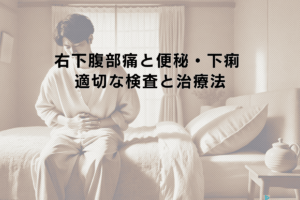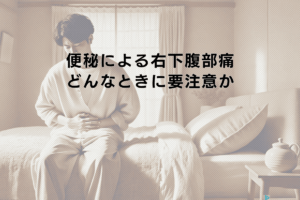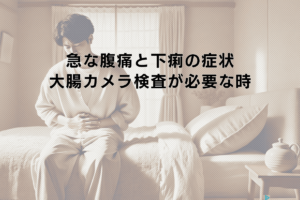お腹の痛みと下痢が同時に起きると日常生活や仕事に支障をきたしやすく、速やかな原因の解明と対処が必要ですが、原因が多岐にわたるため、症状を軽く考えて放置すると重症化することも考えられます。
状態によっては消化器の内視鏡検査(大腸カメラや胃カメラ)を受けることが重要ですので、医療機関の受診を検討してください。
この記事では、お腹が痛くて下痢になる主な原因や検査方法を解説し、内視鏡検査の必要性について詳しくご紹介します。
お腹が痛くて下痢が続くときに考えたい基本的なポイント
お腹の痛みを伴う下痢にはさまざまな原因があり、急性のものから慢性のもの、生活習慣やストレスに起因するものまで幅広いです。
痛みと下痢の両方が現れるときに着目したい要点を把握すると、医療機関を受診するタイミングや必要な検査の検討に役立ちます。
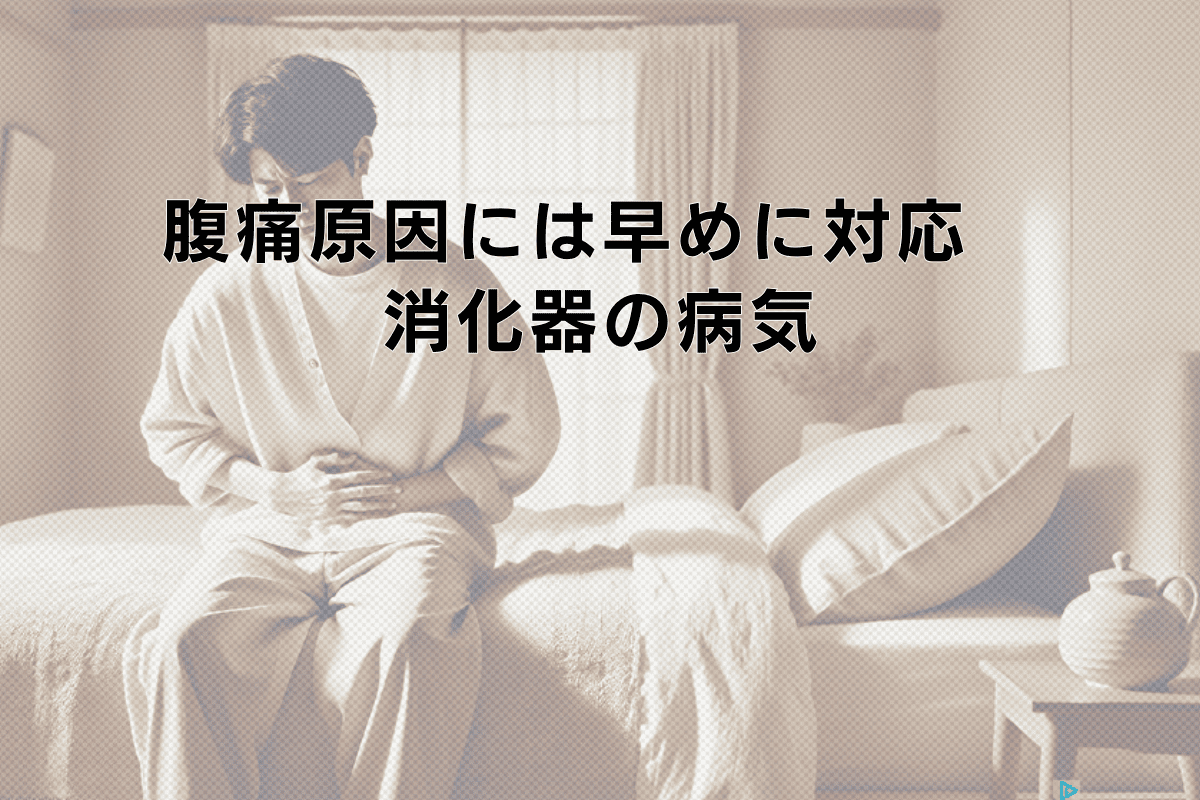
下痢と腹痛が併発するときの主なメカニズム
腸内環境の乱れや感染、炎症などにより腸の運動が亢進すると、水分を十分に吸収しきれずに便がゆるくなり、お腹がゴロゴロして痛みを感じたり、腹部膨満感が出現しやすくなります。
痛みの程度や痛む部位は原因によって異なるため、症状の詳細を記録することが大切です。
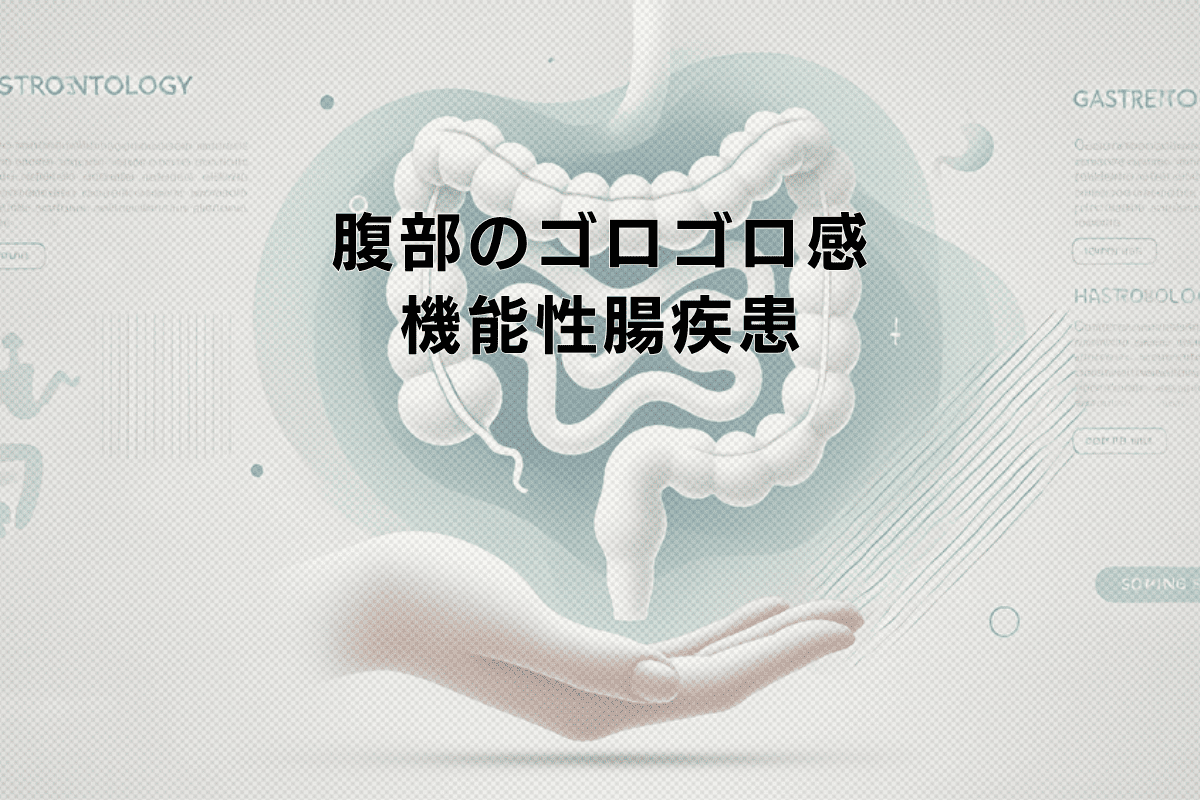
お腹痛い下痢:原因の多さと重要性
「お腹が痛くて下痢になる原因」は食あたりから過敏性腸症候群、炎症性腸疾患や大腸がんなど非常に多岐にわたるため、原因を一括りにして自己判断することは難しく、医師の診察や検査が必要なケースがあります。
短期で終わる場合と長期化する場合の違い
下痢が1~2日でおさまるケースは一時的な食あたりや腸内のちょっとした乱れであることが少なくありません。
ところが1週間以上続いたり、何度も再発したりする場合は腸管の病気や感染症、あるいはストレスなどが関与している可能性があります。長引くときは医療機関の受診を考えてください。
早期診断・早期治療の大切さ
軽度の下痢や腹痛でも放置すると症状が悪化したり、重大な病気が潜んでいるリスクがあります。基本的な問診や検便・血液検査に加えて、内視鏡検査を行うことで、治療につなげやすくなります。
お腹の痛みの主なパターン
| 痛みの種類 | 主な特徴 |
|---|---|
| 差し込むような痛み | 突発的に強い痛みがきては治まる場合が多い |
| 鈍い痛み | 長時間じわじわと痛みが続く |
| 下腹部の痛み | 腸の炎症や便秘・下痢が関与することが多い |
| みぞおちの痛み | 胃潰瘍、胃炎などの上部消化管トラブルが関係する |
急性下痢と慢性下痢を引き起こす主な要因
お腹の痛い下痢には、急性下痢と慢性下痢があります。
急性下痢は数日以内で治まることが多く、細菌・ウイルス感染などが代表的な要因で、慢性下痢は3週間以上持続している状態で、過敏性腸症候群や炎症性腸疾患などが当てはまります。
急性下痢の代表例と注意点
急性下痢として代表的なのは食中毒や細菌性・ウイルス性腸炎で、生ものや衛生状態の悪い場所での食事後、数時間から1日程度で激しい下痢や嘔吐が起こります。高熱や血便を伴う場合は医療機関の受診が大切です。
慢性下痢の代表例と注意点
慢性下痢では、過敏性腸症候群や炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎、クローン病など)を考慮します。これらはストレス、自己免疫の異常、遺伝など複合的な要因で起こり、長期にわたって腹痛や下痢が続くことが特徴です。
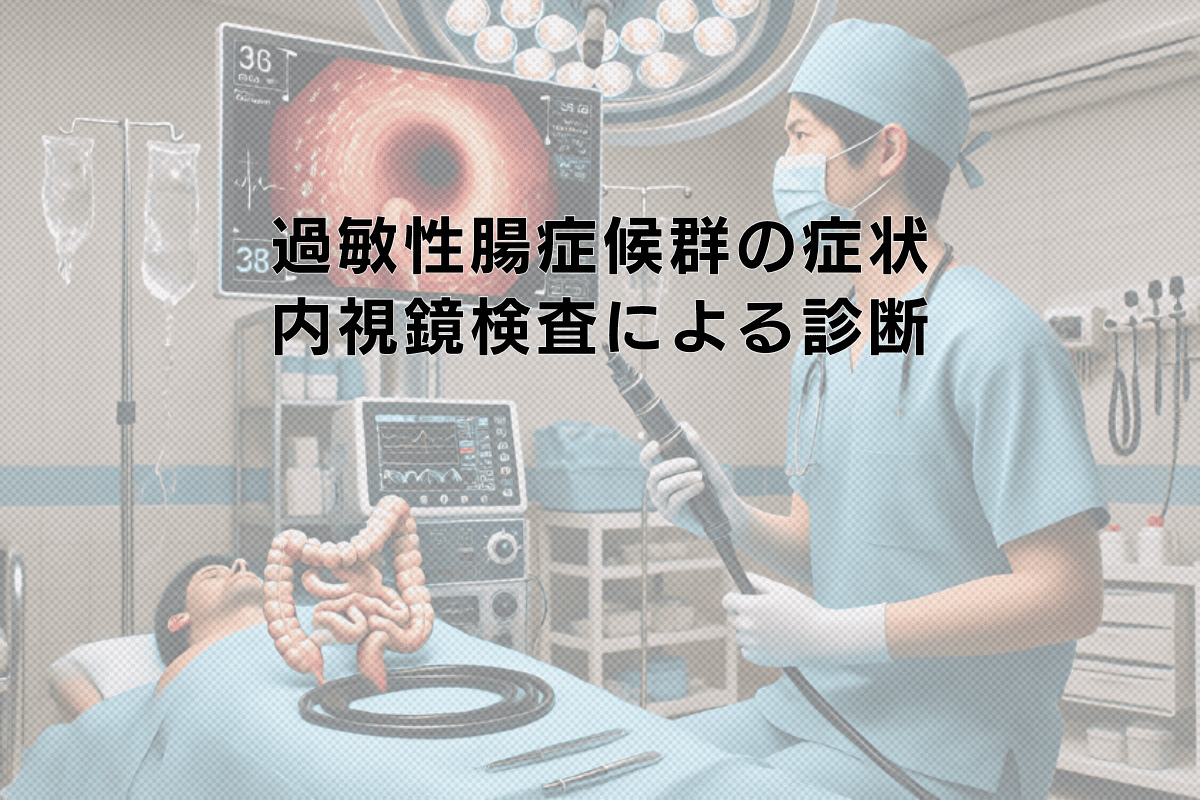
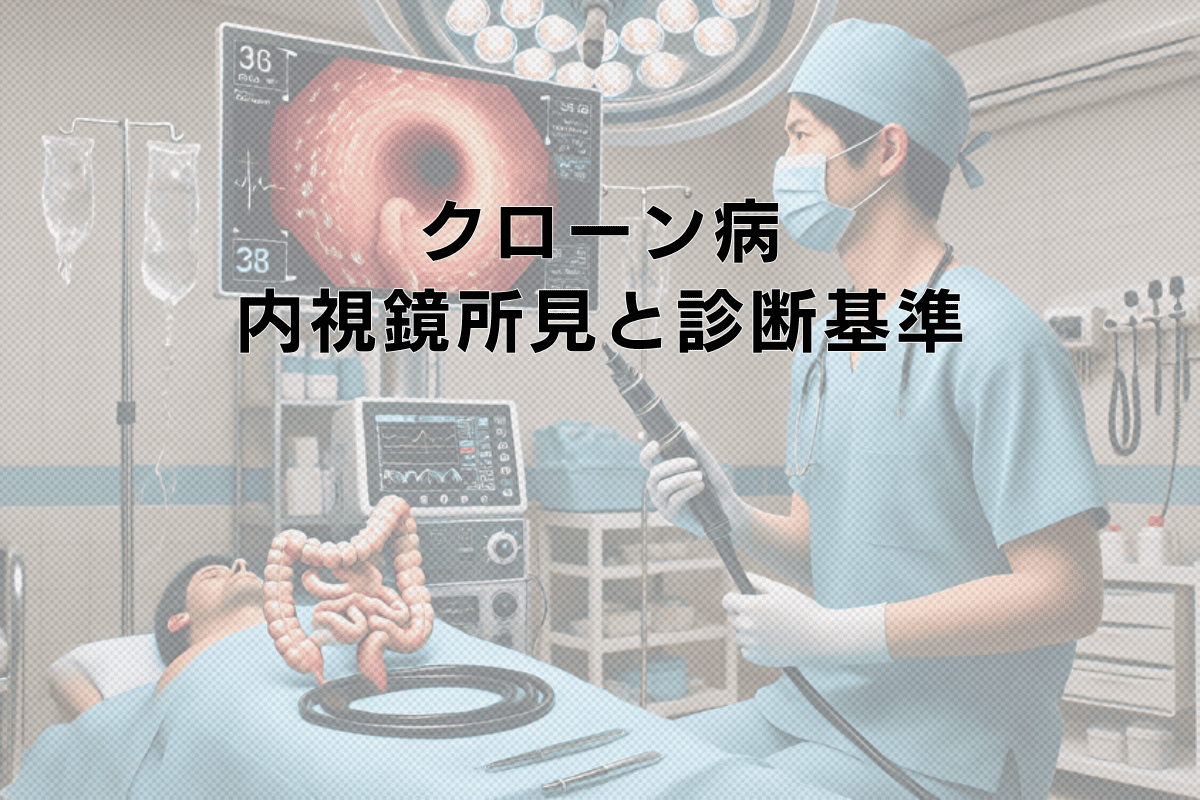

感染性と非感染性の鑑別ポイント
食中毒やウイルス性腸炎のように感染が疑われる場合は、急性の強い症状に加えて周囲に同様の症状の人がいることがありますが、非感染性の場合は症状の強さが一定ではなく、時間帯や食事内容、ストレスの有無で変化しやすいです。
診察時に医師に伝えたい情報
医療機関を受診した際、症状が始まった時期や便の色・性状、発熱の有無などを詳しく説明すると診断に役立ちます。時間や状況が許せば、下痢の頻度や量もおおまかに把握しておくとよいでしょう。
主な慢性下痢の原因と特徴
| 原因 | 主な特徴 |
|---|---|
| 過敏性腸症候群 | 便秘と下痢を繰り返す、ストレスで悪化しやすい |
| 炎症性腸疾患 | 血便や発熱などの全身症状を伴うことが多い |
| 甲状腺機能亢進症など | 代謝が上がりやすい体質になる |
| 薬剤性 | 特定の薬の副作用で慢性的な下痢が続く |
お腹が痛い下痢の背景に潜む重大な病気の可能性
お腹の痛みと下痢が続くとき、単なる食あたりや胃腸風邪以外に重大な病気が関わる可能性があり、症状の強さや期間だけでなく、血便や体重減少などの合併症状に着目すると、早期に専門的な検査の必要性を判断できます。
胃・十二指腸潰瘍などの上部消化管の病変
みぞおちあたりが痛くて下痢を伴う場合、胃や十二指腸に潰瘍がある場合があります。痛みは空腹時に強まり、下痢というより軟便や消化不良が続きやすいですが、人によっては腸が刺激されて下痢に至ることもあります。
大腸ポリープ・大腸がんの可能性
大腸ポリープや大腸がんは初期症状に乏しいものの、便通の異常や血便が見られるケースがあります。下痢と便秘を繰り返すときや便に血液が混ざるときは、早めの大腸カメラ検査を検討してください。

炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎・クローン病)
潰瘍性大腸炎やクローン病は腹痛と下痢を繰り返し、血便や体重減少などを伴うことが多い病気です。若年層で初発するケースが目立ちますが、中高年以降でも発症する可能性があり、早期診断によって重症化を防げます。
症状が重い場合は専門医への相談を
重度の腹痛や下痢に加えて、高熱、嘔吐、血便、黒色便、急激な体重減少などがある場合は速やかに医療機関へ相談してください。画像検査や内視鏡検査が必要になるケースも少なくありません。
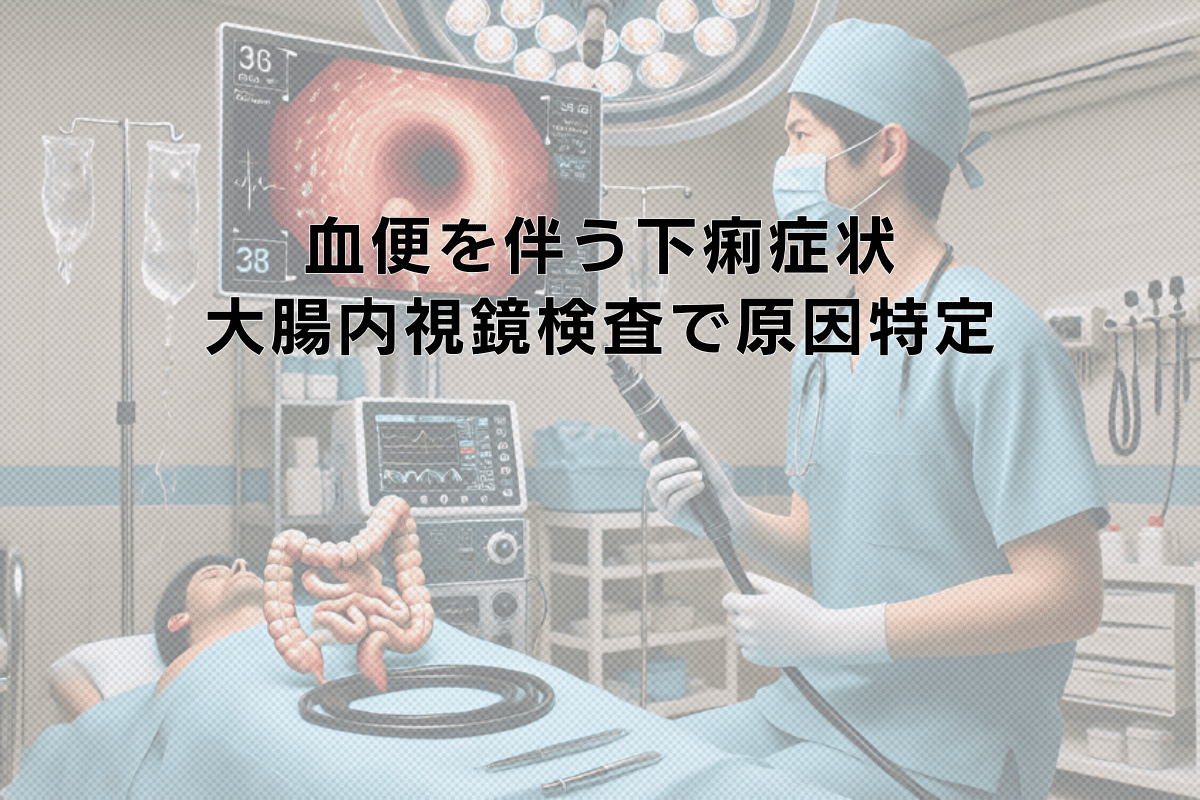
お腹が痛いときに注目したいその他の症状
| 症状 | 可能性のある病気 |
|---|---|
| 高熱 | 細菌性腸炎、ウイルス性腸炎、腸炎以外の感染症など |
| 血便 | 潰瘍性大腸炎、大腸ポリープ、大腸がんなど |
| 体重減少 | 消化管がん、炎症性腸疾患、甲状腺機能亢進症など |
| 嘔吐 | ウイルス性腸炎、胃腸風邪、食中毒など |
下痢を伴う腹痛への基本的な検査とその意義
お腹痛い下痢が治まらずに続く場合、まずは問診や視診・触診などの基本的な診察が行われ、その後、症状に応じて検便、血液検査、画像検査、内視鏡検査などが追加されます。
問診と身体診察
医師はいつから症状が続いているか、どのような便の性状か、食事や生活リズムに変化があったかなどを詳しく尋ねます。さらに腹部を触診して圧痛や張り具合を確認し、全身状態の評価を行うことも含まれます。
検便・血液検査でわかること
検便では細菌やウイルス、寄生虫などの感染の有無を探り、血液検査では炎症反応や貧血、白血球数、電解質のバランスなどを確認します。必要に応じて甲状腺機能などホルモンの数値も確認するので、原因の絞り込みに有効です。
画像検査(CT・MRIなど)の役割
腸管の形状や周辺臓器との関係を視覚的に把握したい場合にCTやMRIが行われます。腸閉塞や腫瘍、臓器の炎症を見つけやすく、外科的処置の要否を検討するうえでも役に立ちます。
内視鏡検査の具体的な手順と特徴
大腸カメラや胃カメラを用いると、直接粘膜の状態を観察できるため病変の有無を正確に把握できます。組織の一部を採取(生検)して病理検査を行えば、炎症の程度や悪性の有無なども評価しやすいです。
下痢をともなう腹痛が長期化する場合は、早めに検討することが望ましいでしょう。
検査種類と特徴
| 検査名 | 主な特徴 |
|---|---|
| 検便 | 細菌・ウイルス検査、便潜血検査などが含まれ、感染性の有無や出血を確認 |
| 血液検査 | 白血球数や炎症反応、貧血、甲状腺機能などを確認 |
| 画像検査(CT/MRI) | 腫瘍や大きな炎症、臓器の形状異常を検出 |
| 内視鏡検査 | 粘膜の状態を直接観察し、必要なら組織を採取し病理検査を行える |
なぜ内視鏡検査が重要なのか
お腹が痛くて下痢が長く続く場合や、原因がはっきりしない場合には、大腸カメラや胃カメラなどの内視鏡検査を行うメリットがあります。直接粘膜を観察し、組織を採取できるため、早期の病変発見につながりやすいです。
大腸カメラ検査のメリットと受診タイミング
大腸カメラ検査では、大腸ポリープや炎症性腸疾患の有無を高い精度で診断できます。ポリープを発見した場合は、検査中に切除が可能なこともあり、将来的な大腸がんリスクを下げる一助となります。
便潜血検査が陽性になった場合や下痢と便秘を繰り返す場合などに受診することが多いです。

胃カメラ検査のメリットと受診タイミング
みぞおち付近の痛みや胃もたれ、吐き気が強く、なおかつ下痢を併発する場合には胃カメラ検査を考慮するとよいです。
胃や十二指腸の潰瘍、ポリープなどの有無を直接確認でき、ピロリ菌感染の有無も、胃カメラと組織検査で判別しやすくなります。

検査時の注意事項と心構え
内視鏡検査を受ける際は、事前の食事制限や下剤の使用などが必要になります。検査当日は医師や看護師の指示に従い、安全に検査を受けることが大切です。痛みが心配な方には鎮静剤を用いる方法が選択されることもあります。
内視鏡検査の費用と保険適用の有無
基本的に病気が疑われる場合の内視鏡検査は保険適用で、費用負担は3割負担が一般的ですが、高額療養費制度などを活用すれば自己負担額が軽減します。
内視鏡検査で発見しやすい病気
| 病気・病変 | 大腸カメラ | 胃カメラ |
|---|---|---|
| 大腸ポリープ | 発見と同時に切除が可能な場合がある | 対象外 |
| 大腸がん | 粘膜の潰瘍化や腫瘍の形状などを直接確認 | 対象外 |
| 胃・十二指腸潰瘍 | 対象外 | 潰瘍の有無を直接観察 |
| ピロリ菌感染 | 対象外 | 粘膜組織採取と迅速ウレアーゼ試験などで判定 |
| 炎症性腸疾患 | 粘膜の炎症範囲・程度を確認 | 状況によっては確認 |
お腹が痛くて下痢が起きる方へおすすめのセルフケア
医療機関での検査や治療は重要ですが、軽度な症状や一時的な腹痛・下痢に対しては、自宅で行えるケアも有効です。ただし症状が長引く場合や激しい痛みが伴うときは早めに受診することを検討してください。
水分補給と食事管理のポイント
下痢で体内の水分や電解質が失われると、脱水症状を起こしやすくなるので、スポーツドリンクなどで水分と塩分を補給しましょう。食事は消化に負担が少ないものを選び、脂っこいものや刺激物は避けると痛みを和らげやすいです。
生活習慣の見直し
ストレスや睡眠不足、過度なアルコール摂取などは腸内環境を乱す原因です。適度な運動を取り入れ、十分な休息を確保すると、腸の働きを整えやすくなります。喫煙者は、消化器症状の改善のためにも禁煙を意識してください。
ストレスとの上手な付き合い方
過敏性腸症候群のようにストレスが主要な要因になることもあるので、リラックス法や日々のストレス発散方法を身につけると、お腹の不調を軽減できる可能性があります。ヨガや呼吸法、ウォーキングなど、自分に合った方法を探すとよいです。
症状が長引くときは医師の判断が必要
セルフケアで改善が見られなかったり、症状が再発を繰り返すときは、医師の診察と必要な検査が欠かせません。下痢や腹痛が長引くときは、医療機関を受診してください。
自宅ケア
- 水分補給をこまめに行い、甘い飲み物や刺激物を避ける
- 温かい食べ物や消化のよいもの(お粥、うどんなど)を中心に摂る
- 充分な睡眠と休息を心がける
- 軽い運動や深呼吸などで腸の動きを整える
- 体を冷やさないように注意する
お腹に負担をかけにくい食事
| 食品ジャンル | おすすめの食品例 |
|---|---|
| 炭水化物 | お粥、うどん、軟らかいパンなど |
| タンパク質 | 豆腐、白身魚、皮のない鶏肉など |
| ビタミン・ミネラル | 柔らかく煮た野菜(にんじん、じゃがいもなど)、果物のすりおろし |
| 水分補給 | 常温の水、麦茶、薄めたスポーツドリンクなど |
内視鏡検査で発見された場合の治療とフォローアップ
内視鏡検査で何らかの病変が見つかった場合は原因に応じた治療を行うと、長期的な再発防止や合併症予防につながります。
病変が見つかった場合の治療フロー
大腸ポリープなどが見つかった場合は、検査時に切除が可能なケースがあり、また、炎症性腸疾患の場合はステロイドや免疫調整薬を用いて炎症を抑える治療を実施します。
胃潰瘍・十二指腸潰瘍でピロリ菌感染が確認された場合は除菌治療を検討してください。
継続的な通院と再検査の必要性
薬物療法の効果を確認したり、新たな病変の発生をチェックするために、定期的な通院や再検査が行われます。症状が落ち着いたあとも医師の指示に沿って再発予防を続けることが重要です。
生活習慣の改善と再発予防
治療後は腸内環境の安定を図るために、バランスの良い食事、適度な運動、ストレスコントロールを行うことが大切です。再発リスクを下げるには、医師や管理栄養士のアドバイスを受けながら生活習慣を見直すことが有効です。
治療が完了しても注意したいポイント
下痢や腹痛が消失しても、原因となった病気が完全に治癒していないことがあるので、自己判断で通院を中断しないでください。症状が再び現れる前にフォローアップを受けて対処すると、重症化を防ぎやすくなります。
検査後の経過観察の流れ
| タイミング | 内容 |
|---|---|
| 検査直後 | 切除や処置を行った部分の止血確認、安静管理 |
| 数日後~数週間後 | 病理検査の結果説明、薬物療法の効果確認 |
| 数か月後(必要に応じ) | 症状の安定度評価、追加治療の要否検討 |
| 半年~1年後 | 再検査の必要性の判断と生活習慣指導 |
よくある質問
症状が長引くお腹の痛みと下痢に関して、多くの方が疑問を抱く点をまとめました。自己判断で必要な検査や治療を見送らず、気になる場合は医療機関への相談を検討してください。
- 内視鏡検査は痛くありませんか?
-
個人差はありますが、鎮静剤(麻酔)を用いることで検査中の苦痛を軽減する方法があります。不安が強い方は検査前に医師に相談してください。
- 下痢を起こした直後に大腸カメラを受けられますか?
-
症状の程度によっては下剤の服用が難しい場合もあるため、医師と相談する必要があり、場合によっては症状が落ち着いてから検査日程を調整することもあります。
- 食事制限はどのくらい必要ですか?
-
検査前日は消化に良いものを中心に摂るなど、簡単な食事制限が必要で、当日の朝からは原則として食事を控えるよう指示されることが多いです。詳細は医療機関からの案内に従ってください。
- 何度も下痢を繰り返していますが、重大な病気ではないでしょうか?
-
短期間で治まる下痢は軽微な原因である可能性もありますが、何度も繰り返す場合は念のため受診を検討してください。重篤な病気が隠れているリスクもあるため、安心のためにも医師に相談をおすすめします。
次に読むことをお勧めする記事
【大腸内視鏡検査の3日前からの食事制限と準備】
下痢と腹痛の原因を探るには内視鏡検査が鍵です。実際に大腸カメラを受ける前に必要な準備と注意点を押さえておくと、検査当日の不安を大きく減らせます。
【腹部のゴロゴロ感と下痢|機能性腸疾患の可能性】
腹痛・下痢の背景には腸の動きが敏感になる機能性腸疾患が潜むことも。ストレスとの関係やセルフケアのヒントを知って、より包括的に腸を整えましょう。
参考文献
Fry LC, Carey EJ, Shiff AD, Heigh RI, Sharma VK, Post JK, Hentz JG, Fleischer DE, Leighton JA. The yield of capsule endoscopy in patients with abdominal pain or diarrhea. Endoscopy. 2006 May;38(05):498-502.
May A, Manner H, Schneider M, Ipsen A, Ell C, null for the CEDAP-Plus Study Group. Prospective multicenter trial of capsule endoscopy in patients with chronic abdominal pain, diarrhea and other signs and symptoms (CEDAP-Plus Study). Endoscopy. 2007 Jul;39(07):606-12.
Shen B, Khan K, Ikenberry SO, Anderson MA, Banerjee S, Baron T, Ben-Menachem T, Cash BD, Fanelli RD, Fisher L, Fukami N. The role of endoscopy in the management of patients with diarrhea. Gastrointestinal endoscopy. 2010 May 1;71(6):887-92.
Katsinelos P, Fasoulas K, Beltsis A, Chatzimavroudis G, Paroutoglou G, Maris T, Mimidis K, Koufokotsios A, Terzoudis S, Atmatzidis S, Kaltsa A. Diagnostic yield and clinical impact of wireless capsule endoscopy in patients with chronic abdominal pain with or without diarrhea: a Greek multicenter study. European journal of internal medicine. 2011 Oct 1;22(5):e63-6.
Valero M, Bravo-Velez G, Oleas R, Puga-Tejada M, Soria-Alcívar M, Escobar HA, Baquerizo-Burgos J, Pitanga-Lukashok H, Robles-Medranda C. Capsule endoscopy in refractory diarrhea-predominant irritable bowel syndrome and functional abdominal pain. Clinical Endoscopy. 2018 Nov 16;51(6):570-5.
Kinoshita Y, Ariyoshi R, Fujigaki S, Tanaka K, Morikawa T, Sanuki T. Endoscopic diagnosis of chronic diarrhea. DEN open. 2022 Apr;2(1):e53.
Yamada E, Kuriyama H, Uchida E, Murata Y, Hata Y, Tagri M, Isozaki Y, Oyamada H, Ozawa Y, Ito T, Mizuki A. Association between endoscopic findings related to colonic diverticula and bowel habits: A multicenter study in Japan. Journal of gastroenterology and hepatology. 2017 Dec;32(12):1938-42.
Suzuki H, Nakamura M, Yamamura T, Maeda K, Sawada T, Mizutani Y, Ishikawa T, Furukawa K, Ohno E, Honda T, Kawashima H. A prospective study of factors associated with abdominal pain in patients during unsedated colonoscopy using a magnifying endoscope. Internal Medicine. 2020 Aug 1;59(15):1795-801.
Nagata N, Kobayashi K, Yamauchi A, Yamada A, Omori J, Ikeya T, Aoyama T, Tominaga N, Sato Y, Kishino T, Ishii N. Identifying bleeding etiologies by endoscopy affected outcomes in 10,342 cases with hematochezia: CODE BLUE-J Study. Official journal of the American College of Gastroenterology| ACG. 2021 Nov 1;116(11):2222-34.
Sato S, Matsui T, Tsuda S, Yao T, Iwashita A, Takagi Y, Nishida T. Endosocopic abnormalities in a Japanese patient with collagenous colitis. Journal of gastroenterology. 2003 Aug;38:812-3.