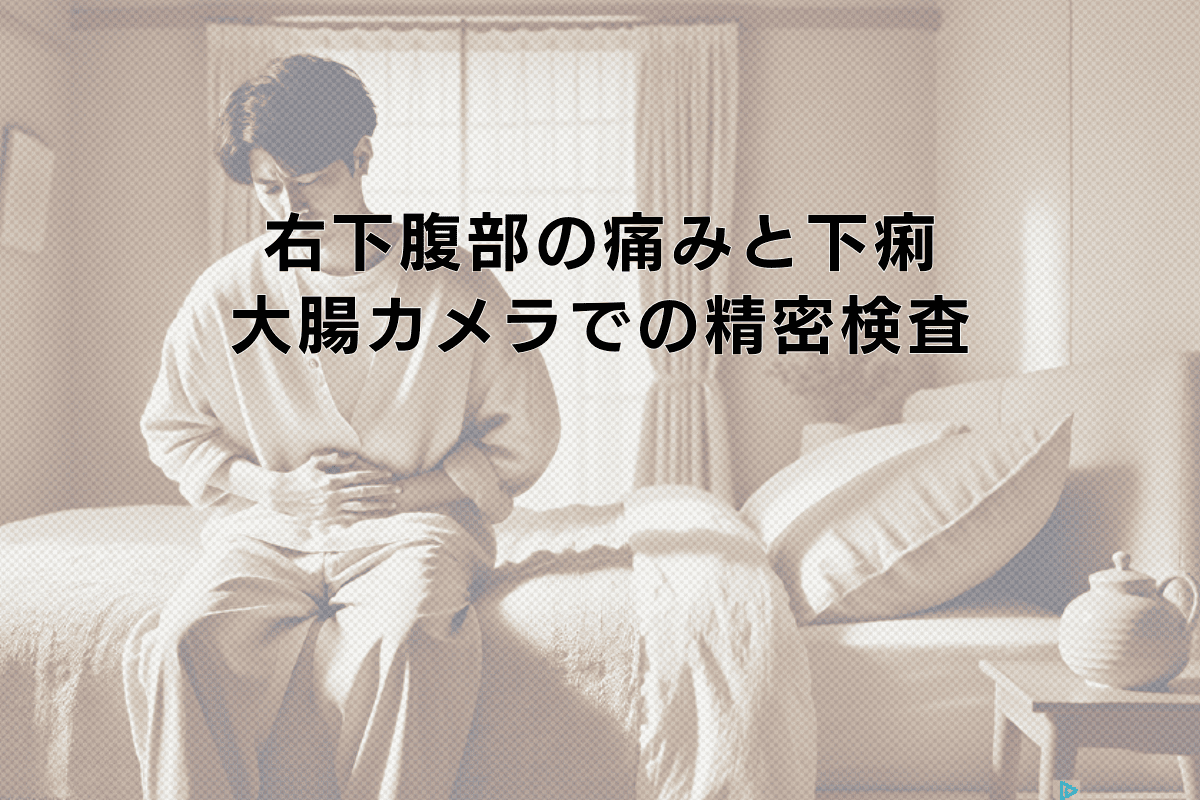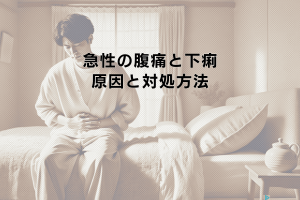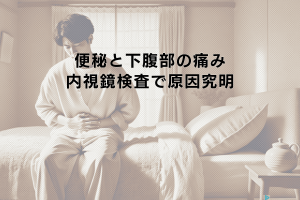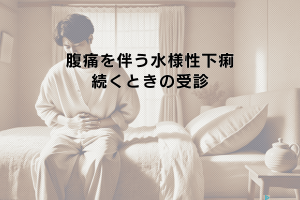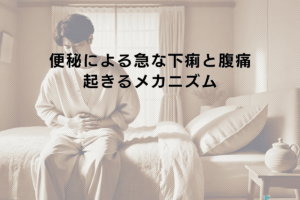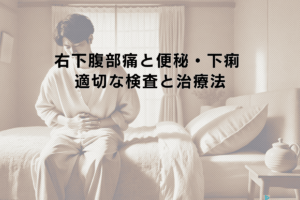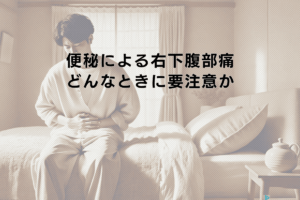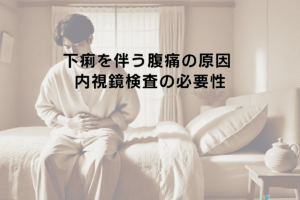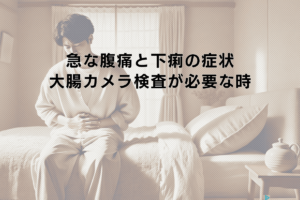突然の右下腹部の痛みと下痢の症状が現れると、多くの方が大きな不安を感じます。それは、急性虫垂炎(いわゆる盲腸)のような、緊急の対応を要する病気のサインである可能性も否定できないからです。
この記事では、右下腹部の痛みと下痢を起こす可能性のある様々な病気、ご自身で注意すべき症状のチェックポイント、医療機関での診察の流れ、正確な診断のために重要な大腸カメラ(大腸内視鏡検査)について、詳しく解説します。
右下腹部の痛みと下痢 なぜ同時に起こるのか
右下腹部の痛みと下痢が同時に起こることには、消化管の構造と機能が深く関係しています。お腹の中では、様々な臓器が互いに影響し合っており、一つの場所の異常が他の部位の症状として現れることは珍しくありません。
栄養を吸収する小腸と、水分を吸収し便を形成する大腸のつなぎ目にあたる右下腹部は、解剖学的に炎症が起こりやすい場所の一つです。
消化管の構造と機能
消化管は、口から始まり肛門に至るまでの一本の長い管であり、それぞれの部位が連携して消化・吸収活動を行っていて、右下腹部には、小腸の最終部分である回腸末端と、大腸の入り口である盲腸があります。
接続部は回盲部と呼ばれ、消化された食べ物が液体状で小腸から大腸へと流れ込む重要な関所です。
また、盲腸からは虫垂という指のような形をした小さな突起が伸びていて、虫垂はリンパ組織が豊富で、腸内の免疫機能に関わっています。
この回盲部に炎症が起こると、栄養や水分の吸収がうまくいかなくなり、腸の動きも異常をきたすため、腹痛や下痢といった症状が顕著に現れるのです。
右下腹部に位置する主な消化管
| 臓器名 | 主な役割 | 炎症が起きた場合の影響 |
|---|---|---|
| 回腸末端(小腸の終わり) | 栄養素(特にビタミンB12)の最終吸収 | 栄養吸収不良による下痢、腹痛、腸管のむくみ |
| 盲腸(大腸の始まり) | 小腸からの内容物を受け入れ、水分吸収を開始 | 腸の動きの異常、腹痛、腹部膨満感 |
| 虫垂 | 免疫機能に関与、腸内細菌叢の維持 | 強い炎症による激しい腹痛(急性虫垂炎) |
炎症が引き起こす症状の連鎖
右下腹部にある臓器に細菌感染やその他の原因で炎症が起こると、体は防御反応として様々な化学物質を放出し、物質の一部は、知覚神経を刺激して痛みを感じさせます。これが腹痛の直接的な原因です。
同時に、このような化学物質は腸の筋肉層にも作用し、腸の動き、すなわちぜん動運動を異常に活発にさせます。
腸の動きが過剰になると、食べ物や水分が腸内を速いスピードで通過してしまい、大腸で水分が十分に吸収される前に便として排出されてしまい、これが下痢となります。
腸の動きと痛みの関係
腸は、ぜん動運動と呼ばれる収縮と弛緩を繰り返すことで、内容物を肛門方向へ運んでいます。炎症があると、規則正しい運動のリズムが乱れます。
腸管が異常に強く収縮すると、内臓がねじれるような、あるいは差し込むような鋭い痛み(疝痛発作)を感じることがあり、また、炎症によって腸の壁全体がむくんで腫れると、持続的で鈍い痛みを感じることもあります。
下痢の際に感じる腹痛は、こうした異常なぜん動運動によって起きることが多く、腸の内容物が炎症部位を通過する際の物理的な刺激も痛みを増強させる要因です。
右下腹部の痛みを伴う下痢で考えられる主な病気
右下腹部の痛みと下痢は、様々な病気のサインとして現れます。ここでは、代表的な病気とその特徴について、より詳しく解説します。
急性虫垂炎(盲腸)
一般的に「盲腸」として知られていますが、医学的には急性虫垂炎と呼び、盲腸から突き出ている虫垂に炎症が起こる病気です。
典型的な症状の経過として、最初はみぞおちのあたりやへその周りに漠然とした不快感や痛みとして始まり、吐き気を伴うこともあります。
数時間から半日ほどかけて、痛みが徐々に右下腹部へと移動し、鋭くはっきりとした痛みになるのが特徴です。炎症が進行すると、発熱や食欲不振が見られ、炎症が周囲の腸に波及することで下痢を引き起こすことがあります。
放置して虫垂の壁が破れると、細菌が腹腔内に広がり、腹膜炎という命に関わる重篤な状態になる可能性があるため、早期の診断と治療が極めて重要です。
感染性腸炎
ウイルスや細菌などが腸に感染して炎症を起こす病気で、いわゆる食中毒やウイルス性胃腸炎もこれに含まれます。
主な症状は、突然発症する下痢、腹痛、嘔吐、発熱です。腹痛は腹部全体に起こることが多いですが、病原体の種類によっては特定の場所に強い炎症を起こすことがあります。
カンピロバクターやエルシニア、サルモネラといった細菌は、小腸の終わりである回腸末端に強い炎症(回腸末端炎)を起こしやすく、右下腹部に限局した強い痛みと発熱をきたすため、急性虫垂炎との区別が難しいことがあります。
生肉や加熱不十分な食品の摂取歴、海外渡航歴などが診断の手がかりです。
主な感染性腸炎の原因
| 種類 | 代表的な病原体 | 特徴・注意点 |
|---|---|---|
| ウイルス性 | ノロウイルス、ロタウイルス | 冬季に流行。嘔吐や水様性の下痢が主症状。脱水に注意が必要。 |
| 細菌性 | カンピロバクター、サルモネラ菌 | 鶏肉や卵などが原因となりやすい。発熱、腹痛、血便を伴うことがある。 |
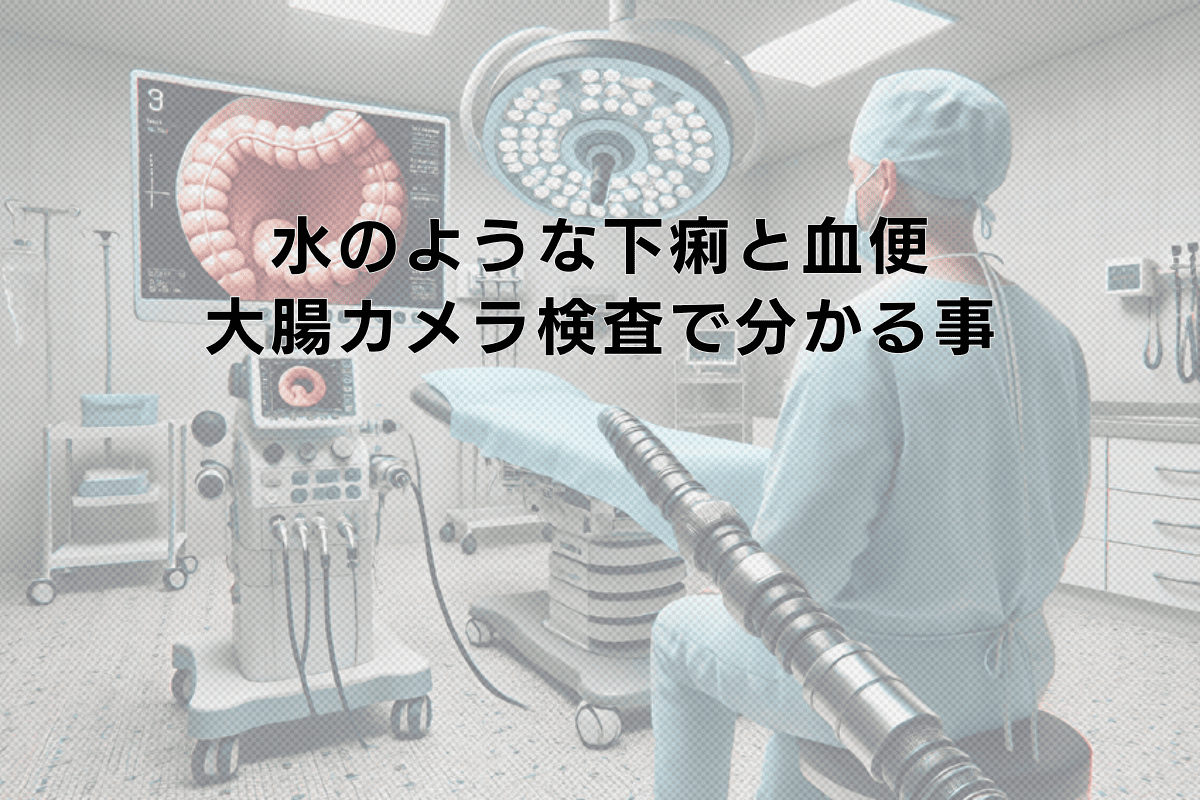
炎症性腸疾患(クローン病・潰瘍性大腸炎)
炎症性腸疾患は、腸に慢性的(長期間続く)な炎症が起こる原因不明の病気の総称で、主にクローン病と潰瘍性大腸炎に分けられます。どちらも腹痛、下痢、血便、体重減少などが主な症状ですが、炎症が起こる場所に違いがあります。
潰瘍性大腸炎は大腸に限定して炎症が起こるのに対し、クローン病は口から肛門までの消化管のあらゆる場所に炎症が起こりえます。
中でもクローン病は、小腸の終わりである回腸末端が好発部位であるため、右下腹部の痛みと慢性的な下痢が続く場合は、この病気の可能性を考える必要があります。
活動期(症状が強い時期)と寛解期(症状が落ち着いている時期)を繰り返すことが多く、長期にわたる専門的な治療と管理が大事な病気です。
大腸憩室炎
大腸の壁の一部が、圧力などによって袋状に外側に飛び出したものを大腸憩室と呼び、憩室に便などが詰まって細菌が繁殖し、炎症を起こした状態が憩室炎です。
憩室は大腸のどこにでもできる可能性がありますが、欧米人では左側(S状結腸)に多いのに対し、日本人を含むアジア人では右側の大腸(上行結腸や盲腸)にできやすい傾向があります。
右側の憩室で炎症が起こると、右下腹部の持続的な痛みと発熱、下痢や便秘といった便通の異常を起こします。急性虫垂炎と症状が非常に似ているため、CTなどの画像検査が診断に有用です。
女性の場合に考えられる婦人科系の病気
女性の場合、右下腹部には卵巣や卵管といった臓器もあるため、婦人科系の病気が原因で痛みが生じている可能性も考慮に入れることが必要です。
卵巣嚢腫の茎捻転(卵巣の根元がねじれること)や破裂、子宮外妊娠、骨盤内炎症性疾患(PID)などが挙げられます。
下痢を直接引き起こすわけではありませんが、強い炎症が近くにある腸を刺激することで、下痢を伴うことがあります。消化器症状に加えて、不正性器出血やおりものの異常などがある場合は、婦人科的な病気も疑われます。
緊急性が高い症状の見分け方
右下腹部の痛みと下痢がある場合、それが自宅で安静にして様子を見ても良いものか、それともすぐに医療機関を受診すべきものか、判断に迷うことがあるでしょう。ここでは、緊急性が高い可能性を示す危険なサインについて、解説します。
痛みの強さと性質の変化
痛みの感じ方は、重篤な状態を見分けるための重要な手がかりになります。最初は我慢できる程度の鈍い痛みだったものが、時間とともにどんどん強くなり、体を動かすのもつらくなる場合は注意が必要です。
咳やくしゃみをする、歩く、車で段差を乗り越えるといった振動がお腹に響くような痛みは、炎症が腹膜(お腹の内側を覆う膜)にまで広がっている可能性を示唆するサイン(腹膜刺激症状)であり、緊急性が高い状態と考えられます。
じっとしていても治まらない、冷や汗が出るほどの激しい痛みは、腸に穴が開いている(消化管穿孔)などの危険な状態の可能性もあります。
伴う症状(発熱・嘔吐・血便)
痛みや下痢に加えて、他の症状が出ていないかどうかも注意深く観察しましょう。38度以上の高熱が続く、何度も嘔吐して水分が全く摂れない、便に明らかに血が混じる(血便)といった症状は、単なる胃腸の不調ではない可能性を示しています。
嘔吐が止まらない場合は脱水症状が急速に進行する危険があります。
また、便に混じる血が、鮮やかな赤色であれば大腸や肛門に近い場所からの出血、黒くてドロドロしたタール状の便(黒色便)であれば胃や十二指腸など上部消化管からの出血が疑われ、いずれも専門的な検査が必要です。
緊急受診を検討すべきサイン
| 分類 | 具体的な症状の例 | 考えられる状態 |
|---|---|---|
| 痛みの性質 | 我慢できない激痛、歩くと響く痛み、お腹が板のように硬い | 腹膜炎、腸管穿孔、腸閉塞など |
| 伴う症状 | 38.5度以上の高熱、頻回の嘔吐、意識がもうろうとする、呼吸が浅く速い | 重度の感染症、敗血症、高度の脱水 |
| 便の状態 | 大量の血便(便器が真っ赤になる)、黒色便(タール便) | 消化管からの活動性出血 |
時間経過と症状の悪化
症状が始まってからの時間経過も重要な判断材料で、数時間のうちに急速に症状が悪化している場合は、病状が活発に進行している証拠です。
最初はお腹全体の不快感だったのが、数時間後には右下腹部の一点を指で押さえると激痛が走るようになるといったケースは、急性虫垂炎でよく見られます。
市販の整腸剤や解熱鎮痛薬を飲んでも全く改善しない、むしろ悪化するような場合も、原因が単純なものではない可能性が高いため、医療機関への受診を急ぐべきです。
すぐに医療機関を受診すべきサイン
以下のリストに当てはまる項目が一つでもある場合は、時間帯や曜日に関わらず、救急外来のある医療機関に連絡し、指示を仰ぐことを強く推奨します。
- 突然発症した、これまでに経験したことのないような立っていられないほどの激しい腹痛
- 意識が遠のく、または、呼びかけへの反応が鈍い
- 呼吸が苦しい、脈が異常に速い、または弱い
- お腹全体が硬く、軽く押しただけでも強い痛みがある
- 便やガス(おなら)が全く出ないのにお腹が張ってくる
医療機関での診察の流れ
症状に不安を感じて医療機関を受診した場合、どのような診察や検査が行われるのでしょうか。ここでは、一般的な診察の流れを説明します。
問診で伝えるべきこと
診察は問診から始まり、医師は症状について詳しく質問することで、病気の原因を探る手がかりを得ます。正確な診断のためには、できるだけ詳しく、正確に情報を伝えることが大切です。
いつから、どのような症状が、どのように変化してきたのかを時系列で話せると、診断の大きな助けになります。
問診で準備しておくと良い情報
| 項目 | 伝えるべき内容の例 |
|---|---|
| 症状の経過 | 昨日のお昼頃からみぞおちがムカムカし始め、夜には痛みが右下腹部に移ってきた。 |
| 便の状態 | 今朝から3回、水のような下痢をしている。色は黄色で、血や粘液は混じっていない。 |
| 食事内容 | 2日前に、友人とバーベキューで鶏肉を食べた。 |
| 既往歴・服薬歴 | 高血圧で薬を飲んでいる。10年前に別の手術でお腹を開いたことがある。 |
身体診察(触診・聴診)
問診の次に行われるのが身体診察です。医師はまず聴診器でお腹の音を聞き、腸の動き(腸蠕動音)が活発か、あるいは逆に弱まっていないかを確認します。
次に、お腹を優しく触ったり、軽く押したり(触診)、叩いたり(打診)して、痛みの場所や強さ、お腹の硬さ、しこりの有無などを調べます。
右下腹部を指でゆっくり押し、素早く離したときに痛みが響くかどうか(反跳痛)は、腹膜に炎症が及んでいるか判断する上で重要な所見です。
また、痛みを和らげるために無意識にお腹の筋肉が硬くなる(筋性防御)所見も、重篤な状態を示唆します。
血液検査や画像検査の目的
問診と身体診察から特定の病気が疑われる場合、診断を確定し重症度を評価するために追加の検査を行います。血液検査では、白血球の数やCRPという炎症反応の数値を見ることで、体内でどの程度の炎症が起きているかを客観的に評価できます。
超音波(エコー)検査やCT検査といった画像検査は、お腹の中の臓器の状態を直接見るためのものです。
超音波検査は放射線被ばくがなく手軽に行える利点があり、腫れ上がった虫垂や、炎症で厚くなった腸壁、腹水の有無などを確認できます。
CT検査は、より広範囲のお腹の中を詳細に観察でき、虫垂炎や憩室炎の診断、さらには膿のかたまり(膿瘍)の形成などを正確に把握するのに非常に有用です。
大腸カメラ(大腸内視鏡検査)による精密検査の重要性
急性期の症状が落ち着いた後も下痢や腹痛が続く場合や、炎症性腸疾患のように慢性的な病気が疑われる場合には、大腸カメラによる精密検査を検討します。
大腸カメラで何がわかるのか
大腸カメラの最大の利点は、大腸の粘膜の状態をリアルタイムで、かつ拡大して詳細に観察できる点です。炎症の有無はもちろん、その範囲、重症度、ポリープやがん、憩室の存在などを直接目で見て確認できます。
感染性腸炎やクローン病、潰瘍性大腸炎といった病気では、それぞれに特徴的な粘膜の所見(縦走潰瘍、敷石像、血管透見像の消失など)が見られるため、診断を確定する上で非常に重要な情報をもたらします。
また、症状の原因がはっきりしない慢性の下痢の場合、顕微鏡レベルの微細な炎症(顕微鏡的大腸炎)が原因であることもあり、その診断には大腸カメラによる組織採取が必須です。
大腸カメラで確認できる主な所見
| 所見 | 何がわかるか | 関連する可能性のある病気 |
|---|---|---|
| 粘膜の発赤・むくみ | 炎症の存在と程度 | 感染性腸炎、炎症性腸疾患、虚血性腸炎 |
| びらん・潰瘍 | 粘膜のただれや、深くえぐれた傷 | クローン病、潰瘍性大腸炎、腸結核 |
| ポリープ・腫瘍 | 粘膜の隆起や、いびつな盛り上がり | 大腸ポリープ、大腸がん、カルチノイド |
検査の準備と当日の流れ
正確で安全な検査を行うためには、大腸の中を空っぽにしておく必要があるため、検査前日は消化の良い食事(検査食など)をとり、就寝前に下剤を服用します。
検査当日は、朝から約1.5から2リットルの液体状の下剤(腸管洗浄液)を数時間かけて飲み、便が透明な液体になるまで腸内を洗浄し、医療機関に到着後、検査着に着替え、検査室のベッドに横になります。
多くの施設では、鎮静剤を点滴で投与し、うとうとと眠っているようなリラックスした状態で検査を受けることが可能です。
検査自体にかかる時間は、個人差はありますが通常15分から30分程度で、検査後は、鎮静剤の効果が覚めるまで1時間ほどリカバリールームで休みます。
組織を採取して調べる病理検査
大腸カメラのもう一つの重要な役割は、検査中に病変が疑われる部分の組織を、少量採取(生検)できることです。
採取した組織は、顕微鏡で詳しく調べる病理検査に提出します。
検査により、炎症の種類を特定したり、がん細胞の有無を確認したりすることができ、最終的な確定診断につながり、見た目だけでは判断が難しい病変も、病理検査によって正体を明らかにすることができます。
検査後の注意点と日常生活でのセルフケア
診断がつき、治療が始まった後や、症状が落ち着いてきた後も、再発を防ぎ、健やかな毎日を送るためには日常生活でのセルフケアが大切です。
検査後の食事と生活
大腸カメラで観察のみを行った場合は、検査後の食事制限は特にありませんが、お腹に優しいものから食べ始めるのが良いでしょう。ただし、組織を採取した場合やポリープを切除した場合は、検査後1週間程度は食事や生活に注意が必要です。
アルコールや香辛料、炭酸飲料などの刺激物は避け、消化の良い食事を心がけてください。
また、激しい運動や重いものを持つなどお腹に力が入るような行動、長時間の移動や旅行、飛行機への搭乗も、気圧の変化などにより後から出血するリスクを高める可能性があるため、医師の許可が出るまでは控えます。
検査後の食事の進め方(例)
| 期間 | 食事内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 検査当日 | おかゆ、うどん、具のないスープ、豆腐など | 油っこいもの、刺激物、乳製品は避ける |
| 検査後2〜3日 | 白身魚の煮付け、鶏のささみ、卵料理などを追加 | 食物繊維の多い野菜や海藻はまだ控える |
| 検査後1週間 | 体調に問題がなければ徐々に普段の食事に戻す | 便の状態を確認しながらゆっくり進める |
症状を悪化させないための食事の工夫
下痢や腹痛の症状が続いているときは、腸に負担をかけない食事が基本です。脂肪分の多い食事や、食物繊維が豊富なごぼう、きのこ類などは消化に時間がかかり、腸を刺激することがあるため控えめにしましょう。
一度にたくさん食べるのではなく、食事の回数を増やして一回量を減らすことも、腸への負担を軽減するのに有効です。
また、冷たい飲み物や食べ物は腸を刺激して動きを活発にしてしまうことがあるため、なるべく常温か温かいものを選んでください。
- 低脂肪・低残渣の食事を心がける
- よく噛んでゆっくり食べる
- 脱水を防ぐため、水分補給をこまめに行う
- 暴飲暴食や深夜の食事を避ける
ストレス管理と十分な休息
腸と脳は自律神経などを介して密接に連携しており、これは「脳腸相関」として知られています。
精神的なストレスを感じると、その情報が脳から腸に伝わり、腸の動きが過敏になったり、痛覚が敏感になったりして、下痢や腹痛の症状が悪化することがあります。
趣味に没頭する時間を作る、軽い運動をする、ゆっくり入浴するなど、自分なりのリラックス方法を見つけ、心と体を休ませる時間を作ることが大切です。
また、睡眠不足は自律神経のバランスを乱し、体の免疫力を低下させるため、腸の炎症にも良くありません。質の良い睡眠を十分にとるように心がけましょう。

よくある質問
最後に、右下腹部の痛みや下痢、大腸カメラに関して、患者さんからよく寄せられる質問と回答をまとめました。
- 痛み止めを飲んでも良いですか
-
自己判断で市販の痛み止めを飲むことは、慎重になるべきです。
急性虫垂炎などの外科的治療が必要な病気が隠れている場合、痛み止めによって症状が一時的に和らぐことで、本来の病気のサインが分かりにくくなり、診断が遅れてしまう危険性があります。
痛みの原因がはっきりしない段階では、薬に頼る前に、まずは医療機関を受診して正確な診断を受けることが最も重要です。
- 大腸カメラは痛いですか
-
検査に対する不安として、痛みを心配される方は少なくありません。大腸は曲がりくねっているため、スコープがカーブを通過する際に多少の張りや圧迫感を感じることがあります。
しかし、近年はスコープ自体が細く、しなやかになり、挿入技術も向上しているため、以前に比べて苦痛は大幅に軽減されています。
また、多くの医療機関では、鎮静剤を点滴で使用し、うとうとと眠っているようなリラックスした状態で検査を受けることができます。
- 症状が一度治まれば、病院に行かなくても大丈夫ですか
-
痛みが一時的に軽快したとしても、根本的な原因が解決したとは限らず、憩室炎や炎症性腸疾患などは、症状が良くなったり悪くなったりを繰り返すことがあります。
また、ごく稀にですが、虫垂炎が薬などで一時的に落ち着く(保存的治療)ことがあっても、再発する可能性は残ります。症状が繰り返す場合や、一度でも強い症状があった場合は、原因を特定しておくことが大切です。
自己判断で放置せず、医療機関で相談してください。
- 子供でも同じような病気になりますか
-
子供でも大人と同じような病気になる可能性はあり、特に、急性虫垂炎や感染性腸炎は、子供によく見られる病気です。
子供は大人と比べて症状をうまく言葉で表現できないことがあるため、機嫌が悪い、食欲がない、お腹を触られるのを嫌がる、体をくの字に曲げている、といった変化に周囲の大人が気づいてあげることが大切です。
いつもと様子が違うと感じたら、早めに小児科などの医療機関を受診してください。
以上
次に読むことをお勧めする記事
【腹痛や下痢が頻繁に起こる原因 検査と治療について】
右下腹部の痛みと下痢について理解したら、次は腹痛と下痢全般の原因や治療選択肢について知っておくと安心です。過敏性腸症候群や感染性腸炎など、幅広い原因について詳しく解説しています。
【クローン病の内視鏡所見と診断基準|治療方針の決定】
右下腹部痛と下痢の背景には慢性炎症性腸疾患が潜むことも。クローン病の内視鏡所見と診断基準を押さえると、鑑別とフォローの全体像がより整理できます。
参考文献
Cai J, Yuan Z, Zhang S. Abdominal pain, diarrhea, constipation-which symptom is more indispensable to have a colonoscopy?. International Journal of Clinical and Experimental Pathology. 2015 Jan 1;8(1):938.
Kinoshita Y, Ariyoshi R, Fujigaki S, Tanaka K, Morikawa T, Sanuki T. Endoscopic diagnosis of chronic diarrhea. DEN open. 2022 Apr;2(1):e53.
Matsumoto Y, Nadatani Y, Otani K, Higashimori A, Ominami M, Fukunaga S, Hosomi S, Kamata N, Kimura T, Fukumoto S, Tanaka F. Prevalence and risk factor for chronic diarrhea in participants of a Japanese medical checkup. JGH Open. 2022 Jan;6(1):69-75.
Yamada E, Inamori M, Uchida E, Tanida E, Izumi M, Takeshita K, Fujii T, Komatsu K, Hamanaka J, Maeda S, Kanesaki A. Association between the location of diverticular disease and the irritable bowel syndrome: a multicenter study in Japan. Official journal of the American College of Gastroenterology| ACG. 2014 Dec 1;109(12):1900-5.
Yamada E, Kuriyama H, Uchida E, Murata Y, Hata Y, Tagri M, Isozaki Y, Oyamada H, Ozawa Y, Ito T, Mizuki A. Association between endoscopic findings related to colonic diverticula and bowel habits: A multicenter study in Japan. Journal of gastroenterology and hepatology. 2017 Dec;32(12):1938-42.
Ihara E, Manabe N, Ohkubo H, Ogasawara N, Ogino H, Kakimoto K, Kanazawa M, Kawahara H, Kusano C, Kuribayashi S, Sawada A. Evidence-based clinical guidelines for chronic diarrhea 2023. Digestion. 2024 Dec 9;105(6):480-97.
Mizukami T, Sugimoto S, Masaoka T, Suzuki H, Kanai T. Colonic dysmotility and morphological abnormality frequently detected in Japanese patients with irritable bowel syndrome. Intestinal research. 2017 Apr 27;15(2):236.
Yamauchi Y, Arai M, Akizue N, Ohta Y, Okimoto K, Matsumura T, Fan MM, Imai C, Tawada A, Kato J, Kato N. Colonoscopic evaluation of diarrhea/colitis occurring as an immune-related adverse event. Japanese Journal of Clinical Oncology. 2021 Mar;51(3):363-70.
Fine KD, Seidel RH, Do K. The prevalence, anatomic distribution, and diagnosis of colonic causes of chronic diarrhea. Gastrointestinal endoscopy. 2000 Mar 1;51(3):318-26.
Shah RJ, Fenoglio-Preiser C, Bleau BL, Giannella RA. Usefulness of colonoscopy with biopsy in the evaluation of patients with chronic diarrhea. The American journal of gastroenterology. 2001 Apr 1;96(4):1091-5.