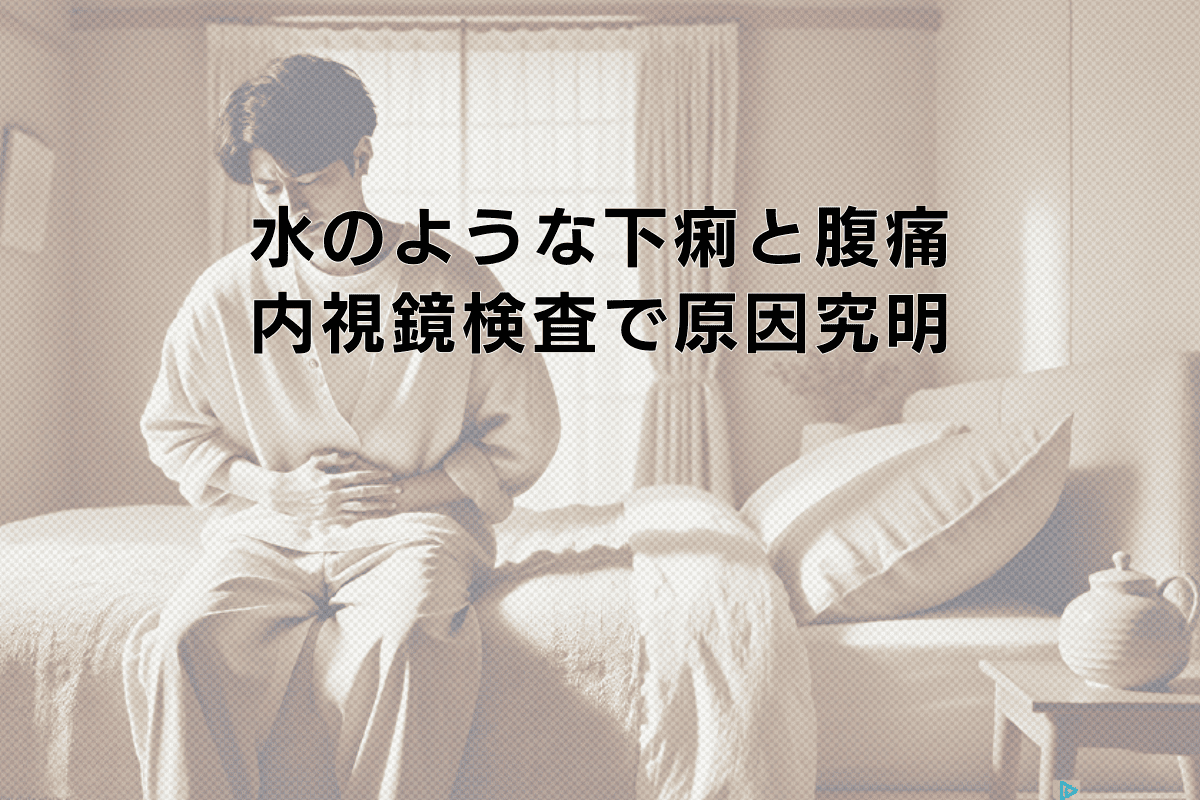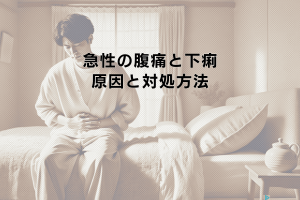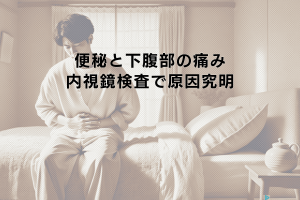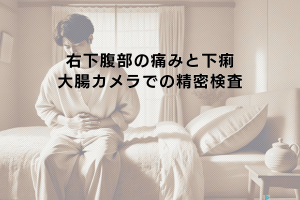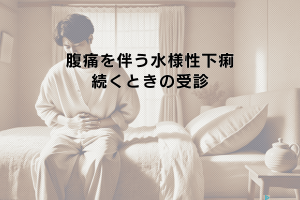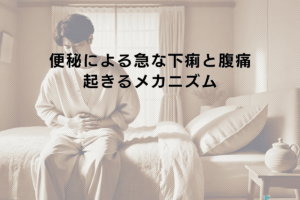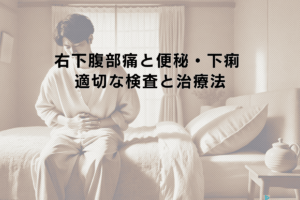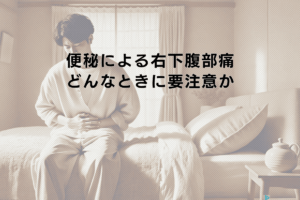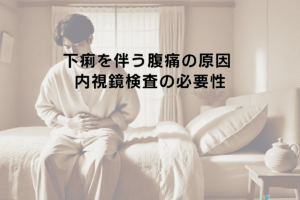腸内の動きが不安定になると、急激に水のような下痢が出たり、腹痛が続いたりして日常生活に支障をきたす場合があります。
とくに大腸や小腸の炎症、感染症などが疑われるときは、早めに内視鏡検査や医師の診断を受けて原因を追究することが大切です。
腹痛がないのに突如として水のような下痢が起きるケースもあり、軽視すると症状が長引いて体力を消耗したり、脱水を招いたりしかねません。
この記事では、水分量の多い下痢と腹痛の主な原因や検査方法、日常生活でのケアについて詳しく解説します。
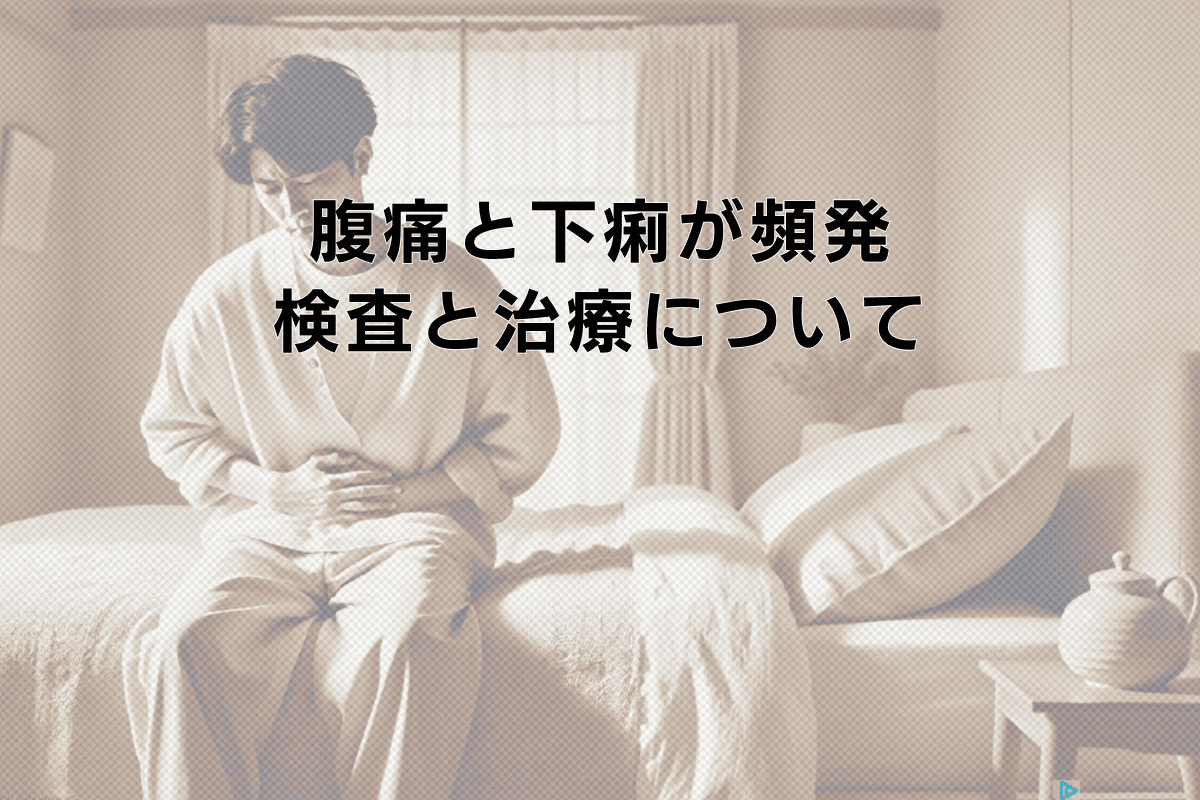
下痢と腹痛が起こりやすい仕組み
水のようにさらさらした便が出る状況は、腸管での水分吸収がうまくいかず、消化や吸収が乱れている証拠だと考えられます。
腸内環境の乱れは、感染症や過敏性腸症候群(IBS)、慢性炎症性腸疾患など多彩な要因によって引き起こされる可能性があります。
また、腹痛が併発する場合は、腸壁が刺激を受けて炎症反応を起こしているなど、何らかの疾患が背景に潜んでいることもあります。
水分量が増える仕組み
食事や飲料水から摂取した水分は、腸管を通過する過程で大半が吸収されて体内に取り込まれます。
しかし、ウイルスや細菌などの感染や過度な腸運動の亢進があると、腸が十分に水分を吸収する前に便として排出してしまい、水のようにさらさらした下痢となることがあります。
腹痛をともなうパターン
水のような下痢だけでなく、腹部にけいれん性の痛みが生じる場合は、腸が激しく動いているか、炎症や潰瘍が発生している懸念があります。
慢性的に続く下痢や腹痛は大腸カメラや胃カメラによる精密検査が必要となるケースがあり、短期間で繰り返すだけでも身体に負担です。
下痢と腹痛を放置すると
数日程度で治まる軽い症状ならともかく、長期的に水下痢が続くと体のミネラルやビタミン、糖分などが不足しやすくなり、脱水症や電解質バランスの乱れによって倦怠感やめまいが起き、免疫力も下がる可能性があります。
頻繁な下痢は肛門周辺のただれや痛みを誘発することもあり、早い段階で原因を見極めて対処することが必要です。
主な症候と可能性
腸内トラブルには多様な原因が考えられ、原因を絞り込むためには、普段の生活習慣、食事内容、ストレス状況などを整理することも大切です。
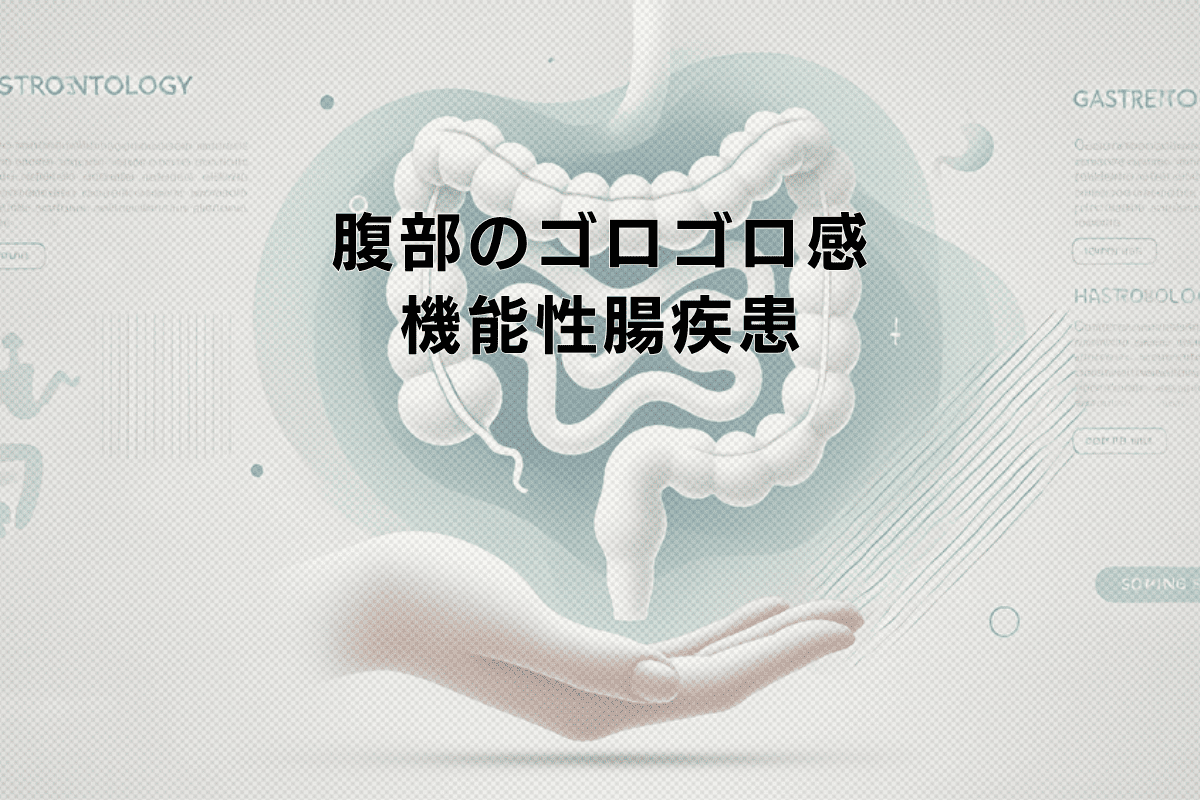
下痢の様子に応じた主な考えられる病因
| 下痢のタイプ | 可能性がある主な原因 | 併発症状 |
|---|---|---|
| 水分が多くほとんど固形物なし | ウイルス性腸炎、細菌感染、暴飲暴食、薬剤性 | 発熱、倦怠感、脱水 |
| 泡立ちや酸っぱいにおいがある | 糖分の過剰摂取、乳糖不耐症、人工甘味料の摂りすぎ | お腹の張り、ガス過多、腸内違和感 |
| 血液や粘液が混じる | クローン病、大腸炎、潰瘍性大腸炎など | 強い腹痛、発熱、体重減少 |
| 脂っぽく油分が浮く | 胆汁酸吸収不良、膵機能低下 | 体重減少、栄養障害 |
感染性と非感染性の要因を見分ける
下痢には大きく分けて感染性と非感染性の原因があり、それぞれで治療方針が異なります。
感染性の多くは急激に始まり、嘔吐や発熱などをともなう例が多いですが、非感染性の場合は慢性的に続く腹痛や体調不良を引き起こすことも珍しくありません。
代表的な感染性の疾患
ロタウイルスやノロウイルス、サルモネラ菌などが腸管で繁殖すると、急性腸炎を発症して下痢や嘔吐、発熱を伴い、調理時の不衛生や食事中の二次感染が原因となる場合も多く、周囲の人にうつすリスクも高いです。
感染性下痢の対応策としては、水分補給や安静、必要に応じた対症療法が中心となります。
感染性腸炎の原因と特徴
| 病原体 | 主な感染経路 | 症状の特徴 |
|---|---|---|
| ノロウイルス | 飲食物の二次汚染や接触 | 激しい嘔吐・下痢、冬季に流行する例が多い |
| ロタウイルス | 接触感染、飛沫感染 | 小児に多く、白色下痢をともなう |
| サルモネラ菌 | 加熱不足の卵や鶏肉など | 腹痛・下痢・発熱が数日続く |
| カンピロバクター | 生または加熱が不十分な鶏肉 | 嘔吐よりも下痢と腹痛が強い傾向 |
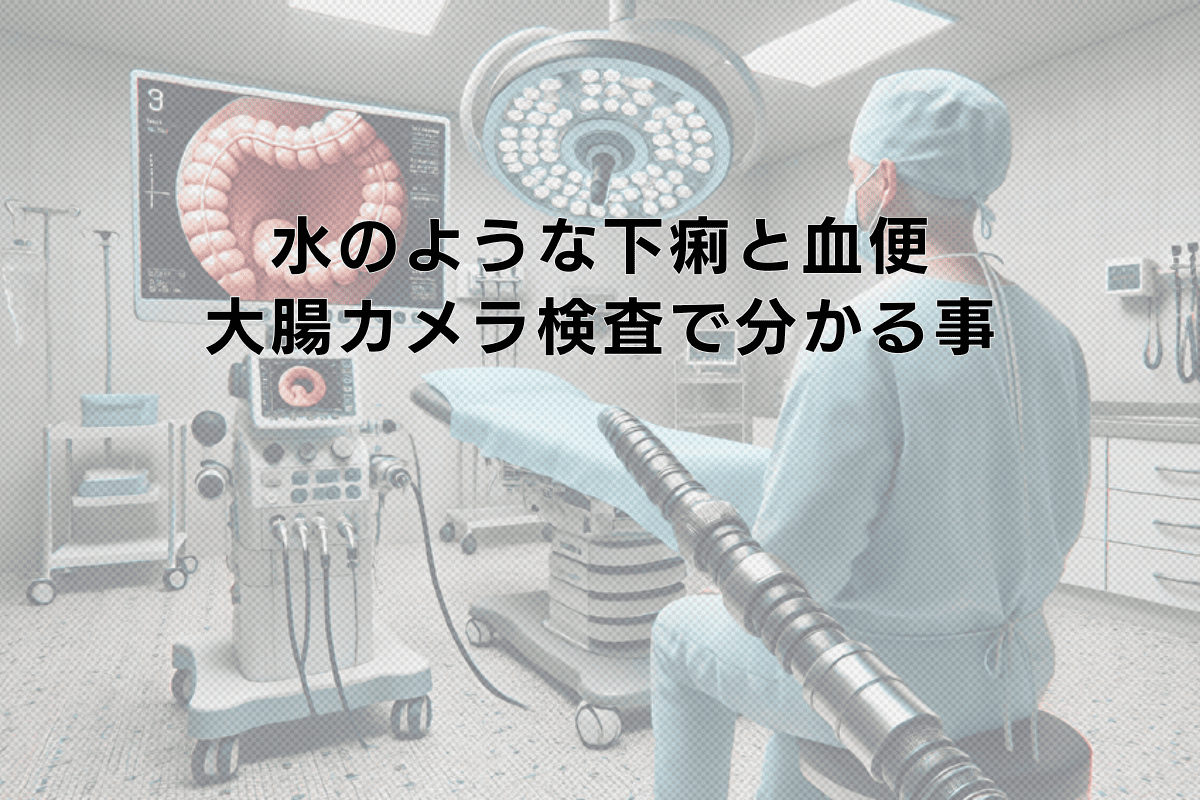
非感染性の疾患
非感染性の下痢は、過敏性腸症候群や炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎・クローン病)などが代表的で、慢性的な経過をたどり、体調やストレス状態によって悪化と寛解を繰り返すパターンもあります。
治療には生活習慣の改善や内視鏡検査による腸壁の観察が欠かせません。
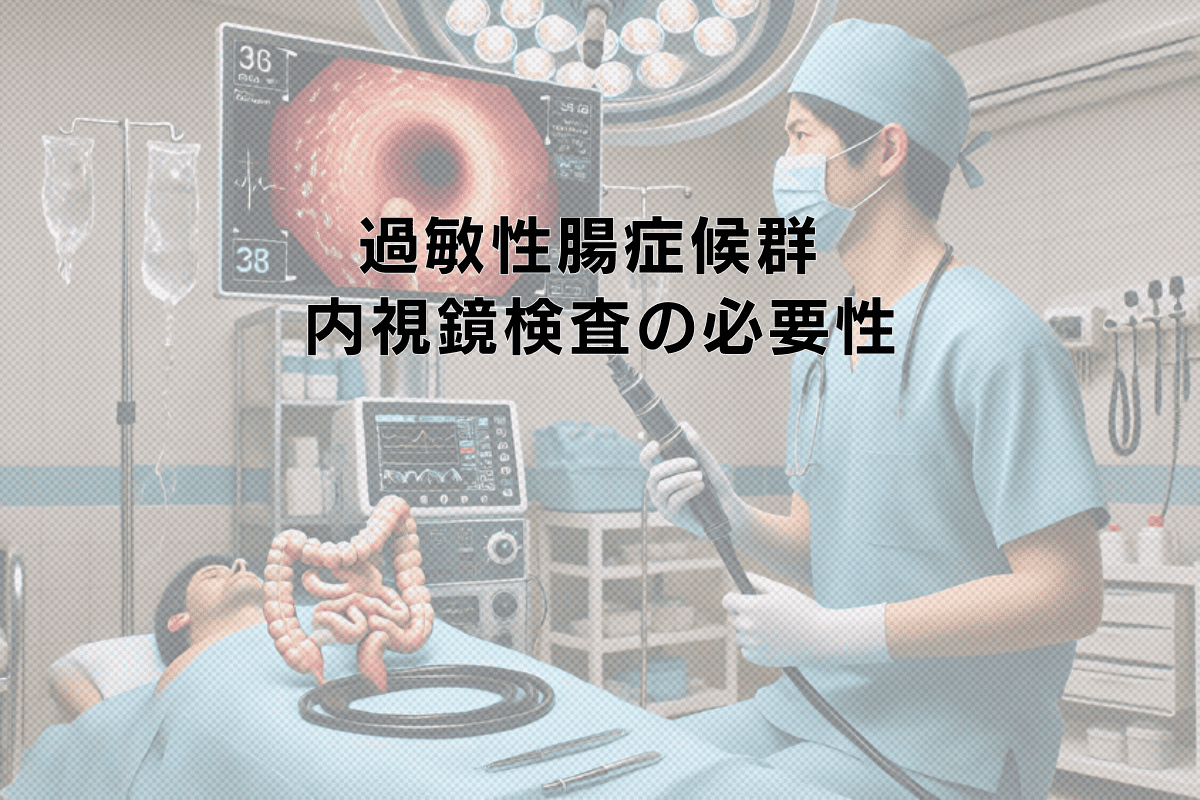
繰り返す下痢の要注意ポイント
感染性であれば数日程度で症状が収束することが多いですが、2週間以上も水様便が続くようなら何らかの慢性疾患を疑ったほうがよいでしょう。
原因不明の慢性下痢は、内視鏡検査を活用して大腸内を直接観察し、腫瘍の有無、炎症の程度を確認するのが近道です。
慢性下痢を引き起こす主な非感染性
| 疾患名 | 特徴的な症状 | 治療アプローチ |
|---|---|---|
| 過敏性腸症候群(IBS) | 下痢と便秘を交互に繰り返し、腹痛を伴う | 生活習慣の改善、薬物療法、カウンセリングなど |
| 潰瘍性大腸炎 | 大腸全体にわたる炎症、血便をともなうことが多い | 免疫調整薬、5-ASA製剤、ステロイドなど |
| クローン病 | 口から肛門までどの部分にも潰瘍ができる可能性 | 栄養療法、免疫調整薬、外科手術 |
| 吸収不良症候群 | 栄養吸収不良による脂肪便や下痢など | 原因に応じた食事制限やサプリメント併用 |
病院受診のタイミング
強い腹痛や高熱、血便が見られる場合は、早急に医療機関を受診することを勧めます。また、下痢が数週間続くときや、体重減少・貧血の兆候がある場合も精密検査を検討してください。
とくに大腸カメラなどの内視鏡検査は、原因不明の下痢を詳細に調べる有効な手段となります。
内視鏡検査の重要性
水のような下痢と腹痛が長引く場合、画像検査や血液検査だけでは原因を明確にできないことがありますが、内視鏡検査(大腸カメラ)なら、大腸粘膜を直接目視で確認できるため、ポリープや潰瘍、炎症の程度を詳細に把握できます。
消化管疾患の正確な診断にとっては欠かせない検査です。

大腸カメラと小腸の検査
通常、大腸カメラは肛門からカメラを挿入し、大腸全体を観察する手法です。小腸の疾患が疑われる場合はカプセル内視鏡や小腸用の内視鏡(ダブルバルーン内視鏡など)を用いる場合があります。
下痢の原因が小腸にあるか大腸にあるかの見極めは、患者の症状や他の検査結果とあわせて総合的に判断されます。
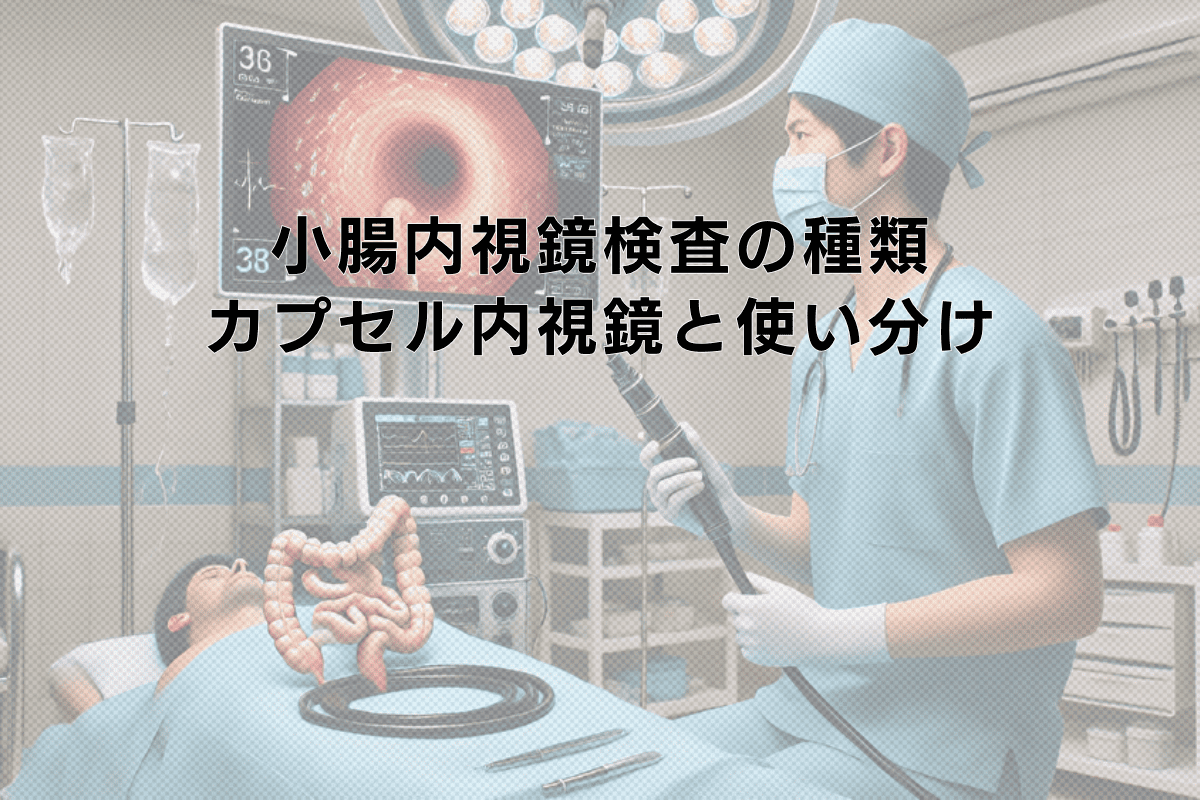
内視鏡検査で確認可能な代表的な病変
| 病変 | 主な特徴 | 検査での所見 |
|---|---|---|
| ポリープ | 良性から悪性までさまざま | 粘膜が隆起し、場合によっては不整形 |
| 潰瘍 | 粘膜層が深くえぐれる病変 | 血管露出や出血を伴うことが多い |
| 炎症 | 赤みやただれが目立つ | 粘膜が発赤し、びらんが見られる |
| 狭窄や瘢痕 | 腸管が細くなり便通が妨げられる可能性 | 内視鏡の通過が困難、腸管径が狭い |
内視鏡検査前の準備
検査の際には腸内をきれいにするための下剤服用が必要です。腸に便や内容物が残っていると、粘膜の観察が困難になるためです。
下剤の種類や飲む量は施設によって異なりますが、多くの場合は検査前日に説明を受け、自宅かクリニック内で数時間かけて内服します。
内視鏡検査前後の注意
- 前日は消化にやさしい食事を取る
- 検査当日はなるべく水分を多めに補給
- 下剤服用後は便が水のようになるまで続ける
- 検査終了後は医師の説明を聞き、異常がないか安静を保つ
検査でわかること
内視鏡検査で発見された病変(ポリープや潰瘍など)は、その場で一部を採取して病理検査を行え、良性か悪性か、炎症の程度など詳しく調べられ、治療方針の決定に大いに役立ちます。
過敏性腸症候群の方にとっても、炎症などの疾患がないことが過敏性腸症候群の診断にとって重要なので、内視鏡検査は必要です。生活習慣の見直しやストレス軽減策を主とする方法が選択されることがあります。
外来・入院の目安
大腸カメラ検査は多くの場合、日帰りで行われますが、重度の炎症が疑われる場合や、高齢者で合併症のリスクがある場合は入院を選ぶ例もあります。
鎮静剤を使用してリラックスした状態で検査する場合は、当日の車の運転は避けるように求められることが多いです。

水のような下痢を改善する日常の対策
原因究明には内視鏡検査を含む医療機関でのアプローチが欠かせない一方、軽い症状や一時的な下痢の場合は、日常的な工夫で早めに回復を目指す方法もあります。とくに脱水を防ぐための水分補給や、食事の見直しが鍵です。
水分と電解質を補う
水のような下痢が続くと、体内の水分だけでなく、ナトリウムやカリウムなどの電解質も失われるので、スポーツドリンクや経口補水液を適度に摂り、体内のバランスを保つことが大事です。
水分を急激に摂りすぎると吐き気や腹痛が増す場合があるため、少しずつこまめに飲む工夫が求められます。
水下痢時におすすめの水分摂取方法
| 状況 | 飲む量とタイミング | 注意点 |
|---|---|---|
| 軽度脱水の可能性があるとき | コップ半分程度を30分おきにゆっくり | 一気飲みを避けて胃腸への負担を減らす |
| 食事がとれないレベルの体調不良時 | 経口補水液や塩分を含む飲料を少量ずつ | ミネラルバランスにも配慮する |
| 嘔吐をともなうほどの激しい下痢のとき | 少量ずつ口に含んでは休む | 症状が深刻なら医療機関を受診 |
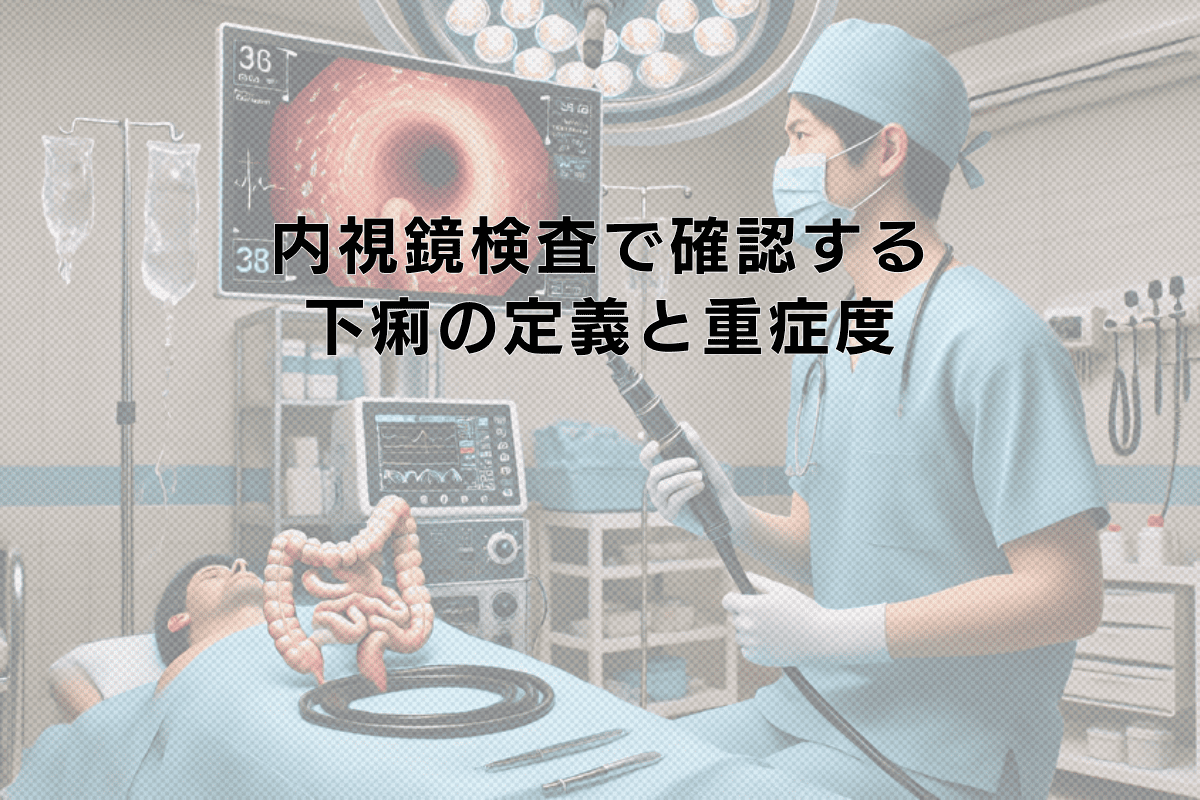
食事内容の見直し
刺激物や油っぽい食品、繊維質が多すぎる食事は下痢を悪化させる原因となりがちです。腸が敏感になっているときは消化によい食材を選び、負担を減らしましょう。
緩やかな食事改善のポイント
- 温かいスープやおかゆなど消化しやすい食品を中心に
- 辛い香辛料やアルコール、カフェインは控える
- 乳製品は体質に合わせて摂りすぎないよう注意
- 腸内環境を整えるヨーグルトや発酵食品も個人差を見ながら少しずつ
休養とストレス緩和
ストレスがたまると自律神経のバランスが崩れ、腸の動きにも悪影響を及ぼし、とくに過敏性腸症候群などが背景にある場合、リラックスできる時間を確保し、睡眠や運動などを意識することで下痢の回数を減らす一助となります。
市販薬の選び方
一時的に下痢を抑えるための市販薬を使用する例もありますが、無理に腸の動きを止めると腹痛が強まることもあります。
下痢止めや整腸剤、ビオフェルミン系の乳酸菌製剤などは症状に合わせて活用するとよいですが、長期間改善が見られないときは独断で続けず、専門医と相談してください。
一般的な下痢止め・整腸剤
| 種類 | 作用機序 | 注意点 |
|---|---|---|
| ロペラミド(腸の運動抑制) | 腸の蠕動を抑えて便を固くする | 感染症による下痢では病原体の排出を妨げる恐れ |
| 乳酸菌製剤 | 善玉菌を補い腸内フローラを整える | 劇的な即効性は少なく、継続的な使用が前提 |
| 整腸漢方薬 | 胃腸を温める、生体リズムを整える | 体質や症状に合わない場合は逆効果の可能性 |
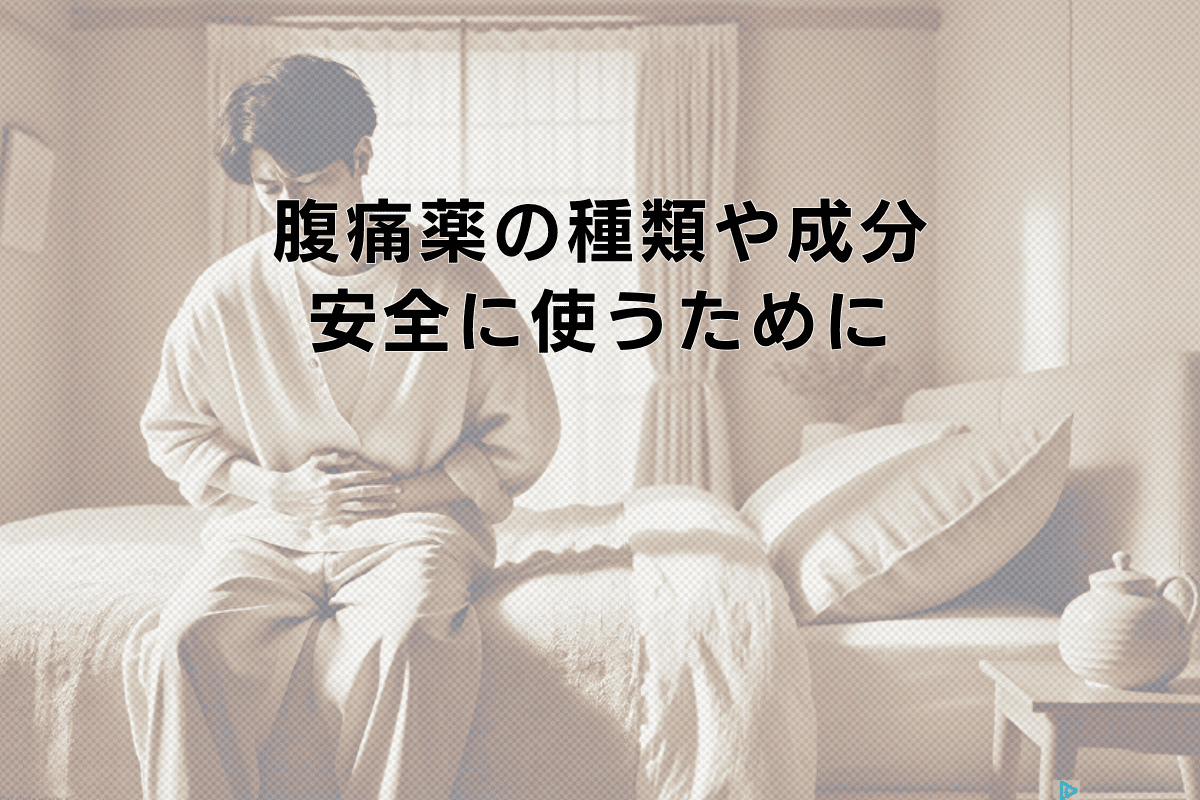
再発防止と健康維持
水のような下痢と腹痛が治まっても、再発を防ぐためには日頃から腸の健康を意識した生活を続けることが重要です。腸は免疫機能の大部分を担う臓器ともいわれ、状態が悪化すると全身の不調につながることもあります。
腸内環境をサポートする要素
腸内細菌のバランスが保たれていると、消化吸収がスムーズになり、ビタミン合成や免疫強化に役立ちます。腸内環境を整えるには、バランスの良い食事や乳酸菌・食物繊維の摂取、適度な運動などが効果的です。
無理なダイエットや偏食は、腸内バランスの乱れを招く恐れがあります。
腸内環境維持に向けた日常習慣
- 朝起きたらコップ1杯の水を飲んで腸を刺激
- 野菜・果物を毎食取り入れ、食物繊維を適度に摂取
- ストレス発散方法を見つけ、睡眠時間を確保
- 適度な有酸素運動やストレッチで血行を促進
便通の観察
便の状態は体の健康を映す鏡で、硬さ・色・においなど日々の変化を把握しておけば、異変を早期に察知できるます。
急な水下痢や腹痛が増え始めたら、生活のどの部分が変化したかを振り返り、早めに医療機関を受診する判断材料としてください。
便の状態チェックリスト
| 確認項目 | 正常時の目安 | 注意が必要な変化 |
|---|---|---|
| 硬さ | やや柔らかく形が保たれている | 水のように液状、またはコロコロの硬便 |
| 色 | 黄褐色〜茶色が自然 | 黒色、赤色、白っぽい色 |
| におい | 食内容によって変化はあるが異常でない | 極端に酸っぱい、生臭い |
| 排便時の痛みや時間 | いきまずスムーズ | 強い腹痛、残便感、激しいいきみ |
定期健診の活用
下痢体質や慢性的な腹痛を抱えている人は、定期的な健康診断や人間ドックでの大腸カメラ検査を検討するとよいでしょう。早期発見できれば症状の悪化を防ぎ、治療や生活指導につなげられます。
胃カメラ検査が必要なケース
腹痛がある場合は、必ずしも大腸だけに原因があるとは限りません。上腹部中心の痛みや胃もたれが強いときは胃カメラによる確認が必要になる場合もあります。
胃や十二指腸に潰瘍ができていたり、ピロリ菌感染があるケースもあり、複数の検査を組み合わせることで総合的な消化管の健康状態を把握することが可能です。

胃と腸の連動性
胃と腸は連続した消化管のため、どちらか一方にトラブルがあるともう一方にも影響が及ぶことがあります。
たとえば、胃酸過多や逆流性食道炎で食事がスムーズに消化されないと、小腸や大腸へ負担がかかり下痢や腹痛につながることが考えられます。
胃腸を連動させる消化過程
| 消化器官 | 主な役割 | 異常が出た場合の影響 |
|---|---|---|
| 口腔 | 咀嚼・唾液による分解 | かみ砕き不足で胃腸への負担が増加 |
| 胃 | 酸やペプシンでの分解 | 胸やけ、胃潰瘍、吐き気などを誘発 |
| 十二指腸 | 胆汁や膵液と混ざり中和 | 胆汁酸吸収不良で下痢が慢性化する場合あり |
| 小腸 | 栄養素の吸収 | マラブソーション、腹部膨満感 |
| 大腸 | 水分吸収・便の形成 | 下痢、便秘、腹痛、炎症性疾患など |
胃カメラ検査の特徴
- 口や鼻からスコープを挿入し、食道・胃・十二指腸を観察
- 胃痛や嘔吐が続く、胃潰瘍や萎縮性胃炎が疑われるときに適用
- ピロリ菌感染の有無を判断するための検査や組織採取も可能
- 鎮静下で検査することが多く、患者の負担を軽減
どのタイミングで胃カメラを受けるか
みぞおち付近の痛みが強い、食後に胃がもたれる、吐き気や食欲不振が続くような場合は胃カメラを検討してください。大腸だけでなく上部消化管にも原因がある可能性を排除しないほうが、診断の正確性を高められます。
複数検査を組み合わせる際の注意点
- 検査前の絶食や下剤服用など準備が必要
- 鎮静剤を使用する場合は安全のための付添人が求められるケースもある
- 一度の来院で上下部内視鏡を同時に行う施設もある
医療機関の受診と治療方針の決定
水のような下痢や腹痛が持続または再発を繰り返すなら、早めの医療機関受診が重要です。原因を特定するためには、血液検査や画像検査、内視鏡検査が有力で、それぞれの結果を踏まえて治療方針を決定します。
専門科の選び方
消化器内科や消化器外科、内科などに加えて、大腸カメラなどの内視鏡検査に特化した施設があり、次の判断基準を参考にすると、受診先を絞り込みやすくなるでしょう。
受診先選びの目安
| 症状 | 推奨される診療科 | 理由 |
|---|---|---|
| 短期間の軽い下痢・腹痛 | 内科、消化器内科 | 感染症や急性胃腸炎の疑い |
| 長期にわたる慢性下痢 | 消化器内科・内視鏡専門 | 潰瘍性大腸炎、クローン病などを考慮 |
| 血便、激しい腹痛がある | 緊急性を伴う場合は救急 | 大腸ポリープ、がん、穿孔リスクなど |
| 水下痢と発熱、脱水症状 | 内科・消化器内科 | 感染性腸炎が疑われる |
治療法の選択
- 薬物療法:抗生物質、整腸剤、抗炎症薬、ステロイドなど
- 栄養療法:食事制限や点滴で腸を休める、特定の栄養補給
- 外科療法:重度の炎症や狭窄に対して手術を検討
- 補助療法:免疫調節剤やメソセラピーなど
重症度によっては入院管理を要し、栄養状態の改善や腸を安静に保つための対応が必要になることもあります。
信頼できる医師との連携
慢性下痢や反復性の腹痛では、医師との長期的なコミュニケーションがカギを握り、症状の変化や薬の副作用を随時共有し、必要に応じて検査や治療プランを見直すことで、症状のコントロールを目指します。
医師と円滑に連携するコツ
- 症状の経過を記録し、伝えやすい形でまとめる
- 疑問点や不安をメモに残し、受診時に質問する
- 処方薬の効果や副作用をこまめに確認し報告する
- 通院の頻度や検査計画を事前に相談し、自分の生活に組み込む
まとめ
水のような下痢と腹痛は、消化器の不調を示す明確なサインで、感染症による一過性の下痢から、過敏性腸症候群や炎症性腸疾患などの慢性疾患まで、その原因は多岐にわたります。
症状が数日で収まらず体重減少や貧血などを伴うようなら、内視鏡検査を含む精密検査を考慮する時期です。
大腸カメラや胃カメラは、消化管を直接観察し、原因を究明するうえで有効な手段で、ポリープや潰瘍、炎症などが見つかれば治療方針を明確に立てられます。一方で軽度の症状であっても、繰り返す水下痢は身体への負担が大きいです。
日常的に水分や電解質を補給する、刺激の少ない食事を心がける、生活習慣を改善するなどの対策で身体をケアし、不調を感じたら早めに医師の診断を受けてください。
次に読むことをお勧めする記事
【大腸内視鏡検査とはどのような検査なのか】
水のような下痢と腹痛の原因を理解したら、次は実際の内視鏡検査について知っておくと安心です。検査を検討されている方に特に参考になる内容です。
【脂肪便のような下痢症状と消化管内視鏡検査での評価基準】
下痢の質が変わるとき、栄養吸収障害の可能性も。脂肪便の見分け方と内視鏡評価ポイントを知り、より包括的に腸の健康を守りましょう。
参考文献
Fry LC, Carey EJ, Shiff AD, Heigh RI, Sharma VK, Post JK, Hentz JG, Fleischer DE, Leighton JA. The yield of capsule endoscopy in patients with abdominal pain or diarrhea. Endoscopy. 2006 May;38(05):498-502.
May A, Manner H, Schneider M, Ipsen A, Ell C, null for the CEDAP-Plus Study Group. Prospective multicenter trial of capsule endoscopy in patients with chronic abdominal pain, diarrhea and other signs and symptoms (CEDAP-Plus Study). Endoscopy. 2007 Jul;39(07):606-12.
Burgers K, Lindberg B, Bevis ZJ. Chronic diarrhea in adults: evaluation and differential diagnosis. American family physician. 2020 Apr 15;101(8):472-80.
Fine KD, Seidel RH, Do K. The prevalence, anatomic distribution, and diagnosis of colonic causes of chronic diarrhea. Gastrointestinal endoscopy. 2000 Mar 1;51(3):318-26.
Fernández-Bañares F, Esteve M, Salas A, Alsina M, Farré C, González C, Buxeda M, Forné M, Rosinach M, Espinós JC, Viver JM. Systematic evaluation of the causes of chronic watery diarrhea with functional characteristics. Official journal of the American College of Gastroenterology| ACG. 2007 Nov 1;102(11):2520-8.
Katsinelos P, Fasoulas K, Beltsis A, Chatzimavroudis G, Paroutoglou G, Maris T, Mimidis K, Koufokotsios A, Terzoudis S, Atmatzidis S, Kaltsa A. Diagnostic yield and clinical impact of wireless capsule endoscopy in patients with chronic abdominal pain with or without diarrhea: a Greek multicenter study. European journal of internal medicine. 2011 Oct 1;22(5):e63-6.
Shen B, Khan K, Ikenberry SO, Anderson MA, Banerjee S, Baron T, Ben-Menachem T, Cash BD, Fanelli RD, Fisher L, Fukami N. The role of endoscopy in the management of patients with diarrhea. Gastrointestinal endoscopy. 2010 May 1;71(6):887-92.
Brenner DM, Domínguez-Muñoz JE. Differential diagnosis of chronic diarrhea: an algorithm to distinguish irritable bowel syndrome with diarrhea from other organic gastrointestinal diseases, with special focus on exocrine pancreatic insufficiency. Journal of clinical gastroenterology. 2023 Aug 1;57(7):663-70.
Valero M, Bravo-Velez G, Oleas R, Puga-Tejada M, Soria-Alcívar M, Escobar HA, Baquerizo-Burgos J, Pitanga-Lukashok H, Robles-Medranda C. Capsule endoscopy in refractory diarrhea-predominant irritable bowel syndrome and functional abdominal pain. Clinical Endoscopy. 2018 Nov 16;51(6):570-5.
Kinoshita Y, Ariyoshi R, Fujigaki S, Tanaka K, Morikawa T, Sanuki T. Endoscopic diagnosis of chronic diarrhea. DEN open. 2022 Apr;2(1):e53.