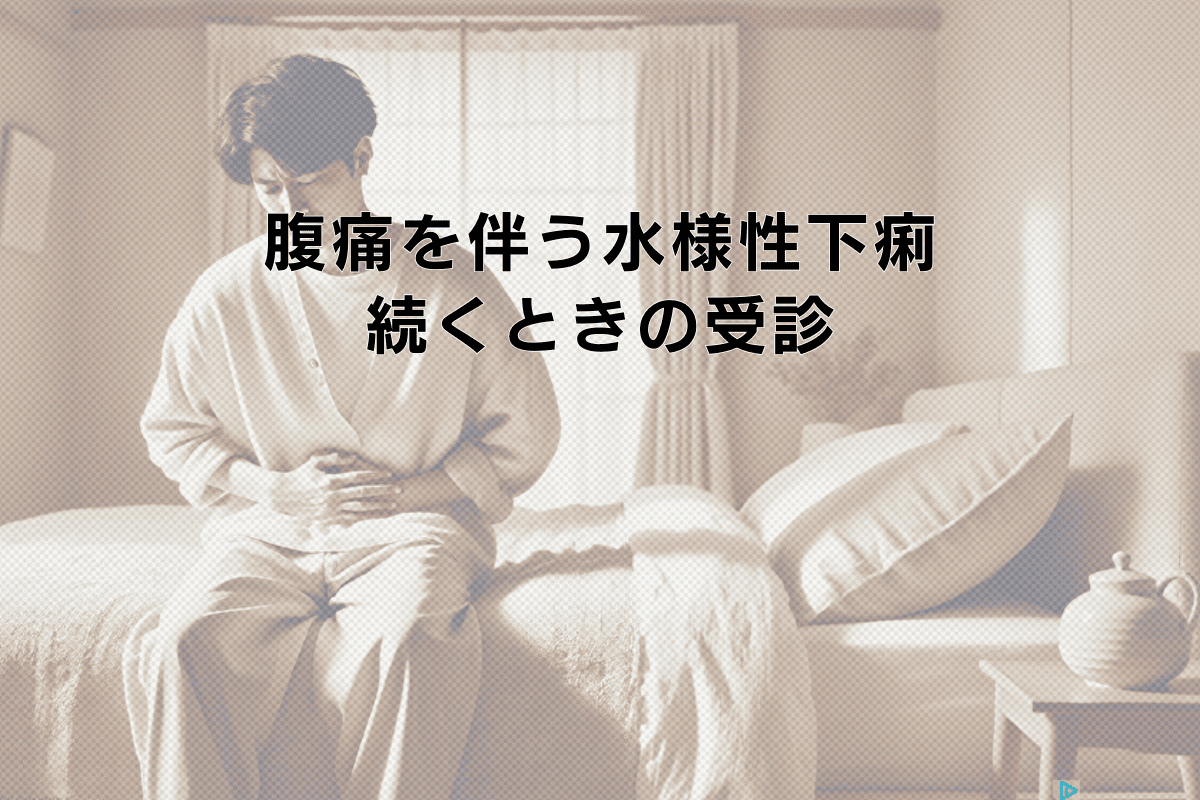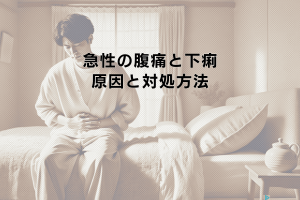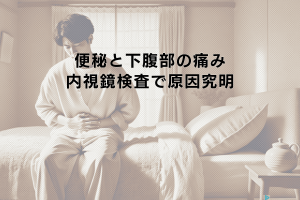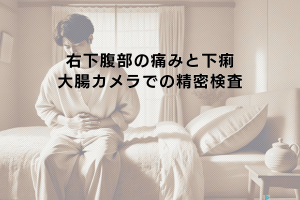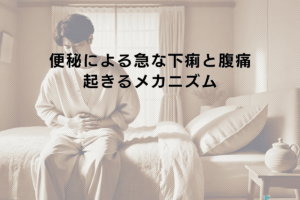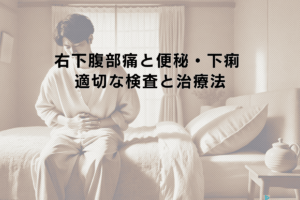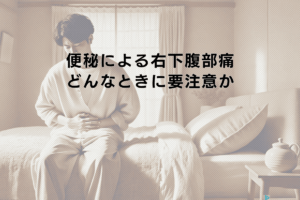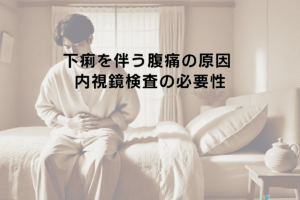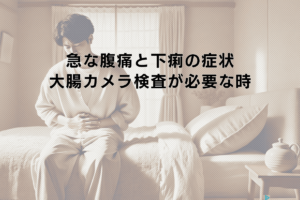突然の腹痛と、水のように止まらない下痢。日常生活に大きな支障をきたすこの症状は、誰にとってもつらく、不安なものです。
一過性のものだろうと思っていても、なかなか治らないと「何か悪い病気なのでは」と心配になるかもしれません。
この記事では、腹痛を伴う水様性下痢が続く場合に考えられる原因や、ご自身でできる対処法、そしてどのような場合に医療機関を受診すべきかについて、詳しく解説します。
腹痛と水様性下痢 なぜ起こるのか
腹痛と水様性下痢は、消化管、特に腸が何らかの異常をきたしているサインです。腸は食べ物を消化吸収し、残りを便として排出する働きを担っていますが、この機能が障害されると下痢が起こります。
腸のぜん動運動の異常
腸はぜん動運動という収縮と弛緩を繰り返す動きによって、内容物を先へ先へと送っています。
ウイルスや細菌などの病原体、あるいはストレスなどによってこの運動が過剰になると、内容物が腸を通過する時間が短くなり、水分が十分に吸収される前に排出され、下痢となります。
この異常なぜん動運動が、差し込むような腹痛(疝痛)を起こすこともあります。
腸管からの過剰な水分分泌
特定の細菌が出す毒素などは腸の粘膜を刺激し、腸管内へ体内の水分を大量に分泌させ腸の内容物と混ざり合うことで、便が水っぽくなります。
コレラ菌による下痢が典型例で、一度に大量の水分が失われるため、激しい脱水症状を起こすことがあります。
腸での水分吸収の低下
腸の粘膜が炎症を起こすと水分や栄養素を吸収する能力が低下し、ウイルス感染や炎症性腸疾患などによって腸粘膜がダメージを受け、本来吸収されるはずの水分が吸収されず、そのまま便として排出されてしまいます。
炎症が伴うため、腹痛も同時に起こることが多いです。
浸透圧性の下痢
人工甘味料や一部の下剤のように、腸で吸収されにくい物質を一度に多く摂取すると、腸管内の浸透圧が高まります。
すると、体は腸管内と体内の浸透圧のバランスを取ろうとして、腸管壁から水分を移動させ、腸管内の水分量が増え下痢が起こります。暴飲暴食による下痢も、消化しきれない食べ物が同様の働きをすることが一因です。
考えられる主な原因疾患
腹痛と水様性下痢を起こす原因は多岐にわたりますが、大きく分けて、ウイルスや細菌などによる感染性のものと、それ以外の非感染性のものがあります。原因によって対処法や治療法が異なるため、原因を推測することが重要です。
感染性胃腸炎(ウイルス性・細菌性)
最も頻度の高い原因の一つが感染性胃腸炎で、ノロウイルスやロタウイルスなどのウイルス、あるいはカンピロバクターやサルモネラ菌などの細菌に感染することで発症します。
汚染された食品の摂取(食中毒)や、感染者からの接触感染が主な経路です。冬場はウイルス性、夏場は細菌性が多くなる傾向があります。
感染性胃腸炎の主な原因
| 種類 | 代表的な病原体 | 特徴 |
|---|---|---|
| ウイルス性 | ノロウイルス、ロタウイルス | 感染力が強く、冬に流行しやすい。嘔吐を伴うことが多い。 |
| 細菌性 | カンピロバクター、サルモネラ菌、病原性大腸菌 | 加熱不十分な肉や卵が原因となることが多い。血便や発熱を伴うことがある。 |
| 寄生虫 | クリプトスポリジウム | 数は少ないが、汚染された水などを介して感染する。 |
過敏性腸症候群(IBS)
検査をしても腸に明らかな炎症や潰瘍といった異常が見つからないにもかかわらず、腹痛や腹部の不快感、そして下痢や便秘などの便通異常が慢性的に続く疾患です。
ストレスが症状の悪化に関与していると考えられており、特に精神的な緊張が高まると、急な腹痛と共に水様性の下痢が起こることがあります。下痢と便秘を繰り返す混合型もあります。
炎症性腸疾患(IBD)
クローン病や潰瘍性大腸炎に代表される、腸に原因不明の慢性的な炎症が起こる疾患の総称です。
自己免疫機能の異常が関与していると考えられていて、腹痛や下痢が長期間にわたって続くだけでなく、血便、体重減少、発熱などの全身症状を伴うこともあります。若年層での発症が多いのも特徴です。
IBSとIBDの症状の比較
| 項目 | 過敏性腸症候群 (IBS) | 炎症性腸疾患 (IBD) |
|---|---|---|
| 主な症状 | 腹痛、下痢・便秘、腹部膨満感 | 腹痛、下痢、血便、発熱、体重減少 |
| 検査所見 | 明らかな異常は見つからない | 腸に炎症、びらん、潰瘍が見られる |
| 関連要因 | ストレス、生活習慣の乱れ | 遺伝的要因、免疫異常、環境要因 |
薬剤性の下痢
特定の薬剤の副作用として下痢が起こることもあります。抗生物質(抗菌薬)は、腸内の善玉菌まで殺してしまうため、腸内環境のバランスが崩れて下痢を起こすことがあります。
その他、痛み止めや一部の血圧の薬、抗がん剤など、下痢の原因となりうる薬剤は数多くあり、新しい薬を飲み始めてから下痢が始まった場合は薬剤性の可能性を考えます。
市販薬を使用する際の注意点
急な下痢に対して、まずは市販薬で対応しようと考える人も多いでしょう。しかし、原因によっては市販薬の使用が症状を悪化させる可能性もあるため、使用には注意が必要です。
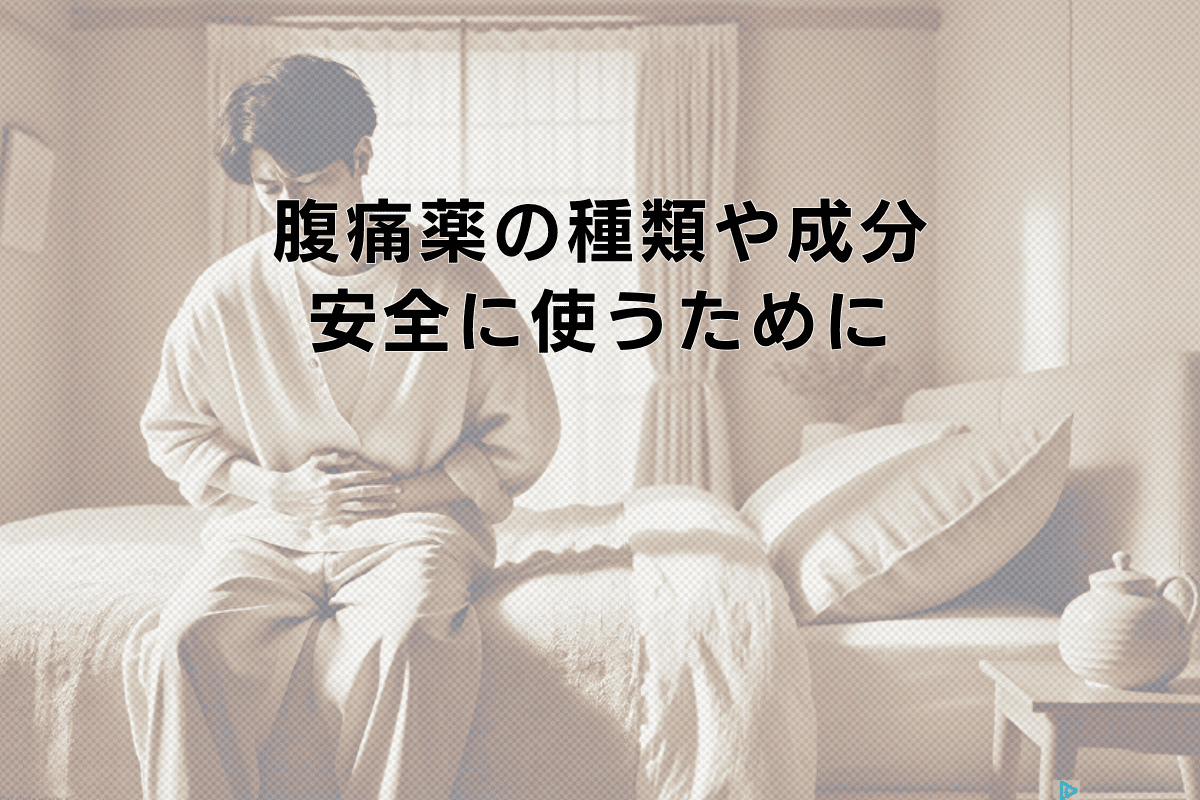
自己判断で下痢止め薬を使わない
特に注意が必要なのが、腸の動きを無理に止めるタイプの下痢止め薬(止瀉薬)です。
感染性胃腸炎の場合、下痢は体内のウイルスや細菌を排出しようとする防御反応で、安易に下痢止め薬を使ってしまうと、病原体が腸内に留まり、かえって回復を遅らせたり症状を重くする危険性があります。
血便や高熱がある場合は、自己判断での下痢止め薬の使用は絶対に避けるべきです。
市販の下痢止め薬の種類と働き
| 薬の種類 | 主な働き | 使用上の注意点 |
|---|---|---|
| 腸運動抑制薬 | 腸のぜん動運動を抑えて下痢を止める。 | 感染性の下痢には原則使用しない。 |
| 収れん薬 | 腸の粘膜を保護し、過剰な水分分泌を抑える。 | 効果は比較的おだやか。 |
| 吸着薬 | 腸内の有害物質や水分を吸着して便として排出する。 | 他の薬の効果を弱めることがある。 |
整腸剤は比較的安全に使える
乳酸菌やビフィズス菌といった善玉菌を補給する整腸剤は、乱れた腸内環境を整えることを目的としており、下痢を無理に止めるものではないため、下痢め薬に比べて比較的安全に使用できます。
抗生物質の服用による下痢などにも有効な場合がありますが、症状が改善しない合は医療機関を受診しましょう。
症状が改善しない場合は使用を中止する
市販薬を1〜2日使用しても症状が全く改善しない、あるいは悪化するようであれば、市販薬で対応できる範囲を超えている可能性が高いです。その場合は直ちに使用を中止し、速やかに医療機関に相談してください。
自宅でできる対処法と水分補給
医療機関を受診するまでの間あるいは軽症で様子を見る場合に、症状を和らげ、悪化を防ぐために自宅でできる対処法があります。特に重要なのが、脱水を防ぐための水分補給です。
安静にしてお腹を温める
下痢や腹痛があるときは体力を消耗しているので、まずは無理をせず、体を休めることが第一です。腹部を毛布やカイロなどで温めると、腸の過剰な動きが和らぎ、痛みが少し楽になることがあります。ただし、低温やけどには注意してください。
脱水を防ぐための水分補給
水様性下痢では、便と共に大量の水分と電解質(ナトリウムやカリウムなど)が失われるので、脱水を防ぐために、こまめな水分補給が何よりも大切です。
一度に大量に飲むと腸を刺激してしまうため、少量ずつ、頻回に摂取することを心がけましょう。
水分補給に適した飲み物
| 推奨される飲み物 | ポイント | 避けた方が良い飲み物 |
|---|---|---|
| 経口補水液 | 水分と電解質を効率よく吸収できる。 | 牛乳などの乳製品 |
| 麦茶、湯冷まし | 刺激が少なく、日常的な水分補給に適している。 | ジュース、炭酸飲料 |
| スポーツドリンク | 糖分が多いため、水で薄めると良い場合がある。 | コーヒー、アルコール |
消化の良い食事を少量ずつ摂る
下痢がひどいときは無理に食べる必要はありませんが、症状が少し落ち着いてきたら、消化の良い食事を少量から再開します。腸に負担をかけないよう、よく煮込んだうどんやお粥、スープ、豆腐、白身魚などが適しています。
- おかゆ
- すりおろしリンゴ
- 野菜スープ
- 豆腐
脂肪分の多い食事や、香辛料などの刺激物、食物繊維の多い野菜、冷たい食べ物は、腸を刺激して下痢を悪化させる可能性があるため、回復するまでは避けましょう。
医療機関を受診するべきタイミング
多くの急性下痢は数日で改善しますが、中には早急な治療を必要とする危険なサインが隠れていることもあります。どのような場合に医療機関を受診すべきか、具体的な目安を知っておくことが大切です。
すぐに受診が必要な危険なサイン
以下のような症状が見られる場合は、重篤な疾患や重い脱水症状の可能性があります。様子を見ずに速やかに、場合によっては夜間や休日でも救急外来を受診することを検討してください。
緊急性の高い症状
| 症状 | 考えられる状態 | 対応 |
|---|---|---|
| 激しい腹痛、冷や汗、意識が朦朧とする | 重度の脱水、ショック状態、腸閉塞など | 救急要請も検討する。 |
| 便に血が混じる(血便) | 細菌性腸炎、炎症性腸疾患、大腸がんなど | 速やかに医療機関を受診する。 |
| 高熱(38.5℃以上)を伴う | 重症の感染症の可能性 | 内科または消化器内科を受診する。 |
| 水分が全く摂れない、嘔吐が続く | 重度の脱水のリスクが非常に高い | 点滴による水分補給が必要。 |
数日経っても改善しない場合
危険なサインはなくても腹痛や水様性下痢が2〜3日以上続いたり、市販薬を飲んでも一向に良くなる気配がない場合は、医療機関を受診しましょう。特に、高齢者や乳幼児、持病のある方は脱水になりやすいため、早めの相談が大事です。
下痢を繰り返す、慢性化している場合
数週間以上にわたって下痢が続いたり、良くなったり悪くなったりを繰り返したりする場合は、過敏性腸症候群や炎症性腸疾患などの慢性的な病気が背景にある可能性があります。
自己判断で様子を見続けず、一度消化器内科で精密検査を受けてください。
消化器内科で行う検査の流れ
消化器内科を受診すると、症状の原因を特定するためにいくつかの検査を行い、問診で得られた情報をもとに、医師が必要な検査を選択します。
問診と身体診察
まず、医師が症状について詳しく尋ねます。いつから症状が始まったか、腹痛の性質、便の状態、食事内容、海外渡航歴、服用中の薬など、できるだけ正確に伝えることが診断の助けになります。
その後、聴診や腹部の触診などを行い、お腹の状態を確認します。
血液検査
血液検査では、体内の炎症の程度(白血球数やCRP値)や、脱水の有無、貧血の程度、栄養状態などを調べ、感染症の重症度を判断したり、炎症性腸疾患の可能性を探ります。
便検査
下痢の原因を特定するために非常に重要な検査で、便を少量採取し、細菌やウイルスの有無を調べます(便培養検査、抗原検査)。また、便に血液が混じっていないかを確認する便潜血検査も行います。
腹部画像検査と内視鏡検査
腹部超音波(エコー)検査やCT検査は、腸の状態や他の臓器に異常がないかを確認するのに役立ちます。
症状が長引く場合や炎症性腸疾患などが疑われる場合には、大腸カメラ(大腸内視鏡検査)を行い、直接大腸の粘膜を観察し、必要であれば組織を採取して病理検査に出すこともあります。
主な検査とその目的
| 検査名 | 検査内容 | わかること |
|---|---|---|
| 血液検査 | 採血を行う。 | 炎症、脱水、貧血の有無や程度。 |
| 便検査 | 便を採取して調べる。 | 病原体の有無、便中の出血の有無。 |
| 大腸内視鏡検査 | 肛門から内視鏡を挿入し大腸を観察する。 | 炎症、潰瘍、ポリープ、がんの有無。 |
治療法と日常生活での注意点
検査によって診断が確定したら原因に応じた治療を開始し、同時に、症状を悪化させないための日常生活での注意点もあります。
原因に応じた薬物療法
感染性胃腸炎の場合ウイルス性であれば特効薬はなく、症状を和らげる対症療法が中心です。
細菌性が原因で重症の場合は抗生物質を使用し、過敏性腸症候群であれば、腸の動きを整える薬や、不安を和らげる薬などが処方されます。
また、炎症性腸疾患の場合は、炎症を抑える薬(5-ASA製剤、ステロイドなど)を用いて、病状をコントロールします。
脱水に対する治療
脱水が軽度であれば経口補水液による水分補給で対応しますが、水分が口から摂れない場合や脱水が重度の場合は、点滴による水分・電解質の補給が必要です。
食事療法と生活習慣の改善
治療と並行して、食事に気をつけることも回復を早める上で大切で、症状が落ち着くまでは、腸に負担の少ない食事を心がけましょう。
回復期の食事のポイント
| 積極的に摂りたい食品 | しばらく避けたい食品 | 調理法の工夫 |
|---|---|---|
| お粥、うどん、豆腐、白身魚、鶏ささみ | 揚げ物、ラーメン、焼肉、香辛料 | 「煮る」「蒸す」など油を使わない調理法を選ぶ。 |
| バナナ、リンゴ(加熱したもの) | ごぼう、きのこ類、海藻類 | 食材を細かく刻み、柔らかく調理する。 |
| じゃがいも、かぶ | 柑橘類、炭酸飲料、アルコール | 人肌程度の温度で食べる。 |
ストレスが症状の引き金になっている場合は、十分な休養を取り、リラックスできる時間を持つことも大切です。規則正しい生活リズムを整えることが、腸の健康にもつながります。
腹痛と下痢に関するよくある質問
最後に、腹痛と水様性下痢に関してよく寄せられる質問と回答をまとめました。
- 家族にうつさないためにはどうすれば良いですか?
-
感染性胃腸炎が疑われる場合、家庭内での感染拡大を防ぐことが非常に重要です。トイレの後や調理・食事の前には、石けんと流水で丁寧に手洗いをし、タオルの共用は避けましょう。
嘔吐物や便を処理する際は、使い捨ての手袋とマスクを着用し、次亜塩素酸ナトリウムを含む消毒液で汚れた場所をしっかりと消毒することが有効です。
- 下痢が続くと痩せますか?
-
下痢が続くと水分や栄養素の吸収が不十分になるため、一時的に体重が減少することがあります。これは主に体内の水分が失われることによるもので、健康的な痩せ方ではありません。
意図していないにもかかわらず体重減少が続く場合は、炎症性腸疾患など他の病気の可能性もあるため、医療機関に相談してください。
- ストレスで水様性下痢になることはありますか?
-
脳と腸は自律神経などを介して密接に関連しており、これを脳腸相関と呼びます。
強いストレスや精神的な緊張を感じると、自律神経が乱れて腸の動きが過剰になり、腹痛を伴う水様性下痢を起こすことがあり、過敏性腸症候群(IBS)の典型的な症状の一つです。
- いつから普通の食事に戻して良いですか?
-
便の形が元に戻り、腹痛などの症状がなくなったら、徐々に普段の食事に戻していきます。
急に脂肪の多い食事や刺激の強い食事に戻すと、再び症状が悪化することがあるため、消化の良いものから少量ずつ、品目を増やしていくのが良いでしょう。数日かけてゆっくりと慣らしていくことが大切です。
次に読むことをお勧めする記事
【毎日の下痢症状が続くときの大腸内視鏡検査による診断基準】
“基本を押さえたら、次は実際にどんな検査で何が分かるの?”が気になるところ。検査で確認するポイントが具体的に分かり、受診の準備に役立ちます。
【腸の健康が体を支える 腸内環境を整える】
腹痛と水様性下痢について理解が深まると、腸の健康全般についても知りたくなる方が多いようです。総合的な腸の健康管理に役立つ内容です。
参考文献
Tokuda Y, Takahashi O, Ohde S, Shakudo M, Yanai H, Shimbo T, Fukuhara S, Hinohara S, Fukui T. Gastrointestinal symptoms in a Japanese population: a health diary study. World Journal of Gastroenterology: WJG. 2007 Jan 28;13(4):572.
Matsumoto Y, Nadatani Y, Otani K, Higashimori A, Ominami M, Fukunaga S, Hosomi S, Kamata N, Kimura T, Fukumoto S, Tanaka F. Prevalence and risk factor for chronic diarrhea in participants of a Japanese medical checkup. JGH Open. 2022 Jan;6(1):69-75.
Burgers K, Lindberg B, Bevis ZJ. Chronic diarrhea in adults: evaluation and differential diagnosis. American family physician. 2020 Apr 15;101(8):472-80.
Barr W, Smith A. Acute diarrhea in adults. American family physician. 2014 Feb 1;89(3):180-9.
Hammer HF. Management of chronic diarrhea in primary care: the gastroenterologists’ advice. Digestive Diseases. 2021 Feb 15;39(6):615-21.
Corinaldesi R, Stanghellini V, Barbara G, Tomassetti P, De Giorgio R. Clinical approach to diarrhea. Internal and emergency medicine. 2012 Oct;7:255-62.
Juckett G, Trivedi R. Evaluation of chronic diarrhea. American family physician. 2011 Nov 15;84(10):1119-26.
Tribble DR. Antibiotic therapy for acute watery diarrhea and dysentery. Military medicine. 2017 Sep 1;182(suppl_2):17-25.
Lacy BE. Diagnosis and treatment of diarrhea-predominant irritable bowel syndrome. International journal of general medicine. 2016 Feb 11:7-17.
Manatsathit S, Dupont HL, Farthing M, Kositchaiwat C, Leelakusolvong S, Ramakrishna BS, Sabra A, Speelman P, Surangsrirat S. Guideline for the management of acute diarrhea in adults. Journal of Gastroenterology & Hepatology. 2002 Feb 2;17.