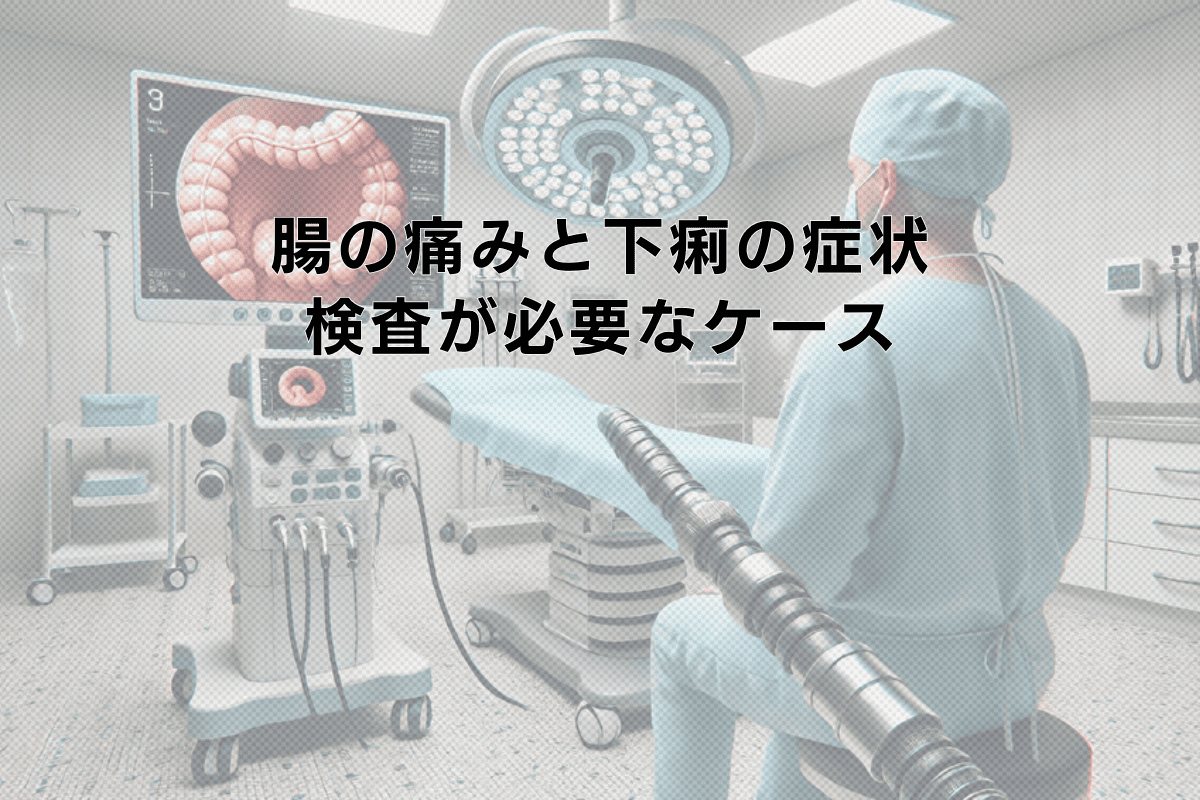腸の痛みや下痢が続くときは「ただの食あたりだろう」と放置しがちですが、長引く症状の背景には大腸や小腸の病気が潜んでいる場合があります。
腸の痛みと下痢の症状があると日常生活の質が下がり、体力的にも精神的にも負担を感じることが少なくありません。
この記事では、腸が痛い下痢や腸の痛みと下痢が同時に起こる理由、痛みを感じにくい下痢の注意点、そして検査が必要なケースについてわかりやすく解説します。
腸の痛みと下痢の症状が気になるときに知りたい基本情報
腸の痛みと下痢が続くときは、食事の内容やストレス状態など、複数の要因が影響している可能性があります。
胃腸炎や過敏性腸症候群など比較的よくみられる病態もあれば、ポリープや炎症性腸疾患など精密検査が必要な病気が隠れていることも考えられます。
まずは腸のしくみや下痢の定義を整理し、なぜこうした症状が起こるのか理解することが重要です。
腸の働きと痛みの仕組み
腸は主に栄養の吸収と水分の調節を担っています。小腸では食物が消化酵素と混ざりながら栄養分を吸収し、大腸では水分が吸収されて便が形成されます。腸の痛みは、粘膜の炎症や過度の収縮運動が原因となることが多いです。
下痢の定義と種類
一般的に、便の水分量が増加して形が崩れた状態を下痢と呼びます。回数の多さも指標のひとつですが、回数よりも便の性状がポイントになります。急性の下痢と慢性の下痢では考え方が異なるため、症状が続く日数も意識することが大切です。
腸の痛みと下痢を伴う主な症状
- 急性胃腸炎:突然の下痢や嘔吐などが特徴です。ウイルスや細菌が原因となることが多いです。
- 過敏性腸症候群:ストレスなどの心理的要因で腸の機能に影響が出て、痛みや下痢、便秘が周期的に起こります。
- 潰瘍性大腸炎などの炎症性腸疾患:血便を伴うケースが多く、慢性的に腹痛や下痢が続くことがあります。
腸の痛みと下痢が与える日常生活への影響
トイレに行く回数が増えるため、外出や仕事にも支障が出やすくなります。長引く下痢で栄養吸収が十分に行えず、体重減少や倦怠感、集中力の低下を感じることも少なくありません。
腸の痛みと下痢に関する理解を深める項目
| 症状・状態 | 特徴 | 受診の目安 |
|---|---|---|
| 急性胃腸炎 | 短期間で強い症状が出ることが多い | 3日以上続くまたは水分補給が困難な場合 |
| 過敏性腸症候群 | ストレスで痛みや便通異常が繰り返されやすい | 痛みと下痢が断続的に続き生活に支障が出る時 |
| 炎症性腸疾患 | 血便や強い腹痛を伴うことが多い | 症状が1週間以上持続または出血がある場合 |
| 大腸ポリープ・がん | 初期症状が少なく、下痢・便秘の変化で気づく | 便に血液が混ざるなど異常がみられたとき |
腸の痛みの原因となる主な疾患
腸に痛みが生じる原因は数多くあります。感染症から炎症性疾患、機能性疾患まで多岐にわたり、下痢との組み合わせが特徴的なものも少なくありません。腸の痛み下痢を繰り返す方にとって、早めに原因を突き止めることが大切です。
感染性腸炎
ノロウイルスやロタウイルス、病原性大腸菌などが代表的で、感染源は食品や人との接触です。激しい下痢と嘔吐、発熱を伴うことがあります。感染性腸炎は急性症状が多いため早めの受診が望ましいです。
炎症性腸疾患
潰瘍性大腸炎やクローン病は自己免疫の乱れが原因のひとつと考えられ、長期間にわたり腹痛や下痢、時に血便を繰り返す特徴があります。症状の進行状況によっては、内視鏡検査などの精密検査を考えたほうがいい疾患です。
大腸ポリープや大腸がん
初期段階では自覚症状が少なく、便通の変化や下血によって見つかることが多いです。ポリープの一部はがん化の可能性もあるため、内視鏡検査による早期発見が重要です。腸の痛みが続く場合は念のため検査してください。
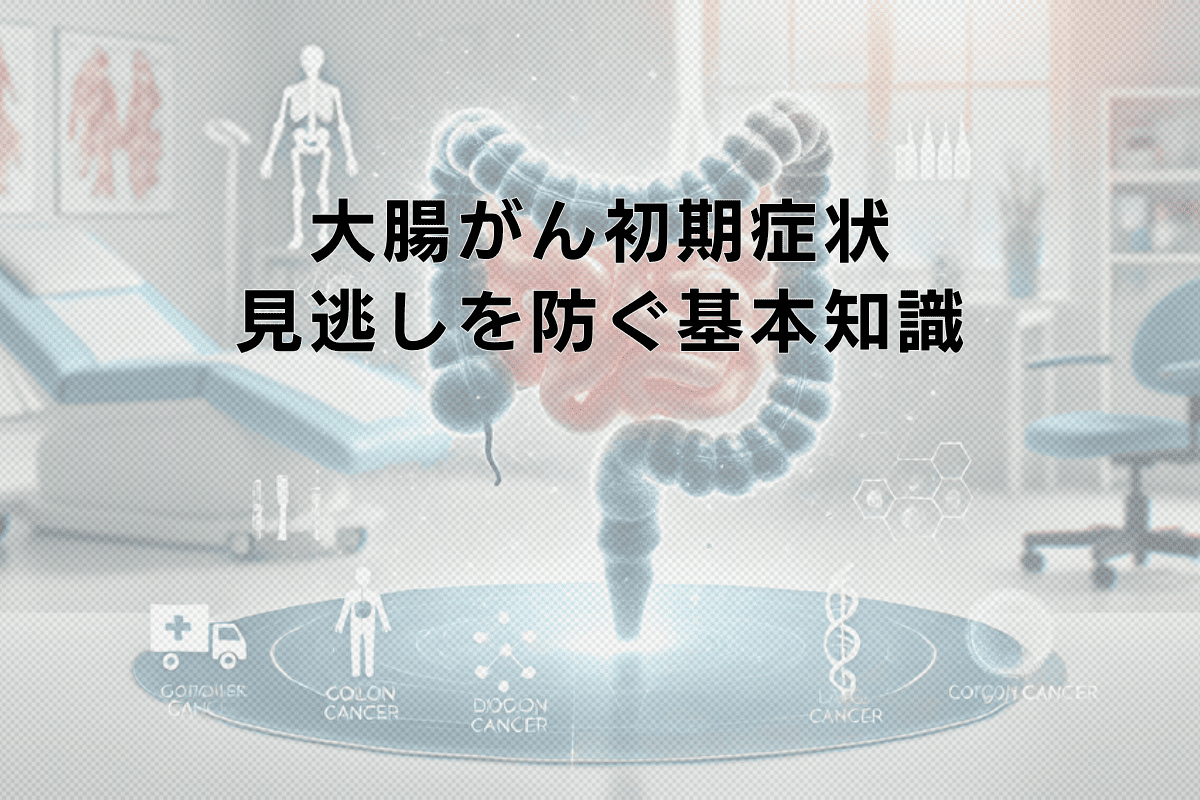
病気の特徴と発症リスク
| 疾患名 | 特徴 | リスク要因 |
|---|---|---|
| 感染性腸炎 | 急な下痢と嘔吐、発熱 | 衛生環境の悪化、生ものの摂取 |
| 潰瘍性大腸炎 | 血便や慢性的な下痢、腹痛 | 免疫の異常、遺伝的素因 |
| クローン病 | 口から肛門まで消化管全体に炎症が起こり得る | 免疫の異常、遺伝的素因 |
| 大腸ポリープ | 初期症状がほぼないが、がん化の可能性がある | 食生活の乱れ、年齢、遺伝 |
| 大腸がん | 血便や便通異常、体重減少を伴うことが多い | 食生活、喫煙、遺伝、年齢 |
過敏性腸症候群
下痢型、便秘型、混合型の3種類が知られ、ストレスや緊張によって症状が悪化することがあります。腸の痛みと下痢が一緒に起こるケースが多く、検査では異常が見つからないのに症状が続くのが特徴です。
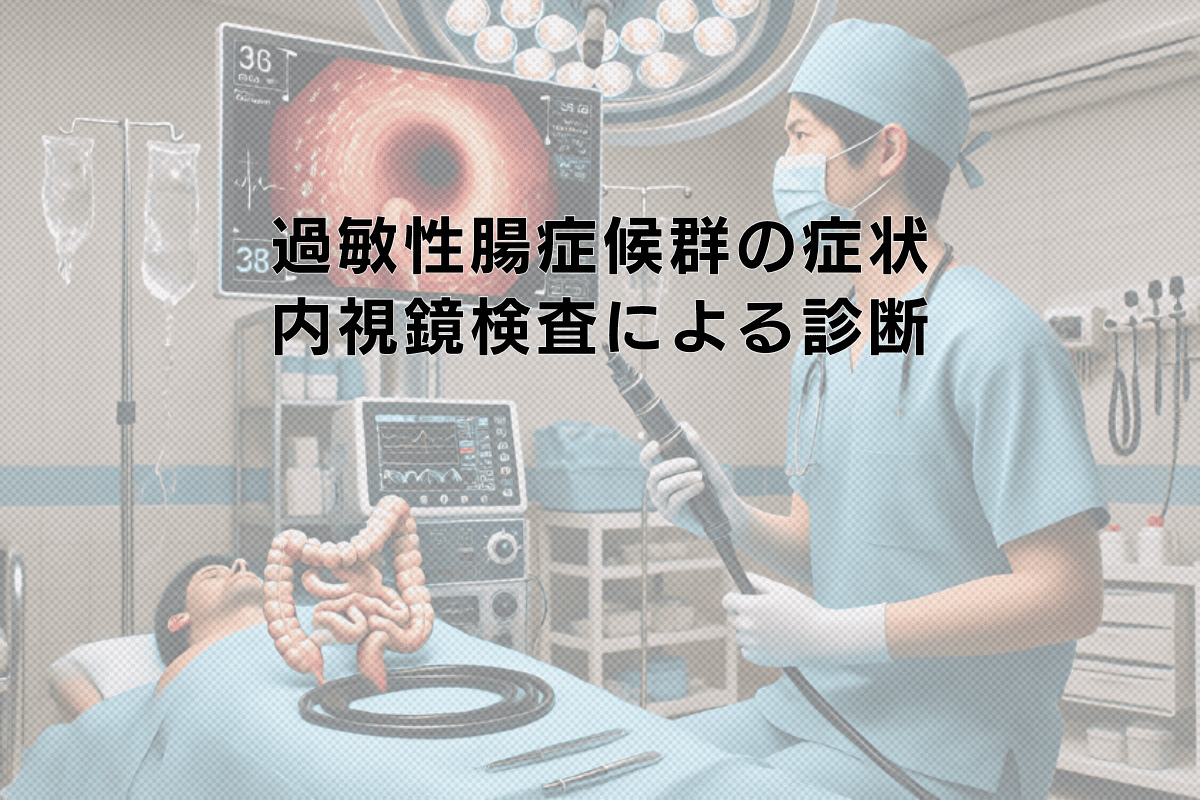
下痢が続くときに考えられる背景
下痢は水分の再吸収がうまくいかないことで便が柔らかくなる現象ですが、原因は多岐にわたり、複数の誘因が重なると慢性化する傾向があります。
下痢が続く背景にある要因をつかむことで、早期改善や検査の判断につながります。
食事内容と生活リズムの影響
油分の多い食事や香辛料の摂取が続くと腸に刺激を与え、下痢につながる場合があり、また、十分な睡眠や規則正しい食事時間が保てない生活も消化管のリズムを乱しやすいです。
ストレスとの関係
ストレスを強く感じると、自律神経のバランスが乱れやすくなります。副交感神経と交感神経の切り替えがうまくいかなくなることで、腸の動きが過剰になったり抑制されたりして下痢や便秘を繰り返す人も少なくありません。
痛みを伴う下痢と痛みを感じにくい下痢
腸が痛い下痢はわかりやすいサインですが、痛みをほとんど感じない下痢も注意が必要です。自覚症状が少ない分、重大な病気の発見が遅れることがあります。
長引く下痢のリスクと栄養不足
下痢が長く続くと体内の水分や電解質が失われやすくなり、脱水や栄養不足による体力低下を招く可能性があるため、医療機関での早期相談が大切です。
下痢が長引いた場合に考える要因
| 要因 | 具体例 | 対策 |
|---|---|---|
| 食習慣の乱れ | 高脂質・高糖質の食事、外食過多 | バランスの良い食事、食物繊維や発酵食品の積極的な摂取 |
| 水分補給の不足 | 喉が渇いてから飲む、飲む量が少ない | こまめな水分摂取、スポーツドリンクなどで電解質を補う |
| ストレスの蓄積 | 勤務環境の変化、睡眠不足、精神的緊張 | リラクゼーション、適度な運動、専門家のカウンセリング利用 |
| 腸内細菌バランスの乱れ | 過度の飲酒、抗生物質の長期使用など | プロバイオティクスやプレバイオティクスの活用 |
| 隠れた病気 | 炎症性腸疾患、大腸ポリープ、大腸がんなど | 早期の内視鏡検査、大腸カメラでの精査 |
腸の痛みと下痢の症状が同時に起こる理由
腸の痛みと下痢が同時に起こる背景には、腸管の蠕動運動が過剰になっているケースが多いです。
過敏性腸症候群のように、精神的なストレスがきっかけで腸が敏感に反応する場合もあれば、炎症性疾患など物理的な炎症や潰瘍が原因で痛みと下痢が併発することもあります。
蠕動運動の乱れによる影響
腸は一定のリズムで収縮と弛緩を繰り返し、消化物を肛門へ送ります。このリズムが乱れると、過度な収縮で痛みが生じ、同時に便が十分に水分を吸収できない状態で排出されるため下痢を招きます。
腸内フローラのバランス低下
腸内には多数の細菌が存在し、消化や免疫機能をサポートしていて、抗生物質の使用や生活習慣の乱れで腸内フローラが変化すると、下痢や腹痛が起こりやすくなります。

ストレスホルモンの影響
ストレスを感じると、コルチゾールやアドレナリンなどのホルモンが分泌されて腸の動きが変化し、痛みや下痢だけでなく、便秘やガス溜まりなども起きやすいです。
腸の痛みと下痢の同時発生を考える視点
| 観点 | 主なメカニズム | 改善の糸口 |
|---|---|---|
| 自律神経のバランス | 交感神経と副交感神経が乱れて蠕動運動をコントロールしにくくなる | ストレスマネジメント、適度な休息 |
| 腸内環境の乱れ | 善玉菌の減少や悪玉菌の増加で炎症を引き起こしやすい | 乳酸菌やビフィズス菌の摂取 |
| 粘膜や筋層の炎症 | 潰瘍や炎症性疾患で腸壁が傷つき痛みと下痢が同時に現れやすい | 消炎剤、内視鏡検査での原因特定 |
| 食事内容の偏り | 刺激物やアルコール過剰で腸粘膜に負担がかかり痛み・下痢を誘発 | 食事の見直し、刺激物の控え |
過敏性腸症候群との関連
ストレスが原因で腸の運動が過度になる過敏性腸症候群は、腸の痛み下痢が同時に起こる代表的な病態のひとつです。精神的な負担を軽減する工夫と共に、医療機関での診断と生活指導を受けると症状が緩和しやすくなります。
痛みを感じにくい下痢の場合の注意点
腸痛い下痢であれば受診を検討しやすいですが、痛みがあまりない下痢は放置されることがあり、痛くない下痢にも重大な病気が潜んでいる可能性があるため、注意が必要です。
痛みが少ない下痢の特徴
- 便の回数や形状は明らかに異常なのに腹部の違和感が少ない
- 体重減少や貧血が進行してから気づくケース
- 消化管の感覚が鈍くなっている場合
痛みが少ない下痢で考えられる疾患
大腸ポリープや大腸がんの初期段階では、強い痛みを伴わない下痢が続くことがあり、腸内の腫瘍によって便の通りが悪くなり、下痢と便秘を繰り返すことも珍しくありません。
痛みが軽微な下痢時に疑うべき可能性
| 疾患・状態 | 主な症状と経過 | 検査のすすめ方 |
|---|---|---|
| 大腸ポリープ | 血便や便通の乱れ程度で痛みが少ない | 早期の大腸カメラ検査 |
| 大腸がん | 初期にはほぼ無症状のことが多い | 便潜血検査や大腸カメラ検査 |
| 吸収不良症候群 | 栄養吸収がうまくいかず慢性的な下痢 | 血液検査と内視鏡検査 |
| 寄生虫感染 | 腹痛よりも長引く下痢で発覚しやすい | 便検査での寄生虫確認 |
痛みを感じにくい下痢が続くときのリスク
- 慢性的な脱水や電解質異常
- 免疫力低下による別の感染症リスク増加
- 貧血や低栄養状態
早めの相談が必要な理由
痛みが少ない下痢は、患者本人の危機感が低くなりやすく、検査や治療が後回しになりがちです。悪化すると治療期間も長引きやすいため、下痢の程度や回数をメモに残して早期相談を意識するとよいでしょう。
受診を検討すべき症状と検査の種類
腸の痛みと下痢が続く場合、自己判断で市販薬を使い続けるだけでは十分に対処できないケースがあります。数日経っても症状が改善しないときや、血便や体重減少などのサインがある場合は、医療機関で精密検査を受けてください。
受診を考えるタイミング
- 腸の痛みと下痢が1週間以上続く
- 便に血が混ざっている
- 高熱が続き、体力が極端に落ちている
- 体重が急激に減っている
- 痛みを感じにくい下痢でも便が極端に水っぽい、色が黒っぽいなどの異常を感じる
症状と受診すべき目安
| 症状 | 受診の目安 | 主に考えられる検査 |
|---|---|---|
| 1週間以上の下痢 | 慢性化の可能性がある | 血液検査、便検査 |
| 血便が見られる | 消化管の出血、腫瘍性病変を疑う | 大腸カメラ、胃カメラ、CT検査 |
| 体重減少が顕著 | 栄養吸収不良や腫瘍性病変の可能性 | 内視鏡検査、腸の粘膜生検 |
| 激しい腹痛と発熱を伴う | 細菌性・ウイルス性感染症を疑う | 血液培養、便培養、内視鏡検査 |
| 痛みがなく下痢だけが続く | 大腸ポリープや初期がんを疑う | 大腸カメラ、便潜血検査 |
主な検査の種類
- 大腸カメラ(下部内視鏡検査):大腸全体を観察し、ポリープや炎症、潰瘍などを直接確認できます。必要に応じて生検(組織採取)を行うことでがんや炎症性疾患の診断を行います。
- 胃カメラ(上部内視鏡検査):食道から胃・十二指腸を観察し、出血や潰瘍の有無を確認します。腹痛の原因が胃や十二指腸にある場合もあるため、総合的に消化管を調べるときに有効です。
- CT検査:腫瘍や炎症の広がりを画像で把握しやすく、状況に応じて内視鏡検査と合わせて行うことがあります。
- 便培養・便潜血検査:細菌やウイルスなどの感染症を調べたり、消化管出血の有無を確認したりします。
検査でわかることと治療へのつながり
内視鏡検査ではポリープやがん細胞などの有無を詳細に確認でき、検査の段階でポリープ切除が可能な場合もあります。原因が特定されれば、抗炎症薬や免疫調整薬など適切な治療方針を立てられ、改善の見込みが高まります。
内視鏡検査の利点と注意点
| 項目 | 利点 | 注意点 |
|---|---|---|
| 大腸カメラ | 直視で大腸全体を把握し、ポリープ切除も可能 | 前処置で腸を空にする必要がある |
| 胃カメラ | 上部消化管の細部を確認し、早期病変を見つけやすい | 器具挿入による嘔気や不快感が出る場合がある |
| 同日内視鏡検査 | 胃と大腸を同日に検査でき、通院回数の削減が期待できる | 検査時間が長くなり、前処置や sedation(鎮静)の管理が必要 |
日常生活で取り入れたいケア方法
腸の痛みと下痢を軽減し、再発リスクを下げるためには生活習慣の見直しが大切で、食事や運動、ストレスマネジメントなど、身近な工夫で腸内環境をサポートできます。
気になる症状がある場合は、まずは日常のセルフケアを意識しながら、改善が見られなければ医療機関で検査を検討してください。
食事のポイント
- 食物繊維を適度に摂る:野菜や果物、海藻、全粒穀物など
- 発酵食品を取り入れる:ヨーグルト、納豆、味噌など
- 脂質や糖質の過剰摂取を避ける:特に外食やお惣菜はカロリーと塩分に注意
- 刺激の強い香辛料やアルコールは控えめに
腸の調子を整えやすい食品
| 食品グループ | 食材例 | 効果・特徴 |
|---|---|---|
| 野菜類 | ブロッコリー、キャベツ、ほうれん草など | 食物繊維やビタミンが豊富で便通改善に役立つ |
| 発酵食品 | ヨーグルト、キムチ、納豆、味噌など | 乳酸菌や酵母による腸内環境の調整 |
| 海藻類 | わかめ、ひじき、昆布、もずく | ミネラルを多く含み、便の通過をスムーズにする |
| 果物 | りんご、バナナ、柑橘類 | ビタミンや果糖が手軽に摂取できる |
ストレス管理と睡眠
ストレスを溜めない習慣づくりは、腸の痛み下痢の予防につながり、趣味や適度な運動でリラックスする時間を確保し、十分な睡眠をとるように意識すると腸内環境が安定しやすくなります。
運動のメリット
ウォーキングやヨガなどの軽い運動を継続すると、腸の蠕動運動が活性化して便通が整い、血流も良くなるため、消化管へ十分な酸素や栄養が行き渡りやすい環境をつくります。
生活改善に役立つヒント
- 仕事や家事の合間に軽くストレッチを取り入れる
- 食事時間を一定に保ち、夜食を控える
- スマートフォンを寝る前に長時間見ないようにする
- 週に数回ウォーキングなどの軽運動を取り入れる
- 心配事や不安はノートに書き出して客観視する
定期検診とセルフチェック
便の性状や回数、腹痛のタイミングなどを日々メモしておくと、自分の腸の傾向を把握しやすくなり、定期的に内視鏡検査や大腸カメラを受けると、ポリープや大腸がんの早期発見にもつながります。
よくある質問
腸の痛みと下痢の症状を抱える人から寄せられる代表的な質問をまとめました。少しでも不安を減らすきっかけになれば幸いです。
- 下痢が続いているときに食事はどうすればいいですか?
-
水分補給を意識しつつ、消化に良いものを少量ずつとるのがおすすめです。脂肪分や香辛料の多い食事は控え、野菜や果物などのバランスにも気を配ると回復しやすくなります。
- 腸が痛い下痢のときはすぐに薬で止めたほうがいいのでしょうか?
-
状況によっては整腸剤や下痢止め薬が有用ですが、原因によっては体外への排出が必要な場合もあります。原因不明のまま薬だけで対処し続けると、症状がかえって長引いたり悪化したりすることがあります。医師に相談してからのほうが安心です。
- 大腸カメラと胃カメラはどのように使い分ければいいでしょうか?
-
主に便通異常や大腸の異常が疑われるときは大腸カメラ、上腹部の痛みや吐き気が強いときは胃カメラが選択されやすいです。ただし、症状の範囲によっては両方の検査を受けるほうが原因を確実に突き止めやすくなります。
- 痛みを感じにくい下痢でも受診したほうがいいですか?
-
はい。腸の痛みがないからといって安全とは限りません。体重減少や便の異常が気になる場合は早めに受診し、内視鏡検査や血液検査などで原因を突き止めることをおすすめします。
次に読むことをお勧めする記事
【大腸内視鏡検査の3日前からの食事制限と準備】
大腸カメラを具体的に検討している方へ。検査3日前から当日までの食事・下剤のポイントを押さえると、前処置がスムーズに行えます。
【腸にいい食べ物を知る 腸内環境を整える方法】
腸の痛みと下痢について理解が深まったところで、日常的な腸内環境ケアの知識も合わせて持っていただくと、予防と再発防止により効果的です。
参考文献
Cai J, Yuan Z, Zhang S. Abdominal pain, diarrhea, constipation-which symptom is more indispensable to have a colonoscopy?. International Journal of Clinical and Experimental Pathology. 2015 Jan 1;8(1):938.
Kinoshita Y, Ariyoshi R, Fujigaki S, Tanaka K, Morikawa T, Sanuki T. Endoscopic diagnosis of chronic diarrhea. DEN open. 2022 Apr;2(1):e53.
Tomizawa M, Shinozaki F, Hasegawa R, Shirai Y, Motoyoshi Y, Sugiyama T, Yamamoto S, Ishige N. Abdominal ultrasonography for patients with abdominal pain as a first-line diagnostic imaging modality. Experimental and Therapeutic Medicine. 2017 May 1;13(5):1932-6.
Nagata N, Ishii N, Manabe N, Tomizawa K, Urita Y, Funabiki T, Fujimori S, Kaise M. Guidelines for colonic diverticular bleeding and colonic diverticulitis: Japan Gastroenterological Association. Digestion. 2019 Jan 14;99(Suppl. 1):1-26.
Cai J, Yuan Z, Zhang S. Abdominal pain, diarrhea, constipation-which symptom is more indispensable to have a colonoscopy?. International Journal of Clinical and Experimental Pathology. 2015 Jan 1;8(1):938.
Al-Shamali MA, Kalaoui M, Hasan F, Khajah A, Siddiqe I, Al-Nakeeb B. Colonoscopy: evaluating indications and diagnostic yield. Annals of Saudi medicine. 2001 Sep;21(5-6):304-7.
Fry LC, Carey EJ, Shiff AD, Heigh RI, Sharma VK, Post JK, Hentz JG, Fleischer DE, Leighton JA. The yield of capsule endoscopy in patients with abdominal pain or diarrhea. Endoscopy. 2006 May;38(05):498-502.
Burgers K, Lindberg B, Bevis ZJ. Chronic diarrhea in adults: evaluation and differential diagnosis. American family physician. 2020 Apr 15;101(8):472-80.
Shah RJ, Fenoglio-Preiser C, Bleau BL, Giannella RA. Usefulness of colonoscopy with biopsy in the evaluation of patients with chronic diarrhea. The American journal of gastroenterology. 2001 Apr 1;96(4):1091-5.
Fine KD, Seidel RH, Do K. The prevalence, anatomic distribution, and diagnosis of colonic causes of chronic diarrhea. Gastrointestinal endoscopy. 2000 Mar 1;51(3):318-26.