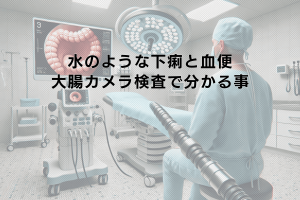お腹の調子が安定せず、軟便になったかと思えば、数日後には便秘に悩まされる便通の異常を繰り返している方は少なくありません。
多くの場合、一時的な体調の変化やストレスが原因ですが、背後には消化器系の病気が隠れている可能性も考えられます。
この記事では、軟便と便秘が繰り返される原因を深く掘り下げ、背景に潜む可能性のある病気、正確な診断のためにどのような大腸検査が大切になるのかを詳しく解説します。
軟便と便秘を繰り返す症状とは
便の状態は、日々の健康状態を映し出す鏡のようなもので、軟便と便秘を繰り返すという状態は、腸の働きが正常でないことを示唆しています。
軟便の定義と状態
軟便とは、通常よりも水分量が多く、形が定まらない柔らかい便のことで、泥状やペースト状の便がこれにあたります。健康な便は適度な硬さを持つバナナ状ですが、軟便はそれよりも明らかに柔らかく、排便時に形を保てません。
腸内での水分吸収がうまくいっていない、あるいは腸の動きが活発になりすぎて、便が腸を通過する時間が短くなっている場合に起こり、一時的なものであれば心配はいりませんが、長く続く場合は注意が必要です。
便の状態を判断する国際的な基準
| タイプ | 形状 | 状態 |
|---|---|---|
| 1 – 2 | 硬くコロコロ、またはソーセージ状で表面にひび割れ | 便秘傾向 |
| 3 – 4 | 表面が滑らかなソーセージ状、またはひび割れがある | 正常範囲 |
| 5 – 7 | 柔らかい半固形、泥状、または水様状 | 軟便・下痢傾向 |
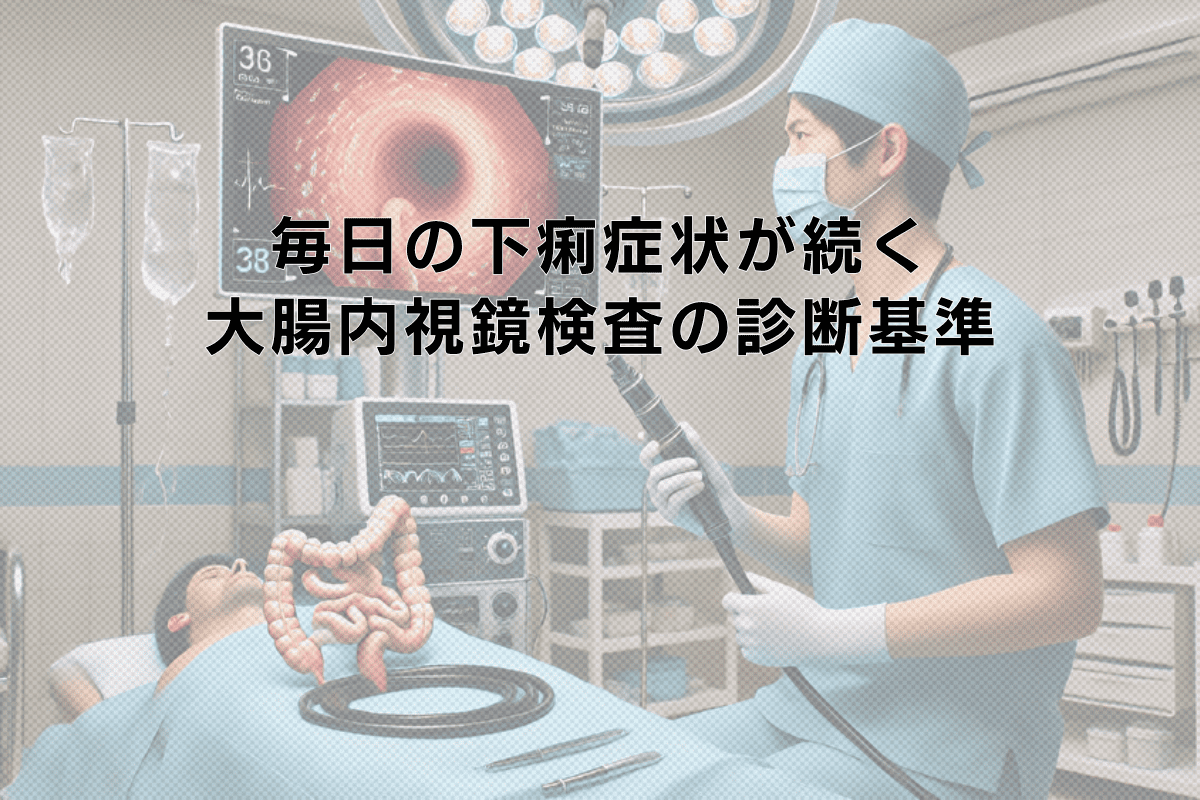
便秘の定義と状態
便秘は、排便の回数が少ない、便が硬くて出しにくい、排便後もすっきりしない(残便感がある)状態です。医学的には、週の排便回数が3回未満であることや、排便時に強くいきむ必要があることなどが定義に含まれます。
便が腸内に長時間とどまることで水分が過剰に吸収され、硬く、排出が困難になり、腹部の張りや不快感、腹痛などを伴うことも多く、生活の質を大きく低下させる原因にもなります。
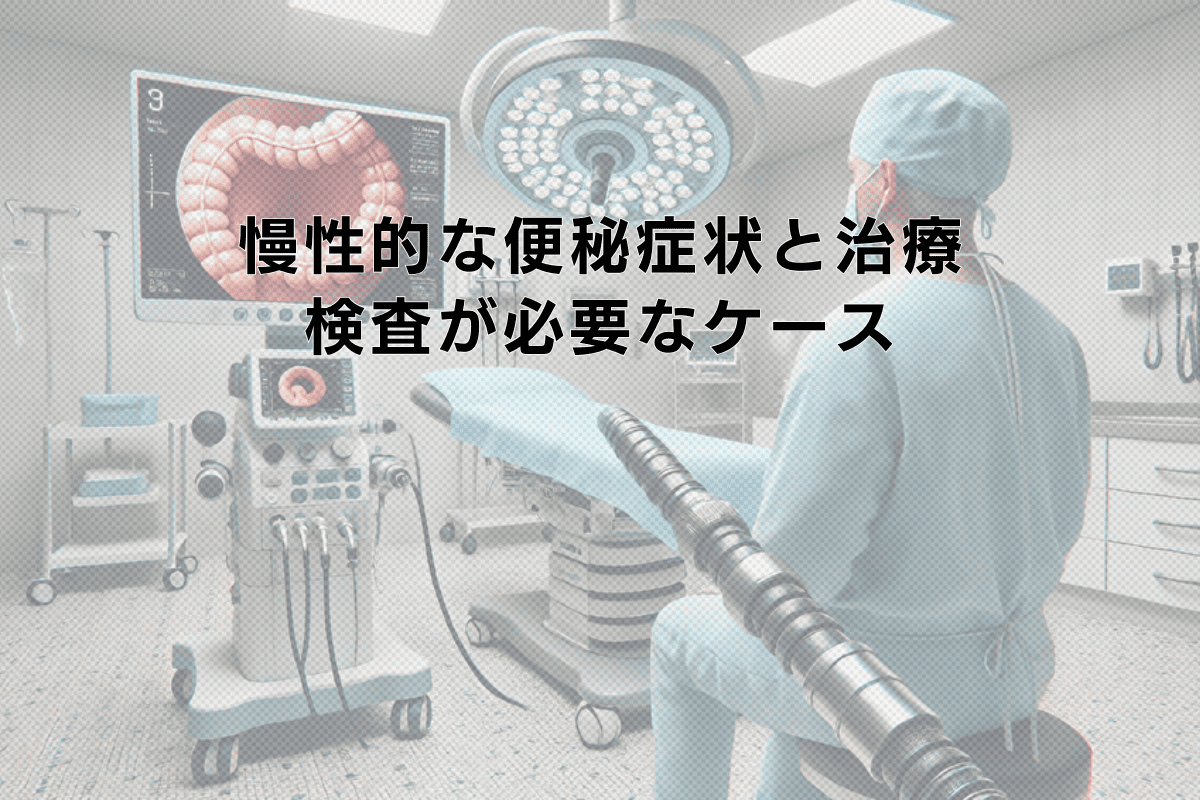
症状が交互に現れる背景
軟便と便秘が交互に現れるのは、腸の運動機能に異常が生じているサインで、腸の動きが過剰に活発になれば、便の水分が十分に吸収されずに軟便となり、動きが鈍くなると、便が腸内に長く留まり便秘になります。
腸の運動の不安定さが、症状を繰り返す根本的な原因です。この状態は、腸そのものに炎症や腫瘍などの目に見える異常がないにもかかわらず、機能的な問題で起こることがあります。
多くの人が経験する症状ですが、自己判断で放置せず、原因を考えることが大切です。
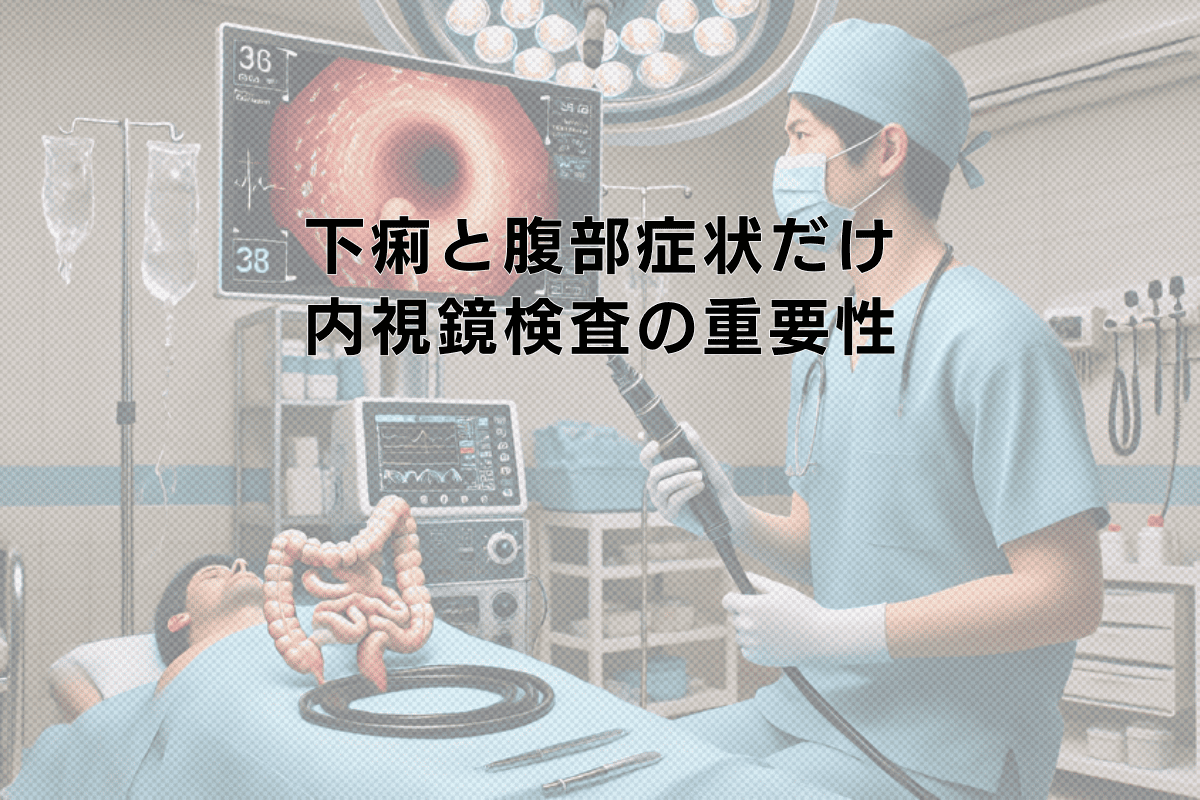
なぜ軟便と便秘が繰り返されるのか?考えられる原因
便通の異常が繰り返される背景には、さまざまな原因が考えられ、日常生活の中に潜む要因から、心身のバランスの乱れ、そして腸内環境の変化まで、複数の要素が複雑に絡み合っていることが多いです。
生活習慣の乱れ
不規則な生活は、腸の働きに直接的な影響を与え、睡眠不足や食事の時間がバラバラであることは、体内時計を乱し、自律神経のバランスを崩す大きな要因です。
腸の運動は自律神経によってコントロールされているため、バランスが崩れると腸の動きも不安定になり、軟便や便秘を起こしやすくなり、また、運動不足も腸のぜん動運動を低下させ、便秘の原因となることが知られています。
日々の生活習慣チェック
| 項目 | 腸への影響 | 改善のポイント |
|---|---|---|
| 睡眠時間 | 睡眠不足は自律神経を乱し、腸の働きを不安定にする | 毎日6〜8時間の質の良い睡眠を心がける |
| 食事の時間 | 不規則な食事は腸のリズムを崩す | できるだけ毎日同じ時間に3食とる |
| 運動習慣 | 運動不足は腸の動きを鈍くし、便秘につながる | ウォーキングなど軽い運動を日常に取り入れる |
ストレスによる自律神経の不調
脳と腸は密接に関連しており、脳腸相関として知られていて、精神的なストレスを感じると、脳がその信号をキャッチし、自律神経を介して腸に影響を与えます。
強いストレスや持続的な緊張状態は、交感神経を優位にし、腸の血管を収縮させて動きを抑制し、便秘を起こすことがあります。
また、ストレスから解放されたときなどに副交感神経が過剰に働くと、腸が過敏に反応して動きが活発になり、軟便や下痢になることもあり、心の状態が直接的にお腹の不調として現れることは珍しくありません。
ストレスが腸に与える影響
| ストレスの種類 | 自律神経の反応 | 腸への主な影響 |
|---|---|---|
| 精神的ストレス(緊張・不安) | 交感神経が優位になる | 腸の動きが抑制され、便秘傾向になることがある |
| 身体的ストレス(過労・睡眠不足) | 自律神経全体のバランスが崩れる | 腸の機能が不安定になり、便通異常を起こしやすい |
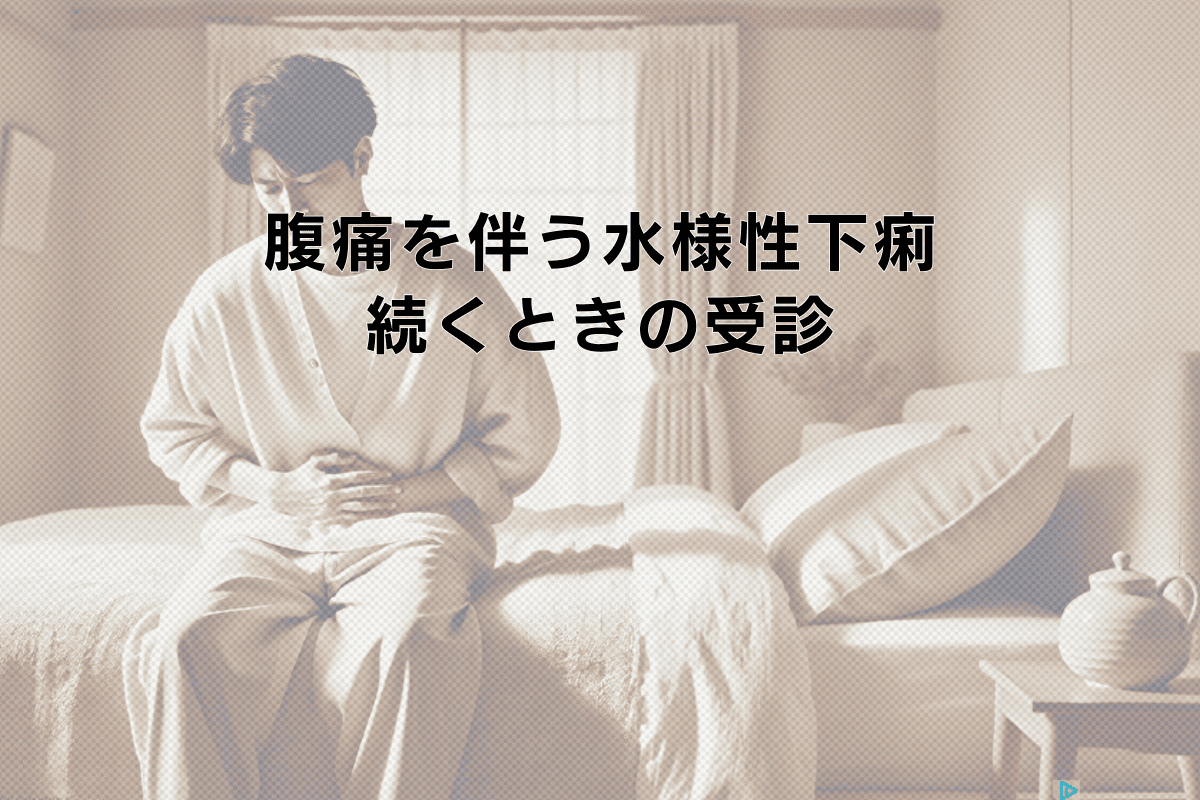
食生活の影響
何を食べるかということも、便の状態を左右する重要な要素で、香辛料の多い刺激物や脂っこい食事、アルコールの過剰摂取は、腸の粘膜を刺激して動きを活発にし、軟便の原因となります。
また、冷たいものの摂りすぎもお腹を冷やし、消化機能の低下を招きます。一方で、食事量が極端に少なかったり、食物繊維が不足したりすると、便のかさが減って腸への刺激が弱まり、便秘につながります。
食物繊維には水に溶けやすい水溶性食物繊維と、水に溶けにくい不溶性食物繊維があり、両方をバランス良く摂ることが理想的な便通には重要です。
腸内環境の悪化
私たちの腸内には、数百兆個もの細菌が生息しており、腸内フローラと呼ばれる生態系を形成していて、腸内細菌のバランスが、健康な便通を維持する上で非常に大きな役割を果たしています。
善玉菌が優位な状態では腸内環境は良好に保たれますが、悪玉菌が増えると腸の働きが乱れ、便秘や軟便を起こしやすくなります。抗生物質の使用、偏った食生活、加齢など、腸内環境が悪化する要因はさまざまです。
また、悪玉菌が作り出す有害物質は、腸の運動を異常にさせたり、不快なガスの原因になったりもします。
軟便と便秘を繰り返すときに考えられる病気
生活習慣の改善やストレス管理を試みても症状が改善しない場合や、他の気になる症状を伴う場合には、何らかの病気が原因である可能性を考える必要があります。
過敏性腸症候群(IBS)
過敏性腸症候群(Irritable Bowel Syndrome, IBS)は、大腸に炎症や腫瘍といった器質的な異常が見られないにもかかわらず、腹痛や腹部の不快感を伴い、便秘や下痢などの便通異常が長く続く病気です。
ストレスが症状の引き金になることが多く、腸の知覚過敏や運動異常が原因と考えられていて、軟便と便秘を交互に繰り返すタイプは、混合型IBSと呼ばれます。
過敏性腸症候群は命に関わるものではありませんが、症状が日常生活に大きな支障をきたすことがあります。
過敏性腸症候群の主なタイプ
| タイプ | 主な症状 | 特徴 |
|---|---|---|
| 下痢型 | 突然の腹痛と下痢・軟便 | 緊張する場面などで症状が出やすい |
| 便秘型 | 硬い便と排便困難 | 腹部の張りを伴うことが多い |
| 混合型 | 下痢・軟便と便秘を繰り返す | 症状が変動しやすい |
大腸がんやポリープ
大腸がんや大腸ポリープは、初期段階では自覚症状がほとんどないことが多いですが、進行すると便通に影響を及ぼすことがあります。
がんやポリープが大きくなることで腸管が狭くなり、便が通りにくくなって便秘になったり、逆に腸が刺激されて軟便になったりし、便秘と軟便を繰り返すという症状も、大腸がんのサインの一つとして知られています。
特に、便に血が混じる(血便)、便が細くなる、原因不明の体重減少、貧血などの症状を伴う場合は、早急な検査が必要です。
大腸がんは早期に発見すれば治癒率が非常に高いがんであり、症状から病気の可能性を疑い、検査を受けることが極めて重要になります。
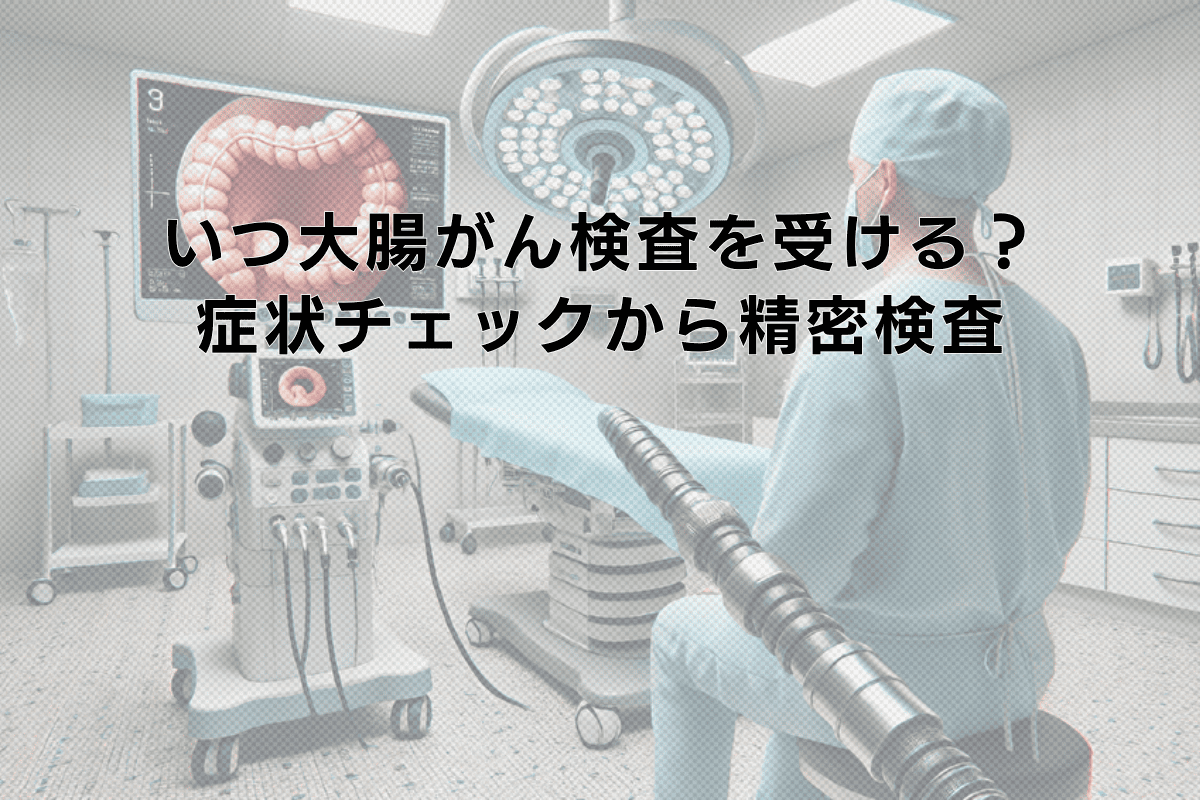
炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎・クローン病)
炎症性腸疾患(Inflammatory Bowel Disease, IBD)は、腸に原因不明の慢性的な炎症が起こる病気の総称で、潰瘍性大腸炎とクローン病があります。
このような病気では、腸の粘膜がただれたり、潰瘍ができたりすることで、軟便や下痢、血便、腹痛などの症状が続きます。
症状が良くなったり(寛解)、悪くなったり(再燃)を繰り返すのが特徴で、活動期には便秘と軟便が交互に現れることもあります。
若年層での発症が多く、長期にわたる治療が必要となる難病ですが、適切な治療により症状をコントロールし、通常の生活を送ることが可能です。
その他の消化器疾患
上記以外にも、さまざまな消化器疾患が便通異常の原因となることがあります。感染性腸炎はウイルスや細菌の感染によって起こり、急性の下痢や腹痛を起こしますが、回復期に便通が不安定になることがあります。
また、憩室炎(けいしつえん)といって、大腸の壁の一部が外側に袋状に飛び出した憩室に炎症が起こると、腹痛や便通異常の原因になります。
症状だけで原因を特定するのは困難であり、正確な診断のためには専門医による診察と適切な検査が欠かせません。
特に注意したい症状
| 症状 | 考えられる主な背景 |
|---|---|
| 血便・黒色便 | 消化管のどこかに出血がある可能性(大腸がん、炎症性腸疾患など) |
| 急な体重減少 | がんなどの消耗性疾患の可能性 |
| 激しい腹痛 | 腸閉塞、穿孔、重度の炎症などの緊急を要する状態の可能性 |
大腸検査の重要性と目的
軟便と便秘を繰り返す症状が続く場合、原因を正確に突き止めるために大腸検査は非常に重要な役割を果たします。ここでは、なぜ大腸検査を受けることが大事なのか、目的を解説します。
病気の早期発見
大腸検査の最も大きな目的は、大腸がんやポリープ、炎症性腸疾患といった重大な病気の早期発見です。
大腸がんは、早期の段階で発見し治療を開始すれば、高い確率で治癒が期待できますが、初期には自覚症状がほとんどないため、症状が出てからでは進行しているケースも少なくありません。
便通の異常という体からのサインを見逃さず、検査を受けることで、万が一病気が隠れていたとしても、有利な状態で治療を始めることができます。
症状の正確な原因特定
軟便と便秘を繰り返すという症状は、さまざまな原因によって生じます。
それが生活習慣による一時的なものなのか、過敏性腸症候群のような機能的な問題なのか、あるいは大腸がんのような器質的な病気なのかを、症状だけで正確に判断することはできません。
大腸検査、特に大腸内視鏡検査では、医師が直接大腸の内部を観察できるため、粘膜のわずかな色の変化や形の異常も見逃さず、症状の根本原因を特定することが可能です。
適切な治療方針の決定
原因がはっきりすれば、効果的な治療方針を立てることができます。過敏性腸症候群であれば、生活習慣の指導や薬物療法が中心となり、炎症性腸疾患であれば、炎症を抑えるための専門的な治療が必要です。
もし大腸ポリープが見つかれば、内視鏡検査の際にその場で切除することも可能で、将来のがん化を防ぐことにつながります。
原因がわからないまま対症療法を続けても、根本的な解決には至らず、検査によって正しい診断を得ることが、症状改善への最短ルートです。
主な大腸検査の種類と特徴
大腸の状態を調べるためにはいくつかの検査方法があり、それぞれに特徴や利点、限界があります。どの検査が適しているかは、個人の症状や年齢、既往歴などによって異なります。

便潜血検査
便潜血検査は、便の中に目には見えない微量の血液が混じっていないかを調べる簡易的な検査で、健康診断などで広く行われています。
大腸がんやポリープがあると、便が通過する際に表面から出血することがあるため、血液を検出することが目的で、自宅で便を採取して提出するだけなので、体への負担が全くないのが最大の利点です。
ただし、この検査はあくまでスクリーニング(ふるいわけ)検査で、陽性だからといって必ずしも大腸がんがあるわけではなく、痔など他の原因で陽性になることもあります。
逆に、進行した がんでも常に出血しているとは限らないため、陰性でも安心はできません。陽性となった場合は、精密検査として大腸内視鏡検査を必ず受けてください。
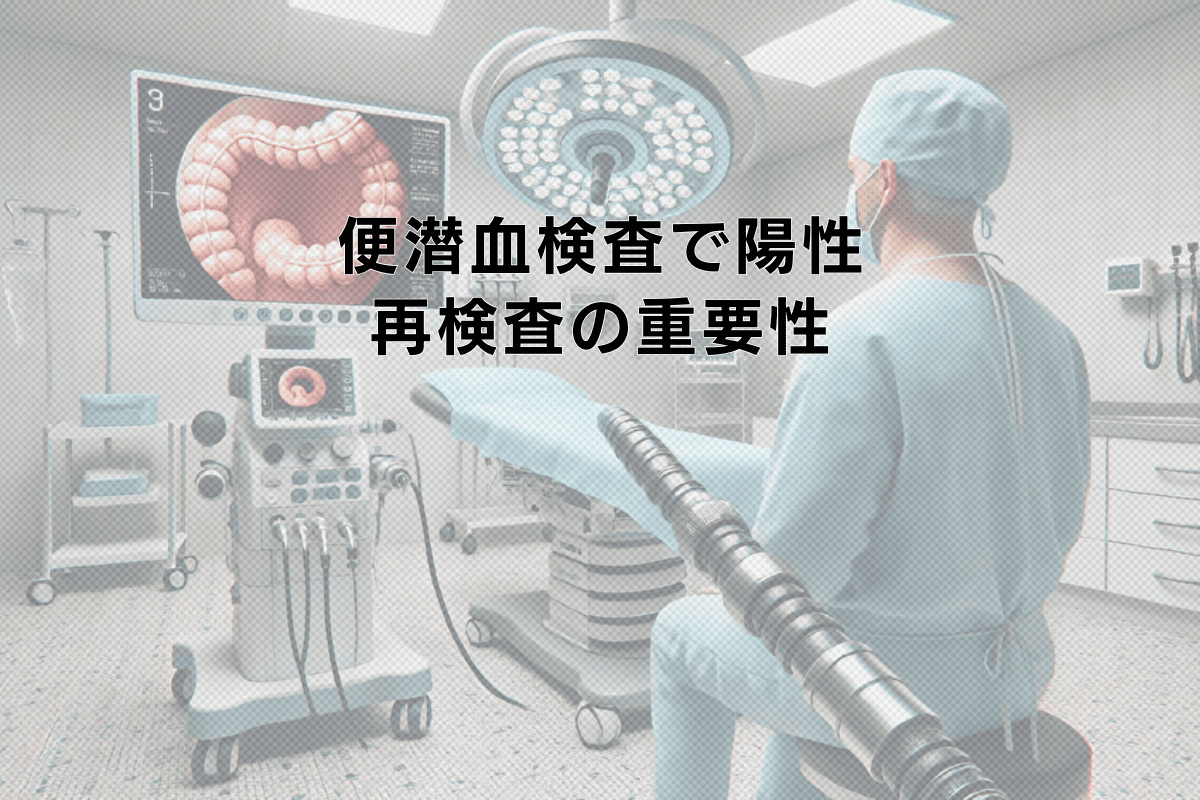
大腸内視鏡検査(大腸カメラ)
大腸内視鏡検査は、肛門から細いスコープ(内視鏡)を挿入し、直腸から盲腸までの大腸全体を直接観察する検査で、高解像度のカメラで粘膜の状態を詳細に見ることができるため、非常に精度が高いのが特徴です。
小さなポリープや早期のがん、炎症の程度などを正確に診断でき、また、検査中に疑わしい部分が見つかった場合、組織の一部を採取して(生検)、病理検査で確定診断を行うことができます。
さらに、前がん病変であるポリープを発見した際には、その場で切除することも可能で、検査前に下剤を飲んで腸をきれいにする必要がありますが、診断と治療を同時に行える、最も確実で有益な検査です。
大腸CT検査(バーチャル大腸内視鏡検査)
大腸CT検査は、CTスキャナを用いて大腸を撮影し、そのデータをコンピュータで処理して3D画像を作成することで、あたかも内視鏡で大腸の中を見ているかのような画像を得る検査です。
肛門から炭酸ガスを注入して大腸を膨らませる必要がありますが、内視鏡を挿入する苦痛はなく、検査時間も比較的短く、体の負担が少ないのが利点です。
ただし、平坦な病変や小さなポリープの発見は内視鏡検査に比べて不得意であり、色の変化もわかりません。
また、異常が見つかった場合、組織の採取やポリープの切除はできないため、結局、確定診断や治療のために大腸内視鏡検査が必要です。
主な大腸検査の比較
| 検査方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 便潜血検査 | 自宅ででき、体への負担がない | 精度が低く、早期がんを見逃す可能性あり |
| 大腸内視鏡検査 | 精度が非常に高い、組織採取やポリープ切除が可能 | 下剤の服用が必要、検査中に苦痛を感じることがある |
| 大腸CT検査 | 内視鏡挿入がなく苦痛が少ない | 小さな病変は見つけにくい、組織採取や治療は不可 |
注腸X線検査
注腸X線検査は、肛門からバリウムと空気を注入し、大腸を膨らませた状態でX線撮影を行う検査です。大腸全体の形や大きさ、粘膜の凹凸を調べることができ、大きなポリープやがん、腸の狭窄などを見つけるのに役立ちます。
内視鏡が挿入困難な場合などに行われることがありますが、近年では大腸内視鏡検査や大腸CT検査が主流となり、実施される機会は減ってきていて、粘膜の色の変化を捉えることはできず、小さな病変の発見は困難です。
大腸内視鏡検査(大腸カメラ)の流れ
軟便と便秘を繰り返す症状の原因を調べる上で、最も精度の高い大腸内視鏡検査について、流れを知っておくことは不安の軽減につながります。事前の準備から検査後の注意点まで、一連の流れを詳しく解説します。
検査前の準備(食事制限と下剤)
正確な検査のためには、大腸の中を空っぽにしておく必要があり、検査前日から準備が始まります。
通常、検査前日は、消化の良い食事を摂るように指示され、繊維質の多い野菜やキノコ類、種のある果物などは、腸の中に残りやすいため避ける必要があり、夕食は早めに済ませ、その後は絶食です。
検査当日の朝から、腸管洗浄剤(下剤)を約1〜2リットル、数時間かけて服用し、便が透明な液体になれば準備完了です。
検査前日に避けるべき食品の例
| 食品カテゴリ | 具体的な食品例 | 避ける理由 |
|---|---|---|
| 繊維の多い野菜・果物 | きのこ、海藻、ごぼう、キウイ、いちご | 消化されにくく、腸内に残りやすい |
| 種や粒のある食品 | ごま、ナッツ類、とうもろこし | 内視鏡の視野を妨げる可能性がある |
| 脂肪の多い食品 | 揚げ物、脂身の多い肉、バター | 消化に時間がかかり、腸に負担をかける |
- おかゆ
- 素うどん
- 豆腐
- 白身魚

検査当日の流れ
医療機関に到着したら、まず体調の確認や着替えを行い、検査台の上に横になり、血圧計や心電図モニターなどを装着し、全身の状態を管理しながら検査を進めます。
検査に対する不安や緊張が強い方のために、鎮静剤(眠くなる薬)を使用することも可能です。鎮静剤を使うと、うとうとと眠っているようなリラックスした状態で検査を受けることができます。
検査中の様子(鎮静剤の使用など)
医師が肛門から内視鏡をゆっくりと挿入していきます。大腸を観察しやすくするために、炭酸ガスなどを送気して腸を膨らませるため、お腹が張る感じがすることがあります。
医師はモニターに映し出される大腸の内部映像をすみずみまで確認しながら、ゆっくりと内視鏡を進めていき、一番奥の盲腸まで到達させ、その後、内視鏡を抜きながら、再度じっくりと観察し、この引き抜く過程での観察が特に重要です。
検査時間は通常15〜30分程度で、ポリープが見つかった場合は、その大きさや形に応じて切除することもあります。切除自体に痛みを感じることはほとんどありません。
検査後の注意点
検査が終了したら、リカバリールームでしばらく休み、鎮静剤を使用した場合は、薬の効果が切れて意識がはっきりするまで1時間ほど休憩が必要です。
鎮静剤を使用した当日は、ふらつきなどが残る可能性があるため、車やバイク、自転車の運転はできません。公共交通機関を利用するか、家族に送迎を頼みましょう。
食事は医師の指示に従い、通常、検査終了後1時間程度で水分から摂取可能となり、問題がなければ軽い食事から再開できます。
ポリープを切除した場合は、出血予防のため、数日間はアルコールや香辛料などの刺激物を避け、激しい運動も控えることが大切です。
検査を受ける医療機関の選び方
大腸検査、特に内視鏡検査を受けるにあたり、どの医療機関を選ぶかは非常に重要です。ここでは、医療機関選びの際に注目すべき点について解説します。
消化器内科や胃腸科の専門性
消化器内科や胃腸科を標榜している医療機関、特に日本消化器内視鏡学会の専門医や指導医が在籍している施設を選ぶとよいでしょう。専門医は、内視鏡の操作技術や病変の診断能力に関する豊富な知識と経験を持っています。
質の高い検査は、正確な診断に直結するので、ホームページなどで医師の経歴や資格を確認するのも一つの方法です。
検査実績の豊富さ
内視鏡検査は、医師の技術と経験が大きく影響する検査です。年間の検査件数が多い医療機関は、それだけ多くの症例を経験しており、技術力も高いと考えられます。
見逃しの少ない精密な観察や、安全で苦痛の少ない挿入技術、そして迅速かつ適切なポリープ切除など、検査の質は実績に比例する傾向があります。医療機関のウェブサイトに検査実績が公開されている場合があるので、参考にすると良いでしょう。
検査設備と環境
使用している内視鏡の性能も、検査の質を左右します。高解像度の画像が得られる最新の内視鏡システムや、病変を強調して表示する特殊な光(NBIなど)を搭載した機器を導入している施設では、より微細な病変の発見が期待できます。
また、検査後の休憩スペースが確保されているか、院内が清潔でプライバシーに配慮されているかなど、患者さんがリラックスして過ごせる環境が整っているかも大切なポイントです。
医療機関選びのチェックポイント
| 観点 | 確認事項 |
|---|---|
| 専門性 | 消化器内視鏡専門医が在籍しているか |
| 実績 | 年間どのくらいの検査を行っているか |
| 設備 | 高性能な内視鏡システムを導入しているか |
| 配慮 | 鎮静剤の使用、女性医師の在籍など、患者の希望に対応可能か |
事前の説明と相談のしやすさ
検査を受ける前には、誰しも多くの疑問や不安を抱えています。検査の必要性や流れ、起こりうる偶発症などについて、事前に時間をかけて丁寧に説明してくれる医療機関を選びましょう。
また、患者さんからの質問に親身に耳を傾け、わかりやすく答えてくれる医師やスタッフがいるかどうかも重要です。信頼関係を築ける医療機関であれば、安心して検査に臨むことができます。

軟便と便秘に関するよくある質問
ここでは、軟便と便秘を繰り返す症状や大腸検査に関して、多くの方が疑問に思う点についてお答えします。
- どのくらいの期間症状が続いたら受診すべきですか
-
決まった期間はありませんが、症状が2週間以上続く場合や、市販薬を試しても改善しない場合は、一度医療機関を受診することをお勧めします。
血便、急な体重減少、激しい腹痛、50歳以上で初めて症状が出た、といった場合は、期間にかかわらず早めに相談してください。単なる体調不良と自己判断せず、専門家の意見を聞くことが大切です。
- 大腸検査は痛いですか
-
痛みや苦痛の感じ方には個人差があり。腸の長さや曲がり具合、癒着の有無などによって、内視鏡の挿入時に痛みや張りを感じることがあります。
しかし、多くの医療機関では、患者さんの苦痛を和らげるために、鎮静剤を使用するなどの工夫をしています。鎮静剤を使用すれば、うとうとと眠っている間に検査が終わることがほとんどです。
- 食生活で気をつけることはありますか
-
日々の食生活を見直すことは、症状の改善につながる可能性があり、まずは、バランスの取れた食事を心がけることが基本です。
便秘傾向の時は、水溶性食物繊維(海藻、果物など)と不溶性食物繊維(野菜、きのこなど)をバランス良く摂り、十分な水分を補給しましょう。
軟便傾向の時は、腸を刺激する香辛料や脂っこいもの、冷たいもの、アルコールは控えめにし、消化の良い食事を心がけてください。ヨーグルトなどの発酵食品も、腸内環境を整える助けになります。
- 検査後にすぐ日常生活に戻れますか
-
検査のみで、鎮静剤を使用しなかった場合は、検査後すぐに日常生活に戻ることができます。鎮静剤を使用した場合は、安全のため当日の車や自転車の運転はできません。
休憩後に帰宅となりますが、その日は家でゆっくりと過ごし、ポリープを切除した場合は、数日間は食事や運動に制限が必要です。注意点については、検査を受けた医療機関の指示に必ず従ってください。
次に読むことをお勧めする記事
【過敏性腸症候群の症状と内視鏡検査の必要性】
軟便と便秘を繰り返す原因について読んで、『過敏性腸症候群って具体的にどんな病気?』と思った方もいらっしゃるのでは?ストレスと腸の関係や、内視鏡検査で確認すべきポイントなど、さらに詳しく解説しています。
【いつ大腸がん検査を受けるべきか|症状チェックから精密検査ガイド】
交互に続く便通異常を読んだ皆さんには、“受けるべきタイミング”の客観的目安を知ることも有益です。症状チェックと検査選択をまとめて確認できます。
以上
参考文献
Komori S, Akiyama J, Tatsuno N, Yamada E, Izumi A, Hamada M, Seto K, Nishiie Y, Suzuki K, Hisada Y, Otake Y. Prevalence and risk factors of constipation symptoms among patients undergoing colonoscopy: a single-center cross-sectional study. Digestion. 2024 Aug 9;105(4):299-309.
Matsumoto Y, Nadatani Y, Otani K, Higashimori A, Ominami M, Fukunaga S, Hosomi S, Kamata N, Kimura T, Fukumoto S, Tanaka F. Prevalence and risk factor for chronic diarrhea in participants of a Japanese medical checkup. JGH Open. 2022 Jan;6(1):69-75.
Okuda M, Kunitsugu I, Yoshitake N, Sasaki S. The relationship between functional constipation and dietary habits in school-age Japanese children. Journal of nutritional science and vitaminology. 2019 Feb 28;65(1):38-44.
Tokuda Y, Takahashi O, Ohde S, Shakudo M, Yanai H, Shimbo T, Fukuhara S, Hinohara S, Fukui T. Gastrointestinal symptoms in a Japanese population: a health diary study. World Journal of Gastroenterology: WJG. 2007 Jan 28;13(4):572.
Nakagawa H, Yamazaki H, Ozaka A, Yamamoto R, Sasaki S, Hamaguchi S, Fukuhara S. Association Between Constipation and Fecal Incontinence in Community-Dwelling Older Adults in Japan. Journal of the American Medical Directors Association.
Otani T, Iwasaki M, Inoue M, Sasazuki S, Tsugane S, Japan Public Health Center–Based Prospective Study Group. Bowel movement, state of stool, and subsequent risk for colorectal cancer: the Japan public health center–based prospective study. Annals of Epidemiology. 2006 Dec 1;16(12):888-94.
Kawamura Y, Yamamoto S, Funaki Y, Ohashi W, Yamamoto K, Ozeki T, Yamaguchi Y, Tamura Y, Izawa S, Hijikata Y, Ebi M. Internet survey on the actual situation of constipation in the Japanese population under 70 years old: focus on functional constipation and constipation-predominant irritable bowel syndrome. Journal of gastroenterology. 2020 Jan;55(1):27-38.
Oshima T, Miwa H. Epidemiology of functional gastrointestinal disorders in Japan and in the world. Journal of neurogastroenterology and motility. 2015 Jul 3;21(3):320.
Ohkusa T, Koido S, Nishikawa Y, Sato N. Gut microbiota and chronic constipation: a review and update. Frontiers in medicine. 2019 Feb 12;6:19.
Kurokawa S, Kishimoto T, Mizuno S, Masaoka T, Naganuma M, Liang KC, Kitazawa M, Nakashima M, Shindo C, Suda W, Hattori M. The effect of fecal microbiota transplantation on psychiatric symptoms among patients with irritable bowel syndrome, functional diarrhea and functional constipation: an open-label observational study. Journal of affective disorders. 2018 Aug 1;235:506-12.