お腹の調子が悪く、下痢が続くとつらいものです。
腸閉塞という言葉を聞くと、便が全く出なくなる状態を想像するかもしれませんが、実際には腸閉塞が原因で下痢が続くことがあります。
これは腸が完全に詰まっていない不完全な閉塞の状態で起こりやすく、腹痛や嘔吐などを伴う場合は注意が必要です。
この記事では、なぜ腸閉塞で下痢が起こるのか、原因や特徴、医療機関で行う検査や治療法について詳しく解説します。
腸閉塞で下痢が続くのはなぜか
腸閉塞という病名は腸が完全に詰まるイメージを抱かせますが、実際には様々な病態があります。下痢という症状が伴う場合、背景には特有の状態が隠れていることが多いです。
腸閉塞の基本的な理解
腸閉塞とは、何らかの原因で小腸や大腸といった腸管の内容物(食べ物や消化液、ガスなど)の流れが滞ってしまう状態です。
腸管が物理的に塞がれる機械的閉塞を伴う病態と、腸の動きが悪くなる機能的な病態に大別され、一般的に腸閉塞とは前者の機械的閉塞状態を指し、後者はイレウスと呼ばれます。
食べ物や便が先に進めなくなるため、腹痛、腹部の膨満感、嘔吐といった症状が現れます。通常、便やガスが出なくなるのが典型的な症状と考えられていますが、必ずしもそうとは限りません。
腸閉塞と下痢の意外な関係
腸が塞がれているのになぜ下痢が起こるのか、疑問に思うかもしれません。腸管が完全に塞がっているのではなく、部分的に狭くなっている不完全な閉塞の状態で起こる現象です。
狭くなった部分を、腸内に溜まった消化液や水分が何とか通り抜けようとして、固形の便は通過できなくても大量の水分が一度に肛門から排出され、水様性の下痢として現れます。
この状態は、腸が内容物を排出しようと過剰に動くことで、腹痛を伴うことが多いです。
不完全閉塞と下痢
不完全閉塞では腸管の狭窄部より口側の腸管が拡張し、水分や消化液が大量に溜まります。腸管の内圧が高まると腸壁からさらに水分が分泌され、溜まる液体量は増加します。
溜まった液体が狭窄部を通過して下流に流れ込む際に、下痢を引き起こしますが、下痢は腸が完全に機能を失ったわけではなく、何とか内容物を先に送ろうと反応している結果です。
しかし、この状態が続くと脱水や電解質異常につながるため、決して安心できるものではありません。
完全閉塞と不完全閉塞の違い
| 項目 | 不完全閉塞 | 完全閉塞 |
|---|---|---|
| 便やガスの状態 | 下痢や少量の排便・排ガスがある | 完全に停止する |
| 主な症状 | 波のある腹痛、嘔吐、下痢 | 持続的な激しい腹痛、嘔吐 |
| 腹部の膨満感 | 軽度から中等度 | 高度に張ることが多い |
下痢以外の腸閉塞のサイン
下痢が続いている場合でも、それが腸閉塞から来るものかを見極めるためには、他の症状にも注意を払うことが重要です。腸閉塞に特徴的なサインを知ることで、早期に医療機関を受診するきっかけになります。
- 周期的に繰り返す強い腹痛
- お腹が張る感覚(腹部膨満感)
- 吐き気や嘔吐(特に緑色や茶色の吐物)
- 食欲の著しい低下
症状が下痢と同時に現れた場合は単なる胃腸炎ではなく腸閉塞の可能性を考え、速やかに専門医の診察を受けることが大切です。
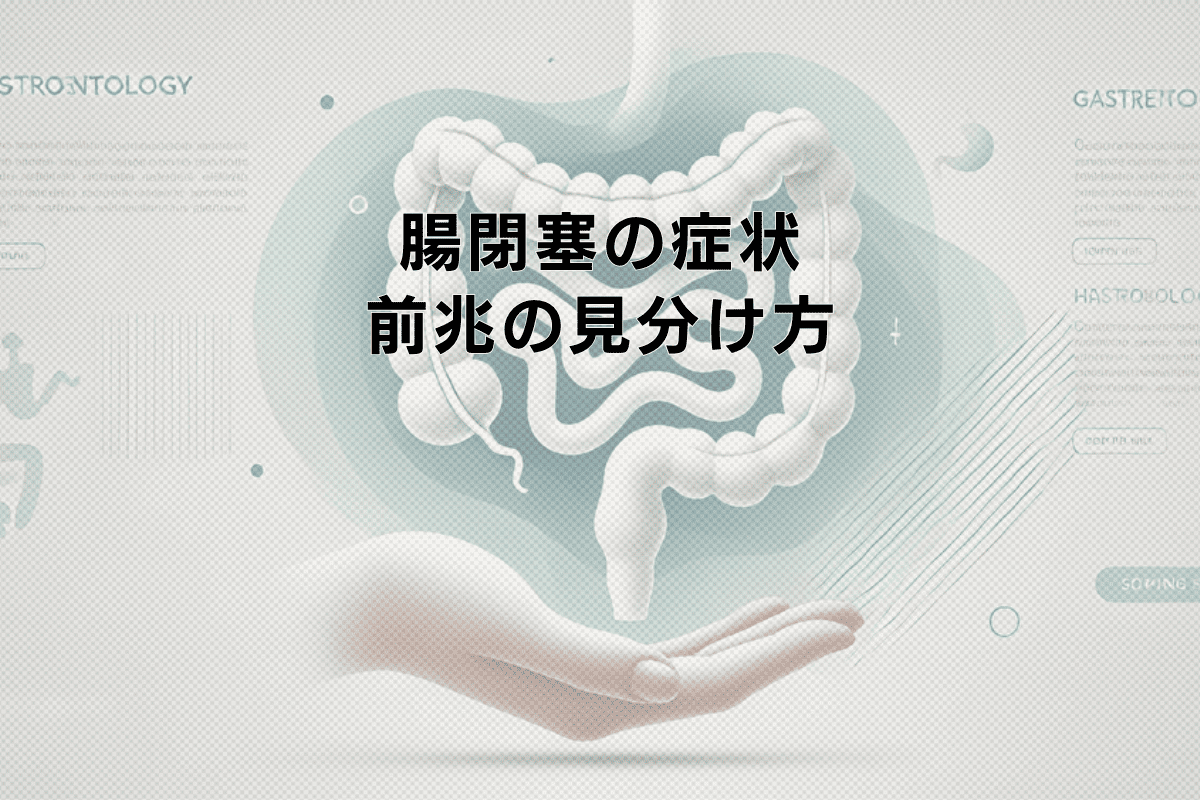
腸閉塞が疑われる下痢の特徴
下痢は非常にありふれた症状ですが、中には危険な病気が隠れているサインの場合もあり、腸閉塞を原因とする下痢にはいくつかの特徴的な兆候があります。
腹痛を伴う下痢
腸閉塞による下痢は多くの場合、特徴的な腹痛を伴います。
痛みはお腹が締め付けられるような、あるいは差し込むような強い痛みで、数分から数十分の間隔で良くなったり悪くなったりを繰り返す疝痛発作(せんつうほっさ)であることが多いです。
これは、腸が狭くなった部分を内容物が通過しようとする際に、腸が強く収縮するために起こり、ただの下痢とは違う周期的な激しい腹痛がある場合は、腸閉塞を強く疑うべきサインです。
嘔吐や吐き気を伴う下痢
腸の内容物の流れが滞ると、口側に逆流し強い吐き気や嘔吐を起こします。
最初は胃の内容物を嘔吐しますが、症状が進行すると胆汁を含んだ緑色がかった液体や、さらには便のような臭いがする茶褐色の液体(糞便様嘔吐)を吐くこともあります。
下痢に加えて嘔吐が見られる場合、腸閉塞がかなり進行している可能性があり、緊急の対応が必要です。
症状から見る危険度の判断
| 症状 | 特徴 | 考えられる状態 |
|---|---|---|
| 下痢 | 水様性で大量、腹痛を伴う | 不完全な腸閉塞の可能性 |
| 腹痛 | 周期的で激しい痛み(疝痛) | 腸管が無理に収縮している |
| 嘔吐 | 便のような臭いがする | 閉塞が長く続いている危険なサイン |
便の状態と量の変化
腸閉塞による下痢は、便の状態にも特徴があります。閉塞部位より肛門側に残っていた便がまず排出され、その後、閉塞部位より口側に溜まった水分が排出されるため、最初は普通の便が出てから水様性の下痢に変わることがあります。
また、下痢便の量は非常に多くなることもあれば、逆にチョロチョロと少量しか出ないこともあります。便の色や臭い、量など、普段との違いに気づくことが大切です。
注意すべきその他の症状
腹痛や嘔吐以外にも、注意すべき症状があります。腸に血流障害が起きる絞扼性(こうやくせい)腸閉塞の場合、冷や汗、頻脈、血圧低下といったショック症状が現れることがあります。命に関わる非常に危険な状態で、一刻も早い治療が必要です。
また、発熱を伴う場合は、腸管の炎症や穿孔(穴が開くこと)の可能性も考えられます。下痢とともに全身症状が見られる場合は、ためらわずに救急要請を検討してください。
腸閉塞の原因となる病気
腸閉塞は最終的な診断名ではなく、何らかの根本的な原因があって起きる状態です。ここでは、腸閉塞を起こす代表的な病気について解説します。
手術後の癒着
成人の機械的腸閉塞で最も多い原因は、過去に受けた腹部の手術による腸管の癒着です。開腹手術を行うとお腹の中の臓器や腹膜が傷つき、修復過程で本来は離れているはずの腸同士や、腸と腹壁がくっついてしまうことがあります。
癒着した部分が折れ曲がったり締め付けられることで、腸の内容物の通過が悪くなり腸閉塞を起こします。胃や大腸、婦人科系の手術など、どんな腹部手術でも癒着が起きる可能性があります。
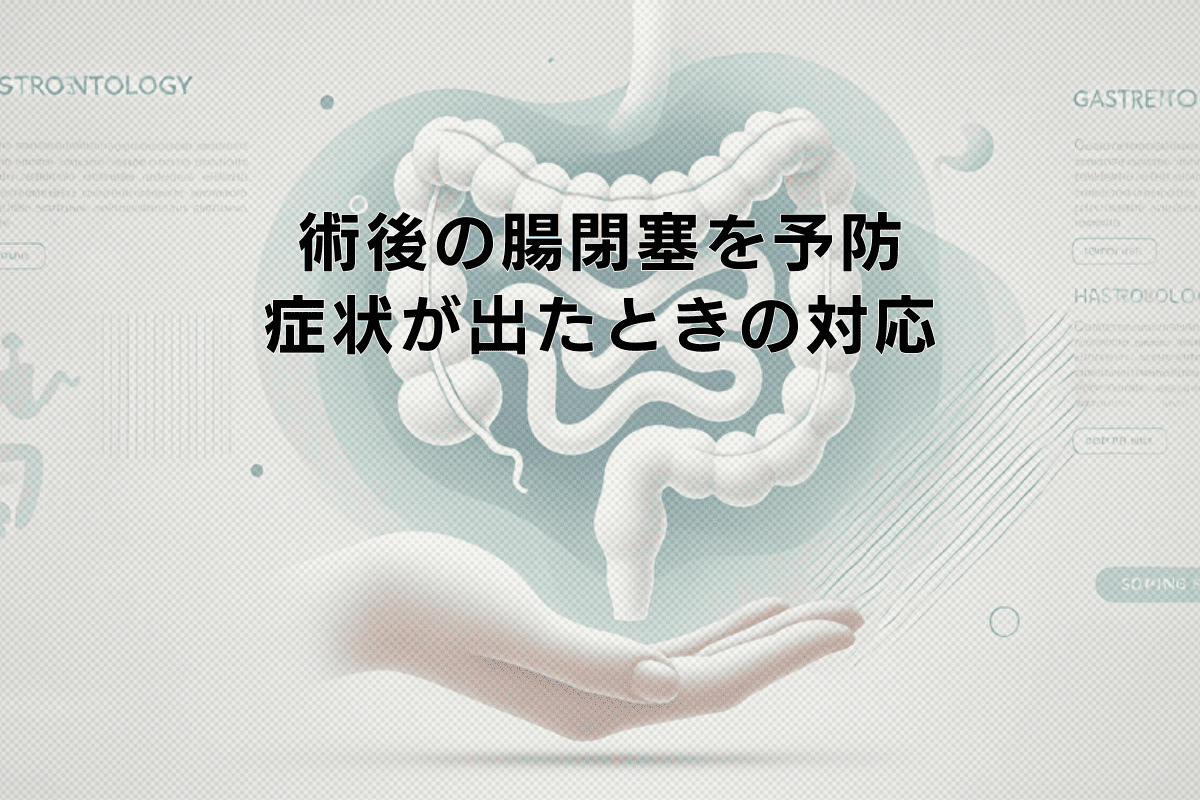
腸閉塞の主な原因
| 原因 | 概要 | 関連する症状 |
|---|---|---|
| 腹部手術後の癒着 | 手術の傷が治る過程で腸がくっつく | 手術歴のある人の反復する腹痛 |
| 大腸がんなどの腫瘍 | がんが大きくなり腸管を塞ぐ | 便が細くなる、血便、体重減少 |
| クローン病など | 腸の炎症で内壁が厚くなり狭くなる | 慢性的下痢、腹痛、発熱 |
大腸がんなどの腫瘍
特に高齢者において注意が必要なのが、大腸がんや小腸の腫瘍です。がんが腸管の内側に向かって大きくなることで、徐々に腸の内腔が狭くなり、最終的に腸閉塞を起こします。
初期には症状が出にくいですが、進行すると便が細くなる、便に血が混じる(血便)、腹痛、体重減少といった症状が現れます。
こういう症状とともに腸閉塞の兆候が見られる場合は、腫瘍の可能性を念頭に置いた精密検査が必要です。
クローン病などの炎症性腸疾患
クローン病や腸結核などの炎症性腸疾患も腸閉塞の原因で、腸管に慢性的な炎症を起こし、腸の壁が厚く硬くなり内腔が狭くなります(狭窄)。特にクローン病は小腸に好発するため、小腸閉塞の原因として重要です。
長期にわたる下痢や腹痛、発熱、体重減少などの症状がある場合は、疾患の可能性も考えられます。
その他の原因(ヘルニア、異物など)
その他にも、様々な原因で腸閉塞は起こります。足の付け根(鼠径部)や腹壁の弱い部分から腸が飛び出す腹壁ヘルニア(脱腸)では、飛び出した腸が締め付けられて閉塞を起こすことがあります(ヘルニア嵌頓)。
また、高齢者では、胆石が胆嚢から腸に落ちて詰まる胆石イレウスや、大量の硬い便が詰まる糞便性イレウスも原因となり、まれに、誤って飲み込んだ異物が原因となることもあります。
医療機関で行う検査
腸閉塞が疑われる症状で医療機関を受診した場合、診断を確定し、原因や重症度を評価するためにいくつかの検査を行います。
問診と身体診察
検査の第一歩は詳しい問診から始まりまり、医師は、症状(いつから、どんな痛みか、下痢や嘔吐の状況)、過去の手術歴、持病、服用中の薬などについて詳しく質問します。症状の経過を時系列で正確に伝えることが大事です。
- 症状が始まった正確な日時
- 腹痛の性質(周期的か、持続的か)
- 嘔吐物の色や臭い
- 最後に便やガスが出たのはいつか
その後身体診察に移り、聴診器でお腹の音(腸の動く音)を確認したり、お腹を触って圧痛の場所や張り具合、しこりの有無などを調べます。
血液検査でわかること
血液検査は全身の状態を評価するために行い、脱水の程度(ヘマトクリット値の上昇)、炎症の有無(白血球数やCRPの上昇)、電解質のバランスの乱れなどを確認します。
検査結果は、点滴治療の内容を決定する上でも重要な情報です。また、腸管の血流が悪くなる絞扼性腸閉塞を疑う場合には、乳酸値やCPKといった項目が上昇することがあり、緊急手術の判断材料の一つになります。
血液検査で確認する主要項目
| 検査項目 | 目的 | 異常値が示すこと |
|---|---|---|
| 白血球数、CRP | 炎症の程度の評価 | 腸管の炎症、穿孔の可能性 |
| 電解質 (Na, K, Cl) | 体液バランスの評価 | 嘔吐や下痢による脱水、腎機能低下 |
| 乳酸値、CPK | 腸管虚血(血流障害)の評価 | 絞扼性腸閉塞の可能性 |
画像検査(レントゲン、CT)
画像検査は腸閉塞の診断において中心的な役割を果たし、まず行われるのが腹部のレントゲン(X線)検査です。
立ったり座ったりした状態で撮影すると、閉塞によって溜まった腸内のガスと液体の境界が水平な線として写る鏡面像(ニボー)が確認できることがあり、腸閉塞の存在を推定できます。
より詳しい情報を得るためには、CT検査が非常に有用です。
CTでは、腸の拡張の程度、閉塞している場所、閉塞の原因(癒着、腫瘍など)、さらには腸管の血流状態や腹水の有無まで詳細に評価でき、治療方針の決定に不可欠な情報を提供します。
画像検査の種類と特徴
| 検査方法 | わかること | 特徴 |
|---|---|---|
| 腹部レントゲン検査 | 腸管内のガスや液体の貯留 | 簡便で迅速に行える初期検査 |
| 腹部CT検査 | 閉塞部位、原因、重症度の詳細な評価 | 診断精度が非常に高く、治療方針決定に有用 |
| 腹部超音波検査 | 拡張した腸管や腹水の有無 | 放射線被ばくがなく、繰り返し行える |

内視鏡検査の役割
大腸がんなどの腫瘍が原因で大腸が閉塞している場合には、大腸内視鏡検査(大腸カメラ)を行うことがあります。内視鏡で直接閉塞の原因となっている病変を観察し、組織の一部を採取して病理診断を行うことが可能です。
また、治療として、狭窄部にステントという金属の筒を留置して、一時的に腸管を広げる処置を行うこともあります。ただし、腸の張りが非常に強い場合や小腸の閉塞では、内視鏡検査が困難なこともあります。

腸閉塞による下痢の治療法
腸閉塞の治療は、原因、重症度、そして全身状態によって大きく異なります。下痢を伴う不完全な閉塞の場合、まずは手術をせずに内科的な治療(保存的治療)で改善を目指すことが一般的です。
保存的治療の基本
保存的治療の目的は、腸を休ませて自然な回復を促すことです。腸閉塞の状態では口から食事や水分を摂ると、腸内に溜まって症状を悪化させるため、治療の基本は絶食と点滴になります。
こうすることで腸への負担をなくし脱水状態を補正しながら、腸管のむくみや拡張が改善するのを待ちます。多くの癒着性の腸閉塞は、保存的治療で改善が期待できます。
保存的治療の主な内容
| 治療法 | 目的 | 具体的な内容 |
|---|---|---|
| 絶食・絶飲 | 腸管を安静に保つ | 口からの食事・水分摂取を中止する |
| 点滴(輸液) | 脱水の補正、栄養補給 | 水分、電解質、栄養素を血管から補う |
| イレウス管による減圧 | 腸内の圧力を下げる | 鼻から管を入れ、溜まった消化液を排出する |
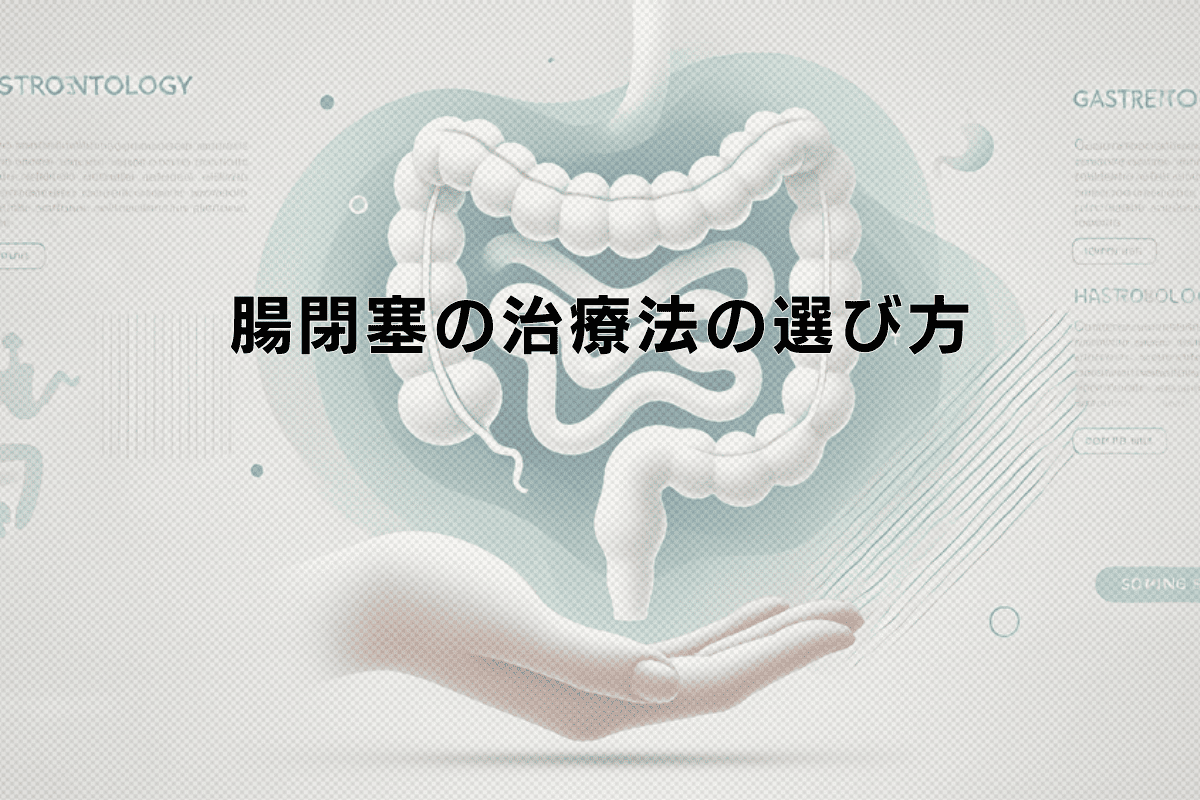
入院による絶食と点滴
腸閉塞の治療は、原則として入院が必要です。入院後直ちに絶食・絶飲とし、点滴を開始し、点滴により生命維持に必要な水分、ナトリウムやカリウムといった電解質、栄養を補給します。
嘔吐や下痢で失われた水分と電解質を補正することで、全身状態の安定化を図ります。軽症の場合は、数日間の点滴と絶食だけで腸管のむくみが取れ、ガスの排出や排便が見られて症状が改善することもあります。
腸管の減圧(イレウス管)
お腹の張りが強い場合や嘔吐が続く場合には、腸管の圧力を下げる(減圧する)処置を行います。イレウス管と呼ばれる長いチューブを鼻から挿入し、胃を経て閉塞部位の近くまで到達させ、溜まっている消化液やガスを体外に排出する治療法です。
腸内の圧力が下がることで腹痛やお腹の張りが楽になり、腸管の血流が改善し、むくみが取れやすくなります。患者さんにとってはやや苦痛を伴う処置ですが、腸閉塞の治療において非常に重要です。
原因疾患に対する治療
腸閉塞の症状が改善した後や保存的治療と並行して、原因となっている病気に対する治療を行います。
大腸がんが原因であればがんに対する手術や化学療法を計画し、クローン病などの炎症性腸疾患であれば、炎症を抑えるための薬物治療が必要です。
手術が必要になる場合
多くの腸閉塞は保存的治療で改善しますが、中には手術が必要になるケースもあります。手術のタイミングを逃すと命に関わることもあるため、判断は慎重に行われます。
手術を判断する基準
保存的治療を数日間行っても症状が改善しなかったり悪化する場合は、手術を検討します。腹痛や腹部膨満感が続く、イレウス管からの排液が減らない、画像検査で改善が見られない、といった状況です。
また、最初から腫瘍やヘルニア嵌頓(かんとん)など、保存的治療では治らない原因が明らかな場合も、手術の適応となります。
絞扼性腸閉塞の危険性
絞扼性腸閉塞は、腸が癒着した部分でねじれたり締め付けられたりして、腸自身への血流が途絶えてしまう状態です。
血流がなくなると腸は短時間で壊死(組織が死ぬこと)してしまい、腸に穴が開いて腹膜炎を起こすなど、命に関わる事態に陥ります。この状態は一刻を争う緊急事態であり、診断がつき次第緊急手術が必要です。
- 持続的で極めて激しい腹痛
- お腹を押すと強く痛む(限局性圧痛)
- 発熱、頻脈、血圧低下
手術が緊急で必要になるサイン
| サイン | 内容 | 緊急性 |
|---|---|---|
| 持続する激痛 | 痛みが周期的でなく、絶え間なく続く | 非常に高い(絞扼の可能性) |
| 腹膜刺激症状 | お腹を押した時より離した時に響く痛み | 非常に高い(腹膜炎の可能性) |
| ショック症状 | 冷や汗、血圧低下、意識レベルの低下 | 極めて高い(敗血症の可能性) |
行われる手術の種類
癒着が原因の場合は癒着している部分を剥がす癒着剥離術が行われ、腫瘍が原因であればその部分の腸管を切除し、残った腸をつなぎ合わせる手術を実施します。
絞扼によって腸がすでに壊死してしまっているときは、その部分を切除する必要があります。また、広範囲に腸を切除した場合は、一時的に人工肛門(ストーマ)を造設することもあります。
日常生活で注意すべきこと
一度腸閉塞を経験すると、再発への不安を抱える方も少なくありません。特に癒着による腸閉塞は再発しやすいため、日常生活での注意が重要です。
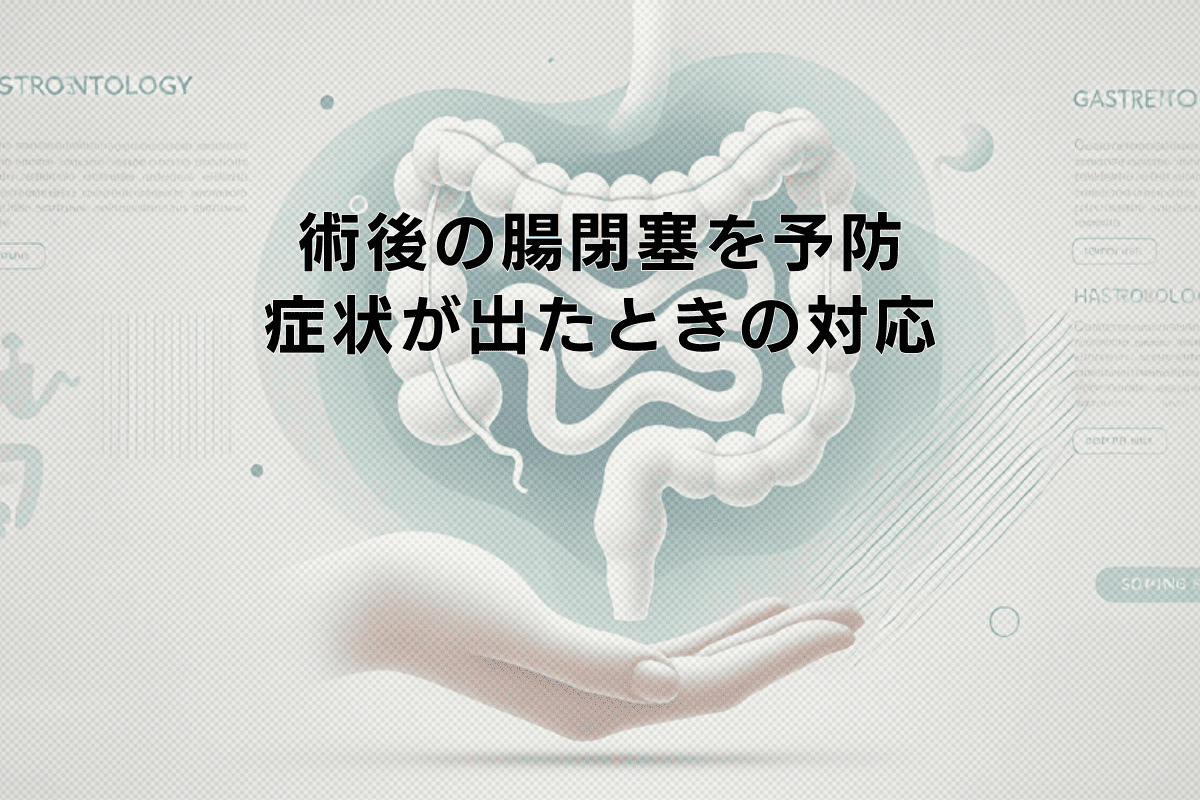
食事の工夫と水分補給
腸閉塞後の食事で最も大切なのは、消化の良いものをよく噛んでゆっくり食べることです。一度にたくさん食べると腸に負担がかかるため、食事は1日3回にこだわらず少量ずつ数回に分けて摂るのが良いでしょう。
食物繊維の多い野菜(ごぼう、たけのこなど)やきのこ類、こんにゃく、海藻類などは、消化されにくく腸に詰まりやすいので、摂りすぎに注意が必要です。また、脱水を防ぐために、こまめな水分補給も忘れないでください。

退院後の食事のポイント
| 項目 | 推奨されること | 避けるべきこと |
|---|---|---|
| 食べ方 | よく噛む、ゆっくり食べる、腹八分目 | 早食い、ドカ食い |
| 食品の選択 | おかゆ、うどん、豆腐、白身魚、鶏ささみ | 食物繊維の多い野菜、きのこ、海藻 |
| 水分補給 | 1日に1.5リットル程度を目安にこまめに摂る | 一度に大量の冷たい水を飲む |
体調変化の記録
ご自身の体調を日々記録することは、再発の早期発見に役立ちます。お通じの状態(回数、形状)、腹痛の有無や程度、お腹の張り具合、食事内容などを簡単にメモしておくと良いでしょう。
もし、腸閉塞の初期症状と思われる腹痛やお腹の張りが現れたら、記録を持って医療機関を受診すれば、医師が状態を把握しやすく迅速な診断と治療につながります。
医療機関へ相談するタイミング
軽いお腹の張りや少し便が出にくい程度であれば、食事を控えめにして様子を見ることもできますが、次のような症状が現れた場合は再発の可能性を考え、早めに医療機関に相談してください。
- 我慢できないほどの強い腹痛が続く、または繰り返す
- 吐き気や嘔吐がある
- 便やガスがまったく出なくなる
以前に腸閉塞の治療を受けたことがある方は症状を自己判断せず、かかりつけの医師に相談することが大切です。
よくある質問
最後に、腸閉塞やそれに伴う下痢に関して、患者さんからよく寄せられる質問と回答をまとめました。
- 腸閉塞は自然に治りますか?
-
癒着などが原因の軽度の不完全閉塞であれば、食事を控えめにして腸を休ませることで、自然に症状が改善することもありますが、自己判断で様子を見続けるのは危険です。
腹痛や嘔吐を伴う場合は腸管の状態が悪化している可能性があり、医療機関での診断と治療が必要で、特に、絞扼性の腸閉塞は自然に治ることはなく、放置すると命に関わります。
- 下痢止めを飲んでもよいですか?
-
癒着などが原因の軽度の不完全閉塞であれば、食事を控えめにして腸を休ませることで、自然に症状が改善することもあります。
ただし、腹痛や嘔吐を伴う場合は、腸管の状態が悪化している可能性があり、医療機関での適切な診断と治療が必要です。特に、絞扼性の腸閉塞は自然に治ることはなく、放置すると命に関わります。
- 再発することはありますか?
-
腸閉塞は再発しやすい病気の一つで、特に手術後の癒着が原因の場合は、体質的に癒着を起こしやすかったり、手術で剥がした部分が再び癒着することがあります。
再発を完全に防ぐことは難しいですが、食事の工夫や体調管理を日頃から行うことで、再発のリスクを低減することは可能です。
次に読むことをお勧めする記事
【腸閉塞の症状から診断まで – 状態に応じた適切な検査】
腸閉塞が疑われるとき、実際にどの検査を受け、何が分かるのかを押さえると安心です。受診前に知っておくと当日の流れが掴みやすくなります。
【大腸がん初期症状の見逃しを防ぐ】
腸閉塞の背景には腫瘍が隠れる場合もあります。大腸がんの初期サインを合わせて知ることで、原因の全体像をより包括的に捉えられます。
参考文献
Iida H, Inamori M, Sekino Y, Sakamoto Y, Yamato S, Nakajima A. A review of the reported cases of chronic intestinal pseudo-obstruction in Japan and an investigation of proposed new diagnostic criteria. Clinical journal of gastroenterology. 2011 Jun;4:141-6.
Matsumoto Y, Nadatani Y, Otani K, Higashimori A, Ominami M, Fukunaga S, Hosomi S, Kamata N, Kimura T, Fukumoto S, Tanaka F. Prevalence and risk factor for chronic diarrhea in participants of a Japanese medical checkup. JGH Open. 2022 Jan;6(1):69-75.
Kinoshita Y, Ariyoshi R, Fujigaki S, Tanaka K, Morikawa T, Sanuki T. Endoscopic diagnosis of chronic diarrhea. DEN open. 2022 Apr;2(1):e53.
Ihara E, Manabe N, Ohkubo H, Ogasawara N, Ogino H, Kakimoto K, Kanazawa M, Kawahara H, Kusano C, Kuribayashi S, Sawada A. Evidence-based clinical guidelines for chronic diarrhea 2023. Digestion. 2024 Dec 9;105(6):480-97.
Masaki T, Sugihara K, Nakajima A, Muto T. Nationwide survey on adult type chronic intestinal pseudo-obstruction in surgical institutions in Japan. Surgery today. 2012 Mar;42:264-71.
Juckett G, Trivedi R. Evaluation of chronic diarrhea. American family physician. 2011 Nov 15;84(10):1119-26.
Schiller LR. Chronic diarrhea. GI/Liver Secrets Plus E-Book: GI/Liver Secrets Plus E-Book. 2014 Nov 17:414.
Schiller LR, Pardi DS, Sellin JH. Chronic diarrhea: diagnosis and management. Clinical Gastroenterology and Hepatology. 2017 Feb 1;15(2):182-93.
Fine KD, Seidel RH, Do K. The prevalence, anatomic distribution, and diagnosis of colonic causes of chronic diarrhea. Gastrointestinal endoscopy. 2000 Mar 1;51(3):318-26.
Faulk DL, Anuras S, Christensen J. Chronic intestinal pseudoobstruction. Gastroenterology. 1978 May 1;74(5):922-31.










