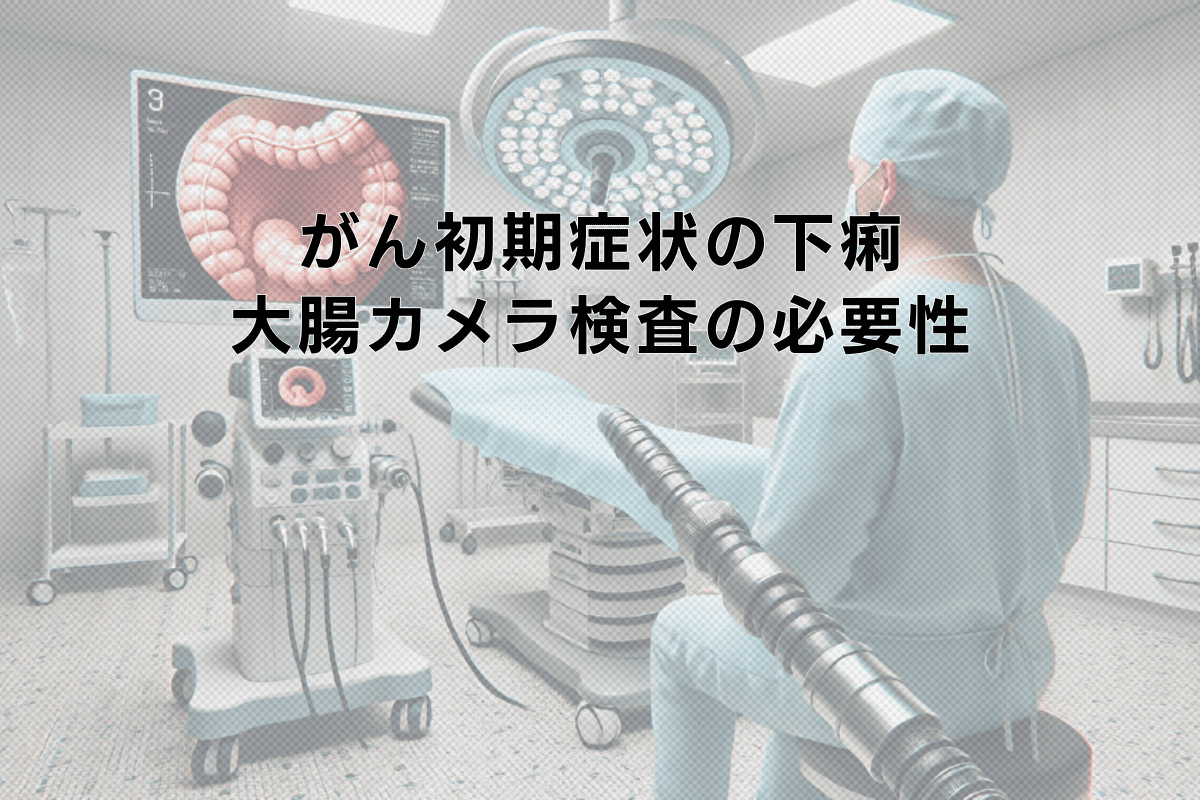がんの初期症状としてよく知られるのは体重減少や倦怠感などですが、下痢が続く状態にも目を向けることが大切です。
特に大腸がんのような消化器系のがんでは、お腹の不調が早期のサインになる場合があり、違和感が続く場合は見逃さず、早めに医療機関を受診して適切な検査を検討してください。
本記事では、下痢とがんの関連性、大腸カメラ検査の重要性、日常生活で注意するポイントなどを解説します。
下痢とがんの関係に注目する理由
下痢が一時的であれば感染症や食事の影響が原因になることが多いですが、長期間続く場合は消化器系の重大な病気を疑う余地があります。
軽視できない症状を正しく見極めるために、下痢が続く状態とがんにどのような関係があるかを知ることは重要です。
下痢が続く状態と初期がんの可能性
下痢が続く状態と聞くと、食生活の乱れやストレス、過敏性腸症候群などを連想するかもしれませんが、がんの初期症状として下痢が表れる場合もあり、体内で進行している異変を映し出すサインになっている可能性があります。
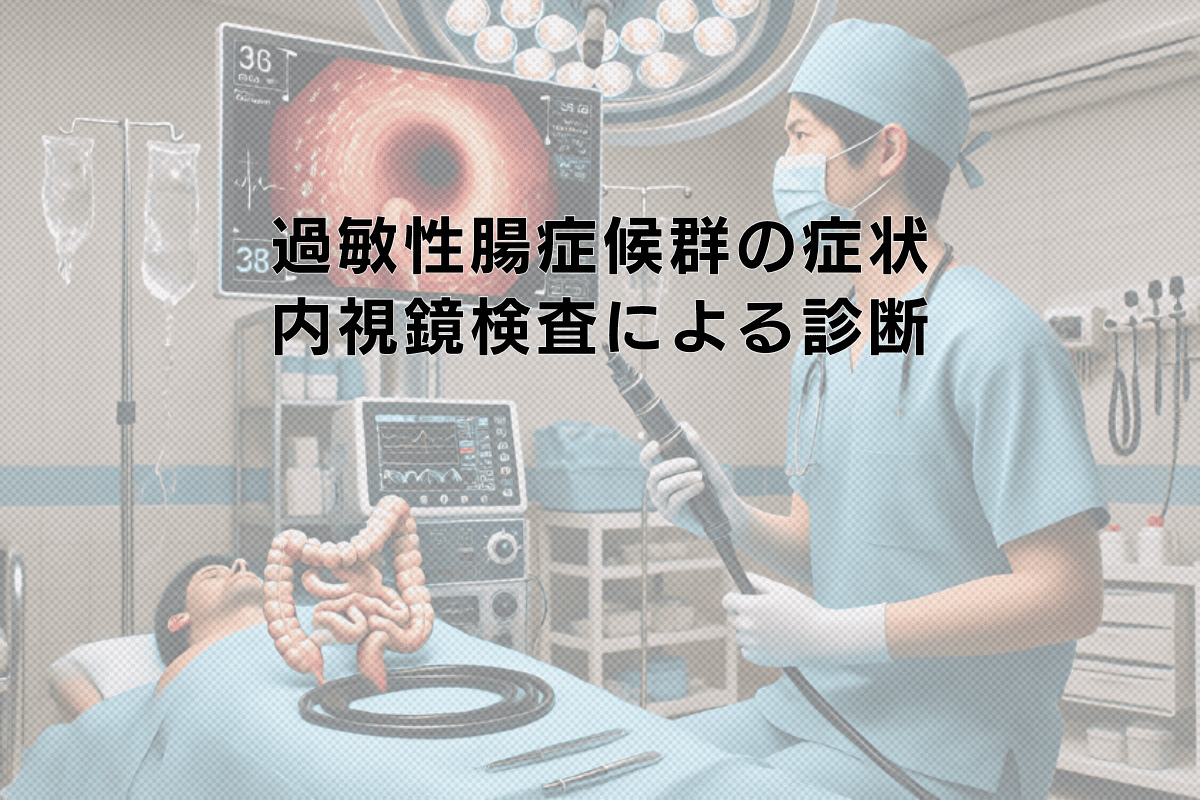
大腸がんでは、腸内の腫瘍によって腸管が刺激され、便が十分に固形化せず軟便や下痢になりやすいことがあり、がん細胞が成長すると便通に変化が生じ、血便や下痢が続く状態につながることもあるのです。

医療機関では、下痢の症状が長期にわたる患者に対して「最近食事を急に変えたか」「体重減少はあるか」「他に痛みや出血はないか」といった問診を行い、がんの可能性を見極めようとします。
| 種類 | 特徴 | 代表的な原因 |
|---|---|---|
| 急性の下痢 | 数日以内に治まる | 細菌性食中毒、ウイルス感染 |
| 慢性的な下痢 | 2週間以上続く | 消化器系疾患、ホルモン異常、潰瘍性大腸炎 |
| 間欠的な下痢 | 良くなったり悪くなったりを繰り返す | 過敏性腸症候群、炎症性腸疾患、ストレス |
下痢が続く時は、急性なのか慢性なのかを見極めることが鍵です。数日で自然に治る下痢であれば食事の見直しや水分補給で改善することが多いですが、慢性的な下痢はがんなど重大な原因が隠れている可能性を否定できません。
腸内環境の変化が起こすリスク
慢性的に下痢が続くと腸内環境が乱れます。下痢と同時に便秘を繰り返す過敏性腸症候群のような疾患がある場合でも、腸内バランスが崩れます。
腸内細菌叢が正常に働かないと、体内で作られる免疫細胞のバランスにも影響を及ぼし、全身的な体調不良につながることがあるので注意が必要です。
腸内環境が悪化すると、体力が落ちやすくなるだけでなく、腫瘍の発生や成長を促す要因が増えるという説も考えられていて、下痢が続くような消化器の不調は、がんなど悪性疾患のリスクを高めかねません。
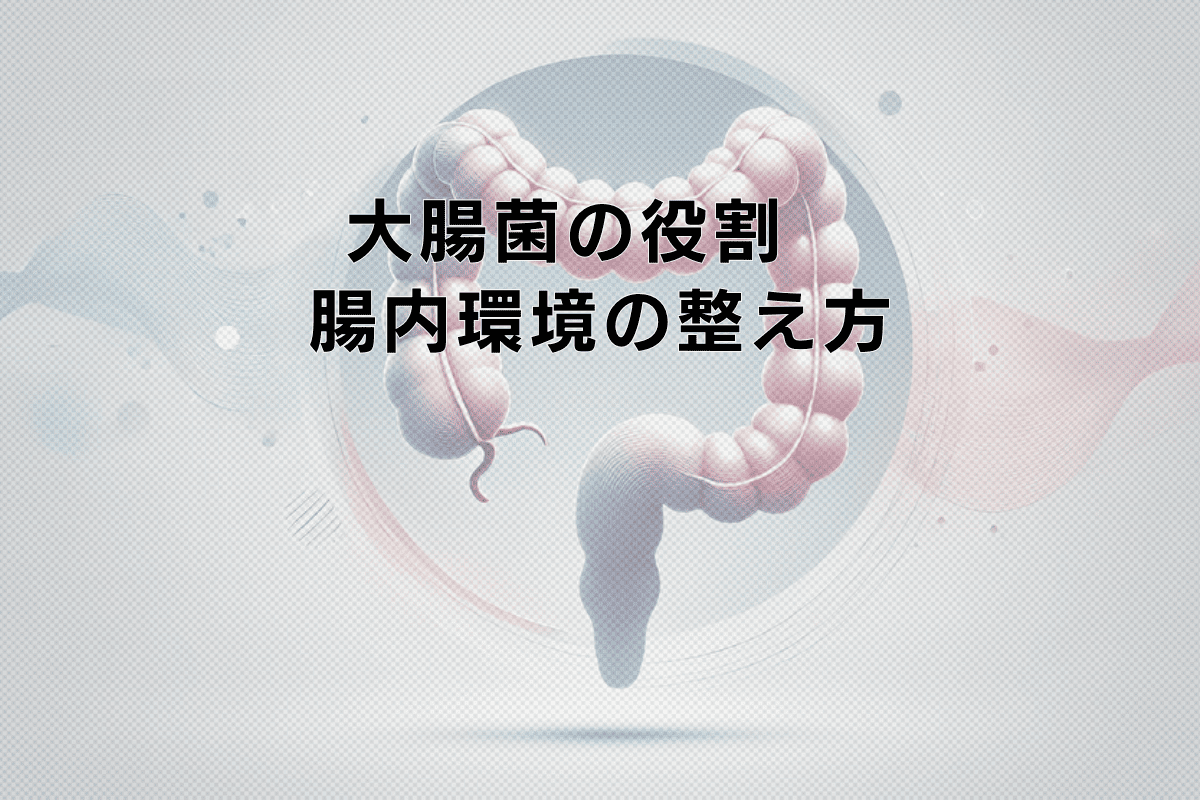
早期発見の重要性
がん全般に言えることですが、早期発見できれば治療の選択肢は増え、予後もよくなる傾向があり、大腸がんでも同様で、初期段階であれば内視鏡による切除など体への負担が比較的軽い方法を選択できる可能性が高まります。
下痢が続くことでがんを疑い、検査を早めに受けることが大切です。
下痢が続く場合に考慮したい検査
長期間下痢に悩む方の中には、「食事に原因があるのではないか」「ただの風邪だろう」と思って受診を後回しにするケースがありますが、原因を探るための検査を受けることが早期診断への近道になります。
とりわけ大腸がんの早期発見には、大腸カメラ検査が大きく貢献します。
大腸カメラ検査の有用性
大腸カメラ検査は、大腸の粘膜を直接観察できる優れた方法で、ポリープや炎症、がん組織の有無を視認し、疑わしい部位があればその場で組織検査を行うことも可能です。
下痢が続く状態で受診した患者に大腸カメラ検査を実施し、初期の大腸がんが見つかるケースもあります。

大腸カメラ検査の主な流れ
| 手順 | 概要 | ポイント |
|---|---|---|
| 事前準備 | 腸内をきれいにする薬剤の服用など | 検査精度を高めるための下剤使用 |
| 検査 | 内視鏡で大腸内部を観察 | 気になる部位は組織採取やポリープ切除 |
| 終了後 | 医師の説明 | 結果や今後の対策を相談 |
大腸カメラ検査は、内視鏡の進歩により負担が軽減されてきました。また、麻酔や鎮静剤を使うことで痛みを抑える方法も選択できます。
血液検査や便潜血検査の意義
下痢が続く場合、血液検査や便潜血検査も有用で、血液検査では貧血や炎症反応を確認して、がんに限らずほかの消化器疾患の可能性も含めて調べられます。
便潜血検査は、自覚症状がなくても便にわずかに混ざる血液を捉え、早い段階で大腸がんの疑いを見つけるきっかになります。
血液検査や便潜血検査は、大腸カメラ検査のように直接視認できるわけではありませんが、診断のヒントを得るためには大切な検査で、下痢が続く理由を知る手がかりとして行うケースが多いです。
検査を考慮するべき状況
- 下痢の期間が2週間以上の場合
- 体重が急激に減少した場合
- 血便が混ざっていると感じる場合
- 発熱や強い腹痛を伴う場合

胃カメラとの比較
がんに対する内視鏡検査は、大腸カメラのほかに胃カメラも代表的で、胃がんや食道がん、十二指腸潰瘍など上部消化管の病変を調べる場合は胃カメラが選ばれます。
一方、下痢が続くような症状では主に大腸のトラブルを想定するため、大腸カメラ検査が中心になるケースが多いです。
ただし、腹部全体に痛みがある、上腹部の痛みが強いなどの症状がある場合は胃カメラと大腸カメラの両方を検討することもあります。

がんを疑う下痢の特徴
下痢のすべてががんに直結するわけではありませんが、下痢が続く状態で特有のサインが表れている場合は注意が必要です。
血液混入の有無
便に血液が混ざっているときは、がんのみならず大腸ポリープや痔核などさまざまな原因が考えられます。
血液が真っ赤な場合は肛門付近からの出血の可能性が高く、便が黒っぽくなる場合は上部消化管からの出血を疑い、下痢と血便が同時に起きるときは大腸がんや炎症性腸疾患のリスクが高まるため、医療機関に相談することが重要です。
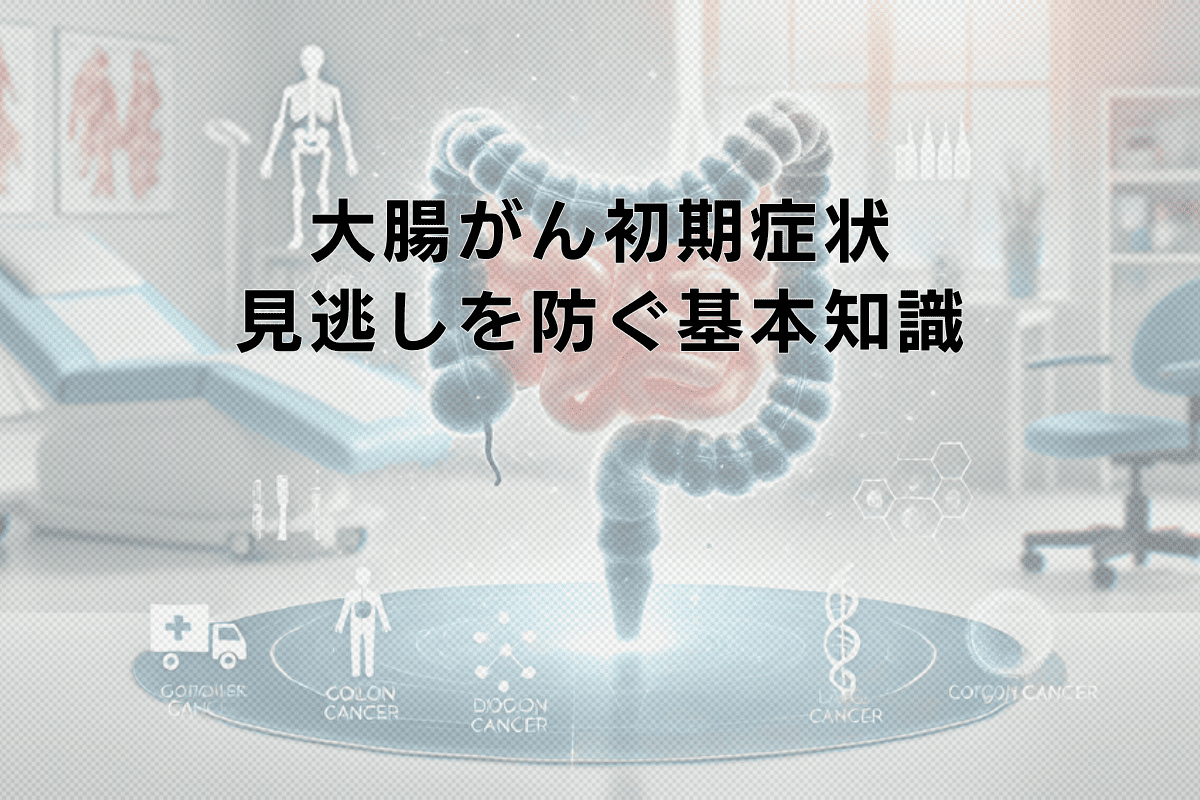
血便が疑われるときのチェック項目
| 項目 | 着目点 |
|---|---|
| 色調 | 鮮血、暗赤色、黒色 |
| 便の形状 | 固形、泥状、液状 |
| 痛みの有無 | 腹痛、肛門痛 |
| その他の症状 | 発熱、体重減少 |

体重減少と倦怠感の併発
がんの進行により身体の栄養吸収が阻害されたり、免疫系が過度に消耗したりすると、体重減少や倦怠感が起こりやすくなります。下痢が続くなかで、食事量をそれほど変えていないのに体重が落ち続けるときは要注意です。
体内に炎症や腫瘍があると、身体がエネルギーを消費しやすくなるため疲労が強く感じられ、下痢とともにこうした症状がある方は、できるだけ早く医療機関を受診してください。
夜間頻繁に起こる下痢
夜間に何度もトイレに行くほど下痢が強い場合、過敏性腸症候群などの機能性疾患だけでなく、大腸がんの可能性にも言及されることがあります。
ストレスなどによる下痢は日中に集中しやすい傾向がある一方、夜間の下痢が頻発する場合は大腸に物理的な異常がある可能性が否定できず、睡眠の質も下がり、体力の低下を招くので軽視できないサインです。
大腸カメラ検査を受けるタイミング
大腸カメラ検査は、下痢が続く状態だけに限らず、40歳を過ぎたら定期的に受けることを推奨されるものの、実際には忙しさや恐怖感から先延ばしにする方も少なくありません。
下痢とがんの関連性を考慮すると、検査を受けるタイミングを見極めることが大切です。
40歳以上と家族歴
大腸がんは、加齢に伴って発症リスクが高まるので、40歳以上で下痢が続く場合や、大腸がんの家族歴がある場合は積極的に検査を検討すると安心です。
遺伝的要因があると、若い年代でも大腸がんに罹患することがあり、症状が軽度でも検査を行うことで早期発見につながります。
大腸がんのリスクファクター
| リスク要因 | 具体例 | 対策の考え方 |
|---|---|---|
| 年齢 | 40歳以上 | 定期的な内視鏡検査 |
| 家族歴 | 親族に大腸がん罹患者あり | 早期の受診や遺伝子検査 |
| 食習慣 | 高脂肪食・野菜不足 | バランスの良い食事 |
| 喫煙・飲酒 | 長期喫煙や大量飲酒 | 生活習慣の改善 |
専門医への相談
下痢が続く場合でも、自己判断で様子を見る方が多いですが、がんをはじめとした重大な病気の可能性を排除するには専門医の診察が欠かせません。
大腸カメラ検査は内科や消化器内科で実施しているところが多く、経験豊富な医師に相談すれば検査時の痛みや準備についても説明してもらえます。
- 2週間を超える下痢
- 血液や粘液が混ざる便
- 強い腹痛や発熱を伴う便通異常
- 大腸がんの家族歴がある
上記のような要素がある方はできるだけ早い受診が望ましいです。
定期検診との組み合わせ
大腸カメラ検査を単発で受けるのではなく、便潜血検査や血液検査と組み合わせると、見落としを減らせます。
健康診断で便潜血検査に引っかかったが、すぐに再検査を受けなかったという話を耳にすることもあります。忙しい方ほど、下痢が続く症状の有無にかかわらず、定期的に検査を組み合わせて受診する意義が高いです。
大腸カメラ検査に対する抵抗感の克服
大腸カメラ検査は、実際に受けるまで抵抗感を抱く方が多く、事前準備や検査時の痛み、検査後の体調など不安は尽きません。しかし、最近の医療現場では患者さんへの負担を減らす工夫が増え、以前より受けやすくなっています。
検査前の食事制限と下剤
大腸カメラ検査では腸内をきれいにする必要があるため、前日は消化の良い食事にし、当日は指定された下剤を使用します。「下剤を飲むのがつらい」という声も聞かれますが、医師や看護師が飲みやすい方法や味を工夫することもあります。
気になる点は事前に相談すると、負担を軽減しやすいです。
下剤摂取時のポイント
| ポイント | 理由 |
|---|---|
| 時間を分けてこまめに飲む | 一気に飲むと気分不良を起こしやすい |
| 味付きの下剤を選択 | 苦みを感じにくくするため |
| 十分な水分補給 | 脱水を防止し、下剤の効果を高める |
| 歩いて腸を動かす | 腸の動きを活発にし、排出を促進する |
下剤は身体に合わない場合もあるため、どうしても飲みにくいときは早めに医師に相談が必要です。
鎮静剤の活用
検査時の痛みが不安な方は、鎮静剤の利用を検討すると恐怖感がやわらぎやすいです。鎮静剤を使用すると意識がぼんやりした状態で検査が進み、痛みを感じにくくなるケースがあります。
使用後は一時的に眠気が残るため、車の運転を控えるなどの注意が必要ですが、日常生活への影響を少なくしたい方にとって、鎮静剤の活用は有力な選択肢です。
鎮静剤の注意点
- 人によって効き方に差がある
- 検査後に休む時間を確保する必要がある
- 高齢者や持病がある方は医師と詳細に相談する
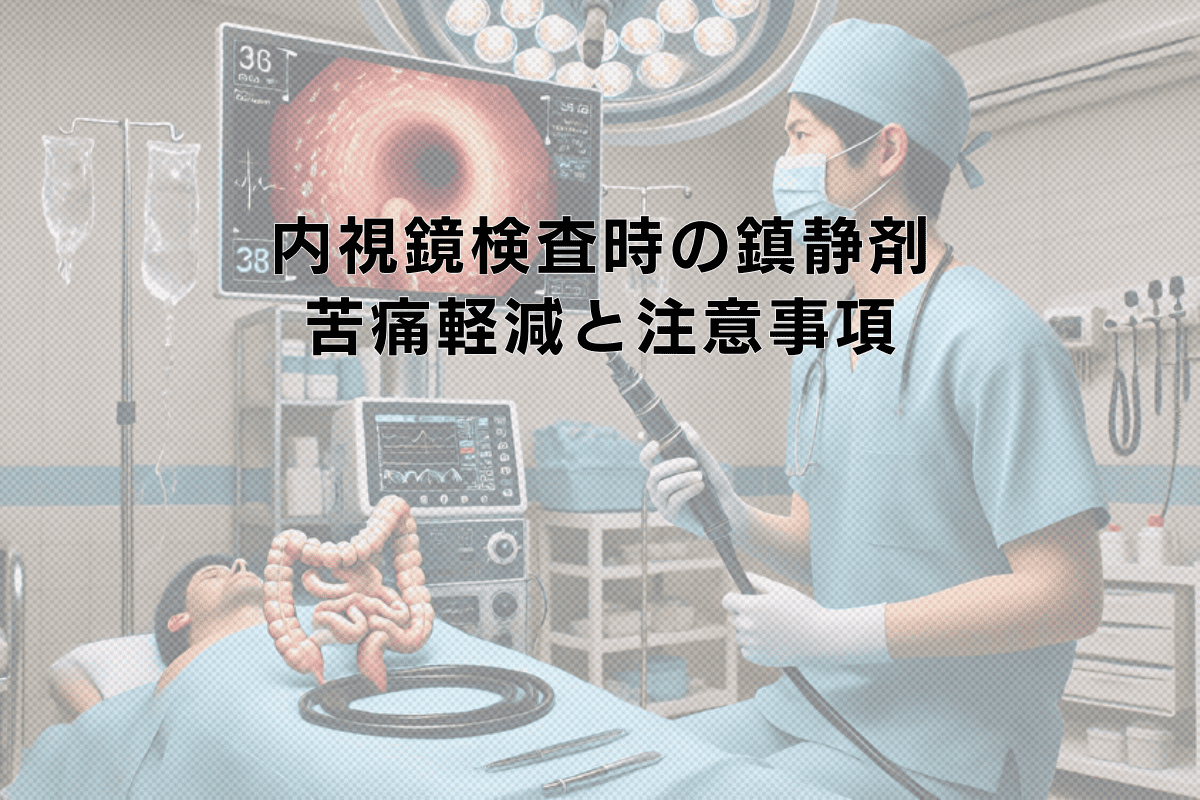
検査後の流れ
大腸カメラ検査が終わると、医師から検査所見の説明があり、ポリープなどが見つかった場合は同時に切除したり、生検を行ったりすることがあります。
その後は当日の体調を考慮しながら帰宅し、日常生活に戻る流れです。問題がなければ数年に1度の検査で済む場合もあります。
下痢を見逃したときのリスク
「下痢が続くなんてよくあること」と放置していると、重大な病気の発見が遅れるリスクがあり、特に大腸がんは進行具合によっては症状が顕在化しにくいため、見逃しを招きやすい点に注意が必要です。
大腸がんの進行と治療の重み
大腸がんは早期であれば内視鏡での切除が可能なケースも多いですが、進行するにつれて手術範囲が広くなり、抗がん剤治療や放射線治療の必要性が高まります。
下痢が続くなどのサインを見過ごして手遅れになると、入院や強い薬の使用で体力を大きく消耗する場面が増えます。早期に発見すれば数日で退院できる可能性があるのに対し、進行期では長期療養が必要です。
大腸がんと治療負担
| 段階 | 治療法の例 | 負担度 |
|---|---|---|
| 早期 | 内視鏡的切除, 局所切除 | 低め |
| 中期 | 外科的手術, 術後化学療法 | 中程度 |
| 進行期 | 拡大手術, 長期化学療法, 放射線併用 | 高め |
がんが進行すると治療の選択肢が狭まりやすいだけでなく、治療後の合併症のリスクも増すため、身体への影響が大きくなります。
他臓器への転移
大腸がんが進行すると、肝臓や肺などへの転移を起こすことがあり、一度転移が起きると治療の難易度が上がり、長期的な治療計画を立てる必要が出てきます。
下痢が続く状況を放置し、大腸がんが進行したあとで検査を受けても、治療のハードルが一気に高くなる可能性があります。
生活習慣で腸を守るヒント
下痢が続く状態を防ぐためには、普段の生活習慣が鍵を握り、大腸がんリスクを下げるためには、腸に優しい食事や適度な運動を心がけることが大切です。
食生活の改善
高脂肪食や過剰なアルコール摂取は大腸がんのリスク要因とされ、腸内の負担を減らすためには、野菜や果物、食物繊維を多く含む食品を積極的に取り入れることが大事です。
また、飲酒量をコントロールし、喫煙を避けることも腸の健康維持につながります。
食物繊維の種類と主な食品
| 食物繊維 | 含まれる食品 | 特徴 |
|---|---|---|
| 水溶性食物繊維 | 海藻類、オクラ、果物 | 便を柔らかくし排出をスムーズにする |
| 不溶性食物繊維 | ごぼう、玄米、きのこ類 | 便のかさを増やし腸を刺激する |
| 両方含む食品 | 野菜全般、豆類 | バランスよく腸内環境を整える |
水溶性と不溶性の両方を意識して摂取すると、腸の働きを整えやすくなります。
適度な運動
運動習慣があると、腸の蠕動運動が活発になり、便通が良くなることが多いです。ウォーキングや軽いジョギング、ヨガなど無理のない範囲で継続できる運動を行うことが大切です。
運動はストレス解消にも役立ち、下痢や便秘の症状を緩和する可能性があります。
- 1日30分程度のウォーキング
- 呼吸を整えながら行うヨガやストレッチ
- ジム通いが難しい場合は家でスクワットや軽い筋トレ
ストレス管理の大切さ
過度なストレスは自律神経を乱し、腸の働きを鈍らせる要因になるので、リラックスできる時間を意識的に設けたり、趣味や休息に時間を割いたりして、精神的な負担を軽くすることが腸への良い影響につながります。
下痢が続く症状に悩む方の中には、ストレスケアを行うだけで改善を実感する場合もあるほどです。
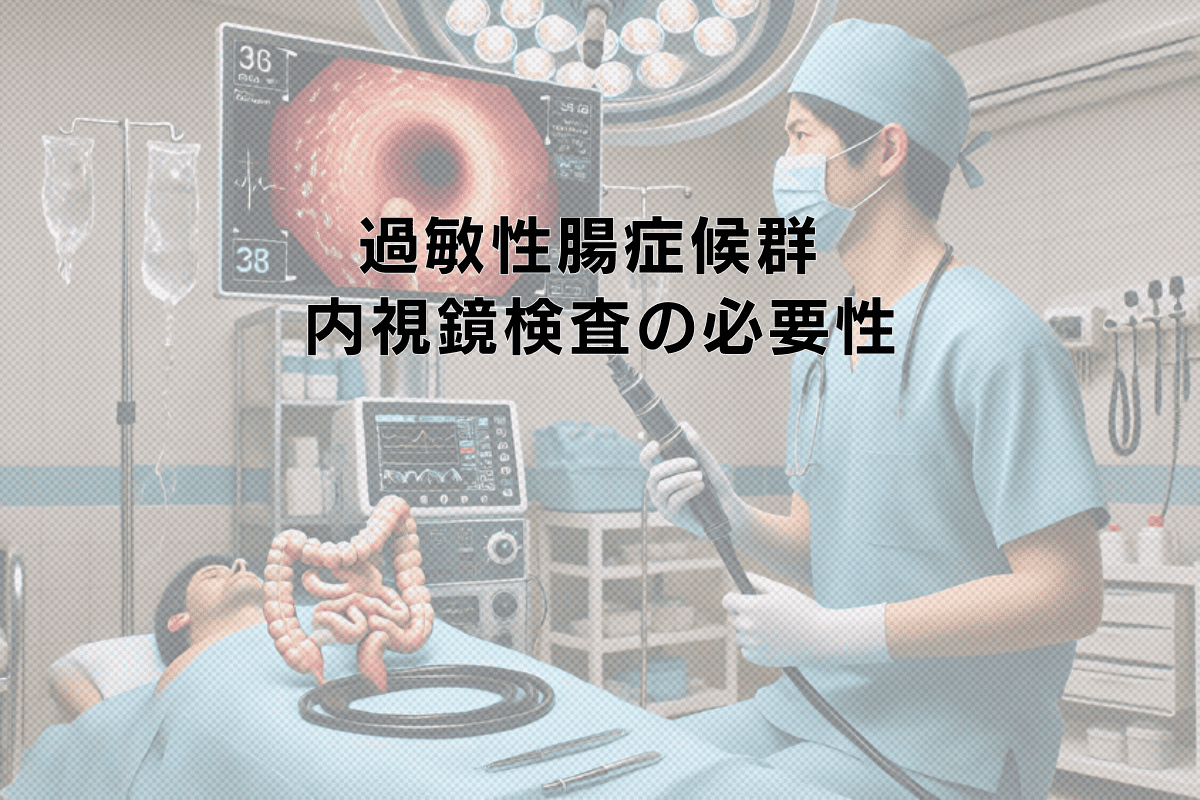
よくある質問
下痢が続く場合の受診や検査に関して、多くの人が抱く疑問についてまとめます。該当する悩みがあれば早めに医師に相談してください。
- 下痢が続く状態はどのくらい様子を見ればいいですか?
-
3日以内に自然に治る下痢は、食あたりや軽いウイルス感染が原因のケースが多いですが、2週間以上続く下痢がある場合や、体重が減少している場合は早めの受診が必要です。
時間だけでなく、血便や腹痛など他の症状があるかも見極めの指標になります。
- 下痢が続くとき、大腸がん以外で考えられる病気は何がありますか?
-
潰瘍性大腸炎やクローン病、過敏性腸症候群など、下痢を引き起こす消化器系の病気は複数あり、ピロリ菌による胃の不調や甲状腺ホルモン異常でも下痢が続く例があります。
自己判断だけで原因を特定するのは難しいため、専門医の診察と検査が大切です。
- 大腸カメラ検査が怖いのですが、少しでも楽に受ける方法はありますか?
-
鎮静剤を使う方法や、医療機関によっては下剤の飲み方を工夫してくれる場合があり、痛みや違和感があるときは、遠慮なく検査担当者に伝えると適切な対処をしてもらえます。
事前の相談で不安を減らすと、検査がスムーズになりやすいです。
- 家族に大腸がんの人がいる場合、症状がなくても検査を受けるべきですか?
-
家族に大腸がんを発症した人がいると遺伝的なリスクが上昇する可能性があるので、症状の有無に関わらず、定期的に内視鏡検査を受けることで早期発見につながります。
医師と相談して検査の間隔を決め、日常の健康管理にも気を配ることが大切です。
次に読むことをお勧めする記事
【痛みのない下痢が続くときの大腸カメラ検査の重要性】
下痢が続くものの痛みがないと“様子見”になりがちです。本記事で検査の必要性を理解したら、痛みがなくても検査が重要な理由と負担を減らすコツを具体的に確認してみてください。
【腸の健康が体を支える 腸内環境を整える】
下痢や便秘を繰り返す方には、腸内細菌バランスの整え方も重要なテーマ。食事と生活習慣の工夫で腸を守る総合的な方法を学びましょう。
参考文献
Otani T, Iwasaki M, Inoue M, Sasazuki S, Tsugane S, Japan Public Health Center–Based Prospective Study Group. Bowel movement, state of stool, and subsequent risk for colorectal cancer: the Japan public health center–based prospective study. Annals of Epidemiology. 2006 Dec 1;16(12):888-94.
Nagata N, Ishii N, Manabe N, Tomizawa K, Urita Y, Funabiki T, Fujimori S, Kaise M. Guidelines for colonic diverticular bleeding and colonic diverticulitis: Japan Gastroenterological Association. Digestion. 2019 Jan 14;99(Suppl. 1):1-26.
Sekido Y, Ogino T, Takeda M, Hata T, Hamabe A, Miyoshi N, Uemura M, Mizushima T, Doki Y, Eguchi H. Surgery for Colorectal Cancer Associated with Crohn’s Disease—Toward a Medical Treatment Strategy Based on the Differences Between Japan and Western Countries. Cancers. 2025 Mar 3;17(5):860.
Nagata N, Niikura R, Aoki T, Shimbo T, Sekine K, Okubo H, Watanabe K, Sakurai T, Yokoi C, Yanase M, Akiyama J. Association between colonic diverticulosis and bowel symptoms: A case‐control study of 1629 A sian patients. Journal of Gastroenterology and Hepatology. 2015 Aug;30(8):1252-9.
Yamauchi Y, Arai M, Akizue N, Ohta Y, Okimoto K, Matsumura T, Fan MM, Imai C, Tawada A, Kato J, Kato N. Colonoscopic evaluation of diarrhea/colitis occurring as an immune-related adverse event. Japanese Journal of Clinical Oncology. 2021 Mar;51(3):363-70.
Holtedahl K, Borgquist L, Donker GA, Buntinx F, Weller D, Campbell C, Månsson J, Hammersley V, Braaten T, Parajuli R. Symptoms and signs of colorectal cancer, with differences between proximal and distal colon cancer: a prospective cohort study of diagnostic accuracy in primary care. BMC family practice. 2021 Dec;22:1-3.
Vega P, Valentin F, Cubiella J. Colorectal cancer diagnosis: Pitfalls and opportunities. World journal of gastrointestinal oncology. 2015 Dec 15;7(12):422.
Cai J, Yuan Z, Zhang S. Abdominal pain, diarrhea, constipation-which symptom is more indispensable to have a colonoscopy?. International Journal of Clinical and Experimental Pathology. 2015 Jan 1;8(1):938.
Hamilton W, Sharp D. Diagnosis of colorectal cancer in primary care: the evidence base for guidelines. Family Practice. 2004 Feb 1;21(1):99-106.
Demb J, Kolb JM, Dounel J, Fritz CD, Advani SM, Cao Y, Coppernoll-Blach P, Dwyer AJ, Perea J, Heskett KM, Holowatyj AN. Red flag signs and symptoms for patients with early-onset colorectal cancer: a systematic review and meta-analysis. JAMA Network Open. 2024 May 1;7(5):e2413157-.