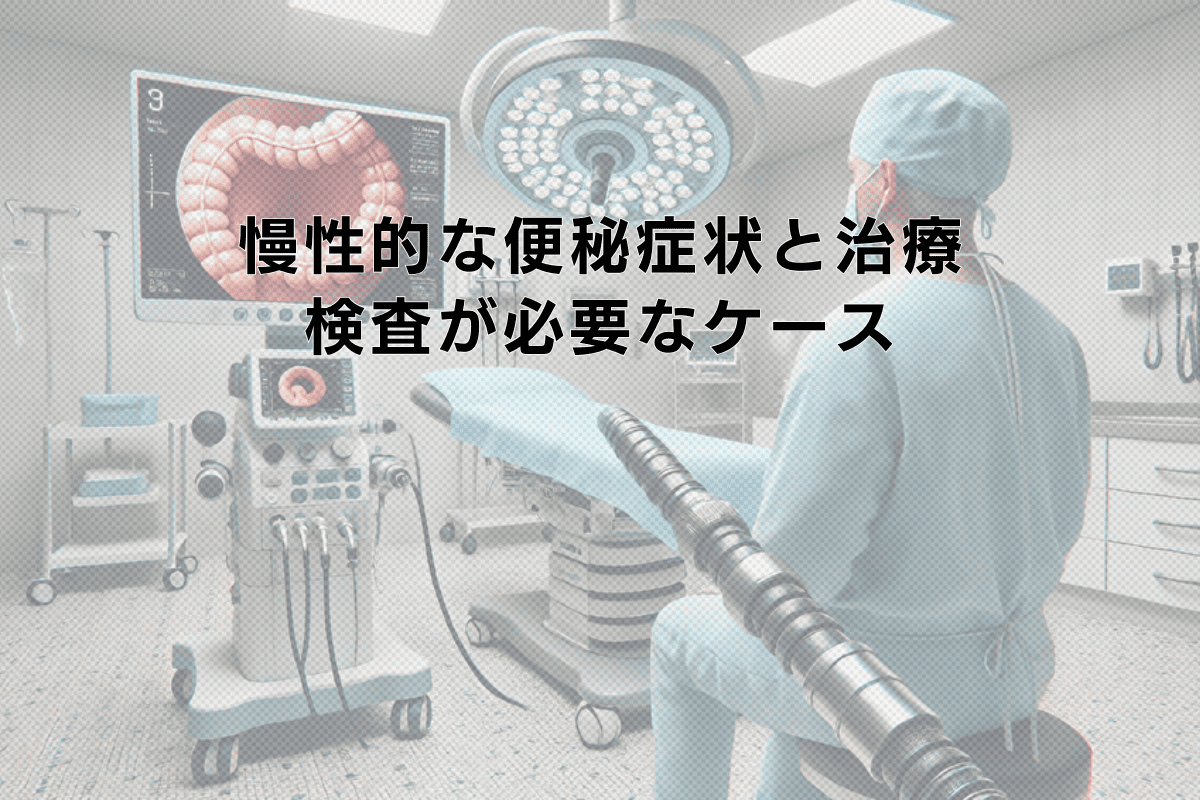長期間にわたり便通が滞りがちな状態は、日常生活の質を大きく損ねる要因になります。また、単純に食物繊維や水分が足りないだけと考えて放置すると、原因が潜在的な病気にある可能性を見落とすかもしれません。
ひどい便秘を自覚したときは、セルフケアだけでなく、医療機関での検査を検討することが大切です。
本記事では慢性的な便秘に着目し、考えられる原因や典型的な症状、さらにどのような治療法があるのかを詳しく解説します。
内視鏡検査が必要となるケースや普段から意識したい生活習慣のポイントも含め、便秘と向き合ううえで知っておくと役立つ情報をまとめました。
便秘の基礎知識
便秘は「排便が少ない」「出にくい」「残便感がある」といった症状の総称であり、一時的なものから長期にわたるものまでさまざまなパターンがあります。
日常的に便がスムーズに出ない状態は苦痛を伴いやすく、生活面にも影響が及ぶことが少なくありません。
便秘の定義と種類
一般的には排便の回数が週に2回以下、あるいは本人が強い不快感を覚えるときに便秘と判断されますが、排便回数だけでなく、便の硬さや排便時の痛みなども指標になります。
便秘には大きく分けて急性と慢性があり、急性の場合は旅行や環境変化などの一時的な影響が原因になりやすいです。一方、慢性の場合は数週間から数か月、あるいは年単位で便秘状態が続くことも珍しくありません。
排便のメカニズム
食べたものは胃から小腸、大腸へと送られ、水分や栄養を吸収されたのちに便として排出され、この過程で大腸がうまくぜん動運動を行い、便をスムーズに肛門まで運んでいくことが理想的です。
しかし、腸の動きが遅すぎたり、逆に早すぎたりすることで便の状態に影響が出て、水分を吸収しすぎると硬くなり、出にくい便になります。
慢性的な便秘が及ぼす影響
慢性の便秘は、腹部の張りやガスの発生、食欲不振などを起こし、体調全般に悪影響を及ぼします。また、肌荒れや頭痛、集中力の低下など、便秘とは一見関係なさそうに思える症状が出るケースもあります。
さらに、トイレで長時間いきむことが習慣化すると、痔や肛門周辺のトラブルを誘発する可能性も高まります。
便秘かどうかを見極めるポイント
排便が2~3日に1回でも、本人がまったく苦痛を感じず、便の状態が良いのであれば、必ずしも異常とは限らず、逆に、毎日排便があっても、極端に硬い便や排便に長時間かかる状態なら便秘かもしれません。
自分の便や排便感に注目することが、早期発見の手がかりとなります。
便秘の目安と状態
| 指標 | 目安 |
|---|---|
| 排便回数 | 週に2回以下で苦痛を伴う場合は検討が必要 |
| 便の硬さ | かたい便が続き、排出に時間がかかる状態 |
| 残便感 | 排出後もまだ便が残っている感覚が続く |
| いきみ | 排便時に強くいきむ習慣がある |
慢性的な便秘の原因とリスク
慢性の便秘を訴える方の背景には、食生活をはじめとする生活習慣の乱れやストレス、腸そのものの機能障害など、いくつかの要因が存在する可能性があります。
なかには別の病気が潜んでいるケースもあり、見過ごすと深刻な事態に発展することもあるため注意が必要です。
食習慣や水分不足
偏った食事や食物繊維の少ないメニュー、十分でない水分摂取は、便を硬くし排出しにくい状態を作りやすいです。また、油分が過剰に多い食事は腸の動きを乱す要因にもなり、結果的に便秘を長引かせます。
運動不足
日常的な運動量が少ないと、下半身や腹部の筋力が低下しやすく、腸の動きも鈍くなりがちで、ウォーキングや軽いジョギングなどの有酸素運動を取り入れれば腸に刺激を与え、便通が改善する可能性があります。
運動不足がもたらす腸内への影響
| 項目 | 変化 |
|---|---|
| 筋力の低下 | 腹筋や骨盤底筋群の衰えでいきみにくくなる |
| 血行不良 | 腸への血流が滞り、ぜん動運動が弱まりやすい |
| 代謝の低下 | 消化機能全体の低下につながる |
ストレスと自律神経
腸は「第二の脳」とも呼ばれ、自律神経の影響を大きく受け、過剰なストレスは自律神経のバランスを乱し、腸のぜん動運動を抑制したり、逆に不規則にしてしまう場合があります。
寝不足や精神的な緊張が続く生活を送っている方は、便秘を招きやすい傾向があります。
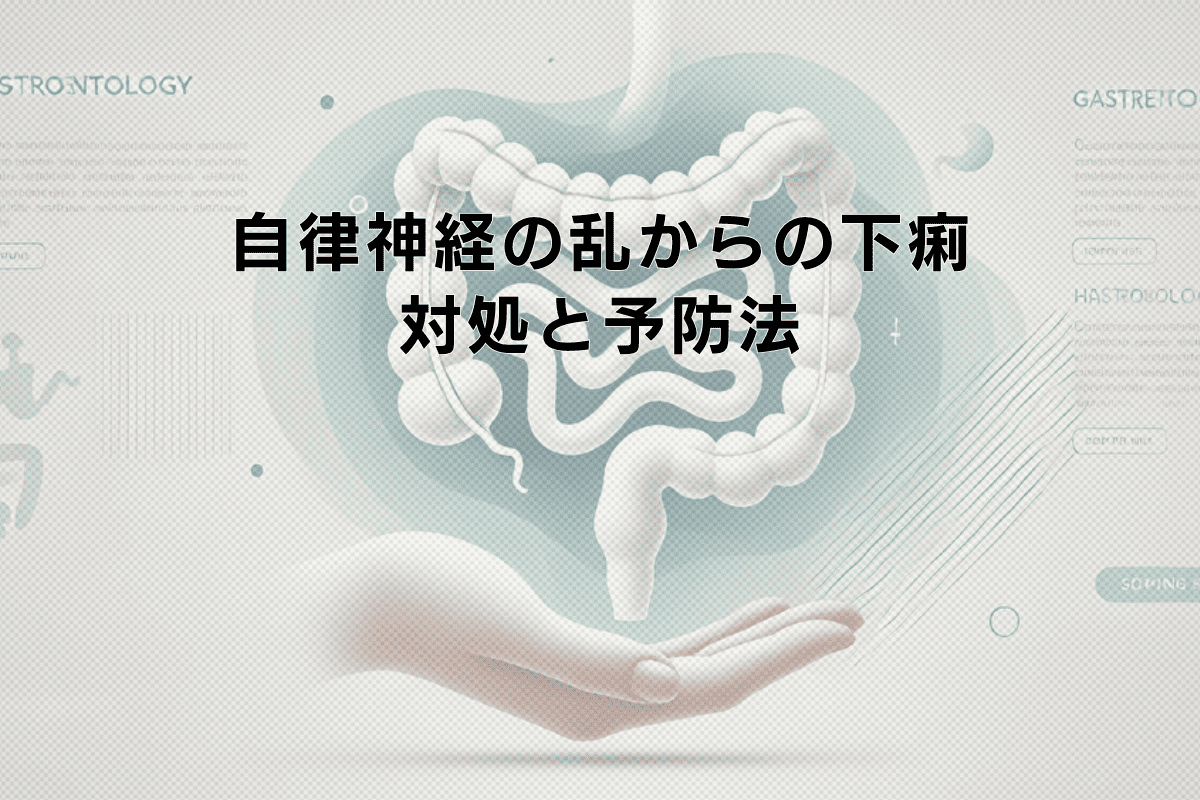
病気が原因の便秘
大腸の病気や甲状腺機能の低下など、特定の疾患が便秘を誘発するケースも見受けられます。腸閉塞や大腸がんが隠れている場合もあり、単なる食事不足では説明がつかない便秘が長期間続くなら、早めに医療機関を受診したほうが安心です。
病気と便秘の関連性
| 疾患例 | 便秘との関わり |
|---|---|
| 大腸がん | 腸管内が狭くなり通過障害が起きる |
| 甲状腺機能低下症 | 新陳代謝が低下し、腸の動きが鈍くなる |
| 糖尿病 | 神経障害や血行不良が便秘を助長する |
便秘に伴う症状とサイン
長引く便秘には、腹部だけでなく全身にさまざまなサインが現れることがあり、排便の周期や便の状態とあわせて、体のどこに異常が起きているかをチェックすると、早期に対応しやすいです。
腹痛や腹部膨満感
腸内で便が滞留するとガスが増えてしまい、腹痛やお腹の張りが生じやすく、ひどい場合は、食欲不振や吐き気をともなうこともあります。こうした症状が続くと日常生活において大きなストレスになります。
肌荒れや吹き出物
便秘によって腸内に有害物質が増え、それが血液を通じて全身に影響するという説もあります。便秘の結果として肌荒れや吹き出物、ニキビなどのトラブルが増える場合があり、美容面でも悩みが尽きなくなる方もいます。
便秘と肌トラブルの関連
| 肌への影響 | 要因 |
|---|---|
| 吹き出物やニキビ | 老廃物が腸内に長く留まり、毒素が巡る |
| 乾燥やくすみ | ビタミン吸収が不十分になりやすい |
| 肌のごわつき | 血流不全で皮膚細胞へ栄養が行き渡りにくい |
頭痛やイライラ
腸の不調は脳へも影響を与えます。便秘により腸内環境が乱れ、セロトニンといった神経伝達物質の分泌に影響が出ると、頭痛やイライラ、集中力の低下が起きることがあります。
ストレスと便秘の関係性は相互作用を持っているため、悪循環に陥りやすい点に注意が必要です。
排便時の痛み
硬い便を排出しようとすると、肛門付近に強い刺激が加わり、痛みや出血を伴う場合があり、排便行為そのものを避けようとする心理的な要因が加わり、ますます便秘が悪化するケースがあります。
肛門周囲の痛みが長引くなら痔の併発も疑われるので、医師に相談しましょう。

自宅でできる便秘対策と注意点
便秘が続いていても、生活習慣の改善によって症状が軽くなる場合があり、まずは食生活や運動習慣を見直すことで、腸の活動をスムーズにする努力が効果を発揮できます。
食事の見直し
食物繊維は便のかさを増やし、腸内での通過を助ける働きがあり、野菜や果物、豆類、海藻類を意識的に摂取すると腸内環境の改善が期待できるでしょう。
過度な脂質や糖質の摂りすぎは腸の動きを妨げる場合があるため、バランス良いメニューを心がけることが大切です。
食物繊維の種類と含まれる食材
| 種類 | 代表的な食材 | 期待される働き |
|---|---|---|
| 水溶性 | りんご、バナナ、わかめ、こんにゃくなど | 腸内でゲル状になり便を柔らかくする |
| 不溶性 | ごぼう、ブロッコリー、豆類など | 腸を刺激しぜん動運動を促す |

水分と適度な油分
水分が不足すると便が硬くなってしまいます。1日に摂取する水分量は1.5〜2Lを目安にするとよいです。
また、極端な油分カットを行うと腸内の滑りが悪くなるケースもあるため、オリーブオイルや魚の脂など良質な油を適度に取り入れてください。
- 1日に何度か分けて水を飲む
- 朝起きた直後のコップ1杯の水分で腸に刺激を与える
- オイルはサラダやスープに少し加えて摂取する
運動の習慣化
軽いストレッチやウォーキングでも、腸に一定の刺激が加わり便通を促す可能性があり、朝のウォーキングや簡単な体操は自律神経のリズムを整え、腸の活動を促進する働きが期待できます。
長時間座り続けることが多い職業や生活スタイルの方は、意識して体を動かしましょう。
運動の頻度と便通の関係
| 運動パターン | 便通への影響 |
|---|---|
| 毎日20〜30分のウォーキング | 腸が適度に刺激され排便リズムが整いやすい |
| 週1回程度の激しい運動 | 激しい運動は一時的な効果があるが継続しにくい |
| デスクワーク中心 | 腸が動きにくく筋力低下で便通が不安定になりやすい |
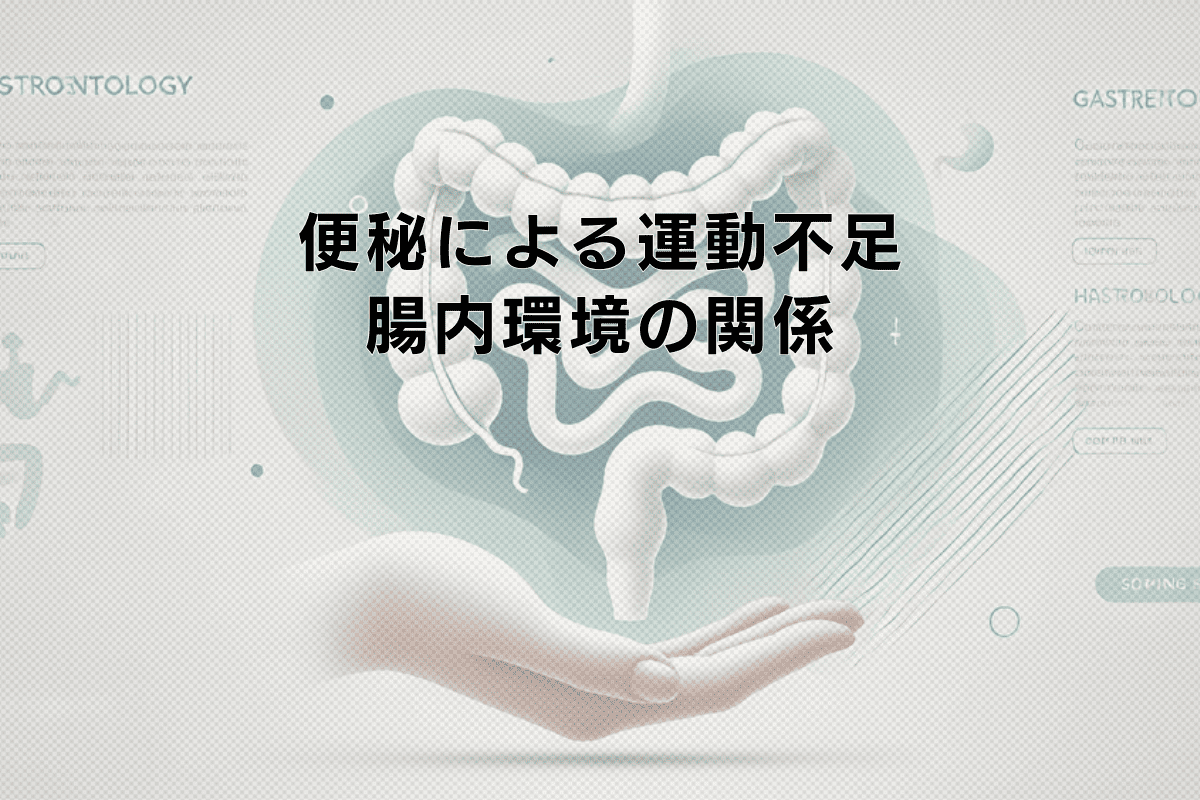
市販薬の利用
便秘薬にはさまざまな種類がありますが、薬によっては長期使用で腸が薬に頼るようになるリスクがあり、市販薬を使用する場合は用法をよく確認しながら、症状に応じて短期的に活用します。
自己判断での乱用は控え、改善が見られない場合は医師や薬剤師に相談してください。
医療機関での診断と検査
自宅での対策を行っても便秘が続いたり、痛みや出血などの異変が見られる場合は、医療機関を受診して正確な診断を受ける必要があります。便秘の背後に重大な疾患が隠れている可能性を除外するためにも、早めの受診が望ましいです。
問診と身体診察
医師はまず問診で生活習慣や食事の内容、排便の回数、便の状態などを確認し、これにより、機能性の便秘か器質的な病変による便秘かの目安がつきやすくなります。また、必要に応じて、腹部診察や直腸診も行う場合があります。
- 食事内容、排便頻度、ストレス状況を共有する
- 便の形状や色、硬さなどの具体的な情報を伝える
- 既往症や家族歴があれば報告しておく
内視鏡検査や画像検査
便秘が長期間続いている場合や便に血が混ざるなどの症状がある場合は、大腸カメラ(大腸内視鏡検査)やCT、X線検査などで大腸を直接確認します。
大腸に腫瘍やポリープが存在しないか、通過障害を起こす要因がないかを詳しく調べる目的で、検査前には下剤や食事制限などの準備が必要です。

内視鏡検査と画像検査の比較
| 方法 | 概要 | 特徴 |
|---|---|---|
| 大腸カメラ | 肛門から内視鏡を挿入し、大腸全体を観察 | ポリープなどを直接切除することも可能 |
| CTスキャン | X線を用いて断層画像を撮影 | 大腸だけでなく他の臓器もチェックしやすい |
| 注腸X線検査 | 造影剤を注入して大腸の形状を撮影 | 内視鏡に比べると詳細に観察しにくい |
血液検査やその他の検査
便秘の原因が内臓疾患やホルモン異常にある場合、血液検査で異常値が検出されることがあり、甲状腺機能や糖尿病関連の値をチェックすることで、病態の全体像がより明確になります。
排便障害が原因かどうかを判別するために、肛門括約筋の圧力を測定する検査などを行うこともあります。
病気を見逃さない重要性
便秘を抱える方のなかには、「単なる便秘だから」と軽視してしまう場合がありますが、大腸がんや炎症性腸疾患など、重篤な病気が便秘の背景に潜んでいる可能性もゼロではありません。
特に、急に便秘の状態が変わり、血便や体重減少などが認められたら早急に医師の診察を受けることが大切です。
便秘の治療法と薬物療法
医療機関で便秘と診断されても、治療アプローチは原因や症状の程度に応じて異なり、薬物療法や習慣改善、場合によっては外科的処置が検討されることがあります。
生活習慣指導
食事や運動、ストレスケアなど、日常生活の改善が大前提になるケースが多いです。
便秘の原因が明らかに生活習慣にあると判断されれば、医師や管理栄養士のアドバイスに沿ってバランスの良い食生活を心がけたり、運動を継続的に行うことで改善が期待できます。
- 毎日の水分摂取量を記録して、意識的に増やす
- 朝にトイレへ行く習慣を作り、自然な便意を逃さない
- ストレス解消にリラックス法や趣味を取り入れる
薬物治療の概要
便秘薬には刺激性下剤、浸透圧性下剤、胆汁酸分泌促進薬など、さまざまな種類があります。
刺激性下剤は腸管を直接刺激して排便を促す反面、腸を慣れさせてしまうリスクがあり、浸透圧性下剤は腸内に水分を集め、便を柔らかくする方法をとるため、比較的マイルドな効き目です。
医師は患者さんの便秘のタイプや年齢、全身状態を考慮して薬を選びます。
下剤の種類と特徴
| 薬の種類 | 特徴 | 適用される便秘のタイプ |
|---|---|---|
| 刺激性下剤 | 腸を刺激して排便を誘発 | 反応が鈍く慢性化した便秘 |
| 浸透圧性下剤 | 腸管内に水分を引き込み便を柔らかくする | 比較的軽度〜中等度の便秘 |
| 酸化マグネシウム | マグネシウムイオンが腸を刺激 | 慢性便秘や妊娠中の便秘でも使われやすい |
| 胆汁酸分泌促進薬 | 胆汁酸を増やしてぜん動運動を促進 | 胆汁酸不足が原因の便秘 |
その他の治療選択肢
薬物治療でも改善がみられない場合は、骨盤底筋のトレーニングやバイオフィードバック療法などを組み合わせて治療を行うことがあります。
大腸や直腸に器質的な病変(大腸がんなど)が存在する場合は外科的な対応が必要になるケースも考えられます。
医師と患者の連携
便秘は慢性化しやすいものの、医師と連携を取りながら自分に合った治療法を模索することで、症状の緩和をめざすことができます。
自己判断で薬を増減するのではなく、定期的に診察を受けて薬の効果や副作用をチェックしながら調整していくことが大切です。
内視鏡検査が必要なケースと受け方
便秘が長期にわたる場合や、便通異常に加えて血便や体重減少などの症状が出ている場合、大腸カメラなどの内視鏡検査が推奨されることがあります。慢性便秘の背景に危険な病変がないか、しっかり確認するための重要なプロセスです。
内視鏡検査を考慮すべき症状
大腸がんや炎症性腸疾患などを疑わせる症状があるときは、ただの便秘と放置せず、内視鏡検査を検討し、便に血が混じる、急激な体重減少、夜間にも継続する腹痛などは要注意です。
- 血便が続く
- 便の形状が細くなったり変化が大きい
- 腹痛が断続的でなく持続的に強くなっている
検査前の準備
大腸カメラ検査では、腸内を空にして視界を確保する必要があるため、検査前日は消化に良い食事を取り、当日は専用の下剤を服用して腸内をきれいにします。
食事内容や下剤の服用方法は医療機関から詳細な指示があるので、それを守ることが大切です。
大腸カメラ検査前日の流れ
| 時間帯 | 内容 |
|---|---|
| 検査前日夕方 | 消化の良い食事を摂る |
| 就寝前 | 医師の指示に応じて下剤を服用する場合がある |
| 検査当日朝 | 起床後すぐに下剤を飲み始め、腸内を空にする |
| 検査直前 | 水分補給を適宜行い、脱水にならないよう注意 |

検査当日の流れ
検査当日は問診と簡単な身体チェックの後、検査が始まります。痛みに弱い方や検査に対して強い不安がある方は、医師と相談して鎮静剤や麻酔の使用が可能な場合があります。
大腸内視鏡は肛門からゆっくりと挿入し、大腸の内部を観察しながら進め、ポリープなどの病変が見つかった場合は、その場で切除することも多いです。
検査後の注意点
検査後は腸内に空気が残っているため、お腹の張りや軽い不快感を感じるかもしれませんが、数時間ほど安静にしてガスを排出すると徐々に楽になります。
ポリープ切除を行った場合は出血などのリスクもあるため、医療スタッフからの指示に従って行動し、自宅に戻ってからも体調に気を配ってください。
内視鏡検査のメリットと注意点
| メリット | 注意点 |
|---|---|
| 大腸内の状態を直接確認できる | 検査前の下剤服用が負担になる場合がある |
| ポリープ切除が同時に可能 | 挿入時の不快感を伴うことがある |
| がんの早期発見に効果的 | 鎮静剤の使用により一時的に眠気が残る |
よくある質問
慢性の便秘を抱える方や、大腸カメラなどの検査を検討している方から寄せられる問いがいくつかあります。医療機関での診断や治療を検討するときの目安として参考にしてください。
- 毎日便意があっても、便が硬ければ便秘に該当しますか?
-
便秘かどうかの判断は回数だけでなく、便の硬さや排便時の苦痛の有無によっても決まります。毎日排便がある場合でも、便が硬くて出しにくい、強い痛みを伴うなどの症状があるなら、便秘と捉えることがあります。
- 長年便秘に悩んでいるので、大腸カメラは受けたほうがいいですか?
-
慢性的な便秘が続き、便に血が混じる・腹痛が増している・体重減少があるといった症状があれば、一度は受けておくと安心です。大腸内に病変が見つかることもありますし、検査で異常がないとわかれば安心感が得られます。
- 便秘薬を使い続けると効き目が落ちると聞きますが本当でしょうか?
-
刺激性の下剤を長期間使用すると、腸が薬に慣れやすい可能性があります。医師の指示のもとで処方された薬を使い、自己判断での増減を避ければ、必要以上に効き目が落ちるリスクは抑えられます。
- 運動だけで便秘は改善しますか?
-
人によっては運動習慣の導入だけで大きく改善する場合もありますが、それだけで不十分な場合もあります。食生活やストレスケアなど、総合的なアプローチをすることでより良い結果が期待できます。
次に読むことをお勧めする記事
【大腸検査 下剤で腸を整える手順と注意点】
検査の大敵は“下剤がつらい”という不安。実際に飲む量やタイミング、楽に乗り切るコツを解説しています。検査予定の方は、事前に読んでおくと安心です。
【腸にいい食べ物を知る 腸内環境を整える方法】
慢性的な便秘について理解が深まったところで、さらに腸内環境全般の改善についても知っておくと、より包括的な対策ができます。食生活の具体的な改善方法が見えてくる内容です。
参考文献
Tomita T, Kazumori K, Baba K, Zhao X, Chen Y, Miwa H. Impact of chronic constipation on health‐related quality of life and work productivity in Japan. Journal of gastroenterology and hepatology. 2021 Jun;36(6):1529-37.
Ihara E, Manabe N, Ohkubo H, Ogasawara N, Ogino H, Kakimoto K, Kanazawa M, Kawahara H, Kusano C, Kuribayashi S, Sawada A. Evidence-based clinical guidelines for chronic constipation 2023. Digestion. 2025 Feb 19;106(1):62-89.
Matsumoto M, Misawa N, Tsuda M, Manabe N, Kessoku T, Tamai N, Kawamoto A, Sugama J, Tanaka H, Kato M, Haruma K. Expert consensus document: diagnosis for chronic constipation with faecal retention in the rectum using ultrasonography. Diagnostics. 2022 Jan 25;12(2):300.
Manabe N, Kamada T, Kusunoki H, Hata J, Haruma K. Usefulness of ultrasonographic evaluation of stool and/or gas distribution for the treatment strategy of chronic constipation. JGH Open. 2019 Aug;3(4):310-5.
Ohkusa T, Koido S, Nishikawa Y, Sato N. Gut microbiota and chronic constipation: a review and update. Frontiers in medicine. 2019 Feb 12;6:19.
Jamshed N, Lee ZE, Olden KW. Diagnostic approach to chronic constipation in adults. American family physician. 2011 Aug 1;84(3):299-306.
Camilleri M, Ford AC, Mawe GM, Dinning PG, Rao SS, Chey WD, Simrén M, Lembo A, Young-Fadok TM, Chang L. Chronic constipation. Nature reviews Disease primers. 2017 Dec 14;3(1):1-9.
Rao SS, Rattanakovit K, Patcharatrakul T. Diagnosis and management of chronic constipation in adults. Nature Reviews gastroenterology & hepatology. 2016 May;13(5):295-305.
Lacy BE, Levenick JM, Crowell M. Chronic constipation: new diagnostic and treatment approaches. Therapeutic Advances in Gastroenterology. 2012 Jul;5(4):233-47.
Forootan M, Bagheri N, Darvishi M. Chronic constipation: A review of literature. Medicine. 2018 May 1;97(20):e10631.