お腹の調子が長期間にわたって不安定で、便がゆるい状態が続いたかと思えば、今度は便が出にくくなり腹部の重苦しさに悩まされ、下痢と便秘が混在するような症状は日常生活に大きな負担となりがちです。
慢性的な下痢を繰り返すだけでなく、便秘も併発するケースでは、大腸や小腸など消化管に何らかのトラブルが起きている可能性も考えられます。原因を突き止めるために医療機関での受診と検査が大切です。
内視鏡検査や大腸カメラ・胃カメラ検査の必要性が出てくる場合もあるので、まずは症状の特徴や原因を理解し、早めの対策を検討してください。
慢性下痢を伴う便秘症状とは
お腹がゆるい状態が続いているのに、何日も便が出ない期間が混ざる症状は、単なる軽い消化不良とは異なります。
下痢と便秘が入り交じるこのような状態は、過敏性腸症候群や炎症性腸疾患、その他消化器系の疾患など、多様な原因と関連している可能性があり、日常で見られる下痢や便秘との違いを理解しておくことが重要です。
日常的な便秘と比べたときの特徴
一般的な便秘は、食物繊維不足や水分不足、運動不足などが影響して便が硬くなることが多く、便意があっても排便が困難になるのが特徴です。
慢性的に下痢を伴う便秘の場合は、急に水っぽい便が出たり、腸が過度に刺激されたような腹痛を感じたりする点が異なります。いわゆる「便秘なのに下痢?」という状況が続くなら、単純な生活習慣の乱れだけではないかもしれません。
どのような人が悩みやすいか
ストレスを抱えやすい人、食生活が偏りがちな人、何らかのアレルギーや過敏症がある人などは、このような便通異常を起こしやすい傾向があります。
また、女性はホルモンバランスの影響で腸の動きが左右されやすく、便秘や下痢の悩みを抱えがちです。こうした体質的・生活習慣的要因に加えて、腸の病気が潜んでいるケースも否定できません。
下痢と便秘が混在する時期の長さ
下痢と便秘が時期によって交互に現れる状態が、数日から1週間程度ならまだ一時的なものかもしれませんが、1か月以上続く、あるいは何度も繰り返すなら、慢性下痢や過敏性腸症候群などの可能性を検討する必要があります。
長引くお腹の不調は、生活の質を大きく損ねるため、早めの対策が望ましいです。
痛みや吐き気の有無
下痢と便秘を繰り返すだけでなく、強い腹痛や吐き気をともなう場合は、炎症性腸疾患や大腸ポリープ、大腸がんなど重大な疾患も視野に入れて医療機関を受診したほうが良いでしょう。
急激に体重が減少する、便に血が混ざる、貧血があるなどの症状が加わるなら、より入念な検査が大切です。
慢性下痢を伴う便秘の一般的なサイン
| サイン | 具体例 |
|---|---|
| 下痢と便秘の反復 | 数日間便が出ない後に突然の下痢が起こるなど |
| 腹痛や腹部の不快感 | 差し込むような腹痛、ガス溜まりによる張り |
| 体調全般への影響 | 疲れやすい、集中力の低下、イライラ感 |
| 排便の仕方が安定しない | 便が硬いときもあれば水様便が出ることもある |
| 体重の変動や食欲不振 | 食欲が落ちる、体重の減少または増加(むくみ) |
上記のようなサインを見逃さず、早めに医療機関へ相談することが身体的・精神的負担の軽減につながります。
腸内環境と症状のメカニズム
便秘と下痢の混在を考える際には、腸内環境の状況と腸の運動機能を知ることが役立ち、腸の動きや腸内細菌のバランスが崩れると、便通のリズムが大きく乱れ、さまざまな不快症状につながります。
腸の蠕動運動と便通
健康な状態では、大腸がゆっくりとリズミカルに収縮して便を肛門方向へ押し出し、水分を適度に再吸収しながら形のある便を形成します。
しかし、ストレスや生活リズムの乱れ、特定疾患などで腸が過度に刺激されると、蠕動運動が強くなって水分を十分に吸収できず下痢を起こす場合があり、逆に、腸の動きが低下すると便が大腸内に長く留まり、便秘となります。
腸内細菌のバランス
腸内には善玉菌・悪玉菌・日和見菌と呼ばれる細菌群が共存しており、そのバランスが腸内環境を左右します。悪玉菌が増えすぎたり、善玉菌が減少したりすると、腸内に有害物質が蓄積される恐れがあります。
結果として腸粘膜がダメージを受けやすくなり、下痢や便秘などの症状が生じやすくなるので、善玉菌を増やす食生活やサプリメントの利用などは、バランスを整える助けです。
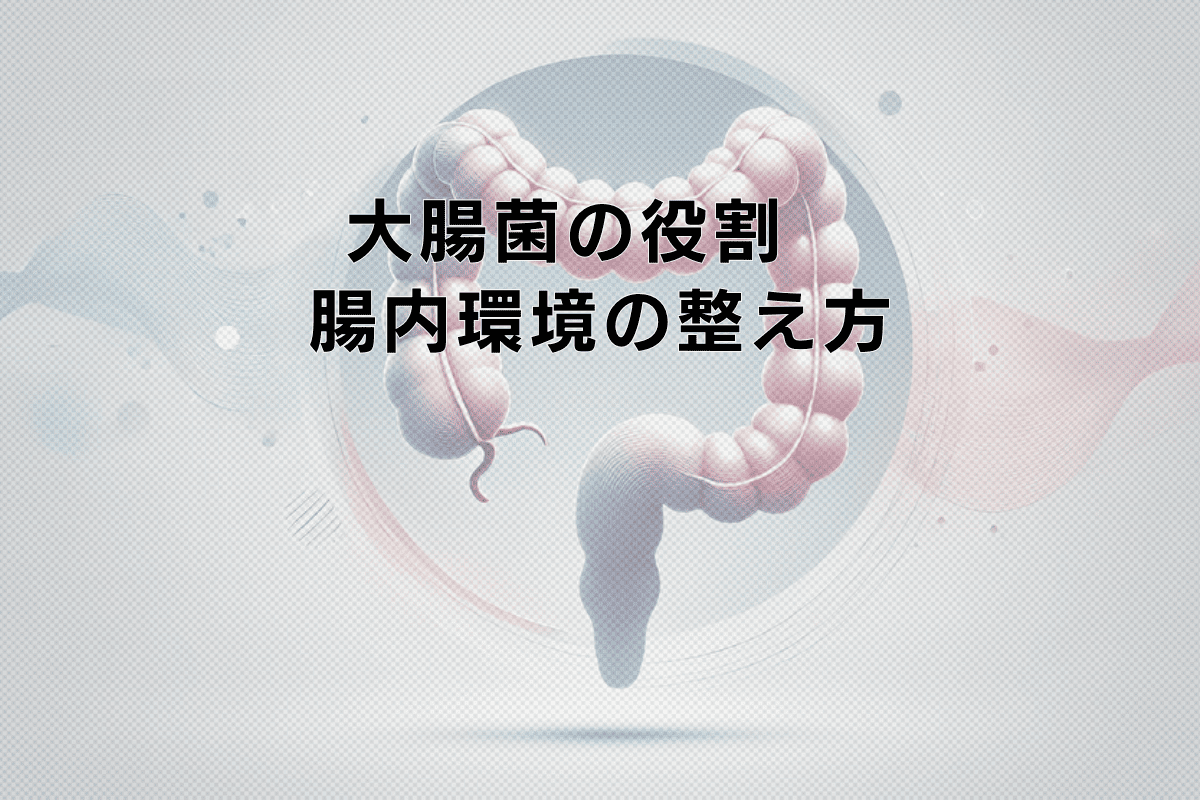
自律神経の影響
自律神経は交感神経と副交感神経で構成され、消化管の働きに大きく関与し、強いストレスを受けて交感神経が優位になると、腸の蠕動が不規則になり、便通異常が起こりやすくなる点が注目されています。
ストレスをうまく解消し、自律神経のバランスを整えることも症状の改善には大切です。

消化管における水分と塩分の吸収
大腸は水分と塩分の吸収を担う重要な役割をもっています。大腸の機能に障害が生じると、水分調節がうまくいかず、下痢や便秘になりやすくなります。
慢性下痢が続けば脱水症状や電解質異常のリスクが高まり、全身状態にも影響を及ぼす可能性があります。
便通異常を招きやすい腸内環境
| 項目 | 悪化例 | 改善策 |
|---|---|---|
| 腸内細菌バランス | 善玉菌が減少し、悪玉菌が優勢になる | 発酵食品や食物繊維の摂取、善玉菌の補給を考慮 |
| 蠕動運動の乱れ | 早すぎる動きで下痢、遅すぎる動きで便秘を起こす | ストレス管理や適度な運動、生活リズムの整備 |
| 水分再吸収の不調 | 水分吸収が不足し便が水っぽくなる、吸収過多で硬便になる | 十分な水分補給とバランスの良い食生活を意識 |
| 自律神経の崩れ | 過度のストレスや睡眠不足で腸の機能が乱れる | リラックス法や睡眠環境の改善 |
| 食習慣の偏り | 過剰な糖質・脂質摂取で腸粘膜に負担がかかる | ビタミン・ミネラル・食物繊維を意識的に摂る |
腸内環境のコントロールは、便通を安定させるうえで非常に重要で、下痢と便秘が同時に起きる背景には、こうした多面的な要因が絡み合っていると考えてください。
考えられる主な原因
慢性の下痢と便秘を併発している場合は、単純な食べ過ぎや水分不足だけでは説明できない可能性があり、過敏性腸症候群や炎症性腸疾患、大腸がんなど、幅広い病気が隠れている場合もあるため、原因に合わせたアプローチが必要です。
過敏性腸症候群
精神的ストレスや生活リズムの乱れが引き金となって腸の機能が過剰に反応し、便通が乱れる病気で、下痢型・便秘型・混合型などのタイプがあり、混合型の場合には慢性下痢と便秘が交互に起こりやすいのが特徴です。
検査をしても明確な器質的異常が見つからない一方で、長期間にわたり症状が続くことが多々あります。
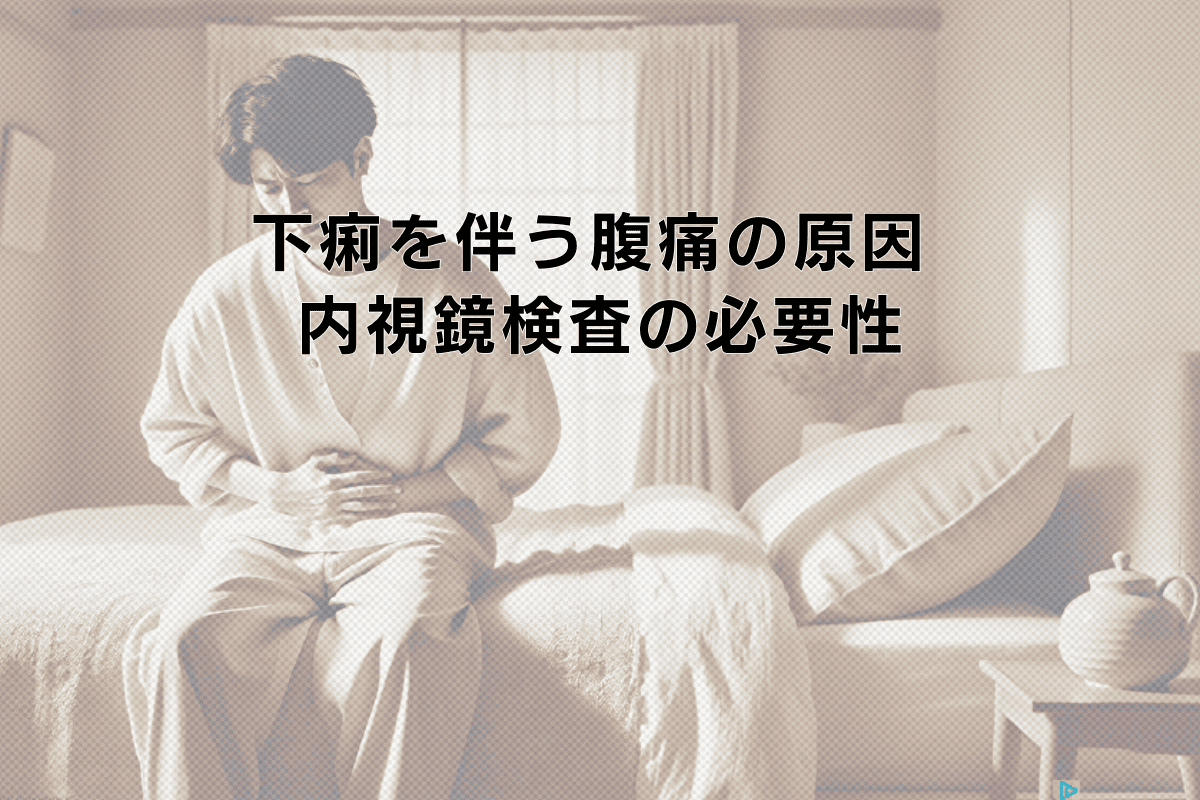
炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎・クローン病など)
腸管に潰瘍や炎症が起こる病気で、腹痛や血便など重い症状が生じやすく、下痢が長期間にわたって続く一方、部分的な腸狭窄や腸の動きの低下で便秘も起こるケースがあります。
炎症が強い場合には、内視鏡検査や血液検査で異常所見が確認されることが多いです。

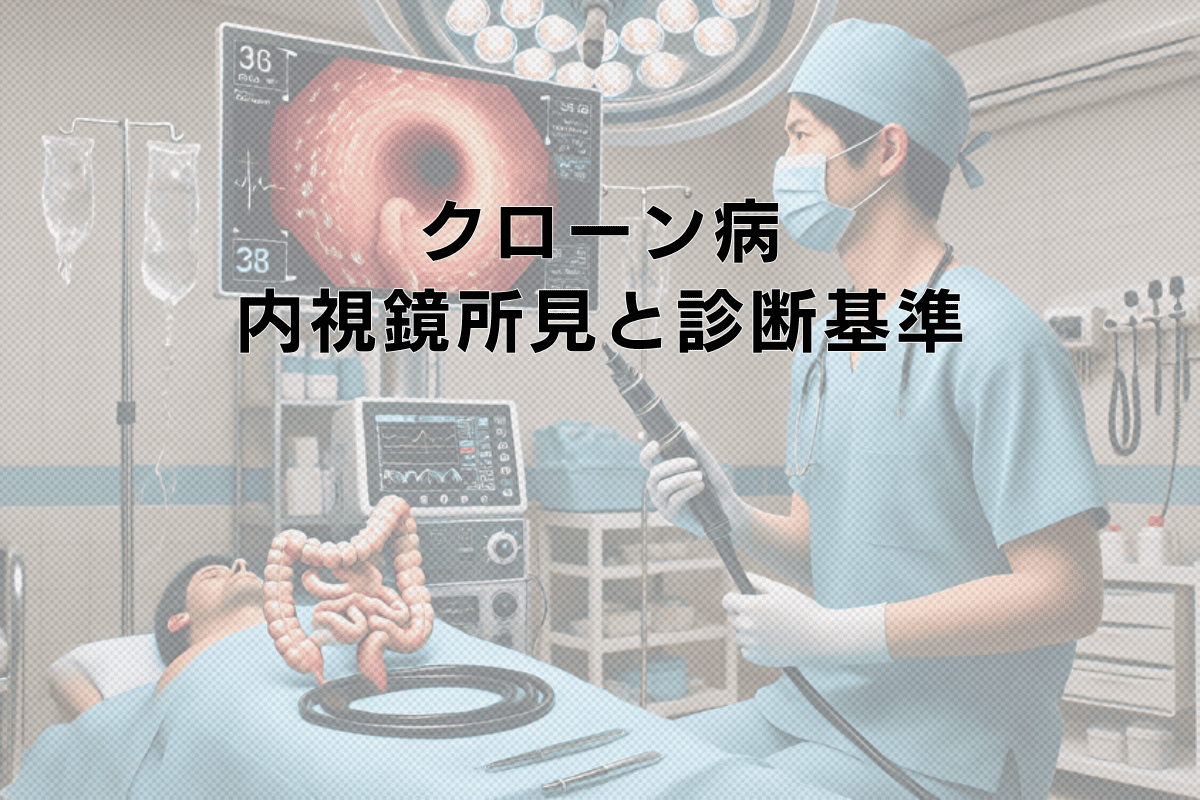
大腸ポリープや大腸がん
大腸ポリープは良性の腫瘍ですが、種類によってはがん化する可能性があり、大腸がんは初期では症状が出にくいこともありますが、進行すると便通異常や血便、体重減少などの症状を伴いやすいです。
便秘と下痢を交互に繰り返す場合でも、大腸内に腫瘍があると通過障害を起こして便が出にくくなったり、一部の腸粘膜が刺激されて下痢を起こすことがあります。
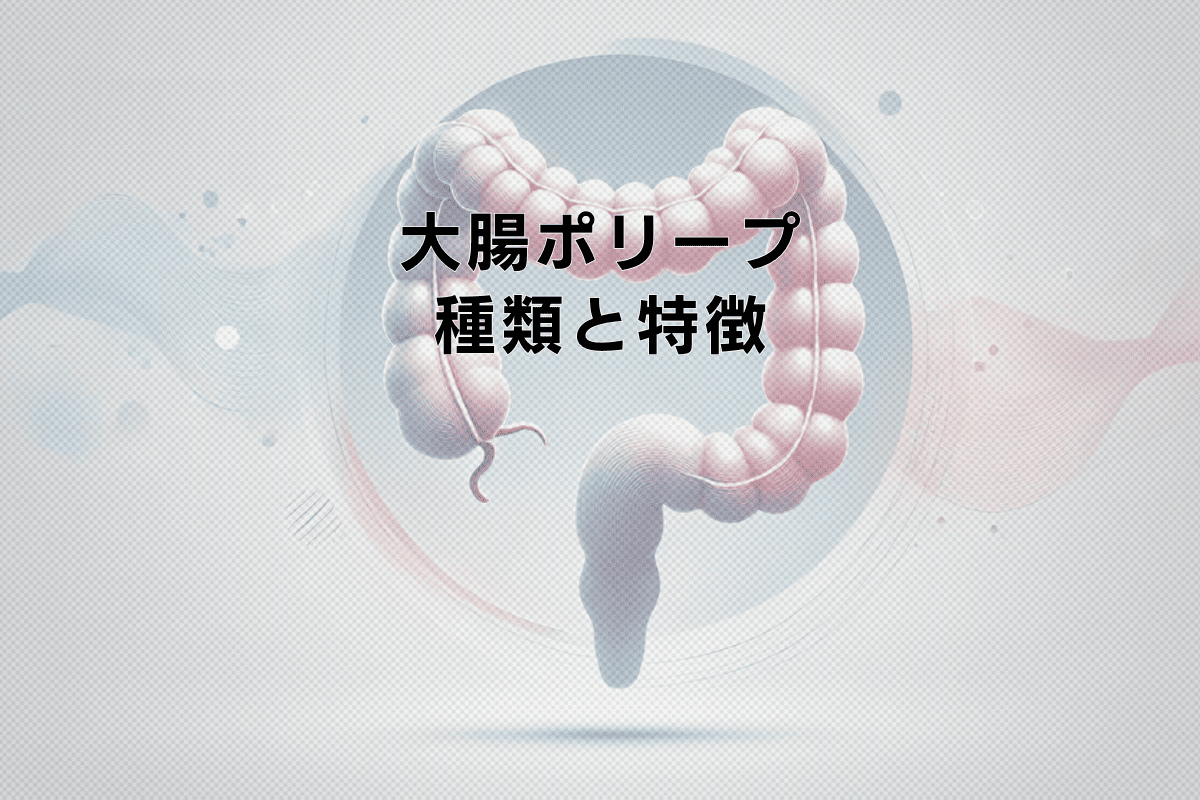
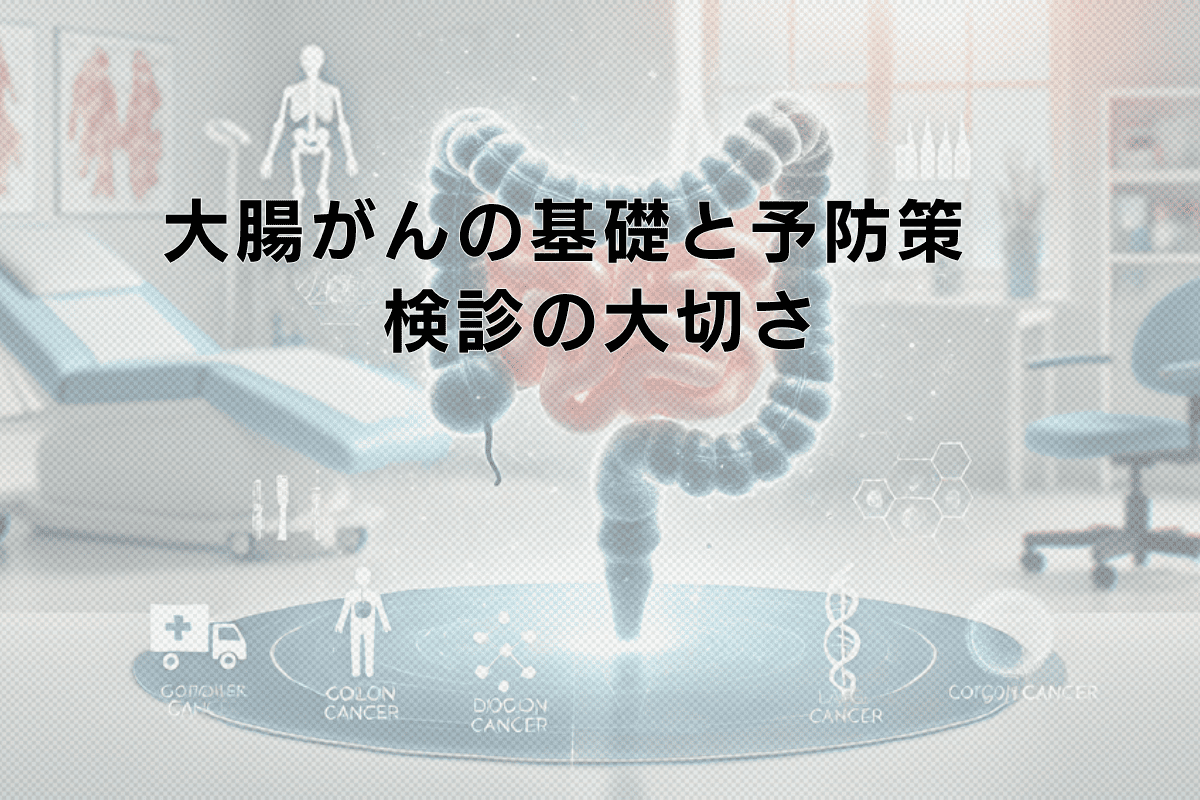
食物アレルギーや吸収不良症
乳製品に含まれる乳糖を分解できない乳糖不耐症や、小麦に含まれるグルテンに対して過敏を示すセリアック病など、特定の食品を摂取すると下痢や便秘が誘発される症例もあります。
食べ物が体質に合っていない場合、腸の蠕動が乱れやすく、慢性的な便通異常を起こすことがあるため注意が必要です。
ホルモンバランスの影響
女性は生理周期や更年期を迎える時期などでホルモンバランスが大きく変化します。
プロゲステロンが増えるタイミングでは腸の動きが緩やかになる場合があり、便秘につながりやすく、また、ストレスや睡眠不足で自律神経の調整がうまくいかなくなることも腸の乱れの要因です。
下痢と便秘を引き起こしやすい代表的な原因
| 原因カテゴリー | 主な例 | 特徴 |
|---|---|---|
| 機能性疾患 | 過敏性腸症候群 | 検査で大きな異常がないのに便通異常が続く |
| 器質的疾患 | 炎症性腸疾患、大腸がん、大腸ポリープなど | 大腸や小腸に異常があり、下痢や便秘が慢性化しやすい |
| 食品関連 | 食物アレルギー、吸収不良症、乳糖不耐症など | 特定の食品を食べると症状が急に強まることがある |
| ホルモン影響 | 女性ホルモンの変動、更年期障害 | 周期的な便秘、下痢の波が出やすい |
| 自律神経の乱れ | 過度のストレス、睡眠不足、うつ状態など | 腸の動きが過剰になったり低下したりしやすい |
原因をしっかり把握することで、対策や検査方法を検討できます。
受診の目安と検査方法
下痢と便秘の混在が断続的に続き、日常生活に支障をきたすほどの腹痛や不快感がある場合、早めに医療機関を受診してください。
受診の目安
- 便の状態が日常的に水っぽく、あるいは極端に硬くなっている
- 1か月以上続く便通異常
- 腹痛や下血、強い吐き気を伴う場合
- 夜間に何度もトイレに駆け込むほど症状がつらい場合
- 体重の急激な減少や発熱など、全身状態の悪化が見られる場合
上記のような状態が続くなら、一度専門医への相談を検討し、排便回数や便の状態を記録しておくと、受診の際の参考資料になります。
大腸内視鏡検査(大腸カメラ)
大腸内視鏡検査は肛門から内視鏡を挿入し、大腸全体や一部の小腸の状態を直接観察する検査です。粘膜の炎症や潰瘍、ポリープ、がんなどの異常を見つけることが可能で、必要に応じて組織の一部を採取する生検も行えます。
慢性下痢や便秘が続く場合、大腸カメラで腸内を確認することは重要な判断材料です。

胃カメラ検査
下痢と便秘を繰り返す状態が胃や十二指腸のトラブルと関連している可能性もあり、胃カメラ検査では、口や鼻から内視鏡を挿入して食道・胃・十二指腸を観察します。
潰瘍や炎症、腫瘍などが見つかれば、下痢の原因となる消化器疾患を疑えます。

便潜血検査や便培養検査
消化管からの出血が疑われるときには便潜血検査を実施することで、腸内出血の有無を確認でき、また、慢性の下痢が細菌感染や寄生虫感染の可能性もある場合には、便培養検査で病原体を特定することもあります。
これらは侵襲性が低い検査なので、比較的手軽に実施できることがメリットです。

主な検査と特徴
| 検査項目 | 概要 | 目的 |
|---|---|---|
| 大腸内視鏡検査 | 肛門から内視鏡を挿入して大腸内を直接観察 | ポリープやがん、炎症など器質的異常の発見や生検が可能 |
| 胃カメラ検査 | 胃や十二指腸を観察し、潰瘍や炎症、腫瘍などを確認 | 胃・十二指腸の疾患が下痢の原因かどうかを把握 |
| 便潜血検査 | 便中に血液が混ざっていないかを調べる | 消化管出血の有無や大腸がんのスクリーニング |
| 便培養検査 | 便を培養して細菌や寄生虫などの感染源を特定する | 細菌・寄生虫感染が原因の下痢を見分ける |
| 血液検査 | 炎症反応や貧血状態、電解質バランスなどを確認 | 炎症性疾患や栄養状態の把握、全身状態の評価 |
症状や医師の判断によって、上記の検査を組み合わせて行う場合があり、いずれの検査も、慢性的な便通異常を解明する重要な手段です。
日常生活で気をつけたいポイント
慢性下痢と便秘を繰り返す症状を和らげるには、医療機関での検査や治療と合わせて、日常生活の見直しが大切です。食生活・運動・ストレスケアなど、基本的な生活習慣に注目すると改善の手がかりが得られるかもしれません。
食事のタイミングと内容
朝昼晩の食事タイミングが不規則だと、腸のリズムも乱れやすくなり、決まった時間に朝食をしっかり摂ることで、大腸の蠕動運動をスムーズに促すことが期待できます。
消化に悪い高脂肪食や刺激の強い香辛料などは腸を刺激するため、症状がひどいときは避けたほうが良いでしょう。
水分補給
便秘を避けるには適度な水分摂取が大切ですが、下痢が続いている場合には経口補水液などで電解質を補給しながら脱水を防ぐことも考慮してください。
コーヒーやアルコールには利尿作用があり、かえって水分不足を招くリスクもあるので注意が必要です。
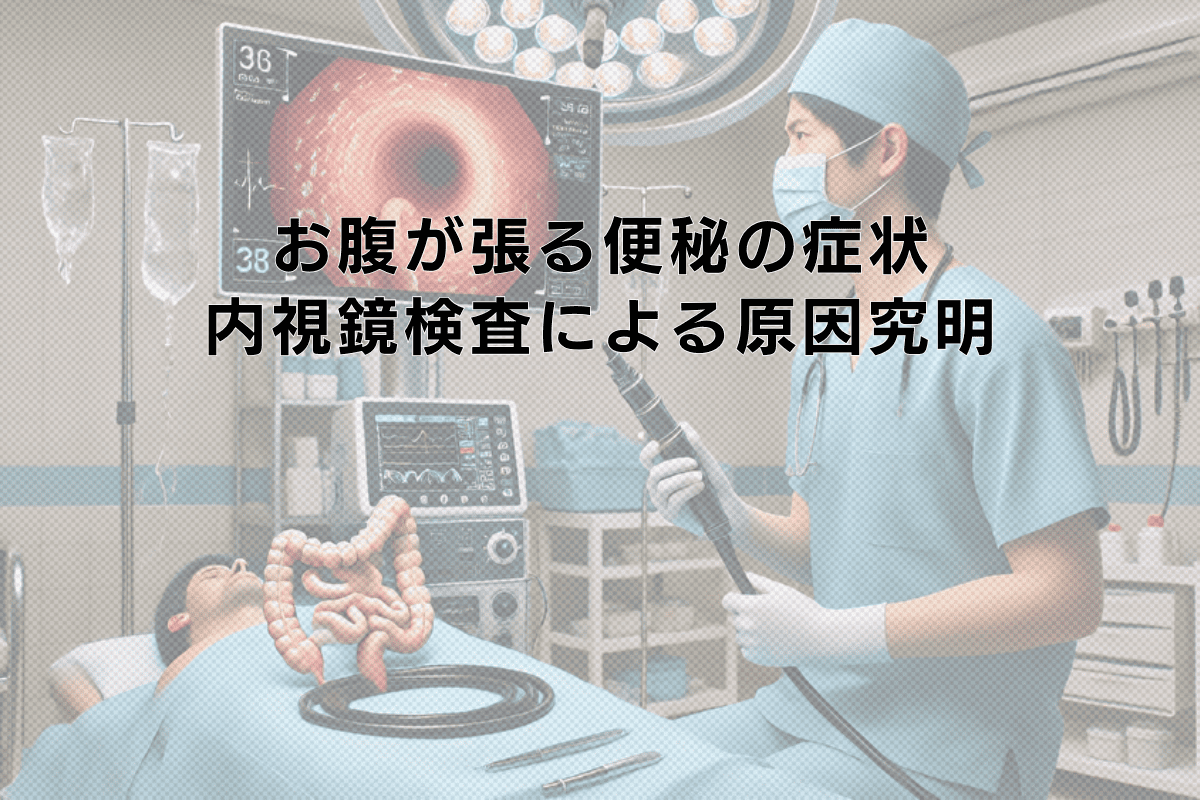
適度な運動
ウォーキングやストレッチなど、軽い運動を続けると腸の働きが活性化して便通のリズムが整いやすくなり、運動不足が続くと腹筋が弱まり、便を押し出す力が低下するので、特に便秘がちの方には運動の習慣化が役立ちます。
ストレスマネジメント
腸はストレスに敏感な器官で、仕事や家事、育児などで心身の負担が大きいと、腸が過度に反応して下痢や便秘を起こしやすくなります。趣味やリラクゼーション、十分な睡眠時間の確保など、ストレスを軽減する方法を工夫してください。
下痢と便秘を繰り返す場合の生活習慣のヒント
- 毎日決まった時間に食事をとる
- 食物繊維や発酵食品を意識して摂る
- 寝る前のスマホ使用を控え、十分な睡眠を確保する
- 軽い体操やウォーキングなどを習慣にする
- 一人で悩まず医師や栄養士に相談する
生活面を見直し、体質改善に向けて少しずつ取り組むことが症状の安定に結びつくことが多いです。
食品選びのポイント
| 食品分類 | 例 | 便通への影響 |
|---|---|---|
| 水溶性食物繊維 | りんご、バナナ、オクラ、海藻類 | 腸内環境を整え、便を柔らかく保ちやすい |
| 不溶性食物繊維 | 玄米、全粒粉パン、ブロッコリー、きのこ類 | 便のかさを増やして排便を促しやすくする |
| 発酵食品 | ヨーグルト、納豆、味噌、キムチ | 善玉菌を増やし腸内のバランスをサポート |
| 脂質の多い食品 | 揚げ物、バター、濃厚な生クリーム | 過剰に摂ると腸を刺激して下痢を誘発しやすい |
| 刺激物 | 香辛料、アルコール、炭酸飲料、濃いコーヒー | 腸の蠕動を急激に高めて下痢を起こしやすい |
食事制限に強いストレスを感じるようなら、無理せず医師や管理栄養士と相談して進めると安心です。
食生活の改善とセルフケア
食事のコントロールとあわせて、腸に優しいセルフケアを行うと、慢性下痢と便秘の繰り返しをやわらげやすくなり、少しの心がけで腸内環境に良い影響を与えられる方法をいくつか紹介します。
小まめな食事回数
1度に大量に食べると腸に大きな負担がかかり、下痢を誘発しやすくなり、逆に食事を控えすぎると便が形成されにくく、便秘につながるリスクがあります。
1日に3度の食事に加え、小腹が空いたときに軽食をとるなど、身体の状態に合わせて小まめに栄養を補給する方法も検討してください。
朝の水分補給
起床後にコップ1杯の水を飲むと、腸を刺激して排便を促す効果が期待でき、冷たい水が苦手なら、白湯や常温の水でも十分に腸を刺激します。習慣化すれば朝の便通がスムーズになる場合があるため、試してください。
食事の取り方に関する心得
- 朝食を抜かずにしっかり食べて腸を動かす
- 暴飲暴食や急激なダイエットは腸に負担がかかる
- ゆっくりよく噛んで食べ、胃腸の負担を軽減する
- 食後すぐに横になるより、軽い散歩や家事で身体を動かす
- カフェインやアルコールの摂取量を見直す
マッサージやストレッチ
便秘が続くときは、腹部をやわらかくマッサージして腸の動きを助ける方法があり、仰向けに寝て『の』の字を描くようにおへそ周りをさするやり方が代表的です。
また、軽いストレッチや体操で腹筋や背筋を刺激し、腸の蠕動をサポートするといった工夫も役立ちます。
腹式呼吸
精神的なリラックス効果を得ながら腸を刺激する方法として、腹式呼吸があります。息をゆっくり吸い込みながらお腹を膨らませ、吐くときはお腹をへこませるように意識してください。
呼吸を整えて自律神経の乱れを和らげることが期待できるでしょう。
体操やストレッチ
| 運動・ストレッチ | 方法 | 効果 |
|---|---|---|
| 腹部マッサージ | 仰向けに寝て、おへそ周りを時計回りにやさしくさする | ガスや便を動かして排出を助ける |
| お尻上げ体操 | 仰向けで膝を立て、腰を持ち上げて10秒ほどキープする | 骨盤周辺の血流改善と腸の蠕動刺激 |
| 膝抱えストレッチ | 仰向けで両膝を抱え、胸に近づけるようにして数秒キープする | 腰回りをほぐし、便の通過をサポート |
| ウォーキング | 1日20~30分程度の速足で歩く | 全身の血流促進とストレス解消 |
| 腹式呼吸(呼吸法) | お腹を大きく膨らませてから、ゆっくりと口から息を吐き出す | 自律神経の調整とリラックス効果 |
セルフケアを続けながら症状の変化を観察し、明らかな改善が感じられない場合は医療機関を受診して専門的なアドバイスをもらうと安心です。
内視鏡検査や大腸カメラを検討する意義
慢性的に便通異常が続くとき、特に下痢と便秘が交互に起きる場合は、大腸や消化器官の状態を直接目で確認する検査が大切になる可能性があります。
検査を敬遠する方もいますが、長期の下痢・便秘に隠れた病気を見逃さないためには、内視鏡検査を早めに検討する意義が大きいです。
大腸カメラでの診断の重要性
大腸カメラでは、大腸の粘膜を詳細に観察でき、炎症やポリープが見つかれば、その場で組織を採取し、病理検査に回すことも可能です。
大腸がんや炎症性腸疾患など、放置するとリスクが高まる病気を早期に発見できる利点があり、慢性下痢や便秘で悩む人の中には、実は腸内に病変があったというケースも少なくありません。
胃カメラとの併用
下痢の原因が胃や十二指腸の潰瘍やポリープなど上部消化管にある場合もあるので、腹痛や食欲不振などがある方は、医師の判断により胃カメラと大腸カメラを同時に受けることが検討されます。
短期間で上下部消化管を一度にチェックできるメリットもある一方、検査時の負担などを考慮して医師と相談して決めると良いでしょう。
内視鏡検査でわかることとメリット
- 腸内の炎症、潰瘍、ポリープ、出血の有無が直接確認できる
- 生検により細胞レベルでの病理診断が可能
- 原因不明だった腹痛や下痢・便秘の背景を明確にできる
- 初期の大腸がんやポリープを早期発見できる
- 画像資料を残すことで治療経過を追いやすい
内視鏡検査の前準備
大腸カメラの場合は、腸内を洗浄してきれいにしてから検査を行い、検査前日から食事内容を軽めにしたり、下剤を使用したりする手間がかかります。
初めて受ける方は不安を感じるかもしれませんが、スムーズに進めるために医療スタッフからの説明をしっかり聞き、不明点を解消しておくことが大切です。
受診後のフォローと治療方針
検査結果をもとに、薬物治療や生活習慣指導などが行われます。炎症が見つかった場合には、ステロイドや免疫調整薬などが処方されることもあります。
ポリープや腫瘍が発見された場合は、必要に応じて切除や専門病院での治療につながる場合もあります。
大腸カメラ検査の流れ
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| 問診・診察 | 症状や病歴を医師と確認し、検査の必要性と方針を検討 |
| 前日準備 | 食事制限と下剤の服用で腸内を洗浄し、便を出し切る |
| 検査当日 | 病院で再度下剤や腸管洗浄剤を使用し、カメラを挿入して検査する |
| 検査結果 | 異常が見つかれば組織検査や切除、追加検査が行われる |
| アフターケア | 検査後の安静や帰宅後の過ごし方、食事などに関する説明を受ける |
一時的な不安や手間があっても、身体に重大な病気を抱えていないかを調べることは、今後の健康維持にとって大切です。
よくある質問
慢性下痢と便秘が入り交じる症状について、多くの方が抱える疑問をいくつか取り上げます。自己判断だけで放置するよりも、適切な情報をもとに専門家へ相談するほうが早期の解決につながりやすいです。
- 便がやわらかい日と硬い日が交互にあるのは珍しくないですか?
-
軽度の症状なら珍しくないケースです。食べ過ぎや一時的なストレスなどで腸の動きが乱れ、一過性に便の性状が変わることはよくあります。
しかし、これが長期間続く、腹痛が激しいなどの要素が加わるなら、何らかの疾患の可能性を考えるべきです。
- 市販の下剤や止瀉薬で対応していいのでしょうか?
-
市販薬で一時的に症状を緩和するのも悪くはありませんが、慢性化している場合や原因不明の症状がある場合、医師による診断が必要です。
市販薬を続けて使うことで症状を悪化させるリスクもあるため、自己判断に頼りすぎないように気をつけてください。
- 食事制限をすれば良くなりますか?
-
食事制限だけで改善する場合もあれば、それだけでは不十分なこともあり、食物アレルギーや腸内環境の乱れが背景にある場合、適切な診断と生活習慣の総合的な見直しが欠かせません。
栄養バランスを崩しすぎないよう、医療機関や管理栄養士に相談して食事内容を調整すると効果的です。
- 大腸カメラは痛みが強いと聞きますが、受けるべきですか?
-
苦痛を感じにくい麻酔や鎮静薬を使った検査を行う医療機関も増えていて、痛みが不安ならその旨を医師に伝え、鎮静下での検査を検討してください。
慢性的な症状で原因がはっきりしない場合、大腸カメラは原因究明のために有用な選択肢です。
次に読むことをお勧めする記事
【大腸内視鏡検査の3日前からの食事制限と準備】
慢性下痢と便秘の基本を押さえたら、次は実際の大腸内視鏡検査の準備について知っておくと安心です。検査を受ける予定の方や将来的に検査を検討されている方に特に参考になる内容です。
【腸の健康が体を支える 腸内環境を整える】
便通だけでなく全身の健康に直結する腸内環境。食事・運動・睡眠など多面的に整える方法を紹介する本記事で、根本的な体質改善を目指しましょう。
参考文献
Ono M, Kato M, Miyamoto S, Tsuda M, Mizushima T, Ono S, Nakagawa M, Mabe K, Nakagawa S, Muto S, Shimizu Y. Multicenter observational study on functional bowel disorders diagnosed using Rome III diagnostic criteria in Japan. Journal of Gastroenterology. 2018 Aug;53:916-23.
Oshima T, Miwa H. Epidemiology of functional gastrointestinal disorders in Japan and in the world. Journal of neurogastroenterology and motility. 2015 Jul 3;21(3):320.
Ihara E, Manabe N, Ohkubo H, Ogasawara N, Ogino H, Kakimoto K, Kanazawa M, Kawahara H, Kusano C, Kuribayashi S, Sawada A. Evidence-based clinical guidelines for chronic diarrhea 2023. Digestion. 2024 Dec 9;105(6):480-97.
Matsumoto Y, Nadatani Y, Otani K, Higashimori A, Ominami M, Fukunaga S, Hosomi S, Kamata N, Kimura T, Fukumoto S, Tanaka F. Prevalence and risk factor for chronic diarrhea in participants of a Japanese medical checkup. JGH Open. 2022 Jan;6(1):69-75.
Kawamura Y, Yamamoto S, Funaki Y, Ohashi W, Yamamoto K, Ozeki T, Yamaguchi Y, Tamura Y, Izawa S, Hijikata Y, Ebi M. Internet survey on the actual situation of constipation in the Japanese population under 70 years old: focus on functional constipation and constipation-predominant irritable bowel syndrome. Journal of gastroenterology. 2020 Jan;55:27-38.
Kurokawa S, Kishimoto T, Mizuno S, Masaoka T, Naganuma M, Liang KC, Kitazawa M, Nakashima M, Shindo C, Suda W, Hattori M. The effect of fecal microbiota transplantation on psychiatric symptoms among patients with irritable bowel syndrome, functional diarrhea and functional constipation: an open-label observational study. Journal of affective disorders. 2018 Aug 1;235:506-12.
Browning SM. Constipation, diarrhea, and irritable bowel syndrome. Primary Care: Clinics in Office Practice. 1999 Mar 1;26(1):113-39.
Lacy BE. Diagnosis and treatment of diarrhea-predominant irritable bowel syndrome. International journal of general medicine. 2016 Feb 11:7-17.
Jamshed N, Lee ZE, Olden KW. Diagnostic approach to chronic constipation in adults. American family physician. 2011 Aug 1;84(3):299-306.
Talley NJ, Dennis EH, Schettler-Duncan AV, Lacy BE, Olden KW, Crowell MD. Overlapping upper and lower gastrointestinal symptoms in irritable bowel syndrome patients with constipation or diarrhea. Official journal of the American College of Gastroenterology| ACG. 2003 Nov 1;98(11):2454-9.










