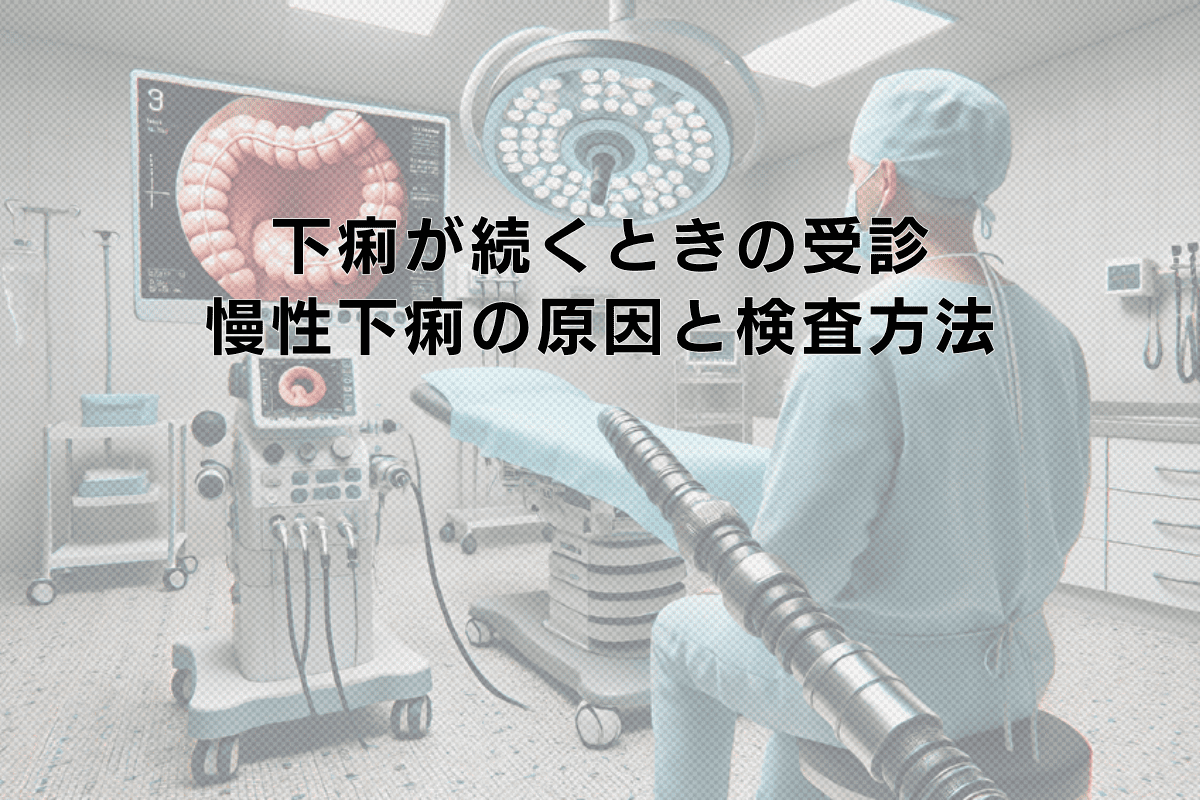下痢が長引くと普段の生活を妨げるだけでなく、体調面や栄養状態にも悪影響が出やすくなり、仕事や家事、外出などにも支障をきたし、精神的にも大きな負担となることがあります。
長期間おなかの調子が整わないと、腸の病気が隠れている可能性がありますので、早めに専門の医療機関を受診し、きちんと原因を探ることが大切です。
本記事では、下痢が続く場合の受診目安や考えられる原因、検査方法を詳しく解説します。
下痢が続く状態とは
長期間にわたって下痢が止まらないと、体力が落ちやすいだけでなく、別の合併症が起こるリスクも高まります。とくにずっと軟便や水様便が続いている場合は、急性ではなく慢性化した可能性があります。
ここでは、下痢が慢性化する定義や特徴、体内で起こっているメカニズムなどを確認しながら、長引く症状の位置づけを把握しておきましょう。

一般的な下痢と慢性下痢の違い
食べ過ぎやストレス、ちょっとした胃腸炎などが原因で下痢になることは日常でもよくあるもので、多くは数日~1週間ほどで治まり、特別な治療を受けなくても自然に回復するケースが多いです。
一方、3週間から1か月以上続くような状態は慢性下痢と呼ばれ、検査を行い原因を調べる必要が高まり、短期間の不調とは異なり、長期的な経過観察が必要になります。
ずっと軟便や水様便が続く場合
ゆるい便が長期にわたる状態は体内の水分と電解質のバランスにも影響を与え、皮下や筋肉に必要な水分が不足しやすくなり、倦怠感や脱力感が目立つようになることもあります。
ずっとゆるい便が続く場合、食事や生活習慣だけでなく、腸の機能低下や腸内環境の変化など多角的な観点でアプローチが必要です。
腸内環境の変化と下痢の関連
下痢が慢性化する要因の1つに、腸内環境の乱れがあり、腸内にいる善玉菌が減少し、有害な菌が増えると便が水っぽくなったり、おなかの痛みを伴うこともあります。
加えて、ストレスなどで腸の蠕動運動が乱れると、水分吸収が不十分になり、ゆるい便が続く可能性があります。
受診時に把握しておきたいポイント
長期化している下痢について医療機関を受診するときは、自分の症状を整理しておくと診断がスムーズです。
下痢が始まった時期や便の状態、痛みや発熱の有無、食生活や服薬状況などをメモしておくと診察で役立ち、より正確な情報が得られれば、原因を特定しやすくなり、必要な検査の計画も立てやすくなります。
下痢の持続期間と可能性
| 下痢の期間 | 主な可能性 | 対応の方向性 |
|---|---|---|
| 数日~1週間程度 | 急性胃腸炎、感染症、食あたりなど | 水分補給や消化に良い食事 |
| 2週間前後 | 細菌性腸炎、ウイルス性腸炎など | 症状や培養検査による診断 |
| 3週間~1か月以上 | 慢性下痢(機能性・炎症性など) | 内科や消化器科で精査 |
| 数か月以上 | 慢性炎症性腸疾患、過敏性腸症候群など | 検査や治療を継続的に検討 |
慢性下痢の原因
長期間にわたって下痢が続く原因は多岐にわたり、感染症由来の場合もあれば、自己免疫疾患や食事内容が影響していることもあり、医師による総合的な診断が不可欠です。
ここでは、代表的な原因について概要を押さえ、受診時に思い当たる要因がないかを洗い出してみることを提案します。
過敏性腸症候群(IBS)
ストレスや不安などの心理的要因が腸の運動を乱し、慢性的な下痢や便秘を繰り返す病態で、仕事や人間関係で緊張状態が続く方に多く見られます。
重症化すると日常生活に支障が出るだけでなく、食事面でも制限が出たり、外出が不安になるなどの問題が生じます。
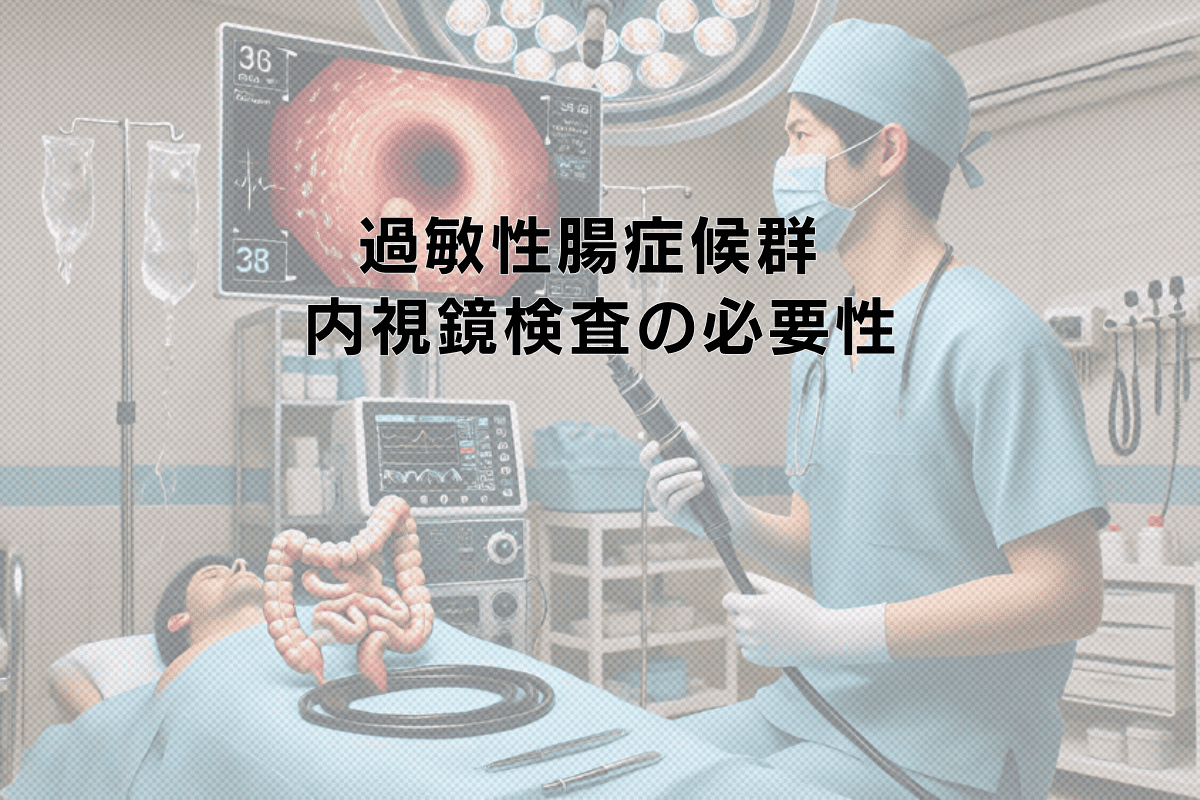
潰瘍性大腸炎やクローン病など炎症性腸疾患
腸の粘膜に慢性的な炎症が起こる病気で、下痢や血便、腹痛などが持続することがあり、潰瘍性大腸炎は主に大腸が、クローン病は小腸から大腸まで広範囲が炎症の対象となります。
体重減少や貧血など全身症状を伴うことも多く、内視鏡検査による早期発見と治療方針の確立が重要です。

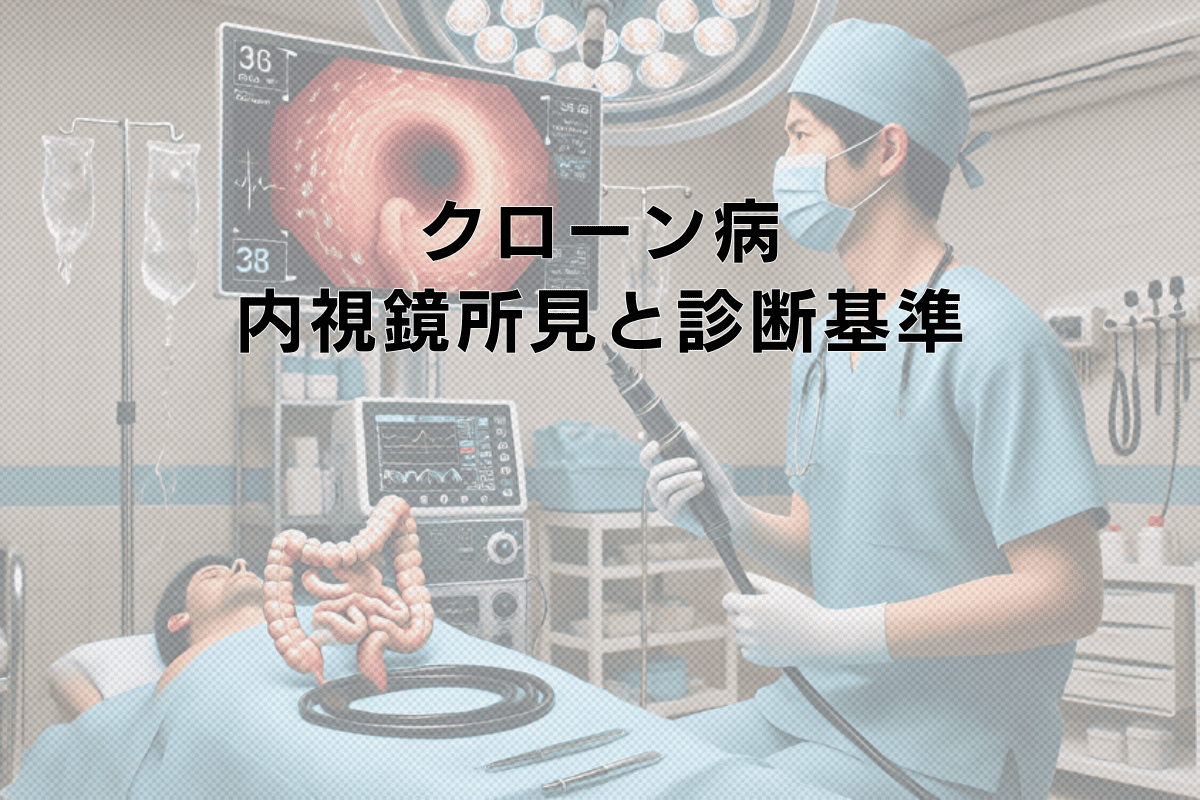
甲状腺機能亢進症やホルモンバランス異常
甲状腺機能亢進症(バセドウ病など)は、新陳代謝が異常に活発になることで下痢を起こす場合があり、また、ホルモンバランスの乱れは腸の蠕動運動に影響を与えやすく、他の慢性疾患と併発しているケースも見られます。
血液検査などでホルモンの状態をチェックする意義も大きいです。
薬剤性の下痢
抗生物質や下剤、特定のサプリメントなど、薬の影響で下痢が慢性的に起こる場合があります。
薬の使用を中止または変更することで改善が見られるケースもあるため、自己判断で薬をやめる前に必ず処方元の医師や薬剤師に相談すると安心です。
慢性下痢の原因
| 原因 | 主な特徴 | 検査・診断方法 |
|---|---|---|
| 過敏性腸症候群(IBS) | ストレスで症状が増悪、便通異常が断続的に続く | 問診、生活背景、除外診断 |
| 炎症性腸疾患 | 血便や腹痛を伴い、腸内に炎症が起こりやすい | 内視鏡検査、大腸生検、画像検査など |
| 甲状腺機能亢進症 | 代謝亢進による動悸や発汗、便通異常 | 血液検査(甲状腺ホルモン値) |
| 薬剤性の下痢 | 服用中の薬が原因となり下痢を誘発 | 医師や薬剤師への相談、服薬情報の確認 |
食事と生活習慣の影響
長期間おなかの不調が続く方の中には、食事内容が偏っているケースもあり、刺激物やアルコール、カフェインの多量摂取が下痢を起こしやすくなることはよく知られています。
さらに、過度なダイエットや栄養バランスの乱れも腸の機能を低下させる一因です。生活習慣の見直しも並行して進めると、症状の軽減につながる可能性があります。
下痢が続くときに考慮したい症状の特徴
慢性的な下痢は、多くの場合、単に便がゆるいだけでなく、他の症状が伴うことが少なくありません。下痢に加えて、発熱や腹痛、血便などがあるかないかで、疑われる病気の方向性が大きく変わります。
腹痛やおなかの張り
下痢が続くとき、おなか全体に鈍い痛みがある場合や、特定の部分が差し込むように痛む場合があり、差し込む痛みは小腸や大腸の一部に強い炎症や刺激が起きているサインかもしれません。
また、おなかの張りを強く感じるときはガスがたまりやすくなっている可能性もあるため、食物繊維の摂り方など日常的なケアが必要となることがあります。
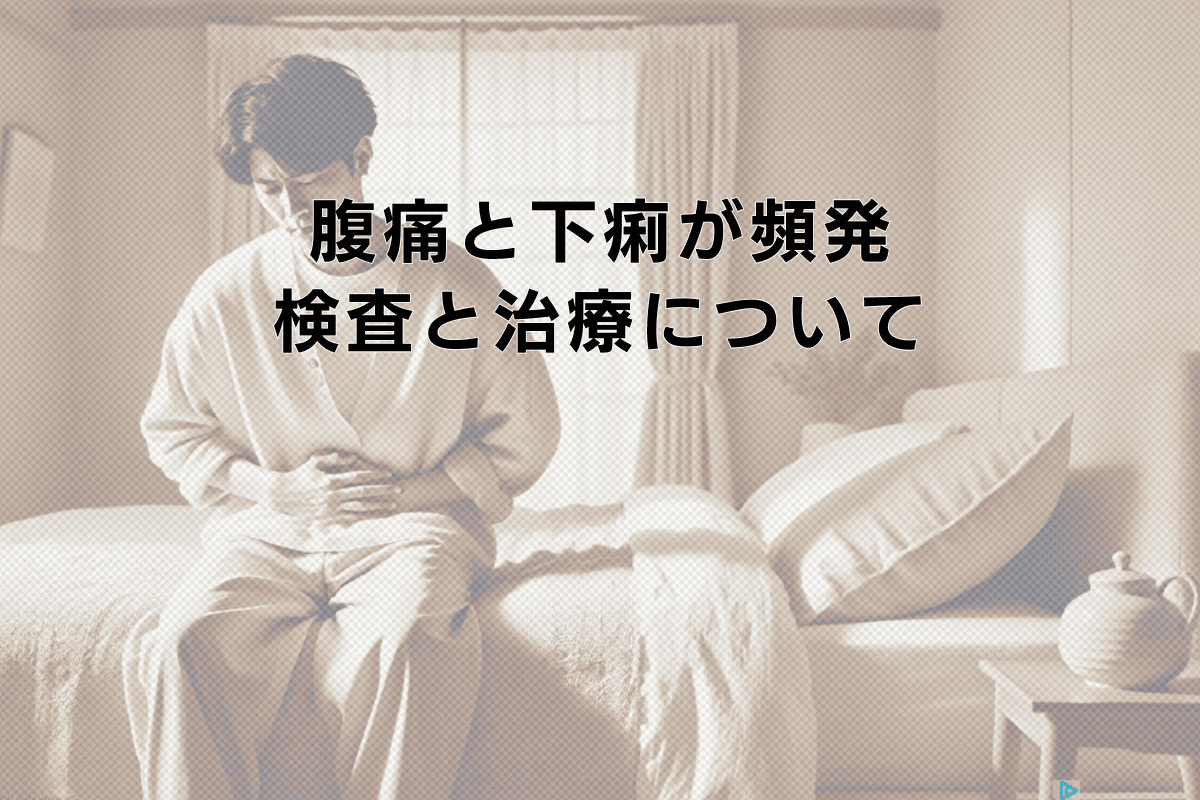
血便やタール便
便に血が混じる場合は、大腸の粘膜などに傷があるか、潰瘍ができていることが考えられます。
真っ赤な血便は大腸の下部に近い部分からの出血が疑われ、黒っぽいタール状の便の場合は小腸や胃など上部消化管からの出血が降りてきている可能性があります。このような便が続くときは速やかに医療機関へ相談してください。
発熱や全身倦怠感
下痢に加えて発熱や強い倦怠感があるときは、身体のどこかで炎症や感染が進行している合図となる場合があります。
ウイルスや細菌感染による腸炎も考えられますが、自己免疫疾患などが原因で腸だけでなく他の臓器にも影響が出ているケースも否定できず、状況次第では点滴治療が必要です。
体重減少や食欲不振
長期間の下痢は水分だけでなく栄養素の吸収にも大きな影響を及ぼし、吸収不良が続いて栄養状態が悪化すると、体重が大きく減少し疲れやすさを感じる方が増えます。
タンパク質やビタミン、ミネラル不足が進むと免疫力も低下しやすくなるため、診察を受ける際には体重変動や食欲の有無を詳細に伝えることが重要です。
下痢に伴う症状がある場合のチェック表
| 付随症状 | 疑われる状態・病気 | 受診の優先度 |
|---|---|---|
| 腹痛や下腹部の張り | 過敏性腸症候群、炎症性腸疾患など | 早めの受診が望ましい |
| 血便、タール便 | 大腸ポリープ、潰瘍性大腸炎、消化管潰瘍など | 出血の程度により緊急度大 |
| 発熱、全身のだるさ | 感染性腸炎、炎症性腸疾患、甲状腺異常など | 医療機関への相談が必要 |
| 体重減少や食欲不振 | 吸収不良症候群、重症感染症、自己免疫疾患など | 栄養面でも早い対応が必要 |
受診の目安と注意したいポイント
慢性的な下痢が続くとき、どのタイミングで医療機関を受診するか迷う方は少なくありません。症状が軽いからと放置してしまうと、取り返しのつかない合併症を招く恐れもあります。
3週間以上続く下痢は早めに相談
一般的な目安として、3週間以上ゆるい便や下痢が続く場合は早めの受診が大切です。
3週間を超えても症状が改善しない場合、単なる急性胃腸炎や一時的な食あたりではない可能性が高く、慢性化した背景に何らかの疾患が潜んでいるかもしれません。
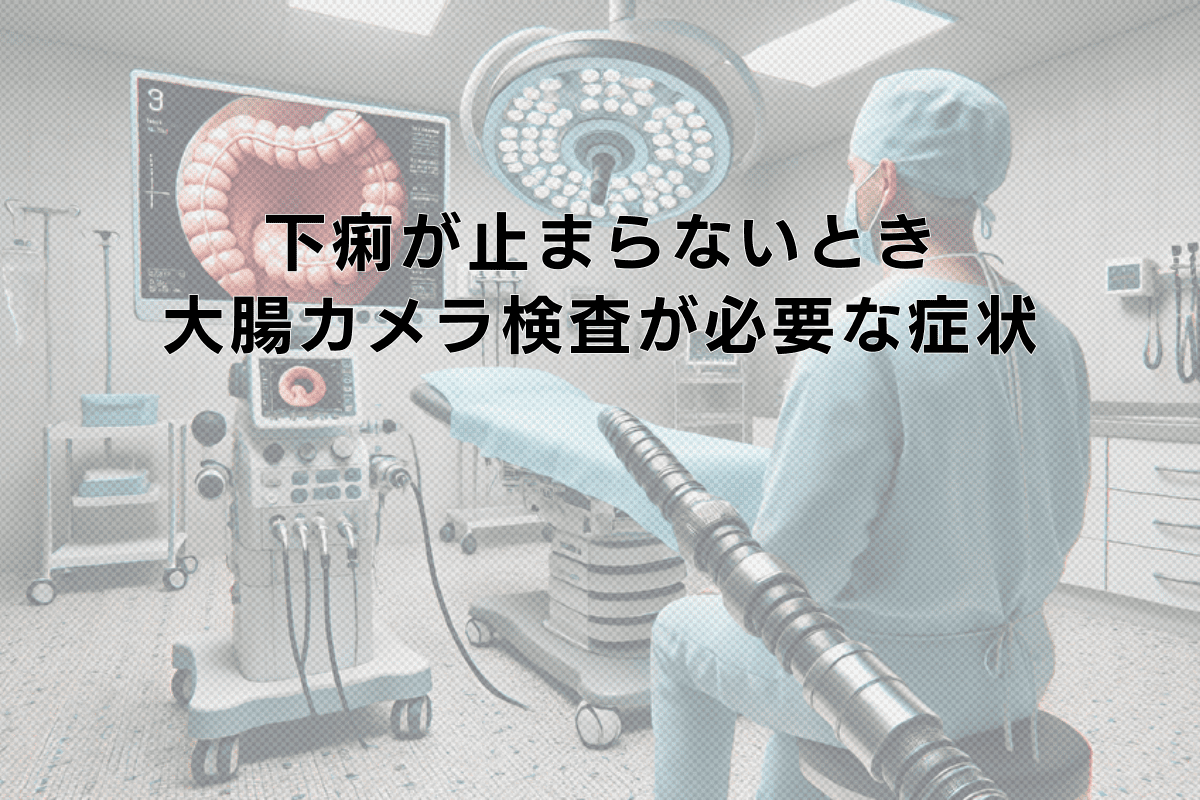
主な情報をスムーズに伝えるための準備
- 下痢の開始時期や最初のきっかけ
- 便の回数と1日の中でのパターン
- 腹痛や血便、発熱などの付随症状
- 食生活や生活リズムの変化
- 現在服用中の薬やサプリメント
情報をあらかじめ記録しておくことで、診察時間を有効に使いやすくなり、医師からの質問にも落ち着いて答えやすいです。
内科か消化器内科か
どの診療科を受診すればよいか判断に迷うケースもあり、一般的には内科を受診し、必要に応じて消化器内科へ紹介されるパターンが多いです。
初診時に血液検査や便検査などを行い、重篤な病気が疑われるときはより専門的な検査を実施します。
緊急性の高い症状
強い腹痛や大量の血便、急激な脱水症状などが見られるときは、早朝や夜間でも迷わず救急受診が選択肢になります。
意識障害やふらつきが出た場合も危険サインとなるため、我慢せず医療機関に連絡したり、周囲の人に助けを求める行動が望ましいです。
診察までのセルフケア
医療機関を受診するまでの間は、水分と電解質の補給が大切で、食事は胃腸に負担をかけない消化の良いものを中心にとり、脂質や糖分の多い食品は控えると症状悪化を予防できます。
ただし絶食を続けると栄養不足に陥るため、医師の診察前であっても可能な範囲でバランスを意識してください。
受診のタイミングと緊急度
| 症状・状況 | 受診のタイミング | 考えられる対応 |
|---|---|---|
| 3週間以上続く下痢 | なるべく早い通院が望ましい | 内科や消化器内科で初期検査 |
| 血便や激しい腹痛がある | 時間帯に関係なく緊急での受診が安心 | 救急外来や当番医に連絡 |
| 脱水症状や意識障害 | 即時の救急対応 | 点滴治療や入院の検討 |
| 軽度の下痢が1週間程度 | 水分補給と安静を優先しつつ経過観察 | 感染性胃腸炎など短期的に回復の可能性 |
慢性下痢の検査方法
下痢が慢性化している場合、医師は問診や症状の経緯を確認した上で、さらに詳しい検査を提案します。特に原因不明の慢性下痢が続く場合には、内視鏡検査(大腸カメラ・胃カメラ)が選択肢です。
大腸カメラ検査
大腸の内壁を直接観察し、炎症や潰瘍、ポリープの有無を調べる検査で、慢性下痢が続くとき、潰瘍性大腸炎やクローン病などの炎症性腸疾患を疑う際に実施されます。
必要に応じて組織を一部採取して病理検査を行うことで、悪性疾患や特異的な病変を早期に発見できることが利点です。

大腸カメラ検査の流れ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 前日準備 | 下剤や食事制限で腸内をきれいにする |
| 当日検査前 | 追加の下剤を飲み、腸内洗浄を行う |
| 検査本番 | 内視鏡を肛門から挿入し、大腸内を観察 |
| 組織採取 | 必要があればポリープなどを生検する |
| 検査後 | 安静と食事の指示に従い、結果を待つ |

胃カメラ検査
下痢が続く原因が胃や十二指腸にある場合もあり、胃カメラ検査が実施されることがあります。ピロリ菌感染や消化性潰瘍が原因で消化不良が起こり、下痢を伴うケースも否定できません。
大腸カメラとあわせて実施するケースもあり、消化管全体の状態を総合的に把握することで治療方針を立てやすくなります。

便検査
便の性状や細菌・ウイルスの有無を調べ、下痢の直接的な原因が感染症や寄生虫などによるものでないかを確認する検査です。
腹痛や発熱を伴う場合に実施されやすく、細菌培養や虫卵検査も含めて詳細に調べることで早期発見と治療につなげられます。
血液検査と画像検査
ホルモン異常や慢性炎症の有無を確認するために、血液検査で白血球数やCRP(炎症マーカー)、甲状腺ホルモン値などを調べることがあります。
また腹部CTやMRIなどの画像検査で腸管壁の肥厚やリンパ節の腫れをチェックし、内視鏡検査だけではわかりにくい病変を捉えることも可能です。
消化管検査の種類と目的
| 検査名 | 主な目的 | 特徴 |
|---|---|---|
| 大腸カメラ | 大腸内の炎症やポリープ、がんなどを直接確認 | 生検やポリープ切除が同時に可能 |
| 胃カメラ | 胃や十二指腸の潰瘍、炎症、がんなどを確認 | ピロリ菌感染のチェックも併せて行いやすい |
| 便検査 | 感染症や寄生虫、血便の有無などを分析 | 採取が簡便で体負担が少ない |
| 血液検査、画像検査 | ホルモン値、炎症反応、臓器の形態異常を把握 | 総合的な身体状態を知るうえで有用 |
日常生活でできる対策
検査や治療を進める一方で、日常生活のケアもとても大切です。慢性的な下痢を改善・緩和するために、食事や生活習慣を見直し、腸にやさしい環境を整えることが有効です。
ここでは、具体的な対策をいくつか提案し、日常的に実践しやすい内容を取り上げます。
食事における注意点
腸に負担をかけやすい食品は、下痢が続いているときには避けます。
脂質や香辛料が多い料理は消化管を刺激しやすく、症状を悪化させる可能性があり、炭酸飲料やカフェインの過剰摂取も腸を刺激するため、少量にとどめてください。
消化しやすいタンパク質としては、豆腐や白身魚、鶏ささみなどがおすすめです。
日常の食事内容
| 食品グループ | 具体例 | 下痢時のポイント |
|---|---|---|
| 炭水化物 | 白米、おかゆ、うどん、パン | 脂質控えめで調理し消化を助ける |
| タンパク質 | 鶏肉(ささみ)、白身魚、豆腐 | 揚げ物ではなく茹でる・蒸す調理法が無難 |
| 野菜・果物 | ニンジン、カボチャ、りんごなど | 加熱して繊維を柔らかくする |
| 乳製品 | ヨーグルト、プロバイオティクス系 | 腸内細菌を整える場合に適度な摂取 |
| 刺激物 | 香辛料、アルコール、カフェイン | 症状がある間はできるだけ控える |
水分補給と電解質のバランス
水分を失いやすい下痢では、こまめな水分補給が欠かせず、水や麦茶、経口補水液などを少量ずつ頻回に摂るよう意識すると、電解質の不足も補いやすくなります。
スポーツドリンクは糖分が多い傾向があるため、飲みすぎないように注意が必要です。
水分と栄養をうまく補うためのポイント
- 1回に大量の水を摂らず、少量を何度も飲む
- 温かいスープやお茶で胃腸への負担を減らす
- 経口補水液は適度に活用し塩分不足を補う
- 脂っこいスープは控えて消化を考慮する
- 飲み過ぎ食べ過ぎを避け胃腸を休ませる時間を持つ
腸内環境を整える取り組み
プロバイオティクス(善玉菌)の含まれた乳酸菌飲料や発酵食品を日常的に取り入れると、腸内環境の改善に役立つ場合があります。
ただし、乳製品でおなかがゴロゴロしやすい方は、無理に摂取せず、納豆や漬物など他の発酵食品を活用する方法もあります。腸内フローラを整えることは下痢だけでなく便秘や肌状態のケアにもつながることが期待されます。

ストレスと睡眠
ストレスや寝不足は腸の蠕動運動を乱し、長引く下痢の要因になることがあります。質の良い睡眠を確保するためには、寝る前のスマートフォン使用を控えたり、照明を落とした落ち着いた環境で過ごすことが大事です。
リラックス法やウォーキングなど、適度な運動を取り入れると自律神経が整い、腸にもやさしい影響が期待できます。
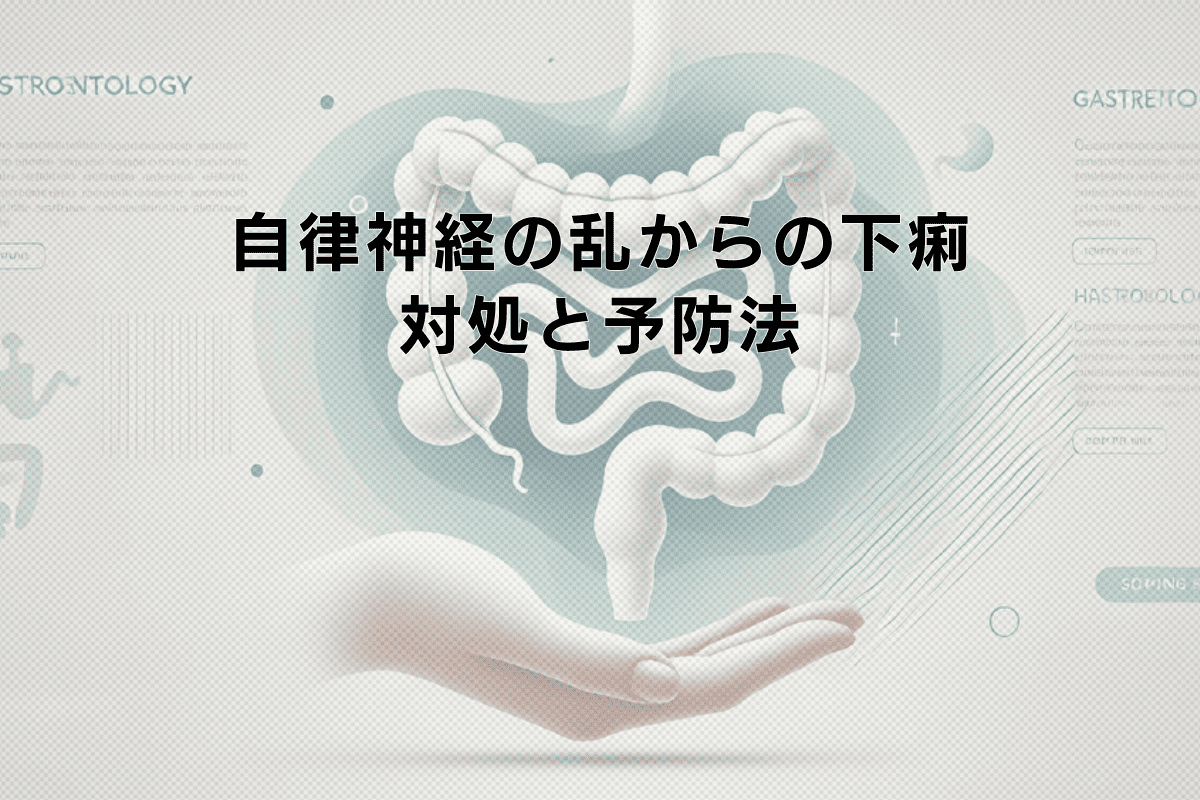
ストレス軽減と腸ケアの相関
| ストレス要因 | 腸への影響 | 軽減のための具体策 |
|---|---|---|
| 過度な仕事量・学業 | 自律神経の乱れで腸機能が低下 | タスク管理の見直しや小休憩を挟む |
| 人間関係のトラブル | ストレスホルモン分泌増で蠕動乱れ | カウンセリングや友人への相談 |
| 睡眠不足 | 免疫力低下とホルモンバランス悪化 | 就寝前のスマホ断ち・睡眠環境の改善 |
| 過剰なカフェイン摂取 | 血管収縮と神経過敏 | カフェインレス飲料やハーブティーへの切り替え |
よくある質問
長引く下痢に関して、多くの方が疑問を持ちやすいトピックをまとめました。
漫然と市販薬を飲んでいたり自己判断で食事制限を行っている方もいらっしゃるかもしれませんが、専門家の診察とあわせて理解を深めることで不安を軽減しやすくなります。
- 食事を全く摂らなければ下痢は治まりますか?
-
極端な絶食は推奨されません。確かに食物を一切摂らなければ便の量は減りますが、同時に栄養不良による体力の低下や免疫力の低下が進む恐れがあります。
おかゆやスープなどの消化にやさしいものを少しずつ摂るほうが長期的には回復につながりやすいです。
- 市販の下痢止めを長期間使用しても大丈夫でしょうか?
-
下痢止め薬は一時的に症状を抑えるには有用ですが、慢性的な症状の原因を根本的に解消するわけではありません。
長期にわたり頻繁に使用すると腸内環境がさらに乱れる可能性もあるため、症状が続く場合は専門の医療機関を受診して原因を特定することが大切です。
- ずっとおなかがゆるいと検査を受ける必要はあるのでしょうか?
-
長期間のゆるい便が続くときは、検査を受ける意義が大きく、特に炎症性腸疾患やホルモン異常など、治療を要する病気が潜んでいる場合は検査でないと発見が難しいことがあります。
放置して悪化すると治療期間や負担が増す可能性もあるため、医師と相談し必要な検査を検討してください。
- 大腸カメラや胃カメラ検査が不安ですがどうしたらよいですか?
-
初めて受ける方は特に不安を感じることが多いです。検査前に医師や看護師に不安点を伝え、鎮静剤の使用などを相談できる場合があります。
また、検査手順や注意事項を事前に理解しておくと心の準備がしやすく、リラックスして受けられる方が多いです。
次に読むことをお勧めする記事
【痛みのない下痢が続くときの大腸カメラ検査の重要性】
慢性下痢の検査方法を押さえたら、実際にどのように検査が行われるのかも知っておくと安心です。鎮静剤使用の有無や当日の流れを具体的に解説しています。
【腸の内視鏡検査で分かること – 検査前の準備から検査後の注意点】
下痢の原因を広く捉えるには、腸全体を評価できる内視鏡検査の基本も知っておくと、今後の健康管理に役立ちます。
参考文献
Ihara E, Manabe N, Ohkubo H, Ogasawara N, Ogino H, Kakimoto K, Kanazawa M, Kawahara H, Kusano C, Kuribayashi S, Sawada A. Evidence-based clinical guidelines for chronic diarrhea 2023. Digestion. 2024 Dec 9;105(6):480-97.
Matsumoto Y, Nadatani Y, Otani K, Higashimori A, Ominami M, Fukunaga S, Hosomi S, Kamata N, Kimura T, Fukumoto S, Tanaka F. Prevalence and risk factor for chronic diarrhea in participants of a Japanese medical checkup. JGH Open. 2022 Jan;6(1):69-75.
Hisabe T, Hirai F, Matsui T, Watanabe M. Evaluation of diagnostic criteria for Crohn’s disease in Japan. Journal of gastroenterology. 2014 Jan;49:93-9.
Iida H, Inamori M, Sekino Y, Sakamoto Y, Yamato S, Nakajima A. A review of the reported cases of chronic intestinal pseudo-obstruction in Japan and an investigation of proposed new diagnostic criteria. Clinical journal of gastroenterology. 2011 Jun;4:141-6.
Oshima T, Miwa H. Epidemiology of functional gastrointestinal disorders in Japan and in the world. Journal of neurogastroenterology and motility. 2015 Jul 3;21(3):320.
Schiller LR, Pardi DS, Sellin JH. Chronic diarrhea: diagnosis and management. Clinical Gastroenterology and Hepatology. 2017 Feb 1;15(2):182-93.
Juckett G, Trivedi R. Evaluation of chronic diarrhea. American family physician. 2011 Nov 15;84(10):1119-26.
Burgers K, Lindberg B, Bevis ZJ. Chronic diarrhea in adults: evaluation and differential diagnosis. American family physician. 2020 Apr 15;101(8):472-80.
Schiller LR. Evaluation of chronic diarrhea and irritable bowel syndrome with diarrhea in adults in the era of precision medicine. Official journal of the American College of Gastroenterology| ACG. 2018 May 1;113(5):660-9.
Donowitz M, Kokke FT, Saidi R. Evaluation of patients with chronic diarrhea. New England Journal of Medicine. 1995 Mar 16;332(11):725-9.