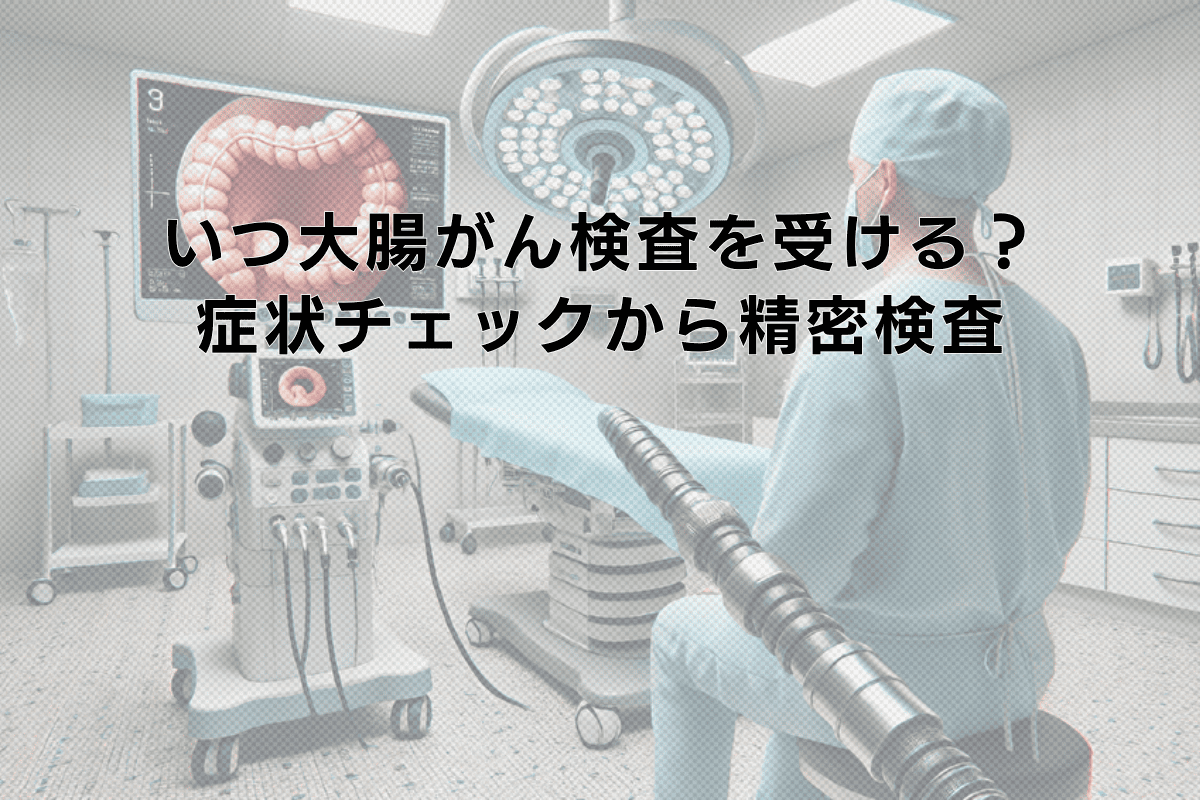大腸がんを心配しながらも、いつ検査を受けるべきか迷う方は多く、便に血が混じっていないか、下痢や便秘が続いていないか、いわゆる大腸がんの症状をチェックしながら過ごすのは不安なものです。
定期的な検査に加えて、ご自身の生活習慣や家族歴を振り返ることも大切です。この記事では、大腸がんを疑うサインから内視鏡検査までの流れをわかりやすくまとめました。
クリニックで行う精密検査の概要や治療方針にも触れているので、早期発見を目指すうえで参考にしてください。
大腸がんとは何か
大腸に発生する悪性腫瘍のことで、日本人のがんの中でも発症率が高く、早期に発見することが重要になってきます。初期に気づきやすい症状があまり多くないため、疑わしい兆候を放置しないことが大切です。
大腸がんの概要
大腸は、食物の消化・吸収が進んだ後に便を形成する場所で、ここにできる腫瘍が大腸がんです。多くは粘膜から変化したポリープから発展し、長い時間をかけて進行します。
大腸内で腫瘍が大きくなると、便の通過を妨げたり、粘膜を傷つけたりして出血を引き起こす場合があります。
腸の末端付近にがんができると、便の形が細くなる、血便が出るなどの症状が見られることがありますが、進行しないと症状が乏しい場合もあるため、多くの人が何となく体調不良を感じながらも受診を後回しにしてしまいがちです。
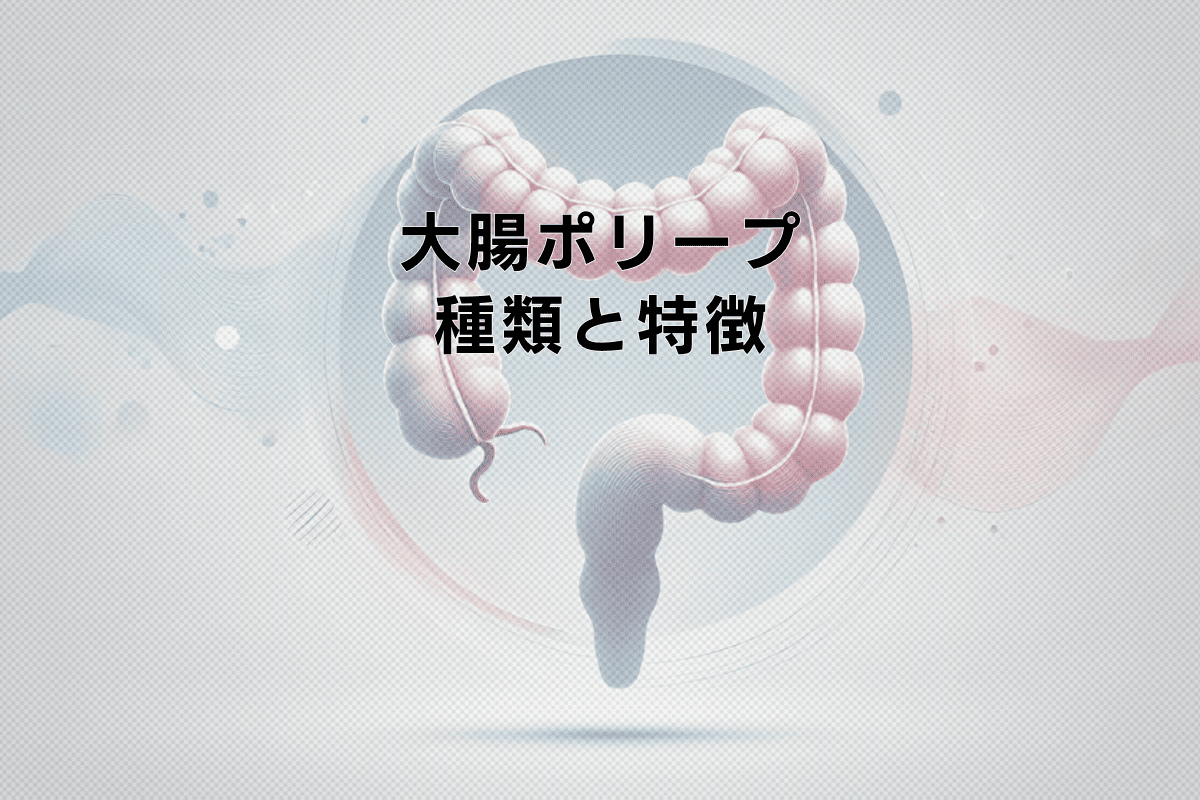
発生のメカニズム
大腸がんは粘膜に生じた細胞の異常増殖によって始まり、小さなポリープの段階で見つかれば、内視鏡を使って切除できる可能性が高まります。放置すると大腸の壁を超えて浸潤し、転移することもあるため、予防の観点での検査が重要です。
遺伝的要因をもつ方や食生活が偏っている方、飲酒や喫煙が多い方では、より注意が必要です。腸内環境を整える食習慣や適度な運動、定期的な大腸がんの検査を心がけると早期発見につながります。
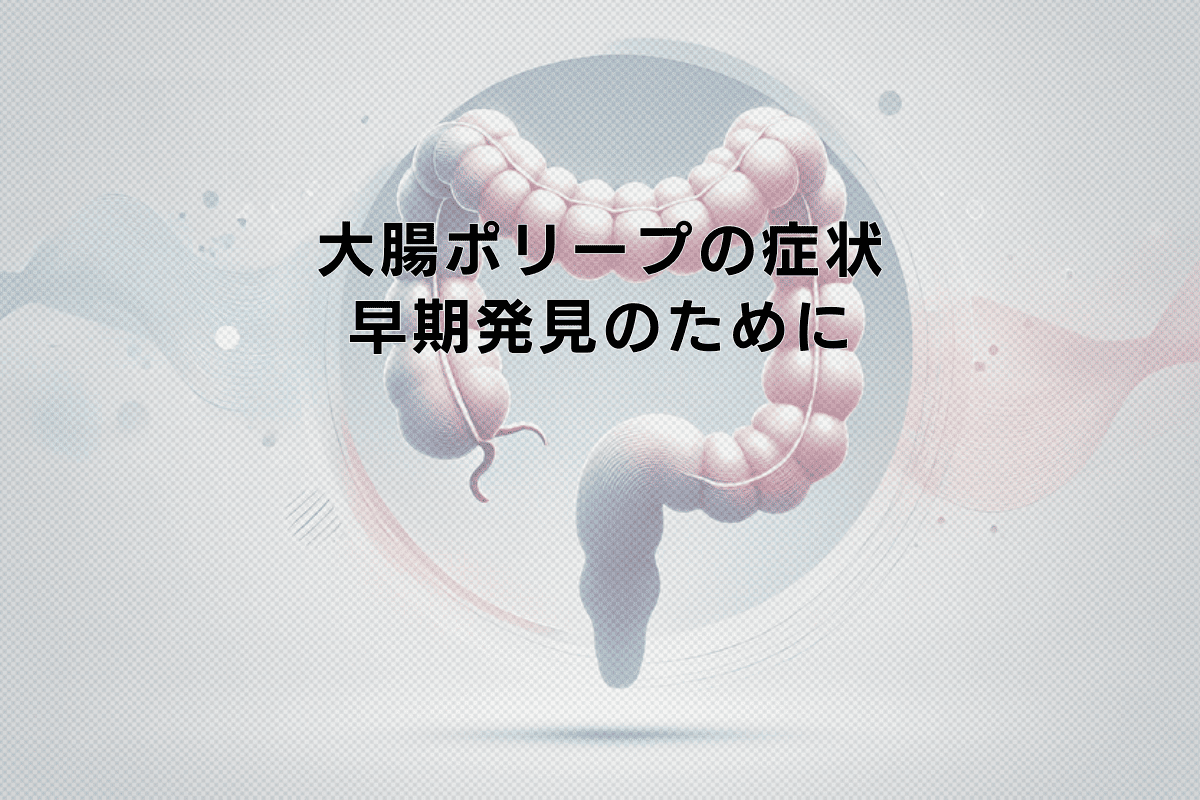
大腸がんの症状チェックの重要性
腹部の違和感や便通の変化を放置してしまうと、気づいたときには病状が進行していることがあり、体重減少や便に粘液が混ざるなど、気になるサインを見つけた場合は、医師の診察を受けると安心です。
大腸がんの症状をチェックすることが早期発見の大きな手助けになります。
早期では症状が軽微だったり、ほとんどないまま進行してしまうため、自覚症状だけを頼りにしないこともポイントで、特に40歳を超えるころから検査のタイミングを視野に入れると、見落としを減らしやすくなります。
リスク要因
大腸がんのリスクを上げる主な要因には、食生活と生活習慣の偏り、喫煙や過度の飲酒が含まれ、肉や脂質の多い食事ばかりを続けると、腸内の悪玉菌が増えやすくなり、腸粘膜への刺激が強くなる可能性があります。
野菜や果物、食物繊維を十分に摂らない方も注意が必要です。
さらに、炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病)をもつ場合や、血縁者に大腸がんの方がいる場合は、定期的なスクリーニング検査が推奨されます。

大腸がんの主なリスク要因
| リスク要因 | 概要 |
|---|---|
| 高脂肪・低食物繊維の食事 | 肉や揚げ物ばかりで野菜摂取が少ない場合にリスク上昇が報告されている |
| 飲酒・喫煙 | 過度のアルコール摂取や長年の喫煙習慣は腸粘膜のダメージを増やす傾向がある |
| 遺伝的素因 | 親族に大腸がんがいる場合や遺伝性疾患がある場合に注意が必要 |
| 運動不足 | 腸の動きが低下して便秘や腸内細菌バランスが崩れやすくなる |
| 炎症性腸疾患 | 潰瘍性大腸炎やクローン病などによって粘膜の炎症が続く状態 |
大腸がん検査の種類
大腸がんの検査方法には便潜血検査や内視鏡検査などいくつかの方法があり、それぞれ検査方法やメリットが異なります。それぞれの特徴を理解し自分に合った検査方法を知ることが、早期発見のためにも大切です。
便潜血検査
便の中に血液が混じっているかどうかを調べる手軽な検査で、専用のキットを使い、自宅で便を採取して提出します。目視ではわからない血液の痕跡を見つけるため、定期的に行うことで大腸がんリスクの早期発見につながります。
ただし、陽性だった場合でも大腸がんと確定するわけではないので、陽性時は追加の検査として、内視鏡検査を受けることが大切です。また陰性でも大腸がんがないとは断言できないので、家族歴、既往歴のある方は内視鏡検査を受けることを検討してください。

内視鏡検査(大腸カメラ)
大腸内視鏡(大腸カメラ)は肛門から内視鏡を挿入し、大腸の内部を直接観察する方法で、小さな病変や早期のポリープでも目視で確認でき、その場で切除できる点が大きな特徴です。
ポリープが疑われる場合や、便潜血検査で陽性となった場合は、大腸カメラを選ぶと病変の有無を直接確認できます。検査前に腸を洗浄するための下剤を飲む必要がありますが、得られる情報量が豊富です。

CTコロノグラフィ
CTコロノグラフィは、CTスキャンを使って大腸の内部を画像化する方法で、内視鏡を挿入しないので、身体的負担が軽めという特徴があります。
ただし、疑わしい病変を発見しても、その場で切除や組織採取ができないため、病変が見つかった場合は別途内視鏡検査が必要です。大腸カメラに抵抗がある方や腸の形状により内視鏡が通りにくい方に検討されます。
血液検査
大腸がんの可能性を示唆する腫瘍マーカー(CEAやCA19-9など)を測定する検査です。あくまでも補助的な位置づけであり、腫瘍マーカーの値だけでは大腸がんかどうか判断できないため、他の検査と組み合わせて利用します。
がんの進行度の確認や経過観察に使われることが多いです。
大腸がんの検査方法と特徴
| 検査方法 | 特徴 | 追加処置 |
|---|---|---|
| 便潜血検査 | 自宅で便を採取して提出する簡易的な方法 | 要検査時は内視鏡の受診が必要 |
| 大腸カメラ | 直接観察できるため病変の切除や生検が可能 | 下剤服用が必要、ポリープ切除可 |
| CTコロノグラフィ | CTで画像化するため身体への負担が軽め | 病変発見時は内視鏡が必要 |
| 血液検査 | 腫瘍マーカーなどを測定して目安をつかむ補助的な役割 | 正確な診断にはほかの検査が必須 |
症状チェックの目安
大腸がんの症状をチェックするポイントとしては、便通の変化や便の状態、腹部の痛みなどがよく挙げられ、続くようなら受診を考えるタイミングです。何となく調子が悪いと感じても、実際には早期がんだったという例も少なくありません。

初期症状の特徴
大腸がんの初期症状は、軽度の腹部不快感や便通のわずかな乱れにとどまることもあります。大腸は長いため、病変の位置によって症状が出にくい場合もあるのです。
血便が見られないからと安心せず、下痢と便秘を繰り返す、便が細くなったと感じるなど、少しでも気になる点があれば検査を検討してください。
初期に見られやすい変化
- なんとなく続く下痢と便秘の交互出現
- 便が細くなったり、形がいびつに感じられる
- 軽い腹痛やお腹の張りが慢性的に起こる
- 微量の血液が便につくが気づきにくい
下痢・便秘の持続が疑われる場合
大腸がんと下痢・便秘は直接的に結びつくわけではありませんが、がんによって大腸内の通過が阻害されると便が出にくく便秘を起こしやすくなり、また、一部の部位にがんができていると腸粘膜の炎症が生じ、下痢を繰り返すケースがあります。
便秘や下痢の異常が続いたときは、大腸がん検査を意識した受診を考えるきっかけになります。
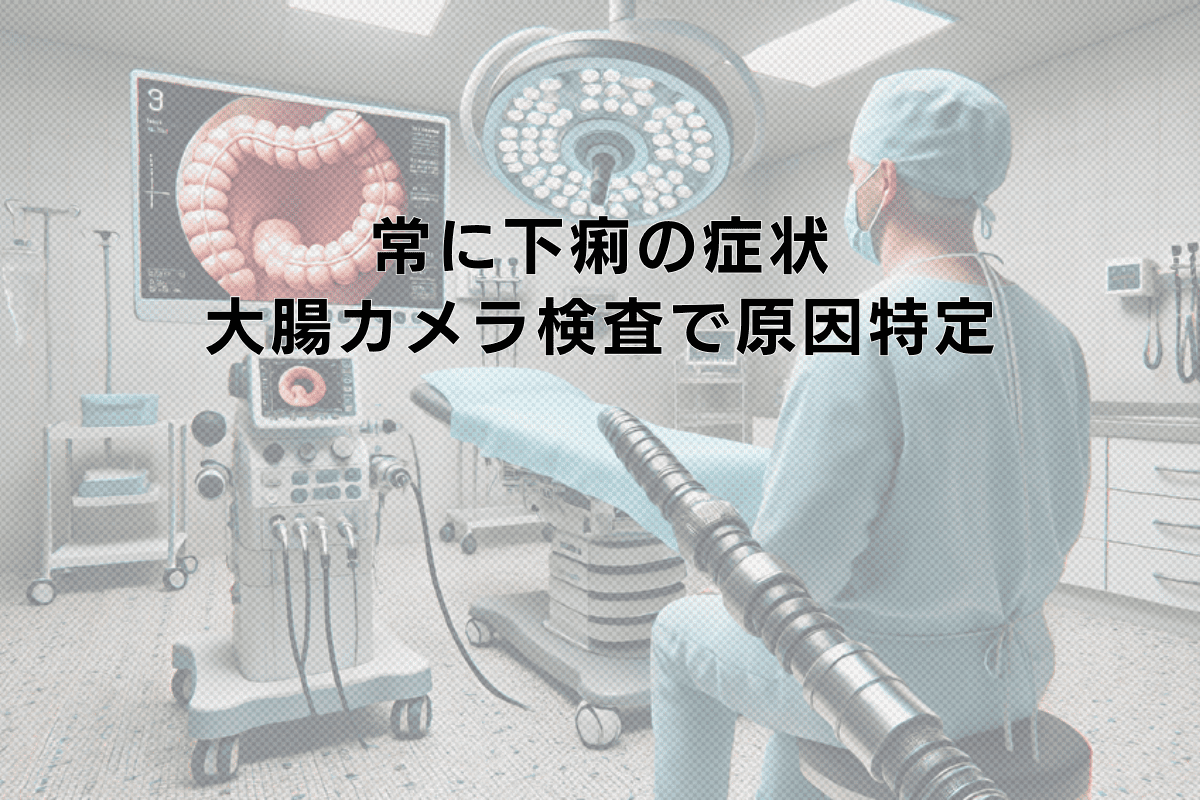
血便や便の形状変化に注目
がんやポリープが大腸の管腔内を圧迫することで、便の形状が極端に細くなったり、表面に血液や粘液が付着したりする場合があり、肉眼でわかるほどの血液が混じっていれば受診を迷わないかもしれません。
しかし、血液が少量だと気づかないことも多いため、色や形に異変があれば早めに医療機関で相談することが大切です。

便の変化を確認するときの留意点
| チェック項目 | 留意点 |
|---|---|
| 便の色 | 真っ赤な血液だけでなく、暗い色の血も注意 |
| 便の形状 | 筋ばったように細くなる、表面がボソボソして均一でない場合は要注意 |
| 便のにおい | いつもと違って強い悪臭を伴う場合は腸内環境悪化の可能性 |
| 排便回数 | 急に増減する変化が続く場合は異常の兆候 |
| 痛みや不快感の有無 | 肛門付近の痛みやお腹の張り、腹痛があるかどうか |
腹痛や腹部膨満感のサイン
腹痛や腹部膨満感はさまざまな病気のサインとして現れますが、大腸がんでも腸内に腫瘍があると便の通過障害を起こしやすくなります。
特に右側結腸にがんがある場合は、便がまだ液状に近い段階なので症状が出にくい一方、左側結腸にがんがある場合は便の通過を妨げやすいため、腹痛や膨満感が目立つことがあります。
長期化すると栄養吸収の面でも影響が及び、体重減少につながることもあるので用心してください。
どのタイミングで受けるべきか
大腸がん検査を受ける目安として、40代以降になると定期検査を考える方が増え、また家族歴や既往歴などがあれば、より早い段階から検査を検討してもよいでしょう。
年齢だけでなく、便通などの自覚症状や生活習慣に応じた柔軟な検討が求められます。
40代以降の定期的な検査
日本では40歳を迎えたあたりから生活習慣病のリスクが高まるとともに、大腸がんにかかる可能性も増える傾向があります。
市区町村の健診や職場の健康診断で、便潜血検査を年1回実施している方も多いですが、陽性が出た場合は放置せず内視鏡検査を受けることが推奨されています。
検査を受けることで、早期発見だけでなくポリープの切除を通じた予防も期待できます。
年齢別に推奨される定期検査
| 年齢層 | 推奨される検査の頻度 | ポイント |
|---|---|---|
| 40代 | 年1回の便潜血検査+必要に応じた内視鏡検査 | 家族歴や生活習慣に応じて検査の選択を検討 |
| 50代 | 年1回の便潜血検査+定期的な内視鏡検査 | がん発症率が上がる世代なので意識して受診 |
| 60代以降 | 年1回の便潜血検査+症状次第で内視鏡検査 | がん以外にも合併症が増えるため、総合的な検査が重要 |
家族歴がある場合
血縁者に大腸がんやポリープが多発した例がある場合は、遺伝性要因がないか確認することが大切です。家族性大腸腺腫症などの遺伝性疾患が疑われることもあり、より注意深いスクリーニングを実施するケースがあります。
通常の健診よりも早い段階、たとえば30代から便潜血検査と内視鏡検査を並行して受けることも検討しましょう。
ポリープや炎症性腸疾患の既往がある場合
過去に大腸ポリープを切除したことがある場合や、潰瘍性大腸炎やクローン病などの炎症性腸疾患の既往がある方は、定期的な内視鏡検査を強く意識すると安心です。
以前にポリープが見つかった方は、新たなポリープができていないか、既存のポリープが大きくなっていないかを確認する意味合いがあります。炎症性腸疾患をもつ方は粘膜が傷つきやすいため、念入りな観察が必要です。
内視鏡検査への抵抗感と受診のポイント
大腸カメラ検査を敬遠する理由の1つに「痛みや恥ずかしさ」が挙げられますが、検査時の鎮静剤や服装の工夫で負担が和らぐ場合が多いので、医療機関の方針を確認してください。
検査前の下剤も飲みづらいイメージがあるかもしれませんが、医師やスタッフから飲み方のコツを聞くと取り組みやすくなります。
検査を受けるメリットが身体的・精神的な不安を上回ることを実感できると、早期発見へのモチベーションが高まります。
大腸カメラへの不安を和らげる工夫
- 痛みや嘔吐感を軽減する鎮静剤の使用
- リラックスできる検査着や個室対応のクリニックを選ぶ
- 下剤は冷やして飲むと苦味が感じにくくなることもある
- 適度に水分を摂取しながら無理せず準備を進める
大腸がん検査の流れ
大腸がん検査の流れを把握すると、実際に受診するときの不安が軽くなります。便潜血検査から内視鏡検査までの手順とポイントを整理し、自分の状況に合った方法を選ぶとよいでしょう。
検査前の準備
内視鏡検査では、大腸内を観察しやすくするために下剤で腸の内容物を排出します。味や飲む量が心配という声もありますが、水やスポーツドリンクなどと併用することで負担を少なくできます。
腸内をきれいにしておくと病変を見つけやすくなるため、前日からの食事にも気を配る必要があり、消化に負担をかけないメニューを選び、指示された食事制限を守ってください。

内視鏡検査前の食事におすすめの内容
| 食品・メニュー | ポイント |
|---|---|
| おかゆ・うどん | 消化がよく腸内に残りにくい |
| 白身魚の煮物 | たんぱく質も摂りやすく油分が少なめ |
| 野菜スープ | 食物繊維が少ない具材や薄味で調理する |
| りんごやバナナなど | 果物でも食物繊維が少なめのものを選ぶ |
大腸カメラ検査の手順
医師が肛門から内視鏡を挿入し、大腸の内壁を観察します。視野を確保するために空気や炭酸ガスで腸内を膨らませるので、一時的にお腹の張りを感じるかもしれません。
ポリープや怪しい病変を発見した場合は、その場で切除または生検を行えます。検査時間は個人差がありますが、約15~30分程度です。痛みに強い不安がある方は鎮静剤の使用について相談できます。
CTコロノグラフィの手順
CTコロノグラフィを行う際も、事前の腸内洗浄が必要で、検査ではカテーテルを肛門から差し込み、腸内にガスを注入してふくらませた状態で撮影します。
痛みは少ないものの、内視鏡のように直接ポリープを切除できないというデメリットがあります。撮影時間そのものは短めですが、病変が疑われた場合は追加で大腸カメラの検査が必要です。
検査方法の比較
| 項目 | 大腸カメラ | CTコロノグラフィ |
|---|---|---|
| 病変発見後の対処 | その場で切除や生検が可能 | 追加で大腸カメラが必要になることが多い |
| 身体的負担 | 鎮静剤の使用で和らげやすいがやや緊張を伴う場合がある | 直接カメラを入れないため負担は軽め |
| 得られる情報量 | カメラによる肉眼観察で詳細がわかりやすい | 画像解析で腸内全体を3D的に把握可能 |
| 検査前の準備 | 下剤による腸内洗浄が必要 | 同様に腸内洗浄が必要 |
検査後の注意点
内視鏡検査でポリープを切除した場合は、当日や翌日に出血する場合があるので、しばらくは激しい運動を控え、指示された食事制限や安静を守ってください。
鎮静剤を使用した場合は当日車の運転を避け、可能なら付き添いの方と一緒に帰宅すると安心です。検査結果については数日後に説明を受けることが多く、切除した組織の病理検査結果はさらに時間がかかることがあります。
院内での精密検査と治療方針
精密検査では、腫瘍の有無や大きさ、広がりなどを詳細に調べ、腫瘍が発見された場合、医師が切除方法や治療の選択肢を検討します。
早期発見で内視鏡治療が可能なケースも多いため、自覚症状が少ない段階で検査に踏み切るメリットは大きいです。
ポリープ切除
内視鏡で大腸内部を観察しながら、スネアと呼ばれる器具を使ってポリープを切り取る方法です。切除は電気メスを使うことが多く、出血を予防しながら取り除けます。
ポリープを取るだけでがんを防ぐ可能性が高まるため、小さいうちに発見することが望ましいです。切除後は取り除いた組織を病理検査に出し、悪性か良性かを評価します。
組織検査
切除や生検で得た組織は、病理専門医による顕微鏡検査に回し、がん細胞が存在するか、どのくらい浸潤しているのかを判断します。がん細胞が見つかった場合は、ステージ(進行度)に応じて治療計画を立てます。
内視鏡治療で対応できるものから外科的な手術が必要になるケースまでさまざまです。
病理検査からわかること
- 腫瘍の良性・悪性の区別
- がんの深達度(大腸の壁への浸潤度合い)
- 転移の可能性を示す細胞の特徴
- 切除断端へのがん細胞の有無
早期発見と治療選択肢
早期の段階で発見した場合は、内視鏡的切除による治療で完結することがありますが、進行がんの場合は外科的手術や化学療法、放射線療法などの選択肢を検討します。いずれの場合も、早期に着手した方が体への負担も少なくなりやすいです。
内視鏡で切除できる範囲か否かによって治療方針が変わるため、症状がないからといって放置するのはよくありません。
再発防止に向けた生活習慣
大腸がんは治療後も再発がゼロになるわけではなく、再発リスクを下げるためには、継続的な検査とともに生活習慣の改善が必要です。
高脂肪・低食物繊維の食事を続けるより、野菜や海藻、乳酸菌を含む食品を積極的に取り入れると腸内環境の改善につながります。また、適度な運動や禁煙、節酒を意識することも重要です。
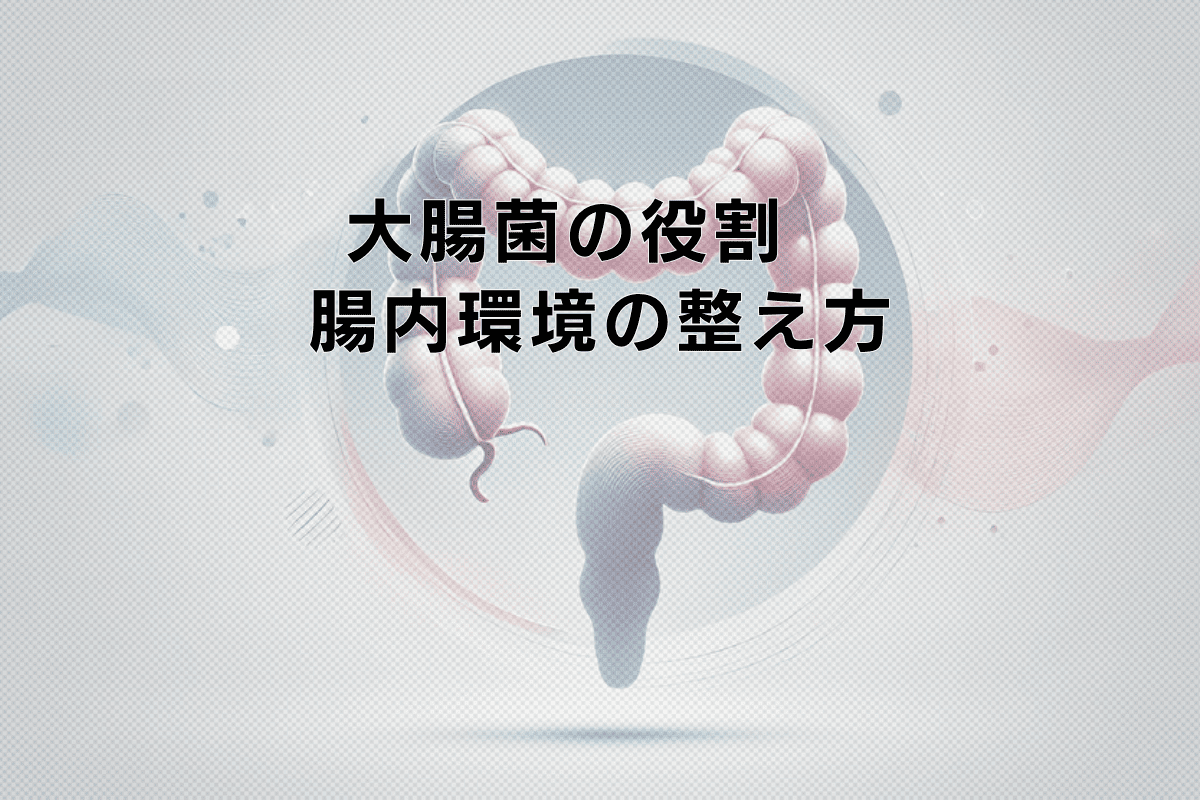
再発を予防するために心がけたい要素
| 取り組み | 具体例 |
|---|---|
| 食生活の改善 | 野菜や海藻、豆類、果物などの摂取を増やす |
| 定期的な運動 | ウォーキングやストレッチを習慣化する |
| 定期検査の継続 | 指定された時期に内視鏡検査を受け直す |
| 禁煙・節酒 | 喫煙習慣がある方はできるだけ減らす |
大腸がん検査に関するよくある質問
大腸がん検査を受けるうえで、疑問や不安を感じる場面があるかもしれません。ここでは検査にまつわる代表的な質問と、一般的な見解を紹介します。
- 便潜血検査だけで十分なのでしょうか?
-
便潜血検査は手軽に受けられるスクリーニング方法ですが、それだけで大腸がんかどうかを確定できるわけではありません。陽性反応が出た場合は、内視鏡検査やほかの詳しい検査を受けて確かめる必要があります。
逆に陰性でも、検出されなかった微小な病変が存在する可能性がないとは言い切れないため、症状がある場合は医師に相談すると安心です。
- 大腸カメラは痛いイメージがあるのですが、実際はどうですか?
-
個人差はありますが、鎮静剤を使用するクリニックでは、眠っている間に検査が終わることが多いです。痛みが少なくなる工夫を医師や看護師が行うので、昔ほどの苦痛は感じにくい傾向があります。
緊張感が強いと腹部のこわばりも生じやすいので、リラックスできる対策を心がけるとさらに負担を減らせます。
- 検査でポリープが見つかったら、必ず切除しなければならないのでしょうか?
-
ポリープには良性と悪性(がん化を含む)があり、形や大きさ、位置などで対応が変わります。医師が必要と判断した場合は切除を行い、病理検査をすることで安全性を高めます。
小さなポリープでも、がん化のリスクがあると判断されれば切除の対象になり、医師の説明を聞いて理解したうえで選択することが大切です。
- 検査前の食事制限はどの程度厳密に守らなければいけませんか?
-
内視鏡検査の精度を高めるために、前日からの食事制限はなるべく守るほうが望ましいです。消化に時間がかかる食材を口にすると、大腸内視鏡の視野が悪くなる可能性があります。
検査日当日の朝は指示通りの食事や水分摂取にとどめ、下剤を飲んで腸をきれいにする流れを医師の指示に従って行いましょう。
次に読むことをお勧めする記事
【大腸がん検査方法の選び方 – 血液検査から内視鏡検査まで】
大腸がん検査の基本を押さえたら、次は実際の検査方法の選択について知っておくと安心です。ご自身の状況に応じた最適な検査方法を選ぶために特に参考になる内容です。
【大腸ポリープの内視鏡治療 – 早期発見と切除術の重要性】
大腸がんを予防するにはポリープ管理が重要です。ポリープ切除術の実際を知れば、検査後の対応がよりイメージしやすくなります。
参考文献
Lopes G, Stern MC, Temin S, Sharara AI, Cervantes A, Costas-Chavarri A, Engineer R, Hamashima C, Ho GF, Huitzil FD, Moghani MM. Early detection for colorectal cancer: ASCO resource-stratified guideline. Journal of global oncology. 2019 Feb;5:1-22.
Demb J, Kolb JM, Dounel J, Fritz CD, Advani SM, Cao Y, Coppernoll-Blach P, Dwyer AJ, Perea J, Heskett KM, Holowatyj AN. Red flag signs and symptoms for patients with early-onset colorectal cancer: a systematic review and meta-analysis. JAMA Network Open. 2024 May 1;7(5):e2413157-.
Jellema P, Van der Windt DA, Bruinvels DJ, Mallen CD, van Weyenberg SJ, Mulder CJ, de Vet HC. Value of symptoms and additional diagnostic tests for colorectal cancer in primary care: systematic review and meta-analysis. Bmj. 2010 Apr 1;340.
Vega P, Valentin F, Cubiella J. Colorectal cancer diagnosis: Pitfalls and opportunities. World journal of gastrointestinal oncology. 2015 Dec 15;7(12):422.
Burnett-Hartman AN, Lee JK, Demb J, Gupta S. An update on the epidemiology, molecular characterization, diagnosis, and screening strategies for early-onset colorectal cancer. Gastroenterology. 2021 Mar 1;160(4):1041-9.
Olde Bekkink M, McCowan C, Falk GA, Teljeur C, Van de Laar FA, Fahey T. Diagnostic accuracy systematic review of rectal bleeding in combination with other symptoms, signs and tests in relation to colorectal cancer. British Journal of Cancer. 2010 Jan;102(1):48-58.
Hatch QM, Kniery KR, Johnson EK, Flores SA, Moeil DL, Thompson JJ, Maykel JA, Steele SR. Screening or symptoms? How do we detect colorectal cancer in an equal access health care system?. Journal of Gastrointestinal Surgery. 2016 Feb 1;20(2):431-8.
Astin M, Griffin T, Neal RD, Rose P, Hamilton W. The diagnostic value of symptoms for colorectal cancer in primary care: a systematic review. British Journal of General Practice. 2011 May 1;61(586):e231-43.
Fritz CD, Otegbeye EE, Zong X, Demb J, Nickel KB, Olsen MA, Mutch M, Davidson NO, Gupta S, Cao Y. Red-flag signs and symptoms for earlier diagnosis of early-onset colorectal cancer. JNCI: Journal of the National Cancer Institute. 2023 Aug 1;115(8):909-16.
Herrero JM, Vega P, Salve M, Bujanda L, Cubiella J. Symptom or faecal immunochemical test based referral criteria for colorectal cancer detection in symptomatic patients: a diagnostic tests study. BMC gastroenterology. 2018 Dec;18:1-0.