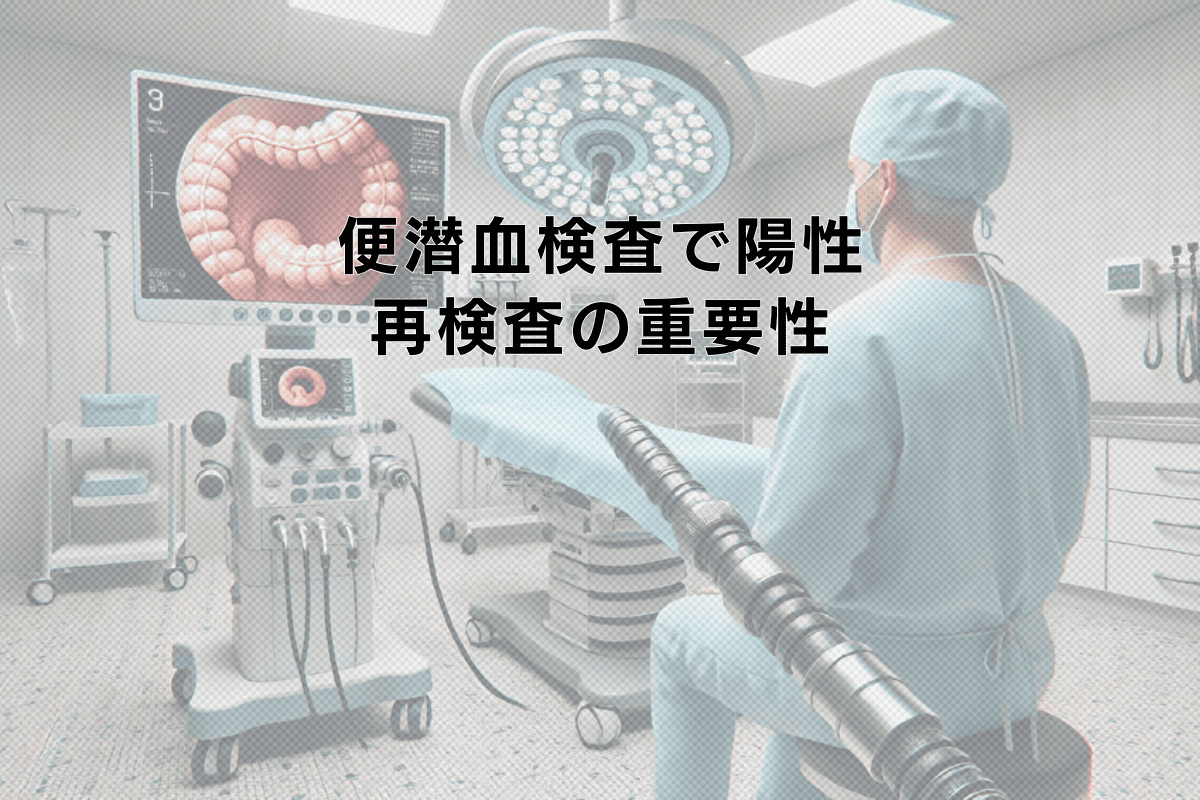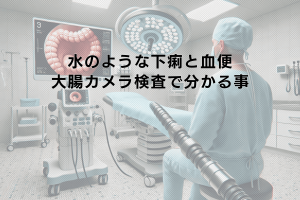健康診断や市区町村のがん検診で受ける機会のある、便潜血検査の結果が陽性であった場合、多くの方が不安な気持ちになることと思いますが、陽性という結果は、必ずしも大腸がんを意味するわけではありません。
便潜血検査は、消化管のどこかから微量の出血があることを示すスクリーニング検査です。
この記事では、便潜血検査で陽性という結果を受け取った方々が抱える疑問や不安に寄り添いながら、なぜ精密検査が必要なのか、どのような検査を行うのか、検査で何がわかるのかについて、詳しく解説していきます。
便潜血検査とはどのような検査か
便潜血検査は、多くの人が健康診断などで経験する身近な検査の一つですが、目的や仕組みについて詳しく知る機会は少ないかもしれません。ここでは、便潜血検査の基本的な知識について解説し、この検査が持つ意味と役割への理解を深めます。
検査の目的と仕組み
便潜血検査の主な目的は、大腸がんの早期発見です。大腸がんやポリープがあると、便が腸内を通過する際に組織と接触し、目には見えないごく微量の出血を起こすことがあり、この血液を検出するのが便潜血検査です。
一般的に、免疫法という検査方法を用い、ヒトの血液(ヘモグロビン)にのみ反応する抗体を使用するため、食事に含まれる動物の血液などに影響されず、より精度の高い結果を得ることができます。
通常、2日間にわたって便を採取し、それぞれの日に出血がなかったかを確認し、手軽さから、大腸がん検診の入り口として広く採用されています。
どのような病気が見つかる可能性があるのか
便潜血検査が陽性となった場合、原因は様々です。大腸がんの可能性はもちろんですが、それ以外の病気が原因であることも少なくありません。
陽性の結果は、消化管からの出血サインであり、原因を特定するための第一歩と考えることが重要です。
便潜血検査で発見のきっかけとなる病気
| 病気の分類 | 代表的な病名 | 簡単な説明 |
|---|---|---|
| 悪性腫瘍 | 大腸がん | 大腸の粘膜に発生するがんで、早期発見が治療の鍵です。 |
| 良性腫瘍 | 大腸ポリープ | 将来がん化する可能性のあるポリープも含まれます。 |
| 炎症 | 潰瘍性大腸炎、クローン病 | 大腸の粘膜に炎症や潰瘍ができる病気です。 |
| その他 | 大腸憩室症、虚血性腸炎 | 腸の壁にできた窪みや、血流障害による炎症からの出血です。 |
| 肛門疾患 | 痔(内痔核、切れ痔など) | 排便時のいきみなどによる肛門付近からの出血です。 |
陽性イコールがんではない
便潜血検査で陽性という結果を受け取ると、すぐに大腸がんを心配してしまうかもしれませんが、実際に陽性反応が出た人のうち、精密検査で大腸がんが見つかる割合は、統計的に数パーセント程度といわれています。
多くの場合、がん化する可能性のあるポリープや、痔などの肛門疾患、その他の良性の病気が原因です。陽性という結果は、あくまで精密検査が必要な状態を示すサインであり、過度に悲観する必要はありません。
大切なのは、結果を冷静に受け止め、原因を特定するために次の行動へ移ることです。

陽性という結果が意味すること
陽性という通知は、体に何らかの変化が起きている可能性を示唆する重要な情報です。ここでは、陽性結果の背景にある可能性と、放置することのリスクについて解説します。
陽性反応の原因として考えられること
便に血液が混じる原因は一つではなく、消化管の入り口である口から出口の肛門までのどこかで出血があれば、陽性反応が出る可能性があります。
ただし、便潜血検査(免疫法)は主に下部消化管、特に大腸からの出血を検出することに優れています。
胃や十二指腸からの出血は、便として排出されるまでに血液が変性してしまうため、検出されにくい傾向があるので、陽性の場合は大腸の病気を第一に考え、精密検査を進めていきます。
- 大腸がん
- 大腸ポリープ
- 炎症性腸疾患
- 大腸憩室からの出血
- 痔などの肛門疾患
偽陽性の可能性について
偽陽性とは、実際には病気がないにもかかわらず、検査結果が陽性になることです。便潜血検査の場合、生理中の経血が混入したり、痔による一時的な出血を拾ったりすることで偽陽性となることがあります。
ただし、痔だと思っていた出血が、大腸の奥にある病気のサインである可能性も否定できません。
出血の原因が痔であるかどうかは、精密検査を行って初めて確定できるため、どのような理由が考えられるにせよ、陽性という結果が出た場合は、一度専門の医療機関で相談することが原則です。
陽性の原因となりうる主な疾患
| 原因 | 出血の可能性 | 備考 |
|---|---|---|
| 大腸がん・ポリープ | 高い | 持続的または断続的な出血が見られます。 |
| 炎症性腸疾患 | 高い | 腹痛や下痢などの症状を伴うことがあります。 |
| 痔 | 高い | 排便時に鮮やかな色の血が出ることが多いです。 |
| 生理中の経血混入 | あり | 女性の場合、検査時期の調整が大切です。 |
陽性結果を放置するリスク
便潜血検査で陽性となっても、特に自覚症状がないため、精密検査をためらってしまう方もいるかもしれません。しかし、放置することは最も避けるべき行動です。
便潜血検査は、初期の無症状の時期にがんを発見できる数少ない機会の一つです。もし陽性の原因が早期のがんであった場合、この機会を逃すと、がんが進行し、腹痛や血便、便秘などの症状が現れてから発見されることになります。
進行した状態で見つかると、治療の選択肢が限られたり、体への負担が大きい治療が必要になったりする可能性が高まります。早期発見・早期治療のためにも、陽性結果は軽視せず、速やかに精密検査を受けてください。
なぜ再検査ではなく精密検査が必要なのか
陽性の結果が出た後、もう一度同じ便潜血検査を受けて陰性を確認しようと考える方もいますが、推奨される方法ではありません。一度陽性が出た場合に求められるのは、同じ検査の繰り返しではなく、より詳しく内部を調べる精密検査です。
便潜血検査の限界
便潜血検査は、あくまで出血の有無を調べるスクリーニング検査です。出血の原因が何であるか、消化管のどこから出血しているのかを特定することはできません。
また、がんやポリープは常に出血しているわけではなく、出血したり止まったりを繰り返すことがあるため、一度陽性が出た後に再度便潜血検査を行って陰性だったとしても、体の中に病気が存在しない証明にはなりません。
たまたま出血していないタイミングで検査をしただけの可能性があるのです。
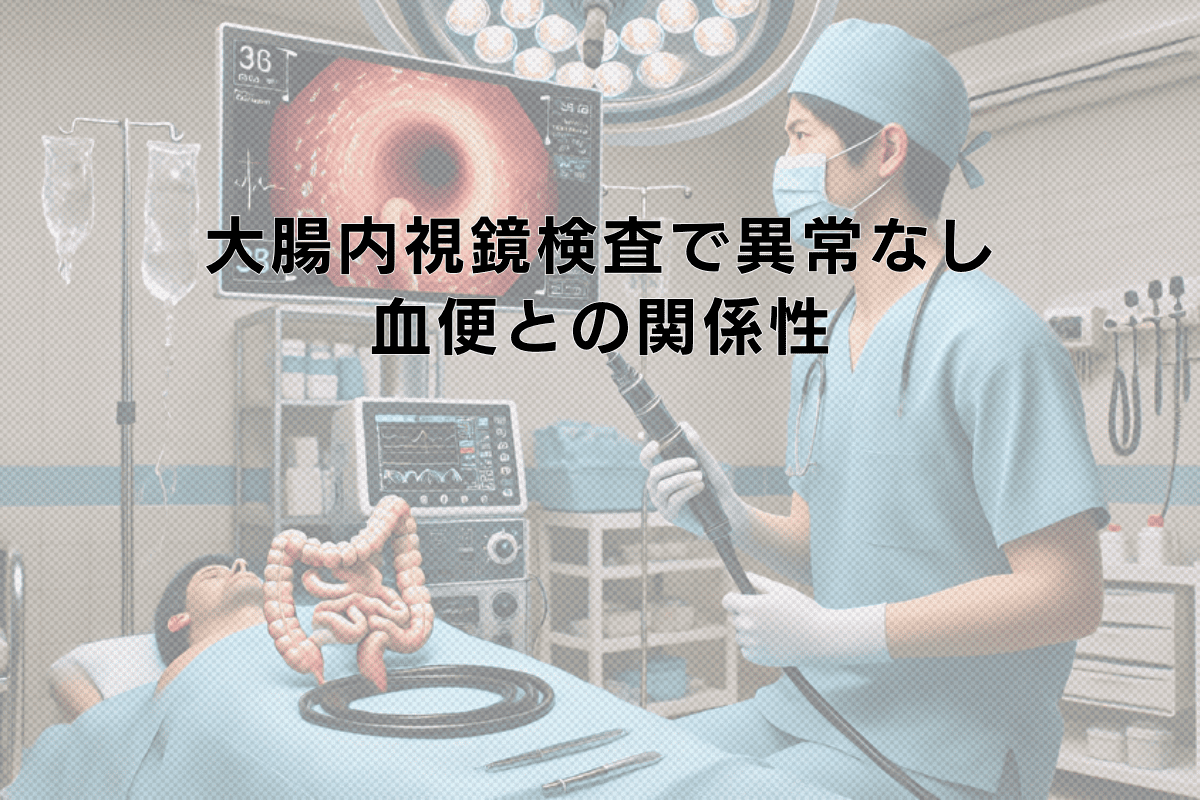
精密検査で初めてわかること
精密検査の目的は、出血の原因を直接目で見て確認することです。代表的な精密検査である大腸内視鏡検査(大腸カメラ)では、小型カメラを用いて大腸の内部を隅々まで観察します。
検査により、出血源の特定はもちろん、がんやポリープ、炎症などの病変の有無、大きさや形状、場所を正確に把握することができます。便潜血検査が影を見つける検査だとすれば、精密検査は影の正体を突き止める検査です。
検査方法の比較
| 検査項目 | 便潜血検査 | 精密検査(大腸内視鏡) |
|---|---|---|
| 目的 | 出血の有無を確認する | 出血原因を特定し、病変を直接観察する |
| わかること | 目に見えない微量の血液の存在 | がん、ポリープ、炎症などの有無、大きさ、場所 |
| 確実性 | 病変があっても陰性の場合がある | 直接観察するため非常に高い診断能力を持つ |
再度の便潜血検査が無意味な理由
陽性反応が出たことは、少なくとも一度は出血があったという事実を示していて、その後の検査で陰性が出たからといって、その事実が消えるわけではありません。
出血の原因が体内に残っている可能性を考慮すると、再度の便潜血検査で安心材料を得ようとすることは、病気の発見を遅らせるリスクを伴います。
一度でも陽性が出た場合は、原因を究明するために、より精度の高い精密検査へ進むことが最も合理的で安全な選択です。
精密検査の具体的な内容
便潜血検査で陽性となった後に行う精密検査には、いくつかの方法があり、現在、最も標準的で推奨される方法は、全大腸内視鏡検査(大腸カメラ)です。
ここでは、一般的な精密検査の流れと、大腸内視鏡検査がどのようなものかについて解説します。
一般的な精密検査の流れ
医療機関を受診すると、まずは医師による問診が行われ、現在の自覚症状、過去の病歴、家族の病歴、普段の生活習慣などについて詳しく確認し、その後、便潜血検査の結果を踏まえて、どのような精密検査を行うかを決定します。
ほとんどの場合、大腸内視鏡検査が選択されますが、患者さんの状態によっては他の検査が検討されることもあります。検査の日程を決め、検査前の準備や注意点について詳しい説明を受けます。
全大腸内視鏡検査(大腸カメラ)について
大腸内視鏡検査は、先端に高性能な小型カメラが付いた細くて柔らかいチューブ(内視鏡)を肛門から挿入し、直腸から盲腸までの大腸全体を直接観察する検査です。
モニターに映し出される鮮明な映像を見ながら、医師が粘膜の状態をリアルタイムで確認し、粘膜の色や血管の走行、凹凸などを詳細に観察することで、微小な病変も見逃しにくくなっています。
検査の精度が非常に高く、診断と治療を同時に行える場合もあるため、大腸疾患の精密検査におけるゴールドスタンダードです。
大腸内視鏡検査でできること
この検査の大きな利点は、ただ観察するだけではない点にあり、検査中に疑わしい部分が見つかった場合、その場で様々な対応が可能です。
特に、大腸がんの前段階であるポリープを発見した場合、その場で切除できることは大きなメリットで、ポリープを切除することは、将来の大腸がんを予防する最も確実な方法の一つです。
切除したポリープは回収し、病理検査で良性か悪性かを詳しく調べます。
その他の精密検査方法
何らかの理由で大腸内視鏡検査が難しい場合には、注腸X線検査やCTコロノグラフィなどが選択されることがあります。
注腸X線検査は、肛門からバリウムと空気を注入して大腸を膨らませ、X線撮影を行う検査で、CTコロノグラフィは、CTスキャンを用いて大腸の3次元画像を構築する検査です。
このような検査は、大腸内視鏡検査に比べて体への負担が少ないという利点がありますが、病変の色の変化が分からなかったり、小さな病変の発見が難しかったり、組織の採取やポリープの切除ができないという欠点もあります。
そのため、異常が見つかった場合は、結局大腸内視鏡検査が必要になることがほとんどです。
大腸内視鏡検査の準備と当日の流れ
大腸内視鏡検査を安全かつ正確に行うためには、事前の準備が非常に重要です。大腸の中を空にして、粘膜をきれいに観察できる状態にする必要があります。

検査前の食事と注意点
通常、検査の前日は消化の良い食事を心がけ、きのこや海藻、種子の多い果物、玄米など、繊維質が多く腸に残りやすい食品は避けてください。医療機関によっては、検査食と呼ばれる専用の食事が用意されている場合もあります。
夕食は早めに済ませ、その後は絶食となり、水分は水やお茶など、色のついていない透明なものであれば摂取可能です。普段から服用している薬がある場合は、事前に医師に相談し、指示に従うことが大切です。
特に血液をサラサラにする薬(抗血栓薬)を服用している方は、休薬が必要な場合があるため、必ず申し出てください。
検査前日の食事例
| 時間 | 食事内容の例 | 避けるべき食品 |
|---|---|---|
| 朝食 | 食パン(バターやジャムは可)、おかゆ | 野菜、果物、全粒粉パン |
| 昼食 | 素うどん、白身魚の煮付け、豆腐 | きのこ類、海藻類、こんにゃく |
| 夕食 | 具のないスープ、ゼリー飲料 | 固形物全般、乳製品 |
下剤(腸管洗浄剤)の服用について
検査当日、大腸の中を完全にきれいにするために、多量の下剤(腸管洗浄剤)を服用し、通常、約1リットルから2リットルの液体状の下剤を数時間かけてゆっくりと飲みます。
服用を開始してしばらくすると便意が始まり、何度もトイレに通うことになり、最終的に、便が固形物のない水のような状態になれば、検査の準備は完了です。
下剤の服用は検査準備の中で最も大変な部分ですが、正確な検査のためにはとても重要な工程です。最近では、錠剤タイプの下剤や、飲む量が少ないもの、味を工夫したものなど、様々な種類があります。
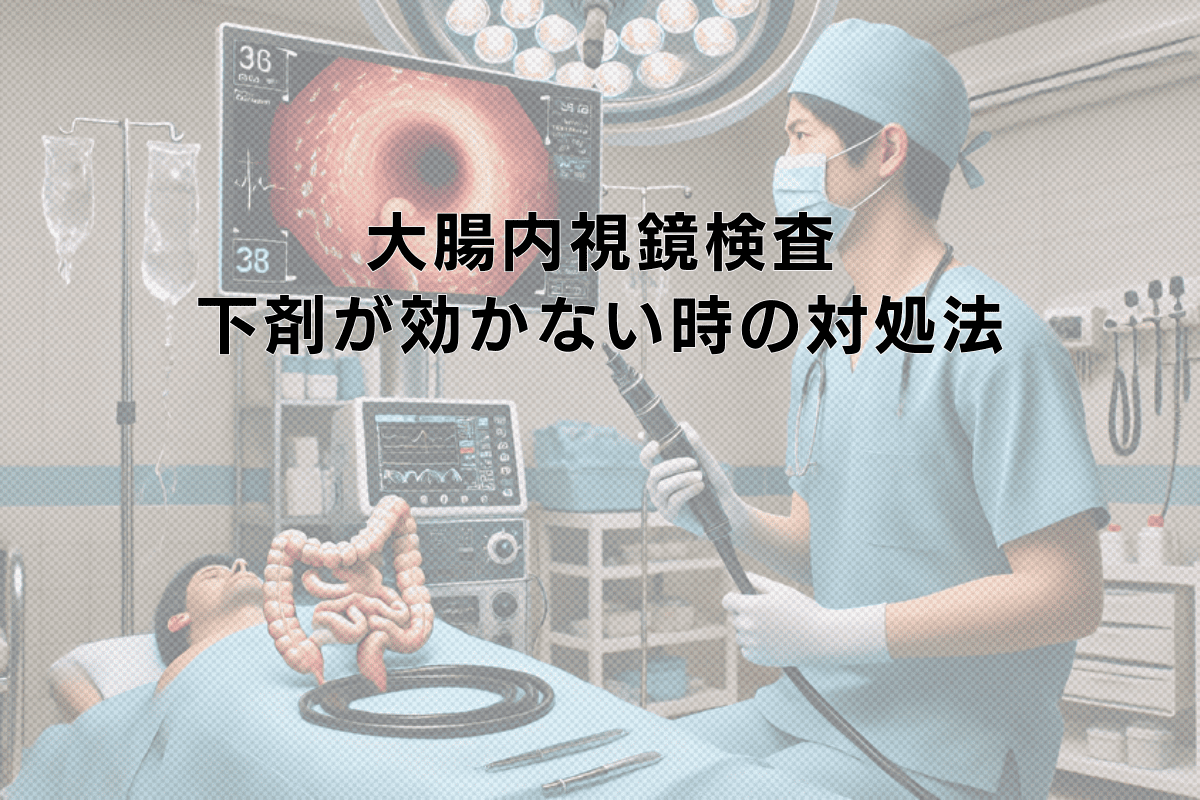
検査当日の流れと所要時間
医療機関に到着後、更衣室で検査着に着替え、検査室に入りベッドに横になり、鎮静剤を使用する場合は、点滴の準備をします。
検査は、医師が内視鏡を肛門からゆっくりと挿入し、大腸の一番奥まで進めてから、抜きながら詳細に観察していきます。検査自体の所要時間は、個人差がありますが、通常15分から30分程度です。
ポリープを切除するなどの処置を行う場合は、もう少し時間がかかります。鎮静剤を使用した場合は、検査後にリカバリールームで1時間ほど休憩してから、医師の説明を受けることになります。
検査当日は、鎮静剤の影響が残る可能性があるため、車やバイク、自転車の運転はできません。
精密検査でわかる代表的な病気
大腸内視鏡による精密検査は、出血の原因を特定するだけでなく、様々な大腸の病気を発見する機会です。ここでは、精密検査によって診断される代表的な病気について解説します。
大腸がん
精密検査で発見される最も重要な病気が大腸がんで、大腸の粘膜から発生する悪性の腫瘍です。早期の段階では自覚症状がほとんどなく、便潜血検査が発見の唯一のきっかけとなることも少なくありません。
内視鏡検査では、がんの大きさ、形状、場所を正確に把握でき、また、組織の一部を採取して病理検査にかけることで、がん細胞の有無を確定診断します。ごく早期のがんであれば、内視鏡で切除することも可能です。
進行度合いに応じて、外科手術や化学療法などの治療方針が決定されます。
大腸ポリープ
大腸ポリープは、大腸の粘膜にできるイボのような隆起のことです。ポリープには、将来がん化する可能性のある腫瘍性のものと、その可能性がほとんどない非腫瘍性のものがあります。
内視鏡検査では、ポリープの見た目からある程度の判断が可能ですが、確定診断のためには切除して病理検査を行うことが一般的です。
特に腫瘍性ポリープ(腺腫)は、大腸がんの前段階と考えられており、内視鏡検査の際に切除することで、大腸がんの予防につながります。
多くのポリープは無症状であり、便潜血検査陽性をきっかけとした精密検査で偶然発見されることが大半です。
ポリープの種類の比較
| 項目 | 腫瘍性ポリープ(腺腫) | 非腫瘍性ポリープ |
|---|---|---|
| がん化の可能性 | あり | ほとんどない |
| 内視鏡での対応 | 多くの場合、切除を推奨 | 小さいものは経過観察の場合もある |
| 代表的な種類 | 腺腫 | 過形成性ポリープ、炎症性ポリープ |
炎症性腸疾患
炎症性腸疾患は、腸に原因不明の炎症が起こる病気の総称で、代表的なものに潰瘍性大腸炎やクローン病があり、下痢や腹痛、血便などの症状を繰り返し、長期にわたる治療が必要です。
内視鏡検査では、特徴的な粘膜の炎症や潰瘍、ただれなどを直接観察することができ、また、組織を採取して病理検査を行うことで、診断を確定します。便潜血検査陽性が、病気を発見するきっかけになることもあります。
- 潰瘍性大腸炎
- クローン病
その他の病気
上記以外にも、精密検査では様々な病気が見つかる可能性があり、例えば、大腸の壁の一部が外側に袋状に飛び出す大腸憩室症です。また、一時的に大腸への血流が悪くなることで炎症が起こる虚血性腸炎なども、出血の原因となります。
出血の原因を一つ一つ丁寧に確認し、総合的に診断を下すことが精密検査の役割です。
精密検査を受ける医療機関の選び方
便潜血検査で陽性となり、精密検査を受ける決心がついたら、次に考えるのはどこで検査を受けるかということです。安心して質の高い検査を受けるためには、いくつかのポイントがあります。
専門医がいるかどうかの確認
大腸内視鏡検査は、医師の技術や経験によって検査の質が大きく左右されます。消化器病専門医や消化器内視鏡専門医の資格を持つ医師が在籍しているかどうかは、一つの重要な指標です。
専門医は、内視鏡の操作技術に優れているだけでなく、病変を見分ける診断能力や、ポリープ切除などの処置に関する豊富な知識と経験を持っています。医療機関のウェブサイトなどで、医師の経歴や資格を確認することをお勧めします。
検査設備が整っているか
使用される内視鏡の性能も、検査の精度に影響します。高解像度の画像が得られる最新の機器や、特殊な光を用いて微細な病変を観察できる機能を搭載した内視鏡など、設備が充実しているかどうかも確認したいポイントです。
また、炭酸ガス送気装置を使用している医療機関も増えています。検査中にお腹の張りを起こす原因となる空気に代わり、体への吸収が早い炭酸ガスを使用することで、検査後の不快感を軽減できます。
ポリープ切除に対応できる設備が整っているかも重要です。
事前の説明が丁寧か
検査を受ける前は、誰でも不安を感じるものなので、不安を和らげるためには、事前の丁寧な説明が欠かせません。
検査の必要性、具体的な流れ、起こりうる偶発症、費用などについて、分かりやすい言葉で時間をかけて説明してくれる医療機関は信頼できます。
また、患者さんからの質問に真摯に答えてくれるかどうかも、その医療機関の姿勢を知る上で大切な点です。
医療機関選びのチェックリスト
| チェック項目 | 確認する内容 | どこで確認するか |
|---|---|---|
| 専門性 | 消化器内視鏡専門医が在籍しているか | ウェブサイト、院内掲示 |
| 設備 | 高性能な内視鏡、炭酸ガス送気装置の有無 | ウェブサイト、電話での問い合わせ |
| 説明と対応 | 事前の説明が分かりやすく、質問しやすいか | 診察時の印象、口コミ |
| 鎮静剤の使用 | 苦痛を軽減するための鎮静剤に対応しているか | ウェブサイト、電話での問い合わせ |
アクセスしやすさも考慮
大腸内視鏡検査は、事前の診察、検査当日、そして結果説明と、複数回通院することが一般的です。そのため、自宅や職場から通いやすい場所にあるかどうかも、意外と重要なポイントになります。
検査当日は、下剤の影響で体調が万全でないことや、鎮静剤を使用した場合に車の運転ができないことなどを考えると、公共交通機関でのアクセスが良い、あるいは家族の送迎がしやすい立地であると安心です。
便潜血検査陽性に関するよくある質問
ここでは、便潜血検査で陽性となった方からよく寄せられる質問と回答をまとめました。不安や疑問の解消にお役立てください。
- 症状がなくても精密検査は受けるべきか
-
必ず受けてください。大腸がんやその前段階であるポリープは、早期の段階ではほとんど自覚症状がありません。症状がないから大丈夫だろうと自己判断してしまうことが、病気の発見を遅らせる最も大きな原因となります。
便潜血検査は、症状のない段階で病気のサインを捉えるための検査です。症状の有無にかかわらず、陽性の結果が出た場合は、必ず精密検査を受けるようにしてください。
- 精密検査は痛いのか
-
過度に心配する必要はありません。大腸内視鏡検査に対して、痛い、苦しいといったイメージを持つ方も多いですが、近年では検査技術や機器の進歩により、苦痛は大幅に軽減されています。
経験豊富な専門医が内視鏡を操作することに加え、多くの医療機関では、希望に応じて鎮静剤を使用します。
鎮静剤を使うと、うとうとと眠っているようなリラックスした状態で検査を受けられるため、痛みや不快感をほとんど感じずに終えることが可能です。
- 検査後すぐに日常生活に戻れるか
-
多くの場合、大きな制限なく日常生活に戻れます。観察のみで検査が終了した場合は、食事もすぐに普段通りに戻すことができます。
ポリープを切除した場合は、出血予防のために、数日間は飲酒や激しい運動、長時間の移動などを控える必要がありますが、デスクワークなどの日常生活は問題なく行えます。
ただし、鎮静剤を使用した場合は、当日は車や自転車の運転ができませんので、その点は注意が必要です。公共交通機関を利用するか、ご家族に送迎を依頼してください。
- 痔がある場合陽性になりやすいのか
-
痔(特に内痔核など)があると、排便時に出血し、便潜血検査で陽性反応を示すことがありますが、陽性の原因が本当に痔だけによるものかは、大腸全体を精密検査で確認しない限り断定できません。
痔があるから陽性になったのだろうと自己判断し、精密検査を受けなかった結果、大腸がんの発見が遅れてしまったというケースもあります。
痔の自覚がある方でも、陽性という結果を重く受け止め、必ず精密検査を受けるようにしてください。
次に読むことをお勧めする記事
【大腸がん検診から精密検査への流れ – 内視鏡検査の手順と注意点】
便潜血検査陽性の基本を押さえたら、次は実際の精密検査の流れについて知っておくと安心です。検診から大腸内視鏡検査に至る具体的な手順を理解したい方に特に参考になる内容です。
【ポリープの良性・悪性の見分け方と診断基準】
便潜血検査について理解が深まったところで、さらに発見される可能性のあるポリープの良性・悪性の違いについても知っておくと、より全体像が見えてきます。将来のがん予防という観点からも重要な知識です。
以上
参考文献
Lee KJ, Inoue M, Otani T, Iwasaki M, Sasazuki S, Tsugane S. Colorectal cancer screening using fecal occult blood test and subsequent risk of colorectal cancer: a prospective cohort study in Japan. Cancer detection and prevention. 2007 Jan 1;31(1):3-11.
Hiwatashi N, Morimoto T, Fukao A, Sato H, Sugahara N, Hisamichi S, Toyota T. An evaluation of mass screening using fecal occult blood test for colorectal cancer in Japan: a case‐control study. Japanese journal of cancer research. 1993 Nov;84(11):1110-2.
Tanaka K, Sobue T, Zha L, Kitamura T, Sawada N, Iwasaki M, Inoue M, Yamaji T, Tsugane S. Effectiveness of screening using fecal occult blood testing and colonoscopy on the risk of colorectal cancer: The Japan Public Health Center-based Prospective Study. Journal of Epidemiology. 2023 Feb 5;33(2):91-100.
Morikawa T, Kato J, Yamaji Y, Wada R, Mitsushima T, Shiratori Y. A comparison of the immunochemical fecal occult blood test and total colonoscopy in the asymptomatic population. Gastroenterology. 2005 Aug 1;129(2):422-8.
Saito H. Screening for colorectal cancer by immunochemical fecal occult blood testing. Japanese journal of cancer research. 1996 Oct;87(10):1011-24.
Nakazato M, Yamano HO, Matsushita HO, Sato K, Fujita K, Yamanaka Y, Imai Y. Immunologic fecal occult blood test for colorectal cancer screening. Japan Medical Association Journal. 2006 Oct 18;49(5/6):203.
Kobayashi Y, Watabe H, Yamada A, Suzuki H, Hirata Y, Yamaji Y, Yoshida H, Koike K. Impact of fecal occult blood on obscure gastrointestinal bleeding: observational study. World Journal of Gastroenterology: WJG. 2015 Jan 7;21(1):326.
Taniguchi T, Hirai K, Harada K, Ishikawa Y, Nagatsuka M, Fukuyoshi J, Arai H, Mizota Y, Yamamoto S, Saito H, Shibuya D. The relationship between obtaining fecal occult blood test and beliefs regarding testing among Japanese. Health Psychology and Behavioral Medicine. 2015 Jan 1;3(1):251-62.
Nakama H, Kamijo N. Accuracy of immunological fecal occult blood testing for colorectal cancer screening. Preventive medicine. 1994 May 1;23(3):309-13.
Saito H, Soma Y, Koeda J, Wada T, Kawaguchi H, Sobue T, Aisawa T, Yoshida Y. Reduction in risk of mortality from colorectal cancer by fecal occult blood screening with immunochemical hemagglutination test. A case‐control study. International Journal of Cancer. 1995 May 16;61(4):465-9.