腸管が詰まって通りが悪くなる腸閉塞は、適切な治療を行わない場合、重篤な合併症につながる可能性がある病気です。初期に見られる症状は単に腹部の不快感だけではなく、嘔吐や便秘など消化管全体に影響することが少なくありません。
腸閉塞の定義や原因を理解し、どのようなサインがあるかを早めに把握できれば、スムーズに医療機関を受診して検査を受けることが期待できます。
本記事では腸閉塞の特徴的な症状と診断方法、内視鏡検査などさまざまな検査技術について紹介し、病態に応じた対処のポイントを詳しく解説します。
腸閉塞の基本を理解する
腸閉塞とは、消化管のどこかに閉塞または狭窄が生じ、腸内容物が先へ進みにくくなる状態を指します。小腸や大腸が詰まることでさまざまな症状が現れ、緊急性を要するケースも珍しくありません。
原因には術後癒着や腫瘍など多岐にわたり、適切な検査を行うことで病態を把握し、治療方針を決定します。
腸閉塞とはどのような状態か
腸閉塞は、腸管の通過障害によって内容物やガスの移動が遮断されることで、腹部に強い張り感や痛みを覚え、嘔吐や排便異常などがみられます。
完全に閉塞している場合と部分的に通過できる場合では症状の現れ方や緊急度が異なるため、早期の診断が重要です。
腸閉塞を引き起こす主な要因
手術歴のある方は、術後の癒着によって腸管が狭くなることが多く報告されています。腸管内部に発生した腫瘍が通過路をふさぐケースや、大腸ポリープが大きくなり狭窄を招く場合もあります。
さらに結石や食物塊が詰まることや、腸のねじれ(腸捻転)が原因となる例も挙げられます。
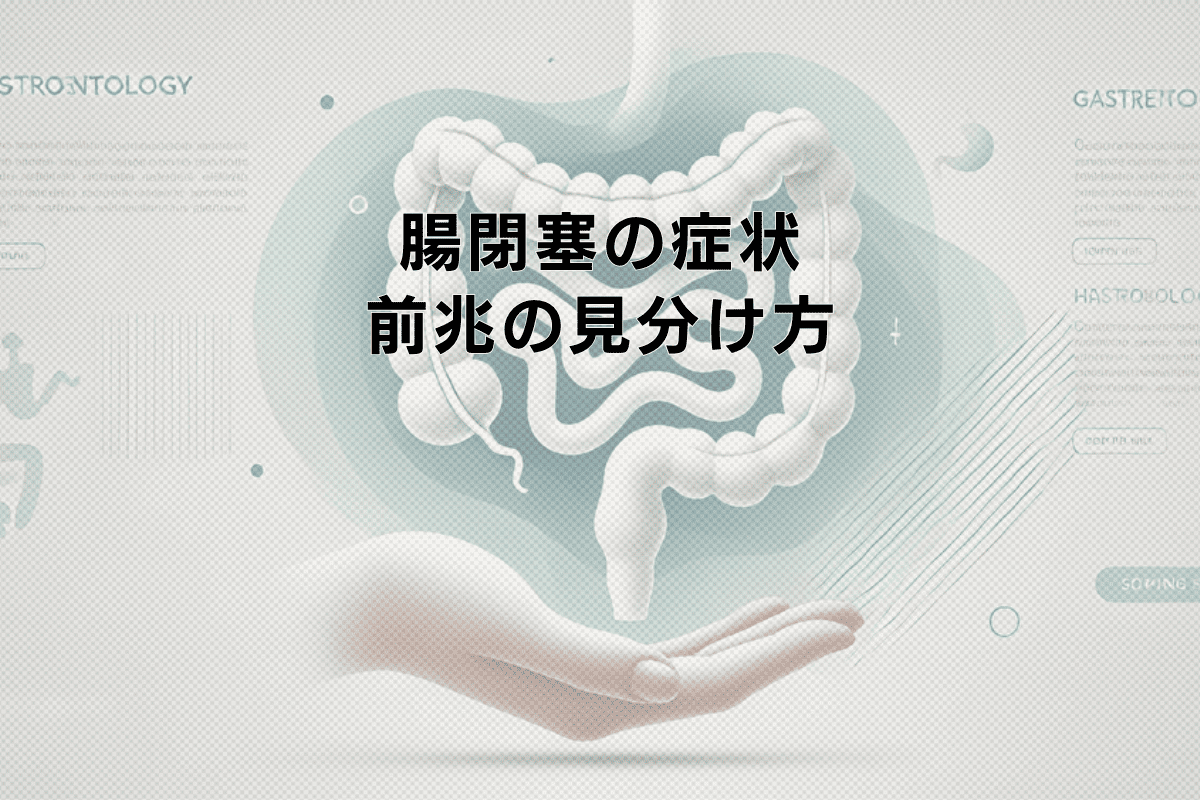
小腸と大腸で異なる特徴
腸閉塞は、小腸で起きる場合と大腸で起きる場合で症状の出方がやや異なります。小腸性は嘔吐が目立つ傾向があり、大腸性では便が排出されないことで下腹部の張りや痛みを感じることが多いです。
どちらに該当するかを把握するために、画像検査などで診断を進めます。
腸閉塞にみられる典型的な症状
腹痛や嘔吐は腸閉塞に特徴的とされ、同時に排便・排ガスが途絶える場合が少なくありません。歩くのが困難なほどの激しい痛みを伴うこともあり、放置すると腸管が壊死に至る危険性があります。
高齢者は痛みに対する感覚が低下しており、症状に気づくのが遅れる例も考えられるため注意が必要です。
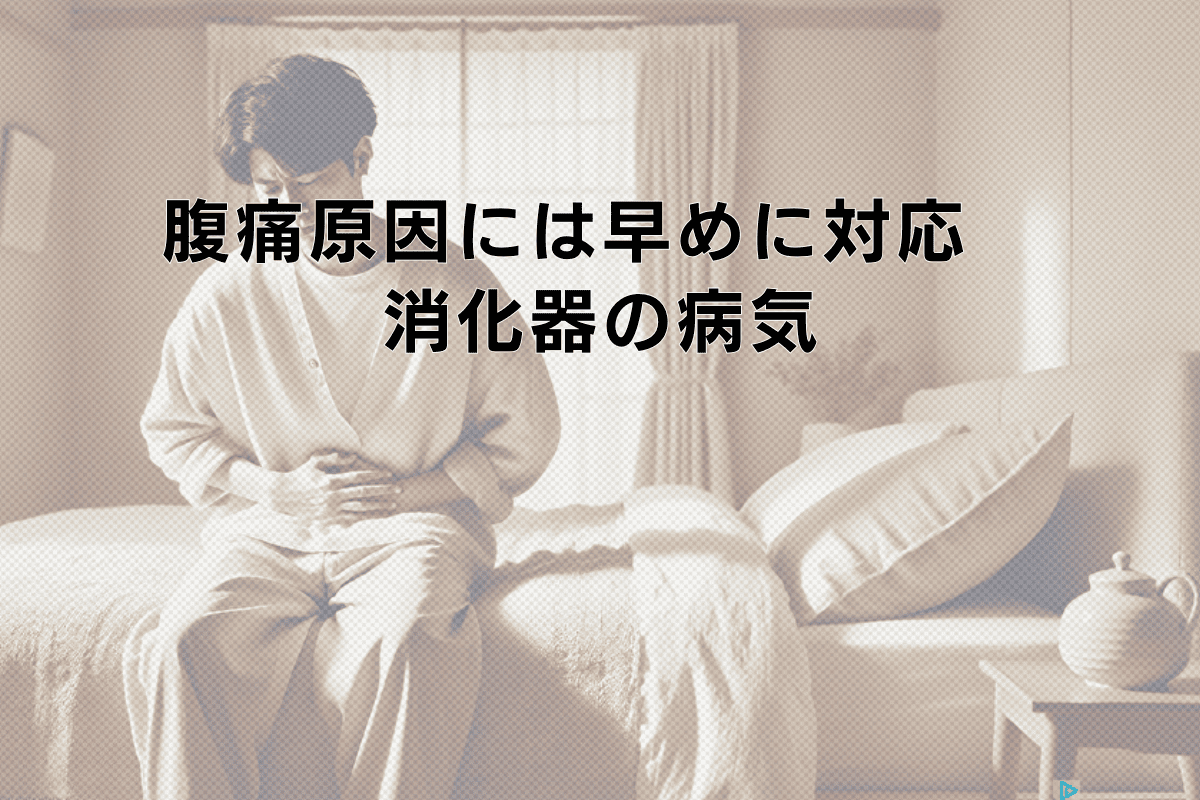
病期や程度別の症状と主な特徴
| 病期・程度 | 主な症状 | 特徴 |
|---|---|---|
| 早期 | 軽度の腹部膨満感、食欲不振 | まだ腸管の通過が部分的に可能であることが多い |
| 進行 | 明確な腹痛、嘔吐、便やガスの停止 | ガスや食物の流れが途絶し、腸内圧が上昇している |
| 重篤 | 強い腹痛や嘔吐、腹部の硬直、発熱など | 腸管の壊死や穿孔、腹膜炎を合併するリスクが高まる |
腸閉塞の原因を探る
腸閉塞を正しく判断するためには、原因の把握が欠かせません。大きく分けて機械的な要因と機能的な要因があり、治療方法や検査の進め方はそれぞれ異なり、原因を明確にすることで、適切な治療計画が立てやすくなります。
機械的要因による腸閉塞
腸管そのものが物理的に塞がったり狭くなったりするパターンが機械的要因です。代表的なものとして術後癒着が挙げられ、腹部手術後の瘢痕組織によって腸が引っ張られることがあり、ヘルニアや腸捻転、腫瘍なども該当します。
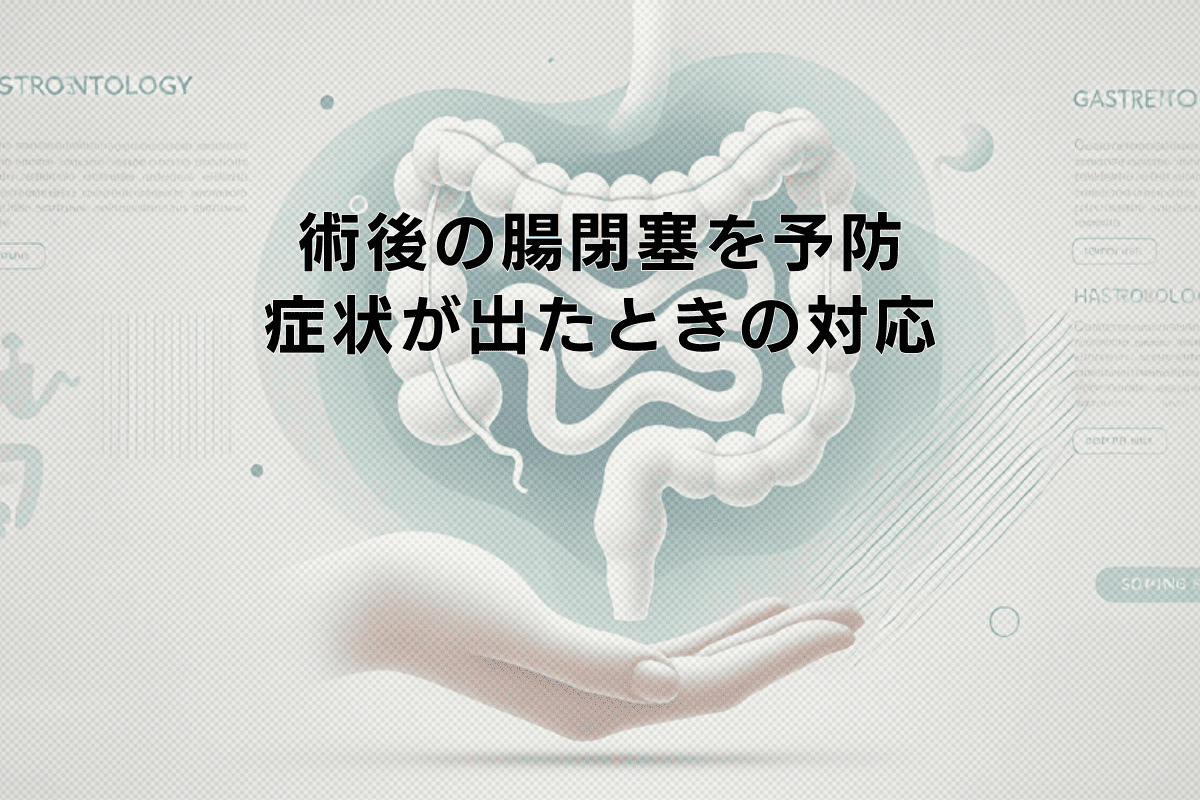
機能的要因による腸閉塞
腸管の運動機能が低下し、通過障害を引き起こすケースは機能的要因と呼ばれます。イレウスや神経因性の麻痺が関与し、腸管自体に物理的な閉塞がないにもかかわらず内容物が進まない状況です。
高齢者や重度の病気で寝たきり状態が続く方に多く見られます。
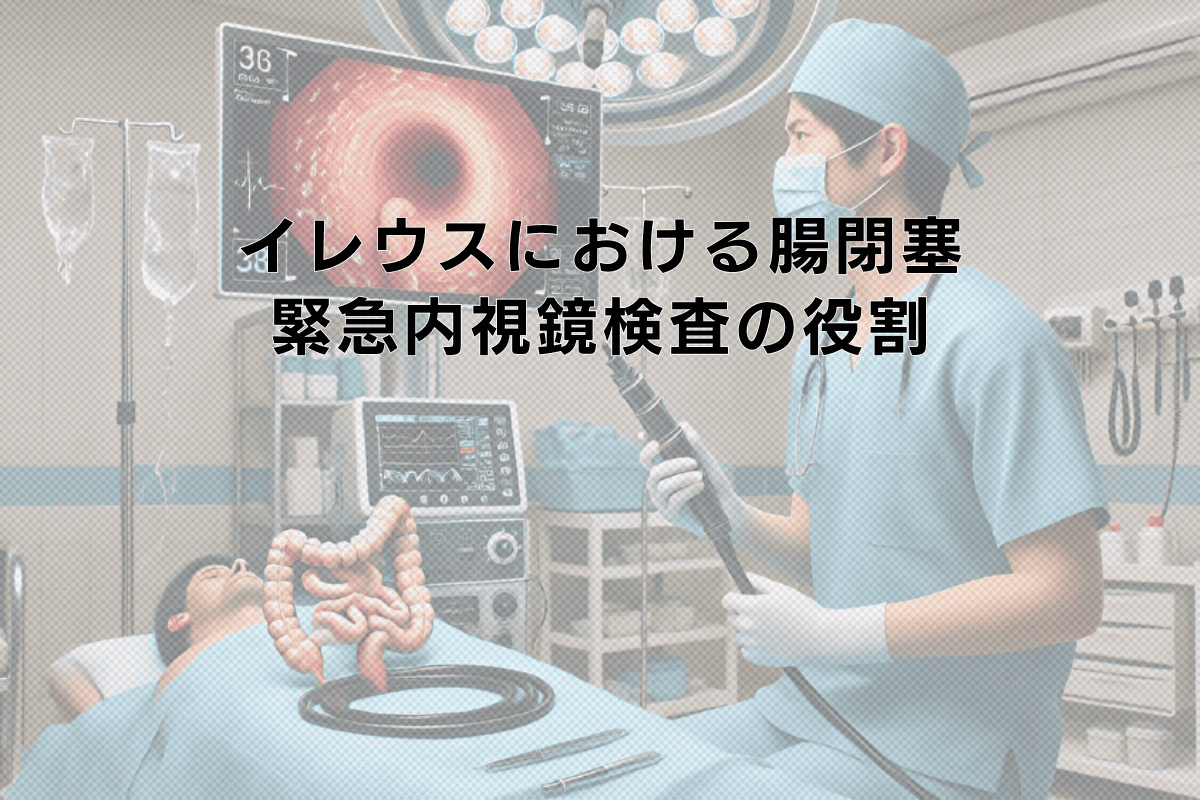
術後の癒着と腸閉塞
腹部手術の歴史がある方は、癒着性腸閉塞の可能性を常に考慮しなくてはなりません。手術の種類や手術からの経過年数を医師に伝えることで、早期発見につなげることができます。
単純に手術後すぐだけでなく、長期間経過してから発生することもあるため油断は禁物です。
腸閉塞の再発を招く要素
腸閉塞の既往があると、腸管の損傷や癒着部位が増え、再発リスクを高める例があります。また便秘が慢性化している場合や、食事の摂取バランスが偏っている場合、食物繊維不足による便塊形成が起こりやすくなり注意が必要です。
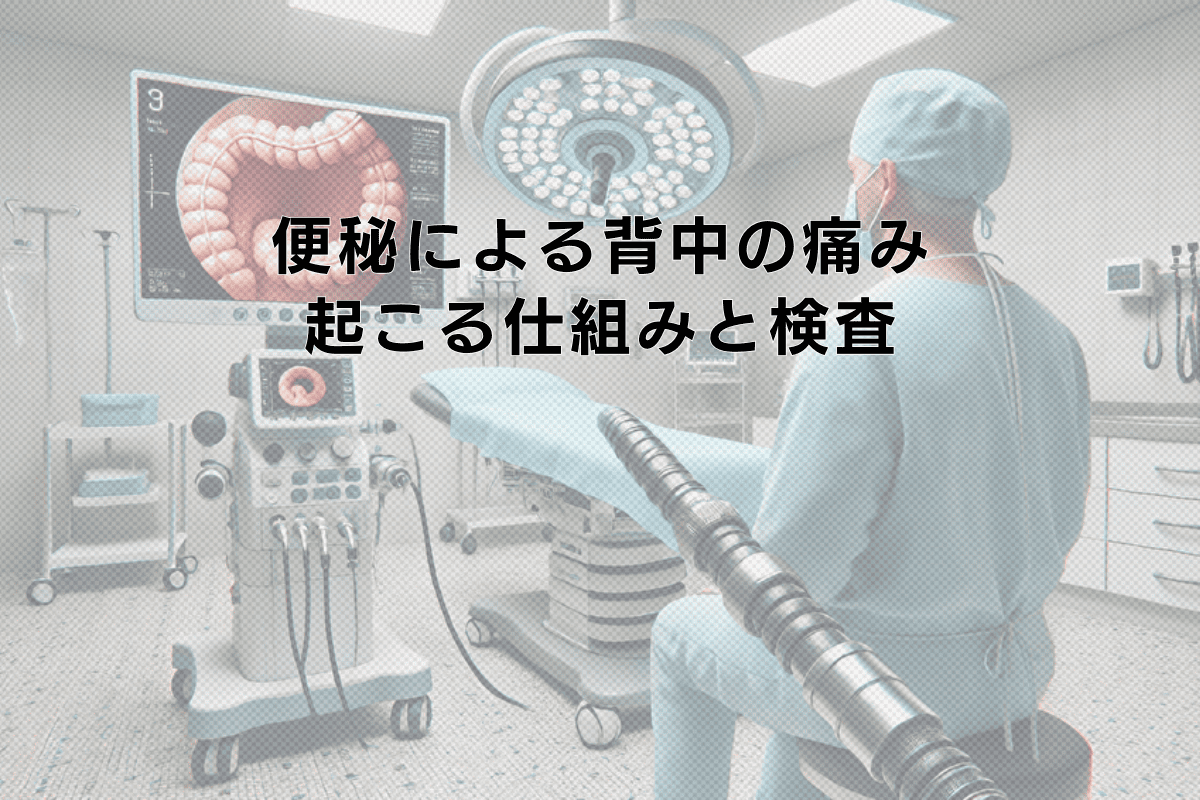
腸閉塞を起こしやすい機械的要因
| 原因 | 主な病態 | 発症のきっかけ |
|---|---|---|
| 術後癒着 | 腸管周囲が瘢痕組織でつながり、通過障害をもたらす | 腹部手術後の数日〜数年後 |
| 腸捻転 | 腸がねじれることで通路が塞がる | 便秘、腸管運動の異常、加齢など |
| 腫瘍 | 腸管内部や周囲にできた腫瘍がチューブ状の腸を圧迫 | 大腸がん、小腸腫瘍など |
| ヘルニア | 腸管が体腔外へ飛び出す状況で絞扼され、血流障害を伴う | 腹壁ヘルニアや鼠径ヘルニアの嵌頓 |
| 食物塊 | 未消化の食物が塊になり腸管を詰まらせる | 食べ物をよくかまない、義歯トラブル |
腸閉塞の症状を見極めるポイント
腸閉塞の症状は、初期には「なんとなくお腹が張る」程度かもしれませんが、急速に悪化するケースもあるため警戒が必要です。典型的な症状を把握し、疑わしい状態に早期対応できるかどうかが、治療成績に大きく影響します。
代表的な症状と経過
腹部膨満や嘔吐は腸閉塞で頻繁にみられる症状で、さらに便・ガスの停止が加わった場合にかなり強い疑いを持つべきです。
進行すると脱水症状や電解質バランスの異常がみられ、全身状態が悪化しやすくなります。発熱や強い腹痛がある場合は、腸管壊死の可能性も否定できません。
痛みの性質と場所
小腸に起こった場合は上腹部中心の痛みが、また大腸に起こった場合は下腹部の痛みが目立つ傾向があると考えられています。ただし、個人差が大きいため痛みだけで腸閉塞の部位を断定するのは難しく、検査での確定診断が求められます。
嘔吐や排ガス停止の意味
嘔吐は閉塞が小腸にあるほど早期から強く表れる可能性があり、大腸の閉塞でも嘔吐は起こり得ますが、症状が出るまでに時間がかかることが多いです。
排便・排ガスがまったくない場合は、大腸性の閉塞や完全閉塞を疑う指標となるため、自己判断せずに医療機関を受診してください。
症状が疑わしい時の生活上の注意
腸閉塞が疑われる段階では、無理に食事を摂取することや安易な下剤の使用は控えたほうが良いでしょう。
過剰な水分摂取も嘔吐を悪化させるリスクがあり、すでに症状が進行している時は、自宅療養を選ばず早めに医療機関へ行くことが大切です。
腸閉塞を見分けるためのヒント
- 腹部の膨満感が強い
- 断続的な腹痛が続く
- 便が数日出ない・ガスも出ない
- 嘔吐が止まらない
- 胃腸薬を飲んでも症状が改善しない
状態に応じた適切な検査方法
腸閉塞が疑われたときは、身体診察や画像検査を組み合わせて診断を進め、状態によっては内視鏡検査を実施することもあり、その結果から治療方針を決める流れです。
画像検査の基礎
X線検査やCT検査は腸閉塞の診断で欠かせないツールで、腹部X線では拡張した腸管内のガス像や液面形成を確認でき、CT検査ではより詳細な部位や原因を特定するのに役立ちます。
早期発見だけでなく、狭窄の程度や合併症の有無を見極めるうえでも有用です。

代表的な画像検査の比較
| 検査名 | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 腹部X線 | 比較的簡易で迅速な撮影が可能 | 透過性の違いによるガス像を把握 | 詳細な情報は少ない、放射線被ばくあり |
| 腹部CT | 断層画像で腸管の状態や周囲臓器の様子を確認 | 原因部位や絞扼などを詳細に評価 | 被ばく量が多い、造影剤の副作用に注意 |
| MRI | 磁気を利用した画像検査 | 被ばくがない、軟部組織の描出に優れる | 検査時間が長い、機器や費用面での制限がある |
| 腹部超音波 | 超音波を当てて臓器の形状や動きを観察 | 被ばくがない、簡易検査に適する | 腸ガスが多いと画像が見にくい |
内視鏡検査が果たす役割
胃カメラや大腸カメラなどの内視鏡検査は、消化管内部を直接観察できるため腫瘍や狭窄部位の状態を詳細に評価できます。
大腸の閉塞の疑いが強い場合は大腸カメラを使用し、閉塞の原因を確定することがあります。また腸閉塞が大腸がんが原因である場合は、ステントやイレウスチューブの留置など、大腸カメラを用いて腸閉塞を改善させるための処置を行うこともあります。ただし、急性期で腸管が大幅に拡張している場合などはリスクを伴うため、医師の判断が大切です。
血液検査による補助的情報
腸閉塞そのものを血液検査だけで断定することはできませんが、白血球数の増加やCRP値の上昇があれば炎症が強い可能性があります。
電解質異常や腎機能の指標を確認することで、嘔吐や脱水の度合いを把握し、治療計画に反映させることができます。
どの検査を選ぶかの目安
一般的には、腹部X線やCTでまず全体像を把握します。原因部位が大腸と特定できる場合には診断確定および腸閉塞改善のための処置を行う目的で大腸内視鏡を行うことがあります。また、小腸内部の狭窄が疑われる場合、腸閉塞が改善してから小腸内視鏡を行うこともあります。
患者さんの全身状態や既往歴によって検査順序が変わる場合もあるため、担当医と相談しながら方針を決めます。
内視鏡検査が推奨される主なシチュエーション
| シチュエーション | 目的 | 検査の注意点 |
|---|---|---|
| 大腸癌やポリープが疑われる | 腸内視診による腫瘍の確認、ステント・イレウスチューブの留置 | 閉塞が高度の場合、安全に検査が行えないことがある |
| 腸管癒着が疑われる | 部分的な狭窄の程度を視認して治療方針を立てる | 内視鏡挿入に伴うリスクを考慮 |
| 術後フォロー | 再発リスクをチェックし、狭窄部位が存在しないかを評価 | 癒着が強いと操作が難航する可能性 |
| 不明な出血源検索 | 腸閉塞と併存する消化管出血の精査 | 急性期では循環動態を優先 |
腸閉塞と内視鏡検査の関連性
内視鏡検査は大腸カメラや胃カメラを利用して、腸内視野を直接確認する方法で、腸閉塞が疑われる場合には、原因の特定や病変の有無を調べるための選択肢として検討されることが少なくありません。
大腸カメラで分かること
大腸内視鏡では大腸内部の様子を直接目視できるため、がんなどによって腸管が狭くなっているかどうかを詳細に確認でき、また、その場で生検を行ったり、閉塞部にステントやイレウスチューブを留置すし拡張した腸管を減圧することもできるので、診断だけでなく初期治療にも役立ちます。
術後癒着による狭窄部位が大腸に近い位置の場合でも、大腸カメラが有用な場合があります。

胃カメラが必要なケース
基本的には腸閉塞の場合、大腸カメラが注目されがちですが、胃や十二指腸付近の通過障害が疑われる場合、胃カメラで確認する意義があり、腫瘍性病変や胃酸過多による狭窄などが原因のとき、早期治療への手がかりになります。

内視鏡検査のリスクと注意点
強い腹部膨満や激しい嘔吐がある状態では、内視鏡検査が危険となる場合があり、腸管が極端に拡張していると穿孔リスクが上がるため、まずは減圧などの処置で状態を落ち着かせることが必要です。
また、検査前の下剤摂取が困難なケースもあるため、医師が個別に安全性を評価し、適切なタイミングで実施します。
内視鏡検査を受けるメリット
内視鏡検査によって腸内を直接観察できると、CTやX線ではわかりにくい粘膜の細かな変化や腺腫の有無を知ることができ、閉塞の原因が腫瘍であれば、その場で切除や生検を行うことで早期治療の可能性が広がります。またステントやイレウスチューブを留置することで、腸管の減圧を行うことができます。
病態を把握しつつ初期対応につなげられる点は大きな利点です。
内視鏡検査と画像検査の特性比較
| 検査手法 | 特徴 | 主に有用な点 | 留意すべき点 |
|---|---|---|---|
| 大腸カメラ | 大腸内を直接観察し、ポリープや腫瘍の切除や生検も可能 ステント・イレウスチューブを留置し減圧処置ができる | 粘膜レベルで異常を確認できる | 前処置に下剤を使用。重度閉塞時はリスク |
| 胃カメラ | 食道、胃、十二指腸を直接視認 ステント・イレウスチューブを留置し減圧処置ができる | 上部消化管の病変を詳細に評価 | 強い嘔吐や閉塞があると困難な場合がある |
| CT | 広範囲を迅速に撮影し、断層像で原因部位を把握 | 腸管外や周辺臓器も含めた評価が可能 | 被ばく量が多く、造影剤アレルギーに注意 |
| X線 | 簡易撮影でガス像や液面などを確認 | 早い段階で通過障害の有無を推測 | 情報量が限られる。詳細は不十分 |
腸閉塞の治療と検査後の管理
腸閉塞と診断された後、状態に応じて保存的治療や手術療法が検討されます。検査で原因部位や重症度を把握したうえで、具体的な治療方法を選ぶのが一般的です。
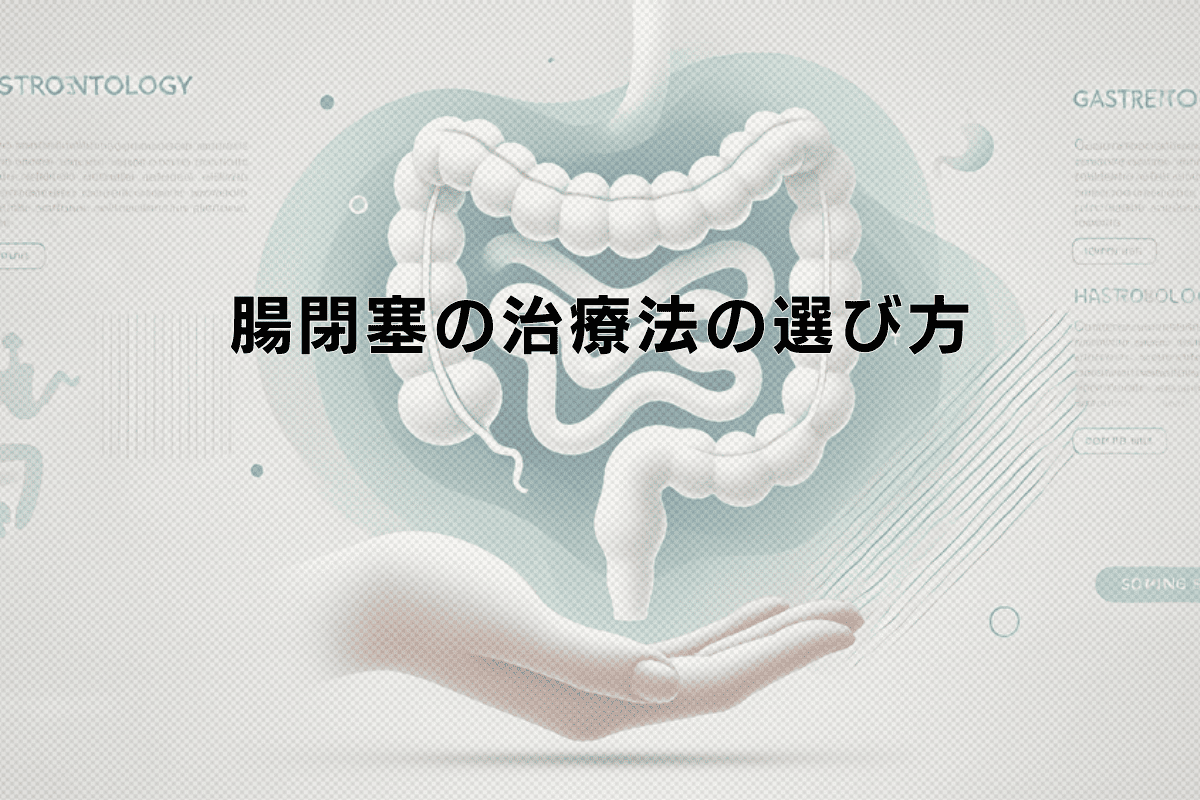
保存的治療の選択肢
腸管にねじれや絞扼がない場合、まずは点滴や経鼻胃管・イレウスチューブによる減圧などの保存的治療を行い、腹部の張りや嘔吐を軽減しつつ、腸の動きを回復するのを待ち、自然に通過障害が改善するかどうかを見極めます。
機能性の麻痺が原因の場合も、こうした保存的治療が中心となることが多いです。
保存的治療で用いられる主な方法
| 方法 | 主な目的 | 利点 |
|---|---|---|
| 経鼻胃管・イレウスチューブ挿入 | 胃や小腸に溜まった液体やガスを排出する | 腹部膨満や嘔吐を軽減 |
| 輸液・点滴 | 脱水や電解質異常を補正 | 全身状態を安定させる |
| 腸管運動促進薬 | 腸管の蠕動運動を助ける | 麻痺性イレウスなど機能的閉塞に有効 |
| 絶食・経口摂取制限 | 腸への負担を減らし、症状悪化を防ぐ | 腸内圧を下げ、炎症を緩和 |
手術療法が必要な場合
絞扼性イレウスや腫瘍による完全閉塞が疑われるケースでは、手術による速やかな治療が求めら、腸管の切除や癒着の剥離、腫瘍の切除などを行い、通過障害を解消します。
手術の種類や侵襲度は患者さんの症状や全身状態によって異なり、内視鏡的手術や開腹手術などが選択肢です。
検査後の経過観察とフォロー
腸閉塞が一旦落ち着いても、原因となった疾患が完全には取り除かれていない場合、再発リスクが残ることがあります。定期的に内視鏡検査や画像検査を受け、狭窄の進行や新たな病変の発生をチェックすることが大切です。
便通異常や腹部違和感が再び現れたら早期に医療機関を受診しましょう。
合併症の防止に向けた注意
長期にわたる閉塞状態は、腸管破裂や腹膜炎など重大な合併症につながる恐れがあり、激しい痛みや吐血・下血、発熱などの異常がみられる際は、緊急対応が必要です。
治療後もしばらくは食事や排便状況に配慮し、規則正しい生活を意識することで再発や悪化を防ぐことが期待できます。
腸閉塞治療後の注意事項
- 医師から指示のあった食事制限や水分摂取量を守る
- 適度な運動で腸の蠕動を促す
- 胃腸に負担をかけない姿勢や体位を心掛ける
- 排便記録を取り、便の状態を確認する
- 不調や痛みがあれば早めに相談する
受診タイミングと専門医の役割
腸閉塞は緊急性が高い場合もあるため、症状を自覚したら我慢せずに医療機関へ相談することが大切です。特に内視鏡検査が必要な局面では、専門の施設や専門医が在籍する病院を選ぶことで適切な対応が期待できます。
いつ受診すべきか
腹痛や嘔吐、便が出ないなどの異常を1~2日放置すると、腸閉塞が急速に進行するリスクがあり、普段から便秘がちの方でも、異常な腹部膨満や激痛がある場合は自己判断を避け、速やかに救急外来や消化器内科を受診してください。
高齢者や基礎疾患を有する方は特に慎重な対応が求められます。
内視鏡専門医の強み
内視鏡検査の技術は経験を積んだ専門医によって大きく差が出ることもあります。
腸閉塞が疑われる段階では、必要に応じて内視鏡専門医と連携をとり、スムーズに検査を実施できる体制が整っている医療機関を選ぶと診断と治療が円滑に進みやすいです。専門的なノウハウによって合併症のリスクを抑えた検査が可能となります。
かかりつけ医との連携
初期症状の段階でかかりつけ医を受診する方も多く、その際には、腹部X線や血液検査などの初期評価を行い、消化器専門医のいる施設に紹介してもらう流れになります。
もし定期的に内視鏡検査を受ける必要があるなら、かかりつけ医に相談して検査のタイミングや連携の方法を決めておくと安心です。
セカンドオピニオンを考える場合
手術療法や高度な治療が必要と告げられた際、セカンドオピニオンを求めることも選択肢の一つです。腸閉塞の原因が複雑だったり、再発リスクが高い例では、複数の専門医から意見を聞くことでベターな治療計画を模索できます。
消化器専門医選びのポイント
| 項目 | 着目する理由 | 具体的な確認方法 |
|---|---|---|
| 内視鏡検査の実績 | 腸閉塞の場合、内視鏡を用いる可能性が高い | 検査件数や施設の機器、専門医の数 |
| 救急対応の可否 | 急性症状が多いため、緊急時の対応力が重要 | 24時間体制の救急外来や病床の有無 |
| 連携病院・専門センター | 大規模病院や関連施設と協力できる体制があると安心 | 病院ホームページや受付での問い合わせ |
| 診療科の連携 | 腸閉塞は多科と連携する場合も少なくない | 外科や消化器内科、放射線科の連携状況 |
予防と早期発見の大切さ
腸閉塞は、日常のちょっとした心がけによって発症リスクを下げたり、早期に見つけたりできる可能性があります。特に食生活や定期的な検診が大きく影響するため、意識的に生活習慣を整えることが有効です。
食生活の工夫
偏った食事や摂食嚥下障害などは腸閉塞の発症リスクを高める要因になり得ます。繊維質が豊富な野菜や果物を適度に摂取し、よくかんで食べることで腸内をスムーズに通過しやすくすることが期待できます。
また、食事の量をコントロールし、急激な満腹状態を避けることも大切です。
適度な運動と排便習慣
腹筋を動かすような軽い体操やウォーキングは、腸の蠕動運動を促進する作用が期待できます。便秘になりにくい生活リズムを作るために、決まった時間にトイレに行くなどの習慣づくりを心掛けることが望ましいです。
慢性的な便秘が続くと、腸内の圧力が高まって閉塞の引き金になる場合があります。
定期的な検診と内視鏡検査
大腸がん検診や人間ドックなどで定期的に内視鏡検査を受けることで、ポリープや早期がんを発見しやすくなり、腫瘍性病変が進行して大腸を狭くする前に対処できれば、腸閉塞のリスクを減らせます。
特に高齢者や家族歴がある方は積極的に検診を受けることを検討しましょう。
腸閉塞が疑われるサインを見逃さない
腹部に違和感がある、便通が著しく乱れている、あるいは嘔吐を繰り返しているなどのサインがあれば、早めに医療機関を受診します。自己判断で市販薬を乱用すると症状をかえって悪化させるリスクがあるため注意が必要です。
病院を受診するときは普段の食生活や便の状態を医師に伝えられるよう、簡単に記録を残しておくのも有用です。
腸閉塞予防に役立つポイント
- よくかんでゆっくり食事をとる
- 食物繊維や水分を意識して摂る
- 長期の便秘に対して早めに相談する
- 適度な運動で腹部を動かす
- 定期的に内視鏡検査などのチェックを受ける
まとめ
腸閉塞は、急激な進行や重大な合併症を引き起こす恐れがある病態で、嘔吐や腹部の膨満、排便がないなどの症状に気づいた段階で、早急に適切な検査を受けることが重要です。
X線やCT、内視鏡検査などを活用して原因を見極め、保存的治療か手術療法かを判断します。
大腸カメラや胃カメラといった内視鏡検査は、腸閉塞の原因となる狭窄や腫瘍を直接確認したり、必要に応じて治療を行ったりできる大きなメリットがあります。
ただし強い腹部膨満時にはリスクがあるため、症状と全身状態を踏まえたうえで専門医の判断が欠かせません。
日常生活でも腸の健康を意識し、食事・排便・運動習慣を整えることで、腸閉塞のリスクを下げることが期待でき、腸の違和感や慢性的な便秘がある場合、定期的に検査を受けることで早期発見・早期治療につなげられます。
腸閉塞の診断から治療までは多岐にわたりますが、正確な情報を得て、専門医と相談しながら適切な対処を行うことで、合併症を防ぎながら回復を目指すことが可能です。
次に読むことをお勧めする記事
【腸閉塞の原因と治療法|早期発見と対処の重要性】
腸閉塞の症状や診断方法について理解が深まったら、次は具体的な治療法や予防策について知っておくと安心です。治療後の管理や再発予防を検討されている方に特に参考になる内容です。
【大腸がん検査方法の選び方 – 血液検査から内視鏡検査まで】
腸閉塞の原因として腫瘍性病変が気になる方は、がん検診の検査選択を学ぶことで、早期発見のチャンスが広がります。
参考文献
Franklin Jr ME, Gonzalez Jr JJ, Miter DB, Glass JL, Paulson DJ. Laparoscopic diagnosis and treatment of intestinal obstruction. Surgical Endoscopy And Other Interventional Techniques. 2004 Jan;18:26-30.
Frager D. Intestinal obstruction: role of CT. Gastroenterology Clinics. 2002 Sep 1;31(3):777-99.
Jackson PG, Raiji M. Evaluation and management of intestinal obstruction. American family physician. 2011 Jan 15;83(2):159-65.
Jackson P, Cruz MV. Intestinal obstruction: evaluation and management. American family physician. 2018 Sep 15;98(6):362-7.
Suri S, Gupta S, Sudhakar PJ, Venkataramu NK, Sood B, Wig JD. Comparative evaluation of plain films, ultrasound and CT in the diagnosis of intestinal obstruction. Acta radiologica. 1999 Jul;40(4):422-8.
Lim JH. Intestinal obstruction. InUltrasound of the gastrointestinal tract 2013 Feb 17 (pp. 45-51). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
Berry RE. Diagnosis and treatment of acute intestinal obstruction. Journal of the American Medical Association. 1952 Feb 2;148(5):347-55.
Colombo C, Ellemunter H, Houwen R, Munck A, Taylor C, Wilschanski M. Guidelines for the diagnosis and management of distal intestinal obstruction syndrome in cystic fibrosis patients. Journal of Cystic Fibrosis. 2011 Jun 1;10:S24-8.
Nelms DW, Kann BR. Imaging modalities for evaluation of intestinal obstruction. Clinics in colon and rectal surgery. 2021 Jul;34(04):205-18.
Griffiths S, Glancy DG. Intestinal obstruction. Surgery (Oxford). 2023 Jan 1;41(1):47-54.










