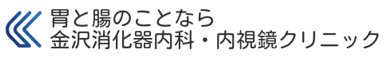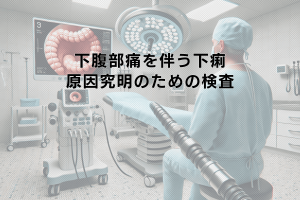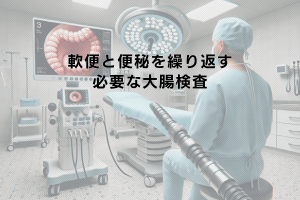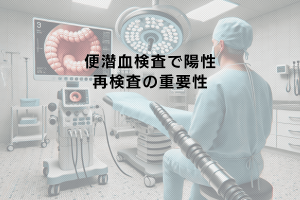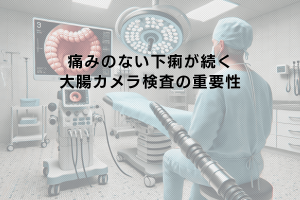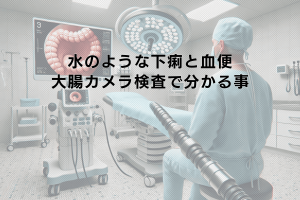下痢の際に便に粘液が混じる症状は、不安を感じるものです。
粘液は本来、腸の粘膜を保護する大切な役割を持っていますが、粘液が目に見えて増え、下痢と共に排出される時、腸が何らかの炎症や刺激に反応しているサインと考えられます。
原因は、一時的なストレスや食事によるものから、感染性腸炎、過敏性腸症候群(IBS)、さらには潰瘍性大腸炎やクローン病といった炎症性腸疾患、まれに大腸がんなどの病気が隠れている可能性も否定できません。
この記事では、下痢と粘液の関係、考えられる原因、そして大腸カメラ検査の意義について詳しく解説します。
まず知っておきたい便に混じる粘液の正体
便に粘液が混じっていると、何か悪い病気ではないかと心配になるかもしれません。粘液便そのものは、腸の正常な機能の一部でもありますが、量や見た目、伴う症状によっては注意深い観察が必要です。
粘液は腸のどこで作られるか
口から摂取した食物は、食道、胃、小腸、大腸を経て便として排出されます。長い消化管のうち、特に大腸の粘膜には、粘液を分泌する細胞が多数あり、杯細胞(さかずきさいぼう)と呼ばれ、その名の通り、杯のような形をしています。
大腸は、小腸で消化吸収された内容物から水分を吸収し、便を形成する最終段階を担います。この過程で、固形化していく便がスムーズに腸内を移動し、排出されるよう、杯細胞が粘液を分泌して腸壁を保護し、潤滑油のような働きをしています。
腸粘液が持つ本来の役割
腸粘液は単なる潤滑剤ではなく、腸の健康を維持するために、非常に多様で重要な役割を担っていて、体外から入ってくる食物や細菌と常に接している最前線です。
粘液は、この粘膜表面を覆うバリアとして機能し、腸壁が直接的なダメージを受けるのを防いでいます。
また、腸内には多種多様な腸内細菌が存在しますが、粘液層はこれらの細菌が腸の細胞に過剰に近づきすぎないよう、適度な距離を保つ役割も果たしています。
腸粘液の主な機能
| 機能 | 具体的な働き | 腸への貢献 |
|---|---|---|
| 粘膜保護 | 便の物理的な摩擦から腸壁を守る。 | 腸粘膜の損傷を防ぐ。 |
| 潤滑 | 便の移動をスムーズにし、排便を助ける。 | 便秘の緩和や快適な排便。 |
| バリア機能 | 細菌やウイルス、毒素が腸壁に侵入するのを防ぐ。 | 感染症の予防と腸内環境の安定。 |
健康な状態でも粘液は存在する
粘液は腸の健康維持に必要であり、健康な人でも日々一定量が作られ、便と共に排出されていますが、通常は便とよく混ざり合っているため、肉眼で粘液だけをはっきりと認識することはほとんどありません。
粘液の存在に気づくのは、量が通常よりも明らかに増えた時や、便の表面にゼリー状のかたまりとして付着している時です。
粘液が目に見えること自体が、必ずしも異常とは限りませんが、腸内環境の変化を示す一つのサインである可能性はあります。
便の表面に付着する粘液
便全体に混ざっているのではなく、便の表面を覆うように付着している粘液は、大腸の出口に近い部分(S状結腸や直腸)での分泌が亢進していることを示唆します。
この部分で炎症や刺激が起こると、粘液の分泌が活発になり、便が通過する際にその表面に付着することがあります。
また、便秘の人が硬い便を排泄する際に、腸が粘膜を保護しようとして粘液を多く出すこともありますが、下痢と同時に起こる場合は、単なる便秘とは異なる原因を考えることが必要です。
下痢の際に粘液がみられる主な原因
下痢の時に粘液が混じる場合、腸が通常よりも活発に粘液を分泌している状態を示しており、これは、腸粘膜が何らかの刺激や炎症に対して防御反応を示している結果と考えられます。
原因は多岐にわたり、一時的なものから慢性的な病気までさまざまです。
腸の炎症による粘液の過剰分泌
腸の粘膜に炎症が起こると、粘膜を保護しようとする生体反応として、杯細胞が刺激され粘液の分泌が著しく増加します。
炎症が起こると、腸壁の細胞が傷つき、そこから水分(滲出液)も多く分泌され、粘液と混ざり合い、便の水分量を増やして下痢を起こすのです。
炎症の原因としては、細菌やウイルスの感染、あるいは免疫系の異常によるもの(炎症性腸疾患など)が挙げられ、炎症が強い場合は、粘液に血液が混じる(粘血便)こともあります。
腸の運動異常と粘液の排出
腸の機能に問題が生じ、便を送り出す運動(蠕動運動)が過剰に活発になると、腸の内容物が急速に通過し、水分吸収が不十分となって下痢を起こします。このような腸の運動異常は、自律神経のバランスの乱れと関連が深いです。
ストレスが誘因となる過敏性腸症候群(IBS)では、腸が刺激に敏感になり、下痢や便秘を繰り返します。この際、腸の運動が亢進することで、腸内で作られた粘液も便と一緒に排出されやすくなり、粘液便として認識されることがあります。
下痢と粘液の主な原因分類
| 原因の分類 | 主な例 | 粘液がみられる理由 |
|---|---|---|
| 機能的な問題 | 過敏性腸症候群(IBS) | 腸の運動異常により粘液が排出されやすい。 |
| 炎症性の問題 | 感染性腸炎、炎症性腸疾患 | 粘膜の炎症とびらんにより粘液分泌が亢進。 |
| その他の要因 | 食事(刺激物、アレルギー)、薬剤 | 腸への直接的な刺激により粘液分泌が増加。 |
感染症が起こす腸粘膜の反応
細菌(サルモネラ、カンピロバクター、病原性大腸菌など)やウイルス(ノロウイルス、ロタウイルスなど)が腸に感染すると、急性の腸炎を起こします。
病原体や毒素が腸粘膜を直接攻撃し、強い炎症反応が起こります。体は病原体を排出しようとして、腸の運動を活発にし、水分や粘液の分泌を増やし、水のような下痢や粘液を伴う下痢、時には発熱や腹痛、嘔吐などの症状が現れます。
感染性腸炎による粘液便は、体が異物と戦っている証拠です。
食事やストレスの影響
特定の食べ物も腸を刺激し、粘液の分泌を増やすことがあります。
香辛料の多い刺激的な食事、脂っこい食事、アルコールの過剰摂取などは、腸粘膜に負担をかけ、一時的に下痢や粘液の増加を起こすことがあり、また、食物アレルギーが関与している場合もあります。
精神的なストレスも腸の機能に大きく影響し、ストレスは自律神経のバランスを乱し、腸の運動や感受性に異常をもたらし、過敏性腸症候群(IBS)の主な誘因の一つです。
ストレスを感じると下痢をしやすく、その際に粘液が目立つという人は少なくありません。
粘液を伴う下痢で考えられる消化器の病気
粘液を伴う下痢が続く場合、一時的な体調不良ではなく、背景に特定の消化器の病気が隠れている可能性があります。原因を特定し、適切な治療につなげるためには、どのような病気が考えられるかを知っておくことが重要です。
過敏性腸症候群(IBS)
過敏性腸症候群(Irritable Bowel Syndrome: IBS)は、大腸カメラ検査などでは粘膜に明らかな炎症や潰瘍といった異常が見つからないにもかかわらず、腹痛や腹部の不快感を伴う下痢や便秘が慢性的に続く病気です。
ストレスや生活リズムの乱れ、腸内細菌叢の変化などが関与していると考えられています。
IBSでは、腸が知覚過敏な状態になり、わずかな刺激(食事や精神的ストレスなど)でも腸の運動が異常に活発になったり、痙攣したりします。
下痢型のIBSの場合、急な便意と共に下痢が起こり、腸粘液が過剰に排出されることがあり、また、便が兎の糞のようにコロコロになる便秘型や、下痢と便秘を繰り返す混合型もあります。
IBSの主な症状タイプ
- 下痢型(IBS-D): 頻繁な下痢、腹痛、粘液便
- 便秘型(IBS-C): 硬い便、排便困難、腹部膨満感
- 混合型(IBS-M): 下痢と便秘を交互に繰り返す
- 分類不能型(IBS-U): 上記のいずれにも当てはまらない
炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎・クローン病)
炎症性腸疾患(Inflammatory Bowel Disease: IBD)は、腸に慢性的な炎症や潰瘍を起こす原因不明の病気の総称です。主に潰瘍性大腸炎とクローン病の二つがあります。
免疫系の異常が関与していると考えられており、症状が良くなったり(寛解)悪くなったり(再燃)を繰り返す特徴があります。
潰瘍性大腸炎は、主に大腸の粘膜に炎症が起こり、直腸から連続的に炎症が広がり、特徴的な症状は、粘液と血液が混じった便(粘血便)や下痢、腹痛です。
クローン病は、口から肛門までの消化管のあらゆる場所に炎症が起こりうる病気で、炎症が粘膜の深い層まで及ぶ(縦走潰瘍)ことがあります。下痢や腹痛、体重減少、発熱などが主な症状ですが、粘液便もみられます。
潰瘍性大腸炎とクローン病の比較(主な特徴)
| 特徴 | 潰瘍性大腸炎 | クローン病 |
|---|---|---|
| 主な炎症部位 | 大腸(特に直腸から連続的) | 消化管全体(小腸・大腸に多い) |
| 炎症の深さ | 粘膜層(浅い) | 全層性(深い) |
| 主な症状 | 粘血便、下痢、腹痛 | 下痢、腹痛、体重減少、発熱 |
感染性腸炎(細菌やウイルス)
前述の通り、細菌、ウイルス、寄生虫などの病原体に感染することによって起こる腸炎です。多くは急性に発症し、下痢、腹痛、発熱、嘔吐などを伴います。病原体が腸粘膜を傷つけることで炎症が起こり、粘液の分泌が増加します。
原因となる病原体によっては、粘液だけでなく血液が混じることもあります(出血性大腸炎など)。
食中毒や、汚染された水・食品の摂取、あるいは人から人への感染(ノロウイルスなど)が原因で、ほとんどの場合は数日から1週間程度で自然に回復しますが、症状が激しい場合や、高齢者・小児では脱水症状に注意が必要です。
感染性腸炎の主な原因
| 分類 | 主な病原体 | 特徴 |
|---|---|---|
| 細菌性 | カンピロバクター、サルモネラ、病原性大腸菌 | 鶏肉や卵の生食、加熱不足が原因となることも。血便を伴う場合がある。 |
| ウイルス性 | ノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルス | 冬季に流行しやすい。感染力が強い。水様性の下痢や嘔吐が主。 |
大腸がんや大腸ポリープ
大腸がんや大腸ポリープ(特に腺腫)が原因で粘液便がみられることもあります。初期段階では自覚症状がほとんどありませんが、がんやポリープが大きくなると、その表面から粘液が分泌されたり、出血したりすることがあります。
便が腸を通過する際に、がんやポリープの表面をこするため、便に粘液や血液が付着し、また、がんによって腸が狭くなる(狭窄)と、便が通りにくくなり、便秘と下痢を繰り返す(便通異常)こともあります。
粘液便に加えて、便が細くなる、残便感がある、腹痛、体重減少などの症状が伴う場合は、特に注意が必要です。大腸がんは早期発見が非常に重要な病気であり、粘液便が続く場合には大腸カメラ検査による確認が推奨されます。
危険なサイン?すぐに医療機関を受診すべき症状
粘液を伴う下痢は、多くの場合、様子を見ているうちに改善することもありますが、中には深刻な病気が隠れており、早期の対応が必要なケースもあります。
どのような症状がみられたら医療機関を受診すべきか、目安を知っておきましょう。
粘液に血液が混じる(粘血便)
最も注意すべきサインの一つが、粘液に血液が混じるいわゆる粘血便で、便に赤い血が筋状に付着している、粘液自体が赤黒い、あるいは便全体が血液と混じって暗赤色になっているなど、見た目はさまざまです。
血液が混じるということは、消化管のどこかで出血が起きていることを意味します。
大腸の粘膜が炎症や潰瘍によって深く傷ついている(潰瘍性大腸炎、クローン病、感染性腸炎など)、あるいは大腸ポリープや大腸がんから出血している可能性があります。
痔(いぼ痔やきれ痔)による出血も考えられますが、下痢と粘液を伴う場合は腸自体の問題を疑う必要があるので、自己判断せず、必ず消化器内科を受診してください。
激しい腹痛や高熱を伴う
下痢や粘液便に加えて、我慢できないほどの激しい腹痛、差し込むような痛みが続く場合も注意が必要です。
これは、腸の炎症が非常に強いこと(重症の感染性腸炎や炎症性腸疾患の再燃など)や、腸の運動が極度に異常になっていることを示唆します。
また、38度を超えるような高熱を伴う場合、体内で強い炎症や感染が起きているサインです。特に細菌性の腸炎では高熱が出やすく、適切な抗菌薬治療が必要となることがあります。
激しい腹痛や高熱がある場合は、夜間や休日であっても医療機関への相談を検討してください。
症状が長期間続くあるいは悪化する
一時的な下痢や粘液便であれば、1〜2日で症状が和らぐことが多いです。
しかし、市販の薬を飲んでも症状が改善しない、あるいは一度治まったように見えてもすぐに再発するなど、症状が1週間以上慢性的に続く場合は、単なる食べ過ぎや一過性のストレスとは異なる原因が考えられます。
過敏性腸症候群や、炎症性腸疾患(IBD)のような慢性的な病気は、症状が良くなったり悪くなったりを繰り返し、症状が長引くほど、体力の消耗や栄養状態の悪化にもつながります。
症状が続く、あるいは徐々に悪化していると感じたら、受診のタイミングです。
受診を推奨する症状
- 粘液に血液が混じっている
- 激しい腹痛や持続する腹痛
- 38度以上の発熱
- 症状が1週間以上続いている
- 下痢や粘液便の頻度・量が悪化している
- 体重が意図せず減少している
体重減少や貧血がみられる
下痢が続くと、水分だけでなく栄養素の吸収も妨げられ、食事をきちんと摂っているつもりでも、意図せず体重が減少することがあります。特に半年間で5%以上の体重減少がある場合は、注意信号です。
炎症性腸疾患や大腸がんなど、体がエネルギーを消耗する病気や、栄養吸収を著しく妨げる病気の可能性があります。
また、貧血の症状(めまい、立ちくらみ、動悸、倦怠感)がみられる場合、粘血便のように目に見える出血がなくても、消化管内で持続的に微量の出血が起きている(慢性出血)可能性が疑われます。
消化器内科で行う検査の流れ
粘液を伴う下痢の症状で消化器内科を受診した場合、まずは症状の原因を特定するための検査を行います。ここでは、一般的に行われる検査の流れを紹介します。
問診で症状を詳しく確認
検査の第一歩は、患者さんから詳しいお話を伺う問診です。
いつから症状が始まったか、下痢や粘液の頻度・性状(水様便か、泥状便か)、粘液の色(透明か、白濁しているか、血が混じっているか)、腹痛の有無や程度、発熱や嘔吐などの他の症状を確認します。
また、食事の内容(特に症状が出る前に食べたもの)、最近の生活環境の変化やストレスの有無、海外渡航歴、服用中の薬剤、過去の病気の履歴(既往歴)やご家族の病気の履歴(家族歴)などもお聞きします。
便検査や血液検査の目的
問診の次に行われることが多いのが、便検査と血液検査です。
便検査では、便の中に血液が混じっていないか(便潜血検査)、細菌やウイルスの感染がないか(便培養検査、抗原検査)、寄生虫がいないかなどを調べます。
血液検査では、体内で炎症が起きていないか(白血球数、CRPなど)、貧血が起きていないか(赤血球数、ヘモグロビン値)、栄養状態はどうか(アルブミンなど)、肝臓や腎臓の機能に異常はないかなどを確認します。
消化器内科での主な検査
| 検査の種類 | 主な目的 | この検査で分かること(例) |
|---|---|---|
| 問診 | 症状の全体像の把握 | 症状の経過、考えられる誘因、緊急性の判断 |
| 便検査 | 便の性状の確認 | 便潜血の有無、感染症(細菌・ウイルス)の有無 |
| 血液検査 | 全身状態の評価 | 炎症反応の程度、貧血の有無、栄養状態 |
必要に応じた画像検査(腹部エコーなど)
症状や他の検査結果に応じて、画像検査が行われることもあります。
腹部超音波(エコー)検査は、臓器(肝臓、胆のう、すい臓、腎臓など)の状態や、腸のむくみ(腸壁肥厚)、腹水の有無などを大まかに確認できる検査で、腹痛が強い場合などに、他の内臓の病気が隠れていないか調べるために有用です。
場合によっては、腹部CT検査が行われることもあり、腸の炎症の範囲や程度、腸以外の臓器の異常をより詳細に調べるのに役立ちます。
大腸カメラ検査の検討
検査を行っても原因がはっきりしない場合や、問診の段階で炎症性腸疾患や大腸がんなどが強く疑われる場合、あるいは粘血便がみられる場合には、大腸カメラ検査(大腸内視鏡検査)が検討されます。
大腸カメラ検査は、肛門から内視鏡(先端にカメラがついた細く柔らかいチューブ)を挿入し、大腸(直腸から盲腸まで)の内部を直接観察する検査です。
粘液の原因となっている炎症、潰瘍、ポリープ、がんなどを目で見て確認できるため、確定診断のために非常に重要な検査となります。
大腸カメラ検査で粘膜を直接確認する重要性
粘液を伴う下痢の原因を正確に診断する上で、大腸カメラ検査は中心的な役割を果たします。血液検査や画像検査では分からない、大腸粘膜の微細な変化を直接捉えることができる唯一の検査方法です。
大腸粘膜の状態をリアルタイムで観察
大腸カメラ検査の最大の利点は、医師がモニターを通して大腸の内部をリアルタイムで、隅々まで観察できる点にあります。
粘膜の色調の変化(赤くなっている、白っぽくなっている)、血管の走り方(血管透見像)、粘膜の腫れ(浮腫)、ただれ(びらん)や潰瘍の有無、出血の箇所などを詳細に確認します。
過敏性腸症候群(IBS)の場合は、基本的に粘膜に異常な所見は見られませんが、感染性腸炎では粘膜のびらんや発赤、浮腫が、潰瘍性大腸炎では特徴的な粘膜のもろさや広範囲の炎症像が観察されます。
大腸カメラで確認できる主な所見
- 粘膜の発赤・腫脹(炎症)
- びらん・潰瘍(粘膜の欠損)
- ポリープ(粘膜の隆起)
- がん(不整な隆起や陥凹)
- 出血部位
炎症や潰瘍の範囲と程度の把握
炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病)が疑われる場合、大腸カメラ検査は診断に不可欠です。潰瘍性大腸炎は、基本的に直腸から始まり、口側(盲腸側)に向かって連続的に炎症が広がる特徴があります。
炎症が直腸だけにとどまっているのか、大腸全体に広がっているのかを把握することは、病気の重症度を判断し、治療法を選択する上で非常に重要です。
クローン病は、炎症が連続せず、正常な粘膜を挟んで飛び飛びに発生する(スキップ・リージョン)ことや、特徴的な縦走潰瘍が見られることがあります。大腸カメラでこのような所見を確認することが、二つの病気を鑑別する手がかりとなります。
ポリープや早期がんの発見
粘液便や便通異常の原因として、大腸ポリープや大腸がんの可能性も考慮しなければなりません。検査でポリープが発見された場合、その場で切除(内視鏡的ポリープ切除術)が可能な場合も多いです。
ポリープには、がん化する可能性のある腺腫と、がん化の心配が少ない過形成性ポリープなどがあるので、切除することは、将来の大腸がん予防に直結します。
大腸ポリープの種類(簡易)
| ポリープの種類 | 特徴 | 対応 |
|---|---|---|
| 腺腫性ポリープ | がん化する可能性がある(前がん病変) | 内視鏡的切除が推奨されることが多い |
| 過形成性ポリープ | 基本的にはがん化しないとされる | 小さいものは経過観察の場合もある |
診断を確定するための組織採取(生検)
大腸カメラ検査では、疑わしい病変が見つかった場合、その場で粘膜の一部を少量採取(生検)することができ、採取した組織は、顕微鏡で詳しく調べる病理検査に回されます。
病理検査によって、炎症がどの程度のものか、感染症に特徴的な所見がないか、あるいはポリープやがんの細胞が良性か悪性か、といった最終的な確定診断が可能です。
潰瘍性大腸炎とクローン病の鑑別や、大腸がんの診断は、生検による病理診断が決め手となり、見た目だけでは判断が難しい場合でも、組織を調べることで正確な情報が得られます。
検査後の診断と日常生活での注意点
大腸カメラ検査やその他の検査結果が出揃うと、医師は情報を総合的に判断し、粘液を伴う下痢の原因についての診断を行います。
検査結果に基づく診断の告知
医師は、検査で得られた所見(大腸カメラの画像、病理検査の結果、血液検査の数値など)を患者さんに示しながら、診断名を説明します。
過敏性腸症候群(IBS)、感染性腸炎、潰瘍性大腸炎、クローン病、あるいは大腸ポリープや大腸がんなどの診断が告げられます。
この時、なぜその診断に至ったのか、病気の現在の状態(重症度や活動性)、今後どのような経過をたどる可能性があるのかについても説明があります。
疑問や不安な点があれば医師に質問し、ご自身の状態を正確に理解することが大切です。
病気に応じた治療方針
診断名によって、治療方針は大きく異なります。
感染性腸炎であれば、水分補給を中心とした対症療法が基本となり、細菌性が疑われる場合には抗菌薬が処方されることがあります。
過敏性腸症候群(IBS)であれば、まずは食事や運動、睡眠といった生活習慣の見直しとストレス管理が中心で、その上で、腸の運動を調整する薬や、便の硬さを調節する薬などが用いられます。
炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎、クローン病)の場合は、腸の異常な炎症を抑えるための薬物治療(5-ASA製剤、ステロイド、免疫調節薬、生物学的製剤など)が中心となり、長期的な管理が必要です。
大腸ポリープが見つかった場合は、内視鏡的に切除が行われることが多く、大腸がんが発見された場合は、進行度に応じて内視鏡治療、手術、化学療法などが検討されます。
食事面で気をつけること
粘液を伴う下痢の症状がある場合、腸はデリケートな状態になっているので、診断された病気によって推奨される食事内容は異なりますが、一般的に腸への負担を減らすことが基本です。
下痢や炎症が強い時期は、消化が良く、腸を刺激しない食事が大切で、脂っこい食事、香辛料などの刺激物、アルコール、カフェイン、冷たすぎる飲み物は避けてください。
また、炎症性腸疾患の場合は、食物繊維の多い食品が腸の負担になることもあるため、医師や栄養士の指導に従う必要があります。
診断後の一般的な食事の注意点(概要)
| 診断名(例) | 食事のポイント | 避けた方がよい食品(例) |
|---|---|---|
| IBS(下痢型) | 低FODMAP食の検討、刺激物を避ける | 高脂肪食、香辛料、アルコール、カフェイン |
| 炎症性腸疾患(活動期) | 低脂肪・低残渣(食物繊維が少ない)食事 | ごぼう、きのこ類、海藻類、脂身の多い肉 |
| 感染性腸炎 | 消化の良いもの、十分な水分補給 | 冷たい飲料、生もの、高脂肪食 |
生活習慣の見直しとストレス管理
腸の健康は、日々の生活習慣と密接に関連していて、特にIBSのようにストレスが大きく関与する病気では、生活習慣の改善が症状の緩和に直結することがあります。
十分な睡眠時間の確保、規則正しい食生活、適度な運動は、自律神経のバランスを整え、腸の機能を安定させるのに役立ちます。
また、ご自身が何に対してストレスを感じやすいかを認識し、リラックスできる時間を持つことも重要です。
生活習慣で見直したい点
- 睡眠不足の解消
- 1日3食の規則正しい食事
- ウォーキングなどの適度な運動
- ストレス発散方法の確保
Q&A
粘液を伴う下痢症状や大腸カメラ検査に関して、よく寄せられる質問にお答えします。
- 粘液が少しだけ便についている場合も受診は必要ですか?
-
健康な状態でも粘液は作られており、便秘の時などに一時的に粘液が目に見えることもあります。下痢や腹痛、発熱、血便などの他の症状がなく、粘液の付着が一時的なものであれば、過度に心配する必要はありません。
しかし、粘液が目に見える状態が何日も続く場合や、粘液の量が明らかに増えていると感じる場合は、腸内環境に何らかの変化が起きている可能性があるので、一度、消化器内科で相談してください。
- 子どもの下痢に粘液が混じっている場合はどうしたらよいですか?
-
子どもの場合、下痢の多くはウイルス性の感染性腸炎によるもので、粘液が混じることも珍しくありません。最も大切なことは、下痢による脱水症状を防ぐことです。
水分(湯冷まし、麦茶、幼児用のイオン飲料など)を少量ずつ頻回に与えましょう。
機嫌が良く、水分が摂れていれば、家で様子を見ることも可能ですが、ぐったりしている、水分を全く受け付けない、血便が出た、高熱が続くといった場合は、早急にかかりつけの小児科を受診してください。
- 大腸カメラ検査はどのくらいの頻度で受けるべきですか?
-
大腸カメラ検査を受ける頻度は、その方の年齢、過去の検査結果、家族歴(血縁者に大腸がんの方がいるか)などによって異なります。
40歳を過ぎて一度も検査を受けたことがない方、便潜血検査で陽性となった方、あるいは大腸ポリープを切除した経験がある方、炎症性腸疾患と診断されている方などは、定期的な検査が推奨されます。検査で異常がなかった場合でも、年齢やリスクに応じて3〜5年に1回程度の検査が勧められることがありますが、適切な間隔は個人差が大きいため、医師と相談して決めることが重要です。
- 検査のために下剤を飲むのが不安です?
-
大腸カメラ検査で正確な観察を行うためには、腸の中を空にしておく必要があり、検査前に下剤(腸管洗浄剤)を服用します。
約1リットルから2リットルの量を数時間かけて飲む必要があり、準備が大変ですが、最近では、下剤の種類も増えており、従来のものより飲みやすくなったものや、錠剤タイプのもの、飲む量が比較的少ないものなども選択肢としてあります。
また、院内で下剤を服用する(院内下剤)方法や、検査時の鎮静剤の使用など、できるだけ苦痛を軽減する工夫を行っている医療機関も多いです。
以上
参考文献
Yamauchi Y, Arai M, Akizue N, Ohta Y, Okimoto K, Matsumura T, Fan MM, Imai C, Tawada A, Kato J, Kato N. Colonoscopic evaluation of diarrhea/colitis occurring as an immune-related adverse event. Japanese Journal of Clinical Oncology. 2021 Mar;51(3):363-70.
Arai M, Taida T, Fan MM, Imai C, Tawada A, Takiguchi Y. Evaluation of diarrhea as immune-related adverse event by colonoscopy. Annals of Oncology. 2018 Oct 1;29:vii56.
Kinoshita Y, Ariyoshi R, Fujigaki S, Tanaka K, Morikawa T, Sanuki T. Endoscopic diagnosis of chronic diarrhea. DEN open. 2022 Apr;2(1):e53.
Loktionov A, Chhaya V, Bandaletova T, Poullis A. Assessment of cytology and mucin 2 in colorectal mucus collected from patients with inflammatory bowel disease: Results of a pilot trial. Journal of Gastroenterology and Hepatology. 2016 Feb;31(2):326-33.
Bo-Linn GW, Vendrell DD, Lee E, Fordtran JS. An evaluation of the significance of microscopic colitis in patients with chronic diarrhea. The Journal of clinical investigation. 1985 May 1;75(5):1559-69.
Sakdyyah A, Bestari MB, Suryanti S. Description of colonoscopy and histopathology of chronic diarrhea causes in non-neoplasm: literature review. The Indonesian Journal of Gastroenterology, Hepatology, and Digestive Endoscopy. 2021 May 12;22(1):52-9.
Juckett G, Trivedi R. Evaluation of chronic diarrhea. American family physician. 2011 Nov 15;84(10):1119-26.
Loktionov A, Chhaya V, Bandaletova T, Poullis A. Inflammatory bowel disease detection and monitoring by measuring biomarkers in non‐invasively collected colorectal mucus. Journal of Gastroenterology and Hepatology. 2017 May;32(5):992-1002.
Järbrink-Sehgal ME, Rassam L, Jasim A, Walker MM, Talley NJ, Agréus L, Andreasson A, Schmidt PT. Diverticulosis, symptoms and colonic inflammation: a population-based colonoscopy study. Official journal of the American College of Gastroenterology| ACG. 2019 Mar 1;114(3):500-10.
Misra V, Misra SP, Dwivedi M, Singh PA, Agarwal V. Microscopic colitis in patients presenting with chronic diarrhea. Indian Journal of Pathology and Microbiology. 2010 Jan 1;53(1):15-9.