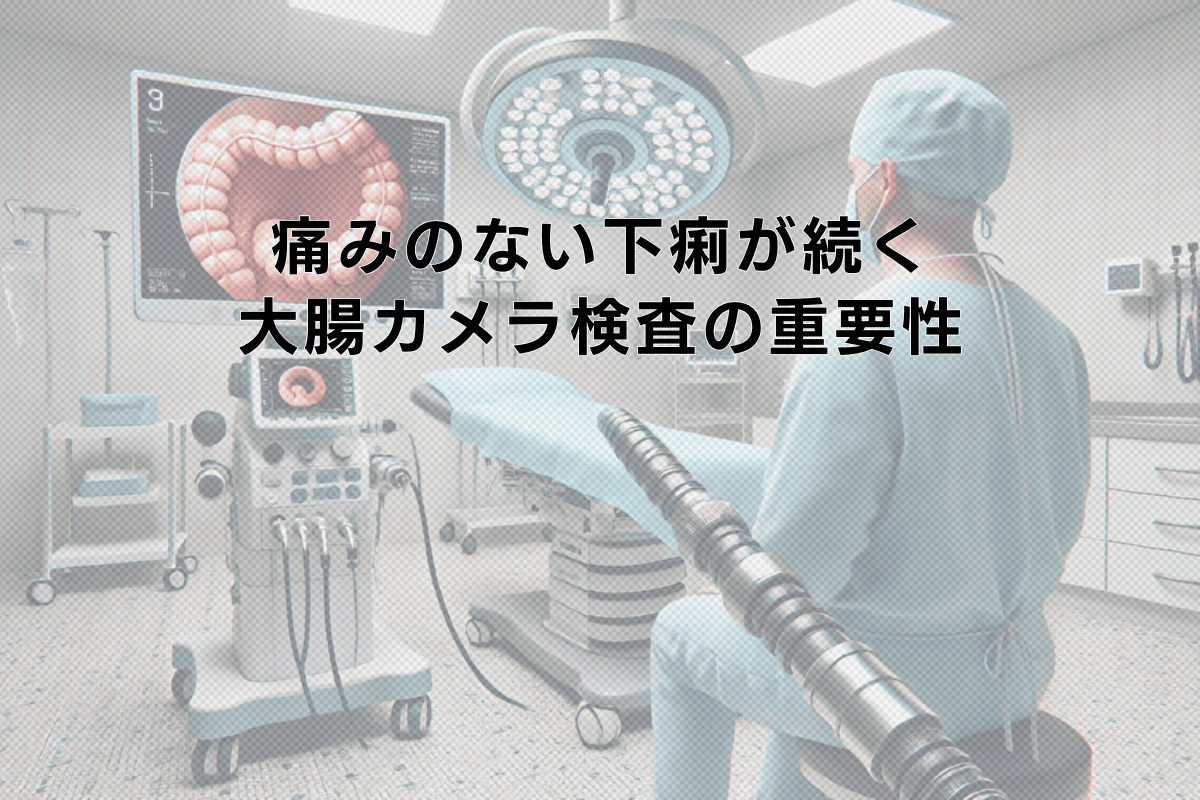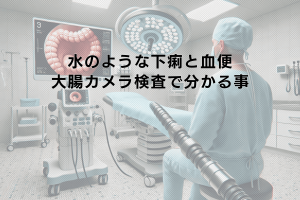お腹は痛くないのに、なぜか下痢だけが続いている。このような経験はありませんか。腹痛がないと、つい大丈夫だろうと自己判断してしまいがちですが、その症状は体が発している重要なサインかもしれません。
痛みを伴わない下痢は、単なる体調不良だけでなく、腸の中で静かに進行する病気の可能性も示唆します。
この記事では、痛みのない下痢がなぜ起こるのか、背後に隠れている可能性のある疾患、そしてなぜ大腸カメラ検査が重要なのかを、詳しく解説していきます。
痛みのない下痢を軽く考えてはいけない理由
多くの人が下痢と聞くと、キリキリとした差し込むような腹痛をセットで連想します。そのため、痛みがなければ緊急性は低く、しばらく様子を見れば治るだろうと考えがちです。
しかし、消化器の専門的な観点から見ると、その考えには大きな注意が必要です。
なぜ痛みがないと放置しやすいのか
人間の体は、痛みを最も分かりやすい危険信号として認識するようにできています。激しい腹痛があれば、誰もが何か異常が起きていると感じ、医療機関を受診しようと考えるでしょう。
一方で、痛みがなければ日常生活への直接的な支障が少なく感じられ、多忙な仕事や日々の家事を優先してしまいがちです。
また、原因を昨日の食事や最近のストレスのせいだと安易に自己判断し、市販薬で一時的に症状を抑えて様子を見てしまうケースも少なくありません。
この受診への心理的なハードルの低さが、知らず知らずのうちに重大な病気の発見を遅らせる大きな原因となることがあるのです。
腹痛は重要な警告サインだがなくても問題はある
腹痛は、腸がけいれんするように強く動いたり、粘膜に強い炎症が起きたりしていることを示す分かりやすいサインです。しかし、病気の種類や進行度、発生している場所によっては、はっきりとした痛みを伴わないことも珍しくありません。
例えば、大腸の粘膜にできた小さなポリープやごく初期のがんは、それ自体が痛みの神経を刺激することはほとんどありません。下痢という症状だけが、腸内の異常を示す唯一の手がかりのこともあるのです。
痛くないから大丈夫、という思い込みが、最も危険な落とし穴になり得ます。
症状がないことがかえって危険なサインの場合も
特に注意したいのは、日本人に増加傾向のある大腸がんのような病気です。大腸がんは初期段階ではほとんど自覚症状がありません。
がんが静かに成長し、腸の内側を塞ぐほど大きくなって初めて、便が細くなったり、便秘や腹痛といったはっきりした症状が現れます。
痛みのない下痢が続いている段階は、病気を根治可能な早期の段階で発見できる、またとない機会である可能性もあるのです。
下痢が体に与える長期的影響
| 影響の種類 | 具体的な内容 | 解説 |
|---|---|---|
| 栄養吸収障害 | 体重減少、貧血、倦怠感、肌荒れ | 腸の内容物が速く通過するため、ビタミンやミネラルなど必要な栄養素を十分に吸収できなくなる。 |
| 脱水と電解質異常 | めまい、脱力感、不整脈、筋肉のけいれん | 水分と共に生命維持に重要なナトリウムやカリウムといった電解質が大量に失われる。特に高齢者は重症化しやすい。 |
| QOLの低下 | 外出への不安、トイレの場所の常時確認、会食の回避 | いつ便意が来るか分からないという切迫した不安が、仕事や学業、社会生活全般に大きな制約をもたらす。 |
痛みのない下痢を引き起こす主な原因
痛みを伴わない下痢が続く背景には、さまざまな原因が考えられ、一時的な食生活の乱れといった身近なものから、専門的な治療が必要な病気まで多岐にわたります。ここでは、代表的な原因をより詳しく紹介します。
生活習慣や食生活の乱れ
最も一般的で、多くの人が経験する原因の一つが、日々の生活習慣です。
特に、脂肪分の多い食事、香辛料などの刺激物、人工甘味料、乳製品、アルコールの過剰摂取、そして冷たい飲み物の一気飲みなどは、腸を過剰に刺激し下痢を起こすことがあります。
また、不規則な生活や慢性的な睡眠不足、精神的なストレスによる自律神経の乱れも、腸の正常な蠕動運動を妨げる大きな一因です。
下痢を誘発しやすい食品や習慣
| カテゴリー | 具体例 |
|---|---|
| 脂肪分の多い食品 | 揚げ物、脂身の多い肉、生クリーム、スナック菓子 |
| 刺激物・アルコール | 香辛料(唐辛子など)、炭酸飲料、コーヒー、お酒全般 |
| 生活習慣 | 早食い、睡眠不足、過労、強い精神的ストレス |
過敏性腸症候群(IBS)下痢型
ストレスや不安を感じるとお腹の調子が悪くなる、通勤や通学の途中、大事な会議の前などに急な便意に襲われる、という方は過敏性腸症候群(IBS)の可能性があります。
IBSは、大腸カメラ検査などで腸に炎症や潰瘍などの目に見える異常がないにもかかわらず、下痢や便秘、腹部膨満感などの症状が慢性的に続く病気です。
脳と腸が互いに影響を及ぼしあう脳腸相関という関係が深く関わっていると考えられており、ストレスが脳を介して腸の運動異常や知覚過敏を起こします。
特に下痢型では、痛みはそれほど強くないものの、突然の我慢できない便意が特徴で、日常生活に大きな影響を及ぼします。
炎症性腸疾患(IBD)
炎症性腸疾患は、腸の粘膜に原因不明の慢性的な炎症や潰瘍ができる病気の総称で、主に潰瘍性大腸炎とクローン病があります。
活動期には激しい腹痛や血便を伴うことが多いですが、症状が軽い場合やごく初期の段階、あるいは寛解に近い状態では、痛みのない下痢だけが続くこともあります。
若年層に発症することが多く、治療を受けずに放置すると症状が悪化し、入院や手術が必要になることもあるため、早期の正確な診断と治療開始が非常に重要です。
潰瘍性大腸炎とクローン病の初期症状
| 項目 | 潰瘍性大腸炎 | クローン病 |
|---|---|---|
| 主な炎症場所 | 大腸の粘膜に限定されることが多い | 口から肛門までの全消化管に起こりうる |
| 特徴的な初期症状 | 粘血便(粘液と血液が混じった便)、下痢、しぶり腹 | 腹痛、下痢、体重減少、発熱、全身倦怠感 |
大腸がんや大腸ポリープ
痛みのない下痢で最も見逃してはならないのが、大腸がんやその前段階である大腸ポリープ(特に腺腫)です。初期にはほとんど症状がありません。
しかし、ポリープやがんの表面から少しずつ水分(滲出液)が分泌されたり、腫瘍の存在が腸の正常な蠕動運動に影響を与えたりすることで、原因不明の下痢を起こすことがあり、便秘と下痢を繰り返す場合もあります。
特に40歳を過ぎてから原因不明の下痢が始まった場合や、家族に大腸がんの人がいる場合は、一度専門医に相談し検査を検討しましょう。
特に注意が必要な下痢のサイン
痛みのない下痢が続くとき、それが単なる体調不良なのか、あるいは精密検査が必要な病気のサインなのかを見極めるために、下痢以外の症状にも注意深く目を向けることが非常に大切です。
下痢以外の症状をチェックする
下痢という一つの症状だけでなく、体全体に現れる他の変化にも注意しましょう。
ダイエットをしていないのに理由なく体重が半年で数キログラム減る、便に明らかに血が混じる、健康診断で貧血を指摘された、といった症状は、消化管のどこかで異常が起きている可能性を強く示唆します。
- 原因不明の体重減少(半年で5%以上)
- 便に血が混じる(黒い便も含む)
- 夜間、下痢で目が覚める
- 発熱が続く、あるいは繰り返す
- 貧血や立ちくらみ、動悸、息切れ
便の状態からわかること
便は消化管からの手紙とも言われ、健康状態を知るための貴重な情報源です。毎日、ご自身の便の色や形、状態を確認する習慣をつけましょう。
便がイカ墨や海苔の佃煮のように黒っぽい場合は、食道や胃、十二指腸など、肛門から遠い上部消化管での出血が疑われ、血液が胃酸によって酸化されるために黒く見えます。
また、イチゴジャムのような粘液と血液が混じった便は、潰瘍性大腸炎に特徴的な所見です。
便の状態で注意したいポイント
| 便の状態 | 考えられる原因 |
|---|---|
| 黒いタール状の便 | 上部消化管(胃や十二指腸)からの出血、胃潰瘍、十二指腸潰瘍など |
| 赤黒い、あるいは新鮮な血が混じる便 | 大腸や肛門付近からの出血、大腸がん、大腸ポリープ、炎症性腸疾患、痔など |
| 粘液が多く混じる便(粘血便) | 大腸の炎症(特に潰瘍性大腸炎)、感染性腸炎など |
続く期間と頻度
暴飲暴食など原因が明らかな一時的な下痢であれば、数日で自然に治まることがほとんどですが、市販の下痢止めを飲んでもすっきりと改善しない下痢が2週間以上続く場合は、慢性的な下痢と考え専門的な評価が重要です。
単なる食べ過ぎやストレスではない、何らかの器質的な(目に見える異常がある)原因が隠れている可能性を考慮する必要があります。
なぜ大腸カメラ検査が必要なのか
痛みのない下痢の原因を正確に突き止めるために、大腸カメラ検査(大腸内視鏡検査)は他のどの検査よりも有効で重要な検査です。
腸の内部を直接観察できる
大腸カメラ検査は、先端に高性能な小型カメラ(CCD)がついた、直径1cm程度の細くしなやかなスコープを肛門から挿入し、直腸からS状結腸、下行結腸、横行結腸、上行結腸、盲腸までの大腸全体をリアルタイムで詳細に観察する検査です。
医師はモニターに映し出される鮮明なハイビジョン画像を見ながら、粘膜の色や血管の走行パターン、炎症や潰瘍、ポリープやがんの有無などを隅々まで確認します。
症状だけでは確定診断はできない
痛みのない下痢という症状は、これまで見てきたように、実にさまざまな原因で起こり得ます。
過敏性腸症候群のように命に別状のない機能的な疾患から、大腸がんのように早期発見が予後を大きく左右する悪性疾患まで、同じような症状を呈することがあります。症状や問診だけでこれらを正確に鑑別することは専門医でも不可能です。
大腸カメラ検査で腸の中を実際にくまなく確認し、がんや炎症などの器質的な異常がないことを確かめて初めて、機能的な問題である過敏性腸症候群と安心して診断できます。
大腸カメラで発見可能な主な疾患
| 疾患名 | 内視鏡で確認できる所見 |
|---|---|
| 大腸がん | 不整な形の隆起や陥凹、易出血性の表面構造、ひだの集中 |
| 大腸ポリープ | 粘膜からきのこ状、あるいは平坦に盛り上がった隆起 |
| 炎症性腸疾患 | 粘膜のびまん性の発赤、血管透見像の消失、びらん、潰瘍 |
組織を採取して病理診断を行える
大腸カメラ検査のもう一つの大きな利点は、検査中にポリープやがん、炎症など、疑わしい部分を見つけた場合、その場で鉗子という小さな器具を使って組織の一部を採取(生検)できることです。
採取した組織は、顕微鏡で詳しく調べる病理診断に提出され、病理診断によって細胞の顔つきを見て良性か悪性か(がん細胞か否か)、炎症の程度などを最終的に確定します。
ポリープが見つかった場合も、多くはその場で切除することができ、検査と治療を同時に行うことも可能です。
大腸カメラ検査の実際
大腸カメラ検査と聞くと、痛い、苦しい、恥ずかしいといったネガティブなイメージを持つ方も多いかもしれません。しかし、近年の医療技術や薬剤の進歩により、検査は以前よりもずっと楽に、快適に受けられるようになっています。
検査前の準備(食事と下剤)
正確で安全な検査のためには、大腸の中を空っぽにしてきれいにする必要があり、検査前日から食事の調整を始めます。消化の良い、腸に残りにくい検査食(レトルトなどで市販もされています)を利用するのも良い方法です。
おかゆ、素うどん、豆腐、白身魚、具のないスープなどを中心に摂り、きのこや海藻、種のある果物、繊維の多い野菜などは避けます。
そして検査当日の朝、自宅または医療機関で、腸管洗浄剤(下剤)を約1〜2リットル、数時間かけてゆっくりと飲みます。下剤によって、最終的に便がレモン色の水様便になり、腸内がきれいになったら準備完了です。
検査前日の食事の注意点
| 食べて良いもの | 避けるべきもの |
|---|---|
| 素うどん、おかゆ、豆腐、白身魚 | 繊維の多い野菜、きのこ類、海藻類、種のある果物、玄米 |
| 具のないスープ、食パン(耳なし)、プリン | 牛乳、ヨーグルトなどの乳製品、色の濃いジュース |
検査当日の流れ
医療機関に到着したら、専用の検査着に着替え検査室に入り、ベッドに左側を下にして横になると、鎮静剤や鎮痛剤を点滴から投与します。
薬を使うことで、うとうとと眠っているような、あるいはぼんやりとリラックスした状態で検査を受けられます。検査自体にかかる時間は、観察のみであればおおよそ15〜30分程度です。
ポリープの切除など、何らかの処置を行った場合は、もう少し時間がかかることもあります。
検査中の痛みや苦痛は?
多くの方が心配する検査中の痛みや苦痛ですが、鎮静剤の使用によりほとんど感じることなく検査を終える方が大半です。
また、スコープを挿入する医師の技術も向上しており、経験豊富な専門医は、お腹が張らないように二酸化炭素を送気したり、体の向きを適宜変えたりしながら、苦痛を最小限に抑えるさまざまな工夫をしています。
不安な点や疑問点は、検査前に医師や看護師に遠慮なく伝えてください。
検査で病気が見つかった後のこと
大腸カメラ検査は病気を発見して終わりではなく、正確な診断に基づいた治療へとつなげるための重要なスタートラインです。ここでは、検査で代表的な病気が見つかった場合の、その後の対応について説明します。
過敏性腸症候群(IBS)と診断された場合
検査の結果腸に特に異常が見つからなかった場合は、症状と合わせて過敏性腸症候群の可能性が高まります。
この場合、まずは生活習慣の改善から始め、食事内容の見直し(低FODMAP食など)、十分な睡眠、適度な運動、ストレス管理などが治療の基本です。
それでも症状が改善しない場合は、腸の動きを整える薬、便の硬さを調整する薬、あるいは腸の知覚過敏を抑える薬などを用いた薬物療法を行います。
炎症性腸疾患(IBD)と診断された場合
潰瘍性大腸炎やクローン病と診断された場合は、消化器内科の中でも特にIBDを専門とする医師による継続的な治療が必要になります。
現在のところ完治させることは難しいですが、炎症を抑えて症状のない状態(寛解)を長く維持することが治療の目標です。
主に、5-ASA製剤、ステロイド、免疫調節薬、生物学的製剤など、さまざまな薬を病状の重症度や炎症の範囲に合わせて使い分けます。
IBDの主な治療法
| 治療法の種類 | 概要 |
|---|---|
| 薬物療法 | 腸の炎症を抑える薬が中心。症状に合わせて複数の薬を組み合わせる。近年、新薬が次々と登場している。 |
| 栄養療法 | 特にクローン病で重要。腸を休ませるために成分栄養剤(エレンタールなど)を使用することがある。 |
| 外科手術 | 薬物療法で効果がない場合や、腸閉塞、穿孔などの合併症が起きた場合に検討される。 |
大腸ポリープが見つかった場合
大腸ポリープの多くは、放置すると将来がん化する可能性のある腺腫であるため、検査中に発見されたポリープは、その場で切除するのが一般的です。
これを内視鏡的ポリープ切除術(ポリペクトミー)と呼び、切除したポリープは病理診断で詳しく調べ、がん細胞が含まれていないか、取り切れているかなどを確認します。
ポリープを切除することで、将来の大腸がんを効果的に予防することにつながります。
痛みのない下痢に関するよくある質問
最後に、痛みのない下痢に関して患者さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
- 市販の下痢止めを飲み続けても大丈夫ですか
-
市販の下痢止めは、会議中や移動中など、一時的に症状を抑えるのには有効ですが、根本的な原因を解決するものではありません。
特に、細菌やウイルスによる感染性の下痢の場合、下痢止めで腸の動きを無理に止めると、かえって病原体や毒素を体内に留まらせてしまい、回復を遅らせることがあります。
原因がはっきりしない下痢が続く場合は、自己判断で薬を飲み続けるのではなく、一度医療機関を受診し診断を受けましょう。
- 何週間くらい下痢が続いたら受診すべきですか
-
明確な絶対的基準はありませんが、一般的に消化器内科では、4週間以上続く下痢を「慢性下痢」と定義し、精密検査の対象として考えます。
しかし、実際には2週間以上症状が改善しない場合は、単なる一過性の不調ではない可能性を考え、受診を検討するのが良いでしょう。
特に、体重減少や血便などの警告サインを伴う場合や、40歳以上で初めて経験するような長引く下痢の場合は、期間にかかわらず早めに相談することをお勧めします。
- 大腸カメラ以外に調べる方法はありますか
-
大腸の状態を調べる検査には、他にも便潜血検査や注腸X線検査、CTコロノグラフィ(バーチャル大腸内視鏡)などがあります。
便潜血検査は、便に微量の血液が混じっていないかを調べる簡便な検査で、大腸がん検診で広く用いられていますが、早期がんやポリープでは陰性となることも多く、感度は高くありません。
また、他の検査は、大腸の粘膜を直接観察したり、組織を採取したりすることができないため、情報の精度や範囲に限界があります。確定診断のためには、最終的に大腸カメラ検査が必要となることがほとんどです。
参考文献
Kinoshita Y, Ariyoshi R, Fujigaki S, Tanaka K, Morikawa T, Sanuki T. Endoscopic diagnosis of chronic diarrhea. DEN open. 2022 Apr;2(1):e53.
Komori S, Akiyama J, Tatsuno N, Yamada E, Izumi A, Hamada M, Seto K, Nishiie Y, Suzuki K, Hisada Y, Otake Y. Prevalence and Risk Factors of Constipation Symptoms among Patients Undergoing Colonoscopy: A Single-Center Cross-Sectional Study. Digestion. 2024 Aug 9;105(4):299-309.
Shah RJ, Fenoglio-Preiser C, Bleau BL, Giannella RA. Usefulness of colonoscopy with biopsy in the evaluation of patients with chronic diarrhea. The American journal of gastroenterology. 2001 Apr 1;96(4):1091-5.
Read NW, Krejs GJ, Read MG, Santa Ana CA, Morawski SG, Fordtran JS. Chronic diarrhea of unknown origin. Gastroenterology. 1980 Feb 1;78(2):264-71.
Frexinos J, Fioramonti J, Bueno L. Colonic myoelectrical activity in IBS painless diarrhoea. Gut. 1987 Dec 1;28(12):1613-8.
Greenberger NJ. Diagnostic approach to the patient with a chronic diarrheal disorder. Disease-a-Month. 1990 Mar 1;36(3):135-79.
Browning SM. Constipation, diarrhea, and irritable bowel syndrome. Primary Care: Clinics in Office Practice. 1999 Mar 1;26(1):113-39.
Pham HT, Sellin JH. Utility of specific diagnosis tests in evaluating chronic diarrhea in clinical practice. Gastroenterology. 2003 Apr 1;124(4):A146-7.
Clarke G, Robb A, Sugarman I, McCallion WA. Investigating painless rectal bleeding—is there scope for improvement?. Journal of pediatric surgery. 2005 Dec 1;40(12):1920-2.
Engin O, Kilinc G, Sunamak O. Colonoscopy. Colon Polyps and Colorectal Cancer. 2021:45-74.