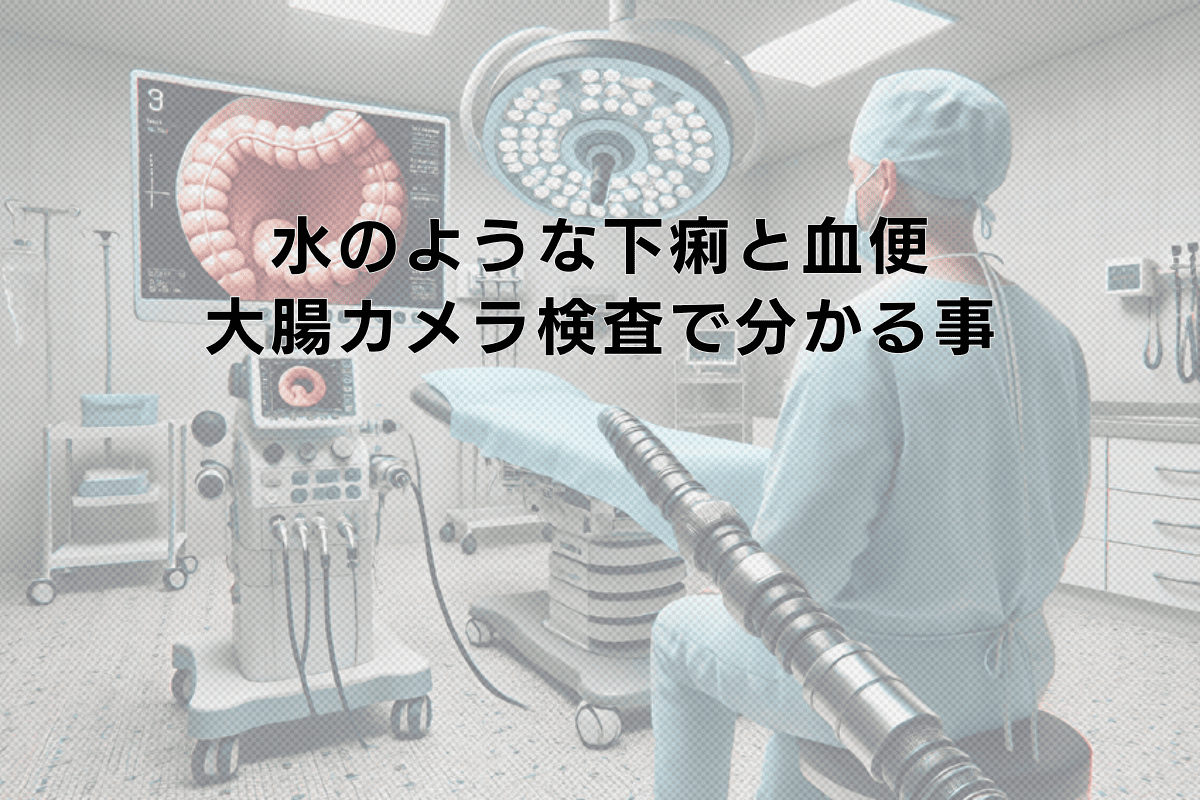突然の水のような下痢そして便に血が混じる症状は、多くの方が不安に感じる体のサインです。
特にお腹が痛くない場合、かえって原因が分からず戸惑うこともあるでしょう。
この記事では、水のような下痢と血便という症状に焦点を当て、背景にどのような原因が考えられるのか、そしてなぜ大腸カメラ検査が重要なのかを詳しく解説します。
水のような下痢と血便が同時に起こる意味
水のような下痢と血便はそれぞれが消化管の異常を示すサインですが、同時に現れた場合、大腸の粘膜に何らかの炎症や損傷が起きている可能性を考えます。単なる食べ過ぎや一時的な体調不良とは異なる、注意が必要な状態かもしれません。
なぜ水のような下痢になるのか
水様性の下痢は、腸管からの水分吸収がうまくいかなくなるか、あるいは腸管内に多量の水分が分泌されることで発生します。
通常、食べた物は胃や小腸で消化され大腸で水分が吸収されて固形の便になりますが、大腸の粘膜に広範囲の炎症が起きると、細胞が傷つき水分吸収機能が著しく低下します。
また、病原菌やウイルスに感染した場合作り出す毒素は腸の細胞を刺激し、腸管内に大量の水分と電解質を分泌させ(分泌性下痢)、便が固まることなく、水のような状態で排出されてしまうのです。
血便が示す大腸からのサイン
血便は、消化管のどこかから出血していることを示す明確な証拠です。便に混じる血液の色によって、出血部位をある程度推測できます。
胃や十二指腸など肛門から遠い上部消化管で出血した場合は、血液が胃酸の影響を受けて黒っぽいタール状の便に、鮮やかな赤色や赤黒い色の血が便に付着したり混じったりしている場合は、大腸や直腸、肛門といった下部消化管からの出血です。
水のような下痢と共に血便が見られる場合、大腸の粘膜が広範囲にわたってただれたり、深い潰瘍ができていたりする状態が考えられ、出血量が多い場合は便全体が赤黒くなることもあります。
血便の色の違いと推測される出血部位
| 便の色 | 状態 | 推測される出血部位 |
|---|---|---|
| 鮮血便(鮮やかな赤色) | 便の表面に血液が付着、排便後に滴下 | 肛門、直腸など |
| 暗赤色便(赤黒い色) | 便と血液が混在、粘液を伴うことも | 大腸の奥(結腸など) |
| 黒色便(タール便) | 黒く粘り気のある便、特有の臭い | 胃、十二指腸など |
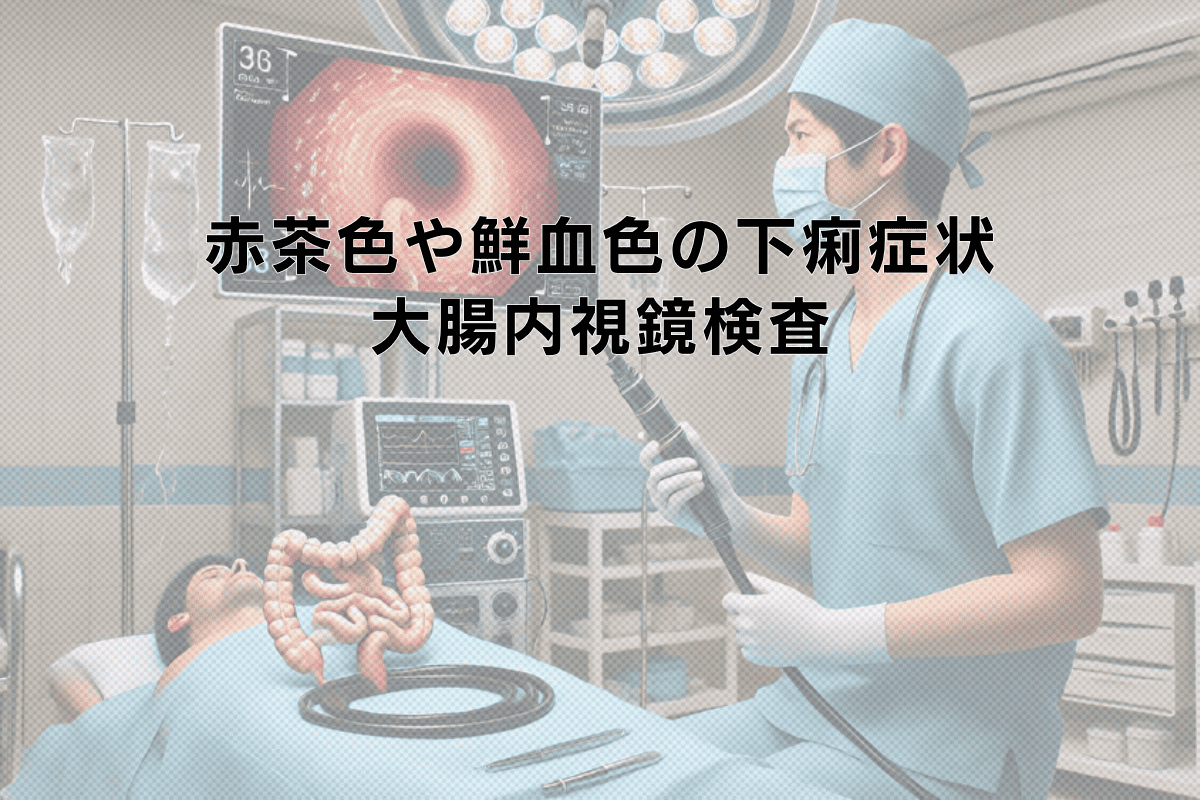
腹痛がない場合でも安心できない理由
水のような下痢や血便があっても腹痛を伴わかったり軽度であるケースもありますが、腹痛の有無は病気の重症度とは必ずしも一致しません。潰瘍性大腸炎の初期や直腸に限定した炎症の場合、強い痛みを伴わないことがあります。
また、大腸がんや大腸ポリープからの出血は、初期段階ではほとんど痛みを伴いません。
痛みがないからといって大腸の粘膜の炎症や出血が軽いとは限らず、自覚症状が少ないことで発見が遅れ病気が進行してしまう可能性もあり、十分な注意が必要です。
水様性下痢と血便から考えられる病気
水様性下痢と血便を起こす原因は一つではありません。感染症から炎症性の病気、さらには腫瘍に至るまで、さまざまな可能性を考える必要があります。
感染性腸炎
細菌やウイルス、原虫などが腸に感染して炎症を起こす病気です。
サルモネラ菌(鶏卵など)、カンピロバクター(鶏肉など)、腸管出血性大腸菌(O-157など、加熱不十分な牛肉など)といった細菌が原因の場合、激しい下痢や血便、腹痛、発熱などを伴うことが多くあります。
ウイルス性ではノロウイルスやロタウイルスが代表的ですが、血便を伴うことは比較的まれです。感染性腸炎は、汚染された食品や水の摂取、あるいは感染者との接触によって起こるため、原因究明には食事内容や行動歴の聴取が重要になります。
感染性腸炎の主な原因
| 種類 | 代表的な病原体 | 主な症状 |
|---|---|---|
| 細菌性 | カンピロバクター、サルモネラ菌、腸管出血性大腸菌 | 激しい下痢、腹痛、血便、発熱 |
| ウイルス性 | ノロウイルス、ロタウイルス | 嘔吐、水様性下痢、腹痛 |
潰瘍性大腸炎
大腸の粘膜に原因不明の炎症が起こり、びらん(ただれ)や潰瘍ができる病気です。国の指定難病の一つであり、遺伝的な要因や環境因子、免疫系の異常などが複雑に関与して発症すると考えられています。
若年層での発症が多い傾向にありますが、高齢で発症する方もいて、主な症状は、粘液と血液が混じった便(粘血便)や下痢です。悪化すると水のような下痢や血便が頻繁に起こり、発熱や体重減少、貧血などを伴うこともあります。
症状が良くなったり(寛解)悪くなったり(再燃)を繰り返すのが特徴で、長期にわたる治療と管理が必要です。まれに関節や皮膚、眼などに合併症が起こることもあります。
クローン病
潰瘍性大腸炎と同じく、原因不明の炎症が消化管に起こる病気で、こちらも指定難病です。
口から肛門までの消化管のあらゆる場所に非連続的(病変と正常な部分が混在する)な炎症が起こる可能性がありますが、特に小腸の終わりから大腸にかけて好発し、主な症状は腹痛と下痢で、血便を伴うこともあります。
潰瘍性大腸炎と異なり炎症が消化管の深い層まで及ぶことが特徴で、腸に穴が開いたり(穿孔)、腸管が狭くなったり(狭窄)、瘻孔(ろうこう)というトンネルができてしまうこともあります。
また、栄養の吸収が障害されやすく、体重減少や成長障害が見られることもあります。
炎症性腸疾患の比較
| 特徴 | 潰瘍性大腸炎 | クローン病 |
|---|---|---|
| 主な炎症場所 | 大腸の粘膜(連続的) | 消化管全体(非連続的) |
| 炎症の深さ | 浅い(粘膜層) | 深い(全層性) |
| 主な症状 | 粘血便、下痢 | 腹痛、下痢、体重減少 |
虚血性大腸炎
大腸への血流が一時的に悪化することで、大腸の粘膜に炎症や壊死が起こる病気です。動脈硬化のある高齢者や、糖尿病、高血圧、脂質異常症などの生活習慣病を持つ方、また、便秘で強くいきむ習慣のある方などに起こりやすいとされます。
突然の激しい腹痛(特に左下腹部)で発症し、その後、下痢、そして半日~1日後に血便(鮮血便)が見られるのが典型的な経過です。
多くの場合一時的な血流障害が原因であるため、絶食や点滴による腸の安静で数日以内に改善しますが、血流障害が高度で腸管が壊死に陥った場合は、緊急手術が必要になることもあります。
大腸がんや大腸ポリープ
大腸がんや大きな大腸ポリープの表面がもろくなると、硬い便が通過する際の物理的な刺激で出血し血便の原因となることがあります。
出血が少量の場合は便潜血検査でなければ分からないこともありますが、持続的に出血することで貧血が進行する場合もあります。
下痢を伴うことは必須ではありませんが、腫瘍が腸管を狭くすることで便通に異常をきたし、下痢と便秘を繰り返すこともあります。初期の段階では自覚症状がほとんどないため、血便は病気を発見する重要なきっかけです。
医療機関を受診する前に確認すべきこと
正確な診断のためには、医師に自身の状態を詳しく伝えることが大切です。受診前にいくつかの点を確認し、メモなどにまとめておくと、診察がスムーズに進み診断の精度も高まります。
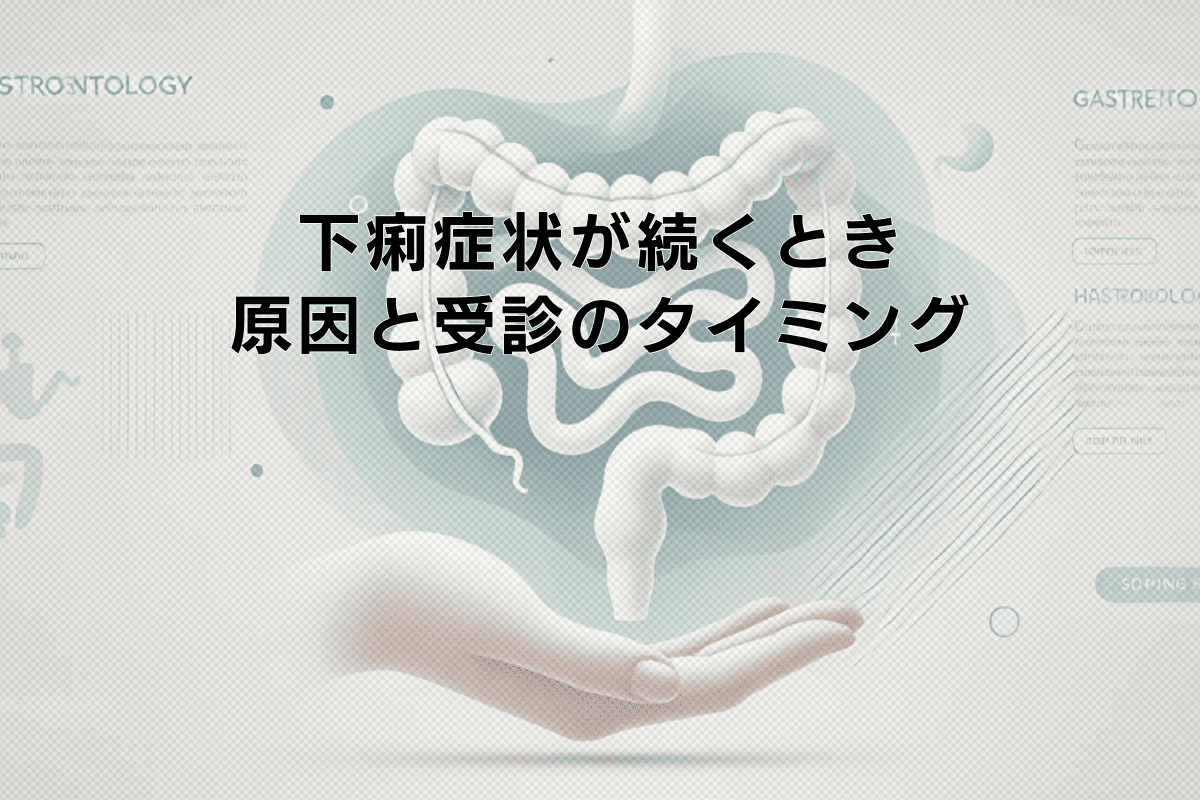
便の状態を詳細に観察する
ただ下痢や血便があったと伝えるだけでなく、状態を具体的に説明できると診断の大きな助けになります。
- いつから始まったか
- 1日に何回下痢をするか
- 便の色(赤、黒、赤黒いなど)
- 血液の混じり方(便の表面に付着、全体に混ざっているなど)
- 粘液の有無
下痢や血便以外の症状を把握する
腹痛の有無や程度はもちろん、それ以外の全身の症状も大事な情報です。原因となっている病気を絞り込む上で役立ち、一見関係ないように思える症状も診断の手がかりになることがあります。
確認したい付随症状
| 症状の種類 | 確認事項 | 考えられること |
|---|---|---|
| 熱 | 発熱の有無、体温の推移 | 感染性腸炎、炎症の悪化 |
| 吐き気・嘔吐 | 嘔吐の有無、回数、内容物 | ウイルス性胃腸炎、腸閉塞 |
| 体重 | 意図しない体重減少の有無 | 炎症性腸疾患、悪性腫瘍など |
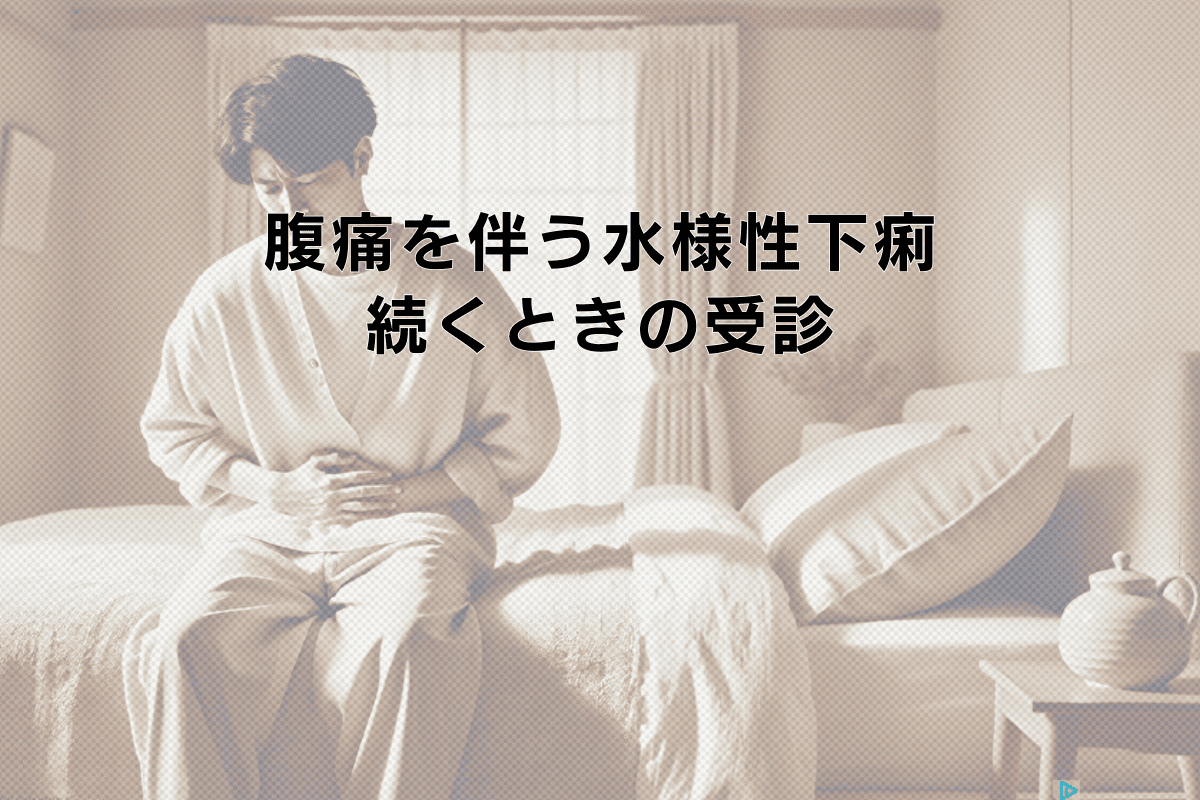
最近の生活状況を振り返る
症状が始まる前の食事内容や行動も原因を探る手がかりになり、特に、普段食べないものを口にした場合や、海外渡航歴などは感染症を疑う上で重要です。服用中の薬(抗生物質、痛み止めなど)が原因で腸炎が起こることもあります。
- 生肉や加熱不十分な肉、魚介類を食べなかったか
- 最近、海外旅行に行っていないか
- 周りに同じような症状の人はいないか
- 最近、新しい薬を飲み始めていないか
大腸カメラ検査(内視鏡検査)の実際
水のような下痢と血便の原因を特定するために、大腸カメラ検査は極めて有用な検査です。大腸の内部を直接観察することで、粘膜のわずかな色の変化やただれ、潰瘍、ポリープ、がんなどを高い精度で発見できます。
大腸カメラ検査で分かること
大腸カメラ検査では、先端に高性能カメラが付いた細くしなやかなスコープを肛門から挿入し、直腸から盲腸までの大腸全体を観察します。医師はモニターに映し出される鮮明な映像を見ながら、粘膜の状態を隅々まで確認します。
炎症の範囲や程度、ポリープやがんの有無、出血の原因となっている箇所などを特定できます。また、特殊な光(NBIなど)を用いて血管や粘膜の模様を強調表示し、病変の良悪性をより詳しく判断することも可能です。
疑わしい部分が見つかった場合はその場で組織の一部を採取(生検)し、顕微鏡で調べる病理検査で確定診断を行います。
検査の準備段階
正確な検査のためには、大腸の中を空にしてきれいにする必要があります。腸内に便が残っていると小さな病変が見逃される原因になるため、準備がとても大切です。
検査前日は消化の良い食事(検査食など)をとり、夜に錠剤や液体タイプの下剤を服用し、検査当日は、朝から約1.5リットルから2リットルの液体状の腸管洗浄剤を数時間かけて飲み、腸内を完全に洗浄します。
検査前の食事の注意点
| 種類 | 推奨される食事(消化の良いもの) | 避けるべき食事(消化に悪いもの) |
|---|---|---|
| 主食 | おかゆ、うどん、食パン(耳なし) | 玄米、雑穀米、ラーメン、パスタ |
| おかず | 豆腐、鶏ささみ、白身魚、はんぺん、卵 | きのこ類、海藻類、こんにゃく、豆類、脂身の多い肉 |
| その他 | 具のないスープ、ゼリー、透明な飴 | 牛乳、ヨーグルト、色の濃いジュース、アルコール、種のある果物 |

検査当日の流れと所要時間
腸管洗浄剤を飲み終え、最終的に便が透明な黄色い液体になったら検査の準備は完了です。検査室で専用の検査着に着替え、ベッドに横になります。多くの施設では鎮静剤や鎮痛剤を使用してリラックスした状態で検査を開始します。
検査自体にかかる時間は通常15分から30分程度ですが、ポリープを切除するなどの処置を行う場合は、もう少し時間がかかります。
検査終了後は、鎮静剤の効果が覚めるまで1時間ほどリカバリールームで安静にしてから、医師による結果説明を受けます。
検査後の過ごし方
検査当日は鎮静剤の影響が残る可能性があるため、終日、車やバイク、自転車の運転はできません。食事は医師の指示に従いますが、観察のみで終了した場合は、消化の良いものから普段の食事に戻していきます。
ポリープを切除した場合は出血や穿孔のリスクを減らすため、数日間はアルコールや刺激物の摂取、激しい運動、長時間の移動、旅行などを控えることが大切です。
大腸カメラ以外の診断方法
症状や患者さんの状態、あるいは大腸カメラ検査が困難な場合には、他の検査法を検討することもあります。
便潜血検査
便の中に目に見えない微量の血液が混じっていないかを調べる簡易的な検査で、主に大腸がん検診で用いられます。
水のような下痢と血便がある場合はすでに出血が明らかなため、この検査を省略して直接的な観察ができる大腸カメラ検査を行うことが一般的です。便潜血検査はあくまでスクリーニングであり、診断を確定するものではありません。
血液検査
体内の炎症の程度(CRP値や白血球数)や、貧血の有無(ヘモグロビン値)、栄養状態(アルブミン値)などを調べるために行い、病気の活動性や重症度を客観的に判断する指標となります。
また、炎症性腸疾患の鑑別のために、特定の抗体を調べることもあります。
血液検査で確認する主な項目
| 検査項目 | 何が分かるか | 異常値が示す可能性 |
|---|---|---|
| 白血球数、CRP | 体内の炎症の有無や程度 | 感染症、炎症性腸疾患の活動性 |
| 赤血球数、ヘモグロビン | 貧血の有無や程度 | 消化管からの慢性的な出血 |
| アルブミン | 栄養状態、炎症の慢性度 | 栄養吸収障害、重度の炎症 |
CTコロノグラフィ(仮想大腸内視鏡検査)
CTスキャンを用いて大腸の3D画像を構築し、あたかも内視鏡で観察しているかのように大腸の内部を調べる検査です。
炭酸ガスで大腸を膨らませて撮影し、大腸カメラと比べて体の負担が少なく検査時間も短いですが、平坦な病変の発見が難しいことや、粘膜の色調変化が分からない、組織の採取(生検)ができないという欠点があります。
また、放射線被ばくも考慮する必要があります。異常が見つかった場合は、治療方針決定のために改めて大腸カメラ検査が必要です。

症状緩和と再発予防のための生活習慣
診断がつき治療が始まった後も、日々の生活習慣を見直すことは症状の管理や再発予防において非常に重要です。
消化の良い食事を基本とする
腸に炎症があるときは、消化管に負担をかけない食事が基本です。症状が強い時期は、低脂肪・低残渣(食物繊維が少ない)の食事を心がけます。
脂質の多い揚げ物や肉類、食物繊維の多いごぼうなどの根菜やきのこ類、刺激の強い香辛料などは、腸を刺激して下痢を悪化させる可能性があるため避けた方がよいでしょう。
食事で心がけたいこと
| カテゴリ | 積極的にとりたいもの | 控えたほうがよいもの |
|---|---|---|
| 炭水化物 | おかゆ、よく煮込んだうどん、パン粥 | 食物繊維の多いパン、パスタ、玄米 |
| タンパク質 | 鶏ささみ、豆腐、卵、白身魚(たら、かれい) | 脂身の多い肉、加工肉(ハム、ソーセージ)、青魚 |
| その他 | リンゴのすりおろし、バナナ、野菜スープ | 香辛料、カフェイン、炭酸飲料、アルコール |

ストレスとの上手な付き合い方
ストレスは腸の働きをコントロールしている自律神経のバランスを乱し、症状を悪化させる一因となることがあり、炎症性腸疾患などはストレスが再燃のきっかけになることも知られています。
完全にストレスをなくすことは難しいですが、十分な睡眠時間を確保する、趣味や好きなことに没頭する時間を作る、ヨガや瞑想、深呼吸などで意識的にリラックスする時間を持つなど、自分に合った方法でストレスを管理することが大切です。
こまめな水分補給の重要性
水のような下痢が続くと、体から大量の水分と電解質(ナトリウムやカリウムなど)が失われ、脱水症状を起こす危険があり、脱水を防ぐためにはこまめな水分補給が欠かせません。
ただの水を飲むだけでなく、電解質と糖分がバランス良く含まれた経口補水液を利用するのが最も効果的です。
糖分は腸管での水分とナトリウムの吸収を助ける働きがありますが、スポーツドリンクは糖分が多すぎることがあるため、下痢がひどい場合は経口補水液が推奨されます。
よくある質問(FAQ)
水のような下痢と血便に関して、多くの方が抱く疑問にお答えします。
- 症状が一時的に治まっても放置して大丈夫ですか
-
一度症状が治まっても、原因となる病気が治癒したとは限りません。炎症性腸疾患のように良くなったり悪くなったりを繰り返す病気の場合、一時的な症状の改善はよくあることです。
また、大腸がんからの出血も常に出血しているわけではなく、出たり止まったりを繰り返します。原因が特定されないまま放置すると、気づかないうちに病状が進行してしまう可能性があります。
症状が一度でもあった場合は、軽視せずに医療機関に相談することをお勧めします。
- 市販の下痢止め薬を使用しても良いですか
-
自己判断で市販の下痢止め薬を使用するのは、原則として避けるべきです。
特に、細菌性腸炎(感染性腸炎)が疑われる場合、下痢止め薬で腸の動きを無理に止めてしまうと、病原菌や毒素が体外へ排出されにくくなり、かえって症状を悪化させたり回復を遅らせる危険性があります。
血便を伴うような重篤な腸炎のサインがある場合は、まず原因を特定することが最優先です。
- 大腸カメラ検査は痛いでしょうか
-
スコープを挿入する際や、腸の曲がり角を通過する際に、お腹が張るような感覚や痛みを感じることがあります。
しかし、現在では多くの医療機関で鎮静剤や鎮痛剤を使用し、うとうとと眠っているようなリラックスした状態で検査を受けられるように工夫しています。
苦痛を最小限に抑えることで医師も落ち着いて詳細な観察が可能となり、より質の高い検査につながります。
- 大腸カメラ検査で組織を採った場合、結果はいつ分かりますか
-
検査中に組織の一部を採取した場合(生検)組織は病理検査に提出され、病理専門医が顕微鏡で詳細に観察し、診断を確定します。通常、結果が出るまでに1週間から2週間程度が必要です。
次回の外来受診時に、担当医から直接詳しい説明を受けます。
次に読むことをお勧めする記事
【大腸内視鏡検査の前日に必要な準備と食事の注意点】
大腸カメラの重要性を理解したら、前日の準備と食事を具体的に知っておくと安心です。実際に必要な持ち物や流れまで、検査当日の不安を減らす実用情報がまとまっています。
【大腸がん検査方法の選び方 – 血液検査から内視鏡検査まで】
水様性下痢や血便の背景には複数の検査選択肢があります。便潜血・内視鏡・CTコロノグラフィ等の違いを把握し、状況に合う検査計画を立てる助けになります。
参考文献
Kinoshita Y, Ariyoshi R, Fujigaki S, Tanaka K, Morikawa T, Sanuki T. Endoscopic diagnosis of chronic diarrhea. DEN open. 2022 Apr;2(1):e53.
Juckett G, Trivedi R. Evaluation of chronic diarrhea. American family physician. 2011 Nov 15;84(10):1119-26.
Corinaldesi R, Stanghellini V, Barbara G, Tomassetti P, De Giorgio R. Clinical approach to diarrhea. Internal and emergency medicine. 2012 Oct;7:255-62.
Holtz LR, Neill MA, Tarr PI. Acute bloody diarrhea: a medical emergency for patients of all ages. Gastroenterology. 2009 May 1;136(6):1887-98.
Burgers K, Lindberg B, Bevis ZJ. Chronic diarrhea in adults: evaluation and differential diagnosis. American family physician. 2020 Apr 15;101(8):472-80.
Sylwestrowicz T, Kelly JK, Hwang WS, Shaffer EA. Collagenous colitis and microscopic colitis: the watery diarrhea-colitis syndrome. American Journal of Gastroenterology (Springer Nature). 1989 Jul 1;84(7).
Headstrom PD, Surawicz CM. Chronic diarrhea. Clinical Gastroenterology and hepatology. 2005 Aug 1;3(8):734-7.
Lee JH, Rhee PL, Kim JJ, Koh KC, Paik SW, Han JH, Ree HJ, Rhee JC. The role of mucosal biopsy in the diagnosis of chronic diarrhea: value of multiple biopsies when colonoscopic finding is normal or nonspecific. The Korean journal of internal medicine. 1997 Jun;12(2):182.
Marshall JB, Singh R, Diaz-Arias AA. Chronic, unexplained diarrhea: are biopsies necessary if colonoscopy is normal?. American Journal of Gastroenterology (Springer Nature). 1995 Mar 1;90(3).
Fernández-Bañares F, Esteve M, Salas A, Alsina M, Farré C, González C, Buxeda M, Forné M, Rosinach M, Espinós JC, Viver JM. Systematic evaluation of the causes of chronic watery diarrhea with functional characteristics. Official journal of the American College of Gastroenterology| ACG. 2007 Nov 1;102(11):2520-8.