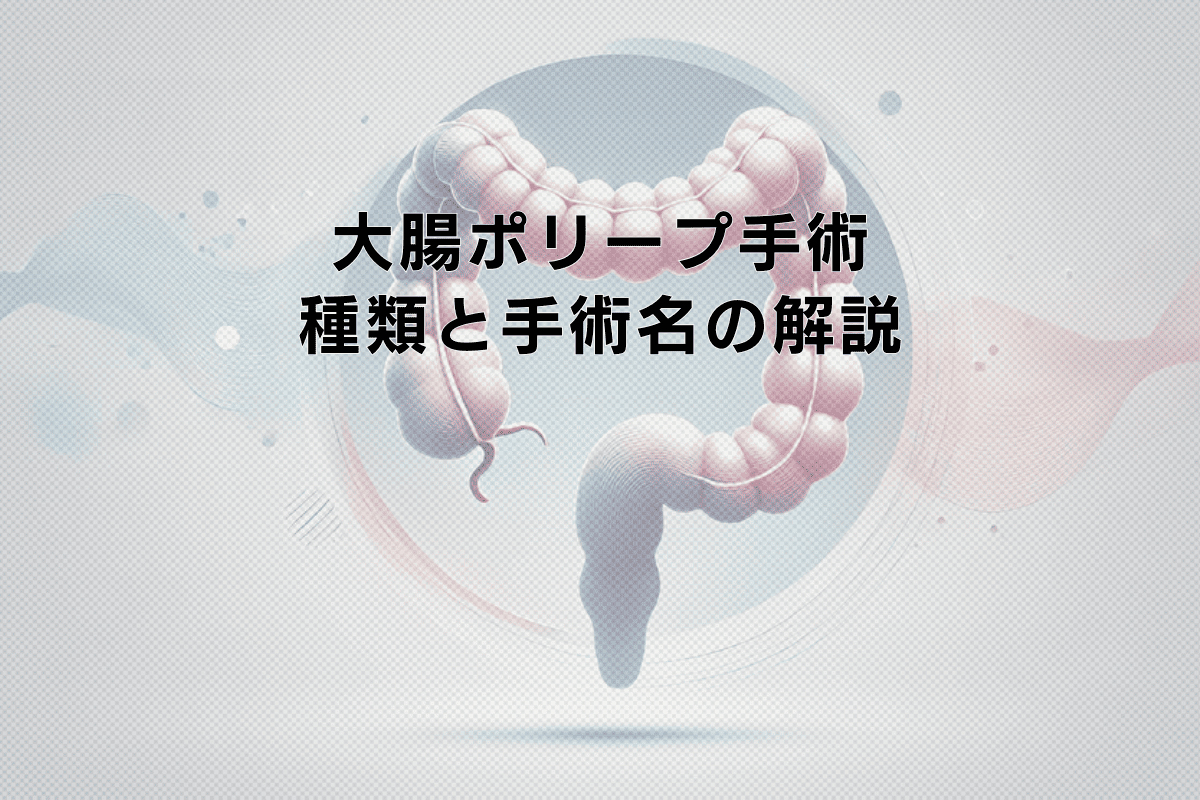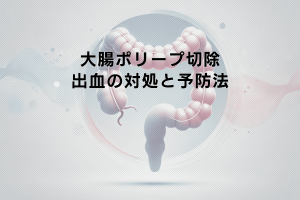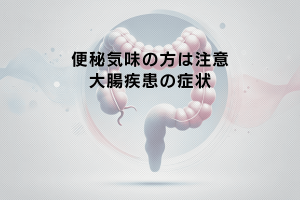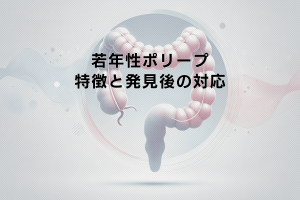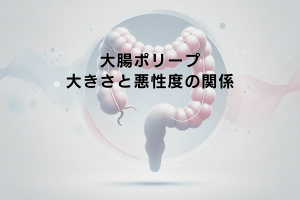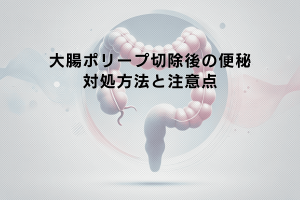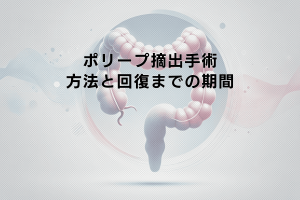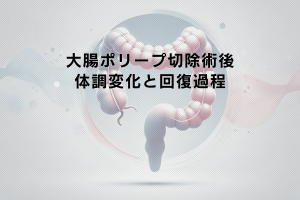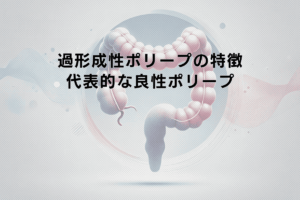大腸ポリープと診断され、手術について情報を集めている方や、ご家族が手術を控えている方もいらっしゃるかもしれません。大腸ポリープの手術にはいくつかの種類があり、それぞれに特徴があります。
この記事では、大腸ポリープ手術の種類と手術について、できる限りわかりやすく解説します。手術に関する疑問や不安を少しでも解消し、適切な情報に基づいて医療機関にご相談いただくための一助となれば幸いです。
大腸ポリープとは何か?
大腸ポリープという言葉を聞いたことがある方は多いでしょう。しかし、具体的にどのようなものなのか、詳しく知る機会は少ないかもしれません。
ポリープの定義と発生部位
大腸ポリープとは、大腸の最も内側にある粘膜の表面から、内腔(腸管の内部空間)に向かって盛り上がった、いわゆるできものの総称です。
形はキノコのように茎を持つもの(有茎性:ゆうけいせい)や、平べったく盛り上がるもの(無茎性:むけいせい、または広基性:こうきせい)、表面が陥凹(へこんでいる)するものなど、さまざまです。
ポリープの形状による主な分類
| 形状の分類 | 特徴 | 一般的な呼び方 |
|---|---|---|
| 有茎性ポリープ | 粘膜表面から茎(くき)を持ってキノコのように突出している。 | くきのあるポリープ |
| 亜有茎性ポリープ | 有茎性と無茎性の中間的な形状で、短く太い茎を持つ。 | くきの短いポリープ |
| 無茎性ポリープ(広基性ポリープ) | 茎を持たず、粘膜からなだらかに盛り上がっている。 | 平たいポリープ |
ポリープの種類と特徴
大腸ポリープは、その組織の性質によって大きく腫瘍性ポリープと非腫瘍性ポリープに分けられます。これらは治療方針を決定する上で非常に重要な分類です。
腫瘍性ポリープ
腫瘍性ポリープの代表的なものが腺腫(せんしゅ)です。腺腫は、良性ではありますが、放置すると時間をかけて大きくなり、その一部ががん化する可能性があるため、大腸がんの前がん病変と考えられています。
全ての腺腫ががんになるわけではありませんが、がん化のリスクを持つため、発見された場合は切除を検討することが一般的です。
非腫瘍性ポリープ
非腫瘍性ポリープには、過形成性ポリープや炎症性ポリープなどがあります。過形成性ポリープは、基本的にはがん化しないと考えられていますが、一部にはがん化との関連が指摘される特殊なタイプも存在するため、専門医による正確な診断が重要です。
炎症性ポリープは、潰瘍性大腸炎やクローン病といった炎症性腸疾患に伴って発生することがあり、これも通常はがん化しません。
ポリープの種類とがん化の可能性の概要
| ポリープの主な種類 | 組織学的な特徴 | がん化の可能性 |
|---|---|---|
| 腺腫(腫瘍性) | 異型細胞で構成される。大腸がんの前段階。 | あり(大きさや異型度による) |
| 過形成性ポリープ(非腫瘍性) | 細胞の過形成による。基本的には低いが、一部注意が必要なタイプも。 | 低い(一部例外あり) |
| 炎症性ポリープ(非腫瘍性) | 慢性的な炎症の結果として発生。 | 非常に低い |
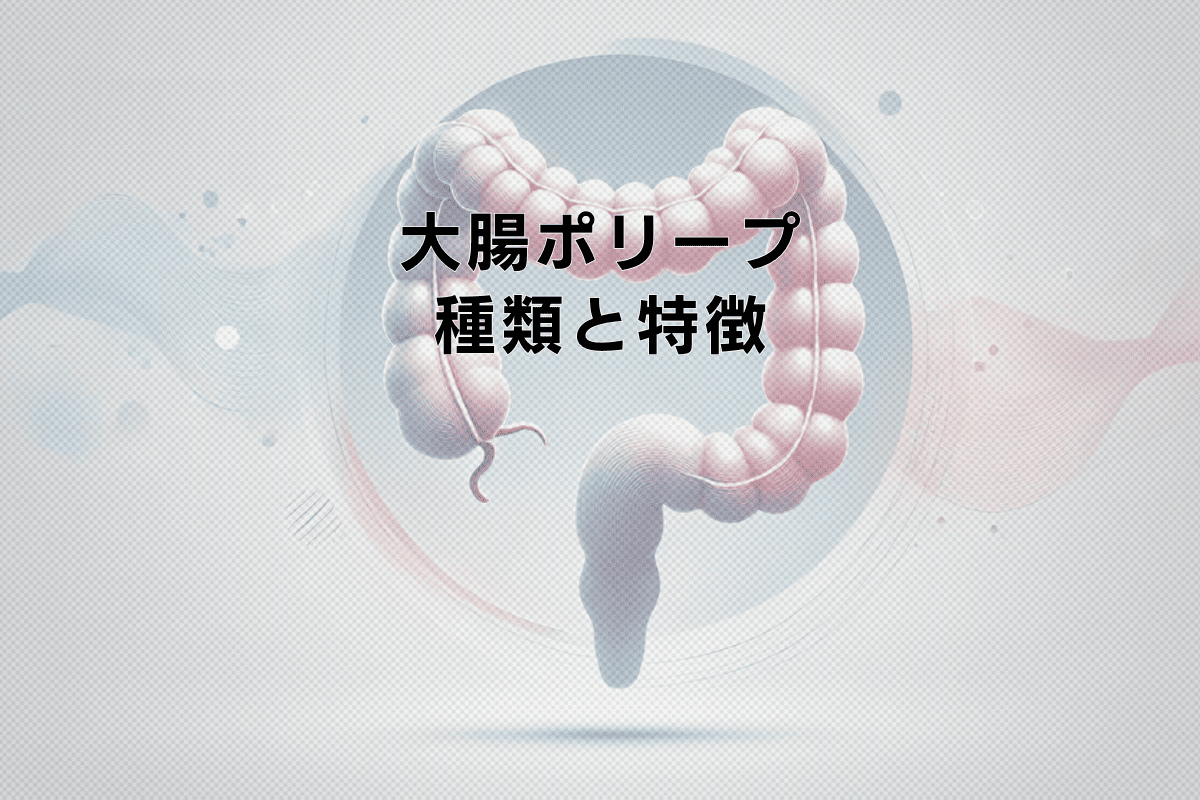
ポリープを放置するリスク
発見された大腸ポリープ、特に腫瘍性ポリープである腺腫を放置すると、どのようなリスクがあるのでしょうか。最大の懸念は、やはりがん化です。
全ての腺腫ががんになるわけではありませんし、がん化するとしても数年から十年以上かかることが多いと言われていますが、どのポリープがいつがん化するかを正確に予測することは困難です。
ポリープが大きくなるにつれて、がん細胞を含む可能性が高まり、また、ポリープが大きくなると、出血や腸重積などの症状を引き起こすこともあります。
なぜ大腸ポリープの手術が必要なのか
大腸ポリープが見つかった場合、なぜ手術(内視鏡による切除)を勧められるのでしょうか。理由と、手術を検討する基準について解説します。
がん化予防が最大の目的
大腸ポリープの手術を行う最大の目的は、大腸がんの予防です。大腸ポリープの中には、将来的にがんへと進行する可能性のある「腺腫」という種類があります。腺腫の段階で切除することで、がんへの進行を未然に防げます。
もちろん、全てのポリープががんになるわけではありませんが、現在の医療技術では、どのポリープが確実にがん化し、どのポリープがそうでないかを100%見分けることは難しいのが現状です。
手術を検討するポリープの基準
どのようなポリープが見つかった場合に手術(切除)を検討するのか、いくつかの判断基準があり、総合的に評価されます。
大きさによる判断
ポリープの大きさは、切除を判断する上で重要な要素の一つで、一般的に、腺腫の場合、大きさが5mmを超えると、がん細胞を含む可能性がわずかながら出てくると言われているため、5mmを超える腺腫は切除を推奨されることが多いです。
特に10mm(1cm)以上の大きさになると、がん細胞を含む可能性がさらに高まるため、原則として切除の対象となりますが、5mm未満の小さなポリープであっても、医師の判断や患者さんの希望によって切除を検討することもあります。
ポリープの大きさと一般的な対応の目安
| ポリープの大きさ | 一般的な対応方針の例 | 考慮事項 |
|---|---|---|
| 5mm未満 | 経過観察、または切除(医師の総合的判断による) | 形状、個数、患者さんの背景(年齢、家族歴など)も考慮 |
| 5mm~10mm未満 | 多くの場合、切除を推奨 | がん化リスクを低減するため |
| 10mm以上 | 原則として切除を推奨 | がん細胞を含む可能性が高まる。切除方法も慎重に検討 |
形状や色調による判断
ポリープの形状や色調も、がん化のリスクを判断する手がかりとなり、表面が陥凹しているタイプ(陥凹型)のポリープは、小さくても早期がんである可能性が比較的高いとされています。
また、ポリープの表面が不整であったり、が強かったりする場合も、がん化を疑う所見の一つです。
内視鏡検査では、通常光観察に加えて、特殊な光を用いたり(NBIなどの画像強調観察)、色素を散布したりすることで、ポリープの表面構造や血管のパターンを詳細に観察し、これらの情報を基に切除の必要性を判断します。
生検結果による判断
内視鏡検査の際に、ポリープの一部を少量採取し、顕微鏡で詳しく調べる病理検査を行うことがあり、ポリープが腺腫なのか、それ以外の種類のポリープか、また腺腫であれば細胞の異型度(正常からの逸脱の度合い)がどの程度か、といった情報が得られます。
異型度が高い場合(高度異型)や、既にがん細胞が見つかった場合は、当然切除の対象となります。ただし、生検はポリープ全体のごく一部を調べるものなので、生検結果が良性であっても、ポリープ全体が良性であるとは限りません。
内視鏡による大腸ポリープ切除術の概要
大腸ポリープの多くは、内視鏡を用いた低侵襲な方法で切除することが可能です。ここでは、内視鏡治療の基本的な考え方や流れについて説明します。
内視鏡治療とは
内視鏡治療とは、先端に高性能カメラと処置具を出すための鉗子口(かんしこう)がついた細長い管状の医療機器(内視鏡、いわゆる大腸カメラ)を肛門から挿入し、大腸の内部を直接モニター画面で観察しながらポリープを切除する治療法です。
お腹を切開する必要がないため、外科手術に比べて患者さんの体への負担が格段に少ない低侵襲治療の代表的なものです。
内視鏡治療の利点と注意点
内視鏡治療には多くの利点がありますが、一方でいくつかの注意点もあります。
内視鏡治療の主な利点
- 体への負担が少ない(開腹しないため、術後の痛みが軽く、回復が早い)
- 入院期間が短い、あるいは日帰りでの治療が可能(病変の大きさや種類、施設の方針による)
- お腹に傷が残らないため、美容的な観点からも優れている
- 多くの場合、ポリープの段階や早期がんであれば根治が期待できる
内視鏡治療の主な注意点
内視鏡治療は比較的安全な手技ですが、リスクが皆無ではなく、主な偶発症としては、出血や穿孔があります。頻度は低いものの、起こった場合には追加の処置や緊急手術が必要になることもあります。
また、非常に大きなポリープや、がんが深く浸潤している可能性のあるポリープ、内視鏡が届きにくい場所にあるポリープなどは、内視鏡治療の適応とならない場合や、技術的に困難な場合があります。
治療の安全性と確実性を高めるためには、十分な経験と技術を持つ医師が、適切な設備のもとで行うことが重要です。
代表的な大腸ポリープ手術の種類と名称
大腸ポリープの内視鏡治療には、ポリープの大きさや形状、深達度(病変が腸の壁のどの深さまで及んでいるか)の予測に応じて、いくつかの異なる手技があります。

ポリペクトミー(スネアポリペクトミー)
ポリペクトミーは、内視鏡を用いたポリープ切除術の中で最も基本的な手技の一つです。
「スネア」と呼ばれる、金属製の輪っか状のワイヤーを内視鏡の先端から出し、ポリープの茎や根元に引っ掛け、そして、スネアを締め付けてポリープを絞扼(こうやく:締め付けること)し、切除します。
高周波電流を用いる方法(ホットポリペクトミー)
従来から広く行われている方法で、スネアでポリープを絞扼した後に高周波電流を流し、その熱でポリープを焼き切り、切除と同時に止血効果も期待できるのが特徴です。
茎のあるポリープ(有茎性ポリープ)や、ある程度の大きさのある無茎性ポリープ(茎のない平坦なポリープ)に適しています。
コールドポリペクトミー
近年、特に小さなポリープ(一般的に10mm未満、特に5mm以下の微小なもの)に対して普及している方法で、高周波電流を使用せず、スネアでポリープを機械的に切除します。
高周波による熱凝固がないため、術後の出血や穿孔のリスクがホットポリペクトミーに比べて低いとされることや、粘膜下層への熱損傷が少ないため、切除後の組織評価がしやすいといったことが利点です。
内視鏡的粘膜切除術(EMR)
EMRは、平坦なポリープや、根元が広くてスネアだけでは引っ掛けにくいポリープ(広基性ポリープ)に対して行われる手技です。
この方法では、まずポリープの下の粘膜下層に生理食塩水やヒアルロン酸ナトリウムなどの液体を注射針で注入し、ポリープが人工的に盛り上がり、周囲の正常な粘膜との境界が明確になります。
また、粘膜下層が厚くなることで、その下にある固有筋層(腸の壁の筋肉の層)からポリープが離れ、安全に切除しやすくなります。
EMRの適応となるポリープ
EMRは、一般的に大きさが2cm程度までの、がん化が疑われる場合でも粘膜内にとどまっているか、粘膜下層へのごく浅い浸潤と判断されるポリープが良い適応です。
液体を注入することで病変を持ち上げ、スネアをかけて高周波電流で焼き切り、ポリペクトミーでは一括で切除しにくいような、ある程度広がりのある病変も、この方法であれば安全かつ確実に切除できる可能性が高まります。
EMRの手順
EMRの基本的な手順は、(1) ポリープの粘膜下層に局注液(生理食塩水など)を注入して病変を隆起させる、(2) 隆起した病変にスネアをかける、(3) 高周波電流を流して切除する、という流れです。
切除したポリープは回収し、病理検査で詳しく調べます。
内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)
ESDは、EMRでは一括切除が難しいような大きな早期がんや、線維化(組織が硬くなること)を伴うポリープなどに対して行われる、より高度な内視鏡治療技術です。
EMRがスネアを用いて病変を「焼き切る」のに対し、ESDは専用の電気メス(ITナイフ、デュアルナイフなど様々な種類があります)を用いて、病変周囲の粘膜を全周性に切開し、さらにその下の粘膜下層を少しずつ剥ぎ取っていくようにして病変を切除します。
ESDの適応と特徴
ESDの最大の利点は、大きな病変であっても分割せずに一括で切除できる可能性が高いことで、より正確な病理診断(がんの深達度や脈管侵襲の有無など)が可能となり、治療の根治性を高められます。
従来であれば外科手術が必要とされたような大きな早期大腸がんも、ESDによって内視鏡的に切除できるケースが増えていますが、ESDはEMRに比べて手技の難易度が高く、治療時間も長くなる傾向があります。
また、出血や穿孔といった偶発症のリスクもEMRよりやや高いです。
ESDの手順と難易度
ESDの手順は、(1) 病変の範囲を特定するためにマーキング(目印をつける)を行う、(2) 粘膜下層に局注液を注入して病変を十分に隆起させる、(3) 電気メスで病変周囲の粘膜を切開する、(4) 粘膜下層を慎重に剥離していく、(5) 病変を完全に切除する、という流れです。
主な内視鏡手術
| 日本語での主な名称 | 英語名称(一般的な略称) | 簡単な特徴 |
|---|---|---|
| (内視鏡的)ポリペクトミー | (Endoscopic) Polypectomy | スネア(輪状のワイヤー)でポリープを焼き切る、または機械的に切除する。 |
| 内視鏡的粘膜切除術 | Endoscopic Mucosal Resection (EMR) | ポリープの下に液体を注入して浮かせ、スネアで焼き切る。 |
| 内視鏡的粘膜下層剥離術 | Endoscopic Submucosal Dissection (ESD) | 専用の電気メスでポリープ周囲と下層を剥ぎ取るように切除する。 |
その他の切除法
上記以外にも、ごく小さなポリープ(数ミリ程度)に対して、生検鉗子(組織を採取するための小さな鉗子)に高周波電流を流してポリープを焼灼・切除する「ホットバイオプシー」という方法も以前は行われていました。
ただ、深部への熱凝固が不確実であることや、切除組織が小さく正確な病理診断が難しい場合があることなどから、近年ではコールドポリペクトミーに取って代わられつつあります。
大腸ポリープ手術後の過ごし方と注意点
内視鏡による大腸ポリープ切除術は、体への負担が少ない治療ですが、術後にはいくつかの注意点があり、安全に回復し、偶発症を防ぐために、医師や看護師の指示をよく守ることが大切です。
手術当日の注意
手術当日は、鎮静剤を使用した場合、その影響がしばらく残ることがあります。ふらつきや眠気、判断力の低下などが見られるため、帰宅時には付き添いの方がいることが望ましいです。
車の運転、バイクや自転車の運転、危険な機械の操作などは絶対に避けてください。
食事については、医師の指示に従います。多くの場合、当日は消化の良いもの(おかゆ、うどんなど)から開始するか、水分のみ、あるいは絶食となることもあります。
アルコールは厳禁で、帰宅後は、できるだけ安静に過ごしましょう。軽いシャワーは可能な場合もありますが、長時間の入浴は避けるように指示されることが多いです。
食事制限と内容
手術後数日間は、切除部位の安静と治癒を促すために、食事内容に注意が必要で、基本的には、消化が良く、腸管への刺激が少ない食事が推奨されます。
手術後の食事の進め方の一般的な目安
| 時期 | 食事内容の目安 | 特に避けるべきもの |
|---|---|---|
| 手術当日~術後1日目 | 医師の指示により、水分、流動食(重湯、スープなど)、または三分粥など。 | 固形物、刺激物、脂質の多いもの、アルコール |
| 術後2~3日目 | 五分粥~全粥、消化の良い煮魚、豆腐、やわらかく煮た野菜など。 | 香辛料、コーヒー、炭酸飲料、繊維の多い野菜、きのこ類、海藻類 |
| 術後4日目~1週間程度 | 徐々に普通の食事に近づける。ただし、暴飲暴食は避ける。 | 引き続き、刺激の強いものや脂っこいものは控えめに。 |
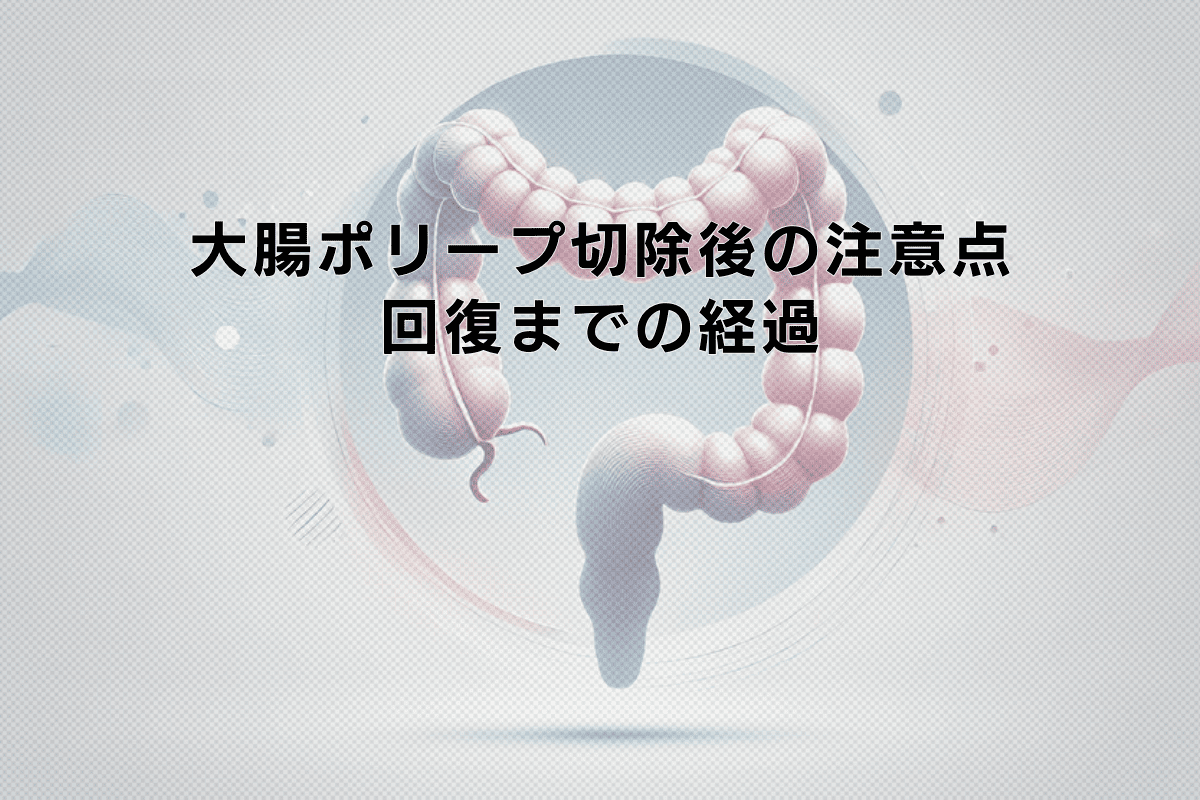
活動制限と日常生活
手術後の数日間から1週間程度は、日常生活においてもいくつかの活動制限があり、 腹圧のかかるような激しい運動(ジョギング、筋力トレーニングなど)や、重い物を持つ作業は避ける必要があります。
これらは、切除部位からの出血のリスクを高める可能性があるためで、 長時間の入浴やサウナも、血行が良くなりすぎることで出血を助長する可能性があるため、控えるように指示されます。
シャワー浴は、医師の許可があれば翌日から可能なことが多いです。 飲酒は、血管を拡張させ出血しやすくなるため、少なくとも1週間程度は禁止されるのが一般的で、喫煙も、創傷治癒を遅らせる可能性があるため、控えることが望ましいです。
デスクワークなどの軽作業であれば、日帰り手術の場合、翌日や翌々日から可能なこともありますが、これも自己判断せず、必ず医師に確認してください。
偶発症とその対応
内視鏡的大腸ポリープ切除術は比較的安全な治療法ですが、ごく稀に偶発症が起こることがあり、主なものとして「出血」と「穿孔」があります。
これらの兆候が見られた場合は、速やかに治療を受けた医療機関に連絡し、指示を仰ぐことが重要です。
術後の注意すべき症状
| 症状 | 考えられる偶発症 | 対処法 |
|---|---|---|
| 持続する強い腹痛、お腹の硬直、高熱 | 穿孔、腹膜炎 | 直ちに医療機関に連絡し受診 |
| 大量の血便、頻回の血便、黒色便、めまい | 術後出血(活動性) | 医療機関に連絡し指示を仰ぐ |
| 軽い腹痛、少量の出血が続く | 軽度の出血、切除後の炎症 | 医療機関に相談(緊急性は低い場合もあるが自己判断しない) |
手術後のフォローアップと再発を防ぐために
大腸ポリープを切除した後も、それで終わりではなく、定期的な経過観察と、再発予防のための生活習慣の改善が重要になります。
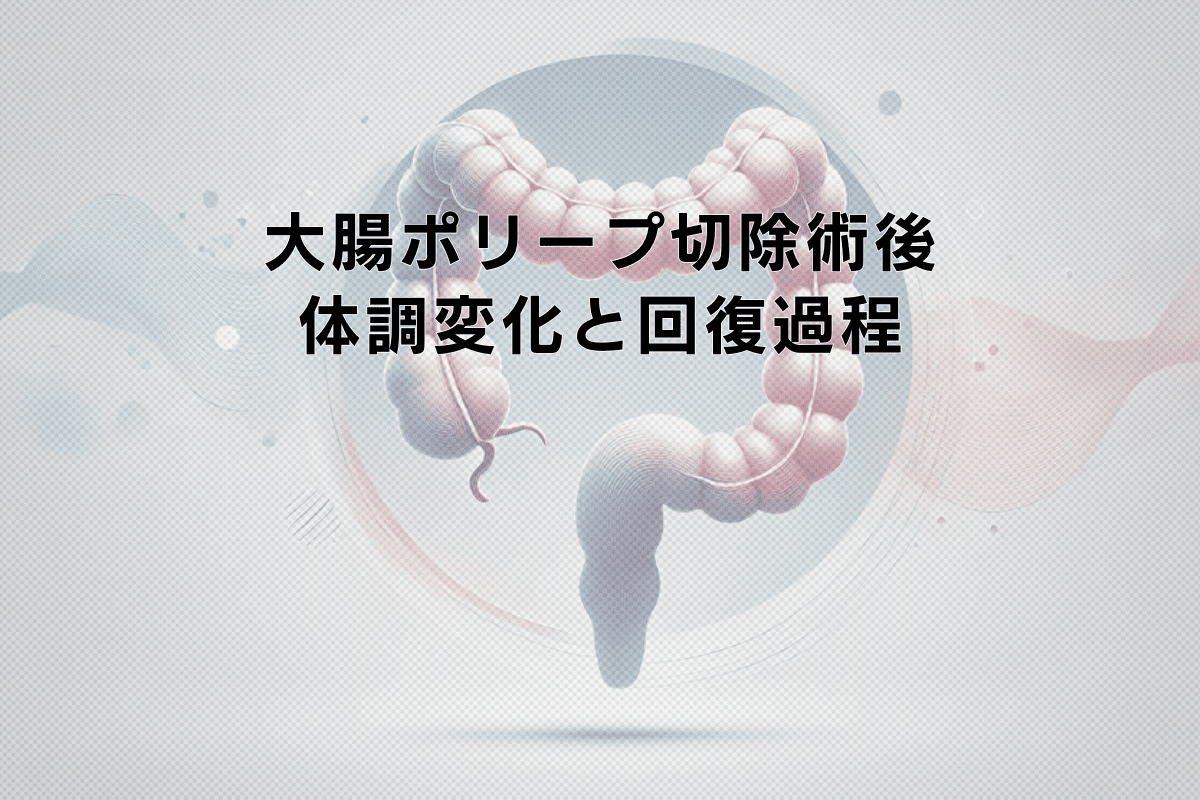
定期的な内視鏡検査の重要性
一度大腸ポリープを切除しても、それで安心というわけではなく、ポリープができやすい体質の方は、大腸の別の場所に新たなポリープが発生する可能性があります。
また、切除したポリープが大きかったり、多数あったり、あるいは病理検査の結果でがん細胞が含まれていたりした場合には、より慎重な経過観察が必要です。
そのため、手術後は医師の指示に従い、定期的に大腸内視鏡検査を受けることが極めて重要です。
検査の間隔は、最初にあったポリープの数、大きさ、種類(病理組織診断)、切除の完全性、そして患者さん自身の家族歴や年齢などを総合的に考慮して決定されます。
一般的には、1年から3年ごとの検査を勧められることが多いですが、状況によってはより短い間隔での検査が必要な場合もあります。
再発のリスク因子
大腸ポリープが再発しやすい、あるいは新たに発生しやすいとされるいくつかのリスク因子が知られています。
- 年齢(高齢になるほどリスクは高まる傾向)
- 性別(一般的に男性の方がややリスクが高いとされる)
- 過去のポリープの既往(多発していた、大きなポリープがあったなど)
- 大腸がんの家族歴(血縁者に大腸がんやポリープの人がいる)
- 生活習慣(下記参照)
これらのリスク因子を持つ方は、特に定期的な検査を欠かさないように心がけることが大切です。
生活習慣の見直し
大腸ポリープの発生や再発には、遺伝的な要因だけでなく、日々の生活習慣も深く関わっていると考えられていて、全てをコントロールすることはできませんが、生活習慣を見直すことで、リスクをある程度低減できる可能性があります。
食生活の改善点
バランスの取れた食事が基本です。特に、食物繊維を豊富に含む野菜、果物、豆類、きのこ類、海藻類などを積極的に摂取することが推奨されます。
食物繊維は、便通を整え、腸内環境を改善する効果が期待でき、 一方で、赤肉(牛肉、豚肉、羊肉など)や加工肉(ハム、ソーセージ、ベーコンなど)の過剰な摂取は、大腸がんのリスクを高める可能性が指摘されているため、摂取量に注意が必要です。
また、高脂肪食や過度な飲酒も避けた方が良いでしょう。

運動習慣の推奨
適度な運動習慣も、大腸ポリープや大腸がんの予防に役立つと考え、運動は、腸の蠕動運動を活発にし、便通を改善する効果があり、また、肥満の予防や解消にもつながり、これは大腸がんのリスク低減にも間接的に貢献します。
特別な運動でなくても、ウォーキング、ジョギング、水泳など、自分が継続しやすい有酸素運動を、週に数回、1回30分程度から始めてみると良いでしょう。
日常生活の中で、エレベーターではなく階段を使う、一駅分歩くなど、こまめに体を動かすことも有効です。
再発予防に繋がる可能性のある生活習慣のポイント
| 生活習慣の項目 | 具体的な心がけ | 期待される主な効果 |
|---|---|---|
| 食事 | 野菜・果物・豆類を多く摂る。食物繊維を意識する。赤肉・加工肉の摂取は控えめに。 | 腸内環境の改善、便通促進、発がん物質との接触時間短縮。 |
| 運動 | 週に150分程度を目安に、継続しやすい有酸素運動を行う。 | 腸管運動の促進、肥満予防、免疫機能の維持。 |
| 禁煙 | 喫煙は多くの病気のリスク因子。禁煙する。 | 大腸がんを含む複数のがんリスク低減。 |
| 節酒 | アルコールの過剰摂取を避ける。適量を守る。 | 大腸がんリスクの低減。 |
よくある質問 (FAQ)
大腸ポリープの手術に関して、患者さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。ただし、個々の状況によって異なる場合があるため、最終的には担当医にご確認ください。
- 手術は痛いですか?
-
多くの場合、内視鏡検査や治療の際には鎮静剤や鎮痛剤を使用するため、検査中や手術中に強い痛みを感じることはほとんどありません。うとうとしている間、あるいは眠っている間に終わることが多いです。
手術後には、お腹が張った感じ(腹部膨満感)や、軽い鈍痛を感じることがありますが、これは内視鏡で空気や炭酸ガスを腸内に入れた影響や、ポリープを切除したことによる一時的なものです。
- 入院は必要ですか?
-
入院の必要性は、切除したポリープの大きさや数、使用した切除手技(ポリペクトミー、EMR、ESDなど)、患者さんの全身状態、そして医療施設の方針によって異なります。
比較的小さなポリープを数個、コールドポリペクトミーやホットポリペクトミーで切除した場合は、日帰り手術として行われることもあります。
EMRやESDで大きなポリープを切除した場合や、出血・穿孔のリスクが比較的高いと判断される場合、抗凝固薬などを服用している方、ご高齢の方などは、術後の偶発症に備えて数日間程度の入院を勧められることが一般的です。
- 費用はどのくらいかかりますか?
-
大腸ポリープの内視鏡手術は、健康保険が適用される治療です。
ただし、自己負担額は、切除したポリープの個数や大きさ、実際に行われた手術の種類(ポリペクトミー、EMR、ESDなど)、入院の有無や期間、使用した薬剤、個室を利用した場合はその差額ベッド代など、さまざまな要因によって変動します。
また、高額療養費制度の対象となる場合もあります。
以下の記事も参考にしてください
【内視鏡検査費用の目安と流れ 胃と大腸のチェック方法】
内視鏡検査の費用の仕組みや保険診療の考え方を分かりやすく解説。検査前の準備から受診までの流れ、自己負担額の目安について詳しくご紹介し、安心して検査を受けられるよう情報をまとめています。 - 手術後、仕事はいつからできますか?
-
仕事への復帰時期は、行った手術の種類、患者さんの回復具合、そして仕事の内容(デスクワークか、体を動かす仕事かなど)によって大きく異なります。
日帰り手術で、術後の経過が順調であれば、デスクワークなどの軽作業は翌日や翌々日から可能な場合もあります。
次に読むことをお勧めする記事
【大腸ポリープ切除後の生活上の注意点|回復までの経過】
大腸ポリープ手術の基本を押さえたら、次は実際の手術後の生活管理について知っておくと安心です。食事や運動、入浴などの日常生活での注意点を具体的に知りたい方に特に参考になる内容です。
【大腸ポリープ毎年発見される方の検査と予防対策】
ポリープが頻繁に見つかる方には、次回以降の検査間隔や生活習慣の見直しによって再発リスクを抑える方法をまとめたこちらの記事がおすすめです。
参考文献
Tanaka S, Saitoh Y, Matsuda T, Igarashi M, Matsumoto T, Iwao Y, Suzuki Y, Nozaki R, Sugai T, Oka S, Itabashi M. Evidence-based clinical practice guidelines for management of colorectal polyps. Journal of Gastroenterology. 2021 Apr;56:323-35.
Sano Y, Hotta K, Matsuda T, Murakami Y, Fujii T, Kudo SE, Oda Y, Ishikawa H, Saito Y, Kobayashi N, Sekiguchi M. Endoscopic removal of premalignant lesions reduces long-term colorectal cancer risk: results from the Japan Polyp Study. Clinical Gastroenterology and Hepatology. 2024 Mar 1;22(3):542-51.
Horiuchi A, Nakayama Y, Kajiyama M, Tanaka N, Sano K, Graham DY. Removal of small colorectal polyps in anticoagulated patients: a prospective randomized comparison of cold snare and conventional polypectomy. Gastrointestinal endoscopy. 2014 Mar 1;79(3):417-23.
Shimada S, Hotta K, Takada K, Imai K, Ito S, Kishida Y, Kawata N, Yoshida M, Yamamoto Y, Maeda Y, Minamide T. Complete endoscopic removal rate of detected colorectal polyps in a real world out-patient practical setting. Scandinavian Journal of Gastroenterology. 2023 Apr 3;58(4):422-8.
Kawamura T, Takeuchi Y, Asai S, Yokota I, Akamine E, Kato M, Akamatsu T, Tada K, Komeda Y, Iwatate M, Kawakami K. A comparison of the resection rate for cold and hot snare polypectomy for 4–9 mm colorectal polyps: a multicentre randomised controlled trial (CRESCENT study). Gut. 2018 Nov 1;67(11):1950-7.
Ichise Y, Horiuchi A, Nakayama Y, Tanaka N. Prospective randomized comparison of cold snare polypectomy and conventional polypectomy for small colorectal polyps. Digestion. 2011 Jul 1;84(1):78-81.
Kawamura T, Takeuchi Y, Yokota I, Takagaki N. Indications for cold polypectomy stratified by the colorectal polyp size: a systematic review and meta-analysis. Journal of the Anus, Rectum and Colon. 2020 Apr 28;4(2):67-78.
Yamashina T, Uedo N, Akasaka T, Iwatsubo T, Nakatani Y, Akamatsu T, Kawamura T, Takeuchi Y, Fujii S, Kusaka T, Shimokawa T. Comparison of underwater vs conventional endoscopic mucosal resection of intermediate-size colorectal polyps. Gastroenterology. 2019 Aug 1;157(2):451-61.
Noda H, Ogasawara N, Sugiyama T, Yoshimine T, Tamura Y, Izawa S, Kondo Y, Ebi M, Funaki Y, Sasaki M, Kasugai K. The influence of snare size on the utility and safety of cold snare polypectomy for the removal of colonic polyps in Japanese patients. Journal of Clinical Medicine Research. 2016 Jul 30;8(9):662.
Nakajima K, Sharma SK, Lee SW, Milsom JW. Avoiding colorectal resection for polyps: is CELS the best method?. Surgical endoscopy. 2016 Mar;30:807-18.