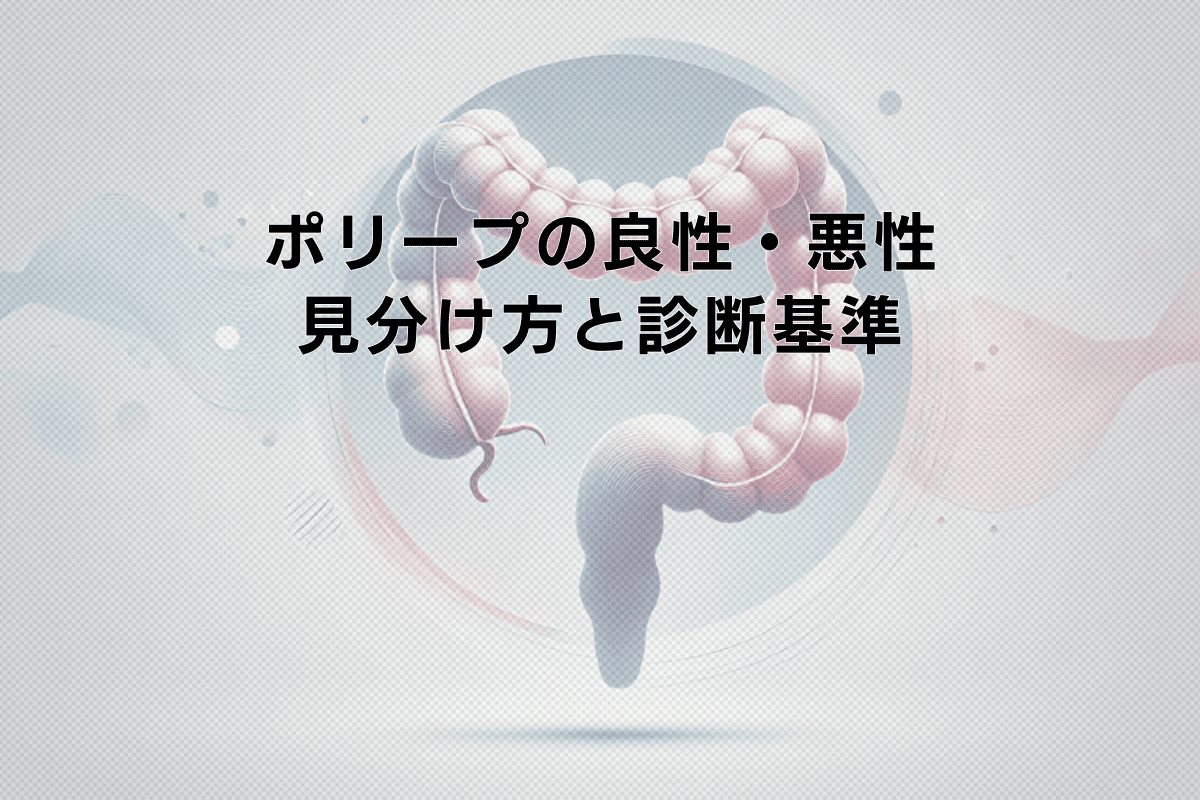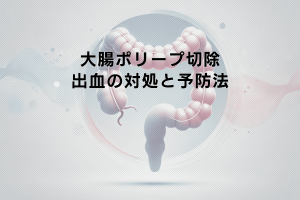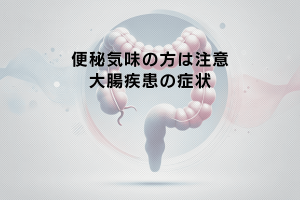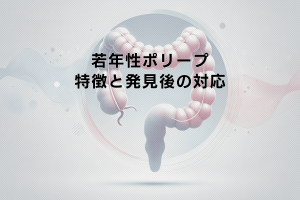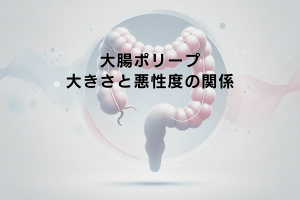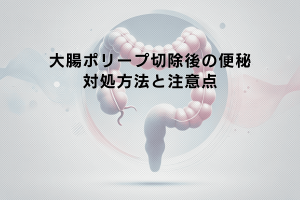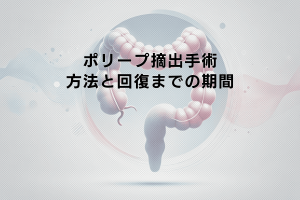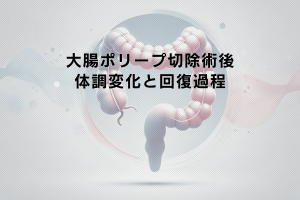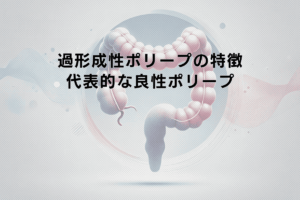ポリープと診断されると、多くの方が良性なのか、それとも悪性(がん)なのかと不安に感じるかもしれません。ポリープには様々な種類があり、性質も異なります。
この記事では、消化器系を中心に、ポリープの良性と悪性の違い、見分け方のポイント、そしてどのような検査や基準で診断が行われるのかを、分かりやすく説明しましょう。
ポリープとは何か?基本的な知識
ポリープという言葉を耳にしたことがある方は多いと思います。ここでは、ポリープの基本的な定義や発生する原因、一般的な症状について解説します。
ポリープの定義と発生部位
ポリープとは、消化管やその他の臓器の粘膜表面から、内腔に向かってきのこ状やいぼ状に盛り上がった隆起物を指す総称で、特定の病名を指すわけではなく、形状に対する呼び名です。
ポリープは体の様々な場所に発生する可能性があり、特に胃、大腸、胆嚢、子宮、声帯、鼻腔などで見つかることがあります。
ポリープができる原因
ポリープが発生する原因は、ポリープの種類や発生部位によって異なりますが、一般的には以下のような要因が関与していると考えられています。
- 遺伝的要因
- 食生活の乱れ(高脂肪食、低繊維食など)
- 加齢
- 慢性的な炎症(例:ピロリ菌感染による慢性胃炎)
- 喫煙や過度な飲酒などの生活習慣
いろいろな要因が複雑に絡み合い、粘膜細胞の異常な増殖を起こすことでポリープが形成されると考えられていますが、全てのポリープの原因が特定できるわけではありません。
ポリープの一般的な症状
多くのポリープ、特に初期の小さなものは自覚症状がないことがほとんどです。そのため、健康診断や人間ドックの内視鏡検査などで偶然発見されるケースが多くあります。
ポリープが大きくなると現れる症状
- 腹痛、腹部不快感
- 便秘や下痢などの便通異常
- 血便、下血(便に血が混じる、黒い便が出る)
- 貧血(慢性的な出血による)
- (鼻ポリープの場合)鼻づまり、嗅覚障害
- (声帯ポリープの場合)声のかすれ
ポリープの種類と特徴
ポリープには様々な種類があり、それぞれ性質や悪性化のリスクが異なります。
胃ポリープの種類と特徴
胃にできるポリープには、主に以下の種類があります。
胃ポリープの主な種類
| ポリープの種類 | 特徴 | 悪性化リスク |
|---|---|---|
| 過形成性ポリープ | 胃の炎症が長く続いた結果、粘膜が過剰に増殖してできる。ピロリ菌感染との関連が指摘される。 | 低い(稀にがん化) |
| 胃底腺ポリープ | 胃の底部(胃底腺領域)に多発することが多い。ピロリ菌のいないきれいな胃にできやすい。 | 非常に低い(原則としてがん化しない) |
| 腺腫性ポリープ(胃腺腫) | 細胞に異型(正常とは異なる形)が見られるポリープ。前がん病変と考えられ、大きくなるとがん化するリスクがある。 | あり(大きさに応じて高まる) |
胃ポリープの多くは良性ですが、腺腫性ポリープのようにがん化する可能性のあるものもあるため、種類に応じた対応が必要です。
大腸ポリープの種類と特徴
大腸にできるポリープも複数の種類があり、特に腺腫性ポリープは注意が必要です。
大腸ポリープの主な種類
| ポリープの種類 | 特徴 | 悪性化リスク |
|---|---|---|
| 腺腫性ポリープ(大腸腺腫) | 大腸ポリープの中で最も多く、大腸がんの多くはこのポリープから発生する。 | あり(大きくなるほどリスク上昇) |
| 過形成性ポリープ | 直腸やS状結腸に多く見られる。基本的には良性で、がん化のリスクは低いとされるが、一部特殊なタイプは注意が必要。 | 低い(一部例外あり) |
| 炎症性ポリープ | 潰瘍性大腸炎やクローン病などの炎症性腸疾患に伴って発生する。がん化のリスクは低い。 | 低い |
| 鋸歯状ポリープ/病変(SSA/P, SSLなど) | 近年注目されているポリープで、過形成性ポリープに似ているが、がん化する経路が異なるものがある。 | あり(種類による) |
大腸ポリープ、特に腺腫性ポリープは、大きさが5mmを超えるとがん細胞が含まれる可能性が出てきて、10mm以上ではよりそのリスクが高まるため、発見された場合は内視鏡的に切除することが推奨されることが多いです。
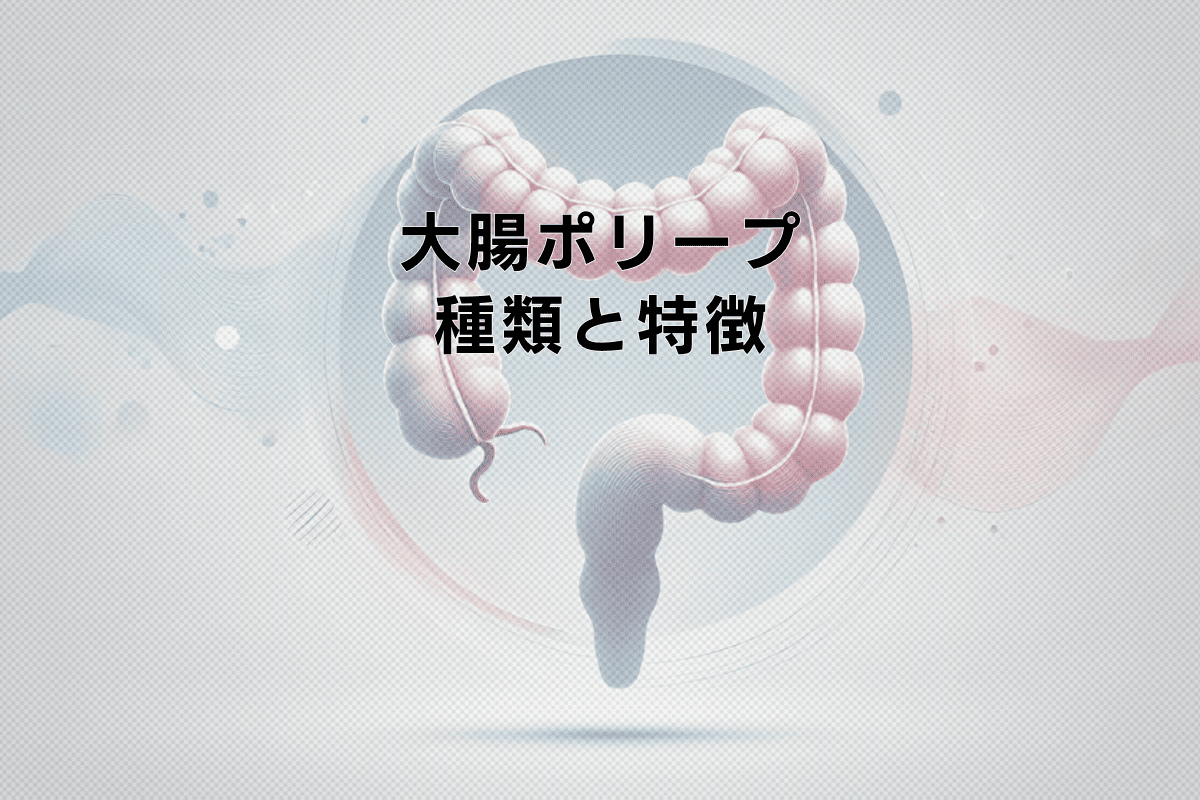
その他の部位にできるポリープ
消化管以外にもポリープは発生します。
代表的な消化管以外のポリープ
| ポリープの種類 | 主な発生部位 | 簡単な説明 |
|---|---|---|
| 胆嚢ポリープ | 胆嚢 | 多くはコレステロールポリープで良性。10mmを超えるものや増大傾向のあるものは悪性の可能性を考慮。 |
| 声帯ポリープ | 声帯 | 声の酷使や喫煙などが原因で発生。声がれの原因となる。 |
| 鼻ポリープ(鼻茸) | 鼻腔・副鼻腔 | アレルギー性鼻炎や慢性副鼻腔炎(蓄膿症)に伴って発生。鼻づまりや嗅覚障害の原因となる。 |
ポリープの良性と悪性はどう違うのか
ポリープと診断された際に最も気になるのが、良性なのか悪性(がん)なのかという点でしょう。ここでは、良性ポリープと悪性ポリープの基本的な違いについて解説します。
良性ポリープとは
良性ポリープは、細胞の増殖がコントロールされており、周囲の組織に浸潤(しみ込むように広がること)したり、他の臓器に転移したりすることはありません。成長速度も比較的ゆっくりで、生命に直接的な危険を及ぼすことは少ないです。
良性ポリープの主な特徴
- 増殖が緩やか
- 周囲組織への浸潤がない
- 遠隔転移がない
ただし、良性ポリープの中にも、放置すると将来的に悪性化する可能性のあるもの(前がん病変)があり、大腸の腺腫性ポリープや胃の腺腫性ポリープが該当します。
良性だから安心、と自己判断せず、医師の指示に従って経過観察や治療を受けることが大切です。
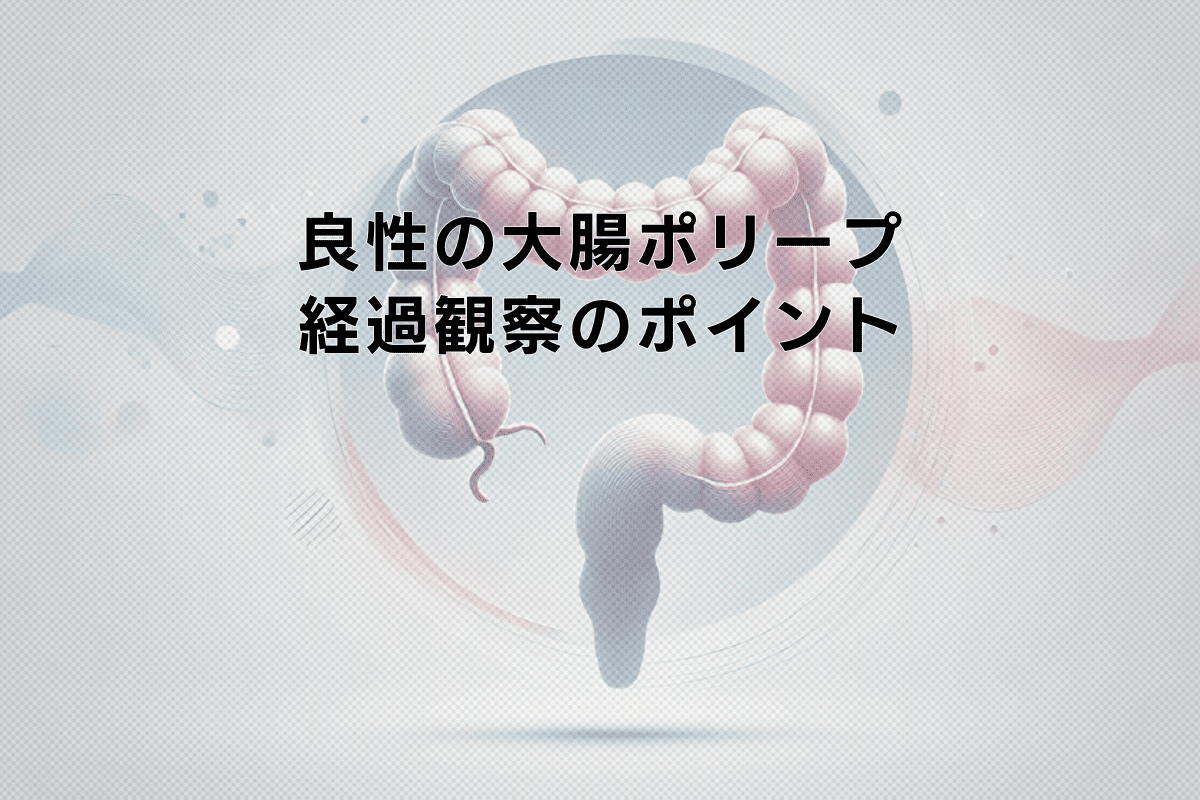
悪性ポリープ(がん)とは
悪性ポリープとは、ポリープの形をとったがん(悪性腫瘍)のことを指し、がん細胞は無秩序に増殖し、周囲の組織に浸潤したり、血液やリンパの流れに乗って他の臓器に転移したりする能力を持っています。
放置すると進行し、生命を脅かす可能性があります。
悪性ポリープ(がん)の主な特徴
- 無秩序な細胞増殖
- 周囲組織への浸潤
- 遠隔転移の可能性
ポリープが悪性であるかどうかは、主に内視鏡検査時の見た目(大きさ、形、色調など)や、生検による病理組織学的検査によって判断し、早期のがんであれば、内視鏡的に切除することで根治が期待できる場合も多いです。
良性と悪性の境界にあるポリープ
ポリープの中には、現時点では明確に良性とも悪性とも言えない、いわば境界領域の病変もあり、異型度という指標で評価されることがあります。
異型度とは
異型度とは、細胞の顔つきが正常からどれだけずれているか(異なっているか)を示す度合いです。
異型度が低い場合は良性に近く、異型度が高い場合は悪性(がん)に近い、あるいは既にがん化している可能性があると判断され、異型度の評価は、治療方針を決定する上で非常に重要な情報となります。
異型度が高いポリープや、がん化が疑われるポリープは、より慎重な対応が求められ、多くの場合、内視鏡的切除や外科手術による治療が検討されます。
ポリープを発見するための検査方法
ポリープ、特に初期のものは自覚症状が乏しいため、定期的な検査による早期発見が重要です。
内視鏡検査(胃カメラ・大腸カメラ)
内視鏡検査は、先端に小型カメラが付いた細い管(スコープ)を口や肛門から挿入し、消化管の内部を直接観察する検査です。
胃ポリープの発見には胃カメラ(上部消化管内視鏡検査)、大腸ポリープの発見には大腸カメラ(下部消化管内視鏡検査)が行われます。
検査の準備と流れ
胃カメラの場合、検査前日の夕食後から絶食が必要です。
大腸カメラの場合は、検査前に下剤を服用して腸内を空にし、検査当日は、鎮静剤を使用することもあり、その場合は検査後の車の運転などが制限されます。
検査時間は、観察のみであれば胃カメラで10~15分程度、大腸カメラで20~30分程度で、ポリープ切除などを行う場合は、もう少し時間がかかります。
内視鏡検査でわかること
内視鏡検査では、ポリープの有無だけでなく、大きさ、形状、色調、表面構造などを詳細に観察でき、また、疑わしい部分があれば、その場で組織の一部を採取(生検)して病理検査に提出し、良性か悪性かを診断できます。
小さなポリープであれば、検査と同時に切除することも可能です。
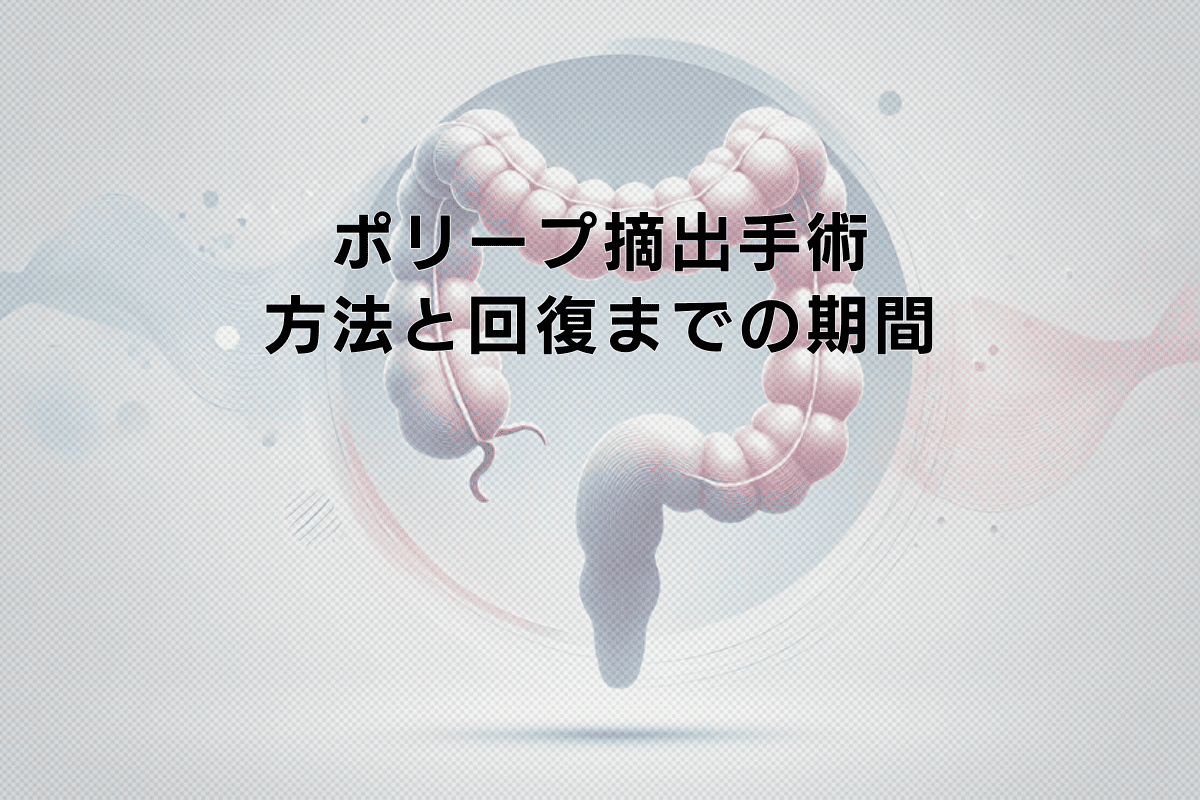
生検(組織検査)の必要性
見た目だけでは良性か悪性かの判断が難しい場合や、悪性が疑われる場合には、生検を行い、採取した組織を顕微鏡で詳しく調べることで、確定診断を得ることができます。生検は診断精度を高めるために非常に重要な検査です。
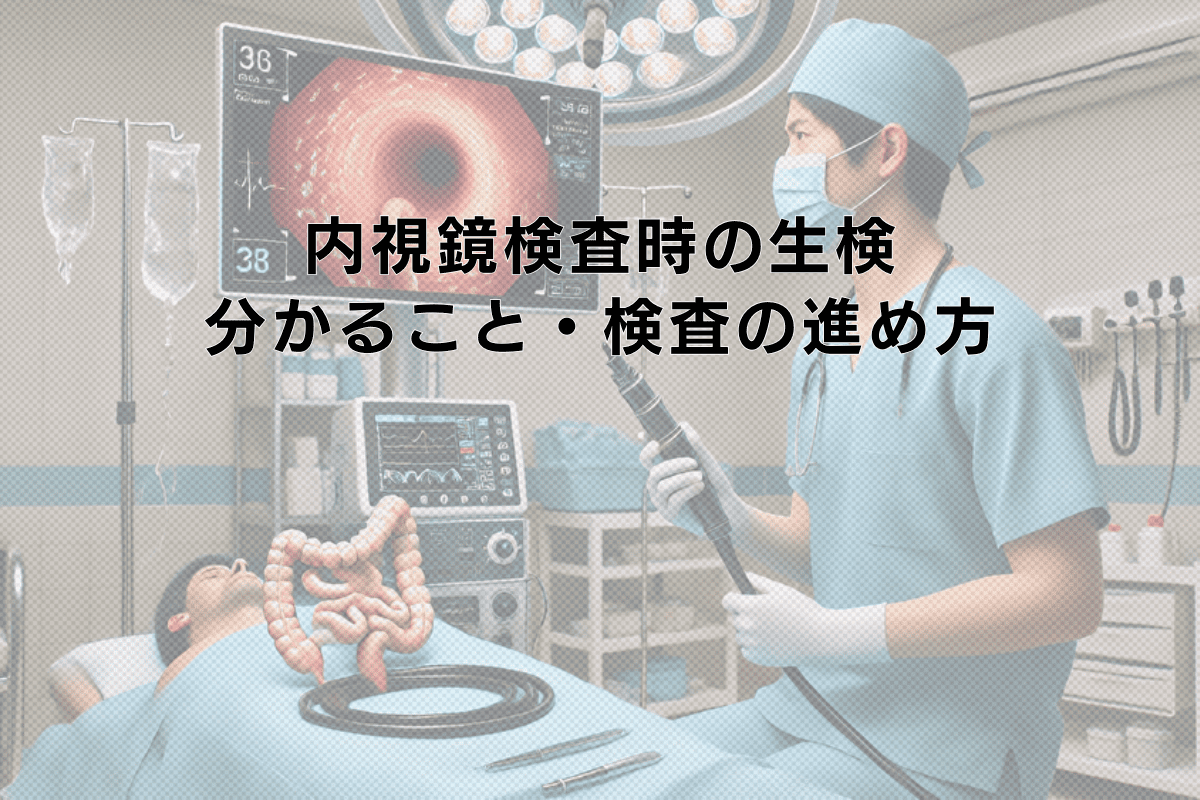
画像検査(バリウム検査、CT検査など)
内視鏡検査以外にも、ポリープの発見に用いられる画像検査があります。
主な画像検査とその特徴
| 検査方法 | 特徴 | 主な役割 |
|---|---|---|
| X線バリウム検査(胃・大腸) | バリウムという造影剤を飲んだり肛門から注入したりしてX線撮影を行う。 | 消化管全体の形態や大きな病変のスクリーニング。 |
| CTコロノグラフィ(CTC) | CTスキャンを用いて大腸の3次元画像を構築する。仮想内視鏡検査とも呼ばれる。 | 大腸ポリープのスクリーニング。下剤の服用は必要だが、大腸カメラより苦痛が少ないとされる。 |
| 腹部超音波(エコー)検査 | 超音波を用いて腹腔内の臓器を観察する。 | 胆嚢ポリープの発見などに有用。比較的簡便に行える。 |
画像検査は、内視鏡検査に比べて体への負担が少ない場合がありますが、小さなポリープの発見率や診断の精度では内視鏡検査に劣ることがあります。また、異常が見つかった場合は、確定診断のために内視鏡検査が必要になることが一般的です。
便潜血検査
便潜血検査は、便の中に微量の血液が混じっていないかを調べる検査で、主に大腸がん検診として広く行われています。
ポリープやがんがあると、目に見えない程度の出血をすることがあるため、この検査が陽性となった場合は、精密検査として大腸内視鏡検査を受けることが推奨されます。
便潜血検査の意義と限界
便潜血検査は簡便で費用も比較的安価なため、多くの人を対象としたスクリーニング検査として有効です。
しかし、早期のがんやポリープでは必ずしも出血があるわけではないため、検査結果が陰性であっても、ポリープやがんが絶対にないとは言い切れません。また、痔など良性の病気でも陽性になることがあります。

ポリープの診断基準と悪性度の判定
ポリープが見つかった場合、そのポリープが良性なのか、悪性の可能性があるのかを正確に診断することが治療方針を決定する上で極めて重要です。
大きさによる判断基準
ポリープの大きさは、悪性度を判断する上での重要な指標の一つで、一般的に、ポリープは大きくなるほど悪性化する(がんを含む)可能性が高まります。
ポリープの大きさとがん化リスクの目安(大腸ポリープの場合)
| ポリープの大きさ | がんを含む可能性 |
|---|---|
| 5mm以下 | 低い(数%以下) |
| 6mm~9mm | 約5~10% |
| 10mm~19mm | 約10~25% |
| 20mm以上 | 約25~50%以上 |
ただし、これはあくまで目安であり、小さなポリープでも悪性のもの(早期がんなど)が存在することもありますし、大きなポリープでも良性のものもあります。
大きさだけでなく、次に述べる形状や色調、そして生検結果などを総合的に評価します。
形や色調による判断基準
内視鏡検査では、ポリープの形状(有茎性か無茎性か、表面が平滑か凹凸不整かなど)や色調(周囲の粘膜と同じか、発赤が強いか、白色調かなど)を詳細に観察します。
悪性を疑う所見
- 不整な形状、いびつな形
- 表面の凹凸不整、びらんや易出血性
- 色調の異常(強い発赤、褪色、白色変化など)
- 陥凹(へこみ)を伴うもの
近年では、NBI(Narrow Band Imaging)やBLI(Blue LASER Imaging)、LCI(Linked Color Imaging)といった特殊な光を用いた観察技術(画像強調観察)が普及しており、これらを用いることでポリープ表面の微細な血管構造や模様を強調して表示させることが可能です。
生検(組織検査)による確定診断
最終的な良悪性の診断に使われるのは、ポリープの一部または全部を採取し、顕微鏡で細胞の顔つきや構造を調べる病理組織学的検査(生検)です。
病理医が細胞の異型度(正常からのずれの程度)や、がん細胞の有無、浸潤(がん細胞が組織の奥深くまで入り込んでいるか)の程度などを評価します。
病理診断の主な評価項目
| 評価項目 | 内容 |
|---|---|
| 組織型 | ポリープの種類(例:腺腫、過形成性ポリープ、がんなど)を分類 |
| 異型度 | 細胞の形態が正常からどれだけ逸脱しているかを示す(低異型度、高異型度など) |
| 浸潤の有無・深達度 | がん細胞が粘膜下層やそれ以深に浸潤しているか、その深さ |
良性ポリープが悪性化する可能性と予防
良性と診断されたポリープでも、種類によっては将来的に悪性化(がん化)するリスクを持つものがあります。ここでは、どのようなポリープが悪性化しやすいのか、またその予防について解説します。
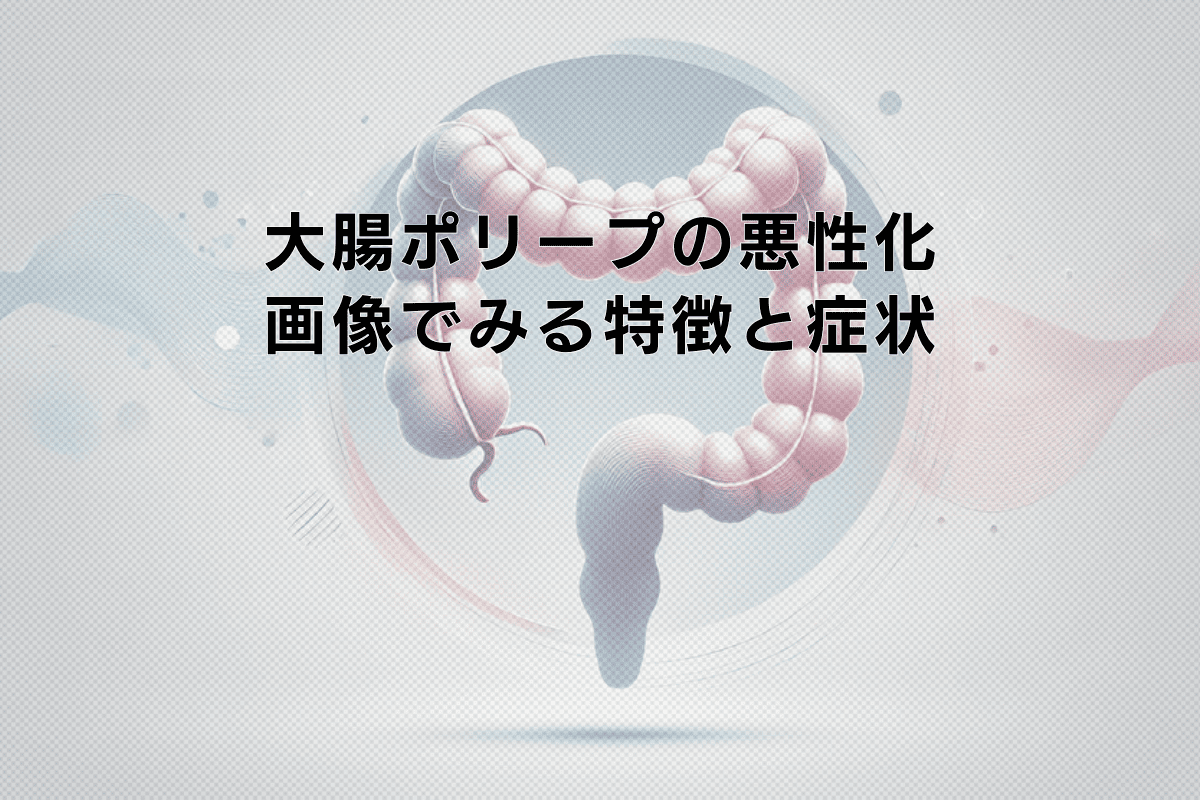
悪性化しやすいポリープの種類
全ての良性ポリープが悪性化するわけではなく、悪性化のリスクが高いとされる代表的なポリープは、大腸の腺腫性ポリープ(腺腫)と胃の腺腫性ポリープ(胃腺腫)です。
これらは前がん病変と考えられており、時間の経過とともに大きくなり、その過程でがん細胞が発生する可能性があります。
悪性化リスクに関連する要因
- ポリープの種類(特に腺腫)
- ポリープの大きさ(大きいほどリスクが高い)
- ポリープの組織型や異型度(病理検査による評価)
- ポリープの数(多発している場合は注意)
- 家族歴(家族に大腸がんや特定の遺伝性疾患の人がいる場合)
特に大腸の腺腫は、数年から十数年かけてゆっくりとがん化していくと考えられているため、腺腫の段階で発見し切除することが、大腸がんの予防に繋がります。
ポリープの成長と悪性化の期間
ポリープが発見されてから悪性化するまでの期間は、ポリープの種類や個人の体質、生活習慣などによって大きく異なります。
一般的に、大腸腺腫ががんに進行するまでには平均して5年から10年以上かかると言われていますが、進行が速いケースもあります。
悪性化のリスクがあるポリープが見つかった場合は、医師の指示に従って定期的な内視鏡検査を受け、ポリープの大きさや形状の変化を注意深く観察することが重要です。
定期検査の重要性を示すポイント
| 検査項目 | 観察ポイント |
|---|---|
| ポリープの大きさ | 前回検査時からの増大の有無 |
| ポリープの形状・色調 | 悪性化を示唆する変化の有無(陥凹、発赤、易出血性など) |
| 新規ポリープの発生 | 前回検査時にはなかったポリープの出現 |
定期的な検査により、ポリープが小さいうちに、あるいはがん化する前に発見し、適切な処置を行うことが、がんによる深刻な結果を避けるために大切です。
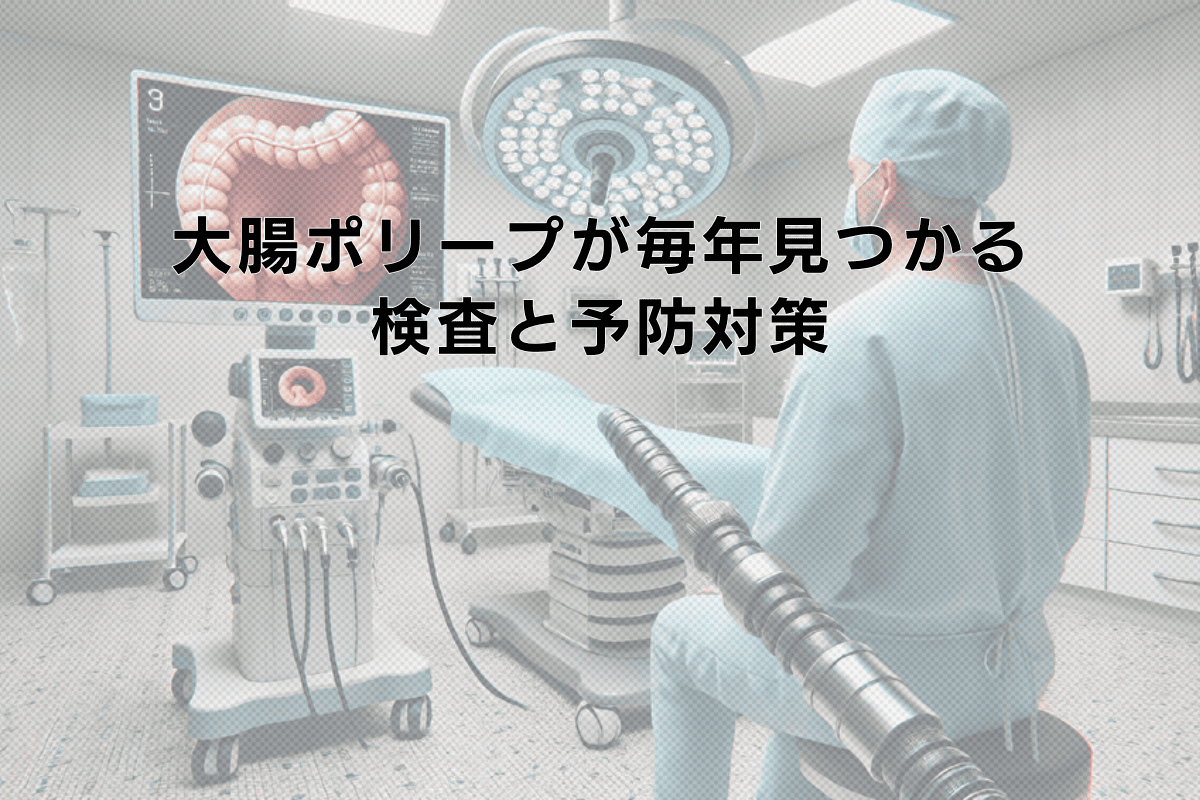
ポリープの発生・悪性化を予防するためにできること
ポリープの発生や悪性化を完全に防ぐことは難しいですが、リスクを低減するために日常生活で心がけられることがあります。
生活習慣における予防策
- バランスの取れた食事:野菜や果物を多く摂り、食物繊維を十分に摂取する。脂肪の多い食事や赤肉・加工肉の過剰摂取を控える。
- 適度な運動:定期的な運動習慣は、大腸がんのリスクを下げると報告されています。
- 禁煙:喫煙は多くのがんのリスクを高めます。ポリープの発生や悪性化にも関与すると考えられています。
- 節度ある飲酒:過度なアルコール摂取は避ける。
- 体重管理:肥満も大腸がんのリスク因子の一つです。
生活習慣の改善は、ポリープだけでなく、様々な生活習慣病の予防にも繋がり、また、ピロリ菌に感染している場合は、除菌治療を受けることで胃がんや胃ポリープ(一部)のリスクを低減できる可能性があります。
ポリープ切除後の注意点と経過観察
内視鏡検査でポリープが発見され、切除が必要と判断された場合、多くは内視鏡を用いた低侵襲な治療が行われます。
ポリープ切除の方法
消化管のポリープ切除は、主に内視鏡を使って行われます。代表的な手技には以下のようなものがあります。
主な内視鏡的ポリープ切除術
| 切除方法 | 対象となるポリープ | 簡単な手技内容 |
|---|---|---|
| ポリペクトミー(スネア切除) | 茎のあるポリープや比較的小さな隆起性ポリープ | スネアという金属の輪をポリープの根元にかけ、高周波電流を流して焼き切る。 |
| 内視鏡的粘膜切除術(EMR) | 平坦なポリープや少し大きめのポリープ | ポリープの下の粘膜下層に生理食塩水などを注入して病変を浮かせ、スネアで焼き切る。 |
| 内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD) | 大きな早期がんやEMRでは一括切除が難しい病変 | 専用の電気メスで病変周囲の粘膜を切開し、粘膜下層を剥離して病変を一括で切除する。高度な技術を要する。 |
どの方法で切除するかは、ポリープの大きさ、形状、推定される深達度(がんの場合)などを考慮して決定し、多くの場合は日帰りまたは短期入院で治療可能です。
切除後の合併症と対策
内視鏡的ポリープ切除は比較的安全な治療法ですが、稀に合併症が起こる可能性があり、主な合併症は、出血(術中や術後数日以内)や穿孔(消化管に穴が開くこと)です。
合併症のリスクを低減し、万が一起こった場合に速やかに対処するために、切除後は医師の指示に従い、一定期間の安静や食事制限(消化の良いものを少量から)、運動制限などが必要となります。
特に、切除後1週間程度は、アルコール摂取や激しい運動、長時間の入浴、旅行などは控えるよう指導されることが一般的です。
もし、切除後に持続する腹痛、発熱、黒色便や多量の血便などの症状が現れた場合は、速やかに治療を受けた医療機関に連絡してください。
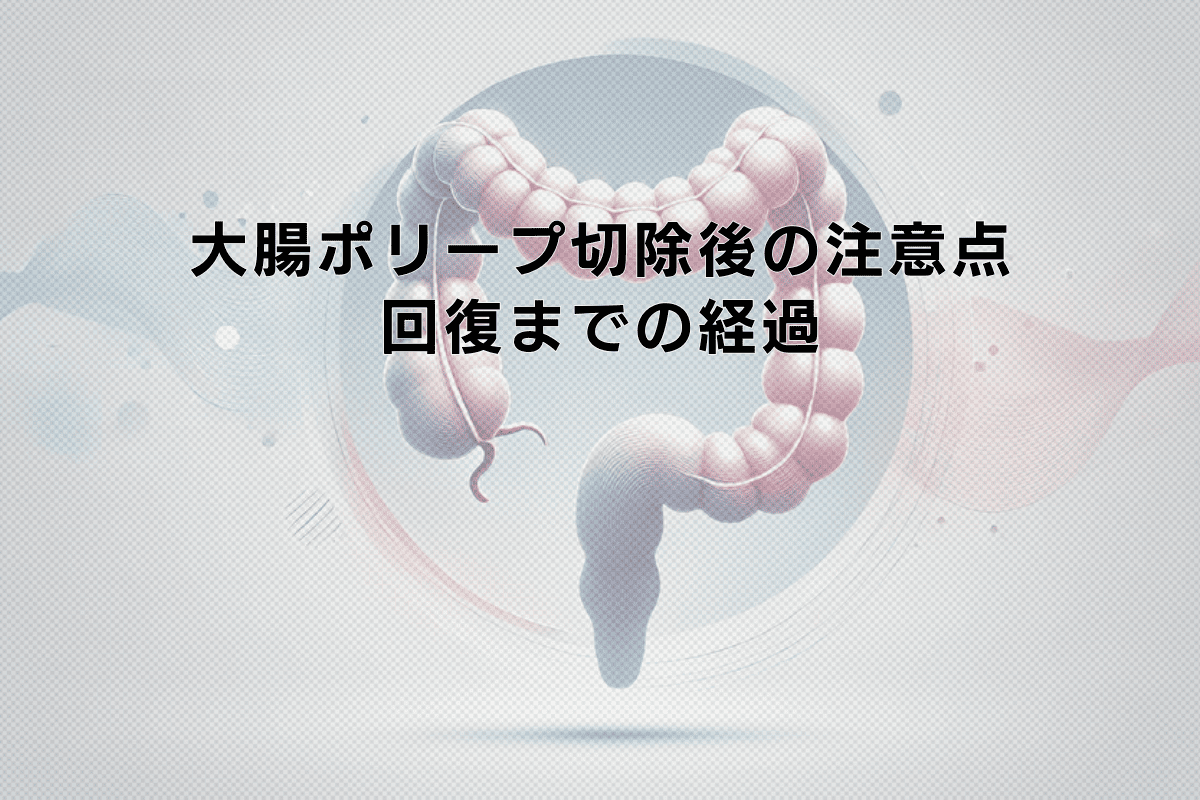
切除後の定期的な検査
ポリープを切除した後も、再発や新たなポリープの発生がないかを確認するために、定期的な内視鏡検査による経過観察が重要です。
検査の間隔は、切除したポリープの種類、数、大きさ、病理組織学的診断、患者さんの年齢や家族歴などを総合的に考慮して決定されます。
ポリープに関するよくある質問(Q&A)
ここでは、ポリープに関して患者さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
- ポリープは自覚症状がないこともありますか?
-
はい、特に小さなポリープや初期のポリープは自覚症状がないことがほとんどで、症状がなくても定期的な検診や人間ドックで内視鏡検査を受けることが、ポリープの早期発見には重要です。
症状が出てからでは、ポリープが大きくなっていたり、進行している場合もあります。
- ポリープは必ず切除する必要がありますか?
-
全てのポリープを切除する必要はなく、ポリープの種類、大きさ、形状、そして生検による病理組織学的診断の結果などを総合的に判断します。
悪性化のリスクが高いと考えられる場合や、既にある程度の大きさになっている場合に切除が推奨されます。
- ポリープの検査は痛いですか?
-
内視鏡検査(胃カメラや大腸カメラ)に対して、苦痛を感じるかどうかは個人差がありますが、胃カメラでは咽頭反射(吐き気)が、大腸カメラではお腹の張りや挿入時の違和感を感じることがあります。
ただし、最近では細径スコープの使用や、鎮静剤(眠くなる薬)や鎮痛剤を使用することで、苦痛を大幅に軽減して検査を受けることが可能です。
- ポリープの切除は日帰りでできますか?
-
ポリープの大きさや数、種類、患者さんの全身状態などによりますが、多くの比較的小さなポリープの内視鏡的切除は日帰りで行うことが可能です。
大きなポリープの切除や、出血のリスクが高いと判断される場合、あるいは複数のポリープを切除する場合などは、短期の入院を勧めることもあります。
- ポリープが再発することはありますか?
-
ポリープを切除しても、同じ場所に再発したり、別の場所に新たなポリープが発生したりする可能性はあり、ポリープができやすい体質や生活習慣などが背景にある場合、一度切除しても安心はできません。
ポリープを切除した後も、医師の指示に従って定期的な内視鏡検査を受け、経過を観察していくことが非常に重要です。
次に読むことをお勧めする記事
【大腸ポリープの悪性化リスク|画像でみる特徴と症状】
どんな見た目だと悪性の可能性があるの?」「画像ではどう見えるの?」と感じた方に、悪性化のリスクや特徴をわかりやすく解説した記事です。
【大腸ポリープ切除後の生活上の注意点|回復までの経過】
ポリープの診断について理解が深まると、関連する切除後の生活についても知りたくなる方が多いようです。意外な注意点が見えてくる内容です。
参考文献
Minoda Y, Ogino H, Chinen T, Ihara E, Haraguchi K, Akiho H, Takizawa N, Aso A, Tomita Y, Esaki M, Komori K. Objective validity of the Japan Narrow‐Band Imaging Expert Team classification system for the differential diagnosis of colorectal polyps. Digestive Endoscopy. 2019 Sep;31(5):544-51.
Furukawa H, Kosuge T, Shimada K, Yamamoto J, Kanai Y, Mukai K, Iwata R, Ushio K. Small polypoid lesions of the gallbladder: differential diagnosis and surgical indications by helical computed tomography. Archives of Surgery. 1998 Jul 1;133(7):735-9.
Azuma T, Yoshikawa T, Araida T, Takasaki K. Differential diagnosis of polypoid lesions of the gallbladder by endoscopic ultrasonography. The American journal of surgery. 2001 Jan 1;181(1):65-70.
Sano Y, Ikematsu H, Fu KI, Emura F, Katagiri A, Horimatsu T, Kaneko K, Soetikno R, Yoshida S. Meshed capillary vessels by use of narrow-band imaging for differential diagnosis of small colorectal polyps. Gastrointestinal endoscopy. 2009 Feb 1;69(2):278-83.
Irie H, Kamochi N, Nojiri J, Egashira Y, Sasaguri K, Kudo S. High b-value diffusion-weighted MRI in differentiation between benign and malignant polypoid gallbladder lesions. Acta radiologica. 2011 Apr;52(3):236-40.
Togashi K, Konishi F, Ishizuka T, Sato T, Senba S, Kanazawa K. Efficacy of magnifying endoscopy in the differential diagnosis of neoplastic and non-neoplastic polyps of the large bowel. Diseases of the colon & rectum. 1999 Dec 1;42(12):1602-8.
Bruno R, Alì G, Fontanini G. Molecular markers and new diagnostic methods to differentiate malignant from benign mesothelial pleural proliferations: a literature review. Journal of Thoracic Disease. 2018 Jan;10(Suppl 2):S342.
Su MY, Hsu CM, Ho YP, Chen PC, Lin CJ, Chiu CT. Comparative study of conventional colonoscopy, chromoendoscopy, and narrow-band imaging systems in differential diagnosis of neoplastic and nonneoplastic colonic polyps. Official journal of the American College of Gastroenterology| ACG. 2006 Dec 1;101(12):2711-6.
Youker JE, Welin S, Main G. Computer analysis in the differentiation of benign and malignant polypoid lesions of the colon. Radiology. 1968 Apr;90(4):794-7.
Mathews AA, Draganov PV, Yang D. Endoscopic management of colorectal polyps: From benign to malignant polyps. World Journal of Gastrointestinal Endoscopy. 2021 Sep 16;13(9):356.