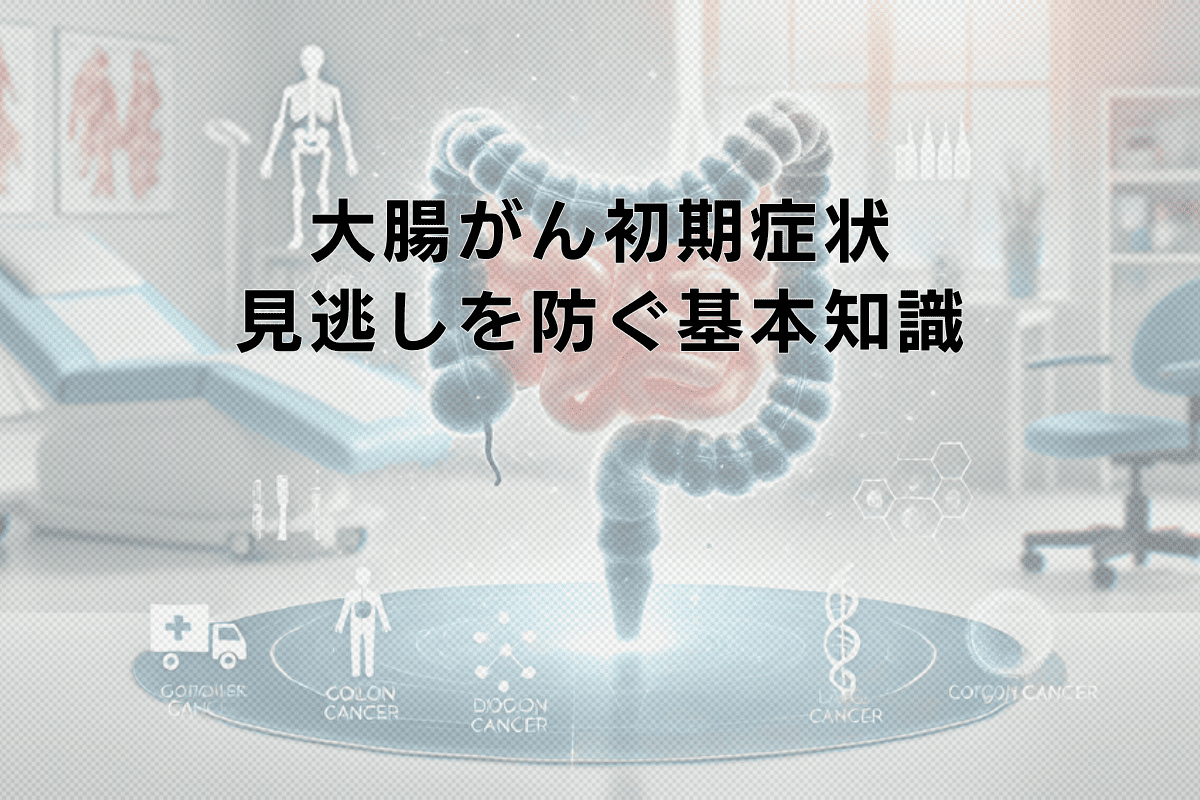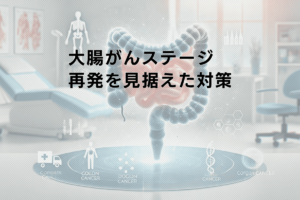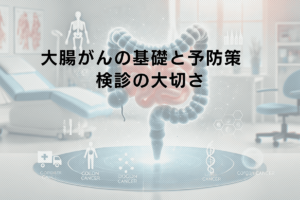大腸がん初期症状として現れやすい便の変化や下痢・便秘について、気づきにくいサインをどのように把握し、早期発見につなげるかを中心に解説します。
食習慣や生活習慣などの原因やリスク要因に触れつつ、検査方法や治療の流れを丁寧に紹介し、受診のタイミングを考えるきっかけとなれば幸いです。
少しでも気になる症状があれば医療機関に相談していただくことが大切です。
大腸がんの基本情報
大腸がんは、消化管の最後の部分である大腸に腫瘍が発生する疾患です。
日本では胃がんや肺がんに並び、がん全体の死亡率で上位を占める傾向があり、年々患者数が増えています。
しかし、早期発見できれば治療の選択肢は広がり、切除後の回復が期待できることも多くなっています。
大腸とは何か
大腸は、小腸で吸収されきれなかった水分や栄養素をさらに吸収し、便として形成する器官です。
盲腸、結腸、直腸、肛門と分かれ、全長はおよそ1.5~2m程度あり、食道や十二指腸などと並ぶ消化器官の一部であり、排便に大きく関わっています。
大腸がんとはどのような疾患か
大腸がんは、大腸の粘膜にある細胞が異常増殖を起こして発生する悪性腫瘍です。最初は小さなポリープとして発生し、それが徐々に大きくなっていく過程で悪性化(がん化)していきます。
結腸がんと直腸がんに大別されますが、症状や治療法は似通う部分が多く、初期段階では便の変化や下痢・便秘を繰り返すなどの軽微なサインで気づくことがある一方、自覚症状がほとんどないケースもあります。
大腸がんが増えている背景
大腸がんが多くなっている背景として、
- 欧米型の高脂質・低食物繊維の食事
- 運動不足や肥満
- 飲酒や喫煙
などが指摘されています。高齢化の進行も大きな要因であり、がん全般の罹患数が増えるのにともない、大腸がんの患者も増加傾向にあります。
家族歴や遺伝などが関与することもあるため、身近に大腸がんを経験した人がいる場合は注意が必要です。
早期発見の大切さ
大腸がんは早期発見が大切です。できるだけ早い段階で見つければ、内視鏡による切除や局所治療を行いやすく、リンパ節や肝臓などへの転移リスクを抑制できます。
進行してから初めて検査を受けると、手術の負担や後遺症のリスクが高まる傾向があり、自覚症状が出にくいがんとしても知られるため、日頃の体調変化や検診の受診が重要です。
大腸がんの初期症状について
大腸がんは初期症状が目立たないことが多く、腹痛や排便異常などが見られても一時的な体調不良と勘違いされやすい側面があります。
しかし、初期に気づくことで大腸内視鏡による検査と早期の治療につなげることが期待でき、多くの場合、病変が比較的浅い段階(粘膜や粘膜下層にとどまるステージ)なら切除範囲も限定的で済む可能性があります。
便秘や下痢の繰り返し
大腸がんの初期では、正常な排便リズムが変化しやすいです。便秘が続いたかと思えば突然下痢になるなど、便通が不安定になってしまうケースが見られます。
これには腫瘍が大腸の通路を部分的に狭めたり、炎症を起こしたりすることが関係すると考えられます。
ストレスや過敏性腸症候群などのほかの疾患が原因で同様の症状が出ることもありますが、軽視せずに医師の診察を受けることが重要です。
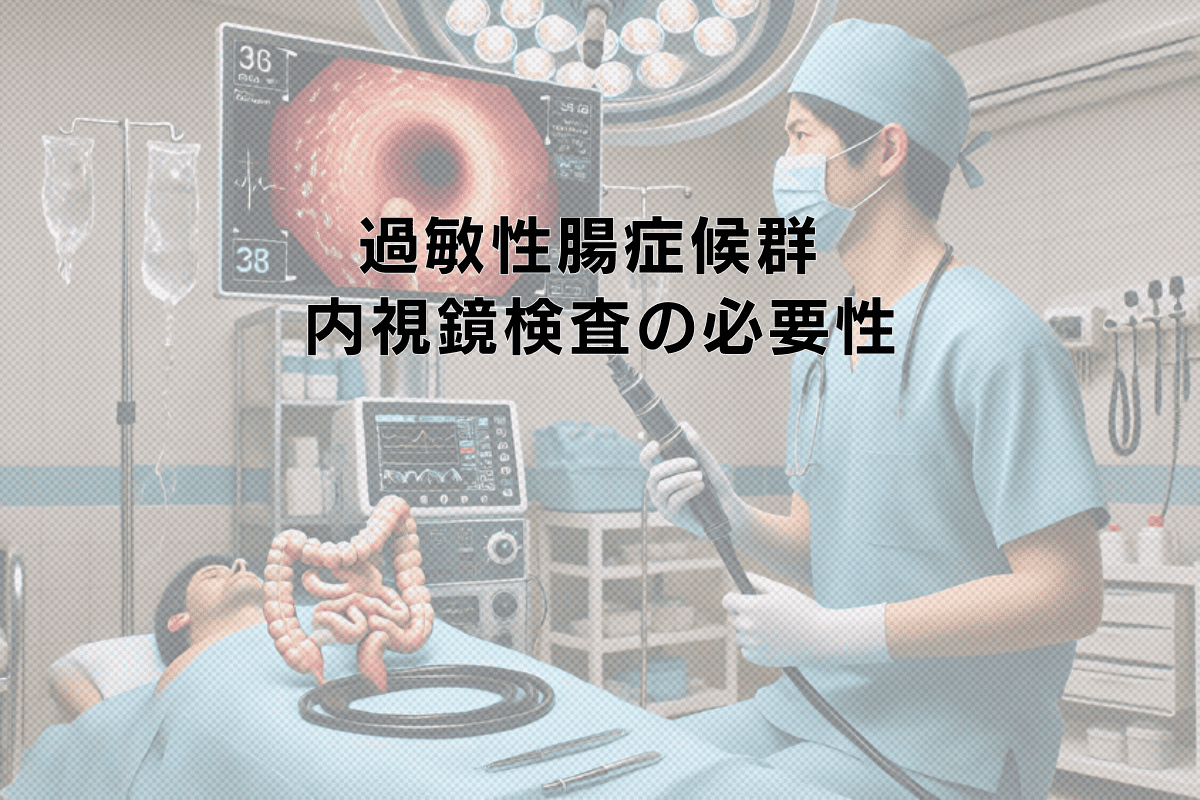
血便と出血の有無
大腸がん初期の特徴として、血便や出血がある場合があります。出血量が少ないと、便に混じった血液を肉眼で確認しにくいこともあるため、便潜血検査が早期発見の一助です。
血便の色調は赤色~黒っぽいものまで幅があり、場所によっては暗めの色になることもありますが、「血便=直腸」だけではなく、結腸からの出血でも血便が見られます。
腹痛や腹部の違和感
大腸がん初期には腹部の違和感や軽度の腹痛が起こり、腫瘍が大きくなり腸内の通過を妨げてくると、下痢や便秘だけでなく、腹痛が引き起こされるケースも見受けられます。
痛みの程度は人によって異なり、軽い張り感やしこりのように感じることもあります。痛みが持続したり、右下腹部や左下腹部など特定の位置に明確な痛みがある場合には、結腸や盲腸付近に病変がある可能性も示唆されます。
自覚症状が出る可能性
初期の段階で、はっきりした自覚症状が出る人もいれば、まったく症状がないまま進行してしまう人もいます。
特に自覚症状で気づくときには、がんがある程度進行している場合が多いため、症状の有無に関わらず、定期的な検査や健康診断を受けることが大切です。
大腸がん初期症状
| 主な初期症状 | 特徴 |
|---|---|
| 便秘・下痢の繰り返し | 腸内通過障害や腫瘍刺激によるリズムの乱れ |
| 血便・下血 | 少量でも要注意。便潜血検査で検出される場合もある |
| 腹痛・腹部の違和感 | 軽度から中程度の痛み。場所によって原因部位が異なる |
| 排便後の残便感 | 大腸の一部に通過障害が生じている場合などに多い |
大腸がんが進行する際の特徴
大腸がんが進行すると、腫瘍が大きくなるほか、リンパ節や肝臓などほかの臓器への転移リスクも高まり、初期症状を見逃して放置すると治療の選択肢が限られ、負担が増大する可能性があります。
段階が進むにつれて、より明確な症状や重篤な体調不良が現れることもあるため注意が必要です。
進行の段階と症状の変化
大腸がんはステージごとに病変の深さや転移の有無が分類されます。早期(ステージ0~Ⅰ)では粘膜下層までにとどまることが多く、自覚症状も少なめです。
しかし、ステージⅡやⅢに入ると、腸管を超えた浸潤やリンパ節への転移がみられ、腹痛や便通異常がより顕著に現れます。
末期(ステージⅣ)になると遠隔転移(肝臓や肺への転移など)が生じ、体重減少や貧血が深刻化し、倦怠感など全身症状が出る場合が多いです。
便の形状や色の変化
進行期には便の太さが細くなったり、長期にわたって黒っぽい便が続いたりする変化が起こることがあり、血液が便に混じっている状態が継続すると、黒いタール状の便になる場合もあります。
便に粘液が混じっているなど、通常とは異なる形状や匂いを感じたら、医療機関への受診をお勧めします。
貧血や体重の減少
長期間にわたる出血が少しずつ蓄積すると、慢性的な貧血を引き起こしやすくなるため、ふらつきや動悸が起こりやすい状態になったり、体重が減少したりすることがあります。
初期段階で激しい貧血に陥ることは少ないですが、貧血があるのに原因がはっきりしない場合は、大腸がんを含む消化器疾患を疑うこと必要があります。
転移の可能性と合併症
大腸がんが進行すると、腫瘍細胞が血液やリンパ液を通じて他の臓器へ転移する可能性が高まります。転移先として多いのは肝臓であり、次いで肺やリンパ節などです。
転移の有無で治療方針や手術の可否が変わるため、早期段階で転移を確認し、治療を行うことが重要です。放置すると腸閉塞や腹膜炎を起こす危険性もあり、緊急手術が必要になるケースも出てきます。
進行度合い
- 早期(ステージ0~Ⅰ): 多くの場合、自覚症状は軽度または無症状
- 中期(ステージⅡ~Ⅲ): 腸壁を越えたりリンパ節転移があったりする
- 末期(ステージⅣ): 肝臓や肺など遠隔臓器へ転移が認められる
大腸がんの原因とリスク要因
大腸がんの発症はひとつの要因だけでなく、複数の要因が重なって起こり、遺伝的因子に加えて、食事や生活習慣などの環境要因も大きく影響するといわれます。
食習慣や生活習慣との関係
食事の欧米化に伴い、肉類や脂質の摂取量が増えて野菜や食物繊維の摂取量が減ると、大腸がんのリスクが高まると考えられています。
さらに、過度の飲酒や喫煙、運動不足、肥満などもリスクを上乗せするとみなされ、これらの要因は同時に生活習慣病のリスクを高めることにもつながり、動脈硬化や糖尿病と合併して体調を悪化させやすいです。
ポリープからのがん化
大腸ポリープには腫瘍性ポリープと非腫瘍性ポリープがあり、腫瘍性ポリープ(腺腫)は放置するとがん化する可能性が高く、大腸がんの原因になることがあります。
大腸内視鏡検査でポリープが発見された際、医師がリスクを判断し、内視鏡で切除するケースが多いです。切除後の病理検査で悪性の変化がないかを確認し、必要に応じて追加治療を考えます。
遺伝的な要因や家族歴
家族に大腸がんを経験した人がいる場合はリスクが高まり、遺伝性非ポリポーシス大腸がん(HNPCC)や家族性大腸腺腫症(FAP)といった特定の遺伝病では、若い年齢での大腸がん発症が多いです。
家族歴のある方は、リスクの高い時期に合わせて定期的な内視鏡検査や健康診断を受けるのが推奨されます。
ほかの疾患との関連性
潰瘍性大腸炎やクローン病などの慢性的な炎症を伴う疾患を長期にわたって患っている場合、大腸がんのリスクが高まります。これらの疾患のある方は、主治医と相談しながら定期的に内視鏡検査を行い、粘膜の状態を観察することが重要です。
大腸がんの主なリスク要因
| リスク要因 | 内容 |
|---|---|
| 食事の欧米化(高脂質) | 肉中心の食生活は結腸・直腸への負担増に結びつく |
| 運動不足・肥満 | 体重の増加や代謝異常が腸内環境を悪化させる恐れ |
| 遺伝的要因(家族歴) | 特定の遺伝疾患や近親者にがん歴がある場合は要注意 |
| ポリープの放置 | 腺腫性ポリープは大腸がんへの進行リスクが高まる |
| 炎症性腸疾患 | 潰瘍性大腸炎やクローン病では長期的にリスクが上がる |
大腸がんの検査方法
気になる症状がある場合や健康診断などで大腸がんの可能性を指摘された場合、さまざまな検査を行うことで正確な診断に至ります。検査にかかる費用や手間はありますが、行うことで今後の治療方針が明確になり、症状の進行を防ぎやすくなります。
便潜血検査
便潜血検査は、便に血液が混じっているかどうかを調べる簡単な検査です。
少量の血液でも検出可能なため、初期の大腸がんやポリープなどで出血している場合に発見しやすい利点がありますが、痔や肛門周辺の炎症でも陽性になる場合があるため、陽性結果が出ても必ずしも大腸がんであるとは限りません。
また感度(病気がある方が陽性となる確率)が高くないので、陰性であっても大腸がんや大腸ポリープの治療を受けたことがある方や症状がある方は内視鏡検査を受けることをお勧めします。
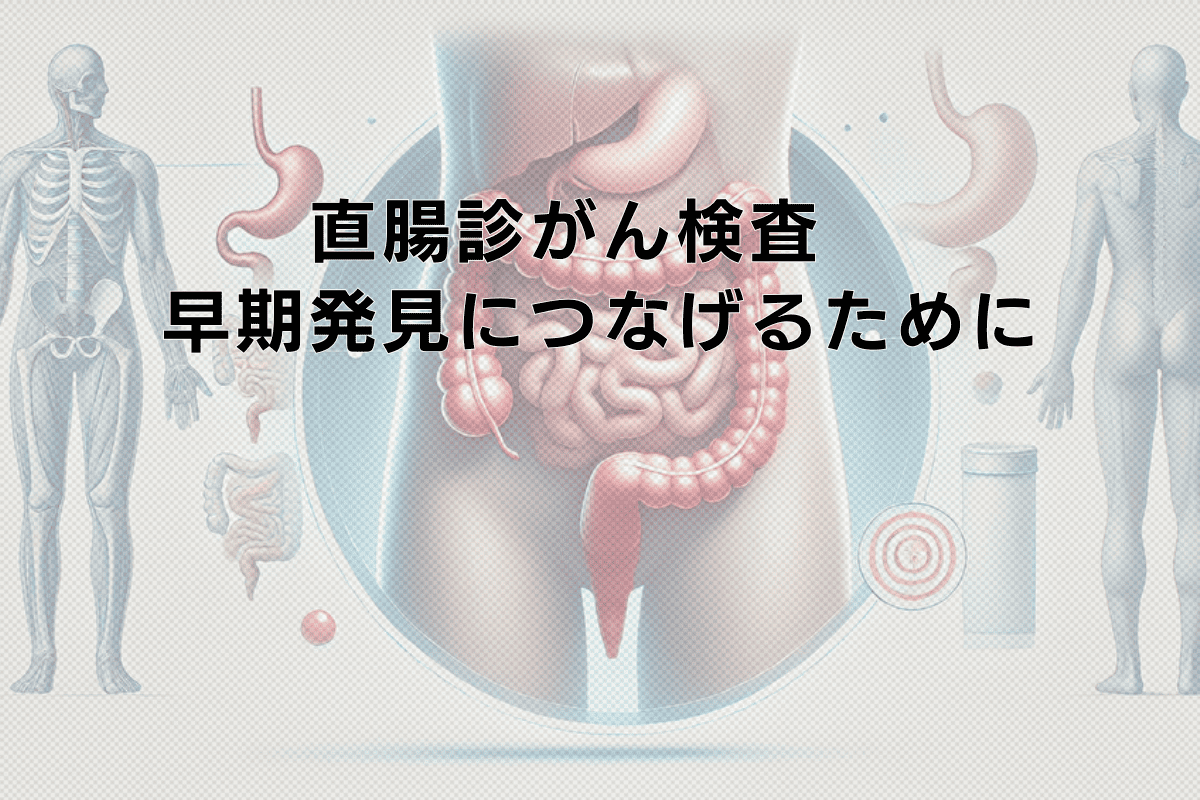
大腸内視鏡検査
大腸の内部を直接観察し、必要に応じて組織の採取やポリープの切除も行えるのが大腸内視鏡検査です。カメラを肛門から挿入し、盲腸まで観察しながら病変の有無をチェックします。
腸管をきれいにするために前処置として下剤を飲み、腸内を空にする必要がありますが、腫瘍やポリープなどの病変をダイレクトに確認できるため、確定診断や治療方針の決定に有用です。

画像検査(CT、MRIなど)
CT検査やMRI検査は、腸壁やまわりの臓器を立体的に把握するために行われ、進行度を評価するときや、転移の有無を調べるときに役立ちます。
大腸CT検査(仮想内視鏡)を行うことで、内視鏡挿入が難しい場合にもある程度の診断が可能になりますが、ポリープを見つけた際にそのまま切除することはできません。
診断後の流れ
検査によって大腸がんが疑われる場合は、病変の部位や状態をさらに詳細に調べ、病理検査などで組織の性状を確認し、その後、病期(ステージ)に応じて治療方針を決定します。
もしも早期がんと判明すれば、内視鏡治療のみで完結する可能性がありますが、進行が認められれば外科的手術や化学療法(抗がん剤治療)などを組み合わせて行います。
主な大腸がん検査
| 検査名 | 特徴 | 用途 |
|---|---|---|
| 便潜血検査 | 便中の血液を検知し、スクリーニングに用いる | 早期発見、健康診断 |
| 大腸内視鏡検査 | 直接観察し、生検や切除が可能 | 確定診断、治療方針の決定 |
| CT/MRI検査 | 体の断面画像や立体画像で臓器を評価 | 進行度・転移の有無の確認 |
| 注腸造影検査 | 造影剤で大腸の形状を見る | 内視鏡が困難な場合などの補助的検査 |
大腸がんの治療と受診のタイミング
大腸がんはステージによって治療方針が異なるため、早期に発見して適切な治療を行うことが重要です。進行するほど治療が複雑化し、患者の身体的・経済的負担も増える可能性があります。
内視鏡治療と手術の違い
早期大腸がんの場合は、内視鏡治療による局所切除が選択されることがあり、大腸内視鏡検査中に特殊な器具を用いて腫瘍やポリープを切除し、病理検査でがん細胞の浸潤範囲を確認します。
一方、腸壁の深い部分までがんが浸潤している場合やリンパ節転移が疑われる場合は、外科的に部分切除または結腸・直腸の大きな範囲を切除する手術が選択肢です。

抗がん剤治療や放射線治療
外科的手術だけでなく、進行度合いによっては抗がん剤治療(化学療法)や放射線治療を組み合わせることで、治療効果を高める場合があります。
抗がん剤治療は転移や再発を抑えるために行うことが多く、放射線治療は主に直腸がんの一部のケースで手術前後に使用されることがあります。
早期発見のメリット
大腸がんを早期に発見すると、身体への負担を最小限に抑えやすく、内視鏡治療のみで済む場合は、術後の回復も比較的早く、入院期間も短縮される可能性があります。
また、治療後の再発リスクも少なくなる傾向があり、早期発見のためには自覚症状がなくても定期的な検査を受けることが望ましいです。
受診のポイント
下痢や便秘、血便、腹痛などが2週間以上続く場合や、排便時に何らかの違和感を覚えた場合は、消化器を専門とする医療機関への受診が必要です。
忙しさや費用を理由に後回しにせず、適切な診療を受けることが症状の進行を食い止めることにつながります。
受診時に確認したいポイント
- 下痢・便秘などの症状がいつから続いているか
- 血便の色や頻度
- 体重減少や貧血の症状の有無
- 家族に大腸がんや胃がんの歴史がないか
- 過去の大腸内視鏡検査歴や結果
大腸がんを予防するために
大腸がんのリスクを少しでも下げるためには、日常の生活習慣を見直すことが大切です。確実に発生を防げるわけではありませんが、リスクを低減する可能性は十分にあります。
普段の食事と生活習慣
食物繊維を多く含む野菜や果物、海藻類を積極的に摂取し、肉類や脂質の過剰摂取を控えることが推奨されます。
また、適度な運動習慣を継続し、肥満にならないよう体重管理を行うことも大腸がんの発生リスクを下げるために重要で、飲酒や喫煙はできるだけ控えるか、量を減らしてください。
おすすめしたい食事
| 食材 | 理由 |
|---|---|
| 野菜・果物 | 食物繊維やビタミン・ミネラルが豊富 |
| 海藻類・きのこ | 水溶性食物繊維が多く、腸の働きを整えやすい |
| 大豆製品 | 良質なたんぱく質とイソフラボンを含む |
| 青魚 | EPAやDHAが炎症を抑える作用がある可能性 |
| 乳酸菌食品 | 腸内環境を良好に保つ働きが期待される |
定期的ながん検診
国や自治体、医療機関では大腸がん検診として便潜血検査などを実施しています。40歳以上になると受診機会が増えますが、自覚症状の有無にかかわらず、定期検診を活用してください。
異常が見つかった場合は内視鏡検査で確認できるので、早期発見に直結します。
受診しやすい医療機関を選ぶ
大腸がんは、症状の進行度合いや患者さんの状態によって治療の流れが変わります。内視鏡検査や手術が必要になる場合があるため、消化器内科や内視鏡検査に対応している医療機関を選ぶと、検査や受診がスムーズに進みやすいです。
医療機関の診療科や設備を事前に確認し、自分が通いやすい場所と時間帯を考えると通院が続けやすくなります。
早期発見・早期治療の重要性
大腸がんは、他のがん種(胃がん・肺がんなど)と同様に、早期に対応すればするほど予後の改善が期待できるので、大腸がん検診を定期的に受けたり、少しでも気になる症状があれば医師に相談することが大切です。
万が一がんであっても、初期の段階で治療を開始できれば身体的負担を最小限に抑えることができるケースも多くなっています。
生活習慣を見直
- 野菜・果物を1日350g以上摂る
- 適度な運動(ウォーキングなど)を週に数回取り入れる
- 飲酒量を控え、禁煙を検討する
- 定期的に健康診断や内視鏡検査を受ける
まとめと受診のすすめ
大腸がんは、下痢や便秘、血便などの初期症状を見逃してしまうと進行し、治療に多大な労力が必要になります。大腸がんと診断されても早期であれば内視鏡切除で済む可能性が高いため、定期検診の受診が重要です。
生活習慣を整え、異変に気づいたら早めに医療機関へ相談してください。
大腸がんについて振り返る
大腸がんは大腸の粘膜から発生する悪性腫瘍で、年齢や食事内容、家族歴など複数のリスク因子が絡み合うことで発症します。
下痢や便秘が続いたり、便に血液が混じるなどの症状があれば注意が必要です。ただし、発生しても初期症状が乏しい場合があり、健康診断や定期検診での便潜血検査や大腸内視鏡検査が早期発見に有効になります。
気になる症状を感じたら
少しでも異常を感じる場合は、クリニックや病院を受診し検査を受けることが望ましく、便潜血検査で陽性が出ても痔などが原因の場合もありますが、「痔だから大丈夫」と決めつけるのは危険です。
血便が続く・腹痛や下痢・便秘が長引く場合は、他の消化器疾患や大腸がんの可能性も考慮し、専門医の診断を受けてください。
クリニックで受けられるサポート
多くの医療機関では、胃カメラや大腸カメラなどの消化器内視鏡検査が受けられ、また、内科や外科の専門医が在籍しているところでは、診断から治療に至るまでの流れをスムーズに行う体制があります。
必要に応じて病理検査、CT検査、MRI検査などの追加検査を紹介してくれる場合もありますので、疑問や不安があれば積極的に相談してください。
大腸がん治療の流れ
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| スクリーニング | 便潜血検査などで異常を見つける |
| 精密検査 | 大腸内視鏡検査やCT検査などで確定診断 |
| 治療方針 | 病期に応じて内視鏡治療・手術・化学療法を選択 |
| フォローアップ | 定期的な内視鏡検査や画像検査で再発有無を確認 |
これからの健康管理
がんの予防や早期発見には、日常の中での体調の変化に気づくことと定期的な検診が欠かせません。便の色や形がいつもと違う、腹痛や貧血を感じるなど、自分自身の身体のサインを無視せずに向き合う姿勢が大切です。
大腸だけでなく、胃がんや食道がんなど他の消化器がんにも目を向けながら、健康診断を活用して全身の状態を知るように心がけましょう。
定期受診
- 1年に1回は健康診断を受ける
- 便潜血検査を活用し、必要があれば大腸内視鏡検査を行う
- 症状がなくても定期的に医療機関を受診する
- 食事や運動など生活習慣を長期的に改善する
- 家族歴や持病がある場合は主治医と相談し検査頻度を調整する
健康管理
| チェック項目 | 具体的な取り組み |
|---|---|
| 食事 | 野菜・果物を十分に取り、脂質を控えめにする |
| 運動 | ウォーキングや軽い筋トレを定期的に行う |
| アルコール・タバコ | 過度の飲酒をやめる、禁煙または減煙を検討する |
| 検診・健康診断 | 定期的な便潜血検査や内視鏡検査を受ける |
| ストレス管理・睡眠 | ストレスを発散し、十分な睡眠を確保する |
次に読むことをお勧めする記事
【大腸がん症状を知る 兆候から治療まで】
大腸がんの初期症状について理解が深まったところで、さらに進行期の症状や治療選択肢についても知っておくと、より全体像が見えてきます。症状から治療まで包括的に学べる内容です。
【大腸ポリープの症状と早期発見のために知っておきたいこと】
大腸がんについて理解が深まると、関連する大腸ポリープについても知りたくなる方が多いようです。がん化の前段階であるポリープとの関係性が見えてくる内容です。
参考文献
Freeman HJ. Early stage colon cancer. World journal of gastroenterology: WJG. 2013 Dec 12;19(46):8468.
Cappell MS. Pathophysiology, clinical presentation, and management of colon cancer. Gastroenterology Clinics of North America. 2008 Mar 1;37(1):1-24.
Ahmed M. Colon cancer: a clinician’s perspective in 2019. Gastroenterology research. 2020 Feb;13(1):1.
McDermott FT, Hughes ES, Pihl E, Milne BJ, Price AB. Prognosis in relation to symptom duration in colon cancer. British journal of surgery. 1981 Dec;68(12):846-9.
Holtedahl K, Borgquist L, Donker GA, Buntinx F, Weller D, Campbell C, Månsson J, Hammersley V, Braaten T, Parajuli R. Symptoms and signs of colorectal cancer, with differences between proximal and distal colon cancer: a prospective cohort study of diagnostic accuracy in primary care. BMC family practice. 2021 Dec;22:1-3.
Duineveld LA, van Asselt KM, Bemelman WA, Smits AB, Tanis PJ, van Weert HC, Wind J. Symptomatic and asymptomatic colon cancer recurrence: a multicenter cohort study. The Annals of Family Medicine. 2016 May 1;14(3):215-20.
Jullumstrø E, Lydersen S, Møller B, Dahl O, Edna TH. Duration of symptoms, stage at diagnosis and relative survival in colon and rectal cancer. European Journal of Cancer. 2009 Sep 1;45(13):2383-90.
Alsayed MA, Surrati AM, Altaifi JA, Alharbi AH, Alfouti RO, Alremaithi SM. Public Awareness of Colon Cancer Symptoms, Risk Factor, and Screening at Madinah-KSA. International Journal Of Pharmaceutical Research & Allied Sciences. 2019 Jan 1;8(1).
Benson AB, Arnoletti JP, Bekaii-Saab T, Chan E, Chen YJ, Choti MA, Cooper HS, Dilawari RA, Engstrom PF, Enzinger PC, Fleshman JW. Colon cancer. Journal of the National Comprehensive Cancer Network. 2011 Nov 1;9(11):1238-90.
Labianca R, Nordlinger B, Beretta GD, Mosconi S, Mandalà M, Cervantes A, Arnold D, ESMO Guidelines Working Group. Early colon cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Annals of oncology. 2013 Oct 1;24:vi64-72.