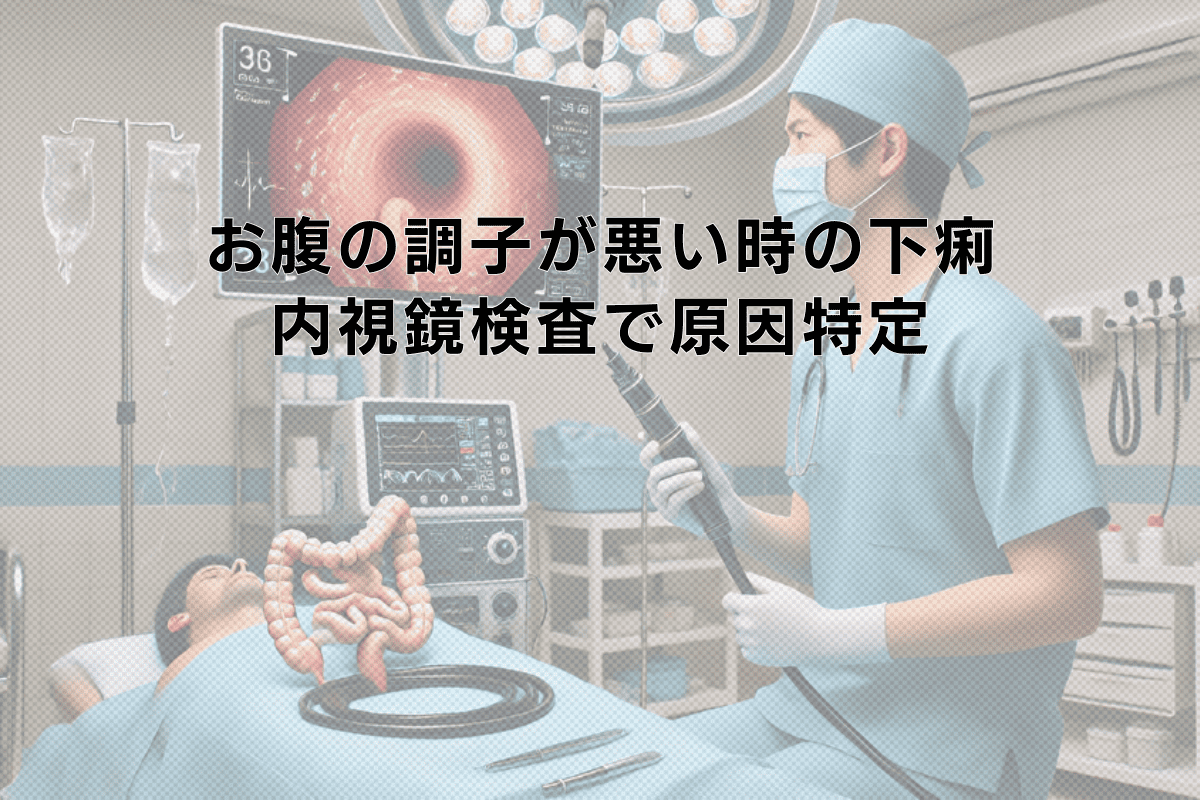お腹の調子が悪く、下痢が続くのはつらいものです。この記事では、下痢の原因として考えられることや、医療機関での検査、特に内視鏡検査について詳しく解説します。
ご自身の症状と照らし合わせながら、適切な対処法を見つけるための一助となれば幸いです。つらい症状でお困りの方は、この記事を参考に、専門医への相談を検討して下さい。
お腹の調子が悪い時の下痢 考えられる原因
お腹の調子が悪く下痢が起こる時、その背景には様々な要因が潜んでいます。日常生活における些細な変化から、特定の病気が原因となることまで、幅広く考える必要があります。
食生活の乱れやストレス
現代社会において、食生活の乱れや精神的なストレスは、多くの人が抱える問題で、消化器系の機能に直接的な影響を与え、下痢を起こすことがあります。
脂質の多い食事や香辛料の過剰な摂取は、消化管を刺激し、腸の動きを活発にしすぎることで下痢を誘発し、また、不規則な食事時間や早食いも消化不良を招き、下痢の原因となり得ます。
精神的なストレスは自律神経のバランスを崩し、腸の蠕動運動に異常をきたすことで、下痢や便秘を繰り返す過敏性腸症候群(IBS)の一因です。
下痢を起こしやすい食習慣
| 要因 | 具体例 | 影響 |
|---|---|---|
| 脂質の多い食事 | 揚げ物、肉類の脂身 | 消化に時間がかかり、腸を刺激 |
| 刺激物 | 香辛料、カフェイン、アルコール | 腸の蠕動運動を亢進 |
| 冷たい飲食物 | アイスクリーム、冷たい飲み物 | 腸を冷やし、機能を低下 |
ウイルスや細菌による感染症
ウイルスや細菌への感染も、急性の下痢を起こす主な原因の一つで、ノロウイルスやロタウイルスといったウイルス、サルモネラ菌やカンピロバクターといった細菌が代表的です。
病原体は、汚染された食品や水を介して、あるいは感染者との接触を通じて体内に侵入します。
体内に侵入した病原体は腸管内で増殖し、毒素を産生するなどして腸粘膜に炎症を起こし、下痢や嘔吐、腹痛、発熱といった症状が現れます。特に抵抗力の弱い乳幼児や高齢者は重症化しやすいため、注意が必要です。
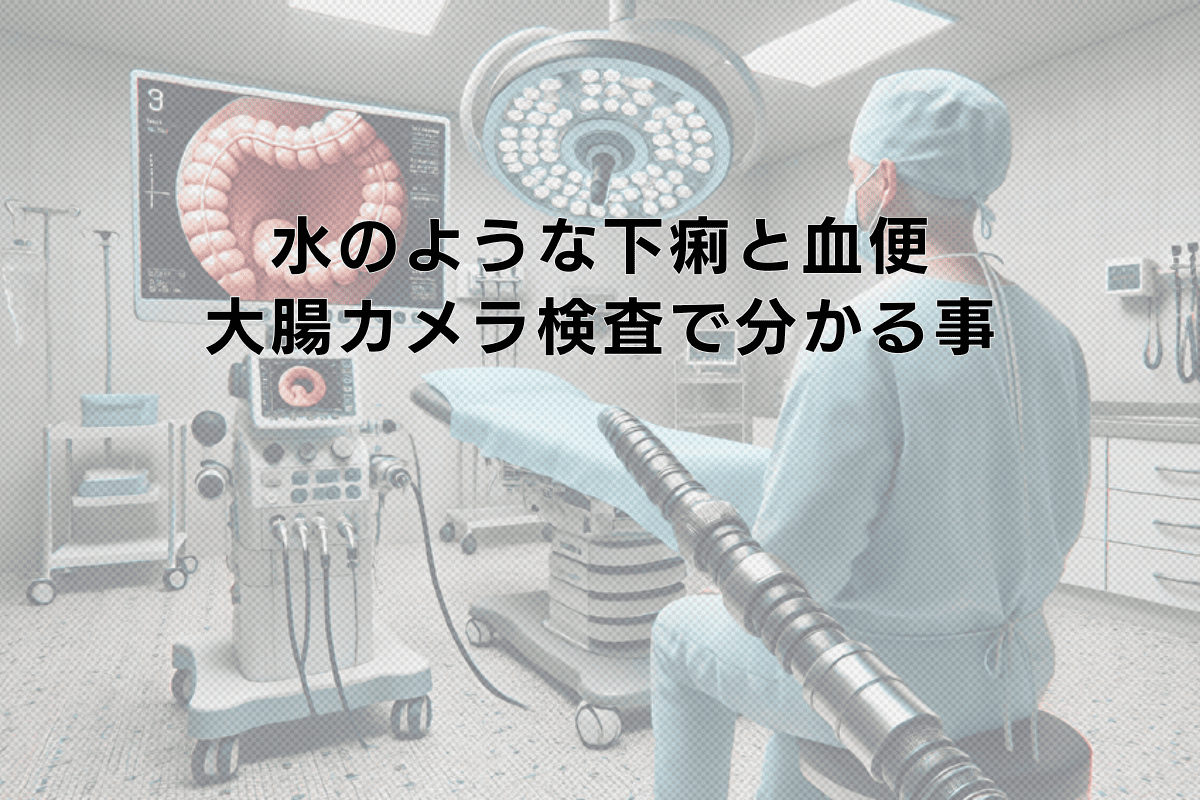
薬の副作用
服用している薬の副作用として下痢が現れることもあり、特に抗生物質は、腸内の悪玉菌だけでなく善玉菌まで殺してしまうため、腸内細菌叢のバランスが崩れ、下痢を起こすことがあり、薬剤関連性腸炎と呼ばれます。
また、一部の痛み止め(非ステロイド性抗炎症薬:NSAIDs)、マグネシウムを含む制酸薬、化学療法薬なども、副作用として下痢を起こすことが知られています。
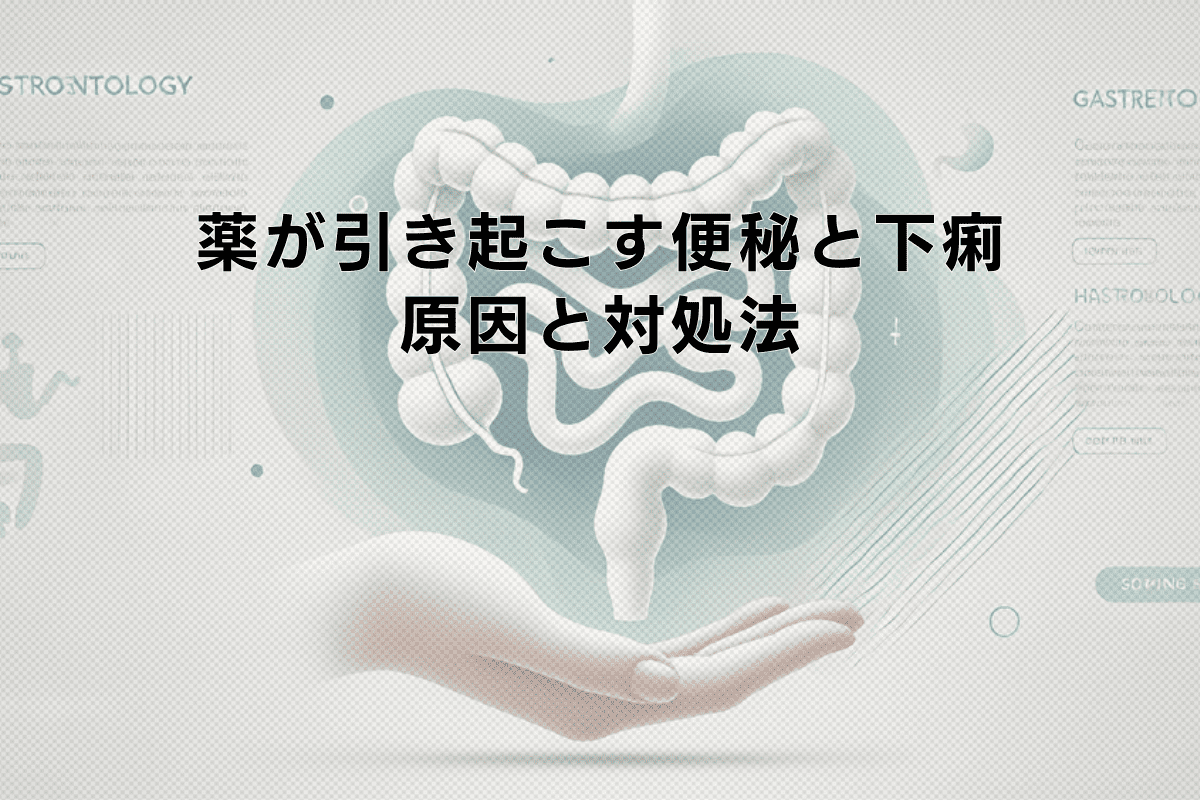
特定の病気の可能性
慢性的な下痢や、急な下痢であっても他の症状を伴う場合は、何らかの病気が背景にある可能性を考える必要があります。
過敏性腸症候群(IBS)、クローン病や潰瘍性大腸炎といった炎症性腸疾患(IBD)、大腸がんや大腸ポリープ、吸収不良症候群、甲状腺機能亢進症などが挙げられます。
下痢が続く場合に考えられる主な病気
一時的な下痢であれば自然に治まることも多いですが、長期間続く下痢や、他の症状を伴う下痢の場合は、背景に何らかの病気が隠れている可能性があります。ここでは、下痢が続く場合に考えられる代表的な病気について解説します。
過敏性腸症候群(IBS)
過敏性腸症候群(Irritable Bowel Syndrome, IBS)は、大腸や小腸に明らかな炎症や潰瘍などの器質的な異常が見られないにもかかわらず、腹痛や腹部不快感、そして下痢や便秘などの便通異常が慢性的に続く病気です。
ストレスや生活習慣の乱れ、腸内細菌叢の変化などが関与していて、下痢型、便秘型、混合型、分類不能型などのタイプがあり、下痢型では、特に緊張や不安を感じた時などに急な便意と共に水様便や泥状便が出ます。
IBSの主な症状タイプ
| タイプ | 主な便通異常 | 特徴的な症状 |
|---|---|---|
| 下痢型 | 頻回の下痢、水様便 | ストレス時に悪化しやすい |
| 便秘型 | 硬い便、排便困難 | 腹部膨満感を伴うことあり |
| 混合型 | 下痢と便秘を繰り返す | 症状が変動しやすい |
炎症性腸疾患(IBD)
炎症性腸疾患(Inflammatory Bowel Disease, IBD)は、消化管に原因不明の慢性的な炎症を引き起こす病気の総称で、主にクローン病と潰瘍性大腸炎の二つがあります。
遺伝的な要因や免疫系の異常、腸内細菌、食生活などが複雑に関与して発症し、主な症状は、下痢、血便、腹痛、体重減少、発熱などで、症状が良くなったり(寛解期)、悪くなったり(活動期)を繰り返すことが特徴です。
大腸がん・大腸ポリープ
大腸がんや大腸ポリープも、下痢の原因となることがあります。
進行した大腸がんでは、腫瘍が腸管を狭窄させたり、腸の動きに影響を与えたりすることで、便通異常(下痢や便秘、あるいはその繰り返し)、血便、腹痛、体重減少などの症状が現れることがあります。
大腸ポリープの中には、がん化する可能性のあるもの(腺腫性ポリープなど)もあり、早期の大腸がんは自覚症状が乏しいことが多いため、定期的な検診(便潜血検査や内視鏡検査)が早期発見には非常に重要です。
その他の消化器疾患
上記以外にも、下痢を引き起こす消化器疾患は様々です。
セリアック病や乳糖不耐症などの吸収不良症候群では、特定の栄養素をうまく吸収できないために下痢が起こり、また、虚血性大腸炎は、大腸への血流が悪くなることで炎症が発生し、突然の腹痛や下痢、血便が見られます。
憩室炎は、大腸の壁にできた憩室というポケット状のくぼみに炎症が起こる病気で、腹痛や発熱、下痢などを伴うことがあります。
医療機関を受診する目安
下痢はありふれた症状ですが、中には注意が必要なケースや、専門的な治療を要する病気が隠れていることもあります。
自己判断で様子を見たり、市販薬だけで対処したりしていると、原因の特定が遅れたり、症状が悪化することがあるので医療機関を受診することが大切です。
こんな症状は要注意
単なる下痢だけでなく、以下のような症状を伴う場合は、医療機関を受診してください。
医療機関受診を考慮すべき症状
| 症状 | 考えられる背景 | 対応 |
|---|---|---|
| 高熱(38℃以上) | 重度の感染症、炎症 | 速やかな受診 |
| 激しい腹痛 | 腸閉塞、穿孔、重度の炎症 | 緊急受診も考慮 |
| 血便・粘血便 | 大腸がん、炎症性腸疾患、感染症 | 専門医の診察 |
| 体重減少(意図しない) | 悪性腫瘍、吸収不良、慢性炎症 | 精密検査の必要性 |
| 嘔吐が続く | 脱水、電解質異常のリスク | 水分補給と受診 |
下痢が続く期間
下痢が続く期間も、受診の目安です。
一般的に、急性の下痢は数日から1週間程度で改善することが多いですが、2週間以上続く場合は「遷延性下痢」、4週間以上続く場合は「慢性下痢」とされ、何らかの基礎疾患が背景にある可能性が高まります。
慢性的な下痢は、過敏性腸症候群や炎症性腸疾患、吸収不良症候群、あるいはまれに大腸がんなどが原因となっていることもあります。
市販の下痢止めを漫然と使用し続けるのではなく、長引く場合は原因を特定するために医療機関を受診し、検査を受けることが重要です。
脱水症状のサイン
下痢が続くと、体内の水分や電解質が大量に失われ、脱水症状を起こすことがあり、特に乳幼児や高齢者は脱水になりやすいため注意が必要です。
脱水症状のサインとしては、口の渇き、尿量の減少(色が濃くなる)、めまい、立ちくらみ、頭痛、倦怠感、皮膚の弾力性が失われたり、目がくぼんだりすることもあります。
重度の脱水は意識障害やショック状態に至ることもあり、命に関わる危険性もあります。経口補水液などで水分と電解質を補給することが基本ですが、症状が強い場合や改善しない場合は、点滴による水分補給が必要です。
脱水症状の主なサイン
- 強い口渇感
- 尿量の著しい減少、濃い色の尿
- めまい、ふらつき
- 皮膚の乾燥、弾力性の低下
- 頻脈、血圧低下(重度の場合)
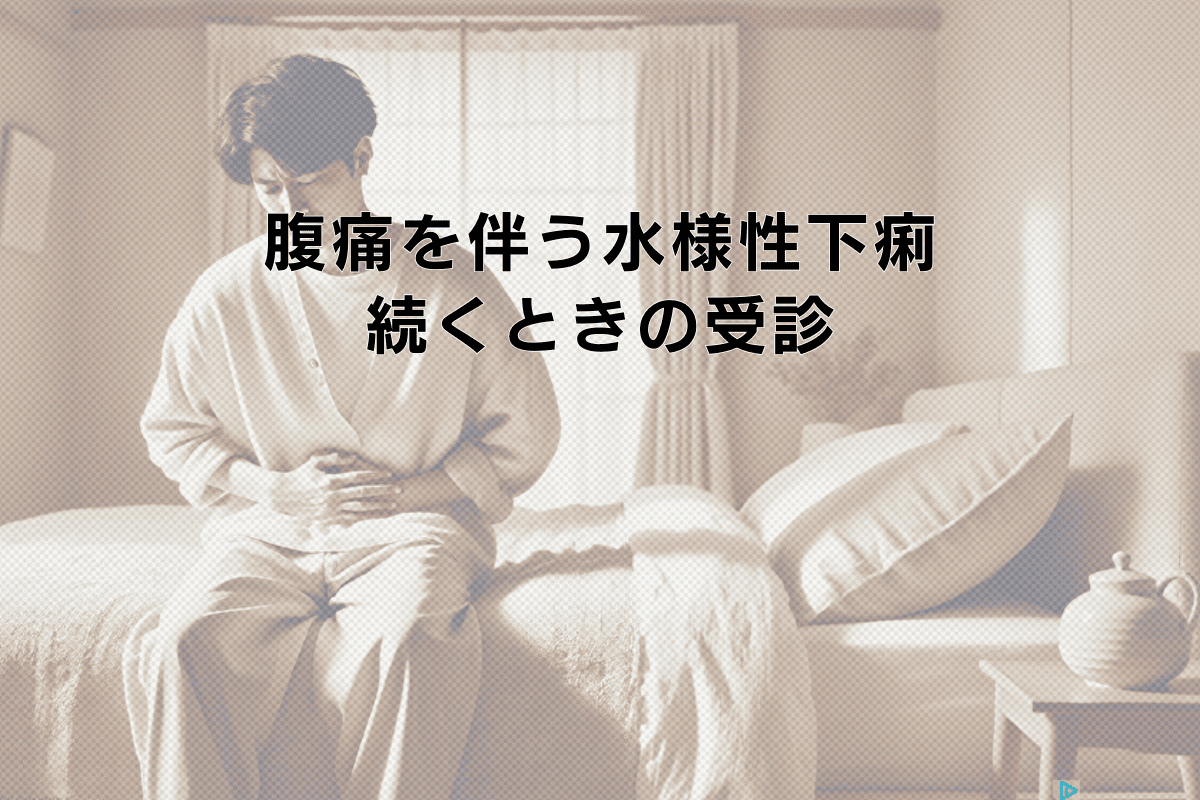
医療機関で行う検査
下痢の原因を特定し、適切な治療法を選択するためには、医療機関での検査が重要です。
問診と診察
まず、医師による詳しい問診が行われます。
いつから下痢が始まったか、下痢の回数や性状、腹痛の有無や程度、発熱、嘔吐、体重減少などの随伴症状、食事内容、最近の海外渡航歴、服用中の薬、既往歴、家族歴など、診断の手がかりとなる情報を詳細に聞き取ります。
その後、腹部の聴診や触診などの身体診察を行い、お腹の状態を確認します。
血液検査・便検査
血液検査では、炎症の程度(白血球数、CRPなど)、貧血の有無、栄養状態(アルブミンなど)、肝機能、腎機能、電解質バランスなどを調べ、全身状態の把握や、特定の病気(例えば炎症性腸疾患など)の活動性の評価、脱水の程度の確認などができます。
便検査では、便中の血液の有無(便潜血検査)、細菌やウイルスの感染の有無(便培養検査、ウイルス抗原検査など)、寄生虫の有無などを調べます。
主な血液検査項目と目的
| 検査項目 | 主な目的 | 異常値が示唆すること |
|---|---|---|
| 白血球数 | 感染や炎症の有無 | 高値:感染症、炎症 |
| CRP | 炎症の程度 | 高値:炎症性疾患、感染症 |
| ヘモグロビン | 貧血の有無 | 低値:消化管出血、栄養不良 |

画像検査(レントゲン・超音波)
腹部レントゲン検査(腹部単純X線検査)では、腸管内のガスや便の分布、腸閉塞の有無、異常な石灰化などを大まかに確認できます。緊急性の高い状態(腸閉塞や消化管穿孔など)が疑われる場合に行われることがあります。
腹部超音波検査(腹部エコー検査)は、超音波を用いて腹腔内の臓器(肝臓、胆嚢、膵臓、腎臓、脾臓など)や腸管の状態をリアルタイムに観察する検査で、腸管壁の肥厚や腹水の有無、腫瘍性の病変などを評価することが可能です。
画像検査は、内視鏡検査ほど詳細な情報は得られませんが、スクリーニングや他の臓器の異常を確認するために有用です。
内視鏡検査の必要性
問診、診察、血液検査、便検査、画像検査などを行っても原因が特定できない場合や、炎症性腸疾患、大腸がん、大腸ポリープなどが強く疑われる場合には、内視鏡検査(胃カメラ・大腸カメラ)の実施を検討します。
内視鏡検査は、消化管の内部を直接カメラで観察し、粘膜の状態を詳細に評価できるため、診断精度が非常に高い検査です。
また、疑わしい病変が見つかった場合には、その場で組織の一部を採取(生検)して病理検査を行うことで、確定診断を得られます。
さらに、ポリープが見つかれば切除することも可能で、医師が内視鏡検査の必要性を判断した場合は、目的や流れについて十分な説明を受け、検査を受けることを検討しましょう。
内視鏡検査(胃カメラ・大腸カメラ)とは
内視鏡検査は、先端に小型カメラが付いた細長い管(スコープ)を体内に挿入し、食道、胃、十二指腸、あるいは大腸の内部を直接観察する検査です。
胃カメラ(上部消化管内視鏡検査)
胃カメラ検査は、正式には上部消化管内視鏡検査と言い、口または鼻からスコープを挿入し、食道、胃、十二指腸の粘膜を観察し、逆流性食道炎、胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃がん、食道がんなどの病気の発見に役立ちます。
また、ピロリ菌感染の診断や、ポリープや早期がんの切除も行うことができ、検査時間は通常10分から15分程度です。検査中は、鎮静剤を使用することで、苦痛を軽減することもできます。
胃カメラで観察する部位
- 食道
- 胃
- 十二指腸球部・下行脚
大腸カメラ(下部消化管内視鏡検査)
大腸カメラ検査は、正式には下部消化管内視鏡検査と言い、肛門からスコープを挿入し、直腸から盲腸までの大腸全体の粘膜を観察します。
大腸がん、大腸ポリープ、炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病)、大腸憩室症、虚血性大腸炎などの診断に有用です。
ポリープが見つかった場合には、その場で切除でき、検査時間は、観察のみであれば20分から30分程度ですが、ポリープ切除などを行う場合はもう少し時間がかかります。
検査前には、腸管内をきれいにするために下剤を服用する必要があり、胃カメラと同様に、鎮静剤を使用して楽に検査を受けられます。
大腸カメラ検査の準備
| 準備段階 | 内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 検査前日 | 消化の良い食事、指定された下剤の服用(一部) | 腸管内容物を減らす |
| 検査当日(朝) | 多量の下剤(洗腸剤)を服用 | 腸管内を完全にきれいにする |
| 検査直前 | 鎮静剤・鎮痙剤の使用(希望や必要に応じて) | 苦痛の軽減、腸の動きを抑制 |
検査の目的とわかること
内視鏡検査の主な目的は、消化管粘膜を直接観察することにより、炎症、潰瘍、ポリープ、がんなどの病変を早期に発見し、正確に診断することです。
肉眼的な観察に加えて、色素を散布して微細な病変を強調したり(色素内視鏡)、特殊な光を用いて血管や粘膜表面の構造を詳細に観察したり(NBIなどの画像強調内視鏡)することもできます。
病変の良悪性の鑑別や、がんの深達度診断などにも役立ち、最も重要なのは、疑わしい部分から組織を採取(生検)し、病理検査で確定診断を得られる点です。
鎮静剤の使用について
内視鏡検査に対して、「苦しい」「つらい」といったイメージをお持ちの方も少なくありません。しかし、近年では鎮静剤(静脈麻酔)を使用することで、眠っているようなリラックスした状態で検査を受けることが可能です。
鎮静剤を使用すると、検査中の不快感や苦痛が大幅に軽減されるため、より精密な検査を行うことができ、嘔吐反射が強い方や、以前の検査でつらい思いをされた方、不安感が強い方などには、鎮静剤の使用を推奨します。
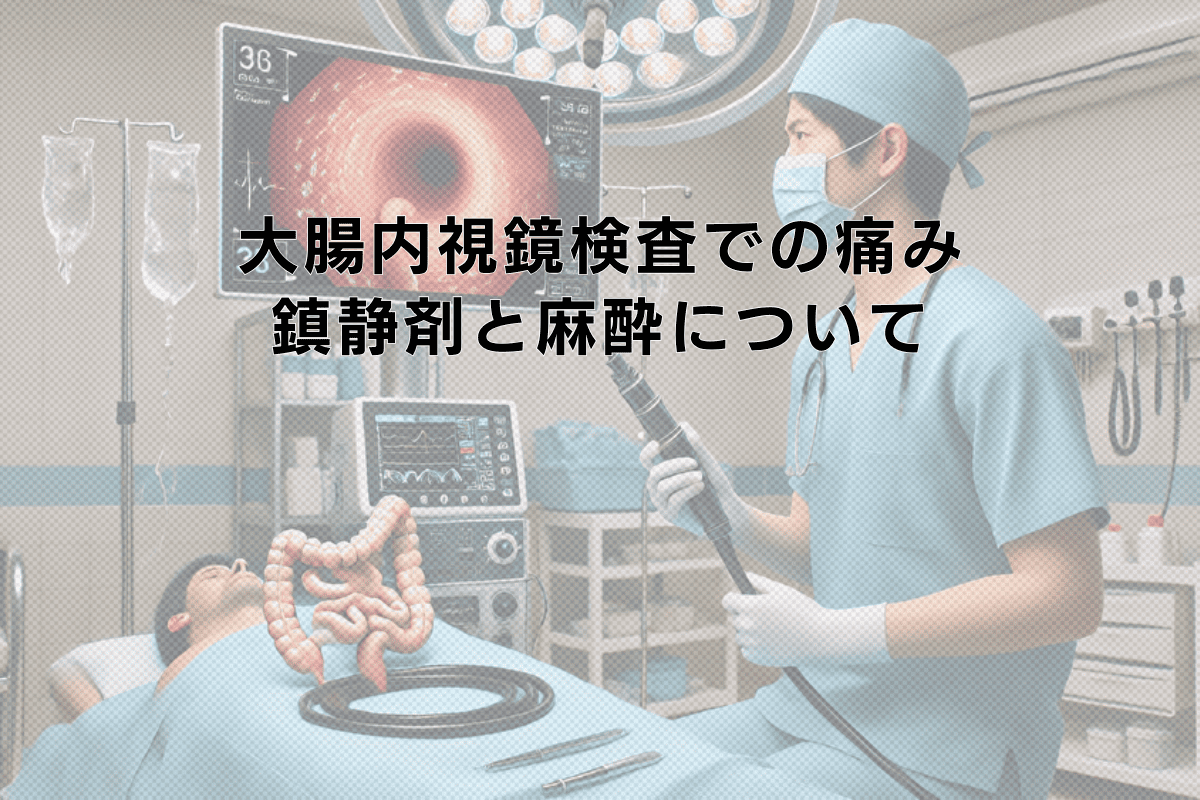
内視鏡検査でわかること
内視鏡検査は、消化管内部の情報を直接的に得るための強力なツールです。医師はモニターに映し出される鮮明な画像を通じて、粘膜の微細な変化も見逃さずに捉えられます。
粘膜の状態を直接観察
内視鏡検査の最大の利点は、消化管の粘膜をリアルタイムで直接観察できることです。
炎症による発赤や腫脹、びらん(ただれ)、潰瘍の深さや形状、出血の有無、ポリープの大きさや形、色調、表面構造、そしてがんを疑うような隆起や陥凹、不整な粘膜パターンなどを詳細に評価します。
レントゲン検査や超音波検査では捉えきれない微細な病変や、平坦な病変の発見も可能になり、早期の胃がんや大腸がんは、自覚症状がない段階でも、内視鏡検査によって発見されることがあります。
観察される主な粘膜所見
| 所見 | 特徴 | 関連する可能性のある疾患 |
|---|---|---|
| 発赤・腫脹 | 粘膜が赤く腫れている状態 | 胃炎、食道炎、腸炎 |
| びらん・潰瘍 | 粘膜の浅いまたは深い欠損 | 胃潰瘍、十二指腸潰瘍、炎症性腸疾患 |
| ポリープ | 粘膜の隆起性病変 | 胃ポリープ、大腸ポリープ(腺腫など) |
| 腫瘍性病変 | 不整な隆起や陥凹、易出血性 | 食道がん、胃がん、大腸がん |
ポリープやがんの早期発見
特に大腸内視鏡検査は、大腸がんやその前段階である大腸ポリープの発見に非常に有効です。
多くの大腸がんは、良性のポリープ(主に腺腫)から発生するので、内視鏡検査で腺腫性のポリープを発見し、切除することで、将来のがん化を予防できます。
また、胃内視鏡検査では、早期胃がんの発見が可能で、早期がんであれば、内視鏡的に切除できる場合も多く、体への負担も少なく治療できます。
自覚症状がない段階でも、定期的な内視鏡検査を受けることで、病気を早期に発見し対応をとることが重要です。
組織検査(生検)による確定診断
内視鏡検査中に疑わしい病変が見つかった場合、鉗子を使って組織の一部を採取し、これを生検またはバイオプシーと言います。
採取した組織は、病理医が顕微鏡で詳しく観察し、良性か悪性か、炎症の種類や程度などを診断し(病理組織診断)、理診断は、がんの確定診断や炎症性腸疾患の診断において、非常に重要な情報です。
炎症の程度や範囲の把握
炎症性腸疾患(クローン病や潰瘍性大腸炎)の診断や治療効果の判定においても、内視鏡検査は中心的な役割を果たします。
炎症が消化管のどの範囲に、どの程度の強さで起きているのかを直接観察することで、病気の活動性を評価し、治療方針を決定し、また、治療によって炎症がどの程度改善したかを確認するためにも、定期的な内視鏡検査が行われます。
潰瘍性大腸炎では、特徴的な粘膜のびまん性の炎症や出血、偽ポリポーシスなどが観察され、クローン病では縦走潰瘍や敷石像、非連続性の病変などが特徴的な所見です。
内視鏡検査の準備と流れ
内視鏡検査を安全かつ正確に行うためには、事前の準備がとても大切で、検査当日の流れや検査後の注意点についても理解しておくことで、安心して検査に臨むことができます。

検査前の食事制限
胃カメラ検査の場合、通常、検査前日の夕食は消化の良いものを午後9時頃までに済ませ、その後は絶食となります。水分(水やお茶など透明なもの)は検査当日の数時間前まで摂取可能な場合がありますが、医療機関の指示に従ってください。
大腸カメラ検査の場合は、より厳格な食事制限が必要で、検査の2~3日前から、きのこ類、海藻類、種実類、繊維の多い野菜など、消化しにくい食品を避けるように指示されます。
検査前日は、専用の検査食を食べるか、消化の良いもの(おかゆ、うどん、白身魚など)を少量摂取し、早めの時間に夕食を済ませ、その後は絶食です。
大腸カメラ検査前の食事の注意点
| 避けるべき食品 | 摂取しても良い食品(例) | 理由 |
|---|---|---|
| 繊維の多い野菜(ごぼう、きのこ類) | 白米、うどん、豆腐 | 腸内に残渣が残りにくい |
| 種のある果物(キウイ、いちご) | バナナ、りんご(皮なし) | 種が観察の妨げになる |
| 海藻類、こんにゃく | 鶏むね肉(皮なし)、白身魚 | 消化に時間がかかるため |
下剤の服用(大腸カメラの場合)
大腸カメラ検査を正確に行うためには、大腸の中を空にしてきれいにする必要があり、検査前日または当日の朝から、多量の下剤(腸管洗浄剤)を服用します。
下剤の種類や服用方法は医療機関によって異なりますが、一般的には約1~2リットルの液体を数時間かけて飲むと、数回から十数回の排便があり、最終的には便が水様透明になれば準備完了です。
検査当日の流れ
検査当日は、指定された時間に来院し、受付後、更衣室で検査着に着替えます。胃カメラの場合は、喉の麻酔(スプレーやゼリー)を行い、鎮静剤を使用する場合は、点滴の準備をします。
検査室に入り、検査台に横になると、医師や看護師の指示に従って検査が始まり、胃カメラは通常10~15分、大腸カメラは20~30分程度(ポリープ切除などがあれば延長)です。
鎮静剤を使用した場合は、検査後1~2時間程度、リカバリールームで安静にしてから帰宅となります。
検査後の注意点
胃カメラ検査後、喉の麻酔が切れるまでは飲食を控えます(通常1時間程度)。鎮静剤を使用しなかった場合は、すぐに日常生活に戻れます。
大腸カメラ検査後も、特に問題がなければ飲食は可能ですが、最初は消化の良いものから摂るようにしましょう。ポリープを切除した場合は、数日間はアルコールや刺激物の摂取、激しい運動、長時間の入浴などを避ける必要があります。
また、血便や持続する腹痛など、異常を感じた場合は速やかに医療機関に連絡してください。
よくある質問
内視鏡検査に関して、患者さんから寄せられることの多い質問とその回答をまとめました。検査に対する不安や疑問を少しでも解消し、安心して検査を受けていただくための一助となれば幸いです。
- 内視鏡検査は痛いですか
-
痛みの感じ方には個人差がありますが、医療機関では様々な工夫をして苦痛を軽減するように努めていて、胃カメラの場合、喉の麻酔をしっかり行うことで嘔吐反射を抑えます。
また、鼻から挿入する経鼻内視鏡は、口からの挿入に比べて吐き気が少ないと言われています。
大腸カメラの場合も、スコープの挿入技術や、お腹の張り感を軽減するための炭酸ガス送気などにより、苦痛を和らげることができ、最も効果的なのは鎮静剤の使用です。
- 検査時間はどのくらいですか
-
一般的な目安としては、胃カメラ(上部消化管内視鏡検査)の場合、観察のみであれば10分から15分程度です。ピロリ菌の検査や生検(組織検査)を行う場合でも、数分程度の追加で済みます。
大腸カメラ(下部消化管内視鏡検査)の場合、大腸全体の観察のみであれば20分から30分程度で、ポリープが見つかり、その場で切除(ポリペクトミー)を行う場合は、さらに10分から30分程度時間がかかります。
- 検査後すぐに食事はできますか
-
胃カメラ検査の場合、喉の麻酔が切れるまで(通常、検査後1時間程度)は飲食を控えていただき、麻酔が切れたことを確認してから、まずは少量の水分を摂取し、むせたりしなければ食事も可能です。
大腸カメラ検査の場合、鎮静剤を使用していなければ、検査終了後すぐに飲食できますが、お腹の張り感が残っていることもあるため、最初は消化の良いものから摂ることをお勧めします。
ポリープを切除した場合は、出血予防のために、当日は消化の良い食事にし、アルコールは控えるように指示されることが一般的で、数日間は刺激物や脂っこいものも避けた方が良いでしょう。
次に読むことをお勧めする記事
【内視鏡検査で確認する下痢の定義と重症度の判定基準】
“下痢の種類によって検査や対応は違う?”と思った方へ。浸透圧性・分泌性などの分類から、感染症やIBDとの鑑別、内視鏡が必要になる目安まで、整理して理解できます。
【内視鏡検査費用の目安と流れ 胃と大腸のチェック方法】
下痢の原因や検査について理解が深まったところで、内視鏡検査の費用や具体的な流れについても知っておくと、より実践的な理解ができます。
参考文献
Cai J, Yuan Z, Zhang S. Abdominal pain, diarrhea, constipation-which symptom is more indispensable to have a colonoscopy?. International Journal of Clinical and Experimental Pathology. 2015 Jan 1;8(1):938.
Semrad CE. Approach to the patient with diarrhea and malabsorption. Goldman’s cecil medicine. 2012 May 8:895.
Juckett G, Trivedi R. Evaluation of chronic diarrhea. American family physician. 2011 Nov 15;84(10):1119-26.
Rangan V, Singh P, Ballou S, Hassan R, Yu V, Katon J, Nee J, Iturrino J, Lembo A. Improvement in constipation and diarrhea is associated with improved abdominal pain in patients with functional bowel disorders. Neurogastroenterology & Motility. 2022 Apr;34(4):e14253.
Barr W, Smith A. Acute diarrhea in adults. American family physician. 2014 Feb 1;89(3):180-9.
Corinaldesi R, Stanghellini V, Barbara G, Tomassetti P, De Giorgio R. Clinical approach to diarrhea. Internal and emergency medicine. 2012 Oct;7:255-62.
Meisenheimer ES, Epstein C, Thiel D. Acute diarrhea in adults. American Family Physician. 2022 Jul;106(1):72-80.
Fry LC, Carey EJ, Shiff AD, Heigh RI, Sharma VK, Post JK, Hentz JG, Fleischer DE, Leighton JA. The yield of capsule endoscopy in patients with abdominal pain or diarrhea. Endoscopy. 2006 May;38(05):498-502.
Schiller LR. Chronic diarrhea. GI/Liver Secrets Plus E-Book: GI/Liver Secrets Plus E-Book. 2014 Nov 17:414.
Talley NJ, Dennis EH, Schettler-Duncan AV, Lacy BE, Olden KW, Crowell MD. Overlapping upper and lower gastrointestinal symptoms in irritable bowel syndrome patients with constipation or diarrhea. Official journal of the American College of Gastroenterology| ACG. 2003 Nov 1;98(11):2454-9.