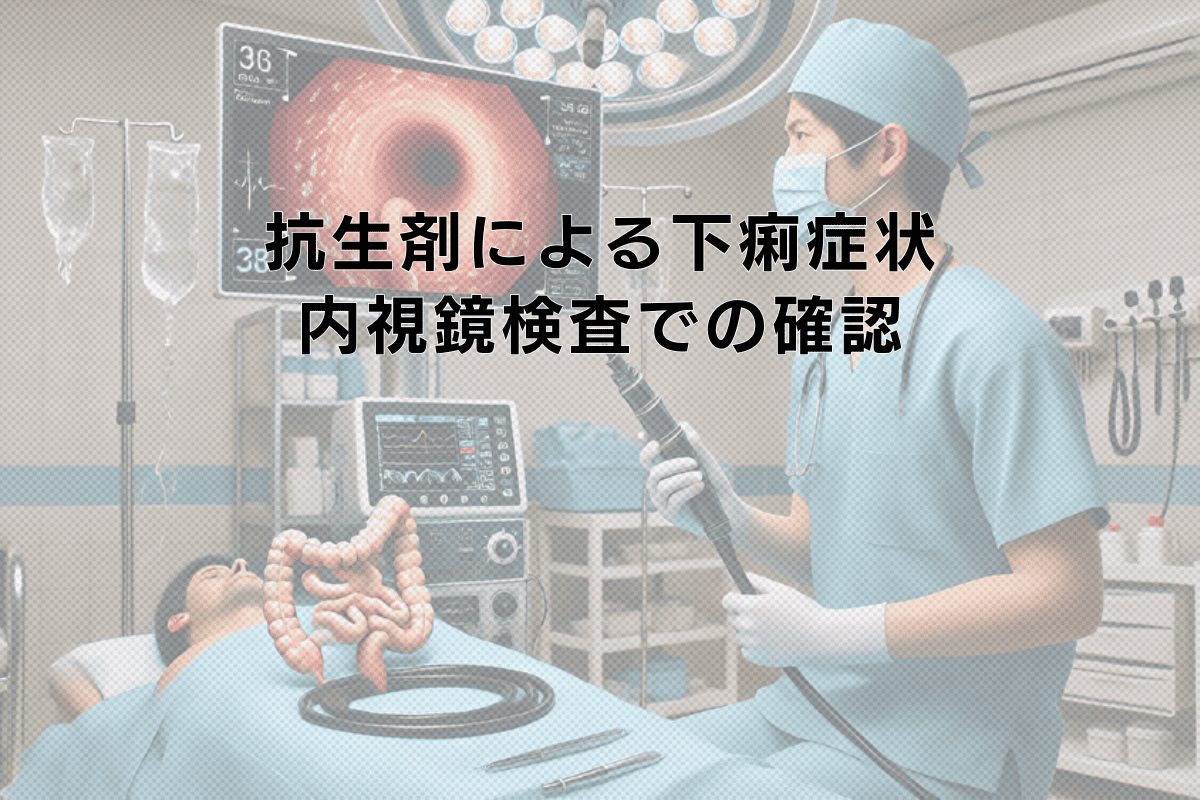抗生剤は、細菌が原因となる感染症の治療に大きな役割を果たす薬ですが、副作用として下痢を起こすことがあります。
下痢は、抗生剤が病気の原因となる細菌だけでなく、腸内にいる健康維持に必要な細菌にも影響を与え、腸内環境のバランスを乱してしまうために生じます。
この記事では、なぜ抗生剤で下痢が起こるのか、詳しい理由から、ご自身でできる対処法、症状が重い場合に腸内の状態を直接確認できる内視鏡検査の重要性まで、解説します。
抗生剤を服用すると下痢が起こる理由
抗生剤を飲むと下痢になるという経験は、決して珍しいものではありません。
薬の作用が、病原菌だけでなく、体に本来必要な腸内細菌にも影響を及ぼし、バランスが崩れることで、腸の機能に一時的な不調が生じ、下痢という症状になって現れます。
腸内細菌のバランスが崩れる
腸内には、数百種類、数十兆個以上もの細菌が生息しており、腸内細菌叢(ちょうないさいきんそう)、または腸内フローラと呼ばれ、互いに影響し合いながら絶妙なバランスを保ち、私たちの健康を支えています。
しかし、抗生剤、特に幅広い種類の細菌に効果を示す広域スペクトラム抗生剤を服用すると、病気の原因菌だけでなく、腸内にいる多くの細菌も区別なく減少させてしまいます。
腸内細菌のバランスが急激に崩れることをディスバイオシスと呼び、これが抗生剤による下痢の根本的な原因となり、腸内細菌の多様性が失われることで、腸本来の機能が低下してしまうのです。
善玉菌と悪玉菌の役割
腸内細菌は、働きによって大きく善玉菌、悪玉菌、そして日和見菌の3つに分けられます。
善玉菌は消化吸収を助けたり、ビタミンの合成、免疫機能を正常に保ったりする有益な働きをし、悪玉菌は、腸内で有害物質を作り出すなど、体に良くない影響を及ぼすことがあります。
健康な状態では善玉菌が優位で、悪玉菌の活動が抑えられていますが、抗生剤の使用で善玉菌が減少すると、悪玉菌や、普段は無害でも体が弱ると悪さをする日和見菌が増殖しやすいです。
このことが腸内環境の悪化を招き、下痢症状を起こす一因となります。
腸内細菌の主な働き
| 細菌の種類 | 主な働き | 代表的な細菌 |
|---|---|---|
| 善玉菌 | 消化吸収の補助、免疫機能の調整、ビタミン合成 | ビフィズス菌、乳酸菌 |
| 悪玉菌 | 有害物質の産生、腸内腐敗、発がん性物質の生成 | ウェルシュ菌、ブドウ球菌 |
| 日和見菌 | 優勢な方の菌に味方する、善玉にも悪玉にもなりうる | バクテロイデス、大腸菌(無毒株) |
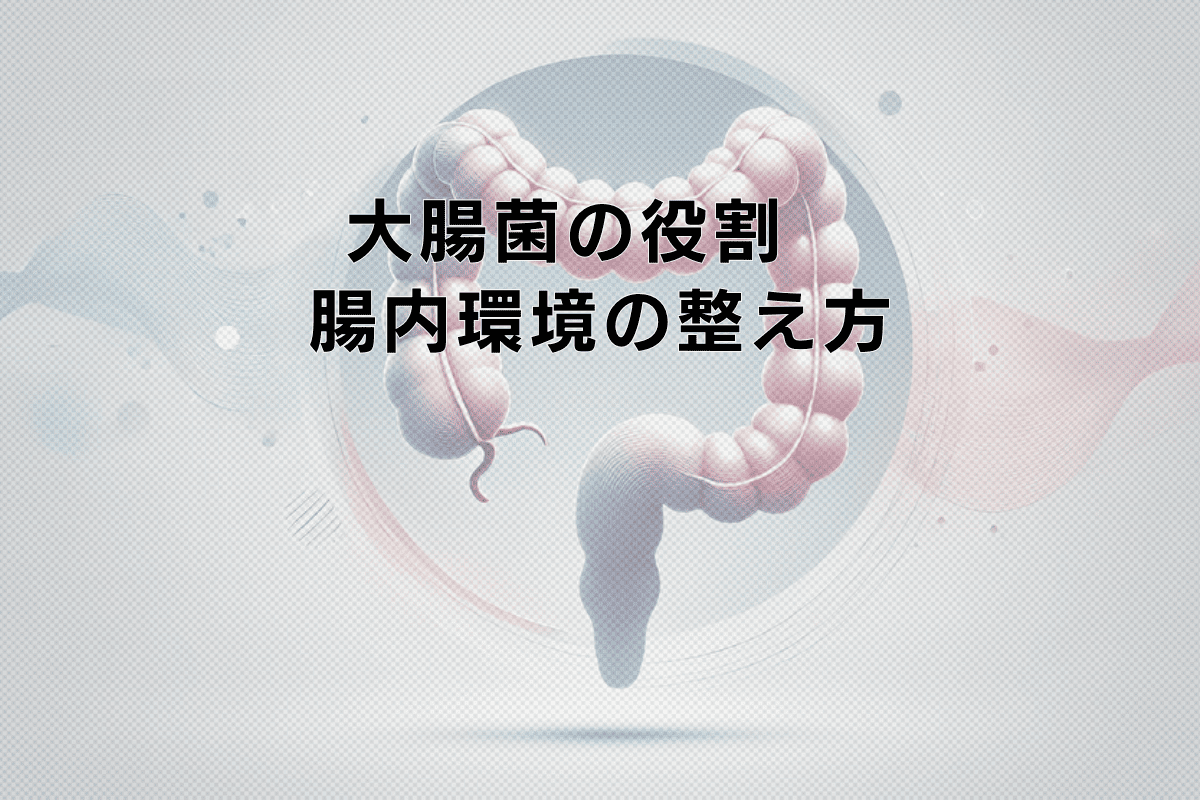
腸の運動が活発になる影響
腸内細菌のバランスの変化は、腸そのものの動きである蠕動(ぜんどう)運動にも影響を与え、腸内環境が悪化すると、腸内細菌が作り出す物質のバランスも変化し、腸の神経を刺激して蠕動運動が過剰になることがあります。
腸の動きが活発になりすぎると、便が腸を通過する時間が短くなり、便に含まれる水分が十分に吸収されないまま排出されるため、水分の多い、いわゆる下痢便となります。
一部の抗生剤には、直接腸の運動を亢進させる作用を持つものもあり、これも下痢を起こす要因の一つです。
抗生剤関連下痢症とは
抗生剤の服用が原因で起こる下痢は、医学的に「抗生剤関連下痢症(Antibiotic-Associated Diarrhea, AAD)」と呼ばれ、単に便が緩くなるというだけでなく、時には重篤な合併症を起こす可能性のある病態として認識されています。
すべての抗生剤にこのリスクは伴いますが、特に発症頻度や重症度に違いが見られます。
単純な下痢との違い
風邪をひいたり、冷たいものを食べ過ぎたりした時に起こる一時的な下痢と、抗生剤関連下痢症との大きな違いは、原因が腸内細菌叢の乱れにある点です。
多くの場合、抗生剤の服用を中止すれば自然に改善しますが、中には服用を終えてから数週間後に発症することもあります。
また、一部は特定の細菌が異常増殖することによって起きる、重篤な腸炎へと進行する危険性をはらんでおり、単なる副作用と軽視できない場合があります。
偽膜性腸炎のリスク
抗生剤関連下痢症の中で、最も注意が必要なのが「偽膜性腸炎(ぎまくせいちょうえん)」です。
クロストリディオイデス・ディフィシル(Clostridioides difficile)という菌が、抗生剤によって他の腸内細菌が減少した隙に異常増殖し、産生する毒素によって大腸の粘膜に激しい炎症を起こします。
この菌は芽胞(がほう)という硬い殻を作るため、胃酸や消毒薬にも強く、非常に感染力が高く、頻回の下痢、腹痛、発熱などを伴い、重症化すると命に関わることもあります。特に高齢者や長期入院中の患者さんで、発症リスクが高いです。
偽膜性腸炎を疑う症状
- 1日に何度も起こる水様性の下痢
- 粘液や血液が混じった便
- しぶるような強い腹痛
- 38度以上の発熱や悪寒
症状の程度と分類
抗生剤関連下痢症の症状は、軽い軟便から重篤な偽膜性腸炎まで幅広くあり、多くは、抗生剤の服用中から服用後数日にかけて見られる軽度から中等度の下痢です。この場合、腹痛は軽いか、ほとんどないこともあります。
一方で、偽膜性腸炎のように特定の病原菌が関与する場合は、症状が重くなる傾向があり、適切な診断と治療のためには、下痢の回数や性状、腹痛の有無、発熱などの全身症状を詳しく観察することが大切です。
症状の重症度による違い
| 項目 | 軽症・中等症 | 重症(偽膜性腸炎など) |
|---|---|---|
| 下痢の回数 | 1日数回程度 | 1日10回以上など頻回 |
| 便の性状 | 軟便〜水様便 | 水様便、時に血便・粘液便 |
| 腹痛・発熱 | ないか、軽いことが多い | 強い腹痛や高熱を伴うことがある |
発症するタイミング
抗生剤関連下痢症は、抗生剤を服用し始めてから2〜3日で発症することが多いですが、タイミングは一様ではありません。服用期間中はもちろんのこと、時には服用を終えてから1〜2ヶ月後に症状が現れる遅発性のケースもあります。
抗生剤によって腸内環境が変化した後、原因菌であるクロストリディオイデス・ディフィシルなどが時間をかけて増殖するために起こるため、抗生剤を飲み終えた後も、しばらくは体調の変化に注意を払うことが大切です。
もし原因がはっきりしない下痢が続く場合は、最近の抗生剤の服用歴を医師に伝えてください。
下痢を起こしやすい抗生剤の種類
抗生剤は種類によって下痢の副作用が起こりやすいものと、そうでないものがあり、多くの種類の細菌に効果がある「広域スペクトラム抗生剤」ほど、腸内細菌叢への影響が大きく、下痢を起こしやすいです。
ペニシリン系抗生剤
ペニシリン系は、古くから使われている代表的な抗生剤で、アモキシシリンなどがこの系統に含まれます。
クラブラン酸という薬効を高める成分と配合された製剤(アモキシシリン・クラブラン酸)は、呼吸器感染症や皮膚感染症など、幅広い領域で用いられますが、下痢や軟便の副作用が比較的起こりやすいです。
これは、腸内細菌叢への影響が大きいためと考えられています。
セフェム系抗生剤
セフェム系抗生剤も、風邪や気管支炎、尿路感染症など、さまざまな感染症に用いられることが多い薬です。ペニシリン系と同様に、幅広い細菌に効果を示すため、腸内の善玉菌にも影響を及ぼしやすく、下痢の原因となることがあります。
第三世代と呼ばれるセフェム系抗生剤は、その傾向が強く、経口薬だけでなく、注射薬としても広く使用されています。
主な抗生剤の系統と特徴
| 抗生剤の系統 | 特徴 | 下痢の起こりやすさ |
|---|---|---|
| ペニシリン系 | 幅広い感染症に使用。特定の合剤で下痢の頻度が高い。 | やや高い |
| セフェム系 | 使用頻度が高い。世代によって腸内への影響が異なる。 | やや高い |
| マクロライド系 | 消化管運動を促進する作用も持つ。 | 比較的高い |
| ニューキノロン系 | 広域で強力な抗菌力を持つ。偽膜性腸炎のリスクあり。 | やや高い |
マクロライド系抗生剤
クラリスロマイシンやアジスロマイシンなどが含まれるマクロライド系の抗生剤は、呼吸器感染症などによく処方されます。この系統の薬は、腸内細菌への影響に加えて、消化管の運動を活発にする「モタゴニスト作用」という働きも持っています。
モタゴニスト作用によって腸の動きが促進され、下痢や腹痛が起こりやすくなることがあり、他の抗生剤による下痢とは少し異なる理由で発生します。
その他の抗生剤
上記以外にも、リンコマイシン系のクリンダマイシンや、ニューキノロン系のレボフロキサシンなども、抗生剤関連下痢症、特に偽膜性腸炎のリスクがある薬として知られています。どの抗生剤であっても下痢が起こる可能性はゼロではありません。
もし薬を服用中に下痢が始まった場合は、どの薬を飲んでいるかを把握しておくことが大切です。お薬手帳などを活用し、処方された薬の情報を記録しておくことをお勧めします。
抗生剤による下痢の症状と持続期間
抗生剤を服用し始めてから下痢が続くと、いつまでこの状態が続くのか不安になるものです。症状の出方や続く期間には個人差がありますが、一般的な傾向を知っておくことで、落ち着いて対処しやすくなります。
主な症状の特徴
抗生剤による下痢の多くは、腹痛を伴わないか、伴っても軽い鈍痛程度の軽症で、便の性状は、普段より少し柔らかい軟便から、形のない水様便までさまざまです。
通常、発熱や嘔吐といった他の症状は見られませんが、偽膜性腸炎を合併した場合は、激しい腹痛や発熱、血便など、より重い症状が現れます。

症状セルフチェック
| チェック項目 | 一般的な抗生剤による下痢 | 偽膜性腸炎の疑い |
|---|---|---|
| 下痢の回数 | 多くても1日数回 | 頻回(トイレから離れられない) |
| 腹痛 | ない、または軽い | 強い痛み、しぶるような痛み |
| 発熱 | ほとんどない | 高熱が出ることがある |
| 便の状態 | 軟便〜水様便 | 血液や粘液が混じることがある |
下痢が続く平均的な日数
症状の持続期間は、原因となっている抗生剤の種類や個人の体質によって異なりますが、多くの場合は抗生剤の服用を中止してから数日以内に軽快します。服用中であっても、体が慣れてくることで症状が和らぐこともあります。
一般的には、服用中止後1週間以内には便の状態が元に戻ることが多いです。ただし、腸内細菌叢が完全に元に戻るには数週間から数ヶ月かかることもあります。
服用終了後も症状が続く場合
抗生剤の服用を終えたにもかかわらず、1週間以上下痢が続く、あるいは症状が悪化するような場合は注意が必要です。乱れた腸内細菌叢がなかなか回復しない、または偽膜性腸炎を発症している可能性が考えられます。
服用終了から数週間経ってから下痢が始まった場合は、偽膜性腸炎の可能性を念頭に置く必要があります。
また、まれに抗生剤の使用が引き金となり、過敏性腸症候群のような状態に移行することもあり、このような場合は、自己判断で様子を見ずに、速やかに医療機関に相談してください。
自宅でできる対処法と注意点
抗生剤による下痢が起こった際、症状が軽ければ自宅でのセルフケアで対応できることもありますが、間違った対処は症状を悪化させる可能性もあるため、正しい知識を持つことが大切です。
ここでは、ご自身でできる対処法と注意点を解説します。
水分補給の重要性
下痢の症状がある時、最も気をつけなければならないのが脱水症状で、下痢によって体内の水分と電解質(ナトリウムやカリウムなど)が大量に失われます。
特に高齢者や小さなお子さんは脱水になりやすいため、こまめな水分補給が非常に重要です。ただの水を飲むだけでなく、電解質も効率良く補給できる経口補水液の活用が推奨され、麦茶や野菜スープなども良いでしょう。
カフェインやアルコール、糖分の多いジュースは避けてください。
脱水症状のサイン
- 口の中や唇の渇き
- 尿の回数や量が減る、色が濃くなる
- めまいや立ちくらみ
- 皮膚の弾力がなくなる
食事で気をつけること
下痢で弱った胃腸に負担をかけないよう、食事内容にも配慮が必要で、消化が良く、腸を刺激しない食べ物を選びましょう。
食事は一度にたくさん食べず、数回に分けて少量ずつ摂るのがポイントで、症状が落ち着いてきたら、徐々に普段の食事に戻していきます。
食事に関するポイント
| 心がけたい食事 | 避けたほうがよい食事 | |
|---|---|---|
| 内容 | おかゆ、うどん、白身魚、豆腐、りんごのすりおろし、バナナ | 脂っこいもの、香辛料、冷たいもの、食物繊維の多い野菜、乳製品 |
| ポイント | 温かく、消化しやすいものを中心に摂取する | 腸を刺激したり、消化に時間がかかったりするものは控える |
整腸剤の利用について
整腸剤は、乳酸菌やビフィズス菌といった善玉菌を補い、乱れた腸内環境のバランスを整える助けとなり、抗生剤による下痢の予防や症状の緩和に有効な場合があります。
市販の整腸剤を使用することも一つの方法ですが、医療機関で処方される整腸剤もあります。抗生剤を処方される際に、あらかじめ医師や薬剤師に相談しておくとよいでしょう。
プロバイオティクス(善玉菌そのもの)だけでなく、プレバイオティクス(善玉菌のエサになるオリゴ糖など)を意識して摂ることも有効です。
自己判断での服用中止は危険
下痢がつらいからといって、ご自身の判断で抗生剤の服用を中止することは絶対に避けてください。
処方された期間、きちんと飲み切らないと、治療対象の感染症の原因菌を完全に死滅させることができず、症状が再発したり、悪化したりする恐れがあります。
さらに、中途半端な服用は薬剤耐性菌を生み出す原因にもなり、将来的に薬が効きにくくなるという社会全体の問題にもつながります。下痢の症状がひどく、服用を続けるのが難しい場合は、必ず処方した医師に相談し、指示を仰いでください。
医療機関を受診するべき症状の目安
抗生剤による下痢の多くは軽症ですが、中には専門的な治療が必要なケースや、危険な病気が隠れているサインである場合もあります。以下の症状がある場合は、様子を見ずに消化器内科への受診を検討してください。
激しい腹痛や血便がある場合
単なる下痢ではなく、我慢できないほどの強い腹痛や、しぶるような痛みが伴う場合は注意が必要です。また、便に血が混じる(血便)、あるいは全体が赤黒くなるような場合は、大腸の粘膜がひどく傷ついている可能性があります。
このような症状は、偽膜性腸炎や他の重篤な腸の病気も考えられるため、緊急を要するサインです。すぐに消化器内科などの専門医を受診してください。
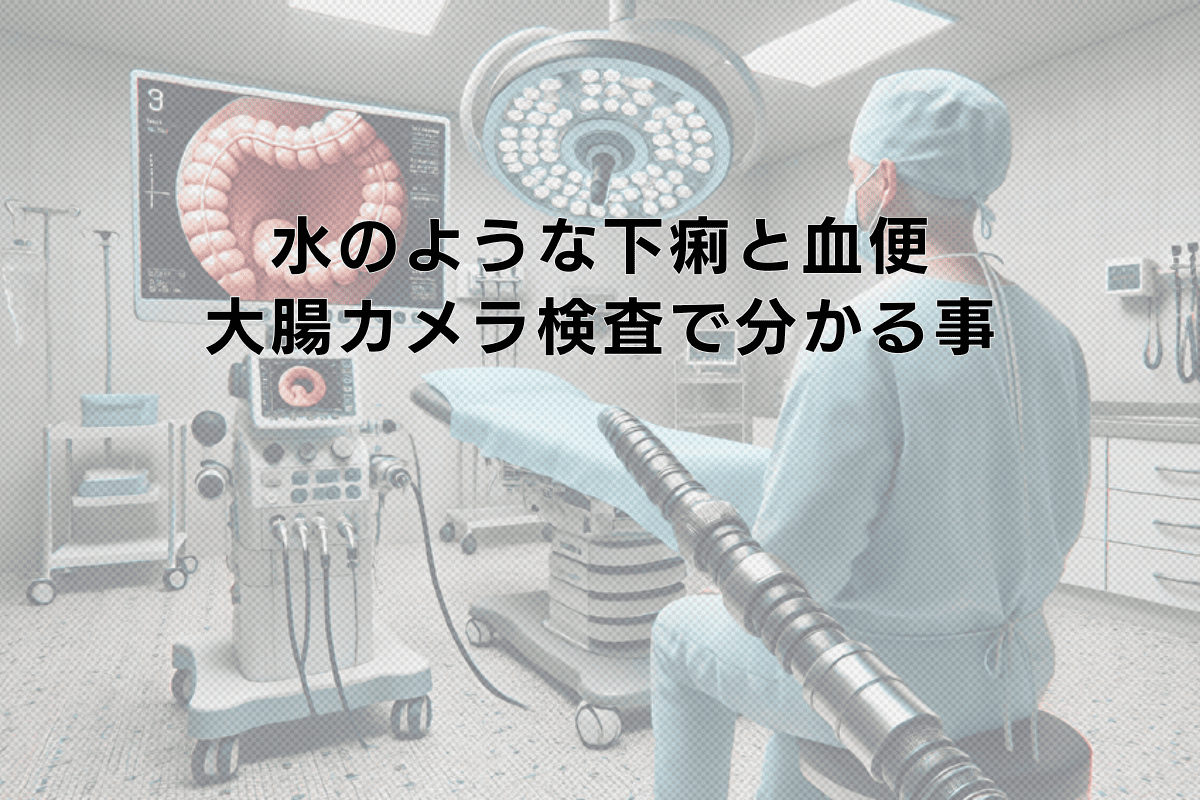
高熱や脱水症状が見られる時
下痢に加えて38度以上の高熱が出ている場合も、体内で強い炎症が起きているサインです。偽膜性腸炎などでは高熱を伴うことが少なくありません。
また、水分を摂っても下痢の回数が多く、ぐったりしている、尿がほとんど出ないといった脱水症状が見られる場合も、点滴による水分・電解質の補給が必要になることがあります。
高熱や脱水症状の放置は、全身状態の悪化につながるので、すぐに医療機関を受診してください。
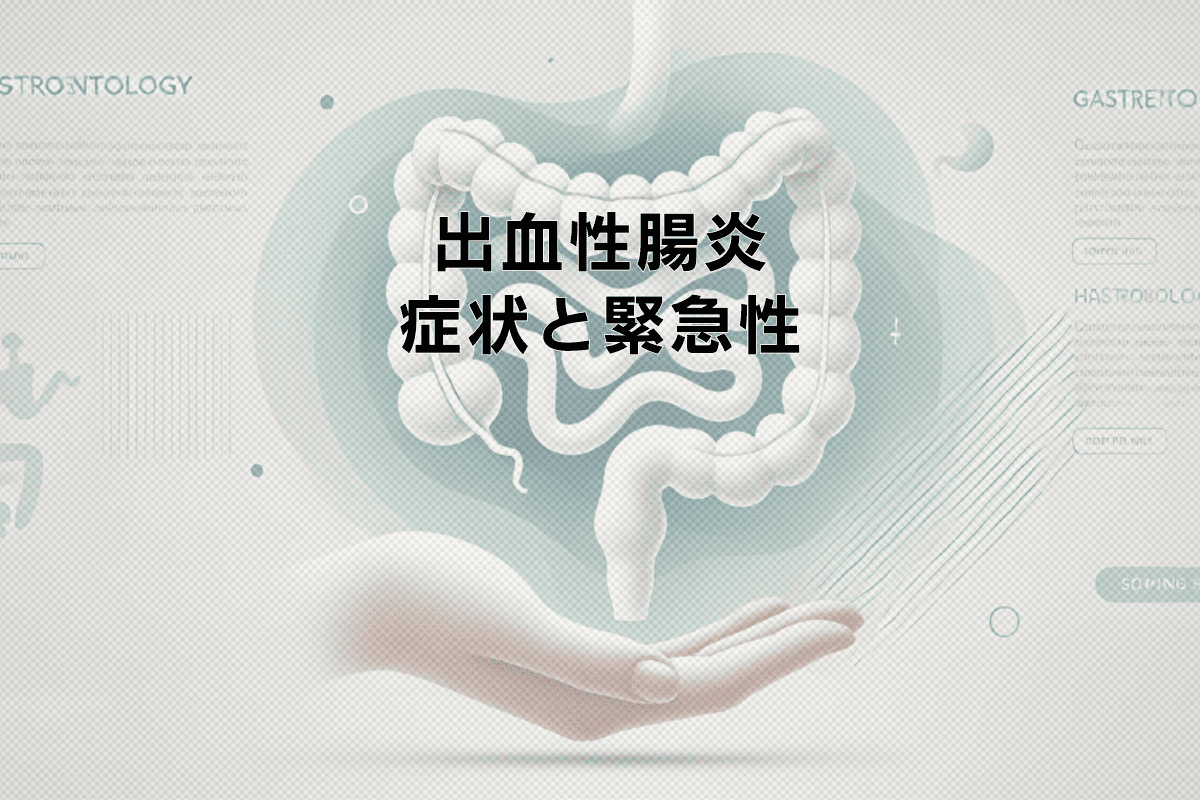
受診を強く推奨する症状
| 症状の種類 | 具体的な内容 | 考えられる状態 |
|---|---|---|
| 便の異常 | 血液が混じる、粘液が多い、白い膜のようなものが混じる | 重篤な腸炎(偽膜性腸炎など) |
| 腹部の症状 | これまでに経験したことのないような激しい腹痛 | 腸管の強い炎症、穿孔のリスク |
| 全身の症状 | 高熱、強い倦怠感、意識がもうろうとする | 重症感染症、高度の脱水、敗血症 |
下痢が長期間続くケース
抗生剤の服用を終えてから1週間以上経っても下痢が改善しない、あるいは一度治まったのに再び下痢が始まったという場合も、医療機関への相談をお勧めします。
乱れた腸内環境が自力で回復できていないか、偽膜性腸炎などが遅れて発症している可能性も否定できません。原因を特定し、治療を受けることで、症状の慢性化を防ぎ、つらい状態から早く回復することができます。
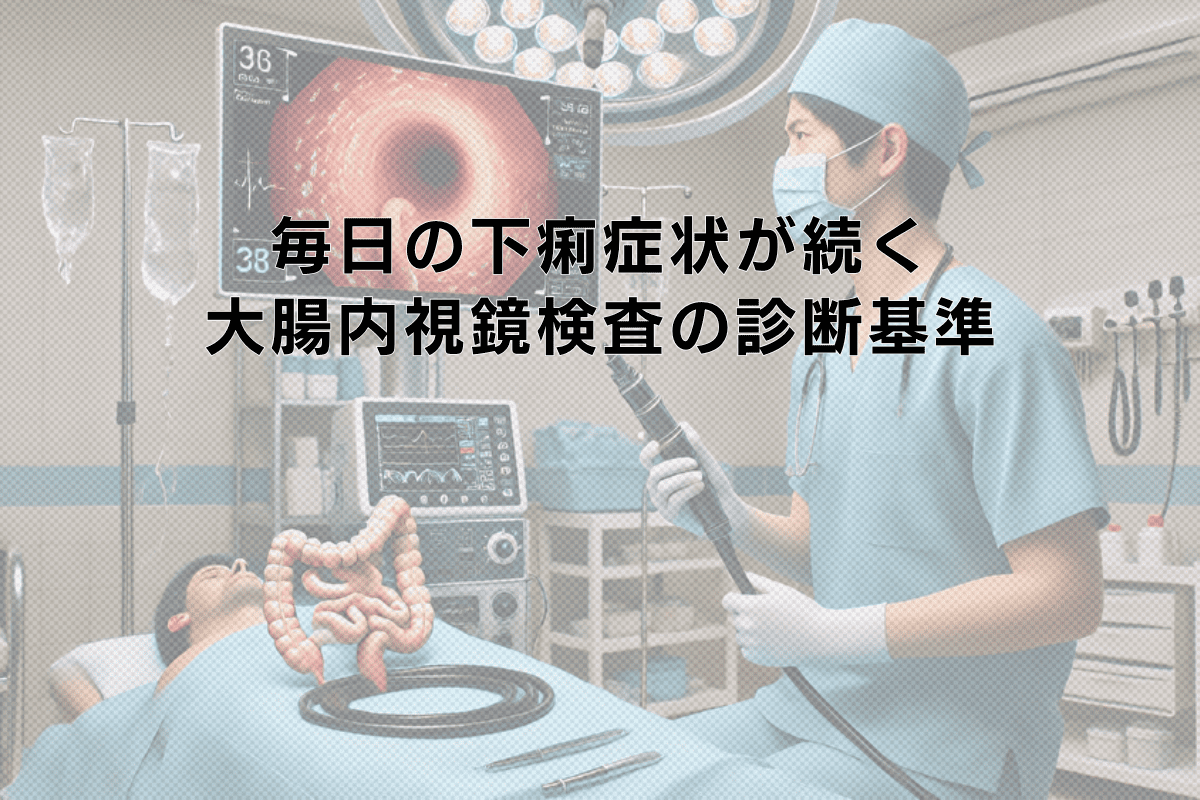
内視鏡検査で腸内環境を調べる重要性
症状が長引いたり、重症化したりしている抗生剤関連下痢症の診断において、内視鏡検査(大腸カメラ)は非常に有益な情報をもたらします。
問診や便の検査だけではわからない腸の中の状態を、医師が直接目で見て確認できるため、正確な診断と適切な治療方針の決定に欠かせない検査です。
腸内の状態を直接観察する
内視鏡検査では、先端に高性能カメラがついた細いスコープを肛門から挿入し、大腸全体の粘膜を隅々まで観察し、炎症の有無やその程度、範囲、特徴などをリアルタイムで評価できます。
単なる機能的な下痢なのか、それとも粘膜に異常をきたす器質的な病気なのかを判断する上で、最も確実な方法の一つです。
腸内環境の乱れが、実際に大腸の粘膜にどのような影響を及ぼしているのかを視覚的に捉えることができます。CTスキャンなど他の画像検査では捉えきれない、粘膜表面の微細な変化を詳細に確認できる点が大きな利点です。
内視鏡検査で確認できる主な所見
- 粘膜の発赤(赤み)や血管透見像の消失
- 浮腫(むくみ)による粘膜の腫れ
- びらんや潰瘍(ただれや、えぐれ)
- 偽膜の付着
偽膜性腸炎の診断
特に偽膜性腸炎の診断において、内視鏡検査は決定的な役割を果たします。偽膜性腸炎に特徴的なのは、大腸の粘膜に付着する黄色から白色の苔のような「偽膜」で、内視鏡で直接確認することが、最も確実な診断方法です。
便の毒素検査も診断の補助にはなりますが、結果が出るまでに時間がかかることや、偽陰性(本当は菌がいても陰性に出る)の可能性もあるため、内視鏡所見は迅速かつ正確な診断に極めて重要になります。
偽膜性腸炎の内視鏡所見
| 所見 | 特徴 | 診断における重要度 |
|---|---|---|
| 偽膜 | 黄白色で、島状あるいは敷石状に粘膜に付着する | 非常に高い(確定診断につながる) |
| 発赤・浮腫 | 大腸粘膜全体が赤く腫れぼったくなる | 高い(炎症の存在を示す) |
| 易出血性 | スコープの接触などで粘膜から出血しやすくなる | 中程度(炎症の活動性を示す) |
他の腸の病気との鑑別
下痢や血便、腹痛といった症状は、抗生剤関連下痢症以外にも、潰瘍性大腸炎やクローン病といった炎症性腸疾患、あるいは感染性腸炎など、さまざまな病気で起こり得ます。
抗生剤を服用していたという事実だけで、全ての症状を抗生剤の副作用と断定することはできません。内視鏡検査を行い、粘膜の状態を詳細に観察することで、他の病気の可能性を否定したり、あるいは発見したりすることができます。
例えば、炎症性腸疾患では特徴的な潰瘍の形状や分布が見られ、症状の原因を正しく見極める「鑑別診断」のために、内視鏡は不可欠な検査です。
検査後の対応
内視鏡検査によって診断が確定すれば、結果に基づいた治療方針が立てられ、偽膜性腸炎であれば、原因菌に対する特異的な抗菌薬の投与が必要です。軽度の腸炎であれば、整腸剤の処方や食事指導で経過を見ることがあります。
また、検査の際に組織の一部を採取(生検)し、病理検査で詳しく調べることもあります。
よくある質問
ここでは、抗生剤による下痢に関して、患者さんからよく寄せられる質問と回答をまとめました。
- 抗生剤を飲むたびに下痢になります。体質でしょうか。
-
その可能性は十分に考えられます。腸内細菌叢の構成は一人ひとり異なり、いわば個人の指紋のようなものです。
もともとの腸内環境が、抗生剤の影響を受けやすい状態である場合、薬を服用するたびに下痢を繰り返すことがあります。
もし特定の抗生剤で必ず下痢をする場合は、その薬の名前を記録しておき、次に医療機関にかかる際に医師や薬剤師に伝えることが大切です。下痢を起こしにくい別の系統の薬を選択するなどの対策が可能な場合があります。
- 子供が抗生剤で下痢をした場合、どうすればよいですか。
-
まず、脱水症状に注意してください。子供は大人に比べて体内の水分量が多いため、脱水になりやすい傾向があります。水分をこまめに与え、おしっこの回数や色、機嫌などをよく観察しましょう。
ぐったりして元気がない、水分を受け付けないといった場合は、速やかに小児科を受診してください。食事は消化の良いものを少しずつ与え、お尻がかぶれないように、おむつ交換を頻繁に行い、清潔を保つことも大事です。
自己判断で抗生剤をやめたり、大人用の下痢止めを使ったりするのは避けてください。
- 整腸剤は抗生剤と一緒に飲んでも大丈夫ですか。
-
多くの場合で問題ありません。抗生剤による腸内環境の乱れを軽減する目的で、整腸剤が一緒に処方されることもよくあります。
整腸剤に含まれる善玉菌が、抗生剤によってダメージを受けた腸内フローラの回復を助けることが期待されます。
ただし、薬の飲み合わせには様々な組み合わせがあるため、念のため処方を受けた医師や薬局の薬剤師に確認するとより安心です。市販の整腸剤を利用する場合も、専門家に相談することをお勧めします。
- 下痢止めを飲んでも問題ないでしょうか。
-
自己判断で市販の下痢止めを飲むのは避けるべきです。細菌の毒素が原因となっている偽膜性腸炎のような状態で下痢止め(ロペラミド塩酸塩など)を使用すると、腸の動きを無理に止めてしまいます。
原因となる毒素や菌を体外に排出するのを妨げ、かえって症状を悪化させたり、重篤な合併症を起こしたりする危険性があります。
下痢は体にとっての防御反応の一面もあります。つらい症状ではありますが、まずは原因に対する治療が優先されます。下痢の症状を抑えたい場合は、必ず医師に相談してください。
次に読むことをお勧めする記事
【水のような下痢と腹痛の症状 – 内視鏡検査による原因究明】
抗生剤以外にも、感染性腸炎など多様な原因で水様性下痢は起こります。原因別の特徴と検査の考え方を合わせて学ぶことで、全体像がよりクリアになります。
【薬が引き起こす便秘と下痢の症状|原因と対処法】
抗生剤による下痢について学んだ皆さんには、薬剤全般が腸に与える影響についても知っていただくと、より包括的な理解ができます。整腸剤の使い方や、薬の副作用への対処法についても詳しく解説しています。
以上
参考文献
Takedani Y, Nakamura T, Fukiwake N, Imada T, Mashino J, Morimoto T. Clinical characteristics and factors related to antibiotic-associated diarrhea in elderly patients with pneumonia: a retrospective cohort study. BMC geriatrics. 2021 May 17;21(1):317.
Sasaki Y, Murakami Y, Zai H, Nakajima H, Urita Y. Effect of antibiotics for infectious diarrhea on the duration of hospitalization: a retrospective cohort study at a single center in Japan from 2012 to 2015. Journal of Infection and Chemotherapy. 2018 Jan 1;24(1):59-64.
Kinoshita Y, Ariyoshi R, Fujigaki S, Tanaka K, Morikawa T, Sanuki T. Endoscopic diagnosis of chronic diarrhea. DEN open. 2022 Apr;2(1):e53.
Komatsu M, Kato H, Aihara M, Shimakawa K, Iwasaki M, Nagasaka Y, Fukuda S, Matsuo S, Arakawa Y, Watanabe M, Iwatani Y. High frequency of antibiotic-associated diarrhea due to toxin A-negative, toxin B-positive Clostridium difficile in a hospital in Japan and risk factors for infection. European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. 2003 Sep;22(9):525-9.
Bartlett JG. Antibiotic-associated diarrhea. New England journal of medicine. 2002 Jan 31;346(5):334-9.
Shen B, Khan K, Ikenberry SO, Anderson MA, Banerjee S, Baron T, Ben-Menachem T, Cash BD, Fanelli RD, Fisher L, Fukami N. The role of endoscopy in the management of patients with diarrhea. Gastrointestinal endoscopy. 2010 May 1;71(6):887-92.
Högenauer C, Hammer HF, Krejs GJ, Reisinger C. Mechanisms and management of antibiotic-associated diarrhea. Clinical infectious diseases. 1998 Oct 1;27(4):702-10.
Bartlett JG. Antibiotic-associated diarrhea. Clinical Infectious Diseases. 1992 Oct 1;15(4):573-81.
Jabbar A, Wright RA. Gastroenteritis and antibiotic-associated diarrhea. Primary Care: Clinics in Office Practice. 2003 Mar 1;30(1):63-80.
Hurley BW, Nguyen CC. The spectrum of pseudomembranous enterocolitis and antibiotic-associated diarrhea. Archives of internal medicine. 2002 Oct 28;162(19):2177-84.