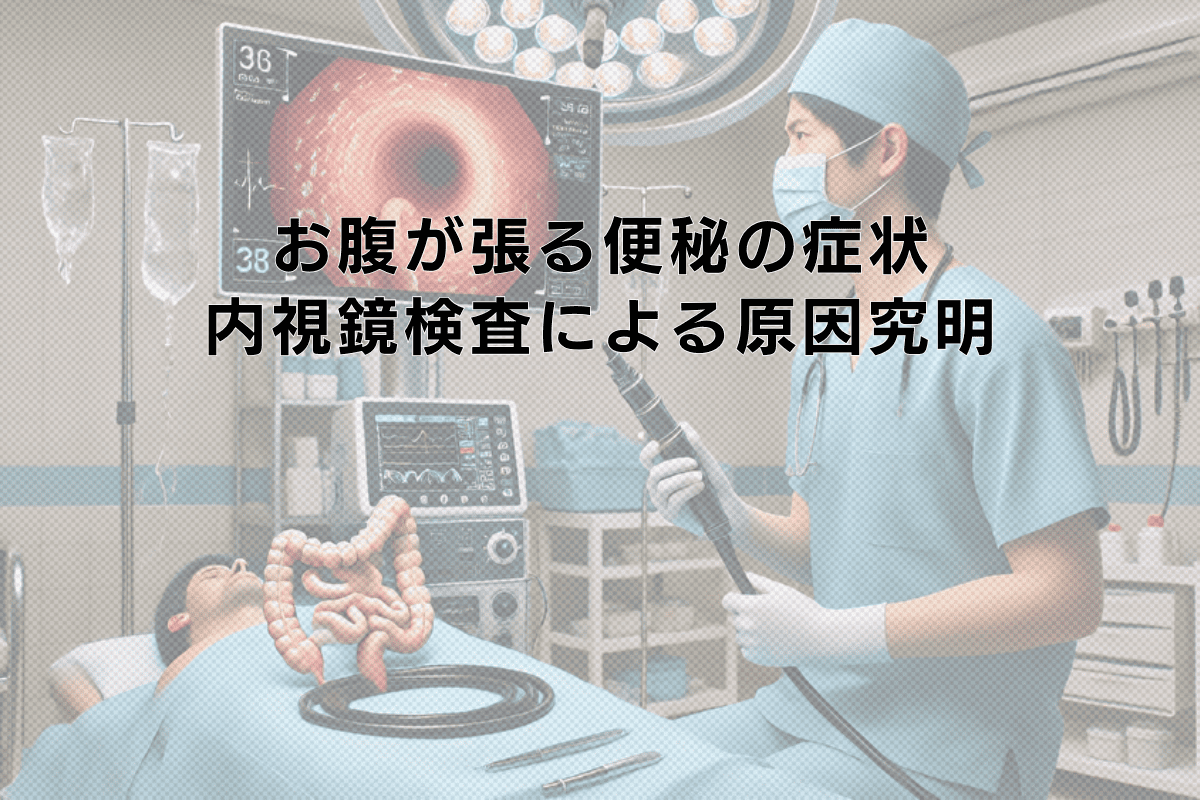便秘でお腹が張る状態が続くと、日常生活に大きな負担を感じてしまいます。便通がうまくいかないとガスが腸内にたまり、腹部の膨満感に加えて痛みや食欲低下を引き起こす場合もあります。
さらに、見落としてはいけない病気が潜んでいる可能性も否定できません。
この記事では、便秘によるお腹の張りの原因や内視鏡検査(大腸カメラ・胃カメラ)による原因究明の重要性、治療法について詳しく解説します。
便秘でお腹が張る仕組み
便秘でお腹が張る状態は、単なる腸の動きの乱れだけでなく、さまざまな要因が複雑に関係していて、腸内にガスが過剰に発生すると腹部に圧迫感が生じ、体のだるさや不快感を覚える方も多いです。
便秘とは?
便秘とは、一般的に排便の回数が減少したり、便が硬くなったりして、スムーズな排出ができない状態で、理想的な排便回数は人によって異なりますが、週に2回以下や日常的に排便が困難なケースは便秘と考えられることが多いです。
便秘にはいくつかの種類が存在し、主に以下のような特徴が見られます。
- 器質性便秘:腸自体やその周辺に病変があって便が通りにくくなるケース
- 機能性便秘:生活習慣、ストレス、食生活などが原因で腸の働きが低下するケース
- 一過性便秘:旅行や仕事の変化など、一時的な要因で便秘が生じるケース
これらの要因が重なっている場合もあり、原因に応じた対処が必要です。
お腹が張るメカニズム
便秘でお腹が張る主な原因は、腸内に滞留している便とガスの存在で、ガスが多く発生する背景には、食事内容や腸内細菌のバランスが関係します。腸内環境が乱れると悪玉菌が増加し、腐敗が進むことでさらにガス量が増えることがあります。
ガスがたまると腹部が膨らんだ状態になり、苦しさや痛みを感じるケースもあるため注意が必要です。

お腹の張りに影響する主な要素
| 要素 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 食事の内容 | 脂質の多い食事や食物繊維不足による便通の停滞 |
| 腸内細菌のバランス | 悪玉菌の増加でガスが過剰に発生する |
| ストレス | 自律神経の乱れで腸の動きが低下し便の排出が滞る |
| 運動不足 | 腸への刺激が減り、腸管がうまく蠕動しない |
| 水分摂取の不足 | 便が硬くなり排出が困難になる |
これらの要因が重複すると、さらにお腹の張りや便秘が悪化しやすくなります。
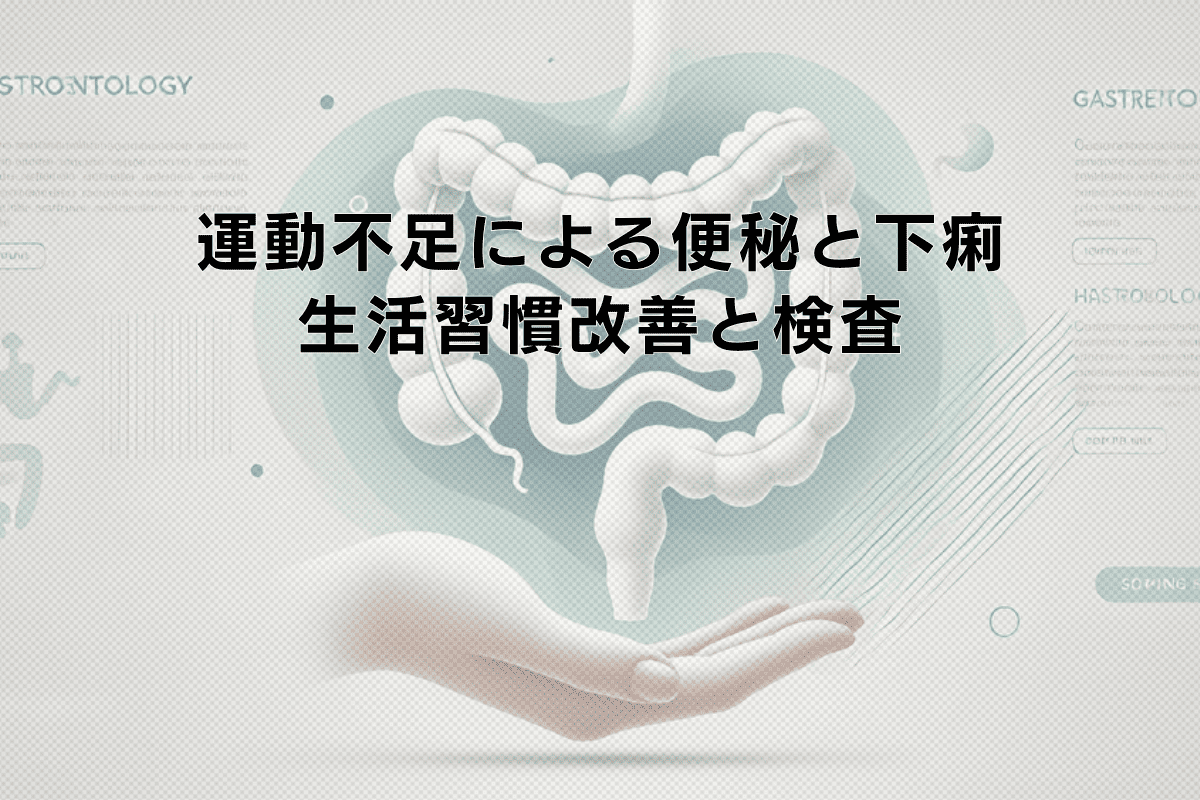
ガスのたまり方
食事に含まれる炭水化物や糖質は、腸内細菌のエサになり発酵過程でガスを放出します。適量のガスは生理的に排出されますが、便秘があると腸内に長くとどまります。
ガスが腸管内に充満すると膨満感をともない、排便や排ガスのタイミングを逃すと症状が強まる傾向にあります。
また、日常生活で自然に空気を飲み込むこともガス過多の一因です。早食いや炭酸飲料の過度な摂取などで空気を取り込みすぎる場合、腸の働きが落ちているとガスがより長く体内にとどまりやすくなります。
便秘が招く症状
便秘とお腹の張りは単に腹部の不快感だけでなく、体全体にさまざまな影響を及ぼします。
便秘による不調の種類
- 肌荒れや吹き出物の増加
- 食欲低下や吐き気
- 頭痛や肩こり
- 腹痛や腰痛
- 倦怠感や集中力の低下
これらの症状が長引く場合は、別の病気が隠れている可能性もあるため、早めに医療機関を受診してください。
お腹が張る便秘に多い主な原因
便秘でお腹が張る背景には、食習慣の乱れやストレスなど、生活上の要因が深くかかわり、さらに、内臓器官そのものに問題があるケースもあり、一概に「排便習慣の乱れだけ」とはいい切れません。
原因を知ることで、自身に合った対策を見つけることが重要です。
食習慣・生活習慣
便秘とお腹の張りを引き起こしやすい食習慣や生活習慣には特徴があり、高脂質・高カロリーの食事や慢性的な運動不足は、腸内環境を乱す要因の1つです。
過度なダイエットで食事量が極端に減ったり、食物繊維や水分を十分に摂れていなかったりすると、腸の動きが低下して便が滞留しやすくなります。
生活習慣と便秘発症リスク
| 生活習慣 | 便秘リスクへの影響 |
|---|---|
| 高脂質・高タンパク中心の食事 | 腸内に脂肪が残りやすく蠕動運動が衰えやすい |
| 野菜・果物不足 | 食物繊維不足による便のかさ不足と硬さの増加 |
| 極端なダイエット | 摂取量が減り便の材料が不足、便意が起こりにくい状態になる |
| 夜型の生活習慣 | 自律神経の乱れによる腸の働きの低下 |
| アルコール・喫煙 | 腸への刺激や血流への悪影響で便通が不安定になる |
バランスの良い食事や適度な運動、適切な睡眠リズムを保つことが重要です。
ストレスと自律神経
ストレスがかかると体は交感神経が優位になり、血液や神経機能のバランスが乱れやすくて、腸は自律神経と深く関係しているため、ストレスが溜まるほど腸の動きが悪くなります。
緊張状態が続くとリラックスできず、便意も起こりにくくなるため、お腹の張りを感じるほど便秘が進行するケースがあります。
運動不足
現代社会では、仕事や学業などで座りっぱなしの時間が増え、運動量が不足になり、体を動かす機会が減ると血行が滞り、腹筋や腸の周囲の筋肉を使う機会も少なくなります。その結果、便を押し出す力が弱まり、ガスがたまりやすくなるのです。
運動習慣の確立に向けたポイント
- ウォーキングや軽いジョギングなど、有酸素運動を週に数回取り入れる
- デスクワーク中心の場合、1時間に1度は立ち上がって体を伸ばす
- お腹まわりの筋肉を鍛える体操やストレッチを習慣化する
- 自分が楽しめるスポーツやダンスを見つけて継続する
日常に運動を取り入れることで腸の動きをサポートし、お腹の張りを軽減する効果が期待できます。
内臓疾患の可能性
便秘が長期化したり、血便が混じったりする場合は、大腸ポリープや腸管癒着など器質的な異常も疑われます。何をしても便秘が改善せず、お腹が張る症状がずっと続くようなケースでは、早めに専門医の診察を受けたほうがいいでしょう。
大腸がんや炎症性腸疾患なども、初期段階では便秘とガス溜まりの症状だけということもあります。
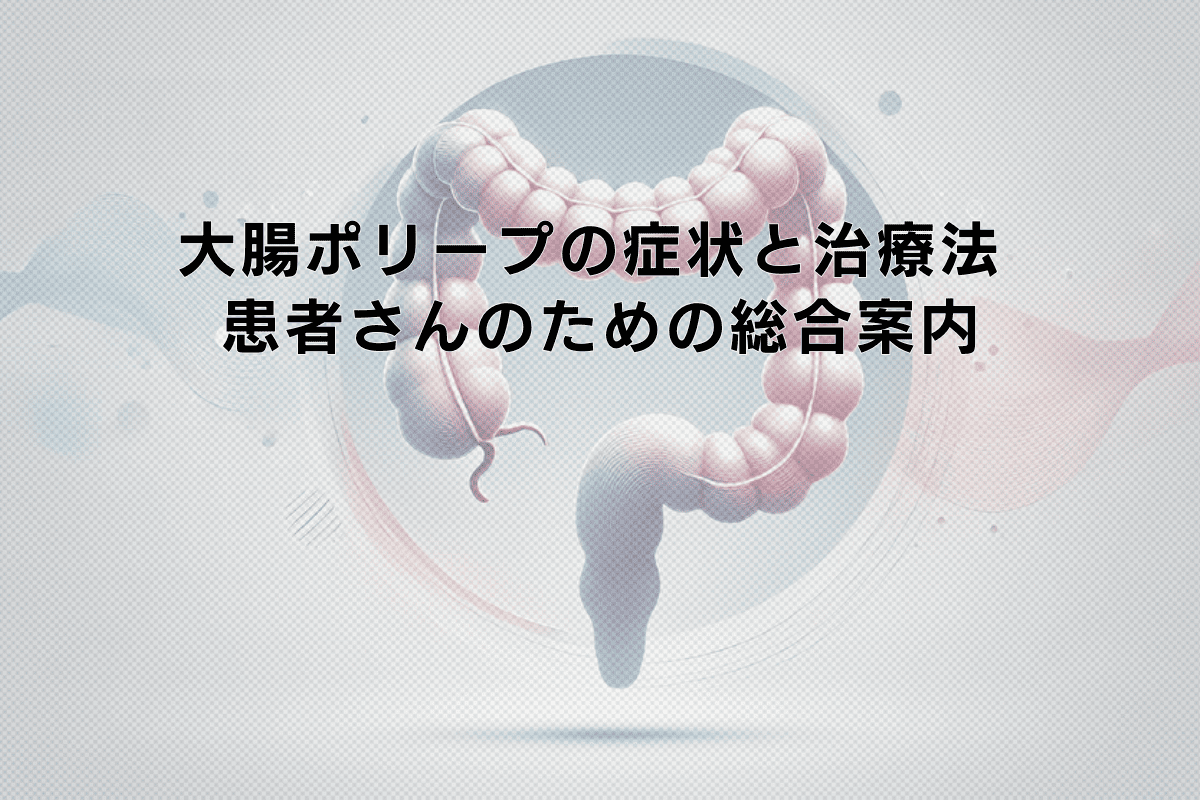
お腹の張りと内視鏡検査の関係
お腹が張る便秘症状を抱える方の中には、重大な病気が潜んでいるケースも否定できません。内視鏡検査(大腸カメラや胃カメラ)を活用すると、単なる便秘なのか、あるいは大腸の器質的病変があるのかを直接目視で確認できます。
予防や早期発見という意味でも、内視鏡検査を考慮する意義は大きいです。
内視鏡検査の必要性
内視鏡検査の最大の利点は、腸内を直接観察できる点です。便秘が続く中で、腸壁に炎症や潰瘍、大腸ポリープがある場合、治療の方向性が大きく変わります。
画像検査や血液検査だけでは判断がつかない微小な病変も、内視鏡検査であれば発見できる可能性が高いです。
内視鏡検査を受けるメリット
| メリット | 意味 |
|---|---|
| 直接観察による精確な診断 | 腸壁の色や形状など、微細な変化を確認可能 |
| 早期発見と治療 | ポリープや炎症が見つかった場合、早い段階で処置や薬物治療に移行できる |
| 生検(組織採取)ができる | 疑わしい病変から直接組織を採取して病理検査を行い、悪性か良性かを判断 |
| 結果の即時確認 | 医師が検査中に異常の有無を確認し、そのまま画像で患者に説明を行うことも可能 |
| 痛みや出血の原因をはっきりさせられる | 原因不明の腹痛や便潜血などの背景を明確にする |
内視鏡検査は大変だと思う方もいますが、適切に検査を受ければ安心感や症状改善につなげやすくなります。
大腸カメラの役割
大腸カメラは主に肛門から大腸全体を観察する検査方法で、便秘やお腹が張る症状においては、大腸の内壁状態を直接チェックできる点が大きな特徴です。
大腸の動きが悪くなっているのか、大腸に潰瘍や腫瘍、ポリープなどがあるのかを把握できるため、原因究明と治療方針の決定に大いに役立ちます。

胃カメラでわかること
「お腹が張るのに胃カメラ?」と思う方もいるかもしれませんが、胃カメラ(上部内視鏡検査)で確認できる範囲には食道や胃、十二指腸が含まれます。
便秘症状と直接は関係しない部位というイメージがありますが、胃や十二指腸に異常があると消化全体に影響を及ぼし、結果的に腸の動きが弱るケースもあります。
胃カメラを受けるメリット
- 胃や食道、十二指腸潰瘍などの有無を早期段階で確認できる
- 消化不良や慢性的な胸やけが腸の動きに波及しているかを評価しやすい
- ピロリ菌の感染確認や胃がんリスクの把握も同時に行える
- 上部消化管の炎症が原因で腸への負担が増している場合を突き止める

このように、大腸カメラと胃カメラの併用で、消化管全体を包括的に調べられることがメリットです。
検査の流れ
検査前には飲食制限や下剤の服用などの準備が必要です。
大腸カメラの場合は腸内を空っぽにしてから検査を行うことで、より詳細に腸壁を観察できます。検査中は鎮静剤を使うケースもあり、リラックスした状態で受けられるよう配慮が進んでいます。
検査後は安静時間を経て結果の説明を受け、必要に応じて治療がスタートします。
便秘とお腹の張りを解消する生活改善
便秘とお腹の張りが気になる場合、生活習慣を見直すことが大切です。
腸内の動きは食事や運動、ストレスレベルなど、多岐にわたる要素に影響を受けるので、日常のちょっとした工夫が腸にとってプラスに働き、便通の改善やガス溜まりの軽減につながります。
食事面でのポイント
まずは食物繊維と水分を意識しましょう。食物繊維には不溶性と水溶性の2種類があり、それぞれ役割が異なります。不溶性食物繊維は便のかさを増やして腸を刺激し、水溶性食物繊維は便を柔らかくして排出をスムーズにします。
どちらも偏りなく摂取すると、腸の調子が整いやすいです。
食物繊維を多く含む食材と特徴
| 食材 | 特徴 |
|---|---|
| 野菜(キャベツ、大根など) | 不溶性食物繊維が豊富で便のかさを増やし腸を刺激する |
| 果物(リンゴ、柑橘類など) | 水溶性食物繊維が含まれ、便を柔らかくして排出しやすくする |
| 海藻(昆布、ひじき、もずくなど) | 水溶性食物繊維が多く、ミネラルやビタミンも豊富 |
| きのこ類(しいたけ、しめじ) | 不溶性と水溶性の両方がバランスよく含まれる |
| 豆類(大豆、インゲン豆など) | 食物繊維に加え植物性タンパク質も豊富で腸内環境を整えやすい |
加えて、発酵食品(ヨーグルト、納豆、キムチなど)も取り入れると善玉菌が増え、腸内環境の改善につながります。
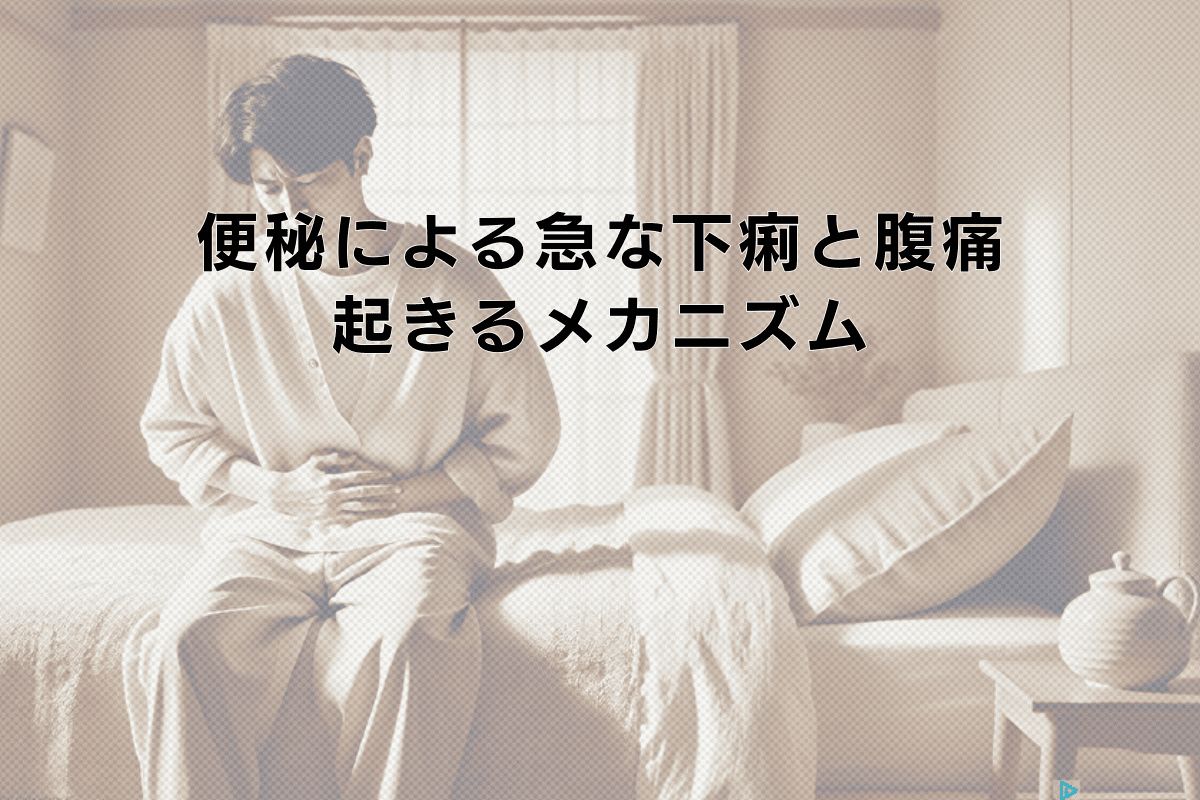
水分摂取のコツ
水分が不足すると便が硬くなり、排出に時間がかかり、喉の渇きを感じる前にこまめに水を飲むことが重要です。
寝起きにコップ1杯の水を飲むと、胃腸が刺激されて自然と便意を誘発しやすくなり、食物繊維を十分に摂るときには、特に水分補給を忘れないよう心がけましょう。
腸内環境を整える方法
腸内環境を整えることは便秘やお腹の張り改善には欠かせません。食事だけでなく、ストレスコントロールや適度な運動も腸の動きに影響します。
腸内環境を良好に保ちやすい取り組み
- 規則正しい生活リズムを保つ
- ビフィズス菌や乳酸菌を含む食品を摂る
- 過度な飲酒や喫煙を控える
- 入浴やマッサージでリラックスし、自律神経を整える
腸内環境が整うと便通がスムーズになりやすく、ガスもたまりにくくなります。
生活リズムの調整
人間の身体は朝起きて光を浴びると交感神経が優位になり、夜になると副交感神経が高まり休息へ向かい、このリズムが乱れると腸も影響を受けます。夜更かしや不規則な食事タイミングは便通の乱れを招く大きな原因です。
就寝時間と起床時間をできるだけ一定に保ち、朝食をしっかり摂ることで、腸の働きを整えやすくなります。
便秘によるお腹の張りと市販薬・病院での治療
便秘が慢性化すると自力での改善が難しくなることもあり市販薬を試す方は多いですが、自己判断だけで長期間使用するとかえって腸が動きにくくなる場合もあるため注意が必要です。
病院での治療や内視鏡検査を含む検査を組み合わせることで、より確実に原因と対策を把握しやすくなります。
市販薬の種類と選び方
市販薬には大きく分けて刺激性下剤、膨潤性下剤、浸透圧性下剤などがあり、刺激性下剤は腸を直接刺激して排便を促すタイプで即効性がありますが、連用すると腸が慣れてしまう懸念もあります。
膨潤性下剤は便のかさを増やす働きがあり、比較的緩やかに効き、浸透圧性下剤は腸内に水分を集めて便を柔らかくするという仕組みです。
市販薬の種類と特徴
| 種類 | 作用の仕方 | 注意点 |
|---|---|---|
| 刺激性下剤 | 腸壁を刺激して腸の動きを活発にする | 慣れが生じる恐れがあり、長期連用は避けたほうがよい |
| 膨潤性下剤 | 水分を吸収して便のかさを増やし排泄を促す | 十分な水分補給が必要で、即効性はやや低い |
| 浸透圧性下剤 | 腸内に水分を引き寄せ、便を柔らかくする | 人によってはお腹の痛みや下痢を感じるケースがある |
| 酸化マグネシウム系 | マグネシウムの力で便中の水分保持力を高める | 腎機能が低下している人は医師に相談したほうが安心 |
自分の便秘のタイプに合った市販薬を選ぶと同時に、長引く場合は専門医を受診することも検討してください。
医療機関での処方薬
医療機関では、原因に応じて刺激性下剤や浸透圧性下剤以外にも、腸内環境を整える整腸剤やプロバイオティクス製剤などが処方されることがあります。
医師の診断のもと処方されるため、既往症や体質に合わせて薬が選択されるメリットがあり、自己判断で市販薬を使い続けるよりも、安全かつ効果的に便秘を改善できる可能性が高いです。
他の検査手段との違い
便秘とお腹の張りの原因を探るには、血液検査や超音波検査、CT検査なども参考になりますが、大腸カメラで腸内を直接観察する場合と比べると、見落としが生じるリスクは上がります。
画像には映りにくい小さな病変や微細な粘膜の変化を確認できるのは内視鏡検査の特長です。
検査方法ごとの特徴
- 超音波検査:非侵襲的で簡便だが、ガスが多いと腸の状態を十分に確認しにくい
- CT検査:断面画像で腸の形状や周辺臓器を捉えやすいが、放射線被ばくがある
- 血液検査:炎症や貧血、栄養状態を把握できるが、腸の内部構造までは確認できない
- 内視鏡検査:直接観察が可能で組織検査も行える
こうした選択肢を組み合わせながら、正確な診断と治療方針を立てることが重要です。
病院で行う治療の流れ
病院を受診した際には問診や触診、必要に応じて血液検査や画像検査を行います。さらに腸内の状況を詳細に調べるために内視鏡検査が提案されることがあります。
検査結果に基づいて薬物療法を開始したり、生活指導が行われるケースも多く、原因がはっきりすれば、治療のゴールを具体的に定めやすいです。
内視鏡検査で原因を究明するメリット
便秘でお腹が張る原因をしっかり把握するためには、直接的な観察が欠かせません。内視鏡検査を受けると、腸内の状態を目で確認できるだけでなく、ポリープや炎症があれば同時に処置を行える場合もあり、早期の治療につなげやすくなります。
腸の状態を直接確認できる
内視鏡検査ではカメラが付いた細い管を肛門から挿入し、大腸を隅々まで観察し、リアルタイムでモニターに映る腸内の様子を見ることで、病変の有無を正確に把握できます。
大腸カメラによる観察結果で問題がなければ、便秘の原因が大腸の器質的疾患でないことを確認できる点もメリットです。
内視鏡検査による大腸内観察で把握できる情報
| 情報 | 具体的内容 |
|---|---|
| 粘膜の色や質感 | 潰瘍、炎症、出血などの微細な変化を見落とさず確認可能 |
| ポリープや腫瘍の存在状況 | サイズや位置を正確に把握し、必要に応じて切除や生検を実施 |
| 腸内の形状・動き | 狭窄や憩室の有無、腸の動きなど機能面もある程度推測できる |
| 便がたまっている箇所と硬さ | 便の停滞場所や状態を直接確認し、治療方針の参考にする |
| その他の器質的異常 | 出血点や炎症性ポリープ、リンパ節の腫れなど幅広く発見できる |
初期段階で見つけられれば、治療や生活改善の効果が高まりやすくなります。
早期発見につながる
お腹の張りが長引くときは、大腸がんなどの早期発見の機会にもなり、大腸ポリープの段階で切除すればがん化を防げる可能性があり、定期的な大腸カメラ検査を推奨する医師が多いのはそのためです。
症状が軽いうちに検査を受けておけば、もし異常が見つかっても軽度のうちに対処できるかもしれません。
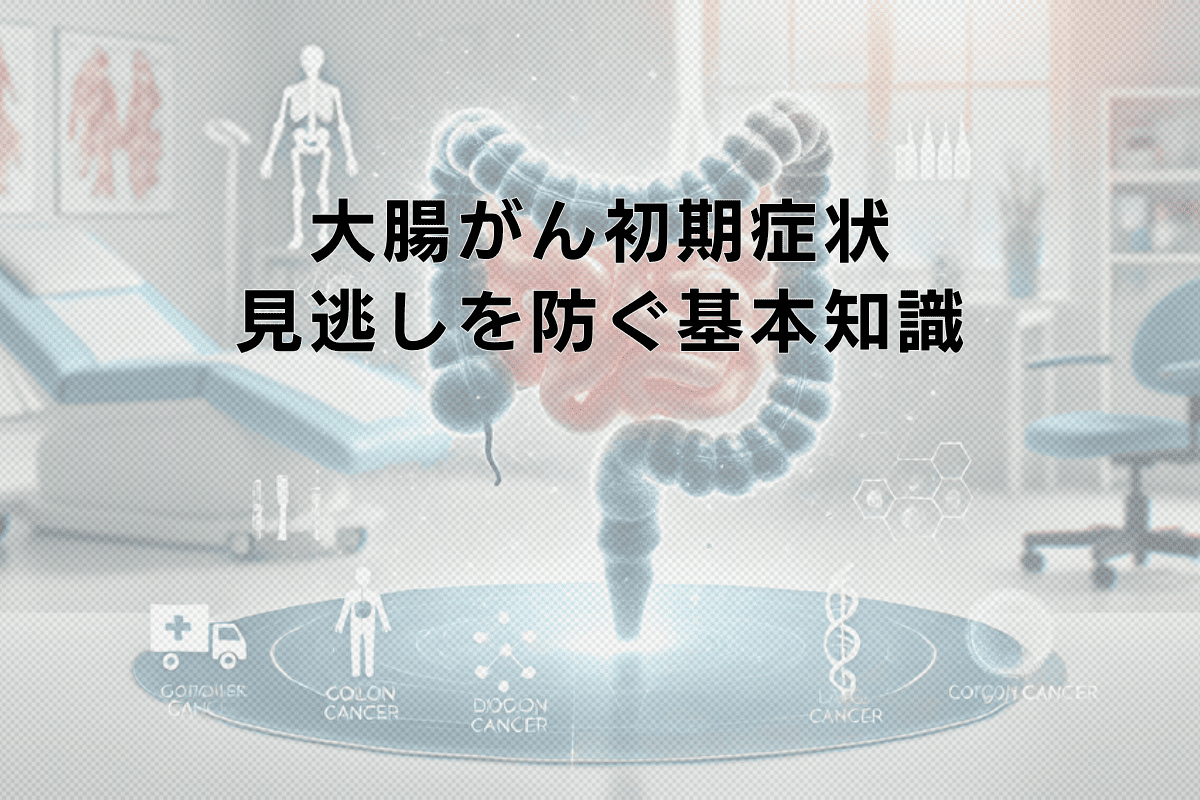
検査後のフォローアップ
検査結果はその場で医師が確認し、必要な場合は処置や薬物療法を開始し、内視鏡検査で異常が見つからなくても、便秘やお腹が張る症状が続く場合は、生活指導や他の検査が検討されるケースもあります。
再発予防のために定期的に受診して、腸の状態を継続的に把握することが大切です。
内視鏡検査後に意識したいこと
- 医師の指示に従った食事制限や水分摂取を心がける
- もしポリープ切除などを行った場合は、安静期間や禁忌事項をしっかり守る
- 再発リスクを考慮し、定期検査や健康診断を活用する
- 生活習慣の見直しを継続し、便秘やガス溜まりを起こしにくい環境を作る
体調管理の意識を高めることで、検査後の快適な生活を維持しやすくなります。
再発防止と健康管理
便秘やお腹の張りは再発することも多い症状で、内視鏡検査で一時的に異常が見つからなくても、その後のライフスタイル次第でまた腸内環境が乱れることがあります。
定期的な運動習慣やバランスの取れた食事、ストレスコントロールを継続することが、再発を防ぐうえで極めて重要です。医療機関で定期検査を受けることで安心感も高まります。
内視鏡検査の受診を検討すべき症状
便秘によるお腹の張りが続く場合、何か大きな病気が潜んでいないか気になる方も多いはずです。以下のような症状があるなら、早い段階で内視鏡検査を含む詳しい検査を検討する必要があります。
便に血が混じる
排便時に便やトイレットペーパーに血が付く場合、大腸ポリープや炎症性腸疾患、大腸がんなどの可能性があります。痔による出血もありますが、自己判断で済ませずに念のため医療機関に相談しましょう。

便に血が混じる際の要チェックポイント
| 項目 | 注目すべき点 |
|---|---|
| 血の色 | 鮮血なのか、暗赤色なのか |
| 量の多さ | 多量出血なのか、わずかな血液付着なのか |
| 頻度 | 毎回混じるのか、時々なのか |
| 痛みや痒みの有無 | 痔や肛門周囲の傷が原因なのか見極める手がかりになる |
| 便の形状や硬さ | 出血以外の腸内異常が隠れていないかを考慮する |
血が混じる現象が続くなら、一刻も早く大腸カメラを検討することを推奨します。
体重減少と倦怠感
便秘やお腹の張りに加えて、理由のはっきりしない体重減少や強い倦怠感がある場合は注意が必要で、大腸がんや消化器系のほかの病気によって栄養吸収がうまくいっていない可能性があります。
腸内での炎症が持続していたり、消化機能が落ちていると体全体の調子も崩しやすくなります。
便通異常が慢性化した場合
頑固な便秘が何週間も続いたり、突然下痢と便秘を繰り返すような不安定な状態が続くときも、専門医による検査が役立ちます。
過敏性腸症候群の可能性や、腸の狭窄が徐々に進んでいるケースもあるため、原因を正確に把握することが欠かせません。
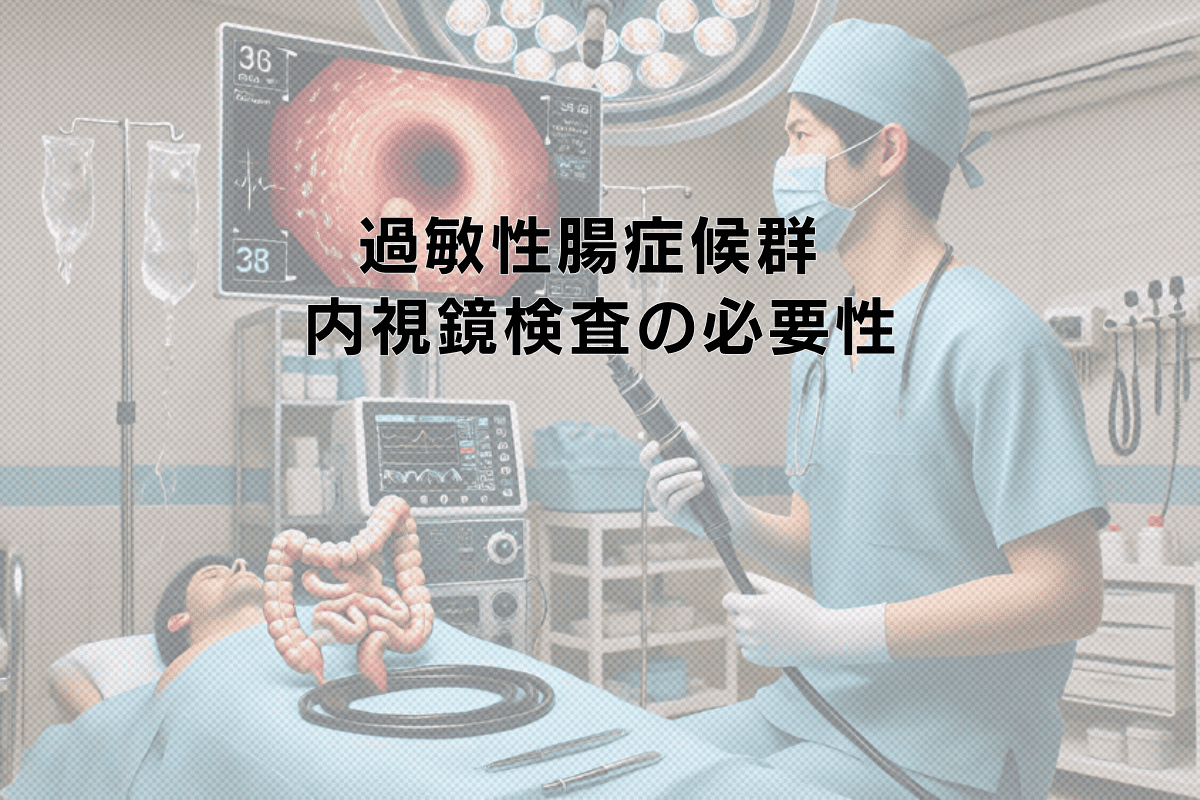
検診や人間ドックの機会
定期的な健康診断や人間ドックは、大腸カメラや胃カメラの検査をオプションで付ける機会でもあり、便秘でお腹が張る症状が普段から気になる方ほど、こうしたタイミングを活用すると安心感が得られやすいです。
特に40代以上では、大腸がんのリスクも徐々に高まるため、定期的な受診を検討しましょう。
Q&A
便秘でお腹が張るときに「検査を受けるべきか」「どんな治療法があるのか」など、多くの方が疑問を抱きます。ここでは、よくある質問とその答えを簡潔にまとめました。
- 毎日便通はあるのにお腹が張ります。これは便秘なのでしょうか?
-
毎日便通があっても、十分に排出しきれていない「隠れ便秘」が原因でお腹が張る場合があり、便の量や形状が少なかったり、便が硬く腸内に残っているとガスがたまってしまうことがあります。
便通の回数だけでなく、排便後のすっきり感や便の状態にも注目してください。
- 便秘とガスを軽減するサプリや整腸剤は効果がありますか?
-
サプリや整腸剤には、腸内環境を整える効果が期待できるものもあり、ビフィズス菌や乳酸菌を補う製品は、悪玉菌の増殖を抑えてガスの発生を抑制する可能性があります。
ただし根本的な生活習慣の改善や、必要に応じた内視鏡検査での原因究明も同時に行うと、より早く症状緩和につながりやすいでしょう。
- お腹の張りがしんどいときは、どのように対処すればいいですか?
-
ガスが原因の場合は、軽い体操や腹部マッサージなどで腸に刺激を与えるとガスが排出されやすくなり、ガス抜きポーズや足上げ運動などをするのも1つの方法です。
また、水分をしっかり補給し、腸内環境を整える食事を心がけることも大切です。強い痛みや吐き気があるときは、早めに医師に相談してください。
- 長期間便秘薬を使っているのですが、やめても大丈夫でしょうか?
-
便秘薬に依存している場合、自力での排便が難しくなる可能性があり、自己判断で急にやめるのではなく、医師に相談しながら徐々に減薬するのが理想的です。
同時に食事内容の改善や適度な運動習慣を取り入れて、自然な腸の動きを取り戻すことを目指しましょう。
次に読むことをお勧めする記事
【大腸検査が気になる方へ 内視鏡検査の注意点】
便秘とお腹の張りの原因について理解できたら、次は実際の大腸カメラ検査について知っておくと安心です。検査を検討されている方に特に参考になる内容です。
【腸の健康が体を支える 腸内環境を整える】
便秘の背景には腸内環境の乱れも関係します。食事・運動・睡眠を総合的に見直すポイントを学ぶと、再発予防に役立ちます。
参考文献
Otani K, Watanabe T, Takahashi K, Nadatani Y, Ominami M, Fukunaga S, Hosomi S, Kamata N, Tanaka F, Nagami Y, Taira K. Upper gastrointestinal endoscopic findings in functional constipation and irritable bowel syndrome diagnosed using the Rome IV criteria: a cross-sectional survey during a medical check-up in Japan. BMC gastroenterology. 2023 May 3;23(1):140.
Kanazawa M, Miwa H, Nakagawa A, Kosako M, Akiho H, Fukudo S. Abdominal bloating is the most bothersome symptom in irritable bowel syndrome with constipation (IBS-C): a large population-based Internet survey in Japan. BioPsychoSocial Medicine. 2016 Dec;10:1-8.
Komori S, Akiyama J, Tatsuno N, Yamada E, Izumi A, Hamada M, Seto K, Nishiie Y, Suzuki K, Hisada Y, Otake Y. Prevalence and Risk Factors of Constipation Symptoms among Patients Undergoing Colonoscopy: A Single-Center Cross-Sectional Study. Digestion. 2024 Aug 9;105(4):299-309.
Yamada E, Kuriyama H, Uchida E, Murata Y, Hata Y, Tagri M, Isozaki Y, Oyamada H, Ozawa Y, Ito T, Mizuki A. Association between endoscopic findings related to colonic diverticula and bowel habits: A multicenter study in Japan. Journal of gastroenterology and hepatology. 2017 Dec;32(12):1938-42.
Kessoku T, Misawa N, Ohkubo H, Nakajima A. Current treatment practices for adult patients with constipation in Japan. Digestion. 2024 Jan 8;105(1):40-8.
Oshima T, Miwa H. Epidemiology of functional gastrointestinal disorders in Japan and in the world. Journal of neurogastroenterology and motility. 2015 Jul 3;21(3):320.
Filliettaz SS, Gonvers JJ, Peytremann-Bridevaux I, Arditi C, Delvaux M, Numans ME, Lorenzo-Zuniga V, Dubois RW, Juillerat P, Burnand B, Pittet V. Appropriateness of colonoscopy in Europe (EPAGE II)–functional bowel disorders: pain, constipation and bloating. Endoscopy. 2009 Mar;41(03):234-9.
Cash BD, Acosta RD, Chandrasekhara V, Chathadi KV, Eloubeidi MA, Fanelli RD, Faulx AL, Fonkalsrud L, Khashab MA, Lightdale JR, Muthusamy VR. The role of endoscopy in the management of constipation. Gastrointestinal endoscopy. 2014 Oct 1;80(4):563-5.
Popovic DD, Filipovic B. Constipation and colonoscopy. World Journal of Gastrointestinal Endoscopy. 2024 May 16;16(5):244.
Cai J, Yuan Z, Zhang S. Abdominal pain, diarrhea, constipation-which symptom is more indispensable to have a colonoscopy?. International Journal of Clinical and Experimental Pathology. 2015 Jan 1;8(1):938.