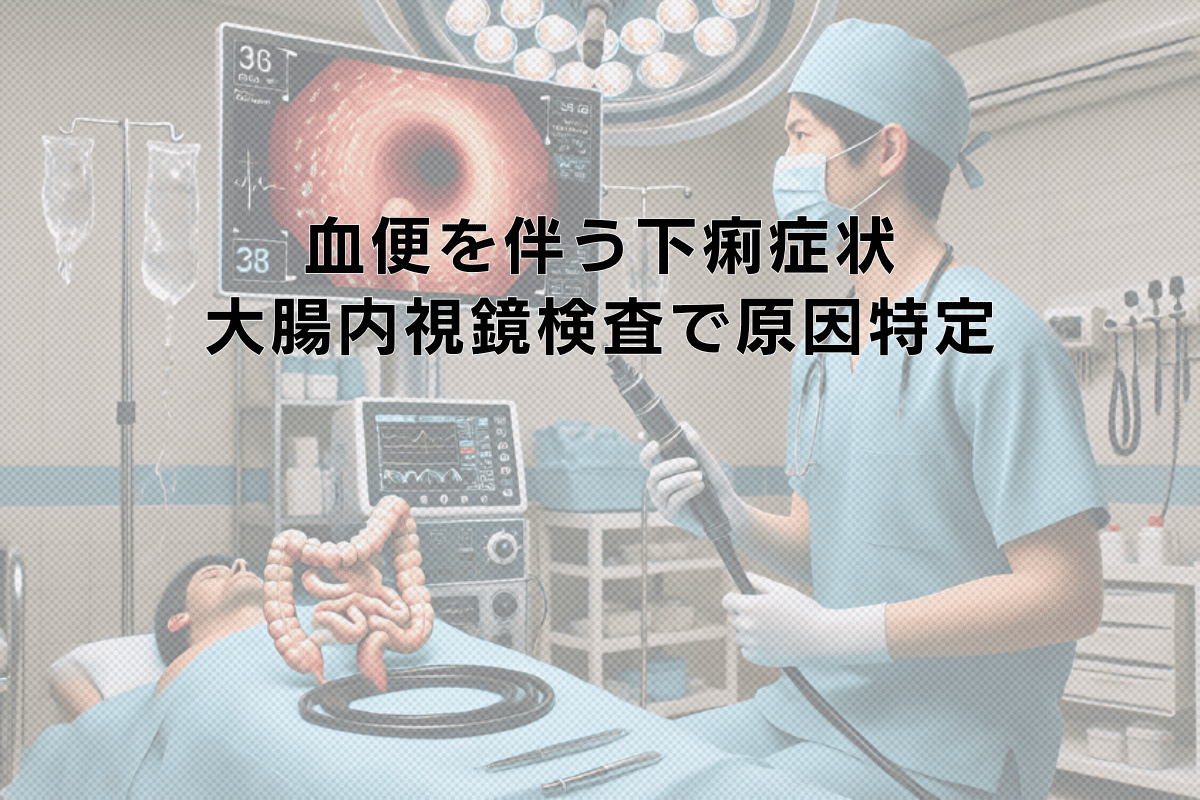血便を伴う下痢症状を認める場合、大腸をはじめとする消化管のトラブルを疑う兆候を把握し、正確な診断を行いながら治療につなげることが必要です。
下痢に血が混じる場合や、下痢と血便が長く続いている場合は単なる食あたりや軽度の胃腸炎では説明できないケースがあり、ポリープや腫瘍、潰瘍性大腸炎など深刻な病気の可能性も否定できません。
こうした症状の原因を見極めるための大腸内視鏡検査は、直腸や結腸の表面を直接観察したり組織を採取したりできる点で重要です。
健康診断や一般的な血液検査だけでは特定しにくい病変を早期に見つける一助となるため、下痢と血便が気になる方は内視鏡検査を選択肢に入れると安心です。

下痢に血が混じる時に知っておきたい基礎知識
下痢に血が混じる状態は通常の腹痛や軟便とは異なり、消化管のどこかに炎症や出血、ポリープや腫瘍などがある可能性を想定したほうがよいサインです。
血の色合いや混じり方によって、病変の位置や程度に違いがあるため、自己判断で放置してしまうと病状が進行するリスクがあります。
ここでは、下痢と血便が起こるしくみや、日常的に意識しておくポイントを整理します。
血便を伴う下痢のメカニズム
胃や腸が何らかの原因で傷つくと、消化管の粘膜が出血します。そのまま便と混ざって排泄されるため、「下痢に血が混じる」という状態になります。
胃や十二指腸など上部消化管での出血の場合、排便時には黒っぽいタール状になりやすい一方、大腸や直腸での出血だと赤い血液が目立ちます。
下痢が加わると、正常な消化吸収機能が大きく乱されている可能性が高く、急性・慢性的な腸炎、炎症性腸疾患などの詳細な精査が重要です。
腹痛や発熱の合併症状
下痢と血便に腹痛や発熱を伴う場合、感染性腸炎や炎症性腸疾患が原因になっている可能性があり、腹痛が激しい、夜間も何度も便意に襲われる、トイレの後も痛みや不快感が続くなどの状態では注意が必要です。
こうした症状が長引くほど、胃腸に負担がかかり体力も消耗するため、軽度だと思っていても早めの受診が大切になります。
便の色や形状の観察ポイント
下痢に血が混じるとき、便の状態を観察することは診断の手掛かりになります。便自体の色合い、血の色、粘液の有無などを把握することで、大腸のどの部分に問題がありそうかをある程度推測できます。
短期間でも観察してメモを取っておくと、医師の診察時に具体的な情報を伝えることができ、スムーズな病状把握につながります。
下痢と血便の目安
| 観察ポイント | 具体的な様子 | 考えられる病変 |
|---|---|---|
| 血の色 | 赤い・暗赤色・黒色 | 大腸下部~上部、または胃など |
| 粘液 | 透明や白、黄など | 腸炎、潰瘍性大腸炎 |
| 臭い | 腐敗臭が強いなど | 腸内細菌バランスの乱れ |
症状を見落とさない心がけ
下痢や血便に関する症状は一時的に治まったように感じても、時間が経って再発することがあります。痛みや出血量が軽減しても、根本的な病変が残っていればまた症状がぶり返す可能性があるため、注意深く体調の変化を追う必要があります。
体調管理や食事内容の見直しとともに、自己判断をせず医師に相談する姿勢が大切です。
- 長引く下痢に血が混じる場合は早めに受診する
- 便の色や性状を日常的にチェックする
- 一時的に治まっても原因の除去が重要になる
主な自覚症状と経過の目安
| 自覚症状 | 経過観察のポイント | 医療機関への相談目安 |
|---|---|---|
| 軽度の下痢と血便 | 食事内容を改善後も続く場合 | 2~3日以上継続 |
| 腹痛・発熱の合併 | 内服薬や水分補給で変化を観察 | 1日以上症状が強い |
| 慢性的な違和感 | 便の状態がほぼ毎日不安定 | 1週間以上改善なし |
血便を伴う下痢に隠れる主な疾患
下痢と血便が合わさった場合、腸の炎症やポリープ、感染症など多岐にわたる疾患の可能性が浮かびます。痛みや熱がないからといって放置すると取り返しのつかない状態になるリスクもあるため、早期の原因特定が重要です。
炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎、クローン病など)
潰瘍性大腸炎は大腸の粘膜にびらんや潰瘍ができる病気で、特に血便や下痢が頻発しやすいと知られています。クローン病は口から肛門まで消化管のあらゆる部分に炎症が及ぶことがある難治性の病気です。
いずれも慢性的に症状をきたし、寛解と再燃を繰り返す傾向があります。
- 何度も便意をもよおす
- 下痢が続き血便が目立つ
- 腹痛や倦怠感、体重減少が起こりやすい

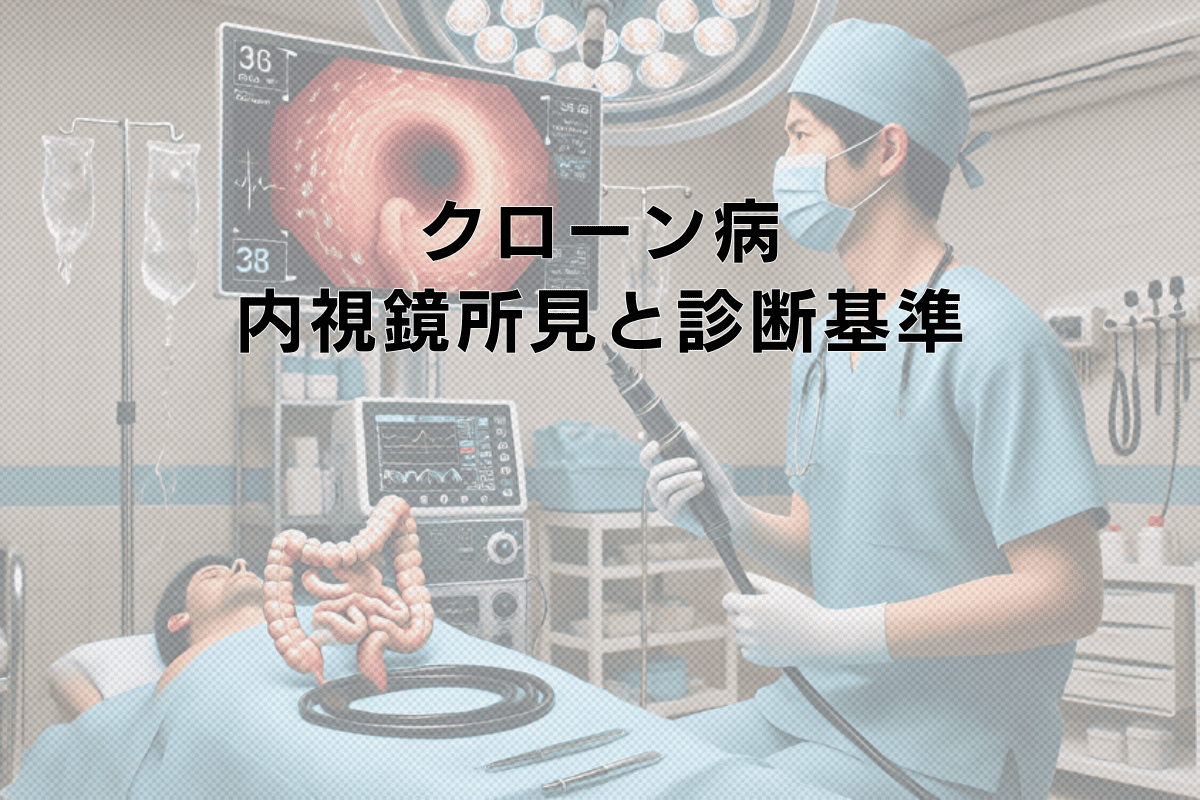
大腸がん・大腸ポリープ
大腸がんやポリープは、大腸の粘膜から生じる腫瘍であり、初期は自覚症状が少ないことが特徴で、腫瘍が大きくなると腸内を刺激し、便に血が混ざったり、下痢や便秘を繰り返したりすることがあります。
早期発見であれば内視鏡で治療することも可能なので、血便や異常な便通が続く場合は積極的に検査を検討すると安心です。

大腸がん・ポリープの特徴
| 項目 | 初期段階 | 進行段階 |
|---|---|---|
| 症状 | ほとんどなし | 血便、腹部不快感、体重減少 |
| 発見方法 | 内視鏡検査や便潜血検査 | 画像検査や組織検査 |
| 治療方法 | 内視鏡切除など | 外科的手術、化学療法 |
感染性腸炎
細菌やウイルスなどの感染によって腸が炎症を起こす感染性腸炎も、下痢と血が混じる症状の代表例で、サルモネラや腸管出血性大腸菌、ロタウイルスなど、原因となる病原体によって症状の強弱や合併症のリスクが異なります。
突然の激しい下痢や発熱を伴う場合は食中毒の可能性もあるため、水分補給を意識しながら医師の判断を仰ぐことが大切です。
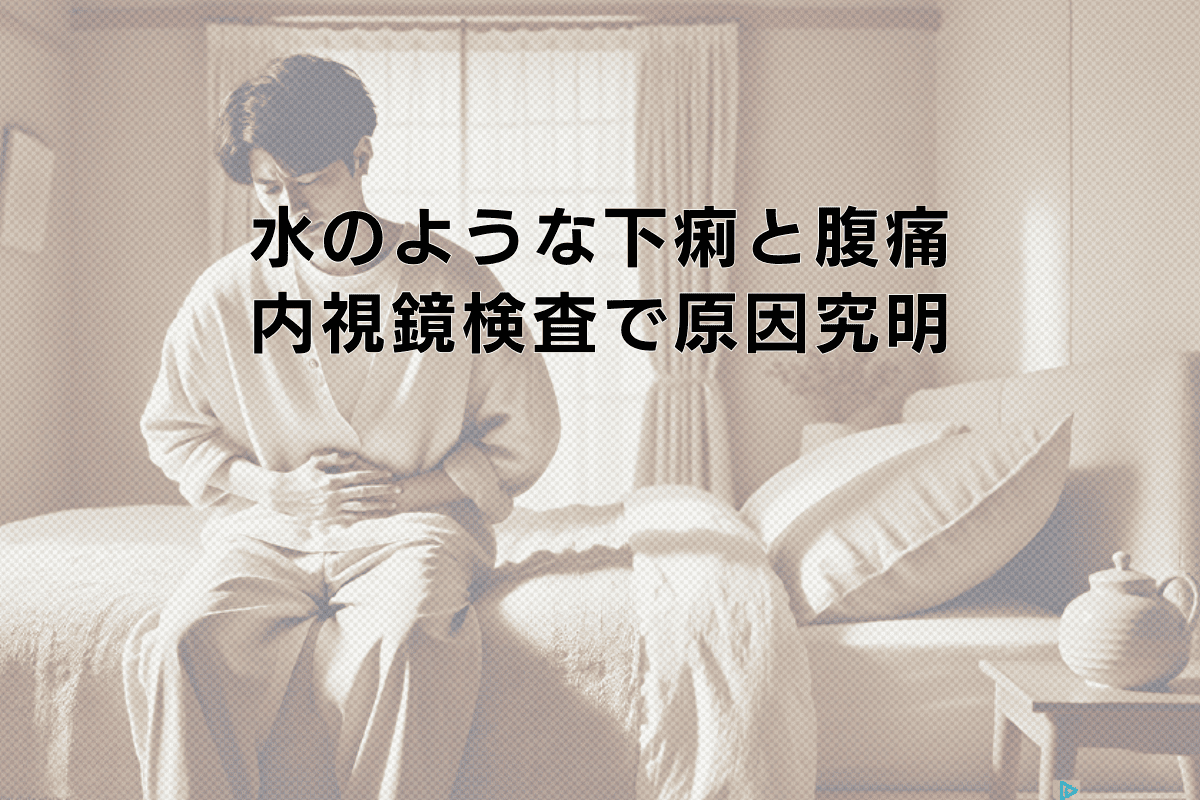
痔核や肛門裂傷
便に血液が混ざる原因として、痔核や肛門付近の裂傷も考えられます。硬い便や強いいきみなどで肛門周辺が傷つくと、わずかな出血が便に付着して見える場合があります。
ただし痔核や裂傷だけでは下痢を伴うことは少ないため、下痢が続き血が混じる状態が顕著な場合は他の疾患も並行して疑うべきです。
大腸内視鏡検査が必要になるタイミング
下痢や血便が断続的に続くと、腸粘膜のダメージが蓄積していくおそれがあります。医療機関での診察とともに行う大腸内視鏡検査は、粘膜の状態を直接観察しながら原因を特定できる有力な手段です。
症状が2~3日以上改善しない場合
急性のウイルス性腸炎や軽度の食あたりであれば、整腸剤を飲んだり水分補給を徹底したりすることで数日以内に下痢は落ち着く傾向があります。
それにもかかわらず、血が混じる症状が2~3日以上継続している場合は、大腸内視鏡検査を検討してください。検査によって腸粘膜の損傷の程度や炎症の範囲を把握できれば、早期治療の可能が高まります。

便潜血検査で陽性反応が出た場合
定期健康診断などで行う便潜血検査において陽性反応が出た場合、腸内出血が起こっている可能性が高く、下痢と血便の症状がある場合は、大腸ポリープや大腸がんをはじめとする重大な病変のリスクを慎重に考慮することが必要です。
便潜血検査で陽性なら、大腸内視鏡検査へ進みます。

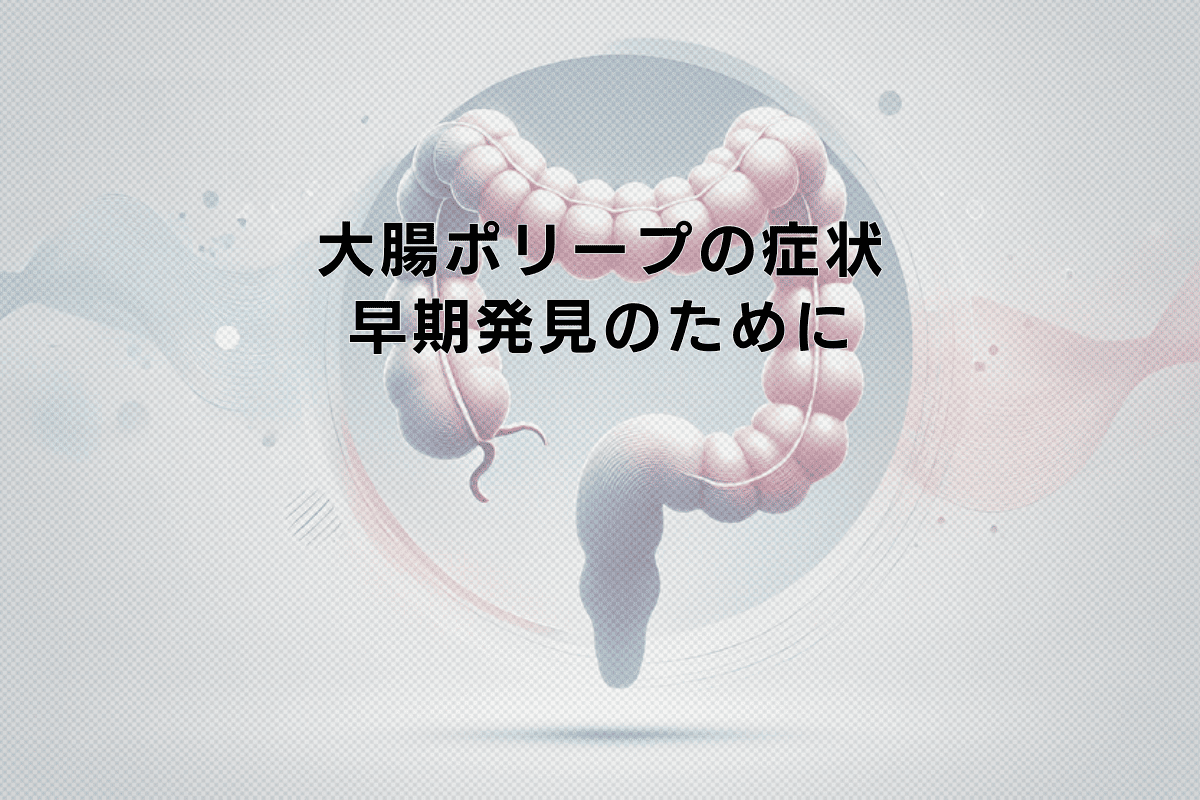
大腸内視鏡検査を考えるきっかけ
| きっかけ | 理由 | 対応策 |
|---|---|---|
| 便潜血陽性 | 腸内出血の存在 | 専門医による詳細検査 |
| 下痢と血便が長引く | 感染症以外の炎症や腫瘍の可能性 | 内視鏡で原因を直接確認 |
| 下腹部痛が続く | IBDなど慢性疾患の疑い | 組織生検で確定診断 |
40代以降の年齢層
大腸がんの発症リスクは40代以降から徐々に高まる傾向があり、若年層だからといって安心できるわけではありませんが、下痢と血便があり、年齢的に気になる方は、早めに検査を受けましょう。
大腸内視鏡検査による早期発見は、治療の選択肢を広げるうえでも大切です。
- 40代以降は年1回程度の健康診断に加え、消化器系の専門医による相談も検討する
- 家族に大腸がんやポリープの既往がある場合はリスクが高くなる
- 下痢と血便を感じたら放置せず受診する
家族歴や既往歴のある場合
炎症性腸疾患や大腸がん、ポリープなどの疾患には、家族や近親者との間で発症リスクに関係があると指摘されるケースがあります。
家族が若い年齢で消化器系の病気を経験している場合、少しでも下痢や血便の症状を感じたら早期検査に踏み切るのが望ましく、既往歴として胃や大腸に病変が見つかった経験がある方も同様に注意が必要です。
下痢と血便が見られる時の検査方法
下痢に血が混じる状態の原因を探るためには、多角的な検査の組み合わせが求められます。症状や既往歴を踏まえながら、血液検査や画像検査、大腸内視鏡検査などを行うことで、より正確な診断が可能です。
それぞれの検査方法の特徴を把握しておくと受診時に役立ちます。
血液検査と便検査
血液検査では炎症の程度、貧血の有無、肝機能や腎機能の評価など、全身状態を把握でき、便検査では細菌やウイルス、寄生虫の有無、潜血の程度などをチェックすることで、感染性腸炎や出血性疾患の可能性を検討します。
これらの検査によって、さらに踏み込んだ内視鏡検査が必要かどうかを総合的に判断する流れが一般的です。
主な血液・便検査の項目
| 検査項目 | チェック内容 | 意義 |
|---|---|---|
| 炎症反応(CRP) | 腸内炎症の程度 | 炎症性腸疾患を疑う |
| 貧血(Hb) | 血液量の指標 | 長期出血による貧血リスク |
| 便潜血 | 目に見えない血液の有無 | 大腸がんやポリープなどの出血 |
| 便培養 | 細菌やウイルスの増殖 | 感染性腸炎の判定 |
X線検査やCT/MRI
大腸内部の病変を詳細に見るには大腸内視鏡検査が有効ですが、前段階として腹部のX線検査やCT、MRIで大まかな位置や大きさ、腸管の形状変化を把握するケースがあります。
特に急性腹症の疑いがある場合、CTなどを使うことで腸に穴が開いていないか、重篤な合併症を起こしていないかを確認し、画像上で重大な所見があれば、緊急的に内視鏡検査を行う判断が下ることもあります。
大腸内視鏡検査
肛門から内視鏡を挿入し、大腸の内側全体を直接観察する検査が大腸内視鏡検査で、粘膜の炎症や潰瘍、ポリープ、腫瘍などを目視で確認でき、必要に応じて組織を一部採取する生検も行えるため、診断精度が高いのが利点です。
下痢と血便が続く原因を調べるには非常に有力な検査方法になります。
- ポリープが見つかった際は、その場で切除できる場合もある
- 潰瘍の範囲や深さを正確に評価できる
- 検査前に腸内洗浄剤を使用し、腸内をきれいにする準備が必要になる
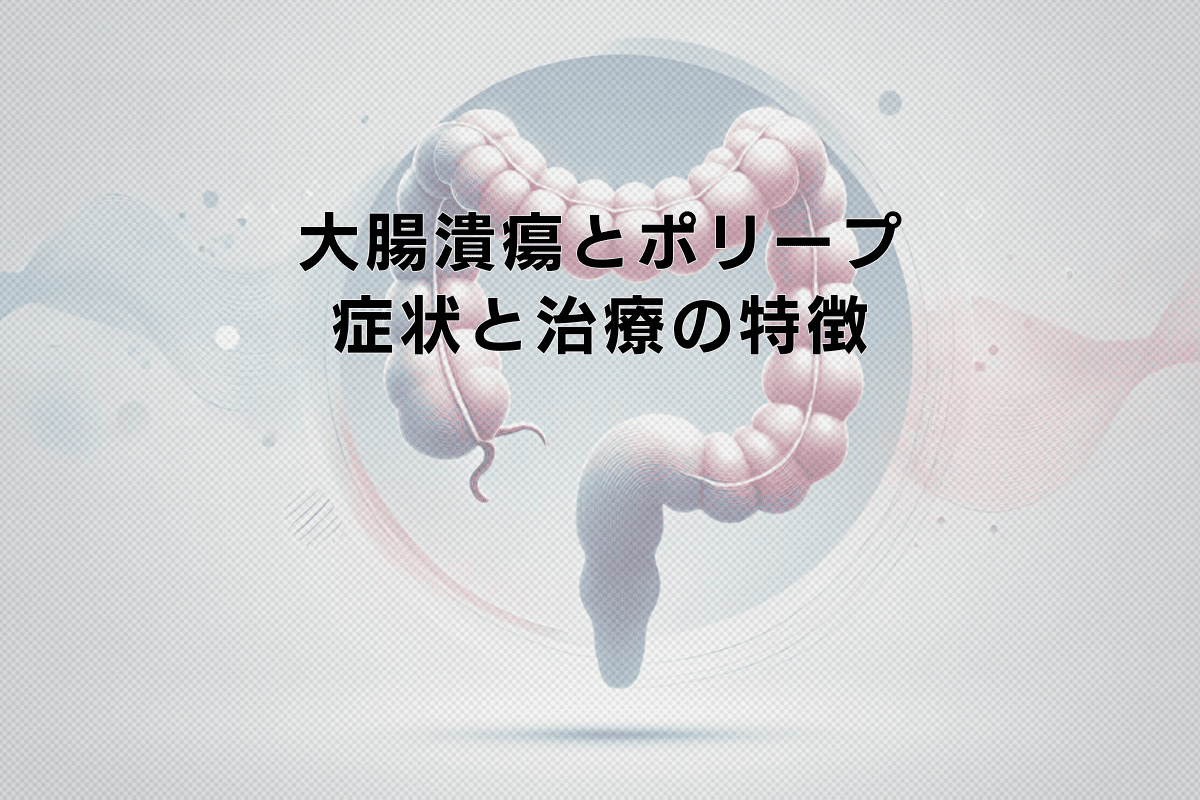
大腸内視鏡検査の実施手順
| 手順 | 内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 前処置 | 下剤や腸洗浄剤を使用し腸をきれいにする | 視野確保と正確な観察 |
| 検査中 | 内視鏡を挿入し大腸内を直接観察 | 炎症やポリープの発見 |
| 生検 | 異常部位の一部を採取 | 病理検査で病変の性質を判断 |
| 切除 | ポリープなどを発見した場合、内視鏡で切除 | 病変の治療と進行防止 |
組織生検による確定診断
大腸内視鏡検査で発見した炎症部位やポリープから組織を採取し、病理検査で確定診断を行う方法も下痢と血便の原因解明には大切です。
肉眼ではわからない細胞レベルの情報が得られるため、悪性か良性か、炎症性疾患か感染症かなどを正確に区別できます。
大腸内視鏡検査による原因特定の流れ
大腸内視鏡検査を受ける前後の流れを知っておくと、検査への不安が軽減します。下痢に血が混じる場合など、原因を突き止めたい方は、準備や検査当日の手順、検査後の経過観察を把握しておくと心に余裕が生まれます。
事前問診と前処置
大腸内視鏡検査を行う前には、生活習慣や服用薬の有無、アレルギー歴などを確認するための問診を受け、高血圧や心臓病、糖尿病の治療中の場合は、服薬の調整が必要になることがあります。
また、検査の2~3日前から食事制限を始める場合があり、前日や当日には腸内洗浄剤を飲んで腸を空っぽにする作業が大切です。
- 胃腸に負担の少ない食事を心がける
- 前処置のスケジュールに従う
- 規定の時間までに水分をしっかりとる
前処置の注意点
| ポイント | 理由 | 具体例 |
|---|---|---|
| 食事制限 | 大腸内の残留物を減らす | 消化の良いお粥やスープ中心 |
| 腸洗浄剤の使用 | 視野を確保しやすくする | 下剤を時間通りに摂取 |
| 服薬の調整 | 検査時の安全確保 | 医師の指示に従って休薬の判断 |

検査当日の流れ
検査当日は医療機関に到着してから、あらためて体調チェックや血圧測定、検査室での準備などを行い、鎮静剤を使用することが多いため、検査中の痛みや不快感が軽減される場合が多いです。
内視鏡が肛門から挿入され、大腸の粘膜をモニターで確認し、異常があれば組織採取やポリープ切除をすることがあり、検査時間は個人差がありますが、概ね20~30分程度で終了します。
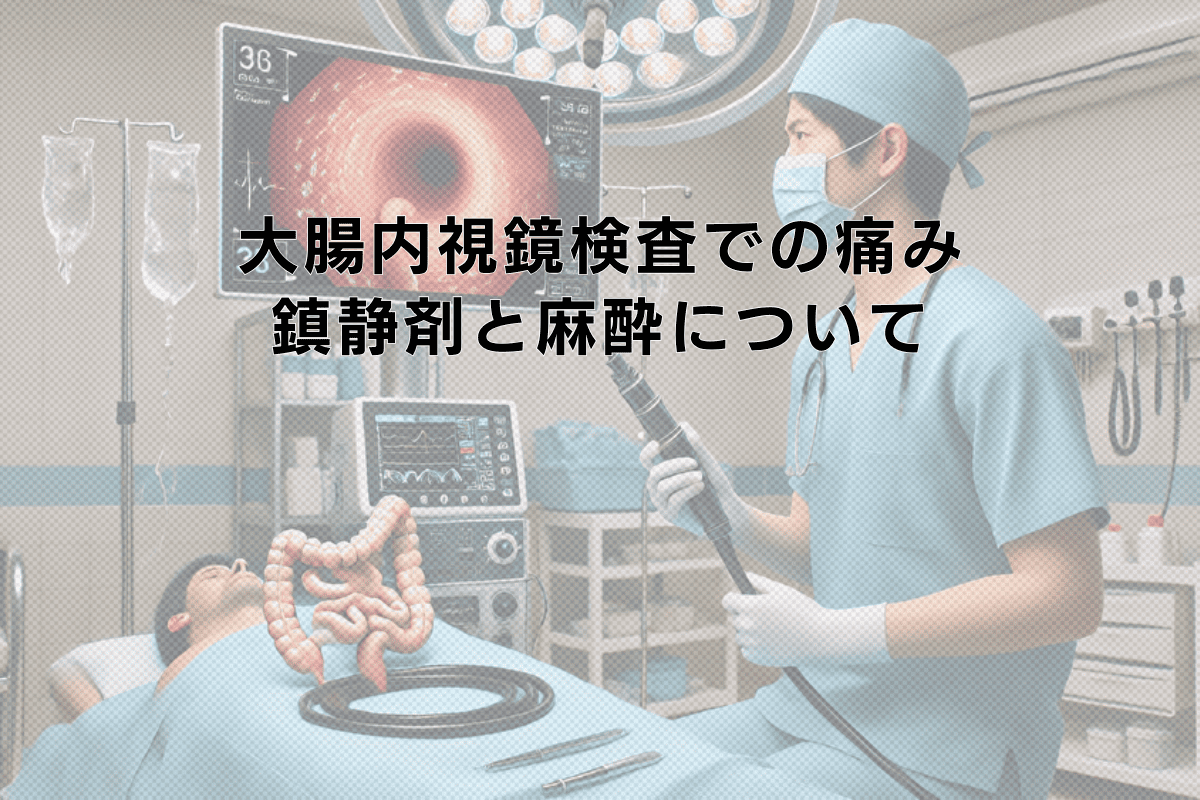
検査後の経過観察
鎮静剤の影響が残るため、検査後は回復室や待機スペースで一定時間休息します。腹部にガスが溜まりやすく、おなかの張りを感じることがありますが、徐々に軽減します。
ポリープ切除などの処置を行った場合は、出血リスクを考慮して食事や運動を数日間控えるように指示を受けることがあり、下痢と血便が原因で検査を受けた方は、術後も症状の変化に注意を払いましょう。
- 水分補給はこまめに行う
- 術後しばらくは激しい運動を避ける
- 体調に異変を感じたら医療機関に連絡を入れる
検査後の注意点
| 注意点 | 理由 | 具体的な対策 |
|---|---|---|
| 腹部の張り | 内視鏡検査で空気を入れるため | ガスを排出しやすいようリラックス |
| 出血リスク | 生検やポリープ切除による傷 | 便に血がついていないか観察 |
| 体調の変化 | 鎮静剤の影響や消化器への刺激 | ゆっくり休んで回復を待つ |
検査結果のフィードバック
検査結果は医師から直接説明を受けることになり、ポリープや炎症部位が見つかった場合、その場で写真やモニター映像をもとに説明を受けることが多いです。
生検を行った場合は、病理検査の結果が数日~2週間程度で判明し、それによって治療方針が決まり、下痢と血便の原因が明確になったら、治療へと移行します。
血便を伴う下痢の治療と予防
下痢と血便の主原因が特定できたら、状態に応じた治療をスタートします。治療法は原因疾患によって異なるため、自己判断で市販薬を使うだけでは改善しないケースが多々あります。
加えて、再発を防ぐための日常生活の工夫や定期的な検査も大切です。
原因別の治療法
炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎、クローン病)
薬物療法で炎症を抑えることが中心で、状況によっては免疫調整薬やステロイドを活用し、寛解を目指します。重症の場合は手術を検討する場合もあります。
大腸ポリープ・大腸がん
大腸内視鏡検査で発見したポリープは、大きさや形態によって内視鏡切除が選択肢に上がります。がんが疑われる場合は、外科的切除や化学療法など多岐にわたる治療方針を検討します。
感染性腸炎
病原体に応じて抗生物質や整腸剤を使い、脱水予防のため十分な水分と電解質補給を行います。下痢と血便の症状が強い時は入院加療が必要なこともあります。
日常生活で気をつけたい点
下痢と血便の症状が改善しても、生活習慣が乱れると再発リスクが高まる可能性があるので、消化器に負担をかけすぎず、胃腸の調子を整える工夫が肝心です。
- バランスの良い食事を心がける
- アルコールや刺激物を控える
- 規則正しい睡眠と適度な運動を行う
胃腸にやさしい食材
| 食材 | 特徴 | 摂取のメリット |
|---|---|---|
| おかゆ・うどん | 消化しやすい炭水化物 | 腸への刺激が少ない |
| 豆腐・白身魚 | 良質なたんぱく質 | 胃腸に負担がかかりにくい |
| りんご・バナナ | 食物繊維とビタミン | 腸内環境を整えやすい |
| ヨーグルト | 乳酸菌が豊富 | 腸内細菌のバランス維持 |
再発予防と定期検査
炎症性腸疾患やポリープがある場合、症状が落ち着いていても定期的に内視鏡検査を受けることが望ましく、再発や新たな病変の発見が遅れると、治療機会を失う恐れがあります。
年齢が上がるにつれて大腸の病変リスクが増えるため、状態が落ち着いているときこそ検診を活用すると安心です。
- 症状が落ち着いていても半年~1年に1回の検診を検討する
- 新たな下痢や血便を感じたらすぐに医療機関へ相談する
- 家族歴や既往歴がある場合は短い周期で検査を受ける
再発リスク管理
| ポイント | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 定期受診 | 寛解後も経過観察 | 年に数回の内視鏡検査 |
| 自己観察 | 便通や体調変化の記録 | 発熱や腹痛も見逃さない |
| 生活習慣 | ストレス管理や睡眠の確保 | 喫煙や過度な飲酒を避ける |
予防に役立つ健康習慣
下痢と血便が続くと、腸の粘膜がダメージを受け、栄養吸収や免疫機能にも悪影響が及ぶことがあり、普段から腸内環境を整える習慣を身につけるとともに、ストレスをためず体を冷やさない工夫なども心がけると良い方向に導きやすいです。
十分な水分摂取と適度な食物繊維の摂取も腸に良い影響を与えます。
よくある質問
下痢に血が混じる症状や大腸内視鏡検査に対して、不安や疑問を抱く方は多くいます。よく寄せられる質問をいくつか取り上げ、それに対する考え方や対処法を紹介します。
- 検査は痛みを強く感じますか?
-
個人差はありますが、鎮静剤を使用するケースが多いため、強い痛みを感じる方は少ないです。
腸管にガスを入れる際におなかの張りを感じることがありますが、医師や看護師が観察しながら進め、安全面にも配慮されているので、痛みが心配な場合は遠慮せず相談し、鎮静方法を検討してもらいましょう。
- 大腸内視鏡検査の準備は大変なのでしょうか?
-
検査当日の前処置では腸洗浄剤を飲んで大腸を空にする作業が必要です。味や量に苦労する方もいますが、視野をしっかり確保するために大切な手順となります。
途中で気分不良などを感じたら無理をせず医療スタッフに伝え、自宅で前処置を行う場合は、トイレ環境を整えておくこともポイントです。
- 病変が見つかった場合、その場で切除できますか?
-
ポリープが小さく切除可能な状態であれば、内視鏡を使って同時に処置を行うことがあり、生検と呼ばれる組織採取であればより簡単に行えます。
ただし、病変が大きかったり、形状や位置が難しい場合は、一度検査だけで状況を確認し、後日あらためて切除の手術をすることがあります。
- 下痢と血便の症状が落ち着いているときも検査を受けるべきですか?
-
症状が落ち着いているからこそ内視鏡検査を受けやすいタイミングで、炎症性腸疾患などは一時的に症状が消えても、再燃のリスクを常に抱えています。
定期的な検査で腸内をチェックし、再発や新たな病変を見逃さないようにすることが重要です。
次に読むことをお勧めする記事
【大腸内視鏡検査とはどのような検査なのか】
血便と下痢の原因について理解が深まったら、次は実際の大腸内視鏡検査がどのようなものか知っておくと安心です。検査を検討されている方に特に参考になる内容です。
【潰瘍性大腸炎とは|症状と内視鏡検査による診断】
血便を伴う下痢に関連する疾患として、潰瘍性大腸炎の特徴や診断方法について詳しく学べる内容です。
参考文献
Kinoshita Y, Ariyoshi R, Fujigaki S, Tanaka K, Morikawa T, Sanuki T. Endoscopic diagnosis of chronic diarrhea. DEN open. 2022 Apr;2(1):e53.
Nagata N, Ishii N, Manabe N, Tomizawa K, Urita Y, Funabiki T, Fujimori S, Kaise M. Guidelines for colonic diverticular bleeding and colonic diverticulitis: Japan Gastroenterological Association. Digestion. 2019 Jan 14;99(Suppl. 1):1-26.
Nagata N, Kobayashi K, Yamauchi A, Yamada A, Omori J, Ikeya T, Aoyama T, Tominaga N, Sato Y, Kishino T, Ishii N. Identifying bleeding etiologies by endoscopy affected outcomes in 10,342 cases with hematochezia: CODE BLUE-J Study. Official journal of the American College of Gastroenterology| ACG. 2021 Nov 1;116(11):2222-34.
Tada M, Shimizu S, Kawai K. Emergency colonoscopy for the diagnosis of lower intestinal bleeding. Gastroenterologia Japonica. 1991 Jul;26(Suppl 3):121-4.
Holtz LR, Neill MA, Tarr PI. Acute bloody diarrhea: a medical emergency for patients of all ages. Gastroenterology. 2009 May 1;136(6):1887-98.
Corinaldesi R, Stanghellini V, Barbara G, Tomassetti P, De Giorgio R. Clinical approach to diarrhea. Internal and emergency medicine. 2012 Oct;7:255-62.
Bardhan PK, Beltinger J, Beltinger RW, Hossain A, Mahalanabis D, Gyr K. Screening of patients with acute infectious diarrhoea: evaluation of clinical features, faecal microscopy, and faecal occult blood testing. Scandinavian journal of gastroenterology. 2000 Jan 1;35(1):54-60.
Brandt LJ. Bloody diarrhea in an elderly patient. Gastroenterology. 2005 Jan 1;128(1):157-63.
Shah RJ, Fenoglio-Preiser C, Bleau BL, Giannella RA. Usefulness of colonoscopy with biopsy in the evaluation of patients with chronic diarrhea. The American journal of gastroenterology. 2001 Apr 1;96(4):1091-5.
Burgers K, Lindberg B, Bevis ZJ. Chronic diarrhea in adults: evaluation and differential diagnosis. American family physician. 2020 Apr 15;101(8):472-80.