慢性的に下痢が続くと、日常生活の質が下がるだけでなく、大腸や小腸の炎症や病変が潜んでいる可能性があり、「ただの腹痛」と放置すると、病状の進行を見落とすかもしれません。
原因を特定するためには、問診や各種検査に加え、内視鏡検査による早期診断が非常に重要です。
検査を受けて原因を把握し、身体への負担を軽くするためにも、早めの受診を検討してください。
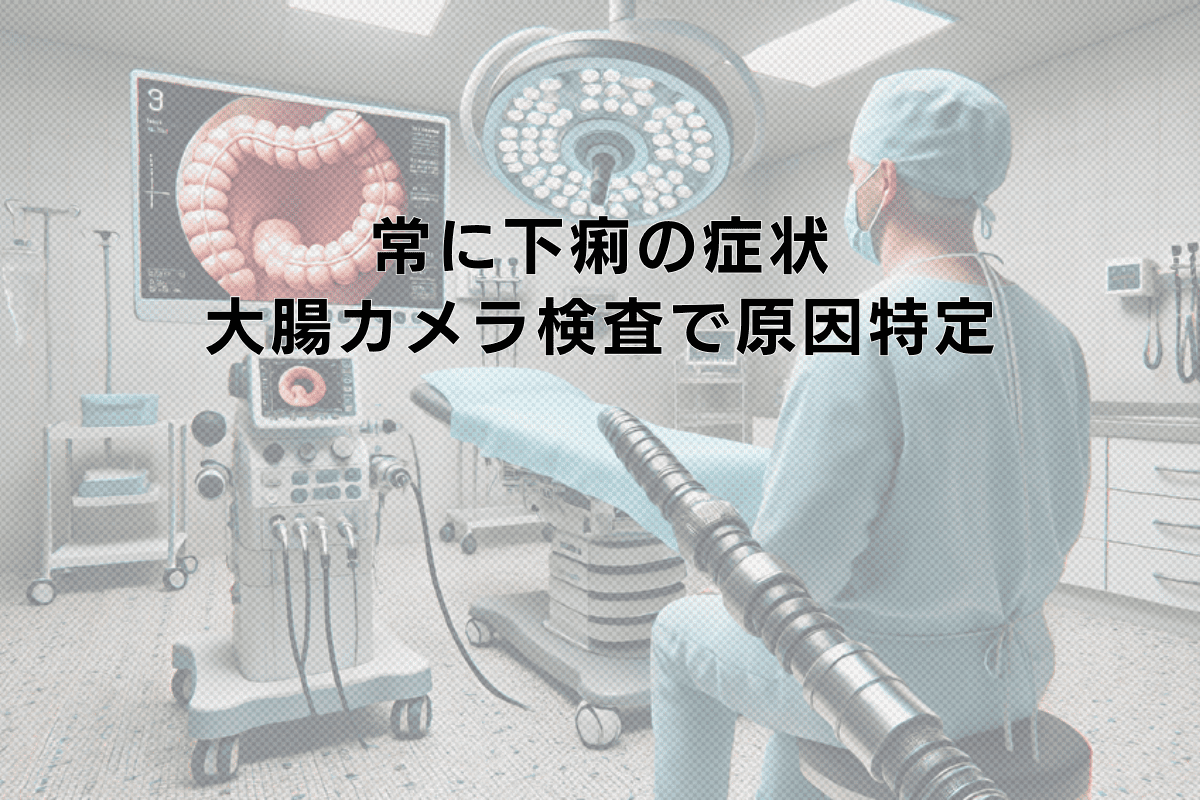
下痢が続く状態とは何か
長引く下痢に悩む方は少なくありません。頻繁にトイレへ行く必要性や腹痛による不安感が生じるため、日常生活に大きな支障をきたすことがあります。
短期間ならまだしも、数週間以上にわたって下痢が続く場合は、単なる体調不良以上の要因がある可能性があります。
下痢が続く状態の定義
医療の分野では、下痢の期間が2~3日程度でおさまる「急性下痢」と、4週間以上続く「慢性下痢」に分けることがあります。
短期間で症状が治まる急性下痢は、ウイルスや細菌の一時的な感染が原因として多いです。
長期間にわたって下痢が続く場合は、過敏性腸症候群や腸内の炎症性疾患、あるいは甲状腺機能亢進症などの内分泌異常まで、多岐にわたる原因が考えられます。
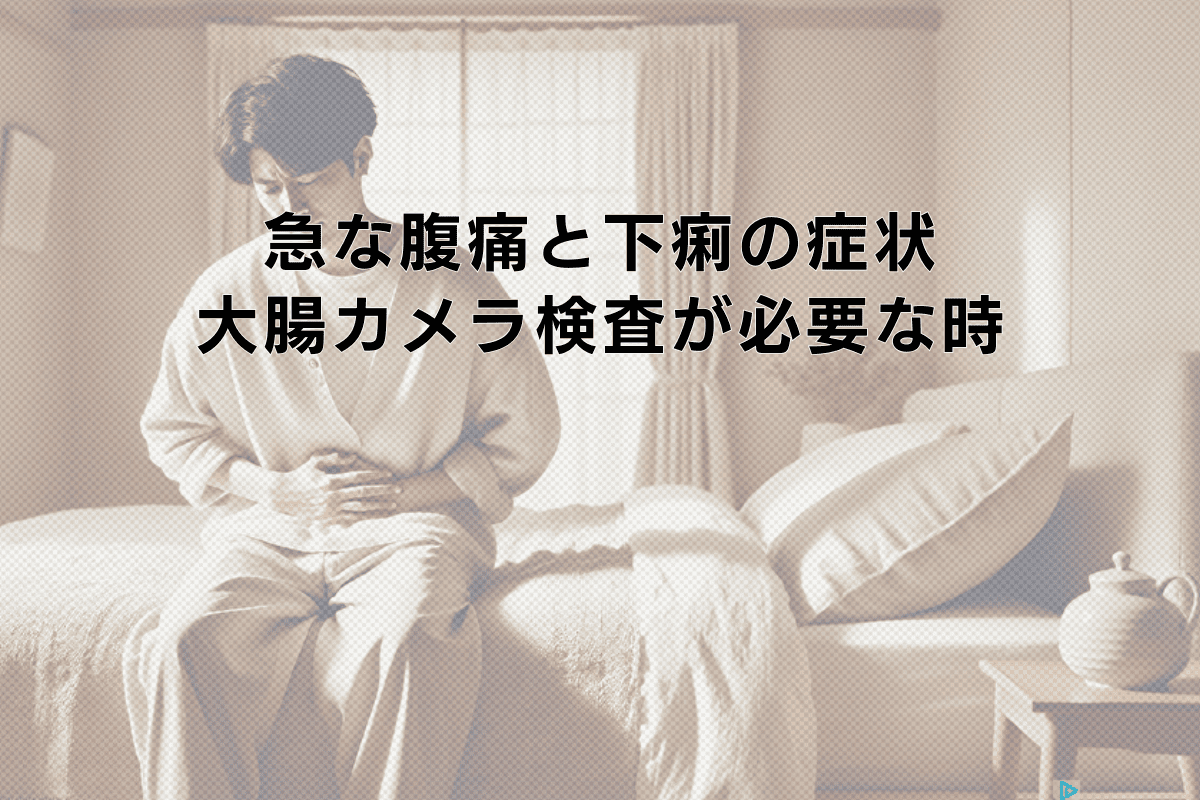
日常生活への影響
続く下痢は、身体的な負担だけでなく、精神面や社会生活面への影響をもたらします。
- 出かける際に常にトイレの場所を気にしなければならない
- 腹部の痛みや不快感により外出や仕事を躊躇してしまう
- 長時間の移動や会議などが精神的に大きなストレスになる
- 睡眠不足や食欲不振につながり、栄養状態の悪化を招く
長期的にこうした状態が続くと、体力のみならず、生活の質そのものが落ちていきます。
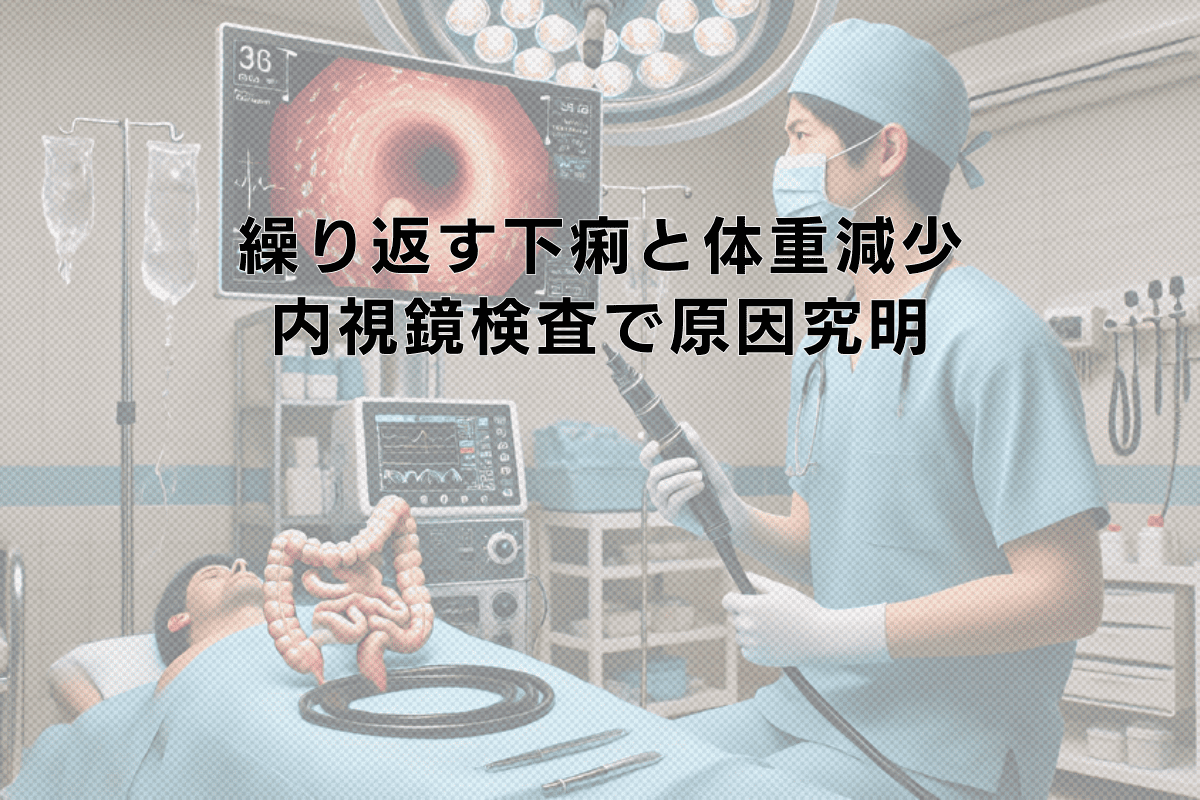
治療の方向性を決めるための視点
下痢に対して、整腸薬の使用などで一時的に対処できることがありますが、原因を突き止めないままでは再発や悪化のリスクが残ります。
慢性的に下痢が続くときは、症状を緩和させるだけでなく、何が下痢の原因になっているのかを正確に捉えることが大切です。内視鏡検査はそのために重要な検査手段です。
症状が続くときに相談すべき専門科
内科の中でも、消化器領域を扱う医師が下痢の原因を突き止めるための診断・治療を行います。
胃カメラや大腸カメラなどの内視鏡検査を通じて、粘膜の状態を直接確認することができるため、まずは消化器内科や胃腸内科へ相談するとよいでしょう。
長期下痢と関連が深い主な要因
| 要因 | 主な例 | 特徴 |
|---|---|---|
| 炎症性腸疾患 | 潰瘍性大腸炎、クローン病 | 血便や粘液便、体重減少が起こりやすい |
| 感染症 | 細菌性赤痢、結核など | 発熱や脱水を伴うことがある |
| 過敏性腸症候群 | IBS(下痢型、便秘型、混合型) | 腹痛と便通異常が慢性的に反復する |
| 内分泌異常 | 甲状腺機能亢進症など | 発汗や動悸、体重減少などの症状も伴う |
| 食物アレルギー・不耐症 | 乳製品・グルテンなど | 食事内容との関連性が強い |
| 薬剤性 | 抗生物質、下剤の過剰使用など | 投与歴の確認が必須 |
下痢が続く要因は多岐にわたるので、自己判断や市販薬のみで対処するのは避け、専門医の診察を受けて詳細な検査を検討してください。
下痢の原因に隠れる代表的な疾患とその特徴
下痢の背景には、思いもよらない疾患が隠れているかもしれません。体調不良と軽く捉えると、治療のタイミングを逸するリスクがあります。
過敏性腸症候群(IBS)の特徴
過敏性腸症候群は、腸内環境の乱れやストレスなどが関係し、慢性的な腹痛や下痢・便秘を繰り返す病気です。腸の検査を行っても明らかな器質的異常が見つからない場合が多いものの、症状は日常生活に大きな影響を与えます。
- 腹痛が食後に強まる
- トイレに行ったあとに腹痛がやや落ち着く
- ストレスが高まると下痢が悪化しやすい
ストレスケアや食事の見直しなどで改善が見込める一方、自己流の対策では限界があるため、医師に相談したうえで内視鏡検査を検討したほうが安心です。
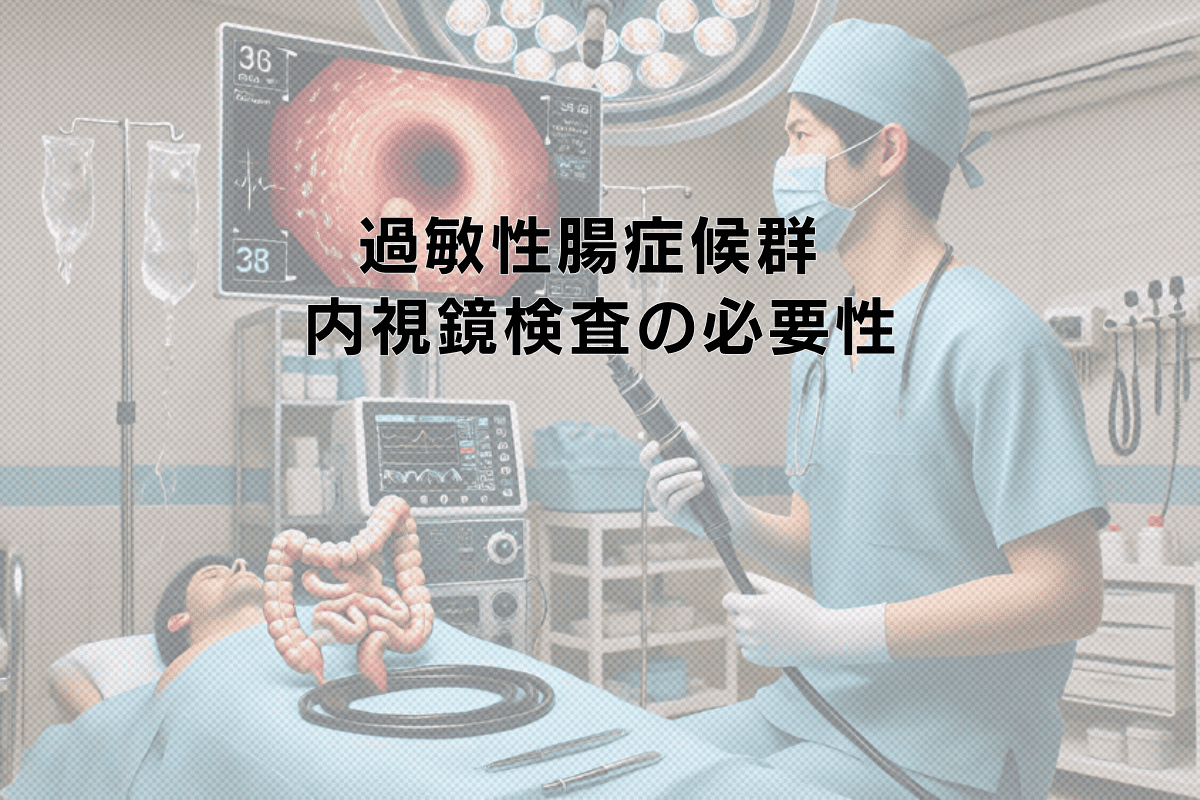
潰瘍性大腸炎やクローン病といった炎症性腸疾患
炎症性腸疾患の代表例として知られる潰瘍性大腸炎やクローン病は、腸粘膜に慢性的な炎症が起こる疾患で、粘膜の状態を把握するには大腸カメラが有力な手段です。
- 潰瘍性大腸炎:大腸粘膜表層にびらんや潰瘍が発生し、血便や腹痛が起こりやすい
- クローン病:口から肛門まで消化管のあらゆる部分に炎症が広がる可能性がある
治療には、免疫調整薬やステロイド薬などが用いられる場合がありますが、早い段階での診断が治療の方向性に大きく関わります。

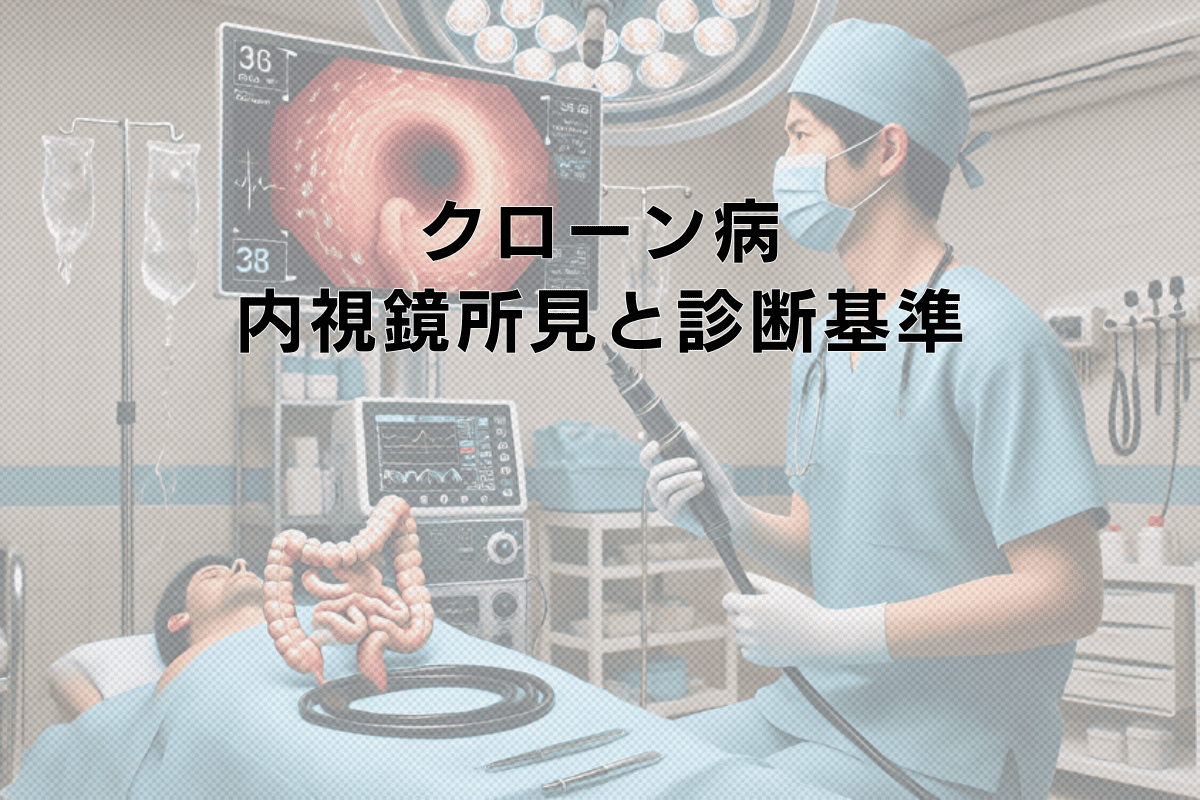
感染症と継続的な下痢
細菌やウイルス感染による下痢は、急性で強い症状を起こすイメージがありますが、一部の感染症は潜伏期間が長かったり、体力や免疫力の低下に伴い慢性化したりすることもあり、数週間にもわたって下痢が続くケースがあります。
実際には血液検査や便の培養検査、内視鏡検査を組み合わせて原因を追究します。
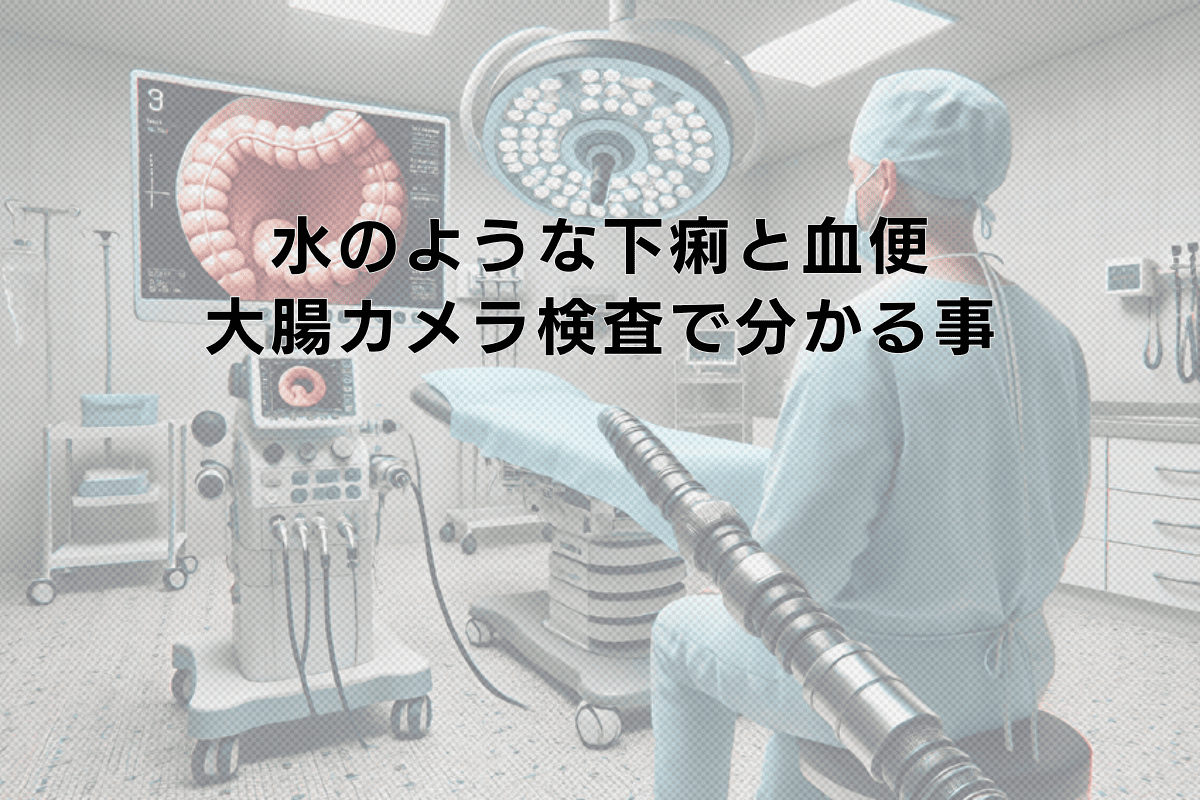
内分泌系疾患との関連
甲状腺機能亢進症や副腎疾患など、内分泌系の異常も下痢を誘発する要因です。甲状腺機能亢進症では、腸の動きが活発になりすぎて便の回数が増えたり、体重減少や動悸、発汗過多といった症状がみられることがあります。
これらの異常を見逃さないためには、血液検査に加えて内視鏡検査で腸粘膜の状態を調べることも重要です。
慢性下痢の主な疾患の特徴
| 疾患名 | 症状の特徴 | 主な検査 |
|---|---|---|
| 過敏性腸症候群 | 腹痛や下痢・便秘を繰り返す | 大腸カメラ、血液検査 |
| 潰瘍性大腸炎 | 粘液便や血便、腹痛 | 大腸カメラ、血液検査 |
| クローン病 | 全消化管にわたる潰瘍や狭窄 | 大腸カメラ、小腸内視鏡(カプセルなど) |
| 細菌・ウイルス感染 | 発熱や脱水症状を伴うことがある | 便培養検査、血液検査、大腸カメラ |
| 甲状腺機能亢進症 | 動悸、発汗、体重減少、頻回の便通 | 血液検査、超音波検査、大腸カメラ |
身体のどの部位に原因があっても、長期にわたり下痢が続くなら腸の様子を直接見ることが有効で、放置せず、早期に専門家へ相談しましょう。
大腸カメラ検査が果たす重要な役割
下痢が続く原因を調べるうえで、大腸カメラによる内視鏡検査は重要度が高く、腸の内側を直接観察することで、出血や炎症、潰瘍、ポリープなどを確認できます。
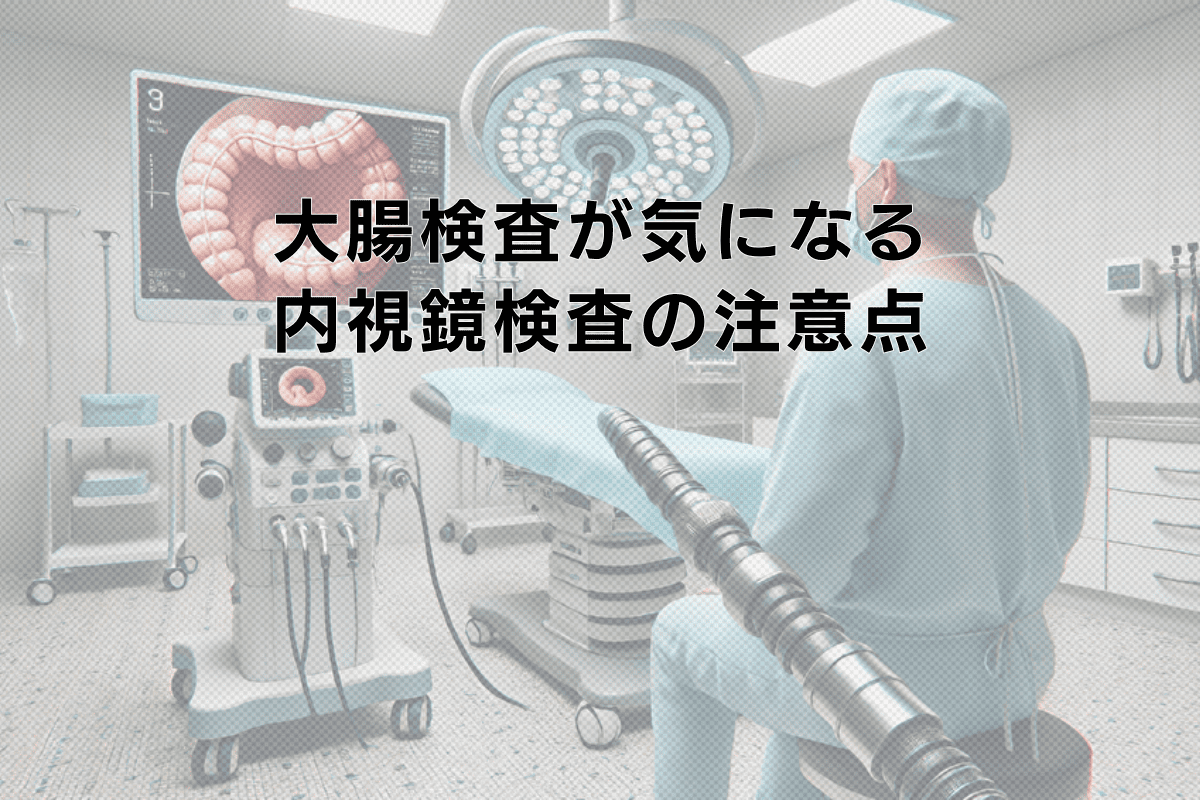
大腸カメラ検査の基本的な流れ
大腸カメラ検査は、専用の内視鏡を肛門から挿入し、大腸全体を映像で観察する手技で、検査前には腸内をきれいにするための下剤を飲みます。
空腹の状態で検査を行うため、検査当日朝から飲食を控えることが多いです。鎮静剤を使用する場合もあり、痛みや不安をやわらげながら実施します。
大腸カメラでわかること
腸の粘膜に小さな潰瘍やびらんがある場合、早期に発見できるのが大腸カメラの強みです。病変の一部を切り取って組織検査を行う「生検」によって、炎症の程度や悪性細胞の有無を調べることもできます。
単なる下痢だけではなく、大腸がんやポリープなどの早期診断にもつながります。
検査前後の注意点
大腸カメラ検査を受ける際には、医師の指示に従った事前準備が重要です。下剤の使用や水分摂取の管理などを行わないと、腸内に残渣が残って正確な観察が困難になります。
また、検査後は一時的に腸内に空気を入れているため、お腹の張りや違和感が残ることがあります。数時間程度で解消することが多いですが、異常を感じた場合は速やかに医療機関へ連絡してください。
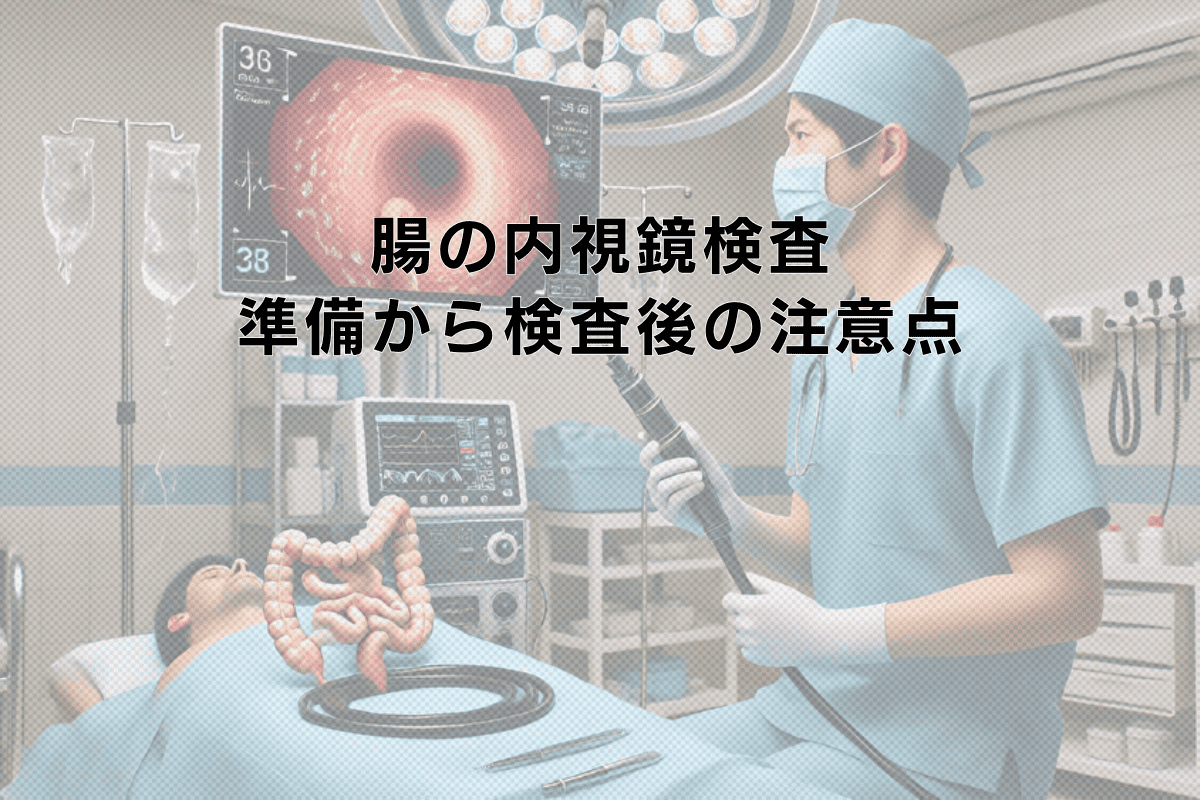
大腸カメラに関する疑問
| 疑問 | 回答 |
|---|---|
| 痛みは強いのか | 鎮静剤を使用して緩和できる場合が多い |
| 準備にはどれくらい時間がかかる | 下剤の服用や食事制限を含め、検査前日から注意が必要 |
| 日常生活に影響はあるのか | 検査当日は食事制限や鎮静剤の影響で安静が望ましい |
| 検査費用はどの程度か | 保険診療適用の場合と自費診療で異なるため確認が必要 |

検査に対して不安を強く感じる方がいますが、適切な説明を受けたうえで臨めば、安全に実施できます。
胃カメラ検査を併用する意義
下痢が続く原因は大腸だけにあるとは限りません。胃や小腸の一部が関係するケースもあるため、医師が必要だと判断した場合は、胃カメラ検査もあわせて行う場合があります。

胃や十二指腸のトラブル
胃や十二指腸に潰瘍があると、腸の運動機能が乱れやすくなり、下痢につながることもあり、とくにピロリ菌感染が背景にある場合、胃痛を自覚していなくても便通異常を訴えるケースがあります。
胃カメラ検査で病変を確認できれば、除菌治療などで下痢の軽減が期待できます。
セリアック病や小腸トラブル
セリアック病のように、小腸の粘膜がグルテンに対して過敏に反応することで消化吸収障害を起こし、下痢が長期間にわたって続くことがあります。胃カメラでは十二指腸まで観察でき、生検によって粘膜の状態を把握することが可能です。
胃カメラ検査での観察
| 観察箇所 | 重要な所見 |
|---|---|
| 食道 | 食道炎、びらん、逆流性食道炎など |
| 胃 | 潰瘍、びらん、ポリープ、ピロリ菌感染の可能性 |
| 十二指腸 | 潰瘍、腫瘍、セリアック病に伴う絨毛萎縮など |
下痢と直接関係ないように思える部位でも、連動して便通に影響を及ぼすことがあります。
胃カメラと大腸カメラを同日に行うメリット
内視鏡検査を同日に行うと、検査のための絶食期間や鎮静剤の使用回数をまとめられるため、患者さんの身体的負担が減りますが、医療機関によって対応が異なるため、担当医と相談しながら選ぶとよいでしょう。
胃・大腸の内視鏡検査に関する主な比較
| 項目 | 胃カメラ | 大腸カメラ |
|---|---|---|
| 挿入経路 | 口(または鼻)から挿入 | 肛門から挿入 |
| 検査対象 | 食道・胃・十二指腸 | 大腸全体 |
| 前処置 | 6~8時間程度の絶食、水分摂取制限 | 下剤による腸内洗浄、食事制限 |
| 検査時間 | 数分~10分程度の場合が多い | 15~30分程度 |
| 検査後の負担感 | のどの違和感、鈍痛など | 腹部膨満感、ガス溜まりなど |
同時実施を検討する際は、体力面や予定を踏まえて決めることが大切です。
内視鏡検査を受けるタイミングと注意点
下痢が続く方の中には、「検査が大げさではないか」と迷う方もいるかもしれませんが、次のような兆候がある場合は、早めに内視鏡検査を考えることが必要です。
内視鏡検査を検討したほうがよい症状
- 血便や粘液便がみられる
- 腹痛のために仕事や家事がままならない
- 体重の減少が目立つ
- 下痢の頻度が増え、トイレから離れづらい
- 食欲不振や倦怠感が続いている
下痢が続く原因がはっきりしないまま我慢していると、重大な疾患を見逃す可能性があります。
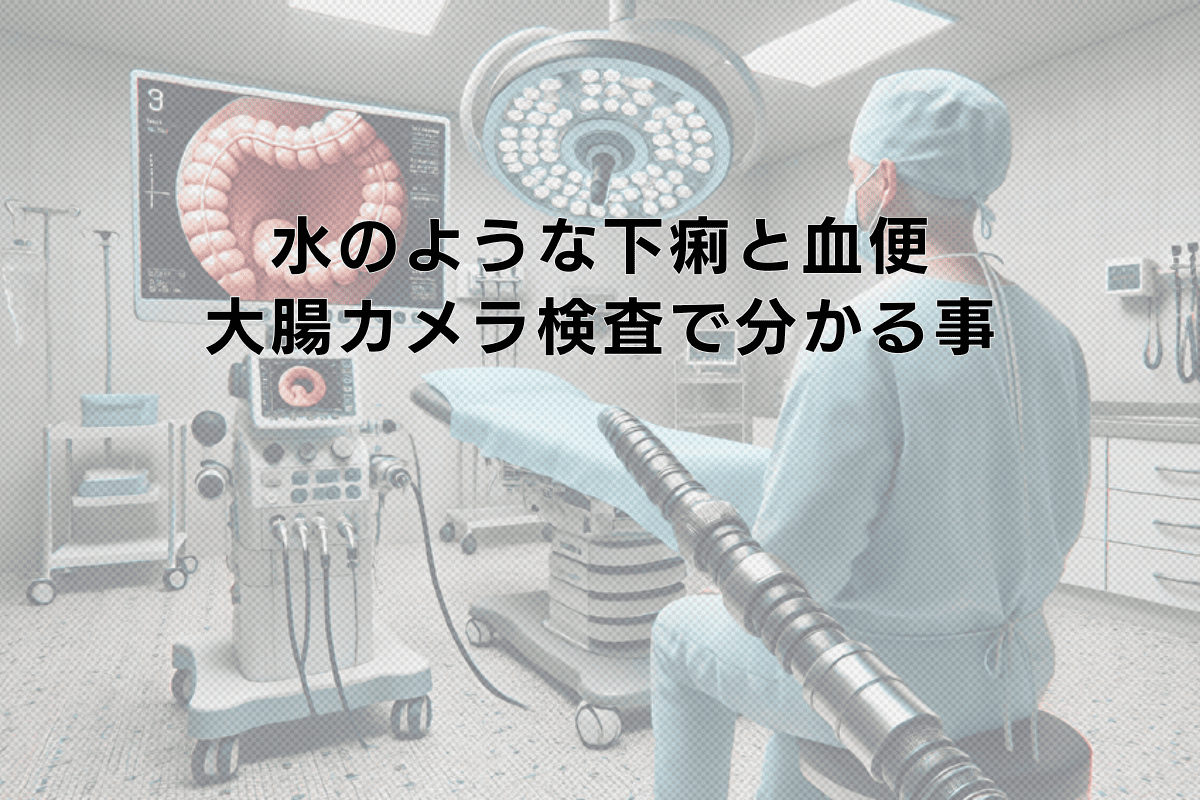
生活習慣の見直しと受診の目安

便通異常がありながらも、過度なダイエットや偏った食事をしているケースは少なくありません。まずは塩分・水分・バランスのとれた食事に留意することも大切です。
それでも下痢が改善しない場合は、医師の診断に基づいた早期の内視鏡検査を検討しましょう。
消化器内科を受診する際の準備事項
- 日頃の食事内容や生活習慣をメモしておく
- 下痢の回数や便の性状(液状・粘液・血液混入など)を記録しておく
- 体重や体温を定期的に測定し、推移を把握しておく
- 現在飲んでいる薬(市販薬含む)やサプリメントの種類を整理しておく
こうした情報があると、医師が診断の方針を立てやすくなります。
受診時に役立つ情報整理の方法
| 項目 | 具体例 |
|---|---|
| 食事内容 | 朝食・昼食・夕食、それぞれのメニューと時間 |
| 便の状態 | 1日の排便回数、便の硬さや色、血液混入の有無など |
| 体調変化 | 発熱、腹痛の程度、吐き気など |
| 服用薬 | 病院から処方された薬、市販薬、健康食品の名称と量 |
| ストレス要因 | 仕事の変化、人間関係、睡眠不足など |
事前に整理しておくと、医師への説明がスムーズに進みます。
大腸カメラ・胃カメラ検査を受けるメリットとリスク
内視鏡検査が大切とはいえ、不安がある方もいると思います。安心して検査を受けるために、メリットとリスクを事前に知っておくとよいでしょう。
メリット
- 腸や胃の粘膜を直接観察できるため、軽微な病変を見逃しにくい
- 生検を行うことで、悪性の可能性や炎症の程度を調べられる
- 病変が見つかった際に、その場でポリープ切除などが可能な場合がある
- 早期に治療方針を立てることで、長引く症状の改善につなげられる
リスク
- 内視鏡の挿入に伴う痛みや不快感
- ごくまれに穿孔や出血などの合併症
- 鎮静剤の副作用(ふらつき、血圧低下など)
- 検査後に数時間の安静が必要な場合がある
実際には、医療技術の進歩や医療スタッフの経験によって、安全に実施できるケースが多いです。
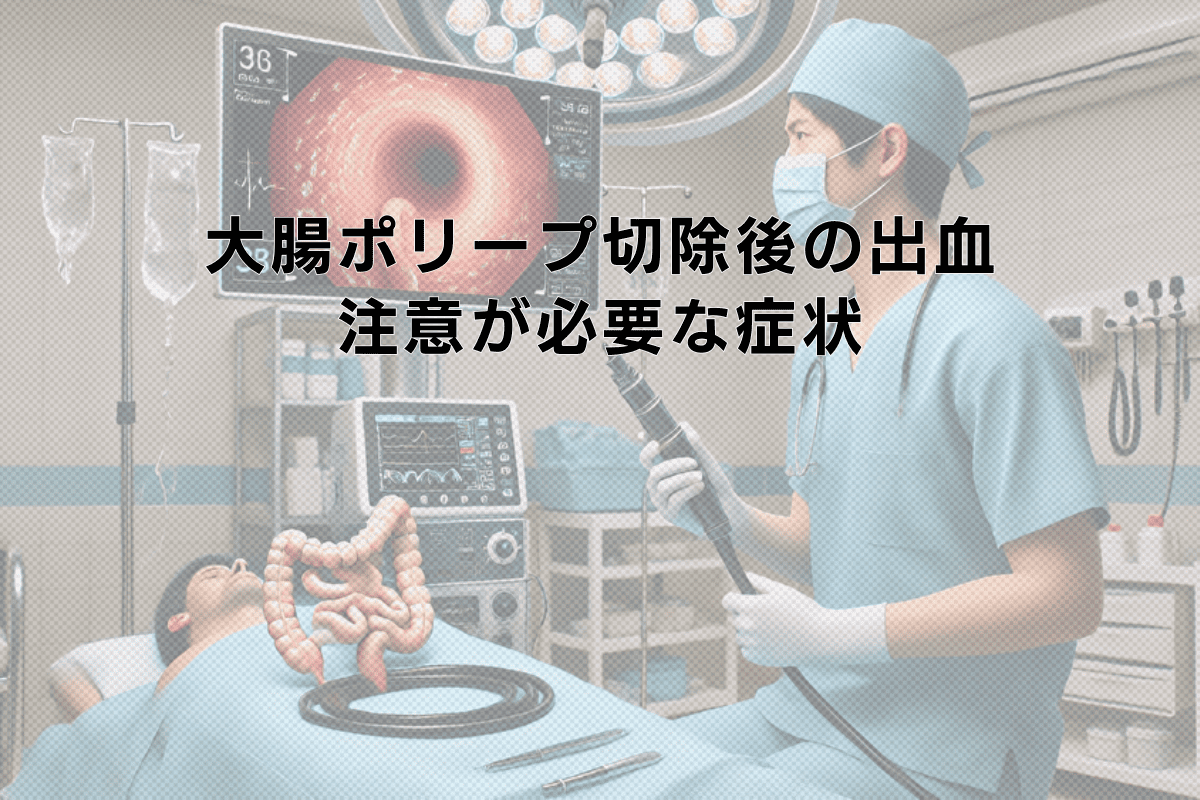
不安を減らすための対策
- 信頼できる医師や医療機関を選ぶ
- 事前説明をしっかり受け、疑問点を解消しておく
- 検査当日はできるだけリラックスできる環境を整える
- 鎮静剤の使用について相談する(不安が強い場合)
安心して内視鏡検査を受けるためのポイント
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 医療スタッフとのコミュニケーション | 検査方法や段取りについて十分に説明を受ける |
| 身体の状況に合った鎮静 | 痛みや恐怖感が強い場合は鎮静剤の使用を検討する |
| 安静にできるスケジュール確保 | 検査後は休憩を取れるよう予定を調整する |
| 不安要素の事前相談 | 痛みや副作用など、気になる点を遠慮なく相談する |
十分な準備と情報収集によって、検査への不安が和らぎやすくなります。
早期診断が下痢の長期化を防ぐカギ
下痢が続く原因を放置すると、日々の生活の質が低下するだけでなく、病状の進行を許すリスクがあり、早期診断と早期治療が、下痢の長期化を防ぎ、合併症や重篤化を回避するうえで重要です。
下痢が続く場合のデメリット
- 仕事や家事への支障により、社会生活の質が下がる
- 腸内環境の悪化が進みやすい
- 体力や免疫力が低下し、他の病気にもかかりやすくなる
- 栄養不足や脱水状態になりやすい
早期に検査を受けるメリット
- 原因を特定し、適切な治療を始められる
- 食事療法や生活改善の指導をスムーズに行える
- 大腸がんなどの重大な疾患が見つかった場合でも、早期治療が行いやすい
- 下痢に伴う体力低下や精神的ストレスの軽減を図れる
受診のモチベーションを高めるヒント
健康状態が少しでも気になるときには、勇気を出して医師の診察を受けることが得策です。長期化すると検査そのものに対する不安が増大しやすいため、少しでも異常を感じたら早めに行動を起こしてください。
下痢の継続によるリスクと対策
| リスク | 具体的対策・行動 |
|---|---|
| 栄養不良や脱水 | こまめに水分補給、食事バランスを見直す |
| 症状の慢性化 | 早期に医療機関を受診する |
| 腸の炎症や病変の進行 | 内視鏡検査で粘膜を直接チェック |
| 社会生活や精神面への悪影響 | 適切な診断と治療でQOLを維持する |
自分の身体の異変に気づいたら、早い段階で相談することが健康管理につながります。
まとめ
下痢が続く状態は、原因が複雑に絡み合っていることが多く、判断を先延ばしにすると症状が慢性化してしまうリスクがあります。単なる体調不良と見過ごさず、まずは専門家による適切な問診や検査を受けることが重要です。
大腸カメラや胃カメラといった内視鏡検査によって、腸や胃の内側を直接確認する行為は、症状の原因を解き明かす近道になります。
下痢の原因を正しく理解し、必要に応じて内視鏡検査を受けることで、症状の慢性化を防ぎ、日常生活の不安や不便を軽減できる可能性があります。身体のSOSサインを見逃さず、気になる症状がある場合は早めに医療機関を受診してください。
次に読むことをお勧めする記事
【毎日の下痢症状が続くときの大腸内視鏡検査による診断基準】
慢性下痢の検査手順を押さえたら、実際の内視鏡所見がどう映るか具体例で確認すると安心です。検査に踏み切れない方に特に参考になります。
【腸の健康が体を支える ―腸内環境を整える食事・栄養―】
慢性下痢の背景には腸内環境の乱れも関与します。食事・運動・睡眠のバランスを学び、検査後の再発予防に役立ててください。
参考文献
Schiller LR, Pardi DS, Sellin JH. Chronic diarrhea: diagnosis and management. Clinical Gastroenterology and Hepatology. 2017 Feb 1;15(2):182-93.
Fine KD, Seidel RH, Do K. The prevalence, anatomic distribution, and diagnosis of colonic causes of chronic diarrhea. Gastrointestinal endoscopy. 2000 Mar 1;51(3):318-26.
DuPont HL. Persistent diarrhea: a clinical review. Jama. 2016 Jun 28;315(24):2712-23.
Schiller LR, Pardi DS, Spiller R, Semrad CE, Surawicz CM, Giannella RA, Krejs GJ, Farthing MJ, Sellin JH. Gastro 2013 APDW/WCOG Shanghai working party report: chronic diarrhea: definition, classification, diagnosis. Journal of gastroenterology and hepatology. 2014 Jan;29(1):6-25.
Marshall JB, Singh R, Diaz-Arias AA. Chronic, unexplained diarrhea: are biopsies necessary if colonoscopy is normal?. American Journal of Gastroenterology (Springer Nature). 1995 Mar 1;90(3).
Bo-Linn GW, Vendrell DD, Lee E, Fordtran JS. An evaluation of the significance of microscopic colitis in patients with chronic diarrhea. The Journal of clinical investigation. 1985 May 1;75(5):1559-69.
Juckett G, Trivedi R. Evaluation of chronic diarrhea. American family physician. 2011 Nov 15;84(10):1119-26.
Read NW, Krejs GJ, Read MG, Santa Ana CA, Morawski SG, Fordtran JS. Chronic diarrhea of unknown origin. Gastroenterology. 1980 Feb 1;78(2):264-71.
Sokic-Milutinovic A, Pavlovic-Markovic A, Tomasevic RS, Lukic S. Diarrhea as a clinical challenge: general practitioner approach. Digestive Diseases. 2022 May 10;40(3):282-9.
Limburg PJ, Ahlquist DA, Sandborn WJ, Mahoney DW, Devens ME, Harrington JJ, Zinsmeister AR. Fecal calprotectin levels predict colorectal inflammation among patients with chronic diarrhea referred for colonoscopy. Official journal of the American College of Gastroenterology| ACG. 2000 Oct 1;95(10):2831-7.










