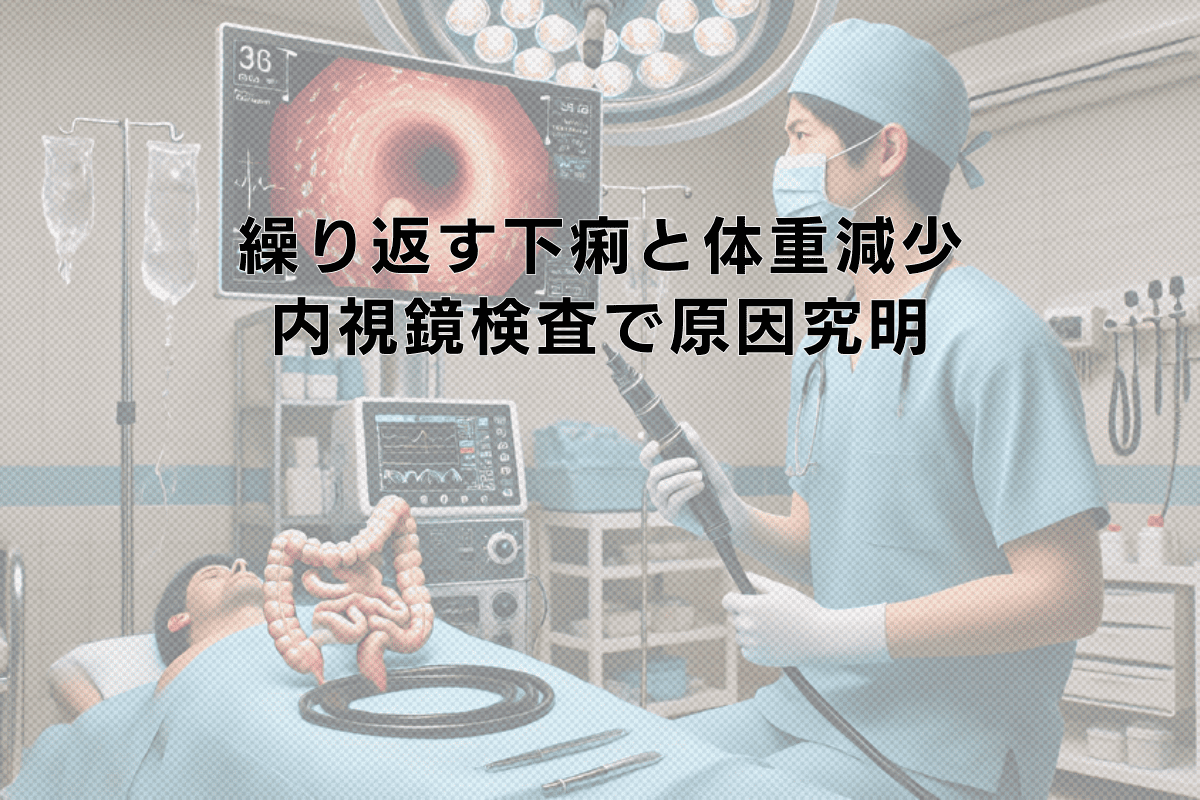腸の不調が続くと、生活の質が大きく低下します。特に下痢を繰り返し、食事量が減るなどして体重が落ちていくと、不安を感じる方は多いです。
こうした場合、原因として機能性の問題だけでなく、腸や胃の器質的な病変が潜んでいることもあります。
内視鏡検査を受けるかどうかは迷うところですが、放置すると症状が悪化するおそれがあるため、専門の医師に相談したうえで検査を検討することが重要です。
この記事では、繰り返す下痢や体重が減少してしまう背景と、内視鏡検査による原因究明について、詳しく解説します。
繰り返す下痢と体重が落ちていく状況の概要
下痢が続いて体重が落ちる状況は、生活や食事習慣にも影響を及ぼし、栄養が十分に吸収されず、日常生活でだるさや疲れやすさが生じる場合があります。
長引く場合は単なる体質だけでなく、何らかの疾患が絡んでいる可能性があるため、できるだけ早めに原因を探ることが大切です。
下痢が繰り返されるメカニズム
腸は食事から栄養や水分を吸収する器官で、通常は大腸で水分が再吸収されますが、それがうまくいかない状態では便が水分を多く含んだままの状態になります。
腸の運動が過剰になったり、腸の粘膜に問題が起きたりすると、ゆるい便が出やすくなります。
体重が落ちる理由
下痢が続くと、食事量が減少しやすくなります。加えて、栄養の吸収率も低下するため、体重が落ちやすくなり、体型が明らかに痩せるときは、過度なエネルギー不足やたんぱく質不足が潜んでいることがあります。
エネルギー源として体内の脂肪や筋肉が分解されることも考えられ、早めの対処が欠かせません。
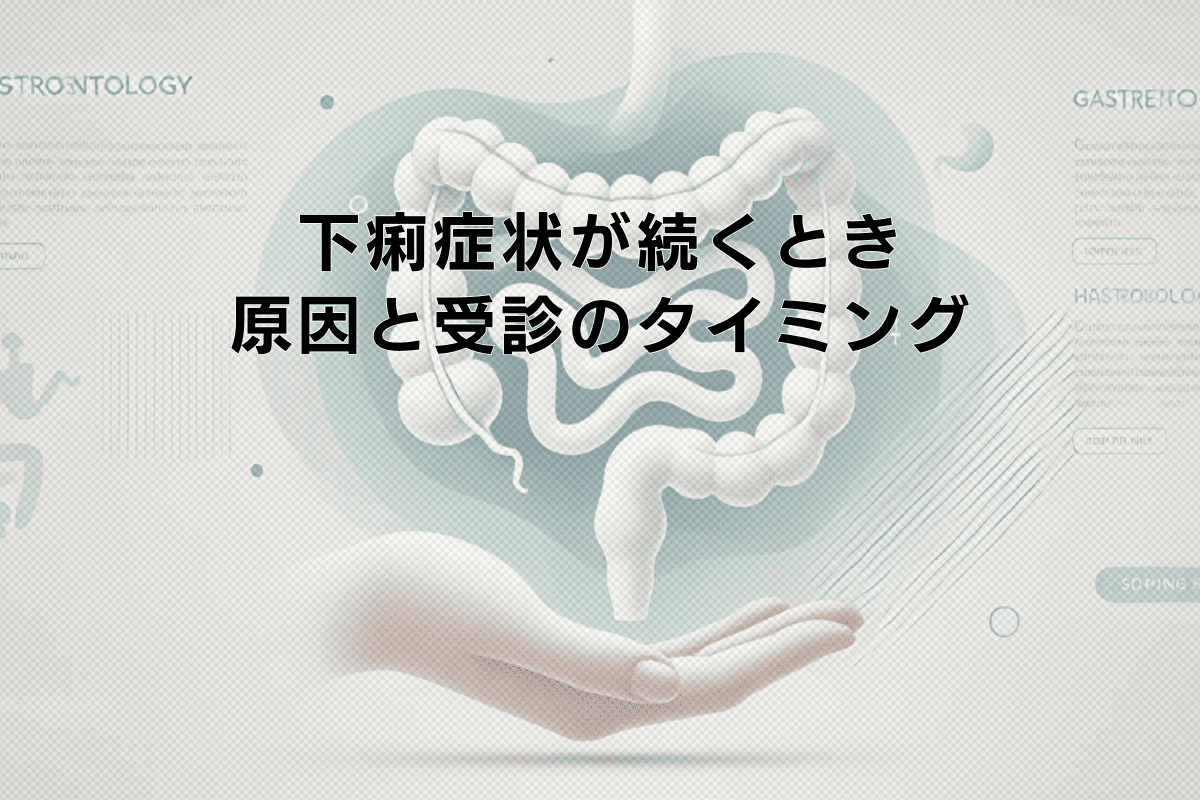
背後にある多様な原因
下痢と体重の減少には、急性の感染症から慢性的な炎症性疾患、ストレス性の腸機能障害、腸内細菌叢の乱れまで多岐にわたる原因があります。
体調管理を安易に済ませるのではなく、必要に応じて内視鏡検査や血液検査を検討することが問題解決への近道です。
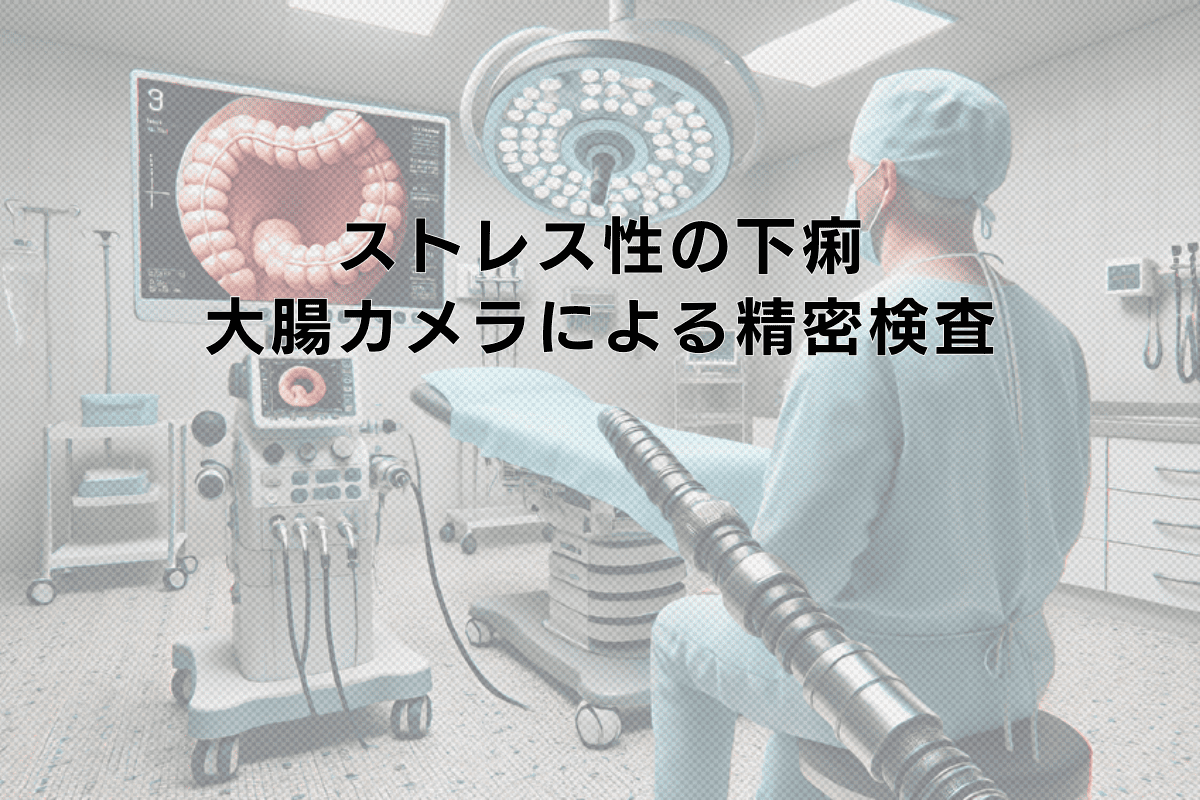
下痢と体重減少に関連する注意点
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 水分不足 | 頻回の下痢で脱水症が起こる |
| 電解質バランス | ナトリウムやカリウムが不足しやすい |
| 栄養障害 | タンパク質・ビタミン不足につながりやすい |
| 疲労感 | 睡眠不足やストレスが追い打ちをかける |
下痢が続くと体重が減りやすい理由
下痢は単に便がゆるい状態だけを指すわけではなく、栄養吸収の効率にも影響を及ぼします。体重が落ちる原因を知ることで、どのような対処をすれば症状を改善しやすいかを考えやすくなります。
栄養吸収の問題
腸の機能が落ちると、糖質・脂質・タンパク質だけでなく、ビタミンやミネラルの吸収も滞るケースが多いです。食べたつもりでも十分に栄養が取り込まれないため、体は必要なエネルギーを補えず、少しずつ体重が落ちます。
- 脂溶性ビタミン(A・D・E・K)の吸収障害
- 消化酵素の分泌不足
- 腸内細菌叢の乱れによる消化不良
- たんぱく質不足による筋肉量の低下

食欲低下
下痢を繰り返すと、食べる量そのものが減ることも多く、下腹部の張りや痛み、消化不良による吐き気などで食欲が落ちる状況では、体重が落ちやすくなります。悪循環に陥らないよう、体に合った食事を見つける意識が重要です。
水分の過不足による影響
下痢が続けば体は脱水傾向になりますが、水分を過剰に摂りすぎると胃腸に負担をかける可能性があります。水分量のコントロールが難しくなると、より不安定な状態に陥りやすいです。適度な電解質を含んだ水分摂取が役立ちます。
不足しがちな栄養素と水分補給のポイント
| 栄養素 | 症状や影響 |
|---|---|
| タンパク質 | 筋力低下、免疫力低下 |
| ビタミンB群 | エネルギー代謝の低下、疲労感 |
| 鉄 | 貧血、倦怠感 |
| マグネシウム | 筋肉のけいれん、神経機能の低下 |
繰り返す下痢と体重の減少をもたらす主な疾患
繰り返される下痢や体重が落ちてしまうケースでは、機能性疾患だけでなく炎症性疾患など、何らかの病変が存在する可能性も見逃せません。自己判断で放置すると状態が悪化する恐れがあり、正確な診断が必要です。
過敏性腸症候群(IBS)
ストレスや食習慣の影響で腸管運動に異常が起きる疾患です。便秘型と下痢型、または両方を繰り返す混合型があります。
下痢型では食後に急激に便意を感じることが多く、食べるとお腹が痛くなるという理由で食事量が減少し、結果的に痩せることがあります。
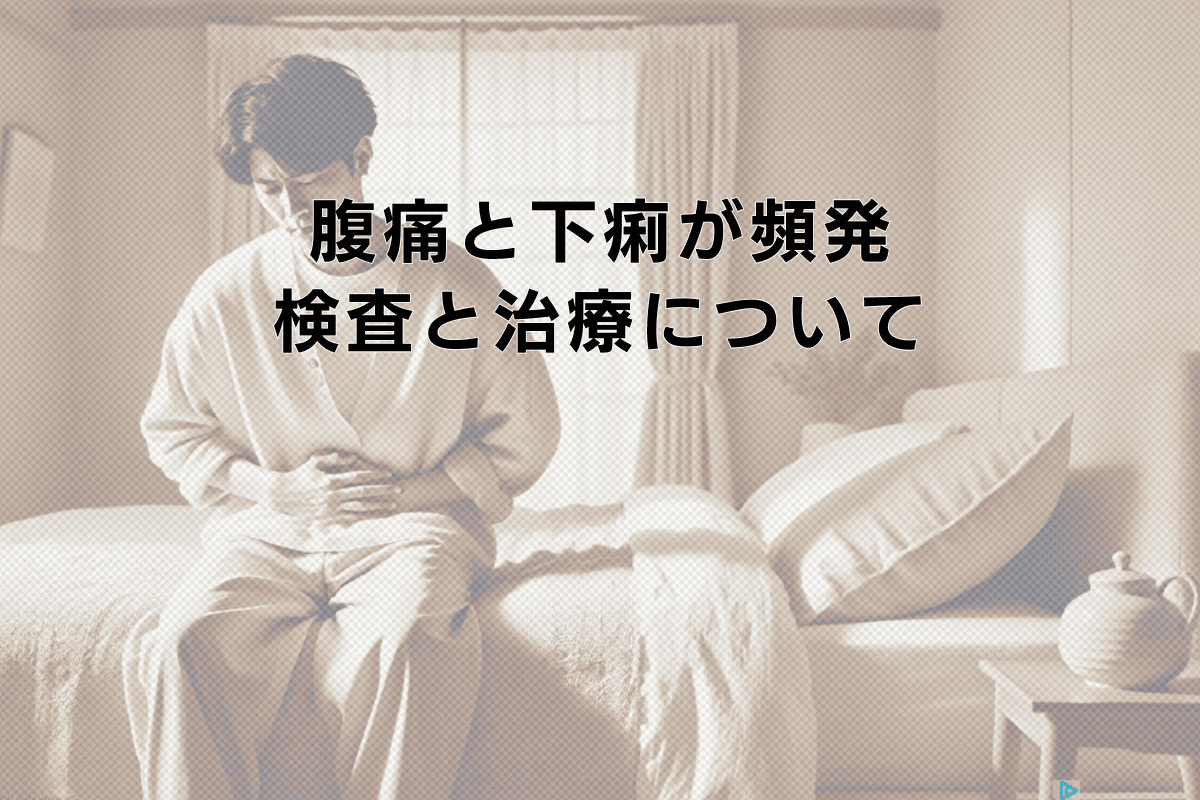
炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎・クローン病)
腸の粘膜に慢性的な炎症が起こり、下痢や血便などの症状が見られ、腸がただれてしまい、栄養吸収がうまくいかなくなるために体重が落ちやすいです。
クローン病は小腸から大腸まで幅広く病変が及ぶことがあるため、全身症状として倦怠感や貧血などが伴うケースもあります。

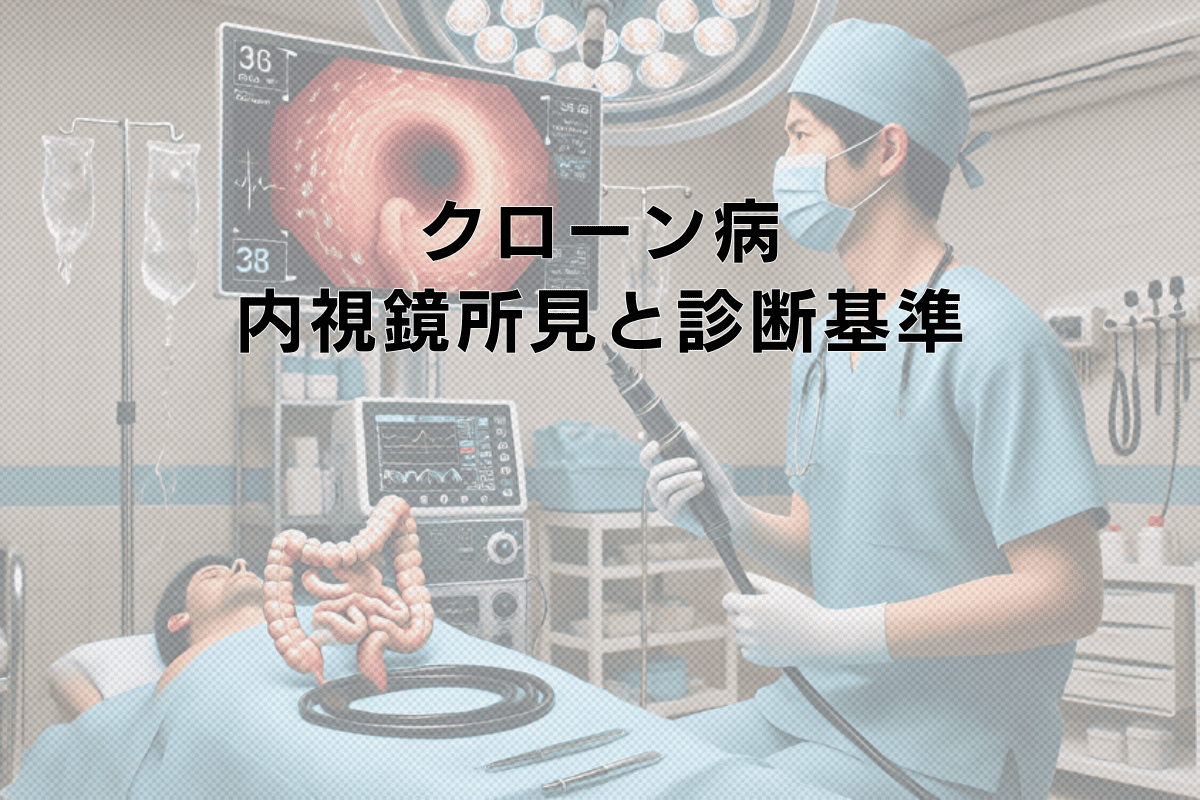
感染性腸炎や寄生虫感染
細菌やウイルス、寄生虫などによる感染症で、一時的な激しい下痢と嘔吐が起こる場合があります。多くは急性期の症状が中心ですが、慢性化する病態もあり、長期的に体重が落ちる要因です。
主な疾患と下痢の特徴
- 便が細くなっている
- 血液や粘液が混ざる
- 急な発熱を伴う
- 発症後に急激な体重低下が見られる
こうした場合は、早めに受診して原因を突き止めると安心です。
内視鏡検査が原因究明に役立つ理由
下痢や体重の減少が続く方にとって、内視鏡検査は大きな負担や不安を感じるものですが、内視鏡によって直接胃や大腸の状態を観察することで、原因が明確になる可能性が高まります。
画像検査だけではわからない粘膜の変化を直接確認できる点が特徴です。
胃カメラ(上部消化管内視鏡)の活用
下痢や体重の減少が主に大腸から来るように思える場合でも、胃や十二指腸など上部消化管の病変が原因になっていることがあり、胃カメラ検査では食道や胃、十二指腸の粘膜を直接観察しながら必要に応じて組織の一部を採取できます。
胃潰瘍や胃がんなども、下痢や体重減少につながる可能性があります。

大腸カメラ(下部消化管内視鏡)の活用
大腸カメラでは大腸全域と回盲部(小腸とのつなぎ目付近)までを確認できます。
大腸ポリープや炎症、潰瘍などの有無を調べることができ、疑わしい部分があれば組織検査を行え、大腸がんの早期発見にもつながるため、慢性的な下痢や不明の体重減少がある方にとって有力な選択肢です。
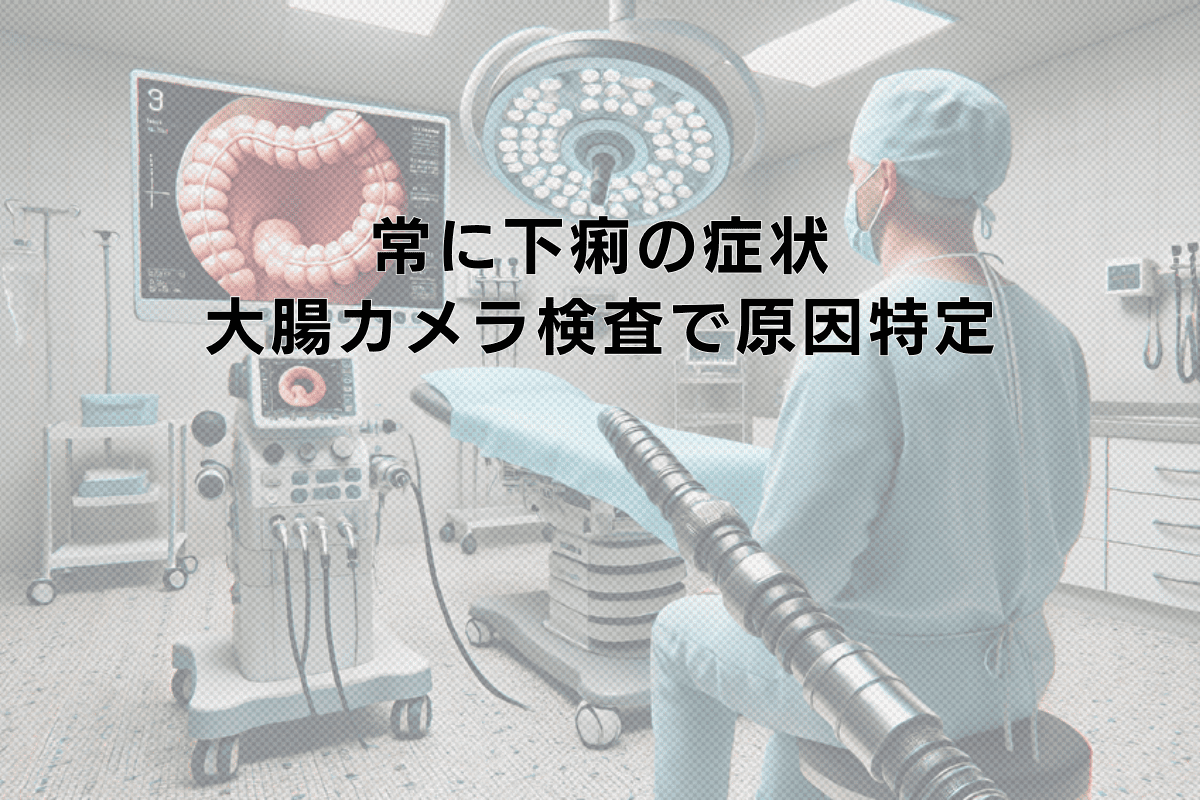
画像診断との併用
内視鏡検査は胃や大腸の粘膜状態を把握しやすいですが、小腸全域を詳細に観察する場合にはカプセル内視鏡など別の手法が役立つこともあります。
CTやMRIなどで炎症の広がりや腫瘍の有無を確認しつつ、内視鏡でより詳細な情報を補う場合もあります。
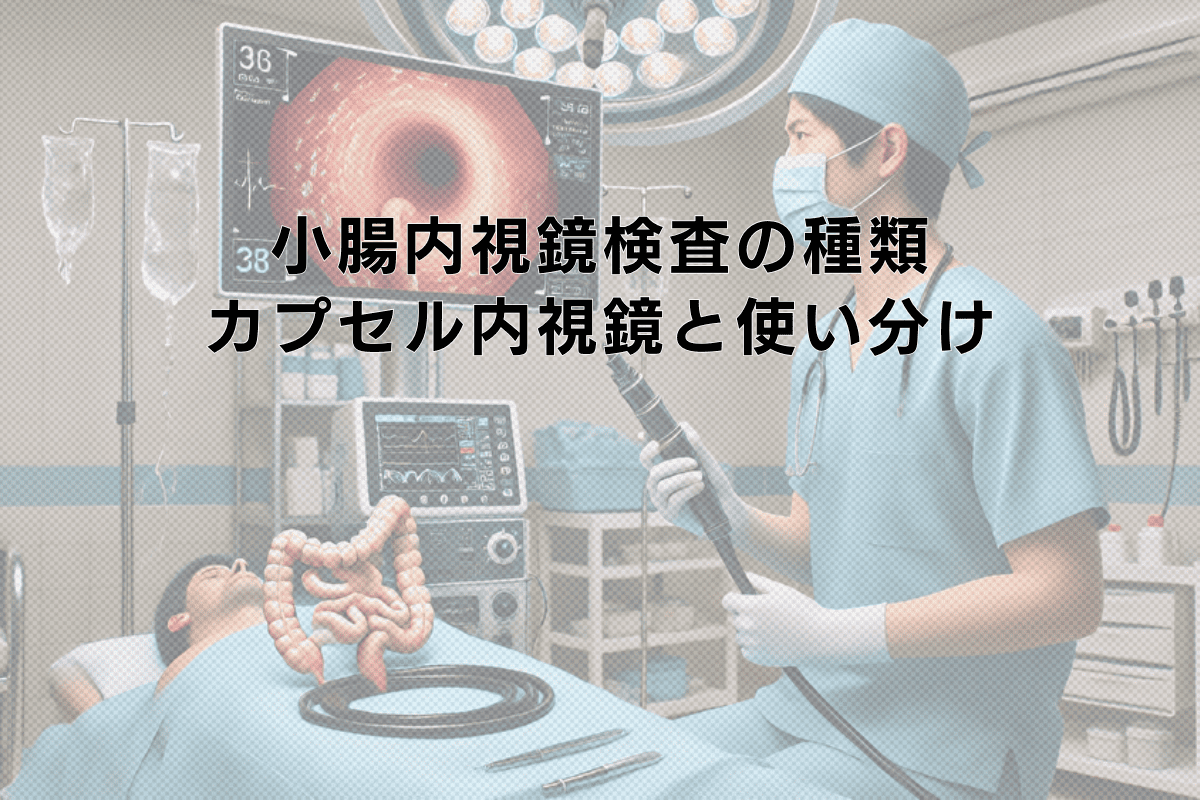
内視鏡検査と他の検査手法の違い
| 検査種類 | 観察範囲 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 胃カメラ | 食道~十二指腸 | 粘膜を直接見る | 準備が必要 |
| 大腸カメラ | 大腸全域 | 病変を直接確認 | 下剤を使う |
| カプセル内視鏡 | 小腸 | 全域チェック可能 | 費用が高め |
| CT/MRI | 全身 | 広範囲を把握 | 粘膜の細部は不明 |
内視鏡検査の前に意識したい準備
内視鏡検査を受けるうえで、前日の食事制限や下剤の飲用方法など、事前に知っておきたい情報がいくつかあります。正しい準備を行うことで、検査当日のトラブルを減らし、より正確な結果を得やすくなります。

食事制限
大腸カメラの場合は、消化に時間がかかる食品を控える必要があり、繰り返し下痢をしている方は体調を考慮しながら、検査前の食事内容を決めましょう。消化にやさしい食品や、刺激物を避けた食事が中心です。
- 繊維の多い野菜を一時的に控える
- 脂肪分の高い肉や揚げ物を避ける
- 刺激の強い香辛料やアルコールを控える
下剤の使用
大腸内視鏡検査では腸内をきれいにするため、指定の下剤を飲んで排泄を促します。下痢が続いている方はすでに便がゆるい状態ですが、検査結果をより正確にするには下剤で腸内を空っぽにする作業が必要です。
医師の指示に従い、無理のない方法で取り組んでください。
精神的な負担の軽減
内視鏡検査に不安を感じる方は少なくないので、事前に検査の流れを把握し、鎮静剤を使用するかなどを医師に相談すると落ち着いて検査に臨みやすいです。検査当日はできるだけ時間に余裕を持ち、緊張を和らげる工夫が役立ちます。
検査前の注意点と対策
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| 食事 | 消化に負担の少ないものを中心に |
| 水分摂取 | 適度に補給しつつ、指定時間前は控える |
| 内服薬 | 持病の薬がある場合は医師に確認 |
| 体調管理 | 発熱や体調不良を感じたら早めに相談 |
内視鏡検査当日の流れと留意点
内視鏡検査を受ける当日は、受付や検査前説明、着替えなど、いくつかの手順を踏んでから検査が始まります。具体的な流れを理解しておくと、心の準備ができて少し安心感を持てるでしょう。
鎮静剤の利用
胃カメラや大腸カメラでは、口や肛門から内視鏡を挿入するため、違和感や痛みを伴う場合がありますが、鎮静剤を使うと、うたた寝のような状態で検査を受けられます。
大腸の曲がり角などではチクっとした痛みを感じる方もいますが、鎮静剤の効果である程度やわらげることが可能です。
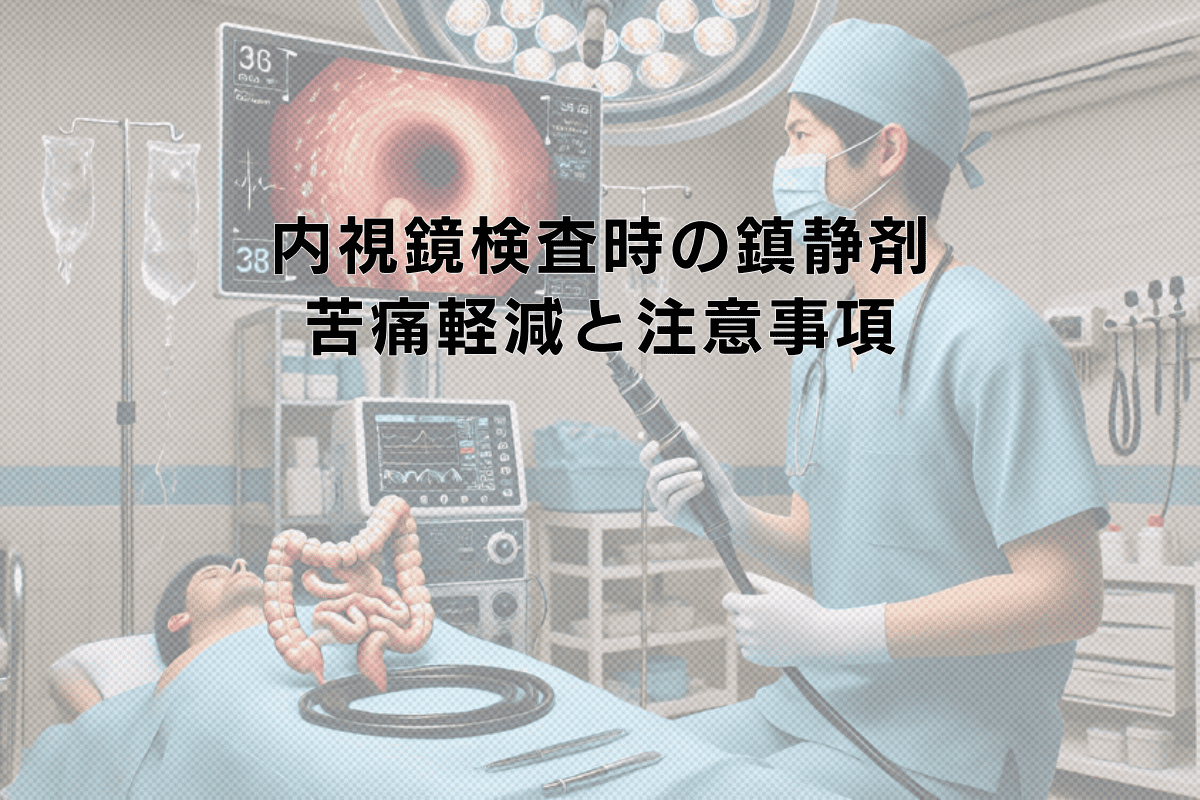
検査手順のイメージ
大腸カメラの場合は、検査台に横になり、肛門から内視鏡をゆっくり挿入していき、腸内に空気や二酸化炭素を入れて腸を広げながら観察を進めますが、そのときにお腹に膨満感を感じることがあります。
医師がカメラを操作しながら腸内をチェックし、必要に応じて生検(組織の一部を採取)を行います。
見つかる可能性がある所見
大腸ポリープ、潰瘍、炎症、腫瘍など、多彩な所見が確認でき、下痢や体重の減少が続いている場合、腸内の炎症や粘膜のただれなどが見つかることがあり、検査後に病理検査の結果が判明してから、治療方針が固まります。
内視鏡検査当日の一般的な流れ
| 流れ | 内容 |
|---|---|
| 受付・問診 | 体調や既往歴の確認 |
| 準備 | 着替えなどを行う |
| 検査開始 | 内視鏡を挿入し観察 |
| 検査後 | 安静にして鎮静剤の効果が切れるのを待つ |
| 結果説明 | 視覚的な画像を見ながら医師と相談 |
- 安静時間が必要
- 車の運転を控えたほうがよい
- 生検の有無で追加の処置や説明が必要
- 痛みや不調がある場合はすぐに伝える
検査後の過ごし方と再発予防
検査後は、腸内が刺激されている状態になるため、下痢を繰り返す方にとっては一時的に症状が強まることもあります。医師からのアドバイスを踏まえながら体を休め、再発のリスクを減らす工夫が大切です。
検査直後のケア
大腸カメラで空気や二酸化炭素を注入するので、お腹が張る感覚が残る場合がありますが、しばらく休むことでガスが抜け、膨満感が落ち着くことが多いです。鎮静剤を使った場合は、意識がしっかり戻るまで安静に過ごします。
検査後の注意点
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 飲食 | 当日は消化のよい食事が望ましい |
| 入浴 | 軽めのシャワー程度にとどめる |
| 運動 | 激しい運動は避ける |
| 結果説明 | 場合によっては後日になる |
食生活や生活習慣の見直し
下痢を繰り返して体重が落ちている方は、腸にやさしい食事を継続して取り入れる工夫が望ましく、また、ストレスや睡眠不足が腸内環境に影響を及ぼすケースも見られます。可能な範囲で心身のケアを心がけると症状の改善につながりやすいです。
- 十分な休息と睡眠
- 腸内環境を整える発酵食品(ヨーグルト、納豆など)の活用
- アルコールや刺激物の摂取量を抑える
- 定期的な運動で腸の動きを活発化
継続的なフォローアップ
症状が改善した後も、再発を防ぐために定期的なフォローアップが必要で、炎症性腸疾患など慢性疾患が見つかった場合は、症状の変化に応じた治療計画が求められます。自己判断で通院を中断せず、医師と相談しながら体調を管理してください。
生活習慣におけるポイント
| 項目 | 具体的な方法 |
|---|---|
| 食事 | 高たんぱく・低脂肪食を意識 |
| ストレス対策 | 趣味や運動、カウンセリングを活用 |
| 定期検査 | 指示されたペースで通院 |
| 体重管理 | 適度な食事制限と栄養バランスの見極め |
よくある質問
- 下痢が続いて体が痩せる場合、必ず大腸カメラが必要ですか?
-
明確な判断には医師の総合的な診察が欠かせません。症状や採血結果によっては大腸カメラ以外の検査で十分と判断される場合もあります。
ただし、長引く下痢や著しい体重の減少がある場合、胃や大腸の粘膜を直接観察できる検査が有用です。
- 胃カメラと大腸カメラの両方を受けると負担が大きくなりますか?
-
身体への負担は個人差があり、胃カメラと大腸カメラを同日に実施するクリニックもありますが、各々の検査準備や所要時間を考慮したうえで決めることが大切です。
医師やスタッフと相談して、体調やスケジュールに合った検査計画を立てましょう。
- 内視鏡検査の結果、炎症など特に問題が見つからなかった場合はどうしたらよいのでしょう?
-
内視鏡検査で異常が見当たらなかった場合でも、過敏性腸症候群や腸内細菌の乱れなど別の要因が下痢や体重の減少に影響しているケースがあります。
食事指導や生活習慣の改善をすすめつつ、追加の血液検査やアレルギー検査などを検討することもあります。
- 検査中の痛みが心配ですが、対策はありますか?
-
大腸カメラに対して不安を強く感じる方は、鎮静剤の使用を検討すると痛みや苦痛を軽減できます。医師や看護師が検査中に声をかけながら行うため、心配事や痛みがある場合は遠慮なく伝えてください。
次に読むことをお勧めする記事
【下痢を伴う腹痛の原因と検査 – 内視鏡検査の必要性】
下痢と体重減少の基本を押さえたら、次は実際の検査や治療の選択肢について知っておくと安心です。腹痛を伴う下痢症状でお悩みの方に特に参考になる内容です。
【腸の健康が体を支える 腸内環境を整える】
痢と体重減少の背景には腸内細菌バランスも影響します。腸内環境を整える方法を知って、自分に合った生活習慣のヒントを得ましょう。
参考文献
Kinoshita Y, Ariyoshi R, Fujigaki S, Tanaka K, Morikawa T, Sanuki T. Endoscopic diagnosis of chronic diarrhea. DEN open. 2022 Apr;2(1):e53.
Ihara E, Manabe N, Ohkubo H, Ogasawara N, Ogino H, Kakimoto K, Kanazawa M, Kawahara H, Kusano C, Kuribayashi S, Sawada A. Evidence-based clinical guidelines for chronic diarrhea 2023. Digestion. 2024 Dec 9;105(6):480-97.
Matsumoto Y, Nadatani Y, Otani K, Higashimori A, Ominami M, Fukunaga S, Hosomi S, Kamata N, Kimura T, Fukumoto S, Tanaka F. Prevalence and risk factor for chronic diarrhea in participants of a Japanese medical checkup. JGH Open. 2022 Jan;6(1):69-75.
Saito Y, Kodashima S, Matsuda T, Matsuda K, Fujishiro M, Tanaka K, Kobayashi K, Katada C, Horimatsu T, Muto M, Ohtsuka K. Current status of diagnostic and therapeutic colonoscopy in Japan: The Japan Endoscopic Database Project. Digestive Endoscopy. 2022 Jan;34(1):144-52.
Ashitani K, Tsuzuki Y, Yamaoka M, Ohgo H, Ichimura T, Kusano T, Nakayama T, Nakamoto H, Imaeda H. Endoscopic features and diagnostic procedures of eosinophilic gastroenteritis. Internal Medicine. 2019 Aug 1;58(15):2167-71.
Watanabe C, Komoto S, Tomita K, Hokari R, Tanaka M, Hirata I, Hibi T, Kaunitz JD, Miura S. Endoscopic and clinical evaluation of treatment and prognosis of Cronkhite–Canada syndrome: a Japanese nationwide survey. Journal of gastroenterology. 2016 Apr;51:327-36.
Kinoshita Y, Furuta K, Ishimaura N, Ishihara S, Sato S, Maruyama R, Ohara S, Matsumoto T, Sakamoto C, Matsui T, Ishikawa S. Clinical characteristics of Japanese patients with eosinophilic esophagitis and eosinophilic gastroenteritis. Journal of gastroenterology. 2013 Mar;48:333-9.
Shen B, Khan K, Ikenberry SO, Anderson MA, Banerjee S, Baron T, Ben-Menachem T, Cash BD, Fanelli RD, Fisher L, Fukami N. The role of endoscopy in the management of patients with diarrhea. Gastrointestinal endoscopy. 2010 May 1;71(6):887-92.
Yamada E, Kuriyama H, Uchida E, Murata Y, Hata Y, Tagri M, Isozaki Y, Oyamada H, Ozawa Y, Ito T, Mizuki A. Association between endoscopic findings related to colonic diverticula and bowel habits: A multicenter study in Japan. Journal of gastroenterology and hepatology. 2017 Dec;32(12):1938-42.
Lok KH, Hung HG, Li KK, Li KF, Szeto ML. Congenital chloride diarrhea: a missed diagnosis in an adult patient. Official journal of the American College of Gastroenterology| ACG. 2007 Jun 1;102(6):1328-9.