水のような便が長期間続くと、日常生活に大きな支障が生じるだけでなく、重い病気が隠れている可能性も否定できません。単なる体調不良と考えて放置すると、症状が悪化して医療機関を受診するタイミングを逃してしまう場合もあります。
今回の記事では、長引く水様性下痢に関わる代表的な原因、どのような症状に注意を払うべきか、そして内視鏡検査(大腸カメラ)の必要性について詳しく解説します。
気になる症状がある方はもちろん、今は大きなトラブルがない方も備えとして読んでください。
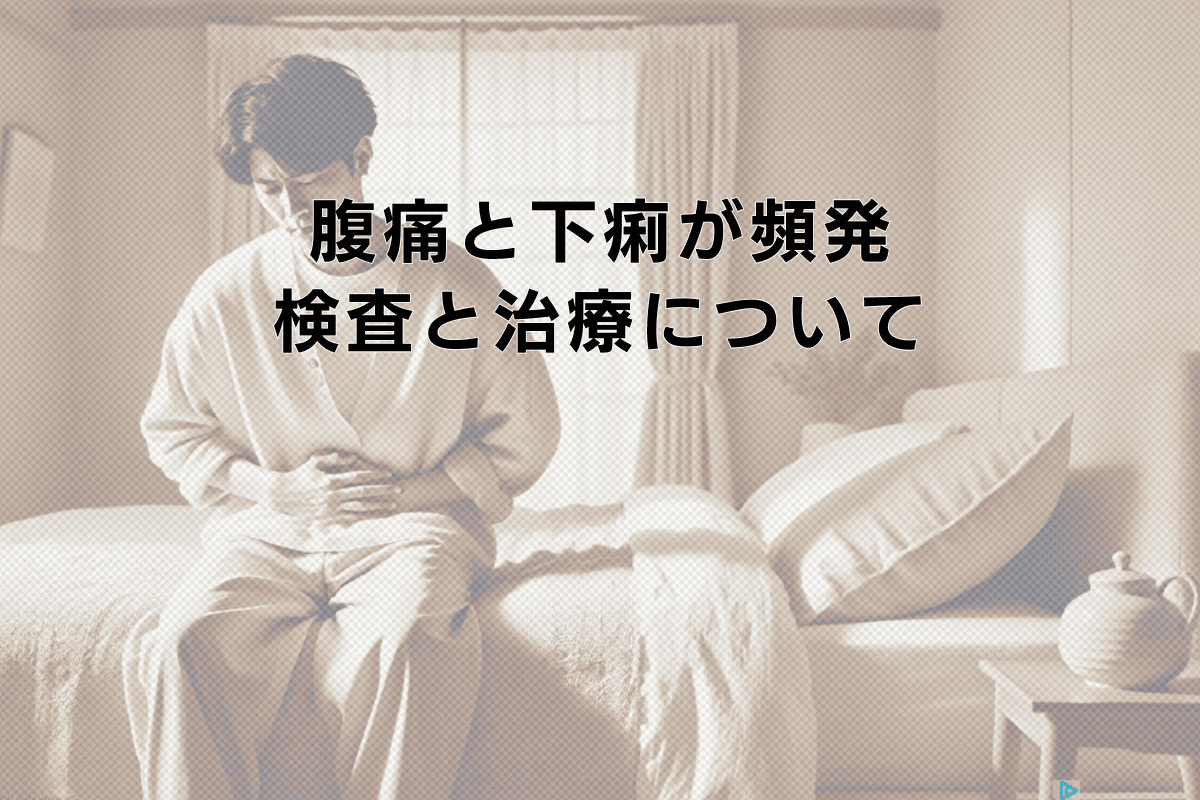
水様性下痢が続く原因の全体像
長い期間にわたって便が水っぽい状態で排出されると、体内の水分や栄養が不足しやすくなり、脱水だけでなく電解質バランスが乱れることで、けいれんや倦怠感など全身的な不調が出ることもあります。
まずは水様性下痢が続く原因の大まかな方向性を把握してみましょう。
感染症による下痢
ウイルスや細菌などによる感染症は、水様性下痢を引き起こす代表的な要因です。ノロウイルスやロタウイルスなどは急性期に激しい症状を伴いますが、長引くケースでは細菌性の腸炎や寄生虫感染の可能性も考えられます。
食事や生活習慣の影響
過度なアルコール摂取、脂質の多い食事、冷たいものの摂りすぎが腸の働きを乱すことがあります。さらにストレスや睡眠不足などの要因も腸の機能を低下させ、ゆるい便が続くきっかけとなることがあります。
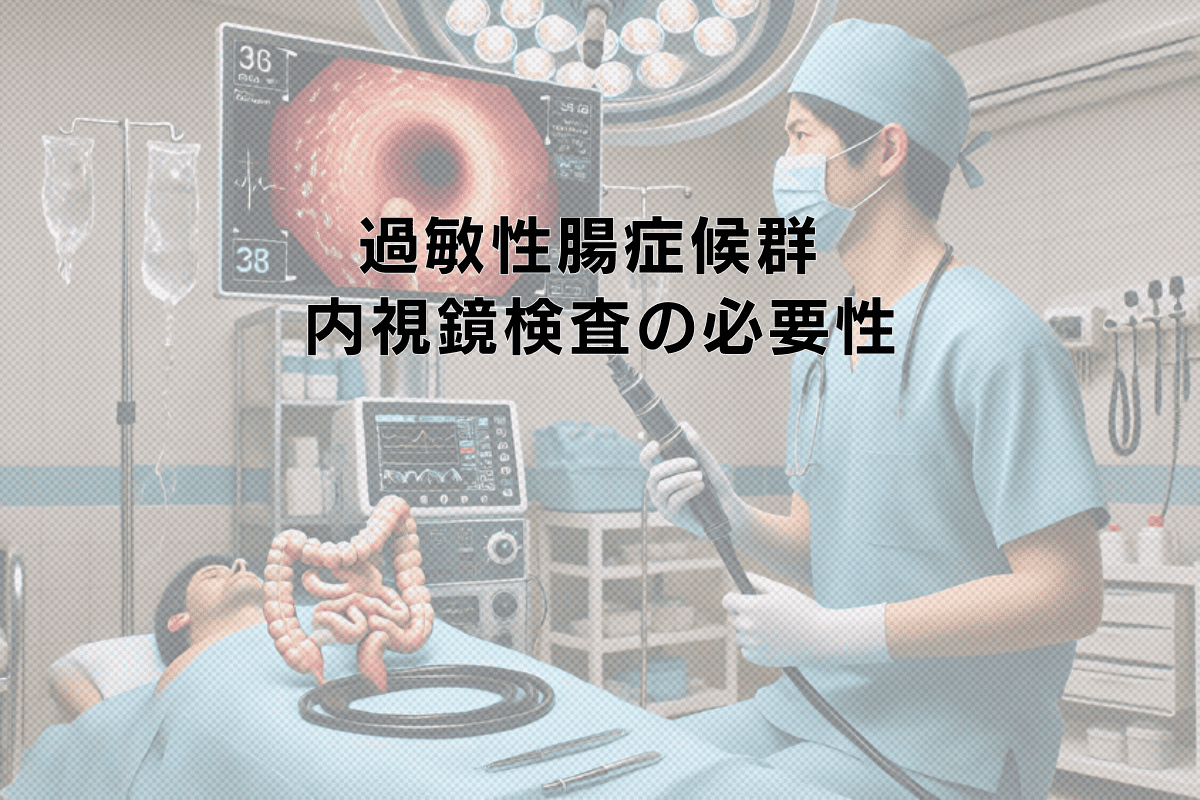
消化管の慢性的な疾患
潰瘍性大腸炎やクローン病などの炎症性腸疾患は、慢性的に水のような下痢を起こし、炎症が長引くと腸壁がダメージを受け、腹痛や体重減少を伴うことも多いです。
基礎疾患や薬剤によるもの
糖尿病や甲状腺機能亢進症などのホルモンバランスの乱れが続くと、便が水のようになるケースがあり、また抗生物質や下剤などの薬剤による副作用で下痢が止まらない状況に陥る人もいます。
水様性下痢が続くときに考えられる主な要因
| 要因の分類 | 具体的な例 |
|---|---|
| 感染症 | 細菌性腸炎(赤痢菌、サルモネラ菌など)、ウイルス性腸炎(ノロウイルスなど) |
| 食事・生活習慣 | 脂質過多、冷たい飲食物の摂りすぎ、ストレス過多、アルコールの過剰摂取 |
| 消化管の慢性疾患 | 潰瘍性大腸炎、クローン病、過敏性腸症候群 |
| ホルモンバランスの乱れ | 甲状腺機能亢進症、糖尿病 |
| 薬剤の影響 | 抗生物質、NSAIDs、下剤の長期使用など |
いろいろな要因が複雑に絡み合い、水っぽい便がなかなか改善しないケースも珍しくありません。一時的に食事内容を見直すだけでは治らない場合もあるため、油断しないことが大切です。
医療機関を受診するタイミング
下痢が長期化し、脱水症状や腹痛、便に血液が混じるなどの異常が見られたときは、早めに医療機関で検査を受けることが望ましく、特に1週間以上、水様性下痢が止まらない場合は注意が必要です。
医療機関の受診を考慮したい症状
- 体重減少が顕著に見られる
- 便が白色や黒色を呈する
- 便に血液が混じる
- 強い腹痛や発熱がある
先送りにすると重大な疾患を見落とす可能性があるので、「まだ大丈夫」と思わず検査に踏み切ることが重要です。
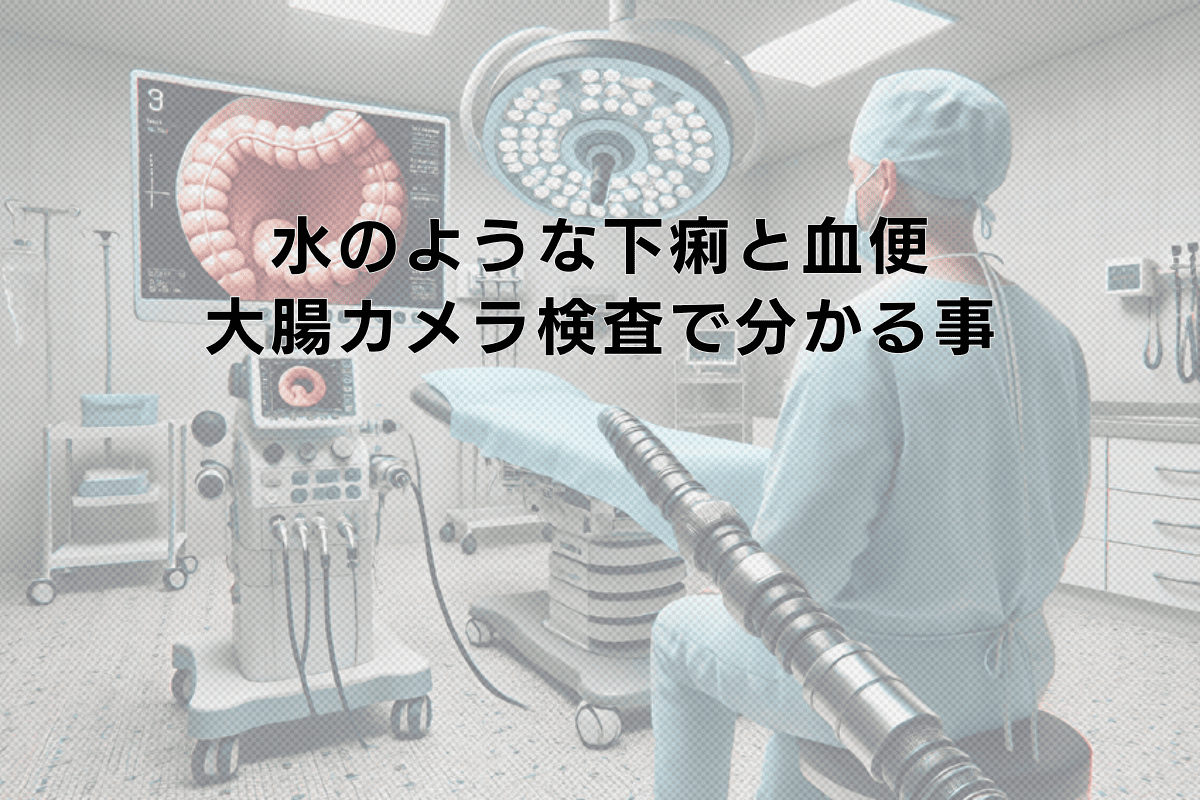
主な疾患と水様性下痢との関係
ここでは「水 下痢 止まらない」という状況に直結しやすい代表的な疾患に注目します。自分の症状を理解する上で、どのような病気が候補となるのかを知っておくと受診時の相談もしやすくなります。
潰瘍性大腸炎
潰瘍性大腸炎は大腸に慢性的な炎症が生じる自己免疫系の疾患で、主に血便を伴いやすいですが、水様性下痢が長期化することも珍しくありません。
特に大腸全体が炎症を起こす全大腸型では、水のような便が頻回に出ることで栄養不足や脱水を起こします。

クローン病
小腸から大腸に至る広範囲の消化管で炎症が起きるクローン病は、腹痛を伴いながら水分を含む便が続きます。症状が悪化すると深刻な瘻孔や狭窄を生じ、日常生活に大きく影響します。
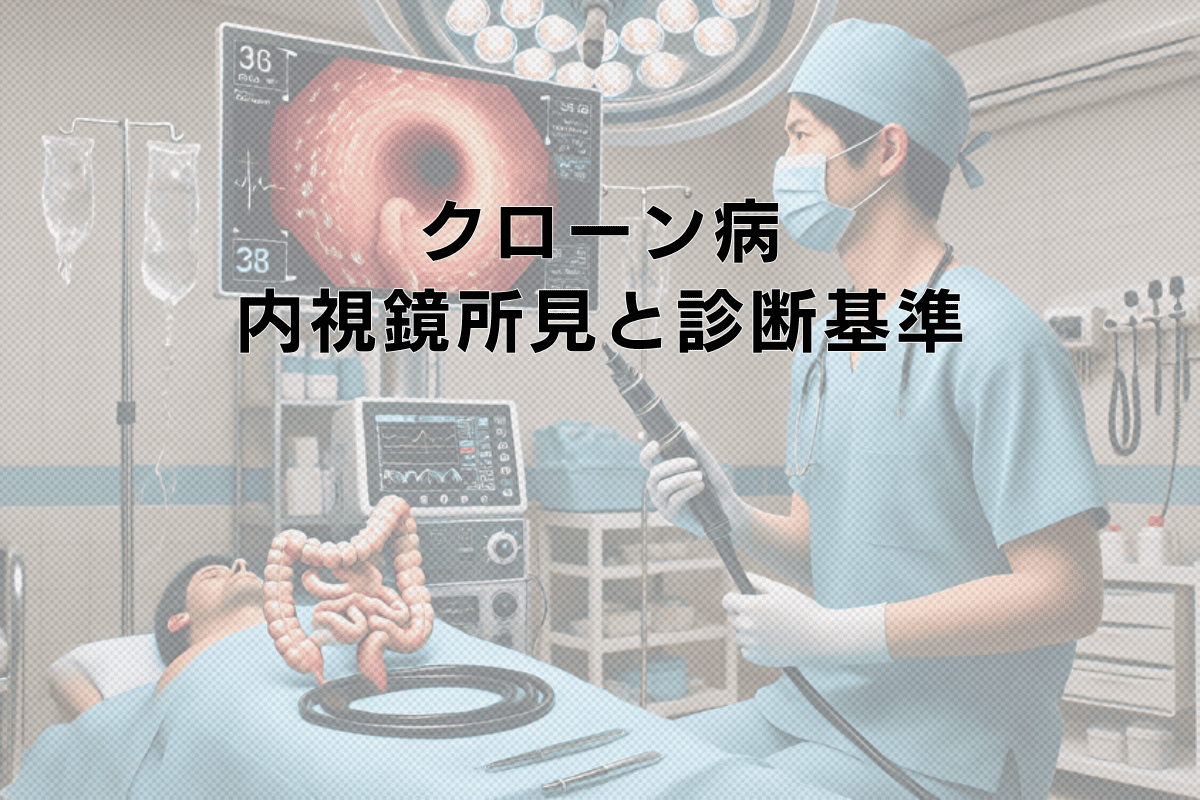
過敏性腸症候群
過敏性腸症候群では、ストレスや食生活の乱れをきっかけとして下痢型や便秘型、あるいは下痢と便秘を繰り返す混合型があります。
急な強い腹痛を伴うケースもあり、トイレに急行しても水っぽい便しか出ないという状況が断続的に続くことがあります。
感染性腸炎(慢性化したケース)
急性期の感染症であれば短期間で回復することが多いですが、一部の病原菌や寄生虫による腸炎は慢性化の可能性があり、症状が長期化するほど治療が複雑になることもあるので、早めに検査を行うことが大切です。
慢性化しやすい主な疾患
| 疾患名 | 主な症状 | 特徴 |
|---|---|---|
| 潰瘍性大腸炎 | 血便、水様便、腹痛、体重減少 | 自己免疫反応が関与、病変が連続的に広がる |
| クローン病 | 水様性下痢、腹痛、痔瘻、体重減少 | 口から肛門までの消化管に病変が飛び飛びで出現 |
| 過敏性腸症候群 | 下痢、便秘、腹痛、ガスの膨満感 | ストレスとの関連が深い、検査では明らかな炎症が見られにくい |
| 感染性腸炎(慢性) | 持続的な下痢、発熱、血便の場合も | 細菌・寄生虫が原因、適切な抗菌薬が必要になる場合がある |
先に挙げたような病気だけでなく、出血を伴わない炎症や腸管の機能異常でも下痢が持続するケースは少なくありません。自己判断で様子を見る期間が長引かないようにする心掛けが大切です。
長期化した下痢のリスク
体内に栄養や水分が十分吸収されないまま長い間過ごすと、免疫力が低下しやすくなり、さらに腸内環境のバランスが崩れることで、ほかの感染症にかかりやすくなるなどのリスクも考えられます。
症状を見極めるためのポイント
同じ水様性下痢であっても、腹痛の有無や排便の回数、便の色や臭いなどを細かく把握すると、原因にアプローチしやすくなります。
便の性状を確認する
便の硬さや色は、腸内環境を映し出す鏡のようなものです。水のようにさらさらの場合は吸収機能が低下している可能性が高く、脂分が浮くような便の場合は脂質代謝に何らかの問題があると考えられます。
便の観察の着眼点
| チェック項目 | 具体的な状態 |
|---|---|
| 色 | 茶褐色、黄土色、黒色、赤色など |
| 硬さ | 固形に近いか、水っぽいか |
| におい | 酸っぱい、臭いがきつい |
| 混入物 | 血液、粘液、脂肪のようなもの |
排便後に軽く観察するだけでも、腸の状況がある程度推測できます。
腹痛や発熱の有無
激しい腹痛を伴うかどうか、微熱や高熱が出ているかは病状を把握するうえで大切な情報です。慢性的に水様性下痢が続く場合、腹痛をあまり感じないケースもありますが、その場合でも体温を測ってみると微妙な変化に気づくことがあります。
トイレの回数とタイミング
「朝だけ水っぽい便が出る」「食後すぐに下痢になる」などの時間的な規則性は、過敏性腸症候群をはじめとする機能性疾患によく見られます。
また一日中下痢が続いてまったくコントロールできない場合は、炎症性腸疾患や感染症など器質的な問題を疑うことが必要です。
症状の強さとタイミングを記録しておきたい点
- 1日の排便回数
- 排便時刻
- 便が水のように出始めた時期
- 食事との関係(どの食べ物を摂った後に症状が悪化しやすいか)
こうした情報は医療機関を受診した際に医師に伝えると、診断がスムーズに進みやすいです。
体重や体調の変化
水様性下痢が長期間続くと栄養が吸収されにくくなるため、体重が減少することがあり、また、貧血やだるさ、集中力の低下など全身症状が出たときは、早めに原因を突き止めて対策を練ることが望ましいです。
水様性下痢に伴う全身症状のチェックリスト
| 自覚症状 | 考えられる影響 |
|---|---|
| 体重減少 | 栄養不足、吸収不良 |
| 倦怠感 | エネルギー不足、電解質バランスの乱れ |
| めまい | 脱水による循環血液量の減少 |
| 動悸、息切れ | 脱水や電解質異常、貧血の可能性 |
| 集中力の低下 | 糖分不足、ビタミン・ミネラル欠乏 |
便だけでなく、全身のコンディションがどのように変化しているかを知ることが診断の手がかりになります。
内視鏡検査の意義
慢性的な水様性下痢が続く場合、腸の粘膜に何らかの異常が生じている可能性があり、腸内の状態を直接確認するうえで大腸カメラなどの内視鏡検査は重要です。ここからは内視鏡検査が果たす役割や、必要性について説明します。
内視鏡検査とは何か
内視鏡検査には主に胃カメラと大腸カメラがあり、口から挿入して胃や十二指腸などを調べるのが胃カメラ、肛門から挿入して大腸全体の粘膜を観察するのが大腸カメラです。
どちらも細長いスコープの先端にカメラが付いており、モニターを見ながら粘膜の状態を詳しく観察できます。
カメラ検査でわかること
炎症や潰瘍の範囲、出血や腫瘍の有無などを直接目視で確認できることは大きなメリットです。必要に応じて生検(粘膜を一部採取する検査)を行い、組織レベルでの詳しい診断を行うこともできます。
なぜ水様性下痢に内視鏡検査が必要か
水様性下痢は腸の機能異常だけでなく、粘膜に潰瘍や腫瘍があったり、炎症が広範囲に及んでいたりするケースも想定されます。画像診断や血液検査では把握しきれない詳細を確認し、的確な治療方針を決めるために内視鏡検査が大切です。
内視鏡検査で確認できる主なポイント
- 炎症の有無と範囲
- 出血や腫瘍の有無
- 腸内ポリープなどの存在
- 粘膜の状態や色調
腸の内側を直接見ることで、単なる機能性ではなく器質的な要因があるかどうかを判断しやすくなります。
早期発見・早期治療の重要性
長引く下痢の背景に、初期の大腸がんや高リスクのポリープが隠れている可能性は否定できません。自覚症状が下痢だけだと見逃しがちですが、検査を行うことで早期発見につながり、治療の選択肢が広がります。
内視鏡検査によるメリット
| メリット | 解説 |
|---|---|
| 直接観察 | 粘膜の状態をモニターでリアルタイムに確認し、正確な診断に役立つ |
| 生検の実施 | 必要に応じて組織を採取し、病理学的な評価が可能 |
| 早期発見 | ポリープや初期がんなど症状が出にくい病変も見つけやすい |
| 予防的処置が可能 | 大腸ポリープなどは検査時に切除できる場合がある |
| 診断精度の向上 | 他の検査では見逃す可能性がある細かい病変も把握できる |
内視鏡検査には多少の負担が伴いますが、慢性的な下痢の原因を明らかにして対策を立てるうえで有効な手段です。
水のような便が続く場合のリスクと合併症
軽視されがちな水様性下痢ですが、体への影響や合併症を考慮すると安易に放置できない症状です。
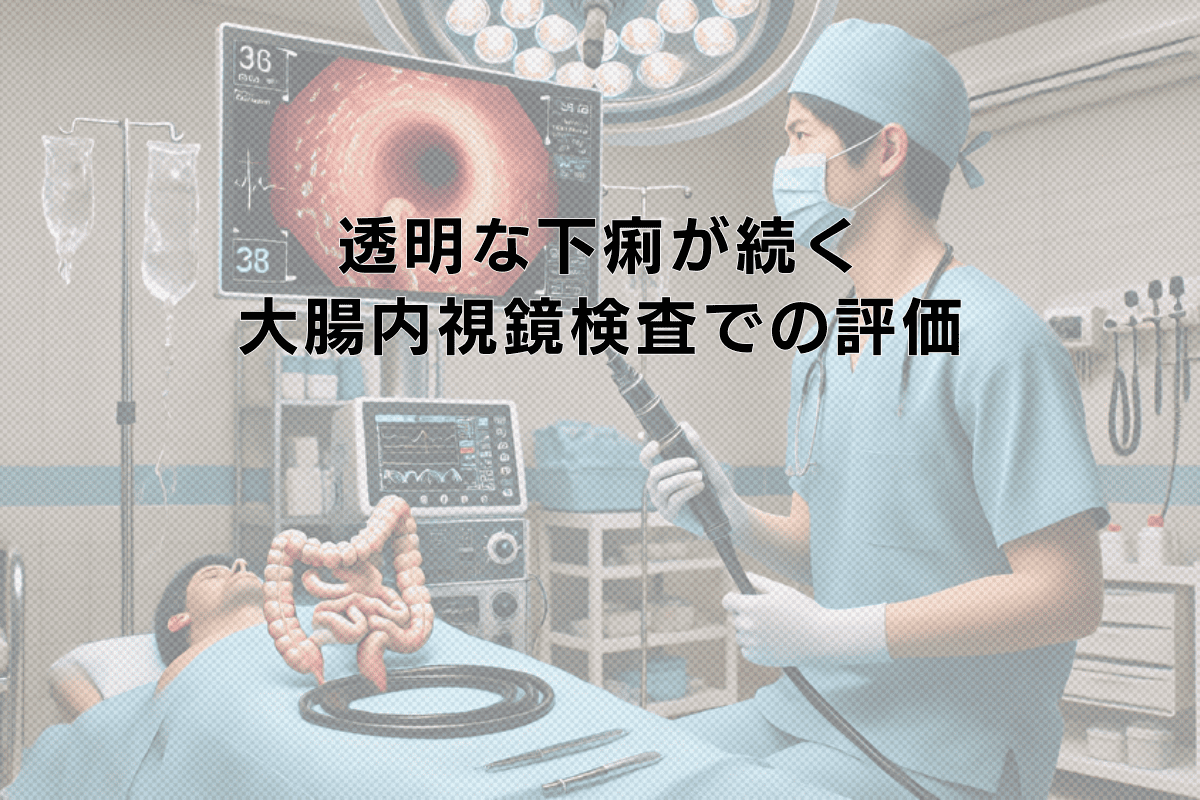
脱水と電解質異常
便として大量の水分が排出されるため、体内の水分量が不足しやすくなり、またナトリウムやカリウムなどの電解質が体外に排出されることで、筋肉のけいれんや不整脈など深刻な症状が引き起こされることもあります。
栄養不足と免疫低下
水様性下痢は栄養素の消化吸収を妨げやすく、タンパク質やビタミン、ミネラルなどが不足しがちになり、免疫力が落ちると感染症にかかりやすくなるだけでなく、傷や炎症の回復にも時間がかかります。
腸内環境の悪化
善玉菌が減って悪玉菌が優勢になると、腸内で有害物質が増加しやすく、胃腸障害がさらに悪化し下痢の悪循環から抜け出しにくくなる可能性があります。
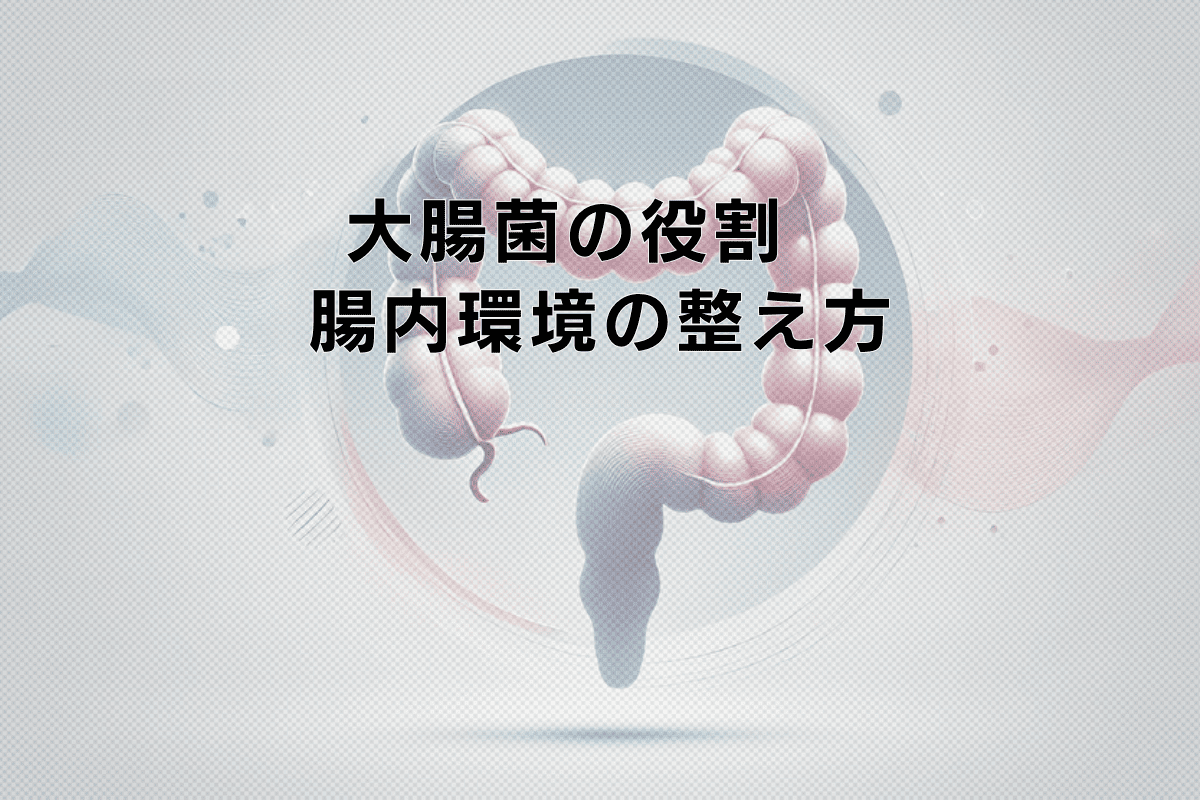
長期的な下痢が招く合併症
| 合併症・状態 | 具体例 |
|---|---|
| 脱水症状 | 口渇、めまい、低血圧、倦怠感など |
| 電解質バランスの乱れ | カリウム不足による不整脈、ナトリウム不足による血圧低下 |
| 栄養不良 | 体重減少、貧血、皮膚や髪の毛のトラブル |
| 免疫力の低下 | 風邪などの感染症にかかりやすくなる |
| 腸の粘膜障害の進行 | 炎症が悪化し、慢性的な腸疾患に発展するリスク |
身体のさまざまな機能へ影響が及ぶことを考えると、長期化した下痢には早めの対処が重要です。
メンタル面への影響
トイレの心配が常につきまとい、外出や仕事に支障をきたすことでストレスが高まり、過敏性腸症候群などでは、ストレスによる悪循環で症状が長引くケースもあるため注意が必要です。
ストレスが強まることで起こりやすい変化
- 不安感が高まり、外出を避けがちになる
- 仕事や人間関係で支障が出て自信を失う
- 食欲不振や寝つきの悪さが続く
内視鏡検査の種類と選び方
内視鏡検査と言っても、胃カメラや大腸カメラといった方法だけでなく、カプセル内視鏡などさまざまな選択肢があり、それぞれの特徴を知って、自分に合った検査を検討することが大切です。
胃カメラ(上部消化管内視鏡)
食道や胃、十二指腸の炎症や潰瘍、腫瘍の有無を直接確認でき、水様性下痢の原因が上部消化管にある場合には有効です。経口タイプと経鼻タイプがありますが、医療機関によって対応が異なります。

大腸カメラ(下部消化管内視鏡)
主に大腸全体と末端の小腸(回盲部)の状態を観察する検査で、潰瘍性大腸炎やクローン病、大腸がんの早期発見には欠かせない方法です。疑わしい病変が見つかった場合は同時に生検やポリープ切除を行えます。

胃カメラと大腸カメラの比較
| 項目 | 胃カメラ | 大腸カメラ |
|---|---|---|
| 主な対象範囲 | 食道、胃、十二指腸 | 大腸全域、回盲部付近 |
| 検査の目的 | 胃炎、胃潰瘍、胃がんなどの発見 | 大腸ポリープ、大腸がん、炎症性疾患の発見 |
| 侵襲度 | 比較的軽度 | やや体への負担が大きい |
| 前処置 | 6時間程度の絶食など | 下剤や食事制限などが必要 |
| 合併症リスク | ごく稀に出血や穿孔 | ごく稀に出血や穿孔 |
症状の性質や専門医の判断によって、どちらの検査を優先するかが決まります。
カプセル内視鏡
カプセル型の小さなカメラを飲み込み、自然に排出されるまでの間に画像を撮影します。小腸の内部を詳しく調べたい場合に使われることが多いですが、大腸全体の精密検査には通常の大腸カメラが向いています。
適切な検査を選ぶポイント
医師は問診や血液検査、症状の経過などを総合的に判断して、どの内視鏡検査を行うか決定し、水様性下痢の場合、大腸カメラを中心に、場合によっては胃カメラを併用することもあります。
自分の症状を正確に医師に伝えることで、検査の選択がスムーズになるでしょう。
検査前後の準備と注意点
初めて内視鏡検査を受ける人にとっては、準備方法や検査後の過ごし方が気になるところです。腸をきれいにする作業や食事制限など、スムーズに検査を受けるためのポイントを紹介します。
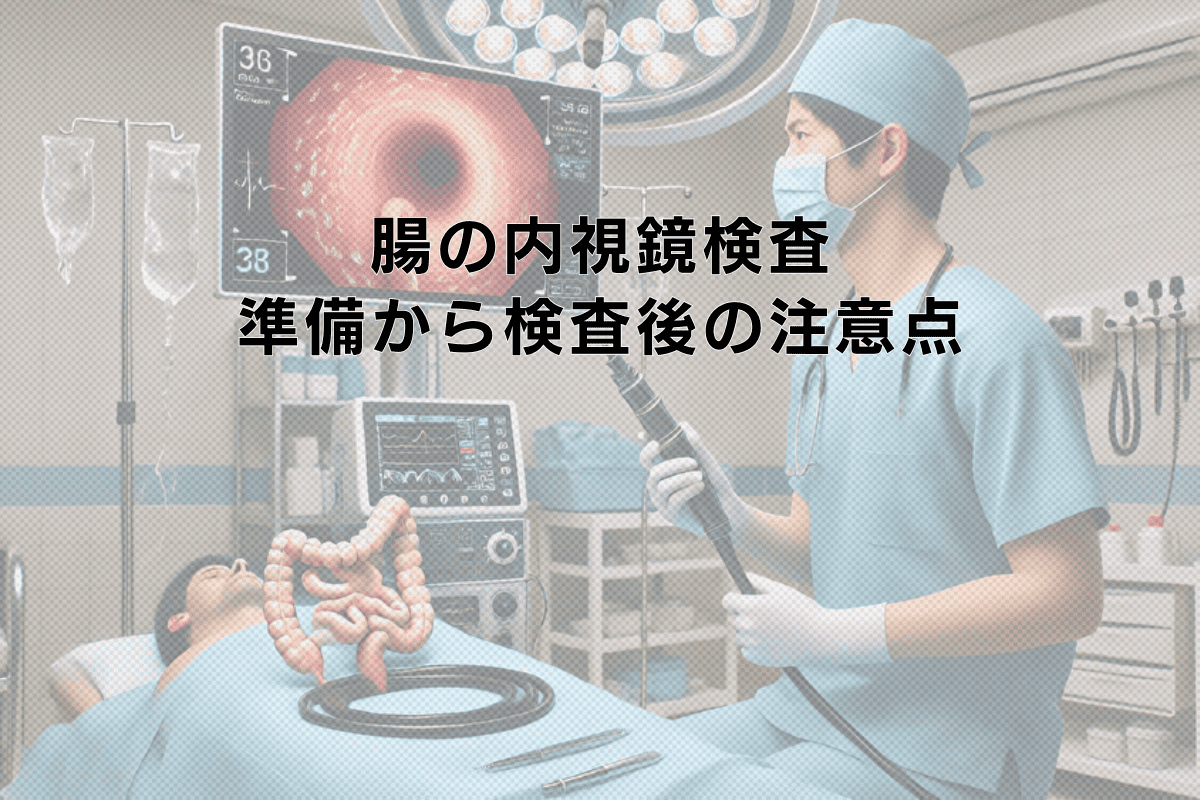
検査前の食事制限
大腸カメラを受ける場合、前日から食事制限があり、消化の良いものを選び、検査当日は下剤を飲んで腸の中を空にしなければなりません。胃カメラの場合も、検査の6時間ほど前からは絶食が一般的です。
検査前に控えたい食品
| 食品分類 | 控えたい例 | 代替案 |
|---|---|---|
| 繊維質の多い野菜 | キノコ類、海藻類、根菜類など | ほうれん草や柔らかい葉物の少量摂取 |
| 種や皮が多い果物 | イチゴ、ブドウ、ゴマ入り食品など | 皮をむいたリンゴや白桃のコンポート |
| 脂質の多い食品 | 揚げ物、ベーコン、チーズなど | 茹でた鶏ささみや白身魚 |
| 香辛料・刺激物 | カレー、キムチ、唐辛子入り食品 | 薄味のスープやおかゆ |
検査の精度を上げるためには、腸内に残渣が残らないようにすることが大切です。
下剤の服用
大腸カメラの場合、下剤を飲んで腸内をきれいにします。大量の水分を一気に飲むため、稀に気分が悪くなることもありますが、飲み方のコツや味つきの下剤を活用することで比較的乗り越えやすいです。
下剤を飲むときに気をつけたいポイント
- 指定された時間内に飲み終えるようにする
- 体調を見ながら少しずつ摂取量を調整する
- トイレに行きやすい環境を整えておく
腸が十分きれいでないと検査の精度が落ちます。
検査中のリラックス法
検査時に痛みや不快感を覚える人もいます。医療機関によっては鎮静剤を使うことができるので、希望があれば検査前に相談してください。呼吸を深くゆっくりとするなど自分なりのリラックス法を身につけると、緊張がやわらぐことがあります。
検査後の注意
検査後は麻酔や鎮静剤が残っているとふらつきや眠気を感じることがあるため、当日はできるだけ安静に過ごし、車の運転や激しい運動は控えてください。
また大腸カメラで生検やポリープ切除を行った場合は、医師から提示された注意事項を守りましょう。
内視鏡検査後の留意点
| 項目 | 注意の内容 |
|---|---|
| 運動 | 当日は軽めのウォーキング程度にとどめる |
| 食事 | 刺激の少ない、消化の良い食事を選ぶ |
| 入浴 | 長時間の入浴や熱い湯は避け、短めのシャワー程度に |
| アルコール・喫煙 | できるだけ控える |
| 便に血が混じる場合 | 過度な出血があれば早めに医療機関へ連絡 |
検査後の過ごし方にも注意を払うことで、合併症やトラブルを防ぎやすくなります。
よくある質問
水様性下痢が続く理由や内視鏡検査について、受診や検査を検討している方からよく寄せられる質問をまとめました。気になることがあれば一つの目安にしていただければ幸いです。
- 下痢が1週間以上続いていますが、すぐに受診したほうがいいですか?
-
1週間以上下痢が止まらず、しかも水のような便が頻回に出る場合は早めの受診がおすすめで、体重減少や倦怠感が重なっているなら、なおさら受診の優先度は高いです。
- 下痢以外の症状はありませんが内視鏡検査が必要ですか?
-
下痢以外に目立った症状がなくても、慢性化すれば腸内で炎症が広がっている場合があります。特に水っぽい便が長く続くときは一度検査を受けてみると安心です。
早期発見によって大腸ポリープや炎症性腸疾患などが見つかる可能性もあります。
- 内視鏡検査は痛そうで不安ですが大丈夫でしょうか?
-
大腸カメラでは個人差がありますが、下剤の服用や検査時の空気の注入による張り感などで不快感を覚えることが多いです。ただ、医療機関によっては鎮静剤や炭酸ガス送気を活用し、負担を軽減する工夫を行っています。
恐怖心が強い場合は事前に相談してください。
以下の記事を参考にして下さい。
⇒内視鏡検査時の鎮静剤使用による苦痛軽減と注意事項 - 普段は整腸剤だけで対処しています。これでも問題ないですか?
-
軽度の下痢なら市販薬や整腸剤で改善することもありますが、水様性下痢が長期化しているときは何らかの器質的病変がある可能性を見逃せません。
自己判断だけで続けるよりも、一度専門医の診断を受けて原因をはっきりさせるほうが安心です。
次に読むことをお勧めする記事
【水のような下痢と腹痛の症状 – 内視鏡検査による原因究明】
水様性下痢の原因を押さえたら、次は腹痛を伴うケースで検査が必要になるタイミングを知っておくと安心です。症状が重なる方に特に役立つ内容です。
【内視鏡検査で確認する下痢の定義と重症度の判定基準】
下痢について理解が深まったところで、次は重症度の客観的な判定方法も押さえておくと、医師への相談がスムーズです。
参考文献
Ihara E, Manabe N, Ohkubo H, Ogasawara N, Ogino H, Kakimoto K, Kanazawa M, Kawahara H, Kusano C, Kuribayashi S, Sawada A. Evidence-based clinical guidelines for chronic diarrhea 2023. Digestion. 2024 Dec 9;105(6):480-97.
Konishi KI, Mizuochi T, Yanagi T, Watanabe Y, Ohkubo K, Ohga S, Maruyama H, Takeuchi I, Sekine Y, Masuda K, Kikuchi N. Clinical features, molecular genetics, and long-term outcome in congenital chloride diarrhea: a nationwide study in Japan. The Journal of Pediatrics. 2019 Nov 1;214:151-7.
Ono M, Kato M, Miyamoto S, Tsuda M, Mizushima T, Ono S, Nakagawa M, Mabe K, Nakagawa S, Muto S, Shimizu Y. Multicenter observational study on functional bowel disorders diagnosed using Rome III diagnostic criteria in Japan. Journal of Gastroenterology. 2018 Aug;53:916-23.
Ito R, Sakagami J, Kataoka K, Nakamura H, Motoyoshi T, Takada R, Kanemitsu D, Yasuda H, Mitsufuji S, Okanoue T. Chronic diarrhea and protein-losing gastroenteropathy caused by Dientamoeba fragilis. Journal of gastroenterology. 2004 Nov;39:1117-9.
Pawlowski SW, Warren CA, Guerrant R. Diagnosis and treatment of acute or persistent diarrhea. Gastroenterology. 2009 May 1;136(6):1874-86.
Kinoshita Y, Sanuki T, Oouchi S, Kawashima K, Ishihara S. Bile Acid Diarrhea: An Etiology of Chronic Diarrhea Easily Overlooked. Shimane Journal of Medical Science. 2021;38(3):89-97.
Ikuta SI, Yasui C, Kawanaka M, Aihara T, Yoshie H, Yanagi H, Mitsunobu M, Sugihara A, Yamanaka N. Watery diarrhea, hypokalemia and achlorhydria syndrome due to an adrenal pheochromocytoma. World journal of gastroenterology: WJG. 2007 Sep 14;13(34):4649.
Ihana-Sugiyama N, Nagata N, Yamamoto-Honda R, Izawa E, Kajio H, Shimbo T, Kakei M, Uemura N, Akiyama J, Noda M. Constipation, hard stools, fecal urgency, and incomplete evacuation, but not diarrhea is associated with diabetes and its related factors. World journal of gastroenterology. 2016 Mar 21;22(11):3252.
Schiller LR, Pardi DS, Sellin JH. Chronic diarrhea: diagnosis and management. Clinical Gastroenterology and Hepatology. 2017 Feb 1;15(2):182-93.
Juckett G, Trivedi R. Evaluation of chronic diarrhea. American family physician. 2011 Nov 15;84(10):1119-26.










