大腸は消化管の最後を担う器官であり、日頃の食生活やストレス、加齢の影響を受けやすい部分です。ポリープや腫瘍などの病変が存在しても初期段階では症状が出にくいため、定期的な検査が大切です。
腸の内側を直接観察できる内視鏡による大腸の検査は、早期発見や正しい治療方針の選択に役立ち、健康管理においても注目を集めています。
これを機に、大腸の構造や検査方法を理解し、大きな病気を予防するための一歩を踏み出してみましょう。
大腸内視鏡検査の概要と目的
大腸の内視鏡では長いスコープを肛門から挿入して腸全体をチェックしながら、腫瘍やポリープ、炎症などを直接確認できます。体の中を直接見ることで早期診断を目指し、必要に応じてポリープ切除や組織の採取も行います。
大腸内視鏡による観察の特徴
大腸の内視鏡は先端にカメラとライトが付いた細長い機器で、肛門から結腸、直腸へと進めていき、腸壁の状態をくまなく確認します。大腸の中を直接見るため、X線やCTとは異なり細かな病変も見つけやすいです。
- 腸壁のわずかな変化でも捉えやすい
- ポリープや怪しい部位をその場で切除・採取できる
- 粘膜の色調や形状の異常を把握しやすい
このように、画像検査だけでは見つかりにくい初期の病変も発見しやすいことが特徴です。
X線やCT検査との違い
レントゲンやCTでは腸の外観や大まかな形態をチェックしやすい一方で、小さなポリープや軽度の粘膜変化は把握しにくい場合がありますが、内視鏡検査は直接カメラが腸内を映すので、微細な変化も見落としにくいです。
ただし、体への負担や検査時間なども考慮すると、それぞれの方法にメリットと限界があります。
画像診断と内視鏡検査の特性
| 検査方法 | 特性 | メリット |
|---|---|---|
| X線検査 | 透過性を利用して大腸の形を把握しやすい | 短時間で実施しやすい、腸閉塞などを確認しやすい |
| CT | 断面画像から立体的に状態を把握しやすい | 全身の評価ができる、大腸以外の臓器の状態も確認可 |
| 内視鏡 | 肉眼レベルで粘膜表面を直接観察できる | 初期の病変や微細な変化を捉えやすく、同時に治療も可能 |
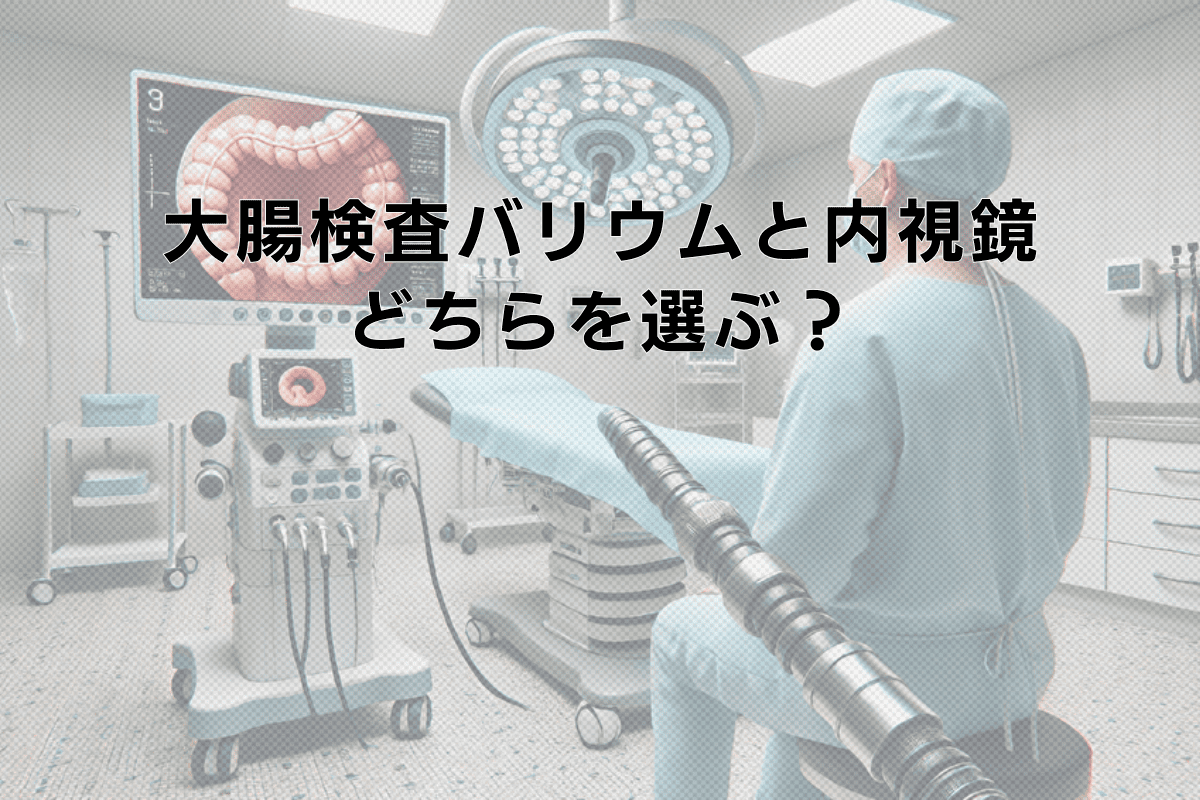
なぜ大腸内視鏡が推奨されるのか
大腸内視鏡は、大腸がんの早期発見や炎症性腸疾患の診断に直結します。特に大腸がんは初期の段階ではほとんど症状を感じにくいですが、内視鏡であれば小さなポリープの段階で発見できる可能性が高まります。
さらに検査中に必要に応じてポリープを切除すれば、その場で治療が完了するケースもあります。
検査にはデメリットも
大腸内視鏡は直接カメラを挿入するため、腹部に張りを感じたり、人によっては痛みを伴う可能性があります。また、事前の下剤使用や検査時間、医療機関によっては麻酔の使用の有無など、患者さんの負担になる点もあります。
メリットとデメリットを把握しながら、自分に合う受診スタイルを選ぶことが大切です。

受診がすすめられる症状やリスク要因
大腸内視鏡を受けたほうが良いかどうかは、症状や年齢、家族歴などによって変わってきます。早期受診を考えるきっかけとして、どのような症状やリスク因子があるのかを知っておくと便利です。
検査を受ける必要性を感じやすくなる主なポイントを把握すれば、病気の早期発見につながりやすくなります。
腹痛や便秘・下痢が続く
おなかの痛みや便秘・下痢などの症状は、多くの場合、一時的な体調不良や過敏性腸症候群などと結びつけてしまいがちですが、症状が長期化すると大腸ポリープや大腸がん、潰瘍性大腸炎などの疾患が隠れている可能性があります。
普段と違う便通異常が2週間以上続くときは、医療機関への相談を検討しましょう。
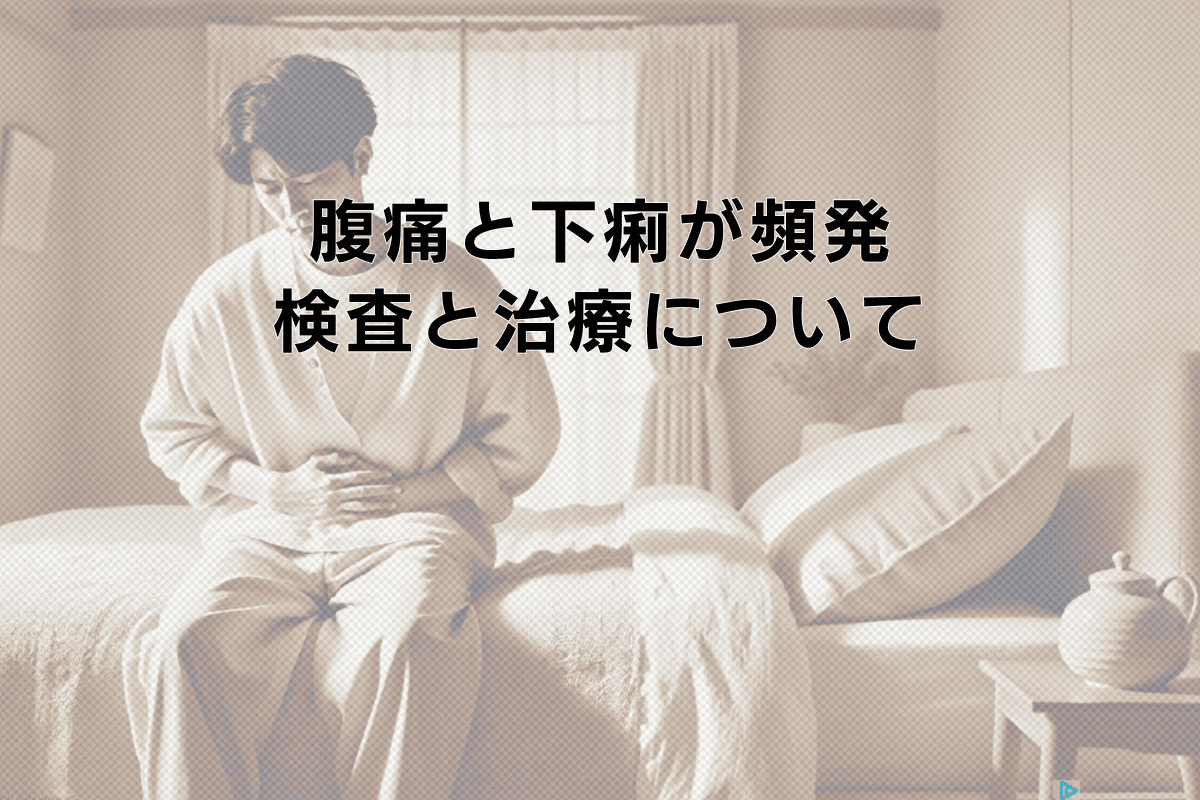
便に血が混じる
便に鮮血や暗い色の血が付着する場合切れ痔や痔核が原因かもしれませんが、大腸ポリープや大腸がんなどの疾患が疑われるケースもあります。痔だから大丈夫と自己判断せず、一度内視鏡で確認すると安心できます。
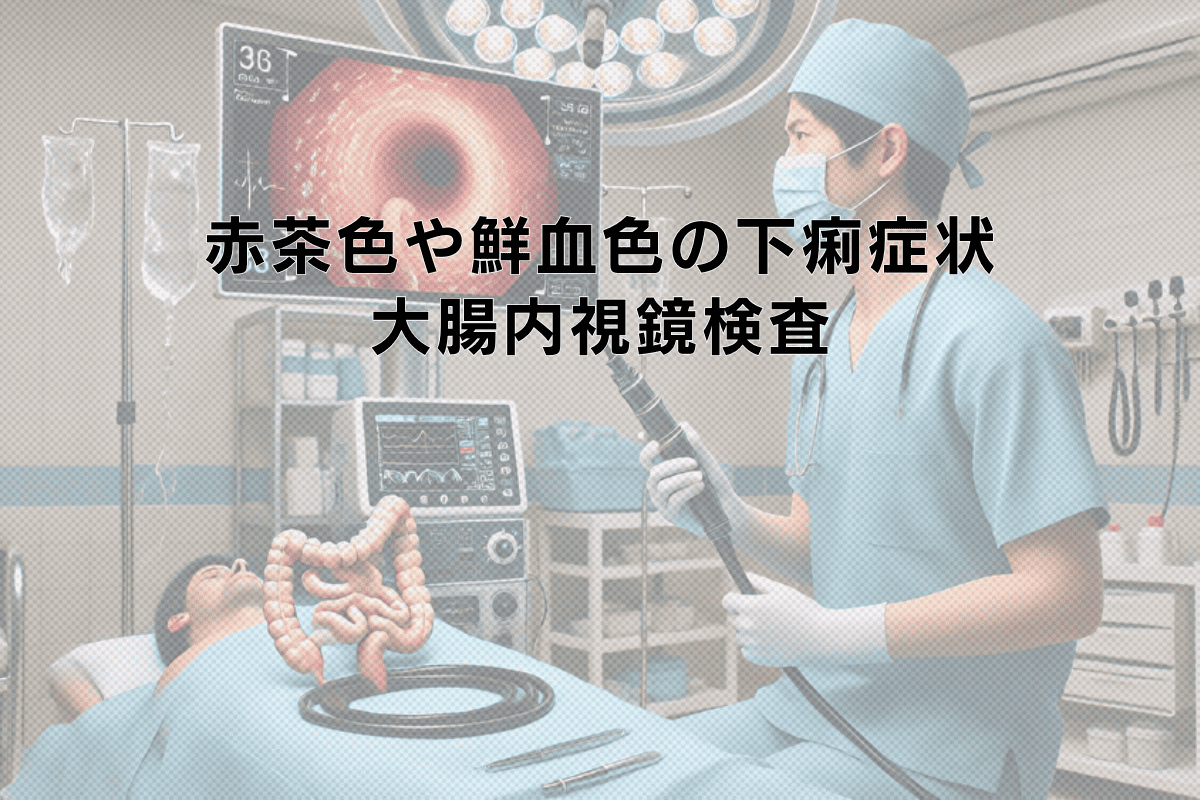
血便の色と考えられる要因
| 血便の色合い | 考えられる部位や原因 |
|---|---|
| 鮮紅色 | 直腸や肛門付近の出血(切れ痔、痔核、直腸ポリープなど) |
| 暗赤色 | 結腸からの出血(ポリープ、大腸がん、虚血性大腸炎など) |
| 黒色 | 消化管上部(胃や十二指腸など)からの出血、場合によっては大腸がん |
家族に大腸がん患者がいる
がんの中には遺伝的要素が強いタイプもあり、大腸がんを家族が経験している場合、ある程度のリスク上昇が考えられるため、定期的な検査が推奨されます。
家族歴が複数ある場合は若年でも安心できないケースがあるので、早めの検査を検討してください。

40代以降の定期検査
40代を過ぎると生活習慣病やがんのリスクが高まる時期で、大腸がんは50代以降に増える傾向がありますが、近年では40代での発症も少なくありません。
症状がなくても年に1度、大腸の検査を含む健康診断を考えることで、早期に異常を見つけられる可能性が上がります。
検査前の準備(食事制限や下剤使用)
大腸内視鏡では、腸内をできるだけきれいな状態にして観察を行うため、検査前の食事制限や下剤の使用が大切です。準備を怠ると検査に時間がかかったり、観察が不十分になったりして、正確な診断が難しくなることもあります。
食事のとり方
検査前日は消化に負担をかけない食事に切り替えると、腸の中に残渣がたまりにくくなります。脂っこいものや繊維の多い野菜、キノコ類、海藻類などは避け、可能であれば医療機関で推奨される食事指導に従いましょう。
また、水分はこまめに摂取し、脱水を防ぐことも重要です。
検査前日から当日のおすすめ食材と控えたい食材
| 分類 | おすすめ食材 | 控えたい食材 |
|---|---|---|
| 主食 | 白米、おかゆ、素うどん | 玄米、雑穀米、ラーメン、パスタ |
| おかず | 白身魚、豆腐、卵料理 | 揚げ物、脂の多い肉、繊維質の多い野菜(ごぼう、れんこん) |
| デザート類 | ヨーグルト(果実なし)、プリン | フルーツ入りヨーグルト、ゼリー、果物 |
| 飲み物 | 水、お茶、スポーツ飲料(透明タイプ) | 牛乳、コーヒー、ジュース、アルコール |
下剤の内服
内視鏡検査では、大腸内を空に近い状態にしないと、ポリープや腫瘍の見落としが生じやすくなるので、指定されたタイミングで下剤を飲み、排便を促します。
下剤の種類は機関によって異なり、大量の水で薄めた溶液を数時間かけて飲むケースや、少量タイプの下剤を複数回服用するケースもあります。

下剤服用時の注意点
下剤を飲んでいる最中はおなかの不快感や腹痛が起こることがあるので、トイレに行きやすい環境を整えておき、室温や服装にも配慮すると安心です。脱水を防ぐため水分補給を怠らないようにしながら、指示された量をきちんと飲み切りましょう。
下剤服用時に押さえたいポイント
- 余裕を持った時間を確保して飲む
- こまめな水分摂取で脱水を防ぐ
- 強い腹痛や嘔吐がある場合は医療機関へ連絡する
検査前のその他の注意事項
薬を常用している場合や妊娠中・授乳中など、個別の状況によっては下剤の種類や服用タイミングが変わることがあります。また、糖尿病の方はインスリン注射や薬の調整を行うこともあるため、事前の問診でしっかり伝えておくことが大切です。
検査当日の流れとポイント
大腸内視鏡検査当日は、受付から検査終了までに一定の手順があり、スムーズに検査を受けるために、どのような流れで進むのかを知っておくと心構えがしやすくなります。
受付・問診
検査当日は余裕を持った時間にクリニックへ行き、受付を済ませます。問診票や体調の確認を行い、下剤がしっかり効いているか、排便状態がどうかなどを確認します。
医師や看護師から検査の最終説明を受けた後に、更衣室でリラックスできる服装に着替えることが多いです。
前処置室での待機
さらに腸内がきれいかどうかをチェックするため、看護師が便の状態やおなかの症状を確認し、腸の動きが不十分な場合は追加の下剤や浣腸などで腸内を整えることがあります。
待機中は緊張しがちですが、ゆっくり呼吸を整えて準備を続けましょう。
当日の持ち物や服装
| 持ち物 | 服装 | その他 |
|---|---|---|
| 保険証、診察券 | ウエストがきつくないズボンやスカート | お腹を締め付けない下着 |
| 常用薬(病院から指示がある場合) | 脱ぎ着しやすい羽織もの | サンダルやスリッパがあると便利 |
| 検査結果などの書類(再検査の場合) | 衛生的に脱ぎやすい靴 | 検査後に休憩する用の小さなタオルなど |
内視鏡室へ移動
前処置室で準備が整ったら内視鏡室へ移動したあとはベッドに横になり、場合によっては鎮静剤を使うことがあります。鎮静剤を使うと検査中の苦痛が和らぐ反面、眠気やふらつきが出るので、医療スタッフが安全を確認しながら進めます。
検査後の回復室での安静
検査が終わったら回復室でしばらく横になり、意識がはっきりしているか、吐き気や痛みがないかを確認し、ポリープ切除などを行った場合は出血が起きやすいため、少し長めに安静時間をとることもあります。
問題がなければ医師から検査結果の簡単な説明を受け、帰宅が可能です。
検査中の痛みや不安への対策
大腸内視鏡に対して「痛い」「苦しい」というイメージを抱く方は少なくありません。実際に個人差はありますが、検査の技術向上や鎮静剤の活用によって、負担を軽減する取り組みが進んでいます。
空気ではなく二酸化炭素を使う
大腸内視鏡では腸を広げるために従来は空気を使うケースが多かったのですが、近年では二酸化炭素を用いる方法も増えています。
二酸化炭素は体内への吸収が早く、検査後の腹部膨満感を軽減しやすいです。医療機関によって対応が異なるので、痛みや膨満感が気になる方は相談してください。
鎮静剤の使用
鎮静剤を用いて検査を行うと、半分眠っているような状態になり、苦痛や怖さを感じにくくなりる一方で、鎮静剤には副作用として血圧低下や呼吸抑制のリスクがあります。
そのため、使用時は医師や看護師が血圧や酸素濃度を綿密にモニタリングしながら実施することが重要です。
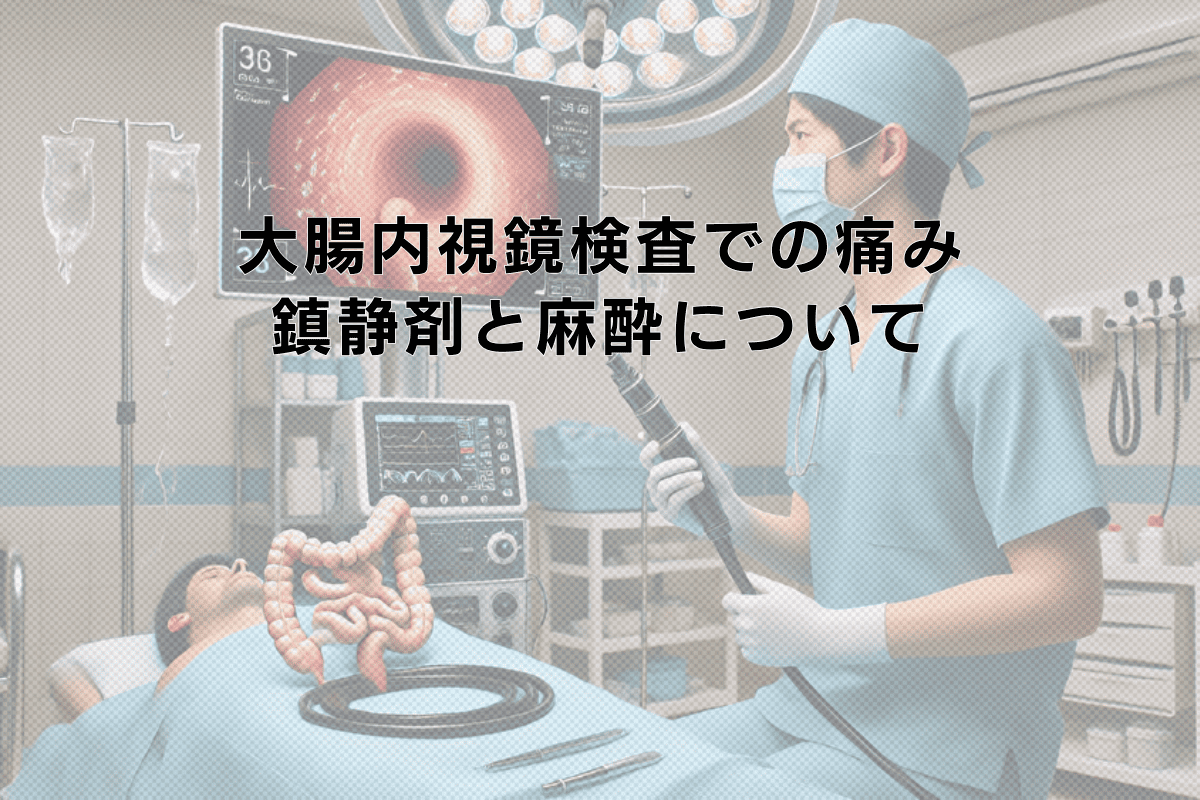
鎮静剤使用のメリットと注意点
| 項目 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|
| 検査中の痛みや不安軽減 | 半覚醒の状態になるため苦痛の記憶が残りにくい | 検査後しばらくはふらつきや眠気が出ることがある |
| 医療スタッフの操作 | リラックスした状態で内視鏡を通しやすい | 血圧や呼吸の変化を頻繁に観察する必要がある |
| 帰宅時の行動制限 | 車の運転は避ける、公共交通機関やタクシー利用など安全面に配慮しやすい | 外出先で倒れる危険性や転倒のリスクがあるため、検査当日は休息を意識する |
熟練した医療スタッフによる配慮
検査の苦痛を大きく左右するのは技術だけでなく、医療スタッフの配慮も関係し、ゆっくりカメラを進める工夫、腸の曲がり角に合わせた操作、患者さんとのコミュニケーションなど、細やかな対応があると安心につながりやすいです。
事前に不安な点を率直に伝えておくと、スタッフ側も配慮しながら検査を進めやすくなります。
痛みへの対策としてできること
- 事前に鎮静剤のメリット・リスクを相談して決める
- 腹部の張りを軽減するための呼吸法を意識する
- 痛みを感じたら我慢せずスタッフに知らせる
患者さん自身が情報を把握しておくと、不安が軽減し、より落ち着いた気持ちで検査にのぞめます。
検査でわかる病気と治療
大腸の内視鏡検査では、腸内の病変を発見すると同時に、一部はその場で治療が可能です。検査を受けることで見つかる代表的な病気や、それぞれの治療方針を知っておくと、検査後の選択肢をイメージしやすくなります。
大腸ポリープ
ポリープは良性の腫瘍であり、将来的にがん化する可能性があるものや、良性のまま止まるものなどさまざまです。
大腸内視鏡ではポリープを確認した際に切除できる場合が多く、小さなポリープなら日帰りで切除することも可能です。切除したポリープは、病理検査で詳しい性質を調べます。
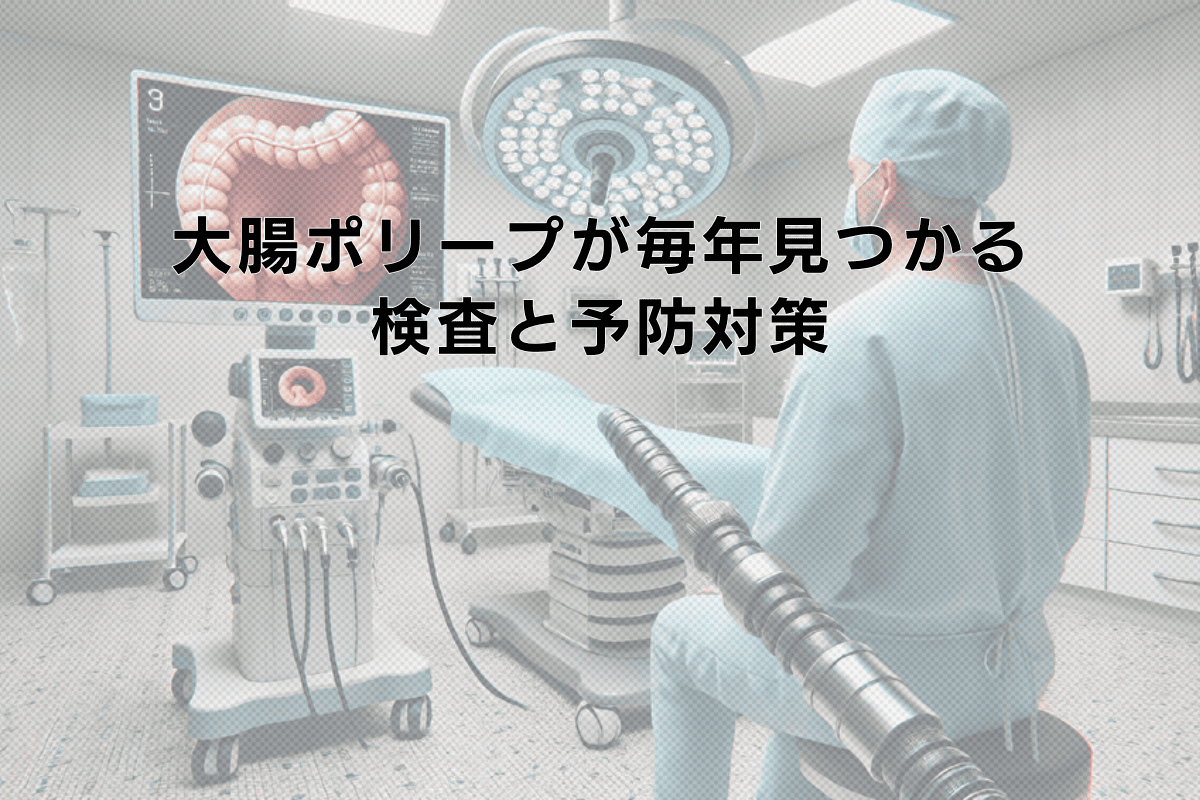
大腸ポリープの種類と特徴
| 種類 | 特徴 | リスク |
|---|---|---|
| 腺腫性ポリープ | がん化リスクが高め(特に腺腫の一部) | 早期発見と切除が推奨される場合がある |
| 過形成性ポリープ | 小さい場合は良性であることが多い | 大きくなると切除検討が必要になる |
| 炎症性ポリープ | 炎症性腸疾患に伴う二次的なポリープ | 原因となる炎症のコントロールが重要 |
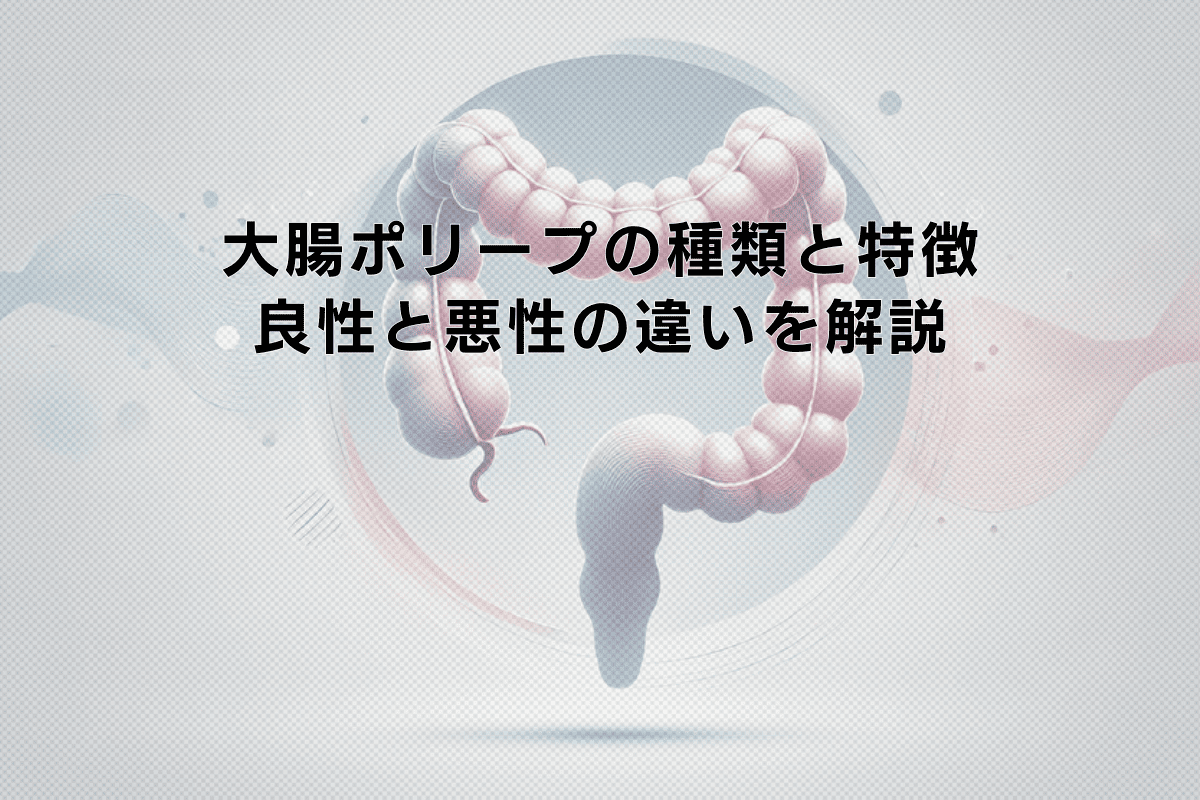
大腸がん
大腸がんは日本人のがん死亡原因の上位に挙げられますが、内視鏡検査を定期的に受けていれば早期発見の可能性が高まります。早期段階で発見できれば内視鏡で切除し、追加治療をほとんど行わずにすむケースもあります。
しかし、進行度が高いと外科手術や化学療法などが必要になるため、早期の受診が非常に大切です。

潰瘍性大腸炎やクローン病
腸に炎症が広範囲にわたって生じる潰瘍性大腸炎、口から肛門まであらゆる部位に炎症を起こす可能性のあるクローン病も、内視鏡検査で診断に近づきます。
症状が似ていても炎症の分布や特徴が異なるため、内視鏡所見と組織検査から正確な診断を行い、薬物治療や食事療法を組み合わせてコントロールしていきます。

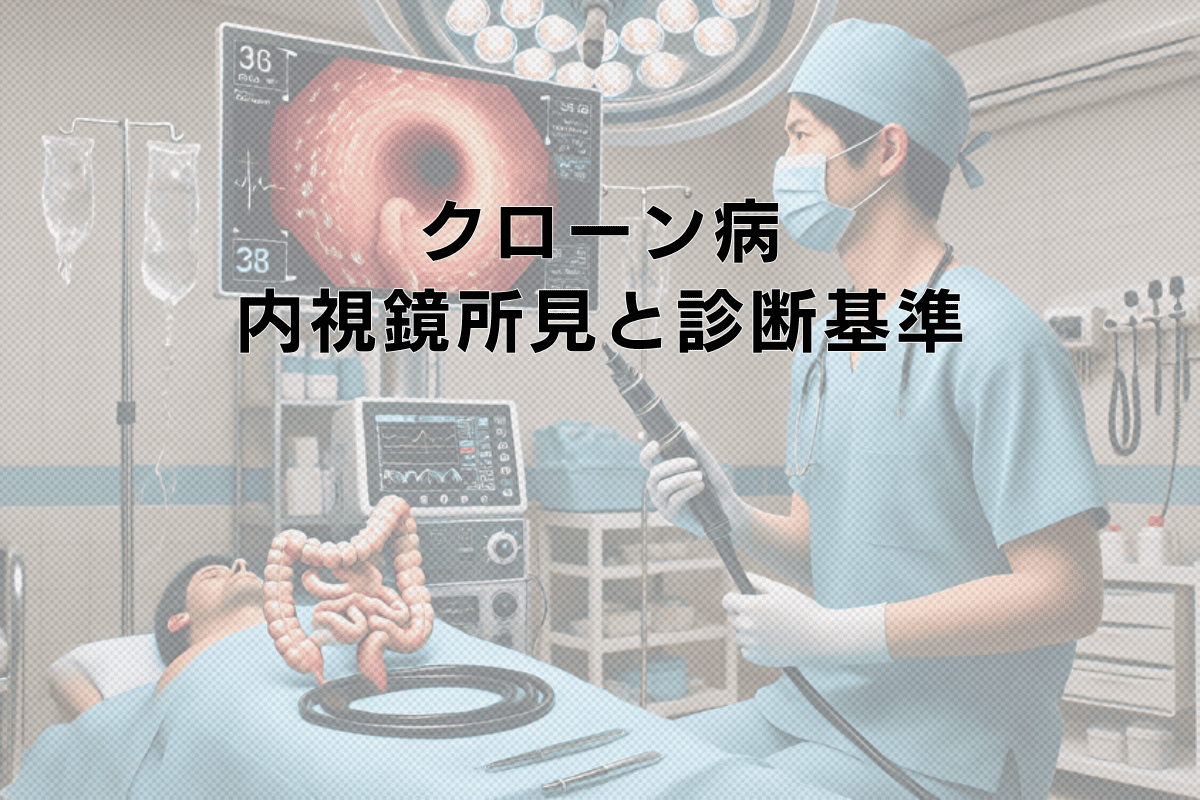
虚血性大腸炎や感染症
虚血性大腸炎は腸への血流不足が原因で発症し、急な腹痛や下血を伴うことがある病気です。内視鏡で腸壁の状態を確認すると診断や治療方針が立てやすくなります。
また、大腸菌などの感染症による腸炎も粘膜の様子から推測でき、細菌検査の結果と合わせて治療を決めます。
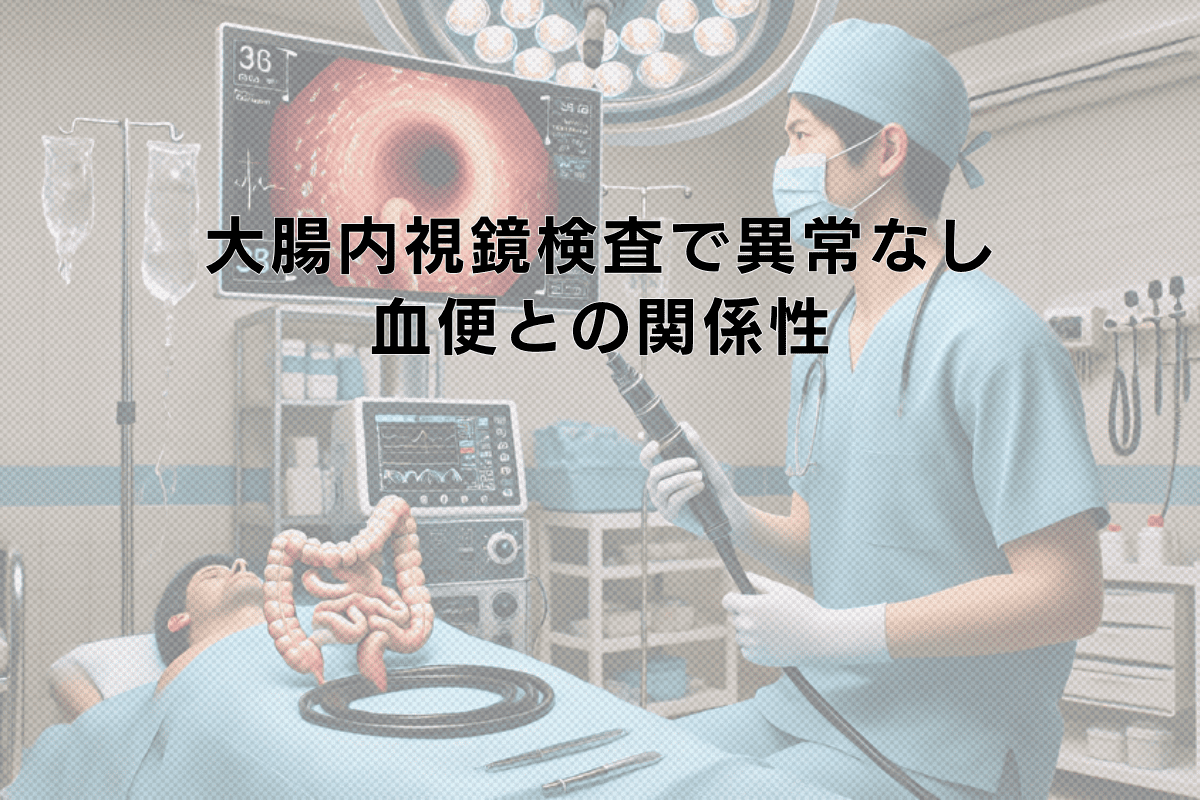
大腸内視鏡検査後の過ごし方と注意点
検査が終わると日常生活に戻れますが、ポリープ切除や組織採取を行った場合は一時的な制限や注意が必要になることがあります。検査後の体調管理を怠らず、異常を感じたら医療機関に連絡することが大切です。

食事や運動制限
ポリープ切除を行った場合、翌日までは激しい運動やアルコールの摂取を控えるように指示されることが多く、組織を切り取った部位から出血するリスクがあり、安静を意識すると安心です。
また、消化に優しい食事を選ぶと腸内への負担を減らせます。
検査後に気をつけたいポイント
- 切除後は出血や腹痛をチェックする
- 高温の入浴や過度な運動は数日間控える
- アルコールや刺激物の摂取を控えて腸粘膜をいたわる
便通と排便の状態
内視鏡検査で使う下剤や空気(二酸化炭素)の影響で、検査後は便秘や下痢が起こる方もいます。一時的な症状なら心配不要なことが多いですが、出血や腹痛を伴う場合は医療機関へ連絡してください。
便の色が黒っぽい場合なども、切除部位の出血があるかどうかチェックしてもらうことが大切です。
痛みや張りが続くとき
検査後に軽い腹部の張りや痛みを感じることはありますが、通常は数時間から1日程度で治まります。持続的な強い痛みや血便が出た場合は、切除部位の出血や穿孔などの合併症が疑われるので、すぐに医療機関へ連絡して指示を仰いでください。
検査後のフォローアップ
大腸内視鏡検査では、その場で病変を見つけて治療した場合や、生検を行った場合もあります。後日、病理検査の結果を受け取る必要があるので、担当医の指示どおりに再診して今後の治療方針や定期検査の間隔を確認しましょう。
再受診や定期検査のタイミング
| ケース | 受診タイミング | 内容 |
|---|---|---|
| ポリープ切除のみ | 検査後1週間前後(医師指定) | 出血や痛みの有無、切除部位の回復状況をチェック |
| 生検を行った(病理検査が必要) | 検査後2週間前後 | 検査結果の説明、病変の良悪性の判定 |
| 潰瘍性大腸炎やクローン病の疑い | 随時(症状の経過をみながら) | 炎症コントロールの具合、薬の調整 |
| 年齢や家族歴によるリスク管理目的の検査 | 1年から2年ごとの定期検査 | ポリープの出現や病状の変化を確認 |
クリニックでの受診メリット
大腸内視鏡は病院だけでなく、内視鏡検査を専門的に行うクリニックでも受けられます。大病院と異なり、予約の取りやすさや待ち時間の少なさなど、受診を検討する上でのメリットがあります。
予約の取りやすさと柔軟な対応
大病院は検査枠が限られていて予約が数か月先になることも珍しくありません。一方、クリニックは検査の専門日を複数設定している場合が多く、比較的スムーズに予約できることがあります。
平日忙しい方や突発的に休みがとれた方にも柔軟に対応しやすい体制を整えているところもあるので、相談してみましょう。
専門医が身近にいる安心感
クリニックでも内視鏡の専門医が在籍しているケースが多く、検査技術や診断能力に優れた医師が担当します。
外科的な大規模治療が必要と判断された場合は、大きな病院に紹介してくれるため、一次的なスクリーニングや早期診断の段階では十分に頼れます。
クリニック受診のポイント
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| アクセスの良さ | 自宅や職場から通いやすい立地を選ぶと継続的な受診が行いやすい |
| 設備の充実度 | クリニックによっては大病院と同等の内視鏡設備を用意している |
| スタッフとの連携 | 小規模だからこそ患者さんの状態を継続的に把握しやすい |
| 紹介先の病院との連携 | 大きな治療が必要になった際のスムーズな情報共有が期待できる |
アフターフォローが受けやすい
クリニックは通いやすい環境が整っていることが多く、検査後の経過観察や定期チェックを継続しやすいです。気軽に来院できるため、検査後に疑問点が生じたときも相談しやすいでしょう。
特にポリープ切除後の受診や、炎症性腸疾患の治療管理では長期の付き合いが必要になるため、通院のしやすさは重要です。
より身近に健康管理ができる
大腸内視鏡は「がんや大きな病気を見つけるためだけの検査」というイメージを抱きやすいですが、実際には便通異常やお腹の張りといった身近な症状に対しても力を発揮します。
クリニックで気軽に相談しながら検査を受けることで、小さな異常も見逃さず健康管理を進めることが可能です。
次に読むことをお勧めする記事
【大腸内視鏡検査の前日に必要な準備と食事の注意点】
大腸内視鏡検査の基本を押さえたら、次は実際の検査前日の準備について知っておくと安心です。検査を初めて受ける方や、前回の準備がうまくいかなかった方に特に参考になる内容です。
【大腸ポリープの基本症状から治療法まで – 患者さんのための総合案内】
大腸内視鏡検査について理解が深まると、検査で最も多く発見される大腸ポリープについても知りたくなる方が多いようです。ポリープの種類や治療法との意外な繋がりが見えてくる内容です。
参考文献
Kurlander JE, Sondhi AR, Waljee AK, Menees SB, Connell CM, Schoenfeld PS, Saini SD. How efficacious are patient education interventions to improve bowel preparation for colonoscopy? A systematic review. PloS one. 2016 Oct 14;11(10):e0164442.
Ahmed WR, Makkawy MM, Sayed ZA, Azer SZ. Effect of different nursing educational methods on the quality of bowel cleanliness for patients undergoing colonoscopy. Journal of Nursing Education and Practice. 2016 Jul 1;6(7):54.
Rex DK, Schoenfeld PS, Cohen J, Pike IM, Adler DG, Fennerty BM, Lieb JG, Park WG, Rizk MK, Sawhney MS, Shaheen NJ. Quality indicators for colonoscopy. Official journal of the American College of Gastroenterology| ACG. 2015 Jan 1;110(1):72-90.
Hassan C, East J, Radaelli F, Spada C, Benamouzig R, Bisschops R, Bretthauer M, Dekker E, Dinis-Ribeiro M, Ferlitsch M, Fuccio L. Bowel preparation for colonoscopy: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) guideline–update 2019. Endoscopy. 2019 Aug;51(08):775-94.
Rex DK, Schoenfeld PS, Cohen J, Pike IM, Adler DG, Fennerty BM, Lieb JG, Park WG, Rizk MK, Sawhney MS, Shaheen NJ. Quality indicators for colonoscopy. Official journal of the American College of Gastroenterology| ACG. 2015 Jan 1;110(1):72-90.
Mathus-Vliegen E, Pellisé M, Heresbach D, Fischbach W, Dixon T, Belsey J, Parente F, Rio-Tinto R, Brown A, Toth E, Crosta C. Consensus guidelines for the use of bowel preparation prior to colonic diagnostic procedures: colonoscopy and small bowel video capsule endoscopy. Current Medical Research and Opinion. 2013 Aug 1;29(8):931-45.
Fisher DA, Maple JT, Ben-Menachem T, Cash BD, Decker GA, Early DS, Evans JA, Fanelli RD, Fukami N, Hwang JH, Jain R. Complications of colonoscopy. Gastrointestinal endoscopy. 2011 Oct 1;74(4):745-52.
Paggi S, Amato A, Anderloni A, Annese V, Barresi L, Buda A, Cesaro P, Di Giulio E, Gullotti G, Fabbri C, Fiori G. Pre-and post-procedural quality indicators for colonoscopy: a nationwide survey. Digestive and Liver Disease. 2016 Jul 1;48(7):759-64.
Rex DK, Bond JH, Winawer S, Levin TR, Burt RW, Johnson DA, Kirk LM, Litlin S, Lieberman DA, Waye JD, Church J. Quality in the technical performance of colonoscopy and the continuous quality improvement process for colonoscopy: recommendations of the US Multi-Society Task Force on Colorectal Cancer. Official journal of the American College of Gastroenterology| ACG. 2002 Jun 1;97(6):1296-308.
Robertson DJ, Kaminski MF, Bretthauer M. Effectiveness, training and quality assurance of colonoscopy screening for colorectal cancer. Gut. 2015 Jun 1;64(6):982-90.










