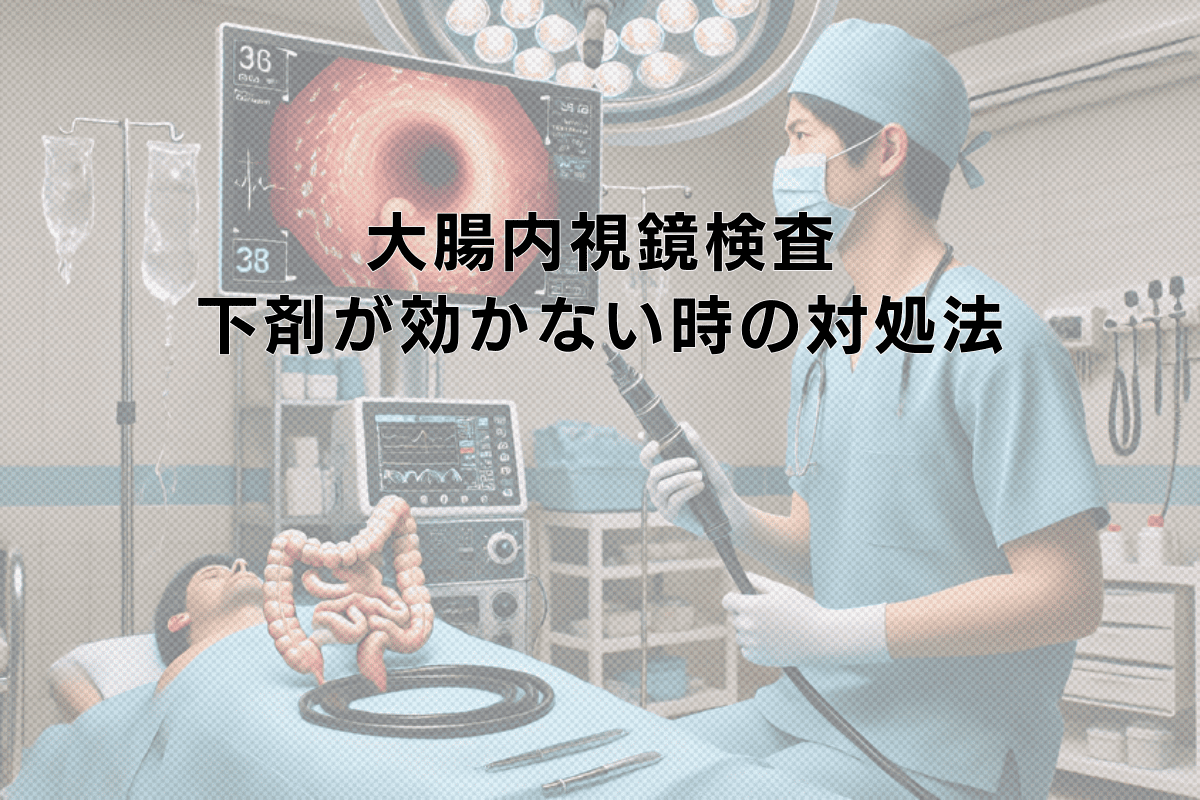大腸内視鏡検査を安全かつ正確に行うためには、下剤(腸管洗浄剤)を服用して大腸の中を完全に空にすることが大切ですが、医療機関の指示通りに下剤を飲んでも、期待される効果がなかなか現れずに強い不安を感じる方は少なくありません。
便意が全く来なかったり、排便があっても腸内がきれいにならなかったりすると、検査がきちんと行えるのか、何か体に異常があるのではないかと心配になることでしょう。
この記事では、大腸内視鏡検査で下剤が効かない場合に考えられる主な原因から、ご自身でできる安全な初期対処法、医療機関へ相談すべきタイミング、今後の検査に向けてできる対策まで、段階を追って詳しく解説します。
なぜ下剤(腸管洗浄剤)が効かないことがあるのか
大腸内視鏡検査の準備で用いる下剤は、腸管洗浄剤とも呼ばれ、腸の内容物を物理的に洗い流すために強力な作用を持っています。
それでも効果が出にくい場合、単に体質的な問題だけでなく、準備段階の食事や過ごし方、下剤の服用方法、さらには精神的な状態など、様々な要因が複合的に絡み合っていることが多いです。
普段からの便秘症の影響
最も一般的で、多くの方が該当する原因の一つが、慢性的な便秘症です。日常的に便秘傾向にある方は、大腸の蠕動運動(ぜんどううんどう)と呼ばれる、便を肛門側へリズミカルに押し出す動き自体が緩やかになっています。
また、便が腸内に長時間滞留することで水分が過剰に吸収され、石のように硬くなって腸壁にこびりついていることさえあります。
そのため、通常量の下剤では腸の動きを十分に促すことができず、硬くなった便を動かすだけの力が不足してしまうのです。
長年にわたり便秘に悩んでいる方や、日常的に刺激性の便秘薬を常用している方は、腸がその刺激に慣れてしまい、下剤に対する反応性が低下している、いわゆる耐性の状態になっている可能性も考えられます。
腸の構造的な問題や既往歴
過去に腹部の手術(例えば、帝王切開、虫垂炎、婦人科系の手術など)を受けたことがある方は、腸管が周囲の組織と癒着を起こしていることがあります。
癒着があると腸の通り道が狭くなったり、動きが悪くなったりして、便がスムーズに通過しにくくなり、また、大腸憩室症のように、腸の壁に小さなくぼみが多数ある場合、そこに便がはまり込んで排出されにくくなっていることもあります。
水分摂取量の不足
腸管洗浄剤の効果を最大限に引き出すためには、十分な水分摂取が極めて重要です。
多くの腸管洗浄剤は、腸管内で水分を保持し、便を軟らかくして容積を増大させることで、腸壁を刺激し蠕動運動を活発にさせ、これを浸透圧性の作用と呼びます。
下剤の服用だけに集中してしまい、水やお茶などの追加の水分摂取が不足すると、腸管内に十分な水分が集まらず、洗浄効果が著しく低下します。
また、体全体が脱水状態に傾くと、生命維持のために体は腸からの水分吸収を優先するため、腸の動きも鈍くなるのです。
下剤そのものに含まれる水分だけでなく、意識的な追加の水分摂取が、腸内を洗い流すための豊かな水流を作り出す鍵を握ります。
水分摂取の目安
下剤服用中は、体内の水分バランスを保ち、洗浄効果を高めるために、意識的な水分補給が重要です。
| タイミング | 推奨される飲み物 | 補給のポイント |
|---|---|---|
| 下剤服用前 | 水、白湯、麦茶 | 体を潤しておく意識でこまめに飲む。前日から意識すると良い。 |
| 下剤服用中 | 水、白湯 | 下剤の合間にコップ1杯程度を目安に飲む。喉の渇きを感じる前に。 |
| 下剤服用後 | 透明なスポーツドリンク、水 | 脱水と電解質異常の予防のため、検査までこまめに補給する。 |
身体の冷えと運動不足
体が冷えると、全身の血行が悪くなりますが、これは胃腸の働きにも直接影響します。内臓の温度が低下すると、消化管の活動を司る自律神経のうち、リラックス時に働く副交感神経の働きが鈍くなり、腸の蠕動運動が弱まってしまいます。
下剤を服用している間、不安から長時間座ったままで動かないでいると、腸への物理的な刺激も少なくなり、便意が起こりにくくなることがあります。
腸管洗浄剤は、あくまで腸が動くことを補助する薬で、軽い運動などで体を温め、腸に外部からの適度な刺激を与えることも、効果を促進する上で重要な要素です。
服用中の他の薬剤との相互作用
普段服用している薬の中には、副作用として便秘を起こすものがあり、腸管洗浄剤の効果を弱めてしまう可能性があります。もし、
以下のような薬を服用している場合は、検査を受ける前に必ず医師や薬剤師に相談し、自己判断で薬を中断することは絶対にしないでください。
| 薬の種類 | 主な用途 | 便秘を引き起こす理由 |
|---|---|---|
| 一部の精神・神経科の薬 | 抗うつ薬、抗精神病薬 | 抗コリン作用により腸の動きを抑制する |
| 医療用麻薬 | がん性疼痛などの強い痛み止め | 腸の蠕動運動を強力に抑制する |
| 一部の降圧薬 | カルシウム拮抗薬 | 腸管の平滑筋の収縮を抑える |
下剤が効かないと感じた時の初期対処法
下剤を飲み始めて1〜2時間経っても便意が全くない、あるいは排便があっても少量でスッキリしない場合、不安になるかもしれませんが、まずは落ち着いて試せる対処法があります。
ただし、我慢できないほどの強い腹痛や、繰り返す吐き気がある場合は対処法を行わずに、速やかに医療機関へ連絡してください。
まずは落ち着いて状況を確認する
焦りや不安といった精神的なストレスは、交感神経を優位にさせ、腸の動きを抑制してしまい、これは、体が緊張状態にあると消化活動が後回しにされる人体の自然な反応です。まずは深呼吸をしてリラックスしましょう。
下剤の効果が現れるまでの時間には個人差があり、便秘症の方などは3時間以上経ってから効果が出始めることもあります。
下剤をいつから飲み始めたか、どのくらいの量を飲んだか、最後に排便があったのはいつか、といった状況を冷静に整理してください。
水分を多めに摂取する
水分不足は下剤の効果を妨げる大きな要因で、下剤の効果を促進するために、水や白湯をコップ1〜2杯(200〜400ml程度)、追加でゆっくり飲んでみましょう。この時、一気に飲むのではなく、10〜15分ほどかけて少しずつ飲むのがポイントです。
胃に負担をかけず、効率よく水分を腸へ届けます。冷たい水は胃腸を過度に刺激し、腹痛の原因になる可能性があるので、常温の水か、人肌程度の白湯が望ましいです。
体を動かして腸を刺激する
長時間座ったままでいると、重力の影響もあり腸の動きは鈍くなります。安静にしすぎず、室内をゆっくりと歩き回ったり、その場で軽く足踏みをしたりするだけでも腸への良い刺激になります。
また、体をゆっくりと左右にひねるストレッチや、仰向けに寝て両膝を抱えて胸に引き寄せる「ガス抜きのポーズ」なども、腹部に適度な圧力をかけ、大腸、特にS状結腸や直腸を刺激し、便意を誘発するのに有効です。
腸を刺激する簡単な動き
無理のない範囲で、以下のような動きを試してみましょう。それぞれ5分から10分程度でも効果が期待できます。
- 室内ウォーキング(少し腕を振って、骨盤を動かす意識で)
- ウエストを左右に大きくひねる運動(椅子に座ったままでも可能)
- おへその周りを時計回りに、手のひらでゆっくりと圧を加えながらマッサージ
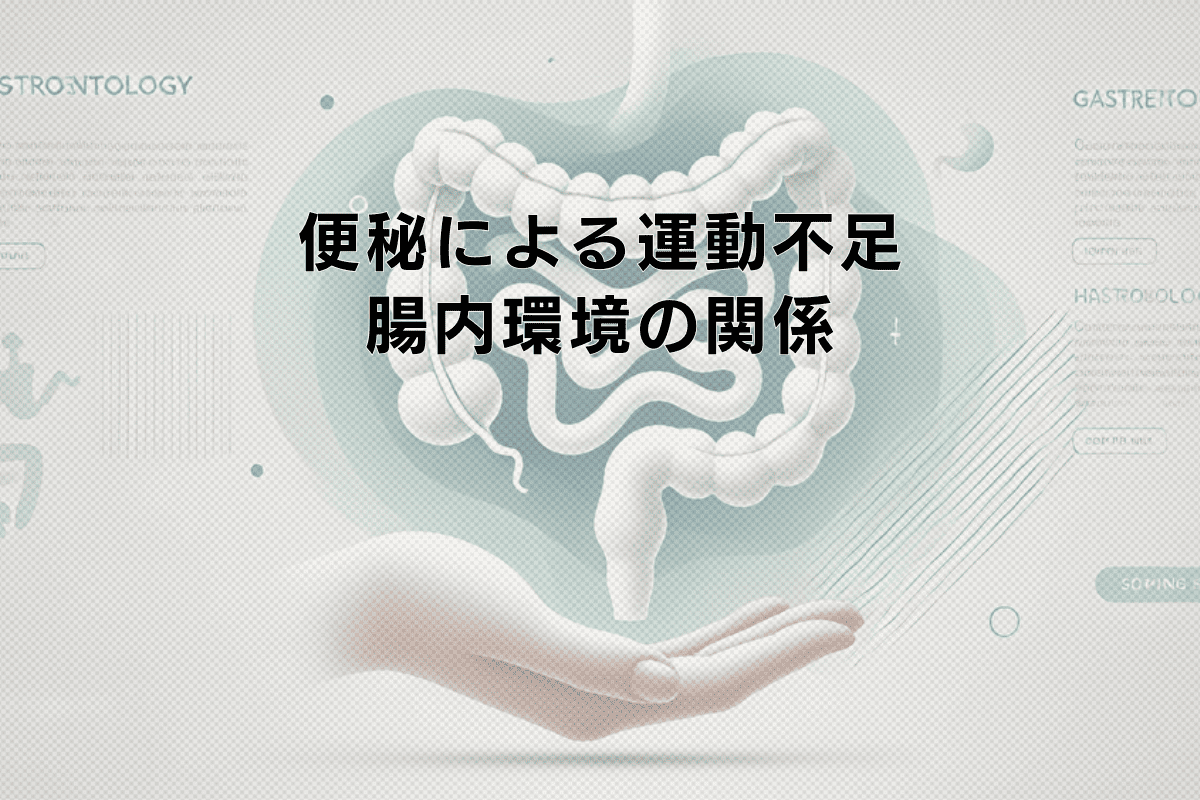
お腹を温める工夫
体の冷え、特に腹部の冷えは腸の働きを直接的に鈍らせます。腹巻を使用したり、お腹や腰にカイロを貼ったり(低温やけどに注意が必要です)、温かい飲み物(白湯など)を飲んだりして、体の内と外から腹部を温めましょう。
体が温まることで副交感神経が優位になり、リラックス効果と共に腸の蠕動運動が活発になるのを助けます。シャワーを浴びて体を温めるのも良い方法ですが、長時間の入浴は脱水を助長する可能性があるので避けてください。
| 対処法 | 具体的な方法 | 期待される効果 |
|---|---|---|
| 体を動かす | 室内を10分ほど歩く、腰をひねるストレッチをする | 物理的な刺激で腸の蠕動運動を直接的に促す |
| 腹部を温める | 腹巻をする、カイロを貼る、温かい飲み物を飲む | 血行を促進し、自律神経を整え内臓の働きを活発にする |
| 腹部マッサージ | おへそ周りを時計回りに5分ほど優しくマッサージする | 腸に直接的な刺激を与え、溜まったガスや便の移動を助ける |
検査前の食事制限の重要性と下剤効果の関係
下剤の効果が十分に出ない最大の原因として、検査前の食事制限が適切に行われていなかったケースが非常に多く見られます。
食事は便の量や硬さ、質に直接影響するため、食事制限の成否が、腸管洗浄のスムーズさを左右すると言っても過言ではありません。
食事制限が不十分な場合の影響
大腸内視鏡検査の食事制限は、単に食事の量を減らすことではなく、消化しにくく、腸内に残りやすい食べ物を徹底的に避けることが目的です。
食物繊維が豊富な野菜やきのこ類、海藻、種のある果物などを摂取すると、消化されずに腸内に残り、便のかさを不必要に増やしてしまい、通常量の下剤では、物理的に増えてしまった便を排出しきれなくなってしまいます。
| 食品カテゴリ | 特に避けるべき食品例 | 腸内に残りやすい理由 |
|---|---|---|
| 穀類 | 玄米、雑穀米、全粒粉パン、オートミール | 豊富な不溶性食物繊維が消化されず、かすとして残留する |
| 野菜・豆類 | ごぼう、きのこ類、とうもろこし、枝豆、海藻類 | 繊維質が硬く、消化管内で分解されにくいため残りやすい |
| 果物・種子類 | キウイ、いちご、トマト、すいか、ごま | 小さな種が消化されず、腸壁に付着したり内視鏡に詰まる恐れがある |
消化に良い食事の選択
検査の数日前、特に便秘症の方は3〜4日前から、消化が良く、腸に残りにくい食事を心がけることが大切です。
炭水化物なら白米やおかゆ、うどん、食パン(ライ麦や全粒粉を含まないもの)、タンパク質なら、皮をむいた鶏肉や白身魚、豆腐、卵、はんぺんなどが適しています。
このような食品は胃腸での消化が速やかで、便としてのかすも少なくなるため、下剤の効果を最大限に引き出すための最高の準備となります。
検査2日前の食事例
便秘症の方は、特に2日前からの食事管理が洗浄の成功率を高めます。
| 食事 | 主食 | 主菜・副菜 |
|---|---|---|
| 朝食 | 食パン(6枚切り1枚)、プレーンオムレツ | 具なしのコンソメスープ |
| 昼食 | かけうどん(薬味なし) | だし巻き卵、豆腐の冷奴(醤油のみ) |
| 夕食 | おかゆ | 鶏ささみのほぐし身、じゃがいもの煮物(皮なし) |
検査前日の食事の注意点
検査前日は、準備の総仕上げとして特に重要で、多くの医療機関が推奨する、消化に配慮して作られた検査食を利用するのが最も安全で確実です。
ご自身で用意する場合は、昼食はおかゆや素うどんなどにとどめ、夕食は具のない透明なスープや透明なゼリー、ジュースなど、固形物を完全に避けるのが一般的です。
色の濃い飲み物(ぶどうジュース、野菜ジュース、コーヒー、色のついたスポーツドリンクなど)は、腸の粘膜に色がついてしまい、炎症などとの区別がつきにくくなるため、水やお茶、透明なスポーツドリンクに限定してください。
下剤(腸管洗浄剤)の種類と自分に合った選択
下剤と一言で言っても、いくつかの種類があり、それぞれに味、飲む量、作用の仕方に特徴があります。
もし以前の検査で下剤が効きにくかった経験がある場合や、服用に強い不安がある場合は、事前に医師に相談することで、ご自身の体質や状況に合った下剤を選択してもらえる可能性があります。

主な腸管洗浄剤の種類と特徴
現在、主流となっているのは、ポリエチレングリコール(PEG)製剤と、硫酸塩類を配合した製剤、ピコスルファートナトリウム製剤です。
PEG製剤は、約2リットルと飲む量は多いですが、体内にほとんど吸収されず、腸管内の水分量を増やして洗浄するため、安全性が高いとされています。
一方、硫酸塩類配合剤は、飲む量が1リットル前後と少ないですが、味が濃く、腎機能に問題がある方には使用しにくい場合があります。
ピコスルファートは、錠剤や少量の液体で、前日の夜に服用し、当日は水やお茶をたくさん飲むタイプで、腸を直接刺激する作用も持ち合わせています。
医師が下剤を選択する基準
医師は、受検者の年齢、性別、体重、既往歴(特に心臓、腎臓の病気)、常用薬の有無、普段の便通の状態、以前の内視鏡検査の経験などを総合的に判断して、最も適切と考えられる下剤を選択します。
高齢者や腎機能が低下している方には安全性の高いPEG製剤を、若い方で飲むのが苦手な方には飲む量が少ないタイプを、便秘が非常に頑固な方には、作用の異なる2種類の下剤を組み合わせるなど、個別に対応を検討します。
事前診察で伝えるべきご自身の情報
下剤の効果に不安がある場合は、検査前の診察時に、ご自身の状況をできるだけ詳しく医師に伝えることが重要です。「これくらい大丈夫だろう」と自己判断せず、ささいなことでも伝えるようにしましょう。
医師に伝えるべき情報リスト
- 普段の便通の頻度(週に何回か、毎日かなど)と便の硬さ
- 便秘薬の服用の有無とその種類、頻度(毎日、週に数回など)
- 以前の大腸内視鏡検査で下剤が効きにくかった経験とその時の状況
- 下剤を飲むことへの不安感(味、量、吐き気など)
| 下剤の種類 | 飲む量 | 長所と短所 |
|---|---|---|
| PEG製剤 | 約2.0L | 長所:安全性が高く、腎機能への影響が少ない。短所:飲む量が多く、時間がかかる。 |
| 硫酸塩配合剤 | 約1.0L + 水分 | 長所:飲む量が比較的少ない。短所:味が濃いめ。腎機能が悪いと使えない。 |
| ピコスルファート系 | 錠剤+多量の水分 | 長所:下剤自体の服用は楽。短所:自己での水分管理が大事で、脱水のリスクがある。 |
医療機関への連絡と相談のタイミング
ご自身で対処法を試しても効果が見られない場合、最も大切なのは自己判断で対応を続けず、速やかに医療機関に連絡することです。専門家の指示を仰ぐことが、安全に検査準備を進める上で最も確実な方法です。
自己判断で対処しないことの大切さ
「もう少し様子を見よう」「市販の便秘薬を追加で飲んでみよう」といった自己判断は、かえって状況を悪化させる可能性があります。
種類が異なる下剤の追加服用は、腸に過度な負担をかけたり、予期せぬ副作用として激しい腹痛や腸けいれん、腸管穿孔(非常にまれ)などを起こしたりする危険があるため、絶対に行わないでください。
医療機関は、下剤が効かないという事態を想定しており、電話で状況を聞き、適切な指示を出す準備ができています。
どの段階で連絡すべきか
連絡するタイミングに迷うかもしれませんが、以下のような状況になったら、ためらわずに電話で相談しましょう。早めに連絡することで、医療機関側も余裕をもって対応策を検討できます。
| 状況 | 連絡の目安 |
|---|---|
| 下剤を半分以上(例:2L中1L)飲んだが、一度も便意がない | これ以上飲み進める前に、すぐに連絡 |
| 我慢できないほどの強い腹痛や、繰り返す吐き気、嘔吐がある | ただちに服用を中止し、すぐに連絡 |
| 全量服用後、1時間以上経っても便が固形のまま、または泥状から変化しない | 医療機関へ向かう前に連絡し、指示を仰ぐ |
連絡時に伝えるべき情報
電話で相談する際は、ご自身の状況を具体的かつ正確に伝えることで、医療スタッフも的確なアドバイスがしやすくなります。慌てず、落ち着いて話すことを心がけましょう。
事前に以下の情報をメモなどに整理しておくと、スムーズに話が進みます。
- お名前と診察券番号
- 服用している下剤の名前、飲み始めた時間と、現在までに飲んだ量
- 最後に排便した時間とその時の便の状態(色、形、固形物の有無)
- 現在の自覚症状(腹痛、吐き気、お腹の張り、気分の悪さなどの有無とその程度)

検査当日に下剤が効ききらなかった場合の対応
万全を期して準備をしても、体質やその日の体調によって、当日に腸内が十分にきれいにならないこともあり得ますが、その場合でも、医療機関では様々な対応策が用意されています。
医療機関到着後の追加処置
自宅での洗浄が不十分な状態で医療機関に到着した場合、まずは看護師が便の状態を確認し、洗浄が足りないと判断されれば、追加の処置を行うことがあります。
追加で下剤をコップ数杯飲んだり、即効性のあるグリセリン浣腸を行ったりして、大腸の奥、特にS状結腸から直腸に残っている便を排出し、腸内をきれいにします。
場合によっては、500mlから1L程度の洗浄液を用いる高圧浣腸を行うこともあります。多くの場合は、これらの追加処置によって検査が可能になりますので、あまり心配しすぎず、スタッフの指示に従ってください。
検査の実施可否の判断基準
最終的に検査を実施するかどうかは、医師が総合的に判断し、大腸の粘膜がある程度観察できる状態であり、受検者の安全が確保できると判断されれば、検査を実施することが多いです。
しかし、固形の便が多く残っており、安全な内視鏡の挿入が困難であったり、ポリープなどの重要な病変を見逃す可能性が高いと判断されたりした場合は、検査を中止、または延期するという決断をします。
これは、不正確な検査で「異常なし」と判断してしまうことのリスクを避ける、受検者の安全と診断の正確性を最優先に考えた結果です。
実施可否の判断フロー
| 洗浄状態 | 判断 | 対応 |
|---|---|---|
| 良好(黄色透明でかすがない) | 実施可能 | 予定通り検査を開始する |
| やや不十分(濁りやかすが多い) | 条件付きで可能 | 追加処置(浣腸など)の後、状態を再評価して検査を試みる |
| 不十分(固形物が明らかに残存) | 延期・中止 | 安全性を最優先し、後日、準備方法を見直して再検査を計画する |
検査が延期になった場合の心構え
もし検査が延期になったとしても、決して準備が失敗したわけではありませんし、落胆する必要はありません。ご自身の腸が時間をかけて準備する必要があるタイプだということが分かった、貴重な情報が得られたと前向きに捉えましょう。
不十分な状態で無理に検査を行うよりも、万全の準備を整えて後日改めて検査を受ける方が、はるかに有意義で精度の高い結果が得られます。
医師や看護師と次回の準備方法についてよく相談し、今回の経験を元に、食事指導の期間を長くする、より作用の強い、あるいは異なる種類の下剤に変更する、前日から入院して専門家の管理下で準備を行うなど、より確実な方法を検討します。
下剤が効かない場合に関するよくある質問
最後に、下剤が効かないことに関して、多くの方が抱く疑問や不安について、Q&A形式で回答します。
- 市販の便秘薬を追加で飲んでも良いですか。
-
腸管洗浄剤と市販の便秘薬では、作用の仕方が大きく異なります。
安易に併用することで、腸に過度な負担がかかり、激しい腹痛や腸けいれん、虚血性腸炎などを起こす危険性があり、また、検査に影響を与える成分が含まれている可能性も否定できません。
どんな場合でも、下剤の追加や変更は自己判断で行わず、必ず検査を受ける医療機関に相談し、専門家の指示を仰いでください。
- 下剤を飲んだらお尻が痛くなりました。どうすれば良いですか。
-
何度も排便を繰り返すことで、肛門の皮膚が刺激されて痛みやヒリヒリ感が出ることがあります。
排便後は、トイレットペーパーで強くこすらず、温水洗浄便座の弱い水流で優しく洗い流すか、濡らしたティッシュや赤ちゃん用のおしりふきで優しく拭き取るようにしましょう。
痛みが強い場合は、ワセリンや非ステロイド系の軟膏を塗布すると刺激が和らぎます。ただし、出血を伴う場合は医療機関に相談してください。
- 吐き気がして下剤を全部飲めませんでした。どうすれば良いですか。
-
無理に飲み続けると嘔吐してしまい、体力を消耗するだけでなく、電解質バランスを崩す原因にもなります。強い吐き気を感じたら、一度服用を中断し、30分ほど休憩することが大切です。
その間に口をゆすいだり、少し体を動かしたりして気分転換を図るのも良いでしょう。吐き気が少し落ち着いたら、以前よりもさらにゆっくりとしたペースで服用を再開してみてください。
それでも服用が困難な場合や、指示された量の7割以上を飲めそうにない場合は、正直に医療機関へ連絡し、状況を伝えて指示を受けてください。
- 以前も効きにくかったのですが、何か対策はありますか。
-
以前の検査で下剤が効きにくかったという経験は、次回の検査準備にとって非常に重要な情報です。
検査を予約する際や、事前の診察時に、必ずその旨を医師や看護師に伝えてください(「前回は全部飲んでも茶色いままだった」など)。
情報をもとに下剤の種類を変更したり、2種類の下剤を組み合わせたり、食事制限の期間を通常より長く設けたり、通常より早い段階から下剤の服用を開始したりするなど、個人に合わせた特別な準備計画を立てることが可能です。
次に読むことをお勧めする記事
【大腸検査 下剤で腸を整える手順と注意点】
“自分にはどの下剤が合うの?”と思った方へ。主要な腸管洗浄剤の特徴と飲み方、注意点を整理し、自己判断のリスク回避に役立つ内容です。
【大腸内視鏡検査の3日前からの食事制限と準備】
下剤が効かない原因を理解したら、次は実際の検査準備をより確実に行う方法を知っておくと安心です。検査3日前からの具体的な食事制限と準備のポイントを詳しく解説しています。特に便秘症の方に参考になる内容です。
以上
参考文献
Tadano T, Abe K, Sasaki S, Terasawa T, Hosono S, Katayama T, Hoshi K, Nakayama T, Hamashima C. Serious adverse events associated with bowel preparation for colonoscopy in Japan: Systematic review. Digestive Endoscopy. 2025 Jun 9.
Saito Y, Oka S, Kawamura T, Shimoda R, Sekiguchi M, Tamai N, Hotta K, Matsuda T, Misawa M, Tanaka S, Iriguchi Y. Colonoscopy screening and surveillance guidelines. Digestive Endoscopy. 2021 May;33(4):486-519.
Parra-Blanco A, Ruiz A, Alvarez-Lobos M, Amorós A, Gana JC, Ibáñez P, Ono A, Fujii T. Achieving the best bowel preparation for colonoscopy. World Journal of Gastroenterology: WJG. 2014 Dec 21;20(47):17709.
Hashimoto Y, Kuribayashi S, Itoi Y, Satou K, Nakata K, Kasuga K, Tanaka H, Hosaka H, Masuo T, Maruhashi K, Furuya K. Safety of full bowel preparation and colonoscopy in elderly patients with ulcerative colitis: A real‐world multicenter retrospective cohort study. Den Open. 2024 Apr;4(1):e275.
Tamai N, Sumiyama K. Optimal bowel preparation for colonoscopy. Digestive Endoscopy. 2025 Feb;37(2):139-46.
Saito Y, Kodashima S, Matsuda T, Matsuda K, Fujishiro M, Tanaka K, Kobayashi K, Katada C, Horimatsu T, Muto M, Ohtsuka K. Current status of diagnostic and therapeutic colonoscopy in Japan: The Japan Endoscopic Database Project. Digestive Endoscopy. 2022 Jan;34(1):144-52.
Saito Y, Oka S, Tamai N, Kudo T, Kuniyoshi N, Shirakura T, Omae Y, Hamahata Y, Arai T, Tanaka S, Uedo N. Efficacy and safety of oral sulfate solution for bowel preparation in Japanese patients undergoing colonoscopy: Noninferiority‐based, randomized, controlled study. Digestive Endoscopy. 2021 Nov;33(7):1131-8.
Gonai T, Toya Y, Kudara N, Abe K, Sawaguchi S, Fujiwara T, Eizuka M, Hirai M, Miura M, Urushikubo J, Yamada S. Is bowel preparation necessary for early colonoscopy in patients with suspected colonic diverticular bleeding?: A multicenter retrospective study with propensity score matching analysis. DEN open. 2024 Apr;4(1):e311.
Niikura R, Nagata N, Yamada A, Honda T, Hasatani K, Ishii N, Shiratori Y, Doyama H, Nishida T, Sumiyoshi T, Fujita T. Efficacy and safety of early vs elective colonoscopy for acute lower gastrointestinal bleeding. Gastroenterology. 2020 Jan 1;158(1):168-75.
Matsumoto M, Fujioka M, Okada T, Naka Y, Amemiya A, Matsushima E, Tamai N, Miura Y, Nakagami G, Sanada H. Evaluation of bowel preparation before colonoscopy by ultrasonographic monitoring of colonic fecal retention: a case series. Medical Ultrasonography. 2021 May 20;23(2):147-52.