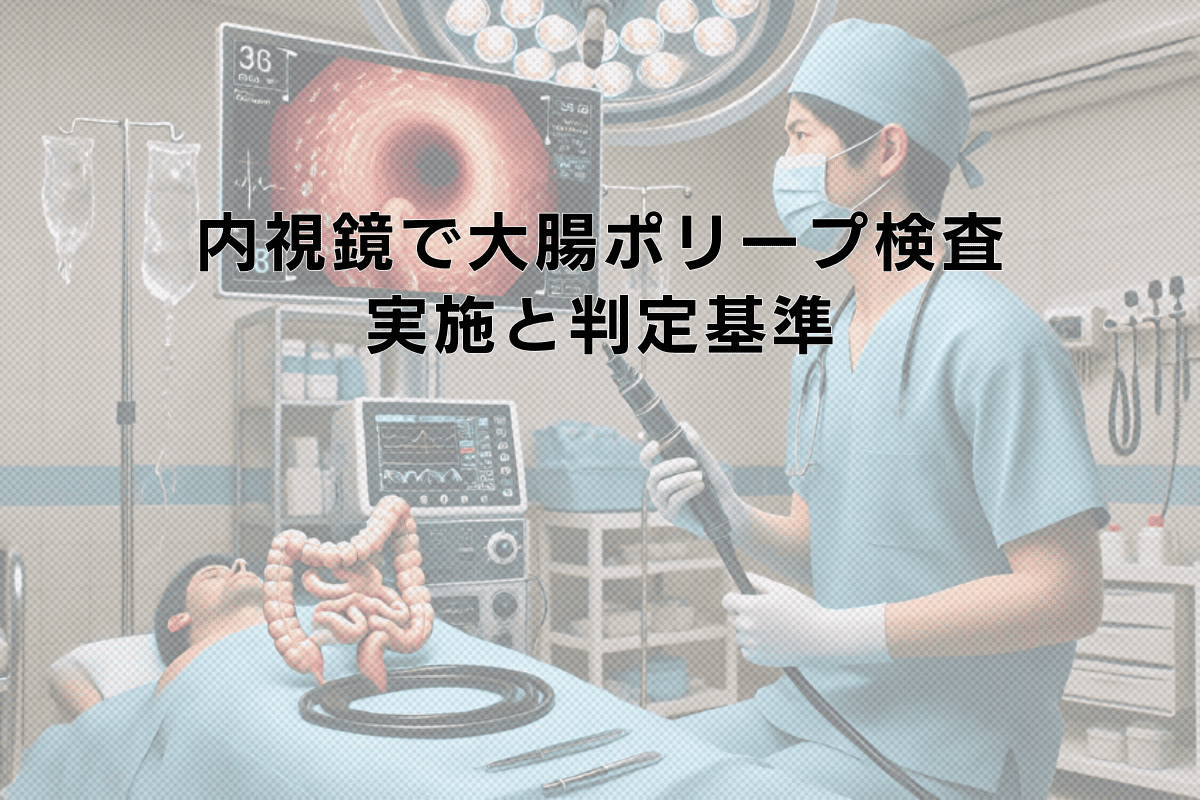大腸ポリープは、大腸の最も内側にある粘膜にできる、いぼ状やきのこ状のできものです。
多くは自覚症状がほとんどなく、気づかないまま過ごしていることが少なくありませんが、ポリープの種類によっては、時間をかけてゆっくりと成長し、やがて大腸がんに進行する可能性があります。
この記事では、大腸ポリープを発見するための内視鏡検査(大腸カメラ)が具体的にどのように行われるのか、発見されたポリープがどのような基準で評価、判定されるのかについて、詳しく解説します。
大腸ポリープとは何か?種類と特徴
大腸ポリープという言葉を耳にしたことがある方は多いでしょう。ここでは、大腸ポリープに関する基本的な知識、分類、そして定期的な検査がなぜご自身の健康を守る上で大切なのかについて、掘り下げていきます。
大腸ポリープの基礎知識
大腸ポリープは、大腸の内壁を覆う粘膜層から発生する、隆起した病変の総称です。大きさは直径1mm程度の微小なものから、数センチを超える大きなものまで、多岐にわたります。
大腸の粘膜には痛みを感じる神経(痛覚神経)がないため、ポリープが発生したり、ある程度の大きさに成長したりしても、痛みや不快感といった症状を起こすことはほとんどありません。
会社の健康診断などで行われる便潜血検査で陽性を指摘されたり、腹痛や便通異常など別の理由で大腸内視鏡検査を受けた際に偶然発見されたりするケースが大半を占めます。
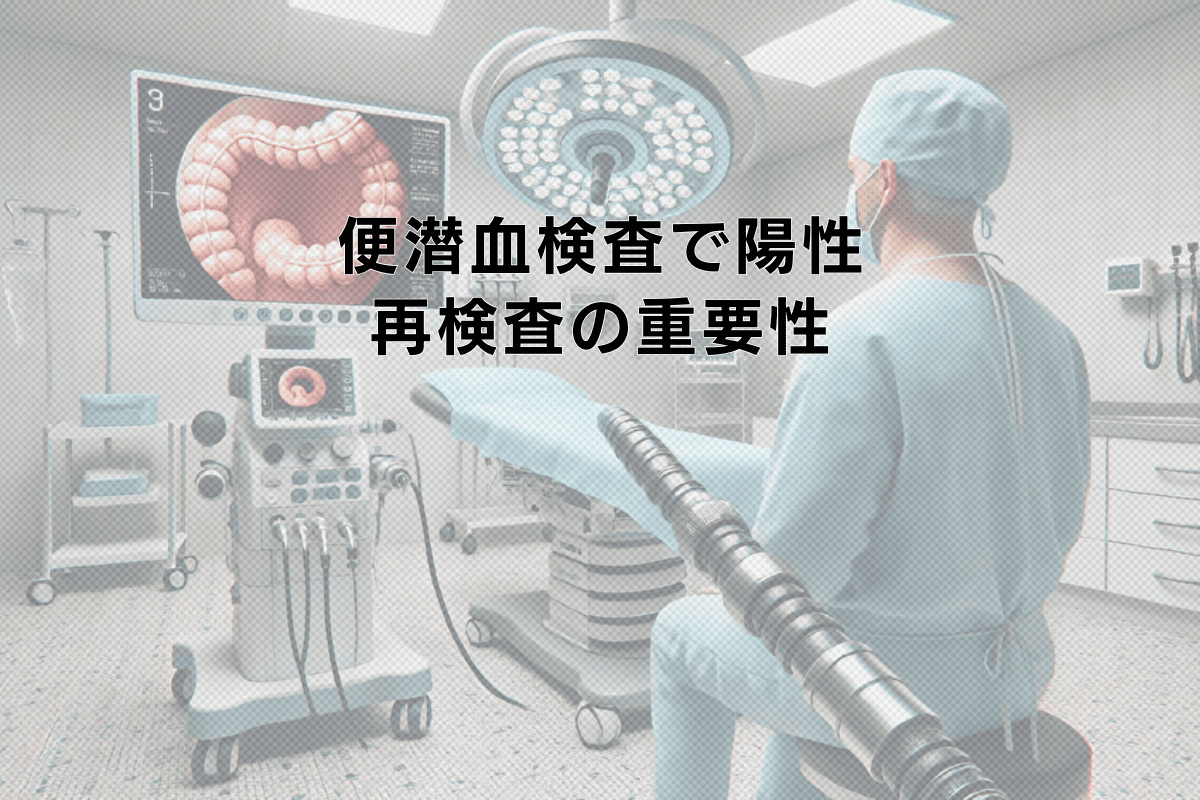
ポリープの種類-腫瘍性と非腫瘍性
大腸ポリープは、細胞の性質と将来的ながん化のリスクに基づいて、大きく腫瘍性ポリープと非腫瘍性ポリープの2つに大別されます。
腫瘍性ポリープは、放置するとがんに進行する可能性があるもので、代表格が腺腫(せんしゅ)です。
大腸がんの約80%以上が腺腫から発生すると考えられており、腺腫ががん化へと至る一連の変化は「腺腫-がん連関(adenoma-carcinoma sequence)」として知られています。
非腫瘍性ポリープは、基本的にはがん化のリスクが低いと考えられているもので、過形成性ポリープ、炎症性ポリープ、過誤腫性ポリープなどが含まれます。
腫瘍性と非腫瘍性の比較
| 分類 | 代表的なポリープ | 特徴 |
|---|---|---|
| 腫瘍性ポリープ | 腺腫 | 大腸がんの前がん病変。大きさや異型度によりがん化リスクが異なり、原則として切除の対象。 |
| 非腫瘍性ポリープ | 過形成性ポリープ | がん化リスクは低いが、サイズが大きいものや特殊なタイプ(鋸歯状病変)は注意が必要。 |
| 非腫瘍性ポリープ | 炎症性ポリープ | 潰瘍性大腸炎など、腸の慢性的な炎症に伴って発生する。炎症が治まると自然に消えることもある。 |
なぜ大腸ポリープの検査が重要なのか
大腸がんの発症経路の多くは、良性の腺腫というポリープが、数年から十数年という長い年月をかけて徐々に大きくなり、その過程で遺伝子の変異が積み重なり、最終的にがん細胞が発生するというものです。
これは裏を返せば、がんへと変化する前のポリープ(腺腫)の段階で内視鏡を用いて発見し、切除してしまえば、大腸がんの発生そのものを未然に防ぐことができる可能性が高いことを意味します。
腹痛や血便などの症状が出現してから医療機関を受診した場合、がんはすでに進行している可能性もあり、症状のない段階で定期的に内視鏡検査を受け、ポリープを発見し対処することが、非常に有効な手段です。
内視鏡検査(大腸カメラ)の準備と流れ
大腸内視鏡検査を快適かつ安全に、そして何より精度の高いものにするためには、事前の準備がとても大切です。ここでは、検査を受けることが決まってから検査当日までの準備内容と、検査全体の時間的な流れについて解説します。
検査前の食事制限について
高精度な検査の実現には、検査前日の食事内容が大きく影響し、腸の中に食べ物の残りかす(便渣)が多くあると、小さなポリープを隠してしまい、見逃しの原因となったり、正確な観察の妨げになったりします。
通常、検査前日の朝食から、消化の良い食事を心がける必要があり、医療機関によっては専用の検査食が用意されている場合もあります。
食物繊維の多い野菜、きのこ、海藻類や、消化に時間のかかる脂質の多い肉類、種子の多い果物などは避け、白米のおかゆ、具のないうどん、食パン、豆腐、白身魚などが推奨されます。
夕食は夜9時頃までに軽めに済ませ、その後は絶食です。水分は脱水を防ぐために重要ですが、摂取できるのは水やお茶、色のついていない透明な液体に限られ、牛乳などの乳製品や、果肉の入ったジュースは避けてください。
検査前日に避けるべき食品の例
| 食品カテゴリ | 避けるべき食品の例 | 理由 |
|---|---|---|
| 野菜・果物 | きのこ類、海藻類、こんにゃく、種のある果物(キウイ、いちご) | 食物繊維は消化されにくく、腸内に長時間残りやすいため。 |
| 穀物 | 玄米、雑穀米、胚芽パン、そば | 消化が悪く、腸のひだ(ハウストラ)に残りやすいため。 |
| その他 | ごま、ナッツ類、脂質の多い肉や魚、乳製品 | 消化に時間がかかる、あるいは腸壁に付着しやすいため。 |

下剤(腸管洗浄剤)の服用方法
検査当日の朝、もしくは前日の夜と当日の朝の2回に分けて、大腸内を洗浄するための下剤(腸管洗浄剤)を服用します。
服用する量は約2リットル程度と多く、大変に感じられるかもしれませんが、きれいな腸の状態を作るためにはすべて飲み干すことが必要です。
下剤は、水に溶かして飲みますが、近年では味の改良が進んだものや、錠剤タイプと少量の液体を組み合わせるものなど、様々な種類が登場しています。
最終的に便が固形物のない、尿のような透明な黄色い液体になれば、腸内が十分にきれいになったサインです。
下剤服用のポイント
- 冷たい水で溶かすと比較的飲みやすい場合がある
- コップ一杯を10分から15分かけてゆっくりとしたペースで飲む
- 服用中は座ったままではなく、室内を軽く歩くなど体を動かすと腸の動きが活発になる

検査当日の準備と来院
検査当日は自宅で下剤を飲み終え、便の状態がきれいになったことを確認してから、指定された時間に来院します。服装は、検査着に着替えるため、着脱しやすいゆったりしたものが便利です。
鎮静剤の使用を希望される場合は、検査後も眠気や判断力の低下が続くことがあるため、当日はご自身での車、バイク、自転車の運転は絶対にできません。
公共交通機関を利用するか、ご家族に送迎を依頼するなど、安全な帰宅手段をあらかじめ確保しておくことが重要です。また、日常的に服用している薬がある場合は、予約時に必ず医師に申し出て、指示に従ってください。
特に、血液をサラサラにする薬(抗血栓薬)は、ポリープ切除を行う際に出血のリスクを高めるため、数日前から休薬の指示が出ることがあります。
検査全体の所要時間
検査そのものにかかる時間は、大腸の長さや形状による個人差、あるいは腸内のきれいさの程度にもよりますが、通常は観察のみであれば15分から30分程度です。
ポリープが見つかり、その場で切除を行う場合は、ポリープの数や大きさ、場所に応じてさらに10分から30分程度の時間が追加でかかります。
来院してから、問診や着替えなどの準備、検査、検査後の休憩時間を含めると、院内での滞在時間は全体で2時間から3時間程度を見込んでおくとよいでしょう。
鎮静剤を使用した場合は、薬の効果が完全に抜けて意識がはっきりするまで、1時間ほど院内のリカバリールームなどで休んでから帰宅となります。
内視鏡による大腸ポリープの発見と切除
十分な前処置で腸内をきれいにし、準備を整えた後、いよいよ内視鏡検査が始まります。大腸内視鏡検査の最大の利点は、ただポリープを見つける(診断)だけでなく、その場で切除(治療)まで一貫して行えることです。
内視鏡の挿入と観察方法
検査は、通常、体の左側を下にした横向きの姿勢(左側臥位)でベッドに寝て行い、肛門から、先端に高性能のCCDカメラとライトが搭載された、細くしなやかな内視鏡(スコープ)をゆっくりと挿入していきます。
医師は、モニターに映し出される鮮明な大腸内部のライブ映像をリアルタイムで見ながら、直腸からS状結腸、下行結腸、横行結腸、上行結腸を経て、大腸の一番奥である盲腸までスコープを進めます。
大腸には多くのひだや曲がり角があるため、そのままでは粘膜の裏側などが見えないので、炭酸ガス(CO2)や空気を送り込んで腸を適度に膨らませ、ひだを伸ばしながら、粘膜の状態を隅々まで観察します。
近年では、吸収の早い炭酸ガスを用いることで、検査後のお腹の張りを軽減する工夫がされています。

ポリープが発見された場合の対応
観察の過程でポリープが発見された場合、医師は大きさ、形状、色調、表面の性状などを詳細に観察し、腫瘍性か非腫瘍性か、がんの可能性はどの程度かをその場でおおよそ判断します。
切除すべきポリープであると判断した場合は、患者さんにあらかじめ得ていた同意のもと、その場で切除治療を行います。5mm程度の小さなポリープであれば、検査時間内で安全かつ迅速に切除が完了することがほとんどです。
ただし、2cmを超えるような大きなポリープや、切除が技術的に難しい場所にあるポリープ、あるいは血液をサラサラにする薬を休薬できていない場合などは、安全を最優先し、後日改めて入院の上で切除を行うこともあります。
全てのポリープが切除対象となるわけではなく、明らかに良性でがん化のリスクが極めて低いと判断される小さな過形成性ポリープなどは、切除せずに経過観察となることもあります。
ポリープ切除術の主な手法
大腸ポリープの内視鏡切除には、ポリープの大きさや形状、予測される病理組織像に応じて、いくつかの方法が使い分けられます。
スネアと呼ばれる金属製の輪をポリープの根元に引っかけて、高周波電流を流して焼き切るホット・スネア・ポリペクトミーや、ポリープの下の粘膜下層に生理食塩水などを注入して病変を浮き上がらせて焼き切る内視鏡的粘膜切除術(EMR)があります。
EMRは平坦な形のポリープに対して特に有効です。
近年では、数mm程度の小さなポリープに対しては、高周波電流を使わずにスネアで物理的に切り取るコールド・ポリペクトミーという手法も広く行われていて、切除後の出血や穿孔のリスクが低いのが大きな利点になります。
主なポリープ切除術
| 切除術の名称 | 対象となるポリープ | 手法の概要 |
|---|---|---|
| コールド・ポリペクトミー | 主に10mm以下の小さなポリープ | 高周波電流の熱を使わず、スネアで機械的に切除する。偶発症のリスクが低い。 |
| 内視鏡的粘膜切除術(EMR) | 平坦な形状や20mm程度までのポリープ | 粘膜下に液体を注入しポリープを人工的に隆起させ、安全に焼き切る。 |
| 内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD) | 主に20mm以上の大きな早期がん | 特殊な電気メスで病変周囲の粘膜を少しずつ剥ぎ取るように切除する。高度な技術を要する。 |
切除時の痛みと鎮静剤の使用
大腸の粘膜自体には痛みを感じる神経がないため、ポリープを切除する処置そのもので痛みを感じることは基本的にありません。
検査中に感じる不快感や苦痛は、主に内視鏡が腸の曲がり角(S状結腸や脾彎曲部など)を通過する際の圧迫感や、腸が送気によって張ることによるお腹の張り感から生じます。
苦痛を最小限に抑え、リラックスして検査を受けられるように、多くの医療機関では鎮静剤(静脈麻酔)の使用を選択肢として用意しています。
鎮静剤を静脈から注射すると、数分でうとうとと眠っているような状態になり、不快感を感じることなく検査を受けることができ、ほとんどの方が、気づいたときには検査が終わっているという感覚です。
切除したポリープの病理診断と判定基準
内視鏡でポリープを切除したら、それで治療が終わりというわけではありません。ここからが、ポリープの正体を突き止めるための重要な工程で、切除したポリープの組織片を専門の病理医が顕微鏡で詳細に調べる、病理診断が行われます。
病理診断の目的と重要性
病理診断の最大の目的は、切除したポリープにがん細胞が含まれているかどうかを確定させることです。そして、がん細胞が含まれていた場合には、がんがどの程度深く広がっているか(深達度)や、細胞の悪性度(異型度)を正確に評価します。
内視鏡の画像診断技術は飛躍的に向上しましたが、それでも良性か悪性かの最終判断が難しいケースはあります。病理診断は、ポリープの正体を細胞レベルで明らかにするための、いわば「答え合わせ」であり、診断のゴールドスタンダードです。
悪性度(がん)の判定
病理診断でポリープが「がん」と診断された場合、次に重要になるのが、がん細胞が腸の壁のどの深さまで達しているかを示す「深達度」です。大腸の壁は、内側から粘膜、粘膜下層、固有筋層、漿膜下層、漿膜という複数の層で構成されています。
がんが最も内側の粘膜内にとどまっている状態、またはその一つ外側の粘膜下層までにとどまっている状態が「早期がん」です。
このうち、リンパ管や血管がほとんど存在しない粘膜内にとどまるがんであれば、リンパ節に転移している可能性は極めて低いため、内視鏡切除だけで治療が完了(根治)したと判断できます。
しかし、がんがリンパ管や血管が豊富な粘膜下層まで深く達している(高度浸潤)場合は、たとえ内視鏡でがんを完全に取りきれていたとしても、すでにリンパ節へ転移している可能性が約10%程度あります。
がんの深達度と治療方針
| がんの深達度 | リンパ節転移のリスク | 主な治療方針 |
|---|---|---|
| 粘膜内がん | ほぼない(0%) | 内視鏡切除で治療完了となることがほとんど。 |
| 粘膜下層への軽度浸潤がん | 低い(1%未満) | 条件が良ければ内視鏡切除で治療完了となる場合がある。 |
| 粘膜下層への高度浸潤がん | 約10%程度 | リンパ節転移のリスクを考慮し、追加の外科手術を検討する。 |
良性ポリープの判定とその後の考え方
病理診断の結果、ポリープが良性の腺腫であった場合、がんになる前の段階で適切に切除できたことを意味し、大腸がんの効果的な予防につながったと考えられます。
ただし、同じ良性の腺腫であっても、細胞の「異型度(いけいど)」という指標で、がんへの近さが評価されます。
異型度とは、細胞の形や核の大きさが正常からどの程度ずれているかを示すもので、異型度が強い(高度異型)ほど、よりがんに近い状態です。
たとえ良性ポリープの切除で治療が完了したとしても、腺腫が発見されたという事実は、その人の大腸にはポリープができやすい素地(体質)があることを示唆しています。
一度ポリープを切除した後も、医師の指示に従って定期的に内視鏡検査を受け、新たなポリープが発生していないか、あるいは見逃された微小なポリープが大きくなっていないかを確認していくことが大切です。
大腸ポリープの大きさや形状による分類
内視鏡検査では、切除したポリープを病理診断に出す前に、その場で得られる視覚的な情報から悪性度をある程度推測します。
ポリープの大きさとがん化のリスク
一般的に、大腸の腺腫ポリープは、大きければ大きいほど、がんに進行する確率、あるいはすでに内部にがん細胞を含んでいる可能性が高く、大きさは、ポリープの性質を判断する上で最も基本的で分かりやすい指標の一つです。
5mm以下の小さなポリープでもがんが見つかることも稀にありますし、2cmを超えていても良性の場合もありますが、統計的には大きさとがん化率は強く相関します。
このため、多くの医療機関では、5mmを超える腺腫ポリープは原則として切除の対象としています。
ポリープの大きさとがん含有率の目安
| ポリープの直径 | がんを含んでいる確率 |
|---|---|
| 5mm以下 | 1%未満 |
| 6mm~9mm | 約2~10% |
| 10mm以上 | 約25~40%以上 |
形状による分類(山田分類など)
ポリープは、肉眼的な形状によっても分類され、肉眼分類と呼ばれ、治療方針を決定する上で重要な情報です。
きのこのように明確な茎を持つ「有茎性ポリープ」と、茎がなく、粘膜からなだらかに盛り上がる「無茎性(または亜有茎性)ポリープ」があります。
さらに、表面が平坦な「平坦型ポリープ」や、逆に中央がへこんでいる「陥凹(かんおう)型ポリープ」もあります。
陥凹している形状のポリープは、サイズが小さくても早期にがん細胞が粘膜の深い部分に及んでいる可能性があり、より注意深い観察と慎重な診断が必要です。
日本では、もともと胃の病変分類として提唱された山田分類や、パリ分類といった国際的な分類法が大腸にも応用されています。
山田分類の概要
| 型 | 形状の特徴 |
|---|---|
| Ⅰ型 | なだらかな隆起 |
| Ⅱ型 | 隆起の周囲にくびれがある |
| Ⅲ型 | 不整な隆起 |
| Ⅳ型 | 茎がある(有茎性) |
表面構造の観察(ピットパターン診断)
近年、特殊な波長の光(NBI:狭帯域光観察など)を当てたり、インジゴカルミンという青い色素を粘膜に散布し、ポリープ表面にある微細な腺管の開口部(ピット)の模様を、最大で100倍程度にまで拡大して詳細に観察できるようになりました。
ピットパターンを分析することで、ポリープが腫瘍性か非腫瘍性か、さらには早期がんかどうかを、切除する前に高い精度で診断することが可能です。これをピットパターン診断と呼び、「光学的生検」ともいわれます。
内視鏡検査後の注意点と生活
無事に検査やポリープ切除が終わった後もいくつかの注意点があり、ポリープを切除した場合は、切除した部分が一時的に傷(人工的な潰瘍)の状態になっており、完全に治癒するまでには時間がかかります。
検査当日の過ごし方
検査当日は、鎮静剤を使用した場合、影響がしばらく残っている可能性があるため、一日ゆっくりとリラックスして過ごすことが大切です。
ご自身では気づかなくても判断力や集中力が低下していることがありますので、車の運転や危険を伴う機械の操作、重要な判断を要する仕事は絶対に避けてください。
検査中にお腹を膨らませたガスの影響で、お腹が張った感じが残ることがありますが、時間とともにおならとして自然に排出され、解消していきますので心配ありません。
ポリープを切除した場合は、飲酒や長時間の入浴(湯船につかること)、激しい運動は、血行が良くなることで切除部位からの出血のリスクを高めるため、医師の指示がある期間(通常1週間程度)は厳禁です。
シャワー程度であれば、当日から可能なことが多いです。
食事や飲酒の再開時期
ポリープを切除しなかった場合は、食事は当日の夕食から普通に摂ることが可能で、ポリープを切除した場合は、切除部位の安静を保ち、治癒を促すため、数日間から1週間程度の食事制限が必要です。
検査当日はお粥や具のないうどん、スープなど、消化が良く、腸に負担のかからない食事から始め、翌日以降、腹痛や出血がないことを確認しながら、豆腐、白身魚、鶏のささみなどのおかずを加え、徐々に普段の食事に戻していきます。
唐辛子などの香辛料を多く使った刺激物や、天ぷらなどの脂質の多い食事は、腸の動きを活発にしすぎるため、数日間は避けましょう。飲酒は、出血のリスクを著しく高めるため、少なくとも1週間は控えるように指示されます。
切除後の食事の進め方の例
- 検査当日:おかゆ、具のないスープ、うどんなど、流動食に近いもの
- 翌日~2日目:豆腐、茶碗蒸し、白身魚の煮付け、鶏のささみなど、柔らかく消化の良いおかずを追加
- 3日目以降:腹部の症状がなければ、食物繊維の少ない野菜などを加え、徐々に通常の食事へ
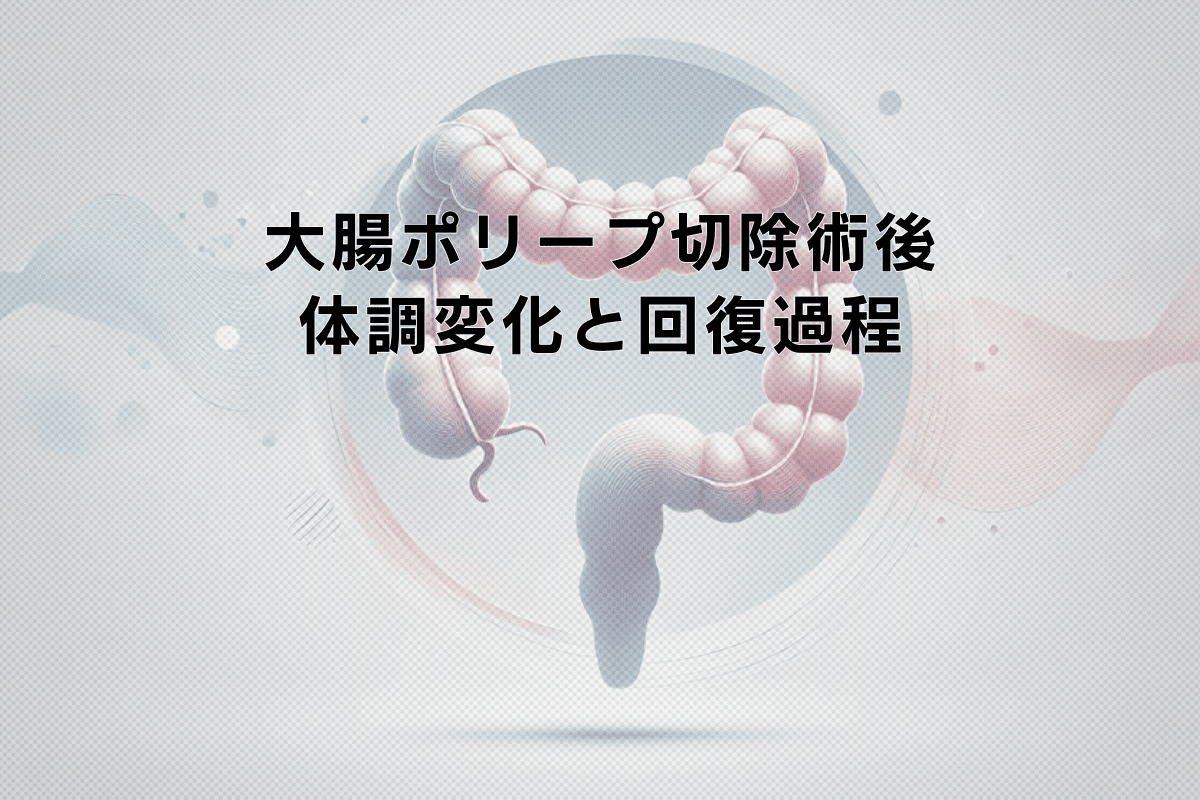
次回の検査時期の目安
次回の内視鏡検査を受けるべき推奨時期は、ポリープが全くなかった場合や、がん化のリスクが極めて低い小さな非腫瘍性ポリープのみだった場合は、数年後(3~5年)の検査でよいことが多いです。
がん化する可能性のある腺腫を切除した場合、大きかったり、数が多かったり、早期がんを含んでいたりした場合は、より短い間隔(多くは1年後)での検査が推奨されます。
これは、今回の検査では認識できなかった微小なポリープが大きくなっていないか、あるいは新たなポリープが発生していないかを早期に発見するためです。
検査結果と次回の推奨時期の目安
| 今回の検査結果 | 次回の推奨時期 |
|---|---|
| 異常なし、または小さな非腫瘍性ポリープのみ | 3~5年後 |
| 1cm未満の腺腫を1~2個切除 | 1~3年後 |
| 1cm以上の腺腫、多数の腺腫、早期がんを切除 | 数ヶ月~1年後(切除断端の確認を含む) |

大腸ポリープ検査に関するよくある質問
最後に、大腸ポリープや内視鏡検査に関して、多くの方が共通して疑問に思われる点や、よく尋ねられる質問について、お答えします。
- 検査はどのくらいの頻度で受けるべきですか
-
特にリスク因子がない方であれば、40歳を過ぎたら一度は大腸内視鏡検査を検討するのが目安です。
前回の検査でポリープが全く見つからなかった健康な腸の状態であれば3年から5年後、腺腫ポリープを切除した方はそのポリープの性質に応じて1年から3年後が目安となりますが、あくまで一般的な話です。
最終的には、ご自身の検査結果に基づいて担当医とよく相談し、個別のサーベイランス計画を決定することが最も大切です。
- ポリープができやすい体質はありますか
-
ポリープができやすい体質や傾向はあり、要因は、遺伝的な要因と、後天的な生活習慣の要因の二つに大別されます。
遺伝的要因としては、ご家族、特に第一度近親者(親子や兄弟姉妹)に大腸がんや大腸ポリープと診断された方がいる場合、ご自身もポリープができやすいです。
生活習慣の要因としては、食生活における動物性脂肪や赤肉(牛、豚肉など)の過剰摂取、野菜や果物不足(食物繊維不足)がリスクを高めることが知られています。
また、肥満、運動不足、過度の飲酒、喫煙といった生活習慣もポリープの発生に深く関与するといわれています。
- ポリープ切除後、生活で気をつけることは何ですか
-
最も気をつけるべきは、切除部位からの出血(後出血)の予防で、ポリープを切除した後の1週間程度は、偶発症のリスクを減らすための生活上の制限を守ることが必要です。
血行を促進する行為、飲酒、激しい運動(ジョギング、ゴルフ、筋力トレーニングなど)、長時間の入浴(湯船につかること)、重いものを持つなどの腹圧がかかる行動は避けてください。
食事も、切除部位の安静を保つため、消化の良いものから段階的に普段の食事に戻していくことが大事です。
もし、帰宅後に持続する強い腹痛や、冷や汗、黒い便、多量の血便など、普段と違う症状が見られた場合は、ためらわずに、すぐに治療を受けた医療機関へ連絡してください。
- 検査を受けるのに適切な年齢はありますか
-
一般的には40歳が一つの節目と考えられていて、その理由は、日本の統計データを見ると、大腸がんの罹患率(新たにがんと診断される人の割合)が40代から緩やかに増加し始め、50代以降で急増するためです。
自治体や職場の検診で受ける便潜血検査で陽性の結果が出た場合は、年齢にかかわらず、必ず精密検査としての大腸内視鏡検査を受けることが推奨されます。
また、血縁者に若くして大腸がんになった方がいるなど、特に遺伝的なリスクが高いと考えられる場合は、40歳を待たずに、より早期からの検査開始を検討することもあります。
次に読むことをお勧めする記事
【大腸内視鏡検査の3日前からの食事制限と準備】
大腸ポリープ検査の基本を押さえたら、次は実際の検査準備について詳しく知っておくと安心です。検査を初めて受ける方に特に参考になる内容で、食事制限の具体的なメニューや下剤の飲み方まで丁寧に解説しています。
【大腸内視鏡検査の間隔はどのくらいが適切なのか】
検査が終わった後に大切なのは計画的なフォローです。リスク別の推奨間隔を押さえれば、自分に合った再検査計画が立てやすくなります。
以上
参考文献
Moriyama T, Uraoka T, Esaki M, Matsumoto T. Advanced technology for the improvement of adenoma and polyp detection during colonoscopy. Digestive Endoscopy. 2015 Apr;27:40-4.
Amano T, Nishida T, Shimakoshi H, Shimoda A, Osugi N, Sugimoto A, Takahashi K, Mukai K, Nakamatsu D, Matsubara T, Yamamoto M. Number of polyps detected is a useful indicator of quality of clinical colonoscopy. Endoscopy International Open. 2018 Jul;6(07):E878-84.
Kashiwagi K, Inoue N, Yoshida T, Bessyo R, Yoneno K, Imaeda H, Ogata H, Kanai T, Sugino Y, Iwao Y. Polyp detection rate in transverse and sigmoid colon significantly increases with longer withdrawal time during screening colonoscopy. PloS one. 2017 Mar 22;12(3):e0174155.
Tanaka S, Saitoh Y, Matsuda T, Igarashi M, Matsumoto T, Iwao Y, Suzuki Y, Nozaki R, Sugai T, Oka S, Itabashi M. Evidence-based clinical practice guidelines for management of colorectal polyps. Journal of Gastroenterology. 2021 Apr;56(4):323-35.
Matsuda T, Fujii T, Sano Y, Kudo SE, Oda Y, Hotta K, Shimoda T, Saito Y, Kobayashi N, Sekiguchi M, Konishi K. Randomised comparison of postpolypectomy surveillance intervals following a two-round baseline colonoscopy: the Japan Polyp Study Workgroup. Gut. 2021 Aug 1;70(8):1469-78.
Sano Y, Fujii T, Oda Y, Matsuda T, Kozu T, Kudo SE, Igarashi M, Iishi H, Fu KI, Kaneko K, Hotta K. A multicenter randomized controlled trial designed to evaluate follow‐up surveillance strategies for colorectal cancer: the Japan Polyp Study. Digestive Endoscopy. 2004 Oct;16(4):376-8.
Sano Y, Hotta K, Matsuda T, Murakami Y, Fujii T, Kudo SE, Oda Y, Ishikawa H, Saito Y, Kobayashi N, Sekiguchi M. Endoscopic removal of premalignant lesions reduces long-term colorectal cancer risk: results from the Japan polyp study. Clinical Gastroenterology and Hepatology. 2024 Mar 1;22(3):542-51.
Inoue T, Murano M, Murano N, Kuramoto T, Kawakami K, Abe Y, Morita E, Toshina K, Hoshiro H, Egashira Y, Umegaki E. Comparative study of conventional colonoscopy and pan-colonic narrow-band imaging system in the detection of neoplastic colonic polyps: a randomized, controlled trial. Journal of gastroenterology. 2008 Jan;43(1):45-50.
Iwama T, Tamura K, Morita T, Hirai T, Hasegawa H, Koizumi K, Shirouzu K, Sugihara K, Yamamura T, Muto T, Utsunomiya J. A clinical overview of familial adenomatous polyposis derived from the database of the Polyposis Registry of Japan. International journal of clinical oncology. 2004 Aug;9(4):308-16.
Niikura R, Hirata Y, Suzuki N, Yamada A, Hayakawa Y, Suzuki H, Yamamoto S, Nakata R, Komatsu J, Okamoto M, Kodaira M. Colonoscopy reduces colorectal cancer mortality: A multicenter, long-term, colonoscopy-based cohort study. PloS one. 2017 Sep 28;12(9):e0185294.