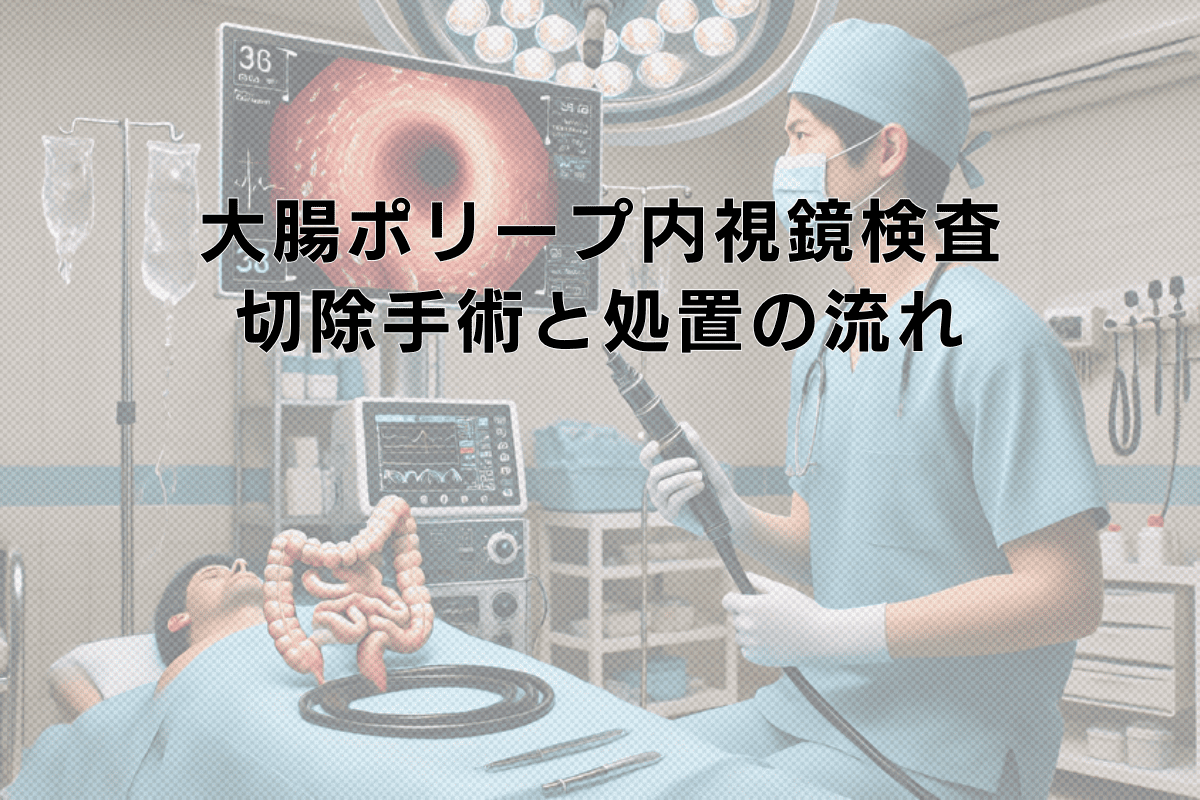大腸ポリープは、腸内の粘膜から発生する隆起性の病変の総称です。多くの場合は良性ですが、一部はがん化してしまう可能性があります。
内視鏡検査を受けることで大腸ポリープを早期に発見し、必要に応じて切除手術を行うことで、大腸がんを予防しやすくなります。
この手技は負担が比較的少なく、日帰りや短期入院で対応できることもあるため、多くの方が受けやすい検査です。
この記事では、大腸ポリープの特徴から内視鏡検査の流れ、切除手術までを詳しく解説し、疑問や不安を抱える方が安心して検査や治療を検討できるよう情報を整理しました。


大腸ポリープとは
大腸ポリープは、腸の内壁に生じる小さな突起物であり、良性腫瘍から前がん病変まで幅広いタイプがあります。
一般的に大腸ポリープが小さいうちは自覚症状がほとんどなく、検診や人間ドックの大腸内視鏡検査で偶然見つかることも少なくありません。
大腸ポリープの分類
大腸ポリープは形態や組織学的特徴で分類され、良性の過形成性ポリープや炎症性ポリープ、がん化リスクが高まる腺腫など、多様な種類があります。
いずれも大きくなるにつれ出血や痛みを生じたり、がん化の可能性が上昇する場合があるため、早期発見と適切な対処が大切です。
発生要因とリスク
大腸ポリープが発生しやすい原因としては、食生活の偏りや飲酒喫煙、遺伝的要因、加齢などが挙げられます。
特に肉類や脂質の過剰摂取、野菜・果物などの食物繊維不足、過度なアルコールの摂取習慣を続けていると大腸ポリープのリスクが上がると考えられています。
症状が出にくい理由
小さな大腸ポリープは、腸内にあるだけでは基本的に痛みや出血などの症状が起こりにくく、大きくなってはじめて便潜血が起きたり、血便や腹痛などが生じる場合があるため、症状を手掛かりに発見するのは難しい面があります。
このため、定期的な内視鏡検査が予防と早期発見に有用です。

発見時の選択肢
大腸ポリープが見つかったとき、多くの場合は内視鏡で切除を検討し、切除するか経過観察とするかは、ポリープの大きさや形状、組織所見を総合的に判断する必要があります。
大腸ポリープの代表的分類と特徴
| 種類 | 特徴 | がん化リスク |
|---|---|---|
| 腺腫性ポリープ | 良性が多いが一定サイズ以上でがん化の可能性 | サイズや形状によってリスクが変動 |
| 炎症性ポリープ | 炎症や潰瘍がきっかけで発生する場合がある | がん化の可能性は低め |
| 過形成性ポリープ | 粘膜の過形成によるものが中心 | 小さいものは低い |
| 鋸歯状ポリープ | 一部でがん化リスクが比較的高いとされる | 大きさ・形態により要注意 |
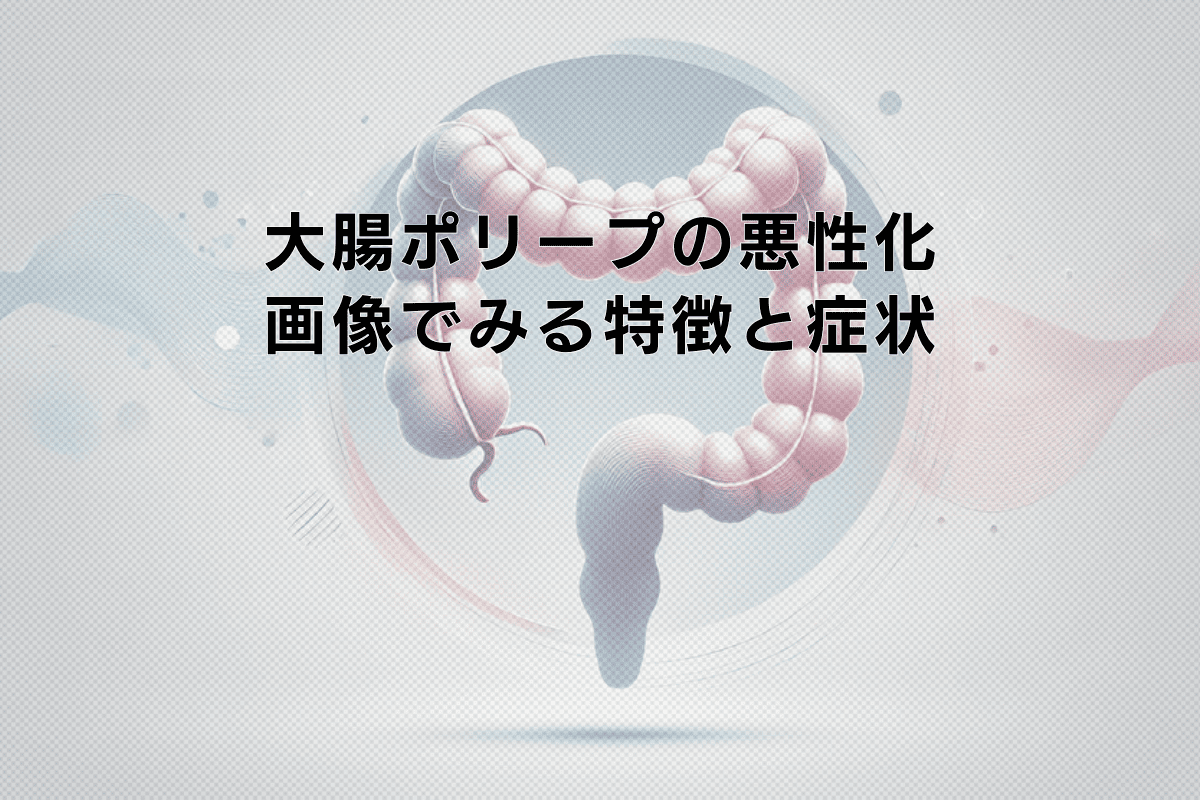
内視鏡検査の必要性
大腸ポリープの有無や腸内環境を評価するうえで、大腸カメラ(大腸内視鏡検査)は信頼性の高い方法です。
採血や便潜血検査だけでは分からない粘膜の状態や小さな病変までも直接確認できるため、異常があれば早期に対処しやすい点が大きなメリットになります。
大腸内視鏡検査でわかること
大腸内視鏡検査では、肛門から内視鏡を挿入して大腸全体の粘膜を直接観察します。
ポリープのみならず、潰瘍性大腸炎やクローン病などの炎症性腸疾患、あるいは大腸がんの初期病変なども確認でき、疑わしい病変があればその場で生検を実施し組織診断が可能です。

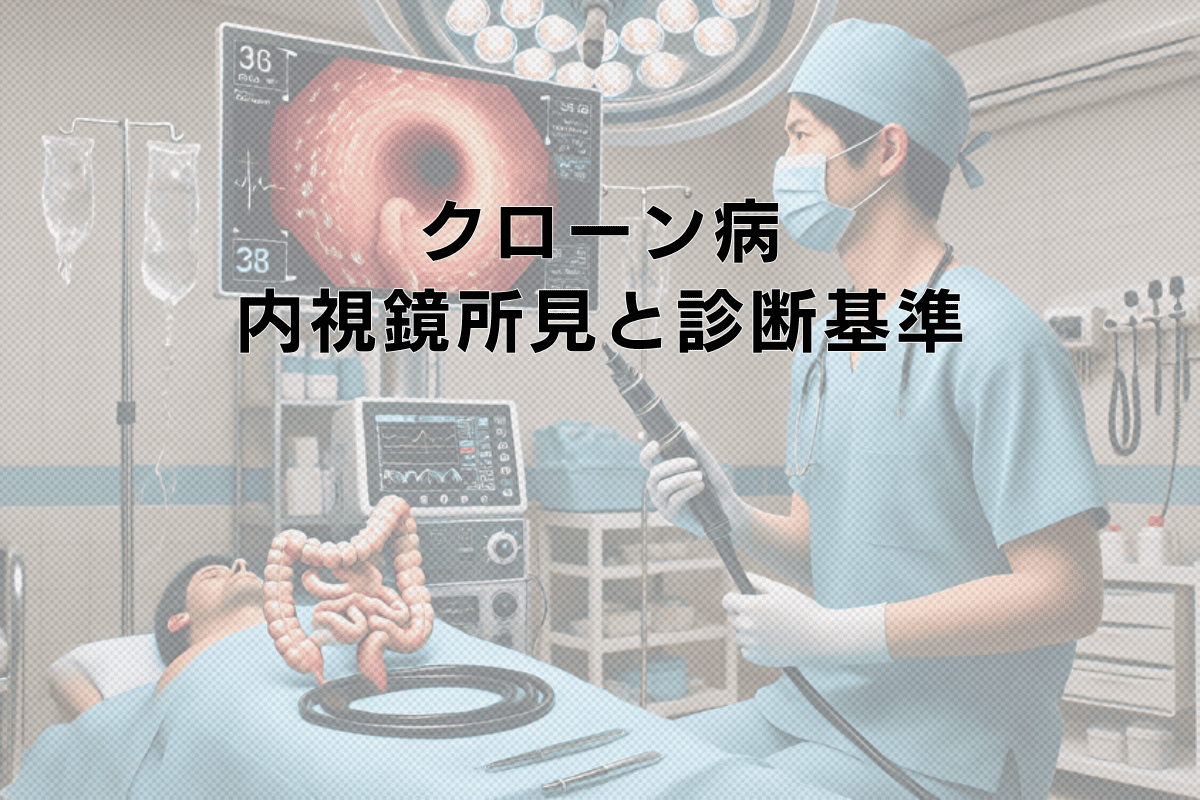
定期検査の推奨
大腸がんは早期に発見して切除すれば治癒が期待できますが、自覚症状のないうちに進行しやすいため、一定年齢以上の方やリスク要因のある方には定期的な内視鏡検査が提案されることがあります。
家族歴やポリープを過去に切除した経験がある方などは、医師と相談しながら検査の間隔を決めると安心です。
定期的に検査を受けたほうがよい方
- 50歳以上で今まで大腸内視鏡検査を受けたことがない
- 便潜血検査で陽性になった
- 血縁者に大腸がん・ポリープの既往がある
- 以前にポリープを切除した経験がある
- 慢性の便秘や下痢が続いている

検査前の準備
大腸内視鏡検査では、腸内をきれいにするために下剤を使用します。
検査日前日から食事制限(消化に良いものを選ぶなど)が行われ、当日は指定の下剤を時間をかけて飲みます。大腸内を空っぽに近い状態にすると、より正確な観察が可能です。


検査にかかる時間
大腸内視鏡検査の所要時間は個人差がありますが、約15~30分程度が一般的ですが、ポリープが見つかって切除を行う場合や、腸の形態や癒着などで挿入に時間がかかる場合は多少延びることがあります。
検査自体の不安や痛みに配慮して、鎮静剤を使うケースも多く、快適に受けられるよう配慮されています。
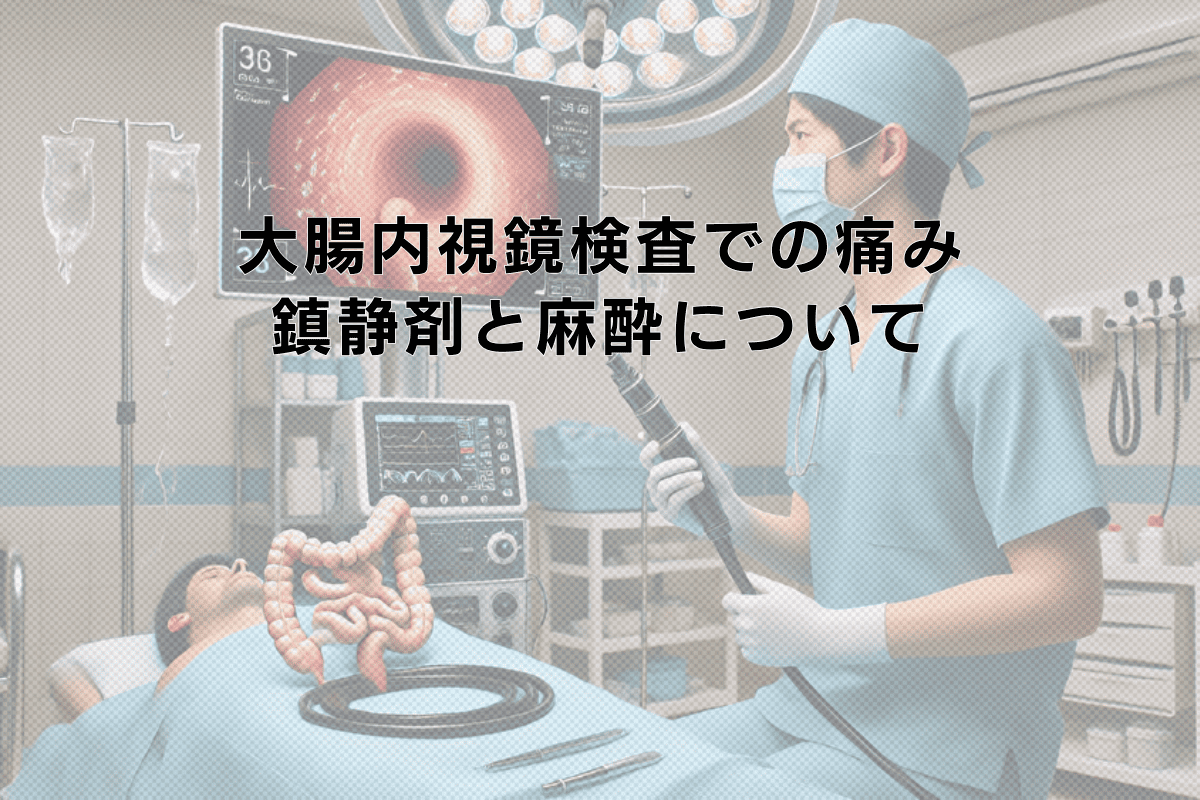
大腸内視鏡検査の主な流れ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 前日 | 消化に優しい食事、早めの夕食 |
| 検査当日の朝 | 水分摂取をしながら指定の下剤を飲む |
| 検査直前 | 検査衣に着替えて軽い問診を受ける |
| 検査時 | 大腸内視鏡を肛門から挿入し、腸内を直接観察 |
| 必要に応じた処置 | ポリープ切除・生検など |
| 検査後の休憩 | 施設内で30分~1時間程度安静にし、状態を確認 |
ポリープ切除を検討するタイミング
大腸ポリープが見つかった際に、医師が切除を提案するか経過観察を勧めるかは、ポリープの大きさや形態、がん化の可能性などを総合的に判断して決まります。
この項目では、どのようなタイミングで大腸ポリープの切除手術を行うか、目安や流れを説明します。
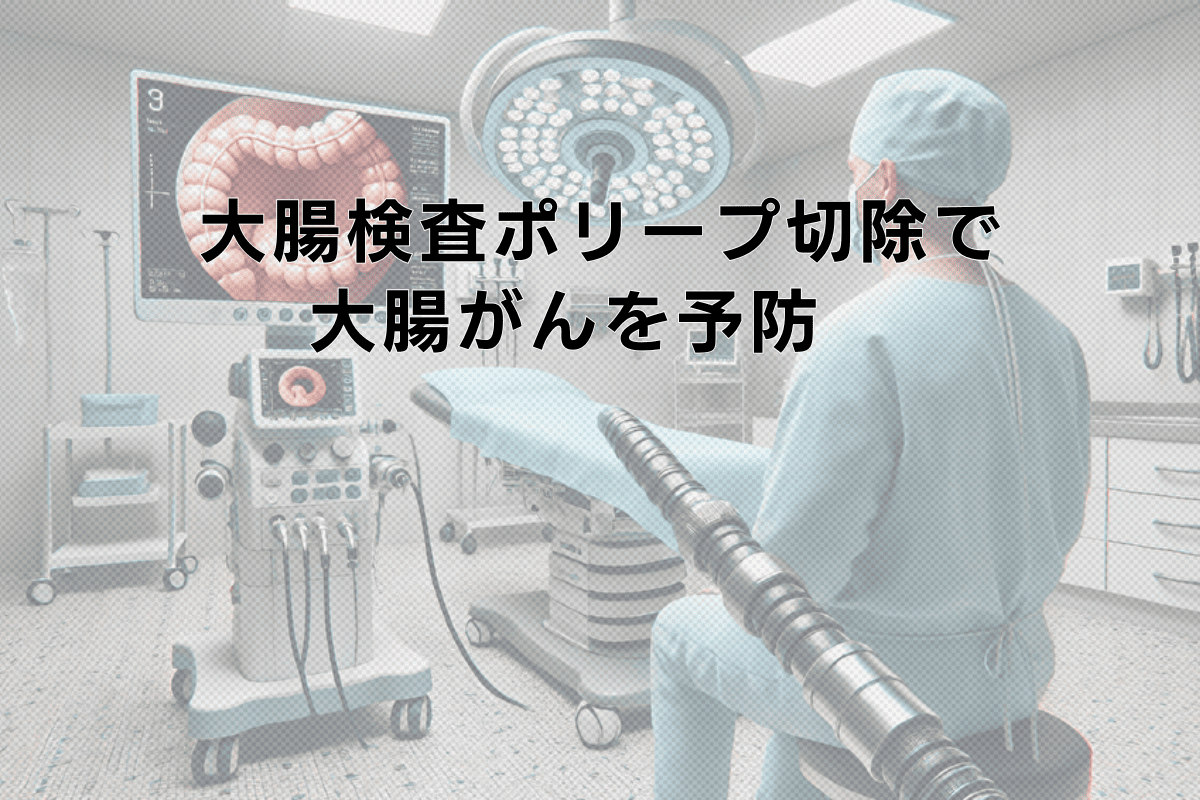
サイズと形状
一般的に、5mm以下の非常に小さいポリープは切除の必要性が低い場合がありますが、特に腺腫性のポリープであれば将来的にがん化のリスクを無視できないため、医師と相談したうえで切除を行うケースも多いです。
10mm以上の大きいポリープや、形状がいびつなポリープはがんの可能性が高まるため、積極的に切除が提案されます。
大腸ポリープの大きさと対応の目安
| ポリープの大きさ | 切除の検討 | 理由 |
|---|---|---|
| 5mm以下 | 場合によって経過観察 | 良性でも将来的リスクを考慮 |
| 5~9mm | 切除を検討 | 腺腫の場合リスク増加、形状も考慮 |
| 10mm以上 | 原則的に切除 | がん化リスクがより高まる |
腺腫性かどうか
大腸ポリープのなかでも腺腫性と呼ばれるタイプは、将来的な悪性化(がん化)のリスクが高いとされているので、検査中に医師が腺腫性の疑いがあると判断した場合は、その時点で切除を行う流れになることが一般的です。
症状の有無
ポリープが原因で出血や腹痛などの症状を起こしている場合は、速やかに切除する必要があります。出血を繰り返すことで貧血を引き起こす恐れや、腸内環境の悪化が進む場合もあるため、医師の提案に沿って手術を検討するとよいでしょう。
患者の年齢や全身状態
高齢の方や基礎疾患を持つ方では、内視鏡手術に伴うリスクと切除のメリットを比較して決定されます。たとえば、ポリープの増大やがん化までの時間、手術に耐えられる身体状況などがポイントです。
内視鏡手術の種類
大腸ポリープの切除には、内視鏡を用いた手術が主流となっていて、腹部を切開する手術に比べて体への負担が軽く、回復も早い傾向があるため、多くの病院で実施されている方法です。ここでは、代表的な切除法をいくつか紹介します。
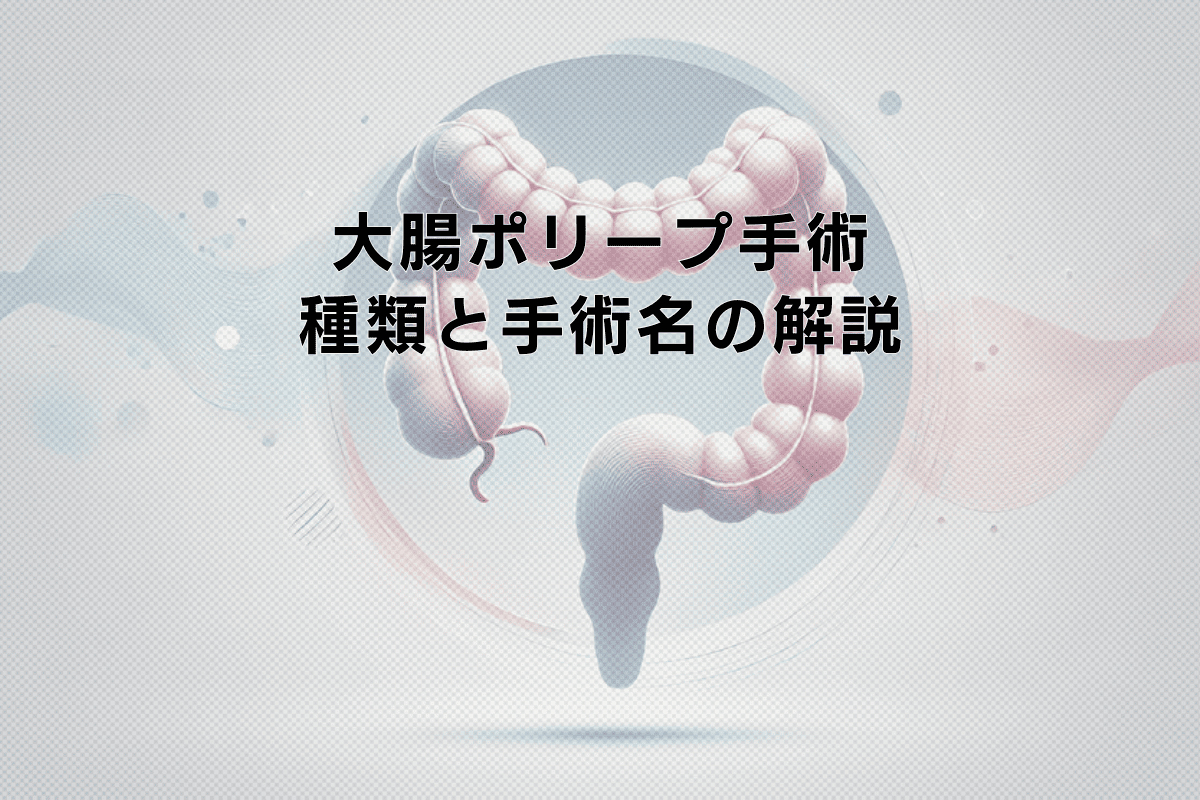
ポリペクトミー
ポリペクトミーは、大腸内視鏡にスネアと呼ばれる輪状の器具を装着し、ポリープの根元を電気的に切断して摘除する方法で、5~10mm程度までのポリープであれば、比較的容易にポリペクトミーが可能です。
ポリペクトミーの特徴
- 手術時間が短い
- 合併症のリスクが比較的低い
- 病変部を回収して病理検査を行える
EMR(内視鏡的粘膜切除術)
EMRは、10mm以上のポリープや平坦型ポリープに適した方法で、生理食塩水などを注入して粘膜を浮かせ、スネアを使って切除する手術です。
大きめのポリープを一括で安全に切除するために考案され、ポリペクトミーでは切除が難しいものに有効とされます。
EMRの流れ
- 生理食塩水を注入して粘膜を持ち上げる
- スネアをかけて電気的に切離
- 切除した病変を回収し、病理検査へ
ESD(内視鏡的粘膜下層剥離術)
ESDはさらに大きい病変や、形状が複雑なポリープ、早期がんが疑われる場合に行われる高度な内視鏡手術です。
専用のナイフを用いて粘膜下層を少しずつ切開しながら剥離する手法であり、病変を広範囲にわたって一塊で取り除ける点が利点になります。
ESDの特徴
- 大きいポリープや広範囲の病変に対応可能
- 病変を一括切除して正確な診断が可能
- 技術的難易度が高く、一定の熟練を要する
粘膜下層浸潤が疑われる場合
早期がんの可能性があり、粘膜下層に浸潤が進んでいると判断された場合、内視鏡手術では切除しきれない可能性が高いです。その際には外科的な切除(開腹手術や腹腔鏡手術)を選択せざるを得ないこともあります。
内視鏡手術と病変の大きさの目安
| 手術法 | 適応する病変の大きさ・形態 | 特徴 |
|---|---|---|
| ポリペクトミー | 5~10mm前後の有茎や半有茎型ポリープなど | 比較的簡単に切除可能 |
| EMR | 10mm以上でも高さのある粘膜下病変など | 一括切除で正確な病理検査が可能 |
| ESD | 20mm以上の平坦型や早期がんが疑われる病変 | 広範囲を剥離できるが技術水準が必要 |
内視鏡手術の実際の流れ
ここでは、内視鏡手術が実際にどのように進められるかを、準備段階から退院までの流れに沿って説明します。手術といっても、一般的な開腹手術に比べると体の負担は小さく、日帰りや数日の入院で済む場合が多いです。
事前準備と検査
大腸内視鏡検査でポリープが見つかり、内視鏡手術が必要と判断された後は、患者さんの全身状態を確認するために血液検査や心電図、胸部レントゲンなどを行い、麻酔や鎮静薬のリスクを評価します。
特に循環器系や呼吸器系の病気がある場合は、主治医と相談しながら対策を立てることが大切です。
事前に確認する項目
- 全身の健康状態
- 服用中の薬(血液をさらさらにする薬など)
- アレルギーの有無
- 過去の手術や麻酔歴
当日の腸内洗浄と麻酔
内視鏡手術を行う前に、腸内を洗浄し粘膜がよく見える状態に整えます。通常は早朝や当日の朝から下剤を飲み、クリアな排便状態を目指します。
麻酔や鎮静は静脈内投与することが多く、眠ったような意識状態で手術を受けるので、不快感や痛みを感じにくいことがメリットです。
ポリープ切除の手順
内視鏡を挿入して腸内を観察し、切除対象のポリープを視認します。大きさや形状、位置によって切除方法を決定し、スネアやナイフなどの器具を使ってポリープを切離して回収します。
切除部位からの出血がある場合は内視鏡的に止血を行い、確認したうえで手術を終了します。
内視鏡手術中の処置内容
| 処置 | 内容 |
|---|---|
| スネア切除 | ポリペクトミーやEMRに用いる輪状の器具で切る |
| 粘膜下層剥離 | ESDで行う専用ナイフを使った段階的切開 |
| 止血処置 | クリップや電気凝固、薬剤注入などで出血を止める |
手術後の経過観察
ポリープを切除した後、出血や穿孔といった合併症がないかを確認するために、手術後しばらく安静にする必要があります。
日帰りの場合でも数時間の安静観察を受け、問題なければ帰宅となります。入院が必要な場合は1~2日程度で退院できるケースが多いです。
手術後に留意したい症状
- 腹痛が強まる
- 便に鮮血が混じる
- 発熱や寒気が続く
- 異常なだるさや貧血感
こうした症状がある場合、合併症の可能性があるため、すぐに医療機関へ連絡してください。
術後の生活と再発予防
内視鏡手術後の回復には個人差がありますが、大きな切開がない分、体へのダメージは軽く日常生活への復帰もしやすいです。ただし、術後の過ごし方によっては出血リスクを高める場合もあるため、以下のような点に留意してください。
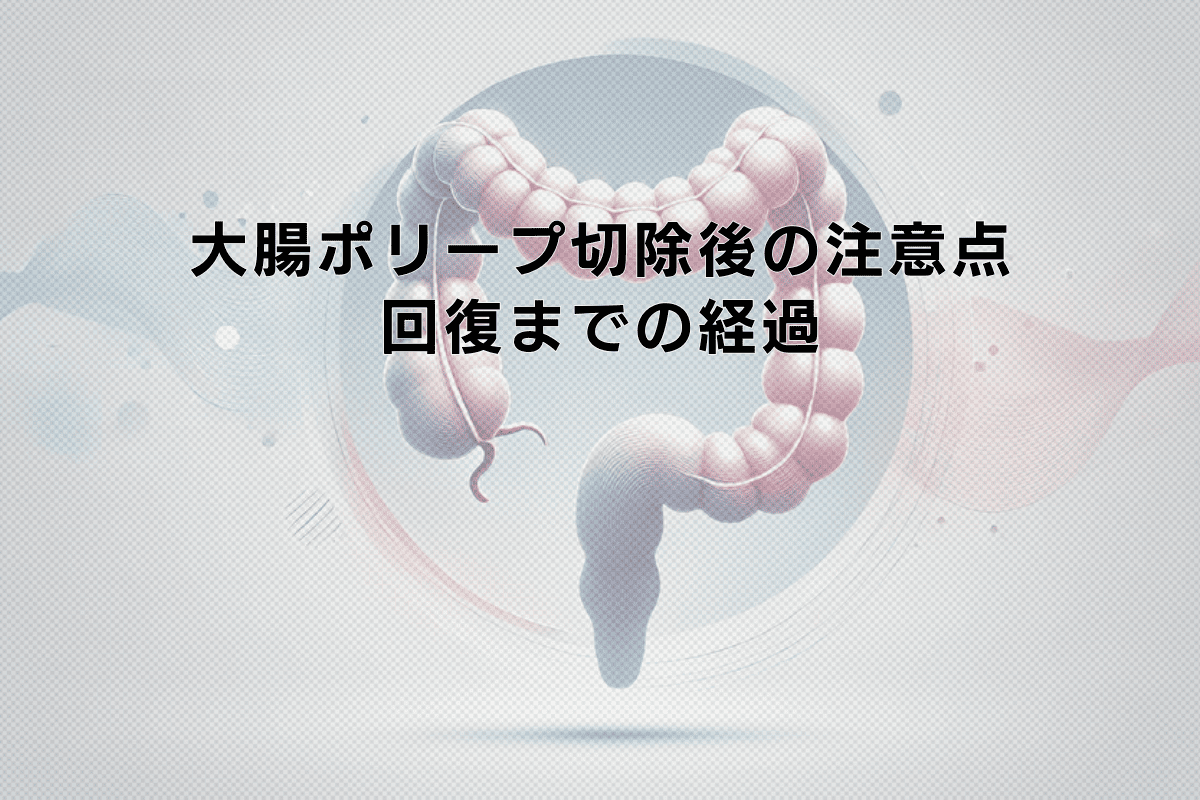
食事や運動
術後数日は消化しやすい食事を心がけ、飲酒や刺激物の摂取は避けてください。また、激しい運動は出血リスクを高める恐れがあるため、徐々に運動量を増やす方法が提案されます。
医師の指示に従い、過度な腹圧をかける動作は避けましょう。
術後1週間程度の食事の注意点
| 時期 | 食事の種類 |
|---|---|
| 術後当日 | 水分中心、液体に近いスープなど |
| 術後2~3日 | 柔らかいおかゆ、うどん、煮込み野菜など |
| 術後4~7日 | 徐々に普段の食事に近づける、油っこいものや辛いものは控えめ |
術後の便通管理
切除後は便潜血が出たり、一時的に便のリズムが崩れることがあるので、水分補給や食物繊維の摂取を調整し、便が固くなりすぎないよう工夫すると、大腸への負担を減らせます。
腸内環境を整えるヒント
- 水をこまめに摂取
- ヨーグルトなど発酵食品を取り入れる
- 食物繊維の豊富な野菜や果物をバランス良く食べる
- 軽いウォーキングやストレッチで腸の動きを活発化
再発予防と定期検査
大腸ポリープを1度切除しても、新たにポリープが発生する場合が多いです。再発を防ぐには、バランスの良い食習慣や適度な運動、禁煙・節酒など生活習慣の改善が有用です。
また、医師の提案に基づき定期的に内視鏡検査を受けることで、再発を早期に発見し適切な対応を取りやすくなります。
生活習慣で意識したい項目
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 禁煙・節酒 | タバコは全身への悪影響が大きく、大腸ポリープリスクも上昇 |
| 食生活 | 野菜や果物を多めに、肉や脂質は適量を守る |
| 適度な運動 | ウォーキングなどの有酸素運動が腸の動きを促進する |
| 十分な睡眠 | ホルモンバランスや免疫力に関与し、体調全般を整える |
よくある質問
ここでは、大腸ポリープの内視鏡検査や切除手術にまつわる疑問を取り上げ、分かりやすく回答します。
- 大腸ポリープが見つかったら必ず切除するのか
-
ポリープの種類や大きさ、形状、組織所見によって異なります。小さいポリープは経過観察となる場合もありますが、腺腫性が疑われたりサイズが10mm以上であれば多くは切除を提案されます。
- 内視鏡手術は痛みが強いか
-
麻酔や鎮静剤を使うことで痛みや不快感は軽減され、うとうとした状態で受ける方が多いです。麻酔が切れた後も軽い腹部違和感などがある程度で、強い痛みは少ないとされます。
- 術後に出血したらどうするか
-
少量の出血であればしばらく様子を見ることもありますが、鮮やかな出血が増えたり、血便が続く場合は速やかに医療機関へ連絡してください。内視鏡による止血処置が必要になることがあります。
- 大腸内視鏡検査が不安で受けられない
-
鎮静剤を使用することで検査時の不快感や痛みをかなり抑えられます。近年は機器の改良や医師の技術向上により、痛みを感じにくい検査体制が整っています。検査前に医師や看護師と相談し、不安を共有することをおすすめします。
次に読むことをお勧めする記事
【大腸内視鏡検査の前日に必要な準備と食事の注意点】
大腸ポリープの切除手術について基本を押さえたら、次は実際の検査前準備について知っておくと安心です。検査を控えている方に特に参考になる内容です。
【大腸ポリープ切除後の出血|正常な経過と注意が必要な症状】
切除後の経過で『血便が出たらどうしよう?』と心配な方へ。不安な症状と受診の目安を具体的に解説しています。
参考文献
Sano Y, Hotta K, Matsuda T, Murakami Y, Fujii T, Kudo SE, Oda Y, Ishikawa H, Saito Y, Kobayashi N, Sekiguchi M. Endoscopic removal of premalignant lesions reduces long-term colorectal cancer risk: results from the Japan Polyp Study. Clinical Gastroenterology and Hepatology. 2024 Mar 1;22(3):542-51.
Shimada S, Hotta K, Takada K, Imai K, Ito S, Kishida Y, Kawata N, Yoshida M, Yamamoto Y, Maeda Y, Minamide T. Complete endoscopic removal rate of detected colorectal polyps in a real world out-patient practical setting. Scandinavian Journal of Gastroenterology. 2023 Apr 3;58(4):422-8.
Tanaka S, Saitoh Y, Matsuda T, Igarashi M, Matsumoto T, Iwao Y, Suzuki Y, Nishida H, Watanabe T, Sugai T, Sugihara KI. Evidence-based clinical practice guidelines for management of colorectal polyps. Journal of gastroenterology. 2015 Mar;50:252-60.
Tanaka S, Saitoh Y, Matsuda T, Igarashi M, Matsumoto T, Iwao Y, Suzuki Y, Nozaki R, Sugai T, Oka S, Itabashi M. Evidence-based clinical practice guidelines for management of colorectal polyps. Journal of Gastroenterology. 2021 Apr;56:323-35.
Horiuchi A, Nakayama Y, Kajiyama M, Tanaka N, Sano K, Graham DY. Removal of small colorectal polyps in anticoagulated patients: a prospective randomized comparison of cold snare and conventional polypectomy. Gastrointestinal endoscopy. 2014 Mar 1;79(3):417-23.
Sano W, Hirata D, Teramoto A, Iwatate M, Hattori S, Fujita M, Sano Y. Serrated polyps of the colon and rectum: Remove or not?. World journal of gastroenterology. 2020 May 21;26(19):2276.
Matsuda T, Fujii T, Sano Y, Kudo SE, Oda Y, Hotta K, Shimoda T, Saito Y, Kobayashi N, Sekiguchi M, Konishi K. Randomised comparison of postpolypectomy surveillance intervals following a two-round baseline colonoscopy: the Japan Polyp Study Workgroup. Gut. 2021 Aug 1;70(8):1469-78.
Ninomiya Y, Oka S, Tanaka S, Boda K, Yamashita K, Sumimoto K, Hirano D, Tamaru Y, Shigita K, Hayashi N, Matsuo T. Clinical impact of surveillance colonoscopy using magnification without diminutive polyp removal. Digestive Endoscopy. 2017 Nov;29(7):773-81.
Sano Y, Fujii T, Oda Y, Matsuda T, Kozu T, Kudo SE, Igarashi M, Iishi H, Fu KI, Kaneko K, Hotta K. A multicenter randomized controlled trial designed to evaluate follow‐up surveillance strategies for colorectal cancer: the Japan Polyp Study. Digestive Endoscopy. 2004 Oct;16(4):376-8.
Kashiwagi K, Inoue N, Yoshida T, Bessyo R, Yoneno K, Imaeda H, Ogata H, Kanai T, Sugino Y, Iwao Y. Polyp detection rate in transverse and sigmoid colon significantly increases with longer withdrawal time during screening colonoscopy. PloS one. 2017 Mar 22;12(3):e0174155.