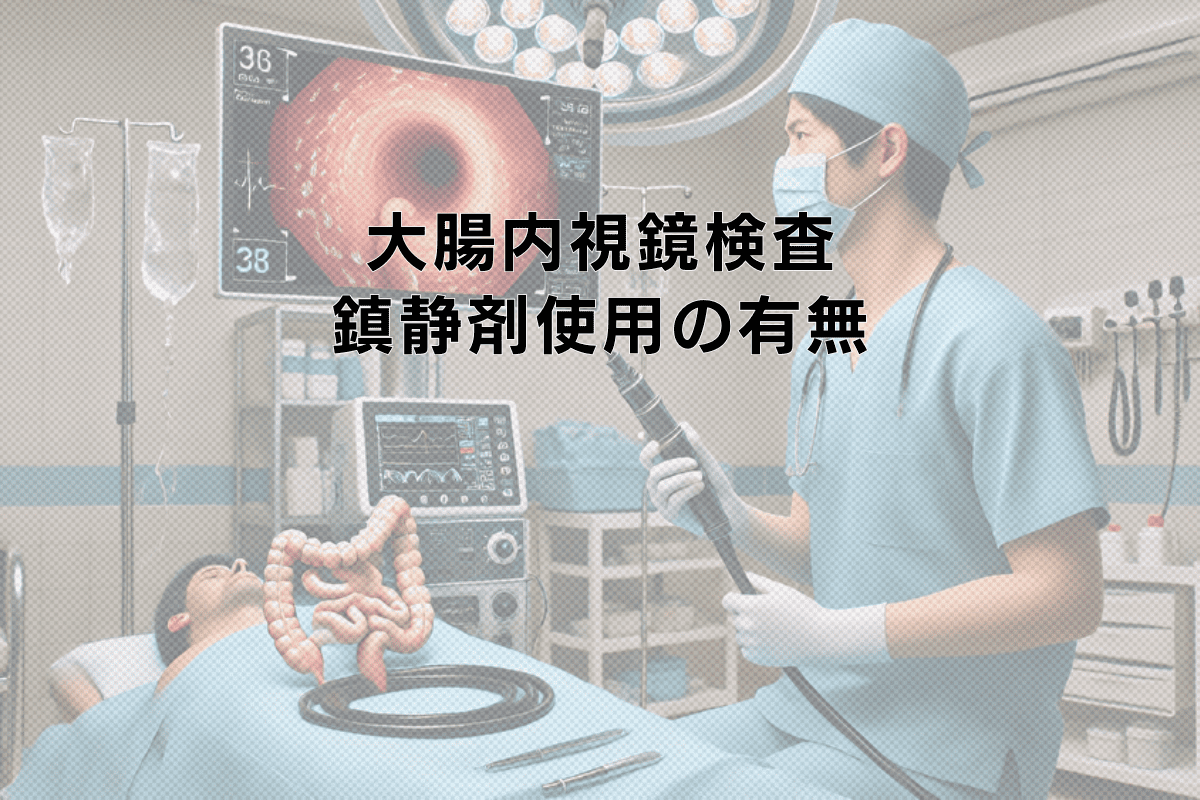大腸内視鏡検査(大腸カメラ)は、大腸がんやポリープといった病変を早期に発見するために非常に重要な検査です。
しかし、検査に対して痛みや不快感といった強い不安を感じる人も少なくありません。その不安を和らげるための有力な選択肢の一つとして、鎮静剤の使用があります。
この記事では、大腸内視鏡検査における鎮静剤使用の有無について、それぞれの特徴を詳しく解説します。ご自身が検査を受ける際に、どちらの方法がより合っているかを多角的に考えるための情報として、ぜひお役立てください。
大腸内視鏡検査とはどのような検査か
大腸内視鏡検査は、先端に高性能な小型カメラが搭載された、柔軟で細長いスコープを肛門から挿入し、直腸からS状結腸、下行結腸、横行結腸、上行結腸、そして最も奥にある盲腸まで、大腸全体の粘膜を直接、詳細に観察する検査です。
検査の目的と重要性
この検査が持つ最も大きな目的は、初期段階では自覚症状がほとんど現れない大腸がんや、将来的にがんへ進行する可能性を持つ大腸ポリープを、症状のない早期の段階で発見し、治療に繋げることです。
大腸がんは早期に発見し治療を行えば、高い確率で治癒が期待できるがんの一つで、また、がん化する前のポリープの段階で切除(ポリペクトミー)することで、がんそのものの発生を未然に防ぐこともできます。
特にがんのリスクが高まり始めるとされる40歳を過ぎたら、明らかな症状がなくても定期的に検査を受けることが望ましいです。
検査の流れ
検査の質は、事前の準備段階から大きく左右されます。検査前日は、消化しやすく腸に残りかすが少ない食事(検査食など)をとり、夜の指定された時間以降は絶食します。
検査当日は、大腸の中を完全にきれいにするため、約1〜2リットルの下剤(腸管洗浄剤)を数時間かけて服用します。
下剤の服用が大変だと感じる人もいますが、最近では少量で飲みやすいタイプも出てきていて、便が透明な液体になったら準備完了のサインです。
検査室で検査着に着替えベッドに横になり、鎮静剤を使用する場合は、この段階で腕の静脈から点滴を開始します。医師がスコープを慎重に挿入し、大腸の内部をくまなく観察します。
検査にかかる時間は腸の長さや形状、癒着の有無、ポリープ切除の有無によって変動しますが、おおよそ15分から30分程度です。検査終了後は、鎮静剤を使用した場合は薬剤の効果が抜けるまで回復室でしばらく休みます。
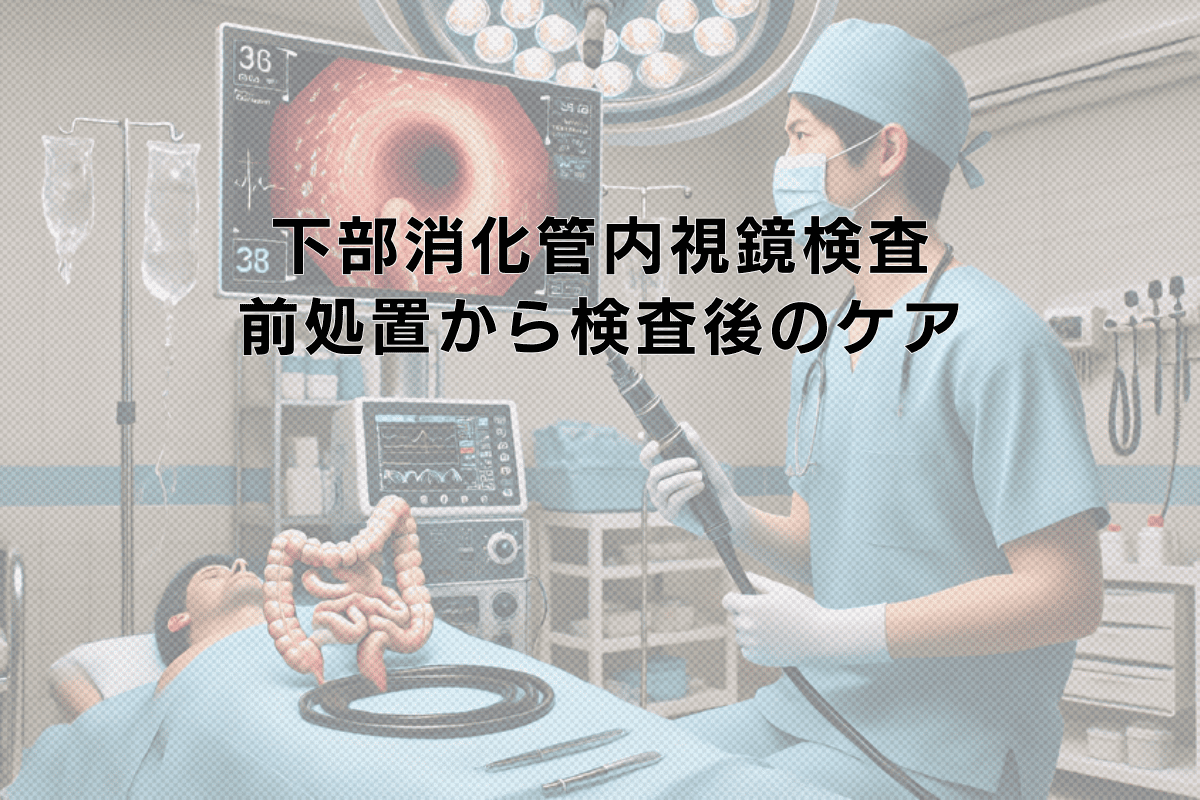
検査でわかること
大腸内視鏡検査によって、大腸がんやポリープ以外にも、さまざまな大腸の病気を診断でき、粘膜の炎症の有無やその範囲、程度を直接目で見て評価できるため、非常に正確な診断に繋がります。
疑わしい部分が見つかった場合は、その場で組織の一部をピンセットのような器具で採取(生検)し、病理検査で良性か悪性かを確定診断することも可能です。
主な対象疾患
鎮静剤を使用する大腸内視鏡検査
鎮静剤を使用する検査は、ウトウトと眠っているような、あるいは心身ともにリラックスした状態で検査を受ける方法です。現在、多くの医療機関で標準的な選択肢として採用されており、検査に伴う身体的・精神的な苦痛を大幅に軽減できます。
鎮静剤とは何か
用いる鎮静剤は、外科手術の際に使用するような意識を完全に失わせる全身麻酔とは異なります。静脈から薬剤を投与することで、中枢神経の働きを穏やかに抑制し、不安や緊張を和らげ、自然な眠気を誘う作用があります。
鎮静の深さは使用する薬剤の種類や量によって精密に調整が可能で、医師からの呼びかけにはかろうじて応じられる程度の浅い鎮静から、ほとんど眠っていて検査中の記憶がない状態まで、患者さんの状態に合わせてコントロールします。
検査中の記憶が残らない健忘効果も特徴で、気づいたら検査が終わっていたと感じる人が少なくありません。
鎮静剤を使用するメリット
鎮静剤を使用することには、単に検査が楽であるという点以外にも、検査の質そのものを高める上で非常に重要な利点があります。
苦痛の軽減
最大のメリットは、検査中にスコープが腸壁を押す感覚や、送気による腹部の張り、腸の曲がり角を通過する際の痛みや不快感をほとんど感じずに済むことです。
過去にお腹の手術歴があり腸に癒着がある方や、体質的に腸が長い(過長結腸)方は痛みを感じやすい傾向がありますが、鎮静剤によってこれらの苦痛が大幅に和らぎます。
検査精度の向上
患者さんがリラックスし、体が無意識に動いてしまうことがないため、医師は観察に完全に集中できます。
眠って受けると病気の見つけやすさが上がったという研究があります。
大腸のヒダの裏側や、見えにくい角度にある場所も時間をかけてじっくりと観察することが可能になり、通常では見落とされがちな平坦な病変や微小なポリープを探しやすく、より精度のいい質の高い検査に繋がるのです。
心理的負担の軽減
過去に受けた内視鏡検査でつらい経験をした人や、検査そのものに対する恐怖心が極度に強い人にとって、鎮静剤は大きな安心材料です。
検査へのネガティブなイメージが払拭され、一度楽な検査を経験することで、今後も定期的な検査をためらわずに受けられるようになるという、長期的な視点での心理的な効果も期待できます。
鎮静剤を使用するデメリットと注意点
多くの利点がある一方で、鎮静剤の使用にはいくつかの注意すべき点や、検査後の生活上の制約があり、事前に十分に理解しておくことが重要です。
副作用のリスク
頻度は決して高くありませんが、鎮静剤には副作用のリスクが伴い、代表的なものは、呼吸が浅くなる呼吸抑制や、血圧の低下などです。
検査中は血圧計や心電図、そして指先に装着して血中酸素飽和度を測定するモニターを装着し、医療スタッフが全身の状態を常に監視しながら安全に最大限配慮して行います。
検査後の制約
鎮静剤を使用した後は、薬剤の効果が完全に体から抜けるまで注意が必要です。個人差はありますが、検査後も眠気やふらつき、判断力の低下がしばらく残ることがあります。
安全のため、検査当日は終日、ご自身での車、バイク、自転車の運転は絶対にできません。移動には公共交通機関を利用するか、ご家族の送迎を手配してください。
追加費用
一部の鎮静剤の使用は、医療機関によっては健康保険の適用外となり、追加の費用がかかることがあります。
費用体系は医療機関ごとに異なるため、検査を受ける前にウェブサイトで確認したり、電話で問い合わせたりしておくと安心です。
鎮静剤使用後の主な制約事項
| 項目 | 制約内容 | 理由 |
|---|---|---|
| 乗り物の運転 | 車、バイク、自転車の運転は終日禁止 | 判断力や反射能力の低下による事故防止のため |
| 仕事・作業 | 危険な作業や重要な判断を伴う業務は不可 | 集中力の低下や眠気が残る可能性があるため |
| 飲食 | 検査後1時間程度は控えることが多い | 薬剤の影響で嚥下反射が鈍り、むせやすくなることがあるため |
鎮静剤を使用しない大腸内視鏡検査
鎮静剤を使わずに、意識がはっきりした状態で検査を受ける方法もあります。経験豊富な医師の高度な技術や医療機関の様々な工夫により、鎮静剤なしでも苦痛を最小限に抑えて検査を終えることは十分に可能です。
鎮静剤なしで検査を行う場合
鎮静剤を使用しない選択は、検査後の予定を優先したいなど、患者さん自身の希望による場合が最も多いです。
その他、鎮静剤の成分に対してアレルギーがある人、重い呼吸器疾患や心疾患、あるいは緑内障(急性閉塞隅角緑内障)などがあり鎮静剤の使用が医学的に危険と判断される人、検査後すぐに車を運転して帰宅する必要がある人などが主な対象となります。
医師と相談の上、鎮静剤なしでの検査が心身への負担が少ないと判断された場合に行います。
鎮静剤を使用しないメリット
鎮静剤を使わないことには、検査後の回復の速さや、医師と対話しながら検査を受けられる点、そして費用の面で利点があります。
検査後の回復が早い
鎮静剤の影響が全くないため、検査終了後の休憩はごく短時間で済みます。ふらつきなどもなく、すぐに普段の生活に戻ることができます。
検査後に仕事の予定がある人や、ご自身で車を運転して帰宅したい人にとっては、これが最大のメリットです。
副作用の心配がない
鎮静剤によるアレルギー反応や呼吸抑制、血圧低下といった副作用の心配が一切ありません。薬剤に対して何らかの不安がある人にとっては、安心して検査を受けられる方法です。
医師と対話しながら検査を受けられる
意識がはっきりしているため、モニターに映し出される自分自身の大腸の内部を見ながら、医師からリアルタイムで説明を受けることができます。
自分の体の状態を直接知ることができるため、病気への理解が深まったり、健康意識が高まったりするきっかけにもなります。
鎮静剤を使用しないデメリットと対策
鎮静剤を使用しない場合は、検査に伴う苦痛を感じる可能性がありますが、苦痛を和らげるための様々な対策も講じられています。
痛みや不快感を感じやすい
スコープがS状結腸など腸の曲がり角を通過する際や、腸が内側から伸ばされる際に、腹部の張りや痛みを感じることがあります。特に、過去に開腹手術を受けたことがある人は、腸の癒着によって痛みが強く出やすいです。
この苦痛が、検査に対する苦手意識の大きな原因となることがあります。
検査への不安感
痛みに対する不安から、検査中に無意識に体に力が入ってしまうことがあります。体が緊張すると腸も硬くなり、かえってスコープの挿入が難しくなったり、痛みをより強く感じたりするという悪循環に陥ることもあります。
痛みを和らげる工夫
鎮静剤を使わない場合でも、医療機関側では様々な工夫で苦痛を軽減する努力をしており、医師のスコープ操作技術はもちろんのこと、使用する設備なども苦痛の度合いに大きく影響します。
| 工夫の種類 | 内容 | 期待される効果 |
|---|---|---|
| スコープ挿入法 | 軸保持短縮法など、腸を伸ばさずにアコーディオンのようにたたむようにスコープを進める技術 | 腸が不必要に引き伸ばされることによる痛みの軽減 |
| 炭酸ガスの使用 | 腸を膨らませる際に、空気の代わりに体への吸収が非常に速い炭酸ガスを使用 | 検査後のお腹の張りを速やかに解消し、不快感を軽減 |
| 体位変換 | 体の向きを右や左、仰向けなどに変えることで、スコープがスムーズに進むように補助 | 重力を利用して腸の屈曲部を通過しやすくする |

鎮静剤使用の有無を判断する基準
最終的に鎮静剤を使用するかどうかは、医師による医学的な判断と、患者さん自身の希望やライフスタイルを丁寧にすり合わせて決定します。どちらか一方的に決めるのではなく、事前の診察で時間をかけてしっかりと話し合うことが大切です。
医師はどのように判断するか
医師は、患者さんの安全確保と、質の高い検査の実施を最優先に考えます。
その上で、年齢、性別、体格、基礎疾患の有無、常用薬の内容、過去の内視鏡検査歴や腹部の手術歴、そして患者さんがどの程度の不安を感じているかを総合的に評価し、どちらの方法がより適しているかを専門家として提案します。
患者自身が考慮すべき点
自分自身でどちらの方法が良いかを考える際には、いくつかのポイントがあり、あらかじめ整理し、医師に伝えることで、より自分に合った納得のいく選択がしやすくなります。
痛みへの耐性
自分が痛みに対してどの程度強いか、あるいは弱いかを客観的に自己評価してみましょう。
痛みに非常に弱い自覚がある、あるいは痛みを想像するだけで強い不安を感じる場合は、無理をせず鎮静剤の使用を前向きに検討するのが良いかもしれません。
検査後の予定
検査当日のスケジュールも極めて重要な判断材料です。検査後に車を運転して帰宅する必要があるか、重要な会議や精密な作業を伴う仕事の予定が入っているかなどを確認しましょう。
鎮静剤を使用するとこれらの活動は厳しく制限されるため、予定との兼ね合いを考える必要があります。
過去の検査経験
以前に大腸内視鏡検査や胃内視鏡検査を受けた経験があれば、その時の状況が最も信頼できる参考情報になります。
非常につらいと感じた経験があるなら鎮静剤の使用を、特に問題なくスムーズに受けられたなら鎮静剤なしを検討するなど、過去の経験をもとに判断できます。
判断の参考ポイント
| 考慮する点 | 鎮静剤使用が推奨される傾向 | 鎮静剤なしでも可能な傾向 |
|---|---|---|
| 痛みへの不安 | 非常に強い、恐怖心がある | あまりない、または耐えられる |
| 過去の検査経験 | つらかった、苦しかった経験がある | 苦痛なくスムーズに受けられた |
| 検査後の予定 | 特に予定はなく、送迎があるか公共交通機関を利用 | 車の運転や仕事の予定がある |
事前の相談が重要
最も大切なのは、検査前の診察時に医師や看護師に自分の希望や不安を率直に、具体的に伝えることです。些細なことでも疑問点を全て解消し、十分に納得した上で検査に臨むことが、心身の負担を軽減する上で大きな助けとなります。
事前に医師に伝えるべきこと
- 過去の内視鏡検査の経験(つらかったか、楽だったかなど)
- 腹部の手術歴(帝王切開や虫垂炎の手術なども含む)
- 現在治療中の病気や服用中の薬(特に血液をサラサラにする薬)
- 薬や食物のアレルギー歴
- 検査に対する不安の具体的な内容と度合い
検査の苦痛を和らげるための他の方法
鎮静剤の使用以外にも、大腸内視鏡検査の苦痛を和らげる方法はいくつかあり、鎮静剤を使用する場合、しない場合のどちらにおいても、より快適な検査の助けとなります。
医師の技術力
検査に伴う苦痛は、担当する医師の技術に大きく左右される側面があります。
経験豊富な内視鏡専門医は、腸を不必要に伸ばすことなく、スムーズにスコープを大腸の最深部まで到達させるための高度な技術(軸保持短縮法など)を習得しています。医療機関を選ぶ際の一つの参考になるかもしれません。
医療機関の設備
どのような設備を導入しているかどうかも、検査の快適性に影響し、特に、お腹の張りを軽減する炭酸ガスの使用や、患者さんの体格や腸の状態に合わせたスコープの選択は重要です。
炭酸ガスの使用
検査では、腸のヒダを丁寧に広げて隅々まで観察するために、腸内に気体を送気します。一般的には空気が使われますが、空気は腸管からの吸収が遅く、検査後にお腹の張りが長時間残りやすいという欠点があります。
一方、炭酸ガス(CO2)は空気の約200倍も速く腸管から吸収されて呼気として体外に排出されるため、検査後のお腹の張りが大幅に軽減され、速やかに回復します。
炭酸ガスと空気の比較
| 項目 | 炭酸ガス(CO2) | 空気 |
|---|---|---|
| 体内への吸収速度 | 非常に速い | 遅い |
| 検査後のお腹の張り | ほとんど残らない、速やかに解消 | 残りやすく、不快感が続くことがある |
| 安全性 | 体に害はなく極めて安全 | 安全 |
細径スコープの選択
通常の大腸スコープよりも直径が細く、より柔軟なスコープ(細径スコープ)を使用することで、挿入時の違和感や痛みを軽減できる場合があります。腸が細い女性や高齢者、癒着が強く疑われる人に対して有効です。
医療機関によっては、患者さんの状態に応じて複数の種類のスコープを使い分けています。
検査前の準備
検査前の準備を指示通りに正しく行うことも苦痛の軽減に繋がります。医師の指示に従い、食事制限をきちんと守り、下剤を正しく服用して腸内を完全にきれいにすることが、スムーズで短時間な検査の基本です。
腸内に便のかすが残っていると、それを洗い流しながらの観察になるため検査時間が長引いたり、最悪の場合、病変の見落としに繋がったりする可能性があります。

鎮静剤に関する詳細な情報https://naishikyo.or.jp/endoscopy/colonoscopy-preparation-guide/
鎮静剤と一言でいっても、いくつかの種類があり、作用や特徴は異なり、また、安全に使用するための医療機関の管理体制も非常に重要です。
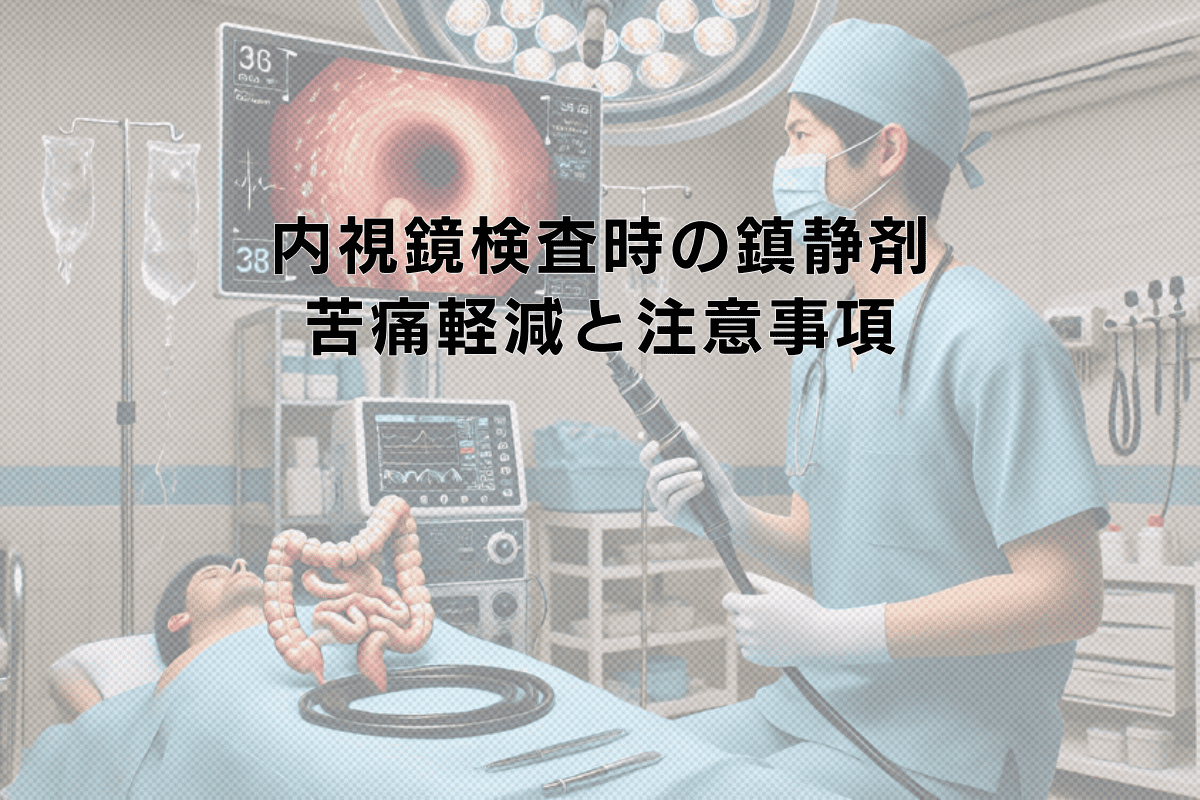
主に使用される鎮静剤の種類
医療機関によって採用している薬剤は異なりますが、一般的に大腸内視鏡検査で用いられる代表的な鎮静剤には以下のようなものがあります。それぞれの特徴を理解し、医師が患者一人ひとりの状態に合わせて最適な薬剤を選択します。
主な鎮静剤の種類と特徴
| 薬剤名 | 特徴 | 注意点 |
|---|---|---|
| ミダゾラム | 抗不安作用、鎮静作用、健忘効果のバランスが良い。作用時間が比較的長い。 | 拮抗薬(作用を打ち消す薬)が存在するため、万一の際に覚醒させやすく調整しやすい。 |
| プロポフォール | 作用の発現が非常に速く、覚醒も速やかで切れが良い。鎮静深度の細かな調整がしやすい。 | 呼吸抑制や血圧低下が起こりやすいため、より厳重な全身状態の監視が必要。拮抗薬はない。 |
| ジアゼパム | 抗不安作用が主で、鎮静作用は比較的穏やか。リラックス効果を目的として使用される。 | 作用時間が長く、検査後も眠気やふらつきが残りやすいことがある。 |
鎮静の深さの調整
鎮静剤の使用目的は、あくまで検査の苦痛を取り除き、安全で質の高い検査を行うことです。そのため、必ずしも完全に眠らせる必要はありません。
患者さんの年齢や体格、基礎疾患の有無、不安の度合いに応じて投与量を細かく調整し、常に最適な鎮静深度を保ちます。
医師が声をかけると反応できる程度の浅い鎮静から、検査中のことを全く覚えていない深い鎮静まで、状況に応じた柔軟な対応が可能です。
安全管理体制
鎮静剤を安全に使用するためには、徹底した管理体制が不可欠です。検査中は、生体情報モニターを用いて、心拍数、血圧、呼吸状態、血中酸素飽和度などをリアルタイムで継続的に監視し続けます。
万が一、呼吸が弱くなったり血圧が低下したりするなどの異常の兆候が見られた場合でも、即座に対応できる体制を整えていて、酸素投与の準備や、緊急時に使用する薬剤・器具も常に備えられています。
検査後の過ごし方の比較
| 項目 | 鎮静剤を使用した場合 | 鎮静剤を使用しない場合 |
|---|---|---|
| 検査後の休憩 | 30分~1時間程度、回復室のベッドで休む | ほとんど不要、または椅子で短時間休む程度 |
| 帰宅方法 | 公共交通機関、家族の送迎など(運転は厳禁) | 制限なし(自身の運転も可能) |
| 食事 | 医師の指示に従う(通常1時間後から可能) | 医師の指示に従う(通常すぐに可能) |
よくある質問
大腸内視鏡検査の鎮静剤に関して、多くの方が抱く疑問についてお答えします。
- 鎮静剤を使うと眠っている間に検査が終わるのですか
-
完全に眠ってしまう場合もありますが、多くはウトウトとまどろんでいるような浅い睡眠状態で、意識が完全になくなるわけではなく、医師からの呼びかけに応じられる程度の鎮静状態を保ちます。
また、鎮静剤には強い健忘効果があるため、検査中の記憶が残らず、結果的にぐっすり眠っていたと感じる人が多いです。
- 鎮静剤なしの検査はどのくらい痛いですか
-
痛みの感じ方には非常に大きな個人差があり、腸の長さや走行(曲がり具合)、過去の手術による癒着の有無、そして何より検査を行う医師の技術力によって大きく異なります。
全く痛みを感じずにリラックスして終わる人もいれば、残念ながら強い痛みを感じる人もいます。不安な場合は、事前に医師にその旨を伝え、痛みを軽減する工夫について十分に相談することが大切です。
- 検査中にポリープが見つかったらどうなりますか
-
検査中に切除可能な大きさや形状のポリープが発見された場合、多くの医療機関ではその場で切除(日帰り手術)を行います。鎮静剤を使用している場合は痛みを感じることはありません。
鎮静剤なしの場合でも、ポリープ切除自体に痛みは伴わず、切除することで将来の大腸がんを予防できるため、非常に有意義です。
ただし、大きなポリープや、出血のリスクが高いと判断された場合は、後日改めて入院の上で切除することもあります。
- 鎮静剤の副作用が心配です
-
鎮静剤には、呼吸抑制や血圧低下、アレルギー反応などの副作用の可能性がありますが、頻度は高くありません。
医療機関では、の副作用の発生を常に想定し、検査中は生体情報モニターで全身状態を厳重に監視し、緊急時にも迅速に対応できる万全の体制を整えています。
安全性が確保された環境で使用しますので、過度に心配する必要はありません。
以上
次に読むことをお勧めする記事
【大腸内視鏡検査とはどのような検査なのか】
鎮静剤使用の判断について読んで、「実際の検査はどのような流れで進むのだろう」と思った方もいらっしゃるのでは?検査の基本的な流れや注意点について詳しく説明しています。
【大腸ポリープの基本症状から治療法まで – 患者さんのための総合案内】
大腸内視鏡検査について理解が深まると、検査で最も多く発見される大腸ポリープについても知りたくなる方が多いようです。ポリープの種類や治療法との意外な繋がりが見えてくる内容です。
参考文献
Takahashi Y, Tanaka H, Kinjo M, Sakumoto K. Sedation-free colonoscopy. Diseases of the colon & rectum. 2005 Apr;48(4):855-9.
Gotoda T, Akamatsu T, Abe S, Shimatani M, Nakai Y, Hatta W, Hosoe N, Miura Y, Miyahara R, Yamaguchi D, Yoshida N. Guidelines for sedation in gastroenterological endoscopy. Digestive Endoscopy. 2021 Jan;33(1):21-53.
Takahashi Y, Tanaka H, Kinjo M, Sakumoto K. Prospective evaluation of factors predicting difficulty and pain during sedation-free colonoscopy. Diseases of the colon & rectum. 2005 Jun 1;48(6):1295-300.
Inoki K, Chiba T, Miura K, Tagawa T, Aoyagi Y, Takeuchi Y, Moriyama N, Kuraoka K, Ohara T, Haruhara Y, Mizuki A. When Endoscopic Sedation is Not an Option: Insights From a Multicenter on‐site Survey on Tolerance for Japanese Gastric Cancer Screening. DEN open. 2025 Aug 11;6(1):e70179.
Triantafillidis JK, Merikas E, Nikolakis D, Papalois AE. Sedation in gastrointestinal endoscopy: current issues. World journal of gastroenterology: WJG. 2013 Jan 28;19(4):463.
Luo DJ, Hui AJ, Yan KK, Ng SC, Wong VW, Chan FK, Cheong JP, Lam PP, Tse YK, Lau JY. A randomized comparison of ultrathin and standard colonoscope in cecal intubation rate and patient tolerance. Gastrointestinal endoscopy. 2012 Mar 1;75(3):484-90.
Nguyen NQ, Toscano L, Lawrence M, Moore J, Holloway RH, Bartholomeusz D, Lidums I, Tam W, Roberts-Thomson IC, Mahesh VN, Debreceni TL. Patient-controlled analgesia with inhaled methoxyflurane versus conventional endoscopist-provided sedation for colonoscopy: a randomized multicenter trial. Gastrointestinal endoscopy. 2013 Dec 1;78(6):892-901.
Terruzzi V, Meucci G, Radaelli F, Terreni N, Minoli G. Routine versus “on demand” sedation and analgesia for colonoscopy: a prospective randomized controlled trial. Gastrointestinal endoscopy. 2001 Aug 1;54(2):169-74.
Abraham N, Barkun A, LaRocque M, Fallone C, Mayrand S, Baffis V, Cohen A, Daly D, Daoud H, Joseph L. Predicting which patients can undergo upper endoscopy comfortably without conscious sedation. Gastrointestinal endoscopy. 2002 Aug 1;56(2):180-9.
Liao WC, Chiu HM, Chen CC, Lee YC, Wu MS, Lin JT, Wu AS, Wang HP. A prospective evaluation of the feasibility of primary screening with unsedated colonoscopy. Gastrointestinal endoscopy. 2009 Oct 1;70(4):724-31.