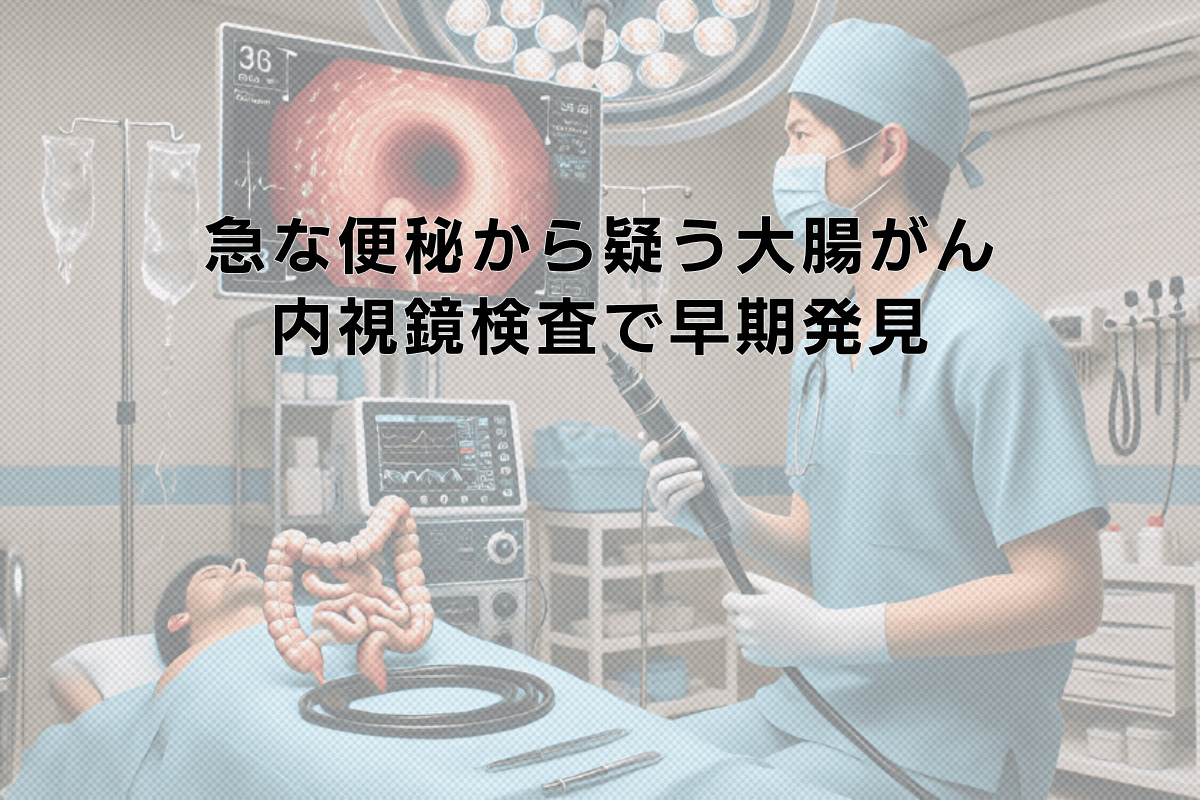急に便秘の症状を感じたとき、大腸がんとの関連を思い浮かべる方は少なくありませんが、実際に便の出が悪くなる背景には食生活や生活習慣だけではなく、腸内にできたポリープや大腸がんが潜んでいることがあります。
大腸がんは早期に発見すれば負担を抑えた治療が期待できるため、内視鏡検査による定期的なチェックが大切です。
本記事では、急に便秘になった場合に考えたい大腸がんの可能性から、内視鏡検査による早期発見の流れまでを解説します。
急に便秘が起きた背景を考える
急に便秘が続くと、大腸がんを疑う場面もありますが、まずは日常生活の見直しや加齢などの要因がないかを考えることが重要です。
症状の程度や期間を把握し、生活習慣との関連を探るとともに、必要に応じて専門の医療機関を受診してください。
食生活や生活習慣との関連
食事の偏りや水分不足、運動不足などが便秘を起こす大きな要因になり、とくに忙しい現代社会では、外食やインスタント食品に偏りがちです。
食物繊維が足りない状況や慢性的なストレスは、腸の働きを低下させ、便通を悪化させることがあり、寝不足や不規則な生活も腸のリズムを乱す可能性があります。
食事の偏りを見直すためのポイント
- 野菜や果物を意識して摂取する
- 水分補給をこまめに行う
- 食事時間をできるだけ一定に保つ
- アルコールや刺激物の過剰摂取を控える
- 1日3食のバランスを考える
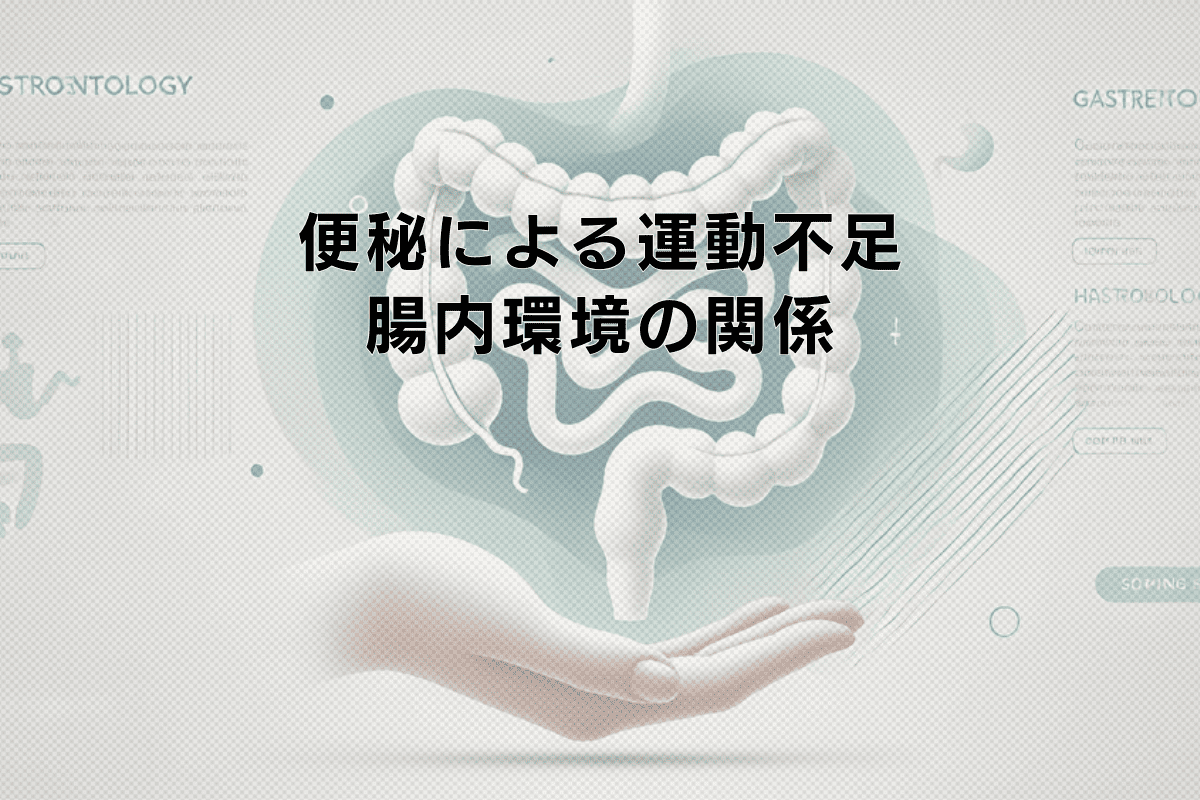
加齢と腸内環境
加齢とともに腸の蠕動運動が低下すると言われて、若い頃は感じなかった便秘が年齢を重ねるにつれて増えることがあります。また、加齢によって腸内細菌のバランスが変化し、善玉菌が減少することも便秘を引き起こす要因の1つです。
高齢者は便秘の影響を受けやすいため、症状が急に変化した場合には大腸がんへの注意も怠らないようにする必要があります。

症状が続く場合の注意点
便通が数日間滞るだけなら生活習慣改善を試してみてもいいですが、便通の変化が数週間以上続いたり、下痢と便秘が交互に起きるなどの異常がみられた場合は早めの医療機関受診を検討してください。
特に血便や腹痛を伴うような症状があれば、大腸がんのリスクが高まります。
大腸がんが疑われる便通の変化の目安
| 変化の種類 | 内容 |
|---|---|
| 便秘・下痢の反復 | 便が出にくい状況とゆるい便が交互に続く |
| 血便が混じる | 便に赤い血液や暗い血液が付着している |
| 便の形状や色の変化 | 細い便が続く、黒っぽい便が続く |
| 腹痛や違和感が増える | 下腹部やわき腹に痛みや張り感が増える |

大腸がんが疑われるサインとリスク要因
急に便秘が起きるだけでなく、ほかの症状も併せて出る場合には大腸がんが疑われます。普段の生活習慣や年齢的な要因、家族の病歴なども大腸がんリスクを高める要因です。
便秘以外の初期症状
大腸がんの初期段階では、便通異常以外にも体重減少や腹部の張り、慢性的な疲労感などがみられることがあるものの、こうした症状は他の疾患とも共通しているため、見逃しやすい面があります。
便秘以外にも「なんとなくお腹が重い」「頻繁に疲れる」といった症状に心当たりがある場合は、内視鏡検査で腸内を確認しておくことが大切です。
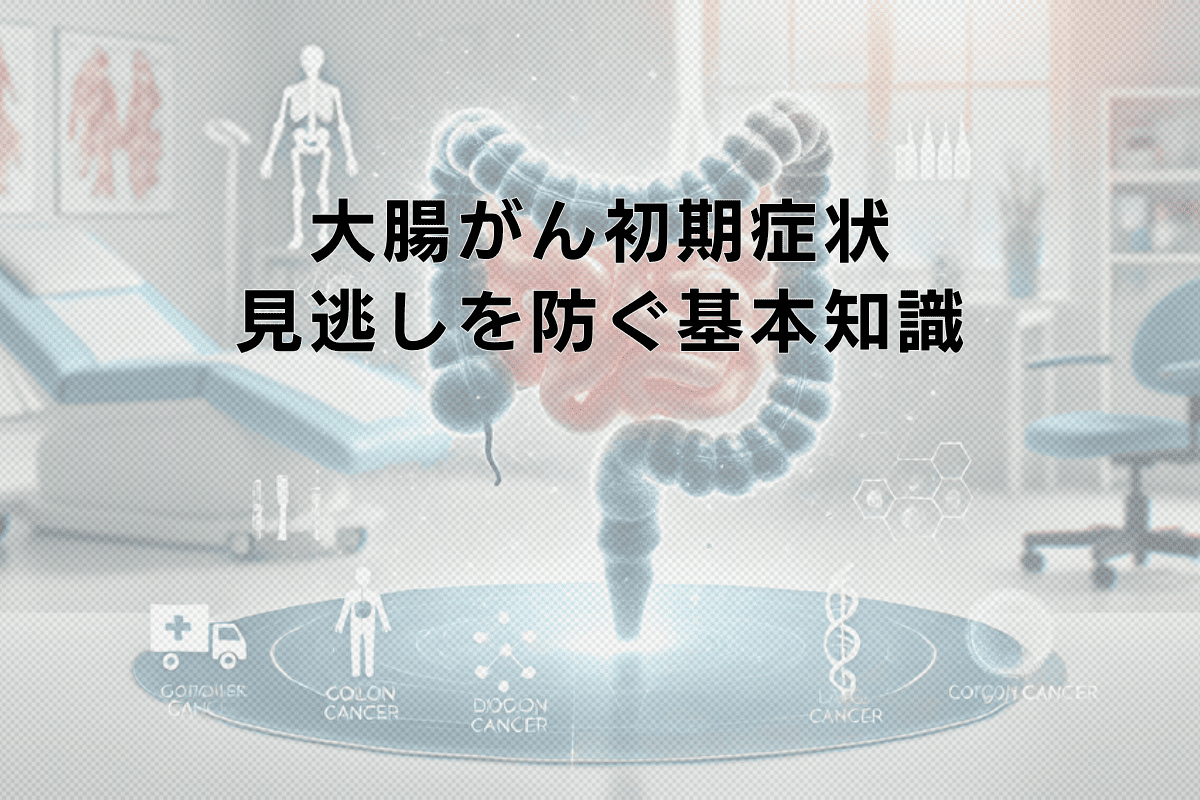
年齢や遺伝的要素の影響
一般的に大腸がんは40代以降で発症率が高まるといわれますが、若い年代であっても安心はできません。
家族に大腸がんの病歴がある場合や、遺伝性の疾患を抱えている場合は、より注意が必要で、年齢や遺伝要素は変えられませんが、定期的な検査によって早期に異常を発見することが可能です。
大腸がんの主なリスク要因
| リスク要因 | 内容 |
|---|---|
| 年齢 | 40代以降で増加しやすい |
| 家族歴 | 血縁者が大腸がんを患っている場合にリスク上昇 |
| 遺伝性の疾患 | 家族性大腸腺腫症などが該当 |
| 食生活 | 高脂肪・低繊維の食事によるリスク増 |
| 運動不足 | 長期間の座り仕事や運動不足 |
忙しい現代人の生活習慣
仕事の都合などで食事時間が不規則になりやすく、栄養バランスが偏ることで便秘や腸内環境の乱れが深刻化するケースがあり、さらにストレスや睡眠不足が重なると免疫力が低下し、大腸がんのリスク要因を高める可能性があります。
急に便秘が続く現象を放置すると、大腸がんの発見が遅れる懸念もあるため注意が必要です。
内視鏡検査の基礎知識
大腸がんの早期発見に有効な手段として、内視鏡検査を受ける方が増えています。内視鏡検査には、大腸カメラや胃カメラなどがあり、それぞれ消化管の異なる部位を観察できます。
痛みへの不安や検査費用への疑問もあるかと思いますが、必要な情報を知り、正しく理解することが大事です。
内視鏡検査のメリットと確認できる範囲
内視鏡検査では、カメラを使って腸内や胃の粘膜を直接観察し、ポリープが見つかれば、その場で切除できることが大きな利点です。また、出血箇所や炎症の有無を確実に把握できます。
レントゲン撮影やCT検査ではわかりにくい微細な変化も確認できるため、早期の段階で大腸がんやほかの病変を見つけやすいです。
内視鏡検査でわかりやすい病変
| 病変の種類 | 内視鏡検査での特徴 |
|---|---|
| ポリープ | 粘膜表面の隆起や突起を直接観察し、切除も可能 |
| がん初期病変 | 色の変化や表面の不整、出血点などを詳細に確認 |
| 炎症性腸疾患 | 潰瘍や粘膜のただれを確認し、生検で詳しく診断 |
| 出血箇所 | 出血源を見極めて止血処置が可能 |
痛みや恥ずかしさに対する配慮
内視鏡検査は「痛そう」「恥ずかしい」というイメージを持たれがちですが、実際には鎮静剤を使用することで苦痛を軽減できます。スタッフもプライバシーに配慮しながら検査を行うため、抵抗感が強い方でも落ち着いて臨むことが可能です。
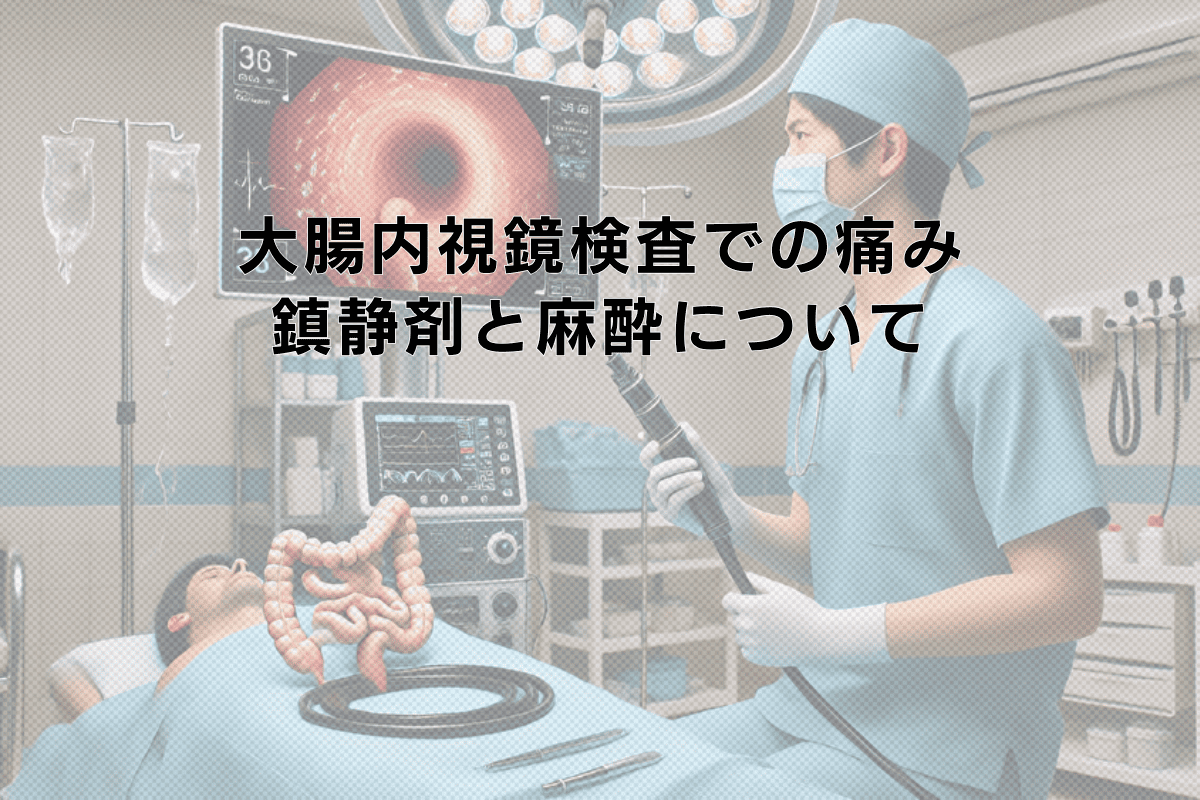
検査と費用の概略
保険診療の範囲内で内視鏡検査を受ける場合、自己負担額は3割程度になるのが一般的ですが、検査内容や処置の有無によって変動します。
オプションで鎮静剤や麻酔を使う場合の追加費用が気になる方は、事前に医療機関へ確認しておきましょう。

大腸カメラ検査の流れ
大腸カメラ検査は腸内を直接観察し、大腸がんやポリープなどを見つけるための有力な方法です。正しい手順を踏んで行えば、安全かつスムーズに終えることが期待できます。

事前準備の食事制限と腸内洗浄
大腸カメラ検査を受ける前には、数日前から食事の内容に気をつける必要があり、消化に時間がかかる食品や繊維質の多い食品を避けることで、検査時に腸内がクリアな状態になります。
また、腸内洗浄用の下剤を飲んで腸をきれいにしておくことが一般的です。
大腸カメラ検査前に避けたい食材
| 食材 | 理由 |
|---|---|
| きのこ類 | 食物繊維が多く、腸に残りやすい |
| 海藻類 | ヌルヌル成分が内視鏡カメラに付着しやすい |
| 種の多い果物 | 種が腸内に残り、観察の妨げになる場合がある |
| ゴボウやレンコンなど根菜 | 繊維が豊富で検査に影響を及ぼす可能性がある |
検査当日の受診手順
検査当日は指定時間までに医療機関へ行き、受付を済ませた後に問診や血圧測定などを行い、場合によっては下剤の追加や点滴を準備し、鎮静剤の投与を受けたうえで検査室へ移動します。
検査時間は個人差がありますが、おおむね15~30分程度と考えられます。
検査後の休息と日常生活への戻り方
検査後は鎮静剤の影響が残ることがあるので、回復室やベッドで休む時間を設け、検査後すぐは腸内に空気が入っており、お腹の張りを感じることがあるものの、時間とともに和らぎます。
当日は自転車や自動車の運転を控え、翌日からは普段通りの生活に戻る方が多いですが、医療機関の指示に従ってください。
大腸カメラ検査のスケジュール
| 検査前の期間 | 事前の食事制限や下剤の服用 |
|---|---|
| 検査当日 | 受付→問診→下剤や点滴→鎮静剤→検査開始 |
| 検査直後 | 回復スペースで休む→医師の説明を受ける |
| 検査翌日以降 | 普段の生活へ復帰。ただし指示に注意する |
胃カメラ検査と併用する理由
胃カメラと大腸カメラを同時に受けると、消化管の全体像を効率よくチェックできます。時間や費用を節約しながら、幅広い疾患を早めに見つけたい方にとって、併用受診は有用です。
消化管全体のトラブルを見逃さないために
胃と大腸は、それぞれ異なる症状を示すことが多いものの、併せて検査することで上部から下部まで一度に観察でき、急に便秘が続くときだけでなく、胃痛や胸やけなどが気になる方も、総合的なチェックが可能です。
ポリープやがんだけでなく、胃潰瘍や胃炎などの初期兆候を把握できる利点があります。
上部消化管と下部消化管の症状
- 上部消化管(胃・食道)の不調:胸やけ、みぞおちの痛み、吐き気
- 下部消化管(大腸)の不調:便秘や下痢、腹部膨満感、血便
時間や費用の節約
別々に検査を受ける場合、予約や通院の手間が増え、費用も2回分かかることが多く、同日に受けると、通院や検査準備の時間を一度で済ませられるため、忙しい方にとって利便性が高いです。
費用面でも、自費検査の場合、医療機関によっては同日検査のセット割引を設定している場合があります。
同日検査における大まかなメリット
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 通院回数 | 1回の通院で胃と大腸の検査を実施可能 |
| 下剤の準備 | 大腸カメラ用の下剤を1度飲むだけで済む |
| 費用 | 人間ドックなどでセット価格を設定している医療機関がある |
| 検査時間 | 麻酔や準備が一度で済むためトータル時間が短縮 |
健診や人間ドックでの活用
大腸がんや胃がんのリスクが高まる年齢層では、健診や人間ドックで胃カメラと大腸カメラを同日に受けるケースが増えていて、一度に幅広い部位を調べられることで、心配な点をまとめてクリアにできます。
家族に胃がんや大腸がんの既往歴がある方などは、より積極的に利用することが勧められています。
早期発見の重要性
大腸がんは早期発見ができれば、身体への負担を抑えた治療が期待でき、逆に、見つかるのが遅れると治療範囲が大きくなったり、再発リスクが上がったりするため、定期的な検査が大切です。
進行度による治療方法の違い
大腸がんは進行度が進むと手術で切除する範囲が広がり、術後の回復期間や生活の質に影響を及ぼすことがあり、早期の段階であれば内視鏡による切除など、身体への負担が比較的少ない方法を選びやすいです。
進行度が中期や後期に入ってから見つかった場合には、化学療法や放射線治療との併用も考慮しなければならないことが多くなります。
大腸がんの進行度と主な治療の目安
| 進行度 | 主な治療方法 |
|---|---|
| 早期 | 内視鏡的切除、内視鏡的粘膜下層剥離術 |
| 中期 | 外科手術、場合によっては化学療法併用 |
| 後期 | 化学療法、放射線治療、外科手術の組み合わせ |
日常生活への影響を最小限に
便秘や下痢などの症状は普段の生活の質を大きく左右し、大腸がんが進行すると、腸閉塞などの合併症を起こすこともあり、さらに生活が制限されやすくなります。
早期発見により、治療後の回復もスムーズになりやすく、普段の仕事や趣味への復帰もしやすいです。
再発リスクを下げるポイント
大腸がんを治療したあとも、再発リスクをゼロにすることは難しいですが、食生活や運動習慣を整え、定期検査を受け続けることで再発リスクを下げることが期待できます。
治療後も便の状態を観察し、異変を感じた場合は早めに医療機関へ相談してください。
再発リスクを下げるために意識したいこと
- 野菜や果物をしっかり摂る食生活
- 適度な有酸素運動と筋力トレーニング
- 定期的な内視鏡検査(術後フォロー)
- ストレス管理と十分な睡眠
- 医師とのコミュニケーションを密に取る
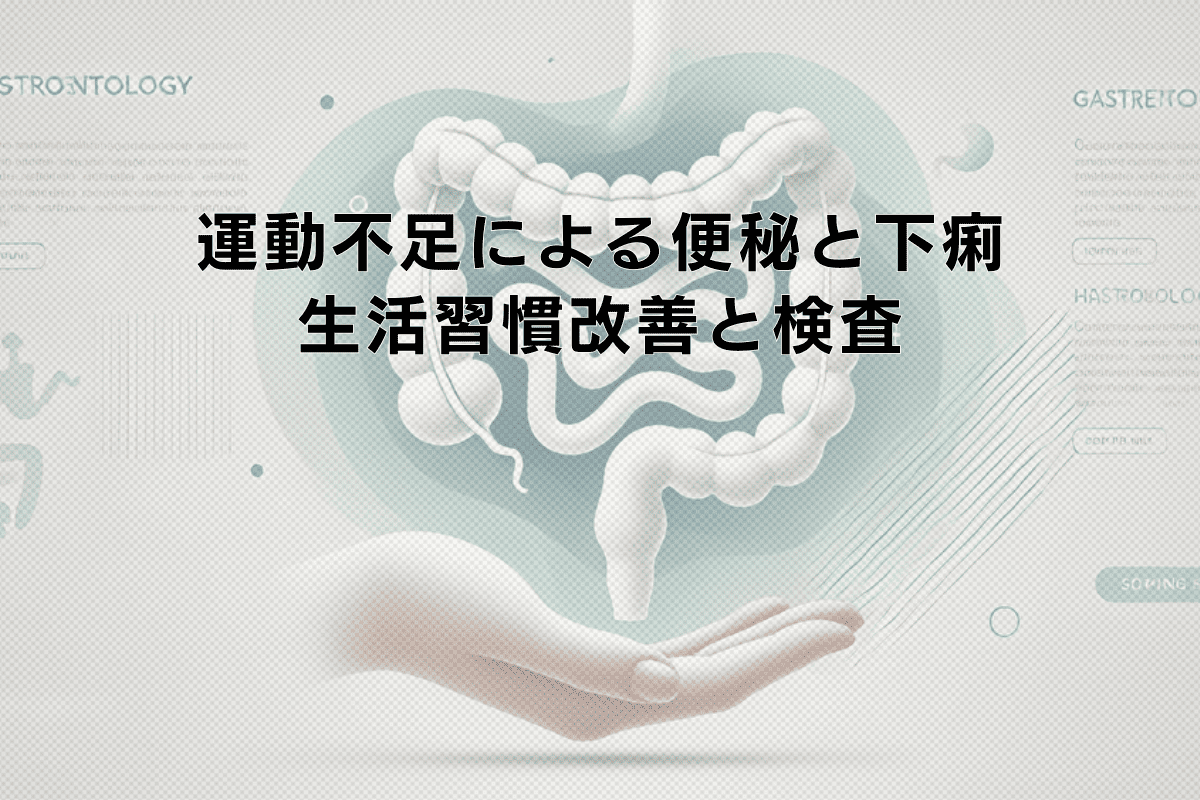
検査をためらう方へのアドバイス
内視鏡検査への抵抗感を抱いている方は少なくありませんが、正しい情報を得ることで不安を軽減できます。病院スタッフと相談しながら、自分に合った方法で検査を受けることが大切です。
不安や恐怖心を和らげる方法
痛みや恥ずかしさだけでなく、検査結果への不安から受診を避けてしまうケースがあります。
こうしたメンタル面のハードルを下げるには、医療機関の説明やカウンセリング、インターネットでの口コミ情報の確認などを活用して、理解を深めることが有用です。
心構えを整えるための例
| アクション | 効果 |
|---|---|
| 事前相談を積極的に活用 | 疑問を解消し安心感を高める |
| 信頼できる知人に相談 | 個人的な体験談が得られる |
| 検査動画や説明資料を見る | 検査内容をイメージしやすくなり恐怖心を軽減 |
痛みやプライバシー対策への工夫
鎮静剤や静脈麻酔を使って眠っている間に検査を受ける方法や、女性スタッフが対応するなど、プライバシーを配慮したクリニックも増えているため、事前に問い合わせてから予約を入れると安心です。
検査中の痛みが心配な方は「痛みを感じにくい内視鏡システム」を導入している施設を探しましょう。
前向きに検査を受けるための準備
身体面だけでなく心理面の準備も検査時の負担を減らし、前日は早めに休み、睡眠を十分に取ることで、当日の体調を良好に保てます。下剤の飲み方や検査日程をきちんと把握することで、余裕をもって行動しやすくなります。
知らないことが多いほど不安を抱えやすいので、疑問点は積極的に医療スタッフへ質問してください。
よくある質問
大腸カメラや胃カメラを受ける際、検査の時間や麻酔の有無など、気になるポイントはいくつもあります。実際によく聞かれる質問と、その回答をまとめました。
- 検査の所要時間
-
大腸カメラと胃カメラを同日に受ける場合、検査自体の時間は1つあたり15~30分ほどですが、準備や回復時間も含めると半日程度になります。
鎮静剤を使用する場合は、回復までの間は自分で車や自転車の運転ができないため、帰宅手段を事前に考えておくとスムーズです。
- 麻酔の有無と安全性
-
一般的に、大腸カメラは鎮静剤や静脈麻酔を使って行うことが多く、麻酔を使うと眠っている間に検査が行われるため、痛みや不快感はほとんど感じません。
麻酔から覚めるまでに多少時間がかかることや、血圧や酸素飽和度の変化をモニターで確認しながら検査を進めるため、医療機関の指示に従って行動する必要があります。
- 予約やスケジュールの取り方
-
内視鏡検査は完全予約制のクリニックが多く、電話やWEBでの予約が可能な施設も増えています。
大腸カメラと胃カメラを同日に受ける場合は日程の確保が重要なので、早めに問い合わせて自分の都合に合った日時を相談してください。特に週末は混みやすいため、余裕をもったスケジュールを立てておきましょう。
次に読むことをお勧めする記事
【大腸がん検査方法の選び方 – 血液検査から内視鏡検査まで】
便秘と大腸がんの関係について理解が深まったら、次は実際の検査方法について知っておくと安心です。検査を検討している方に特に参考になる内容です。
【運動不足による便秘と下痢 – 生活習慣改善と検査の必要性】
便秘と腸の不調は生活全体と密接に関係しています。運動不足が招く腸トラブルを理解し、日々のケアにつなげましょう。
参考文献
Otani T, Iwasaki M, Inoue M, Sasazuki S, Tsugane S, Japan Public Health Center–Based Prospective Study Group. Bowel movement, state of stool, and subsequent risk for colorectal cancer: the Japan public health center–based prospective study. Annals of Epidemiology. 2006 Dec 1;16(12):888-94.
Tashiro N, Budhathoki S, Ohnaka K, Toyomura K, Kono S, Ueki T, Tanaka M, Kakeji Y, Maehara Y, Okamura T, Ikejiri K. Constipation and colorectal cancer risk: the Fukuoka Colorectal Cancer Study. Asian Pac J Cancer Prev. 2011 Jan 1;12(8):2025-30.
Staller K, Olén O, Söderling J, Roelstraete B, Törnblom H, Song M, Ludvigsson JF. Chronic constipation as a risk factor for colorectal cancer: results from a nationwide, case-control study. Clinical Gastroenterology and Hepatology. 2022 Aug 1;20(8):1867-76.
Kashida H, Kudo SE. Early colorectal cancer: concept, diagnosis, and management. International journal of clinical oncology. 2006 Feb;11:1-8.
Holtedahl K, Borgquist L, Donker GA, Buntinx F, Weller D, Campbell C, Månsson J, Hammersley V, Braaten T, Parajuli R. Symptoms and signs of colorectal cancer, with differences between proximal and distal colon cancer: a prospective cohort study of diagnostic accuracy in primary care. BMC family practice. 2021 Dec;22:1-3.
Larkin PJ, Cherny NI, La Carpia D, Guglielmo M, Ostgathe C, Scotté F, Ripamonti CI, ESMO Guidelines Committee. Diagnosis, assessment and management of constipation in advanced cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines. Annals of oncology. 2018 Oct 1;29:iv111-25.
Sundbøll J, Thygesen SK, Veres K, Liao D, Zhao J, Gregersen H, Sørensen HT. Risk of cancer in patients with constipation. Clinical Epidemiology. 2019 Apr 30:299-310.
Patel SG, Karlitz JJ, Yen T, Lieu CH, Boland CR. The rising tide of early-onset colorectal cancer: a comprehensive review of epidemiology, clinical features, biology, risk factors, prevention, and early detection. The lancet Gastroenterology & hepatology. 2022 Mar 1;7(3):262-74.
Hall N, Birt L, Banks J, Emery J, Mills K, Johnson M, Rubin GP, Hamilton W, Walter FM. Symptom appraisal and healthcare-seeking for symptoms suggestive of colorectal cancer: a qualitative study. BMJ open. 2015 Oct 1;5(10):e008448.
Riaz R, Masood N, Benish A. Red flag symptoms: detailed account of clinicopathological features in young-onset colorectal cancer. Intestinal research. 2017 Apr 27;15(2):203.