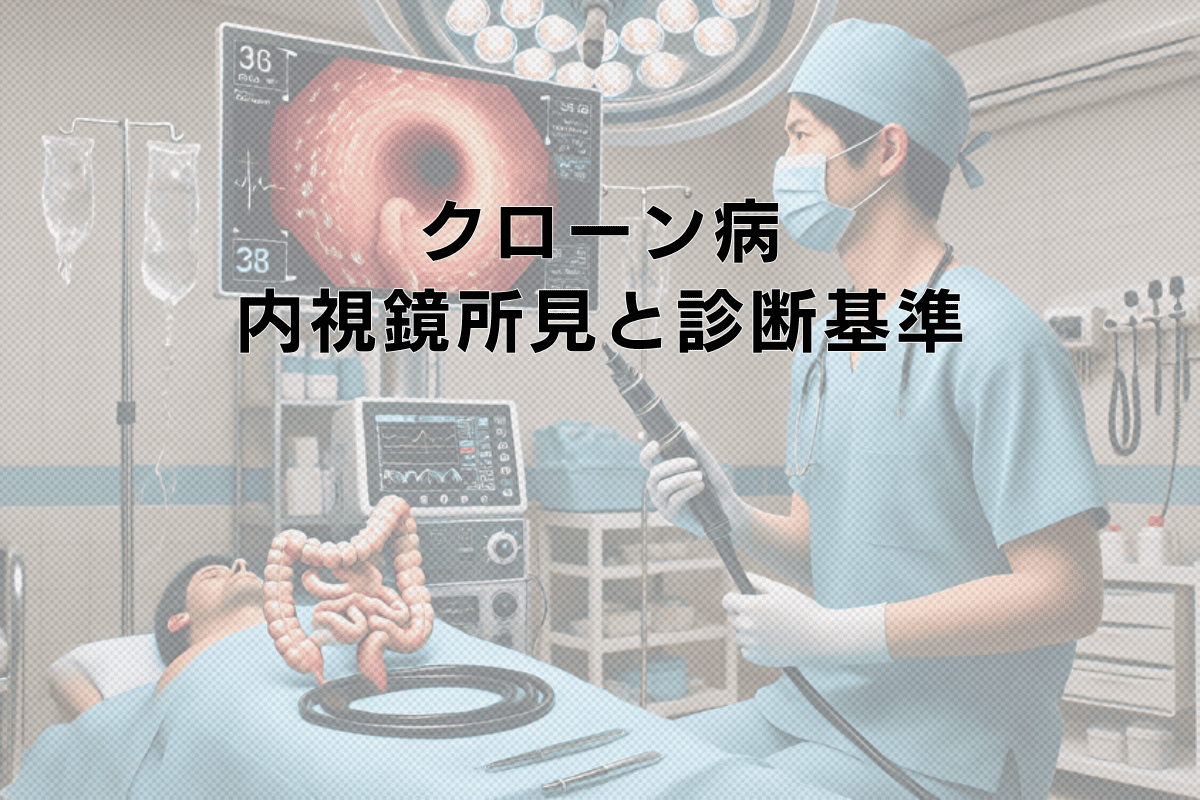クローン病は小腸から大腸、場合によっては口腔など消化管全域にわたって炎症や潰瘍を生じることが特徴です。
初期段階では腹痛や下痢などの軽度な症状だけでなく、食欲低下や体重減少など全身的な体調不良を感じ、放置すると進行が進む恐れがあります。
この病気の診断や治療方針の決定には、内視鏡検査での観察や診断基準を踏まえた正確な評価が重要です。
この記事ではクローン病の概要、症状の特徴、内視鏡所見と診断基準、そして治療方針を決める流れについて解説します。
クローン病とは何か
クローン病は慢性炎症性腸疾患の一種であり、消化管の粘膜を中心に深い潰瘍やびらんを形成しやすいです。口から肛門に至るまで、あらゆる部位に病変が散在する可能性があります。
特に小腸と大腸に多くの炎症が見られ、長期間にわたって症状が続く傾向にあります。
クローン病の概要
クローン病は難治性疾患に分類されており、一度発症すると長く付き合う必要があり、腸管の深い層まで炎症が及びやすく、潰瘍や瘻孔(ろうこう)が形成されるリスクがあります。
再燃と寛解を繰り返すケースもあり、症状が出ていない時期でも内視鏡検査などの定期的な評価を継続することが大切です。
頻度と増加傾向
かつては欧米での報告が多かったクローン病ですが、食生活の変化などに伴い、日本国内でも患者数が増えています。若年層での発症が多いイメージがありますが、実際には幅広い年齢層で確認されています。
医師がクローン病の疑いを持った場合は、できるだけ早い段階で専門的な検査に進むことが望ましいです。
小腸・大腸を中心とした病変
小腸と大腸での病変が多く報告されていますが、口腔や胃などにも炎症が及ぶことがあります。腸の壁の深い層まで病変が拡大しやすい点が特徴であり、狭窄や瘻孔形成の原因にもなります。
患者さんごとに炎症の広がり方や強さが異なるため、個別の検査と治療計画が必要です。

生活への影響
クローン病は長期にわたるコントロールが必要となるため、症状が強いときは食事制限や生活リズムの変更を余儀なくされ、下痢や腹痛のために外出を控えるケースや、栄養摂取に苦労するケースもあります。
治療を行えば症状を抑えられる可能性があるので、まずは疾患について正しい知識を持つことが大切です。
クローン病で起こりやすい病変部位と特徴
| 病変部位 | 主な特徴 | 合併症の例 |
|---|---|---|
| 口腔 | 口内炎、潰瘍 | 口唇の亀裂など |
| 食道 | 潰瘍やびらん | 胃酸の逆流や胸やけ |
| 胃・十二指腸 | 潰瘍、狭窄、浮腫など | 痛みや出血 |
| 小腸(回腸) | 回盲部付近に多い潰瘍や狭窄 | 痛み、栄養不良、瘻孔形成 |
| 大腸 | 不連続性の潰瘍、敷石像所見 | 下痢、便血、狭窄、瘻孔 |
| 肛門周囲 | 痔瘻、肛門周囲潰瘍 | 排便困難、感染リスクの増大 |
こうした多岐にわたる病変部位がクローン病の複雑さを示しています。
クローン病の症状と特徴
クローン病の症状は多岐にわたり、主に消化器症状が中心ですが、時には全身症状が目立つ場合もあります。個人差が大きいため、早い段階でクローン病の症状を把握しておくと受診のタイミングを見誤らずに済みます。
初期症状から代表的な症状まで
初期段階では腹部不快感や下痢を訴えるケースが多く、下痢の回数が増加し半固形状から水様便へと移行し、さらに体重減少や食欲不振が徐々に現れることもあります。
大腸に強い炎症がある場合は血便がみられるケースもあり、知らないうちに慢性化する恐れがあるので注意が必要です。

全身症状にも要注意
クローン病は腸以外の部位にも影響が及ぶことがあり、皮膚や関節、目などに炎症反応が起こると関節痛や皮疹、ぶどう膜炎などを起こす可能性があります。
また、慢性炎症が続くことで貧血や倦怠感などの全身症状が深刻化する場合もあるため、総合的な視点で経過を観察することが必要です。
小児期発症の場合
成長期にある小児期や思春期にクローン病を発症すると、成長障害や発育不良を引き起こす可能性が高まるので、栄養管理や治療計画を考慮する上で、専門医との連携がさらに重要になります。
また、学校生活や部活動などとの兼ね合いも考慮しなければならず、家族や周囲のサポートが必要です。
食事との関連
クローン病の症状を悪化させる要因として、食事内容が挙げられます。脂肪分や食物繊維が多い食事は腸に負担をかけ症状を誘発する場合があります。
ただし、個人差が大きいため、一概にこれだけは避ければいいというわけではなく、医師や栄養士と相談しながら自分に合った食事計画を立てることが大切です。
主なクローン病の症状
| 症状 | 主な特徴 | 日常生活への影響 |
|---|---|---|
| 下痢 | 便の回数増加、水様便 | トイレの場所を常に気にする必要が生じる |
| 腹痛 | 特に回盲部付近に痛みを感じるケースが多い | 食欲低下や活動量減少につながる |
| 血便 | 大腸病変が進行すると起こる | 精神的不安を増幅させる要因になる |
| 発熱 | 炎症が強い際に起こりやすい | 倦怠感や脱力感を伴う場合がある |
| 体重減少 | 栄養吸収障害や食欲低下が原因 | 免疫力低下、体力不足 |
| 倦怠感 | 慢性炎症による全身状態の悪化 | 活動意欲が低下し、休養を要する |
こうした症状のいずれか、あるいは複数が長引いているならクローン病の疑いが考えられます。
クローン病の診断基準
クローン病かどうかを判断するためには、総合的なアプローチが必須です。症状の問診、身体所見、血液検査、画像検査、内視鏡検査などを踏まえて評価し、最終的にクローン病診断基準と照合する流れになります。
現在広く参照される診断基準
国内外で用いられる診断基準にはいくつかの種類がありますが、日本では厚生労働省が定めるガイドラインを参考とし、典型的な症状や内視鏡所見、X線検査所見など、多角的な観点からクローン病と判断できます。
- 小腸や大腸に段階的・離在性の潰瘍が認められる
- 病変が深く、消化管壁全層に広がっている可能性がある
- 病変の境界が比較的はっきりしている
- 痔瘻などの肛門病変が見られることがある
複数の条件を満たしてはじめてクローン病と判断されるため、総合的な検査が求められます。
主要な検査項目
診断のためには様々な検査を組み合わせ、血液検査では炎症の指標であるCRPや血球数の異常などを確認し、画像検査では腸管の狭窄や潰瘍の位置を把握します。
さらに内視鏡検査で粘膜を直接観察し、生検を行って組織レベルの変化を調べることが重要です。
血液検査や画像検査との比較
血液検査やCT、MRI、超音波検査などは身体への負担が比較的少なく、腸管全体の状態を把握するうえで有用ですが、消化管粘膜の詳細な状態や微小病変を見極めるには内視鏡検査が重要です。
クローン病の特徴的な病変を捉えることによって、診断の精度が高まります。
注意が必要な鑑別疾患
クローン病と似た症状を示す病気に潰瘍性大腸炎があり、両者はともに炎症性腸疾患に分類されますが、炎症の広がり方や病変の深さなどに違いがあります。また、感染性腸炎や過敏性腸症候群なども鑑別が必要です。
自分の判断で放置せず、医師の診察や検査を早めに受けてください。

クローン病診断基準にかかわる主な項目
| 検査・項目 | 概要 | クローン病での特徴 |
|---|---|---|
| 血液検査 | 貧血、CRP上昇、白血球増加など | 慢性炎症による指標異常が多い |
| 便中カルプロテクチン | 腸内での炎症レベルを反映 | 高値を示す傾向 |
| 画像検査(CT・MRI) | 腸管の狭窄や腫脹、リンパ節腫大の確認 | 狭窄、腸管肥厚、周辺組織の炎症所見 |
| 内視鏡検査 | 直接粘膜を観察し、生検も行える | 散在性潰瘍や敷石像、肛門病変などが典型 |
| 病理組織学的検査 | 粘膜や腸壁の細胞レベルの状態を確認 | 肉芽腫形成や深い層への浸潤が示唆される場合がある |
診断にはこうした複数のアプローチを組み合わせて、クローン病かどうかの判断を進めます。
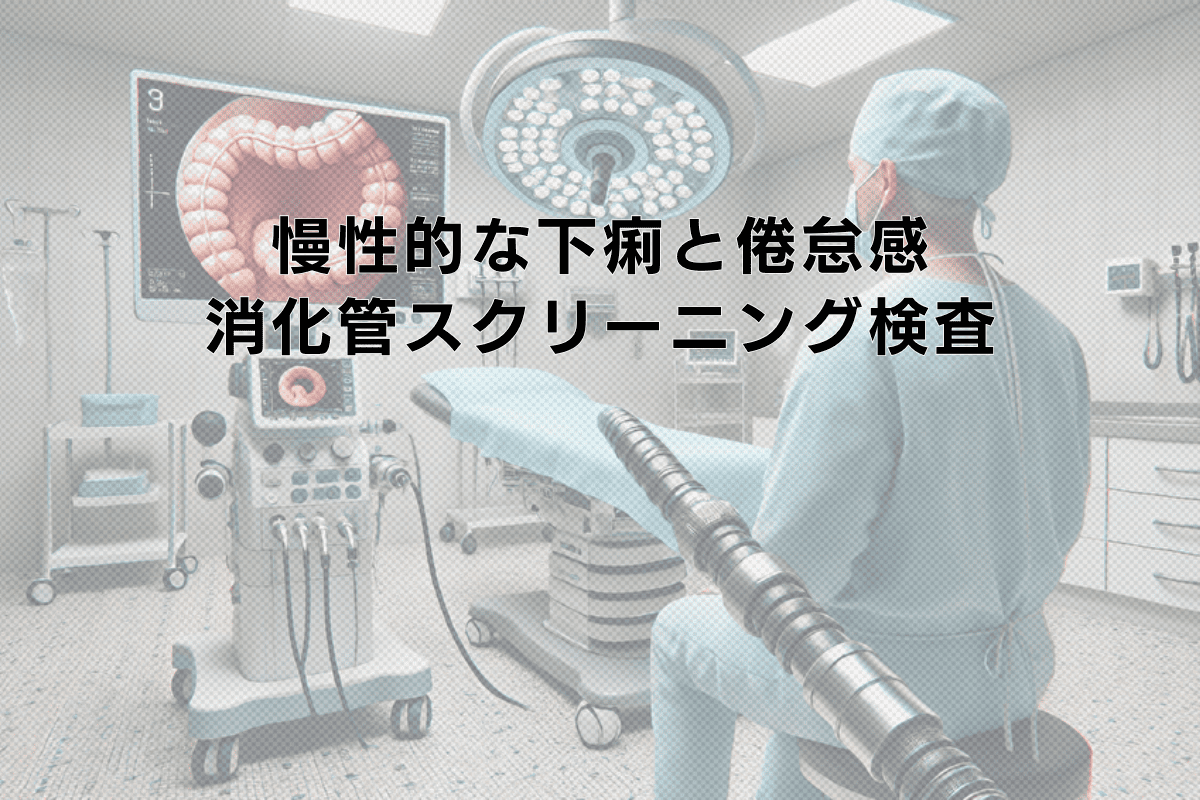
クローン病における内視鏡所見
クローン病の内視鏡所見は診断や経過観察の上で大きな役割を担います。大腸カメラや小腸内視鏡(カプセル内視鏡など)によって腸内の様子を直視することで、病変の広がりや深さを詳しく把握できます。
内視鏡で確認されやすい病変
クローン病の代表的な内視鏡所見には「敷石像(しきいしぞう)」と呼ばれる特徴的なものがあります。これは潰瘍が縦走する形で腸管表面に走り、間に隆起した粘膜が残るため、まるで敷石を敷き詰めたように見える状態を指します。
また、離在性(飛び飛び)の病変もクローン病特有の特徴で、正常粘膜と病変部が交互に現れやすい点が重要です。
大腸カメラでの所見
大腸カメラを挿入して大腸全域を観察することで、下行結腸やS状結腸などにおける潰瘍や狭窄の有無、炎症の程度を直接評価できます。
肛門から近い直腸や肛門周囲にも病変が及ぶ可能性があるので、内視鏡で観察しながら炎症の広がり方や深さを確認し、必要があれば生検を行うことで詳細を調べます。

小腸内視鏡(カプセル内視鏡など)の役割
クローン病は小腸に炎症が起こりやすい点が大きな特徴であるものの、大腸カメラだけでは小腸の全域を把握することはできません。
カプセル内視鏡などを用いると小腸をより詳細に観察でき、特に回腸末端(回盲部付近)に多い病変を把握しやすくなります。潰瘍がどの程度小腸内に及んでいるのかを知ることは、治療方針を決めるうえでも重要な情報です。
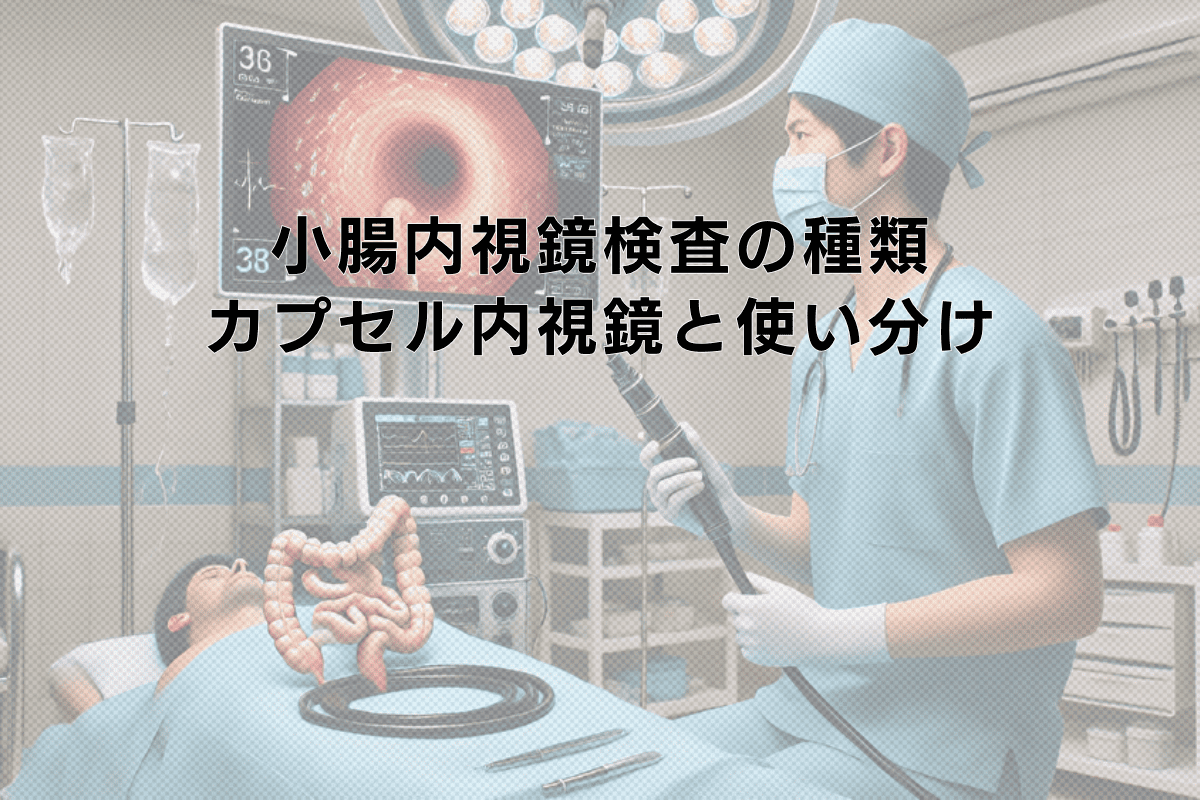
病変の進行度合いと観察ポイント
病変がどの程度進んでいるかを知るためには、内視鏡による定期的なフォローアップが必要です。炎症が強まると潰瘍が大きくなり、腸の狭窄や穿孔、瘻孔形成などのリスクが高まります。
再燃と寛解を繰り返すことが多いため、医師は炎症の有無を観察しつつ治療薬の効果や副作用を総合的に判断し、治療の修正や追加を検討します。
内視鏡所見
| 所見名 | 特徴 | クローン病における意義 |
|---|---|---|
| 敷石像 | 潰瘍が縦走し、間に浮腫状の粘膜が残った状態 | クローン病特有の特徴 |
| 縦走潰瘍 | 縦方向の深い潰瘍で、出血や狭窄を起こしやすい | 病変の深さ・重症度を推測する手がかり |
| 不連続性病変 | 正常粘膜と潰瘍部が交互に出現 | 離在性病変の典型例 |
| 肛門病変 | 痔瘻や肛門周囲潰瘍など | 肛門症状を訴える場合に重要 |
| 生検所見 | 肉芽腫形成や深層への炎症浸潤 | 正確な病理診断の決め手になる |
内視鏡検査はクローン病の確定診断だけでなく、病状や治療効果を把握するためにも欠かせない手段です。
治療方針の決定に役立つ内視鏡検査
クローン病の治療方針は症状の重症度や炎症の広がり、合併症の有無などを総合的に判断したうえで決定します。その中でも内視鏡検査の結果は非常に大きなウエイトを占めます。
早期診断と治療開始の意義
クローン病は放置すると炎症が腸壁全体に及び、狭窄や瘻孔などの深刻な合併症を引き起こしやすくなります。
内視鏡検査によって初期段階で病変を確認できれば、薬物療法や栄養療法を早めに開始し長期的な予後が改善する可能性があります。
炎症コントロールと再発防止
内視鏡を用いた観察で腸内の炎症がどの程度治まっているかを調べられます。症状だけを頼りに治療効果を判断すると、見かけ上は落ち着いているように見えても粘膜の奥では炎症が続いている場合があります。
内視鏡で粘膜治癒が確認できる状態まで管理することで、再発リスクを低減できることが期待されます。
生検でわかること
内視鏡検査で必要に応じて行う生検は、組織のレベルで炎症や肉芽腫の有無などを確認する有用な方法で、クローン病なのか、他の疾患なのか、あるいは併発している疾患があるのかを見極めるうえで役立ちます。
炎症の深さや細胞の変異がないかなどを確かめることで、より正確な治療方針の立案が可能です。
検査間隔とフォローアップ
クローン病は寛解期と再燃期を繰り返すケースが多いため、定期的な内視鏡検査で腸粘膜の状態を評価し、治療内容を調整することが望ましいです。
患者さんの症状や炎症状態、治療反応度を見ながら検査の頻度を決めます。過剰な検査は患者さんの負担になりますが、適度な間隔でフォローアップすることが重要です。
内視鏡検査と治療方針の関係
| 観察ポイント | 意義 | 治療方針への活かし方 |
|---|---|---|
| 炎症の広がり | 病変の範囲や重症度を把握できる | 全身投与薬の選択、栄養療法の検討 |
| 潰瘍の深さや数 | 重症度評価に直結し、狭窄・穿孔リスクの推定が可能 | ステロイドや免疫調整薬の導入タイミング判断 |
| 病変の局在 | 小腸メインか大腸メインかで治療薬の選択が変わる | 5-ASA製剤、抗TNF-α抗体製剤など適切な薬物を選択 |
| 生検所見 | 組織レベルでの炎症、肉芽腫、細胞異型の有無を評価 | クローン病なのか別の疾患なのかを確定させる材料に |
| 合併症の有無 | 痔瘻や瘻孔、穿孔、狭窄の発見 | 外科治療が必要かどうかの判断に直結 |
内視鏡検査は病態を把握するための有効な手段となり、治療方針決定の要になります。
具体的な治療アプローチ
クローン病の治療は、薬物療法、食事や栄養管理、外科的治療などが複合的に用いられ、内視鏡検査によって得られた情報をもとに、治療方法を選びます。
薬物療法の概要
炎症を抑え、再燃を防ぐために用いられる薬剤には多様な選択肢があり、症状や炎症の程度によって、医師はステロイドや免疫調整薬、5-ASA製剤、抗TNF-α抗体などを使い分けます。
炎症のコントロールが主目的ですが、副作用の監視も欠かせません。定期的な血液検査や内視鏡検査によって、薬の効果や安全性を確認することが大切です。
食事療法と栄養管理
クローン病は消化管の病変が深刻化すると、栄養吸収が十分に行えなくなる可能性があり、エネルギー不足やミネラル・ビタミンの欠乏が起こると、体力の低下や合併症リスクが高まります。
そのため、消化管の負担を減らしつつ必要な栄養素をバランスよく摂取する食事療法や、経腸栄養法などを取り入れることがあります。
クローン病治療で考慮する主な薬剤
| 薬剤群 | 代表的な薬剤 | 主な目的 | 副作用例 |
|---|---|---|---|
| アミノサリチル酸製剤 | メサラジン製剤など | 軽度~中等度の炎症抑制 | 胃腸障害、頭痛など |
| ステロイド | プレドニゾロンなど | 強い炎症抑制 | 骨粗鬆症、血糖上昇など |
| 免疫調整薬 | アザチオプリン、6-MPなど | 免疫系の制御 | 骨髄抑制、肝機能障害など |
| 生物学的製剤 | 抗TNF-α抗体製剤など | 強力な炎症抑制 | 感染症リスク増加、注射部位反応 |
| 抗菌薬 | メトロニダゾールなど | 肛門周囲病変や感染対策 | 消化器症状、味覚異常など |
症状や病変部位、重症度などに合わせて選択・組み合わせることが多いです。
外科的治療が必要な場合
薬物療法では炎症のコントロールが難しいケースや、重度の狭窄や瘻孔がある場合は外科的治療を検討することがあり、手術で狭窄部位や瘻孔を切除・改善することで症状の軽減を狙います。
ただし、クローン病は再発の可能性があるため、術後も定期的な検査と薬物療法の継続が重要です。
チーム医療の重要性
クローン病は消化器だけではなく、全身の栄養状態や精神面にも影響を及ぼすため、医師だけでなく、看護師、管理栄養士、薬剤師、臨床心理士など多職種の連携が不可欠です。
患者さんと医療者が共に目標を設定し、治療の効果を評価しながら長期的にサポートを続けることで、QOL(生活の質)の向上が期待できます。
日常生活の注意点とサポート体制
クローン病において治療だけでなく、日常生活での工夫が症状コントロールに大きく寄与し、食事や生活習慣、メンタル面など、多面的なケアが必要です。
症状の自己管理ポイント
クローン病は個人差が大きいため、自分自身の症状を客観的に把握することが大切で、排便回数、便の性状、食事内容、腹痛の強さなどを日記のような形で記録すると、病状変化を早期に捉えやすいです。
日常生活を見直すためのポイント
- 排便回数や便の状態を記録し、異変を早めに察知する
- 定期的に体重や体調の変化をチェックする
- 水分・栄養補給をこまめに行い、脱水や栄養不足を防ぐ
- 腸に負担をかけにくい調理法や食材を選択する
- 激しい運動や長時間の労働を控える工夫を考える
このように工夫すると、自分の状態に合わせた調整が可能になります。
ストレス対策とメンタルヘルス
クローン病はストレスによって症状が増悪することがあり、精神的ストレスが慢性的な腹痛や疲労感を助長することがあります。睡眠や趣味の時間を確保し、リラクゼーション法を活用するなどのストレス対策が役立ちます。
また、必要に応じてカウンセリングなどを利用し、心理面のサポートを得ることが重要です。
定期的な受診と検査の継続
クローン病は再燃と寛解を繰り返すことが多いため、症状が落ち着いているからといって受診を中断すると、次の再燃で病変が急速に進む可能性があります。
定期的な診察と内視鏡検査を続けることで、炎症の兆候を早期にキャッチし、薬物療法や食事療法を調整できます。
クローン病患者の日常サポートに関わる職種
| 職種 | 役割・支援内容 | 連携のメリット |
|---|---|---|
| 消化器内科医 | 診断、治療方針の策定、内視鏡検査の実施 | 専門的視点で病態を評価し、治療を最適化 |
| 管理栄養士 | 栄養指導、食事内容の提案 | 消化器への負担を軽減し栄養状態を改善 |
| 看護師 | 日常的なケアや生活指導、患者の相談対応 | 患者の不安を軽減し、自己管理をサポート |
| 薬剤師 | 処方薬の管理、副作用モニタリング | 薬物治療の効果とリスクを適切に調整 |
| 臨床心理士 | 心理面のカウンセリング、ストレス対処のアドバイス | 精神的負担の軽減により症状悪化を予防 |
医療機関や専門家との連携
クローン病の診療経験が豊富な医療機関は、内視鏡検査や薬物療法のスムーズな実施だけでなく、合併症が疑われる場合の迅速な検査や専門医への紹介など、包括的な対応が行いやすいです。
大きな病院や専門クリニックだけでなく、普段からかかりつけの診療所とも情報共有をしながら、長期的なフォローを続けます。
まとめ
クローン病は、小腸から大腸、さらには口腔や肛門周囲まで、あらゆる消化管部位に慢性炎症や潰瘍を生じる可能性がある難治性疾患です。
クローン病診断基準を満たすかどうかの判断には、問診や血液検査、画像検査など多角的な視点が必要ですが、とりわけ内視鏡検査で観察する「敷石像」「不連続性の潰瘍」といった特徴的な所見は決定的な役割を果たします。
内視鏡所見を踏まえた的確な診断により、治療の方向性が定まり、炎症をコントロールしながら生活の質を守っていく道筋が見えてきます。
治療には薬物療法、食事療法、外科的処置などがあり、いずれも患者さんの状態や炎症の程度に合わせて選択されます。
クローン病は寛解と再燃を繰り返しやすいため、内視鏡による定期的な評価が、再燃予防や合併症の早期発見につながる点を忘れないでください。
長期にわたる病気との付き合いは簡単ではありませんが、消化器内科医や管理栄養士、看護師など専門家との連携で、安定した寛解状態を目指せます。
次に読むことをお勧めする記事
【潰瘍性大腸炎とは|症状と内視鏡検査による診断】
クローン病について読んで、「潰瘍性大腸炎との違いは何だろう?」と思った方もいらっしゃるのでは?同じ炎症性腸疾患でありながら、症状や病変の特徴に違いがある両疾患の鑑別ポイントをご紹介しています。
【小腸内視鏡検査の種類と特徴|カプセル内視鏡との使い分け】
クローン病は小腸にも炎症が及びやすい疾患です。カプセル内視鏡とバルーン内視鏡の特徴を知っておくと、検査選択の幅が広がります。
参考文献
Chen M, Shen B. Endoscopic therapy in Crohn’s disease: principle, preparation, and technique. Inflammatory Bowel Diseases. 2015 Sep 1;21(9):2222-40.
Sulz MC, Burri E, Michetti P, Rogler G, Peyrin-Biroulet L, Seibold F. Treatment algorithms for Crohn’s disease. Digestion. 2020 Sep 29;101(Suppl. 1):43-57.
Chiarello MM, Pepe G, Fico V, Bianchi V, Tropeano G, Altieri G, Brisinda G. Therapeutic strategies in Crohn’s disease in an emergency surgical setting. World Journal of Gastroenterology. 2022 May 14;28(18):1902.
Srinivasan AR. Treat to target in Crohn’s disease: a practical guide for clinicians. World Journal of Gastroenterology. 2024 Jan 7;30(1):50.
Veauthier B, Hornecker JR. Crohn’s disease: diagnosis and management. American family physician. 2018 Dec 1;98(11):661-9.
Baumgart DC. The diagnosis and treatment of Crohn’s disease and ulcerative colitis. Deutsches Ärzteblatt International. 2009 Feb 20;106(8):123.
Gergely M, Deepak P. Tools for the Diagnosis and Management of Crohn’s Disease. Gastroenterology Clinics. 2022 Jun 1;51(2):213-39.
Sauter B, Beglinger C, Girardin M, Macpherson A, Michetti P, Schoepfer A, Seibold F, Vavricka SR, Rogler G, IBD Ahead Swiss National Steering Committee. Monitoring disease activity and progression in Crohn’s disease. A Swiss perspective on the IBD ahead ‘optimised monitoring’recommendations. Digestion. 2014 Aug 1;89(4):299-309.
Deepak P, Park SH, Ehman EC, Hansel SL, Fidler JL, Bruining DH, Fletcher JG. Crohn’s disease diagnosis, treatment approach, and management paradigm: what the radiologist needs to know. Abdominal Radiology. 2017 Apr;42:1068-86.
Benitez JM, Meuwis MA, Reenaers C, Van Kemseke C, Meunier P, Louis E. Role of endoscopy, cross-sectional imaging and biomarkers in Crohn’s disease monitoring. Gut. 2013 Dec 1;62(12):1806-16.