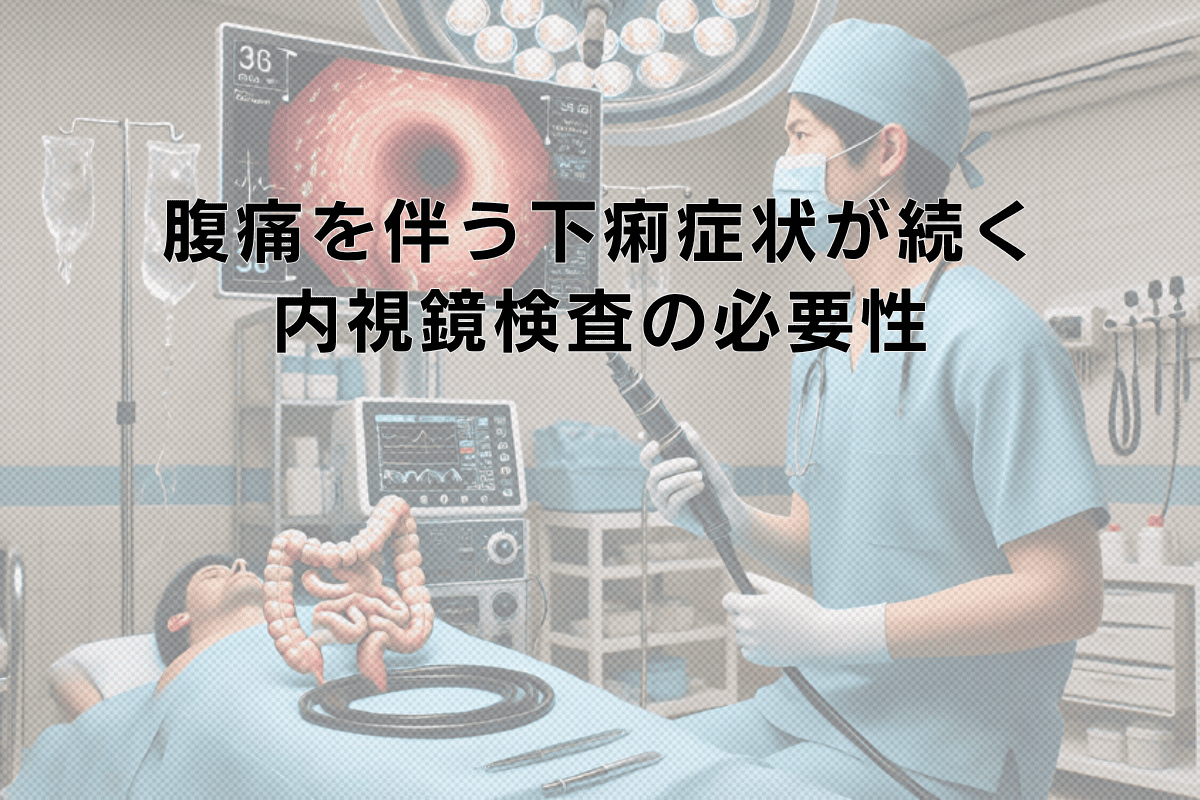腹痛と下痢が重なってしばらく続くと、不快感や体力の低下だけでなく、重大な病気の可能性が心配になります。
短期間で治まるのであれば様子をうかがう方もいるかもしれませんが、繰り返し起こる場合や慢性化している場合には慎重な判断が大切です。
原因を早めに把握し、内視鏡検査など専門的なチェックを受けることで、病気を見逃さずに治療へとつなげやすくなります。
この記事では、腹痛を伴う下痢症状が長引く背景や考えられる疾患、内視鏡検査を受ける意義などについて、詳しく解説いたします。
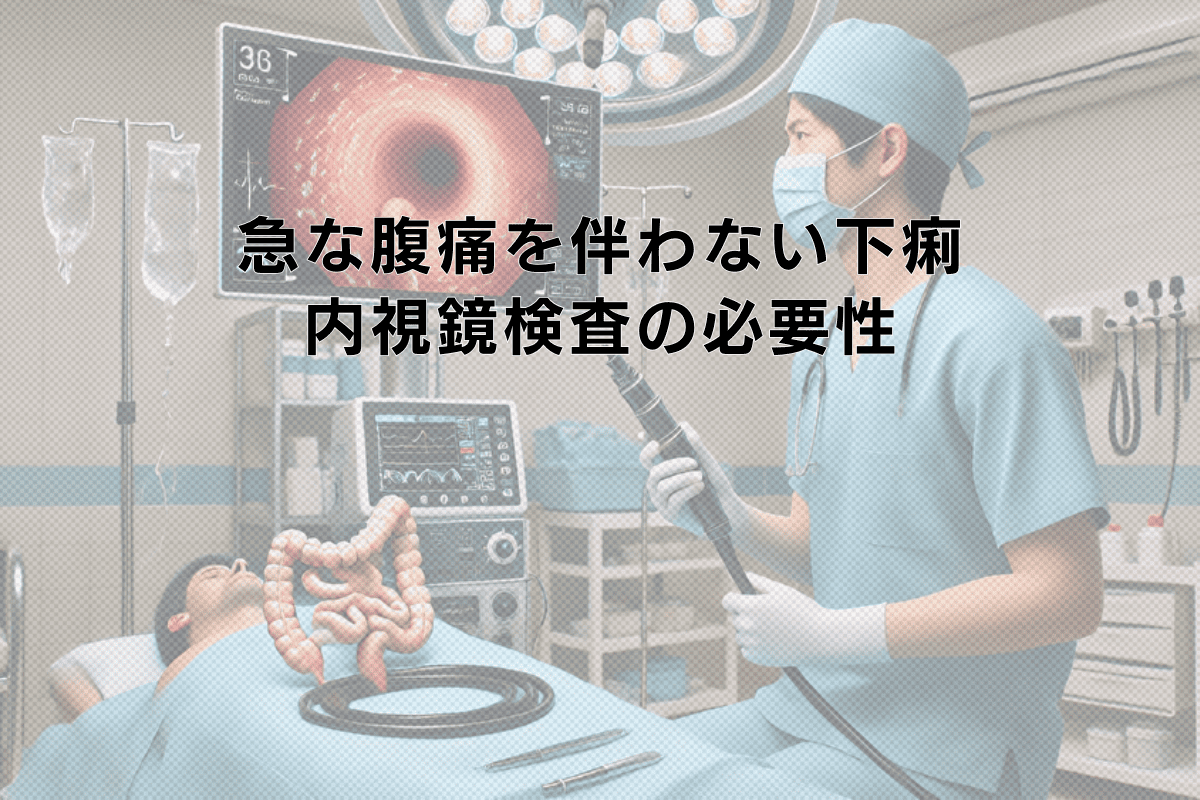
腹痛と下痢症状が続く背景
腹痛と下痢が組み合わさった状態が続くと、日常生活に支障をきたし、仕事や家事をするにも集中が難しくなり、体重減少や倦怠感を伴う場合もあります。こうした悩みを放置すると病気の進行リスクが高まります。
ここでは、腹痛と下痢が長引く背景に関して見ていきましょう。
腸内環境の乱れによる悪影響
腸内環境が乱れると消化機能がスムーズに働かなくなり、腹部の痛みとともに便がゆるくなるケースが多いです。特定の菌が増えすぎることや、ストレス・食生活の偏りなどが影響して腸粘膜に刺激を与えます。
腸内細菌のバランスが崩れると、有害物質の産生が増え、炎症を引き起こすことがあります。

ストレスによる自律神経への影響
精神的なストレスが続くと、自律神経のバランスが崩れ、腸のぜん動運動が不安定になり、過剰に動くと下痢や腹痛が起こりやすく、逆に動きが鈍くなると便秘になりやすいです。
ストレス性の腹痛は原因がはっきりしないこともあり、気づかぬうちに慢性化するケースもあります。
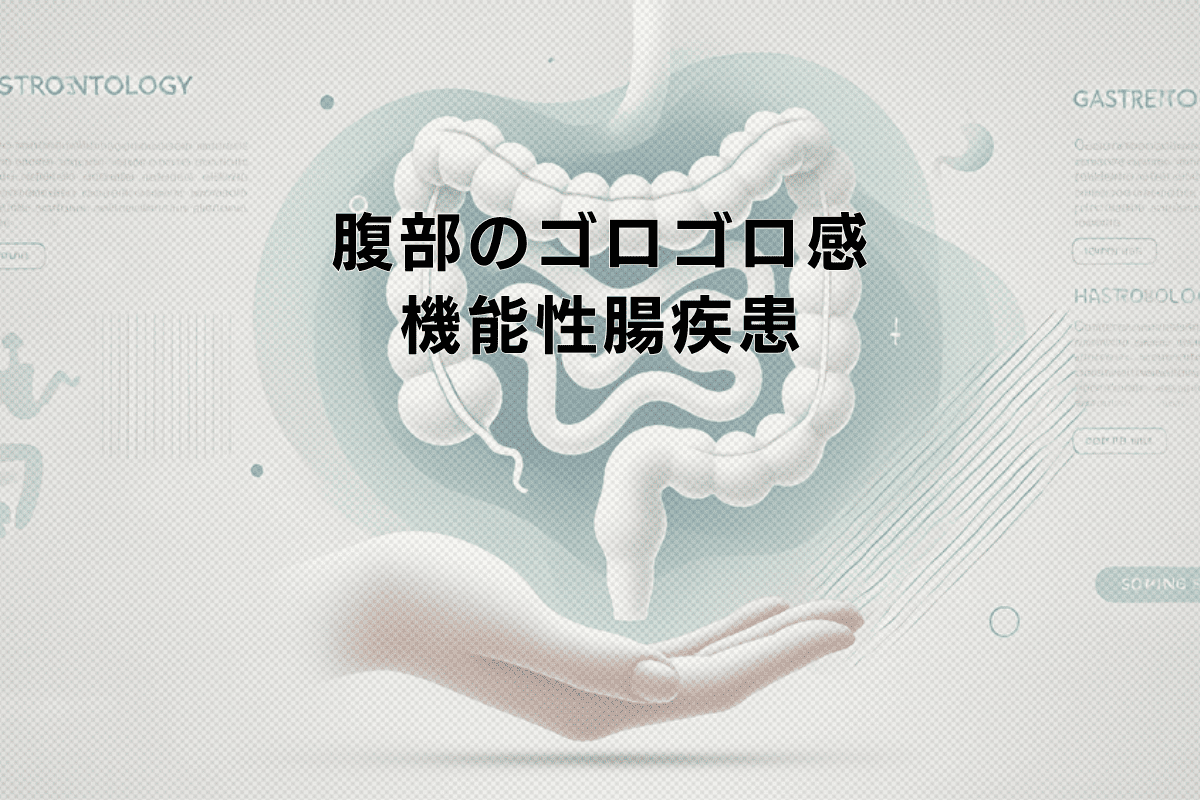
食習慣や食事内容が与える影響
高脂肪食や刺激の強い香辛料を含む食事が続くと、腸への負担が大きくなり、アルコールやカフェインの摂取も腸粘膜に刺激を与え、腹痛と下痢を助長します。さらに、野菜や果物をあまり摂らない食事や、不規則な食事時間も悪影響を及ぼします。
不安感や恐怖心から来る受診の遅れ
おなかの痛みと下痢の組み合わせに対して、「少し休めば良くなるだろう」と自己判断する人もいます。
検査自体への不安や内視鏡検査が苦痛に感じられるという先入観があり受診が後回しになると、病状が進み治療期間が長引いてしまう懸念があります。
腹痛が続く背景
| 背景要因 | 具体的な影響 | 結果 |
|---|---|---|
| 腸内環境の乱れ | 悪玉菌の増加、腸粘膜への刺激 | 慢性的な下痢と腹痛 |
| ストレスによる自律神経 | 腸のぜん動運動の過剰・低下 | 下痢・便秘の反復 |
| 食習慣の乱れ | 高脂肪食や刺激物による腸負担 | 腹部不快感の増大 |
| 受診への不安 | 早期検査を避けて放置 | 病気の進行と治療期間の延長 |
持続的な腹痛と下痢には複数の要因が複雑に絡み合い、特に、ストレスや生活習慣の変化がきっかけになる方は少なくありません。
日常生活で意識したい点
- 辛いものや脂っこい食事の量を控える
- 規則正しい生活リズムを心がける
- 不安や悩みを気軽に相談できる環境を整える
- 胃腸の調子を見ながら軽い運動を行う
腹痛と下痢に悩んだ場合、病院やクリニックを早めに受診し、必要に応じて内視鏡検査を検討することが大切です。
考えられる主な疾患の種類
おなかの痛みと下痢症状が続いた場合、さまざまな疾患が考えられ、症状が軽度であっても、自己判断で放置するより専門的な診察と検査を受けるほうが早期発見につながりやすいです。どのような病気が想定されるのか、主なものを紹介します。
過敏性腸症候群(IBS)
強いストレスや生活リズムの乱れ、あるいは食事の影響によって腸が過敏になり、下痢と便秘を繰り返す病気です。炎症など明確な異常が見られなくても症状が続き、仕事や日常生活に大きな支障をきたすことがあります。
特に若年層から中年層に多く見られますが、あらゆる年代で起こり得ます。
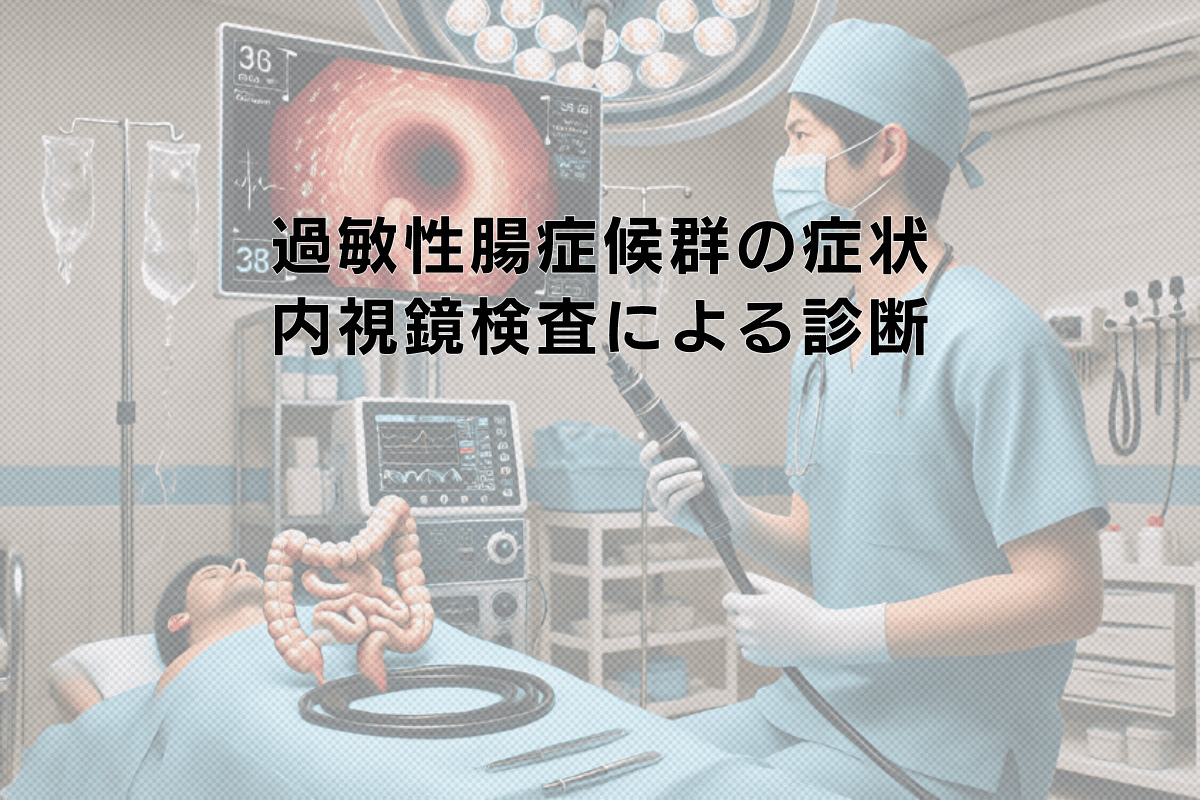
潰瘍性大腸炎
大腸の粘膜に慢性的な炎症やびらん、潰瘍を生じる疾患で、腹痛や下痢とともに血便が出ることも特徴です。原因は明確に解明されていませんが、免疫機能の異常や遺伝的要因が関与していると考えられています。
放置すると大腸の広い範囲に炎症が広がり、大腸がんなどの合併症が生じやすくなるので注意が必要です。

クローン病
口から肛門までの消化管のどの部分にも炎症や潰瘍を引き起こす可能性がある疾患で、潰瘍性大腸炎と同じく炎症性腸疾患に分類されます。下痢と腹痛が長期にわたって続くことが多く、狭窄や瘻孔といった合併症を招きやすい特徴があります。
早期に内視鏡検査で状態を把握することが重要です。
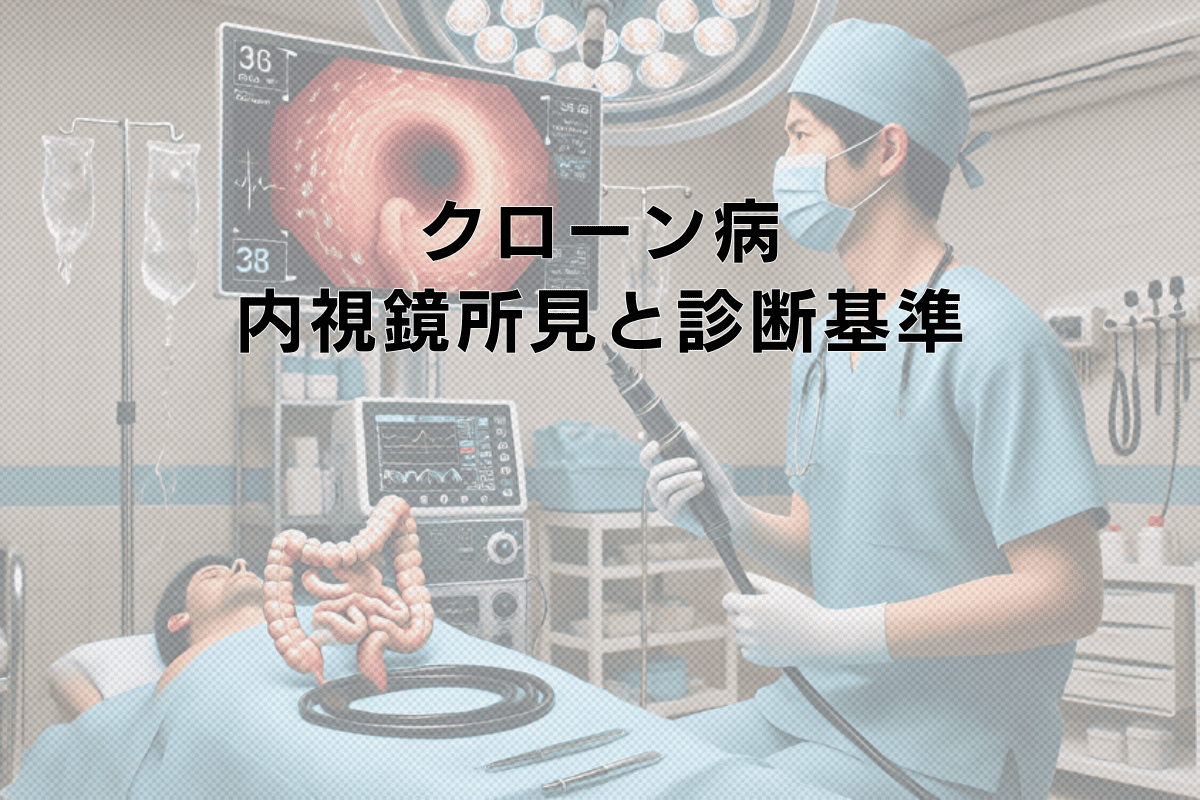
大腸がん
初期には無症状のことが多いものの、腸がんが進むと下痢や便秘が交互に起こったり、血便、腹痛などが現れる場合があります。40代以降でリスクが高まるといわれており、大腸内視鏡検査による早期発見が治療のカギを握ります。
腹痛と下痢が長期的に続く場合は、予防的な意味合いでも検査を受けることがおすすめです。

疾患の特徴
| 疾患名 | 主な症状 | 罹患部位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 過敏性腸症候群 | 腹痛、下痢や便秘の反復 | 大腸機能 | 炎症や潰瘍は認められにくい |
| 潰瘍性大腸炎 | 血便、腹痛、下痢 | 大腸粘膜 | 慢性的に炎症が広がる |
| クローン病 | 長期化する下痢、腹痛、体重減少 | 消化管全域 | 狭窄や瘻孔が発生しやすい |
| 大腸がん | 下痢と便秘の交互、血便、腹部不快 | 大腸(結腸・直腸) | 初期に症状が乏しいことあり |
疾患ごとに特徴的な症状があるものの、専門家でないと判断が難しい場合も多く、放置していると慢性化や合併症が進行するリスクが高まるため、疑いがある場合は早期の検査が望ましいです。
早めに病院で相談したい理由
- 放置すると炎症が広範囲に進む可能性がある
- 合併症を起こすリスクが増す
- 治療期間が長期化する傾向が強まる
- 大腸がんなど重篤な病気を見逃す恐れ
腹痛を伴う下痢が長引くときには、これらの疾患の可能性も念頭に置きながら、医療機関で相談することが大切です。
診察から内視鏡検査に至る流れ
内視鏡検査は決して痛みや苦痛ばかりではなく、正確な診断のために非常に有効な手段ですので、腹痛と下痢の状態が長期化している場合は原因特定の近道となることも多いです。
どのように診察を受けて内視鏡検査へ進むか、一般的な流れを確認しておきましょう。
初診でのヒアリング
まずは医師が問診を行い、症状の出方や継続期間、食生活、ストレス状況などを細かく聞き取ります。腹痛の位置や痛みの強さ、便の頻度や性状などを伝えると、診察の精度が上がります。
血液検査や画像検査
問診で得られた情報に基づき、血液検査や超音波検査、CT検査などを実施し、炎症や腫瘍、血液の異常などを確認します。血液検査では、炎症の程度を示すCRP値や貧血の有無などを調べます。
必要に応じた大腸カメラ・胃カメラ
腹痛や下痢の原因が大腸にあるか、あるいは上部消化管にも問題があるかを判定するために、内視鏡検査を行うことがあり、直視で粘膜の状態を確かめるため、ポリープや潰瘍などの異常を直接確認できます。
必要に応じて組織を一部採取し、病理検査を行います。
診断結果から治療方針の決定
検査結果を踏まえて、薬物療法や生活指導、手術が必要な場合など具体的な治療計画を決定します。また、内視鏡検査で小さいポリープが見つかった場合、その場で切除できることもあります。
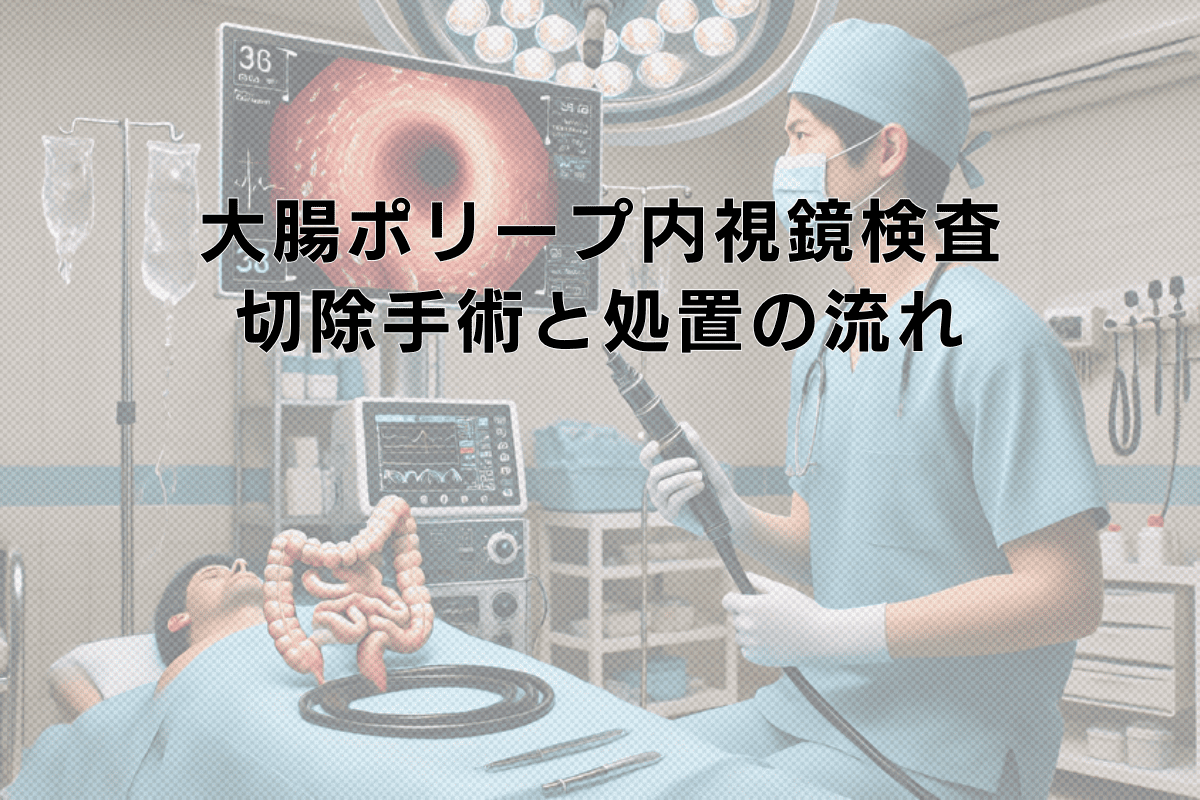
診察から検査までの流れ
| 段階 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 初診・問診 | 症状や生活背景のヒアリング | 痛みの程度、下痢回数などを伝える |
| 血液・画像検査 | 血液検査、エコー、CT検査 | 炎症や腫瘍の可能性を探る |
| 内視鏡検査の実施 | 大腸カメラ・胃カメラ | 直接粘膜を確認し必要なら組織採取 |
| 治療方針の決定 | 薬剤、手術、生活改善など | 検査結果を踏まえた総合的判断 |
診察から検査に至るまで、一連の流れを事前に理解しておくと安心して受診しやすくなります。
より正確な診察につなげるために
- 痛みの様子や便の状態を日記形式で記録する
- 食事内容や摂取時間をメモする
- 生活上の大きな変化(転職、引っ越し、ストレスなど)を把握する
- 過去に内視鏡検査を受けたことがある場合は医師に伝える
こうした情報を準備すると、医師とのコミュニケーションがスムーズになります。
内視鏡検査のメリットと注意点
腹痛を伴う下痢症状が続く場合、内視鏡検査を行うことで実際の腸内の状態を目視で確認できます。粘膜のわずかな異常も見落としにくく、ポリープや炎症の部位などを正確に把握するのに非常に有用です。
リアルタイムでの観察が可能
内視鏡を挿入することで、消化管の粘膜をリアルタイムに観察でき、特殊なカメラとライトが付いたチューブを使い、疑わしい部分があれば拡大してチェックします。
潰瘍や出血点、ポリープの大きさや形状、炎症の広がりを細かく確認でき、必要があれば当日中に切除や組織採取も行いやすいです。
自覚症状があいまいな疾患に対応
おなかの痛みと下痢が続いていても、血液検査や画像検査だけではわかりづらい場合があり、小さな潰瘍や粘膜下のできもの、早期がんなどは、目視で見なければ判断が難しいこともあります。
内視鏡によって病変部位を直接見つけられるため、診断漏れを抑えられることが利点です。
前処置と検査中の不快感
大腸カメラの場合、検査前日に下剤を服用して腸を空っぽにする準備が必要です。検査中にも多少の違和感やおなかの張りを感じることがありますが、検査時間が短縮されるよう工夫して行う場合もあります。
最近は鎮静剤を用いる方法が広く普及しており、検査中の苦痛を軽減できる傾向にあります。

合併症のリスク
まれに腸壁に傷がついたり、穿孔などの合併症が起こる可能性があります。
リスクは低いものの、内視鏡の操作中に腸が弱っている部分がある場合は注意が必要で、検査を受ける前にメリットやデメリットを医師と相談すると安心です。
内視鏡検査の特長と注意点
| 項目 | ポイント | 備考 |
|---|---|---|
| 観察精度 | 高い解像度での目視確認 | 早期病変も発見しやすい |
| 検査中の処置 | ポリープ切除や組織採取 | 即日対応が可能 |
| 前処置の必要性 | 下剤の服用などで腸を洗浄 | 大腸カメラの場合 |
| リスク | 穿孔や出血の可能性 | 発生率は低め |
| 検査時の痛み・不快感 | 鎮静剤で軽減しやすい | 苦痛の度合いは個人差あり |
細かなリスクや前処置の負担はありますが、それを上回る診断精度の高さが大きなメリットです。
内視鏡検査を受けるときの心構え
- 検査前に不安な点を医師や看護師に質問する
- できるだけリラックスできる環境を意識する
- 鎮静剤の有無など事前に検査方法を確認する
- 持病がある場合や服用薬は必ず医師に伝える
こうした準備をしておくと、安心して検査を受けやすくなります。
食事や生活習慣との関係
腹痛と下痢が長引く背景には、食事や生活習慣の問題が深く関わります。バランスの崩れた食事や極端なダイエット、不規則な生活リズムが腸を弱らせてしまうことも多く、検査と治療が必要になる前に、日々の生活を見直すことが重要です。
高脂肪食・刺激物の過剰摂取
過度な油分や辛味成分を含む食事を頻繁にとると、胃腸への負担が増して炎症を促す可能性が高まります。アルコールやカフェイン入り飲料を大量に摂る習慣があると、粘膜が刺激され下痢と腹痛が悪化しやすいです。
食物繊維の不足と腸内細菌
食物繊維の少ない食生活は、腸内の善玉菌を減らし、悪玉菌が優位になる状況をつくります。そうなると、腸粘膜が傷つきやすくなったり、有害物質が増えやすくなります。便の状態や腸の蠕動運動にも影響するため、適度な食物繊維が重要です。
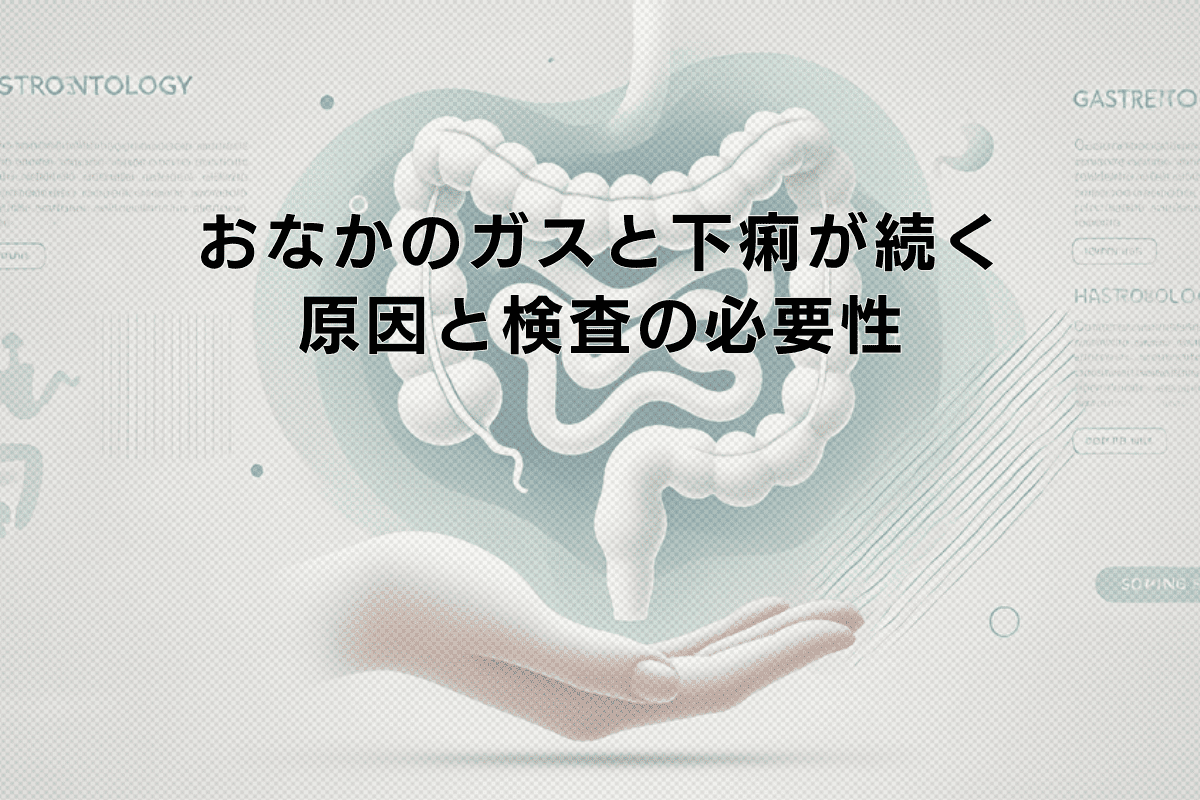
水分摂取と脱水リスク
下痢が続くと体内の水分が失われやすいため、水分補給が追いつかないと脱水状態になるおそれがあります。適切な水分摂取は腸内の内容物を柔らかくし、便通を整える意味でも重要です。
ストレス解消と睡眠リズム
ストレスを溜め込むと自律神経が乱れ、腸機能がアンバランスになりやすく、睡眠不足や深夜までの作業も腸へのダメージを高める一因です。腹痛と下痢を繰り返している人は、十分な休養とリラックス方法の確立を心がけましょう。
腹痛と下痢を悪化させやすい要因
| 要因 | 対応策 | 注意点 |
|---|---|---|
| 高脂肪・刺激物 | 油分や刺激物の摂取を減らす | 急激な制限はストレスになる恐れ |
| 食物繊維不足 | 野菜や果物、穀物を積極的に摂取 | 摂り過ぎると逆におなかが張る |
| 水分不足 | 適度に水分を補給する | 冷たい飲み物の一気飲みに注意 |
| ストレス・睡眠不足 | ストレッチや趣味でのリラックス | 睡眠時間と就寝タイミングを安定させる |
必要な栄養と十分な水分を取りながら、無理のない範囲で生活を整えることで、腸への負担が軽減しやすくなります。
毎日の生活で工夫できること
- 朝食を抜かずにバランスの良い食事を摂る
- こまめに水を飲み、アルコールやカフェインは控えめにする
- 睡眠時間を確保し、就寝前のスマホやパソコン使用を控える
- 適度な有酸素運動で血行を促進する
こうした地道な取り組みが、腹痛と下痢の症状を緩和する助けになることがあります。
クリニックで行う検査の流れ
内視鏡検査を受けるクリニックでは、専門医が問診からフォローアップまで対応します。腹痛を伴う下痢の症状が続くときは原因を特定するため、必要な検査を組み合わせるケースも少なくありません。
どのような流れで検査が実施されるか把握しておきましょう。
受付・カウンセリング
まず受付を済ませ、問診票に必要事項を記入し、その後、医師や看護師とカウンセリングを行い、症状やこれまでの経緯、食生活や持病などを詳細に伝えます。
不安や疑問点があれば早めに相談しておくと、検査当日に落ち着いて臨めます。
血液検査や尿検査
腹痛と下痢の原因を探るため、基本的な血液検査や尿検査を行うことがあり、身体全体の状態を把握し、炎症や感染症の有無を確認します。CRPや白血球数、貧血の有無などを総合的に判断して内視鏡検査の必要性を見極めます。
大腸内視鏡検査の準備
大腸カメラを実施する場合は、検査前日の食事制限や当日朝の下剤服用などが必要です。腸内をできるだけきれいにすることで、ポリープや炎症を見逃さずに確認でき、少々手間はかかりますが、正確な診断には欠かせません。

内視鏡検査と医師からの説明
鎮静剤を用いるかどうかを決め、内視鏡検査を行います。検査終了後、医師から検査結果の概要や治療方針について説明を受けます。もし異常が見つかった場合でも、早期に対応できることが多いため、安心して医師の指示を仰ぎましょう。
クリニックでの検査手順
| 手順 | 内容 | 主な目的 |
|---|---|---|
| 受付・カウンセリング | 問診票記入・症状のヒアリング | 不安や疑問点の共有 |
| 血液・尿検査 | 炎症・感染症・貧血などの確認 | 全身状態を把握し内視鏡検査の可否判断 |
| 内視鏡検査準備 | 下剤の服用、食事制限 | 腸内を清潔にし検査精度を上げる |
| 検査実施と説明 | カメラ挿入・鎮静剤の使用 | 異常部位を直接確認し、治療方針を決定 |
流れを理解しておけば、当日の心構えも整いやすくなります。時間に余裕を持ってクリニックへ行き、スタッフの指示を丁寧に守ることが大切です。
受診の際に持って行くと良いもの
- 過去に受けた検査結果や紹介状
- 普段飲んでいる薬のリストや薬手帳
- 下痢の頻度や便の状態を記録したメモ
- 保険証や医療証、身分証明書
検査後に体調がすぐれないときのために、できれば付き添いの方がいると心強いです。
迷わず早めに受診する重要性
腹痛に伴って下痢が続く状態は、体力や気力が奪われるだけでなく、思わぬ重篤な病気が潜んでいる可能性も否定できません。痛みや不調を抱えたまま我慢するより、早めに受診して原因を突き止めるほうが負担は軽減されます。
放置によるリスク
自己判断で「そのうち治る」と見過ごしていると、病気が進行し治療期間が長期化する恐れがあります。大腸がんなどの場合、初期症状がわかりにくいため、痛みや下痢が出始めた段階で既に病気が進んでいるケースもあります。
少しでも気になる症状があれば医療機関に相談したほうが安全です。
重篤化を防ぐための第一歩
食事や生活習慣の見直しは大切ですが、原因がはっきりしない段階で対策だけを行っても十分でない場合があり、専門医の診察を受けて正確な診断を得ることが、重篤化を防ぐための第一歩です。
早期治療のメリット
原因を早期に特定できれば、薬物療法や食事指導などで比較的簡単に改善へ向かう例もあり、また、内視鏡検査を受けることでポリープを切除できれば、大きな病気への発展を防ぎやすくなります。
負担を最小限に抑えながら、健康を維持する可能性が高まります。
定期的な健診の意識づけ
腹痛と下痢症状がなくても、一定の年齢になれば定期的な大腸内視鏡検査を受けることが推奨される場面があります。とくにがんのリスクが高まる年代の方や、家族に消化器系の病気がある方は積極的に検討すると良いでしょう。
早期受診のメリット
| 受診を早めるメリット | 内容 |
|---|---|
| 病気進行の抑制 | 異変に早く気づけば合併症や転移のリスクが下がる |
| 短期間での治療が期待できる | 薬物療法や生活指導で症状が改善しやすい |
| 身体的・精神的負担の軽減 | 痛みや不安が増大する前に対処可能 |
| 将来的なリスクの低減 | ポリープの早期切除などで大きな疾患を防ぎやすい |
おなかの痛みと下痢が気になる状態は、毎日の暮らしを快適に過ごすためにも早めにクリニックへ相談しましょう。
受診をためらう方が抱えがちな不安
- 内視鏡検査が痛いのではないか
- 仕事を休まなくてはならないか
- 重大な病気を見つけたくない心理がある
- 自己流での改善策で間に合うと思い込んでいる
こうした不安や思い込みを解消しやすいよう、医師や専門スタッフに相談することをおすすめします。
よくある質問
腹痛を伴う下痢症状が長引くと、検査や治療に対する疑問を抱く方が多いです。受診を検討するうえで役立つ質問と、答えを挙げます。
- 内視鏡検査はどのくらいの時間がかかりますか?
-
大腸内視鏡検査の場合、下剤を飲んで腸をきれいにするために数時間を要し、実際の検査自体は個人差はあるものの、約15分~30分程度で終わることが多いです。鎮静剤の使用がある場合は検査後に休憩する時間が必要です。
- 下剤が苦手で飲めるか不安です
-
下剤は複数種類があり、味や濃度にも工夫が施されているものが増えています。飲みやすいフレーバーがある製品もあるので、医師や看護師に相談してください。
こまめに休憩をとりながら飲んだり、冷やすことで飲みやすくなる場合もあります。
- 下痢の状態が続いていても検査は可能ですか?
-
下痢が続いている状態でも検査は可能ですが、脱水や体調不良が強い場合は、点滴などで体調を整えてから検査に臨むことがあります。
あまりにも体力が落ちているときは無理せず、医師の判断に従って検査日を調整するほうが安全です。
- 病変が見つかった場合の治療はどう進みますか?
-
内視鏡検査でポリープや潰瘍など病変が見つかった場合、必要に応じて組織を採取して病理検査を行い、良性ポリープであればその場で切除することも少なくありません。
炎症性疾患や悪性の病変が疑われる場合は、専門医のもとで薬物治療や手術などの治療方針を検討します。早期発見であれば治療の選択肢が広がるため、予後も比較的良好になることが期待できます。
次に読むことをお勧めする記事
【大腸内視鏡検査とはどのような検査なのか】
腹痛と下痢について基本を押さえたら、次は実際の大腸内視鏡検査について知っておくと安心です。検査を検討されている方に特に参考になる内容です。
【腸の健康が体を支える 腸内環境を整える】
腹痛・下痢を繰り返す背景には腸内環境の乱れが潜むことも。食事・生活習慣を見直して、根本から腸を元気にする方法を学びましょう。
参考文献
Fry LC, Carey EJ, Shiff AD, Heigh RI, Sharma VK, Post JK, Hentz JG, Fleischer DE, Leighton JA. The yield of capsule endoscopy in patients with abdominal pain or diarrhea. Endoscopy. 2006 May;38(05):498-502.
Shen B, Khan K, Ikenberry SO, Anderson MA, Banerjee S, Baron T, Ben-Menachem T, Cash BD, Fanelli RD, Fisher L, Fukami N. The role of endoscopy in the management of patients with diarrhea. Gastrointestinal endoscopy. 2010 May 1;71(6):887-92.
May A, Manner H, Schneider M, Ipsen A, Ell C, null for the CEDAP-Plus Study Group. Prospective multicenter trial of capsule endoscopy in patients with chronic abdominal pain, diarrhea and other signs and symptoms (CEDAP-Plus Study). Endoscopy. 2007 Jul;39(07):606-12.
Valero M, Bravo-Velez G, Oleas R, Puga-Tejada M, Soria-Alcívar M, Escobar HA, Baquerizo-Burgos J, Pitanga-Lukashok H, Robles-Medranda C. Capsule endoscopy in refractory diarrhea-predominant irritable bowel syndrome and functional abdominal pain. Clinical Endoscopy. 2018 Nov 16;51(6):570-5.
Kinoshita Y, Ariyoshi R, Fujigaki S, Tanaka K, Morikawa T, Sanuki T. Endoscopic diagnosis of chronic diarrhea. DEN open. 2022 Apr;2(1):e53.
Thakkar K, Dorsey F, Gilger MA. Impact of endoscopy on management of chronic abdominal pain in children. Digestive diseases and sciences. 2011 Feb;56:488-93.
Lukic S, Mijac D, Filipovic B, Sokic-Milutinovic A, Tomasevic R, Krstic M, Milosavljevic T. Chronic abdominal pain: Gastroenterologist approach. Digestive Diseases. 2022 May 4;40(2):181-6.
Song HJ, Moon JS, Jeon SR, Kim JO, Kim J, Cheung DY, Choi MG, Lim YJ, Shim KN, Ye BD, Cheon JH. Diagnostic yield and clinical impact of video capsule endoscopy in patients with chronic diarrhea: a Korean multicenter CAPENTRY study. Gut and liver. 2016 Nov 14;11(2):253.
Shim KN, Kim YS, Kim KJ, Kim YH, Kim TI, Do JH, Ryu JK, Moon JS, Park SH, Hee Park C, Lee KM. Abdominal pain accompanied by weight loss may increase the diagnostic yield of capsule endoscopy: a Korean multicenter study. Scandinavian journal of gastroenterology. 2006 Jan 1;41(8):983-8.
Xue M, Chen X, Shi L, Si J, Wang L, Chen S. Small-bowel capsule endoscopy in patients with unexplained chronic abdominal pain: a systematic review. Gastrointestinal endoscopy. 2015 Jan 1;81(1):186-93.