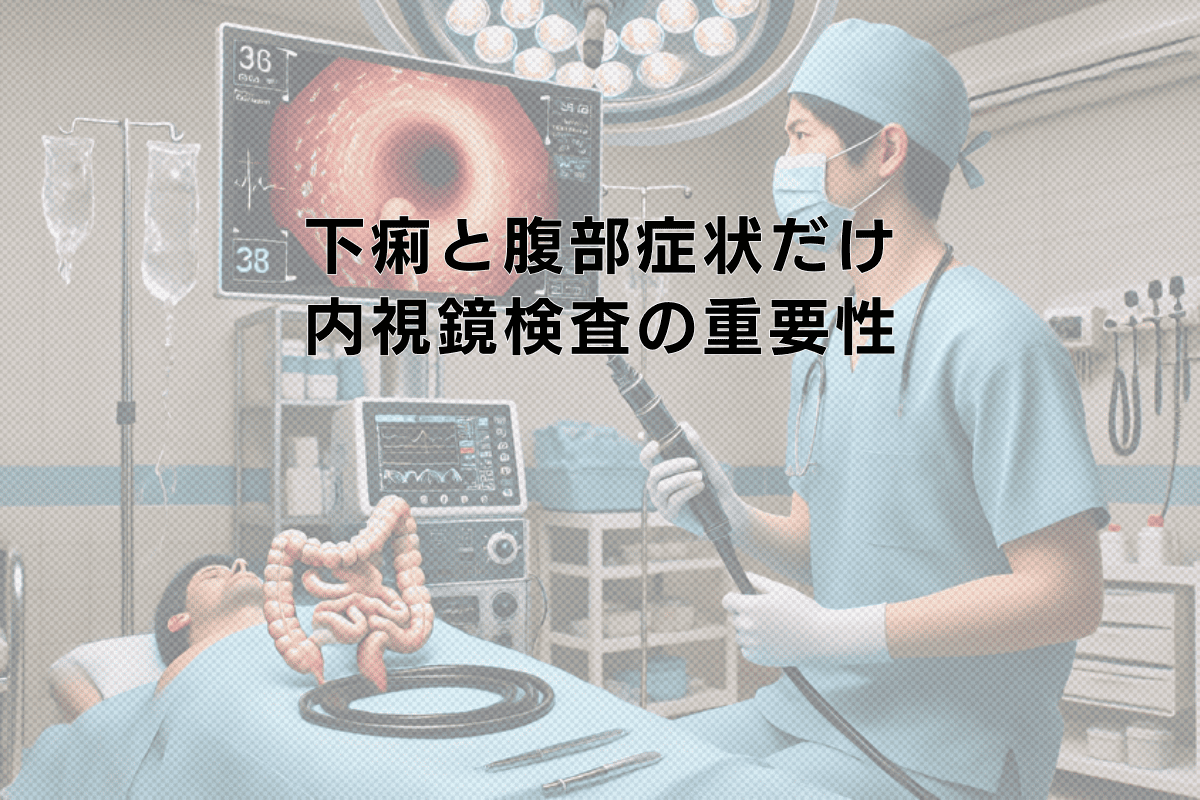「最近、下痢しか出ない」「下痢と便秘を繰り返していて、お腹の調子がずっと悪い」。このような腹部の不快な症状が続くと、日常生活にも影響が出てつらいものです。
一時的な体調不良やストレスが原因と考えがちですが、背後には消化管の病気が隠れている可能性も否定できません。特に、下痢だけでなく腹痛や腹部膨満感といった症状が伴う場合、自己判断で放置するのは危険です。
この記事では、なぜ下痢や腹部症状が続くのか、原因を正確に突き止めるために消化管内視鏡検査がいかに重要であるかを、詳しく解説します。
「下痢しか出ない」と感じる状態と原因
便が固まらず、常に水様便や泥状便が続く状態は、非常に不快なものです。「下痢しか出ない」という感覚は、消化管の機能に何らかの異常が生じているサインですが、原因は多岐にわたり、一過性のものから慢性的な疾患まで様々です。
消化管の水分吸収の異常
私たちの便は、主に大腸で水分が吸収されることで適切な硬さに調整されます。健康な状態では、1日に約1.5リットルの水分が小腸から大腸に送られ、そのうちの90%以上にあたる約1.4リットルが大腸で吸収されます。
しかし、腸管からの水分分泌が過剰になったり、水分吸収能力が低下したりすると、便中の水分量が増加し下痢になります。水分バランスの乱れは、食事内容、ストレス、感染症など、さまざまなことが要因です。
腸のぜん動運動の問題
腸は、ぜん動運動というリズミカルな収縮運動によって内容物を肛門へと運びます。動きが過剰に活発になると、食べ物が腸を通過する時間が極端に短くなり、水分が十分に吸収される前に便として排出されてしまい、下痢となります。
精神的なストレスや不安、特定の食品(カフェインや香辛料など)が自律神経を介して腸を刺激し、ぜん動運動を過剰にします。
下痢の種類と主な原因
| 下痢の種類 | 特徴 | 主な原因 |
|---|---|---|
| 浸透圧性下痢 | 腸管内に水分を引き寄せる物質が原因 | 人工甘味料の過剰摂取、消化不良、一部の下剤 |
| 分泌性下痢 | 腸管からの水分分泌が過剰になる | 食中毒菌(O-157など)、薬剤の副作用、ホルモン産生腫瘍 |
| ぜん動運動性下痢 | 腸の動きが活発になりすぎる | 過敏性腸症候群、ストレス、甲状腺機能亢進症 |
生活習慣との関連性
日々の生活習慣も下痢の症状に大きく影響し、特に食生活は重要で、脂肪分の多い食事、香辛料などの刺激物、アルコール、カフェインの過剰摂取は、腸を直接刺激し下痢を誘発することがあります。
また、不規則な生活や睡眠不足は自律神経のバランスを乱し、腸の機能を不安定にする大きな一因です。慢性的なストレスは、脳腸相関を通じて腸の知覚過敏や運動異常を引き起こし、下痢を悪化させる可能性があります。
「下痢だけど便秘」という矛盾した症状
「下痢と便秘を繰り返す」「下痢気味なのに、すっきり出ないで便が残っている感じがする」。このような一見矛盾した症状は、過敏性腸症候群(IBS)の典型的な症状の一つです。
便秘と下痢が交互に現れるため対策が難しく、多くの方が悩んでいます。
過敏性腸症候群(IBS)の可能性
過敏性腸症候群は、内視鏡検査などで腸に明らかな炎症や潰瘍といった器質的な異常がないにもかかわらず、腹痛や腹部の不快感を伴い、便通異常(下痢や便秘)が長く続く機能性の病気です。
診断には国際的な基準(ローマ基準など)が用いられ、症状の評価に基づいて診断されます。
脳腸相関という考え方
過敏性腸症候群の病態を理解する上で重要なのが、脳と腸がお互いに密接に影響を及ぼしあう脳腸相関です。脳が感じたストレスや不安は、自律神経やホルモンを介して腸に伝わり、腸の運動異常や知覚過敏を起こします。
逆に、腸で生じた刺激や不快感が脳に伝わり、さらなる不安やストレスを感じるという悪循環に陥ることがあり、この相互作用が、症状を慢性化させる一因です。
過敏性腸症候群の分類
| 分類 | 主な症状 | 特徴 |
|---|---|---|
| 下痢型(IBS-D) | 突然の腹痛と激しい下痢、軟便が頻繁に起こる | 男性に比較的多い傾向があり、通勤や会議前など特定の状況で悪化しやすい |
| 便秘型(IBS-C) | 硬い便、排便困難、腹部の張りや残便感 | 女性に比較的多い傾向があり、いきんでも少量しか出ないことが多い |
| 混合型(IBS-M) | 下痢と便秘を数日〜数週間おきに交互に繰り返す | 症状の変動が大きく、対処が最も難しいタイプ |
便秘と下痢を繰り返す背景
混合型の過敏性腸症候群では、腸のぜん動運動が極端に不安定になっています。腸の動きが鈍くなると、便が腸内に長く滞留して水分が過剰に吸収され、硬い便(便秘)になります。
硬い便が腸管を刺激したり、あるいはストレスなどの外的要因が加わったりすると、今度は腸の動きが過剰に活発化し、腸管から水分が大量に分泌され、滞留していた便が水分を多く含んだ下痢便として一気に排出されるのです。
下痢や腹部症状を引き起こす消化管の病気
下痢や腹部の症状は、ありふれたものと思われがちですが、中には注意が必要な消化管の病気が隠れていることがあります。症状が長引く場合や、他の症状を伴う場合は、自己判断せずに専門医に相談することが大切です。
炎症性腸疾患(IBD)
炎症性腸疾患は、腸に原因不明の慢性的な炎症が起こる病気の総称で、主に潰瘍性大腸炎とクローン病があります。どちらも免疫系の異常が関与していると考えられており、下痢や腹痛が主な症状です。
寛解(症状が落ち着いている状態)と再燃(症状が悪化する状態)を繰り返す特徴があり、若年層に発症することが多く、長期的な治療と管理が必要です。
潰瘍性大腸炎とクローン病の比較
| 項目 | 潰瘍性大腸炎 | クローン病 |
|---|---|---|
| 主な炎症場所 | 大腸の粘膜に限定され、直腸から連続的に広がる | 口から肛門までの全消化管に非連続的に発生(飛び石状) |
| 主な症状 | 粘血便、下痢、腹痛、しぶり腹 | 腹痛、下痢、体重減少、発熱、肛門病変 |
| 合併症 | 中毒性巨大結腸症、大腸がん | 腸閉塞、瘻孔(腸に穴が開く)、膿瘍 |
大腸がん・大腸ポリープ
大腸がんやその前段階である大腸ポリープも、下痢や便秘、腹痛の原因となることがあります。がんや大きなポリープが腸を狭くすることで、便が通りにくくなり便秘になったり、腸が刺激されて下痢になったりします。
便が細くなる、血便が出る、下痢と便秘を繰り返すといった便通の変化は、大腸がんの重要なサインである可能性があります。大腸がんは早期に発見し治療すれば治癒率が高い病気であり、症状がある場合の検査は非常に重要です。
顕微鏡的大腸炎
内視鏡で見ただけでは大腸粘膜に明らかな異常が見られないにもかかわらず、慢性の水様性下痢が続く病気で、診断のためには、内視鏡検査の際に採取した組織を顕微鏡で調べる病理組織検査が必須です。
主に膠原線維性大腸炎とリンパ球性大腸炎の2種類があり、中高年の女性に比較的多く見られます。過敏性腸症候群と誤診されているケースも少なくありません。
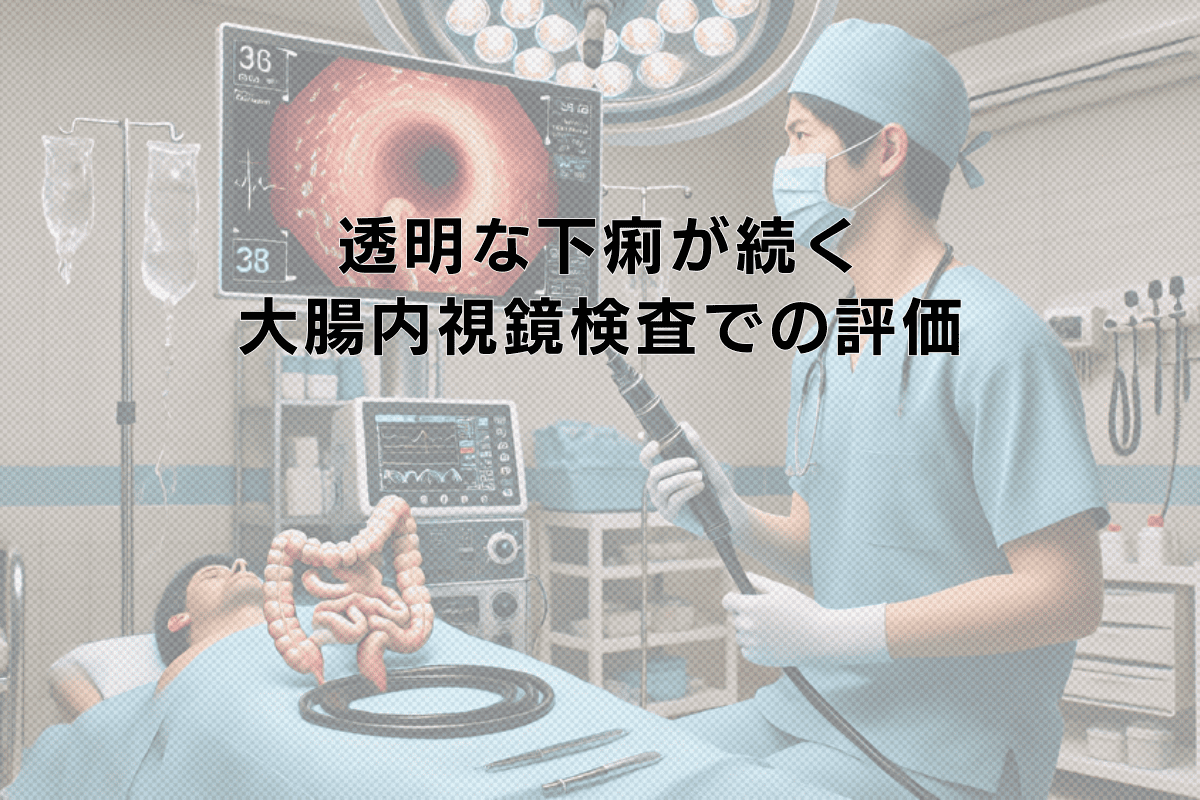
なぜ消化管内視鏡検査が必要なのか
下痢や腹部症状が続く場合、その原因を正確に診断するために、消化管内視鏡検査(胃カメラ・大腸カメラ)は極めて重要な役割を果たします。
問診や血液検査、画像検査だけでは分からない腸の内部の状態を、医師が直接目で見て確認し、さらには組織を採取できる唯一の方法だからです。
症状の原因を直接観察する
内視鏡検査の最大の利点は、食道、胃、十二指腸、そして大腸の粘膜を直接、高解像度の映像でリアルタイムに観察できる点です。
炎症の有無やその範囲・程度、潰瘍の深さ、ポリープやがんなどの病変を、その色や形、大きさ、表面の構造まで詳細に確認でき、症状の根本的な原因を視覚的に捉え、的確な診断を下すことが可能になります。
正確な診断への第一歩
下痢と血便という同じ症状でも、原因が潰瘍性大腸炎なのか、感染性腸炎なのか、虚血性腸炎なのか、あるいは大腸がんなのかによって、治療方針は全く異なります。
内視鏡検査によって腸内の状態を正確に把握することは、治療法を選択するための最も確実な根拠です。誤った自己判断や不確かな診断に基づく治療は、症状を悪化させたり、重大な病気の見逃しにつながったりする危険があります。
内視鏡検査で確認する主なポイント
| 観察項目 | 確認する内容 | 疑われる病気 |
|---|---|---|
| 粘膜の色や血管の様子 | 発赤、むくみ、血管が透けて見えるか(血管透見像) | 炎症性腸疾患、虚血性腸炎、感染性腸炎 |
| びらん・潰瘍の有無 | 粘膜のただれや、深くえぐれている部分の形状や分布 | 炎症性腸疾患、感染性腸炎、薬剤性腸炎 |
| 隆起性病変の有無 | ポリープやがんなどの盛り上がりの大きさ、形、表面構造 | 大腸ポリープ、大腸がん、粘膜下腫瘍 |
組織の一部を採取して詳しく調べる(生検)
内視鏡検査のもう一つの重要な役割は、病変が疑われる部分の組織を鉗子で少量採取(生検)できることです。採取した組織を顕微鏡で詳しく調べる病理組織検査により、がん細胞の有無や炎症の種類、程度などを確定診断します。
顕微鏡的大腸炎のように、見た目では正常に見えても組織レベルで異常がある病気は、生検を行わなければ診断できません。また、ポリープが良性か悪性かを最終的に判断するためにも、この検査は大事です。
消化管内視鏡検査でわかること
消化管内視鏡検査は、一般的に上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)と下部消化管内視鏡検査(大腸カメラ)に分けられます。どちらの検査を行うかは、症状や疑われる病気によって医師が判断します。
大腸粘膜の微細な変化
大腸内視鏡検査では、肛門から盲腸までの大腸全体(約1.5メートル)を隅々まで観察します。
炎症による粘膜のわずかな赤みや腫れ、血管が透けて見えなくなる状態、細かいびらん(ただれ)、深い潰瘍といった変化を詳細に捉えることが可能です。
大腸ポリープの発見と治療
大腸ポリープは、将来的にがんに進行する可能性があるもの(腺腫)と、その可能性が低いものがあります。
近年の内視鏡技術の進歩により、特殊な光(NBIなど)や拡大観察を用いることで、ポリープの表面構造を詳しく観察し、その場で腫瘍性か非腫瘍性かをおおよそ判断できるようになりました。
発見したポリープが切除の対象となる場合、検査中にそのまま切除することもでき、ポリープを切除することは、大腸がんを未然に防ぐ最も有効な予防法です。
大腸がんの早期発見
大腸がんは、早期の段階では自覚症状がほとんどなく、症状が出てから見つかった場合には、すでに進行しているケースも少なくありません。
しかし、内視鏡検査は、症状のない段階の平坦な形をした早期がんや、ミリ単位の小さなポリープさえも発見できる唯一の検査です。定期的な検査を受けることが、大腸がんによる死亡リスクを大幅に減少させることが科学的に証明されています。
大腸内視鏡検査で発見可能な主な病気
| 病名 | 内視鏡での所見 | 症状との関連 |
|---|---|---|
| 大腸がん | 不整な形の隆起や潰瘍、ヒダの集中 | 下痢、便秘、血便、便が細くなる、腹痛 |
| 大腸ポリープ | きのこ状や平坦な隆起、発赤 | 通常は無症状だが、下痢や便秘の原因になることも |
| 炎症性腸疾患 | びまん性の炎症、縦走潰瘍、敷石像、びらん | 慢性の下痢、腹痛、血便、体重減少 |
検査を受ける前の準備と当日の流れ
大腸内視鏡検査を安全かつ正確に行うためには、事前の準備がとても重要です。ここでは、一般的な準備と当日の流れについて説明します。
検査前の食事制限
通常、検査の前日は消化の良い食事(検査食)をとります。きのこや海藻、種子の多い果物(キウイ、いちごなど)、繊維の多い野菜(ごぼうなど)、玄米、ナッツ類など、消化されにくく腸に残りやすい食品は避ける必要があります。
夕食は早めに済ませ、その後は絶食となりますが、水分は水やお茶、スポーツドリンクなど、色のついていない透明な飲み物であれば、検査の数時間前まで摂取可能なことが多いです。
検査前日に避けるべき食品の例
| 食品カテゴリ | 避けるべき食品 | 理由 |
|---|---|---|
| 野菜・果物 | きのこ類、海藻類、ごぼう、キウイ、いちご、トマト | 繊維や種が腸に残り、内視鏡の視野を妨げる |
| 穀物 | 玄米、雑穀パン、全粒粉製品、豆類 | 消化に時間がかかり、腸内に残留しやすい |
| その他 | ごま、ナッツ類、こんにゃく、乳製品 | 腸壁に付着したり、脂肪分が消化を遅らせる |
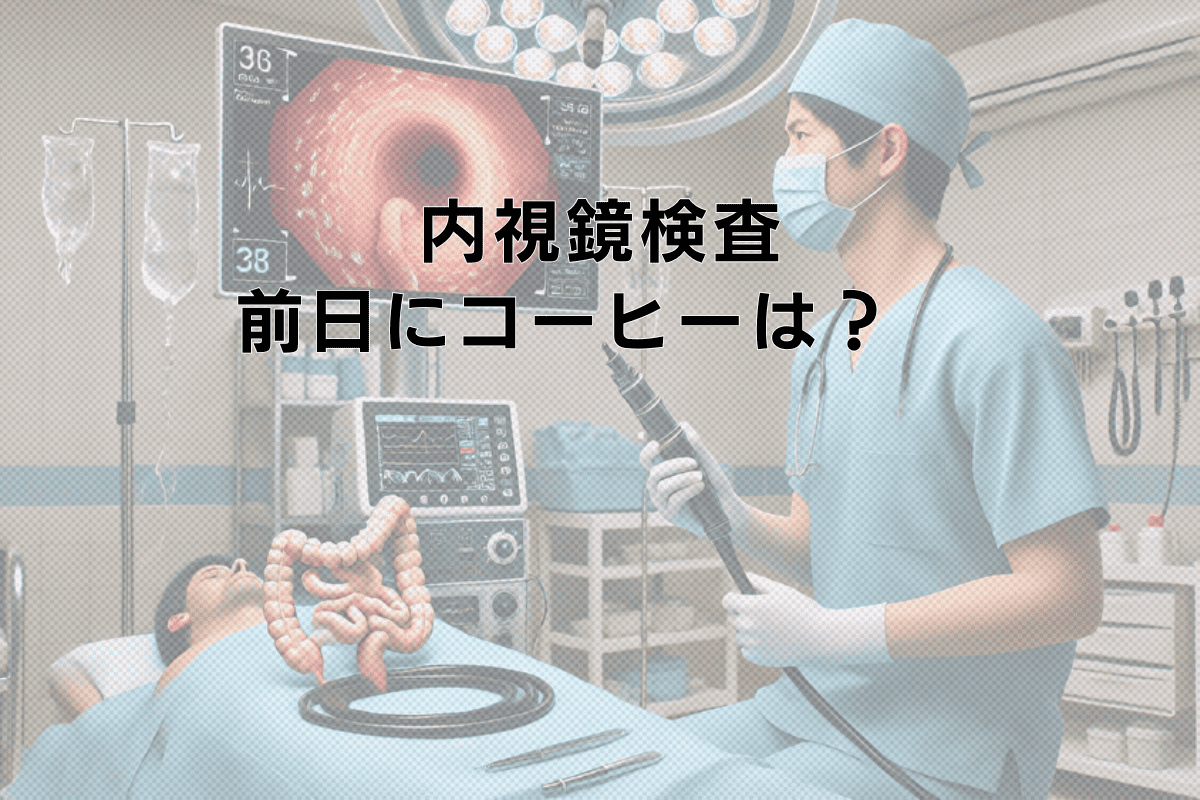
下剤(腸管洗浄剤)の服用
検査当日の朝、または前日の夜から、腸の中をきれいにするための下剤(腸管洗浄剤)を約1〜2リットル、数時間かけて服用し、正確な検査を行うために最も重要な準備です。味のついたものや錠剤タイプなど、いくつかの種類があります。
何度かトイレに通い、最終的に便が尿のような透明な黄色い液体になったら準備完了のサインで、服用がつらい場合は、冷やしたり、少しずつ飲んだりする工夫が有効です。
検査当日の手順
医療機関に到着後、問診や血圧測定などを行い、検査着(お尻の部分に穴が開いたズボン)に着替えます。検査室では、ベッドに左側を下にして横になり、鎮静剤や鎮痛剤を点滴から投与することが多いです。
肛門から内視鏡をゆっくりと挿入し、空気や二酸化炭素で腸を膨らませながら、大腸の一番奥にある盲腸まで進めていき、その後、抜きながら隅々まで観察します。
検査時間は通常15分から30分程度ですが、ポリープ切除などを行う場合はもう少し時間がかかります。
検査後の注意点と生活習慣の見直し
検査が無事に終了した後も、いくつか注意すべき点があります。また、検査結果に基づいて、今後の生活習慣を見直すことが、症状の再発防止や長期的な健康維持につながります。
検査直後の過ごし方
鎮静剤を使用した場合は、意識がはっきりするまで1時間ほどリカバリールームで休みます。鎮静剤の影響が残るため、当日は車、バイク、自転車の運転や、集中力を要する仕事、重要な判断はできません。
食事は、お腹の張りがおさまってから、消化の良いものから少しずつ始めます。
ポリープを切除した場合は、出血や穿孔(腸に穴が開くこと)のリスクを減らすため、数日間はアルコールや刺激物の摂取、激しい運動、長時間の移動、サウナなどを控えてください。
検査後の食事のポイント
| タイミング | 推奨される食事 | 避けるべき食事 |
|---|---|---|
| 検査当日(観察のみ) | おかゆ、うどん、スープ、豆腐、白身魚 | 脂っこいもの、香辛料、アルコール、食物繊維の多いもの |
| ポリープ切除後(数日間) | 上記と同様の消化の良い食事を継続 | 刺激物、アルコール、脂質の多い食事は厳禁 |
検査結果の説明と今後の対策
多くの場合、検査後、回復してから医師から内視鏡画像を見ながら結果の説明があり、もし病気が見つかった場合は、その後の精密検査や治療方針について詳しく相談します。
生検を行った場合は、病理組織検査の結果が1〜2週間後に出るため、後日改めて説明を聞きに行きます。
異常がなかった場合でも、症状の原因が過敏性腸症候群など機能的な問題である可能性が考えられ、食事療法や薬物療法、生活習慣の改善といった対策を講じることが重要です。
症状と向き合うための生活改善
下痢や腹部症状を繰り返さないためには日々の生活を見直すことが大切で、バランスの取れた食事を心がけ、十分な睡眠と休息をとること、ストレスを上手に管理することが、腸の健康を保つ鍵です。
特に過敏性腸症候群の場合は、低FODMAP食(発酵性の糖質を控える食事法)が有効な場合があります。検査をきっかけに、ご自身の体と生活習慣に真剣に向き合う良い機会としてください。
下痢や腹部症状に関するよくある質問
最後に、下痢や腹部症状、そして内視鏡検査に関して多くの方が抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。
- 下痢が続く場合、どのくらいの期間で受診すべきですか?
-
明らかな原因(暴飲暴食など)がなく、下痢が2週間以上続く場合は慢性下痢と考えられ、一度医療機関に相談することをお勧めします。
40歳以上の方、発熱、血便、体重減少、激しい腹痛、貧血などを伴う場合は、重大な病気の可能性も考えられるため、早めに受診してください。
- 大腸内視鏡検査は痛いですか?苦しいですか?
-
以前は痛くて苦しい検査というイメージがありましたが、現在は技術や機器の進歩により、苦痛は大幅に軽減されています。
多くの医療機関で鎮静剤や鎮痛剤を使用することで、うとうとと眠っているようなリラックスした状態で検査を受けることが可能です。
また、お腹の張りを軽減するために、空気の代わりに体への吸収が速い二酸化炭素を使用する工夫もされています。
- 市販の下痢止めを飲んでも良いですか?
-
細菌やウイルスによる感染性腸炎の場合、下痢止めで腸の動きを無理に止めると、病原体や毒素の排出を妨げ、かえって症状を悪化させたり、回復を遅らせたりすることがあります。
自己判断での安易な使用は避けるべきで、特に発熱や血便がある場合は絶対に使用せず、医療機関を受診してください。
- 検査で異常がないのに症状が続きます。なぜですか?
-
内視鏡検査で炎症やポリープなどの器質的な異常が見つからないにもかかわらず、下痢や腹痛が続く場合、過敏性腸症候群(IBS)や、機能性下痢といった機能性消化管疾患の可能性が考えられます。
これは腸の機能的な問題(動きや知覚の異常)が原因であり、病気ではないということではありません。適切な診断のもと、食事療法や薬物療法、生活習慣の改善によって症状をコントロールしていくことが大切です。
次に読むことをお勧めする記事
【大腸内視鏡検査の前日に必要な準備と食事の注意点】
下痢と腹部症状の原因究明に内視鏡検査が重要だと理解できたら、次は実際の検査前日の準備について知っておくと安心です。検査を初めて受ける方や前回の準備がうまくいかなかった方に特に参考になる内容です。
【鎮静剤を使用した痛みの少ない内視鏡検査について】
検査の必要性が見えてきた皆さんには、鎮静の可否や注意点も合わせて知っておくと、負担や不安の軽減につながります。
参考文献
Kinoshita Y, Ariyoshi R, Fujigaki S, Tanaka K, Morikawa T, Sanuki T. Endoscopic diagnosis of chronic diarrhea. DEN open. 2022 Apr;2(1):e53.
May A, Manner H, Schneider M, Ipsen A, Ell C, null for the CEDAP-Plus Study Group. Prospective multicenter trial of capsule endoscopy in patients with chronic abdominal pain, diarrhea and other signs and symptoms (CEDAP-Plus Study). Endoscopy. 2007 Jul;39(07):606-12.
Saito Y, Kodashima S, Matsuda T, Matsuda K, Fujishiro M, Tanaka K, Kobayashi K, Katada C, Horimatsu T, Muto M, Ohtsuka K. Current status of diagnostic and therapeutic colonoscopy in Japan: The Japan Endoscopic Database Project. Digestive Endoscopy. 2022 Jan;34(1):144-52.
Tomizawa M, Shinozaki F, Hasegawa R, Shirai Y, Motoyoshi Y, Sugiyama T, Yamamoto S, Ishige N. Abdominal ultrasonography for patients with abdominal pain as a first-line diagnostic imaging modality. Experimental and Therapeutic Medicine. 2017 May 1;13(5):1932-6.
Matsumoto Y, Nadatani Y, Otani K, Higashimori A, Ominami M, Fukunaga S, Hosomi S, Kamata N, Kimura T, Fukumoto S, Tanaka F. Prevalence and risk factor for chronic diarrhea in participants of a Japanese medical checkup. JGH Open. 2022 Jan;6(1):69-75.
Ihara E, Manabe N, Ohkubo H, Ogasawara N, Ogino H, Kakimoto K, Kanazawa M, Kawahara H, Kusano C, Kuribayashi S, Sawada A. Evidence-based clinical guidelines for chronic diarrhea 2023. Digestion. 2024 Dec 9;105(6):480-97.
Ashitani K, Tsuzuki Y, Yamaoka M, Ohgo H, Ichimura T, Kusano T, Nakayama T, Nakamoto H, Imaeda H. Endoscopic features and diagnostic procedures of eosinophilic gastroenteritis. Internal Medicine. 2019 Aug 1;58(15):2167-71.
May A, Manner H, Schneider M, Ipsen A, Ell C, null for the CEDAP-Plus Study Group. Prospective multicenter trial of capsule endoscopy in patients with chronic abdominal pain, diarrhea and other signs and symptoms (CEDAP-Plus Study). Endoscopy. 2007 Jul;39(07):606-12.
Kinoshita Y, Ariyoshi R, Fujigaki S, Tanaka K, Morikawa T, Sanuki T. Endoscopic diagnosis of chronic diarrhea. DEN open. 2022 Apr;2(1):e53.
Schiller LR, Pardi DS, Sellin JH. Chronic diarrhea: diagnosis and management. Clinical Gastroenterology and Hepatology. 2017 Feb 1;15(2):182-93.