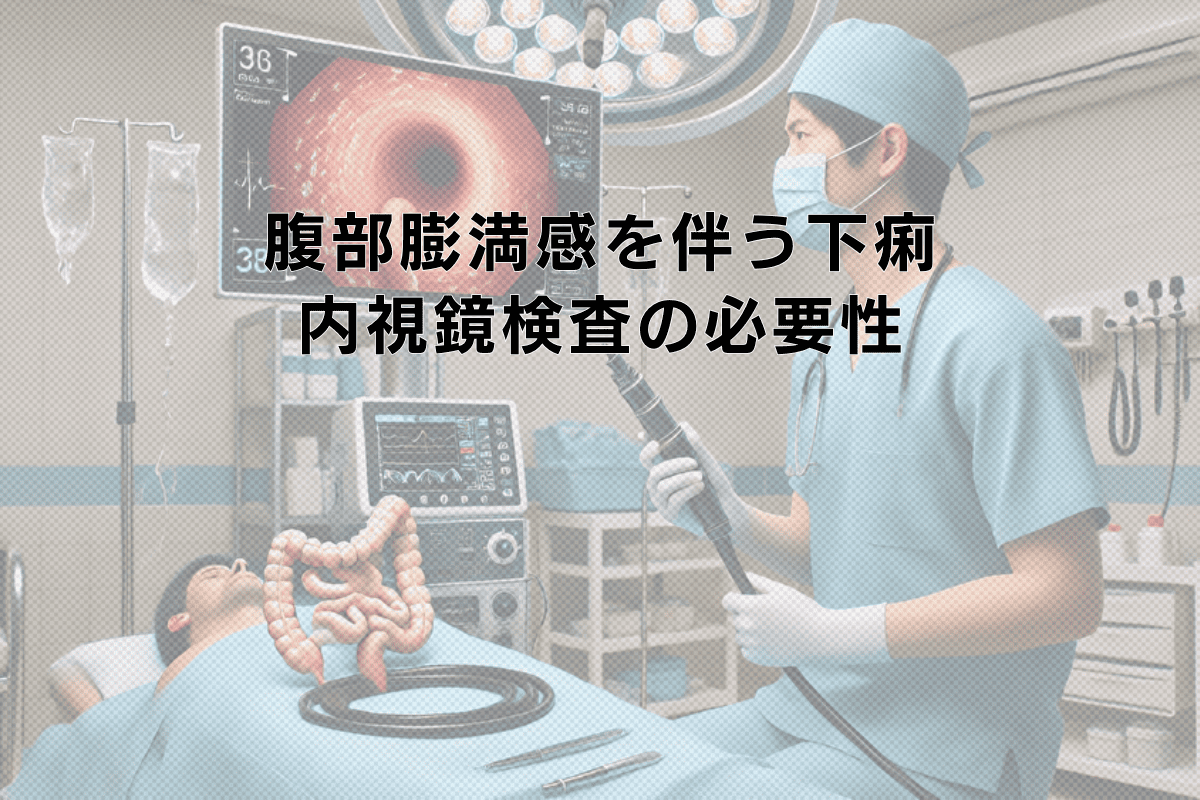お腹がゴロゴロ鳴り急な便意と共に下痢が続き、それに加えて、お腹がパンパンに張るような不快な膨満感。このような症状が同時に現れると、日常生活にも支障をきたし、大きな不安を感じる方も少なくないでしょう。
一時的なものであれば様子を見ることもできますが、症状が長引く場合や繰り返す場合には、背景に何らかの消化器系の問題が隠れている可能性があります。
この記事では、腹部膨満感を伴う下痢の症状について、原因からご自身でできる対処法、そして医療機関での検査、消化管内視鏡検査の重要性について詳しく解説します。
腹部膨満感を伴う下痢とはどのような症状か
下痢とお腹の張り、つまり腹部膨満感は、多くの方が一度は経験したことのある身近な症状ですが、二つが同時に継続的に起こる場合、体からの重要なサインかもしれません。
下痢の定義と状態
一般的に下痢とは、便の水分量が異常に増加し、液状またはそれに近い泥状の便が頻繁に排出される状態です。健康な状態の便の水分量は約70%から80%ですが、これが90%を超えると下痢便となります。
便の回数が増えるだけでなく、一回の排便量が増加することもあります。
下痢は、体内に侵入した病原体や有害物質を速やかに体外へ排出しようとする体の防御反応として起こることもあれば、腸の運動機能や水分吸収機能に問題が生じているサインであることもあります。
期間によって、数日から2週間程度で治まる急性の下痢と、4週間以上続く慢性の下痢に分類します。
腹部膨満感の正体
腹部膨満感は、お腹が張って苦しい、ガスが溜まっている感じがする、お腹が膨らんで見えるといった感覚的な症状の総称です。この不快感は、消化管内に過剰なガスが溜まることによって生じます。
ガスは、食事の際に飲み込む空気や、腸内細菌が食物を分解する過程で発生します。
通常、ガスはげっぷやおならとして自然に排出されますが、何らかの原因でガスの産生量が増えたり、排出がうまくいかなくなったりすると、腸内に溜まって膨満感を起こします。
また、ガスの問題だけでなく、消化不良による内容物の停滞や、腹水の貯留などが原因となることもあります。
二つの症状が同時に起こる背景
下痢と腹部膨満感が同時に起こる場合、消化管の機能に何らかの異常が生じている可能性が高いです。腸の動きが過剰に活発になることで、食べ物が十分に消化・吸収されないまま腸を通過し、下痢を引き起こすことがあります。
この時、腸内細菌が未消化の食物を異常発酵させ、大量のガスを発生させることで腹部膨満感が同時に現れます。
逆に、腸の動きが悪くなることで便やガスが腸内に滞留し、それが刺激となって腸から水分が過剰に分泌され、下痢と膨満感が併発することもあります。
症状の組み合わせから考えられること
下痢と腹部膨満感という症状の組み合わせは、特定の疾患を示唆する重要な手がかりです。過敏性腸症候群(IBS)では、ストレスなどをきっかけに腸の機能異常が起こり、下痢と便秘を繰り返す中で、腹痛や腹部膨満感を伴います。
また、特定の食物に対する不耐症(例えば乳糖不耐症)でも、原因となる食物を摂取した後に下痢とガスの発生による膨満感が現れます。
下痢と腹部膨満感を引き起こす主な原因
下痢と腹部膨満感は、多くの原因によって起こり、食生活やストレスといった日常的なものから、治療を必要とする消化器系の病気まで多岐にわたります。
食生活や生活習慣に起因するもの
日々の生活の中に、症状の原因が隠れていることは少なくありません。特に食生活は、腸の健康に直接的な影響を与えます。
食事内容の問題
暴飲暴食や脂肪分の多い食事、香辛料などの刺激物を多く摂取すると、消化管に負担がかかり消化不良を起こします。未消化の食物は腸内で異常発酵し、ガスを発生させて腹部膨満感の原因となります。
また、腸が刺激されることで蠕動運動が活発になりすぎ、下痢を引き起こすこともあり、アルコールの過剰摂取や、冷たい飲み物の飲み過ぎも同様に腸を刺激し、症状を悪化させる要因です。
食物不耐症とアレルギー
特定の食物に含まれる成分を体がうまく分解・吸収できない状態が食物不耐症です。
代表的なものに乳糖不耐症があり、牛乳や乳製品に含まれる乳糖を分解する酵素が不足しているために、摂取後に下痢や腹部膨満感、腹痛などが生じます。
また、特定の食物に対する免疫系の過剰反応である食物アレルギーも、下痢などの消化器症状を起こすことがあります。
ストレスと自律神経の乱れ
脳と腸は自律神経などを介して密接に関連しており、これを脳腸相関と呼びます。
強いストレスや慢性的な精神的負担は、自律神経のバランスを乱し、腸の運動機能に影響を与え、腸の動きが過敏になることで下痢を起こしたり、逆に動きが鈍くなることでガスが溜まりやすくなったりします。
過敏性腸症候群(IBS)は、この脳腸相関の異常が深く関わっているのです。
感染症によるもの
ウイルスや細菌などの病原体に感染することによって、急性の胃腸炎が起き、下痢や腹部膨満感が生じることがあります。

ウイルス性胃腸炎
ノロウイルスやロタウイルスなどが原因で起こる感染症です。ウイルスが腸の粘膜に感染すると、腸の炎症と機能低下が起こり、激しい下痢や嘔吐、腹痛、発熱などの症状が現れます。
腸の炎症によって水分吸収がうまくいかなくなり、下痢となり、また、腸の動きが低下することでガスが溜まり、膨満感を伴うこともあります。
細菌性腸炎
サルモネラ菌、カンピロバクター、病原性大腸菌などの細菌に汚染された食物を摂取することで発症します。
ウイルス性胃腸炎と同様に、下痢、腹痛、発熱などの症状が見られますが、時には血便を伴うなど、より重篤な症状が現れることもあります。細菌が出す毒素が腸の粘膜を傷つけ、激しい炎症を起こすことが原因です。
消化器系の病気
症状が慢性的であったり、他の症状を伴ったりする場合には、背景に何らかの消化器系の病気が隠れている可能性があります。
主な原因の分類
| 分類 | 具体的な原因 | 特徴 |
|---|---|---|
| 生活習慣 | 暴飲暴食、脂肪分の多い食事、ストレス | 原因となる行動の後に症状が現れやすい |
| 感染症 | ウイルス、細菌 | 急性の発症で、発熱や嘔吐を伴うことが多い |
| 消化器疾患 | 過敏性腸症候群、炎症性腸疾患など | 症状が慢性的、または繰り返す |
過敏性腸症候群(IBS)
検査をしても腸に炎症や潰瘍などの目に見える異常がないにもかかわらず、下痢や便秘、腹痛、腹部膨満感などの症状が長く続く病気です。
ストレスが症状を悪化させる要因となることが多く、下痢型、便秘型、混合型などのタイプに分かれ、腸の知覚過敏や運動異常が主な原因と考えられています。
炎症性腸疾患(IBD)
クローン病や潰瘍性大腸炎といった、腸に慢性の炎症や潰瘍が生じる原因不明の病気の総称で、長期にわたる下痢や血便、腹痛、体重減少などが主な症状です。
腸の粘膜が炎症によって正常に機能しなくなるため、水分や栄養の吸収が妨げられ、下痢となります。炎症によって腸管が狭くなる(狭窄)と、内容物の通過が悪くなり、腹部膨満感を起こすこともあります。
大腸がん・大腸ポリープ
大腸がんや大きな大腸ポリープが腸管内にできると、便の通り道が狭くなり、便が細くなったり便秘と下痢を繰り返したりすることがあります。
腫瘍が大きくなると腸が完全に塞がれてしまい(腸閉塞)、激しい腹痛や腹部膨満感、嘔吐などを起こし、また、腫瘍の表面から出血することで、血便や貧血が見られることもあります。
このような症状、病気が進行してから現れることも少なくないため、早期発見が重要です。
症状を和らげるためのセルフケア
下痢や腹部膨満感が続く場合、医療機関の受診が基本ですが、症状が軽い場合や、生活習慣に原因があると考えられる場合には、ご自身でできるセルフケアによって症状が和らぐことがあります。
食事で気をつけること
腸に負担をかけない食事を心がけることが、症状緩和の基本で、何を、どのように食べるかが重要です。
消化の良い食事を心がける
下痢が続いている時は、腸が刺激に敏感になっているので、おかゆ、うどん、白身魚、豆腐、鶏のささみなど、消化が良く、胃腸に優しい食品を選びましょう。
食物繊維が多い野菜やきのこ類、脂肪分の多い肉類や揚げ物、香辛料の強い料理は、腸を刺激し、症状を悪化させる可能性があるため、一時的に控えてください。
食事の摂り方
| ポイント | 具体的な方法 | 理由 |
|---|---|---|
| 少量頻回食 | 1回の食事量を減らし、食事の回数を増やす | 一度に消化管へかかる負担を軽減する |
| よく噛む | 一口30回を目安によく噛んで食べる | 唾液の分泌を促し、消化を助ける |
| 規則正しい食事 | 毎日決まった時間に食事を摂る | 消化管のリズムを整え、機能を安定させる |
特定の食品を避ける
症状の原因となりやすい特定の食品を避けることも有効です。
冷たい飲み物や炭酸飲料は腸を刺激し、動きを活発にしすぎる可能性があり、また、人工甘味料(ソルビトールなど)を含む食品は、体質によってはお腹が緩くなることがあります。
ガスを発生させやすいとされる豆類、いも類、キャベツなどの食品も、腹部膨満感が強い時には摂取を控えるてください。
ご自身の経験から、特定の食品を食べた後に症状が悪化することに気づいている場合は、その食品を避けることが大切です。
生活習慣の見直し
日々の過ごし方も腸の健康に影響します。規則正しい生活を送り、腸に負担をかけない習慣を身につけましょう。
十分な休息と睡眠
睡眠不足や過労は、自律神経のバランスを乱す大きな原因で、自律神経は腸の働きをコントロールしているため、バランスが乱れると腸の機能にも異常をきたしやすくなります。
毎日決まった時間に就寝・起床し、質の良い睡眠を確保することが大切です。
適度な運動の習慣化
ウォーキングやストレッチなどの軽い運動は、血行を促進し、自律神経のバランスを整える効果が期待でき、また、適度な運動は腸の蠕動運動を正常に保つのに役立ちます。
便秘と下痢を繰り返すタイプの方や、腹部膨満感が強い方には、腸の動きを整える助けとなることがあります。
ストレスとの上手な付き合い方
ストレスは、過敏性腸症候群をはじめとする多くの消化器症状の引き金です。ストレスを完全になくすことは難しいですが、上手に付き合っていく方法を見つけることが症状のコントロールにつながります。
リラックスできる時間を作る
日常生活の中に、心からリラックスできる時間を取り入れましょう。趣味に没頭する、好きな音楽を聴く、ゆっくりと入浴する、アロマテラピーを楽しむなど、自分に合った方法で心と体を休ませることが大切です。
ストレスマネジメントのヒント
- 深呼吸や瞑想
- ヨガや軽いストレッチ
- 信頼できる人との対話
- 自然の中での散歩
医療機関を受診すべき危険なサイン
多くの下痢や腹部膨満感は一時的なものですが、中には重大な病気が隠れている可能性もあります。セルフケアを試みても改善しない場合や、特定の症状が見られる場合には、自己判断で様子を見ずに、速やかに医療機関を受診することが重要です。
症状が長期間続く、または悪化する場合
一時的な食あたりやストレスによる症状であれば、通常は数日から1週間程度で改善に向かいます。
しかし、下痢や腹部膨満感が2週間以上続く場合、あるいは一度治まったと思っても頻繁に繰り返す場合には、慢性的な消化器の病気が背景にある可能性を考えます。症状が徐々に悪化していると感じる場合は、早めの受診が必要です。
激しい腹痛や高熱を伴う
我慢できないほどの激しい腹痛や、38度以上の高熱を伴う下痢は、単なる胃腸炎ではない可能性があります。細菌性腸炎、虫垂炎、憩室炎、腸閉塞など、緊急の対応を必要とする病気も考えられます。
お腹を押すと強く痛む、痛みが持続して動けないといった場合は、ためらわずに医療機関を受診してください。
血便や黒色便が見られる
便に血が混じる(血便)のは、消化管のどこかから出血しているサインです。
鮮やかな赤色の血であれば、肛門に近い大腸や直腸からの出血が疑われ、黒くてドロっとした便(黒色便またはタール便)は、胃や十二指腸など、食道に近い上部消化管からの出血を示唆します。
出血の原因としては、炎症性腸疾患、大腸憩室出血、虚血性腸炎、そして大腸がんなどが考えられます。出血は貧血の原因にもなるため、便の色に異常が見られたら必ず専門医に相談してください。
受診を急ぐべき症状
| 症状 | 考えられる状態 | 対応 |
|---|---|---|
| 持続する激しい腹痛 | 腸閉塞、虫垂炎など | 速やかに医療機関を受診 |
| 血便・黒色便 | 消化管出血(がん、潰瘍など) | 速やかに医療機関を受診 |
| 急な体重減少 | 悪性腫瘍、吸収不良症候群など | 早めに専門医に相談 |
原因不明の体重減少や貧血がある
食事制限をしていないにもかかわらず、ここ数ヶ月で急に体重が減ってきたという場合、注意が必要です。
慢性的な下痢によって栄養が十分に吸収できていない吸収不良症候群や、炎症性腸疾患、あるいは大腸がんなどの悪性腫瘍が隠れている可能性があります。
また、健康診断などで貧血を指摘された場合も、消化管からの慢性的な出血が原因となっていることがあります。
医療機関で行われる診断と検査
下痢と腹部膨満感を主訴に医療機関を受診した場合、医師は原因を特定するために様々な角度から診察と検査を進めます。ここでは、一般的に行われる診断の流れと、主な検査について解説します。
問診で詳しく症状を伝える
診断において最も重要な情報源となるのが、患者さんからの症状に関する詳しい情報です。医師は、以下のような点について質問します。
伝えるべき情報
- いつから症状が始まったか
- 症状の頻度や持続時間
- 便の状態(色、形、血液の有無)
- 腹痛の有無や場所、性質
- 食事やストレスとの関連性
- 既往歴や服用中の薬
身体診察
問診に続いて、医師が直接体に触れて診察を行います。
聴診器でお腹の音(腸の動き)を聞いたり、お腹を触って痛みのある場所やしこりの有無、張りの程度を確認したりすることで、腸の活動状態や炎症の場所などについて、ある程度の推測を立てることができます。
血液検査や便検査
より客観的な情報を得るために、各種検査を行います。
血液検査
血液検査では、体内の炎症の程度(CRP値や白血球数)、貧血の有無(ヘモグロビン値)、栄養状態(アルブミン値など)を調べることができます。感染症が疑われる場合や、炎症性腸疾患の活動性を評価する上で重要な情報です。
便検査
便の中に血液が混じっていないかを確認する便潜血検査は、大腸がんのスクリーニングとして広く行われていてます。また、感染が疑われる場合には、便を培養して原因となる細菌やウイルスを特定することもあります。
主な検査とその目的
| 検査名 | 目的 | 何がわかるか |
|---|---|---|
| 血液検査 | 全身状態の評価 | 炎症、貧血、栄養状態 |
| 便検査 | 便の状態の評価 | 消化管出血の有無、感染症の原因菌 |
| 内視鏡検査 | 消化管内部の直接観察 | 炎症、潰瘍、ポリープ、がんの有無 |
消化管内視鏡検査(胃カメラ・大腸カメラ)
問診や他の検査で原因が特定できない場合や、がんや炎症性腸疾患などの器質的な病気が疑われる場合に、消化管内視鏡検査が検討されます。
これは、先端に小型カメラがついた細い管を口や肛門から挿入し、食道、胃、十二指腸や大腸の内部を直接モニターで観察する検査です。粘膜の状態を詳細に観察できるため、診断を確定する上で非常に重要な役割を果たします。
なぜ消化管内視鏡検査が重要なのか
消化管内視鏡検査は、下痢や腹部膨満感の原因を特定する上で、他の検査では代えがたい多くの情報をもたらします。医師がこの検査を勧めるのには、明確な理由があります。
消化管の内部を直接観察できる
内視鏡検査の最大の利点は、消化管の粘膜をリアルタイムで直接、詳細に観察できることです。
レントゲンやCTなどの画像検査では捉えきれない、粘膜のわずかな色の変化、びらん(ただれ)、潰瘍、ポリープ、がんなどの微細な病変を発見することができます。
症状の原因となっている異常がどこに、どの程度の範囲で、どのような状態で存在するのかを正確に把握できるため、最も確実な診断方法の一つです。
内視鏡で発見可能な主な疾患
| 疾患名 | 内視鏡での所見 | 症状との関連 |
|---|---|---|
| 大腸がん・ポリープ | 隆起や陥凹、出血しやすい表面 | 便通異常、血便、腹部膨満感の原因 |
| 潰瘍性大腸炎 | 粘膜のびまん性な発赤、びらん、出血 | 慢性の下痢、血便、腹痛の原因 |
| クローン病 | 縦走潰瘍、敷石像、狭窄 | 下痢、腹痛、体重減少、腹部膨満感の原因 |
組織の一部を採取して確定診断につなげる
内視鏡検査では、観察中に疑わしい部分が見つかった場合、その場で組織の一部を採取することができ(生検)、採取した組織は、顕微鏡で詳しく調べる病理組織検査に提出されます。
検査によって、病変が炎症によるものなのか、良性のポリープなのか、あるいは悪性のがんなのかを確定的に診断することが可能です。見た目だけでは判断が難しい早期のがんも、病理組織検査によって確実に診断できます。
重大な病気の早期発見と治療
特に大腸がんは、早期の段階では自覚症状がほとんどないことが多く、症状が現れた時にはすでに進行しているケースも少なくありません。下痢や腹部膨満感といったありふれた症状が、大腸がんのサインである可能性もあります。
内視鏡検査は、このような自覚症状の出にくい早期のがんや、がん化する可能性のあるポリープを発見するのに非常に有効です。ポリープが見つかった場合、その場で切除することも可能であり、将来のがんを予防することにもつながります。
治療方針の決定に役立つ
検査によって得られた情報は、治療方針を決定するための重要な根拠となります。炎症性腸疾患と診断された場合、炎症の範囲や重症度を内視鏡で正確に評価することで、適切な種類の薬剤や治療法を選択することができます。
また、治療後の効果判定や、病状の経過観察のためにも内視鏡検査は定期的に行われます。
消化管内視鏡検査の流れと準備
消化管内視鏡検査、特に大腸内視鏡検査(大腸カメラ)は、正確な検査を行うために事前の準備がとても大切です。ここでは、一般的な大腸内視鏡検査を例に、準備と流れを解説します。

検査前の準備
腸の中をきれいにして、粘膜を隅々まで観察できるようにするための準備です。医療機関の指示に正確に従ってください。
食事制限
通常、検査の前日は、消化の良い食事を摂るように指示され、きのこ、海藻、こんにゃく、種のある果物など、繊維質が多く腸に残りやすい食品は避ける必要があります。
夕食は早めの時間に済ませ、その後は絶食となりますが、水分は水やお茶であれば摂取可能です。
検査前日の食事例
| 時間 | 食事内容の例 | 避けるべき食品 |
|---|---|---|
| 朝食・昼食 | おかゆ、素うどん、食パン、白身魚、豆腐 | 野菜、きのこ、海藻、豆類、果物 |
| 夕食(20時頃まで) | 具のないスープ、ゼリー飲料など | 固形物全般 |
| 就寝前 | 水、お茶 | 牛乳、ジュース、アルコール |
下剤の服用
検査当日の朝、または前日の夜から、腸管洗浄剤(下剤)を服用します。約1リットルから2リットルの液体を数時間かけて飲み、腸内に残っている便をすべて洗い流します。
便が透明な液体になるまで、何度かトイレに通うことになり、この準備が検査の精度を左右するため、大変ですが確実に行うことが重要です。
検査当日の流れ
検査着に着替えた後、検査室に入り、鎮静剤を使用する場合は、点滴の準備をします。
検査の実施
体の左側を下にしてベッドに横になり、検査が始まります。肛門から内視鏡をゆっくりと挿入し、大腸の一番奥まで進めてから、抜きながら粘膜を詳細に観察していきます。
腸を膨らませて見やすくするために、炭酸ガスや空気を送り込むため、お腹が張る感じがすることがあります。検査時間は通常15分から30分程度ですが、ポリープの切除などを行う場合はもう少し時間がかかります。
多くの場合、鎮静剤を使用するため、苦痛をほとんど感じることなく検査を終えることが可能です。
検査後の注意点
検査が無事に終了した後も、いくつか注意すべき点があります。
鎮静剤使用後の安静
鎮静剤を使用した場合は、検査後に意識がはっきりするまで、1時間から2時間ほどリカバリールームで休む必要があります。当日は、鎮静剤の影響が残る可能性があるため、車やバイク、自転車の運転は絶対にできません。
公共交通機関を利用するか、ご家族に送迎を依頼してください。
食事と生活
食事は、検査終了後1時間程度経てば摂ることができますが、最初は消化の良いものから食べ始めるようにしましょう。
組織を採取したり、ポリープを切除したりした場合は、数日間はアルコールや刺激物の摂取、激しい運動、長時間の入浴などを避けるよう指示されることがあります。
下痢や腹部膨満感に関して、よくある質問
ここでは、下痢や腹部膨満感に関して、患者さんからよく寄せられる質問と回答をまとめました。
- 市販の下痢止めを飲んでも良いですか
-
急な下痢に対して、一時的に市販薬を使用すること自体が問題となるケースは少ないですが、注意も必要です。特に、細菌やウイルスによる感染性腸炎の場合、下痢は病原体を体外に排出しようとする体の防御反応です。
下痢止めで無理に腸の動きを止めてしまうと、かえって病原体が腸内に留まり、回復を遅らせたり症状を悪化させたりする可能性があります。
発熱や血便を伴う場合や、症状が数日以上続く場合には、自己判断で薬を飲み続けず、医療機関を受診して原因を調べることが大切です。
- 子供や高齢者の場合は特に注意が必要ですか
-
子供、特に乳幼児は、大人に比べて体の水分量が占める割合が高く、下痢によって容易に脱水症状に陥りやすいです。
ぐったりしている、おしっこの量が少ない、泣いても涙が出ないといったサインは脱水の危険信号なので、早めに小児科を受診してください。
高齢者の場合も、持病があったり、体力が低下していたりするため、下痢が重症化しやすく、脱水も起こしやすいです。また、服用している薬の影響で下痢が起こることもあります。
症状が続く場合は、かかりつけ医に相談することが重要です。
- 食事はどのように変えれば良いですか
-
症状があるときは、まず腸を休ませることが基本です。おかゆやよく煮込んだうどんなど、温かくて消化の良いものを中心に、少量ずつ摂ります。
症状が落ち着いてきたら、徐々に食事の量を戻していきますが、脂肪分の多い食事や香辛料、アルコール、カフェインなどの刺激物は、しばらく避けた方が無難です。
また、腹部膨満感が強い場合は、ガスを発生させやすい豆類やいも類、炭酸飲料なども控えると良いでしょう。
- 内視鏡検査は苦しいですか
-
内視鏡検査に対して、苦しい、つらいというイメージをお持ちの方も多いかもしれませんが、近年では検査技術や機器が大きく進歩しています。
多くの医療機関では、患者さんの苦痛を和らげるために、鎮静剤(静脈麻酔)を使用して検査を行っています。
鎮静剤を使用すると、うとうとと眠っているようなリラックスした状態で検査を受けることができるため、苦痛や不快感をほとんど感じずに検査を終えることが可能です。
検査に対する不安が強い方は、鎮静剤の使用について事前に医師やクリニックに相談してください。
以上
次に読むことをお勧めする記事
【おなかのガスと下痢が続く症状 – 原因と検査の必要性】
膨満感と下痢の背景を別角度から整理すると、生活・食事と検査の位置づけがつながります。関連症状の自己管理にも役立ちます。
【腸の健康が体を支える 腸内環境を整える】
症状の原因について理解が深まったところで、腸内環境を整える方法についても知っておくと、より包括的な健康管理ができます。日常生活での予防策や改善方法をご紹介しています。
参考文献
Yamada E, Kuriyama H, Uchida E, Murata Y, Hata Y, Tagri M, Isozaki Y, Oyamada H, Ozawa Y, Ito T, Mizuki A. Association between endoscopic findings related to colonic diverticula and bowel habits: A multicenter study in Japan. Journal of gastroenterology and hepatology. 2017 Dec;32(12):1938-42.
Kinoshita Y, Ariyoshi R, Fujigaki S, Tanaka K, Morikawa T, Sanuki T. Endoscopic diagnosis of chronic diarrhea. DEN open. 2022 Apr;2(1):e53.
Matsumoto Y, Nadatani Y, Otani K, Higashimori A, Ominami M, Fukunaga S, Hosomi S, Kamata N, Kimura T, Fukumoto S, Tanaka F. Prevalence and risk factor for chronic diarrhea in participants of a Japanese medical checkup. JGH Open. 2022 Jan;6(1):69-75.
Tokuda Y, Takahashi O, Ohde S, Shakudo M, Yanai H, Shimbo T, Fukuhara S, Hinohara S, Fukui T. Gastrointestinal symptoms in a Japanese population: a health diary study. World Journal of Gastroenterology: WJG. 2007 Jan 28;13(4):572.
Ono M, Kato M, Miyamoto S, Tsuda M, Mizushima T, Ono S, Nakagawa M, Mabe K, Nakagawa S, Muto S, Shimizu Y. Multicenter observational study on functional bowel disorders diagnosed using Rome III diagnostic criteria in Japan. Journal of Gastroenterology. 2018 Aug;53(8):916-23.
Oshima T, Miwa H. Epidemiology of functional gastrointestinal disorders in Japan and in the world. Journal of neurogastroenterology and motility. 2015 Jul 3;21(3):320.
Otani K, Watanabe T, Takahashi K, Nadatani Y, Ominami M, Fukunaga S, Hosomi S, Kamata N, Tanaka F, Nagami Y, Taira K. Upper gastrointestinal endoscopic findings in functional constipation and irritable bowel syndrome diagnosed using the Rome IV criteria: a cross-sectional survey during a medical check-up in Japan. BMC gastroenterology. 2023 May 3;23(1):140.
Mizukami T, Sugimoto S, Masaoka T, Suzuki H, Kanai T. Colonic dysmotility and morphological abnormality frequently detected in Japanese patients with irritable bowel syndrome. Intestinal research. 2017 Apr 27;15(2):236.
Sasaki Y, Abe Y, Mizumoto N, Nomura E, Ueno Y. Small bowel endoscopic features of eosinophilic gastroenteritis. Diagnostics. 2022 Dec 30;13(1):113.
Hori K, Matsumoto T, Miwa H. Analysis of the gastrointestinal symptoms of uninvestigated dyspepsia and irritable bowel syndrome. Gut and liver. 2009 Sep 30;3(3):192.