胃腸の調子が悪いとき、急にトイレが近くなり下痢が続く経験をしたことはありませんか。原因がハッキリしないまま我慢を続けていると、普段の生活にも支障が出るかもしれません。
下痢がなぜ起こるのかを正しく理解し、検査やケアを受けることが大切です。
本記事では、下痢と大腸カメラや胃カメラなどの内視鏡検査との関係、考えられる背景要因について詳しく解説し、必要に応じた対策のヒントをお伝えします。
下痢と腸の仕組み~まず知っておきたい基礎
日常生活を送るなかで、便通の乱れは多くの人が経験する問題です。下痢の場合、急な腹痛や水様便によって体力や精神的な負担が大きくなるケースもあります。
こうした症状には、腸の動きや水分調整の問題など、さまざまな要因が関係しています。
腸が水分を吸収するメカニズム
体内に取り込んだ食べ物は小腸や大腸を通過しながら、栄養分と水分が吸収され、残ったカスが便となって排出されます。健康的な腸では、この過程で必要な量の水分をしっかり回収するため、便は適度な固さになります。
何らかの原因で水分の回収が追いつかないと、便が軟らかくなり下痢の状態となることが多いです。
腸管運動の異常
腸の動きが早すぎると十分に栄養や水分を吸収できず、水分の多いままの便が排出される一方で、運動が鈍りすぎると便が長くとどまりすぎて水分を吸収しすぎてしまい、便秘になることがあります。
下痢の場合は腸の動きが過剰になり、食べ物が急いで通過することが一因です。
腸内細菌バランスの乱れ
腸内には多種多様な細菌が生息しており、これらのバランスが体の調子を整えるうえで重要で、下痢を起こしやすい方は、腸内の善玉菌と悪玉菌の均衡が崩れている可能性があります。
乱れた食生活や過度のストレス、抗生物質の服用などが背景にあるときに、下痢症状が目立つケースは少なくありません。

下痢の急性と慢性
下痢が数日で治まり、短期間で急激に起こるものを急性下痢と呼び、3週間以上続くものは慢性下痢と呼ばれ、原因や治療法が異なります。慢性的に続く場合、何らかの疾患が隠れていることを疑い、早めに医療機関で検査を受けることが大切です。
腸と下痢に関連するポイント
| 内容 | 説明 |
|---|---|
| 水分吸収の低下 | 腸で水分を回収できず便が水っぽくなる |
| 腸管運動の亢進 | 食べ物が短時間で通過し、水分吸収が不足する |
| 腸内細菌バランスの崩れ | 悪玉菌の増加で便が緩くなる、ガスが増えることがある |
| 急性下痢と慢性下痢 | 発症期間や症状の持続期間によって原因や対策が異なる |
- 正しい排便リズムを知るために自分の便の状態を観察する
- 急性下痢の場合は原因となるウイルスや食中毒などを疑うことがある
- 長引く慢性下痢は炎症性腸疾患などの可能性を視野に入れる
よくある下痢の原因と関連する疾患
下痢を起こす原因は非常に幅広く、日常生活から内臓の疾患までさまざまで、軽度で済むものもあれば、精密検査が必要なケースもあります。原因を見極めるうえで、生活習慣の見直しと検査が重要です。
食中毒や感染症
ウイルスや細菌による感染が大腸や小腸で起こると、急に下痢になることがあり、ノロウイルス、ロタウイルス、サルモネラなど、特定のウイルスや細菌が主な原因です。
多くの場合、嘔吐や発熱などを伴い、集団感染として広がるケースもあります。
食事内容によるもの
脂っこい食事や香辛料の摂りすぎ、アルコールの過剰摂取などは腸への負担を大きくし、急性の下痢を誘発することがあります。
過敏性腸症候群を抱える方は特に、刺激物や冷たい食べ物を摂ると症状が悪化しやすいと感じることがあるかもしれません。
食事と下痢の関係
| 食品・習慣 | 下痢を引き起こしやすい理由 |
|---|---|
| 脂肪分の多い食事 | 消化に時間がかかり、腸への負担が大きい |
| 辛い調味料やアルコール | 腸を刺激し、腸管運動を亢進させる |
| アイスクリームや冷たい飲み物 | 冷たい刺激で腸の動きが乱れやすい |
| カフェインの過剰摂取 | 腸のぜん動運動を活性化し、便をゆるくする |
過敏性腸症候群やストレス
精神的なストレスや緊張が続くと、自律神経のバランスが乱れ、腸の動きも不安定になりやすいです。
過敏性腸症候群では、便が固くなったり、逆に緩くなったりを繰り返し、人前や外出時に下痢の不安を感じる方もいて、ストレスケアや生活リズムの改善が症状のコントロールに役立ちます。
- ストレスを溜め込まないように睡眠時間や休息を大切にする
- 腹痛や下痢に加えて心理的な不安が続くときは医療機関に相談する
- 食習慣の見直しとあわせて心身のケアを行うことが重要
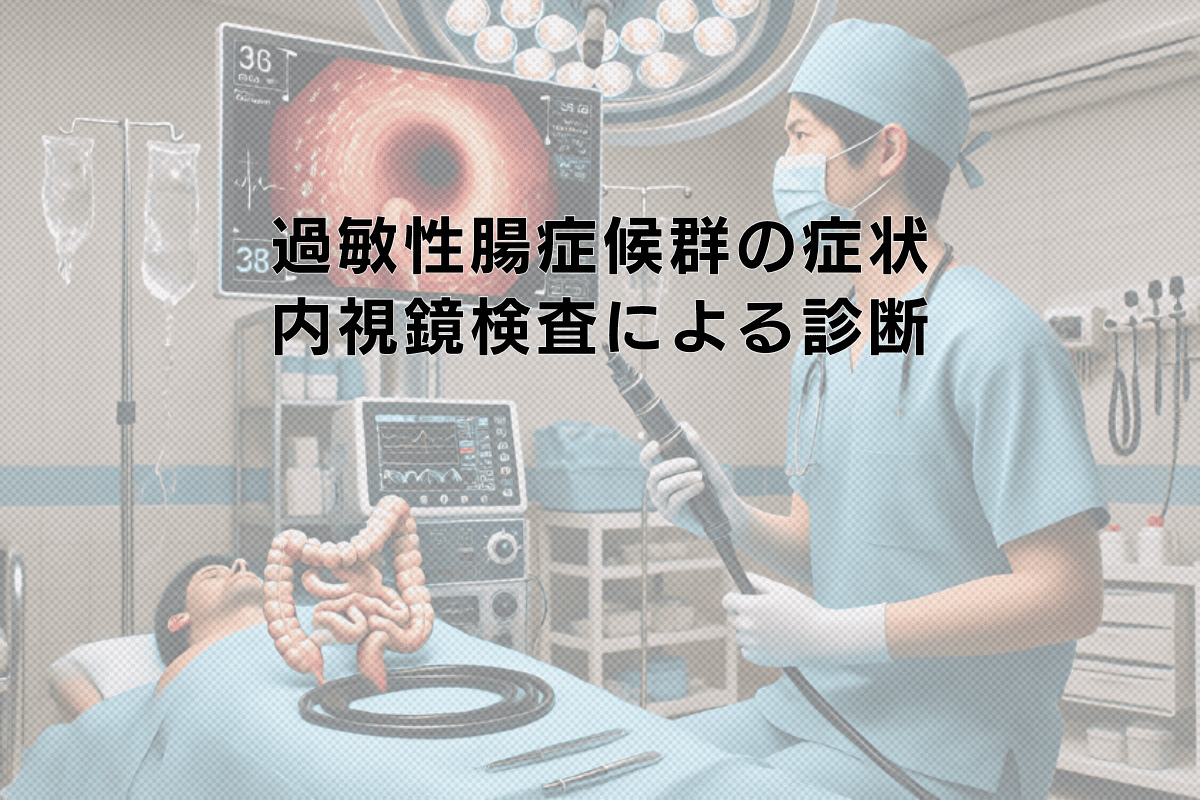
炎症性腸疾患やその他の病気
潰瘍性大腸炎やクローン病などの炎症性腸疾患は、長期的に下痢や腹痛、体重減少などをもたらすことが多いです。また、甲状腺機能亢進症や糖尿病の一部合併症など、全身的な病気が腸機能にも影響して下痢を起こすケースも考えられます。
内視鏡検査を含めた精密検査によって原因を特定することが求められる状況もあるでしょう。
下痢が疑われるとき内視鏡検査を考える意味
下痢が続くときは、病院で血液検査や画像診断などを行うことがあり、その中でも、直接腸の内部を観察できる内視鏡検査(大腸カメラや胃カメラ)は、原因の特定に大きく寄与します。
下痢が長期化していたり、体調が思わしくない状態が続くときは、医療機関での相談が大切です。
大腸カメラと小腸の検査
大腸カメラ検査では、肛門からスコープを挿入して大腸の内壁を直接確認でき、潰瘍やポリープ、炎症の有無などが分かり、必要に応じて組織の一部を採取することも可能です。
小腸の詳細を確認する場合にはカプセル内視鏡や小腸内視鏡などの手段もありますが、検査内容は症状や医師の判断によって異なります。

胃カメラで上部消化管を確認
下痢の原因が胃や十二指腸に起因している可能性も否定できません。胃カメラ検査では上部消化管を詳しく調べられるため、逆流性食道炎や胃潰瘍、十二指腸潰瘍など、消化器全般のトラブルを見逃しにくくなります。
慢性的に胃腸の不調がある場合は、併用して検査を受けることも検討されます。

内視鏡検査
| 種類 | 主な観察範囲 | 分かる可能性がある疾患・異常 |
|---|---|---|
| 大腸カメラ | 大腸全体(必要に応じて回盲部付近) | 潰瘍性大腸炎、クローン病、大腸ポリープ、大腸がん、出血部位など |
| 胃カメラ | 食道~胃~十二指腸 | 逆流性食道炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃がん、ピロリ菌感染など |
| カプセル内視鏡 | 小腸や一部大腸 | 小腸のポリープや炎症、出血、狭窄など |
内視鏡検査のメリットと注意点
内視鏡検査は直接腸内や胃の状態を観察できるため、下痢の原因を突き止めるうえで非常に有用ですが、検査前には腸内をきれいにする下剤の服用や、空腹状態で臨むなどの準備が必要です。
検査当日は若干の苦痛や違和感を感じることがありますが、医療機関によっては鎮静剤を使用して不快感を抑えられる場合もあります。
- 大腸カメラ検査前は腸内洗浄液の服用や食事制限がある
- 内視鏡検査の結果次第でさらに詳細な検査や治療方針を検討する
- 検査のリスクや鎮静剤の使用法などは事前に医師と相談する
検査を受けるタイミング
下痢が長引いて3週間以上続いたり、体重減少や発熱を伴う場合は、慢性下痢や炎症性疾患を疑う必要があります。こうした症状があるときは、早めに内科や消化器科を受診し、医師の判断で内視鏡検査を検討してください。
急性下痢であっても重症化して脱水症状が見られる場合は、入院が必要なこともあるため放置は危険です。
大腸カメラや胃カメラ検査の流れと準備
内視鏡検査を受ける前に、どのような手順や準備が必要なのかイメージしておくと安心につながります。ただ、下痢の原因を明らかにするためとはいえ、検査自体への不安を感じる方も多いかもしれません。
検査の流れを理解しておくと、心の準備がしやすくなるでしょう。
検査前の問診と注意事項
検査を予約するときや実際に病院を訪れるときには、普段の症状や服用中の薬などを医師に正確に伝える必要があります。特に血液をサラサラにする薬などを飲んでいる方は、検査時の出血リスクを考慮しなければなりません。
アレルギーや麻酔への不安がある場合も、事前に相談してください。
内視鏡検査前の確認
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 服用中の薬やサプリ | 抗血栓薬や降圧薬、糖尿病薬の調整が必要な場合がある |
| 過去の病歴・アレルギー | 麻酔や造影剤、消毒薬などに対するアレルギーの有無 |
| 食事制限 | 前日の夜以降は消化に負担のかからない食事にするなど医師の指示を守る |
| 飲水や下剤の使用 | 大腸カメラの場合は指定時間内に腸内洗浄液を飲み、腸を空っぽにする |
検査前日の食事管理
大腸カメラの場合、検査前日の夕食はおかゆなど消化にやさしい食品にして、就寝前から食事を控えるよう指示を受けることが多いです。
胃カメラの場合も、検査数時間前から飲食禁止となる場合があり、制限を守ることで、検査時に腸や胃の中が確認しやすくなり、正確な診断につながります。
- 大腸カメラでは透明な飲み物は許される場合があるが、色の濃いジュースは避ける
- 胃カメラ前は水のみなら飲んでよい時間帯が設定されることが多い
- 食事制限を守らないと検査がスムーズに進まず再検査になる可能性がある

検査当日の流れ
検査当日は、まず問診や体調確認を行い、検査着に着替え、大腸カメラの場合は必要に応じて鎮静剤の使用や局所麻酔を行い、検査室に移動してスコープを挿入します。
検査時間は個人差がありますが、おおむね15~30分程度です。胃カメラは口から内視鏡を入れる方法と、鼻から入れる方法があり、医師と相談して選びます。
大腸カメラと胃カメラの当日検査
| 内容 | 大腸カメラ | 胃カメラ |
|---|---|---|
| 検査前の準備 | 下剤服用や腸内洗浄液を飲んで腸を空にする | 指定時間までに絶食・必要に応じて鎮静剤 |
| スコープの挿入方法 | 肛門から挿入 | 口または鼻から挿入 |
| 所要時間 | 15~30分程度(個人差あり) | 5~15分程度(観察範囲や状態による) |
| 検査後の注意点 | しばらく休憩してお腹の張りが落ち着いてから帰宅 | 鎮静剤使用の有無で帰宅時の注意が異なる |
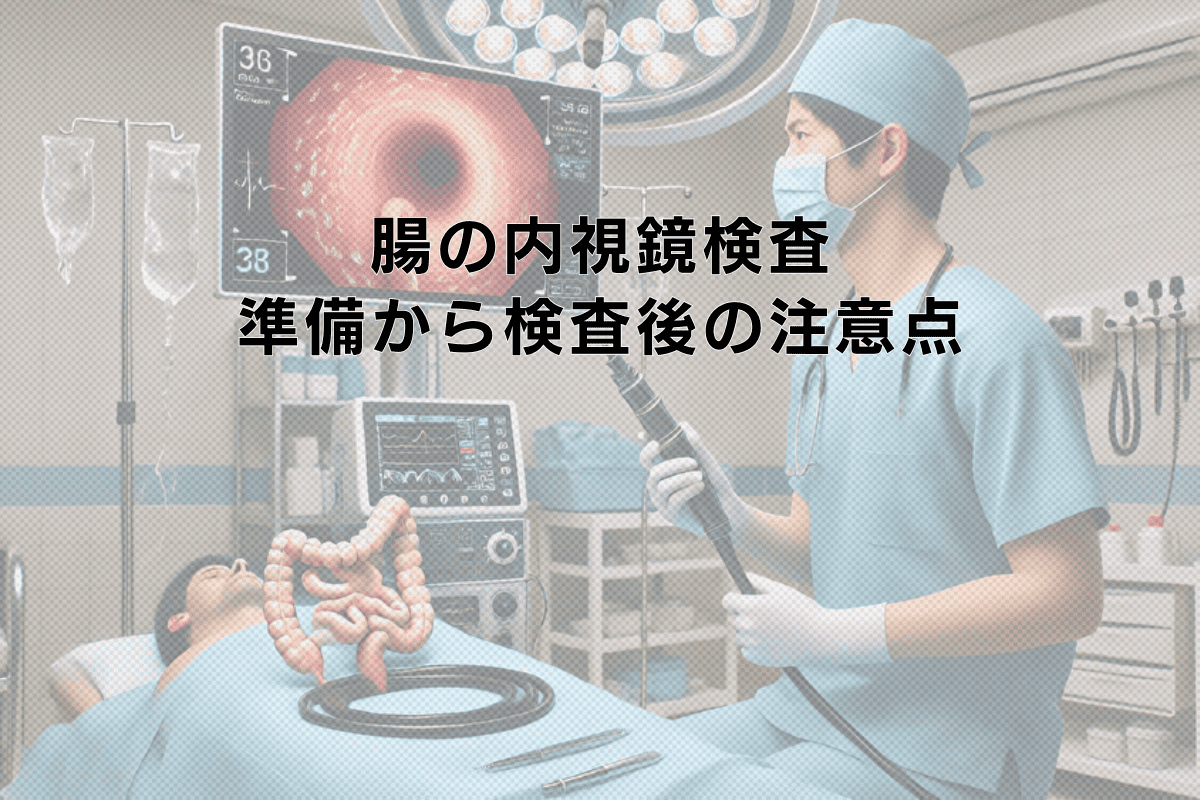
検査後の経過観察
検査でポリープ切除や組織採取を行った場合は、検査後に出血や腹痛などの症状が出る可能性があり、帰宅後も腹部の様子に注意し、異常を感じた場合はすぐに医療機関に連絡してください。
大腸カメラ後はガスを入れて腸をふくらませているので、お腹に張りが残ることがありますが、徐々に解消するケースが多いです。
下痢を緩和・予防する食事と生活習慣
内視鏡検査で明らかな異常が見つかった場合、医師の指導に沿って治療が進み、異常が見つからなかった場合も、普段の食事や生活習慣を改善して腸の調子を整えることが大切です。
食事で意識したいポイント
胃腸に負担をかけず、バランス良く栄養を摂取することが理想的で、辛いものや脂っこい料理は控えめにし、野菜や果物、発酵食品なども組み合わせると良いでしょう。
特に腸内細菌に良い影響を与えるヨーグルトや納豆などは、継続的に取り入れると下痢の予防につながる可能性があります。
腸にやさしい食材と栄養
| 食材 | 特徴 |
|---|---|
| ヨーグルト | 乳酸菌による腸内環境の整備 |
| 納豆・味噌などの発酵食品 | ビフィズス菌などの善玉菌を増やし、腸の動きを穏やかに保つ |
| 根菜類 | 食物繊維が豊富で便の形を整え、腸内の老廃物を排出しやすくする |
| りんごやバナナ | 水分量と食物繊維のバランスが良く、お腹を冷やしにくい |
- 辛味や刺激の強い調味料は下痢を誘発しやすいため注意する
- 炭水化物やたんぱく質、脂質を偏りなく摂ることで腸の働きを安定させる
- 一度に大量に食べるよりも、少量ずつ複数回に分けて食べるほうが負担が少ない

規則正しい生活リズムとストレスケア
自律神経が乱れると腸の動きも乱れやすくなります。生活リズムが崩れ、不規則な食事や睡眠不足が続くと下痢が増える場合があるので、なるべく毎日同じ時間に起きて、決まった時間に食事を摂ることが理想です。
また、ストレスは腸の状態に直結するため、適度な運動や趣味を通じてリラックスできる方法を見つけると良いでしょう。
水分補給と脱水対策
下痢が続くと体から水分や電解質が失われ、脱水状態に陥るリスクがあるので、スポーツドリンクや経口補水液などを上手に使って、水分とミネラルの補給を心がけると安心です。
下痢症状が強いときは、無理に固形物を摂るよりも消化によいスープやゼリー状の食品から少しずつ栄養を取り入れることも選択肢です。
- こまめな水分補給を意識して尿の色をチェックする
- カフェインやアルコールは利尿作用があり、脱水を招きやすいので控えめにする
- 食事が摂りにくいときはスープやゼリー飲料で対応しながら徐々に回復を目指す
下痢のときに避けたい生活習慣
過度の飲酒やたばこ、寝不足は腸への刺激を増やす原因になり、アルコールは胃液や消化液の分泌バランスを乱しやすいため、下痢が頻発している期間はできるだけ量を控えるか休肝日を設けることが望ましいです。
また、タバコのニコチンも血管収縮を引き起こし、胃腸の粘膜に負担をかけます。
内視鏡検査で得られた結果に応じた治療と対策
内視鏡検査を受けると、大腸や胃の内部の状態を直接確認できるため、炎症や出血、腫瘍などが見つかるかもしれません。診断結果次第で治療法は大きく変わりますが、下痢の症状に直結するケースも多いので、正しい対策を続けることが大切です。
ポリープや炎症が見つかった場合
大腸ポリープが見つかった場合は、検査時に内視鏡で切除できる場合があります。
一方で潰瘍性大腸炎やクローン病などの炎症性腸疾患が判明した場合は、薬物療法や食事療法など長期的な治療計画が必要になることが多いです。
主な治療アプローチ
| 疾患名 | 治療方法 | 下痢症状との関連 |
|---|---|---|
| 大腸ポリープ | 内視鏡的切除、定期的な経過観察 | サイズや場所によっては便通に影響する |
| 潰瘍性大腸炎 | 5-ASA製剤やステロイド、免疫調節剤など | 慢性的な下痢や血便を伴うことが多い |
| クローン病 | 抗TNFα製剤や栄養療法、外科手術など | 全消化管にわたる炎症で下痢が続く場合がある |
| 感染性腸炎 | 抗生物質や整腸剤、経口補水など | 細菌やウイルスの種類により症状の度合いが変化 |
内視鏡検査で異常がなかった場合
検査で異常が見つからないケースも珍しくなく、そういったときは、過敏性腸症候群やストレス、食習慣が原因である可能性が高いです。
医師から整腸剤や生活習慣の改善を勧められる場合があり、規則正しい食生活やストレス対策を強化することで症状が和らぐことが期待できます。
- 過敏性腸症候群は精神的な要素も関係するため、心のケアがポイント
- 生検や血液検査を行っても確定診断に至らないときは経過観察しつつ再検査を考慮する
- 異常が見つからずとも症状を軽視せず、日常生活での対策を続けることが重要
投薬の選択と管理
下痢止めや整腸剤、抗生物質など、薬を処方される場合は指示をしっかりと守る必要があり、自己判断で服用を中断したり、過剰に飲んだりすると症状が悪化するおそれがあります。
また、抗生物質の使用で腸内細菌のバランスが乱れることもあるため、状況に応じて医師や薬剤師と相談しながら進めることが望ましいです。
再検査やフォローアップ
ポリープ切除後や炎症性疾患の寛解状態など、経過観察が必要な場面では定期的な内視鏡検査や診察が勧められる場合があります。
再発や新たな異常を見逃さず、早期発見・早期対応するためにも、医療機関から案内があった場合は適切にフォローアップを受けると安心です。
よくある質問
最後に、下痢の原因と内視鏡検査に関して患者さんの方から寄せられる代表的な疑問について回答します。症状や治療法は個々人で異なるため、実際に当てはまりそうな場合は早めに専門家に相談してください。
- 下痢が続いているのですが、何日くらいで病院に行くべきですか?
-
一般的には3日~1週間程度で落ち着く場合が多いですが、下痢が3週間以上続くようなら慢性下痢を疑い、急激な脱水や発熱など重症化の兆候がある場合は、早めに受診したほうが安心です。
- 内視鏡検査は痛みが強いと聞きますが、本当でしょうか?
-
個人差はありますが、鎮静剤を使うことで痛みや不快感はかなり軽減できます。最近では挿入技術の向上により、比較的苦痛が少ない形で検査を受けられる医療機関も増えています。
- 下痢体質の改善にサプリメントは効果がありますか?
-
整腸を目的とした乳酸菌サプリやビフィズス菌サプリなどが市販されています。腸内環境を整えるうえでプラスになる可能性はありますが、根本原因がほかにある場合はサプリだけで改善しないことも考えられます。
- 大腸カメラで異常がなかった場合も不安なのですが、どうすればいいですか?
-
異常が見つからない場合は過敏性腸症候群や生活習慣が原因の可能性があります。医師の指導に従い、ストレス管理や食事・運動の見直しなどを継続しながら、症状が続く場合はフォローアップ検査を受けると安心です。
次に読むことをお勧めする記事
【毎日の下痢症状が続くときの大腸内視鏡検査による診断基準】
頻回の下痢が続くと“検査した方が良いの?”と不安になるもの。実際の診断基準と検査所見を具体例で解説しているので、検査を受けるか迷う方の参考になります。
【腸にいい食べ物を知る 腸内環境を整える方法】
下痢の原因を学んだ皆さんには、腸の健康を根本から支える食事と生活習慣の知識も合わせて持っていただくと、より包括的な理解ができます。
参考文献
Kinoshita Y, Ariyoshi R, Fujigaki S, Tanaka K, Morikawa T, Sanuki T. Endoscopic diagnosis of chronic diarrhea. DEN open. 2022 Apr;2(1):e53.
Yamada E, Kuriyama H, Uchida E, Murata Y, Hata Y, Tagri M, Isozaki Y, Oyamada H, Ozawa Y, Ito T, Mizuki A. Association between endoscopic findings related to colonic diverticula and bowel habits: A multicenter study in Japan. Journal of gastroenterology and hepatology. 2017 Dec;32(12):1938-42.
Saito Y, Kodashima S, Matsuda T, Matsuda K, Fujishiro M, Tanaka K, Kobayashi K, Katada C, Horimatsu T, Muto M, Ohtsuka K. Current status of diagnostic and therapeutic colonoscopy in Japan: The Japan Endoscopic Database Project. Digestive Endoscopy. 2022 Jan;34(1):144-52.
Shen B, Khan K, Ikenberry SO, Anderson MA, Banerjee S, Baron T, Ben-Menachem T, Cash BD, Fanelli RD, Fisher L, Fukami N. The role of endoscopy in the management of patients with diarrhea. Gastrointestinal endoscopy. 2010 May 1;71(6):887-92.
Fine KD, Seidel RH, Do K. The prevalence, anatomic distribution, and diagnosis of colonic causes of chronic diarrhea. Gastrointestinal endoscopy. 2000 Mar 1;51(3):318-26.
May A, Manner H, Schneider M, Ipsen A, Ell C, null for the CEDAP-Plus Study Group. Prospective multicenter trial of capsule endoscopy in patients with chronic abdominal pain, diarrhea and other signs and symptoms (CEDAP-Plus Study). Endoscopy. 2007 Jul;39(07):606-12.
Schiller LR, Pardi DS, Sellin JH. Chronic diarrhea: diagnosis and management. Clinical Gastroenterology and Hepatology. 2017 Feb 1;15(2):182-93.
Wei SC, Hung CC, Chen MY, Wang CY, Chuang CY, Wong JM. Endoscopy in acquired immunodeficiency syndrome patients with diarrhea and negative stool studies. Gastrointestinal endoscopy. 2000 Apr 1;51(4):427-32.
Wahnschaffe U, Ignatius R, Loddenkemper C, Liesenfeld O, Muehlen M, Jelinek T, Burchard GD, Weinke T, Harms G, Stein H, Zeitz M. Diagnostic value of endoscopy for the diagnosis of giardiasis and other intestinal diseases in patients with persistent diarrhea from tropical or subtropical areas. Scandinavian journal of gastroenterology. 2007 Jan 1;42(3):391-6.
Ingle SB, Adgaonkar BD, Hinge CR. Microscopic colitis: Common cause of unexplained nonbloody diarrhea. World journal of gastrointestinal pathophysiology. 2014 Feb 15;5(1):48.










