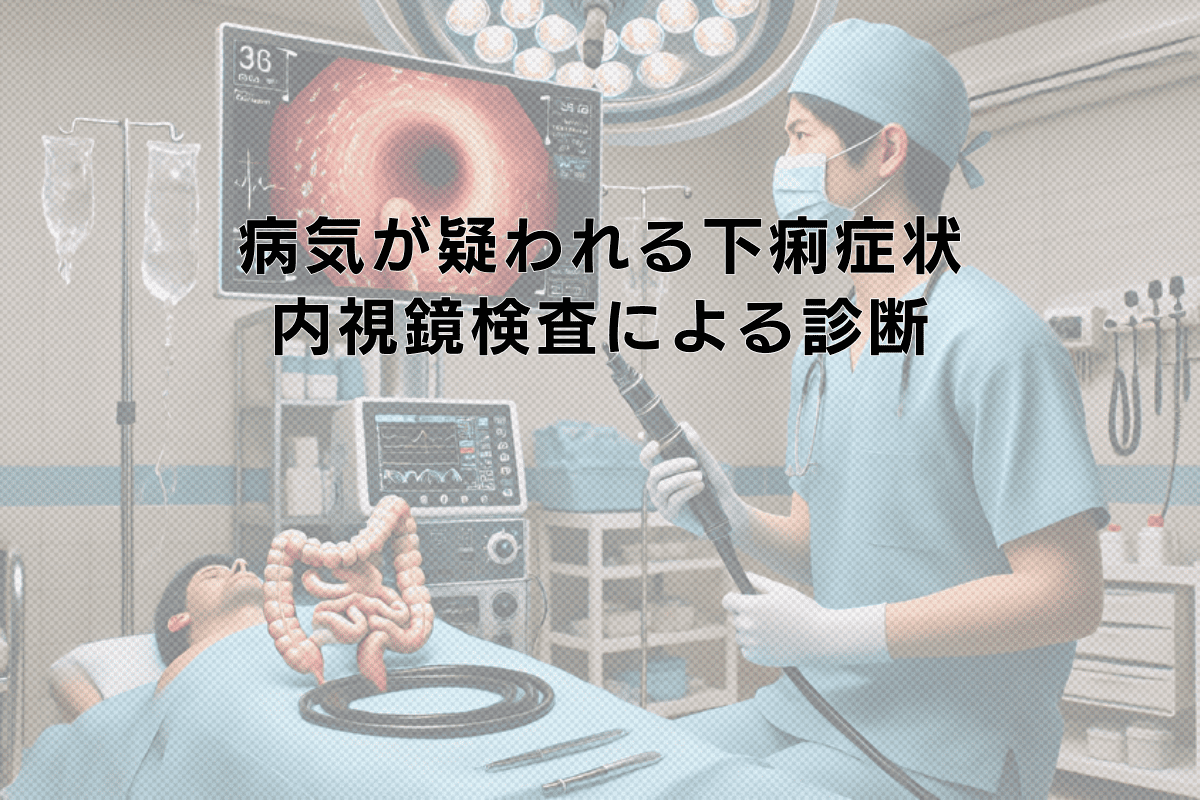下痢が続いていて、もしかしたら何か病気なのではと心配されていませんか。あるいは、下痢の症状から考えられる病名について調べている方もいらっしゃるかもしれません。
この記事では、病気が疑われる下痢の症状、その原因となる可能性のある病気、そして診断に重要な役割を果たす内視鏡検査について、詳しく解説します。
下痢とは?基本的な理解
下痢は多くの人が経験する症状ですが、その定義や体内で何が起こっているのかを正確に理解している方は少ないかもしれません。ここでは、下痢の基本的な知識について解説し、症状への理解を深めます。
下痢の定義と体内で起こること
一般的に下痢とは、便中の水分量が異常に増加し、液状またはそれに近い形状の便が頻回に排出される状態です。
健康な状態では、食べた物は胃や小腸で消化・吸収され、大腸で水分が吸収されて固形の便となりますが、水分の吸収がうまくいかなかったり、腸管からの水分分泌が過剰になったりすると、便が固まらずに下痢として排出されます。
また、腸の動きが活発になりすぎると、便が腸を通過する時間が短くなり、十分に水分が吸収されないまま排出されることもあります。
急性下痢と慢性下痢の違い
下痢は、症状が続く期間によって大きく急性下痢と慢性下痢に分けられ、急性下痢は、一般的に発症から2週間以内に症状が改善するもので、慢性下痢は、症状が4週間以上続く場合です。
2週間から4週間の間は遷延性下痢と呼ぶこともあります。原因も異なり、急性下痢は感染症や食あたりが多いのに対し、慢性下痢の場合は過敏性腸症候群や炎症性腸疾患など、より専門的な対応を要する病気が隠れている可能性があります。
急性下痢と慢性下痢の主な特徴
| 特徴 | 急性下痢 | 慢性下痢 |
|---|---|---|
| 持続期間 | 通常2週間以内 | 通常4週間以上 |
| 主な原因 | ウイルス・細菌感染、食中毒、薬剤など | 過敏性腸症候群、炎症性腸疾患、吸収不良症候群など |
| 対応 | 水分補給、安静、対症療法が中心 | 原因特定のための検査、専門的治療が必要な場合が多い |
下痢に伴いやすい症状
下痢の際には、便の異常だけでなく、様々な随伴症状が現れることがあり、腹痛は下痢とともによく見られる症状で、腸の過剰な動きや炎症によって起きる症状です。また、吐き気や嘔吐を伴うこともあり、特に感染性の下痢ではよく見られます。
発熱も、体が感染と戦っているサインとして現れることがあり、症状の有無や程度は、下痢の原因を探る上で重要な手がかりです。
日常生活における下痢の一般的な原因
病気とまではいかなくても、日常生活の中には下痢を引き起こす可能性のある要因がいくつか存在あり、食べ過ぎや飲み過ぎ、特に脂っこい食事や刺激の強い香辛料の摂取は、消化器に負担をかけ、下痢を誘発する要因です。
また、冷たい飲み物や食べ物を一度に大量に摂ることも、腸を刺激して動きを活発にし、下痢の原因となることがあり、精神的なストレスや緊張も自律神経のバランスを乱し、腸の機能に影響を与えて下痢を起こすことが知られています。
生活習慣の乱れや睡眠不足なども、間接的に腸の健康に影響を及ぼす可能性があります。
- 暴飲暴食
- 冷たい飲食物の過剰摂取
- 精神的ストレス
- アルコールの多量摂取

下痢を起こす主な原因
下痢の症状は共通していても、背後にある原因は多岐にわたり、原因を正しく理解することは、対処法を見つけるための第一歩です。
感染性下痢 ウイルスや細菌
感染性下痢は、ウイルス、細菌、あるいは寄生虫などの病原体が腸管に感染することによって起き、病原体は、汚染された食品や水を介して口から入ることが一般的です。
代表的な原因ウイルスにはノロウイルスやロタウイルスがあり、特に冬場に流行しやすい傾向があります。細菌性のものでは、サルモネラ菌、カンピロバクター、病原性大腸菌(O-157など)がよく知られています。
感染症は、激しい下痢のほか、嘔吐、腹痛、発熱などを伴うことが多く、集団発生することもあります。
主な感染性下痢の原因微生物
| 種類 | 代表的な病原体 | 主な症状 |
|---|---|---|
| ウイルス | ノロウイルス、ロタウイルス | 水様下痢、嘔吐、発熱 |
| 細菌 | サルモネラ菌、カンピロバクター、O-157 | 血便を伴う下痢、腹痛、発熱 |
| 寄生虫 | クリプトスポリジウム、アメーバ赤痢 | 持続する下痢、腹部不快感 |
非感染性下痢 食事やストレス
感染以外の要因でも下痢は起こります。食事内容が原因となることも多く、例えば乳製品に含まれる乳糖を分解する酵素が少ない乳糖不耐症の人は、牛乳を飲むと下痢をすることがあります。
また、人工甘味料(ソルビトールなど)を多く含む食品の摂取も、浸透圧性の下痢を引き起こすことがあり、暴飲暴食や脂質の多い食事、アルコールの過剰摂取も消化不良や腸への刺激となり、下痢の原因です。
さらに、精神的なストレスは自律神経のバランスを崩し、腸の運動を異常に亢進させたり、逆に停滞させたりして、下痢や便秘を起こし、過敏性腸症候群(IBS)の一つのタイプでも見られます。
薬剤性下痢 抗生物質など
特定の薬剤の副作用として下痢があり、これを薬剤性下痢と呼び、抗生物質(抗菌薬)は、腸内の良い細菌も悪い細菌も区別なく殺してしまうため、腸内細菌叢のバランスが崩れ、下痢を起こす要因の一つです。
抗生物質関連下痢症とも呼ばれ、時にはクロストリディオイデス・ディフィシル(旧称クロストリジウム・ディフィシル)という菌が異常増殖し、偽膜性大腸炎という重篤な腸炎を起こすこともあります。
その他にも、マグネシウムを含む制酸薬、一部の降圧薬、抗がん剤、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)なども下痢の原因となることがあります。
下痢を起こしやすい薬剤
| 薬剤の種類 | 代表的な薬剤(一般名) | 備考 |
|---|---|---|
| 抗生物質 | アモキシシリン、セフェム系薬剤 | 腸内細菌叢の乱れ |
| 制酸薬 | 水酸化マグネシウム | 浸透圧性の作用 |
| その他 | 一部の抗がん剤、非ステロイド性抗炎症薬 | 腸管粘膜への直接作用など |
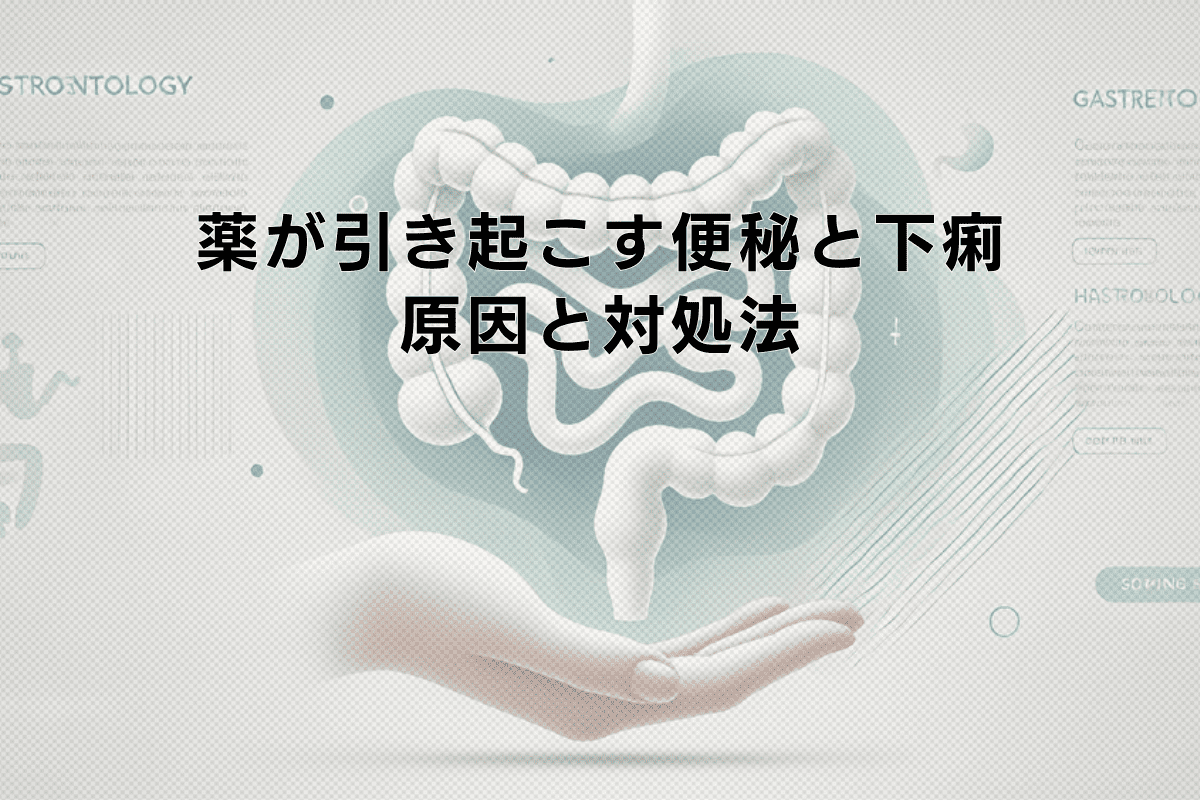
特定の食品や成分に対する不耐性
特定の食品やその成分に対して体がうまく対応できず、下痢などの消化器症状を起こす状態を食物不耐症と呼び、食物アレルギーとは異なり、免疫反応が直接関与するわけではありません。代表的なものに、乳糖不耐症があります。
乳糖は牛乳や乳製品に含まれる糖の一種で、分解するラクターゼという酵素の活性が低いと、乳糖が分解・吸収されずに大腸に達し、浸透圧性の下痢やガスの発生を起こします。
また、グルテン不耐症(セリアック病とは異なる)や、果物や蜂蜜に多く含まれるフルクトース(果糖)の吸収不良なども、下痢の原因となることがあります。
- 乳糖(牛乳、ヨーグルト、チーズなど)
- グルテン(小麦、大麦、ライ麦など)
- フルクトース(果物、蜂蜜、一部の加工食品)
注意すべき下痢のサイン
ほとんどの下痢は数日で自然に治まりますが、中には注意が必要な、あるいは何らかの病気が隠れているサインとなる下痢もあります。ここでは、医療機関の受診を検討すべき下痢の危険な兆候について説明します。
長引く下痢 2週間以上
通常、ウイルスや細菌による急性下痢は数日から1週間程度で改善に向かいます。
下痢の症状が2週間以上続く場合は遷延性下痢、さらに4週間以上続く場合は慢性下痢とされ、単なる食あたりや一時的な体調不良ではない可能性を考えることが必要です。
慢性的な下痢は、過敏性腸症候群(IBS)、炎症性腸疾患(クローン病や潰瘍性大腸炎)、吸収不良症候群、あるいはまれに大腸がんなどの病気が原因となっていることがあります。
原因がはっきりしないまま下痢が長引く場合は、自己判断せずに消化器専門医の診察を受けることを強く推奨し、検査を通じて、下痢の原因となっている病気や病名を特定することが重要です。
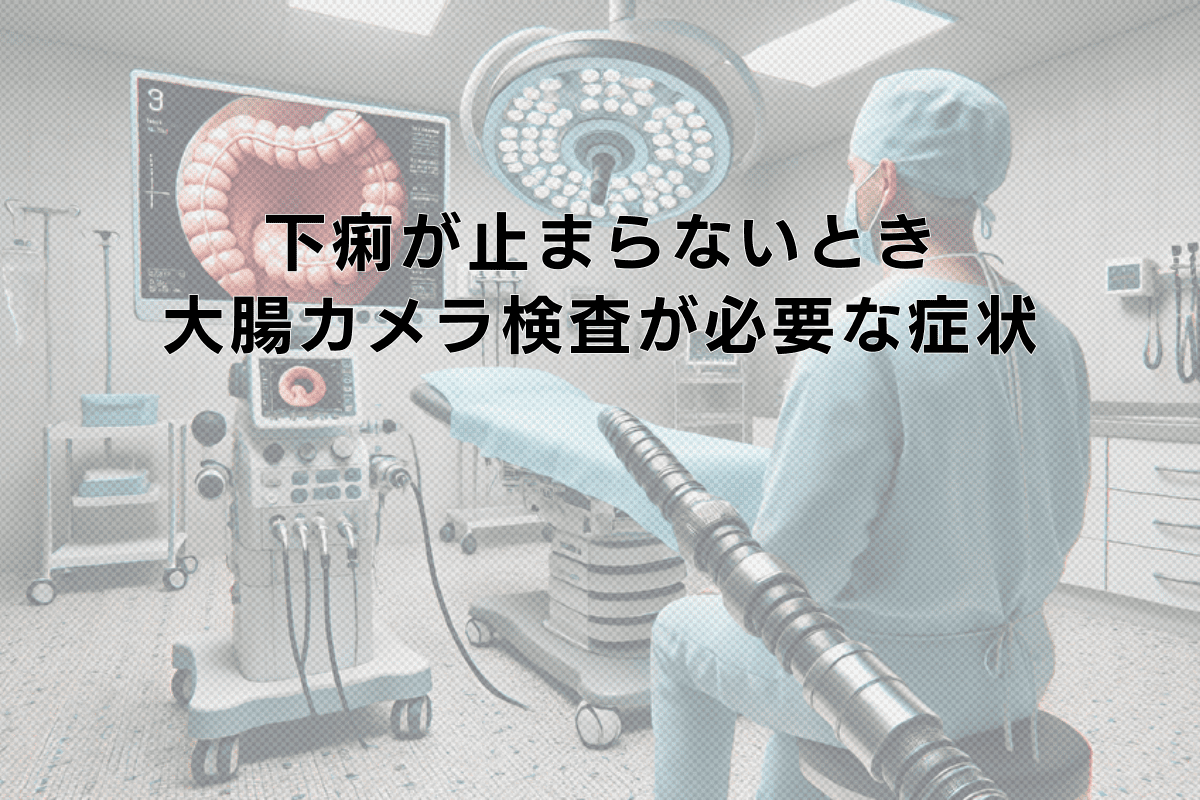
血便や粘液便の出現
便に血が混じる血便や、ゼリー状の粘液が付着する粘液便は、消化管のどこかに出血や炎症があることを示す重要なサインです。鮮やかな赤い血便は、肛門に近い大腸や直腸からの出血(痔や裂肛、大腸炎、大腸がんなど)を示唆します。
また、黒っぽいタール状の便(黒色便)は、胃や十二指腸など上部消化管からの出血が考えられ、粘液便は、炎症性腸疾患や感染性腸炎などで見られます。
症状がある場合は、消化管の病気を疑い、速やかに医療機関を受診し、原因を特定するための検査(特に内視鏡検査)を受けてください。
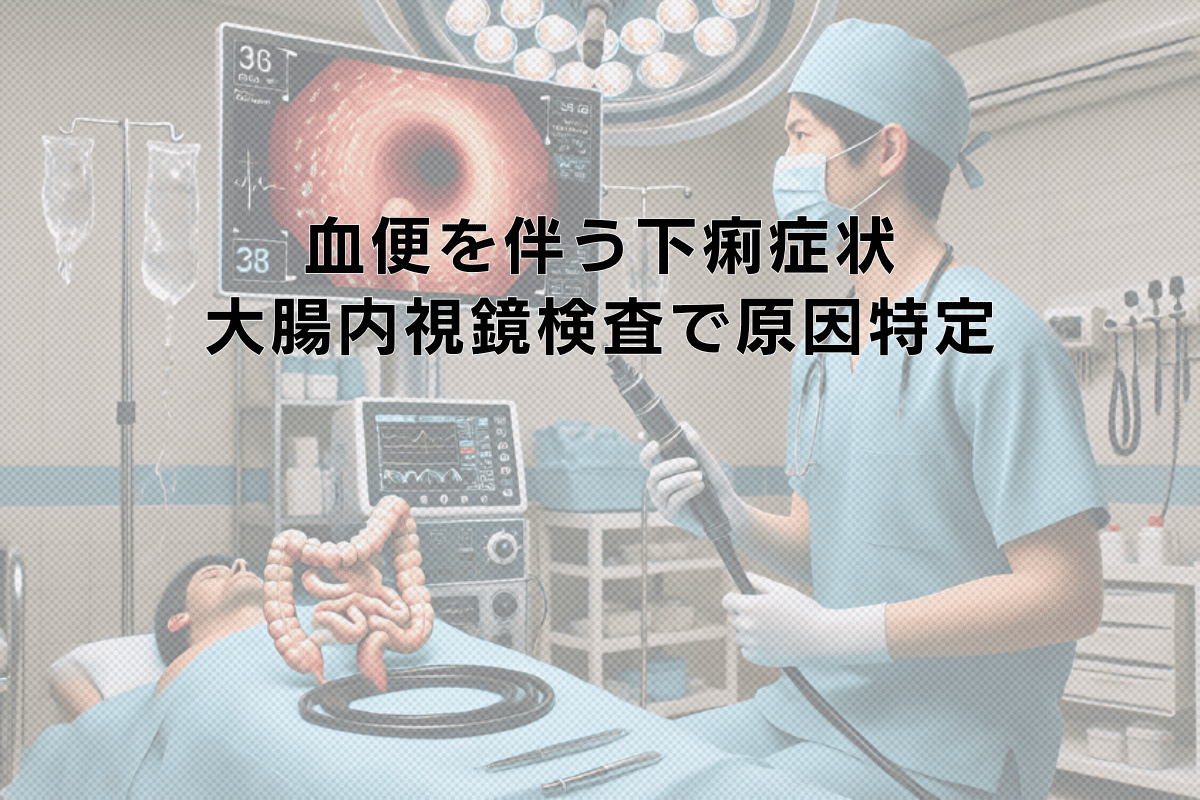
発熱や激しい腹痛を伴う場合
下痢とともに38度以上の高熱が出る場合や、我慢できないほどの激しい腹痛がある場合も注意が必要です。
重症の感染性腸炎(細菌性腸炎など)、虫垂炎、憩室炎、虚血性腸炎、あるいは炎症性腸疾患の急性増悪など、緊急の対応を要する病気のサインである可能性があります。
特に、腹痛が持続的で、押すと特定の場所に強い痛みを感じる(限局性圧痛)場合や、お腹全体が硬くなる(筋性防御)場合は、腹膜炎などの重篤な状態に進行している可能性も考えられます。
警戒すべき下痢の症状チェック
| 症状 | 考えられる状態・病気 | 対応の目安 |
|---|---|---|
| 2週間以上続く下痢 | 慢性下痢(IBS、IBDなど) | 医療機関を受診 |
| 血便・粘液便 | 消化管出血、炎症性疾患、腫瘍など | 速やかに医療機関を受診 |
| 高熱・激しい腹痛 | 重症感染症、虫垂炎、腸閉塞など | 緊急受診を検討 |
| 体重減少、脱水 | 吸収不良、悪性腫瘍、重症下痢 | 医療機関を受診 |
体重減少や脱水症状
下痢が長く続くことで、意図しない体重減少が見られる場合や、脱水症状(口の渇き、皮膚の乾燥、尿量の著しい減少、めまい、立ちくらみなど)が現れた場合も、医療機関への受診が必要です。
体重減少は、栄養の吸収がうまくいっていない(吸収不良症候群)、炎症によって体が消耗している(炎症性腸疾患など)、あるいは悪性腫瘍が存在する可能性などを示唆します。
6ヶ月で5%以上の意図しない体重減少は、詳細な検査が必要なサインで、脱水症状は、高齢者や乳幼児では急速に進行し、重篤な状態に至ることがあるため、早期の水分・電解質補給(経口補水液や点滴)が重要です。
下痢が続く場合に考えられる病気
一時的な下痢は誰にでも起こり得ますが、症状が長引いたり、特定のパターンを示したりする場合、背景に何らかの病気が隠れている可能性があります。
過敏性腸症候群(IBS)
過敏性腸症候群(Irritable Bowel Syndrome, IBS)は、大腸や小腸に明らかな炎症や潰瘍などの器質的な異常が見られないにもかかわらず、腹痛や腹部不快感を伴う下痢や便秘が慢性的に続く病気です。
ストレスや生活習慣の乱れ、腸内細菌叢の変化などが関与していると考えられています。
IBSは症状によっていくつかのタイプに分類され、下痢が主な症状である下痢型IBS、便秘が主な便秘型IBS、下痢と便秘を繰り返す混合型IBSなどです。
下痢型IBSでは、特に通勤中や試験前など、緊張する場面で急な便意や腹痛、下痢が起こりやすいという特徴があります。
炎症性腸疾患(IBD) クローン病と潰瘍性大腸炎
炎症性腸疾患(Inflammatory Bowel Disease, IBD)は、消化管に原因不明の慢性的な炎症を起こす病気の総称で、主にクローン病と潰瘍性大腸炎の二つがあります。
免疫系の異常が関与していると考えられており、若年層に発症しやすい傾向があり、潰瘍性大腸炎は、主に大腸の粘膜にびらんや潰瘍ができる病気で、血便、粘液便、下痢、腹痛などが主な症状です。
炎症は潰瘍性大腸炎では直腸から連続的に広がる特徴がある 一方、クローン病は、口から肛門までの消化管のどの部位にも炎症や潰瘍が起こりうる病気で、小腸や大腸にみられます。
腹痛、下痢、体重減少、発熱などが主な症状で、痔瘻や肛門周囲膿瘍などの肛門病変を合併することも少なくありません。 どちらの病気も、症状が良くなったり(寛解期)、悪くなったり(活動期)を繰り返すことが多く、長期的な管理が必要です。
過敏性腸症候群(IBS)と炎症性腸疾患(IBD)の主な違い
| 項目 | 過敏性腸症候群(IBS) | 炎症性腸疾患(IBD) |
|---|---|---|
| 腸の器質的変化 | なし(機能的な問題) | あり(炎症、潰瘍など) |
| 主な症状 | 腹痛、下痢、便秘(ストレスで増悪しやすい) | 血便、下痢、腹痛、体重減少、発熱 |
| 主な検査 | 症状評価、除外診断 | 内視鏡検査、生検、画像検査 |
感染性腸炎の遷延
通常、ウイルスや細菌による感染性腸炎は数日から数週間で治癒しますが、一部のケースでは症状が長引くことがあります。
「感染後過敏性腸症候群」と呼ぶこともあり、感染が治った後も腸の知覚過敏や運動異常が残り、下痢や腹痛が続く状態です。特にカンピロバクター腸炎などの後に起こりやすいとされています。
また、免疫力が低下している方や、特定の種類の細菌(例えば、クロストリディオイデス・ディフィシル)による感染では、治療が難航し、下痢が慢性化することもあります。
寄生虫感染(ランブル鞭毛虫症など)も、慢性的な下痢の原因です。
大腸がんやその他の腫瘍性疾患
慢性的な下痢の原因として、頻度は高くありませんが、大腸がんやその他の腫瘍性疾患の可能性も念頭に置く必要があります。
0歳以上で、原因不明の下痢が続く、便に血が混じる、便が細くなった、体重が減少するなどの症状がある場合は注意が必要です。
大腸がんは、大腸の粘膜に発生する悪性腫瘍で、進行すると腸管を狭窄させたり、出血したりすることで下痢や便秘、血便などの症状を起こします。また、カルチノイド腫瘍やリンパ腫など、まれな腫瘍も下痢の原因となることがあります。

内視鏡検査の役割と種類
下痢の原因を特定し、適切な治療法を選択するためには、消化管の状態を直接観察することが有効な場合があり、行われるのが内視鏡検査です。
内視鏡検査が診断に役立つ理由
内視鏡検査は、先端に小型カメラが付いた細長い管(スコープ)を体内に挿入し、食道、胃、十二指腸、あるいは大腸といった消化管の内部を直接観察する検査です。
医師はモニターに映し出される鮮明な画像を見ながら、粘膜の色調、凹凸、血管の走行、潰瘍やポリープ、がんなどの病変の有無を確認し、X線検査などでは分かりにくい微細な変化も捉えることができます。
また、内視鏡検査の大きな利点は、疑わしい部分が見つかった場合に、その場で組織の一部を採取(生検)できることです。
採取した組織を顕微鏡で詳しく調べる病理検査を行うことで、炎症の程度や種類、良性・悪性の鑑別など、より正確な診断が可能になります。
上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)
上部消化管内視鏡検査は、一般的に「胃カメラ」として知られていて、口または鼻から内視鏡を挿入し、食道、胃、十二指腸の一部を観察し、胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、逆流性食道炎、食道がん、胃がんなどの病気の診断に役立ちます。
下痢が主症状の場合でも、例えば胃の病気が原因で消化吸収不良が起こっている可能性や、広範囲な炎症が上部消化管にも及んでいる場合(クローン病など)には、重要な情報を提供します。
下部消化管内視鏡検査(大腸カメラ)
下部消化管内視鏡検査は、大腸カメラや大腸ファイバーとも呼ばれ、肛門から内視鏡を挿入し、直腸から盲腸までの大腸全体、場合によっては小腸の一部(回腸末端)まで観察します。
慢性的な下痢、血便、腹痛などの症状がある場合に、原因を調べるために行われ、検査によって、大腸がん、大腸ポリープ、炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病)、感染性腸炎、虚血性腸炎、大腸憩室症などの病気を診断できます。
検査中にポリープが見つかった場合は、その場で切除することも可能です。
主な内視鏡検査の種類と観察範囲
| 検査名 | 通称 | 観察範囲 |
|---|---|---|
| 上部消化管内視鏡検査 | 胃カメラ | 食道、胃、十二指腸 |
| 下部消化管内視鏡検査 | 大腸カメラ | 直腸、結腸、盲腸、回腸末端 |
| 小腸内視鏡検査 | ダブルバルーン内視鏡など | 小腸全体(上部・下部から挿入) |
| カプセル内視鏡 | 飲むカメラ | 主に小腸(胃・大腸用もある) |
カプセル内視鏡や小腸内視鏡
従来の胃カメラや大腸カメラでは観察が難しかった小腸の病変を調べるために開発されたのが、カプセル内視鏡や小腸内視鏡です。
カプセル内視鏡は、ビタミン剤のような小型のカプセル型カメラを飲み込むだけで、消化管の蠕動運動によって移動しながら小腸内部を撮影します。
患者さんの負担が少ないのが特徴ですが、生検や治療はできません。原因不明の消化管出血や、クローン病が疑われるが胃カメラ・大腸カメラで診断がつかない場合などに用いられます。
小腸内視鏡(ダブルバルーン内視鏡など)は、口または肛門から特殊な内視鏡を挿入し、バルーンを使って小腸を手繰り寄せながら深く挿入していく検査です。
小腸全域の観察が可能で、生検や止血などの処置も行えますが、検査時間が長く、患者さんの負担も大きいため、実施できる施設は限られています。
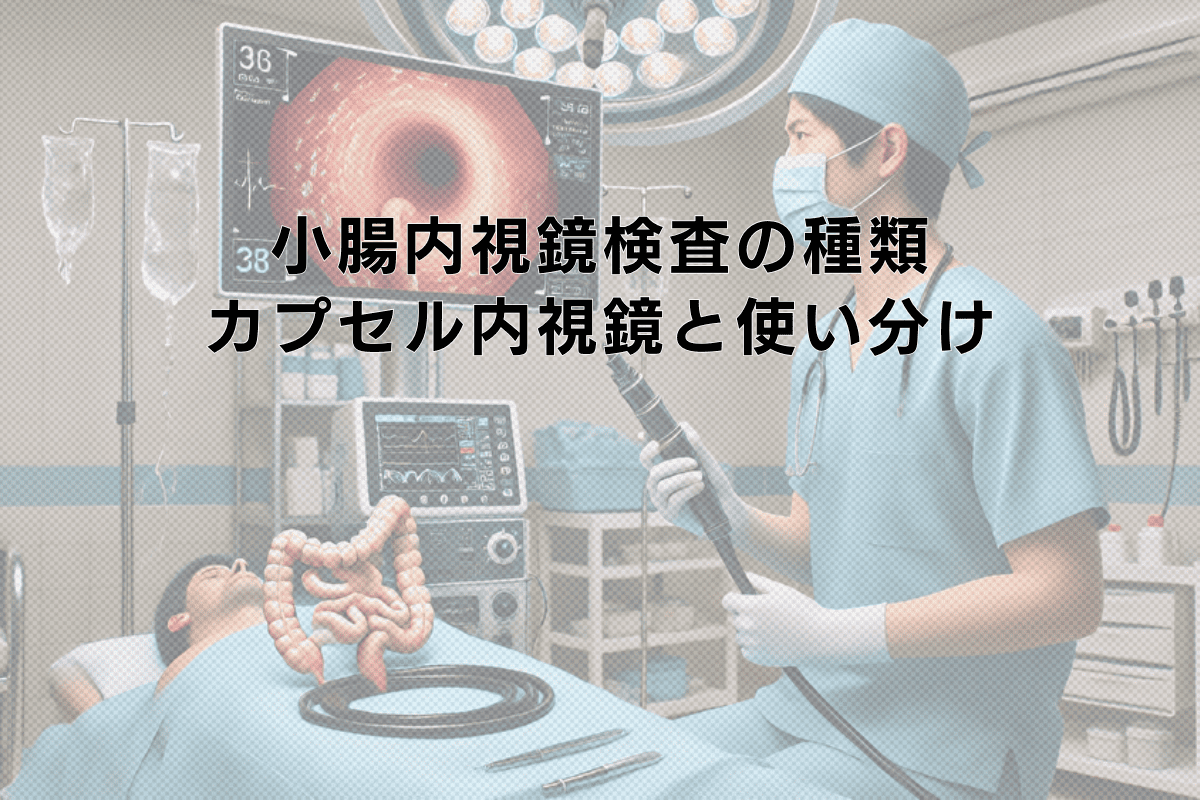
内視鏡検査による鑑別診断の流れ
下痢の原因を特定するために内視鏡検査が推奨された場合、どのような流れで診断が進められるのでしょうか。
検査前の問診と診察
内視鏡検査を行う前には、必ず医師による問診と診察があります。
問診では、下痢の始まった時期、頻度、便の性状(水様便、泥状便、血便、粘液便など)、腹痛の有無や性質、発熱、体重減少などの随伴症状、既往歴、家族歴、服用中の薬剤、食事内容、生活習慣、海外渡航歴などについて詳しく尋ねられます。
検査中の観察と組織採取(生検)
検査当日、準備が整ったら内視鏡室で検査を開始し、上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)では、喉の麻酔や鎮静剤を使用した後に、口または鼻からスコープを挿入します。
下部消化管内視鏡検査(大腸カメラ)では、通常、鎮静剤を使用し、肛門からスコープを挿入し、医師はモニターに映し出される消化管内部の映像をリアルタイムで確認しながら、粘膜の状態を詳細に観察することが可能です。
炎症、潰瘍、ポリープ、腫瘍、出血などの異常がないかを隅々までチェックし、疑わしい病変が見つかった場合や、診断を確定するために必要な場合には、内視鏡の先端から鉗子を出し、組織の一部を少量採取し、病理検査に提出されます。
生検結果に基づく病理診断
内視鏡検査で採取された組織(生検材料)は、病理検査室に送られ、病理医によって顕微鏡を用いた詳細な検査が行われます。
組織を薄くスライスし、特殊な染色を施して細胞の形態や配列、炎症細胞の種類や程度、がん細胞の有無などを観察し、最終的な病名を確定する上で極めて重要な役割を果たします。
例えば、炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病)の診断では、特徴的な炎症のパターンを確認します。
また、ポリープや腫瘍が見つかった場合には、それが良性なのか悪性(がん)なのか、悪性であればどの程度の深さまで達しているのかなどを評価します。
総合的な診断と治療方針の決定
病理診断の結果が出たら、担当医は内視鏡検査の所見、血液検査や画像検査などの他の検査結果、そして患者さんの症状や病歴を全て総合的に評価し、最終的な診断を確定します。
例えば、下痢や血便という症状で大腸内視鏡検査を行い、粘膜に特徴的な炎症所見と生検で活動性の炎症が確認されれば、潰瘍性大腸炎といった病名が診断されます。診断が確定したら、次はその病気に対する治療方針を決定します。
よくある質問
内視鏡検査に関して、患者さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。検査に対する不安を少しでも和らげるためにお役立てください。
- 内視鏡検査は痛いですか
-
多くの方が内視鏡検査に対して「痛い」「苦しい」というイメージをお持ちかもしれませんが、近年では様々な工夫により苦痛は大幅に軽減されています。
鎮静剤を使用すると、うとうとと眠っているような状態、あるいはリラックスした状態で検査を受けることができ、苦痛をほとんど感じずに終えることが可能です。
- 検査の費用はどのくらいかかりますか
-
あくまで目安ですが、保険診療(3割負担)の場合、胃カメラで観察のみであれば数千円から1万円程度、生検を行うとそれに数千円が加算されます。
大腸カメラで観察のみであれば1万円から2万円程度、生検やポリープ切除を行うと、切除するポリープの数や大きさによって費用が加算され、数万円程度になることもあります。
以下の記事も参考にしてください
【内視鏡検査費用の目安と流れ 胃と大腸のチェック方法】
内視鏡検査の具体的な費用や保険適用の詳細について分かりやすく説明。検査を検討されている方の費用面での不安を解消する内容です。 - 検査結果はいつ頃わかりますか
-
内視鏡検査の所見(医師が直接観察した結果)については、検査当日に医師から説明があるのが一般的です。モニターに映し出された画像を見ながら、どのような状態であったか、異常があったかなかったかなどの説明を受けます。
ただし、生検(組織を採取して調べる検査)を行った場合は、その病理診断の結果が出るまでに通常1週間から2週間程度の時間が必要です。 - 検査後、食事はいつから摂れますか
-
下部消化管内視鏡検査(大腸カメラ)の場合、観察のみで特に処置を行わなかった場合は、検査当日から通常の食事に戻って問題ありません。
ただし、腸管洗浄剤の影響で腸の動きが一時的に不安定になっていることもあるため、暴飲暴食は避け、消化の良いものを選びましょう。
もしポリープ切除などの処置を行った場合は、出血予防のために数日間は食事制限(消化の良いもの、刺激物やアルコールを避けるなど)や運動制限が指示されます。
次に読むことをお勧めする記事
【腸の内視鏡検査で分かること – 検査前の準備から検査後の注意点】
内視鏡が必要かもしれないと感じた方へ。検査の準備や当日の流れ、観察ポイントと生検まで具体的に把握できます。受ける前に読んでおくと安心です。
【下痢と栄養吸収障害の関係|内視鏡検査による腸管機能の評価】
下痢が続く背景に吸収不良が潜むことも。乳糖不耐症などの具体例と、内視鏡での評価の意義を合わせて理解すると全体像がクリアになります。
参考文献
Kinoshita Y, Ariyoshi R, Fujigaki S, Tanaka K, Morikawa T, Sanuki T. Endoscopic diagnosis of chronic diarrhea. DEN open. 2022 Apr;2(1):e53.
Ashitani K, Tsuzuki Y, Yamaoka M, Ohgo H, Ichimura T, Kusano T, Nakayama T, Nakamoto H, Imaeda H. Endoscopic features and diagnostic procedures of eosinophilic gastroenteritis. Internal Medicine. 2019 Aug 1;58(15):2167-71.
Yamamoto H, Kita H, Sunada K, Hayashi Y, Sato H, Yano T, Iwamoto M, Sekine Y, Miyata T, Kuno A, Ajibe H. Clinical outcomes of double-balloon endoscopy for the diagnosis and treatment of small-intestinal diseases. Clinical gastroenterology and hepatology. 2004 Nov 1;2(11):1010-6.
Shimura S, Ishimura N, Tanimura T, Yuki T, Miyake T, Kushiyama Y, Sato S, Fujishiro H, Ishihara S, Komatsu T, Kaneto E. Reliability of symptoms and endoscopic findings for diagnosis of esophageal eosinophilia in a Japanese population. Digestion. 2014 Sep 1;90(1):49-57.
Akahoshi K, Kubokawa M, Matsumoto M, Endo S, Motomura Y, Ouchi J, Kimura M, Murata A, Murayama M. Double-balloon endoscopy in the diagnosis and management of GI tract diseases: methodology, indications, safety, and clinical impact. World journal of gastroenterology: WJG. 2006 Dec 21;12(47):7654.
Shen B, Khan K, Ikenberry SO, Anderson MA, Banerjee S, Baron T, Ben-Menachem T, Cash BD, Fanelli RD, Fisher L, Fukami N. The role of endoscopy in the management of patients with diarrhea. Gastrointestinal endoscopy. 2010 May 1;71(6):887-92.
Schiller LR, Pardi DS, Sellin JH. Chronic diarrhea: diagnosis and management. Clinical Gastroenterology and Hepatology. 2017 Feb 1;15(2):182-93.
Wahnschaffe U, Ignatius R, Loddenkemper C, Liesenfeld O, Muehlen M, Jelinek T, Burchard GD, Weinke T, Harms G, Stein H, Zeitz M. Diagnostic value of endoscopy for the diagnosis of giardiasis and other intestinal diseases in patients with persistent diarrhea from tropical or subtropical areas. Scandinavian journal of gastroenterology. 2007 Jan 1;42(3):391-6.
Fine KD, Seidel RH, Do K. The prevalence, anatomic distribution, and diagnosis of colonic causes of chronic diarrhea. Gastrointestinal endoscopy. 2000 Mar 1;51(3):318-26.
Fry LC, Carey EJ, Shiff AD, Heigh RI, Sharma VK, Post JK, Hentz JG, Fleischer DE, Leighton JA. The yield of capsule endoscopy in patients with abdominal pain or diarrhea. Endoscopy. 2006 May;38(05):498-502.