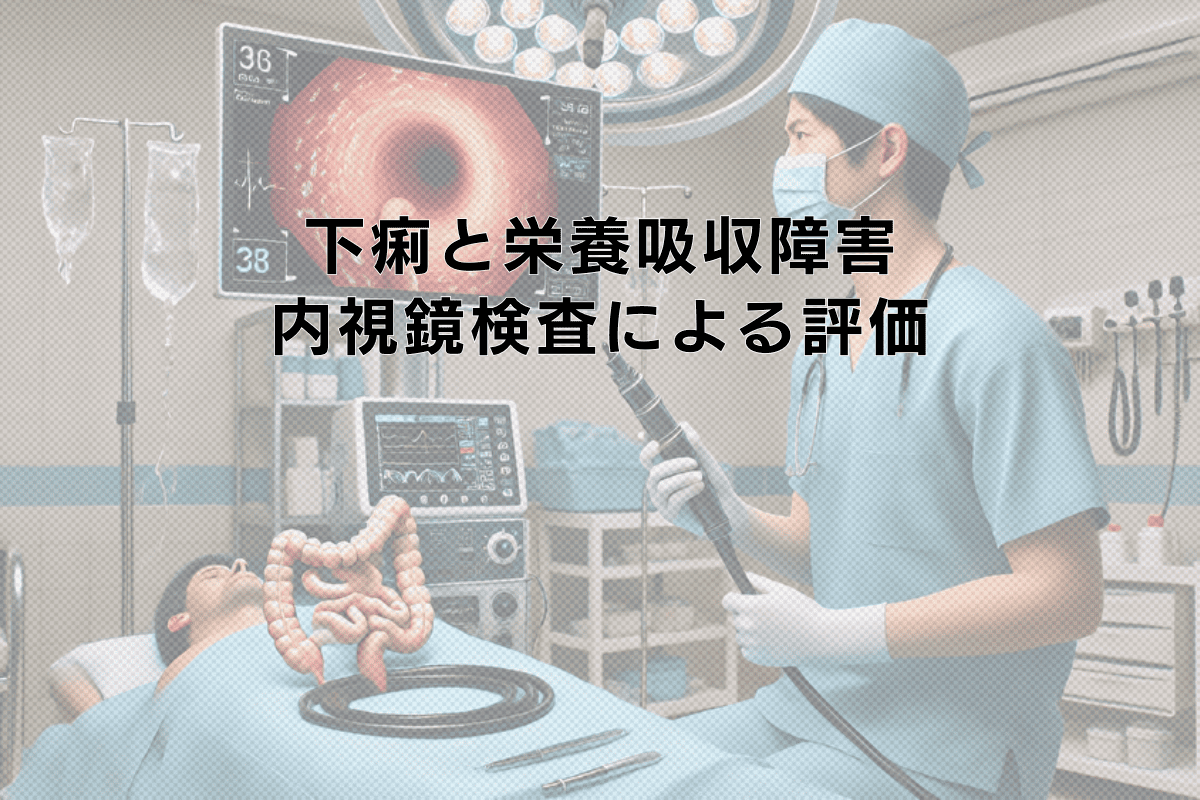「下痢が続いていて、体力が落ちた」「しっかり食べているはずなのに、体重が減ってきた」と感じることはありませんか。
一時的な下痢は誰にでも起こりますが、慢性的な下痢は単に不快なだけでなく、体にとって重要な栄養素の吸収が妨げられる栄養吸収障害のサインかもしれません。
栄養が十分に吸収されない状態が続くと、栄養失調に至ることもあります。
この記事では、下痢と栄養吸収の深い関係、栄養吸収障害が体に与える影響、そして原因を明らかにするための内視鏡検査の重要性について、消化器の専門的な観点から詳しく解説します。
下痢と栄養吸収の基本的な関係
下痢と栄養吸収障害は、コインの裏表のような関係です。なぜ下痢が続くと栄養状態が悪化するのか、背景にある体の仕組みから理解を深めていきましょう。
下痢とは何か
下痢とは便の水分量が異常に増加し、液状またはそれに近い状態(泥状便)で排出される状態です。
健康な状態では大腸が便から水分を吸収し、適度な硬さの便を形成しますが、腸の動きが活発になりすぎたり腸管内での水分分泌が増加したり、あるいは水分吸収がうまくいかなかないと、便中の水分が過剰となり下痢として現れます。
下痢は期間によって、数日から2週間程度で治まる急性下痢と、4週間以上続く慢性下痢に分けられます。
栄養素が吸収される仕組み
私たちが口から摂取した食べ物は、胃で消化され、主に小腸で栄養素として吸収されます。小腸の壁には絨毛と呼ばれる無数のひだがあり、表面積を広げることで効率良く栄養素を取り込んでいます。
炭水化物はブドウ糖に、タンパク質はアミノ酸に、脂肪は脂肪酸とグリセロールに分解され、絨毛から吸収された後、血液に乗って全身の細胞へと運ばれます。
この一連の流れがスムーズに行われることで、生命活動に必要なエネルギーや体を作る材料が得られるのです。
なぜ下痢だと栄養が吸収されにくいのか
下痢のとき、栄養が吸収されにくくなる理由は主に二つあります。
一つ目は腸管の通過時間が短縮されることで、腸のぜん動運動が過剰に活発になると、食べ物が栄養素を十分に吸収する間もなく、速やかに体外へ排出されてしまいます。
二つ目は、腸管粘膜そのものの機能低下です。
ウイルスや細菌による感染、あるいは炎症性の疾患によって小腸の絨毛がダメージを受けると、栄養素を吸収するための表面積が減少し、吸収能力が著しく落ち、食べたものがそのまま排出され、下痢で栄養が吸収されない状態に陥るのです。
栄養吸収障害が体に及ぼす影響の概要
| 影響の種類 | 主な症状 | 解説 |
|---|---|---|
| エネルギー不足 | 倦怠感、体重減少 | 炭水化物や脂質の吸収が低下し、活動に必要なエネルギーが作れなくなります。 |
| タンパク質不足 | 筋力低下、むくみ(浮腫) | 筋肉や臓器、血液の成分となるタンパク質が不足し、体の構成を維持できなくなります。 |
| ビタミン・ミネラル不足 | 貧血、口内炎、皮膚トラブル | 体の調子を整える微量栄養素が欠乏し、さまざまな不調が現れます。 |
下痢を引き起こす主な原因
下痢は非常にありふれた症状ですが、その背後には多岐にわたる原因が隠れています。
感染性の下痢
ウイルス(ノロウイルス、ロタウイルスなど)や細菌(カンピロバクター、サルモネラ菌など)、寄生虫が腸管に感染することで起きる下痢です。
病原体は毒素を産生したり、腸管の粘膜に炎症を起こしたりして、激しい下痢や嘔吐、腹痛、発熱などを伴うことが多くあります。
食中毒や汚染された水からの感染が主な経路で、通常は数日で自然に回復しますが、脱水症状には注意が必要です。
非感染性の下痢
感染症以外の要因で起こる下痢です。
冷たいものや脂っこいものの過剰摂取、アルコールの飲み過ぎ、精神的なストレスなどが挙げられ、一時的に腸の動きを乱し、下痢を起こします。
また、牛乳に含まれる乳糖を分解できない乳糖不耐症のように、特定の食物が原因で下痢を起こす体質的な要因もあります。
薬剤による下痢
服用している薬の副作用として下痢が起こることも少なくありません。特に抗生物質は腸内の善玉菌まで殺してしまい、腸内環境のバランスが崩れることで下痢を起こすことがあります。
そのほか、一部の痛み止めや血圧の薬、糖尿病治療薬なども原因となる可能性があるので、薬を飲み始めてから下痢が続く場合は、処方を受けた医師や薬剤師に相談することが大切です。
慢性的な下痢に関連する主な消化器疾患
| 疾患名 | 主な特徴 | 栄養吸収への影響 |
|---|---|---|
| 過敏性腸症候群(IBS) | ストレスなどで下痢と便秘を繰り返す。腸に炎症はない。 | 直接的な吸収障害は少ないが、症状により食事量が減ることがある。 |
| クローン病 | 口から肛門までの消化管全体に炎症や潰瘍が起こる。 | 小腸の炎症が強い場合、広範囲で栄養吸収が著しく低下する。 |
| 潰瘍性大腸炎 | 主に大腸の粘膜に炎症や潰瘍ができる。 | 大腸での水分・ミネラル吸収が中心のため、影響はクローン病より限定的。 |
栄養吸収障害の種類と特徴
栄養吸収障害は、吸収がうまくいかない栄養素の種類によって、体に現れる症状も異なります。どのような種類の障害があるのかを知っておきましょう。
全般的な吸収不良
広範囲の栄養素(炭水化物、脂質、タンパク質、ビタミン、ミネラル)がまとめて吸収できなくなる状態です。小腸の広範囲にわたる疾患、例えばクローン病やセリアック病、腸管を大規模に切除した後などに起こります。
この場合、体重減少や全身の倦怠感、むくみ(浮腫)、貧血など、全身にわたる深刻な症状が現れやすく、便が白っぽく、水に浮き、悪臭を放つ脂肪便も特徴的なサインの一つです。
特定栄養素の吸収不良
特定の栄養素だけがうまく吸収できない状態です。
代表的なものに、鉄欠乏性貧血の原因となる鉄の吸収障害や、骨がもろくなる原因となるカルシウムとビタミンDの吸収障害があります。
また、悪性貧血の原因となるビタミンB12の吸収障害は、胃の切除後や特定の自己免疫疾患で見られます。原因となる疾患や部位によって、どの栄養素が吸収されにくいかが決まってきます。
特定の栄養素が吸収されない場合の代表例
| 栄養素 | 吸収が障害される主な原因 | 起こりうる症状 |
|---|---|---|
| 脂質 | 膵臓の機能低下、胆汁分泌の障害 | 脂肪便、脂溶性ビタミン欠乏 |
| 鉄 | 胃酸の分泌低下、十二指腸の炎症 | 鉄欠乏性貧血(めまい、動悸) |
| 乳糖 | 乳糖分解酵素の欠乏(乳糖不耐症) | 腹部膨満感、腹痛、下痢 |
消化不良との違い
消化と吸収は密接に関連していますが、異なる働きです。消化は、食べ物を細かく分解する過程であり、主に胃酸や膵臓から分泌される消化酵素が担い、吸収は、細かく分解された栄養素を腸の壁から体内に取り込む過程です。
消化不良は、食べ物をうまく分解できない状態(例:膵機能不全)、吸収不良は、分解された栄養素を取り込めない状態を指します。ただし、消化が不十分なものは吸収もされないため、実際には両者が同時に起きていることも多いです。
慢性的な下痢や栄養失調を考える上では、この両方の側面から原因を探ることが重要になります。
栄養失調が体に与える影響
栄養吸収障害によって栄養失調が進行すると、体にはさまざまな危険信号が現れます。下痢だからと軽く考えず、体に現れる変化に注意を払うことが大切です。
エネルギー不足による症状
私たちの体は炭水化物や脂質を主なエネルギー源として活動し、吸収が妨げられると、ガス欠の状態に陥ります。常に体がだるい、疲れやすい、集中力が続かないといった症状は、エネルギー不足の典型的なサインです。
また、体は不足したエネルギーを補うために、筋肉や脂肪を分解して利用し始めるため、意図しない体重減少が起こります。下痢とともに体重が減っていく場合は、栄養が吸収されていない可能性を強く考えます。
タンパク質不足の影響
タンパク質は、筋肉、皮膚、髪、内臓、血液など、私たちの体を作る主要な材料です。
タンパク質の吸収が不足すると、筋肉量が減って筋力が低下し、また、血液中のタンパク質(特にアルブミン)が減少すると、血管内の水分を保持する力が弱まり、水分が血管の外に漏れ出してむくみ(浮腫)として現れます。
すねや足の甲を押したときに、へこんだまま戻らない場合は注意が必要です。
タンパク質不足が起こす主な体の変化
| 体の部位 | 変化・症状 | 解説 |
|---|---|---|
| 筋肉 | 筋力低下、筋肉量の減少 | 体を構成する材料が不足し、筋肉が分解されてしまうため。 |
| 血液 | むくみ(浮腫)、貧血 | 血中アルブミンの低下や、赤血球の材料不足が原因。 |
| 皮膚・髪・爪 | 乾燥、抜け毛、爪がもろくなる | 新しい細胞を作るための材料が不足し、新陳代謝が滞るため。 |
ビタミン・ミネラル欠乏のサイン
ビタミンやミネラルは微量栄養素と呼ばれ、少量でも体の機能を正常に保つために重要な役割を果たし、欠乏すると多種多様な症状が現れます。
鉄が不足すればめまいや息切れを伴う貧血に、ビタミンB群が不足すれば口内炎や口角炎、皮膚炎に、亜鉛が不足すれば味覚障害や皮膚炎につながります。こうしたサインは、下痢による栄養吸収障害を見つけるための重要な手がかりです。
主なビタミン・ミネラル欠乏による症状
| 栄養素 | 欠乏による主な症状 |
|---|---|
| ビタミンA | 夜盲症(暗いところで見えにくい)、皮膚の乾燥 |
| ビタミンB12 | 悪性貧血、手足のしびれ |
| ビタミンD | 骨の痛み、骨がもろくなる(骨軟化症) |
| 亜鉛 | 味覚障害、皮膚炎、脱毛 |
腸管機能の評価方法
慢性的な下痢や栄養吸収障害が疑われる場合、原因を特定するために医療機関では段階的に検査を進めます。
なぜ腸の状態を詳しく調べる必要があるのか
下痢の原因は多岐にわたるため、症状だけでは正確な診断が困難です。炎症性腸疾患(クローン病や潰瘍性大腸炎)や吸収不良を起こす他の疾患、あるいは大腸がんなどの悪性疾患が隠れている可能性も否定できません。
疾患は早期に発見し、治療を開始することが極めて重要です。
問診と身体診察でわかること
診断の第一歩は、丁寧な問診です。いつから下痢が始まったか、便の性状(色、形、匂い)、回数、腹痛や発熱の有無、食事内容、服用中の薬、海外渡航歴など、詳細な情報が診断の重要な手がかりとなります。
その後、聴診でお腹の音を確認したり、触診で痛みやしこりの有無を調べたりします。体重減少やむくみ、貧血の兆候(顔色や眼瞼結膜の色)など、栄養状態を示す身体的なサインも注意深く観察します。
血液検査や便検査
問診と診察の次に行うのが、血液検査と便検査です。血液検査では、炎症反応の有無(CRP、白血球数)、貧血の有無(ヘモグロビン値)、栄養状態(アルブミン、総タンパク)、特定の臓器の異常(肝機能、腎機能)などを調べられます。
便検査では、便に血液が混じっていないか(便潜血検査)、細菌やウイルスの感染がないかなどを確認します。これらの検査は、体に大きな負担をかけることなく、多くの情報を得られる有効な評価方法です。
内視鏡検査の役割と目的
血液検査や便検査で異常が見つかったり、症状から重篤な疾患が疑われたりする場合には、消化管の内部を直接観察する内視鏡検査(胃カメラ、大腸カメラ)を検討します。
内視鏡検査の最大の目的は、医師が自らの目で食道、胃、十二指腸、大腸の粘膜の状態をリアルタイムで確認することです。炎症、潰瘍、ポリープ、がんなどの病変の有無や広がりを正確に把握できます。
内視鏡検査でわかること
内視鏡検査は、消化管内部を詳しく調べるための非常に重要な検査で、下痢や栄養吸収障害の背後にあるさまざまな病気を見つけ出せます。
上部消化管内視鏡(胃カメラ)の観察範囲
一般的に「胃カメラ」と呼ばれる検査で、口または鼻から細いスコープを挿入し、食道、胃、十二指腸の粘膜を観察します。
栄養吸収の入り口である十二指腸は、鉄やカルシウムなどの重要なミネラルが吸収される場所です。炎症や萎縮があると、栄養吸収障害の原因となります。
胃カメラでは、胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍のほか、セリアック病やクローン病の一部など、栄養吸収に影響を与える疾患の所見を確認できます。
下部消化管内視鏡(大腸カメラ)の観察範囲
大腸カメラで肛門からスコープを挿入し、直腸から盲腸までの大腸全体と、小腸の末端(回腸末端部)を観察します。慢性的な下痢の原因として頻度の高い、潰瘍性大腸炎やクローン病の診断には、この検査が極めて重要です。
特徴的な炎症や潰瘍の分布を確認することで診断します。また、大腸がんやポリープの発見にも有効です。
生検(組織検査)による確定診断
内視鏡検査の大きな利点は、疑わしい部分の組織を少量採取(生検)できることです。採取した組織は、顕微鏡で詳しく調べる病理検査に提出し、炎症の程度や種類、がん細胞の有無などを確定的に診断できます。
見た目だけでは区別がつきにくい炎症性疾患の種類を特定したり、がんかどうかを最終的に判断したりするために、生検は欠かせない手技です。
内視鏡検査で発見が期待できる疾患
| 検査の種類 | 発見できる主な疾患 | 下痢・栄養吸収障害との関連 |
|---|---|---|
| 胃カメラ | 胃潰瘍、十二指腸潰瘍、セリアック病 | 出血による貧血や、十二指腸の炎症による吸収不良を引き起こす。 |
| 大腸カメラ | 潰瘍性大腸炎、クローン病、大腸がん | 腸管の広範な炎症や出血、閉塞が、深刻な下痢や栄養失調の原因となる。 |
| 両方の検査 | クローン病、悪性リンパ腫 | 消化管の広い範囲に病変が及ぶ疾患の全体像を把握する。 |
下痢や栄養吸収障害を感じたときの対処法
つらい下痢の症状や、栄養が足りていないかもしれないという不安を感じたとき、どのように対処すれば良いのでしょうか。ご自身でできるケアと、医療機関を受診するタイミングについて解説します。
まずはセルフケアでできること
症状が軽い場合、まずは体を休ませることが第一です。脱水を防ぐため、水分補給をこまめに行い、水やお茶だけでなく、失われたミネラルを補給できる経口補水液やスポーツドリンクも有効です。
お腹を冷やさないように温かくし、安静に過ごし、食事は消化の良いものを少量ずつ摂るように心がけてください。
消化の良い食事のポイント
- おかゆ、うどん
- 脂肪の少ない鶏ささみ、白身魚
- 豆腐、卵
- りんご、バナナ
食事で気をつけたいポイント
腸に負担をかける食事は下痢を悪化させる可能性があり、症状が落ち着くまでは、刺激の強い食品や消化に悪いものは避けましょう。回復期には、腸内環境を整える発酵食品などを少しずつ取り入れていくことが大切です。
下痢のときに避けたい食事
| カテゴリ | 避けるべき食品の例 | 理由 |
|---|---|---|
| 冷たいもの | アイスクリーム、冷たい飲み物 | 腸を刺激し、ぜん動運動を活発にしすぎるため。 |
| 脂質の多いもの | 揚げ物、ラーメン、脂肪の多い肉 | 消化に時間がかかり、腸に負担をかけるため。 |
| 刺激の強いもの | 香辛料(唐辛子など)、炭酸飲料、アルコール | 腸の粘膜を直接刺激するため。 |
医療機関を受診する目安
セルフケアで改善しない、特定の症状が見られる場合は、自己判断せずに医療機関を受診することが重要です。特に慢性的な下痢は、背景に治療が必要な病気が隠れているサインかもしれません。
医療機関への受診を推奨する症状
- 2週間以上続く下痢
- 高熱や激しい腹痛を伴う
- 便に血が混じる(黒い便も含む)
- 明らかな体重減少がある
- 水分が摂れないほどの脱水症状
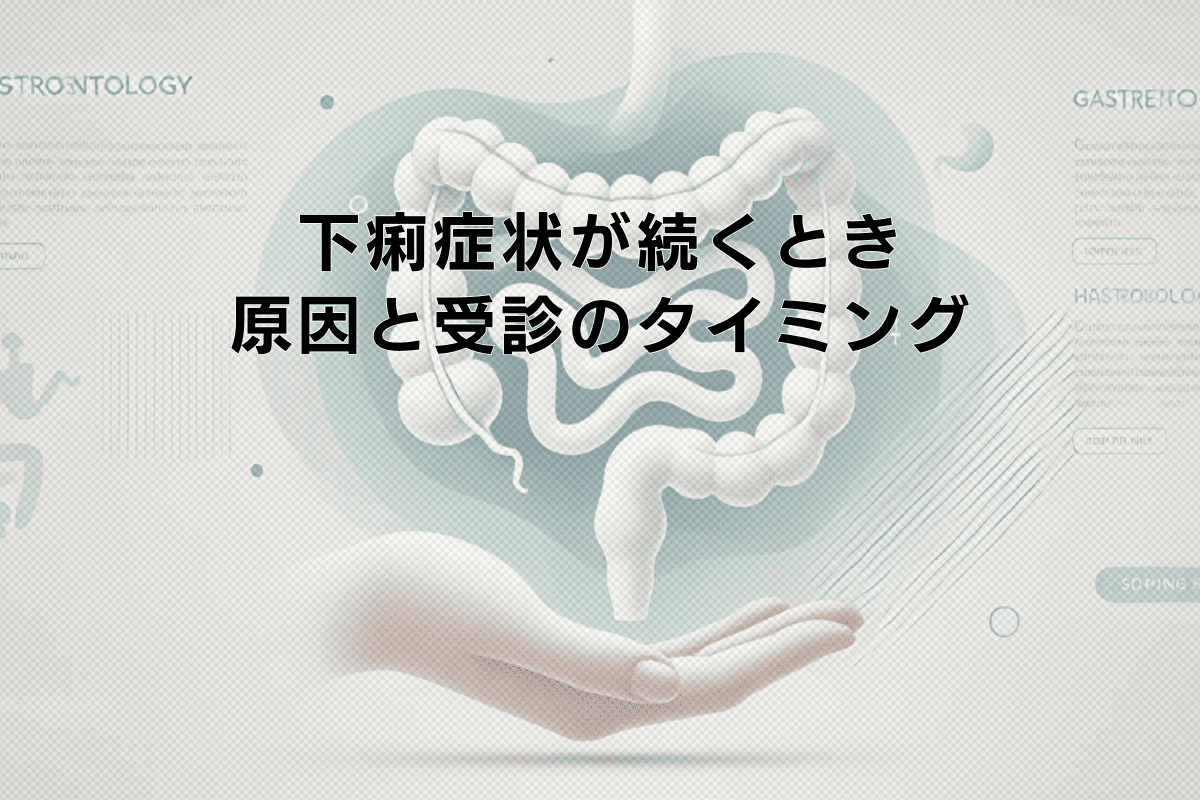
よくある質問
下痢や栄養吸収に関して、患者さんからよく寄せられる質問にお答えします。
- 下痢止めは飲んでも良いですか?
-
自己判断での下痢止めの使用には注意が必要です。ウイルスや細菌の感染が原因の場合、下痢止めで腸の動きを止めると、原因となる病原体や毒素の排出を妨げ、かえって回復を遅らせることがあります。
特に発熱や血便を伴う場合は使用を避け、下痢止めを使う前に、まずは医療機関で下痢の原因を調べてもらうことが大切です。
- プロバイオティクスは効果がありますか?
-
プロバイオティクスは、ヨーグルトや乳酸菌飲料などに含まれる、腸内の善玉菌を増やすことで腸内環境のバランスを整える働きを持つ生きた微生物です。
抗生物質による下痢の予防や、一部の過敏性腸症候群の症状緩和に有効であるという報告がありますが、すべての下痢に効果があるわけではありません。
日々の健康維持や腸内環境の改善のために食生活に取り入れるのは良いことですが、治療の代わりになるものではないと理解し、症状が続く場合は専門医に相談してください。
以下の記事も参考にしてください
⇒【腸にいい食べ物を知る 腸内環境を整える方法】
腸にいい食べ物を意識して取り入れ腸内環境を整える方法について詳しく解説しています。便通が安定しやすくなったり免疫機能を保ちやすくなるメリットが得られます。 - 子供の下痢で特に注意することは何ですか?
-
子供、特に乳幼児は、大人に比べて体内の水分量が占める割合が高く、下痢によって容易に脱水症状に陥るため、水分補給が最も重要で、また、体力の消耗も激しいため、安静にさせることも大切です。
機嫌や顔色、排尿の回数などを注意深く観察し、ぐったりしている、泣いても涙が出ない、半日以上排尿がないなどのサインがあれば、すぐに小児科を受診してください。
- 検査にはどのくらいの時間がかかりますか?
-
血液検査や便検査は、採血や採便自体は短時間で終わりますが、結果が出るまでに数日かかることがあります。
内視鏡検査(胃カメラ・大腸カメラ)は、検査前の準備(食事制限や下剤の服用)に時間がかかりますが、検査自体の所要時間は、胃カメラで10分〜15分程度、大腸カメラで20分〜30分程度が目安です。
ただし、ポリープ切除などの処置を行う場合は、もう少し時間がかかることもあります。
次に読むことをお勧めする記事
【消化器官の機能と働き|内視鏡検査で分かること】
下痢と栄養吸収について理解が深まったところで、消化器官全体の機能と働きについても知っておくと、より包括的な理解ができます。
【慢性的な下痢と倦怠感が続くときの消化管スクリーニング検査】
長引く下痢と全身倦怠の背景には多様な疾患が関与します。血液・便検査と内視鏡を含むスクリーニングの全体像を押さえ、抜け漏れのない検討に役立てられます。
参考文献
Kinoshita Y, Ariyoshi R, Fujigaki S, Tanaka K, Morikawa T, Sanuki T. Endoscopic diagnosis of chronic diarrhea. DEN open. 2022 Apr;2(1):e53.
Manabe N, Tanaka S, Fukumoto A, Nakao M, Kamino D, Chayama K. Double-balloon enteroscopy in patients with GI bleeding of obscure origin. Gastrointestinal endoscopy. 2006 Jul 1;64(1):135-40.
Ashitani K, Tsuzuki Y, Yamaoka M, Ohgo H, Ichimura T, Kusano T, Nakayama T, Nakamoto H, Imaeda H. Endoscopic features and diagnostic procedures of eosinophilic gastroenteritis. Internal Medicine. 2019 Aug 1;58(15):2167-71.
Oshima T, Miwa H. Epidemiology of functional gastrointestinal disorders in Japan and in the world. Journal of neurogastroenterology and motility. 2015 Jul 3;21(3):320.
Ihara E, Manabe N, Ohkubo H, Ogasawara N, Ogino H, Kakimoto K, Kanazawa M, Kawahara H, Kusano C, Kuribayashi S, Sawada A. Evidence-based clinical guidelines for chronic diarrhea 2023. Digestion. 2024 Dec 9;105(6):480-97.
Ando T, Sakumura M, Mihara H, Fujinami H, Yasuda I. A review of potential role of capsule endoscopy in the work-up for chemotherapy-induced diarrhea. InHealthcare 2022 Jan 24 (Vol. 10, No. 2, p. 218). MDPI.
Shen B, Khan K, Ikenberry SO, Anderson MA, Banerjee S, Baron T, Ben-Menachem T, Cash BD, Fanelli RD, Fisher L, Fukami N. The role of endoscopy in the management of patients with diarrhea. Gastrointestinal endoscopy. 2010 May 1;71(6):887-92.
Schiller LR. Diarrhea and malabsorption in the elderly. Gastroenterology Clinics. 2009 Sep 1;38(3):481-502.
Semrad CE. Approach to the patient with diarrhea and malabsorption. Goldman’s cecil medicine. 2012 May 8:895.
Freeman HJ. Small intestinal mucosal biopsy for investigation of diarrhea and malabsorption in adults. Gastrointestinal endoscopy clinics of North America. 2000 Oct 1;10(4):739-53.