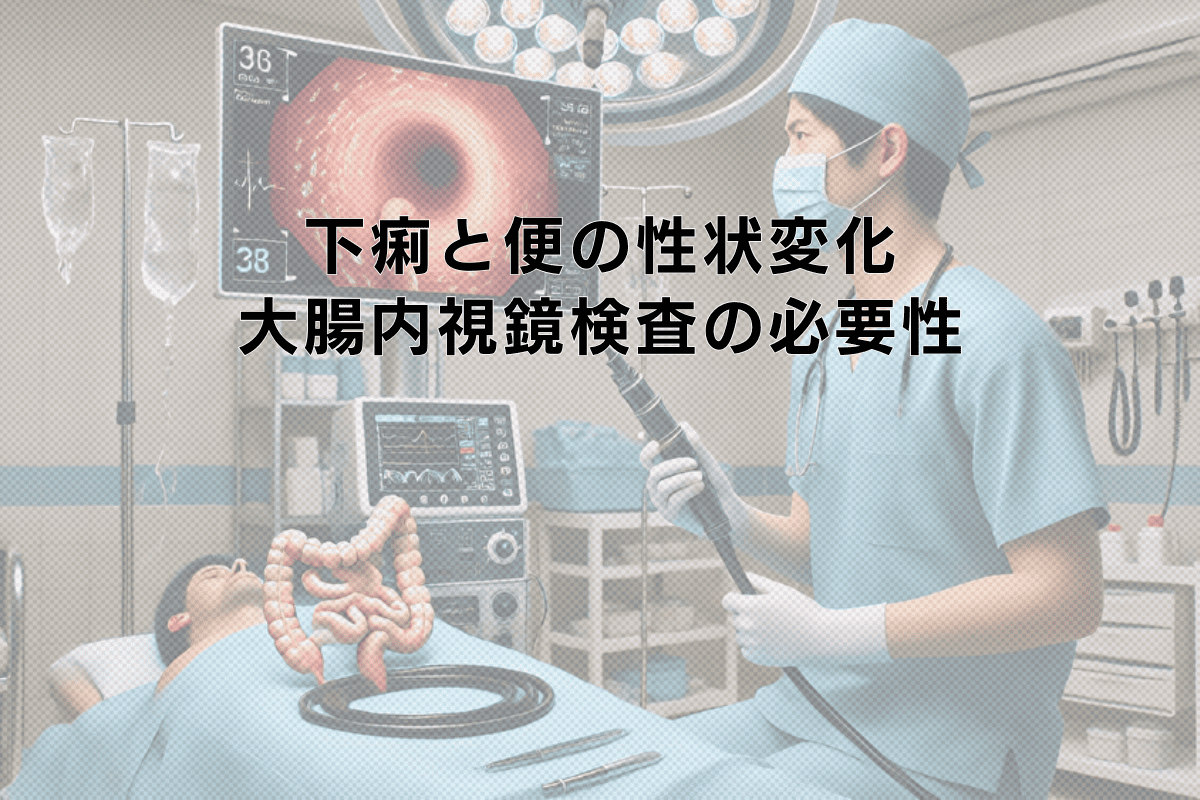慢性的な下痢や便の形状変化が続くと、消化管のどこかに異常が起きている可能性が高いと考えられます。
急に始まった下痢が自然に落ち着くなら大きな問題にならない場合もありますが、便の状態が不安定なままだと大腸ポリープや炎症性疾患、悪性疾患などを見逃してしまうかもしれません。
大腸内視鏡検査は、こうしたリスクを早めに確認するための重要な手段です。便の色や形状、下痢の原因といった手がかりをもとに、検査が必要なケースや受診のポイントを知り、消化管の健康を保ちましょう。
下痢や便の性状変化が教えてくれること
下痢や便の形状の変化は、体内のさまざまな問題を示すサインで、単なる食事の影響だけでなく、腸内環境の乱れや炎症性疾患、消化管の腫瘍など多くの要因が考えられます。
便の状態を観察するときは、色・形・におい・頻度など、多角的にチェックすると原因や対策を見つけやすいです。
下痢と便の定義
一般的に、1日に3回以上の水様便や軟便を下痢と呼ぶことが多く、消化管での水分吸収が十分に行われないことや、腸内での分泌が過剰になることで発生します。
一方、便そのものの形状は腸内の通過速度に左右され、速いほど水分が多く形が崩れやすくなります。

下痢の主な原因とメカニズム
下痢の原因には、感染症や食事、ストレス、薬の副作用などが挙げられ、感染症の場合は細菌やウイルスが腸内で炎症を引き起こし、水分吸収能力を低下させます。
ストレスや過敏性腸症候群の場合も、腸管の動きが乱れ、水分調節がうまくいかなくなり水っぽい便になりやすいです。下痢の原因に便の状態が深く関係しているケースもあるため、自分の便の状態を把握すると早期受診の目安になります。
便の性状変化が体に及ぼす影響
便の形状が細くなったり、何かに粘液が付着していたり、色が黒く変化していたりすると、腸のどこかに異常がある可能性があります。また下痢のまま放置すると栄養不良につながり、脱水症状や貧血を招くリスクも高まります。
長引く下痢や頻繁な便の変化は体力を低下させ、生活の質を下げる原因にもなります。
大腸内視鏡検査が必要となるケース
通常の下痢であれば、数日~1週間ほどで落ち着く場合が多いですが、血便をともなう場合や痛みが強い場合、便が著しく細くなっている場合は大腸内視鏡検査を検討してください。
特に、下痢と便の性状変化に加えて体重減少や倦怠感が目立つときは、炎症性腸疾患や悪性腫瘍を含め幅広い病気を視野に入れる必要があります。
下痢と便の状態
| 便の状態 | 主な特徴 | 可能性のある要因 |
|---|---|---|
| 水様便 | 水分含有量が非常に多い | 感染症、過敏性腸症候群、食事性など |
| 軟便 | やや柔らかく形が崩れやすい | 腸内環境の乱れ、ストレス、軽度の炎症 |
| 普通便 | 固さも色も平均的な状態 | 健康な腸内環境 |
| 粘液便 | 粘液が付着している | 炎症性腸疾患、腸内ポリープ、腸内感染など |
| 血便 | 鮮血や暗赤色の血液が混じる | 痔疾患、炎症、腫瘍、感染性大腸炎など |
なぜ下痢の状態が続く場合に大腸内視鏡検査を考えるのか
下痢が長期間続くときは、表面的には軽い体調不良に思えても、実際にはさまざまな病気の可能性があります。放置すると慢性化や重症化につながり、治療のタイミングを逃してしまうこともあるため注意が必要です。
急性の下痢と慢性の下痢の違い
急性の下痢は1~2週間以内に症状が改善する一過性の状態で、食当たりや感染症が原因となることが多く、水分補給や安静によって回復しやすいのが特徴です。
慢性の下痢は1カ月以上続くケースを指し、腸の炎症や腫瘍、過敏性腸症候群などが関係していることがあります。
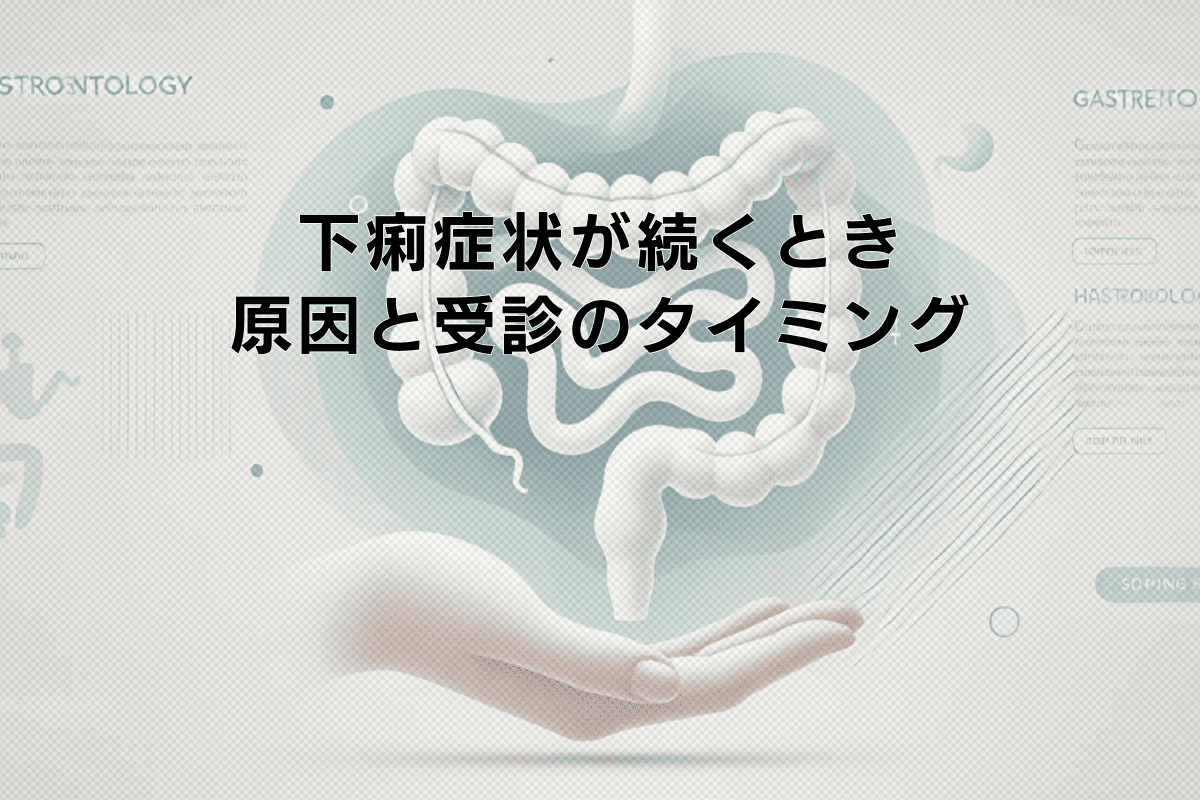
主な急性の下痢の原因
| 原因 | 説明 |
|---|---|
| 細菌性食中毒(サルモネラなど) | 食べ物や水に付着した細菌によって急性炎症を起こす |
| ウイルス感染(ノロなど) | 集団発生することも多く、吐き気や嘔吐を伴う |
| 一過性の暴飲暴食 | 過度な刺激物やアルコールの摂取で腸が過剰に刺激される |
| ストレスによる一時的な腸機能の乱れ | 自律神経のバランスが崩れて腸運動が過敏になる |
下痢が続くと疑われる代表的な疾患
下痢が長引くといくつかの疾患が疑われ、大腸内視鏡検査はこれらの疾患を直接観察して診断できる重要な方法です。
主な慢性の下痢の原因
| 病気名 | 特徴 | ポイント |
|---|---|---|
| 潰瘍性大腸炎 | 血便や粘液便が出やすく、再燃と寛解を繰り返す | 大腸全体や直腸からの炎症 |
| クローン病 | 口から肛門まであらゆる箇所に炎症が及ぶ可能性 | 腸管の狭窄、潰瘍を引き起こす |
| 過敏性腸症候群 | ストレスが大きく関与し、下痢と便秘を繰り返す | 検査で器質的異常が見つからないことが多い |
| 大腸ポリープ・がん | 大腸内壁に腫瘍性変化がみられることがある | 血便や便形状の変化が症状として出やすい |
診察時にチェックすべきポイント
医療機関を受診するときは、下痢の始まりや症状の持続期間、便の色や形状などを細かく伝えると診断の助けになります。さらに、発熱や腹痛、食欲不振、体重減少の有無などを詳細に報告すると、医師は検査の優先度を判断しやすいです。
下痢や便に関する情報を整理する要点
- いつから症状が始まったか(急性か慢性か)
- 1日の排便回数、時間帯
- 血液や粘液の混在の有無
- 腹痛のタイミングや場所
- 発熱や吐き気など、ほかの症状の有無
消化器内科の視点からの検査スケジュール
消化器内科では症状の程度や患者さんの年齢、基礎疾患の有無などを考慮し、必要に応じて大腸内視鏡検査を行います。
症状が急激かつ重症の場合は早めの検査が求められ、慢性的に続く場合は画像検査や血液検査を組み合わせながら判断する流れです。
便の色や形状で予想できる消化管の異常
便の色や形状は、腸管や消化管の状態を映し出す指標です。黒い便の場合は上部消化管からの出血が疑われ、明るい赤色の便なら大腸や肛門付近の出血を示すことが多いなど、色によって原因を推測しやすい特徴があります。
形状の変化も腸管の通過速度や炎症などの影響を受けるため、早めにチェックすることが大切です。
便の色からみる消化管トラブルのサイン
正常な便の色は黄色から茶褐色にかけての色味で、黒色便は胃や十二指腸など上部消化管で出血があるときに見られやすく、赤色便は大腸や肛門などの下部消化管に何らかの損傷や炎症があるケースを示唆します。
白色便の場合は胆汁の分泌が滞っている可能性があるため注意が必要です。
便の色と疑われる症状
| 便の色 | 疑われる主な異常 | 追加で確認したい症状 |
|---|---|---|
| 黒色 | 上部消化管出血、胃潰瘍 | 吐き気、胸やけ、腹痛 |
| 赤色 | 大腸出血、肛門付近の炎症・痔など | 血の混じり方、便意の頻度 |
| 白色 | 胆管閉塞、肝機能障害 | 黄疸、尿の色の濃さ、倦怠感 |
| 黄~茶褐色 | 比較的正常な状態 | 便通や腹痛の有無 |
血便と粘液便のリスク
血が混ざった便は、痔が原因となるケースが多いですが、腫瘍や炎症性腸疾患など大腸内に深刻な異常が潜んでいることもあります。また、粘液便が続く場合は大腸内の炎症やポリープ、または感染症を疑います。
これらの症状は見過ごすと悪化する可能性があるため、医師への相談を後回しにしないよう心がけましょう。
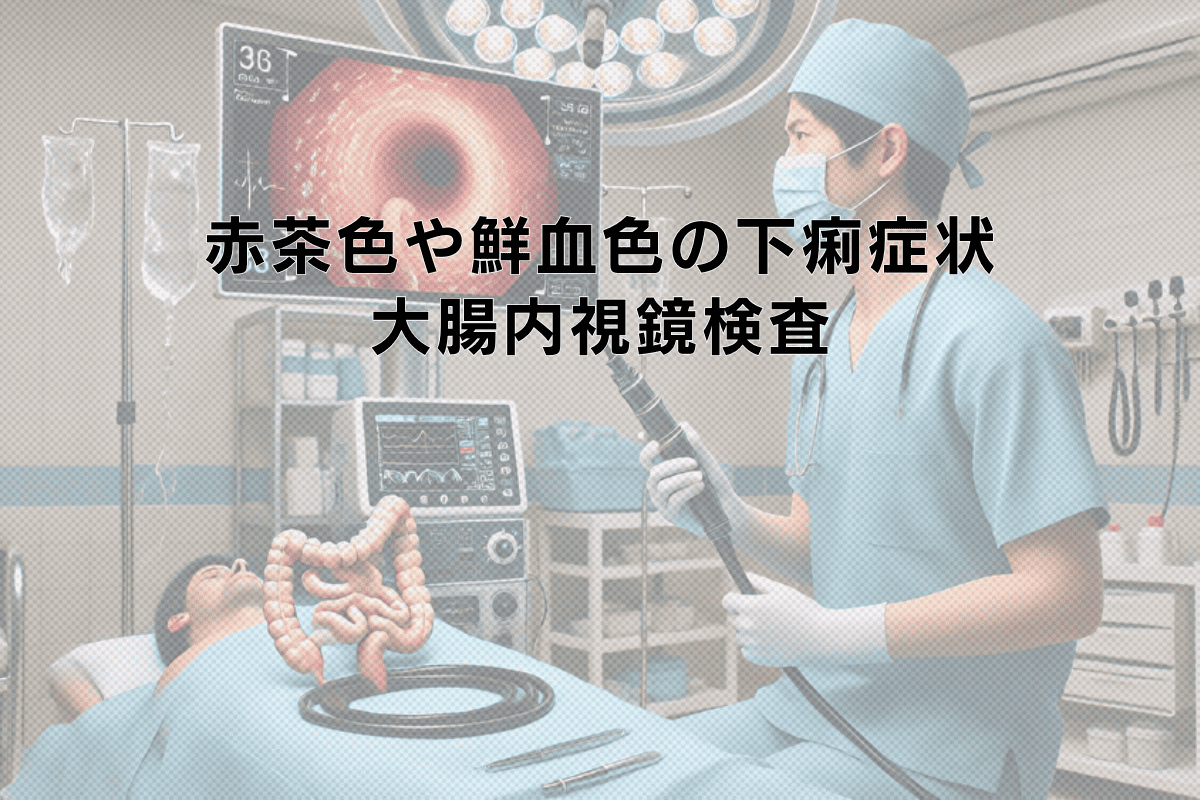
下痢の原因が便の特徴に反映されるケース
便は食べたものを排出するだけでなく、腸内の状態を可視化する手がかりになり、下痢のときに便に脂肪が浮いている場合は脂肪吸収障害を疑い、悪臭が強ければ腸内細菌叢の乱れや感染症の可能性が高まります。
色やにおいに変化があれば、より詳細な検査を検討することが大事です。
便の状態を確認するチェック項目
- 色(黒色か赤色か、それとも白っぽいか)
- におい(普段と比べて強いかどうか)
- 油分の浮き(脂肪が混在していないか)
- 粘液や血液の混在
- 全体的な量と粘度
専門医に相談すべきタイミング
下痢や便の変化が1~2週間以上続き、改善の兆しが見られないときは消化器専門医に相談してください。
特に血液や粘液が混ざる場合、痛みを伴う場合、あるいは体重減少や全身倦怠感がある場合は、重大な病気の可能性を考えて大腸内視鏡検査を早めに検討することが重要です。
大腸内視鏡検査でわかる主な病変
大腸内視鏡検査は、肛門から内視鏡を挿入して大腸内部を直接観察する検査で、腸の粘膜を可視化できるため、微小な病変から大きな腫瘍まで発見しやすい利点があります。
下痢の原因や便の異常をより正確に把握し、治療へつなげるために用いられます。

ポリープやがん
大腸ポリープは良性の場合が多いですが、中にはがん化のリスクを含むものもあり、大腸内視鏡検査で見つけたポリープは、その場で切除できる場合もあるため、早期発見が大切です。
がんの場合も、ステージによっては内視鏡的切除の対象になります。
潰瘍性大腸炎などの炎症性腸疾患
潰瘍性大腸炎やクローン病などの炎症性腸疾患は、内視鏡検査による粘膜観察で確定診断を行う場合が多いです。粘膜にびらんや潰瘍がないか、どの範囲に及んでいるかを直接確認できます。
虫垂炎をはじめとする急性疾患
虫垂炎は主にCTなどの画像検査で判別される症例が多いですが、右下腹部痛に加えて下痢や便の異常が続く場合、必要に応じて内視鏡検査を行って腸内全体の状態を確認することがあります。
その他の良性疾患
憩室炎や虚血性大腸炎なども大腸内視鏡検査で直接観察が可能で、慢性や再発性の下痢がある場合は、こうした疾患を早期に見極めることが生活の質を維持するうえでも重要です。
大腸内視鏡で発見される主な病変
| 病変名 | 特徴 | 治療の方向性 |
|---|---|---|
| 大腸ポリープ | 粘膜の隆起性病変で良性が多い | 内視鏡的切除、組織検査 |
| 大腸がん | 進行度や位置によって症状が異なる | 内視鏡的治療または手術、化学療法など |
| 潰瘍性大腸炎 | 血便や粘液便が出やすく、再燃しやすい | 内科的治療(薬物治療)、症状管理が中心 |
| クローン病 | 消化管全体に病変が及ぶ可能性がある | 内科的治療(薬物)、重症の場合は手術 |
| 憩室炎 | 大腸の憩室部位に炎症が生じる | 保存的治療(抗生物質)、重症時は手術 |
下痢や便の異常を放置するリスク
下痢の原因となる便の異常を軽視すると、身体的にも社会的にも悪影響が広がり、一時的な症状だからと放置してしまうと、深刻な病気が見つかるタイミングを逃す恐れがあります。
日々の生活を快適に送るためにも、見逃さないよう注意しましょう。
栄養不良や脱水
下痢が長引くと、水分だけでなく必要な栄養素も排出しやすくなり、体内の水分量が不足すると、めまいや倦怠感などの日常生活に支障をきたす症状が表れ、重症化すると入院が必要になる場合もあるので注意が必要です。
症状の慢性化による日常生活への影響
慢性的な下痢はトイレの回数や急な便意の制御が難しくなり、外出や仕事に大きな負担を及ぼします。常に不安を抱えながら生活することで精神的なストレスを感じやすくなり、さらに腸の状態を悪化させてしまう可能性があります。
下痢や便の異常を放置するリスク
| リスク | 具体的な影響 | 予防・対策 |
|---|---|---|
| 脱水・電解質バランスの乱れ | めまい、疲労感、血圧低下 | 水分補給や経口補水液の活用 |
| 栄養不良 | 体重減少、免疫力の低下 | バランスの良い食事、サプリメントなどの併用 |
| 病気の進行・見落とし | 炎症性疾患や腫瘍の悪化 | 医療機関への早期受診 |
| 生活の質(QOL)の低下 | 外出が困難、ストレス増大 | 適切な治療やサポートの導入 |
深刻な病気の見逃し
潰瘍性大腸炎やクローン病、大腸がんなど、検査をしなければ発見が難しい病気も数多くあり、下痢や便に異常が見られるときは早期に疑いを持ち、必要に応じて消化器専門医に相談することが肝心です。
適切な検査が大切な理由
大腸内視鏡検査は腸の粘膜を直接観察できるため、初期段階の病変を見つけやすいという利点があり、身体所見や画像検査だけでは見逃しがちな腸粘膜の小さな変化も捉えやすく、早期治療に結びつけられます。
大腸内視鏡検査の流れと注意点
大腸内視鏡検査は下部消化管を詳しく調べるための検査ですが、初めて受ける人にとっては不安や抵抗を感じやすいかもしれません。前処置の方法や検査時の流れを事前に理解すると、安心して臨みやすくなります。
前処置で気をつけること
検査前日から腸内をきれいにするため、下剤の服用や食事制限を行います。腸内に便が残っていると視野が妨げられ、正確な診断が難しくなるので、水分をしっかり摂取し、指定されたルールに従って準備を進めてください。
大腸内視鏡検査の前処置のポイント
| 前処置内容 | 目的 | 注意点 |
|---|---|---|
| 下剤の服用 | 腸内を洗浄し便を排出させる | 医師の指示通りの服用時間と量を守る |
| 食事制限 | 検査前日~当日は消化に良い食事を取る | 繊維質や脂肪分が多い食品は控える |
| 十分な水分補給 | 脱水や便の硬化を防ぎ、排便を促す | 水・お茶などを定期的に摂取 |
| アレルギーや常用薬の確認 | 安全に検査を行うためのリスク管理 | 事前に医師や看護師に申告する |

実際の検査の進み方
検査当日は、検査着に着替えてベッドに横になった状態で、肛門から内視鏡が挿入され大腸全体を隅々まで観察します。ポリープや異常が見つかった場合は、その場で切除や生検を行うことがあります。
検査時間はおおむね15~30分程度が一般的ですが、状況によって変動します。
合併症リスクと対策
内視鏡挿入に伴う穿孔や出血などのリスクはゼロではありませんが、十分な経験のある医師が行えば発生率は低く抑えられます。鎮静剤を使用する場合は、呼吸や血圧などをモニタリングしながら進めるため、痛みや不安を軽減することが可能です。
検査後の過ごし方
検査後は腸内にガスが残り、腹部膨満感を感じることがあるため、しばらくベッド上で安静にし、鎮静剤を使用した場合は当日は自分で車やバイクの運転を行わず、付き添いを依頼すると安心です。
医師から説明された注意点を守りながら、検査後の経過に注意してください。
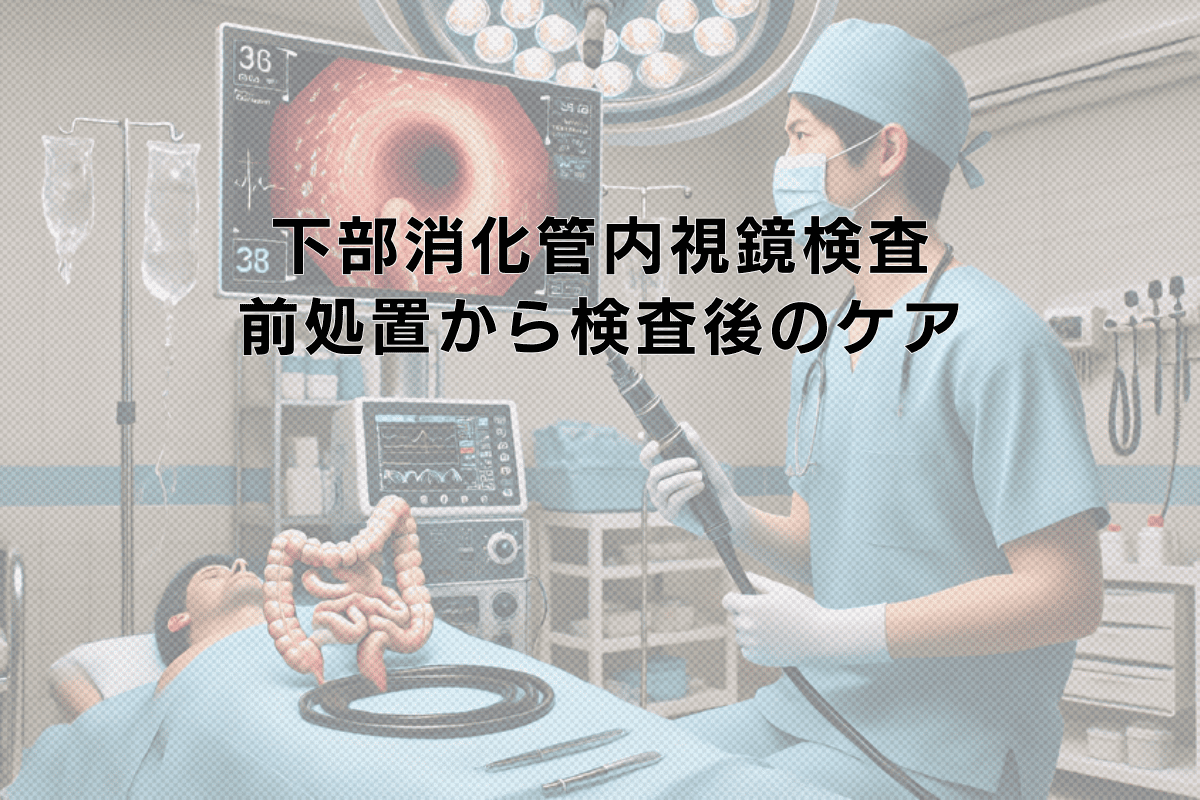
胃カメラ検査との違いと併用が検討されるケース
消化管は上部と下部で症状の原因が異なることがあり、胃カメラ(上部内視鏡)は主に食道や胃、十二指腸までを観察し、大腸内視鏡検査は小腸の終末部から大腸までを観察します。
下痢の原因が下部だけでなく上部にもある可能性がゼロではないため、必要に応じて併用が考慮されます。

胃カメラと大腸内視鏡の役割の違い
胃カメラは食道や胃、十二指腸の粘膜を直接観察します。逆流性食道炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍などの診断に向いています。一方、大腸内視鏡は結腸や直腸、回盲部付近を中心に観察し、大腸ポリープや大腸がん、炎症性疾患を見つけやすいです。
胃カメラ検査との違い
| 検査名 | 主な観察範囲 | 主に疑われる症状・疾患 |
|---|---|---|
| 胃カメラ(上部内視鏡) | 食道~胃~十二指腸 | 胃潰瘍、逆流性食道炎、胃がんなど |
| 大腸内視鏡 | 大腸全域、回盲部~直腸 | ポリープ、がん、炎症性疾患など |
下痢の原因が胃にある場合
胃酸の分泌異常や胃の機能低下が原因で消化が不十分になり、下痢につながることがあります。食べたものが胃で停滞し、腸内で異常発酵を起こすと軟便や水様便が続くことがあるため、上部内視鏡検査も考慮することが必要です。
上部消化管と下部消化管の関係性
食道から胃、十二指腸、小腸、大腸と続く消化管は、それぞれが連携して消化・吸収を行っていて、どこか1カ所で不調が起きると、その影響が別の箇所に波及する可能性があります。
上部と下部の両方を検査すれば、原因不明の下痢を包括的に調べられます。
同日に受けるメリットと注意点
上部と下部の内視鏡検査を同日に受けると、麻酔の準備や検査の日程を1回で済ませられるメリットがあります。ただし、両検査を受ける負担は大きくなるため、体力に自信がない人や基礎疾患がある人は事前に医師に相談してください。
よくある質問
大腸内視鏡検査に関する疑問を解消すると、検査を受ける際の不安を軽減できます。ここでは、下痢や便の状態が気になる方から寄せられやすい問い合わせをまとめました。
- 大腸内視鏡検査は痛いのでしょうか?
-
個人差はありますが、近年は鎮静剤や機器の進歩により、痛みが軽減されるよう配慮した検査が主流です。お腹にガスが入る感じや圧迫感を覚える場合がありますが、痛みが強いときは遠慮なく検査医に伝えてください。
- 下痢があるときに検査を受けても大丈夫ですか?
-
症状によりますが、感染症が疑われる場合などは医師の判断でスケジュールの調整を行います。慢性下痢や炎症性腸疾患が疑われる場合は、むしろ早めの検査が役立ちます。事前に医療機関へ症状を伝えて相談してください。
- 検査後に下痢がひどくなることはありますか?
-
通常の前処置や検査によって腸粘膜が大きく傷つくことは少ないです。ただし、一時的に腸内環境が変わり便通のリズムが乱れる場合があります。水分と栄養を適度にとり、身体を休めることで数日以内に落ち着くケースが多いです。
- 大腸内視鏡検査と胃カメラ検査は同時に受けるべきでしょうか?
-
症状の内容や医師の判断により、下痢の原因に便だけでなく胃の不調が関係している可能性があるときや、総合的な消化管のチェックを行いたいときは同日に受ける選択肢が考えられます。
時間や費用、身体への負担を考慮しながら検討してください。
次に読むことをお勧めする記事
【内視鏡検査前日にコーヒーは大丈夫? 飲む際の注意点】
下痢と便の変化について理解が深まったら、次は実際の大腸内視鏡検査の準備について知っておくと安心です。検査前日の食事や飲み物の注意点など、実践的な情報が特に参考になります。
【ポリープ摘出手術の方法と回復までの期間】
大腸内視鏡検査の必要性を学んだ皆さんには、検査で発見される可能性があるポリープの治療についても知っておくと、より包括的な理解ができます。
参考文献
Saito Y, Oka S, Kawamura T, Shimoda R, Sekiguchi M, Tamai N, Hotta K, Matsuda T, Misawa M, Tanaka S, Iriguchi Y. Colonoscopy screening and surveillance guidelines. Digestive Endoscopy. 2021 May;33(4):486-519.
Yamauchi Y, Arai M, Akizue N, Ohta Y, Okimoto K, Matsumura T, Fan MM, Imai C, Tawada A, Kato J, Kato N. Colonoscopic evaluation of diarrhea/colitis occurring as an immune-related adverse event. Japanese Journal of Clinical Oncology. 2021 Mar;51(3):363-70.
Ehsan A. Colonoscopy: analysis of indications and diagnoses at a specialist unit. Ann Pak Inst Med Sci [Internet]. 2010;6(1):15-9.
Bhagatwala J, Singhal A, Aldrugh S, Sherid M, Sifuentes H, Sridhar S. Colonoscopy—indications and contraindications. Screening for Colorectal Cancer with Colonoscopy. 2015 Dec 2:35-47.
Cai J, Yuan Z, Zhang S. Abdominal pain, diarrhea, constipation-which symptom is more indispensable to have a colonoscopy?. International Journal of Clinical and Experimental Pathology. 2015 Jan 1;8(1):938.
Singal AG, Gupta S, Lee J, Halm EA, Rutter CM, Corley D, Inadomi J. Importance of determining indication for colonoscopy: implications for practice and policy. Clinical Gastroenterology and Hepatology. 2014 Dec 1;12(12):1958-63.
Shah RJ, Fenoglio-Preiser C, Bleau BL, Giannella RA. Usefulness of colonoscopy with biopsy in the evaluation of patients with chronic diarrhea. The American journal of gastroenterology. 2001 Apr 1;96(4):1091-5.
Yusoff IF, Ormonde DG, Hoffman NE. Routine colonic mucosal biopsy and ileoscopy increases diagnostic yield in patients undergoing colonoscopy for diarrhea. Journal of gastroenterology and hepatology. 2002 Mar;17(3):276-80.
Marshall JB, Singh R, Diaz-Arias AA. Chronic, unexplained diarrhea: are biopsies necessary if colonoscopy is normal?. American Journal of Gastroenterology (Springer Nature). 1995 Mar 1;90(3).
Shah RJ, Fenoglio-Preiser C, Bleau BL, Giannella RA. Usefulness of colonoscopy with biopsy in the evaluation of patients with chronic diarrhea. The American journal of gastroenterology. 2001 Apr 1;96(4):1091-5.