突然の下痢や、長く続く下痢の症状に悩んでいませんか。
多くの人が経験する下痢ですが、背景にはさまざまな原因が隠れていて、特に大腸の状態は下痢の性質に深く関わっています。
この記事では、下痢の基本的な知識から便の状態でわかる健康のサイン、そしてどのような場合に専門的な内視鏡検査を検討すべきかについて、詳しく解説します。
下痢の基本と体のサイン
下痢は多くの人が経験する症状ですが、期間や原因は様々です。急性・慢性といった下痢の基本的な分類から、下痢が起こる体の仕組み、対処する上で最も重要な水分補給のポイントや自己判断のリスクについて解説します。
急性下痢と慢性下痢の違い
下痢は、持続期間によって大きく二つに分類され、一つは数日から2週間程度で治まる急性下痢、もう一つは4週間以上続く慢性下痢です。
急性下痢はウイルスや細菌への感染、食あたりなどが主な原因で、慢性下痢は生活習慣やストレス、あるいは何らかの病気が背景にある可能性を考えます。
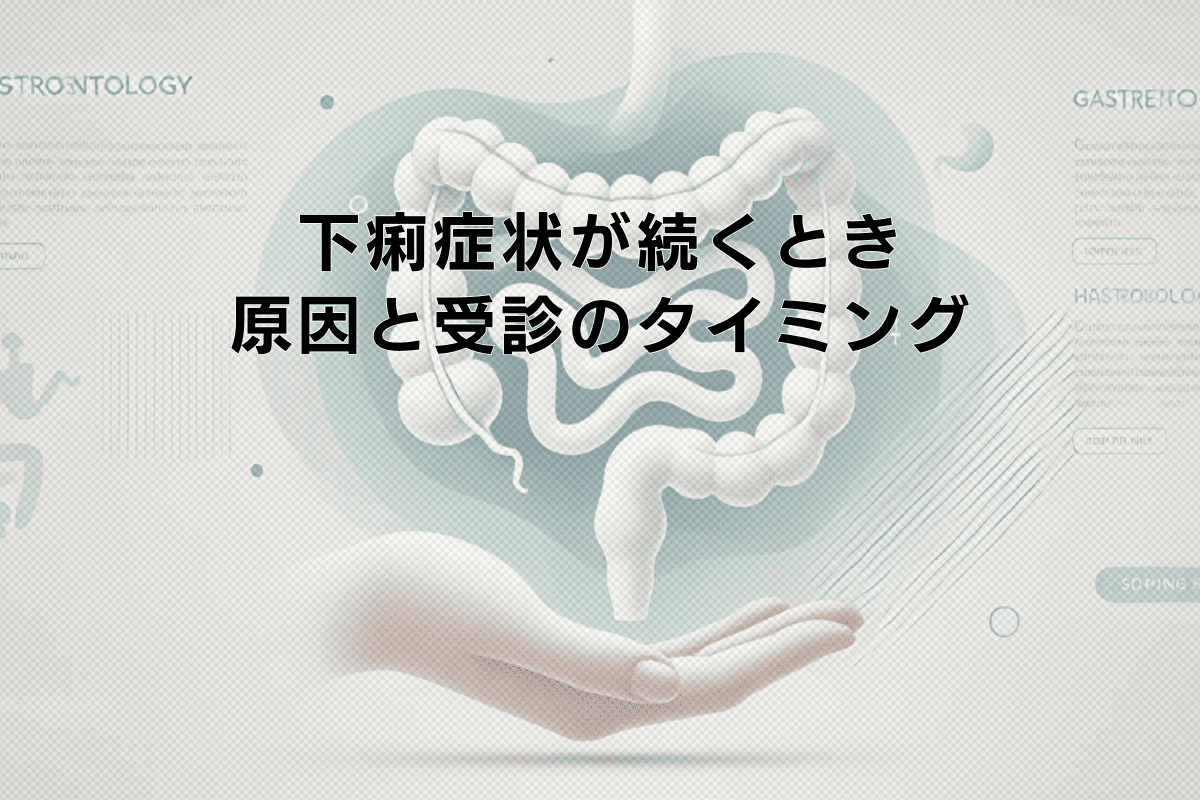
期間による下痢の分類
| 分類 | 持続期間 | 主な原因 |
|---|---|---|
| 急性下痢 | 2週間未満 | ウイルス感染、細菌感染、暴飲暴食 |
| 遷延性下痢 | 2週間~4週間 | 感染後の腸機能低下など |
| 慢性下痢 | 4週間以上 | 過敏性腸症候群、炎症性腸疾患など |
下痢が起こる体の働き
便は、大腸で水分が吸収されることで適度な硬さになりますが、何らかの理由で大腸の水分吸収が不十分であったり、腸からの水分分泌が過剰になると、便の水分量が増加し下痢となります。
また、大腸の動きが活発になりすぎると便が腸内を速く通過してしまい、水分を十分に吸収できずに下痢を起こすこともあります。
体が異物を排出しようとする防御反応のこともあれば、大腸の機能に問題が生じているサインの場合もあるのです。
水分補給の重要性
下痢の症状がある時は、体から水分と同時に電解質(ナトリウムやカリウムなど)が失われます。
脱水症状を防ぐために水分補給は非常に重要ですが、冷たい飲み物や糖分の多いジュース、カフェインを含む飲料は、かえって腸を刺激することがあるため注意が必要です。
常温の水や麦茶、経口補水液などを少しずつ、こまめに摂取することを心がけてください。
自己判断の危険性
一時的な下痢であれば、市販の下痢止め薬で症状が和らぐこともあるものの、安易な使用は原因の特定を遅らせる可能性があります。
特に、細菌やウイルスを体外に排出しようとして起こる感染性の下痢の場合、下痢止め薬で腸の動きを止めると、かえって病原体を体内に留まらせてしまい、症状を悪化させる危険性があります。
症状が長引いたり他の症状を伴う場合は、自己判断で対処せず医療機関に相談することが大切です。
大腸の働きと下痢の関係
下痢の症状は、大腸の働きと深く結びついています。ここでは、下痢と大腸の密接な関係性を掘り下げていきます。
大腸の基本的な役割
大腸は消化吸収された食べ物の残りかすから水分を吸収し、便を形成する役割を担っていて、結腸と直腸から成り立っている全長約1.5メートルほどの臓器です。
水分吸収の機能が正常に働くことで適度な硬さの便を排出できますが、大腸の健康が損なわれると、水分バランスが崩れ下痢や便秘といった症状として現れます。
腸内フローラの乱れと下痢
私たちの腸内には数百種類、数十兆個もの細菌が生息しており、総称して腸内フローラと呼びます。腸内フローラは、消化吸収の補助や免疫機能の調整など、健康維持に重要な役割を果たしています。
食生活の乱れやストレス、抗生物質の使用などによって腸内フローラのバランスが崩れると、悪玉菌が優勢になり腸内環境が悪化し、下痢を引き起こす一因となります。
腸内環境に影響を与える要因
| 良い影響を与える習慣 | 悪い影響を与える習慣 |
|---|---|
| バランスの取れた食事 | 偏った食事(脂肪分の多い食事など) |
| 十分な睡眠 | 睡眠不足、不規則な生活 |
| 適度な運動 | 過度なストレス |
大腸の蠕動運動と便の硬さ
蠕動(ぜんどう)運動とは、大腸が内容物を先へ先へと送り出す動きのことです。運動が適切な速さで行われることで、水分吸収が効率よくなされ便が形成されます。
しかし、ストレスや自律神経の乱れなどによって蠕動運動が過剰になると、内容物が大腸を速く通過しすぎてしまい、水分の吸収が追いつきません。その結果、水分量の多い下痢便となります。
ストレスが大腸に与える影響
脳と腸は、自律神経などを介して密接に連携しており、これを脳腸相関と呼びます。強いストレスを感じると、脳から指令が出て自律神経のバランスが乱れ、大腸の運動機能に影響を及ぼすことがあります。
ストレスによって腸が過敏になったり蠕動運動が活発になったりし、腹痛を伴う起こすことがあります。過敏性腸症候群などは、この脳腸相関が深く関わる代表的な病気です。
便の状態は健康のバロメーター
毎日のお通じは体からの健康に関するメッセージで、便の色や形、粘液や血液の混入といった見た目の変化が、いろいろな体のサインとなります。
便の色からわかること
毎日排出される便の色を観察することで、消化管の健康状態を推測することが可能です。
通常、便の色は胆汁に含まれるビリルビンという色素によって黄褐色から茶褐色になりますが、消化管のどこかで異常が起きると、便の色に変化が現れることがあります。
便の色と考えられる状態
| 便の色 | 考えられる状態 | 補足 |
|---|---|---|
| 黒色(タール便) | 食道、胃、十二指腸からの出血 | 血液が胃酸で酸化して黒くなります。 |
| 赤色(血便) | 大腸や肛門付近からの出血 | 鮮やかな赤色ほど肛門に近い部位からの出血です。 |
| 白色・灰白色 | 胆汁の流れが悪い(胆道系の異常) | バリウム検査後にも見られます。 |
便の形状で判断する
便の形状や硬さは、主に便に含まれる水分量によって決まり、食べ物が大腸を通過する時間と密接に関係しています。理想的な便は適度な水分を含み、スムーズに排出されるものです。下痢の状態では、形状を保てないほど水分が多くなります。
便の形状と水分量の目安
| 形状 | 状態 | 水分量の目安 |
|---|---|---|
| バナナ状 | 健康な状態 | 約70~80% |
| 半練り状 | 下痢気味 | 約80~90% |
| 水様便 | 下痢の状態 | 90%以上 |
粘液や血液の混入
便にゼリー状の粘液や血液が混じっている場合、大腸の粘膜に炎症が起きている可能性があり、粘液は腸の粘膜を保護するために分泌されるものですが、炎症が起こると量が増加します。
また、血液が混じる血便は、潰瘍やポリープ、がんなどの病気のサインである可能性も否定できません。粘液と血液が混じった粘血便が続く場合は、特に注意が必要です。
腹痛や発熱など他の症状
下痢だけでなく他にどのような症状があるかも重要な情報で、激しい腹痛や発熱、嘔吐などを伴う場合は、感染性腸炎の可能性が考えられます。
また、体重の減少がみられる慢性的な下痢は、炎症性腸疾患や吸収不良症候群、悪性腫瘍なども視野に入れる必要があります。複数の症状が組み合わさって現れる場合は、早めに医療機関を受診してください。
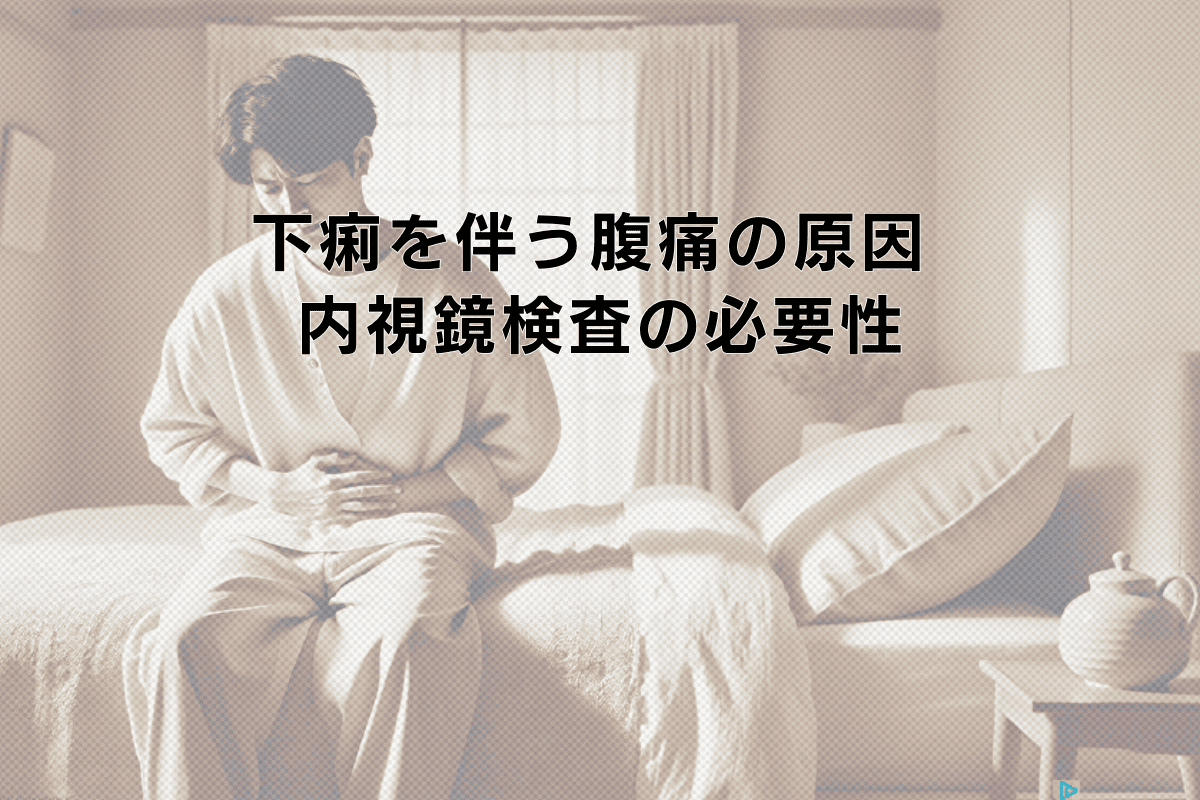
下痢を引き起こす大腸の主な病気
長引く下痢や繰り返す下痢の背景には特定の病気が隠れていることが多く、下痢を主な症状とする大腸の病気について説明します。
過敏性腸症候群(IBS)
過敏性腸症候群は、大腸に明らかな異常がないにもかかわらず、腹痛や腹部の不快感を伴う下痢や便秘が長く続く病気です。
ストレスが症状の引き金になることが多く、主に下痢を繰り返す下痢型、便秘と下痢を交互に繰り返す混合型などがあります。
潰瘍性大腸炎
潰瘍性大腸炎は、大腸の粘膜にびらんや潰瘍ができる原因不明の炎症性腸疾患の一つで、主な症状は持続する下痢、血便、腹痛、発熱などです。
症状が落ち着いている寛解期と、悪化する活動期を繰り返す特徴があり、若年層での発症が多く、長期にわたる治療と管理が必要になります。
クローン病
クローン病も潰瘍性大腸炎と同じく炎症性腸疾患の一つですが、口から肛門までの消化管のあらゆる部位に炎症や潰瘍が起こりうる病気で、特に小腸や大腸が好発部位です。
主な症状は腹痛、下痢、体重減少、発熱、と潰瘍性大腸炎と症状が似ている点もありますが、腸に穴が開いたり(穿孔)、腸管が狭くなったり(狭窄)する合併症を起こしやすい特徴があります。
炎症性腸疾患の比較
| 特徴 | 潰瘍性大腸炎 | クローン病 |
|---|---|---|
| 主な炎症部位 | 大腸の粘膜(連続的) | 消化管全体(非連続的) |
| 主な症状 | 血便、下痢、腹痛 | 腹痛、下痢、体重減少 |
| 合併症 | 中毒性巨大結腸症など | 狭窄、穿孔、痔ろうなど |
感染性腸炎
細菌やウイルスなどの病原体が腸に感染することで起こる急性の下痢で、ノロウイルスやロタウイルスなどのウイルス性、カンピロバクターやサルモネラ菌などの細菌性が主な原因です。
汚染された食品や水、あるいは感染者からの接触を通じて感染します。症状は下痢、腹痛、嘔吐、発熱などで、多くは数日で改善しますが、重症化すると脱水症状などを起こすため、水分補給が大事です。
内視鏡検査(大腸カメラ)を検討するタイミング
原因がはっきりしない下痢が続く場合、大腸内視鏡検査(大腸カメラ)が原因究明の鍵となることがあります。
内視鏡検査でわかること
大腸内視鏡検査は、肛門から内視鏡(先端に小型カメラが付いた細い管)を挿入し、直腸から結腸の最も奥まで大腸全体の粘膜を直接観察する検査です。
医師がリアルタイムで映像を確認できるため、炎症の程度や範囲、ポリープ、がん、潰瘍などの存在を正確に診断できます。また、検査中に疑わしい部分の組織を採取して、病理検査で詳しく調べること(生検)も可能です。
検査を検討すべき症状のサイン
下痢が長く続いていたり特定の症状が見られる場合は、原因を特定するために内視鏡検査が推奨されます。自己判断で様子を見るのではなく、医療機関への相談を検討してください。
内視鏡検査を検討する症状
- 4週間以上続く原因不明の慢性的な下痢
- 便に血が混じる(血便)
- 黒い便(タール便)が出る
- 急な体重減少を伴う下痢
- 原因不明の貧血を指摘された
検査を受ける医療機関の選び方
大腸内視鏡検査は専門的な技術を要する検査で、検査を受ける際は消化器内科を専門とする医師が在籍し、検査実績が豊富な医療機関を選ぶことが望ましいです。
また、検査に伴う苦痛を軽減するために、鎮静剤の使用を選択できるかどうかも、医療機関選びの一つのポイントになります。事前にホームページなどで情報を確認したり、かかりつけ医に相談し、納得のいく医療機関を選びましょう。
検査前の準備について
正確な検査を行うためには、大腸の中を空にしてきれいにする必要があるため、検査前日は消化の良い食事をとり、検査当日は下剤(腸管洗浄剤)を服用します。食事制限や下剤の服用方法は、医療機関の指示に正確に従ってください。
検査前日に控える食事の例
| 控えるべき食品 | 理由 |
|---|---|
| きのこ類、海藻類 | 消化されにくく、腸内に残りやすい |
| 種のある果物(キウイ、いちごなど) | 種が腸壁に付着し、観察の妨げになる |
| 脂肪の多い肉や揚げ物 | 消化に時間がかかる |
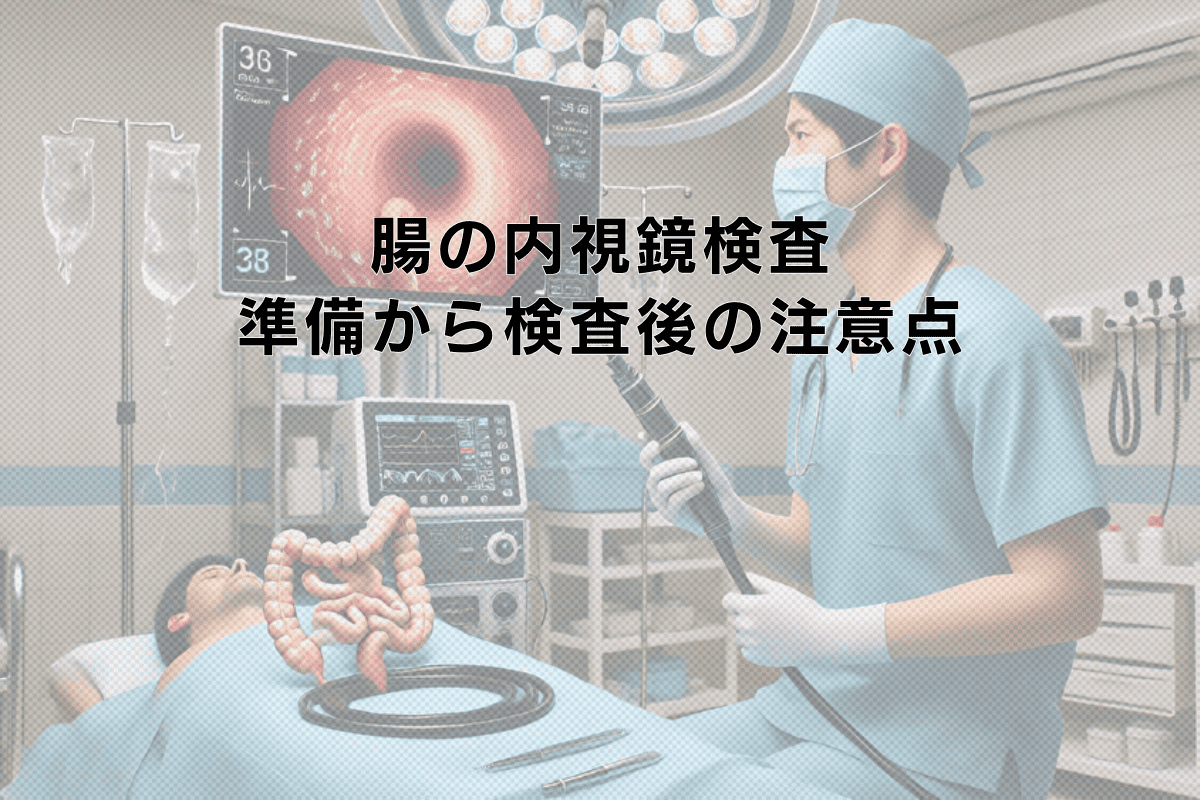
健やかな大腸を保つための生活習慣
日々の生活習慣は、大腸の健康に大きな影響を与えます。ここでは、腸に優しい食生活のポイント、腸内環境を整える発酵食品や食物繊維の摂り方、適度な運動や質の良い睡眠、ストレス管理といった方法を紹介します。
食生活の見直し
腸の健康は日々の食事と密接に関わっており、脂肪分の多い食事や香辛料の強い食べ物、アルコールの過剰摂取は、腸に負担をかけ、下痢の原因となることがあります。
特定の食品を食べた後に下痢をしやすい場合は、その食品を避けることも一つの方法です。
発酵食品と食物繊維
腸内環境を整えるためには、善玉菌を増やす食事が有効です。ヨーグルトや納豆、味噌などの発酵食品には、善玉菌そのものや、善玉菌のエサとなる成分が含まれています。
また、食物繊維は、善玉菌のエサになるだけでなく、便の量を増やして腸の運動を促す働きがあります。ただし、不溶性食物繊維を摂りすぎると、かえって腸を刺激することもあるため、水溶性食物繊維とバランスよく摂取することが大切です。
腸内環境を整える食品の例
| 種類 | 食品の例 | 主な働き |
|---|---|---|
| 発酵食品 | ヨーグルト、納豆、キムチ | 善玉菌を直接補給する |
| 水溶性食物繊維 | 海藻、こんにゃく、果物 | 善玉菌のエサになり、便を柔らかくする |
| 不溶性食物繊維 | ごぼう、きのこ類、豆類 | 便の量を増やし、腸を刺激する |
適度な運動のすすめ
ウォーキングやストレッチなどの適度な運動は、全身の血行を促進し、自律神経のバランスを整える効果が期待できます。運動により腸の蠕動運動が正常化し、便通の改善につながります。
また、ストレス解消にも役立ち、ストレス性の下痢の予防にもなるので、無理のない範囲で、日常生活に運動を取り入れる習慣をつけましょう。
睡眠とストレス管理
睡眠不足や慢性的なストレスは自律神経の乱れを起こし、腸の機能に直接影響を与えます。質の良い睡眠を十分にとることは、心身の回復だけでな腸の健康を保つ上でも重要です。
また、自分なりのストレス解消法を見つけることも大切で、趣味の時間を持つ、リラックスできる音楽を聴く、ゆっくり入浴するなど、心と体を休ませる時間を意識的に作りましょう。
よくある質問
最後に、下痢や大腸内視鏡検査に関して、多くの方が抱く疑問点についてお答えします。
- 下痢止めは飲んでも良いですか
-
下痢止め薬は、腸の動きを抑えることで症状を緩和しますが、原因によっては使用を避けるべき場合があります。
食中毒やウイルス感染など、体内の有害物質を排出しようとして起こる下痢の場合、薬で無理に止めると症状を長引かせる可能性があります。
自己判断での使用は慎重に行い、使用すべきか迷う場合は薬剤師や医師に相談してください。
- 子供の下痢で注意することは何ですか
-
子供、特に乳幼児は、大人に比べて体内の水分量が占める割合が高く、下痢によって脱水症状に陥りやすい傾向があります。水分補給が最も重要で、経口補水液などを少しずつ頻繁に与えることが推奨されます。
機嫌が悪くぐったりしている、尿の量が極端に少ない、唇が乾いているなどのサインが見られたら、速やかに医療機関を受診してください。
- 内視鏡検査は痛いですか
-
大腸内視鏡検査では、腸が曲がっている部分を通過する際や、観察のために空気で腸を膨らませる際に、お腹が張るような感覚や痛みを感じることがあります。
痛みの感じ方には個人差がありますが、多くの医療機関では、患者さんの苦痛を和らげるために鎮静剤(静脈麻酔)を使用する選択肢を用意しています。
鎮静剤を使用すると、うとうとと眠っているような状態で検査を受けられるため、不安や苦痛が大幅に軽減されます。
- 検査にかかる時間はどのくらいですか
-
検査自体の所要時間は、個人差はありますが、通常15分から30分程度です。ポリープを切除するなどの処置を行う場合は、もう少し時間がかかることもあります。
鎮静剤を使用した場合は、検査後に1時間ほど休憩室で休んでから帰宅となり、受付から会計まで、全体では2時間から3時間程度をみておくとよいでしょう。
次に読むことをお勧めする記事
【毎日の下痢症状が続くときの大腸内視鏡検査による診断基準】
“どのくらい続いたら検査?”と迷った方へ。期間別の受診目安と、内視鏡で何を確認するかを分かりやすく整理しています。
【大腸内視鏡検査の3日前からの食事制限と準備】
検査の必要性が見えてきたら、当日までの食事・準備の実際を確認。“何を食べる?”“どれくらい控える?”に具体的に答えます。
参考文献
Kinoshita Y, Ariyoshi R, Fujigaki S, Tanaka K, Morikawa T, Sanuki T. Endoscopic diagnosis of chronic diarrhea. DEN open. 2022 Apr;2(1):e53.
Tadano T, Abe K, Sasaki S, Terasawa T, Hosono S, Katayama T, Hoshi K, Nakayama T, Hamashima C. Serious adverse events associated with bowel preparation for colonoscopy in Japan: Systematic review. Digestive Endoscopy. 2025 Jun 9.
Saito Y, Oka S, Kawamura T, Shimoda R, Sekiguchi M, Tamai N, Hotta K, Matsuda T, Misawa M, Tanaka S, Iriguchi Y. Colonoscopy screening and surveillance guidelines. Digestive Endoscopy. 2021 May;33(4):486-519.
Cai J, Yuan Z, Zhang S. Abdominal pain, diarrhea, constipation-which symptom is more indispensable to have a colonoscopy?. International Journal of Clinical and Experimental Pathology. 2015 Jan 1;8(1):938.
Marshall JB, Singh R, Diaz-Arias AA. Chronic, unexplained diarrhea: are biopsies necessary if colonoscopy is normal?. American Journal of Gastroenterology (Springer Nature). 1995 Mar 1;90(3).
Shah RJ, Fenoglio-Preiser C, Bleau BL, Giannella RA. Usefulness of colonoscopy with biopsy in the evaluation of patients with chronic diarrhea. The American journal of gastroenterology. 2001 Apr 1;96(4):1091-5.
Yusoff IF, Ormonde DG, Hoffman NE. Routine colonic mucosal biopsy and ileoscopy increases diagnostic yield in patients undergoing colonoscopy for diarrhea. Journal of gastroenterology and hepatology. 2002 Mar;17(3):276-80.
Fine KD, Seidel RH, Do K. The prevalence, anatomic distribution, and diagnosis of colonic causes of chronic diarrhea. Gastrointestinal endoscopy. 2000 Mar 1;51(3):318-26.
Lasson A, Kilander A, Stotzer PO. Diagnostic yield of colonoscopy based on symptoms. Scandinavian journal of gastroenterology. 2008 Jan 1;43(3):356-62.
Shen B, Khan K, Ikenberry SO, Anderson MA, Banerjee S, Baron T, Ben-Menachem T, Cash BD, Fanelli RD, Fisher L, Fukami N. The role of endoscopy in the management of patients with diarrhea. Gastrointestinal endoscopy. 2010 May 1;71(6):887-92.










