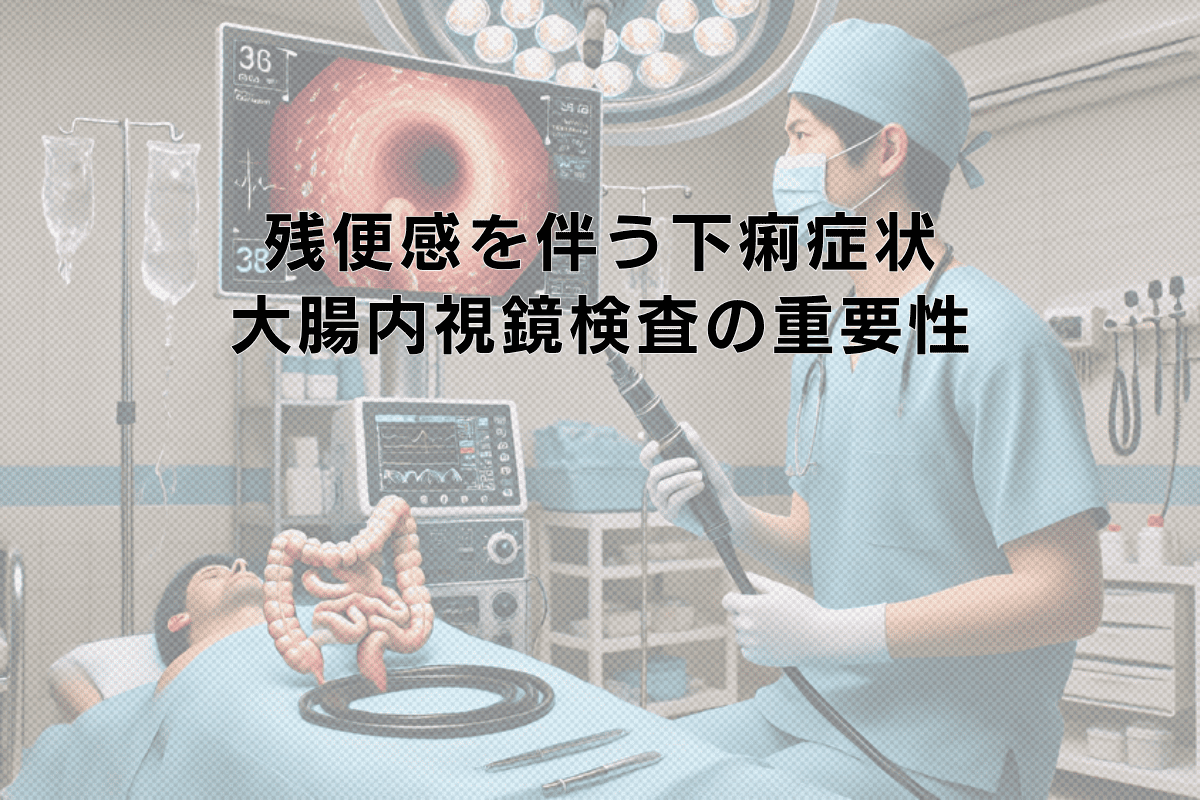何度もトイレに駆け込む下痢の症状に加え、すっきりと便が出きらない残便感が続くと、日常生活にも大きな影響が出てしまい、大変つらいものです。
通勤電車や大事な会議中、あるいは友人との旅行先で急な便意に襲われる不安は、計り知れない精神的な負担となります。多くの場合、一時的な体調不良によるものですが、中には注意が必要な消化器の病気が隠れている可能性も考えられます。
この記事では、残便感を伴う下痢がなぜ起こるのか、原因から考えられる病気、正確な診断のために非常に大切な大腸内視鏡検査の重要性まで、詳しく解説していきます。
残便感を伴う下痢とはどのような症状か
下痢と残便感が同時に現れる状態は、多くの人が一度は経験するかもしれない不快な症状で、この二つの症状が組み合わさることには、体からの特定のサインが隠されている場合があります。
下痢と残便感が同時に起こる体の状態
下痢は、腸のぜん動運動が過剰に活発になったり、腸管での水分吸収がうまくいかなくなったりすることで、便の水分量が増加して液状または泥状になる状態です。
健康な状態では、大腸が便から適切に水分を吸収し、固形の便を形成しますが、何らかの原因で大腸の粘膜に炎症が起きると、水分吸収能力が低下し、下痢を起こします。
残便感は、排便後も便がまだ直腸内に残っているようなすっきりしない感覚を指し、二つが同時に起こる場合、腸、特に大腸の機能に何らかの異常が生じていることを示唆します。
直腸に炎症やポリープ、腫瘍などがあると、それが物理的な刺激となって常に便意を感じさせ、少量ずつしか排便できないため下痢と残便感につながることがあります。
また、腸の動きをコントロールする自律神経のバランスが乱れることでも、腸が知覚過敏となり、同様の症状が現れます。
しぶり腹との違い
残便感を伴う下痢と似た症状に、しぶり腹(テネスムス)があります。しぶり腹は、強い便意を繰り返し感じるものの、いざトイレに行ってもほとんど便が出ないか、出てもごく少量しか出ない状態を指します。
残便感が主に排便後のすっきりしない感覚であるのに対し、しぶり腹は排便の有無にかかわらず、持続する強い便意そのものが主体となる点が特徴です。
両者は密接に関連しており、同時に感じることも少なくありません。しぶり腹は、直腸やS状結腸といった肛門に近い部分に強い炎症がある場合に顕著に見られ、炎症性腸疾患などでよくみられる症状です。
しぶり腹と残便感の主な違い
| 項目 | 残便感 | しぶり腹 |
|---|---|---|
| 主な感覚 | 排便後も便が残っている感覚 | 繰り返し続く強い便意 |
| 排便の状況 | 排便はあるがすっきりしない | 便がほとんど出ないか少量 |
| 関連する主な原因 | 腸の機能低下、炎症、腫瘍など | 直腸付近の強い炎症など |
残便感を伴う下痢を起こす主な原因
残便感を伴う下痢の原因は一つではなく、日々の生活習慣から特定の病気まで多岐にわたります。ここでは、主な原因を四つのカテゴリーに分けて詳しく解説します。
生活習慣の乱れとストレス
腸は、脳と自律神経などを介して密接に連携している(脳腸相関)ため、精神的なストレスの影響を非常に受けやすい臓器です。
強いプレッシャーや不安、緊張が続くと自律神経のバランスが崩れ、腸のぜん動運動に異常が生じ、腸が過敏に反応して下痢になったり、逆に動きが鈍くなって便秘になったりします。
また、睡眠不足や不規則な生活、運動不足も自律神経の乱れを助長し、腸の不調を起こす大きな原因です。現代社会の複雑な人間関係や仕事のプレッシャーが、知らず知らずのうちにお腹の症状として現れていることも少なくありません。
自律神経の乱れにつながる生活習慣
- 慢性的な睡眠不足
- 過度な精神的ストレス
- 運動不足
- 不規則な食事時間
食生活と腸内環境
日々の食事内容も、腸の健康に直接的な影響を与え、香辛料の多い刺激物、脂質の多い食事、アルコール、カフェインの過剰摂取は、腸の粘膜を刺激し、ぜん動運動を過剰にして下痢の原因となることがあります。
また、食事が腸内環境のバランスを崩すこともあります。
腸内には約100兆個もの細菌が生息しており、善玉菌、悪玉菌、日和見菌がバランスを保っていて、食生活の乱れなどによって悪玉菌が優勢になると、腸内で有害物質が作られ、腸の動きが乱れて下痢や便秘を起こしやすくなります。
腸に負担をかけやすい食事の例
| 分類 | 具体例 | 腸への影響 |
|---|---|---|
| 刺激物 | 唐辛子、カレー、わさび | 腸の粘膜を直接刺激し、ぜん動運動を活発化させる。 |
| 高脂質食 | 揚げ物、肉の脂身、生クリーム | 消化に時間がかかり、腸に負担をかける。脂肪酸が腸を刺激することもある。 |
| アルコール | ビール、ワイン、蒸留酒 | 腸の粘膜を傷つけ、水分の吸収を妨げる。 |
感染症による一時的な不調
ウイルスや細菌に感染して起こる感染性胃腸炎も、激しい下痢の原因となります。ノロウイルスやロタウイルスといったウイルス、カンピロバクターやサルモネラ菌といった細菌などが主な要因となり、多くは吐き気や嘔吐、腹痛、発熱を伴います。
この場合の下痢は、体内に侵入した病原体を速やかに排出しようとする体の重要な防御反応です。
通常は数日から一週間程度で症状は改善に向かいますが、炎症によって腸の粘膜がダメージを受けるため、治癒の過程で一時的に腸の機能が不安定になり、残便感を感じることがあります。
背景に隠れている可能性のある病気
生活習慣の改善や時間の経過によっても症状が良くならない場合、背景に何らかの病気が隠れている可能性を考える必要があります。
過敏性腸症候群(IBS)、潰瘍性大腸炎やクローン病といった炎症性腸疾患(IBD)、大腸がんなどが代表的です。これらの病気は、症状が似ていることもありますが、治療法やその後の経過が大きく異なります。
放置すると症状が悪化したり、重篤な状態につながったりする可能性があるため、早期の発見と対応が何よりも重要です。
注意が必要な消化器系の病気
残便感を伴う下痢が長引く場合、単なる体調不良ではなく、特定の消化器系の病気が原因である可能性を疑う必要があります。ここでは、代表的な三つの病気について、それぞれの特徴や症状を詳しく見ていきます。
過敏性腸症候群(IBS)
過敏性腸症候群は、血液検査や内視鏡検査をしても腸に炎症や潰瘍、腫瘍といった明らかな異常が見つからないにもかかわらず、下痢や便秘、腹痛、お腹の張りなどの症状が慢性的に続く病気です。
ストレスが症状の引き金になることが多く、主に腸の運動機能の異常と、刺激に対して腸が敏感に反応してしまう知覚過敏が関係していると考えられています。
残便感を伴う下痢が特徴的な下痢型のIBSでは、通勤中や試験前など、緊張や不安を感じる場面で強い便意に襲われる傾向があります。
命に関わる病気ではありませんが、症状が生活の質を大きく損なうため、薬物療法だけでなく、生活習慣の改善やストレス管理を含めた総合的な治療が大切です。
炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎・クローン病)
炎症性腸疾患は、腸の粘膜に原因不明の慢性的な炎症や潰瘍ができる病気の総称で、主に潰瘍性大腸炎とクローン病があり、どちらも国の指定難病で、近年患者数が増加しています。
潰瘍性大腸炎は大腸の粘膜に炎症が起こり、血便を伴う激しい下痢や腹痛、しぶり腹が主な症状です。
一方、クローン病は口から肛門までの消化管のあらゆる場所に深い炎症が起こる可能性があり、下痢や腹痛、体重減少、発熱などがみられ、また、関節や皮膚、眼など、腸以外の場所にも症状が現れることもあります。
どちらも病気も、症状が良くなる寛解期と悪化する活動期を繰り返す特徴があり、長期にわたる適切な治療と管理が必要です。
症状から見る病気の比較
| 症状 | 過敏性腸症候群(IBS) | 炎症性腸疾患(IBD) |
|---|---|---|
| 血便 | 通常はない | よく見られる(特に潰瘍性大腸炎) |
| 体重減少 | 通常はない | 見られることがある(特にクローン病) |
| 発熱 | ない | 見られることがある |
大腸がんの初期症状
大腸がんは、早期の段階では自覚症状がほとんどないことが多いですが、進行すると様々な症状が現れるようになります。
がんが直腸やS状結腸など、肛門に近い場所にできると、便の通り道が物理的に狭くなるため、便が細くなったり、排便後も便が残っているような残便感を感じたりします。
また、がんの表面はもろく出血しやすいため、便に血が混じる(血便)こともあり、がんが腸を刺激することで、腸の動きが不安定になり、下痢と便秘を繰り返すなど、排便習慣の変化として現れることも少なくありません。
症状は他の良性の病気と似ているため、自己判断は禁物です。特に40歳を過ぎたら、大腸がんのリスクが高まるため、注意が必要です。
医療機関を受診する目安
お腹の不調は誰もが経験するため、いつ病院に行くべきか判断に迷うことが多いですが、中には早急な対応が必要なケースもあります。
自宅で様子を見ても良いケース
症状が軽く、原因がはっきりしている場合は、数日間自宅で様子を見ることができます。
食べ過ぎや飲み過ぎ、特定の食品を食べた後など、一時的な原因による下痢で、この場合は、消化の良い食事を心がけ、常温の水や経口補水液で水分を十分に補給し、腸を休ませることが基本です。
腹痛が我慢できる範囲で、血便や発熱、体重減少などの他の症状がなく、水分補給がしっかりできていれば、自然に回復することがほとんどです。
ただし、症状が2〜3日経っても改善しない場合や、悪化する傾向が見られる場合は、医療機関に相談しましょう。
すぐに相談するべき危険なサイン
以下のような症状が見られる場合は、背景に重大な病気が隠れている可能性があるため、自己判断で様子を見ずに、速やかに消化器内科などの専門医を受診してください。早期発見が、その後の治療経過を大きく左右することがあります。
受診を急ぐべき症状の例
| 症状 | 考えられること | 対応 |
|---|---|---|
| 便に血が混じる(血便) | 炎症性腸疾患、大腸がん、感染症、痔など | 速やかに受診 |
| 原因不明の急な体重減少 | 大腸がん、炎症性腸疾患など | 速やかに受診 |
| 40歳以上で排便習慣が変わった | 大腸がんの可能性 | 一度検査を受けることを推奨 |
| 高熱や激しい腹痛を伴う | 重い感染症や腸の炎症、穿孔など | 速やかに受診 |
何科を受診すればよいか
下痢や残便感といったお腹の症状で困った場合は、消化器内科または胃腸科を受診するのが最も適切で、このような診療科は、食道から胃、小腸、大腸、肝臓、胆のう、膵臓まで、消化器全般を専門としています。
専門医が症状を詳しく聞き、必要な検査を行うことで、正確な診断と治療方針を決定します。もし、かかりつけの内科医がいる場合は、まずはそこで相談し、専門医を紹介してもらうという方法もあります。
消化器内科で行う主な検査
消化器内科を受診すると、問診から始まり、必要に応じて便や血液の検査、画像検査へと進みます。ここでは、一般的に行われる主な検査と目的について説明します。
問診と身体診察
診察はまず問診から始まり、医師は、症状がいつから始まったか、どのような症状があるか、排便の回数や便の状態(色、形、血液の有無)、食事内容、既往歴、服用中の薬、ストレスの有無、家族の病歴などについて詳しく質問します。
事前に症状のメモや日記を用意しておくと、正確な情報を伝えやすいです。その後、お腹の音を聞く聴診、お腹を触ってしこりや圧痛の有無を調べる触診などの身体診察を行い、病気のあたりをつけ、次の検査計画を立てます。
問診でよく聞かれる内容
- 症状の具体的な内容(下痢、残便感、腹痛、血便など)
- 症状が始まった時期と経過
- 食事やストレスなど、症状が悪化するきっかけ
- 過去にかかった病気や家族の病歴
便検査と血液検査
便検査では、便の中に目に見えないレベルの血液が混じっていないか(便潜血検査)、あるいは感染症の原因となる細菌やウイルスがいないかを調べます。便潜血検査は、特に大腸がんのスクリーニングとして非常に重要です。
血液検査では、体内の炎症の程度を示す数値(CRPなど)や貧血の有無(赤血球数、ヘモグロビン値)、栄養状態(アルブミン値など)を確認します。
慢性的な出血があれば貧血がみられ、炎症性腸疾患やがんの可能性を考えるきっかけになり、検査によって、体の中で何が起こっているのかを客観的に評価することができます。
各検査からわかる情報
| 検査名 | 目的 | わかること |
|---|---|---|
| 便潜血検査 | 消化管からの目に見えない出血の有無を調べる | 大腸がんやポリープ、炎症などの可能性 |
| 血液検査 | 全身の状態を把握する | 炎症の有無、貧血、栄養状態、肝機能など |
腹部超音波(エコー)検査
腹部超音波検査は、超音波を使ってお腹の中の臓器の状態を画像として映し出す検査です。
体に負担がなく、放射線被曝の心配もないため、安全に繰り返し行え、腸壁の厚さやむくみ、腸の動き、腹水の有無などを観察できるほか、肝臓や胆のう、膵臓、腎臓といった他の臓器に異常がないかも同時に確認できます。
ただし、腸管内のガスが多いと画像が不鮮明になり、大腸の粘膜の状態を直接、詳細に観察することはできません。
大腸内視鏡検査の役割
上記の検査で異常が疑われたり、原因が特定できなかったりした場合に、最も精密な情報が得られるのが大腸内視鏡検査(大腸カメラ)です。
先端に小型カメラが付いた細長いスコープを肛門から挿入し、直腸から盲腸までの大腸全体の粘膜を直接カラー映像で観察し、炎症や潰瘍、ポリープ、がんなどをリアルタイムで確認できるため、確定診断に非常に重要な役割を果たします。
大腸内視鏡検査の重要性と実際
残便感を伴う下痢の原因を正確に診断する上で、大腸内視鏡検査は極めて重要な位置を占めます。検査と聞くと不安を感じる方も多いかもしれませんが、目的と流れを正しく理解することで、安心して検査に臨むことができます。
なぜ大腸内視鏡検査が重要なのか
大腸内視鏡検査の最大の利点は、大腸の内部を直接、詳細に観察できる点です。
レントゲンやCTなどの画像検査ではわからないような、粘膜のわずかな色の変化や微細な凹凸、数ミリ単位の小さなポリープまで発見することが可能なので、炎症性腸疾患や大腸がんなどの病気を早期に発見し、確定診断を下すことができます。
また、検査中に疑わしい部分が見つかった場合、その場で組織の一部を採取して(生検)、顕微鏡で詳しく調べる病理検査に提出することもできます。
検査でわかること
検査により、多岐にわたる大腸の病気の有無を確認でき、特に、自覚症状だけでは区別が難しい病気の鑑別診断に役立ちます。また、がんの前段階であるポリープ(腺腫)を発見し、その場で切除することも可能です。
ポリープを切除することは、将来の大腸がんを予防する最も確実な方法の一つであり、診断と治療、予防を同時に行える点がこの検査の大きな特徴です。
大腸内視鏡検査で発見可能な主な病気
| 病気のカテゴリー | 具体的な病名 | 検査での所見 |
|---|---|---|
| 腫瘍性疾患 | 大腸がん、大腸ポリープ | 隆起や陥凹、出血、粘膜の模様の乱れ |
| 炎症性疾患 | 潰瘍性大腸炎、クローン病、感染性腸炎 | 粘膜の発赤、びらん、潰瘍、むくみ |
| その他 | 大腸憩室症、虚血性腸炎 | 粘膜のくぼみ(憩室)、粘膜の蒼白や出血 |
検査を受ける前の準備
正確で安全な検査を行うためには、事前の準備がとても大切です。検査前日は、消化の良い食事(おかゆ、素うどん、豆腐、白身魚など)を摂り、きのこや海藻、種子の多い果物、色の濃い野菜など、腸に残りやすい食品は避ける必要があります。
そして、検査当日の朝、自宅で下剤(腸管洗浄剤)を約1〜2リットル、数時間かけて服用し、大腸の中を空っぽにします。便がきれいな水様になるまで飲み続ける必要がありますが、検査の精度を左右する重要な準備です。
この準備が不十分だと、腸内に便が残ってしまい、病変の見逃しにつながる可能性があります。

検査当日の流れと注意点
医療機関に到着後、検査着に着替え、検査室では、体の緊張を和らげるために鎮静剤を使用することが多く、眠っているようなリラックスした状態で検査を受けられます。検査時間は通常15分から30分程度ですが、個人差があります。
医師はモニターで大腸の内部を隅々まで観察し、ポリープが見つかった場合は、大きさや形に応じて切除することがあります。検査終了後は、鎮静剤の効果が覚めるまで1時間ほどリカバリールームで休憩します。
鎮静剤を使用した場合は、当日の車やバイク、自転車の運転はできませんので、公共交通機関を利用するか、家族に送迎を依頼しましょう。
日常生活でできるセルフケア
医療機関での診断と治療はもちろん重要ですが、症状を和らげ、再発を防ぐためには、日々の生活習慣を見直すことも同じくらい大切です。
ここでは、食事、ストレス管理、腸内環境の三つの観点から、ご自身で取り組めるセルフケアについて紹介します。
食生活の見直しと改善点
腸に負担をかけない食事を心がけることが基本で、下痢の症状が強い時は、おかゆやうどん、白身魚、豆腐など、消化が良く、温かいものを中心に摂りましょう。症状が落ち着いてきたら、食物繊維を少しずつ取り入れます。
食物繊維には、水に溶けやすい水溶性食物繊維と、溶けにくい不溶性食物繊維があり、下痢の時は、便をゲル状にしてくれる水溶性食物繊維(海藻、こんにゃく、熟した果物など)を中心に、バランス良く摂ることが推奨されます。
不溶性食物繊維(ごぼう、きのこ、玄米など)は腸を刺激することがあるため、摂りすぎに注意が必要です。
腸の調子を整える食品の例
| 栄養素 | 働き | 含まれる食品 |
|---|---|---|
| 水溶性食物繊維 | 便の硬さを調整し、善玉菌のエサになる | わかめ、昆布、りんご、バナナ、里芋 |
| 発酵食品 | 善玉菌を直接補給する | ヨーグルト、納豆、味噌、チーズ |
| オリゴ糖 | 善玉菌のエサになり、増殖を助ける | 玉ねぎ、ごぼう、大豆、はちみつ |

ストレス管理とリラックス法
腸と脳は密接に関連しているため(脳腸相関)、ストレスを上手に管理することは、腸の健康を保つ上で非常に重要です。まずは、十分な睡眠時間を確保し、体を休ませることを優先してください。
日々の生活の中に、自分が心からリラックスできる時間を取り入れることも効果的で、ぬるめのお風呂にゆっくり浸かる、好きな音楽を聴く、軽いウォーキングをするなど、無理なく続けられることを見つけるのが長続きの秘訣です。
深い呼吸を意識するだけでも、副交感神経が優位になり、心身のリラックスにつながります。
リラックス法の実践例
- 腹式呼吸や瞑想
- ぬるめのお風呂にゆっくり浸かる
- 好きな音楽を聴く、読書をする
- 軽いウォーキングやストレッチ
腸内環境を整える習慣
健康な腸内環境は、多様な善玉菌が優位な状態です。
善玉菌を増やすためには、善玉菌そのものを含む発酵食品(プロバイオティクス)と、善玉菌のエサとなるオリゴ糖や食物繊維(プレバイオティクス)を一緒に摂るシンバイオティクスという考え方が効果的です。
また、適度な運動は腸のぜん動運動を促し、血行を良くするため、腸内環境の改善に役立ちます。
毎日決まった時間にトイレに行く習慣をつけることも、排便のリズムを整える上で助けになり、焦らず、リラックスしてトイレタイムを確保することが大切です。
残便感を伴う下痢に関するよくある質問
- 症状は市販薬で対応できますか。
-
一時的な食べ過ぎやストレスによる下痢であれば、市販の下痢止め薬で症状が和らぐことがあります。
しかし、薬で無理に下痢を止めると、感染症の場合に原因となる菌やウイルスを体内に留めてしまい、かえって回復を遅らせることがあります。
また、残便感を伴う下痢が続く場合、背景に治療が必要な病気が隠れている可能性もあり、市販薬はあくまで対症療法で、根本的な原因の解決にはなりません。
症状が長引く場合や、血便など他の気になる症状がある場合は、自己判断で市販薬を使い続けず、まずは最寄りの医療機関で原因を調べてもらうことが大事です。
- 症状はどのくらい続いたら病院に行くべきですか。
-
明確な日数の基準はありませんが、一般的に2週間以上症状が続くようであれば、一度消化器内科を受診することを検討してください。
市販薬を試しても改善しない、症状がだんだん悪化している、日常生活に支障が出ている、といった場合は早めの受診が望ましいです。
また、期間にかかわらず、便に血が混じる、原因不明の体重減少、高熱、我慢できないほどの強い腹痛といった危険なサインが見られる場合は、様子を見ずにすぐに医療機関へ相談してください。
- 大腸内視鏡検査は痛いですか。
-
検査に対する不安として、痛みや苦しさを心配される方は少なくありません。
大腸は曲がりくねっているため、スコープを挿入する際に腸が押されて痛みや張りを感じることがありますが、近年では医療技術が進歩し、患者さんの負担を軽減するための様々な工夫がなされています。
多くの医療機関では、鎮静剤を使用してうとうとと眠っているようなリラックスした状態で検査を行いますので、痛みや不快感をほとんど感じることなく検査を終えることができます。
また、お腹の張りの原因となるスコープから送る空気に代わり、体への吸収が早い炭酸ガスを使用する施設も増えています。
- 検査費用はどのくらいかかりますか。
-
大腸内視鏡検査の費用は、観察のみの場合、ポリープを切除した場合、あるいは組織を採取して病理検査に出した場合などで自己負担額が変わります。
3割負担の場合、一般的な目安として、観察のみであれば1万円前後、ポリープ切除などの処置を行った場合は2万円から3万円程度になることが多いです。
ただし、あくまで目安であり、使用する薬剤や処置の内容によって異なりますので、正確な費用については検査を受ける医療機関に直接お問い合わせください。
次に読むことをお勧めする記事
【大腸内視鏡検査の3日前からの食事制限と準備】
残便感を伴う下痢の原因を知ったら、次は実際の大腸内視鏡検査の準備について知っておくと安心です。検査を初めて受ける方や、前回の準備がうまくいかなかった方に特に参考になる内容です。
【いつ大腸がん検査を受けるべきか|症状チェックから精密検査まで】
“残便感+下痢”を学んだ皆さんには、便潜血や内視鏡を含む大腸がん検査全体の理解も有用です。症状別の受診タイミングを整理できます。
以上
参考文献
Shen B, Khan K, Ikenberry SO, Anderson MA, Banerjee S, Baron T, Ben-Menachem T, Cash BD, Fanelli RD, Fisher L, Fukami N. The role of endoscopy in the management of patients with diarrhea. Gastrointestinal endoscopy. 2010 May 1;71(6):887-92.
Mueller K, Karimuddin AA, Metcalf C, Woo A, Lefresne S. Management of malignant rectal pain and tenesmus: a systematic review. Journal of Palliative Medicine. 2020 Jul 1;23(7):964-71.
Saad AH. Role of sigmoidoscopy in the diagnosis of lower GIT bleeding. Revista Latinoamericana de Hipertensión. 2019;14(6):697-701.
Kim ES, Jeen YT, Kim JY. A Patient Experiencing Bloody Diarrhea and Tenesmus for Three Weeks. Intestinal research. 2015 Apr 27;13(2):180.
Ok KS, Kim YS, Song JH, Lee JH, Ryu SH, Lee JH, Moon JS, Whang DH, Lee HK. Trichuris trichiura infection diagnosed by colonoscopy: case reports and review of literature. The Korean journal of parasitology. 2009 Aug 28;47(3):275.
Sakdyyah A, Bestari MB, Suryanti S. Description of colonoscopy and histopathology of chronic diarrhea causes in non-neoplasm: literature review. The Indonesian Journal of Gastroenterology, Hepatology, and Digestive Endoscopy. 2021 May 12;22(1):52-9.
Cappell MS, Friedel D. The role of sigmoidoscopy and colonoscopy in the diagnosis and management of lower gastrointestinal disorders: endoscopic findings, therapy, and complications. Medical Clinics. 2002 Nov 1;86(6):1253-88.
Younis H, Moustafa H, Alaam M. Value of colonoscopy in the diagnosis of lower gastrointestinal disorders. Al-Azhar Med J. 2003 Sep;1:1-4.
Orenstein JM, Dieterich DT. The histopathology of 103 consecutive colonoscopy biopsies from 82 symptomatic patients with acquired immunodeficiency syndrome: original and look-back diagnoses. Archives of pathology & laboratory medicine. 2001 Aug 1;125(8):1042-6.
Caklili OT, Tuncer İ, Colak Y, Kosemetin D, Ceyran AB. Colonic duplication in adulthood presenting with diarrhea. Endoscopy. 2013 Dec;45(S 02):E430-1.