人の身体を支えるうえで、飲み込んだ食べ物をエネルギーに変え、不要な物を体外に排出する一連の仕組みは重要で、その中心を担っているのが消化器官です。
胃や大腸にトラブルが生じると、栄養摂取だけでなく身体全体のバランスにも影響が及び、これらの臓器を直接観察して病気の有無を明らかにする方法として、内視鏡検査は大切です。
自覚症状が少ない段階でも、潜んでいる病変を見つけられる可能性があることから、検査を通じて正しいケアにつなげる必要があります。
消化器官とは何か
食事で摂取した栄養素が体内に吸収されるまでの流れを支える部位として、口から始まり肛門に至るまでの消化管と、それに関与する臓器全体を消化器官と呼ぶことがあります。
多くの方が、消化器官と消化管の違いを厳密に意識せず生活を送っていますが、その定義を理解すると、食べ物が身体に与える影響を考えやすくなります。
食べる行為は日常に溶け込んでいるため、異変が起こったときになかなか気づきにくいかもしれません。しかし、食道・胃・大腸などは身体の状態を反映しやすく、セルフケアと定期的な検査で健康維持をサポートすることが可能です。
消化器官と消化管の違い
消化器官は主に、口腔・咽頭・食道・胃・小腸・大腸などの消化管と、消化液を分泌する肝臓・胆嚢・膵臓などの付属器官を含む幅広い概念で、消化管は、口から肛門へと連なる管状構造そのものを指す場合が多いです。
そのため、食道や胃、大腸はどちらの範疇にも入りますが、付属器官と呼ばれるものは消化器官のほうに含まれます。
消化器官を構成する主な臓器
消化器官と総称しても、実際には複数の臓器が役割を分担しています。
主な消化器官と働き
| 臓器 | 働きの概要 |
|---|---|
| 口腔 | 食物を噛み砕き、唾液と混ぜる |
| 咽頭 | 食物と気道を分ける。飲み込む機能に関与 |
| 食道 | 咀嚼した食物を胃へ送り込む筋肉の管 |
| 胃 | 食物を一時的に貯蔵し、胃酸で消化 |
| 小腸 | 消化酵素や胆汁を受け取り、栄養を吸収 |
| 大腸 | 水分を再吸収し、便を形成・排出 |
| 肝臓 | 胆汁の生成や解毒機能。代謝全般に関与 |
| 胆嚢 | 肝臓が生成した胆汁を蓄え、小腸へ分泌 |
| 膵臓 | 消化酵素やホルモンを分泌し、血糖値調整にも関与 |
これらの臓器は互いに協力し合いながら、消化から排泄に至るまでを円滑に行い、いずれかの機能が落ちると、消化や栄養吸収が滞り、体内バランスが乱れやすくなります。
食物が通るプロセスの概要
口で食物をかみ砕く段階から、大腸へ到達し便として排出されるまでには、以下のような流れがあります。
- 口で咀嚼し、唾液の酵素で一部が分解される
- 食道を通り、胃で胃酸などによりさらに分解される
- 小腸で多くの栄養素が吸収される
- 大腸で残った水分が再吸収され、便が形成される
プロセスが円滑に行われるためには、個々の臓器がそれぞれの役割をしっかり果たす必要があります。特に胃や大腸は、食物がとどまる時間が比較的長いため、病気やトラブルが起きやすい部位です。

胃の働きと代表的な疾患
食べたものを一時的に貯蔵し、強い酸によって殺菌・分解する機能をもつ胃は、消化器官の中でも問題が起こりやすく、食習慣や生活リズムが乱れると、胃の粘膜に過度の負担がかかり、胃痛・胸やけ・もたれといった不調が出やすくなります。
ピロリ菌の感染や過度なストレスなど、多くの要因が病気の引き金となるので、内視鏡検査で粘膜の状態を確認することが大切です。
胃が担う消化機能
胃には、以下のような主要な消化機能があります。
- 胃酸による殺菌
- ペプシンをはじめとする酵素によるタンパク質分解
- 食物を攪拌し、粥状になるまで消化を進める
消化機能がうまく働くと小腸での栄養吸収がスムーズになり、身体が必要とするエネルギーを確保しやすくなります。一方で、胃酸の分泌過多やストレスで胃粘膜が荒れると、胃潰瘍や逆流性食道炎などが起こりやすくなるため注意が必要です。
胃にみられる主な疾患
胃の代表的な疾患には次のようなものがあります。
主な胃の疾患と特徴
| 疾患名 | 特徴 |
|---|---|
| 急性胃炎 | 一時的な胃粘膜の炎症。飲酒や薬剤、ストレスが原因になることが多い |
| 慢性胃炎 | ヘリコバクター・ピロリ菌感染や長期的な刺激で慢性的に炎症が続く |
| 胃潰瘍 | 胃酸やピロリ菌などで粘膜が深く傷つく疾患 |
| 逆流性食道炎 | 胃酸が食道へ逆流し、炎症を引き起こす疾患 |
| 胃ポリープ・胃がん | 粘膜の過形成や腫瘍が形成される。内視鏡検査による早期発見が有用 |
胃がんをはじめとする重篤な病気は、初期段階で症状に乏しい場合があり、定期的に内視鏡検査を受けることで早期に病変を見つけられる可能性が高まります。
胃の不調を見逃さないためのポイント
胃の不調を早めに察知するには、日常生活において以下の点を意識することが重要です。
- 食後に胃もたれが続く、食欲不振が改善しない
- 胸やけや酸っぱい液がこみ上げる感じが続く
- みぞおちあたりの違和感や痛みが定期的にある
- 体重減少や貧血など、全身状態に変化が出る
このような症状が長引くときには、早めに医療機関へ相談し、必要に応じて内視鏡検査を検討してください。
大腸の働きと代表的な疾患
小腸で吸収しきれなかった水分やミネラルを再吸収し、便を形成して体外へ送り出す大腸は、消化器官の中でも重要な役割を担う臓器です。
近年は大腸に関する疾患が増えている背景もあり、早期発見や予防が注目されていて、毎日の便通の状態をチェックして、大腸からのシグナルをいち早く把握しましょう。
大腸の消化・吸収機能
大腸での主な機能は、水分や電解質の再吸収と便の形成で、便には体内で不要になった老廃物が多く含まれますが、その前段階で大腸が上手に水分を回収しないと、下痢や脱水状態を招くおそれがあります。
逆に水分を吸収しすぎると便が硬くなり、便秘の原因になる場合があります。
大腸の主な構成
| 区域 | 機能の特徴 |
|---|---|
| 盲腸・上行結腸 | 小腸から送られた内容物を受け取り、水分吸収を開始 |
| 横行結腸 | さらに水分や電解質を吸収しつつ、便が移動しやすいよう攪拌する |
| 下行結腸 | 便を下方へ押し出しながら、まだ残る水分を回収 |
| S状結腸 | 便の貯留と排便反射のきっかけづくり |
| 直腸 | 便意を感じ、排便をコントロールする |
大腸の機能が落ちると、体内バランスが崩れて疲れやすくなったり、腸内環境が乱れて肌トラブルに悩まされたりすることもあります。
大腸にみられる主な疾患
大腸に起こりやすい主な疾患
- 大腸ポリープ:粘膜が過形成や腫瘍性変化を起こしてできた隆起性病変
- 大腸がん:初期段階では症状がほぼなく、便潜血検査や大腸カメラで発見されることが多い
- 潰瘍性大腸炎:粘膜に広範囲で炎症や潰瘍が生じる自己免疫系の病気
- 過敏性腸症候群:検査で異常が見られないにもかかわらず、下痢や便秘、腹痛を繰り返す
早期段階のポリープや初期の大腸がんであれば、大腸カメラ検査による内視鏡治療で対処できる場合があるので、症状の有無に関わらず、適度に検査を受けると安心です。
便通異常におけるサイン
排便回数が減るだけでなく、いくつかの兆候も大腸からのサインとして注目してください。
- 便が細くなっている、形状が普段と異なる
- 血液が混じったり、黒い便が出たりする
- 下痢と便秘を交互に繰り返す
- お腹が常に張る、痛みや違和感がある
便通の異常はストレスや食生活の変化でも起こるため、単発的な症状だけで判断しにくいこともあり、長引く場合には早めに検査を検討することが大切です。
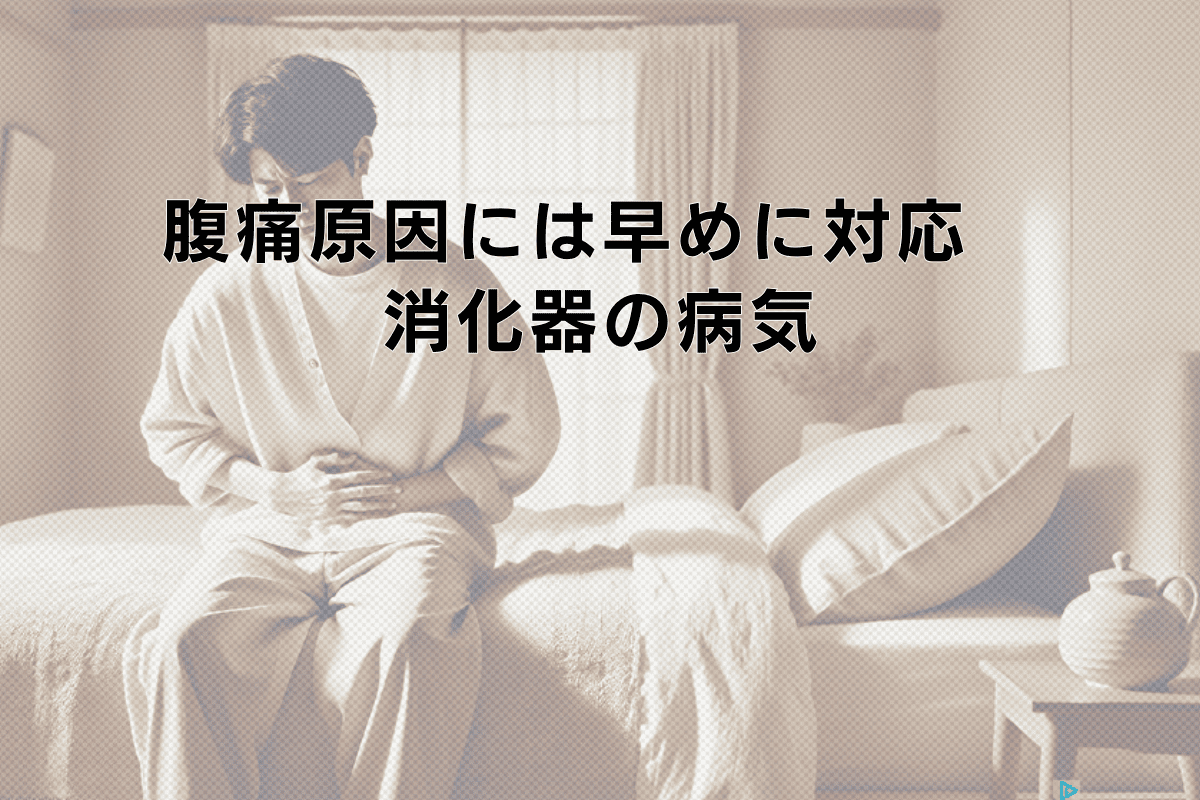
内視鏡検査が果たす役割
胃カメラと大腸カメラを中心とした内視鏡検査は、消化器官を直接観察しながら組織を採取できる点で有用で、病変が小さいうちに見つけられるだけでなく、その場でポリープ切除などの治療を実施できる場合もあります。
検査のイメージから敬遠されがちですが、麻酔や鎮静剤を利用することで苦痛を軽減する方法も一般的です。
胃カメラ検査の概要
胃カメラ検査は、口または鼻から内視鏡を挿入して食道・胃・十二指腸を直接観察する手法です。
- 胃炎・胃潰瘍・胃がんなどの病変確認
- ピロリ菌感染の検査や、必要に応じた生検
- 苦痛軽減のために鼻から挿入する経鼻内視鏡も選択肢の1つ
内視鏡を挿入する部位や検査方法は、医療機関によって異なりので、事前に医師と相談してください。

大腸カメラ検査の概要
大腸カメラ検査は肛門から内視鏡を挿入し、直腸から盲腸までの大腸全体を観察します。
大腸内視鏡検査の特徴
- ポリープが見つかった際、同時に切除や生検を行える
- 大腸がんの早期発見・早期治療のために受診者が増えている
- 検査前に腸内をきれいにするため下剤を飲む必要がある
腸管の洗浄が十分でないと病変の見落としが起こりやすいため、受検前の準備は念入りに行うことが大切です。

それぞれの検査で判明する異常
胃カメラ検査と大腸カメラ検査では、さまざまな異常を直接確認できます。
内視鏡検査ごとに判明しやすい異常
| 検査名 | 主に確認可能な異常 | 付随機能 |
|---|---|---|
| 胃カメラ検査 | 胃炎、胃潰瘍、逆流性食道炎、胃がんなど | 生検・ピロリ菌検査、ポリープ摘除など |
| 大腸カメラ | ポリープ、大腸がん、潰瘍性大腸炎など | ポリープ切除、生検 |
症状がなくても、定期的に受けることで大きなリスクを回避できる可能性があります。特に40代以降は、胃がんや大腸がんのリスクが高まる傾向があるため、医師と相談して正しいタイミングで検査を受けることが推奨されています。
内視鏡検査でわかる疾患とリスク
内視鏡検査では、胃や大腸の病変をダイレクトに観察できるため、早期の病気発見に直結するケースが多いです。
腫瘍性のポリープや炎症所見など、肉眼だけでは判断しにくい変化も画像や生検で確認でき、病変が見つかった場合は、リスクや病期に応じて治療計画を立てられます。
ピロリ菌感染や胃炎
ピロリ菌に感染すると、胃の粘膜に慢性的な炎症が起こりやすく、長期的には胃がんの発生リスクが高まることが知られていますが、内視鏡検査を行い、以下の流れでピロリ菌感染を確認することが可能です。
- 胃の粘膜を直接観察して萎縮度合いや腸上皮化生を評価
- 必要に応じて組織を採取し、ピロリ菌検査(迅速ウレアーゼ試験など)を行う
- 陽性であれば除菌療法を検討する
除菌により胃潰瘍や胃がんのリスクを軽減できる場合があるため、胃カメラ検査での早期発見が大事です。

ポリープや大腸がんの早期発見
大腸に発生するポリープには、腫瘍性と非腫瘍性のものが混在し、腫瘍性ポリープは将来的にがん化する可能性があるため、見つかった時点で切除が検討されることが多いです。
大腸がんは初期症状が乏しく、進行するまでほとんど自覚症状を伴わない場合があります。
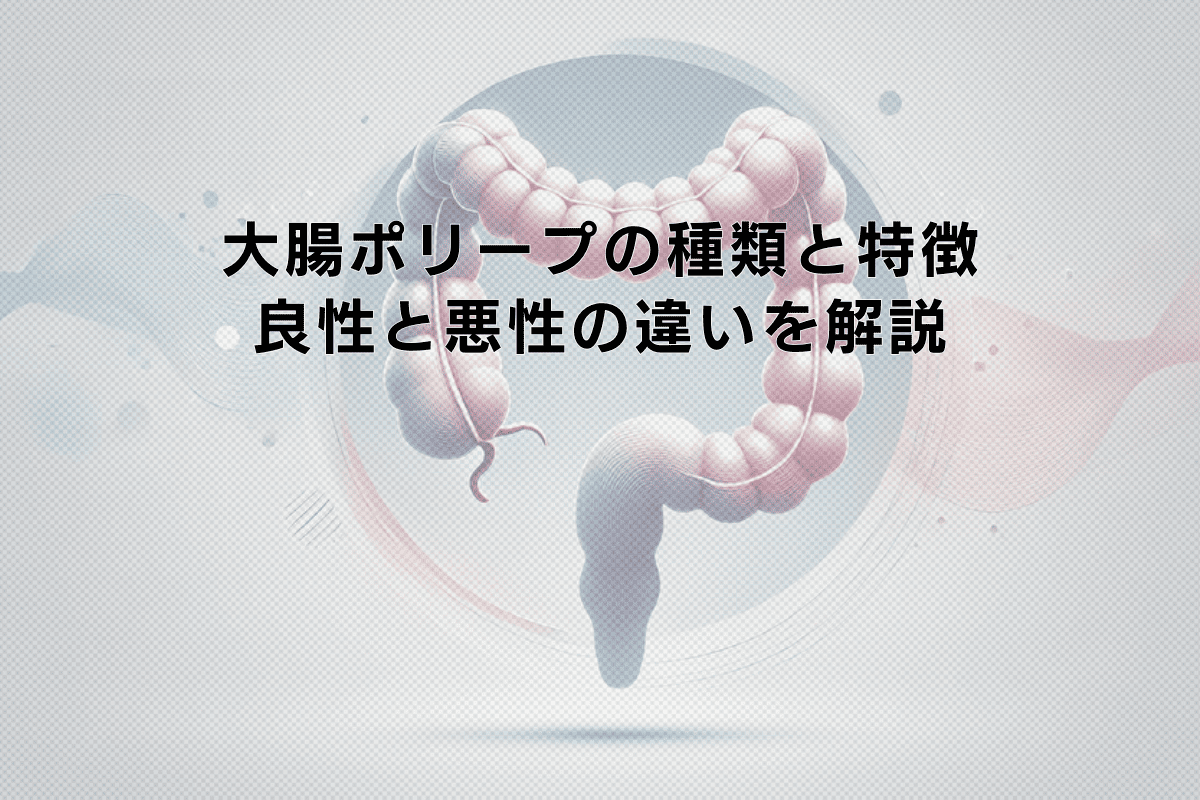
大腸がんの進行と症状の関係
| 病期 | 症状 | 検査での発見 |
|---|---|---|
| 早期 | ほぼ無症状 | 大腸カメラや便潜血検査で発覚 |
| 進行期 | 便潜血、便の形状変化、腹痛など | 自覚症状が表れ、検査で確定診断 |
| 末期 | 体重減少、貧血、便秘や下痢など | 症状が顕著。治療選択が限定的になる |
早期の段階で発見できれば、内視鏡治療や手術の選択肢も増えるため、定期的な検査の受診が有用です。
その他の消化管疾患の発見
内視鏡検査は、胃や大腸だけでなく、小腸や十二指腸に及ぶ病変も把握しやすく、以下のような疾患も見つけられる場合があります。
症状がはっきりしない腹痛や下痢が長引いているときには、小腸や大腸の内視鏡検査を含めて原因を調べることが重要です。
内視鏡検査を受けるメリットと注意点
内視鏡検査には、実際に臓器の内部を観察するからこそのメリットがありますが、検査前の準備や検査時の身体的負担に関する注意点もあります。
できるだけリスクを減らすために、事前の情報収集と医師とのコミュニケーションを大切にしましょう。

内視鏡検査のメリット
内視鏡検査を受けるメリットは、いくつもあります。
- 直接観察できるため、病変を詳しく評価できる
- ポリープなどの小さな病変を見逃しにくい
- 発見したポリープをその場で切除可能な場合がある
- 生検で病理診断ができ、早期の治療方針決定につながる
大腸や胃のがんは、初期に自覚症状が出にくい特徴があるため、早期発見の手段として内視鏡検査の意義が高いです。
検査前後に注意すべきこと
安全かつ正確な診断を得るために、内視鏡検査前後には以下の点に留意するとよいでしょう。
内視鏡検査前後の主な注意点
| 検査 | 準備 | 直後の留意点 |
|---|---|---|
| 胃カメラ | 前日夜からの絶食、水分制限など | のどの麻酔が切れるまで飲食注意、鎮静剤使用の場合は安静 |
| 大腸カメラ | 前日の下剤服用や腸内洗浄、食事制限など | 検査後の腹部膨満感、体調の把握。ポリープ切除時は安静 |
胃カメラ・大腸カメラともに、検査内容や医療機関によって準備方法に違いがあるので、医師やスタッフからの指示をしっかり確認してください。
検査を受けるタイミング
検査を受ける理想的なタイミングは人によって異なります。
検査の検討が勧められる状況
- 40歳を過ぎて定期健診で便潜血検査等に引っかかった
- 長引く胃もたれや胸やけが続き、生活に支障が出ている
- 過去にポリープや胃潰瘍、ピロリ菌感染などの既往がある
- 家族に大腸がんや胃がんの方がいる
症状が出ていなくても、年齢やリスク要因をふまえて一定の間隔で検査を受けておけば、病気の早期発見だけでなく安心にもつながります。
検査に向けた食事や生活習慣のアドバイス
内視鏡検査をよりスムーズに進めるためには、検査直前の食事や日常的な生活習慣に気を配ることが大切です。正しい準備や生活管理により、検査の正確性が高まり、検査後の回復も早くなります。
胃カメラの前後で気をつける食事
胃カメラ検査を受ける場合は、前日の夜から絶食指示が出ることが一般的で、脂っこい食事やアルコールを控え、消化のよいものを選ぶと検査時に胃内の残留物が少なくなり、検査がスムーズになりやすいです。
検査後は、のどの麻酔が切れるまでは飲食を控え、その後も胃に優しい食事を少量ずつ摂ると身体に負担をかけにくいでしょう。
胃に負担をかけやすい食事
| 食事の種類 | 理由 |
|---|---|
| 揚げ物 | 脂質が多く消化に時間がかかる |
| 刺激物(香辛料) | 胃粘膜を刺激して炎症を悪化させる恐れがある |
| アルコール | 胃酸分泌を亢進させ、粘膜に負担がかかる |
| 炭酸飲料 | 胃を膨張させ、もたれやすい |
一定期間控えるだけでも、検査への影響や胃の状態に配慮できます。
大腸カメラの前後で意識したいポイント
大腸カメラは、腸内をきれいにする必要があるため、検査前日には食事制限と下剤服用が必要です。腸内の内容物が多いと、観察の妨げになります。
検査後は腸内を刺激しすぎないために、消化のよい柔らかい食事をとり、激しい運動は控えたほうがよいです。とくにポリープ切除を行った場合は、腸壁がダメージを受けている可能性があるため注意が必要です。
日常生活での予防とセルフケア
消化器官を健やかに保つためには、毎日の生活習慣が鍵です。
セルフケアの方法
- 規則正しい食事のリズムを保ち、噛む回数を増やす
- 野菜や食物繊維を積極的にとり、腸内環境を整える
- アルコールや喫煙は控えめにし、胃腸を休ませる時間を作る
- 適度な運動やストレス発散方法を取り入れて自律神経を安定させる
日々の積み重ねが、長期的な健康維持につながります。
内視鏡検査後の経過観察
内視鏡検査後には、医師の説明に従って経過を観察し、いくつかの点に気をつけると、問題を早期に発見できます。
- 発熱や強い腹痛が生じたらすぐに医療機関へ相談
- 腹部に張りや違和感が続く場合、我慢せずに問い合わせる
- 出血(便に血が混じるなど)の有無を確認
- 指示がある場合は、薬や食事管理を守る
ポリープ切除後や生検後は傷口を刺激しないように注意が必要です。また、異常がなくても、定期的に検査を受けることで安心感を得られます。
よくある質問
消化器官に関する内視鏡検査は、病気の早期発見に役立つ反面、受診者からはさまざまな不安や疑問が寄せられます。代表的な質問を挙げて、答えをまとめました。
- 検査中の痛み
-
胃カメラでは、経口検査よりも細径の経鼻検査が負担を軽減できる場合があります。また、大腸カメラでは、鎮静剤を使うことで痛みを和らげる方法が選択できることがあります。
医療機関によって鎮静方法が異なるため、事前に相談すると安心です。
鎮静剤を使用した内視鏡検査について、以下の記事も参考にしてください。
【鎮静剤で苦痛を減らす 胃カメラを快適に受けるために】
胃カメラ検査で鎮静剤を使用するメリットやデメリット、検査当日の流れから注意点まで詳しく解説。検査への不安を軽減したい方におすすめの内容です。 - 合併症のリスク
-
内視鏡検査の合併症としては、穿孔や出血があげられますが、実際の発生率は非常に低いといわれています。検査後の安静や経過観察を守り、異常を感じたら早めに医療機関へ連絡することが大切です。
- 保険適用や費用
-
通常の診療の一環として内視鏡検査を行う場合、健康保険が適用されますが、検査の目的や治療内容によって自己負担額が変動します。具体的な費用は医療機関によって異なるため、事前に問い合わせましょう。
こちらの記事も参考にしてください。
【内視鏡検査費用の目安と流れ 胃と大腸のチェック方法】
胃カメラ・大腸内視鏡検査の費用について、保険適用の条件から自己負担額の目安まで詳しく解説。検査を検討する際の不安を解消できる内容です。 - 検査後の過ごし方
-
検査直後は、鎮静剤の影響でふらつく可能性があるため、運転や激しい運動を控えるよう求められることがあります。ポリープ切除を行った場合は、一定期間の安静と食事管理が勧められます。異常がなければ翌日から普段の生活に戻る場合も多いですが、体調を見ながら無理をしないことが肝要です。
次に読むことをお勧めする記事
【胃カメラで分かる症状 検査の流れ】
消化器官の基礎を押さえたら、次は実際の胃カメラ検査の流れを知っておくと安心です。検査が初めての方に特に参考になる内容です。
【大腸内視鏡検査とはどのような検査なのか】
消化器官について理解が深まったところで、大腸内視鏡検査の知識も合わせて持っていただくと、より包括的な理解ができます。
参考文献
Shiroshita H, Inomata M, Akira S, Kanayama H, Yamaguchi S, Eguchi S, Wada N, Kurokawa Y, Uchida H, Seki Y, Ieiri S. Current status of endoscopic surgery in Japan: the 15th National Survey of endoscopic surgery by the Japan Society for Endoscopic Surgery. Asian Journal of Endoscopic Surgery. 2022 Apr;15(2):415-26.
Saito Y, Kodashima S, Matsuda T, Matsuda K, Fujishiro M, Tanaka K, Kobayashi K, Katada C, Horimatsu T, Muto M, Ohtsuka K. Current status of diagnostic and therapeutic colonoscopy in Japan: The Japan Endoscopic Database Project. Digestive Endoscopy. 2022 Jan;34(1):144-52.
Shimatani M, Hatanaka H, Kogure H, Tsutsumi K, Kawashima H, Hanada K, Matsuda T, Fujita T, Takaoka M, Yano T, Yamada A. Diagnostic and therapeutic endoscopic retrograde cholangiography using a short-type double-balloon endoscope in patients with altered gastrointestinal anatomy: a multicenter prospective study in Japan. Official journal of the American College of Gastroenterology| ACG. 2016 Dec 1;111(12):1750-8.
Nagahara A, Shiotani A, Iijima K, Kamada T, Fujiwara Y, Kasugai K, Kato M, Higuchi K. The role of advanced endoscopy in the management of inflammatory digestive diseases (upper gastrointestinal tract). Digestive Endoscopy. 2022 Jan;34(1):63-72.
Sharma R. Visualising the digestive tract: Endoscopy. International Journal of Advances in Nursing Management. 2021;9(1):102-3.
Axon AT. Fifty years of digestive endoscopy: successes, setbacks, solutions and the future. Digestive Endoscopy. 2020 Mar;32(3):290-7.
Niwa H. The history of digestive endoscopy. InNew Challenges in Gastrointestinal Endoscopy 2008 Sep 30 (pp. 3-28). Tokyo: Springer Japan.
Hosoe N, Naganuma M, Ogata H. Current status of capsule endoscopy through a whole digestive tract. Digestive Endoscopy. 2015 Jan;27(2):205-15.
Valdastri P, Simi M, Webster III RJ. Advanced technologies for gastrointestinal endoscopy. Annual review of biomedical engineering. 2012 Aug 15;14(1):397-429.
Küper MA, Eisner F, Koenigsrainer A, Glatzle J. Laparoscopic surgery for benign and malign diseases of the digestive system: indications, limitations, and evidence. World Journal of Gastroenterology: WJG. 2014 May 7;20(17):4883.










