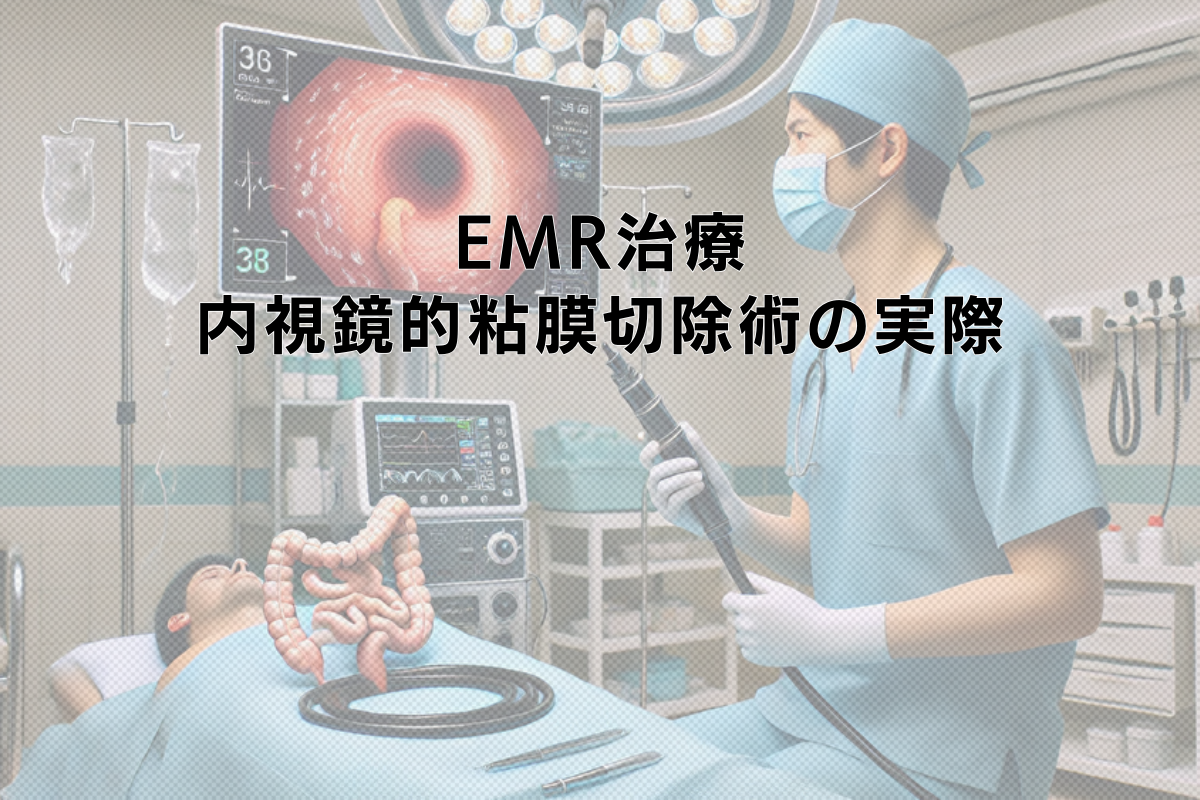内視鏡的粘膜切除術、通称EMRは、消化管の早期がんやポリープなどを開腹手術ではなく、口や肛門から内視鏡を挿入して切除する治療法で、患者さんの身体への負担が少なく、入院期間も短いのが利点です。
この記事では、EMRがどのような治療法なのか、手順、治療前後の注意点、考えられる合併症について、詳しく解説します。EMRは低侵襲治療の代表格ですが、適応や限界を正しく理解することが大切です。
内視鏡的粘膜切除術(EMR)の概要
EMRは、消化器医療における重要な治療技術の一つで、身体の表面に傷をつけることなく、消化管の内部から病変を取り除くことが目的です。
健康診断や人間ドックで発見される機会の増えた早期の消化管病変に対して、有効な選択肢となっています。
EMRとはどのような治療法か
内視鏡的粘膜切除術(EMR)は、内視鏡(カメラ)を用いて消化管の粘膜層に存在する病変を切除する内科的な治療法です。粘膜層は消化管の最も内側にある層で、早期のがんの多くはこの層から発生します。
EMRでは、病変の下の層(粘膜下層)に生理食塩水などの液体を注入して病変を人工的に浮き上がらせ、切除すべき病変とその下にある筋層との間に安全な距離が生まれます。
その後、スネアと呼ばれる金属製の輪を高周波電流を流せる装置に接続し、病変に掛けて焼き切り、一連の操作を全て内視鏡の先端から行うため、お腹を切る必要がない低侵襲の治療です。
EMRの目的と歴史的背景
EMRの主な目的は、リンパ節への転移の可能性が極めて低い早期のがんや前がん病変(将来がんになる可能性のあるポリープなど)を、消化管を温存しながら完全に切除することです。
消化管の機能を損なうことなく病変のみを取り除けるため、治療後の生活の質(QOL)を高く維持できます。1980年代に日本で開発されて以来、手技は改良され、より安全で確実な治療法として確立されてきました。
当初は胃の小さな隆起性病変が対象でしたが、手技の洗練や周辺機器(高周波発生装置、スネア、注入液など)の進化により、食道や大腸、さらには平坦な病変にも応用されています。
内視鏡技術の進歩とがん検診の普及により、治療対象となる早期病変の発見数が増加したことも、EMRが広く普及した大きな要因です。
治療が可能な消化管の部位
EMRは、食道、胃、十二指腸、大腸といった、内視鏡が到達できる消化管のほとんどの部位で実施可能です。それぞれの部位で発生する早期がんやポリープの形状、大きさ、深さなどを考慮して、EMRが適切かどうかを判断します。
特に胃がんや大腸がんの早期発見・早期治療において、この手技は大きな役割を果たしています。
小腸については、通常の内視鏡では到達が困難なため、EMRの対象となることはまれですが、バルーン内視鏡などを用いて治療が行われることもあります。
EMRが適用される主な部位
| 部位 | 主な対象病変 | 特徴 |
|---|---|---|
| 食道 | 早期食道がん、食道異形成 | バレット食道から発生するがんにも適用されます。嚥下機能の温存に貢献します。 |
| 胃 | 早期胃がん、胃腺腫 | 分化型で粘膜内にとどまるがんが主な対象です。胃の温存は食事摂取機能の維持に直結します。 |
| 大腸 | 大腸ポリープ、早期大腸がん | 検診で発見されるポリープの多くが対象になります。大腸がんの予防的治療としても重要です。 |
EMRが適応となる消化管の病変
全ての消化管病変がEMRの対象となるわけではなく、EMRが最も効果を発揮するのは、がん細胞が粘膜層にとどまっており、リンパ節や他の臓器へ転移している可能性がほとんどないと考えられる早期の病変です。
早期がんにおけるEMRの役割
消化管のがんは、進行すると粘膜の下の層へ深く浸潤し、リンパ管や血管を通って他の臓器へ転移します。EMRは、がんが粘膜層内にとどまっている段階、いわゆる早期がんであれば、外科手術と同等の根治性が期待できる治療法です。
消化管そのものを切除する外科手術と比べて、臓器の機能が温存される点が大きな利点で、がんの組織型が比較的大人しい性質の「分化型」であることが、EMRの良い適応条件の一つとされています。
未分化型のがんは、粘膜の浅い部分にあっても転移のリスクがあるため、適応はより慎重に判断されます。
ポリープ(腺腫)の切除
大腸ポリープの多くは腺腫という種類で、良性ではありますが、放置すると時間をかけてがん化する可能性があり、EMRは、このような前がん病変であるポリープを切除し、将来のがん化を予防するためにも広く用いられます。
大きさが数ミリから2センチ程度のポリープに対して、安全かつ確実に切除が可能です。ポリープの形状には、茎を持つ有茎性ポリープと、茎を持たない無茎性ポリープがあり、EMRはどちらのタイプにも対応できます。
EMRで切除する主なポリープの種類
| ポリープの種類 | 特徴 | がん化のリスク |
|---|---|---|
| 腺腫性ポリープ | 最も一般的。放置するとがん化することがある前がん病変。 | 大きさや形状、異型度により異なる。切除が原則。 |
| 過形成性ポリープ | 基本的にはがん化しないとされる。直腸やS状結腸に多い。 | 低いが、一部の種類ではがん化の報告もある。 |
| 炎症性ポリープ | 潰瘍性大腸炎など、腸の炎症が原因で発生。がん化はまれ。 | 極めて低い。炎症のコントロールが重要。 |
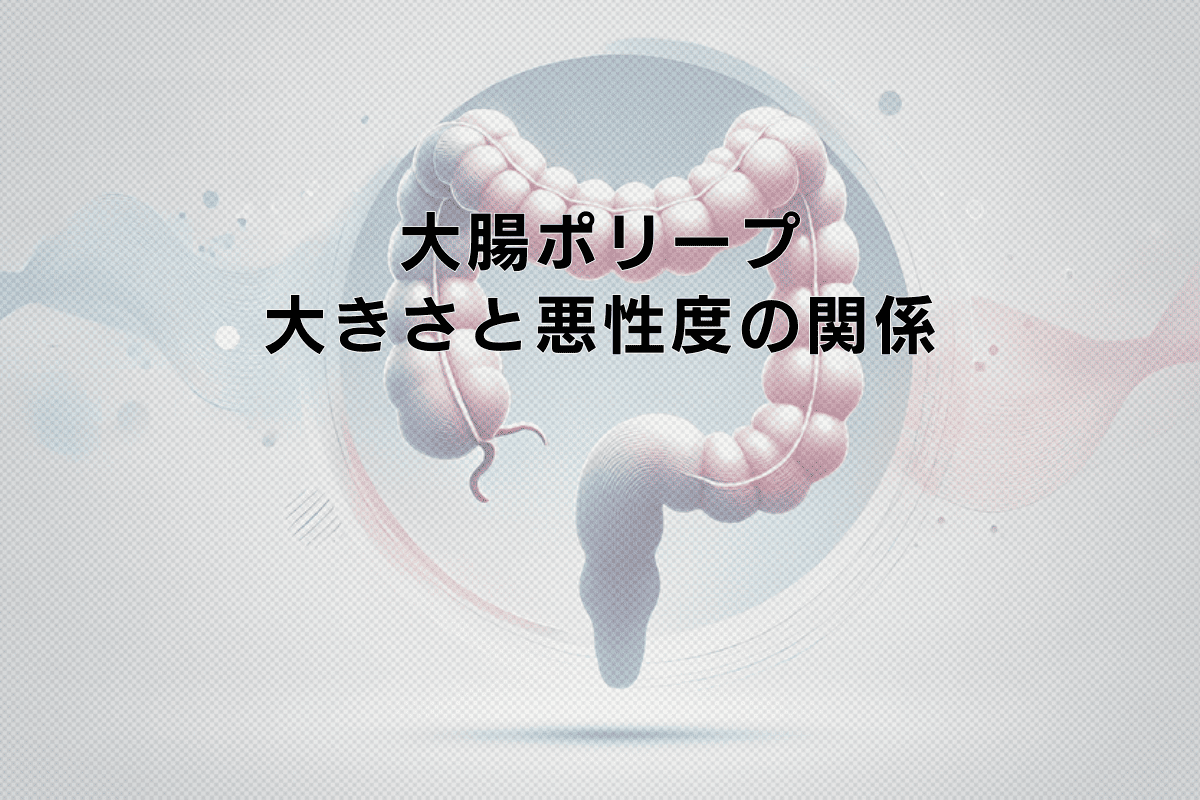
EMR適応を判断する基準
EMRを行うかどうかは、病変の大きさ、形状(肉眼型分類)、内視鏡所見から推測される深達度によって総合的に判断し、大きさが20mm以下で、平坦または少し隆起した形状の病変が良い適応とされます。
治療前に色素内視鏡(インジゴカルミンなど)や拡大内視鏡、超音波内視鏡などを用いて詳細な観察を行い、がんが粘膜下層の深くまで及んでいないことを確認することが重要です。
陥凹型(へこんでいるタイプ)の病変は、早期に深く浸潤する傾向があるため、より慎重な適応判断が求められます。
また、粘膜下層に液体を注入した際に病変が持ち上がらない「ノンリフティングサイン」が見られる場合は、がんが深くまで浸潤している可能性があり、EMRの適応外です。
EMRと他の内視鏡治療との比較
内視鏡を用いた病変の切除術には、EMRの他にもいくつかの方法があり、代表的なものは、内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)やコールドポリペクトミーです。それぞれの治療法には長所と短所があり、患者さんの状態も考慮して決定します。
内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)との違い
ESDは、EMRと同様に内視鏡を用いて病変を切除する治療法ですが、より高度な技術を要します。
EMRがスネアをかけて一括で焼き切るのに対し、ESDは専用の電気メスで病変の周囲の粘膜を切開し、粘膜下層を少しずつ剥がしながら病変を剥離・切除します。
EMRでは一括切除が難しい大きな病変(20mm以上)や、潰瘍の瘢痕(はんこん)を伴う病変でも、正確に一括で切除することが可能で、病理診断の精度を高め、局所再発のリスクを低減する上で非常に重要です。
一方で、ESDは手技時間が長く、出血や穿孔などの合併症のリスクもEMRより高いため、熟練した技術を持つ医師が限られた施設で行います。
EMRとESDの主な相違点
| 項目 | EMR(内視鏡的粘膜切除術) | ESD(内視鏡的粘膜下層剥離術) |
|---|---|---|
| 切除可能な大きさ | 主に20mm以下 | 20mmを超える大きな病変も可能 |
| 治療時間 | 比較的短い(15分~30分程度) | 比較的長い(1時間以上かかることも) |
| 手技の難易度 | 標準的で広く普及している | 高く、偶発症のリスクも高いため熟練を要する |
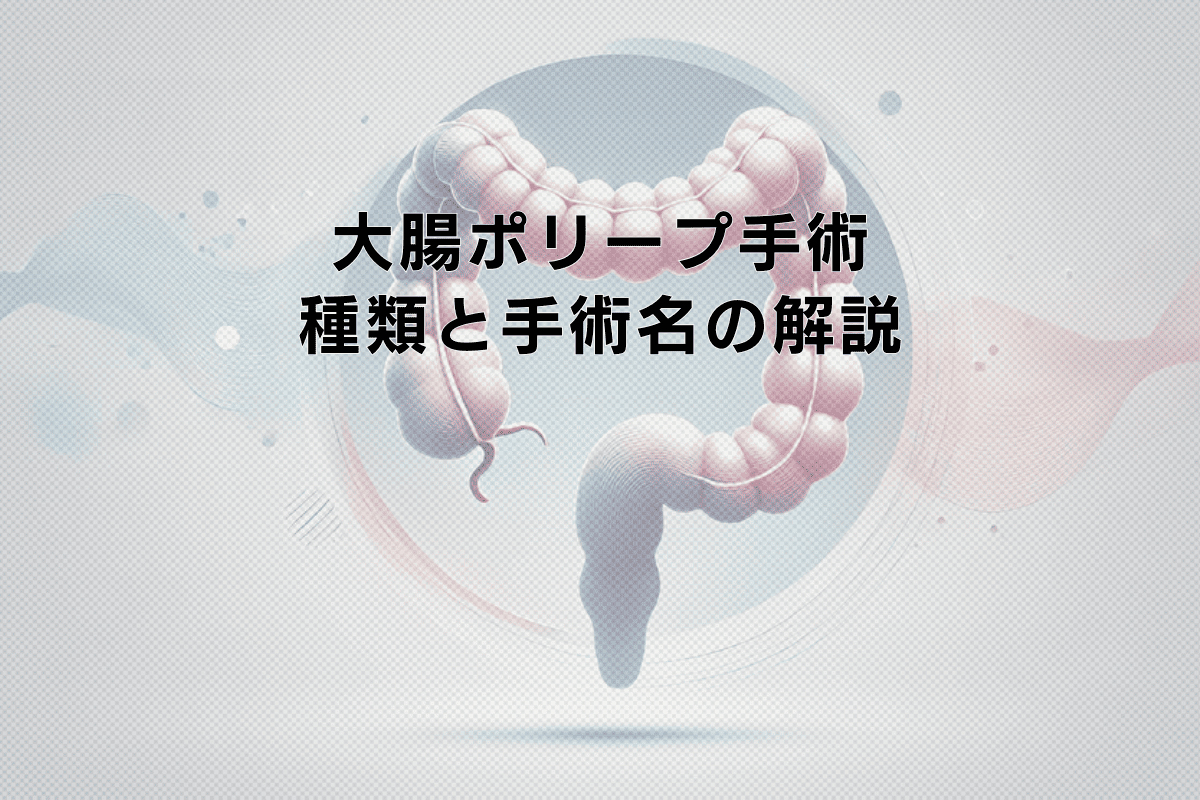
コールドポリペクトミーとの使い分け
コールドポリペクトミーは、主に大腸の小さなポリープ(10mm以下程度)に対して行われる手技です。
高周波電流を用いずに、スネアでポリープを締め付けて機械的に切除し、通電しないため、切除後の出血(後出血)や穿孔のリスクがEMRに比べて低くなっています。熱による組織へのダメージがないため、安全性が高いのが特徴です。
また、抗血栓薬を服用している患者さんでも、休薬せずに治療できる可能性があるという利点もあり、小さなポリープに対しては、この方法が選択されることが増えています。
治療法選択の考え方
どの治療法を選択するかは、消化器内視鏡専門医が病変の状態を詳細に評価した上で決定し、病変の大きさ、予測される組織型、部位、そして患者さんの全身状態などを総合的に勘案します。
小さなポリープならコールドポリペクトミー、20mm以下の早期がんならEMR、20mmを超える大きな早期がんならESD、といったように使い分けられます。
医師は、それぞれの治療法の利点と欠点を患者さんに十分に説明し、理解を得た上で治療方針を決定します。

治療前に行う検査と準備
EMRを安全かつ確実に行うためには、事前の詳細な検査と周到な準備が大事です。治療対象となる病変の正確な評価はもちろんのこと、患者さんの全身状態を把握し、治療に耐えられるかどうかを確認します。
診断を確定するための内視鏡検査
まずは通常の内視鏡検査を行い、病変の存在を確認し、その際に、病変の表面構造を詳しく観察するために色素を散布したり(色素内視鏡)、画像を拡大して微細な血管や模様を観察したり(拡大内視鏡)します。
また、病変の一部を採取して(生検)、病理組織学的に良性か悪性か、悪性であればどの程度の深さまで達しているかを診断します。
検査を組み合わせることで、治療方針の決定精度を高め、特にNBI(Narrow Band Imaging)などの画像強調観察は、腫瘍と非腫瘍の境界を明瞭にし、切除範囲の決定に役立ちます。
治療方針決定のための主な検査
| 検査名 | 目的 | 内容 |
|---|---|---|
| 拡大内視鏡観察 | 病変表面の微細構造(腺管構造や血管網)を観察する | 特殊な光(NBIなど)やズーム機能で詳細に評価します。 |
| 生検(組織検査) | 病変の組織型(腺腫か、がんかなど)を確定する | 鉗子で組織の一部を採取し、顕微鏡で調べます。 |
| 超音波内視鏡(EUS) | 病変の深達度(がんの深さ)を壁深層まで評価する | 内視鏡の先端から超音波を出し、壁の内部を観察します。 |
全身状態の評価と血液検査
治療に先立ち、心臓や肺の機能、血液の固まりやすさなどを評価するために、胸部X線検査、心電図検査、呼吸機能検査、血液検査を行います。
血液をサラサラにする薬(抗血栓薬)を服用している場合は、治療中の出血リスクが高まるため、事前の休薬や代替薬への変更が必要になることがあります。
休薬の判断は、血栓症のリスクと出血のリスクを天秤にかけ、処方している主治医と消化器内視鏡医が連携して慎重に行うことが大切です。
治療前の食事と内服薬の調整
安全な検査と治療のため、消化管の中を空にしておくことが重要です。特に大腸のEMRを行う場合は、数日前からキノコ類や海藻、種のある果物などの消化の悪い食品を避け、前日からは検査食や下剤を服用して腸内をきれいにします。
胃や食道の治療の場合も、前日の夕食後から絶食となり、常用している薬については、自己判断で中止せず、必ず事前に医師や看護師に相談してください。
- 服用中の全ての薬(市販薬やサプリメントを含む)を医師に伝える
- 薬物アレルギーの有無を伝える
- 過去の病気や手術歴を伝える

内視鏡的粘膜切除術の具体的な手順
EMR治療当日は準備が整った後、内視鏡室で処置を開始し、多くの施設では、患者さんの苦痛を和げるために鎮静剤を使用します。
治療当日の流れと鎮静剤の使用
治療室に入ったらまず血圧計などを装着し、点滴を開始し、ここから鎮静剤を投与し、患者さんがリラックスした状態、あるいは浅く眠った状態で治療を始めます。
意識下鎮静と呼ばれる状態で、完全に意識がなくなるわけではありませんが、健忘効果により治療中のことを覚えていない場合が多いです。治療が終了し、鎮静剤の効果が薄れるまで、回復室で安静にしていただきます。
粘膜下層への局所注入
内視鏡を病変のある場所まで挿入し、位置を再確認します。
次に、内視鏡の先端から細い注射針を出し、病変の下の粘膜下層に生理食塩水やヒアルロン酸ナトリウムなどの液体を注入すると、病変が粘膜下層ごと盛り上がり、周囲の正常な粘膜との境界が明確になります。
また、切除する層と、その下にある固有筋層との距離が確保され、穿孔や熱による筋層の損傷を防ぐ、非常に重要な工程です。
注入する液体にインジゴカルミンなどの色素を混ぜることで、粘膜下層を青く染め、切除範囲をより明確にすることもあります。
スネアによる切除と回収
十分に盛り上がった病変に対して、スネアと呼ばれる投げ縄のような形状のワイヤーをかけ、スネアで病変を根元から締め付け、高周波電流を流して焼き切ります。
高周波電流には、組織を切るための切開波と、血管を焼いて血を止めるための凝固波があり、適切に組み合わせて使用します。
切除された病変は、鉗子や専用のネットを用いて体外へ回収した後、病理検査に提出し、がんが完全に取り切れているか(断端陰性)、がんの広がりや深さはどうであったかを最終的に評価します。
EMRの主要な手技
| 手順 | 目的 | 詳細 |
|---|---|---|
| 局所注入 | 病変を挙上させ、安全な切除層を確保する | 生理食塩水やヒアルロン酸ナトリウムなどを粘膜下層に注入します。 |
| スネアリング | 病変を確実に捕捉する | 金属製の輪(スネア)を病変にかけ、根元で締め付けます。 |
| 高周波焼灼・切離 | 病変を切除し、同時に止血を行う | 切開波と凝固波を組み合わせた電流を流して組織を焼き切ります。 |
EMR治療後の経過と注意点
EMRは身体への負担が少ない治療ですが、切除した部位は人工的な潰瘍の状態になっているので、創部が治癒するまでの間は、合併症を予防するためにいくつかの注意点を守って生活することが大切です。
治療直後から入院中の管理
治療直後は、鎮静剤の影響が残っているため、回復室で安静にし、病棟に戻ってからも、数時間はベッド上での安静が必要です。
治療当日は絶食とし、翌日から水分や食事を開始しますが、消化管への負担を避けるため、流動食から始め、徐々に固形物へと段階を上げていきます。
入院中は、出血や腹痛、発熱などの合併症の兆候がないか、採血や腹部の診察などを通して慎重に経過を観察します。上部消化管のEMR後は、胃酸を抑える薬(プロトンポンプ阻害薬など)を点滴や内服で投与し、潰瘍治癒を促進します。
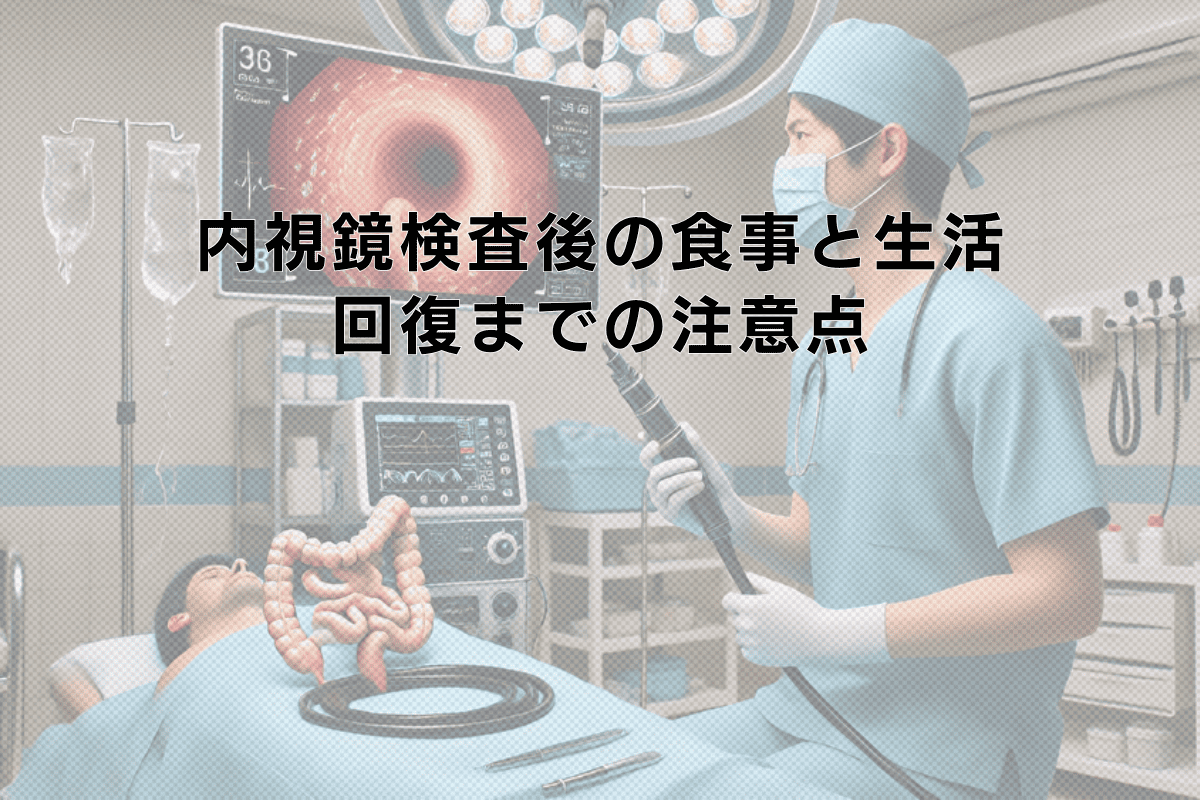
治療後の食事の進め方(一例)
| 時期 | 食事形態 | 注意点 |
|---|---|---|
| 治療当日 | 絶食 | 点滴で水分と電解質、栄養を補給します。 |
| 治療翌日~ | 流動食、三分粥、五分粥 | 消化の良いものから少量ずつ開始し、腹部症状がないか確認します。 |
| 退院後しばらく | 全粥、軟飯、普通食 | 香辛料やアルコール、脂肪分の多い食事など刺激物は避けます。 |
退院後の生活における注意
退院後も、1~2週間程度は消化の良い食事を心がけ、アルコールや香辛料の多い食事は避けましょう。
また、腹圧がかかるような激しい運動や重い物を持つ作業、長時間の運転、旅行なども、後出血のリスクを高める可能性があるため、一定期間は控えるように指導されます。
海外旅行など、すぐに医療機関を受診できないような遠出は、最低でも2週間は避けてください。仕事への復帰時期は、業務内容によって異なるため、医師と相談して決定します。
- 食事はよく噛んでゆっくり食べる
- 暴飲暴食を避ける
- 排便時に強く力まないよう、便通を整える
- 処方された胃薬や整腸剤などは指示通りに服用する
定期的な経過観察の重要性
EMRで病変を切除した後も、定期的な内視鏡検査による経過観察が重要で、第一に治療した部位の局所再発がないか、第二に別の場所に新たな病変(異時性病変)が発生していないかを確認します。
切除した病変の病理結果によっては、リンパ節転移のリスクが想定され、追加で外科手術や化学療法が必要になる場合もあり、これを非治癒切除と呼びます。医師の指示に従って、忘れずに検査を受けてください。
EMR治療における合併症とその対策
EMRは比較的安全な治療法ですが、外科手術と同様に、偶発症や合併症が起こる可能性はゼロではなく、主な合併症としては、出血と穿孔(消化管に穴が開くこと)が挙げられます。
治療中・治療後の出血(後出血)
最も頻度の高い合併症は出血で、治療中に出血がみられた場合は、内視鏡的に止血処置を行います。問題となるのは、治療後数時間から数日経ってから起こる後出血です。
切除した潰瘍の血管が破綻して出血するもので、吐血や黒い便(タール便)、血便といった症状で気づき、発生頻度は数パーセントと報告されています。
多くは再度内視鏡を行ってクリップで止血することが可能ですが、まれに輸血やIVR(血管内治療)、緊急手術が必要です。
出血を疑う主なサイン
| 症状 | 説明 |
|---|---|
| 吐血・下血 | 口から血を吐く、または肛門から鮮血が出る。緊急性が高いサイン。 |
| 黒色便(タール便) | 胃や食道からの出血が腸内で変色し、黒い便となる。出血から時間が経っていることを示す。 |
| めまい・ふらつき | 貧血が進行した場合にみられる症状。立ちくらみや動悸を伴うこともある。 |
消化管穿孔(せんこう)
穿孔は、内視鏡治療によって消化管の壁に穴が開いてしまう合併症で、頻度は出血よりも低く1%未満ですが、起こった場合は腹膜炎などを起こす可能性があり緊急の対応が必要です。
治療中に穿孔が確認された場合は、クリップという小さな金属の器具を用いて、内視鏡的に穴を閉じることができます。
しかし、治療後に時間が経ってから判明した場合(遅発性穿孔)や、クリップでの閉鎖が困難な場合は、絶食管理や抗生剤投与、お腹に溜まった消化液や空気を抜く処置や、緊急の外科手術が必要になることがあります。
持続する強い腹痛や発熱は、穿孔を疑う重要なサインです。
合併症を予防するための取り組み
医療機関では、合併症を予防するために様々な対策を講じていて、例えば、粘膜下層への十分な液体注入による安全な切離層の確保や、太い血管が見える場合の予防的な止血処置などです。
また、患者さん自身が、治療後の食事や生活上の注意点を守ることも、合併症の予防に直結します。万が一、退院後に腹痛や血便などの症状が現れた場合は、速やかに治療を受けた医療機関に連絡してください。
EMR治療に関するよくあるご質問
ここでは、患者さんからよく寄せられるEMR治療に関する質問と回答をまとめました。
- 治療中に痛みはありますか
-
消化管の粘膜には痛覚(痛みを感じる神経)がないため、切除そのもので痛みを感じることはありません。
また、多くの施設では鎮静剤を使用するため、うとうとと眠っているような状態で治療が終わり、内視鏡が入っていることによる苦痛も最小限に抑えられます。
- 入院期間はどのくらいですか
-
入院期間は、治療した臓器や病変の大きさ、患者さんの全身状態によって異なります。一般的には、合併症がなければ3日から7日程度の入院となることが多いです。
順調に経過すれば、より短期間で退院できる場合もあり、具体的な期間については、治療を担当する医師にご確認ください。
- 切除した組織の検査結果はいつ頃わかりますか
-
通常、1週間から2週間程度で判明します。切除した組織は、ホルマリンで固定した後、顕微鏡で詳細に観察する病理検査に提出されます。
検査で、病変の種類(がんか、腺腫か)、がんの深さ、切除した断端に病変が残っていないか、などを最終的に確定します。
この結果が、治療が完了したかどうか、今後のフォローアップ方針を決める上で最も重要な情報です。
- 仕事にはいつから復帰できますか
-
仕事への復帰時期は、業務内容に大きく左右されます。デスクワークなどの事務的な仕事であれば、退院後すぐに復帰できる場合もあります。
一方、重い物を持つ作業や長距離の運転、身体に強い負担がかかる仕事の場合は、出血のリスクを考慮して1~2週間程度の安静期間を設けることが望ましいです。
復帰のタイミングは、ご自身の体調と仕事内容を考慮し、医師とよく相談して決めてください。
次に読むことをお勧めする記事
【大腸ポリープ手術の種類と手術法の解説】
EMRの基本を押さえたら、次はESDやコールドとの実際の使い分けを知っておくと安心です。どの条件で何を選ぶか、治療時間や偶発症の違いまで整理できます。
【内視鏡検査後の食事と生活|検査当日から回復までの注意点】
処置後の過ごし方は合併症予防に直結します。食事・運動量・入浴・再診目安など、生活面を包括的に把握して、安全な回復計画につなげましょう。
以上
参考文献
Kojima T, Parra-Blanco A, Takahashi H, Fujita R. Outcome of endoscopic mucosal resection for early gastric cancer: review of the Japanese literature. Gastrointestinal endoscopy. 1998 Nov 1;48(5):550-4.
Nakamoto S, Sakai Y, Kasanuki J, Kondo F, Ooka Y, Kato K, Arai M, Suzuki T, Matsumura T, Bekku D, Ito K. Indications for the use of endoscopic mucosal resection for early gastric cancer in Japan: a comparative study with endoscopic submucosal dissection. Endoscopy. 2009 Sep;41(09):746-50.
Uedo N, Takeuchi Y, Ishihara R. Endoscopic management of early gastric cancer: endoscopic mucosal resection or endoscopic submucosal dissection: data from a Japanese high-volume center and literature review. Annals of Gastroenterology. 2012;25(4):281.
Ono H, Kondo H, Gotoda T, Shirao K, Yamaguchi H, Saito D, Hosokawa K, Shimoda T, Yoshida S. Endoscopic mucosal resection for treatment of early gastric cancer. Gut. 2001 Feb 1;48(2):225-9.
Katada C, Muto M, Momma K, Arima M, Tajiri H, Kanamaru C, Ooyanagi H, Endo H, Michida T, Hasuike N, Oda I. Clinical outcome after endoscopic mucosal resection for esophageal squamous cell carcinoma invading the muscularis mucosae-a multicenter retrospective cohort study. Endoscopy. 2007 Sep;39(09):779-83.
Tanaka S, Kashida H, Saito Y, Yahagi N, Yamano H, Saito S, Hisabe T, Yao T, Watanabe M, Yoshida M, Saitoh Y. Japan Gastroenterological Endoscopy Society guidelines for colorectal endoscopic submucosal dissection/endoscopic mucosal resection. Digestive Endoscopy. 2020 Jan;32(2):219-39.
Ishihara R, Iishi H, Uedo N, Takeuchi Y, Yamamoto S, Yamada T, Masuda E, Higashino K, Kato M, Narahara H, Tatsuta M. Comparison of EMR and endoscopic submucosal dissection for en bloc resection of early esophageal cancers in Japan. Gastrointestinal endoscopy. 2008 Dec 1;68(6):1066-72.
Kawamura T, Sakai H, Ogawa T, Sakiyama N, Ueda Y, Shirakawa A, Okada Y, Sanada K, Nakase K, Mandai K, Suzuki A. Feasibility of underwater endoscopic mucosal resection for colorectal lesions: a single center study in Japan. Gastroenterology research. 2018 Feb 8;11(4):274.
Kawashima K, Abe S, Koga M, Nonaka S, Suzuki H, Yoshinaga S, Oda I, Hikichi T, Ohira H, Saito Y. Optimal selection of endoscopic resection in patients with esophageal squamous cell carcinoma: endoscopic mucosal resection versus endoscopic submucosal dissection according to lesion size. Diseases of the Esophagus. 2021 May;34(5):doaa096.
Watanabe K, Ogata S, Kawazoe S, Watanabe K, Koyama T, Kajiwara T, Shimoda Y, Takase Y, Irie K, Mizuguchi M, Tsunada S. Clinical outcomes of EMR for gastric tumors: historical pilot evaluation between endoscopic submucosal dissection and conventional mucosal resection. Gastrointestinal endoscopy. 2006 May 1;63(6):776-82.