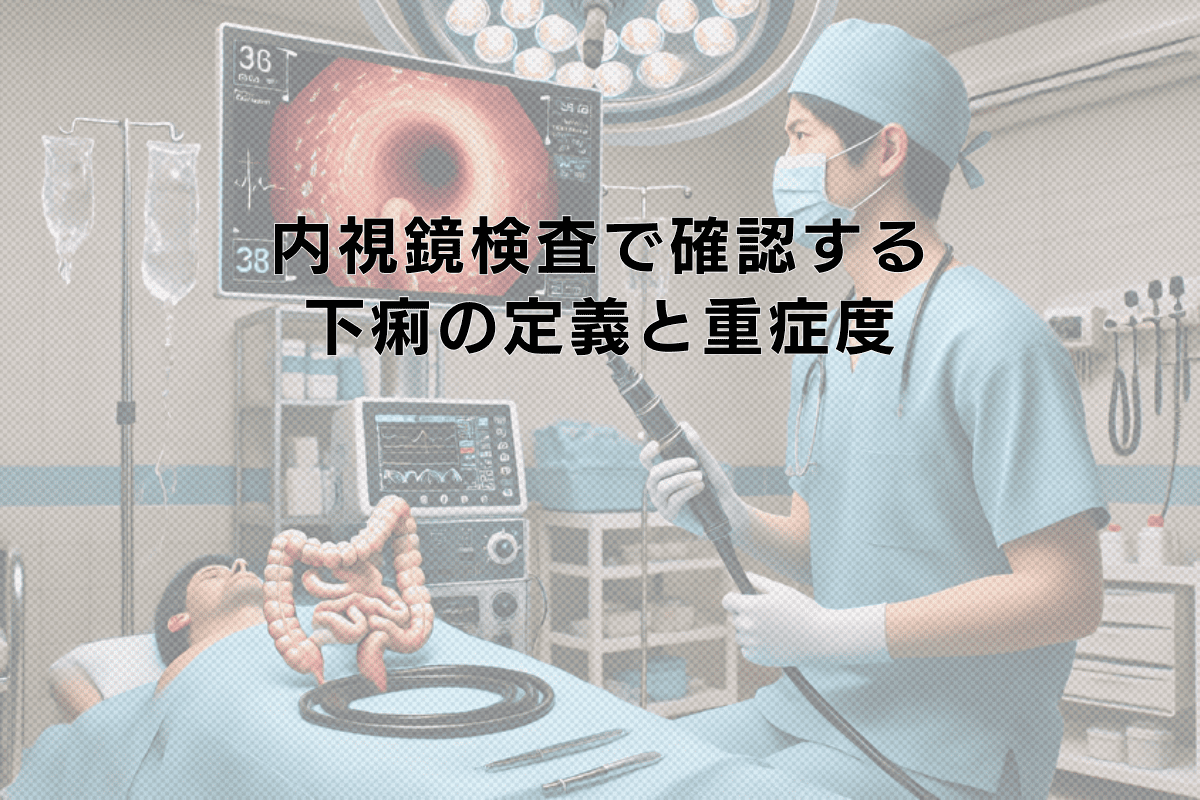急な腹痛と共に便がゆるくなる下痢は、日常生活に支障をきたすだけでなく、体内の水分や電解質バランスの乱れを起こす可能性があり、さらに、慢性的に続く場合は腸の炎症など、何らかの病気が隠れている恐れも否定できません。
そのような場合、医療機関での内視鏡検査は腸内の状態を直接確認できる手段として注目されます。
この記事では、下痢とはどのような状態かという定義や重症度の判定基準に加え、内視鏡を用いた診断の意義について詳しく解説します。
腹部症状が続く方や、大腸カメラや胃カメラによる精密検査を検討している方にも役立つ情報を網羅し、受診の目安や検査内容の理解に役立つ内容をまとめました。
下痢の基礎理解と一般的な定義
下痢の発生にはさまざまな要因が関係し、単なる食あたりから感染症、消化管の慢性疾患、ストレスによる腸機能の乱れまで多岐にわたり、日常生活で一時的に生じるものと、慢性的・再発性に続くものでは対処法が異なる場合もあります。
ここでは下痢の定義や基礎的な知識に焦点を当て、体の仕組みや便の性状から下痢を捉えます。
下痢の定義とは何か
便の水分量が増え通常よりも軟らかい状態で排出されることを下痢と呼び、1日あたりの排便回数が増えるだけでなく、便の形状が著しく崩れ、水様便になる場合のことです。
単なる回数だけでなく、便の性状や排便時の症状などを総合的に見極めることで、「下痢かどうか」を判断し、下痢の定義に該当するかどうかを的確に把握することで、正しいタイミングで医療機関を受診しやすくなります。
水分量と便形状の関係
便の水分量が増えると、軟便・泥状便・水様便へと変化し、排便時に違和感や痛みを伴うケースがあります。水様便まで進むと、腹痛を強く感じたり、トイレが手放せなくなったりと、生活の質が低下しやすくなります。
便の形状によって「軽度の下痢」「重症の下痢」などの概念が使われることがあるため、観察は重要です。
生理学的な観点
大腸では水分や電解質を吸収し、便が適度な固さへと調整されますが、吸収が追いつかないほど腸内が刺激されたり、炎症や過敏性の反応が起きたりすると、便が柔らかいまま排出されやすくなります。
腸内細菌バランスや胃腸の蠕動運動の亢進といった要因も影響するため、下痢には多角的な見方が欠かせません。
一過性と慢性の区別
短期間で収まる一過性の下痢は、食事内容やストレス、感染症などの急性要因が多い傾向です。それに対して数週間から数カ月以上持続する慢性下痢は、過敏性腸症候群や炎症性腸疾患、吸収不良症候群、大腸がんなどの可能性があります。
慢性化した際には専門医による内視鏡検査が必要になるケースが多いため、放置せず早めの対応が大切です。
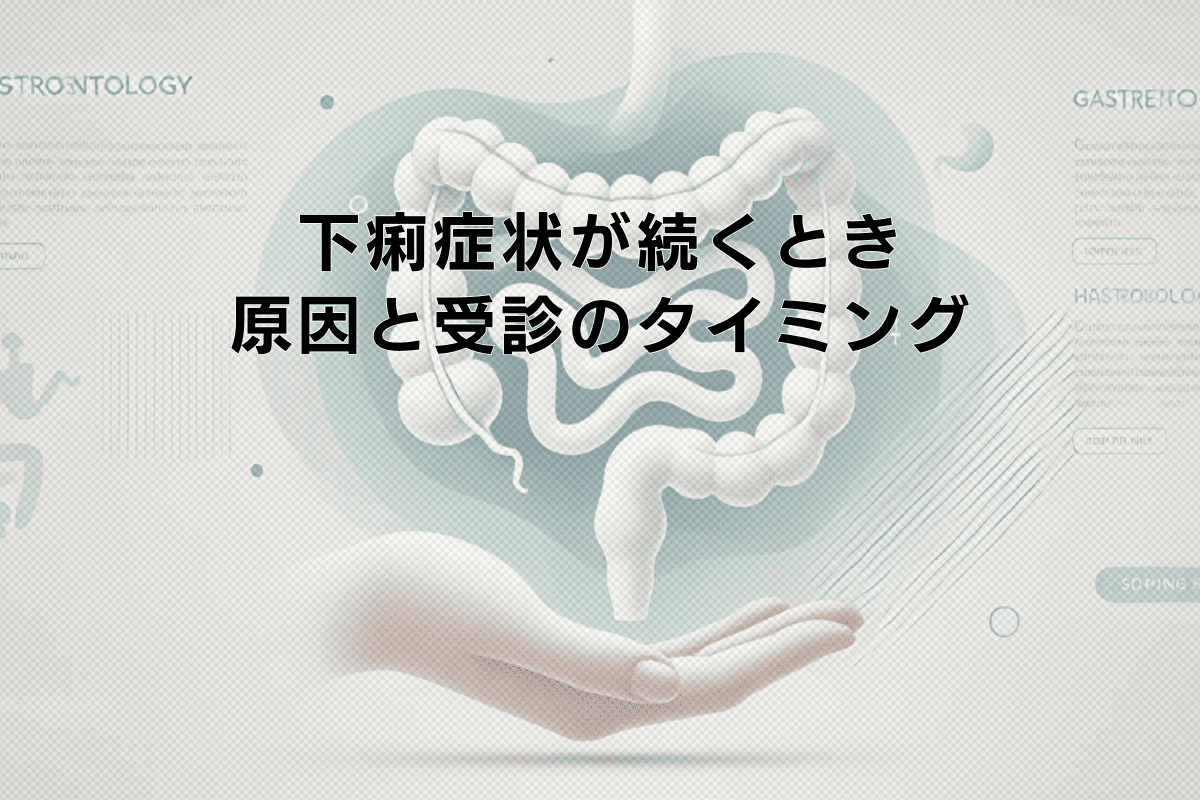
下痢に関わる主な要素
| 要素 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| 原因 | 感染、食事、ストレス、腸疾患など | ウイルス性腸炎、乳糖不耐症など |
| 期間 | 一過性または慢性 | 1〜2日で改善する短期、数カ月続く長期 |
| 便の状態 | 軟便、泥状便、水様便 | ブリストルスケールでタイプ5〜7 |
| 付随症状 | 腹痛、発熱、嘔吐、血便など | 突然の激痛や高熱、タール便など |
- 便の観察は腸の状態を知る重要な指標になる
- 一時的な下痢でも強い腹痛や血便を伴う場合は注意が必要
- 慢性化している下痢は専門的な検査で原因を追究すると安心
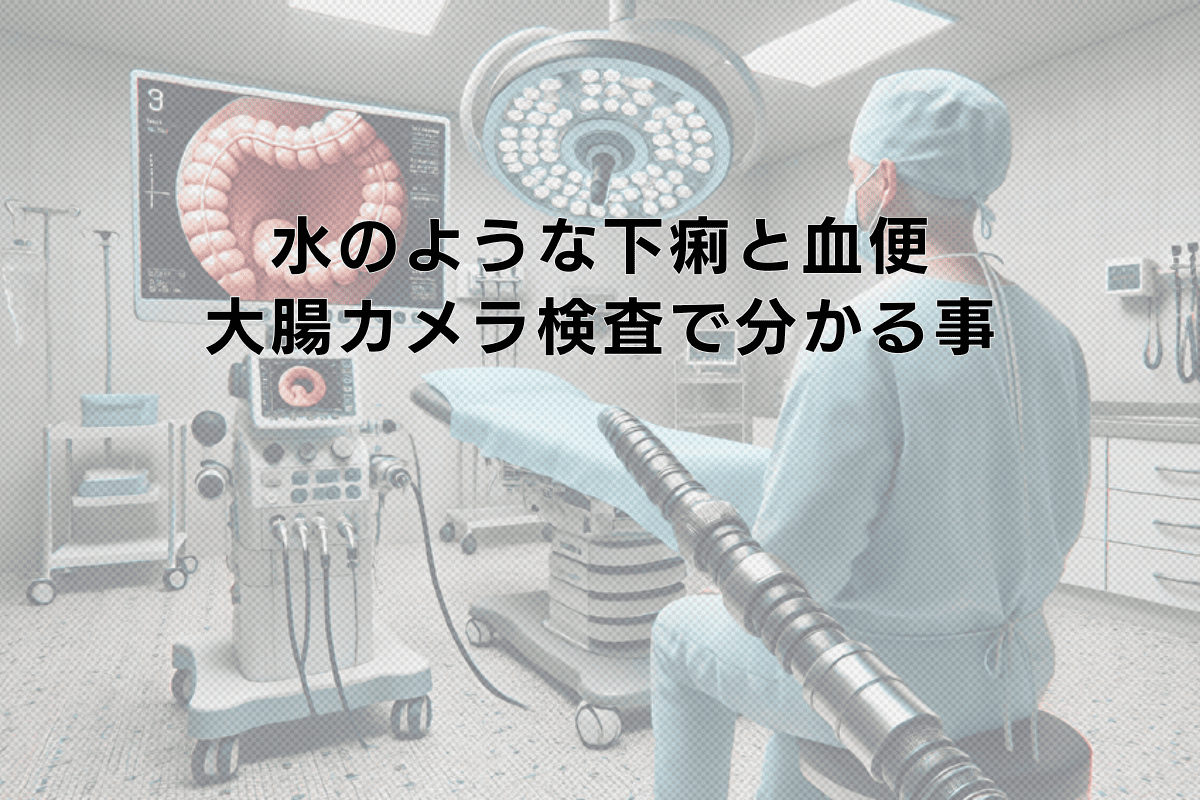
下痢の重症度を知る理由
下痢が単なる体調不良の兆候なのか、それとも医療機関で精密検査を行うレベルなのかを判断するには、重症度の把握が必要で、診察時に症状の程度を具体的に伝えることで、医師は検査や治療方針を提案しやすくなります。
症状の重さを客観的に見極めるのは、患者自身の負担を軽減するうえでも大きな意味があります。
重症度判定のメリット
重症度を正確に判断できると、不要な検査や過剰な薬物療法を避け、必要な治療に集中しやすくなります。また、急性であっても高度な脱水状態などが疑われる場合は、入院や点滴治療を検討したほうが良いケースもあります。
早期に重症度を把握することで合併症を防ぎやすくなるのも大きなメリットです。
下痢の重症度を左右する要素
重症度の目安としては、排便回数や便の性状だけでなく、全身症状や血液検査の結果なども関連します。日常生活に支障が出るほどトイレに行く頻度が多い、脱水でめまいや倦怠感がひどい、下血を伴うなどの場合は医療介入が必要です。
重症度に影響する主な指標
| 指標 | 具体例 | 重要性 |
|---|---|---|
| 排便回数 | 1日8回を超える頻回な下痢 | 生活の質を大きく損ないやすい |
| 便の性状 | ドロドロ〜水様便、血便 | 腸内の炎症や出血を示唆する場合あり |
| 脱水症状 | 口渇、皮膚の乾燥、めまい、尿量減少 | 重症度が高いと点滴を検討することも |
| 体温や腹痛の程度 | 高熱、激しい腹痛、冷や汗 | 感染症や腸の急性病変を疑う材料 |
病院受診の目安
日常的な下痢であっても、急激に悪化したり、数日経っても改善しない場合は早めに受診してください。
激しい嘔吐や持続する発熱、血便を伴う時は緊急性が高まる可能性があるため、自己判断に頼らず専門家の意見を仰いだほうが得策です。
- 1日8回以上の水様便が続くとき
- 下腹部痛が強く、立っていられないほどの痛みを感じるとき
- 血液が混ざる便や、黒色便が出るとき
- 強い脱水症状(口の渇き、尿量減少など)が見られるとき
下痢の原因別分類と特徴
下痢が起こる背景には多種多様な原因が隠れています。それぞれ病態が異なるため治療や対策も変わり、感染性か非感染性か、慢性か急性か、炎症性か機能性かなどの視点で分類すると、腸の状態をより理解できます。
急性の原因
急性下痢は、多くの場合ウイルスや細菌などの感染、食中毒、暴飲暴食、ストレスなどが関係し、消化器官が一時的にダメージを受けることで起こり、身体が病原菌や異物を排出しようとする反応の一環ともいえます。
多くは数日で改善しますが、高熱や血便など重篤な症状が続くなら早期受診が必要です。
慢性の原因
慢性下痢は、腸の炎症性疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病など)や過敏性腸症候群、吸収不良を伴う疾患、腸内細菌の異常増殖、薬剤性など、さまざまな要因が関与します。
生活習慣や食事制限だけで改善しにくい場合は、専門的な検査を受けることで正しい診断と治療方針を立てることが大事です。
機能性と器質性の視点
腸自体に明確な病変や炎症が見つからない機能性下痢(過敏性腸症候群など)と、腸の壁に潰瘍や炎症などの器質的変化がある器質性下痢に分けて考えることも多いです。
機能性の下痢はストレスや自律神経の乱れが原因になりやすいのに対して、器質性の場合は内視鏡検査で病変部位を直接確認しながら対処します。
下痢と関連のある主な疾患
| 疾患名 | 症状の特徴 | 主な検査 |
|---|---|---|
| 感染性腸炎 | 発熱、嘔吐、腹痛、水様便 | 便培養、迅速検査 |
| 潰瘍性大腸炎 | 血便や粘液便、腹痛が続きやすい | 大腸内視鏡検査で炎症・潰瘍の有無を確認 |
| クローン病 | 消化管のさまざまな部位に炎症や潰瘍が生じる。栄養吸収障害も起こりやすい | 小腸・大腸内視鏡、画像検査 |
| 過敏性腸症候群 | ストレスなどで便通異常(下痢型、便秘型、混合型)が起こりやすい | 排除診断として内視鏡検査を行う場合がある |
| 乳糖不耐症 | 乳製品摂取後に下痢や膨満感が生じる | 呼気テストなど |
- 感染性の場合は治療に抗菌薬や整腸薬を使う場合が多い
- 過敏性腸症候群は検査で器質的な異常が見つからないのが特徴
- 炎症性腸疾患は再燃と寛解を繰り返すケースがある
内視鏡検査でわかることと必要性
内視鏡検査には主に上部消化管(胃カメラ)と下部消化管(大腸カメラ)があり、いずれも粘膜を直接観察できるのが大きな利点で、下痢が長引くときや重症度が高いとき、原因を明確にするために検査を行うことがあります。
便の状態や血便の有無、体力の消耗具合などによって検査の優先度が変わりますが、早期に腸壁の状態を確認することは大切な判断材料です。
胃カメラと下痢の関係
下痢が主に大腸の異常で起こるイメージを持つ方は多いですが、消化液の分泌や胃腸全体の運動機能は胃の状態ともつながっています。
胃カメラで食道や胃、十二指腸を観察することで、上部消化管に原因となる病変が潜んでいないかを確認でき、胃酸過多やピロリ菌感染、上部消化管の潰瘍などが疑われる場合、上部の異常から下痢へ波及する可能性も考慮します。

大腸カメラの重要性
大腸カメラでは、腸内の炎症、ポリープ、潰瘍、腫瘍などの器質的変化を詳細に観察でき、慢性的な下痢で炎症性腸疾患や大腸がんが疑われる場合、粘膜の状態を直接確認することは非常に重要です。
必要に応じて組織を一部採取(生検)して詳しい病理検査を行うことで、正しい病名を特定しやすくなります。

大腸カメラで観察する主な所見
| 観察部位 | 確認できる病変 | 重症度判断の目安 |
|---|---|---|
| 直腸 | 炎症、潰瘍、ポリープなど | 病変の広がりや出血の有無 |
| S状結腸 | 潰瘍性大腸炎の好発部位の1つ | 粘膜のただれ具合や炎症の範囲 |
| 下行結腸 | 出血点や腫瘤の存在 | 大腸がんやクローン病を疑う手がかり |
| 横行結腸 | ポリープや限局性の炎症 | 病変が横行結腸に限られるかどうか |
| 上行結腸 | クローン病での縦走潰瘍など | 病変の広範囲性や再発状況の把握 |
| 回盲部 | 潰瘍や狭窄、バルーン状の腸壁 | クローン病の典型病変が出やすい場所 |
内視鏡検査のメリット
内視鏡検査の最大のメリットは、病変を直接視認しながら必要に応じて組織を採取できる点で、目視で粘膜の状態を確認できるため、下痢の原因が炎症性なのか腫瘍性なのか、あるいは機能性なのかを正確に見分ける手がかりが増えます。
正しい治療計画を立てるために必要な情報が得られるため、漫然と下痢を繰り返す患者にとっては治療への大きな一歩です。
- 内視鏡検査は粘膜を観察し、生検で確定診断に近づく
- 胃カメラは上部消化管、大腸カメラは下部消化管を対象とする
- 長引く下痢や血便がある場合は積極的に検査を検討する
重症度判定基準の代表例
下痢の重症度を測るために、学会や医師会などがさまざまな基準を策定し、排便回数や便の性状だけではなく、体内の水分バランスや血液検査の所見も評価対象です。重症度を客観的に把握することで、緊急度や治療方針を判断しやすくなります。
WHOや学術機関の指標
海外ではWHOを含む各学術機関が、急性下痢に対する脱水症状を踏まえた判定基準を提示しています。中〜重度の脱水を起こしているかどうかをチェックリストで確認し、点滴の必要性を早期に判断するのが狙いです。
日本でもこの考え方を参考にしながら、国内の医療機関がそれぞれ指標を設けています。
ブリストルスケールとの併用
便の外観を7つのタイプに分けたブリストルスケールは、日常診療で活用されることが多く、タイプ1はコロコロと硬い便、タイプ7は完全な水様便といったように分類されます。
医師とコミュニケーションをとるとき、スケールを用いて「どのタイプに近いか」を伝えるとスムーズに状況が共有できるでしょう。
ブリストルスケールの概要
| タイプ | 特徴 | 状態 |
|---|---|---|
| 1 | ウサギの糞のような硬い便 | 便秘気味 |
| 2 | かたまり状で表面がデコボコ | 軽度の便秘 |
| 3 | ソーセージ形だが表面にひび割れ | 比較的理想に近い |
| 4 | ソーセージ形で滑らか | 最も理想的な便 |
| 5 | 形が崩れ、柔らかいかたまり | 軟便寄り |
| 6 | 泥状便で不定形 | 下痢といえる範疇に近い |
| 7 | 水様便で固形物なし | 重度の下痢 |
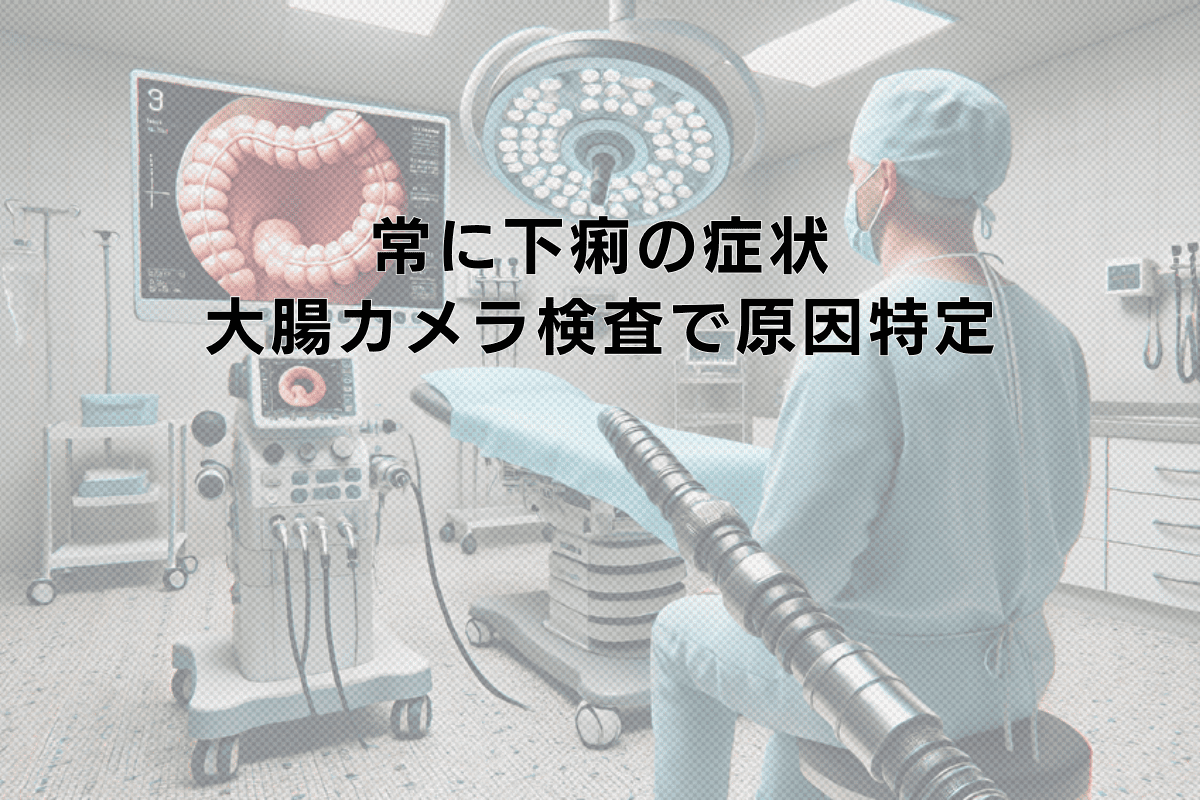
血液検査や腸内カメラの活用
脱水や電解質異常の程度を把握するには血液検査が役立ち、特に、ナトリウムやカリウムなどの電解質や腎機能の指標を確認することで、重症度を数値的に評価できます。
加えて、大腸カメラで直接粘膜を観察し炎症や潰瘍の度合いを確かめることで、下痢の原因と重症度を総合的に判定できる体制を整えられます。
入院の検討基準
重度の下痢で経口補水だけでは改善が見込めず、脱水症状が進んでいる場合は入院治療が必要です。
排便回数が多くて自宅安静が難しい、血便を伴う激しい痛みがある、あるいは腸管に重度の病変が疑われる場合などは、医療機関での点滴管理や精密検査が選択肢に入ります。
下痢を防ぐための日常ケアと受診の目安
下痢を防ぎ、再発リスクを減らすには、食生活や生活習慣の見直しが重要です。また、下痢の症状が出た際のセルフケアや、どのタイミングで医療機関へ行けばいいかなどを知っておくと、正しい対応につながります。
食生活のポイント
バランスの良い食事を心がけることは、腸内環境の安定につながるので、腸の粘膜保護に役立つたんぱく質やビタミン、腸内細菌のバランスを保つ乳酸菌などが含まれる食品を適度に取り入れたいところです。
一方で、刺激の強い香辛料や過剰なアルコール、脂っこい食品ばかりの食生活は下痢を助長する恐れがあります。
- 腸内環境を整えやすい発酵食品(ヨーグルト、納豆など)を取り入れる
- 高脂質で刺激の強い食材は摂取頻度を抑える
- 水分はこまめに補給し、脱水を防ぐ
- アルコールやカフェインを過剰に摂取しない

下痢を起こしにくい食材
| 食材 | 特徴 | 摂取のポイント |
|---|---|---|
| うどんやおかゆ | 消化しやすく胃腸に優しい | 食欲が落ちているときの主食として取り入れやすい |
| 白身魚 | 脂分が少なく、高たんぱく | 焼いたり蒸したりしてシンプルな調理法が望ましい |
| ヨーグルト | 乳酸菌が腸内環境を整える | 過剰摂取は避け、適量を毎日続ける |
| バナナ | 食物繊維とカリウムが豊富 | 朝食やおやつとして取り入れやすく、エネルギー補給になる |
生活習慣の見直し
過度のストレスや寝不足は、自律神経のバランスを崩して腸の蠕動運動を乱す要因になり、適度な運動と十分な睡眠、ストレスを溜め込みすぎないライフスタイルを意識することで、腸への負担を減らします。
便意を我慢せず、一定のリズムで排便できる環境を整えることも大切です。
自宅での対処法
軽度の下痢であれば、整腸薬や経口補水液を利用しながら様子を見る方法が多く、発熱を伴わない場合や、脱水症状が出ていない場合は、安静にして水分と電解質の補給を行うことで改善するケースも少なくありません。
ただし、激しい腹痛や血便など重大な症状がある場合は、早い段階で専門医を受診したほうが安全です。
- 水分補給は、スポーツ飲料や経口補水液を適度に利用する
- 乳酸菌サプリや整腸剤の使用も検討する
- 下痢止め薬の使用は、感染症のとき逆効果になる場合もある
- 体調が悪化する前に医療機関へ連絡する
下痢時の水分補給に適した飲料
| 飲料 | 利点 | 注意点 |
|---|---|---|
| 経口補水液 | 電解質と水分を効率良く補える | 塩分や糖分が一定量含まれるため過剰摂取に注意 |
| スポーツドリンク | ミネラルと糖質のバランスが比較的良い | 糖分が多い商品もあるため成分表の確認が必要 |
| 麦茶 | カフェインが少なく、胃腸に優しい | ミネラル補給という点では弱い場合がある |
| 白湯 | 胃腸を刺激しにくく、手軽に取り入れられる | 電解質は不足しやすいので他の飲料も併用する |

医療機関を受診するタイミング
下痢の原因がはっきりせず、再発を繰り返す場合や症状が急激に悪化する場合は、内視鏡検査を含めた精密診断を検討する段階です。
特に排便時の出血や高熱、長引く下痢は要注意で、症状が1週間以上続く、あるいは体力が著しく奪われているなら受診を先延ばしにしないでください。
よくある質問
下痢や内視鏡検査に関して疑問を持つ方は多いです。ここでは代表的な質問をまとめましたので、受診や検査を検討している方は参考にしてください。
- 病院へ行くべきか迷ったときはどうすればいい?
-
数日で自然に収まる軽度の下痢であれば、適度な休養と水分・栄養補給で様子を見る方法もありますが、排便時の出血、高熱、激しい腹痛、脱水症状が顕著なときは早めに受診したほうが安全です。
下痢が慢性的に続く場合も大腸カメラなどの検査を考慮してください。
- 下痢をしているときに下剤や胃腸薬を勝手に飲んでもいい?
-
自己判断で薬を使うと逆効果になるリスクがあり、例えば、感染症による下痢の場合は、病原菌を体外に排出する過程を止めてしまうおそれもあります。
市販の胃腸薬や整腸薬を利用する際は成分を確認し、症状の経過を観察しながら慎重に検討しましょう。
- 内視鏡検査はいつ受けるのが適切?
-
明らかな病変が疑われる場合や長期的な下痢が続く場合、医師は速やかに内視鏡検査を提案することがあります。検査時期は専門医の判断が重要ですが、体調が安定しすぎていない段階でも実施することが可能です。
便中に血が混ざるなど明確な異常があれば、早めに検査を受けて原因を突き止めることをおすすめします。
- 検査前の食事制限や下剤はどうすればいい?
-
大腸カメラ検査では腸内をきれいにする目的で事前の食事制限や下剤服用が求められるので、医療機関の指示に従ってください。準備を正しく行うことで、検査がスムーズに進み、精度が高まります。
次に読むことをお勧めする記事
【消化器官の機能と働き|内視鏡検査で分かること】
下痢と内視鏡検査について学んだ皆さんには、消化器官全体の働きの知識も合わせて持っていただくと、より包括的な理解ができます。
【腸の健康が体を支える 腸内環境を整える】
下痢対策には腸内環境の安定も欠かせません。善玉菌を増やす食生活と生活習慣を学び、再発予防に役立てましょう。
参考文献
Kinoshita Y, Ariyoshi R, Fujigaki S, Tanaka K, Morikawa T, Sanuki T. Endoscopic diagnosis of chronic diarrhea. DEN open. 2022 Apr;2(1):e53.
Yamauchi Y, Arai M, Akizue N, Ohta Y, Okimoto K, Matsumura T, Fan MM, Imai C, Tawada A, Kato J, Kato N. Colonoscopic evaluation of diarrhea/colitis occurring as an immune-related adverse event. Japanese Journal of Clinical Oncology. 2021 Mar;51(3):363-70.
Hiejima E, Nakase H, Matsuura M, Honzawa Y, Higuchi H, Saida S, Umeda K, Hiramatsu H, Adachi S, Izawa K, Kawai T. Diagnostic accuracy of endoscopic features of pediatric acute gastrointestinal graft‐versus‐host disease. Digestive Endoscopy. 2016 Jul;28(5):548-55.
Nagata N, Shimbo T, Yazaki H, Asayama N, Akiyama J, Teruya K, Igari T, Ohmagari N, Oka S, Uemura N. Predictive clinical factors in the diagnosis of gastrointestinal Kaposi’s sarcoma and its endoscopic severity. PLoS One. 2012 Nov 30;7(11):e46967.
Shimura S, Ishimura N, Tanimura T, Yuki T, Miyake T, Kushiyama Y, Sato S, Fujishiro H, Ishihara S, Komatsu T, Kaneto E. Reliability of symptoms and endoscopic findings for diagnosis of esophageal eosinophilia in a Japanese population. Digestion. 2014 Sep 1;90(1):49-57.
Nagata N, Shimbo T, Sekine K, Tanaka S, Niikura R, Mezaki K, Morino E, Yazaki H, Igari T, Ohmagari N, Akiyama J. Combined endoscopy, aspiration, and biopsy analysis for identifying infectious colitis in patients with ileocecal ulcers. Clinical Gastroenterology and Hepatology. 2013 Jun 1;11(6):673-80.
Matsumoto T, Hisamatsu T, Esaki M, Omori T, Sakuraba H, Shinzaki S, Sugimoto K, Takenaka K, Naganuma M, Bamba S, Hisabe T. Guidelines for endoscopic diagnosis and treatment of inflammatory bowel diseases. Digestive Endoscopy. 2025 Mar 5.
Arimoto J, Endo H, Kato T, Umezawa S, Fuyuki A, Uchiyama S, Higurashi T, Ohkubo H, Nonaka T, Takeno M, Ishigatsubo Y. Clinical value of capsule endoscopy for detecting small bowel lesions in patients with intestinal Behçet’s disease. Digestive Endoscopy. 2016 Feb;28(2):179-85.
Shen B, Khan K, Ikenberry SO, Anderson MA, Banerjee S, Baron T, Ben-Menachem T, Cash BD, Fanelli RD, Fisher L, Fukami N. The role of endoscopy in the management of patients with diarrhea. Gastrointestinal endoscopy. 2010 May 1;71(6):887-92.
Fine KD, Seidel RH, Do K. The prevalence, anatomic distribution, and diagnosis of colonic causes of chronic diarrhea. Gastrointestinal endoscopy. 2000 Mar 1;51(3):318-26.