大腸ポリープは、初期には自覚症状がほとんどないものの、放置すると大腸がんに進行する可能性がある病変ですが、早期に発見し、適切に内視鏡を用いて切除することで、大腸がんの予防につながります。
この記事では、大腸ポリープの基礎知識から、検査方法、内視鏡による治療法、治療後の注意点、そしてポリープ 切除の実際について、分かりやすく解説します。
大腸ポリープの基礎知識
大腸ポリープについて理解を深めることは、早期発見と適切な対応への第一歩です。ここでは、ポリープの基本的な定義、発生要因、症状、そして最も懸念される大腸がんとの関連性について説明します。
大腸ポリープとはどのようなものか
大腸ポリープとは、大腸の粘膜(最も内側の層)にできる隆起性の病変の総称で、形や大きさは様々で、数ミリ程度の小さなものから数センチに及ぶものまであります。
ポリープにはいくつかの種類があり、主に腫瘍性ポリープと非腫瘍性ポリープに大別されます。特に注意が必要なのは腫瘍性ポリープであり、代表が腺腫です。
腺腫は、時間をかけて大きくなり、その一部ががん化する可能性があるため、大腸がんの芽とも呼ばれます。一方、非腫瘍性ポリープには過形成性ポリープや炎症性ポリープなどがあり、一般的にがん化のリスクは低いです。
主なポリープの種類と特徴
| ポリープの種類 | 特徴 | がん化リスク |
|---|---|---|
| 腺腫性ポリープ | 最も一般的。多くは良性だが、がん化する可能性がある。 | あり(大きさや形状による) |
| 過形成性ポリープ | 直腸やS状結腸に多い。通常はがん化しない。 | 低い(一部例外あり) |
| 炎症性ポリープ | 潰瘍性大腸炎など炎症性腸疾患に伴い発生。 | 低い(背景疾患による) |
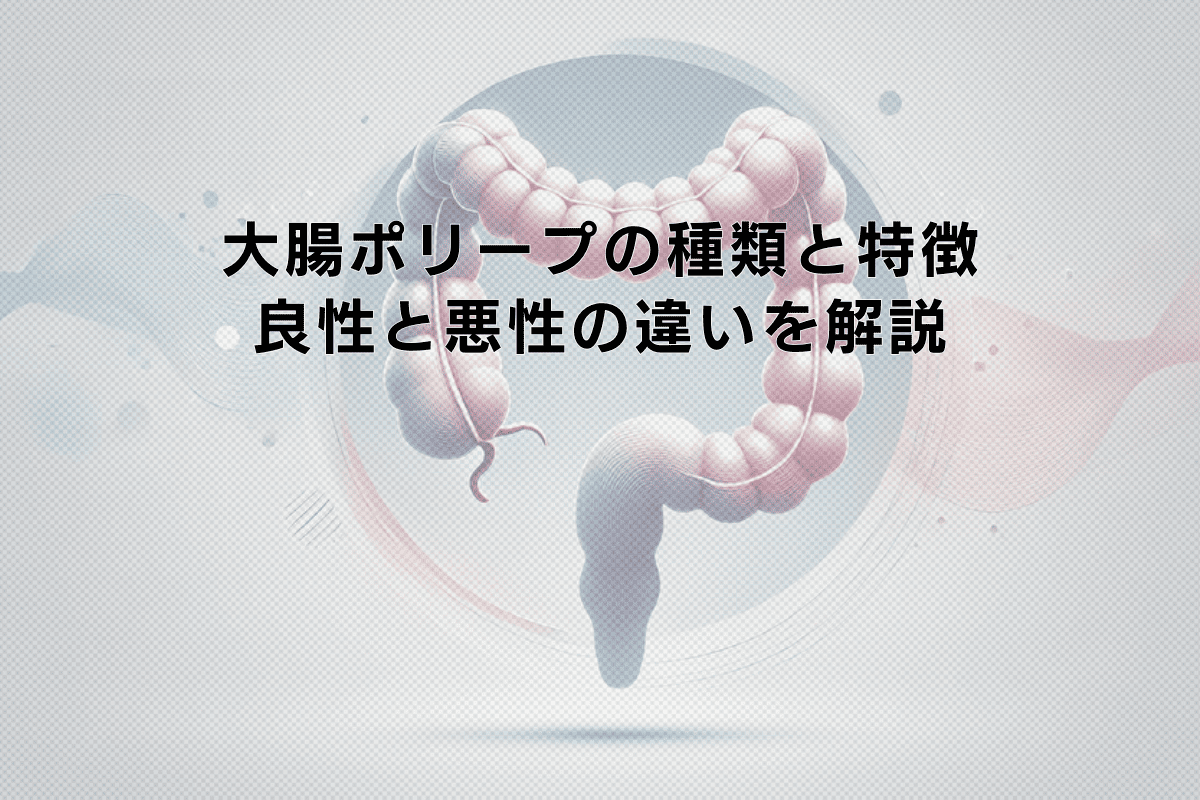
大腸ポリープが発生する主な要因
大腸ポリープの発生には、複数の要因が関与していると考えられています。完全に解明されているわけではありませんが、遺伝的要因と環境要因の両方が影響するとされています。
年齢も重要な要素で、一般的に50歳を過ぎるとポリープの発生率は上昇傾向にあります。食生活の欧米化、特に動物性脂肪や赤肉の過剰摂取、食物繊維の摂取不足は、大腸内環境に影響を与え、ポリープ発生のリスクを高めると指摘されています。
また、肥満、運動不足、喫煙、過度なアルコール摂取といった生活習慣も関連が深いと考えられていて、さらに家族歴も無視できません。
ポリープ発生に関わる主な要因
| 要因カテゴリ | 具体的な要因 | 影響 |
|---|---|---|
| 生活習慣 | 高脂肪・低繊維食、赤肉・加工肉の多量摂取 | リスク上昇 |
| 生活習慣 | 肥満、運動不足、喫煙、過度な飲酒 | リスク上昇 |
| 遺伝・その他 | 加齢(特に50歳以上)、家族歴、遺伝性疾患 | リスク上昇 |
大腸ポリープの自覚症状と放置した場合のリスク
多くの場合、大腸ポリープは初期の段階では自覚症状がありませんが、症状がないからといって安心はできません。
ポリープが大きくなったり、数が増えたりすると、まれに症状が現れることがあります。便に血が混じる(血便)、便の表面に血液が付着する、便通異常(便秘や下痢)、腹痛、腹部膨満感などです。
ポリープを放置した場合の最大のリスクは、大腸がんに進行する可能性があることで、特に腺腫性ポリープは、数年から十数年かけてがん化することがあり、早期の内視鏡 ポリープ切除ががん予防に繋がります。
ポリープに関連する可能性のある症状
- 血便・下血
- 便通異常(便秘・下痢)
- 腹痛・腹部不快感
- 便が細くなる
大腸ポリープと大腸がんの関係性
大腸がんの多くは、良性のポリープ(主に腺腫)が時間をかけてがん化することで発生し、腺腫からがんへという経路は「adenoma-carcinoma sequence」として知られており、大腸がん予防のための基本的な考え方です。
がん化する前のポリープの段階で発見し、内視鏡によって取り除ければ、将来的な大腸がんの発生を効果的に防ぐことが期待できます。
全てのポリープががん化するわけではありませんが、1cmを超える大きさの腺腫や、特殊な形態を示す腺腫(絨毛腺腫など)はがん化のリスクが高いです。
大腸ポリープを発見するための検査
大腸ポリープは自覚症状に乏しいため、定期的な検査による早期発見が何よりも大切です。ここでは、代表的な検査方法である便潜血検査と大腸内視鏡検査を中心に、それぞれの特徴や重要性について解説します。
便潜血検査の役割と限界について
便潜血検査は、便に微量の血液が混じっていないかを調べる簡便な検査で、多くの場合、健康診断や住民検診などで広く行われています。
検査の目的は、大腸ポリープや大腸がんなど、出血を伴う可能性のある大腸の病変を早期に発見する手がかりを得ることです。
便潜血検査は、身体への負担が少なく、多くの人を対象にスクリーニングできる利点がありますが、いくつかの限界もあり、潰瘍性大腸炎やクローン病などの炎症性腸疾患、痔など肛門付近の出血でも陽性となることがあります。
また、出血していないポリープや早期のがんは見逃される可能性があり、陰性イコール病気がないというわけではありません。
大腸内視鏡検査(大腸カメラ)による詳細な観察
大腸内視鏡検査は、先端に小型カメラが付いた細く柔軟なスコープ(内視鏡)を肛門から挿入し、直腸から盲腸までの大腸全体を直接観察する検査です。
この検査の最大の利点は、粘膜を詳細に観察できるため、微小なポリープや早期がんの発見に優れていることです。
さらに、検査中にポリープが発見された場合、その場で組織を採取して病理検査に提出したり、条件が整えば「内視鏡 ポリープ 切除」を行ったりすることもできます。
その他の大腸検査方法の概要
大腸内視鏡検査以外にも、大腸の状態を調べる検査方法がいくつかあります。それぞれに利点と欠点があるため、医師と相談の上、状況に応じて適切な検査を選択することが大切です。
主な大腸検査法の比較
| 検査方法 | 特徴 | 長所・短所 |
|---|---|---|
| CTコロノグラフィ | CTを用いて大腸の3D画像を構築。下剤は必要だが、内視鏡挿入はない。 | 長所: 苦痛少ない、短時間。短所: 小さな平坦な病変の検出は内視鏡に劣る、放射線被曝、生検や治療不可。 |
| 注腸X線検査(バリウム検査) | バリウムと空気を肛門から注入し、X線撮影する。 | 長所: 大腸全体の形態把握。短所: 小さな病変の検出率低い、放射線被曝、前処置大変、苦痛伴うことあり。 |
| カプセル内視鏡 | 小型カメラ内蔵カプセルを服用し、消化管を通過しながら撮影。 | 長所: 苦痛少ない。短所: 大腸用はまだ限定的、生検や治療不可、通過障害リスク。 |

主な内視鏡的ポリープ切除術
大腸内視鏡検査でポリープが発見された場合、その大きさ、形状、推定される組織型などに応じて、様々な「内視鏡 ポリープ 切除」術が選択されます。ここでは代表的な切除術について解説します。
ポリペクトミーの種類と特徴
ポリペクトミーは、比較的小さなポリープや、茎のある有茎性ポリープに対して行われる基本的な切除術です。
内視鏡の先端からスネアと呼ばれる金属製の輪っか状のワイヤーを出し、ポリープの根元に引っ掛けて締め付け、高周波電流を流して焼き切る方法(ホットスネアポリペクトミー)が一般的です。
電流を用いずにスネアで機械的に切除する方法(コールドスネアポリペクトミー)や、鉗子(かんし)でつまんで切除する方法(ホットバイオプシー、コールドポリペクトミー)もあります。
スネアを用いたポリペクトミー
スネアポリペクトミーは、最も広く行われている内視鏡切除術の一つで、ホットスネアポリペクトミーでは、高周波電流によって切除と同時に止血効果も期待できます。
一方、コールドスネアポリペクトミーは、主に微小なポリープ(通常5mm以下)に対して行われ、通電による組織の熱損傷や後出血のリスクが低いということが利点です。
ホットバイオプシーによる切除
ホットバイオプシーは、非常に小さなポリープ(数ミリ程度)に対して行われる方法で、内視鏡の先端から出す生検鉗子でポリープをつまみ、高周波電流を流して焼き切ります。
手技が比較的簡便である一方、切除できる組織の深さが浅いため、大きなポリープやがんが疑われるポリープには適していません。
コールドポリペクトミーの手法
コールドポリペクトミーは、高周波電流を使用せずにポリープを切除する方法の総称で、コールドスネアポリペクトミーの他に、コールドバイオプシーフォースプス(鉗子)で小さなポリープを機械的に切除する方法も含まれます。
熱損傷がないため、穿孔(腸に穴が開くこと)や後出血のリスクが低いとされ、近年、特に小さなポリープに対して積極的に用いられるようになっています。切除後の組織評価も熱変性の影響を受けにくいです。
ポリペクトミー手技の比較
| 手技 | 対象ポリープ(目安) | 特徴 |
|---|---|---|
| ホットスネアポリペクトミー | 5mm~20mm程度、有茎性・亜有茎性 | 高周波電流で切除・止血。広く用いられる。 |
| コールドスネアポリペクトミー | 10mm以下の平坦・隆起性 | 非通電。熱損傷少なく、後出血リスク低い。 |
| ホットバイオプシー | 5mm以下の微小ポリープ | 鉗子でつまみ通電焼灼。簡便だが深部切除は困難。 |
内視鏡的粘膜切除術(EMR)の概要
内視鏡的粘膜切除術(Endoscopic Mucosal Resection, EMR)は、主に茎のない平坦なポリープや、少し大きめのポリープ(一般的に2cm程度まで)に対して行われる治療法です。
この手技では、ポリープの下の粘膜下層に生理食塩水などを注入して病変を持ち上げ(隆起させ)、スネアをかけて高周波電流で焼き切ります。
粘膜下層に液体を注入することで、ポリープと固有筋層(大腸壁の深い層)との間に距離ができ、安全に切除しやすくなるとともに、熱が深部に伝わるのを防ぐ効果があります。
EMRは、ポリペクトミーでは切除が難しい、ある程度の大きさと広がりを持つ病変に対して有効な「内視鏡 ポリープ 切除」法です。
内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)の概要
内視鏡的粘膜下層剥離術(Endoscopic Submucosal Dissection, ESD)は、EMRでは一括切除が難しい大きな平坦型ポリープや、早期大腸がんの一部に対して行われる、より高度な内視鏡治療技術です。
この方法では、病変の周囲の粘膜を電気メスで切開し、その後、粘膜下層を少しずつ剥離して病変を一括で切除します。
EMRでは分割して切除せざるを得ないような大きな病変でも、ESDを用いることで一括切除が可能となり、より正確な病理診断と低い局所再発率が期待できます。
ポリープの大きさや形状に応じた切除術の選択
どの切除術を選択するかは、ポリープの大きさが最も重要な判断基準の一つですが、それ以外にも形状(有茎性か、無茎性か、平坦か、陥凹しているかなど)、内視鏡で観察される表面構造、硬さ、そしてがんの可能性などを総合的に評価して決定されます。
治療法の選択目安
- 微小ポリープ(~5mm): コールドポリペクトミー、ホットバイオプシー
- 小ポリープ(5mm~10mm): コールドスネア、ホットスネア
- 中ポリープ(10mm~20mm): ホットスネア、EMR
- 大ポリープ(20mm~): EMR(分割)、ESD
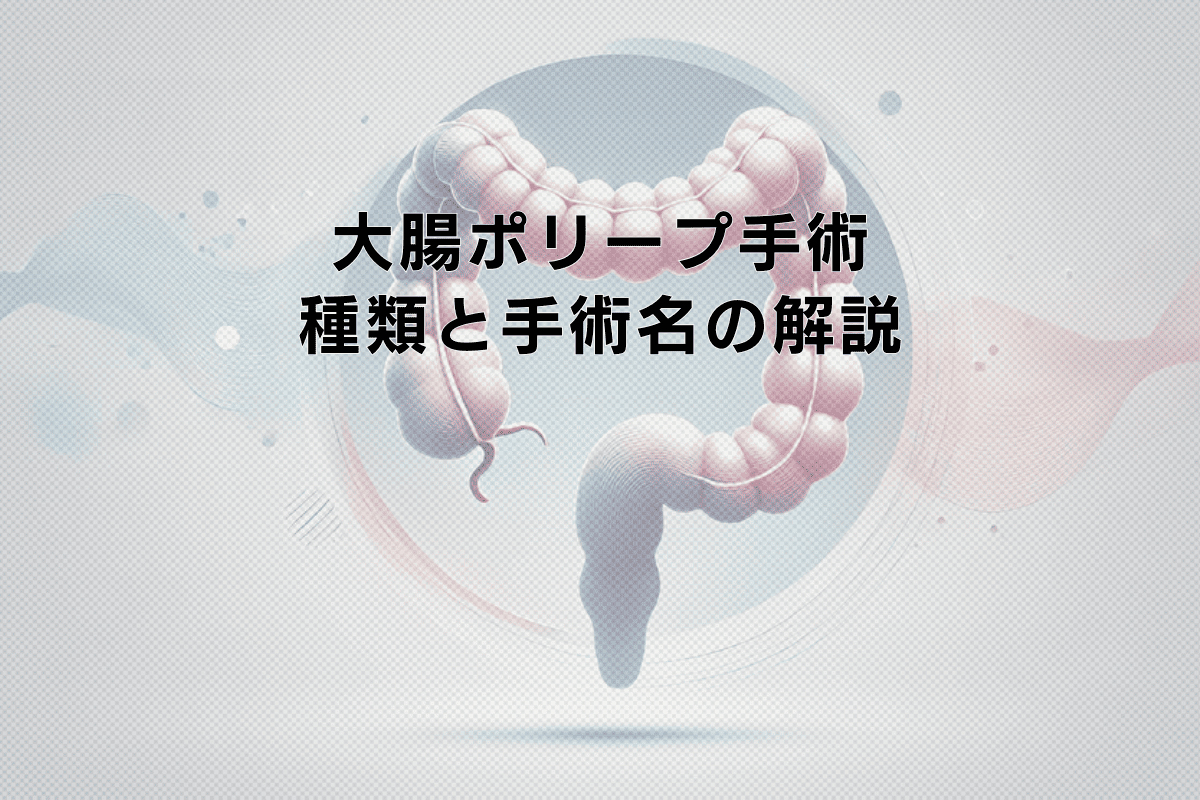
内視鏡治療の具体的な流れと注意点
大腸ポリープの内視鏡治療を受けるにあたり、事前に流れや注意点を理解しておくことは、安心して治療に臨むために大切です。
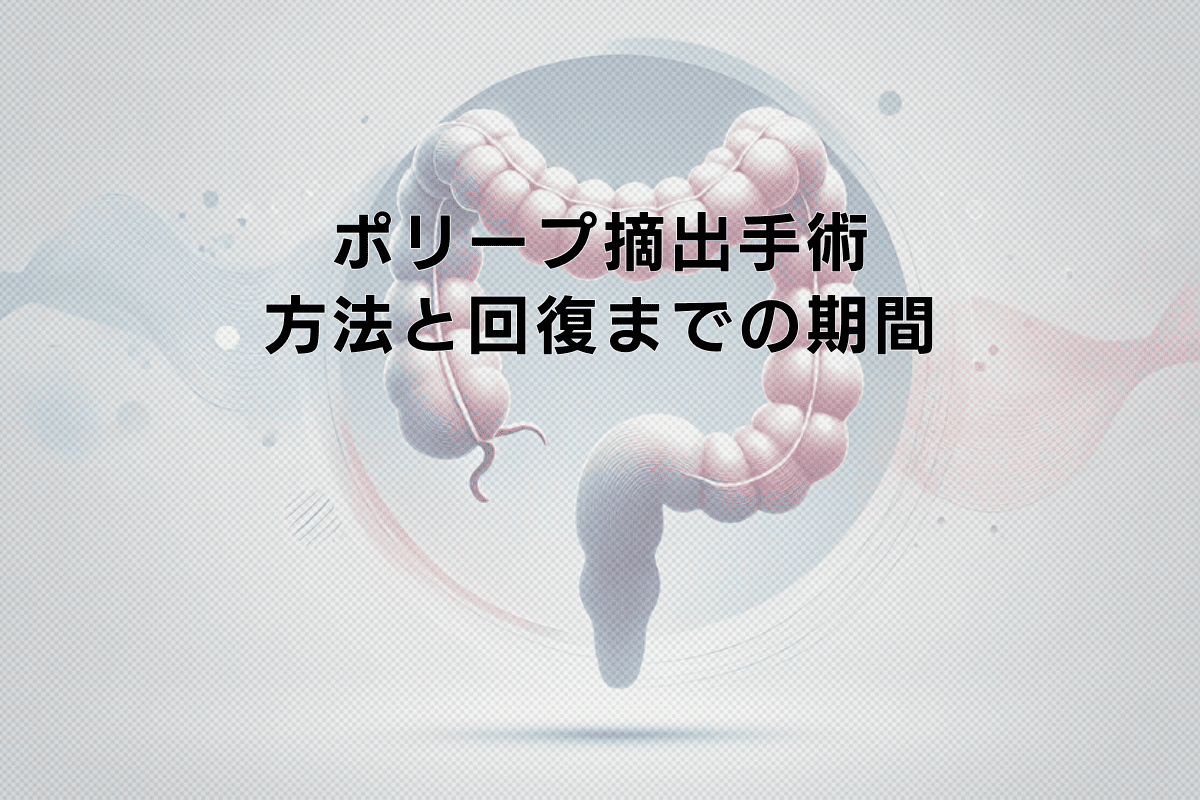
内視鏡的ポリープ切除術に伴う偶発症
内視鏡的ポリープ切除術は比較的安全な治療法とされていますが、手術である以上、稀に偶発症(合併症)が起こる可能性があります。
術後の出血とその対応方法
ポリープ切除後の最も一般的な偶発症は出血で、出血には、切除直後に起こるものと、数時間から数日後(多くは1週間以内)に起こる後出血(遅発性出血)があります。
切除時に血管を電気で焼灼するため、多くの場合、出血はコントロールされますが、切除した部位のかさぶたが剥がれたり、便の刺激で再出血したりすることがあります。
少量の出血であれば自然に止まることもありますが、持続的な出血や多量の出血(便器が真っ赤になるような)が見られる場合は、速やかに医療機関を受診する必要があります。
多くの場合、再度内視鏡を行い、出血部位を確認して止血処置(クリップで血管を閉じる、薬剤を注入するなど)を行いますが、輸血が必要になることは稀です。
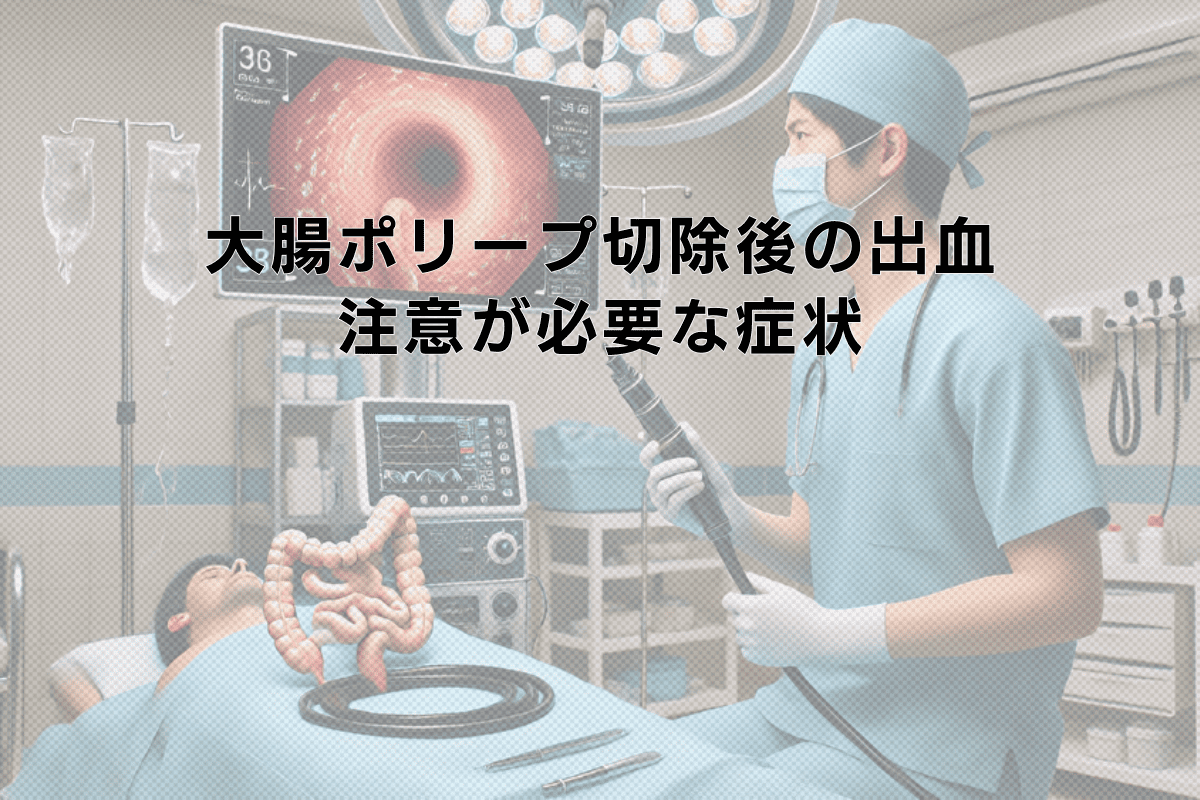
消化管穿孔のリスクと対処法
穿孔(せんこう)とは、大腸の壁に穴が開いてしまう偶発症です。ポリープ切除の際に、電気メスやスネアの操作によって腸壁が深く傷ついたり、熱が深くまで伝わりすぎたりすることで起こる可能性があります。
特に、大きなポリープの切除やESDのような高度な手技では、そのリスクがわずかながら高まります。穿孔が起こると、腸の内容物が腹腔内に漏れ出し、腹膜炎を引き起こす可能性があります。
症状としては、強い腹痛、発熱、嘔吐などが見られます。穿孔が疑われた場合は、緊急の対応が必要です。
小さな穿孔であれば、絶食、抗生物質の投与、内視鏡を用いたクリップ閉鎖などで保存的に治療できることもありますが、状態によっては緊急手術が必要になることもあります。
ポリープ切除後のフォローアップと再発への備え
大腸ポリープを切除した後も、それで終わりではありません。定期的な経過観察と、再発予防のための取り組みが、将来の大腸がんリスクを低減するために大切です。
切除後の定期的な内視鏡検査の必要性
ポリープを切除した後、最も重要なのは定期的な大腸内視鏡検査によるフォローアップで、一度ポリープができたということは、大腸の他の場所にも新たなポリープが発生しやすい体質である可能性を示唆しています。
また、非常に小さなポリープが見逃されていたり、切除したポリープがごく稀に再発したりすることもあります。
そのため、切除したポリープの種類、数、大きさ、組織型(がん細胞が含まれていたかどうかなど)に応じて、医師が次回の検査時期を指示します。
一般的には、初回ポリープ切除後1年から3年以内に再度内視鏡検査を行い、問題がなければその後は3年から5年ごとの検査となることが多いですが、これはあくまで目安です。
高リスクなポリープ(大きな腺腫、多数の腺腫、がん細胞を含むポリープなど)を切除した場合は、より短い間隔での検査が必要となることがあります。
フォローアップ検査の間隔目安
| 切除ポリープのリスク | 初回フォローアップ(目安) | その後の間隔(目安) |
|---|---|---|
| 低リスク(例: 小さな腺腫1~2個) | 3年後 | 3~5年ごと |
| 中リスク(例: 大きな腺腫、多数の腺腫) | 1年後 | 3年ごと |
| 高リスク(例: がんを含むポリープ切除後) | 3~6ヶ月後、その後1年後 | 医師の指示による |
※上記は一般的な目安であり、個々の状態により異なります。必ず医師の指示に従ってください。
大腸ポリープの再発の可能性について
「再発」という言葉には二つの意味合いがあります。一つは、切除したポリープが同じ場所から再び発生すること(局所再発)、もう一つは、切除した場所以外の大腸の別の場所に新たなポリープが発生すること(異時性多発)です。
「内視鏡 的 大腸 ポリープ 切除 術」が適切に行われれば、局所再発のリスクは低いですが、特に大きなポリープを分割して切除した場合などでは、わずかに残った組織から再発することがあります。
一方、異時性多発ポリープは、ポリープができやすい体質の方には比較的よく見られます。研究によれば、ポリープを切除した人の約30~50%が、数年以内に新たなポリープを発見されると報告されています。
生活習慣の見直しによる再発予防への取り組み
大腸ポリープの発生には生活習慣が深く関わっていると考えられているため、ポリープを切除した後も、再発予防のために生活習慣を見直すことが推奨されます。
完全に再発を防ぐことは難しいかもしれませんが、リスクを低減させる努力は大切です。
食生活で心掛けたいこと
バランスの取れた食事が基本で、特に、食物繊維を豊富に含む野菜、果物、豆類、きのこ類、海藻類を積極的に摂取することが勧められています。食物繊維は便通を整え、腸内環境を改善する効果が期待できます。
また、動物性脂肪や赤肉(牛肉、豚肉など)、加工肉(ハム、ソーセージなど)の過剰な摂取は控えるようにしましょう。
カルシウムの摂取も、ポリープ予防に関連する可能性が示唆されています。乳製品や小魚などから適度に摂取するとよいでしょう。

適度な運動のすすめ
定期的な運動習慣も、大腸ポリープの再発予防に役立つと考えられていて、運動は腸の動きを活発にし、便通を改善する効果があります。また、肥満の予防・改善にも繋がり、これはポリープのリスク低減に間接的に貢献します。
ウォーキング、ジョギング、水泳、サイクリングなど、自分が楽しめる有酸素運動を、週に数回、1回30分程度から始めてみるのが良いでしょう。
よくあるご質問
大腸内視鏡検査やポリープ切除に関して、患者さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。治療を検討されている方の不安解消の一助となれば幸いです。
- 大腸内視鏡検査は苦痛を伴いますか
-
大腸内視鏡検査に伴う苦痛の感じ方には個人差があり、お腹の張りや、内視鏡が腸の曲がり角を通過する際に軽い痛みを感じることがあります。
しかし、近年では、細くて柔らかい内視鏡の使用や、医師の挿入技術の向上、そして鎮静剤・鎮痛剤の使用により、苦痛は大幅に軽減されています。
多くの医療機関では、患者さんの希望に応じて鎮静剤を使用し、ウトウトとリラックスした状態で検査を受けられます。
- ポリープを切除すれば大腸がんの心配はなくなりますか
-
大腸ポリープ、特に腺腫を切除することは、そのポリープが将来がん化するリスクを取り除くことになるため、大腸がんの予防に非常に効果的ですが、ポリープを切除したからといって、将来絶対に大腸がんにならないというわけではありません。
切除した場所以外の大腸に新たなポリープが発生する可能性(異時性発生)がありますし、ごく稀に見逃される微小なポリープや、非常に進行の速い特殊なタイプのがんもあります。
そのため、ポリープ切除後も、医師の指示に従って定期的な大腸内視鏡検査を受けることが重要です。
- 内視鏡的ポリープ切除術の費用はどの程度ですか
-
内視鏡的ポリープ切除術の費用は、健康保険が適用されますが、切除したポリープの数や大きさ、行われた切除術の種類(ポリペクトミー、EMR、ESDなど)、使用した薬剤、入院の有無などで異なります。
日帰りで小さなポリープを数個切除した場合、3割負担の方で数万円程度が目安となることが多いですが、大きなポリープの切除やESDなどの高度な治療、あるいは短期入院が必要な場合は、費用がそれ以上になることもあります。
次に読むことをお勧めする記事
【大腸ポリープ切除後の回復と体調変化】
切除後の回復過程でよくある症状や注意点がまとまっており、『術後どんな体調になるのか』心配な方に特に参考になります。
【大腸ポリープ切除後の出血と対応|正常な経過と注意が必要な症状】
『少しの出血は大丈夫?』という疑問に、「いつが軽症で、いつ医療機関を受診すべきか」を丁寧に答えてくれる内容です。
参考文献
Tanaka S, Saitoh Y, Matsuda T, Igarashi M, Matsumoto T, Iwao Y, Suzuki Y, Nishida H, Watanabe T, Sugai T, Sugihara KI. Evidence-based clinical practice guidelines for management of colorectal polyps. Journal of gastroenterology. 2015 Mar;50:252-60.
Tanaka S, Saitoh Y, Matsuda T, Igarashi M, Matsumoto T, Iwao Y, Suzuki Y, Nozaki R, Sugai T, Oka S, Itabashi M. Evidence-based clinical practice guidelines for management of colorectal polyps. Journal of Gastroenterology. 2021 Apr;56:323-35.
Saito Y, Oka S, Kawamura T, Shimoda R, Sekiguchi M, Tamai N, Hotta K, Matsuda T, Misawa M, Tanaka S, Iriguchi Y. Colonoscopy screening and surveillance guidelines. Digestive Endoscopy. 2021 May;33(4):486-519.
Shimada S, Hotta K, Takada K, Imai K, Ito S, Kishida Y, Kawata N, Yoshida M, Yamamoto Y, Maeda Y, Minamide T. Complete endoscopic removal rate of detected colorectal polyps in a real world out-patient practical setting. Scandinavian Journal of Gastroenterology. 2023 Apr 3;58(4):422-8.
Sano Y, Fujii T, Oda Y, Matsuda T, Kozu T, Kudo SE, Igarashi M, Iishi H, Fu KI, Kaneko K, Hotta K. A multicenter randomized controlled trial designed to evaluate follow‐up surveillance strategies for colorectal cancer: the Japan Polyp Study. Digestive Endoscopy. 2004 Oct;16(4):376-8.
Doniec JM, Löhnert MS, Schniewind B, Bokelmann F, Kremer B, Grimm H. Endoscopic removal of large colorectal polyps: prevention of unnecessary surgery?. Diseases of the colon & rectum. 2003 Mar;46:340-8.
Winawer SJ, Zauber AG, Ho MN, O’Brien MJ, Gottlieb LS, Sternberg SS, Waye JD, Schapiro M, Bond JH, Panish JF, Ackroyd F. Prevention of colorectal cancer by colonoscopic polypectomy. New England Journal of Medicine. 1993 Dec 30;329(27):1977-81.
Winawer SJ, O’brien MJ, Waye JD, Kronborg O, Bond J, Frühmorgen P, Sobin LH, Burt R, Zauber A, Morson B. Risk and surveillance of individuals with colorectal polyps. Who Collaborating Centre for the Prevention of Colorectal Cancer. Bulletin of the World Health Organization. 1990;68(6):789.
Zauber AG, Winawer SJ, O’Brien MJ, Lansdorp-Vogelaar I, van Ballegooijen M, Hankey BF, Shi W, Bond JH, Schapiro M, Panish JF, Stewart ET. Colonoscopic polypectomy and long-term prevention of colorectal-cancer deaths. New England Journal of Medicine. 2012 Feb 23;366(8):687-96.
Jover R, Dekker E. Surveillance after colorectal polyp removal. Best Practice & Research Clinical Gastroenterology. 2016 Dec 1;30(6):937-48.










