体に負担が少ない治療法として注目されている内視鏡手術は、主に消化管の病変を対象とした治療に用いている方法で、病変を切除する際の傷が小さく済むことや、術後の痛みを抑えやすい点などが特徴です。
近年は、大腸カメラや胃カメラ検査の延長として内視鏡手術を選択する例が増えています。
外科的治療よりも体へのダメージが軽く、日常生活への復帰も早い場合が多いことから、治療を検討する患者さんが増加傾向にあるようです。
内視鏡手術とは何か
内視鏡手術は、従来の開腹や開胸などに比べて切開の範囲を小さくできる方法で、先端にカメラが付いた内視鏡を挿入し、必要な処置を行います。
傷が小さいため、体力的負担を抑えやすく、術後の社会復帰もスムーズに進みやすいです。
内視鏡手術の成り立ち
開腹手術では広範囲の切開が必要でしたが、内視鏡の普及に伴って小さな切開や口からの挿入で治療を進める技術が開発されました。初めは診断目的が中心でしたが、器具の改良によって治療の領域まで広がった経緯があります。
従来の手術とは異なる発想で、光学機器と特殊な処置具を用いることにより、より細やかな作業が可能で、特に消化器領域では、食道や胃、大腸などの粘膜を直接観察して、病変部を確認しながら切除できます。
内視鏡手術における医師の技量
扱う範囲が狭く、内視鏡の映像を頼りに小さな病変を正確に把握しなければならないため、高度な技術が求められます。
視野が限られる中で、正確な位置取りや器具の操作を行う必要があり、内視鏡に関する専門的な知識と実践力を備えた医師が担当します。
なお、医師だけでなく看護師や臨床工学技士などのサポートも重要で、複数のスタッフが連携してこそ安全性が高まり、良好な治療結果を得やすいです。
内視鏡手術の歴史的背景
内視鏡が広く導入される前は、胃や大腸の検査にはX線検査などが多く使われていました。
しかし、病変の形状や出血の有無などを直接確認できる内視鏡が登場し、さらに治療にまで踏み込む技法が発展したことで、患者さんの負担を抑えながら病変を除去できるようになりました。
内視鏡下で用いる主な治療法
| 治療法名 | 概要 | 対象となる病変例 |
|---|---|---|
| ポリペクトミー | 内視鏡でポリープを切除する方法 | 大腸ポリープ、胃ポリープ |
| EMR(粘膜切除術) | 病変を含む粘膜を内視鏡的に切除する方法 | 早期胃がん、早期大腸がん |
| ESD(粘膜下層剥離術) | 病変が大きい場合に粘膜下層から剥離し切除する方法 | 早期食道がん、広範囲の早期胃がん、早期大腸がん |
内視鏡の登場によって診断だけでなく治療も行いやすくなり、早期発見・早期治療を実現しやすい環境が整ってきました。
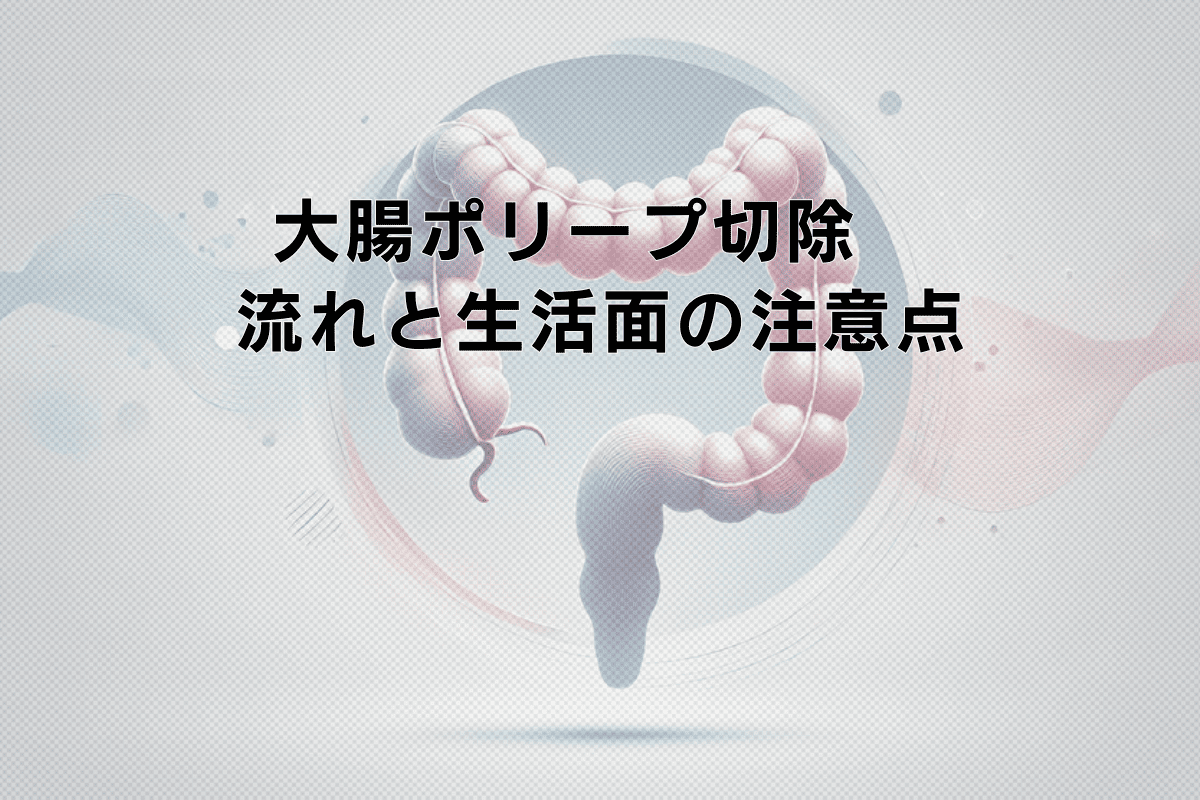
内視鏡手術の種類と治療対象
内視鏡手術にはさまざまな種類がありますが、代表的なものは消化管疾患を対象にした治療で、胃や大腸などの粘膜にできるがんやポリープを、外科的な大きな切開をせずに切除できるのが強みです。
消化管を中心とした内視鏡手術の例
消化管の内視鏡手術では、胃カメラや大腸カメラをベースに、専用の治療器具を使用して病変を切除し、早期がんや大きなポリープにも対応可能で、術後の入院期間が短いことが多いです。
従来の外科手術と比較すると、体への侵襲はかなり小さくなり、病変が大きくなり過ぎていない段階で見つかった場合に有効な選択肢として考えられています。
呼吸器や耳鼻咽喉科領域への応用
内視鏡手術は、消化管以外にも呼吸器領域や耳鼻咽喉科領域で活用されることが増え、副鼻腔や喉頭なども内視鏡を利用して治療できる場合があります。
ただし、消化管と比べると解剖学的な特徴が異なるため、専門のトレーニングを受けた医師が行います。
消化器がん以外の疾患への対応
逆流性食道炎や胃潰瘍などの内科的治療では、内視鏡が診断や治療効果の判定に用いられます。がんやポリープほど侵襲的な処置を必要としない場合がほとんどであり、薬物治療を行いながら観察を継続するケースが多いです。
一方で、出血を伴う潰瘍などには止血処置を行うための内視鏡治療が用いられ、クリップなどのデバイスを使用して、緊急時の止血処置を行います。
主な内視鏡治療の対応範囲
| 対応範囲 | 治療の例 | 使用する機器 |
|---|---|---|
| 早期消化器がん | 内視鏡的粘膜切除術(EMR)、粘膜下層剥離術(ESD) | 大腸カメラ、胃カメラ |
| 良性腫瘍(ポリープ) | 切除、焼灼など | 大腸カメラ、胃カメラ |
| 出血性病変 | 止血クリップ、電気凝固 | 内視鏡治療機器 |
| その他炎症性疾患 | 生検、潰瘍の観察 | 胃カメラなど |
上記のように、多岐にわたる病変や疾患に応用できる点が、内視鏡手術の大きな特徴です。
治療対象を選ぶ際の考慮点
内視鏡手術を選択するかどうかは、病変の大きさや深さ、患者さんの体調などを総合的に判断して決定します。
周辺組織への浸潤が深い場合は外科的手術のほうが望ましいケースもあるため、病変の状態を正確に把握したうえでベストな方法を選ぶことが重要です。
内視鏡治療の適応を選ぶときに確認するポイント
- 病変のサイズ(大きすぎると一括切除が難しくなる)
- 病変の深さ(粘膜下層まで浸潤していないかなど)
- 患者さんの全身状態(持病や服薬状況)
- 患部の場所(内視鏡器具が届きやすいか)
内視鏡手術におけるメリット
低侵襲治療のメリットとして、社会復帰の早さや体への負担の少なさなどが挙げられ、外科的手術と比べて入院期間が短いことが多く、費用面でもメリットを感じる場合があります。

体力的負担の軽減
切開範囲が小さいため、出血量が少なく、痛みも軽減しやすく、高齢者や基礎疾患を持つ患者さんにも比較的対応しやすい場合があり、合併症のリスクを下げる工夫を行うことができます。
また、術後の回復が早いことで、日常生活や仕事への復帰タイミングが短縮しやすいです。
入院期間の短縮と費用
病変の大きさにもよりますが、外科手術よりも入院期間が短くなるケースが多いため、入院費や治療費の負担が抑えられることもあります。
ただし、保険の適用範囲や個々の症例に応じて費用は異なるため、医療機関での説明をしっかり受けることが重要です。
内視鏡手術と外科手術の比較
| 比較項目 | 内視鏡手術 | 外科手術 |
|---|---|---|
| 傷の大きさ | 小さい(またはほぼなし) | 大きな切開を伴う |
| 出血量 | 少ないことが多い | 多くなる可能性がある |
| 術後の痛み | 軽い傾向 | 強い場合がある |
| 入院期間 | 短い傾向 | 長くなる場合がある |
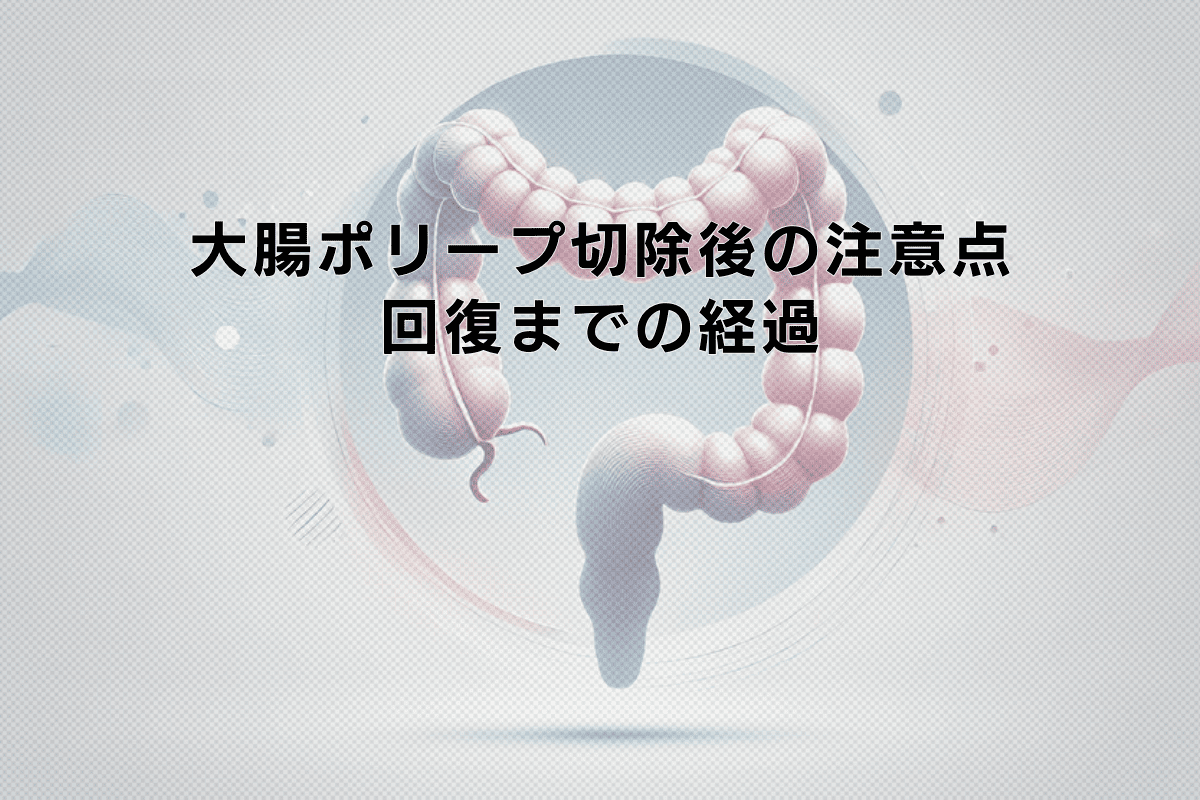
早期がんに対する高い治療効果
粘膜内がんやポリープであれば、内視鏡で十分に切除が可能な場合が多く、転移リスクの低減が期待できます。早期発見により再発のリスクを下げられるため、定期的な検査と組み合わせて効率よく病気に対応できます。
社会的コストの削減
術後の休業期間が短縮することで、患者さん本人や周囲の家族が受ける経済的・心理的負担を和らげ、入院期間やリハビリ期間の短縮は、医療費の観点でもメリットを生み出しやすいです。
内視鏡検査との関係
大腸カメラや胃カメラ検査は、診断だけでなく早期発見・早期治療の観点でも重要です。そのまま治療に移れる場合もあり、内視鏡検査の意義は年々高まっています。
スクリーニングと治療を同時に行う利点
内視鏡検査は、ポリープを発見したら即座に切除できるなど、診断と治療を同時に進められる可能性がある点が大きな利点です。
患者さんの時間的・経済的負担を軽減するだけでなく、がん化する前に処置を施すことで重症化を防げる場合があります。
消化管内視鏡検査でよく見つかる病変
| 病変種類 | 発見の頻度 | 将来的なリスク |
|---|---|---|
| 大腸ポリープ | 高い | 放置すると大腸がん化リスク |
| 胃ポリープ | 比較的高い | 胃がん化リスク |
| 胃潰瘍 | 中程度 | 出血や穿孔リスク |
内視鏡検査では早期がんだけでなく、ポリープや潰瘍なども確認できるため、総合的な管理が行いやすいです。
検査時の麻酔や鎮静剤の使用
検査にともなう痛みや不快感を和らげるために、麻酔や鎮静剤を用いることが多いです。患者さんの苦痛を少なくする目的で眠った状態で行う場合もあり、体の緊張を緩和することで検査自体がスムーズに進みやすくなります。
ただし、鎮静剤を使用する場合は検査後にしばらく安静を要することがあります。車の運転などは避けるよう、事前に説明を受けておくことが大切です。
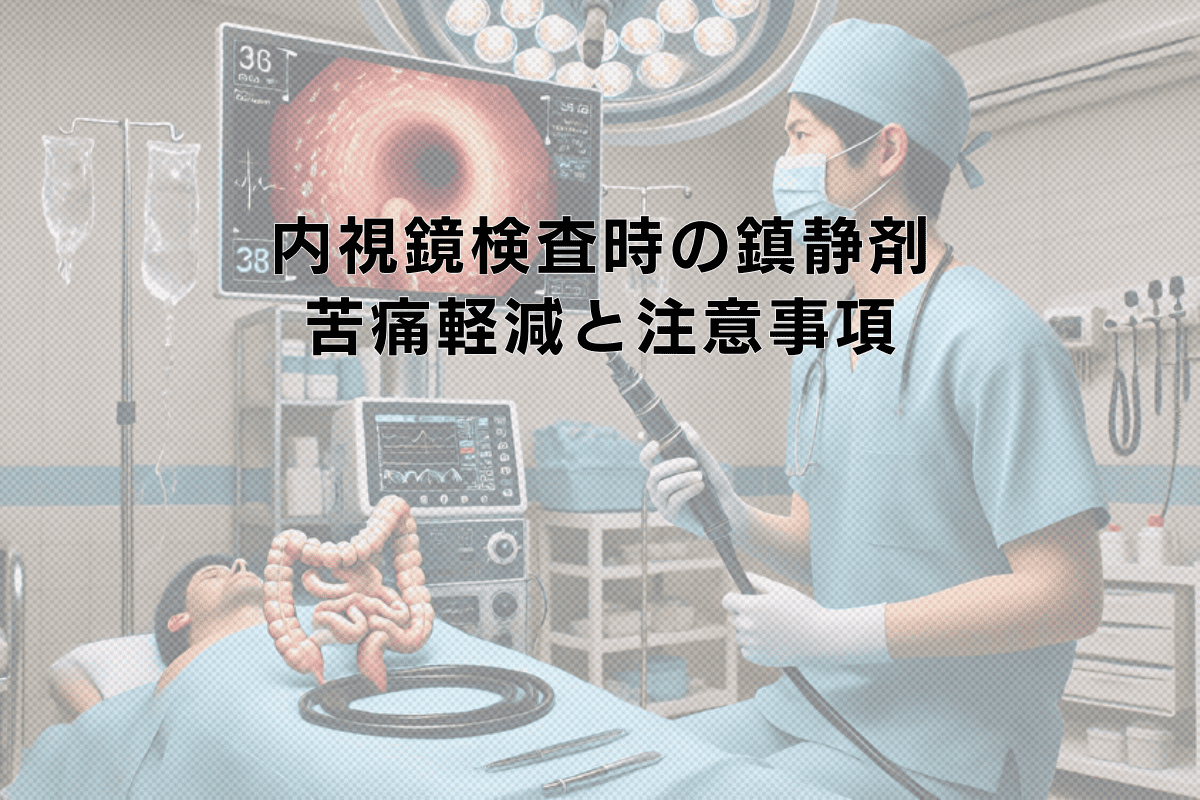
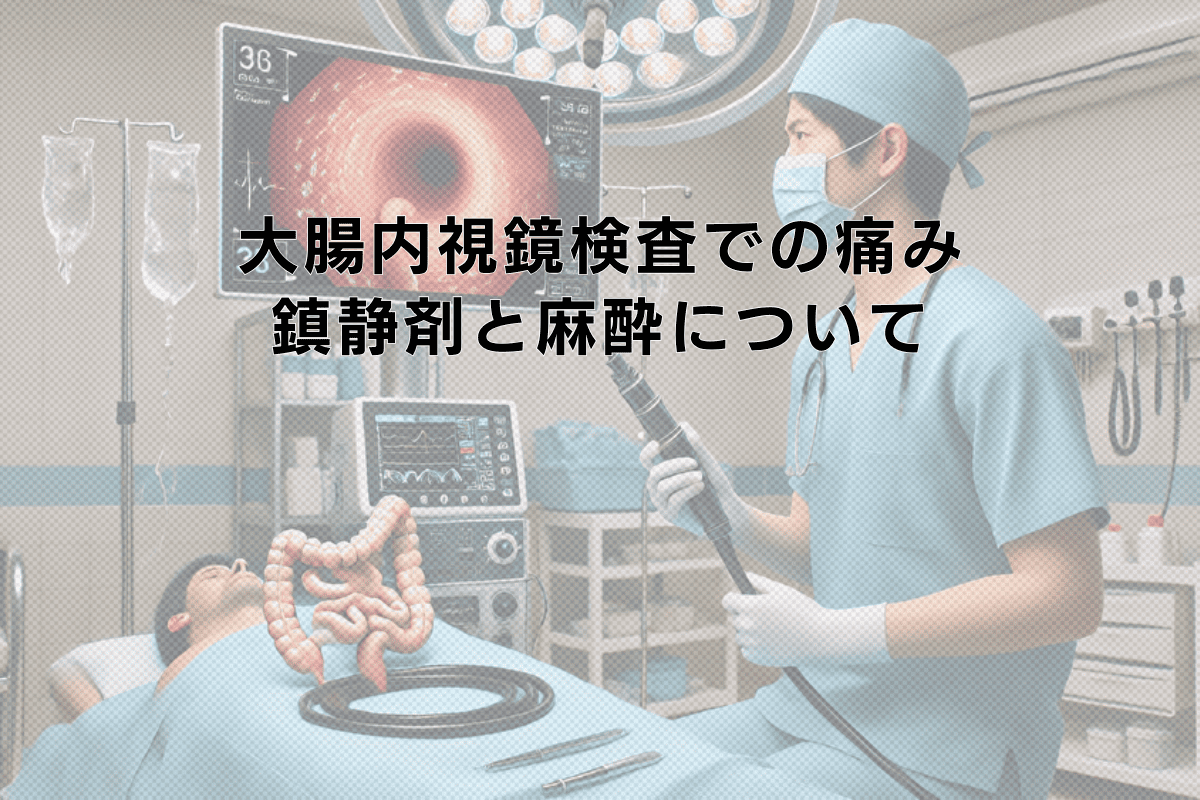
内視鏡検査で治療方針を判断
内視鏡検査で得られた情報をもとに、内視鏡手術が適切かどうかを判断し、病変が予想以上に深い場合は、外科的な治療プランへ移行することもあります。逆に、想定より表層的な病変であれば、より低侵襲な手段を検討できます。
検査頻度の目安
大腸カメラ検査は、ポリープが見つかったことがある人や家族歴がある場合などは早めに行うことが推奨され、胃カメラ検査についても、胃潰瘍の既往歴やピロリ菌感染の有無に応じて、受診タイミングが変わります。
定期的な検査を検討する際に意識したい点
- 家族に大腸がんの既往歴がある場合
- 便潜血検査で陽性反応が出た場合
- 自覚症状(腹痛、体重減少、吐血・下血など)がみられる場合
- 40代以降で健康診断を受けていない場合
痛みへの配慮と術後の過ごし方
内視鏡手術は傷が小さく済む方法とはいえ、全く痛みがないわけではありません。術後の痛みや違和感を最小限に抑えるために、医師は麻酔や鎮静剤を使い、患者さんには術後の過ごし方について細やかなサポートを提供します。
術中の痛み対策
内視鏡による治療は、局所麻酔や鎮静剤を併用することが多く、痛みに弱い方や高齢の方には、静脈麻酔を用いて眠った状態で行うケースもあります。
必要以上に麻酔を強くすると意識レベルを維持しづらくなるため、安全性を考慮した調整が行われます。
術後の痛みや違和感への対処
術後の傷口からの痛みは、開腹手術と比べれば軽度である場合が多いですが、人によっては鈍い痛みや腹部膨満感を感じることもあります。
痛み止めの内服薬を処方することも多く、日常生活を送りながら傷の回復を促す流れが一般的で、十分な水分補給や栄養バランスの良い食事を心がけることが回復を助けます。
内視鏡手術後に気をつけたい生活習慣
| 項目 | 具体的な対策 |
|---|---|
| 食事 | 刺激の少ない食事を心がける |
| 入浴 | 創部の状態を確認して医師の指示に従う |
| 運動 | 数日から1週間程度は軽めに留める |
| アルコール | 回復が進むまでは控える方が望ましい |
合併症予防のための注意点
極端に激しい運動や飲酒などは、消化器官に負担をかけて傷の回復を遅らせる可能性があり、傷口からの出血などを防ぐためにも、術後数日は安静を保ちながら無理のない範囲で生活することが重要です。
感染リスクを下げるために、創部の清潔にも気を配る必要があり、特にお腹を下した場合などは、早めに医療機関へ連絡してください。
痛みのセルフチェック
痛みが強い、あるいは急に増した場合には何らかのトラブルが起きている可能性もあり、自分の状態をこまめにチェックし、少しでも異変を感じた場合は担当医に相談することが早期対応につながります。
術後の症状を観察するポイント
- 術後数日たっても痛みが引かない
- 発熱や吐き気がある
- 出血量が増える、もしくは出血が続く
- 排便や排尿に異常を感じる
事前準備とリスク
内視鏡手術は低侵襲といっても、全くリスクがないわけではなく、安全に治療を進めるためには、事前準備や合併症のリスクを正しく理解することが大切です。
手術前の診察と検査
内視鏡手術を行う前には、血液検査や心電図、胸部レントゲンなどを実施して、全身状態を把握し、大腸カメラの場合は腸内を空にするための下剤を服用することが一般的です。
持病やアレルギー、普段飲んでいる薬がある場合は、医師へ必ず伝えることが大切で、特に抗凝固薬を飲んでいる場合は術中の出血リスクが高まる可能性があるため、投薬の調整が必要になることがあります。
内視鏡手術前の主な確認事項
| 確認内容 | 具体例 |
|---|---|
| 薬の服用歴 | 抗血小板薬、抗凝固薬、糖尿病薬など |
| 既往歴 | 消化器疾患、心臓病、脳血管障害 |
| アレルギー | 薬剤、麻酔薬、ゴム製品など |
| 生活習慣 | 飲酒や喫煙の頻度、食生活 |
術後に起きる可能性がある合併症
内視鏡手術でも、組織を切除したあとに出血が続いたり、穿孔(消化管に穴があく状態)が起きたりするリスクがあり、粘膜下層にまで処置を広げるESDなどでは、病変が大きいほど合併症のリスクが高まります。
出血は時間がたってから起きるケースもあるため、退院後も注意深く観察することが大切です。
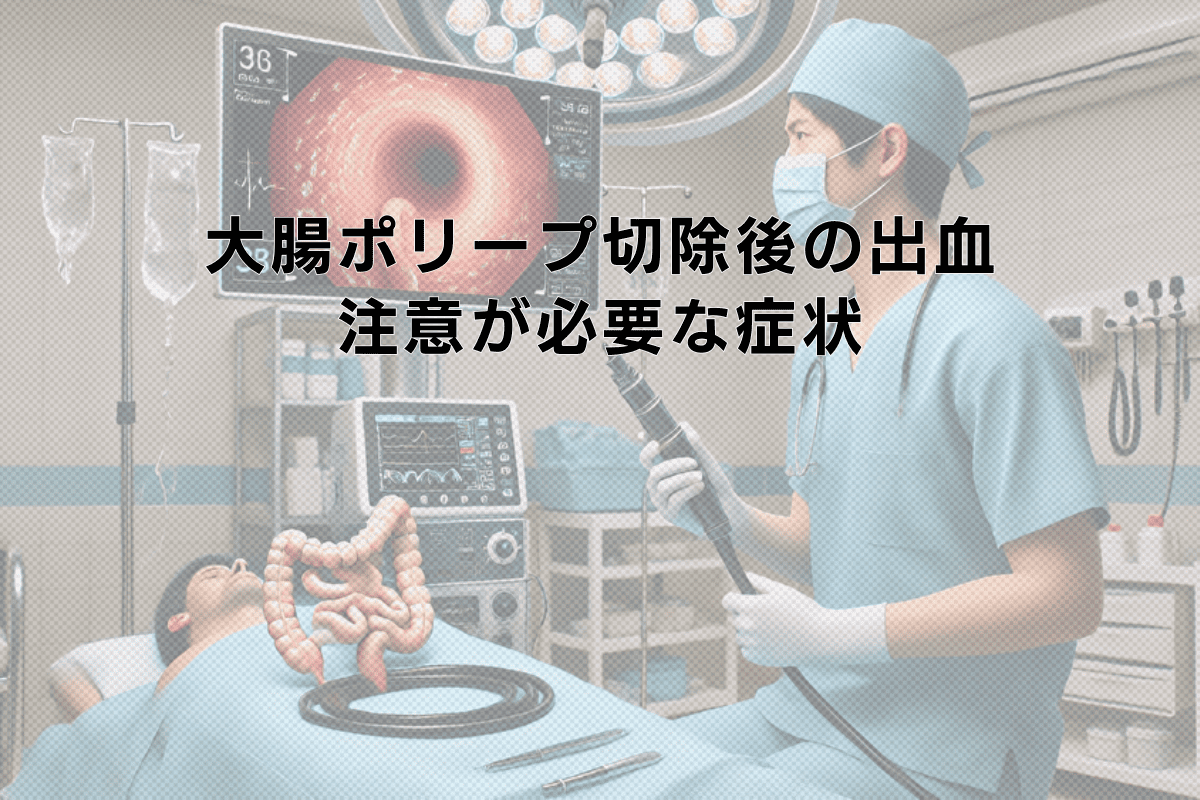
麻酔のリスクと対策
麻酔を用いる場合、呼吸や心拍への影響を考慮しながら投与量を決め、高齢者や基礎疾患を持つ方では特に注意が必要です。麻酔科医がいる医療機関では、麻酔科医がバイタルサインを管理しながら安全に治療を進めます。
内視鏡手術時の麻酔に関する注意点
- 麻酔科医がいる医療機関であれば安全性が高まりやすい
- 術中・術後のバイタルサインを連続的にモニタリングする
- 鎮静剤を多用しすぎないよう投与量を調整する
- 特殊な持病を抱えている方は事前に十分な相談を行う
内視鏡手術を受ける際の疑問
患者さんが内視鏡手術を選ぶとき、さまざまな疑問が生じるでしょう。治療効果のほか、痛みや費用、生活への影響など、事前に把握しておくと安心感が高まります。
どの程度の痛みや違和感があるのか
多くの場合、術後1~2日ほど軽い痛みを感じることがありますが、日常生活を維持できます。完全な無痛は難しくても、従来の開腹手術と比較すると負担が少ないことが一般的です。
内視鏡手術後、どれくらいで仕事復帰できるか
病変の部位や範囲、患者さんの体調によって異なりますが、外科手術と比較すると早めに職場復帰できることが多く、デスクワークなら数日~1週間程度で再開できます。
ただし、重い物を持つ必要がある仕事や激しい身体活動が伴う職業の場合は、体調を見ながら慎重に復帰する時期を考えることが必要です。
術後の復帰時期を決めるときに考慮したい要素
- 仕事の内容(デスクワーク、立ち仕事、力仕事など)
- 術後の回復度合い(傷の状態、痛みの程度)
- 通勤手段(車の運転が必要か、交通機関を利用できるか)
- 上司や同僚の理解(職場内での配慮の有無)
入院や通院はどれくらい必要になるか
内視鏡手術の場合、数日程度の入院や日帰りで行うケースもあり、たとえばポリペクトミーだけなら日帰り可能な場合もありますが、ESDなど大きな切除が必要な場合は数日の入院を要することがあります。
治療費はどのくらいかかるか
治療費は病院や疾患の種類、保険の適用範囲によって異なりますが、大腸ポリープ切除などは保険適用となることが一般的です。
ただし、組織の病理検査や検査入院の有無によって費用に差が生じるので、複数の医療機関で相談して比較検討する方もいます。
内視鏡手術の大まかな費用目安
| 内視鏡治療の種類 | 費用の目安(保険適用時) | 入院日数の目安 |
|---|---|---|
| 内視鏡的ポリペクトミー | 数万円程度 | 日帰りまたは1~2日 |
| EMR(粘膜切除術) | 数万円~十数万円 | 2~3日程度 |
| ESD(粘膜下層剥離術) | 十数万円~数十万円 | 3~5日程度 |
よくある質問
内視鏡手術に関する情報は数多くありますが、患者さんが特に気になる点をいくつかまとめます。疑問点を解消しながら、安心して治療を受けるための参考にしてください。
- 高齢でも内視鏡手術は受けられる?
-
年齢だけで判断するわけではなく、合併症や心肺機能などを含む全身状態で検討します。高齢でも基礎体力がしっかりしている方は、開腹手術よりも内視鏡によるアプローチが体への負担を抑えられる可能性があります。
- ポリープ切除後に再発しやすい?
-
完全に切除できていれば同じ場所に再発するリスクは低いですが、新たなポリープが別の場所に発生することはありえます。定期的に検査を受けることで、早期発見と追加の切除が期待できます。
- 内視鏡手術を受ける前に食事制限は必要?
-
大腸内視鏡検査や手術を受ける際は、前日から食事内容を制限したり、下剤を飲んだりし、胃内視鏡の場合も当日朝食を控えるなどの指示を受けることがあります。
指示が出た場合はしっかり従うことで、正確な検査結果につながります。
- 内視鏡手術が受けられないケースは?
-
病変が広範囲すぎる場合や、深く浸潤している場合は外科的手術が望ましいケースが多いです。また、重度の循環器系疾患などを抱えていて全身麻酔に耐えられない可能性がある場合も慎重に検討します。
次に読むことをお勧めする記事
【大腸ポリープの内視鏡治療 – 早期発見と切除術の重要性】
内視鏡手術の仕組みがわかったら、実際にポリープ切除がどのように行われるのかが気になりませんか?具体的な流れを紹介しています。
【内視鏡検査費用の目安と流れ 胃と大腸のチェック方法】
内視鏡手術について理解が深まると、実際の検査費用や保険適用についても知りたくなる方が多いようです。治療計画を立てる上で重要な情報です。
参考文献
Etoh T, Inomata M, Shiraishi N, Kitano S. Minimally invasive approaches for gastric cancer—Japanese experiences. Journal of surgical oncology. 2013 Mar 1;107(3):282-8.
Abe N, Mori T, Takeuchi H, Yoshida T, Ohki A, Ueki H, Yanagida O, Masaki T, Sugiyama M, Atomi Y. Laparoscopic lymph node dissection after endoscopic submucosal dissection: a novel and minimally invasive approach to treating early-stage gastric cancer. The American journal of surgery. 2005 Sep 1;190(3):496-503.
Saito Y, Yamada M, So E, Abe S, Sakamoto T, Nakajima T, Otake Y, Ono A, Matsuda T. Colorectal endoscopic submucosal dissection: T echnical advantages compared to endoscopic mucosal resection and minimally invasive surgery. Digestive endoscopy. 2014 Jan;26:52-61.
Kinoshita T. Minimally invasive approaches for early gastric cancer in East Asia: current status and future perspective. Translational gastroenterology and hepatology. 2020 Apr 5;5:20.
Etoh T, Shiroshita H, Shiraishi N, Kitano S, Inomata M. Ongoing clinical studies of minimally invasive surgery for gastric cancer in Japan. Translational gastroenterology and hepatology. 2016 Apr 11;1:31.
Namikawa T, Hanazaki K. Laparoscopic endoscopic cooperative surgery as a minimally invasive treatment for gastric submucosal tumor. World Journal of Gastrointestinal Endoscopy. 2015 Oct 10;7(14):1150.
Jeong IH, Kim JH, Lee SR, Kim JH, Hwang JC, Shin SJ, Lee KM, Hur H, Han SU. Minimally invasive treatment of gastric gastrointestinal stromal tumors: laparoscopic and endoscopic approach. Surgical Laparoscopy Endoscopy & Percutaneous Techniques. 2012 Jun 1;22(3):244-50.
FASCRS HM, Lee SW, Mutch MG, Rivadeneira DE, Steele SR, editors. Minimally invasive approaches to colon and rectal disease: technique and best practices. Springer; 2014 Nov 22.
Cruz RA, Ragupathi M, Pedraza R, Pickron TB, Le AT, Haas EM. Minimally invasive approaches for the management of “difficult” colonic polyps. Diagnostic and therapeutic endoscopy. 2011;2011(1):682793.
Hassan C, Repici A, Sharma P, Correale L, Zullo A, Bretthauer M, Senore C, Spada C, Bellisario C, Bhandari P, Rex DK. Efficacy and safety of endoscopic resection of large colorectal polyps: a systematic review and meta-analysis. Gut. 2016 May 1;65(5):806-20.










