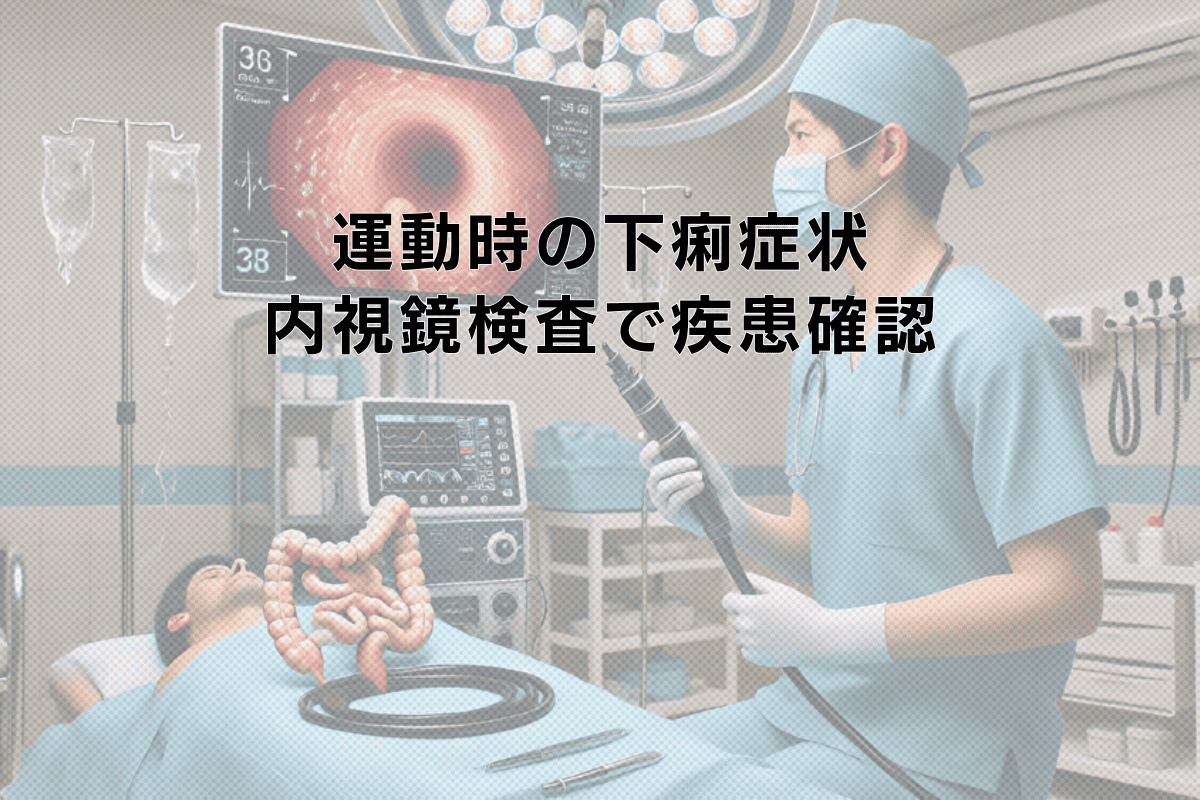健康増進や体力維持のために運動を習慣にしている人は多いでしょう。しかし、ランニングやトレーニングの最中、あるいはその直後に急な腹痛や下痢に見舞われる経験を持つ人も少なくありません。
これは一般的にランナーズ下痢とも呼ばれ、多くは一時的な生理現象です。
この記事では、運動と下痢という一見相反するような関係性について、背景にある体の変化を詳しく解説します。
運動時に下痢が起こりやすくなる理由
運動は心身に多くの良い影響を与えますが、特に消化器系にとっては負担となる側面もあります。運動中に下痢が起こる背景には、体の中でいくつかの変化が同時に発生していることが関係しています。
腸への物理的な振動と刺激
ランニングやジャンプを伴う運動では、体全体が上下に大きく揺れ、振動が内臓、とりわけ腸に直接的な物理的刺激として伝わります。
腸が繰り返し揺さぶられることで、ぜん動運動、つまり内容物を先へ送り出す動きが過剰に活発になることがあり、便の水分が十分に吸収される前に腸を通過してしまい、下痢として排出されるのです。
長距離ランナーにこの症状が多いのは、長時間にわたって腸が刺激を受け続けるためと考えられます。
消化管の血流低下
運動を行う際、体は筋肉へより多くの酸素と栄養を供給しようとするために、心臓は拍動を速め、血液を活動中の筋肉へ優先的に送り込みます。このとき、相対的に消化管など、生命維持に直接的な緊急性が低い器官への血流が一時的に減少します。
血流が低下した消化管は、食べ物の消化や水分の吸収能力が落ちてしまいます。この状態で腸内に未消化の食物や水分が残ると、腸がそれを異物と判断し、速やかに排出しようとするため下痢を引き起こす一因となるのです。
運動強度と消化管血流の関係
| 運動強度 | 消化管への血流 | 下痢のリスク |
|---|---|---|
| 軽い運動(ウォーキングなど) | ほぼ変化なし〜わずかに減少 | 低い |
| 中程度の運動(ジョギングなど) | 約20〜40%減少 | 中程度 |
| 激しい運動(全力疾走など) | 最大で約80%減少 | 高い |
自律神経のバランスの変化
私たちの体をコントロールしている自律神経は、活動時に優位になる交感神経と、リラックス時に優位になる副交感神経です。
運動中は交感神経が活発になり、心拍数を上げ、血圧を上昇させ、一方で、腸の動きは主に副交感神経によってコントロールされています。
運動によって交感神経が極度に優位になると、自律神経全体のバランスが乱れ、腸の正常な機能が妨げられることがあります。
特に、レース前の緊張やプレッシャーといった精神的なストレスも交感神経を刺激し、腸の過剰なぜん動運動を起こして下痢の原因となることがあります。
食事内容とタイミングの影響
運動直前の食事も、運動時の下痢に大きく影響し、脂肪分や食物繊維が豊富な食事は消化に時間がかかるため、運動開始時にも胃や腸に内容物が残っている可能性が高くなります。
その状態で運動を始めると、消化不良を起こしやすくなり、腹痛や下痢につながり、また、カフェインや人工甘味料、乳製品なども、人によっては腸を刺激し、症状を誘発する原因となり得ます。
運動前の食事は、消化の良いものを適切なタイミングで摂ることが大切です。
運動不足が腸の健康に与える影響
運動中の下痢とは対照的に、運動不足もまた腸の不調を起こす大きな要因です。体を動かさない生活が続くと、消化器系全体の機能が低下し、便秘や下痢といった便通異常につながることがあります。
腸のぜん動運動の低下
腸が内容物を肛門側へ送り出すぜん動運動は、腸そのものの筋肉だけでなく、腹筋などの体幹の筋肉の動きにも助けられています。
運動不足によって筋力が低下すると、腸を外から刺激する力が弱まり、ぜん動運動が鈍くなり、便が腸内に長くとどまるようになり、便秘を起こしやすくなるのです。
便秘が続くと、腸内で悪玉菌が増殖することで腸内環境が悪化し、その結果、硬い便と下痢を繰り返すような不安定な状態になることもあります。
腸内環境の悪化
適度な運動は全身の血行を促進し、腸の血流を改善する効果も含まれ、血流が良くなることで、腸の細胞に十分な酸素と栄養が供給され、腸の機能が活発になります。
また、運動は腸内の善玉菌を増やす助けとなり、腸内フローラのバランスを整える効果も期待できます。運動不足が続くと、好影響が得られず、血行不良や腸内環境の乱れから、便通異常や免疫力の低下につながる可能性があります。
運動不足が引き起こす腸の問題
| 要因 | 内容 | 結果として起こりうること |
|---|---|---|
| 筋力低下 | 腹筋など体幹の筋力が弱まる | ぜん動運動のサポートが減り、便秘傾向になる |
| 血行不良 | 全身および消化管の血流が滞る | 腸の活動が低下し、機能不全に陥りやすい |
| 腸内環境の乱れ | 善玉菌が減少し、悪玉菌が優位になる | 便通異常、免疫力の低下、ガスの発生 |
ストレスと腸の関連性
運動は、気分転換やストレス解消に非常に有効な手段です。体を動かすことで、セロトニンなどの幸福感に関わる神経伝達物質が分泌され、精神的な安定をもたらします。
脳と腸は自律神経などを介して密接に連携しており、これを脳腸相関と呼びます。ストレスによって下痢や便秘を起こしやすいのは、この脳腸相関によるものです。運動不足はストレス解消の機会を減らし、間接的に腸の不調を招きます。
注意すべき運動時の下痢の症状
運動に伴う下痢の多くは一時的なもので、体の生理的な反応として心配がいらないケースがほとんどですが、中には消化器系の病気が隠れているサインである可能性もあります。
一時的な症状と持続的な症状の違い
運動中や運動後数時間以内に起こり、その後は自然に回復する下痢は、多くの場合、運動による一過性のものと考えられます。原因として考えられるのは、前述した物理的刺激や血流の変化などです。
一方で、運動の有無にかかわらず下痢が何週間も続く、あるいは運動をするたびに必ず激しい下痢に見舞われるといった場合は、背景に何らかの病気が隠れている可能性を考慮する必要があります。
症状の頻度や持続期間は、医療機関を受診するべきかどうかの重要な判断材料です。
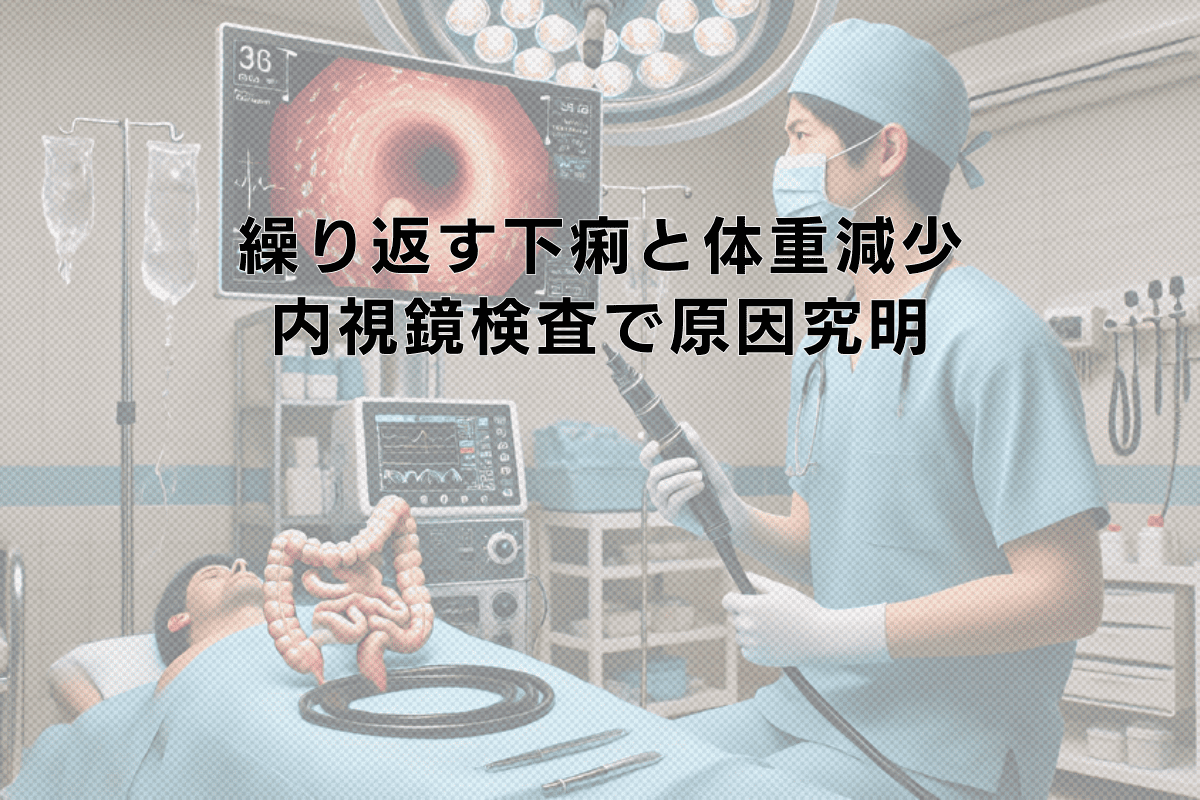
下痢以外の付随する症状
下痢だけでなく、他の症状を伴う場合は特に注意が必要です。発熱、吐き気や嘔吐、強い腹痛が続く、便に血が混じる(血便)、体重が意図せず減少するといった症状がある場合、単なる運動性の下痢ではない可能性が高いです。
このような症状は、感染性腸炎や、炎症性腸疾患などのサインであることもあり、ご自身の体調変化を総合的に見ることが大切になります。
注意が必要な付随症状
- 38度以上の発熱
- 繰り返す嘔吐
- 冷や汗を伴うような強い腹痛
- 便に血や粘液が混じる
- 原因不明の体重減少
症状が悪化する特定の運動
特定の種類の運動や特定の強度での運動でのみ、決まってひどい下痢が起こる場合、その運動が体に合っていない可能性も考えられます。
しかし、以前は問題なかった運動で急に症状が出るようになった、あるいは軽い運動でも症状が現れるようになったという場合は、体の状態に何らかの変化が起きているサインかもしれません。
症状のパターンを記録しておくことは、原因を探る上で役立ちます。
症状と原因の関連性
| 症状のパターン | 考えられる主な原因 | 対処の方向性 |
|---|---|---|
| 激しい運動後に時々起こる | 運動による生理的反応 | 食事や水分補給の見直し、トレーニング調整 |
| 運動の有無に関わらず下痢が続く | 消化器系の基礎疾患、ストレス | 医療機関での精査を検討 |
| 血便や発熱などを伴う | 感染症、炎症性腸疾患など | 速やかに医療機関を受診 |
運動時の下痢を予防・改善するためのセルフケア
運動時の下痢が病気によるものではない場合、生活習慣やトレーニング方法を少し見直すことで、症状を軽減できる可能性があります。ここでは、自分でできる予防策や改善策をいくつか紹介します。
運動前の食事のポイント
運動時の消化管への負担を減らすためには、運動前の食事が非常に重要で、運動開始の2〜3時間前までには食事を済ませておくのが理想です。内容は、消化が良く、エネルギーになりやすい炭水化物を中心にすると良いでしょう。
脂肪分の多い揚げ物や肉類、食物繊維が豊富な生野菜や豆類などは消化に時間がかかるため、運動前は避けてください。
運動前の食事例
| 推奨される食事 | 避けるべき食事 | 理由 |
|---|---|---|
| おにぎり、うどん、バナナ | 天ぷら、ラーメン、カレーライス | 消化が良く、速やかにエネルギーに変わるため |
| エネルギーゼリー、カステラ | 食物繊維の多いサラダ、きのこ類 | 胃腸への負担が少なく、運動の妨げにならないため |
適切な水分補給の方法
運動中の脱水は、消化管への血流をさらに減少させ、下痢の症状を悪化させる原因になります。脱水を防ぐためには、運動前からこまめに水分を摂ることが大切です。
運動中は、一度に大量に飲むのではなく、15〜20分おきに少量ずつ補給することを心がけましょう。
冷たすぎる飲み物は胃腸を刺激することがあるため、常温に近いものがおすすめで、長時間の運動では、水分と同時に失われる塩分やミネラルを補給できるスポーツドリンクが有効です。
トレーニング強度と種類の見直し
もし、特定の高強度なトレーニングの後に決まって下痢をするのであれば、体の限界を超えているサインかもしれません。一時的に運動の強度を下げたり、時間を短縮したりして、体が慣れる時間を作りましょう。
また、ランニングのような上下動の激しい運動で症状が出やすい場合は、水泳やサイクリング、ヨガなど、腸への物理的刺激が少ない運動を試してみるのも一つの方法です。徐々に体を慣らしていくことで、症状が出にくくなることがあります。
生活習慣の改善
腸の健康は、運動や食事だけでなく、日々の生活習慣全体に影響されます。十分な睡眠時間を確保し、心身の疲労を回復させることは、自律神経のバランスを整え、腸の機能を安定させる上で重要です。
また、自分に合ったストレス解消法を見つけ、精神的な負担を軽減することも、脳腸相関の観点から腸の健康に良い影響を与えます。
規則正しい生活リズムを心がけることが、巡り巡って運動時のパフォーマンス向上と不快な症状の予防につながります。
下痢症状の裏に隠れている可能性のある消化器疾患
セルフケアを試みても下痢が改善しない、あるいは悪化する場合には、何らかの消化器疾患が原因となっている可能性があります。運動が症状の引き金になっているだけで、根本的な原因は別にあるのかもしれません。
過敏性腸症候群(IBS)
過敏性腸症候群は、腸に炎症や潰瘍などの目に見える異常がないにもかかわらず、腹痛や腹部の不快感を伴う下痢や便秘が長く続く病気です。
ストレスや生活の乱れが引き金になることが多く、日本人の10人に1人がこの病気を持っているとも言われています。特に、下痢を主な症状とする下痢型のIBSの場合、運動による刺激や精神的な緊張が症状を悪化させることがあります。
診断は、症状の問診や、他の病気がないことを確認するための検査を総合して行います。
炎症性腸疾患(IBD)
炎症性腸疾患は、腸の粘膜に慢性的(長期間続く)な炎症や潰瘍ができる病気の総称で、主に潰瘍性大腸炎とクローン病の二つがあります。
どちらも下痢、腹痛、血便、体重減少などが主な症状で、良くなったり悪くなったりを繰り返すことが特徴です。原因はまだ完全には解明されていませんが、免疫系の異常が関わっていると考えられています。
病気は、放置すると重症化する可能性もあるため、早期の診断と適切な治療の継続が重要で、診断には、大腸内視鏡検査による粘膜の直接的な観察が欠かせません。
主な炎症性腸疾患の特徴
| 疾患名 | 主な炎症の場所 | 特徴的な症状 |
|---|---|---|
| 潰瘍性大腸炎 | 大腸の粘膜(直腸から連続的に広がる) | 粘血便(血液や粘液の混じった下痢)、しぶり腹 |
| クローン病 | 口から肛門までの消化管全体(非連続的に発生) | 腹痛、下痢、体重減少、発熱、肛門病変 |
虚血性大腸炎
虚血性大腸炎は、大腸の血管が何らかの原因で一時的につまり、血流が悪くなることで大腸の粘膜に炎症や潰瘍ができる病気で、突然の激しい腹痛、その後の下痢、そして血便が特徴的な症状です。
運動による消化管の血流低下が引き金になることもあり、特に中高年の方に多く見られ、多くは一時的なもので回復しますが、症状が強い場合は入院治療が必要になります。診断には、症状の経過の確認と大腸内視鏡検査が有用です。
その他の消化器系の病気
上記以外にも、慢性的な下痢の原因となる病気はいくつかあります。
大腸がんや大腸ポリープが大きくなると、便の通過を妨げ、下痢や便秘を繰り返すことがあり、また、細菌やウイルスによる感染性腸炎、特定の薬剤の副作用、あるいは甲状腺機能亢進症のような内分泌系の病気が原因で下痢が続くこともあります。
原因を特定するためには、専門的な検査が必要です。
大腸内視鏡検査でわかること
続く下痢の原因を正確に突き止めるために、大腸内視鏡検査(大腸カメラ)は非常に重要な役割を果たします。
検査の目的と重要性
大腸内視鏡検査の最大の目的は、症状の原因となっている病変がないか、大腸の粘膜を隅々まで観察することです。
レントゲンやCTなどの画像検査では分かりにくい、粘膜のわずかな色の変化や凹凸、炎症の程度などを詳細に確認でき、炎症性腸疾患や虚血性大腸炎、大腸がんなどの病気の確定診断につながります。
また、異常がなかった場合でも、腸に器質的な問題がないことを確認できるため、過敏性腸症候群といった機能的な病気の診断に役立ち、患者さんの安心にもつながります。
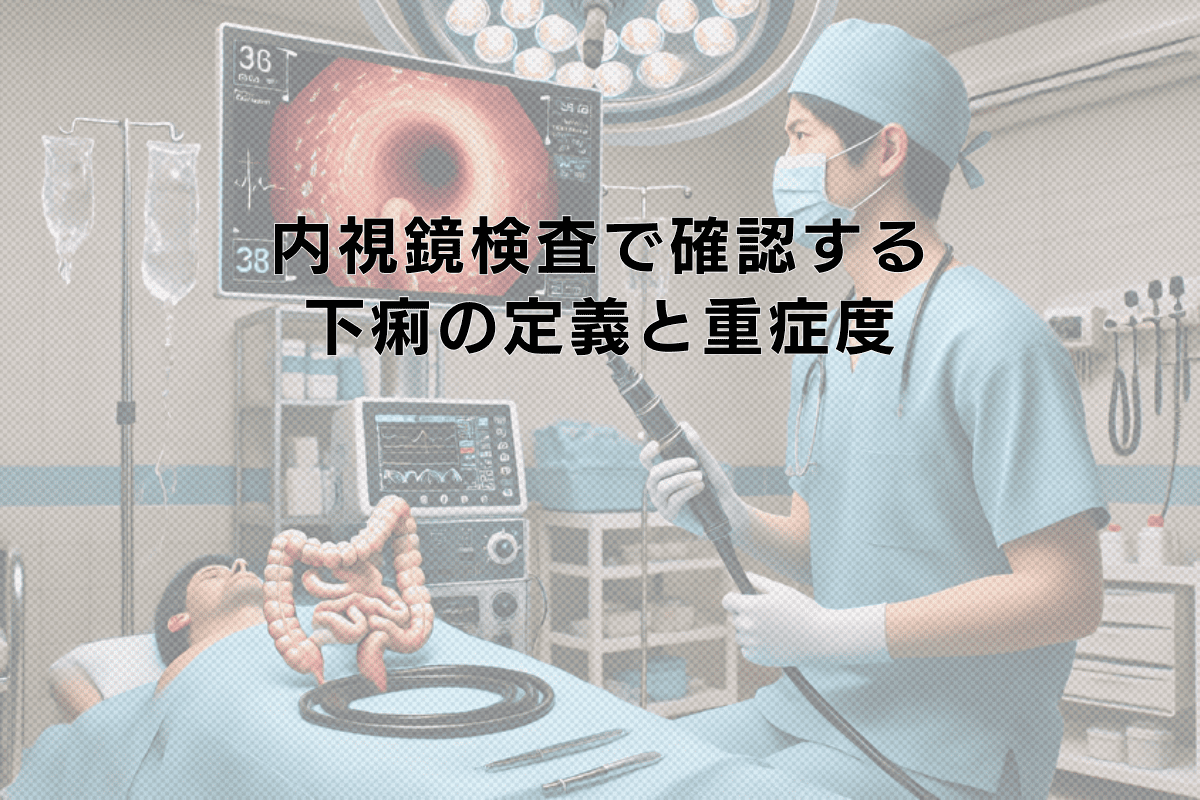
粘膜の状態を直接観察する意義
内視鏡の先端には高性能な小型カメラが搭載されており、モニターを通してリアルタイムで腸内の様子を観察します。
医師は、粘膜が赤く腫れていないか、ただれ(びらん)や潰瘍ができていないか、出血している場所はないかなどを直接確認します。
必要であれば、特殊な光を当てて微細な血管の模様を観察したり、組織の一部を採取(生検)して顕微鏡で詳しく調べたりすることも可能です。
大腸内視鏡検査で発見できる主な病気
| 病気の種類 | 内視鏡で観察される所見 | 確定診断への寄与 |
|---|---|---|
| 大腸がん・ポリープ | 粘膜の隆起(いぼ)、陥凹(くぼみ)、不整な模様 | 早期発見と治療方針の決定に直結する |
| 炎症性腸疾患(IBD) | びまん性の発赤、潰瘍、むくみ、出血 | 特徴的な所見により診断し、炎症の範囲と重症度を評価する |
| 虚血性大腸炎 | 区域性の発赤、むくみ、縦走する潰瘍 | 特徴的な所見から診断が可能 |
ポリープや早期がんの発見
大腸内視鏡検査は、症状の原因を調べるだけでなく、将来がんになる可能性のある大腸ポリープを発見し、その場で切除できることが大きな利点です。ポリープの段階で切除することで、大腸がんの予防につながります。
また、症状が出にくい早期の大腸がんを発見できる唯一の確実な方法でもあり、運動時の下痢といった症状が、重大な病気の早期発見につながるケースも少なくありません。
症状が続く場合の医療機関への相談
不快な症状が続く場合は、自己判断で様子を見続けるのではなく、専門家である医師に相談することが大切です。適切なタイミングで受診し、正しい診断を受けることが、早期回復への第一歩となります。
受診を検討するタイミング
以下のような症状が見られる場合は、医療機関の受診を検討してください。運動時の一時的な下痢であっても、頻度が増えたり、程度がひどくなったりして日常生活に支障をきたすようであれば、一度相談してみましょう。
受診の目安
- 下痢が2週間以上続いている
- 血便や黒い便が出た
- 発熱や嘔吐、強い腹痛を伴う
- 理由なく体重が減ってきた
- 症状のせいで好きな運動ができない
何科を受診すればよいか
腹痛や下痢といったお腹の症状が専門領域なのは、消化器内科や胃腸科です。かかりつけの内科医がいる場合は、まずそこで相談し、必要であれば専門の医療機関を紹介してもらうという方法もあります。
どの科にかかればよいか迷った場合は、まずはお近くの内科や消化器内科に問い合わせてみるとよいでしょう。
医師に伝えるべき情報
診察を受ける際には、ご自身の症状についてできるだけ詳しく、正確に伝えることが、的確な診断の助けになります。事前に情報を整理しておくと、スムーズに診察が進むので、メモにまとめて持参するのも良い方法です。
医師に伝えると役立つ情報
| 項目 | 伝える内容の例 | 診断への貢献 |
|---|---|---|
| 症状 | いつから、どんな下痢(水様便、泥状便)、血は混じるか | 病気の種類や重症度を推測する手がかりになる |
| 頻度・タイミング | 1日に何回か、運動中だけか、食事との関連はあるか | 過敏性腸症候群や食事性の原因などを鑑別するのに役立つ |
| 既往歴・服用薬 | 過去にかかった病気、現在飲んでいる薬やサプリメント | 薬の副作用や他の病気との関連を考慮できる |
運動時の下痢に関するよくある質問
最後に、運動と下痢に関して多くの方が疑問に思う点について、質疑応答の形でお答えします。
- プロテインを飲むと下痢をしやすくなりますか
-
牛乳を原料とするホエイプロテインには乳糖が含まれていて、日本人には、乳糖を分解する酵素(ラクターゼ)の活性が低い人が多く、乳糖不耐症と呼ばれます。
乳糖不耐症の人が一度に多くのプロテインを飲むと、消化しきれない乳糖が腸内で水分を引き込み、下痢の原因となります。
対策としては、乳糖を含まないWPI(ホエイプロテインアイソレート)や、大豆を原料とするソイプロテイン、エンドウ豆を原料とするピープロテインなどを試すことが考えられます。
- 運動をやめれば症状は治まりますか
-
運動が直接的な引き金となっている一時的な下痢であれば、運動を中断したり強度を下げたりすることで症状は改善することがほとんどです。
しかし、運動不足もまた便通異常の原因となるため、完全にやめてしまうのは推奨されません。もし、過敏性腸症候群や炎症性腸疾患などの基礎疾患がある場合は、運動をやめても症状が続く可能性があります。
- 子どもでも運動時に下痢をしますか
-
子どもでも大人と同じように運動時に下痢をすることがあります。子どもの消化器官はまだ発達途上であり、大人よりもデリケートなため、運動による刺激や精神的な緊張の影響を受けやすいと考えられます。
体育の授業や部活動などで症状が出る場合は、食事のタイミングを調整したり、過度なプレッシャーがかかっていないかなど、生活背景にも目を向けることが大切です。
ただし、症状が続く場合や他の症状を伴う場合は、小児科医に相談してください。
- 市販の下痢止めを飲んでも大丈夫ですか
-
運動の予定があり、一時的に症状を抑えたいという場合に、市販の下痢止めを使用すること自体は一つの選択肢ですが、対症療法であり、根本的な解決にはなりません。
細菌やウイルスによる感染性腸炎が疑われる場合に下痢止めを使うと、原因となる病原体の排出を妨げ、かえって回復を遅らせてしまう危険性があります。
安易に薬に頼るのではなく、なぜ下痢が起きるのかを考え、症状が続くようであれば、必ず最寄りの医療機関に相談してください。
以上
次に読むことをお勧めする記事
【過敏性腸症候群(IBS)と検査の必要性】
ランニングや緊張による下痢で「ただの生理現象?」と感じた方に。IBSの可能性や検査の必要性、心と腸の関係について丁寧に説明しています。
【繰り返す下痢と体重減少の症状|内視鏡検査による原因究明】
運動中だけでなく、下痢が続き体重が気になる方にはこちらも。症状を見逃さず検査で原因を探る大切さをわかりやすく解説しています。
参考文献
Tadano T, Abe K, Sasaki S, Terasawa T, Hosono S, Katayama T, Hoshi K, Nakayama T, Hamashima C. Serious adverse events associated with bowel preparation for colonoscopy in Japan: Systematic review. Digestive Endoscopy. 2025 Jun 9.
Matsumoto Y, Nadatani Y, Otani K, Higashimori A, Ominami M, Fukunaga S, Hosomi S, Kamata N, Kimura T, Fukumoto S, Tanaka F. Prevalence and risk factor for chronic diarrhea in participants of a Japanese medical checkup. JGH Open. 2022 Jan;6(1):69-75.
Saito Y, Kodashima S, Matsuda T, Matsuda K, Fujishiro M, Tanaka K, Kobayashi K, Katada C, Horimatsu T, Muto M, Ohtsuka K. Current status of diagnostic and therapeutic colonoscopy in Japan: The Japan Endoscopic Database Project. Digestive Endoscopy. 2022 Jan;34(1):144-52.
Kinoshita Y, Ariyoshi R, Fujigaki S, Tanaka K, Morikawa T, Sanuki T. Endoscopic diagnosis of chronic diarrhea. DEN open. 2022 Apr;2(1):e53.
Yamada E, Kuriyama H, Uchida E, Murata Y, Hata Y, Tagri M, Isozaki Y, Oyamada H, Ozawa Y, Ito T, Mizuki A. Association between endoscopic findings related to colonic diverticula and bowel habits: A multicenter study in Japan. Journal of gastroenterology and hepatology. 2017 Dec;32(12):1938-42.
Ihara E, Manabe N, Ohkubo H, Ogasawara N, Ogino H, Kakimoto K, Kanazawa M, Kawahara H, Kusano C, Kuribayashi S, Sawada A. Evidence-based clinical guidelines for chronic diarrhea 2023. Digestion. 2024 Dec 9;105(6):480-97.
Shah RJ, Fenoglio-Preiser C, Bleau BL, Giannella RA. Usefulness of colonoscopy with biopsy in the evaluation of patients with chronic diarrhea. The American journal of gastroenterology. 2001 Apr 1;96(4):1091-5.
Marshall JB, Singh R, Diaz-Arias AA. Chronic, unexplained diarrhea: are biopsies necessary if colonoscopy is normal?. American Journal of Gastroenterology (Springer Nature). 1995 Mar 1;90(3).
Limburg PJ, Ahlquist DA, Sandborn WJ, Mahoney DW, Devens ME, Harrington JJ, Zinsmeister AR. Fecal calprotectin levels predict colorectal inflammation among patients with chronic diarrhea referred for colonoscopy. Official journal of the American College of Gastroenterology| ACG. 2000 Oct 1;95(10):2831-7.
Kagueyama FM, Nicoli FM, Bonatto MW, Orso IR. Importance of biopsies and histological evaluation in patients with chronic diarrhea and normal colonoscopies. ABCD. Arquivos Brasileiros de Cirurgia Digestiva (São Paulo). 2014;27(3):184-7.